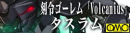※本商品は「ファナティックブラッド」の本編とは異なるアナザーノベルであり、「ファナティックブラッド」ならびに他ゲームコンテンツでプレイングやキャラクター設定の参照元にすることはできませんのでご注意ください。
-
『メメント・モリ』
●
母について、私が覚えていることはそう多くはない。
覚えているのは、彼女が身につけていた種々の品だ。
指輪や、髪飾りといった、手元に残ったものだけだ。
それ以外――彼女の香りや声、その暖かさはいずれもくすみ、煤け、薄れていってしまった。
慌ただしい日々だったのだ。
●
『これからお前は、我がシャール家の長子となる』
《父》はそう言って、幼い彼を見下ろした。天涯孤独の少年を掬い上げたのはシャール家の当主であった。当主の傍らには、子を産めなかった《母》が、その細い身を自ら掻き抱くようにして立っている。
『クローディオ・シャール。それがお前の名だ』
『……はい、お父様』
新しい父の言葉に、幼いクローディオは頷いた。そうして、何度目かの視線を新たな母に向ける。
喪失の痛みは、たしかに少年を蝕んでいたのだろう。そこには、縋るような色があった。
『よろしくお願いします、お母様』
『……ええ』
しかし。視線が合うことは終ぞ無かった。
●
そこには何でも揃っていた。けれど、幼い彼が望んでいたものなど、その気配ひとつも見当たらなかった。
自由など、いらなかった。籠の中の鳥。なるほど、そうであるのならば、どれだけよかっただろう。鑑賞に耐えうるのならば、徒に刺されはすまい。
『不貞の子』
それが、彼に焼き付けられた烙印であった。
――俺は、どうしたらいい。
積み上がる分厚い書籍に、覚えるべき貴族のしきたり。その何れも、幼い彼には過大に過ぎた。
降り注ぎ、重なり続ける落胆と無関心、揶揄の言葉に煩悶する日々が続く。
此処では、与えられない。
幼い彼の心は、ただただ乾いていた。
干上がった喉を潤すには、彼自身が流す涙など何の救いにもなりはしない。
彼が希求し、望むものは、与えられなくては得られないもの。
引き裂かれそうな痛みを覚えながら、自らの裡に、答えを探す。
道は、ただ一つしか、残っていなかった。
「俺は……」
――アイサレタイ。
手を伸ばした。
かつては握り返されていた手。
今はもう、握ってくれるものなどいない、小さな手を。
彼が択んだ道行の名を敢えて告げるのならば、こうなるだろう。
約束された悲劇、と。
●
少年はランプの明かりを友とし、書籍を捲り、ペンを走らせる。
日夜を問わず文字を追い、知識を得た。貴族の何たるを識り、新たな父と母のため、クローディオ・シャールの名に恥じぬ自分で在ろうと努力を重ねた。
必死、だったのだ。結果も出ようものである。
『自覚が芽生えたようだな』
そういう父の手が少年の背を叩いた時には、身が震えるほどの喜びを覚えた。
不貞の子、と罵る者も見かけなくなった。母は、相変わらず目も合わさず、言葉も交わすこともないが、確かに、居場所は生まれていたのだ。ほかならぬ、彼自身の力によって。
――いつか、母だって『私』を見てくれるだろう。私が、もっと努力さえすれば。
「はい、お父様」
感激に弾けんばかりの心を自制して、少年は頭を垂れた。
「私は……シャール家の長子ですから」
心の彼方で薄れゆくものに目を留めることなく、この時の彼はそう思っていたのだ。
●
体調を悪くした母が静養のために屋敷を出て行った後も、彼の努力は衰える所を知らなかった。
奮起すればするだけ、居場所ができる。父も――母だって、きっと喜んでくれる。
当時七歳の彼は、そう信じていたのに。
―・―
こんなはずじゃなかった。
《俺》は遠景に、母を見た。豪奢な馬車から、確かな足取りで歩み降りる母を。
ありとあらゆる使用人が母を迎え、歓迎の声と――祝いの言葉を、惜しみなく告げている。
母は、これまで俺が見たこともない満面の笑みを浮かべている。その細腕に抱かれているやわらかな何かを父に見せると、父も心からの笑みを浮かべた。両の手を広げ、母ごと《それ》を抱きとめる。抱きしめる。固く、愛おしげに。壊さないように加減をしながらも、離すまいと誓う、強い抱擁だった。母に愛のことばを囁く。母は頷いた。何度も、何度も。使用人たちの祝福の声が高まる。感極まった父が大きく頷きながら、感謝の言葉を告げた。
俺は、それを、屋敷の中から眺めていた。
弟との出会いの日だった。
これまでの日々が、徒労に消えた日だった。
どこからか、声が聞こえた。
「もうクローディオ様は必要ないな」
――最悪の一日だった。
●
弟はエクラの導きの中、幸福と共に長じた。
俺と同じ時間を過ごし、同じ日々を過ごし、愛と幸福に包まれながら大きくなる弟。
俺はこれまで以上に足掻いた。努力した。出来ることはなんだってした。
それでも、身を縛る恐怖から解き放たれることはなかった。
時折、夢を見た。父と母。使用人たち。血の繋がりのない縁戚。全てが俺に背を向けている。
呼びかけても振り返ることなく、歩を進め手を伸ばしても距離は縮まることはない。
走る。走る。狂奔する。焦り、叫び、血を吐くように声を荒げても、俺に気づくことはない。
絶望に膝が折れた時、決まって俺はこう言うのだ。
――愛してくれ。
嗄れた声でそう言うと、両親が、使用人が、縁戚が振り返ってくれた。
奇跡的な光景。希求していた皆の姿に、夢の中の俺は狂喜する。顔を上げ、澎湃と涙しながら、両親の名を呼ぼうとしたとき――決まって、それに気づくのだ。
彼らが、俺の後方を見つめていることに。
俺は振り返った。煌々と輝く光に晒され、目が眩む。それでも、その向こうに在るなにかを見通そうと、目を細める。夢の中の俺は予感を抱いている。見てはいけないと、理解もしている。それでも見ないではいられなかった。
聞こえたのは、俺を呼ぶ声だった。
俺を、兄と呼ぶ声が、聞こえた。
●
望むものを得られないままに、兄となった幼い少年は着実に歪んでいった。
強迫の中で成した努力は着実に彼を成長させる。
それと同じ分だけ、彼は自ら望むものから乖離していくことを、そしてその望みが叶えられないことをつきつけられ続けた。
――いつしか彼は、機械になった。
父が期するところを叶え、母が望むところを叶え、弟が求めるところを叶える機械になった。
胸の裡では絶叫しながらも、それをすることで喪われることを恐れ、ひたすらに足掻く機械になった。
彼の望みはいつしか変容していた。
それを、端的に言葉に表せば、このようになるのだろう。
『《私》を、必要としてくれ』
以上が、悲劇と呼ぶに足る、変容の物語。
クローディオ・シャールがどのようにして成ったのかを記す、その始まりの顛末である。
登┃場┃人┃物┃一┃覧┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛
【ka0030/クローディオ・シャール/男性/27歳/メメント・モリ】
ラ┃イ┃タ┃ー┃通┃信┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛
いつもお世話になっております、ムジカ・トラスです。
彼の根本の物語を、がつっとお任せいただいてありがとうございます。
現在のクローディオさんに繋がるモノとして、ちゃんと描けていればいいのですが!
こういった絶望と人格形成はムジカは大好物ではあるのですが、彼が幸せな結末に向かっていけるか少しだけ、心配しなくもないです……ね。
さて――お楽しみいただけましたら、幸いです。それではまた、御縁がありましたら!