ゲスト
(ka0000)
【天誓】これまでの経緯
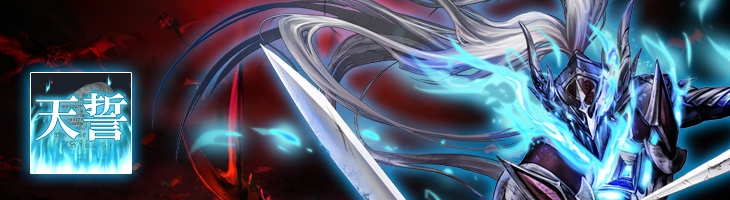


ソサエティが実施した血盟作戦以降、世界各地で精霊が顕現しているのはご存知ですね?
この帝国領でもそれは例外ではありません。しかし、この国と精霊の関係性は正常ではありません。
我々が精霊を護りたいと思っても、彼らはそれを望まないのです。
暴食の眷属から精霊を保護するための戦い。どうか、精霊に近しい皆さんのお力添えをお願いします。
ゾンネンシュトラール帝国皇子:カッテ・ウランゲル(kz0033)
更新情報(12月18日更新)
過去の【天誓】ストーリーノベルを掲載しました。
【天誓】ストーリーノベル
各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。


 「率直に言って、難航していますね」
「率直に言って、難航していますね」
山のように報告書が積まれたデスクを前に、カッテ・ウランゲル(kz0033)は剣呑に呟く。
血盟作戦以後、世界各地に出現した精霊たち。その保護は帝国でも続けられていた。
保護した精霊は大精霊サンデルマンがコロッセオ・シングスピラにまとめてくれるのだが……肝心の精霊が中々保護できない。
帝国兵が遭遇しても精霊は逃げてしまったりする。放置すれば歪虚に襲われる可能性も高いのだが……。
「帝国領に出現する精霊は人間を警戒しています。比較的ヒトに近しい“英霊”であれば対話できるケースもあるのですが」
精霊と言っても、細分化すればいくつかの種類がある。
中でも自然に宿る精霊である“自然精霊”、これが帝国にとっては厄介だった。
「元々、クリムゾンウェストの人々は大なり小なり精霊、すなわち自然と共存していました。しかし帝国はその自然から離れる形で発展を遂げています」
自然とは気まぐれ――アトランダムな存在だ。
ヒトに恩恵を与えもするが、何かを奪いもする。その気まぐれを脱却し、恩恵だけを求めたのが機導術だと言えるだろう。
自然本来の法則性を捻じ曲げる、錬金術の発展形。元々この国と自然は水と油なのだ。
「ふむ……ここはひとつ、大精霊のアドバイスなど頂けるとありがたいのだが?」
ごそっと報告書の山を退けて顔を覗かせたヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、その書類の山の上にちょこんと腰かけたマスコット人形に問いかける。
それは厳密にはマスコット人形ではなく、ヴィルヘルミナの姿形を模した小さな精霊だ。が、その実態は大きな精霊、大精霊サンデルマン。……ややこしいが。
「空気の問題かもしれないな」
「空気……陛下が最も読めないモノですね」
「フッ、我が弟君に良いことを教えてやろう。私は空気を読めないのではない。あえて読まないのだよ」
「陛下、それは受け取り手からすれば同じことです。しかし、空気ですか……。確かに私も聞き覚えがあります」
ヒトと精霊は実は密接な関係にある。
この世界におけるありとあらゆる生物種の中で、唯一人間だけが“精神活動だけ”で精霊に影響を及ぼせる。
「ヒトが持つ生体マテリアルは思考活動を発生源とする……つまり意識、自我といったものをトリガーにしているという説もあります。だから大勢のヒトの信仰が精霊の力になったり、プラスの感情が負のマテリアルを浄化すると」
「ふむ。考えてみると奇妙な関係性だな」
「むしろ正しいのでは? 大精霊……クリムゾンウェストが私たちをこの星の抗体として生み出したのなら、ですが」
カッテは唇を撫でながら、その言葉の意味を深く思考する。が、今はそれよりも……。
「空気というのはつまり、この国の人々が精霊を受け入れていない、そういった総意が存在していると?」
「その通りだ。この国の人間は他の人間に比べても特に身勝手だ。見たいように見、聞きたいことだけを聞く」
「「耳が痛い」」
二人同時に肩を落とす。それもこれも、この国の歴史の闇によるものだろう。
どの国家も、集団も常に矛盾は抱える。だが革命を経たこの国の民は知っているのだ。力こそがすべて、力こそが正義なのだと。
「臣民に精霊のことを説いても理解は得られないでしょう。彼らにとって精霊、自然は自分たちの糧でしかありません。ここは陛下お得意の頓智で何とかなりませんか?」
「我が弟君にもう一つ良いことを教えてやろう。私は頓智が効いているのではなく、勘が鋭いのだ。“降ってこない”と動けん」
「天才と何やらは紙一重ですね……仕方ありません、リーゼロッテ女史にでも協力を依頼しましょう」
「我々よりも精霊に詳しい者たちに力を借りたほうが良いのかもしれんな」
かつてグラズヘイム王国北部辺境領と呼ばれたこの土地は、元々人間種の支配領域ではない。
この土地の精霊と共存していたのは先住民である亜人たちだ。だが、彼らの精霊との繋がり――信仰は、帝国により断たれてしまった。
ヒトは望んで自らの手で精霊との関係性を破壊している――。
それを今更取り戻したいというのは、虫のいい話なのだろう。

 暴食王ハヴァマール。
暴食王ハヴァマール。
世界に七体しか存在しない、歪虚眷属の頂点。“始祖たる七”とも呼ばれし者。
彼は人類の生活圏から遥か北――星の傷跡を擁するリグ・サンガマの向こう側、遥か昔に邪神ファナティックブラッドが滅ぼしたという、世界の“裏側”に立っていた。
生命の枯渇した、虚無の領域。歪虚の支配状態が長らく続き、星が壊死した場所は虚無となる。
漆黒の光が降り注ぐ幻想的な光景は、クリムゾンウェストが重く病んでいる事を意味していた。
だが、最近この虚無の領域に突如として大地が蘇りつつある。エバーグリーンから、一部の土地が転移してきているのだ。
「星とは……無とは……実に不思議なものよ。そうは思わぬか、ナイトハルト」
どっかりと地べたに胡坐をかいた王の言葉に、不破の剣豪ナイトハルトは答えあぐねていた。
この王は偉大にして雄大。まるで深く暗い深海のような穏やかさを持つ。
彼は“死”の概念の体現者だ。死は生物にとって忌むべき終わりだか、彼はそれを救済と捉えている。
人類とは価値観がそもそも違いすぎる。故に、人間――英霊ベースであるナイトハルトにも理解できない部分は多かった。
「は。これこそすべての命が尽き果てた美しき世界。虚無こそ我ら歪虚の理想郷かと」
「ホントにそうじゃろうか? 確かに心地よい静寂……じゃが、何も胸打つ物もない」
「……我が王よ。不躾ながら、王がそのようなことを言うのはいかがなものかと」
ハヴァマールはゆっくりと立ち上がり、そしてナイトハルトと向き合う。
「余は考えておった。何故、強欲王メイルストロムはあのような最期を迎えたのか。故に旅をしてみた。わしには、ああいった……執着、か? それはなかったからな」
「お言葉ですが、なくてよいのでは? アレはそのせいで死んだようなもの。本来、歪虚王がヒトに敗れるはずもなし」
「わしも朧げに思い出したのだ。わしはこの世界に産み落とされた原初の歪虚王の一体。その頃のわしは言葉も持たず、モノを考えることもなかった。では、なぜ今のわしはこうしてお前と話をしているのだろう?」
腕を組み、ナイトハルトは思案する。
「陛下はこれまで数え切れぬ程の人間のマテリアルを取り込んだからではないでしょうか?」
「わしもそう思う。故にそれと知らぬだけで、わしもやはりヒトと同じ心を持っておったのだな」
二度頷き、そして王は空を見上げる。
「だからこそ、わしは救いたかったのだ。わしに挑み、絶望し死んでいった者たちは“生”に囚われていた。わしは――余は、ファナティックブラッドのやり方に乗ることにした」
「それは……あの得体の知れぬ、黙示騎士とかいう連中に協力すると?」
黙示騎士シュレディンガー……確か、あの奇妙な歪虚はそう名乗っていた。
世界を渡る力を持ち、そして邪神の協力者を求めている。暴食王は個人的なこだわりを持たず、邪神の方向性に恭順している。共闘の打診は妥当であった。
「私は反対です。この世界を離れるなど……」
「だろうな。ナイトハルト……特に貴様はまだ囚われておるのだ。貴様がまだ精霊であった頃……いや、生前からの因縁に」
王は静かに騎士の肩を叩き、そして力強く頷く。
「オルクス亡き今、余の軍団をまとめる力を持つのは貴様のみ。余は兵法に疎いからな」
「王……」
「オルクスもきっとそうだ。歪虚となっても消せぬ渇望を貪欲に求めたのだ。それも“暴食”の正しき在り方と肯定しよう。我が軍勢には哀しき想いを抱えたままの者が多い。当然だ、死とは本来救いであるというのに、それを歪虚と形を変えて生き延びさせている。これも余の咎よな」
「それは違います! あなたがいなければ、私たちは……!」
表情などない。だが、確かにハヴァマールは笑う。
「悔恨に満ちた者たちを導くのだ、ナイトハルト。既に余の傷は癒えた。守りは必要ない。思う存分、“武神”の力を振るうがよい」
ぐっと拳を握りしめ、騎士は跪く。
これが最期のチャンスだ。この戦いで決着をつけられなければ、その時は潔く諦めよう。
王が行くというのなら、どこまでもついていく。異世界だろうがなんだろうが、そこが自分の居場所だ。
「それではこのナイトハルト、必ずや帝国を破滅に導いてご覧に見せましょう」
「うむ。近くで応援しておるぞ」
「はっ! ……は? 近くで?」
「傷は癒えたし放浪の旅も飽いた。余も帝国領まで行こう。ナイトハルトよ、余に乗るがよい。足の速さでは余の方が上である」
確かにハヴァマールの移動力はナイトハルトより上だ。具体的にはリアルブルーの乗り物、新幹線くらいの最高速度が出るとか。
……が、全く止まれないし、曲がれない。一度走り出したら進路上にあるすべてのモノを粉砕し突き進むのみ。つまりすごくめだつ。
「あの、王。ここにお残りになられたほうがよろしいのでは。せめて怠惰王か憤怒王と合流するとか」
「……む。迷惑か?」
「いえまさかそんな」
「では乗るがよい。行くぞ、遥かなる南の地へ!!」
ガチャガチャと骨の身体を馬のように変形させたハヴァマールに渋々乗り込むナイトハルト。
(これは……上下が逆なのでは……)
負のマテリアルを用いたジェットブースターと化した暴食王は、大地をえぐり吹き飛ばしながら猛進を始めるのだった。




 「ハンターの皆さんのおかげで、少しずつ精霊の回収が進んできたところだったのですが……」
「ハンターの皆さんのおかげで、少しずつ精霊の回収が進んできたところだったのですが……」
帝都バルトアンデルス城。皇帝の執務室に重役を集め、カッテ・ウランゲル(kz0033)は困った様子で語り出す。
帝国領に顕現し始めた精霊たちを回収する為、各地で精霊と対峙したハンターたち。
四大精霊サンデルマンの力も借りて精霊を保護したり、その場を動けない者には歪虚除けのお守りを渡したりしていたのだが……。
「帝国領内で歪虚の活性化を確認しました。それも、理論上はあり得ないレベルの勢いです」
「理論上あり得ない……って?」
シェリル・マイヤーズ(ka0509)が首を傾げると、カッテは「説明が不足していましたね」と一礼し。
「帝国領内で活動していた暴食の歪虚は、その数を大きく減らしています。四霊剣を討伐した戦いの中で、敵の主戦力は殆ど倒してしまったんです。なのに、かなりの数の歪虚が突然確認されるようになった」
「つまり、どこからともなく帝国領にドバっと歪虚が降って沸いたわけでちゅか?」
北谷王子 朝騎(ka5818)の言葉に頷き、カッテは四大精霊のサンデルマンに視線を向ける。
「サンデルマン、あなたなら感じていますよね? ――暴食王ハヴァマールがこの国に入った事を」
その名前に重い沈黙が広がる。
“始祖たる七”、“暴食王”、“不死の剣王”――様々な呼び名を持つ暴食最強の個体、ハヴァマール。
彼の歪虚は闇光作戦後、血盟作戦でのシミュレーションを除けば誰もその姿を確認していない。
「ハヴァマールは自分のマテリアルを使って歪虚を生み出す能力があります。厳密には自分の体内という空間から召喚する、と言ったところでしょうか。ハヴァマールならば、一夜にして不死者の軍団を作り上げる事も不可能ではありません」
『……その通りだ。この地に非常に強力な負の波動を感じる……それこそ、精霊の気配すらかき消してしまいかねない程に』
「だが、動き方が地味だな。敵の出現数が増えただけで、帝都に攻め入ってくる様子もない。狙いは何だ?」
ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が呟くと、ガチャリと音を立てて身を乗り出す者がいた。
英霊アレクサンダー。シェリルと朝騎はこの英霊に状況を説明し、ここまで案内する為に同行したのだった。
『……狙いは私達、絶火騎士……強い力を持った英霊だろう。貴方達の話が事実なら、歪虚化した騎士王は、目覚めた私たちを見逃すまい』
「ん? するってぇと、あー……ハヴァマールはナイトハルトと行動を共にしてるってことか?」
壁際で退屈そうに話を聞いていた、ブラトンと名乗る大男は、ナイトハルトの名に興味を示したようだった。
「しかし、どうしてナイトハルトが絶火の騎士を狙うんだ?」
「ナイトハルトが“英雄伝説の集合体”という性質を持つ歪虚だから、ですね」
不破の剣豪ナイトハルトは、帝国領を切り開いた初代皇帝「ナイトハルト・モンドシャッテ」の英霊が歪虚化したもの――“ではない”。
勇者ナイトハルトの伝説は人々の間を一人歩きする間に様々な脚色を加えられ、歪んだ物語を紡いだ。
その中には複数の絶火騎士の伝承も盛り込まれていることだろう。
つまりあれは複数の伝承が融合して生み出された、人々にとって都合のいい英雄――正義の体現者であったはずだ。
そう、歪虚に落とされ、完全に歪んでしまう前は……。
「ナイトハルトにとって、絶火騎士の英霊はこれ以上なく相性のいいマテリアル供給源であると同時に、自分自身の一部にも等しいと言えるでしょう」
『強い力を持った英霊を歪虚に奪われれば問題だが……それ以上に、英霊を歪虚化されるのが危険だな……』
『私に……英霊探しの手伝いをさせてもらえないだろうか?』
重苦しく呟くサンデルマンに対し、英霊アレクサンダーは自らの胸に手を当て進言する。
『私も絶火の騎士……それも、“仲間を集める為に旅をした伝承”を持つ英霊だ。私とナイトハルトは世界を旅し、その途中で多くの騎士を仲間に迎え入れた』
「つまり……アレクサンダー、あなたには他の絶火騎士の場所がわかると?」
ゆっくりと大男が頷くと、カッテは口元に手をやり思案する。
「……わかりました。アレクサンダー、分かる範囲、大雑把で構いません。力を感じる方向、その強さを教えてください。サンデルマンの情報と照らし合わせ、絶火騎士の居場所を絞り込みます」
「アレクサンダー……旅に出るの?」
『ああ……。貴女たちには、随分と世話になった。おかげで未来……いや、現代の事も少しは理解したつもりだ』
巨大すぎる身体を窮屈そうに折りながら、英霊はシェリルと朝騎の肩を叩く。
「まあ、どうせ絶火騎士の探索にはハンターも動員されるでちゅし、すぐに再会する事になりそうでちゅね」
「うん……そうだね。また……会おうね? アレクサンダー」
『騎士の誇りに賭けて』
「当然だが、絶火騎士以外の精霊も襲われる事だろう。これまで以上に保護を急ぐ必要がある。……これは人類と歪虚による、精霊の争奪戦になるぞ」
苦々しく、しかし覚悟を決めた様子でヴィルヘルミナはそう締めくくった。

 「ふう……こんなものか」
「ふう……こんなものか」
帝国領に入った暴食王ハヴァマールと不破の剣豪ナイトハルトは、かつて闇光作戦の戦場となったフレーベルニンゲン州に訪れていた。
そしてそこで多数の暴食の歪虚をハヴァマールの“体内”から引きずり出し、それらを帝国領各地へと放つのだ。
「我が王の手を煩わせ、申し訳ございません」
「貴様のグロル・リッターは軒並みヒトの狩人に敗れてしまったからのう。とはいえ、新たに作る事も出来たのではないか?」
ナイトハルトはかつてグロル・リッターと呼ばれるデュラハンの騎士団を率いていた。
いや、厳密にはナイトハルトを慕った亡霊たちが勝手にそう名乗っていただけで、ナイトハルトにそのつもりはなかったのだが。
「貴様には亡霊であれ騎士を引き付ける魅力がある。それを使えば余の手勢など要らぬだろうに」
騎士は首を垂れたまま黙り込んでいる。その様子に王は小さく笑う。
「つくづく不器用だな、ナイトハルト。“王扱い”を嫌うのは、余を慮ってのことか?」
「いえ、それは……」
「暴食に王は一人で良い、自分はその器ではない……やれやれ、余計な事ばかり考えおる。まあ良い、そこは余がカバーしよう」
「重ね重ね、申し訳ありません……しかし、直に尖兵は不要となります」
「――ほう? 本気を出すか、ナイトハルト」
ゆっくりと立ち上がり、ナイトハルトはその腰に下げた剣を抜く。
ぼろぼろに刃毀れした――しかし、異様な美しさを漂わせる刃。これぞ魔剣と呼ぶに相応しい。
「はい。“剣”を使います」
ナイトハルトは“剣豪”と呼ばれ、ありとあらゆる武具を使いこなす武人だ。
暴食は本来武術を扱えない。戦闘に理屈を持ち込むことを嫌うためだ。
しかし、この剣士は“武術”の概念精霊でもあった男。武は思考ではなく呼吸に等しい。
だというのに、何故か剣を使わず徒手空拳で戦っていた。つまり、何らかの理由で加減していたのだ。
「帝国領に目覚めた絶火の騎士……私と同じ伝承を持つ英霊を食らえば、私は完全になります」
「そういえば忘れておったわ。貴様は――まだまだ強くなるのだったな」
ナイトハルトは英霊らの末路。物語の終着点だ。
そこから道を逆走するように英霊を食らっていけば、彼の物語は真の意味で完成を見る。
「その時には、余をも超える歪虚が生まれるやもしれぬな」
「それは買いかぶりすぎですが――真に迫る事は出来ましょう」
「ふはは。さて征くか。場所はわかるのだろう?」
「同じ釜の飯を食った仲間です。方角くらいはわかります」
「では虱潰しだ。暴食の名に相応しくな」
再び馬の姿に変形したハヴァマールに跨り、騎士は夜の平原へと駆け出す。
精霊を巡る人類と暴食の対決は、ここに本格的な開戦を迎えようとしていた。





 「……流石は四霊剣最強と謳われた不破の剣豪だ。まったく、恐れ入った強さだよ」
「……流石は四霊剣最強と謳われた不破の剣豪だ。まったく、恐れ入った強さだよ」
ハンターの報告書を片手にヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)はため息を零す。
これまでもナイトハルトがハンターと交戦する事はあったし、その時は何とか撃退に成功している。
だが、それはナイトハルトが本気ではなかった為だ。
まるで彼は――恐らく本人もそうとは知らぬ間に――ハンターの成長を待ち、促すように立ち回ってきた。
そして今回、その育ち切った果実を刈り取るかのように、蓄えた圧倒的な力を振るおうとしている。
「奴はかつて俺やヒルデブラント、タングラムにゼナイド……その他諸々、国家戦力の筆頭を束ねて挑んだ北伐戦で帝国軍を返り討ちにした歪虚だ。元々四霊剣の中でも頭一つ抜けちゃいたが、まさかここまでとはな……」
オズワルド(kz0027)はやけくそ気味に紫煙をぐっと吸い込み、ため息を共に吐き出す。
「オマケに暴食王まで一緒に行動しているとなっちゃお手上げだぜ?」
「いえ、案外そうでもありませんよ? 事実、ハンターの協力を得た精霊の保護作戦は順調に進んでいます」
カッテ・ウランゲル(kz0033)は指先で唇を撫でながら、デスクに広げた地図を指さす。
「こちらには四大精霊サンデルマン様の加護もありますからね。元々探知系の能力に優れるわけではないナイトハルトには先手を打てています」
もう少し精霊保護には手間取ると思われていたが、ハンターの活躍はなかなかのもので、ほとんど失敗らしい失敗もない。
おかげでコロッセオ・シングスピラに臨時設置された精霊避難所にはどんどん精霊が集まっている。
「……しかし、だからこそいずれ敵は帝都を目指してくるでしょうね。一か所に集まっている精霊をまとめて喰らう好機ですから」
「四大精霊の能力で隠すにも限界があるからなァ……やっぱりお手上げじゃねぇのか?」
「現時点でも、戦力を集中して投入すれば迎撃はできると思います。しかし、こちらも相応の被害を覚悟しなければなりません」
既に歪虚王を複数体葬っているハンター達だ。帝国軍が全力でサポートすれば、暴食王に拮抗する事は可能だろう。
だが、絶対の勝利などあり得ない。ハヴァマールとナイトハルトが同時に攻めてくれば、被害は確実に帝都にも及ぶだろう。
「特に暴食王の能力は厄介です。彼は生体マテリアルの吸収に特化していますから、精霊にとっては天敵も良い所です」
「せめてナイトハルトの方だけでもなんとかできりゃあいいんだがな……」
オズワルドと勝手の話を聞きながら黙り込んでいたヴィルヘルミナだが、何かを思いついたように「よし」と一声発すると。
「――ナイトハルトを弱体化する方法が、ないわけでもない」
「……なにぃ?」
「それは本当ですか、陛下?」
「ああ。というか、まあ、方法自体はシンプルなんだ。我が弟よ、ナイトハルトの強さの根幹どこにあると思う?」
カッテは腰に手を当て思案する。いや、思案するまでもないのだが……姉の言葉の裏まで見通す必要があった。
「ナイトハルトは帝国の勇者伝説、即ち初代皇帝ナイトハルト・モンドシャッテの英霊をベースにしています」
「そうだ。ではそのナイトハルトは何故強い?」
「――“強いと誰もが思っているから”です」
元々、ナイトハルトには“対峙する者の想いを反映する”傾向があった。
例えば好戦的なハンターが対峙すれば暴力で応える。対話を望むハンターには静寂で応える。
「この国の人間ならば誰でも知っている、ナイトハルトの伝説。それは人間だけではなく、亜人の間にも広まっています」
「そうだ。彼は大きく分けて二つの想いを向けられている。最強の騎士にして最悪の征服者――畏敬の念こそ、奴の主食なわけだ」
「信仰の影響を受けるのは英霊だった頃の話。歪虚には関係ないんじゃねぇのか?」
「いや。歪んだ信仰が歪虚の力となってしまうケースはある。これまでにも帝国領では度々確認されているだろう?」
「それにナイトハルトはただの英霊ではありません。というか、彼はナイトハルトですらない。“誰もが望み、誰もが願った、誰かにとって都合のいい正義の代弁者”にすぎなかった」
英霊とは受動的な存在だが、その中でもナイトハルトは群を抜いていた。
人間にとっての味方、そして亜人にとっての敵。彼は本来あり得ない事に、二種類の信仰を得て生まれてしまっている。
「歪虚化した今でも、そういった自分に向けられる想いを――信仰をマテリアルとして吸収している。そういう能力があっても不思議ではありません」
「おいおい……その理屈だと、帝国がある限りあいつは無敵って事になっちまうぞ?」
「オズワルドの言う通りだ。奴はこと、この帝国領の中で戦う限り絶対的な強さを誇る。故に、奴を倒すには帝国という国そのものを変える必要がある」
随分と大げさな結論だが、確かに言わんとすることは理解できる。
帝国という国が今の形であるならば、ナイトハルトは倒せない。ならば、帝国と今とは違う形にしてしまえばいい。
「簡単に仰いますが……その作戦、私は反対ですよ?」
「ん? もう私が何をしようとしているのかわかったのか?」
「貴女は記憶にないでしょうが、これでも生まれた時からの付き合いですからね……」
抱えていたファイリングされた資料をめくり、カッテは目を細める。
「なるほど……花の精霊フィー・フローレ等は有利に働くでしょう。しかし、ネグローリのような英霊は……」
「それはそれでいいんだ。むしろ必要だと思うがね」
「……本気ですか?」
「ああ。どこかでケリをつけなければならない問題だった……そう思わないか?」
姉弟が何の話をしているのか、オズワルドにはさっぱりわからなかった。
だが、ヴィルヘルミナの横顔には強い決意が満ちている。こういう時、何かを言っても無駄なのだ。
「ハァ……姉弟で勝手に決めやがって。んで、そいつはどれくらいかかるんだ?」
「資料集めや各所へのアポイントメントで少々かかります。その間にナイトハルトに先手を取られると私たちの負けですよ?」
「うむ。なので、時間稼ぎが必要だな。ハンターと……あの男にナイトハルトの注意を引いてもらうとしよう」
話は決まったと言わんばかりに歩き出すヴィルヘルミナ。
「――始めるぞ。歪んだ歴史を、正しい形に戻すんだ」
 「――今日、諸君らに集まってもらったのは他でもない。我が国にとって避けては通れない、ある一つの重要な事実について、諸君らに是非を問う為である」
「――今日、諸君らに集まってもらったのは他でもない。我が国にとって避けては通れない、ある一つの重要な事実について、諸君らに是非を問う為である」
帝都バルトアンデルス城に集められた民衆が握りしめているのは、帝都の新聞社がばらまいたビラ。
帝国民にとって、新聞社のビラというのは時に現政府と反政府組織「ヴルツァライヒ」との対立を煽るものだった。
だが、今回は違う。これは、現政権――皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)の意思で流布されたものだ。
壇上に立つ皇帝は、眼下の民衆を眺めながら、張り上げた……しかし威厳にも似た落ち着きを以て語り掛ける。
「私達は、ゾンネンシュトラール帝国は。これまで果たして、“正義”であっただろうか――?」

 「……そんな質問に国民が応じられるとでも?」
「……そんな質問に国民が応じられるとでも?」
城の応接室で、ユレイテル・エルフハイム(kz0085)は溜息交じりに呟いた。
ヴィルヘルミナの真の目的を達成するためには、広い範囲の協力を得る必要があった。
その中の筆頭というべきが、亜人たち。領内最大の亜人コミュニティであるエルフハイムは特に重要な協力者だ。
「君たちエルフの一部が暴動を起こした神森事件。それも、元を正せば帝国という国の興りに問題があった」
「それは……それを、皇帝陛下御自らが口にしてよいのか?」
「良くはないな。良くはない、とされてきた。政治的な判断で、私はそれを口にできなかった」
神森事件の時も、ヴィルヘルミナはあくまで外野だった。
介入したのはあくまでソサエティとハンターたち。帝国がしたのは、自分の身を護る程度の闘いのみだ。
「だが、その歴史の歪みが……“過ちを認めない”人間の想いが。ナイトハルト・モンドシャッテという伝説に力を与えている」
「つまり、あんたはナイトハルトに力を与えている伝説をぶっ壊して奴を討ち取ろうってわけだ。そのために俺達エルフに謝罪し、その謝罪を受け入れろってか」
同席するもう一人の長老、ハジャ・エルフハイムが頬を掻く。
「そうだ。この地に国を築いた父祖――その正義により生じた諸君らへの悪辣を謝罪する」
「……かつての長老会が未だ健在ならば、その言葉を喜んだだろうか。それとも、怒り狂っただろうか」
ふっと、小さく微笑み。ユレイテルは首を横に振る。
「神森事件で私達は帝国に大きな借りがある。その申し出を断れる余力も、今はない。だが、全員を納得させるのは難しいだろう」
「ナイトハルトの力を削ぐには、過去のモメごとを清算するだけじゃ無理だぜ?」
「そこは問題ない。要は、もっと大きな力で打ち消せばよいのだ。信仰を上書きする。ちょうど君たちのイコンとなる浄化の器のように」
「それは……」
大多数の責務を、小さなイチに押し込むという非道だ。
英雄という生き物は。正義の味方という現象は、そうやって産み落とされる。
弱者にとって都合のいい怪物。誰かの願いの化身。“気持ちよく責任を転嫁できる”者こそ、英雄なのだ。
「心配するな。同じ轍は踏まない」
それは“ひとつ”でなければよい。そして、“他人事”でもいけない。
誰もが望み。願いを重ね。しかし、それは遠い遠い、誰の手も届かない幻想ではなく。
願えばそこに足を踏み入れ。肩を並べ。友となり、あるいは自分も、物語の主人公になれるような――。
「私達は、同じ太陽の旗の下に集い、産まれ、そして歴史を紡いできた。私達の悲願は歪虚を討ち滅ぼし、この世界を守護すること。……それはいい。だが、その大義の為に、あまりにも多くの物を犠牲にしてきた」
この国を作るために、伝説の騎士たちが行った亜人への侵略行為。
精霊との繋がりを断ち切るほどの、マテリアルの乱用とそれに由来する環境汚染。
そして何より――歪虚と戦う兵士として駆り立てられた、若者たちの命。
「私はそれらを間違いだったとは言わない。歴史という物語に生きたすべての者たちが“今”を作っている。何か一つでもボタンを掛け違えたなら、今はなかっただろう。だが――!」
ほんの、もう少しだけ。
あと一歩、お互いが歩み寄れていたら?
刃を交える前に。それ以外の方法を模索出来ていたら?
「私は正義を願い続ける。だが、“最善”ではないのだ。ヒトは間違える。最高の結果を求め続けることは難しい。その失敗と、挫折と向き合った時に考えなければいけないのは、目を反らし逃げ出すことではない。その現実と向き合い、戦うことではないだろうか?」
――ヴィルヘルミナ・ウランゲルに、記憶はない。
しかしだからこそ、彼女は自分の行いすべてを正しかったとは思わない。
他人から聞いた、自分で調べた過去。その一つ一つを第三者として客観視し、それでも同じ夢を見た。
「間違いもある。最善ではない時もある。私達は成長する。ひとつひとつの戦い、出来事。諸君らはその中で魂を磨き、信念と向き合い、過去を顧みる強さを得た」
戸惑う民衆に、彼女の言葉はまだ届かない。
だが、それでいい。まずは切欠を与えること。
“わからない”ことを、“議論”させること。
「私は、革命戦争により失われたこの国の正しい歴史を――公表する! そしてこのゾンネンシュトラールの地に生きるすべての種族、すべての精霊、ありとあらゆる力を一つにすることを望む! どうか、諸君らも知ってほしい。そして力を貸して欲しい」
すっと息を吸い。そして、その名を告げる。
「我々はこれより、四霊剣――不破の剣豪、ナイトハルト・モンドシャッテ討伐作戦の開始を宣言する!」

 「そもそも、彼の四霊剣がナイトハルト・モンドシャッテであることは、機密情報でした」
「そもそも、彼の四霊剣がナイトハルト・モンドシャッテであることは、機密情報でした」
作戦準備で慌ただしくなる場内で、カッテ・ウランゲル(kz0033)は四大精霊サンデルマンと向き合う。
「絶対的な正義の象徴であった建国の勇者ナイトハルトが敵としてこの国を滅ぼそうとする現実を民衆が受け入れるには時間がかかるでしょう」
『……ああ。この国の正義が揺らいでいるのを感じる』
「過去に亜人を迫害した歴史を政府自ら公表しましたしね。元々、この国の正義は有名無実にすぎない。国民も薄々は気づいていた。それなのに戦うことを止められなかったのは、恐れていたからです」
父祖が始めた戦いを、途中で止めてしまったら?
過去の過ちを、今の成果で洗い流せないなら?
まだ、なんの答えも得ていない戦争を辞めてしまったら、その時この国はどうなってしまうのだろう?
「悪いことをしたと認められないのは、相手が許してくれないかもしれないから。その責任の重さに、押しつぶされてしまうから」
『………………』
「下らないとお思いでしょう。でも、人間なんてそんな物です。だから、許しを得る事には大きな価値があります」
帝国は様々な種族が、主義主張がないまぜの坩堝だ。
だが、これまでの歴史の中で、少しずつすべては変わってきている。
「ボラ族のような辺境からの移民も……。ブラストエッジのコボルドや、エルフハイムのエルフたちも、力を貸してくれます。難しい交渉でしたが、私も皇帝代理人として尽力しました。後は陛下の作戦が吉と出るか、凶と出るか……」
『正義の揺らぎは、この国に混沌を齎す……このままでは自らの正義に押しつぶされかねない』
「大丈夫です。彼女はそういうところも考えている人ですから」
『……信じているのだな』
「はい。ですから、私たちの作戦がもしも精霊にとって忌むべきものではなかったら。どうか、貴方達の力を貸していただきたいのです」
『……革命者の血、か……』
サンデルマンは正義の精霊。故に、正義の色を誰よりも純粋に見抜くことができる。
目の前の少年や、皇帝は――まるで正義らしい正義を胸に抱いてはいない。
“何も正しくないと思い知りながら、正しいふりをしている”のだ。
そしてそれを承知の上で。見抜かれていると知った上で、サンデルマンと向き合っている。
「私達ウランゲルの血は、より良き世界を求めて革命を起こした簒奪者の血族。私達は知っています。この世界に――正義の味方などいてはならないのだと」
『自分たちの行いは……革命は、間違いであったと?』
「いいえ。革命はまだ終わっていないのです。国という仕組みは、所詮はヒトを囲うもの。真の変革は、今を生きる者ひとりひとりの胸の奥にあるのです」
ヴィルヘルミナは、それを成し遂げようとしている。
きっとずっと、そうしたかった。でも、世界はまだそこに至っていなかった。
変わり続けたからこそ見える物がある。感じられる物がある。信じられる物が――今ならば、あると言える。
「信じましょう――彼らを」






 『ふぅむ……あれが精霊たちを保護しているコロッセオか?』
『ふぅむ……あれが精霊たちを保護しているコロッセオか?』
帝都の程近くにある、コロッセオ・シングスピラ。
そこは今や保護した精霊を匿う避難所。四大精霊サンデルマンの力で歪虚の探知を逃れてきたが、精霊が集まれば集まる程隠し通すのは困難となる。
故に暴食王ハヴァマールと不破の剣豪ナイトハルトもこの場所に辿り着いたわけだが……。
突然、頭上にズトンという音と共に光が瞬いた。
二体の歪虚には理解できるはずもなかったが、それはリーゼロッテ・クリューガー(kz0037)が作り出したマテリアル花火であった。
次々に打ち上がり花を咲かせる光に呆然と立ち尽くす二体。更に、コロッセオからは勇壮な楽隊の奏でる音楽まで響いてくるではないか。
それが作戦の開始を告げる合図だったのだろうか。
無数の魔導トラックが次々と視界に入り、あっという間に二体の歪虚を包囲する。
だが、向けられているのは銃口ではない。これも二体には理解できるはずもなかったが――それはカメラであった。
「リアルブルーのカメラを応用して作った最新式の魔導カメラです。解像度もバッチリですねぇ♪」
「なんで俺達が“撮影”なんかしてるんだ……?」
「いいじゃないですかぁ、暇なんだし。流石に非覚醒者はあれだけの高位歪虚を前にしたら動けませんからね」
トラックの荷台から身を乗り出すクリケット(kz0093)は、荷台に備え付けられた大型のカメラを回す。
ナサニエル・カロッサ(kz0028)は送り込む映像を調整しながらインカムに話しかけた。
「こちら撮影チーム、準備OKです♪ 音声も拾ってま?す♪」
「わーははは! こういう面白そうな事こそ錬魔院の実力の見せどころなのよさ! おらーお前ら、しっかり美麗な映像と音声を国民に届けるのよさ!!」
帝都バルトアンデルス城前に作られたスタジオで映像を受け取ったブリジッタ・ビットマン(kz0119)腕を振り回す。
不本意な作業に駆り出された錬魔院のスタッフが繋いだ映像は、帝都のあちらこちらに作られた街頭モニターに映し出されている。
「皇子、バッチリなのよ! ぶちかませーいっ!」
「ありがとうございます、ブリジッタさん」
スタジオではカッテ・ウランゲル(kz0033)がマイクを手にウィンクを返す。
そしてスイッチを入れると、胸いっぱいに空気を吸い込んだ。
「――帝都の皆さん! この世界の真の英雄が誰か、知りたいですか????!?」
国民はポカーンとしているが、カッテは怯まない。すべて計算通り。
「これよりご覧いただくのは、“大悪党”に身を落としたかつての英雄、ナイトハルト・モンドシャッテとの一大決戦! 勝てばこの国は新たな正義に近づき! 負ければこの国はおしまいです!!」
どよめき、恐怖に引きつる民衆。それも計算通り。
「大英雄と相対するのは、我らが帝国軍の精鋭たち! そして我らが同胞となった亜人や移民の皆さん! ご覧ください、固い絆で結ばれた混成軍の登場です!」
ファンファーレと共に出撃する、帝国混成軍。
そこにはエルフハイムのエルフや辺境移民、はたまたコボルドやゴブリンまで混ざっている。
「この戦いの主役を忘れてはいけませんね。さあさあ、皆さんお待ちかね! ナイトハルトと戦う英雄“たち”、ハンターも登場です!」
『なんじゃ? 何が起きているのじゃ?』
『これは……まさか……!?』
首を傾げるハヴァマールとは異なり、ナイトハルトだけは現状を理解しつつあった。
その身を覆うオーラが不安定になっている。この国全体から供給されていた力が、少しずつ薄れているのだ。
『ぬ……? ナイトハルト、それは……?』
『私への信仰が……揺らぎ始めているようです』
それは、つまり。
自分以外の“誰か”へと、この国の想いが注がれているという事。
『……そうか。そういう事か……。ククク……ハーッハハハハ!!』
「さあ、皆さんはどちらを応援しますか? 悪の英雄ナイトハルト? それとも――私たちを何度も救ってくれた、正義の“ハンター”ですか!?」
誰か“ひとり”が英雄になっても、それは呪いでしかない。
問題解決のための暴力装置。都合が悪くなれば、打ち捨てられるだけ。
どんなに正義を望んでも。救済を泣き叫んでも。何度繰り返しても……。
英雄は救われない。正義の味方は報われない。
でも――それが、“ひとり”ではなかったら……?
闇光作戦や神森作戦で使用されたスペルアンカーで作られた結界。
そこに力を供給するのは、この決戦を見つめるすべての人々の想い。
それは曖昧で、風が吹けば消えてしまうような微かな想い。
だから、ハンターは見せつけなければならない。熱狂させなければならない。
笑い、歌い、何度でも立ち上がり。死の恐怖すら乗り越え、まるで約束された勝利を掴むように。
これが未来だと。これが正義だと。これが――英雄の生き様だと!

 『――人々の総意を信じるのか?』
『――人々の総意を信じるのか?』
兵士たちの先陣に立ち、風を受けるヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)にサンデルマンは語り掛ける。
「そうだ。私は人間が持つ正義を信じる。間違いを正し、自分たちで信じるべきものを選び取る力を信じる」
『それが及ばなかった時。ハンターが真の英雄と認められなかった時。この作戦は崩壊する』
「承知の上さ。でも――それでいいんだ」
人任せの決断ではいけない。
命を賭けた願いでなければ守れない。
「この世界に生きるすべての命が、いつか来る邪神との戦いに打ち勝てるのか。私は人間の可能性を信じる。だから――」
騎士は剣を抜き、大精霊の前に跪く。
「これは“誓い”だ。四大精霊サンデルマン、どうかご照覧あれ。我らの正義を今――星に誓おう」
『……承服した。お前たちの正義を見届けよう。我、四大精霊サンデルマンの名において、新たな英雄譚に“正義”の加護を』
「この映像を見る、正義に味方する皆さんは! 例外なく、“正義の味方”なのです! さあ、胸を張って選びましょう! 私たちの――正義を!!」
『我が王、お別れです。私はこの戦いからは逃れられない。勝っても負けても、それはもう“私”ではないでしょう』
『……で、あるな。良い。最後まで走れ。走り抜けよ、ナイトハルト。貴様の胸の炎のままに』
言葉にならぬ感謝の想いを礼で示し、壊れた英霊は走り出す。
走って走って、走り続けてきた。でもやっと見えたのだ……ゴールが。
(礼を言うぞ……狩人よ)
終わりない旅が終わる。彼らが用意してくれた幕引きから、逃げる事はできない。
その後ろ姿をじっと見つめ、王は足元に作った影より剣を引き抜いた。
『さて……四大精霊と来られては余も動かぬわけには行くまいよ』
それは個にして軍。
影より数え切れぬ程の歪虚を生み出し、王は歩み出す。
『力比べと行こうか。この星を守護する者たちよ――!』
●【天誓】プロローグノベル「望まれぬ救済」(9月29日更新)

カッテ・ウランゲル

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

サンデルマン
山のように報告書が積まれたデスクを前に、カッテ・ウランゲル(kz0033)は剣呑に呟く。
血盟作戦以後、世界各地に出現した精霊たち。その保護は帝国でも続けられていた。
保護した精霊は大精霊サンデルマンがコロッセオ・シングスピラにまとめてくれるのだが……肝心の精霊が中々保護できない。
帝国兵が遭遇しても精霊は逃げてしまったりする。放置すれば歪虚に襲われる可能性も高いのだが……。
「帝国領に出現する精霊は人間を警戒しています。比較的ヒトに近しい“英霊”であれば対話できるケースもあるのですが」
精霊と言っても、細分化すればいくつかの種類がある。
中でも自然に宿る精霊である“自然精霊”、これが帝国にとっては厄介だった。
「元々、クリムゾンウェストの人々は大なり小なり精霊、すなわち自然と共存していました。しかし帝国はその自然から離れる形で発展を遂げています」
自然とは気まぐれ――アトランダムな存在だ。
ヒトに恩恵を与えもするが、何かを奪いもする。その気まぐれを脱却し、恩恵だけを求めたのが機導術だと言えるだろう。
自然本来の法則性を捻じ曲げる、錬金術の発展形。元々この国と自然は水と油なのだ。
「ふむ……ここはひとつ、大精霊のアドバイスなど頂けるとありがたいのだが?」
ごそっと報告書の山を退けて顔を覗かせたヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、その書類の山の上にちょこんと腰かけたマスコット人形に問いかける。
それは厳密にはマスコット人形ではなく、ヴィルヘルミナの姿形を模した小さな精霊だ。が、その実態は大きな精霊、大精霊サンデルマン。……ややこしいが。
「空気の問題かもしれないな」
「空気……陛下が最も読めないモノですね」
「フッ、我が弟君に良いことを教えてやろう。私は空気を読めないのではない。あえて読まないのだよ」
「陛下、それは受け取り手からすれば同じことです。しかし、空気ですか……。確かに私も聞き覚えがあります」
ヒトと精霊は実は密接な関係にある。
この世界におけるありとあらゆる生物種の中で、唯一人間だけが“精神活動だけ”で精霊に影響を及ぼせる。
「ヒトが持つ生体マテリアルは思考活動を発生源とする……つまり意識、自我といったものをトリガーにしているという説もあります。だから大勢のヒトの信仰が精霊の力になったり、プラスの感情が負のマテリアルを浄化すると」
「ふむ。考えてみると奇妙な関係性だな」
「むしろ正しいのでは? 大精霊……クリムゾンウェストが私たちをこの星の抗体として生み出したのなら、ですが」
カッテは唇を撫でながら、その言葉の意味を深く思考する。が、今はそれよりも……。
「空気というのはつまり、この国の人々が精霊を受け入れていない、そういった総意が存在していると?」
「その通りだ。この国の人間は他の人間に比べても特に身勝手だ。見たいように見、聞きたいことだけを聞く」
「「耳が痛い」」
二人同時に肩を落とす。それもこれも、この国の歴史の闇によるものだろう。
どの国家も、集団も常に矛盾は抱える。だが革命を経たこの国の民は知っているのだ。力こそがすべて、力こそが正義なのだと。
「臣民に精霊のことを説いても理解は得られないでしょう。彼らにとって精霊、自然は自分たちの糧でしかありません。ここは陛下お得意の頓智で何とかなりませんか?」
「我が弟君にもう一つ良いことを教えてやろう。私は頓智が効いているのではなく、勘が鋭いのだ。“降ってこない”と動けん」
「天才と何やらは紙一重ですね……仕方ありません、リーゼロッテ女史にでも協力を依頼しましょう」
「我々よりも精霊に詳しい者たちに力を借りたほうが良いのかもしれんな」
かつてグラズヘイム王国北部辺境領と呼ばれたこの土地は、元々人間種の支配領域ではない。
この土地の精霊と共存していたのは先住民である亜人たちだ。だが、彼らの精霊との繋がり――信仰は、帝国により断たれてしまった。
ヒトは望んで自らの手で精霊との関係性を破壊している――。
それを今更取り戻したいというのは、虫のいい話なのだろう。

ハヴァマール

ナイトハルト
世界に七体しか存在しない、歪虚眷属の頂点。“始祖たる七”とも呼ばれし者。
彼は人類の生活圏から遥か北――星の傷跡を擁するリグ・サンガマの向こう側、遥か昔に邪神ファナティックブラッドが滅ぼしたという、世界の“裏側”に立っていた。
生命の枯渇した、虚無の領域。歪虚の支配状態が長らく続き、星が壊死した場所は虚無となる。
漆黒の光が降り注ぐ幻想的な光景は、クリムゾンウェストが重く病んでいる事を意味していた。
だが、最近この虚無の領域に突如として大地が蘇りつつある。エバーグリーンから、一部の土地が転移してきているのだ。
「星とは……無とは……実に不思議なものよ。そうは思わぬか、ナイトハルト」
どっかりと地べたに胡坐をかいた王の言葉に、不破の剣豪ナイトハルトは答えあぐねていた。
この王は偉大にして雄大。まるで深く暗い深海のような穏やかさを持つ。
彼は“死”の概念の体現者だ。死は生物にとって忌むべき終わりだか、彼はそれを救済と捉えている。
人類とは価値観がそもそも違いすぎる。故に、人間――英霊ベースであるナイトハルトにも理解できない部分は多かった。
「は。これこそすべての命が尽き果てた美しき世界。虚無こそ我ら歪虚の理想郷かと」
「ホントにそうじゃろうか? 確かに心地よい静寂……じゃが、何も胸打つ物もない」
「……我が王よ。不躾ながら、王がそのようなことを言うのはいかがなものかと」
ハヴァマールはゆっくりと立ち上がり、そしてナイトハルトと向き合う。
「余は考えておった。何故、強欲王メイルストロムはあのような最期を迎えたのか。故に旅をしてみた。わしには、ああいった……執着、か? それはなかったからな」
「お言葉ですが、なくてよいのでは? アレはそのせいで死んだようなもの。本来、歪虚王がヒトに敗れるはずもなし」
「わしも朧げに思い出したのだ。わしはこの世界に産み落とされた原初の歪虚王の一体。その頃のわしは言葉も持たず、モノを考えることもなかった。では、なぜ今のわしはこうしてお前と話をしているのだろう?」
腕を組み、ナイトハルトは思案する。
「陛下はこれまで数え切れぬ程の人間のマテリアルを取り込んだからではないでしょうか?」
「わしもそう思う。故にそれと知らぬだけで、わしもやはりヒトと同じ心を持っておったのだな」
二度頷き、そして王は空を見上げる。
「だからこそ、わしは救いたかったのだ。わしに挑み、絶望し死んでいった者たちは“生”に囚われていた。わしは――余は、ファナティックブラッドのやり方に乗ることにした」
「それは……あの得体の知れぬ、黙示騎士とかいう連中に協力すると?」
黙示騎士シュレディンガー……確か、あの奇妙な歪虚はそう名乗っていた。
世界を渡る力を持ち、そして邪神の協力者を求めている。暴食王は個人的なこだわりを持たず、邪神の方向性に恭順している。共闘の打診は妥当であった。
「私は反対です。この世界を離れるなど……」
「だろうな。ナイトハルト……特に貴様はまだ囚われておるのだ。貴様がまだ精霊であった頃……いや、生前からの因縁に」
王は静かに騎士の肩を叩き、そして力強く頷く。
「オルクス亡き今、余の軍団をまとめる力を持つのは貴様のみ。余は兵法に疎いからな」
「王……」
「オルクスもきっとそうだ。歪虚となっても消せぬ渇望を貪欲に求めたのだ。それも“暴食”の正しき在り方と肯定しよう。我が軍勢には哀しき想いを抱えたままの者が多い。当然だ、死とは本来救いであるというのに、それを歪虚と形を変えて生き延びさせている。これも余の咎よな」
「それは違います! あなたがいなければ、私たちは……!」
表情などない。だが、確かにハヴァマールは笑う。
「悔恨に満ちた者たちを導くのだ、ナイトハルト。既に余の傷は癒えた。守りは必要ない。思う存分、“武神”の力を振るうがよい」
ぐっと拳を握りしめ、騎士は跪く。
これが最期のチャンスだ。この戦いで決着をつけられなければ、その時は潔く諦めよう。
王が行くというのなら、どこまでもついていく。異世界だろうがなんだろうが、そこが自分の居場所だ。
「それではこのナイトハルト、必ずや帝国を破滅に導いてご覧に見せましょう」
「うむ。近くで応援しておるぞ」
「はっ! ……は? 近くで?」
「傷は癒えたし放浪の旅も飽いた。余も帝国領まで行こう。ナイトハルトよ、余に乗るがよい。足の速さでは余の方が上である」
確かにハヴァマールの移動力はナイトハルトより上だ。具体的にはリアルブルーの乗り物、新幹線くらいの最高速度が出るとか。
……が、全く止まれないし、曲がれない。一度走り出したら進路上にあるすべてのモノを粉砕し突き進むのみ。つまりすごくめだつ。
「あの、王。ここにお残りになられたほうがよろしいのでは。せめて怠惰王か憤怒王と合流するとか」
「……む。迷惑か?」
「いえまさかそんな」
「では乗るがよい。行くぞ、遥かなる南の地へ!!」
ガチャガチャと骨の身体を馬のように変形させたハヴァマールに渋々乗り込むナイトハルト。
(これは……上下が逆なのでは……)
負のマテリアルを用いたジェットブースターと化した暴食王は、大地をえぐり吹き飛ばしながら猛進を始めるのだった。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「伝承争奪戦」(10月18日更新)

カッテ・ウランゲル

シェリル・マイヤーズ

北谷王子 朝騎

サンデルマン

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
帝都バルトアンデルス城。皇帝の執務室に重役を集め、カッテ・ウランゲル(kz0033)は困った様子で語り出す。
帝国領に顕現し始めた精霊たちを回収する為、各地で精霊と対峙したハンターたち。
四大精霊サンデルマンの力も借りて精霊を保護したり、その場を動けない者には歪虚除けのお守りを渡したりしていたのだが……。
「帝国領内で歪虚の活性化を確認しました。それも、理論上はあり得ないレベルの勢いです」
「理論上あり得ない……って?」
シェリル・マイヤーズ(ka0509)が首を傾げると、カッテは「説明が不足していましたね」と一礼し。
「帝国領内で活動していた暴食の歪虚は、その数を大きく減らしています。四霊剣を討伐した戦いの中で、敵の主戦力は殆ど倒してしまったんです。なのに、かなりの数の歪虚が突然確認されるようになった」
「つまり、どこからともなく帝国領にドバっと歪虚が降って沸いたわけでちゅか?」
北谷王子 朝騎(ka5818)の言葉に頷き、カッテは四大精霊のサンデルマンに視線を向ける。
「サンデルマン、あなたなら感じていますよね? ――暴食王ハヴァマールがこの国に入った事を」
その名前に重い沈黙が広がる。
“始祖たる七”、“暴食王”、“不死の剣王”――様々な呼び名を持つ暴食最強の個体、ハヴァマール。
彼の歪虚は闇光作戦後、血盟作戦でのシミュレーションを除けば誰もその姿を確認していない。
「ハヴァマールは自分のマテリアルを使って歪虚を生み出す能力があります。厳密には自分の体内という空間から召喚する、と言ったところでしょうか。ハヴァマールならば、一夜にして不死者の軍団を作り上げる事も不可能ではありません」
『……その通りだ。この地に非常に強力な負の波動を感じる……それこそ、精霊の気配すらかき消してしまいかねない程に』
「だが、動き方が地味だな。敵の出現数が増えただけで、帝都に攻め入ってくる様子もない。狙いは何だ?」
ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が呟くと、ガチャリと音を立てて身を乗り出す者がいた。
英霊アレクサンダー。シェリルと朝騎はこの英霊に状況を説明し、ここまで案内する為に同行したのだった。
『……狙いは私達、絶火騎士……強い力を持った英霊だろう。貴方達の話が事実なら、歪虚化した騎士王は、目覚めた私たちを見逃すまい』
「ん? するってぇと、あー……ハヴァマールはナイトハルトと行動を共にしてるってことか?」
壁際で退屈そうに話を聞いていた、ブラトンと名乗る大男は、ナイトハルトの名に興味を示したようだった。
「しかし、どうしてナイトハルトが絶火の騎士を狙うんだ?」
「ナイトハルトが“英雄伝説の集合体”という性質を持つ歪虚だから、ですね」
不破の剣豪ナイトハルトは、帝国領を切り開いた初代皇帝「ナイトハルト・モンドシャッテ」の英霊が歪虚化したもの――“ではない”。
勇者ナイトハルトの伝説は人々の間を一人歩きする間に様々な脚色を加えられ、歪んだ物語を紡いだ。
その中には複数の絶火騎士の伝承も盛り込まれていることだろう。
つまりあれは複数の伝承が融合して生み出された、人々にとって都合のいい英雄――正義の体現者であったはずだ。
そう、歪虚に落とされ、完全に歪んでしまう前は……。
「ナイトハルトにとって、絶火騎士の英霊はこれ以上なく相性のいいマテリアル供給源であると同時に、自分自身の一部にも等しいと言えるでしょう」
『強い力を持った英霊を歪虚に奪われれば問題だが……それ以上に、英霊を歪虚化されるのが危険だな……』
『私に……英霊探しの手伝いをさせてもらえないだろうか?』
重苦しく呟くサンデルマンに対し、英霊アレクサンダーは自らの胸に手を当て進言する。
『私も絶火の騎士……それも、“仲間を集める為に旅をした伝承”を持つ英霊だ。私とナイトハルトは世界を旅し、その途中で多くの騎士を仲間に迎え入れた』
「つまり……アレクサンダー、あなたには他の絶火騎士の場所がわかると?」
ゆっくりと大男が頷くと、カッテは口元に手をやり思案する。
「……わかりました。アレクサンダー、分かる範囲、大雑把で構いません。力を感じる方向、その強さを教えてください。サンデルマンの情報と照らし合わせ、絶火騎士の居場所を絞り込みます」
「アレクサンダー……旅に出るの?」
『ああ……。貴女たちには、随分と世話になった。おかげで未来……いや、現代の事も少しは理解したつもりだ』
巨大すぎる身体を窮屈そうに折りながら、英霊はシェリルと朝騎の肩を叩く。
「まあ、どうせ絶火騎士の探索にはハンターも動員されるでちゅし、すぐに再会する事になりそうでちゅね」
「うん……そうだね。また……会おうね? アレクサンダー」
『騎士の誇りに賭けて』
「当然だが、絶火騎士以外の精霊も襲われる事だろう。これまで以上に保護を急ぐ必要がある。……これは人類と歪虚による、精霊の争奪戦になるぞ」
苦々しく、しかし覚悟を決めた様子でヴィルヘルミナはそう締めくくった。

ハヴァマール

ナイトハルト
帝国領に入った暴食王ハヴァマールと不破の剣豪ナイトハルトは、かつて闇光作戦の戦場となったフレーベルニンゲン州に訪れていた。
そしてそこで多数の暴食の歪虚をハヴァマールの“体内”から引きずり出し、それらを帝国領各地へと放つのだ。
「我が王の手を煩わせ、申し訳ございません」
「貴様のグロル・リッターは軒並みヒトの狩人に敗れてしまったからのう。とはいえ、新たに作る事も出来たのではないか?」
ナイトハルトはかつてグロル・リッターと呼ばれるデュラハンの騎士団を率いていた。
いや、厳密にはナイトハルトを慕った亡霊たちが勝手にそう名乗っていただけで、ナイトハルトにそのつもりはなかったのだが。
「貴様には亡霊であれ騎士を引き付ける魅力がある。それを使えば余の手勢など要らぬだろうに」
騎士は首を垂れたまま黙り込んでいる。その様子に王は小さく笑う。
「つくづく不器用だな、ナイトハルト。“王扱い”を嫌うのは、余を慮ってのことか?」
「いえ、それは……」
「暴食に王は一人で良い、自分はその器ではない……やれやれ、余計な事ばかり考えおる。まあ良い、そこは余がカバーしよう」
「重ね重ね、申し訳ありません……しかし、直に尖兵は不要となります」
「――ほう? 本気を出すか、ナイトハルト」
ゆっくりと立ち上がり、ナイトハルトはその腰に下げた剣を抜く。
ぼろぼろに刃毀れした――しかし、異様な美しさを漂わせる刃。これぞ魔剣と呼ぶに相応しい。
「はい。“剣”を使います」
ナイトハルトは“剣豪”と呼ばれ、ありとあらゆる武具を使いこなす武人だ。
暴食は本来武術を扱えない。戦闘に理屈を持ち込むことを嫌うためだ。
しかし、この剣士は“武術”の概念精霊でもあった男。武は思考ではなく呼吸に等しい。
だというのに、何故か剣を使わず徒手空拳で戦っていた。つまり、何らかの理由で加減していたのだ。
「帝国領に目覚めた絶火の騎士……私と同じ伝承を持つ英霊を食らえば、私は完全になります」
「そういえば忘れておったわ。貴様は――まだまだ強くなるのだったな」
ナイトハルトは英霊らの末路。物語の終着点だ。
そこから道を逆走するように英霊を食らっていけば、彼の物語は真の意味で完成を見る。
「その時には、余をも超える歪虚が生まれるやもしれぬな」
「それは買いかぶりすぎですが――真に迫る事は出来ましょう」
「ふはは。さて征くか。場所はわかるのだろう?」
「同じ釜の飯を食った仲間です。方角くらいはわかります」
「では虱潰しだ。暴食の名に相応しくな」
再び馬の姿に変形したハヴァマールに跨り、騎士は夜の平原へと駆け出す。
精霊を巡る人類と暴食の対決は、ここに本格的な開戦を迎えようとしていた。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「形なき正義、正義なき容」(11月7日更新)

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

オズワルド

カッテ・ウランゲル

サンデルマン

ナイトハルト

ハヴァマール
ハンターの報告書を片手にヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)はため息を零す。
これまでもナイトハルトがハンターと交戦する事はあったし、その時は何とか撃退に成功している。
だが、それはナイトハルトが本気ではなかった為だ。
まるで彼は――恐らく本人もそうとは知らぬ間に――ハンターの成長を待ち、促すように立ち回ってきた。
そして今回、その育ち切った果実を刈り取るかのように、蓄えた圧倒的な力を振るおうとしている。
「奴はかつて俺やヒルデブラント、タングラムにゼナイド……その他諸々、国家戦力の筆頭を束ねて挑んだ北伐戦で帝国軍を返り討ちにした歪虚だ。元々四霊剣の中でも頭一つ抜けちゃいたが、まさかここまでとはな……」
オズワルド(kz0027)はやけくそ気味に紫煙をぐっと吸い込み、ため息を共に吐き出す。
「オマケに暴食王まで一緒に行動しているとなっちゃお手上げだぜ?」
「いえ、案外そうでもありませんよ? 事実、ハンターの協力を得た精霊の保護作戦は順調に進んでいます」
カッテ・ウランゲル(kz0033)は指先で唇を撫でながら、デスクに広げた地図を指さす。
「こちらには四大精霊サンデルマン様の加護もありますからね。元々探知系の能力に優れるわけではないナイトハルトには先手を打てています」
もう少し精霊保護には手間取ると思われていたが、ハンターの活躍はなかなかのもので、ほとんど失敗らしい失敗もない。
おかげでコロッセオ・シングスピラに臨時設置された精霊避難所にはどんどん精霊が集まっている。
「……しかし、だからこそいずれ敵は帝都を目指してくるでしょうね。一か所に集まっている精霊をまとめて喰らう好機ですから」
「四大精霊の能力で隠すにも限界があるからなァ……やっぱりお手上げじゃねぇのか?」
「現時点でも、戦力を集中して投入すれば迎撃はできると思います。しかし、こちらも相応の被害を覚悟しなければなりません」
既に歪虚王を複数体葬っているハンター達だ。帝国軍が全力でサポートすれば、暴食王に拮抗する事は可能だろう。
だが、絶対の勝利などあり得ない。ハヴァマールとナイトハルトが同時に攻めてくれば、被害は確実に帝都にも及ぶだろう。
「特に暴食王の能力は厄介です。彼は生体マテリアルの吸収に特化していますから、精霊にとっては天敵も良い所です」
「せめてナイトハルトの方だけでもなんとかできりゃあいいんだがな……」
オズワルドと勝手の話を聞きながら黙り込んでいたヴィルヘルミナだが、何かを思いついたように「よし」と一声発すると。
「――ナイトハルトを弱体化する方法が、ないわけでもない」
「……なにぃ?」
「それは本当ですか、陛下?」
「ああ。というか、まあ、方法自体はシンプルなんだ。我が弟よ、ナイトハルトの強さの根幹どこにあると思う?」
カッテは腰に手を当て思案する。いや、思案するまでもないのだが……姉の言葉の裏まで見通す必要があった。
「ナイトハルトは帝国の勇者伝説、即ち初代皇帝ナイトハルト・モンドシャッテの英霊をベースにしています」
「そうだ。ではそのナイトハルトは何故強い?」
「――“強いと誰もが思っているから”です」
元々、ナイトハルトには“対峙する者の想いを反映する”傾向があった。
例えば好戦的なハンターが対峙すれば暴力で応える。対話を望むハンターには静寂で応える。
「この国の人間ならば誰でも知っている、ナイトハルトの伝説。それは人間だけではなく、亜人の間にも広まっています」
「そうだ。彼は大きく分けて二つの想いを向けられている。最強の騎士にして最悪の征服者――畏敬の念こそ、奴の主食なわけだ」
「信仰の影響を受けるのは英霊だった頃の話。歪虚には関係ないんじゃねぇのか?」
「いや。歪んだ信仰が歪虚の力となってしまうケースはある。これまでにも帝国領では度々確認されているだろう?」
「それにナイトハルトはただの英霊ではありません。というか、彼はナイトハルトですらない。“誰もが望み、誰もが願った、誰かにとって都合のいい正義の代弁者”にすぎなかった」
英霊とは受動的な存在だが、その中でもナイトハルトは群を抜いていた。
人間にとっての味方、そして亜人にとっての敵。彼は本来あり得ない事に、二種類の信仰を得て生まれてしまっている。
「歪虚化した今でも、そういった自分に向けられる想いを――信仰をマテリアルとして吸収している。そういう能力があっても不思議ではありません」
「おいおい……その理屈だと、帝国がある限りあいつは無敵って事になっちまうぞ?」
「オズワルドの言う通りだ。奴はこと、この帝国領の中で戦う限り絶対的な強さを誇る。故に、奴を倒すには帝国という国そのものを変える必要がある」
随分と大げさな結論だが、確かに言わんとすることは理解できる。
帝国という国が今の形であるならば、ナイトハルトは倒せない。ならば、帝国と今とは違う形にしてしまえばいい。
「簡単に仰いますが……その作戦、私は反対ですよ?」
「ん? もう私が何をしようとしているのかわかったのか?」
「貴女は記憶にないでしょうが、これでも生まれた時からの付き合いですからね……」
抱えていたファイリングされた資料をめくり、カッテは目を細める。
「なるほど……花の精霊フィー・フローレ等は有利に働くでしょう。しかし、ネグローリのような英霊は……」
「それはそれでいいんだ。むしろ必要だと思うがね」
「……本気ですか?」
「ああ。どこかでケリをつけなければならない問題だった……そう思わないか?」
姉弟が何の話をしているのか、オズワルドにはさっぱりわからなかった。
だが、ヴィルヘルミナの横顔には強い決意が満ちている。こういう時、何かを言っても無駄なのだ。
「ハァ……姉弟で勝手に決めやがって。んで、そいつはどれくらいかかるんだ?」
「資料集めや各所へのアポイントメントで少々かかります。その間にナイトハルトに先手を取られると私たちの負けですよ?」
「うむ。なので、時間稼ぎが必要だな。ハンターと……あの男にナイトハルトの注意を引いてもらうとしよう」
話は決まったと言わんばかりに歩き出すヴィルヘルミナ。
「――始めるぞ。歪んだ歴史を、正しい形に戻すんだ」
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「災い、あるいは歌のように」(11月24日更新)

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
帝都バルトアンデルス城に集められた民衆が握りしめているのは、帝都の新聞社がばらまいたビラ。
帝国民にとって、新聞社のビラというのは時に現政府と反政府組織「ヴルツァライヒ」との対立を煽るものだった。
だが、今回は違う。これは、現政権――皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)の意思で流布されたものだ。
壇上に立つ皇帝は、眼下の民衆を眺めながら、張り上げた……しかし威厳にも似た落ち着きを以て語り掛ける。
「私達は、ゾンネンシュトラール帝国は。これまで果たして、“正義”であっただろうか――?」

ユレイテル・エルフハイム

ナイトハルト
城の応接室で、ユレイテル・エルフハイム(kz0085)は溜息交じりに呟いた。
ヴィルヘルミナの真の目的を達成するためには、広い範囲の協力を得る必要があった。
その中の筆頭というべきが、亜人たち。領内最大の亜人コミュニティであるエルフハイムは特に重要な協力者だ。
「君たちエルフの一部が暴動を起こした神森事件。それも、元を正せば帝国という国の興りに問題があった」
「それは……それを、皇帝陛下御自らが口にしてよいのか?」
「良くはないな。良くはない、とされてきた。政治的な判断で、私はそれを口にできなかった」
神森事件の時も、ヴィルヘルミナはあくまで外野だった。
介入したのはあくまでソサエティとハンターたち。帝国がしたのは、自分の身を護る程度の闘いのみだ。
「だが、その歴史の歪みが……“過ちを認めない”人間の想いが。ナイトハルト・モンドシャッテという伝説に力を与えている」
「つまり、あんたはナイトハルトに力を与えている伝説をぶっ壊して奴を討ち取ろうってわけだ。そのために俺達エルフに謝罪し、その謝罪を受け入れろってか」
同席するもう一人の長老、ハジャ・エルフハイムが頬を掻く。
「そうだ。この地に国を築いた父祖――その正義により生じた諸君らへの悪辣を謝罪する」
「……かつての長老会が未だ健在ならば、その言葉を喜んだだろうか。それとも、怒り狂っただろうか」
ふっと、小さく微笑み。ユレイテルは首を横に振る。
「神森事件で私達は帝国に大きな借りがある。その申し出を断れる余力も、今はない。だが、全員を納得させるのは難しいだろう」
「ナイトハルトの力を削ぐには、過去のモメごとを清算するだけじゃ無理だぜ?」
「そこは問題ない。要は、もっと大きな力で打ち消せばよいのだ。信仰を上書きする。ちょうど君たちのイコンとなる浄化の器のように」
「それは……」
大多数の責務を、小さなイチに押し込むという非道だ。
英雄という生き物は。正義の味方という現象は、そうやって産み落とされる。
弱者にとって都合のいい怪物。誰かの願いの化身。“気持ちよく責任を転嫁できる”者こそ、英雄なのだ。
「心配するな。同じ轍は踏まない」
それは“ひとつ”でなければよい。そして、“他人事”でもいけない。
誰もが望み。願いを重ね。しかし、それは遠い遠い、誰の手も届かない幻想ではなく。
願えばそこに足を踏み入れ。肩を並べ。友となり、あるいは自分も、物語の主人公になれるような――。
「私達は、同じ太陽の旗の下に集い、産まれ、そして歴史を紡いできた。私達の悲願は歪虚を討ち滅ぼし、この世界を守護すること。……それはいい。だが、その大義の為に、あまりにも多くの物を犠牲にしてきた」
この国を作るために、伝説の騎士たちが行った亜人への侵略行為。
精霊との繋がりを断ち切るほどの、マテリアルの乱用とそれに由来する環境汚染。
そして何より――歪虚と戦う兵士として駆り立てられた、若者たちの命。
「私はそれらを間違いだったとは言わない。歴史という物語に生きたすべての者たちが“今”を作っている。何か一つでもボタンを掛け違えたなら、今はなかっただろう。だが――!」
ほんの、もう少しだけ。
あと一歩、お互いが歩み寄れていたら?
刃を交える前に。それ以外の方法を模索出来ていたら?
「私は正義を願い続ける。だが、“最善”ではないのだ。ヒトは間違える。最高の結果を求め続けることは難しい。その失敗と、挫折と向き合った時に考えなければいけないのは、目を反らし逃げ出すことではない。その現実と向き合い、戦うことではないだろうか?」
――ヴィルヘルミナ・ウランゲルに、記憶はない。
しかしだからこそ、彼女は自分の行いすべてを正しかったとは思わない。
他人から聞いた、自分で調べた過去。その一つ一つを第三者として客観視し、それでも同じ夢を見た。
「間違いもある。最善ではない時もある。私達は成長する。ひとつひとつの戦い、出来事。諸君らはその中で魂を磨き、信念と向き合い、過去を顧みる強さを得た」
戸惑う民衆に、彼女の言葉はまだ届かない。
だが、それでいい。まずは切欠を与えること。
“わからない”ことを、“議論”させること。
「私は、革命戦争により失われたこの国の正しい歴史を――公表する! そしてこのゾンネンシュトラールの地に生きるすべての種族、すべての精霊、ありとあらゆる力を一つにすることを望む! どうか、諸君らも知ってほしい。そして力を貸して欲しい」
すっと息を吸い。そして、その名を告げる。
「我々はこれより、四霊剣――不破の剣豪、ナイトハルト・モンドシャッテ討伐作戦の開始を宣言する!」

カッテ・ウランゲル

サンデルマン
作戦準備で慌ただしくなる場内で、カッテ・ウランゲル(kz0033)は四大精霊サンデルマンと向き合う。
「絶対的な正義の象徴であった建国の勇者ナイトハルトが敵としてこの国を滅ぼそうとする現実を民衆が受け入れるには時間がかかるでしょう」
『……ああ。この国の正義が揺らいでいるのを感じる』
「過去に亜人を迫害した歴史を政府自ら公表しましたしね。元々、この国の正義は有名無実にすぎない。国民も薄々は気づいていた。それなのに戦うことを止められなかったのは、恐れていたからです」
父祖が始めた戦いを、途中で止めてしまったら?
過去の過ちを、今の成果で洗い流せないなら?
まだ、なんの答えも得ていない戦争を辞めてしまったら、その時この国はどうなってしまうのだろう?
「悪いことをしたと認められないのは、相手が許してくれないかもしれないから。その責任の重さに、押しつぶされてしまうから」
『………………』
「下らないとお思いでしょう。でも、人間なんてそんな物です。だから、許しを得る事には大きな価値があります」
帝国は様々な種族が、主義主張がないまぜの坩堝だ。
だが、これまでの歴史の中で、少しずつすべては変わってきている。
「ボラ族のような辺境からの移民も……。ブラストエッジのコボルドや、エルフハイムのエルフたちも、力を貸してくれます。難しい交渉でしたが、私も皇帝代理人として尽力しました。後は陛下の作戦が吉と出るか、凶と出るか……」
『正義の揺らぎは、この国に混沌を齎す……このままでは自らの正義に押しつぶされかねない』
「大丈夫です。彼女はそういうところも考えている人ですから」
『……信じているのだな』
「はい。ですから、私たちの作戦がもしも精霊にとって忌むべきものではなかったら。どうか、貴方達の力を貸していただきたいのです」
『……革命者の血、か……』
サンデルマンは正義の精霊。故に、正義の色を誰よりも純粋に見抜くことができる。
目の前の少年や、皇帝は――まるで正義らしい正義を胸に抱いてはいない。
“何も正しくないと思い知りながら、正しいふりをしている”のだ。
そしてそれを承知の上で。見抜かれていると知った上で、サンデルマンと向き合っている。
「私達ウランゲルの血は、より良き世界を求めて革命を起こした簒奪者の血族。私達は知っています。この世界に――正義の味方などいてはならないのだと」
『自分たちの行いは……革命は、間違いであったと?』
「いいえ。革命はまだ終わっていないのです。国という仕組みは、所詮はヒトを囲うもの。真の変革は、今を生きる者ひとりひとりの胸の奥にあるのです」
ヴィルヘルミナは、それを成し遂げようとしている。
きっとずっと、そうしたかった。でも、世界はまだそこに至っていなかった。
変わり続けたからこそ見える物がある。感じられる物がある。信じられる物が――今ならば、あると言える。
「信じましょう――彼らを」
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「ヒロイック・ファンタジー」(11月27日更新)

ハヴァマール

ナイトハルト

リーゼロッテ・クリューガー

クリケット

ナサニエル・カロッサ

ブリジッタ・ビットマン

カッテ・ウランゲル
帝都の程近くにある、コロッセオ・シングスピラ。
そこは今や保護した精霊を匿う避難所。四大精霊サンデルマンの力で歪虚の探知を逃れてきたが、精霊が集まれば集まる程隠し通すのは困難となる。
故に暴食王ハヴァマールと不破の剣豪ナイトハルトもこの場所に辿り着いたわけだが……。
突然、頭上にズトンという音と共に光が瞬いた。
二体の歪虚には理解できるはずもなかったが、それはリーゼロッテ・クリューガー(kz0037)が作り出したマテリアル花火であった。
次々に打ち上がり花を咲かせる光に呆然と立ち尽くす二体。更に、コロッセオからは勇壮な楽隊の奏でる音楽まで響いてくるではないか。
それが作戦の開始を告げる合図だったのだろうか。
無数の魔導トラックが次々と視界に入り、あっという間に二体の歪虚を包囲する。
だが、向けられているのは銃口ではない。これも二体には理解できるはずもなかったが――それはカメラであった。
「リアルブルーのカメラを応用して作った最新式の魔導カメラです。解像度もバッチリですねぇ♪」
「なんで俺達が“撮影”なんかしてるんだ……?」
「いいじゃないですかぁ、暇なんだし。流石に非覚醒者はあれだけの高位歪虚を前にしたら動けませんからね」
トラックの荷台から身を乗り出すクリケット(kz0093)は、荷台に備え付けられた大型のカメラを回す。
ナサニエル・カロッサ(kz0028)は送り込む映像を調整しながらインカムに話しかけた。
「こちら撮影チーム、準備OKです♪ 音声も拾ってま?す♪」
「わーははは! こういう面白そうな事こそ錬魔院の実力の見せどころなのよさ! おらーお前ら、しっかり美麗な映像と音声を国民に届けるのよさ!!」
帝都バルトアンデルス城前に作られたスタジオで映像を受け取ったブリジッタ・ビットマン(kz0119)腕を振り回す。
不本意な作業に駆り出された錬魔院のスタッフが繋いだ映像は、帝都のあちらこちらに作られた街頭モニターに映し出されている。
「皇子、バッチリなのよ! ぶちかませーいっ!」
「ありがとうございます、ブリジッタさん」
スタジオではカッテ・ウランゲル(kz0033)がマイクを手にウィンクを返す。
そしてスイッチを入れると、胸いっぱいに空気を吸い込んだ。
「――帝都の皆さん! この世界の真の英雄が誰か、知りたいですか????!?」
国民はポカーンとしているが、カッテは怯まない。すべて計算通り。
「これよりご覧いただくのは、“大悪党”に身を落としたかつての英雄、ナイトハルト・モンドシャッテとの一大決戦! 勝てばこの国は新たな正義に近づき! 負ければこの国はおしまいです!!」
どよめき、恐怖に引きつる民衆。それも計算通り。
「大英雄と相対するのは、我らが帝国軍の精鋭たち! そして我らが同胞となった亜人や移民の皆さん! ご覧ください、固い絆で結ばれた混成軍の登場です!」
ファンファーレと共に出撃する、帝国混成軍。
そこにはエルフハイムのエルフや辺境移民、はたまたコボルドやゴブリンまで混ざっている。
「この戦いの主役を忘れてはいけませんね。さあさあ、皆さんお待ちかね! ナイトハルトと戦う英雄“たち”、ハンターも登場です!」
『なんじゃ? 何が起きているのじゃ?』
『これは……まさか……!?』
首を傾げるハヴァマールとは異なり、ナイトハルトだけは現状を理解しつつあった。
その身を覆うオーラが不安定になっている。この国全体から供給されていた力が、少しずつ薄れているのだ。
『ぬ……? ナイトハルト、それは……?』
『私への信仰が……揺らぎ始めているようです』
それは、つまり。
自分以外の“誰か”へと、この国の想いが注がれているという事。
『……そうか。そういう事か……。ククク……ハーッハハハハ!!』
「さあ、皆さんはどちらを応援しますか? 悪の英雄ナイトハルト? それとも――私たちを何度も救ってくれた、正義の“ハンター”ですか!?」
誰か“ひとり”が英雄になっても、それは呪いでしかない。
問題解決のための暴力装置。都合が悪くなれば、打ち捨てられるだけ。
どんなに正義を望んでも。救済を泣き叫んでも。何度繰り返しても……。
英雄は救われない。正義の味方は報われない。
でも――それが、“ひとり”ではなかったら……?
闇光作戦や神森作戦で使用されたスペルアンカーで作られた結界。
そこに力を供給するのは、この決戦を見つめるすべての人々の想い。
それは曖昧で、風が吹けば消えてしまうような微かな想い。
だから、ハンターは見せつけなければならない。熱狂させなければならない。
笑い、歌い、何度でも立ち上がり。死の恐怖すら乗り越え、まるで約束された勝利を掴むように。
これが未来だと。これが正義だと。これが――英雄の生き様だと!

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

サンデルマン
兵士たちの先陣に立ち、風を受けるヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)にサンデルマンは語り掛ける。
「そうだ。私は人間が持つ正義を信じる。間違いを正し、自分たちで信じるべきものを選び取る力を信じる」
『それが及ばなかった時。ハンターが真の英雄と認められなかった時。この作戦は崩壊する』
「承知の上さ。でも――それでいいんだ」
人任せの決断ではいけない。
命を賭けた願いでなければ守れない。
「この世界に生きるすべての命が、いつか来る邪神との戦いに打ち勝てるのか。私は人間の可能性を信じる。だから――」
騎士は剣を抜き、大精霊の前に跪く。
「これは“誓い”だ。四大精霊サンデルマン、どうかご照覧あれ。我らの正義を今――星に誓おう」
『……承服した。お前たちの正義を見届けよう。我、四大精霊サンデルマンの名において、新たな英雄譚に“正義”の加護を』
「この映像を見る、正義に味方する皆さんは! 例外なく、“正義の味方”なのです! さあ、胸を張って選びましょう! 私たちの――正義を!!」
『我が王、お別れです。私はこの戦いからは逃れられない。勝っても負けても、それはもう“私”ではないでしょう』
『……で、あるな。良い。最後まで走れ。走り抜けよ、ナイトハルト。貴様の胸の炎のままに』
言葉にならぬ感謝の想いを礼で示し、壊れた英霊は走り出す。
走って走って、走り続けてきた。でもやっと見えたのだ……ゴールが。
(礼を言うぞ……狩人よ)
終わりない旅が終わる。彼らが用意してくれた幕引きから、逃げる事はできない。
その後ろ姿をじっと見つめ、王は足元に作った影より剣を引き抜いた。
『さて……四大精霊と来られては余も動かぬわけには行くまいよ』
それは個にして軍。
影より数え切れぬ程の歪虚を生み出し、王は歩み出す。
『力比べと行こうか。この星を守護する者たちよ――!』
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)





