ゲスト
(ka0000)
【羽冠】これまでの経緯



衣装の新調なんて提案してきたと思えば……そういうことですか。
……未だ至らぬ所ばかりのわたくしですけれど、
務めは果たさなければなりませんね……。
グラズヘイム王国王女:システィーナ・グラハム(kz0020)
更新情報(10月16日更新)
過去の【羽冠】ストーリーノベルを掲載しました。
【羽冠】ストーリーノベル
各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。
●プロローグ「歴史の歩み」(3月26日更新)
●歴史の一片
 はぁ、とセドリック・マクファーソン(kz0026)はため息をついて机上の羊皮紙を見つめた。
はぁ、とセドリック・マクファーソン(kz0026)はため息をついて机上の羊皮紙を見つめた。
近頃はこうして嘆息することがとみに増えた。
――ひたすらに祈りを捧げていたいものだ。
そんな穏やかな日常など十代の頃に聖堂教会に入ってからの数年しかなかったが、そのたった数年がひどく輝いている。身を清め、心を委ねて顔見知りと共に“光”を感じる日々。なんと得難い幸福であったか。
教会においては世俗に塗れた連中を次々と破門に追い込み、国政においてはこの王位なき時代に辣腕を振るうセドリックをしてそんな現実逃避に至らしめるのも、全てはこの机上の密書のせいだ。
破られた封蝋には国内一の大貴族マーロウ家の家紋。中には貴族らしい遠回しな文言でこんなことが書かれている。
『両家の仲も深まってきたからそろそろ王女殿下とうちの孫の婚姻を考える頃合いではないか』
この三ヶ月、何度となく読み返してきた密書だけに暗唱どころか手跡すら脳裏に浮かべることのできるセドリックだが、文章を思い出すたびに腸が煮えくり返りそうな激情が蘇る。
仲が深まっただと? 殿下が一度舞踏会に出ただけではないか!
うちの孫? 奴の孫など十を過ぎたばかりの幼子だろう!
密書を破り捨ててやりたい衝動を堪え、セドリックはぐっと眉間を指で押さえる。そして、ため息。この三ヶ月は暇さえあればこの繰り返しだった。
――せめて殿下が……。
いや、とセドリックは首を振る。どうにもならぬことを考えても仕方がない。現実を直視し“光”の御心に従う。それがエクラ教徒の在り方だ。努めて冷静に考えねばならない。
――奴の孫と殿下が政略結婚をすれば、どうなる?
マーロウ家の現当主ウェルズ・クリストフ・マーロウは王配の祖父として君臨する。未だ若い殿下らではあれを抑え切れないし、自分とて諸侯を束ね殿下の義父となったマーロウに抗するのは困難を極める。
では権勢を振るえるようになった奴は何をする?
歪虚を殺す。それも苛烈にだ。
その点だけを考えればそう悪くはない。目的は一致している。だがやり方が問題だ。
歪虚を殺す、ただその為にあらゆる生活を犠牲にする。
絶対にやらかす。これまでの言動と歪虚への敵意から鑑みて、マーロウは間違いなく歪虚討滅を国家の第一とする。
グラズヘイムという国家を総動員して歪虚を殺す。そこにあるのは人々の安寧ではなく、歪虚と同等の理不尽だ。戦う為に食べ、戦う為に戦う。それは“光”の御心に反するようにセドリックには思えた。
何がマーロウをそうさせているのかなど、そんなことは知らないしどうでもいい。
ただ、奴を自由にさせるべきでないし、その為にこそ政略結婚を成立させるわけにいかない。
――ではどうすればこの婚姻を回避し、それでいて貴族連中を黙らせることができる?
それはただ一つだ。
そしてセドリックは既に、それに向けた手を一つだけ打ってはいる。殿下の衣装を仕立てるという、一手とも呼べないただの準備だが。

 だがそうして秘密裡に諸々の準備を整え、最低限の根回しを行い、殿下には一気呵成に“その道”を駆け上がっていただく。それがこの政略結婚に対する最も有効な一手であるはずだ。
だがそうして秘密裡に諸々の準備を整え、最低限の根回しを行い、殿下には一気呵成に“その道”を駆け上がっていただく。それがこの政略結婚に対する最も有効な一手であるはずだ。
――もはや猶予はない。殿下にはお覚悟を決めていただかねばならぬな……。
衣装を仕立てさせた際に使ったハンター――ラィル・ファーディル・ラァドゥ(ka1929)。にも「そろそろ殿下の子ども扱いをやめろ」というようなことを言いたい放題に言われた。であれば心置きなく王女殿下には大人になっていただこうではないか。なに、使い勝手の良さそうなレイレリア・リナークシス(ka3872)などの人材も見かけたし、確かグリーヴ家やシャール家の者なども殿下の知己にいたはずだ。それだけハンターとの友好を深めてきた殿下ならば、貴族諸侯連合に対する大きな力として彼らに協力を仰ぐことができるだろう。(「【CF】庭園の光」)
セドリックは密書を懐に入れて椅子から立ち上がると、自らの執務室を出て部下たちに告げた。
「しばらく出る。決裁が必要なものは私の机に置いておくように」
王城の奥へと向かいながら先触れを出し、王女殿下との面会を急ぐ。
そうと決めてしまえば少しでも時間が惜しくなる。本来“それ”の準備には年単位の時間が必要なのだから、数ヶ月でやり遂げようと思えばいくら時があっても足りない。
セドリックは先触れから数分遅れで王女殿下の部屋まで辿り着くや、殿下と侍従長しか室内にいないことを確認して微笑を浮かべた。
「王女殿下、殿下には今夏、戴冠していただきます」
●イスルダの亡霊
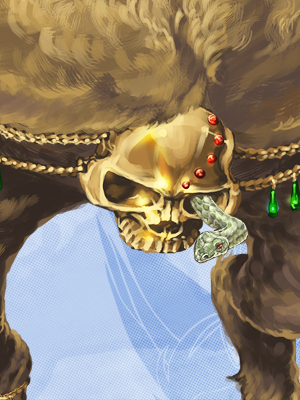
 「ブシ……全て上手くいった……ブシシ……いやまだだ、まだ笑ってはいかぬ……ブシシシ……」
「ブシ……全て上手くいった……ブシシ……いやまだだ、まだ笑ってはいかぬ……ブシシシ……」
小さな金の蛇となったベリアル(kz0203)。は聖堂教会の――ヴィオラ・フルブライト(kz0007)。などという女に拘束されたまま、船上からかつての拠点イスルダを見晴るかした。
ヴィオラはひどく冷たい目で見下ろし、淡々と片手で締め上げてくる。思わず「メ゛ェ゛ェ゛」と悲鳴を上げるベリアルに、女は無表情で告げる。
「妙な真似をすれば『死ねないように』してやりますから大人しくしているように」
「ブシ!? 死ねないように!?」
「可及的速やかにイスルダの現状把握と再開発の目途を立てなければならないので仕方なくお前如きを案内に使ってやっていますが、極論すれば案内などいなくとも大量に人を投入して限界まで働けば問題ないのです。……その余裕がないだけで」
「ブ、ブッシシシ、妙な真似などせぬ! 憎きメフィストメェが滅んだ歓びに浸っておっただけよ、ブシシシ……」
「ならばよいのです。私としては蛇も今度こそ滅ぼしてやりたいのですが」
されるがままになりながら、ベリアルはブシブシとほくそ笑む。
メフィストは死んだ。蛇となって一旦やり過ごすよう助言はくれたもののあの蜘蛛と似た臭いを感じたへクス某という男も動けない。強力な敵たり得るエリ何とかという騎士も引き篭もっているらしい。でなければここに来るのはあの騎士であった筈だ。
つまり面倒事は全て解決した。
あとは元の肉体に代わるものを手に入れ、至高なる御方にお目通りを願うだけだ。叱責はされよう。だがこちらにも言い分はある。
『傲慢の風上にも置けぬ卑劣なる罠により失態を演じてしメェましたが、偉大なるイヴ様の臣下に相応しく見事復活を果たして参りました。やはりイヴ様第一の臣は私しかおりませぬ』
――なかなか良いのではないか? 流石は叡智溢れる私よ……ブシ、ブシシシシ!
一時はどうなることかと思ったが、未来は開かれている。
ベリアルは愚かなる女の手首に軽く巻き付くと、猫なで声で案内してやることにした。
「ブシシ、あの爆発の及ばなかった所はすぐにでも案内できよう。上陸したら瞬く間に私の仕事を果たしてやろうではないか」
「…………豚が」
「ブシ!?」
「そうですね、辺縁部の浄化をしながら港を整え、然る後に爆発跡地の調査としましょう」
「ブシ、ブシシ、それがよかろう。私の神殿なき跡がどうなっておるか、私すら分からぬ」
悠然と雌伏して待つのもまた強者たる者としての在り方ではないか。
澱のように溜まる苛立ちに堪え、ベリアルはニンゲンどもが島へと上陸するのを眺めていた……。

セドリック・マクファーソン
近頃はこうして嘆息することがとみに増えた。
――ひたすらに祈りを捧げていたいものだ。
そんな穏やかな日常など十代の頃に聖堂教会に入ってからの数年しかなかったが、そのたった数年がひどく輝いている。身を清め、心を委ねて顔見知りと共に“光”を感じる日々。なんと得難い幸福であったか。
教会においては世俗に塗れた連中を次々と破門に追い込み、国政においてはこの王位なき時代に辣腕を振るうセドリックをしてそんな現実逃避に至らしめるのも、全てはこの机上の密書のせいだ。
破られた封蝋には国内一の大貴族マーロウ家の家紋。中には貴族らしい遠回しな文言でこんなことが書かれている。
『両家の仲も深まってきたからそろそろ王女殿下とうちの孫の婚姻を考える頃合いではないか』
この三ヶ月、何度となく読み返してきた密書だけに暗唱どころか手跡すら脳裏に浮かべることのできるセドリックだが、文章を思い出すたびに腸が煮えくり返りそうな激情が蘇る。
仲が深まっただと? 殿下が一度舞踏会に出ただけではないか!
うちの孫? 奴の孫など十を過ぎたばかりの幼子だろう!
密書を破り捨ててやりたい衝動を堪え、セドリックはぐっと眉間を指で押さえる。そして、ため息。この三ヶ月は暇さえあればこの繰り返しだった。
――せめて殿下が……。
いや、とセドリックは首を振る。どうにもならぬことを考えても仕方がない。現実を直視し“光”の御心に従う。それがエクラ教徒の在り方だ。努めて冷静に考えねばならない。
――奴の孫と殿下が政略結婚をすれば、どうなる?
マーロウ家の現当主ウェルズ・クリストフ・マーロウは王配の祖父として君臨する。未だ若い殿下らではあれを抑え切れないし、自分とて諸侯を束ね殿下の義父となったマーロウに抗するのは困難を極める。
では権勢を振るえるようになった奴は何をする?
歪虚を殺す。それも苛烈にだ。
その点だけを考えればそう悪くはない。目的は一致している。だがやり方が問題だ。
歪虚を殺す、ただその為にあらゆる生活を犠牲にする。
絶対にやらかす。これまでの言動と歪虚への敵意から鑑みて、マーロウは間違いなく歪虚討滅を国家の第一とする。
グラズヘイムという国家を総動員して歪虚を殺す。そこにあるのは人々の安寧ではなく、歪虚と同等の理不尽だ。戦う為に食べ、戦う為に戦う。それは“光”の御心に反するようにセドリックには思えた。
何がマーロウをそうさせているのかなど、そんなことは知らないしどうでもいい。
ただ、奴を自由にさせるべきでないし、その為にこそ政略結婚を成立させるわけにいかない。
――ではどうすればこの婚姻を回避し、それでいて貴族連中を黙らせることができる?
それはただ一つだ。
そしてセドリックは既に、それに向けた手を一つだけ打ってはいる。殿下の衣装を仕立てるという、一手とも呼べないただの準備だが。

ラィル・ファーディル
・ラァドゥ

レイレリア・リナークシス
――もはや猶予はない。殿下にはお覚悟を決めていただかねばならぬな……。
衣装を仕立てさせた際に使ったハンター――ラィル・ファーディル・ラァドゥ(ka1929)。にも「そろそろ殿下の子ども扱いをやめろ」というようなことを言いたい放題に言われた。であれば心置きなく王女殿下には大人になっていただこうではないか。なに、使い勝手の良さそうなレイレリア・リナークシス(ka3872)などの人材も見かけたし、確かグリーヴ家やシャール家の者なども殿下の知己にいたはずだ。それだけハンターとの友好を深めてきた殿下ならば、貴族諸侯連合に対する大きな力として彼らに協力を仰ぐことができるだろう。(「【CF】庭園の光」)
セドリックは密書を懐に入れて椅子から立ち上がると、自らの執務室を出て部下たちに告げた。
「しばらく出る。決裁が必要なものは私の机に置いておくように」
王城の奥へと向かいながら先触れを出し、王女殿下との面会を急ぐ。
そうと決めてしまえば少しでも時間が惜しくなる。本来“それ”の準備には年単位の時間が必要なのだから、数ヶ月でやり遂げようと思えばいくら時があっても足りない。
セドリックは先触れから数分遅れで王女殿下の部屋まで辿り着くや、殿下と侍従長しか室内にいないことを確認して微笑を浮かべた。
「王女殿下、殿下には今夏、戴冠していただきます」
●イスルダの亡霊
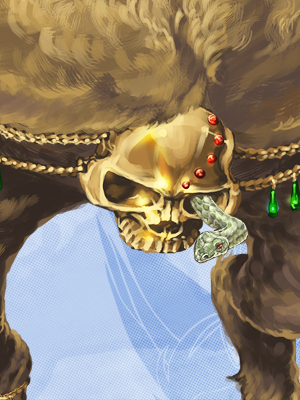
ベリアル

ヴィオラ・フルブライト
小さな金の蛇となったベリアル(kz0203)。は聖堂教会の――ヴィオラ・フルブライト(kz0007)。などという女に拘束されたまま、船上からかつての拠点イスルダを見晴るかした。
ヴィオラはひどく冷たい目で見下ろし、淡々と片手で締め上げてくる。思わず「メ゛ェ゛ェ゛」と悲鳴を上げるベリアルに、女は無表情で告げる。
「妙な真似をすれば『死ねないように』してやりますから大人しくしているように」
「ブシ!? 死ねないように!?」
「可及的速やかにイスルダの現状把握と再開発の目途を立てなければならないので仕方なくお前如きを案内に使ってやっていますが、極論すれば案内などいなくとも大量に人を投入して限界まで働けば問題ないのです。……その余裕がないだけで」
「ブ、ブッシシシ、妙な真似などせぬ! 憎きメフィストメェが滅んだ歓びに浸っておっただけよ、ブシシシ……」
「ならばよいのです。私としては蛇も今度こそ滅ぼしてやりたいのですが」
されるがままになりながら、ベリアルはブシブシとほくそ笑む。
メフィストは死んだ。蛇となって一旦やり過ごすよう助言はくれたもののあの蜘蛛と似た臭いを感じたへクス某という男も動けない。強力な敵たり得るエリ何とかという騎士も引き篭もっているらしい。でなければここに来るのはあの騎士であった筈だ。
つまり面倒事は全て解決した。
あとは元の肉体に代わるものを手に入れ、至高なる御方にお目通りを願うだけだ。叱責はされよう。だがこちらにも言い分はある。
『傲慢の風上にも置けぬ卑劣なる罠により失態を演じてしメェましたが、偉大なるイヴ様の臣下に相応しく見事復活を果たして参りました。やはりイヴ様第一の臣は私しかおりませぬ』
――なかなか良いのではないか? 流石は叡智溢れる私よ……ブシ、ブシシシシ!
一時はどうなることかと思ったが、未来は開かれている。
ベリアルは愚かなる女の手首に軽く巻き付くと、猫なで声で案内してやることにした。
「ブシシ、あの爆発の及ばなかった所はすぐにでも案内できよう。上陸したら瞬く間に私の仕事を果たしてやろうではないか」
「…………豚が」
「ブシ!?」
「そうですね、辺縁部の浄化をしながら港を整え、然る後に爆発跡地の調査としましょう」
「ブシ、ブシシ、それがよかろう。私の神殿なき跡がどうなっておるか、私すら分からぬ」
悠然と雌伏して待つのもまた強者たる者としての在り方ではないか。
澱のように溜まる苛立ちに堪え、ベリアルはニンゲンどもが島へと上陸するのを眺めていた……。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「千年王国、揺れる」(4月6日更新)
●王位の重圧

 「王女殿下、殿下には今夏、戴冠していただきます」
「王女殿下、殿下には今夏、戴冠していただきます」
セドリック・マクファーソン(kz0026)の宣告を聞いた時から、システィーナ・グラハム(kz0020)の脳裏には常にその言葉が駆け巡っていた。部屋で休んでいても、執務室で仕事をしていても、ダイニングルームで会食をしていても、ずっとだ。ずっとそれが付き纏ってくる。
システィーナは基本的に城から出ない。
だから気分が晴れないのかと、お忍びで王都第三街区にまで出てもみたが、それでも胃の奥をじくじくと締め付けられるような圧迫感は消えてくれなかった。が、それも当然かと息をついて、システィーナは目深にかぶったツバの広い帽子をさらに深くかぶり直した。
――王位がそれほど軽いわけがないのです。
通り過ぎる人たちの賑やかな声。露店の掛け合い。騎士団本部に入っていく騎士。ハンターオフィス王都支部から意気揚々と出発するハンターらしき人。王都で最も栄えている第三街区の明るい雰囲気は、少しばかり眩しすぎる。
侍従隊の面々にさり気なく護衛されながら第二城壁に戻り、一転して閑静な街並みを抜けて王城へ帰る。
賑やかな街も、静かな街も、そして新しく整備されつつある第七街区も、全てこのグラズヘイム王国の歴史だ。これだけ大きな国を背負って立つにはどれくらい勉強すればいいのだろう。
システィーナは城の文官に微笑みながら大司教の執務室に向かうと、大司教と侍従長以外の人を排して扉を閉めさせた。
「ご気分は晴れぬようですな」
「大司教さまがあのようなことを突然おっしゃるからです」
「衣装の仕立てで気付いておればよかったでしょう。現にあの時のハンターには何がしかを察した者はいた」
「……謀があるとは思っていました」
「お覚悟は決まりませんか」
無表情の大司教をほんの少し睨みあげ、システィーナは席につく。
「逃げたいわけではありません。やり遂げたいと思っています。わたくしがやらなければならないと」
「それは重畳」
「わたくしなりに頑張りたいと思っています。本当ですよ」
「ほう、光もお喜びでしょう」
「これまでわたくしの我儘で“そう”していなかったのですから、お待ちいただいた以上のものを返さなければとも感じています」
「ご立派なお心掛けです」
「……なのに」
言葉が詰まる。手が震える。そんな自分に嫌気が差す。
もっと若くして家を継がなければならない人だっているし、ハンターには十歳にもならずに戦っている子もいる。なのに自分はこの程度のことで震えている。
大司教は資質か何かを見定めるようにじっと観察してくる。仄かな不快感を微笑に変えて返すと、大司教は深く息を吐いて話を変えた。
「南のパン屋の訴えの件ですが」
肥沃なマーロウ領を差してパン屋と称し、政略結婚とそれに伴う貴族対策を口にする。
「殿下には“こちら”のお歴々との繋がりを確かめていただきたい。“あちら”の切り崩しは私が手配しようと考えていますが、直近の情報を集めきれておりませんので現状では何とも言えませんな」
「異端審問の件で掻き回されて、それから立て直せていませんからね」
「代わりに諜報と交渉にハンターを使うことも考慮に入れています。彼らは存外信用できます」
「……ハンターの皆さまを巻き込んでしまうのは、できれば避けたいですけれど」
「今さらでしょう。使えるならばハンターズソサエティすら巻き込んでしまえばよろしい」
「協定に反しますよ、それは……」
「ならば“こちら”の準備だけでも構いません。物の調達、道の整備、警備計画、頼む場所はいくらでもある」
不機嫌そうに大司教が鼻を鳴らした時、激しいノックが響いた。音の間隔の短さから、やけに急いているように感じる。
侍従長に開けてもらうと、そこには紙束を握り締めた文官が肩で息をしながら立っていた。許可を与えるや、彼はまくし立てるように報告する。
「だっ、王女殿下及び大司教様、これをご覧ください! い、今、下町でこのようなものがばら撒かれていたのですが……これは真実なので……い、いや、いや真偽などもはや関係ない……騒乱が、騒乱が起きるかもしれません!!」
その紙束――号外新聞には、システィーナ・グラハムの政略結婚とそれにまつわる宮廷事情が詳細に書かれていた……。
●ヘルメス情報局号外新聞
『王女殿下に迫る罠!?』
我らがグラズヘイム王国が大敵メフィストを打倒し、同時に仇敵ベリアルの生存が確認されてから三月が経った王国暦1018年春、さらに王国を揺るがす事件が発覚した。
それは王位継承権一位、システィーナ・グラハム王女殿下(20)の婚姻だ。
当情報局の調査によるとこの話の発端は昨年末、王女殿下の後見人セドリック・マクファーソン氏(48)に密書が届いた時まで遡る。密書の差出人は国内の某大貴族のようで、関係者によるとその日以降マクファーソン氏は度々頭を悩ませる姿を見せていたようだ。「あの方があれほど苦悩する姿は見たことがありませんでした」と語る同関係者は、さらに「密書と思われるものは大量の報告書と一緒に大司教の執務室に運び込まれたんですが、その羊皮紙は少し見ただけでも高級そうだと分かるほどでした。おそらくあれは相当な大貴族でしょう」とつづる。
そこで独自に調査を進めたところ、驚くべき事実が判明した。システィーナ・グラハム王女殿下に政略結婚の話が持ち上がっているというのだ。
気になるお相手はなんと、十歳の少年! 国内有数の大貴族の次期当主であるはずの少年だが、王家に婿入りして婚儀を結ぶという。
いったい何故そのような話になったのか。宮廷に詳しい当情報局員は自身の考えを述べる。「宮廷事情は複雑怪奇と言いますけどね、これに関しては一つの軸を念頭に置けば概ね分かりますよ。何しろ貴族間の細かい因縁を超越した動きですからね。軸? あぁ、それは簡単です。王家とそれ以外ですよ」
同局員は図を描きながら説明する。
「まず前提として、今の王家の立ち位置は非常に危ういんです。え? あぁ基盤はね、それなりですから、局面局面で別個に対処していけば何も問題ありませんよ。ただこれね、よく見てください、この伯爵らを結んでみますよ? 伯爵連合、できますよね。囲い込んでますよ。そして南部と北のダフィ……いや北のここが結びつく。分かりやすく土地ごとの主要作物と道も描いてみますか? するとどうですか、物理的にちょっとまずいことになってるでしょう。もちろん極論ですよ、これは。でもそれができるという事実が、宮廷内の動きに関わってくるんですね。争点は……
(中略)
……と指摘した同局員はさらに言い募る。
「次に王家の方を見ますか。王家、つまり国ですから歪虚と前面に立って戦わないといけないんですね、彼らは。いいですか、話に聞いたことがある方もいると思うんですが、歪虚にも王ってのがいるんですよ。私も噂でしか知りませんが、とんでもないらしい。この国に現れるかどうかは分かりませんが、国としては備えないとまずいでしょう。そこで問題になってくるのが、この立ち位置です。どうです、戦いにくいですよね。できればまとまって戦いたい。当然ですよ。当然だからこそ、貴族は強く出られるんです。だってこのパンを買わないと飢えて死ぬなんて時に買い控えするわけにいかないでしょ? 貴族にとってはパンが売れたら大儲け、売れなかったら王家が死ぬ。ま、死んだら後々大変ですから程々で飼い殺すのが良いでしょうけどね。要するに足下見られて吹っ掛けられてるんですよ。
私はね、情報に仕える由緒正しい特派員として申しますと、情けないですよ。え? いやどっちもです。お上も貴族も。ちょっと前に巡礼路が光の柱を立てた事件あったでしょ? あの時は時代が変わるなと、そう思ったものですよ。そう、時代です。この号外を手に取った読者諸兄にも考えていただきたい。この激動の時代を生きる我々は何を考え、どう行動したいか。できることなら私は王女殿下にもパン売り閣下にも直接言ってやりたいですよ。あんたら、光の御許に上った者たちに顔向けができるのかってね。……
(後略)
●次代への道筋
全く以て忌々しい。
ウェルズ・クリストフ・マーロウは目を通していた新聞を机上に放り投げ、一つ舌を打った。熟読し、対策を練ることすら嫌悪感を覚える。
「誰だ、このような低俗な騒ぎを起こしたのは」
マーロウは自室で独りごちる。
今、王国南部シエラリオ地方にある本宅にはマーロウとその孫、そして信頼できる少数の側仕えと配下しかいない。不用心が過ぎるのも考えものだが、苛立ちに任せて独語できる程度には防諜態勢が整っていた。
「シャルシェレットめの若造か?」
だが奴は未だ意識が戻らぬという。では事前に布石を打っていたというのか。それこそあり得ない。
ではマクファーソンか。それにしてはやり口があまりに――そう、美しくない。世俗的でないという点でマクファーソンを信頼している。
ならば情報局独自の動きなのか?
「……、……仕方があるまい」
下手人を考えるより先に手を打たねばならない。卑俗に塗れるようでひどく気は進まないが、些か平民の反応も気にはなる。騒動になるなら鎮めるか、利用するかをしなければ無秩序な暴走がどこに向かうか分かったものではない。
「――私の“子ども達”よ」
小さな呼び声から一分とせぬうちに音もなく室内に姿を現す者たち。マーロウはその迅速さに満足感を覚える。
ささくれ立った心を静めるべく微笑を浮かべ、最も信頼する駒の一つである彼らに命じた。
「私の愛する君たちにいくつかの任務を与えよう。なに、君たちには簡単な作業だ。任務は大きく分けて四つ――」
それぞれに指示を与え、マーロウは椅子の背もたれに身体を預ける。腕を組んで目を瞑ると、自然とため息が漏れた。身体を起こすのも億劫な気分に包まれるが、腹の奥に力を込めて椅子に座り直す。
机に置かれたウィドワール――千年王国に古くからある盤上遊戯だ――の盤面を睨み、コツ、コツと手を二つ進めた。想定外の打ち筋だったが、局面は依然として悪くない。そう考えれば新聞の件も許せる気がした。
……孫の顔でも見るか。
ふと思い立ち、マーロウは重い身体に鞭打って立ち上がる。
我知らず呻きのような声が零れ、マーロウは寄る年波に眉をしかめた。

セドリック・マクファーソン

システィーナ・グラハム
セドリック・マクファーソン(kz0026)の宣告を聞いた時から、システィーナ・グラハム(kz0020)の脳裏には常にその言葉が駆け巡っていた。部屋で休んでいても、執務室で仕事をしていても、ダイニングルームで会食をしていても、ずっとだ。ずっとそれが付き纏ってくる。
システィーナは基本的に城から出ない。
だから気分が晴れないのかと、お忍びで王都第三街区にまで出てもみたが、それでも胃の奥をじくじくと締め付けられるような圧迫感は消えてくれなかった。が、それも当然かと息をついて、システィーナは目深にかぶったツバの広い帽子をさらに深くかぶり直した。
――王位がそれほど軽いわけがないのです。
通り過ぎる人たちの賑やかな声。露店の掛け合い。騎士団本部に入っていく騎士。ハンターオフィス王都支部から意気揚々と出発するハンターらしき人。王都で最も栄えている第三街区の明るい雰囲気は、少しばかり眩しすぎる。
侍従隊の面々にさり気なく護衛されながら第二城壁に戻り、一転して閑静な街並みを抜けて王城へ帰る。
賑やかな街も、静かな街も、そして新しく整備されつつある第七街区も、全てこのグラズヘイム王国の歴史だ。これだけ大きな国を背負って立つにはどれくらい勉強すればいいのだろう。
システィーナは城の文官に微笑みながら大司教の執務室に向かうと、大司教と侍従長以外の人を排して扉を閉めさせた。
「ご気分は晴れぬようですな」
「大司教さまがあのようなことを突然おっしゃるからです」
「衣装の仕立てで気付いておればよかったでしょう。現にあの時のハンターには何がしかを察した者はいた」
「……謀があるとは思っていました」
「お覚悟は決まりませんか」
無表情の大司教をほんの少し睨みあげ、システィーナは席につく。
「逃げたいわけではありません。やり遂げたいと思っています。わたくしがやらなければならないと」
「それは重畳」
「わたくしなりに頑張りたいと思っています。本当ですよ」
「ほう、光もお喜びでしょう」
「これまでわたくしの我儘で“そう”していなかったのですから、お待ちいただいた以上のものを返さなければとも感じています」
「ご立派なお心掛けです」
「……なのに」
言葉が詰まる。手が震える。そんな自分に嫌気が差す。
もっと若くして家を継がなければならない人だっているし、ハンターには十歳にもならずに戦っている子もいる。なのに自分はこの程度のことで震えている。
大司教は資質か何かを見定めるようにじっと観察してくる。仄かな不快感を微笑に変えて返すと、大司教は深く息を吐いて話を変えた。
「南のパン屋の訴えの件ですが」
肥沃なマーロウ領を差してパン屋と称し、政略結婚とそれに伴う貴族対策を口にする。
「殿下には“こちら”のお歴々との繋がりを確かめていただきたい。“あちら”の切り崩しは私が手配しようと考えていますが、直近の情報を集めきれておりませんので現状では何とも言えませんな」
「異端審問の件で掻き回されて、それから立て直せていませんからね」
「代わりに諜報と交渉にハンターを使うことも考慮に入れています。彼らは存外信用できます」
「……ハンターの皆さまを巻き込んでしまうのは、できれば避けたいですけれど」
「今さらでしょう。使えるならばハンターズソサエティすら巻き込んでしまえばよろしい」
「協定に反しますよ、それは……」
「ならば“こちら”の準備だけでも構いません。物の調達、道の整備、警備計画、頼む場所はいくらでもある」
不機嫌そうに大司教が鼻を鳴らした時、激しいノックが響いた。音の間隔の短さから、やけに急いているように感じる。
侍従長に開けてもらうと、そこには紙束を握り締めた文官が肩で息をしながら立っていた。許可を与えるや、彼はまくし立てるように報告する。
「だっ、王女殿下及び大司教様、これをご覧ください! い、今、下町でこのようなものがばら撒かれていたのですが……これは真実なので……い、いや、いや真偽などもはや関係ない……騒乱が、騒乱が起きるかもしれません!!」
その紙束――号外新聞には、システィーナ・グラハムの政略結婚とそれにまつわる宮廷事情が詳細に書かれていた……。
●ヘルメス情報局号外新聞
『王女殿下に迫る罠!?』
我らがグラズヘイム王国が大敵メフィストを打倒し、同時に仇敵ベリアルの生存が確認されてから三月が経った王国暦1018年春、さらに王国を揺るがす事件が発覚した。
それは王位継承権一位、システィーナ・グラハム王女殿下(20)の婚姻だ。
当情報局の調査によるとこの話の発端は昨年末、王女殿下の後見人セドリック・マクファーソン氏(48)に密書が届いた時まで遡る。密書の差出人は国内の某大貴族のようで、関係者によるとその日以降マクファーソン氏は度々頭を悩ませる姿を見せていたようだ。「あの方があれほど苦悩する姿は見たことがありませんでした」と語る同関係者は、さらに「密書と思われるものは大量の報告書と一緒に大司教の執務室に運び込まれたんですが、その羊皮紙は少し見ただけでも高級そうだと分かるほどでした。おそらくあれは相当な大貴族でしょう」とつづる。
そこで独自に調査を進めたところ、驚くべき事実が判明した。システィーナ・グラハム王女殿下に政略結婚の話が持ち上がっているというのだ。
気になるお相手はなんと、十歳の少年! 国内有数の大貴族の次期当主であるはずの少年だが、王家に婿入りして婚儀を結ぶという。
いったい何故そのような話になったのか。宮廷に詳しい当情報局員は自身の考えを述べる。「宮廷事情は複雑怪奇と言いますけどね、これに関しては一つの軸を念頭に置けば概ね分かりますよ。何しろ貴族間の細かい因縁を超越した動きですからね。軸? あぁ、それは簡単です。王家とそれ以外ですよ」
同局員は図を描きながら説明する。
「まず前提として、今の王家の立ち位置は非常に危ういんです。え? あぁ基盤はね、それなりですから、局面局面で別個に対処していけば何も問題ありませんよ。ただこれね、よく見てください、この伯爵らを結んでみますよ? 伯爵連合、できますよね。囲い込んでますよ。そして南部と北のダフィ……いや北のここが結びつく。分かりやすく土地ごとの主要作物と道も描いてみますか? するとどうですか、物理的にちょっとまずいことになってるでしょう。もちろん極論ですよ、これは。でもそれができるという事実が、宮廷内の動きに関わってくるんですね。争点は……
(中略)
……と指摘した同局員はさらに言い募る。
「次に王家の方を見ますか。王家、つまり国ですから歪虚と前面に立って戦わないといけないんですね、彼らは。いいですか、話に聞いたことがある方もいると思うんですが、歪虚にも王ってのがいるんですよ。私も噂でしか知りませんが、とんでもないらしい。この国に現れるかどうかは分かりませんが、国としては備えないとまずいでしょう。そこで問題になってくるのが、この立ち位置です。どうです、戦いにくいですよね。できればまとまって戦いたい。当然ですよ。当然だからこそ、貴族は強く出られるんです。だってこのパンを買わないと飢えて死ぬなんて時に買い控えするわけにいかないでしょ? 貴族にとってはパンが売れたら大儲け、売れなかったら王家が死ぬ。ま、死んだら後々大変ですから程々で飼い殺すのが良いでしょうけどね。要するに足下見られて吹っ掛けられてるんですよ。
私はね、情報に仕える由緒正しい特派員として申しますと、情けないですよ。え? いやどっちもです。お上も貴族も。ちょっと前に巡礼路が光の柱を立てた事件あったでしょ? あの時は時代が変わるなと、そう思ったものですよ。そう、時代です。この号外を手に取った読者諸兄にも考えていただきたい。この激動の時代を生きる我々は何を考え、どう行動したいか。できることなら私は王女殿下にもパン売り閣下にも直接言ってやりたいですよ。あんたら、光の御許に上った者たちに顔向けができるのかってね。……
(後略)
●次代への道筋
全く以て忌々しい。
ウェルズ・クリストフ・マーロウは目を通していた新聞を机上に放り投げ、一つ舌を打った。熟読し、対策を練ることすら嫌悪感を覚える。
「誰だ、このような低俗な騒ぎを起こしたのは」
マーロウは自室で独りごちる。
今、王国南部シエラリオ地方にある本宅にはマーロウとその孫、そして信頼できる少数の側仕えと配下しかいない。不用心が過ぎるのも考えものだが、苛立ちに任せて独語できる程度には防諜態勢が整っていた。
「シャルシェレットめの若造か?」
だが奴は未だ意識が戻らぬという。では事前に布石を打っていたというのか。それこそあり得ない。
ではマクファーソンか。それにしてはやり口があまりに――そう、美しくない。世俗的でないという点でマクファーソンを信頼している。
ならば情報局独自の動きなのか?
「……、……仕方があるまい」
下手人を考えるより先に手を打たねばならない。卑俗に塗れるようでひどく気は進まないが、些か平民の反応も気にはなる。騒動になるなら鎮めるか、利用するかをしなければ無秩序な暴走がどこに向かうか分かったものではない。
「――私の“子ども達”よ」
小さな呼び声から一分とせぬうちに音もなく室内に姿を現す者たち。マーロウはその迅速さに満足感を覚える。
ささくれ立った心を静めるべく微笑を浮かべ、最も信頼する駒の一つである彼らに命じた。
「私の愛する君たちにいくつかの任務を与えよう。なに、君たちには簡単な作業だ。任務は大きく分けて四つ――」
それぞれに指示を与え、マーロウは椅子の背もたれに身体を預ける。腕を組んで目を瞑ると、自然とため息が漏れた。身体を起こすのも億劫な気分に包まれるが、腹の奥に力を込めて椅子に座り直す。
机に置かれたウィドワール――千年王国に古くからある盤上遊戯だ――の盤面を睨み、コツ、コツと手を二つ進めた。想定外の打ち筋だったが、局面は依然として悪くない。そう考えれば新聞の件も許せる気がした。
……孫の顔でも見るか。
ふと思い立ち、マーロウは重い身体に鞭打って立ち上がる。
我知らず呻きのような声が零れ、マーロウは寄る年波に眉をしかめた。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「秘めたもの」(4月16日更新)
●イスルダ島調査開拓団




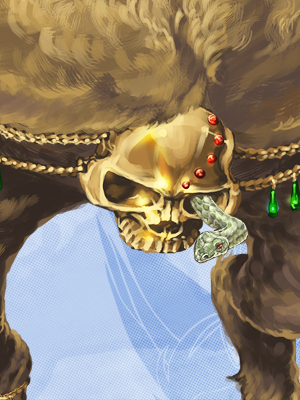






 廃墟のようだった島の港町には賑やかな音と声が響いている。
廃墟のようだった島の港町には賑やかな音と声が響いている。
ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は輸送船から大量の物資が吐き出されていくのを監督しながら、何人かの報告を聞いていた。
「やはり浄化の必要がありますか」
「島内の村――正確には跡地だったけど、その近くにも雑魔が来たんだもの。この港以外は安全な場所なんて少ないでしょうね」
「一応、これを。村までの道とその周辺の状況を軽く書き留めてます」
マリィア・バルデス(ka5848)とエラ・“dJehuty”・ベル(ka3142)が言う。ヴィオラがエラから受け取った地図を見ていると、現地で空から偵察したリュー・グランフェスト(ka2419)が補足する。
「村の近くの森は何かがいる――気がする」
ヴィオラが目を細めて地図を睨む。このまま島中央に進出するのは不安が残る。しかし時間的な問題で段階を踏んで進むことはできない。
島内全域の掃除が必要だが、島中央の神殿跡地とその周辺に広がる黒の爆発跡地の調査も並行して進めなければならない。この港の拠点化も急務だ。そしてそれら全てに、護衛が必要になる。
まず間違いなく、開拓団として組み込まれている騎士団や聖堂戦士団だけでは手が足りない。
――ハンターの増員を願い出るしかありませんね……。
「分かりました。また何かあればお願いします」
三人を見送り、ヴィオラは他の偵察隊の情報を地図に加えていく。が、その量はそう多くない。
できることなら斥候を増やして進めたいのだが――王女殿下の件を考えればあまり悠長にしていられない。先王時代に奪われたイスルダ島の復興というのは、女王としての箔付けに使える。
「ブシ、ブシ、往こうではないか、私の神殿へ!」
「…………臭い息を吐くな、豚が」
「ブシ!?」
「しかし、神殿跡地を早急に調査しなければならないのもまた事実ですね」
だが妙に乗り気なベリアル(kz0203)への警戒も怠ってはならない。
歪虚掃討に浄化、調査に加えて豚蛇の監視までもがヴィオラの双肩に圧し掛かっている。
――全く、この忙しい時に何故あなたはいないのですか!
ヴィオラは蟄居するエリオット・ヴァレンタイン(kz0025)に内心で毒づくと、嘆息して空を仰いだ。
●蓄音石と署名
「それは?」
システィーナ・グラハム(kz0020は卓上に置かれた石と紙束に目をやり、眼前に立つ老騎士を見上げた。
老騎士――ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトは眉をしかめて言う。
「黒の隊のアルト・ヴァレンティーニ(ka3109)を通して騎士団に届きました。スフォルツァ領をはじめ、穏やかならぬ領地があるようですな」
その紙束には一目では数えきれないほどの人の名と、取りまとめたハンターらの所感が記されている。
侍従長に蓄音石の紋様をなぞってもらえば、そこからは「王女様は国の宝だ」だとか「幸せになってほしい」といった声がざわざわとした雰囲気と共に聞こえてくる。短い録音時間を惜しむように詰め込まれた剥き出しの感情に目を丸くしたシスティーナは、次にもう一度聞き直して微苦笑を浮かべた。
「これを、スフォルツァ領の方たちが?」
「当初は王都まで練り歩く予定だったそうで。ハンターの神楽(ka2032)らの取り成しで落ち着きを取り戻し、八島 陽(ka1442)らがこの形に落とし込んだようです」
「……それは……大変、だったのでしょうね」
「これが、いくつもの領地で起こる可能性があります」
「そうですか……」
ゲオルギウスの推測に、システィーナは眉根を寄せた。
気持ちは嬉しい。即位もせず曖昧な状態でやってきた自分でも慕ってくれる国民がいると思うと、胸の奥がじんわりと温かくなる。
けれど為政者としては、少し困る。それにもしこれが“あちら”の領で起こったら、付け入られる隙になる。
何しろ王女を云々と主張しているのだ。王家が裏で糸を引いて騒ぎを起こし、それを元に統治不足だとして貴族領に介入するつもりだろう、と“そんな陰謀論をでっち上げることすらできなくはない”。
それに、とシスティーナは目を伏せる。
歪虚を打倒するために手っ取り早く貴族をまとめる手段を、そう易々と捨てることはできない。いくらマーロウの苛烈な志向が国を荒廃させるとしても、歪虚の闇に呑まれるよりはいいのだから。
さらに言えば最近は聖堂教会の方からの要望も大きくなってきている。「迅速かつ徹底的に歪虚を滅することができる手段があるならそれを選ぶべし」というような要望書が何度かきたのだ。
「これは私見ですが」
ゲオルギウスが声を低くして言う。
「集団心理を誘導された可能性も考慮しておくべきかと。ハンターがその場でそれとなく探ったものの、証拠はなかったようですが」
「……手を拱いていてはまずそうですね」
――戴冠式を早める? いえ……みすぼらしい即位をしたところで虚しい玉座でしかなく、貴族はまとまらない。
歪虚の王に備える。それが第一で、戴冠あるいは結婚は備える手段だ。それを忘れてはいけない。
「できるだけ“準備”を早めてください。けれど丁寧に」
システィーナは努めて平静に指示を出し、席を立った。
●ルーツ
自室に戻ったシスティーナは倒れるように寝台に飛び込んだ。
侍従長にして教育係のオクレールが咎めるが、そんなこと知らない。
「頭が痛いので休みますね」
「然様でございますか。ではお召し換えだけでもなさいませ」
されるがままになっていると、ずっと昔に戻ったようだ。
ぼんやりと自分の着替えを眺めていたところ、ふと視線を感じて机の方を向いてみた。
机上にはユグディラの女王が楚々とした様子で腰かけている。
ふいと目を逸らされ、システィーナもそちらを向けば、そこにはノートがあった。とあるハンターに言われ、書き始めたノート。もう九冊目になるそれは、もはや日記のようになっている。
思い立って一冊目から全て持ってきてもらい、読み返してみた。
日々考えたことからその日の謁見、古の塔の話など雑多に書き散らされていて、色んな意味でとても他人には見せられない。
なんとなく渇いた笑いが零れて、気付けば「お父様」と呟いていた。そして呟いてしまえば、もう止められなかった。
「…………。……分樹は、過去の情報を記録しているのですよね?」
「王女殿下?」
「報告書で読みましたけれど、覚醒者の方は過去の幻に入れるのですよね?」
「システィーナ様」
「以前少し考えたことがあるのですけれど、わたくしでもできるのでしょうか?」
問うとオクレールが僅かに息を呑み、顔を歪めて息を吐く。
「おそらく非覚醒者には難しいかと」
「……ですよね。できたら色々なお話を聞けそうだったのですけれど」
残念だと肩を落とすと、今度はダメな子を見るような目で見られた。
「システィーナ様」
「な、何でしょう?」
「できなければできる者に命じればよいのです。直接お会いになることは叶いませんが、御心を交わすことはできるでしょう」
その日、ハンターオフィスにいくつかの依頼が張り出された。
内容に差はあれど、それらには共通して『あなたのことを教えてほしい』という意図が根底に流れていた。

ヴィオラ・フルブライト

マリィア・バルデス

エラ・“dJehuty”・ベル

リュー・グランフェスト
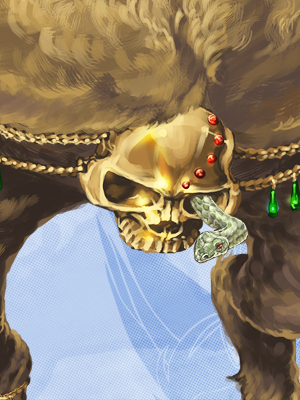
ベリアル

エリオット・ヴァレンタイン

システィーナ・グラハム

ゲオルギウス・グラニフ・
グランフェルト

アルト・ヴァレンティーニ

神楽

八島 陽

ユグディラ女王
ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は輸送船から大量の物資が吐き出されていくのを監督しながら、何人かの報告を聞いていた。
「やはり浄化の必要がありますか」
「島内の村――正確には跡地だったけど、その近くにも雑魔が来たんだもの。この港以外は安全な場所なんて少ないでしょうね」
「一応、これを。村までの道とその周辺の状況を軽く書き留めてます」
マリィア・バルデス(ka5848)とエラ・“dJehuty”・ベル(ka3142)が言う。ヴィオラがエラから受け取った地図を見ていると、現地で空から偵察したリュー・グランフェスト(ka2419)が補足する。
「村の近くの森は何かがいる――気がする」
ヴィオラが目を細めて地図を睨む。このまま島中央に進出するのは不安が残る。しかし時間的な問題で段階を踏んで進むことはできない。
島内全域の掃除が必要だが、島中央の神殿跡地とその周辺に広がる黒の爆発跡地の調査も並行して進めなければならない。この港の拠点化も急務だ。そしてそれら全てに、護衛が必要になる。
まず間違いなく、開拓団として組み込まれている騎士団や聖堂戦士団だけでは手が足りない。
――ハンターの増員を願い出るしかありませんね……。
「分かりました。また何かあればお願いします」
三人を見送り、ヴィオラは他の偵察隊の情報を地図に加えていく。が、その量はそう多くない。
できることなら斥候を増やして進めたいのだが――王女殿下の件を考えればあまり悠長にしていられない。先王時代に奪われたイスルダ島の復興というのは、女王としての箔付けに使える。
「ブシ、ブシ、往こうではないか、私の神殿へ!」
「…………臭い息を吐くな、豚が」
「ブシ!?」
「しかし、神殿跡地を早急に調査しなければならないのもまた事実ですね」
だが妙に乗り気なベリアル(kz0203)への警戒も怠ってはならない。
歪虚掃討に浄化、調査に加えて豚蛇の監視までもがヴィオラの双肩に圧し掛かっている。
――全く、この忙しい時に何故あなたはいないのですか!
ヴィオラは蟄居するエリオット・ヴァレンタイン(kz0025)に内心で毒づくと、嘆息して空を仰いだ。
●蓄音石と署名
「それは?」
システィーナ・グラハム(kz0020は卓上に置かれた石と紙束に目をやり、眼前に立つ老騎士を見上げた。
老騎士――ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトは眉をしかめて言う。
「黒の隊のアルト・ヴァレンティーニ(ka3109)を通して騎士団に届きました。スフォルツァ領をはじめ、穏やかならぬ領地があるようですな」
その紙束には一目では数えきれないほどの人の名と、取りまとめたハンターらの所感が記されている。
侍従長に蓄音石の紋様をなぞってもらえば、そこからは「王女様は国の宝だ」だとか「幸せになってほしい」といった声がざわざわとした雰囲気と共に聞こえてくる。短い録音時間を惜しむように詰め込まれた剥き出しの感情に目を丸くしたシスティーナは、次にもう一度聞き直して微苦笑を浮かべた。
「これを、スフォルツァ領の方たちが?」
「当初は王都まで練り歩く予定だったそうで。ハンターの神楽(ka2032)らの取り成しで落ち着きを取り戻し、八島 陽(ka1442)らがこの形に落とし込んだようです」
「……それは……大変、だったのでしょうね」
「これが、いくつもの領地で起こる可能性があります」
「そうですか……」
ゲオルギウスの推測に、システィーナは眉根を寄せた。
気持ちは嬉しい。即位もせず曖昧な状態でやってきた自分でも慕ってくれる国民がいると思うと、胸の奥がじんわりと温かくなる。
けれど為政者としては、少し困る。それにもしこれが“あちら”の領で起こったら、付け入られる隙になる。
何しろ王女を云々と主張しているのだ。王家が裏で糸を引いて騒ぎを起こし、それを元に統治不足だとして貴族領に介入するつもりだろう、と“そんな陰謀論をでっち上げることすらできなくはない”。
それに、とシスティーナは目を伏せる。
歪虚を打倒するために手っ取り早く貴族をまとめる手段を、そう易々と捨てることはできない。いくらマーロウの苛烈な志向が国を荒廃させるとしても、歪虚の闇に呑まれるよりはいいのだから。
さらに言えば最近は聖堂教会の方からの要望も大きくなってきている。「迅速かつ徹底的に歪虚を滅することができる手段があるならそれを選ぶべし」というような要望書が何度かきたのだ。
「これは私見ですが」
ゲオルギウスが声を低くして言う。
「集団心理を誘導された可能性も考慮しておくべきかと。ハンターがその場でそれとなく探ったものの、証拠はなかったようですが」
「……手を拱いていてはまずそうですね」
――戴冠式を早める? いえ……みすぼらしい即位をしたところで虚しい玉座でしかなく、貴族はまとまらない。
歪虚の王に備える。それが第一で、戴冠あるいは結婚は備える手段だ。それを忘れてはいけない。
「できるだけ“準備”を早めてください。けれど丁寧に」
システィーナは努めて平静に指示を出し、席を立った。
●ルーツ
自室に戻ったシスティーナは倒れるように寝台に飛び込んだ。
侍従長にして教育係のオクレールが咎めるが、そんなこと知らない。
「頭が痛いので休みますね」
「然様でございますか。ではお召し換えだけでもなさいませ」
されるがままになっていると、ずっと昔に戻ったようだ。
ぼんやりと自分の着替えを眺めていたところ、ふと視線を感じて机の方を向いてみた。
机上にはユグディラの女王が楚々とした様子で腰かけている。
ふいと目を逸らされ、システィーナもそちらを向けば、そこにはノートがあった。とあるハンターに言われ、書き始めたノート。もう九冊目になるそれは、もはや日記のようになっている。
思い立って一冊目から全て持ってきてもらい、読み返してみた。
日々考えたことからその日の謁見、古の塔の話など雑多に書き散らされていて、色んな意味でとても他人には見せられない。
なんとなく渇いた笑いが零れて、気付けば「お父様」と呟いていた。そして呟いてしまえば、もう止められなかった。
「…………。……分樹は、過去の情報を記録しているのですよね?」
「王女殿下?」
「報告書で読みましたけれど、覚醒者の方は過去の幻に入れるのですよね?」
「システィーナ様」
「以前少し考えたことがあるのですけれど、わたくしでもできるのでしょうか?」
問うとオクレールが僅かに息を呑み、顔を歪めて息を吐く。
「おそらく非覚醒者には難しいかと」
「……ですよね。できたら色々なお話を聞けそうだったのですけれど」
残念だと肩を落とすと、今度はダメな子を見るような目で見られた。
「システィーナ様」
「な、何でしょう?」
「できなければできる者に命じればよいのです。直接お会いになることは叶いませんが、御心を交わすことはできるでしょう」
その日、ハンターオフィスにいくつかの依頼が張り出された。
内容に差はあれど、それらには共通して『あなたのことを教えてほしい』という意図が根底に流れていた。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「触れてはならぬもの」(5月16日更新)
●三つの報せ




 システィーナ・グラハム(kz0020)は玉座の間でハンターたちの報告と“過去からの言伝”を聞き、溢れそうな感情を慎重に抑え込んだ。
システィーナ・グラハム(kz0020)は玉座の間でハンターたちの報告と“過去からの言伝”を聞き、溢れそうな感情を慎重に抑え込んだ。
「先王陛下はシスティーナ様の御世が光の満ちる世界となることを信じておられました。そしてそのための道筋を整えるのが父としての役目だ、と」
侍女、あるいは姉か母がするような穏やかな表情でクリスティア・オルトワール(ka0131)が言えば、ラィル・ファーディル・ラァドゥ(ka1929)は兄のようにからかい交じりの声色で加える。
「優しいままの王女さんでおってほしい、けど教育は最初甘やかしすぎたて言うとったなぁ」
「っ……」
さっと頬に朱が差すのが自分でも分かる。
泣きたいのか、笑いたいのか、怒りたいのか、自分自身にすら判別できないぐちゃぐちゃの感情を拍動煩い胸に押し込める。システィーナは父からの言伝に関して口外しないようお願いし、胸に手を当て何度か深呼吸した。
――あ、あとで言伝は手紙にしてもらってゆっくり読み返さなければ……。
「そ、それよりマーロウ大公の話です。千年王国と、それを支える己を矜持にしていると、そう父は言ったのですね?」
「あぁ。つまりあの爺は、国を守りてぇのにクソガキがちゃんとしてねぇから妙なことになってんじゃねぇか。ま、息子を殺した歪虚許さねぇみてぇなところもあるだろうけどよ」
首肯したジャック・J・グリーヴ(ka1305)の視線はずっと射抜くようにこちらに向けられている。
システィーナは正面からそれを受け止め、お腹に力を入れた。
「……そうですね。わたくしの、責です」
「ハ、そうだよ。てめぇのせいだ、クソガキ。けど安心しろや。俺様が、俺こそがこの国を立て直してやるからよ!」
「いいえ、それはわたくしがしなければならないことです! あ、貴方じゃない、わたくしがっ……」
喧嘩を売るようなジャックに声を荒げかけた、その時だった。
「盛り上がっているところ悪いが、緊急の話だ。仲良く席につかんかね、若造どもが」
現王国騎士団長、ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが無断で玉座の間に入ってきたのは。
「悪い話と、最悪の話、どちらから先に聞きたいですか、王女殿下」
珍しく諧謔に満ちた台詞を吐いたゲオルギウスは、こちらの返答を待たずして悪い話から始めた。
「王都に暴徒が集まりつつあります」
「……暴徒、とは……ヘルメス情報局の記事で立ち上がった方たちですか? 彼らを暴徒と呼びたくはないのですけれど……」
「ふん、街の外を練り歩くだけならまだしも、王都の城門に押し寄せた連中を暴徒と呼んで何が悪い」
「城門に、押し寄せた……!?」
「最も外である第六城壁で食い止めましたがね。しかし同時に王都内の一部でも蜂起を確認、幾つか部隊を向かわせました」
ゲオルギウスの報告を頭が理解した瞬間、システィーナはさっと青褪めた。
王都内各所で騒動が起こり、外壁の向こうでも人が集まりつつある。このまま手を拱いていては止められなくなるか、あるいは――、大勢の民を、断罪せねばならなくなる。
「っ、い、急いで収束に当たってください、けれどできるだけ穏便に!」
「既にそのようにしておりますので、ご安心を」
「で、ではわたくしは第六城壁へ向かいます。わたくしが直接話せば解散してくれるかもしれませんっ!」
「なるほど、事態が膠着した後ならば有効やもしれませんな。だがそれは最悪の話を聞いてからにしていただきたい」
腰を浮かせたシスティーナは、淡々としたゲオルギウスの忠告に悪寒が走った。震える声で“最悪の話”の先を促すと、老騎士は一つ息を吐いて重大な、あまりに致命的なことを口にした。
「……双丘の泉の取水施設を何者かに襲撃された。狼煙を見てすぐさま緊急部隊を派遣したが、最悪の場合、王都の水源は破壊されるだろう」
ネヴァ山、双丘の泉。
そこには、王都全域に水を供給する古き魔導装置が、設置されている。
●???
「おいおい、親父殿も耄碌したか?」
グラズヘイム王国、王都近郊上空。
飛翔する馬に騎乗し、かつての母国を睥睨したラスヴェート・コヴヘイル・マーロウは、王都に集いつつある群衆の流れと、それに紛れながら王都へ“雑然と進軍”していく戦闘集団を視認して嘆息した。
「……ここは一つ手伝ってやるか。あの親父殿を、この私がだ。いけるな、爺」

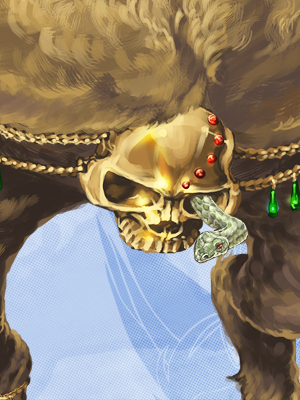 「は、万事恙なく。しかしよろしいのでしょうか、かの御方からは偵察をせよと」
「は、万事恙なく。しかしよろしいのでしょうか、かの御方からは偵察をせよと」
「構わぬ。軽くひと当たりすることもまた偵察よ。兵を集めろ」
「はっ!」
爺が後方に飛んでいく。
ラスヴェートはそれを一顧だにせず、ただ眼下で進軍する軍を見つめ続けていた……。
●イスルダの残滓
黒曜神殿跡地――地下。
歪虚化した先王アレクシウスらとハンターたちが死闘を繰り広げた広間がどこにあるか、それすら判然としないほどに朽ちた廃墟は、濃密な負のマテリアルと“寒々しいにおい”が充満していた。
がらがらと崩れ落ちた瓦礫が音を立てる。潜んだ歪虚が声なき歓声を上げる。
廃墟のうち、比較的原型の残っている地下道へとヴィオラ・フルブライト(kz0007)がベリアル(kz0203)を拘束したまま足を踏み入れる。
ブシシシシ……。
「囀るな」
ヴィオラが気持ち悪い含み笑いを漏らす手元の愚蛇を黙らせる。
――それでも、嘲るような音がどこかから聴こえていた……。

システィーナ・グラハム

クリスティア・オルトワール

ラィル・ファーディル・
ラァドゥ

ジャック・J・グリーヴ

ゲオルギウス・グラニフ・
グランフェルト
「先王陛下はシスティーナ様の御世が光の満ちる世界となることを信じておられました。そしてそのための道筋を整えるのが父としての役目だ、と」
侍女、あるいは姉か母がするような穏やかな表情でクリスティア・オルトワール(ka0131)が言えば、ラィル・ファーディル・ラァドゥ(ka1929)は兄のようにからかい交じりの声色で加える。
「優しいままの王女さんでおってほしい、けど教育は最初甘やかしすぎたて言うとったなぁ」
「っ……」
さっと頬に朱が差すのが自分でも分かる。
泣きたいのか、笑いたいのか、怒りたいのか、自分自身にすら判別できないぐちゃぐちゃの感情を拍動煩い胸に押し込める。システィーナは父からの言伝に関して口外しないようお願いし、胸に手を当て何度か深呼吸した。
――あ、あとで言伝は手紙にしてもらってゆっくり読み返さなければ……。
「そ、それよりマーロウ大公の話です。千年王国と、それを支える己を矜持にしていると、そう父は言ったのですね?」
「あぁ。つまりあの爺は、国を守りてぇのにクソガキがちゃんとしてねぇから妙なことになってんじゃねぇか。ま、息子を殺した歪虚許さねぇみてぇなところもあるだろうけどよ」
首肯したジャック・J・グリーヴ(ka1305)の視線はずっと射抜くようにこちらに向けられている。
システィーナは正面からそれを受け止め、お腹に力を入れた。
「……そうですね。わたくしの、責です」
「ハ、そうだよ。てめぇのせいだ、クソガキ。けど安心しろや。俺様が、俺こそがこの国を立て直してやるからよ!」
「いいえ、それはわたくしがしなければならないことです! あ、貴方じゃない、わたくしがっ……」
喧嘩を売るようなジャックに声を荒げかけた、その時だった。
「盛り上がっているところ悪いが、緊急の話だ。仲良く席につかんかね、若造どもが」
現王国騎士団長、ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが無断で玉座の間に入ってきたのは。
「悪い話と、最悪の話、どちらから先に聞きたいですか、王女殿下」
珍しく諧謔に満ちた台詞を吐いたゲオルギウスは、こちらの返答を待たずして悪い話から始めた。
「王都に暴徒が集まりつつあります」
「……暴徒、とは……ヘルメス情報局の記事で立ち上がった方たちですか? 彼らを暴徒と呼びたくはないのですけれど……」
「ふん、街の外を練り歩くだけならまだしも、王都の城門に押し寄せた連中を暴徒と呼んで何が悪い」
「城門に、押し寄せた……!?」
「最も外である第六城壁で食い止めましたがね。しかし同時に王都内の一部でも蜂起を確認、幾つか部隊を向かわせました」
ゲオルギウスの報告を頭が理解した瞬間、システィーナはさっと青褪めた。
王都内各所で騒動が起こり、外壁の向こうでも人が集まりつつある。このまま手を拱いていては止められなくなるか、あるいは――、大勢の民を、断罪せねばならなくなる。
「っ、い、急いで収束に当たってください、けれどできるだけ穏便に!」
「既にそのようにしておりますので、ご安心を」
「で、ではわたくしは第六城壁へ向かいます。わたくしが直接話せば解散してくれるかもしれませんっ!」
「なるほど、事態が膠着した後ならば有効やもしれませんな。だがそれは最悪の話を聞いてからにしていただきたい」
腰を浮かせたシスティーナは、淡々としたゲオルギウスの忠告に悪寒が走った。震える声で“最悪の話”の先を促すと、老騎士は一つ息を吐いて重大な、あまりに致命的なことを口にした。
「……双丘の泉の取水施設を何者かに襲撃された。狼煙を見てすぐさま緊急部隊を派遣したが、最悪の場合、王都の水源は破壊されるだろう」
ネヴァ山、双丘の泉。
そこには、王都全域に水を供給する古き魔導装置が、設置されている。
●???
「おいおい、親父殿も耄碌したか?」
グラズヘイム王国、王都近郊上空。
飛翔する馬に騎乗し、かつての母国を睥睨したラスヴェート・コヴヘイル・マーロウは、王都に集いつつある群衆の流れと、それに紛れながら王都へ“雑然と進軍”していく戦闘集団を視認して嘆息した。
「……ここは一つ手伝ってやるか。あの親父殿を、この私がだ。いけるな、爺」

ヴィオラ・フルブライト
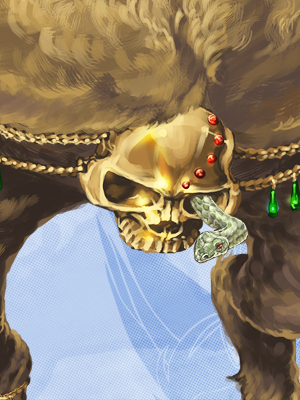
ベリアル
「構わぬ。軽くひと当たりすることもまた偵察よ。兵を集めろ」
「はっ!」
爺が後方に飛んでいく。
ラスヴェートはそれを一顧だにせず、ただ眼下で進軍する軍を見つめ続けていた……。
●イスルダの残滓
黒曜神殿跡地――地下。
歪虚化した先王アレクシウスらとハンターたちが死闘を繰り広げた広間がどこにあるか、それすら判然としないほどに朽ちた廃墟は、濃密な負のマテリアルと“寒々しいにおい”が充満していた。
がらがらと崩れ落ちた瓦礫が音を立てる。潜んだ歪虚が声なき歓声を上げる。
廃墟のうち、比較的原型の残っている地下道へとヴィオラ・フルブライト(kz0007)がベリアル(kz0203)を拘束したまま足を踏み入れる。
ブシシシシ……。
「囀るな」
ヴィオラが気持ち悪い含み笑いを漏らす手元の愚蛇を黙らせる。
――それでも、嘲るような音がどこかから聴こえていた……。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「家族」(5月30日更新)
●変えられぬ過去
心優しき王女殿下は第六城壁へ出向き、自ら大衆の鎮圧に当たるらしい。
ウェルズ・クリストフ・マーロウは王都第二街区に用意した“二つ目の別邸”でその報せを受けた時、鼻で笑うことすらできずに首を振り、大きく一つ息をついた。
――何もできぬのなら、王城に篭っておればよいものを。
あの娘が城壁へ向かってしまえば、王城を囲む算段が無駄になるではないか。
マーロウは眉をしかめて思案し、しかしそちらはそのままでよいかと考え直した。王城を包囲した上で、それを見せつけながら第六城壁で慈愛に満ち満ちた少女と交渉を進めればよい。それはそれは大層心を痛めてくださるに違いない。数千の大衆と、王都と、王城。これだけやって折れぬような娘ではないし、それでもなお我を通すようなら光ある千年王国のために少々躾をせざるを得ない。つまりどちらにしろこちらのやることは大して変わらない。
そう考えるとお優しい彼女の向こう見ずな行動も許容できる。
困った娘だとマーロウは肩を竦め、席を立った。向かうのは第六城壁。敬愛する王女殿下が到着する前にそこに行き、出迎えてやった方がよいだろう。
別邸の玄関を潜り、馬車に乗り込んだ時には既に周囲を愛すべき子らが固めていた。
ホロウレイド騎士団と“子ども達”。どちらもマーロウが保護し、生きる意味を与えてやった若者たちで、優秀で従順な、本当に良い子らだ。
「閣下、カールなる者からの使者が書簡を届けてきておりますが、如何いたしますか」
出発間際、騎士団の一人が扉越しに訊いてくる。「カール?」と考え、それがあの忌々しいダフィールド家の長男であったことを思い出す。
窓から手紙を受け取り、中を見てみた。協力と此度の騒乱における連携に関するあれこれが角ばった手跡で綴られている。
――なるほど、な。
あのダフィールドめの息子にしては随分まともで、能力もありそうに思える。……が。父親に比べれば遥かに与し易い。
「ひとまず私が矢面に立つので後詰として助力を願いたい、今後とも協力できればよいと思うと使者に伝えよ」
「はっ」
馬車が動き出し、車内はゴトゴトという石畳を走る音と振動だけの世界となる。
マーロウは柔らかい座席に深く腰掛け、瞑目した。
独りきりで思い浮かぶのは、孫と、イスルダ島で見た息子のことだ。
マーロウ家に遺された唯一人の心優しい孫。不肖の息子夫婦らが遺した唯一つの宝石。あの子が家を継ぐまでに世界の闇を浄化し尽くさねばならない。優しい――けれど資質的にはあの王女殿下に似て少々危なっかしい――愛おしい忘れ形見は、この穢れに満ちた国を生き抜くことなどきっとできはしない。
故に、今。今しかないのだ。穢れを落とし、あの子の美点が通用する世にする。せねばならぬ。それが遥か昔に栄華を誇った千年王国が蘇る道にも繋がる。この老いた身にできる唯一の奉公ともなるであろう。
――いや、もう一つやらねばならぬことがある、か。
愚息ラスヴェートに引導を渡す。
ホロウレイドにて光の御許へ上ったはずだった、息子。王を守り切ることはできずとも、見事に戦働きを果たしたと信じていた、息子。それがあろうことか穢れに身をやつしてまで未だこの国に居座っていた。それを知った時の恥辱たるや、今思い出しても身震いするほどだった。この年になってあれほどの恥辱、屈辱を覚えることになろうとは思いもしなかった。
――あれは必ず殺す。この一点だけはいくら王女殿下に頭を下げても足りぬ。
マーロウは我知らず昂っていた呼吸を鎮め、そっと目を開く。変化のない車内の一点をまんじりと見ていると、馬車が速度を落としたのが分かった。少しして停車した後、マーロウは自分から扉を開けた。
第六城壁、城門内。
外のざわめきがうねりのように届く。幾つかの領では大衆の活動が立ち消えになったようだが、それでもこの熱量ならば十分あの娘への圧力になるだろう。わざわざ誘導してやった甲斐があったというものだ。王都内部の騒乱はどうも一部でハンターが介入したようで思ったより広がらなかったが。
マーロウが一つ頷いて階段へ向かい、途中の衛兵所で声をかける。
「王国騎士団の者は?」
「は、自分が白の隊所属でありますが……」
「じきに王女殿下もこちらへいらっしゃる。その時は上の歩廊へ案内して差し上げるように。私は外の状況を確認する」
「……は」
――さて。せめて僅かでもあの夢見心地な性格が直っておればよいのだが……。
そうすればすんなりと話が進むやもしれぬ、と楽観的な考えに浸り、自嘲した。あれが理想を口にしないはずがない。
段を上りきり、歩廊へ出る。空は鈍色で、ひどく雲が厚く見えた。
●力と言葉


 「王女殿下、マーロウ閣下が上でお待ちです」
「王女殿下、マーロウ閣下が上でお待ちです」
システィーナ・グラハム(kz0020)は諸々の処理を追認し、後をセドリック・マクファーソン(kz0026)に任せて王都第六城壁へ来た時、門を守る騎士から唐突にそう告げられた。
階段にかけようとしていた足を止め、何度か瞬きしてから先導する騎士の背を見つめる。
「……え?」
「先ほど閣下が来られ、殿下を案内するよう命じられました。……騒動の件は存じております。周囲は私どもが固めますが、ゆめゆめ油断なさいませぬよう」
「……ありがとう。では敵の大将にまみえることとしましょうか」
「王女殿下、『敵』とは穏やかではありませんな。少々言葉を慎まねば殿下の侍従長殿の目が怖い」
後ろから王国騎士団現団長――ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが窘めてくる。そして彼に並び駆ける侍従長マルグリッド・オクレールも小言を続けてくるけれど、システィーナは両手で耳を塞いで先導役の騎士を急かした。
「敵ですよ。水源を脅かすことで王都の人々にまで剣を突き付けたマーロウは……敵です」
「双丘の泉に派遣した者たちが持ち帰るであろう情報がまだ上がってきておらぬ現状、証拠は何もありませんが」
「この状況で、騎士団はそのようなことを言いますか?」
問えば「まさか」という答えと共に後ろから老騎士の嬉しそうな笑いが聞こえてくる。笑いの意味が気にはなるけれど、構わず階上へ。
第六城壁上部歩廊へ出ると、慇懃に頭を垂れたウェルズ・クリストフ・マーロウとその護衛らしき者たちがそこにはいた。軽そうな甲冑を着込んだ護衛とは対照的に、マーロウは狩装束に装飾の少ない剣を佩いている。
前後左右を騎士や侍従隊に囲まれたシスティーナが一歩前に進むと、胸壁の間からその姿が見えたのか、外の人々からざわめきと共に一際大きな歓声が上がった。
許可もなく頭を上げたマーロウがこちらを見据え、瞬き一つ動きを止めた。僅かに目を細め、
「親愛なる王女殿下、少し見ぬ間に幾分凛々しくなられたようですな」
「わたくしも一所に留まってはいられないということです」
「……ふむ、大切な孫を婿にやるこのじいとしましては、殿下が一端の淑女となられるのは大変喜ばしい」
分かりやすく探りを入れてくる。
不測の事態を考えれば戴冠云々などと余計な話をすることはできない。システィーナは微笑して話を流し、尋ねなければならないことを口にした。
「一つ、訊かせてください」
「は、この千年王国の徒に何なりと」
「双丘の泉を襲撃させたのは貴方ですか?」
「なんと! かの泉が襲われた!? あの地が落ちれば王都の命脈は半分尽きたも同然、早急に奪還せねば!」
答えてくれるはずはなかった。侮っている、あるいは見限っている。だから話など通じない。何事もなく話し合うには、時機を失しすぎている。
真に話を通すには――力が、必要だ。
それはひどく空虚な理で、どこか寒々しい。けれど分樹を通して過去の先王――父からそんな話をハンターが聴いてきたはずだ。どうしようもなければぶつかるしかない、と。
「……そうですか。よく分かりました」
「ではこの私めが兵を集めましょう。王都に騒乱が溢れ、水源を脅かされた現状、光ある千年王国を一刻も早く取りまとめねばなりますまい」 「――ウェルズ・クリストフ・マーロウ、貴方に……」
これでいい。いいはずだとシスティーナは自ら言い聞かせる。確かに貴族を糾合して王国の総力を結集するにはこの男と何らかの道を探った方がいいかもしれない。けれど、民を利用するやり口は、どうしようもなく許せない。たとえそれが、正しかったとしてもだ。
胸に手を当て深呼吸一つ、そうして決定的な命令を絞り出した。
「貴方にその資格はありません! 貴方を捕縛……」
――告げるより、早く。
『久しいな、親父殿ォ――!! このラスヴェート、親子の義理にてこの戦に介入させてもらう!!』
遥か上空、雲霞の合間から、黒い騎馬隊が落ちてきた。
心優しき王女殿下は第六城壁へ出向き、自ら大衆の鎮圧に当たるらしい。
ウェルズ・クリストフ・マーロウは王都第二街区に用意した“二つ目の別邸”でその報せを受けた時、鼻で笑うことすらできずに首を振り、大きく一つ息をついた。
――何もできぬのなら、王城に篭っておればよいものを。
あの娘が城壁へ向かってしまえば、王城を囲む算段が無駄になるではないか。
マーロウは眉をしかめて思案し、しかしそちらはそのままでよいかと考え直した。王城を包囲した上で、それを見せつけながら第六城壁で慈愛に満ち満ちた少女と交渉を進めればよい。それはそれは大層心を痛めてくださるに違いない。数千の大衆と、王都と、王城。これだけやって折れぬような娘ではないし、それでもなお我を通すようなら光ある千年王国のために少々躾をせざるを得ない。つまりどちらにしろこちらのやることは大して変わらない。
そう考えるとお優しい彼女の向こう見ずな行動も許容できる。
困った娘だとマーロウは肩を竦め、席を立った。向かうのは第六城壁。敬愛する王女殿下が到着する前にそこに行き、出迎えてやった方がよいだろう。
別邸の玄関を潜り、馬車に乗り込んだ時には既に周囲を愛すべき子らが固めていた。
ホロウレイド騎士団と“子ども達”。どちらもマーロウが保護し、生きる意味を与えてやった若者たちで、優秀で従順な、本当に良い子らだ。
「閣下、カールなる者からの使者が書簡を届けてきておりますが、如何いたしますか」
出発間際、騎士団の一人が扉越しに訊いてくる。「カール?」と考え、それがあの忌々しいダフィールド家の長男であったことを思い出す。
窓から手紙を受け取り、中を見てみた。協力と此度の騒乱における連携に関するあれこれが角ばった手跡で綴られている。
――なるほど、な。
あのダフィールドめの息子にしては随分まともで、能力もありそうに思える。……が。父親に比べれば遥かに与し易い。
「ひとまず私が矢面に立つので後詰として助力を願いたい、今後とも協力できればよいと思うと使者に伝えよ」
「はっ」
馬車が動き出し、車内はゴトゴトという石畳を走る音と振動だけの世界となる。
マーロウは柔らかい座席に深く腰掛け、瞑目した。
独りきりで思い浮かぶのは、孫と、イスルダ島で見た息子のことだ。
マーロウ家に遺された唯一人の心優しい孫。不肖の息子夫婦らが遺した唯一つの宝石。あの子が家を継ぐまでに世界の闇を浄化し尽くさねばならない。優しい――けれど資質的にはあの王女殿下に似て少々危なっかしい――愛おしい忘れ形見は、この穢れに満ちた国を生き抜くことなどきっとできはしない。
故に、今。今しかないのだ。穢れを落とし、あの子の美点が通用する世にする。せねばならぬ。それが遥か昔に栄華を誇った千年王国が蘇る道にも繋がる。この老いた身にできる唯一の奉公ともなるであろう。
――いや、もう一つやらねばならぬことがある、か。
愚息ラスヴェートに引導を渡す。
ホロウレイドにて光の御許へ上ったはずだった、息子。王を守り切ることはできずとも、見事に戦働きを果たしたと信じていた、息子。それがあろうことか穢れに身をやつしてまで未だこの国に居座っていた。それを知った時の恥辱たるや、今思い出しても身震いするほどだった。この年になってあれほどの恥辱、屈辱を覚えることになろうとは思いもしなかった。
――あれは必ず殺す。この一点だけはいくら王女殿下に頭を下げても足りぬ。
マーロウは我知らず昂っていた呼吸を鎮め、そっと目を開く。変化のない車内の一点をまんじりと見ていると、馬車が速度を落としたのが分かった。少しして停車した後、マーロウは自分から扉を開けた。
第六城壁、城門内。
外のざわめきがうねりのように届く。幾つかの領では大衆の活動が立ち消えになったようだが、それでもこの熱量ならば十分あの娘への圧力になるだろう。わざわざ誘導してやった甲斐があったというものだ。王都内部の騒乱はどうも一部でハンターが介入したようで思ったより広がらなかったが。
マーロウが一つ頷いて階段へ向かい、途中の衛兵所で声をかける。
「王国騎士団の者は?」
「は、自分が白の隊所属でありますが……」
「じきに王女殿下もこちらへいらっしゃる。その時は上の歩廊へ案内して差し上げるように。私は外の状況を確認する」
「……は」
――さて。せめて僅かでもあの夢見心地な性格が直っておればよいのだが……。
そうすればすんなりと話が進むやもしれぬ、と楽観的な考えに浸り、自嘲した。あれが理想を口にしないはずがない。
段を上りきり、歩廊へ出る。空は鈍色で、ひどく雲が厚く見えた。
●力と言葉

システィーナ・グラハム

セドリック・マクファーソン

ゲオルギウス・グラニフ・
グランフェルト
システィーナ・グラハム(kz0020)は諸々の処理を追認し、後をセドリック・マクファーソン(kz0026)に任せて王都第六城壁へ来た時、門を守る騎士から唐突にそう告げられた。
階段にかけようとしていた足を止め、何度か瞬きしてから先導する騎士の背を見つめる。
「……え?」
「先ほど閣下が来られ、殿下を案内するよう命じられました。……騒動の件は存じております。周囲は私どもが固めますが、ゆめゆめ油断なさいませぬよう」
「……ありがとう。では敵の大将にまみえることとしましょうか」
「王女殿下、『敵』とは穏やかではありませんな。少々言葉を慎まねば殿下の侍従長殿の目が怖い」
後ろから王国騎士団現団長――ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが窘めてくる。そして彼に並び駆ける侍従長マルグリッド・オクレールも小言を続けてくるけれど、システィーナは両手で耳を塞いで先導役の騎士を急かした。
「敵ですよ。水源を脅かすことで王都の人々にまで剣を突き付けたマーロウは……敵です」
「双丘の泉に派遣した者たちが持ち帰るであろう情報がまだ上がってきておらぬ現状、証拠は何もありませんが」
「この状況で、騎士団はそのようなことを言いますか?」
問えば「まさか」という答えと共に後ろから老騎士の嬉しそうな笑いが聞こえてくる。笑いの意味が気にはなるけれど、構わず階上へ。
第六城壁上部歩廊へ出ると、慇懃に頭を垂れたウェルズ・クリストフ・マーロウとその護衛らしき者たちがそこにはいた。軽そうな甲冑を着込んだ護衛とは対照的に、マーロウは狩装束に装飾の少ない剣を佩いている。
前後左右を騎士や侍従隊に囲まれたシスティーナが一歩前に進むと、胸壁の間からその姿が見えたのか、外の人々からざわめきと共に一際大きな歓声が上がった。
許可もなく頭を上げたマーロウがこちらを見据え、瞬き一つ動きを止めた。僅かに目を細め、
「親愛なる王女殿下、少し見ぬ間に幾分凛々しくなられたようですな」
「わたくしも一所に留まってはいられないということです」
「……ふむ、大切な孫を婿にやるこのじいとしましては、殿下が一端の淑女となられるのは大変喜ばしい」
分かりやすく探りを入れてくる。
不測の事態を考えれば戴冠云々などと余計な話をすることはできない。システィーナは微笑して話を流し、尋ねなければならないことを口にした。
「一つ、訊かせてください」
「は、この千年王国の徒に何なりと」
「双丘の泉を襲撃させたのは貴方ですか?」
「なんと! かの泉が襲われた!? あの地が落ちれば王都の命脈は半分尽きたも同然、早急に奪還せねば!」
答えてくれるはずはなかった。侮っている、あるいは見限っている。だから話など通じない。何事もなく話し合うには、時機を失しすぎている。
真に話を通すには――力が、必要だ。
それはひどく空虚な理で、どこか寒々しい。けれど分樹を通して過去の先王――父からそんな話をハンターが聴いてきたはずだ。どうしようもなければぶつかるしかない、と。
「……そうですか。よく分かりました」
「ではこの私めが兵を集めましょう。王都に騒乱が溢れ、水源を脅かされた現状、光ある千年王国を一刻も早く取りまとめねばなりますまい」 「――ウェルズ・クリストフ・マーロウ、貴方に……」
これでいい。いいはずだとシスティーナは自ら言い聞かせる。確かに貴族を糾合して王国の総力を結集するにはこの男と何らかの道を探った方がいいかもしれない。けれど、民を利用するやり口は、どうしようもなく許せない。たとえそれが、正しかったとしてもだ。
胸に手を当て深呼吸一つ、そうして決定的な命令を絞り出した。
「貴方にその資格はありません! 貴方を捕縛……」
――告げるより、早く。
『久しいな、親父殿ォ――!! このラスヴェート、親子の義理にてこの戦に介入させてもらう!!』
遥か上空、雲霞の合間から、黒い騎馬隊が落ちてきた。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●「女王戴冠」(6月22日更新)
●羽化



 第六城壁での戦いから戻れば、そこにはこれはこれで戦いのような事後処理の山が待っていた。
第六城壁での戦いから戻れば、そこにはこれはこれで戦いのような事後処理の山が待っていた。
システィーナ・グラハム(kz0020)は王城正門を守っていた黒髪の青年を“一般協力者”として手厚く労い、今日のところは帰ってもらう。“歪虚の急襲に際しいち国民として立ち上がり、王城を守り切った名もなき戦士”は、さぞかし聖堂教会にも受けが良い――というより教義からして良くなければいけないだろう。
この一点を以て黒髪の青年――エリオット・ヴァレンタイン(kz0025)の有耶無耶のうちに中断されていた異端審問を有利に乗り切りたい。
「良くやってくれました」
「は、謹慎中の身なれど国の危難に動かずにおれませんでした。勝手をしたことを謝罪します」
「相変わらず固い奴め。戦功さえあれば独断専行は讃えられるものだろう」
システィーナと騎士団長ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが苦笑して黒の騎士長を見送る。
そして文官たちに顔を見せながら執務室へ行き、セドリック・マクファーソン(kz0026)を呼び出せば戦いの本番だ。
王都全域の被害報告や残敵掃討、行方不明者の捜索や倒壊物の報告など、直近で把握し手配しなければならないものも膨大にあるが、それらは一つ一つ消化していくことができる。より面倒なのは、王都に押し寄せた人々の対処と聖堂教会や貴族諸侯の根回しだ。
「王女殿下は彼ら“暴徒”のことをどうされるおつもりですか」
大司教が書類に何事か指示を書きながら淡々と訊いてくる。口調に反して大司教がシスティーナの資質だか何だかをつぶさに見ているのは、あえて暴徒と言ったことから明白だ。
システィーナは眉根を寄せ、口を開いた。
「……まずはわたくしの政略結婚がなくなったことを伝えます。その後は……労役、を。イスルダ島は非覚醒者にはまだ危険ですけれど、リベルタース地方も未だ荒廃していますから、そちらの再開拓を」
「期間は? また彼らの食料や最低限の生活に必要な物資は? 荒廃した地を開拓させる、なるほど結構な試練ですが、その分だけこちらの負担するものは大きくなりましょう」
「で、では一年間の王都復興作業を……」
「ほう、確かに王都での作業ならば余分に予算を割く必要はありませんな。ではそれを選ばれた理由をお教えいただいても? まさか手が足りないからというだけではありますまいな?」
「……彼らの行動もまた王都を破壊するかもしれなかったものです。事実“第七街区”の被害は歪虚によるものより彼らによる被害が大きいでしょう」
“第七街区”はまだ正確には王都ではない。けれど建築中の第七城壁が完成すれば王都に組み込まれる町で、そこに住む人は十年前にリベルタースから命からがら脱出してきた者たちだ。彼らも無碍に扱っていいはずがない。
「ですから自分たちの行いを直視してもらう為には最適かと判断しました」
大司教をまっすぐ見て言うと、彼は書類から顔を上げて一つ頷いた。
「なるほど。では“一年間の王都復興作業、あるいは半年間のリベルタース再開拓”のどちらかを課すという方向で話を進めましょう」
「え……でも」
「少しずつでもいずれやらねばならんことですからな。それより今は戴冠の……」
大司教が話を変えようとした時、扉をノックする音がした。システィーナが許可を出すと、研究者然とした男がのそりと入室してきた。
研究者は大司教に目礼して一枚の紙を渡し、最低限の報告をしてくる。
「敵大将のラスヴェートの持っていた石を解析に回す前に少し見てみたんですがね、これはただ負のマテリアルに侵されているだけの石じゃない。詳しくは分かりませんが、何かしらの仕掛けがありそうです。だいたいラスヴェートの消滅と一緒に消えないということは本来の持ち主は別にいるということですからね。それを何故持っていたのか。怪しすぎる。王都で調べるには危険ですね」
言うが早いか、研究者はそそくさと退室していった。
大司教が嘆息して資料に目を落とし、少ししてこちらの机に置く。走り書きのような乱雑な文字で書き連ねられた所感を見ていると、大司教が咳払いして話を戻した。
「戴冠式の件ですが、教会と王家派の伯爵以上への根回しは終えています」








 「……貴族はマーロウ卿に任せましたけれど、大司教さまも見ていていただけると安心できます」
「……貴族はマーロウ卿に任せましたけれど、大司教さまも見ていていただけると安心できます」
「かしこまりました。――よろしかったのですか?」
マーロウを無罪……とするのは流石に不可能にしても、軽い罰で済ませる。それでよかったのかと大司教は訊いてくる。
大公自身はもしかしたら協力的になるかもしれないけれど、仮にそうなったとしても大公以外に禍根を残しすぎた。戦力的には確かにプラスになるだろう。しかし大公を首魁として処罰して絶対的な王政に移行した方が物事は単純化したはずだ。
それに、強い女王になりたかった。たとえばヴィルヘルミナ――お姉さまのような。血を分けているわけではない。昔から格好良かったあの人に憧れただけだ。でもそんな女王にはもはやなれない。それは解っている。解っていて、システィーナは微笑した。
「えぇ」
脳裏には、同い年くらいだろうか、ごく当たり前の人々の営みを身に纏ったような少女――柏木 千春(ka3061)の姿が焼き付いている。
――そうして事後処理に奔走したのち、システィーナは女王戴冠式を迎えた。
●とある古ぼけた紙片より
時に王国暦1018年6月下旬であった。
その日は朝から王都中、もといグラズヘイム王国中が騒乱に包まれていた。騒乱といえど先日までの結婚騒動ではない。先王アレクシウスの遺した一人娘システィーナ・グラハムの戴冠式の為にである。
布告は僅か三日前。結婚騒動が多少収束したかと思った矢先の布告に民は大いに混乱し、その後、彼女を支持する者は祝福の声を上げた。その後三日、竜の巣を突いたが如き騒ぎは継続し、戴冠の朝となったのであった。
当日のグラズヘイム王国王都イルダーナの大通りは早朝から大勢の人が溢れ返っていた。商魂逞しい露店も既に開いていたものの、かような意味での『祭り』は戴冠式を終えた後が本番である。戴冠式ののちに『女王が』広場で挨拶を行い、それが終わってようやく飲めや歌えの祭りが始まるのだ。今、大通りにいる多くの大衆はただ行進を見学せんが為だけに集まっているに過ぎない。王城から一度第三街区まで下り、第三街区を一周したのちに聖ヴェレニウス大聖堂に入る。それが順路とされていた。
儀礼服に身を包んだ王国騎士団の赤、青、白、黒四隊が第三街区に姿を現した時の大衆の歓声は天を衝くほどであった。ついで聖堂戦士団、侍従隊と続き、システィーナ・グラハムの乗った馬車が通る。王女システィーナは時に馬車から降りては手を振り、幾らか徒歩で順路を進んでから馬車に乗り込むことを繰り返した為、大聖堂に到着する頃には既に日は中天に掛かっていた。
大聖堂は身廊から側廊、翼廊にいたるまで人という人で埋まっていた。
王国貴族やハンターを中心とした招待客の面々もまた筆の乗る個性的な顔ぶれが揃っている。先の王都防衛において参戦したハンターはみな招待されていたようで、互いに談笑している姿も見える。組織されて日が浅い黒の隊の者たちもまた多くが出席しているであろう。欠席した者はいるのだろうか。いるとすれば如何様な理由であろうか。気にはなるがまずは戴冠という歴史的出来事を見届けねばならぬ。
特筆すべきはセルゲン(ka6612)をはじめとした鬼種の者たちも参列が許可されていることか。この様子ならばゾンネンシュトラール帝国の者も招待されているかもしれないが、この人混みでは探すこともできぬ。
ヴァルナ=エリゴス(ka2651)やレイレリア・リナークシス(ka3872)がドレスに身を包み、楚々とした様子で参列している。シャール家のクローディオ(ka0030)とグリーヴ家のジャック・J(ka1305)が並び立ち、何事か語り合っているのを聴き逃したのは痛恨事である。ハンターであり王国貴族でもある彼らはこの場によく馴染んでいる。……よく辺りを窺えば節制の精霊プラトニスもハンターに交じり、談笑していた。これは馴染みすぎではなかろうか?
そのうち教区大司教が戴冠式の始まりを告げ、ヴィオラ・フルブライト(kz0007)や聖堂戦士に左右を固められたシスティーナ・グラハムが入場した。裾の長い空色のドレスに深紅のマントを羽織ったシスティーナの表情は緊張しているようにも、屹然としているようにも見える。
しんと静まり返った大聖堂で、彼女はゆっくりと歩を進める。コツ、コツとヒールの音が響き、その度に彼女は王へと近付いてゆく。内陣を抜け、祭壇の前で跪くと、彼女は“光”に宣誓した。
「光の教義を遵守し、身命を賭して人々の日常を守ることを誓います」
それに応じるが如く祭壇が瞬き、貴族たちが声にならぬ声を漏らした。
システィーナが後陣に置かれた豪奢な椅子に座ると、教区大司教が恭しく王錫と宝珠を授けた。そして最後に、王冠を。
王女であった彼女は微笑を浮かべたまま、冠が落ちないか確認するように僅かに首を傾げ、そののちに立ち上がった。
「わたくしは“光”に誓ったことを破らないと、皆さまに誓います。何でもない日常を守る為、必ずや歪虚を討ち滅ぼさん!」
歓声が爆発した。
この日、この瞬間、九年の空位期間を経て、グラズヘイム王国は女王を得たのだ。
●王
御座所に戻ってきたミュールは、玉座に腰掛ける主の姿を見て黄色い声を上げた。
「イヴさまぁ! 人間がね、いじめるの。ミュールの“ミュール”も殺されちゃった」
片肘をついて座っているイヴにしな垂れかかるミュール。イヴは振り払うこともなければミュールに目を向けることもなく、目を細めた。
「人間如きが未だ囀っているのか」
「うん。ごめんなさい、イヴさま。蜘蛛も羊も役立たずしかいない」
「……そうか。仕方がないな。ならばこの俺が出向いてやるとしよう」
「やったぁ!」
「ご苦労だった、ミュール」
えへへぇ、とミュールははにかむ。頬を赤らめた姿は幸福というものを体現しているかのようだ。
イヴが幼女の頭を撫で、訊く。
「あの男はどうした。ベリアルのもとから来た……」
「えっと……らすなんとか? あれは死んじゃった。必要だった?」
「いいや、構わない」
人間の様子を探る程度の命令すらこなせないものなど部下ではない。
イヴは瞑目して“あれ”の存在を感知する。
まだ消滅してはいない。ならば“あれ”を通して宣戦布告でもしてやろうではないか。せっかくの王の出陣だ。人間如きではあるが、先に布告しておいて盛大に出迎えることを許してやってもいい。
「ミュール、着替えてこい。俺の従者たるに相応しい服にな」
「はぁい!」
ててててーと駆けていく幼女の後ろ姿をイヴはじっと見つめる。そしてその姿が見えなくなると、“あれ”との接続に集中した。
今ごろ人間どもはミュールを撃退して喜んでいるのだろう。それを考えると腸が煮えくり返りそうになるが、人間を滅ぼすのに急行してしまうのは悪手だ。王には王に相応しい振る舞いがあり、段取りがある。宣戦を布告し、蹂躙したのちに出陣しなければならないのだ。
――せいぜい束の間の希望に浸っているがいい。それが絶望へと変わる瞬間こそが、この俺を喜ばせてくれるのだから。
玉座の間に哄笑が響き渡る。
それはちょうど、グラズヘイムの地で一人の女王が誕生した頃だった。

システィーナ・グラハム

エリオット・ヴァレンタイン

ゲオルギウス・グラニフ・
グランフェルト

セドリック・マクファーソン
システィーナ・グラハム(kz0020)は王城正門を守っていた黒髪の青年を“一般協力者”として手厚く労い、今日のところは帰ってもらう。“歪虚の急襲に際しいち国民として立ち上がり、王城を守り切った名もなき戦士”は、さぞかし聖堂教会にも受けが良い――というより教義からして良くなければいけないだろう。
この一点を以て黒髪の青年――エリオット・ヴァレンタイン(kz0025)の有耶無耶のうちに中断されていた異端審問を有利に乗り切りたい。
「良くやってくれました」
「は、謹慎中の身なれど国の危難に動かずにおれませんでした。勝手をしたことを謝罪します」
「相変わらず固い奴め。戦功さえあれば独断専行は讃えられるものだろう」
システィーナと騎士団長ゲオルギウス・グラニフ・グランフェルトが苦笑して黒の騎士長を見送る。
そして文官たちに顔を見せながら執務室へ行き、セドリック・マクファーソン(kz0026)を呼び出せば戦いの本番だ。
王都全域の被害報告や残敵掃討、行方不明者の捜索や倒壊物の報告など、直近で把握し手配しなければならないものも膨大にあるが、それらは一つ一つ消化していくことができる。より面倒なのは、王都に押し寄せた人々の対処と聖堂教会や貴族諸侯の根回しだ。
「王女殿下は彼ら“暴徒”のことをどうされるおつもりですか」
大司教が書類に何事か指示を書きながら淡々と訊いてくる。口調に反して大司教がシスティーナの資質だか何だかをつぶさに見ているのは、あえて暴徒と言ったことから明白だ。
システィーナは眉根を寄せ、口を開いた。
「……まずはわたくしの政略結婚がなくなったことを伝えます。その後は……労役、を。イスルダ島は非覚醒者にはまだ危険ですけれど、リベルタース地方も未だ荒廃していますから、そちらの再開拓を」
「期間は? また彼らの食料や最低限の生活に必要な物資は? 荒廃した地を開拓させる、なるほど結構な試練ですが、その分だけこちらの負担するものは大きくなりましょう」
「で、では一年間の王都復興作業を……」
「ほう、確かに王都での作業ならば余分に予算を割く必要はありませんな。ではそれを選ばれた理由をお教えいただいても? まさか手が足りないからというだけではありますまいな?」
「……彼らの行動もまた王都を破壊するかもしれなかったものです。事実“第七街区”の被害は歪虚によるものより彼らによる被害が大きいでしょう」
“第七街区”はまだ正確には王都ではない。けれど建築中の第七城壁が完成すれば王都に組み込まれる町で、そこに住む人は十年前にリベルタースから命からがら脱出してきた者たちだ。彼らも無碍に扱っていいはずがない。
「ですから自分たちの行いを直視してもらう為には最適かと判断しました」
大司教をまっすぐ見て言うと、彼は書類から顔を上げて一つ頷いた。
「なるほど。では“一年間の王都復興作業、あるいは半年間のリベルタース再開拓”のどちらかを課すという方向で話を進めましょう」
「え……でも」
「少しずつでもいずれやらねばならんことですからな。それより今は戴冠の……」
大司教が話を変えようとした時、扉をノックする音がした。システィーナが許可を出すと、研究者然とした男がのそりと入室してきた。
研究者は大司教に目礼して一枚の紙を渡し、最低限の報告をしてくる。
「敵大将のラスヴェートの持っていた石を解析に回す前に少し見てみたんですがね、これはただ負のマテリアルに侵されているだけの石じゃない。詳しくは分かりませんが、何かしらの仕掛けがありそうです。だいたいラスヴェートの消滅と一緒に消えないということは本来の持ち主は別にいるということですからね。それを何故持っていたのか。怪しすぎる。王都で調べるには危険ですね」
言うが早いか、研究者はそそくさと退室していった。
大司教が嘆息して資料に目を落とし、少ししてこちらの机に置く。走り書きのような乱雑な文字で書き連ねられた所感を見ていると、大司教が咳払いして話を戻した。
「戴冠式の件ですが、教会と王家派の伯爵以上への根回しは終えています」

柏木 千春

セルゲン

ヴァルナ・エリゴス

レイレリア・リナークシス

クローディオ・シャール

ジャック・J・グリーヴ

プラトニス

ヴィオラ・フルブライト

ミュール
「かしこまりました。――よろしかったのですか?」
マーロウを無罪……とするのは流石に不可能にしても、軽い罰で済ませる。それでよかったのかと大司教は訊いてくる。
大公自身はもしかしたら協力的になるかもしれないけれど、仮にそうなったとしても大公以外に禍根を残しすぎた。戦力的には確かにプラスになるだろう。しかし大公を首魁として処罰して絶対的な王政に移行した方が物事は単純化したはずだ。
それに、強い女王になりたかった。たとえばヴィルヘルミナ――お姉さまのような。血を分けているわけではない。昔から格好良かったあの人に憧れただけだ。でもそんな女王にはもはやなれない。それは解っている。解っていて、システィーナは微笑した。
「えぇ」
脳裏には、同い年くらいだろうか、ごく当たり前の人々の営みを身に纏ったような少女――柏木 千春(ka3061)の姿が焼き付いている。
――そうして事後処理に奔走したのち、システィーナは女王戴冠式を迎えた。
●とある古ぼけた紙片より
時に王国暦1018年6月下旬であった。
その日は朝から王都中、もといグラズヘイム王国中が騒乱に包まれていた。騒乱といえど先日までの結婚騒動ではない。先王アレクシウスの遺した一人娘システィーナ・グラハムの戴冠式の為にである。
布告は僅か三日前。結婚騒動が多少収束したかと思った矢先の布告に民は大いに混乱し、その後、彼女を支持する者は祝福の声を上げた。その後三日、竜の巣を突いたが如き騒ぎは継続し、戴冠の朝となったのであった。
当日のグラズヘイム王国王都イルダーナの大通りは早朝から大勢の人が溢れ返っていた。商魂逞しい露店も既に開いていたものの、かような意味での『祭り』は戴冠式を終えた後が本番である。戴冠式ののちに『女王が』広場で挨拶を行い、それが終わってようやく飲めや歌えの祭りが始まるのだ。今、大通りにいる多くの大衆はただ行進を見学せんが為だけに集まっているに過ぎない。王城から一度第三街区まで下り、第三街区を一周したのちに聖ヴェレニウス大聖堂に入る。それが順路とされていた。
儀礼服に身を包んだ王国騎士団の赤、青、白、黒四隊が第三街区に姿を現した時の大衆の歓声は天を衝くほどであった。ついで聖堂戦士団、侍従隊と続き、システィーナ・グラハムの乗った馬車が通る。王女システィーナは時に馬車から降りては手を振り、幾らか徒歩で順路を進んでから馬車に乗り込むことを繰り返した為、大聖堂に到着する頃には既に日は中天に掛かっていた。
大聖堂は身廊から側廊、翼廊にいたるまで人という人で埋まっていた。
王国貴族やハンターを中心とした招待客の面々もまた筆の乗る個性的な顔ぶれが揃っている。先の王都防衛において参戦したハンターはみな招待されていたようで、互いに談笑している姿も見える。組織されて日が浅い黒の隊の者たちもまた多くが出席しているであろう。欠席した者はいるのだろうか。いるとすれば如何様な理由であろうか。気にはなるがまずは戴冠という歴史的出来事を見届けねばならぬ。
特筆すべきはセルゲン(ka6612)をはじめとした鬼種の者たちも参列が許可されていることか。この様子ならばゾンネンシュトラール帝国の者も招待されているかもしれないが、この人混みでは探すこともできぬ。
ヴァルナ=エリゴス(ka2651)やレイレリア・リナークシス(ka3872)がドレスに身を包み、楚々とした様子で参列している。シャール家のクローディオ(ka0030)とグリーヴ家のジャック・J(ka1305)が並び立ち、何事か語り合っているのを聴き逃したのは痛恨事である。ハンターであり王国貴族でもある彼らはこの場によく馴染んでいる。……よく辺りを窺えば節制の精霊プラトニスもハンターに交じり、談笑していた。これは馴染みすぎではなかろうか?
そのうち教区大司教が戴冠式の始まりを告げ、ヴィオラ・フルブライト(kz0007)や聖堂戦士に左右を固められたシスティーナ・グラハムが入場した。裾の長い空色のドレスに深紅のマントを羽織ったシスティーナの表情は緊張しているようにも、屹然としているようにも見える。
しんと静まり返った大聖堂で、彼女はゆっくりと歩を進める。コツ、コツとヒールの音が響き、その度に彼女は王へと近付いてゆく。内陣を抜け、祭壇の前で跪くと、彼女は“光”に宣誓した。
「光の教義を遵守し、身命を賭して人々の日常を守ることを誓います」
それに応じるが如く祭壇が瞬き、貴族たちが声にならぬ声を漏らした。
システィーナが後陣に置かれた豪奢な椅子に座ると、教区大司教が恭しく王錫と宝珠を授けた。そして最後に、王冠を。
王女であった彼女は微笑を浮かべたまま、冠が落ちないか確認するように僅かに首を傾げ、そののちに立ち上がった。
「わたくしは“光”に誓ったことを破らないと、皆さまに誓います。何でもない日常を守る為、必ずや歪虚を討ち滅ぼさん!」
歓声が爆発した。
この日、この瞬間、九年の空位期間を経て、グラズヘイム王国は女王を得たのだ。
●王
御座所に戻ってきたミュールは、玉座に腰掛ける主の姿を見て黄色い声を上げた。
「イヴさまぁ! 人間がね、いじめるの。ミュールの“ミュール”も殺されちゃった」
片肘をついて座っているイヴにしな垂れかかるミュール。イヴは振り払うこともなければミュールに目を向けることもなく、目を細めた。
「人間如きが未だ囀っているのか」
「うん。ごめんなさい、イヴさま。蜘蛛も羊も役立たずしかいない」
「……そうか。仕方がないな。ならばこの俺が出向いてやるとしよう」
「やったぁ!」
「ご苦労だった、ミュール」
えへへぇ、とミュールははにかむ。頬を赤らめた姿は幸福というものを体現しているかのようだ。
イヴが幼女の頭を撫で、訊く。
「あの男はどうした。ベリアルのもとから来た……」
「えっと……らすなんとか? あれは死んじゃった。必要だった?」
「いいや、構わない」
人間の様子を探る程度の命令すらこなせないものなど部下ではない。
イヴは瞑目して“あれ”の存在を感知する。
まだ消滅してはいない。ならば“あれ”を通して宣戦布告でもしてやろうではないか。せっかくの王の出陣だ。人間如きではあるが、先に布告しておいて盛大に出迎えることを許してやってもいい。
「ミュール、着替えてこい。俺の従者たるに相応しい服にな」
「はぁい!」
ててててーと駆けていく幼女の後ろ姿をイヴはじっと見つめる。そしてその姿が見えなくなると、“あれ”との接続に集中した。
今ごろ人間どもはミュールを撃退して喜んでいるのだろう。それを考えると腸が煮えくり返りそうになるが、人間を滅ぼすのに急行してしまうのは悪手だ。王には王に相応しい振る舞いがあり、段取りがある。宣戦を布告し、蹂躙したのちに出陣しなければならないのだ。
――せいぜい束の間の希望に浸っているがいい。それが絶望へと変わる瞬間こそが、この俺を喜ばせてくれるのだから。
玉座の間に哄笑が響き渡る。
それはちょうど、グラズヘイムの地で一人の女王が誕生した頃だった。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)





