ゲスト
(ka0000)
【東征】これまでの経緯


更新情報(9月2日更新)
【東征】本編ストーリーノベル
各タイトルをクリックすると、下にノベルが展開されます。
――エトファリカ連邦国は、黒龍の加護から成る独自の守護結界を有している。
この守護結界の存在こそ、東方が百年間の孤立無援を凌ぐことが出来た最大の理由であると言えよう。
「今現在、この天ノ都周辺には歪虚を拒絶する結界が張られています。しかし、元々この結界は東方全域を覆う程の力を持っていました」
しかし百年以上前に、辺境との連絡を分断したのは北からやってきた歪虚。
「――即ち、今お前らの住む西方で跋扈している連中の一部だ」
辺境で怠惰の歪虚を退けた西方軍が東方の奪還に動き出せば、西方の歪虚もそれを阻止するため、東方へ向かうだろう。
首都天ノ都の南からは憤怒の歪虚本軍。そして北からは西方歪虚の増援が予想される。つまり、東方は挟み撃ちにされる格好だ。
「今、黒龍の結界は弱っちまってる。転移門を開くのに力を使ってるせいだ。つまり、この結界が破られそうなのはお前ら西方連中のせいでもあるんだな?、これが」
ニンマリと笑うスメラギ。この仕事を断ったら西方に帰れなくなる……そんな予感がした。
「北には歪虚最大の領域、“北荻”が存在します。しかし南側には今のところ憤怒の軍があるのみです」
「元々憤怒の連中は何か目的があって南に行ったみたいなんだがな。お前ら心当たりあるか?」
そう言われても思い当たる節は今のところないのだが、もしかしたら何かを見落としているのかもしれない。
「ともあれ、北の歪虚を全滅させようとしてもほぼ無制限に増援が送り込まれるが……南の孤立した憤怒軍を打ち破れば、事実上東方は開放されるわけだ」
「南へ進軍する為には、まずは西方増援を迎え入れる転移門の安定化と結界強度を上げる為、各地の龍脈を奪還し、黒龍の力を取り戻す必要があります」
「大反攻作戦の為の事前準備ってわけだ。お前らが龍脈を取り返してくれりゃ、俺様がガッチリ結界を広げてやる」
「この作戦には、西方諸国にも協力を依頼しております。転移門の力が安定しない為、大規模な増援は見込めませんが……」
「結界の強度が上がれば転移門に力を注げるようになる。それまでは少数精鋭で事を進めるぜ」
一通り話を終えると、スメラギは指を鳴らし。
「俺様達東方は、百年以上、この時を待ってきた。起こり得ない奇跡と理解しながら、それでもと、な。だがお前達は辺境の地で遂に成し遂げたんだ。歪虚から人類の領土を取り戻すっていう奇跡をな」
「我々だけではとても考えられない作戦でした。これも全ては皆様、西のモノノフの力があってこそ」
「どうせ人生は瞬く間、夢の挾間の出来事よ。恐れず惑わず――笑って死のうぜ?」
スメラギの言葉は嘘でも冗談でもない。
この国において、戦いの中で死ぬ事は恐怖すべき結末ではない。
最も恐るべき事。それは、最期に怯え、竦み、みっともなく命を惜しみ、何も守れずに散る事なのだ。
「勝てば英雄、負ければ死ぬだけ。さあ、楽しい遊戯の幕開けだぜ!」
「スメラギ様は帝としてこの国を身体を張って守護していらっしゃいます。ヴィルヘルミナ様もバタルトゥ様も、戦士として兵を率い戦っていらっしゃるのです」
「いや、あいつらが変態なだけだろ。嫌いじゃねーが」
「本当に……東方の事を忘れていたわけではありませんでした。ずっと心配していたし、救いたいと考えていました。けれどわたくしにはその理想を実現するだけの力がなくて……」
「闇雲に歪虚の領域を横断してこっちくるなんて無理だろ?」
「はい……。ですからわたくしは、兵の命と東方の皆さんの命を秤にかけ……へうぅっ!?」
急に頬をつねられ涙目になるシスティーナ。スメラギは深々と溜息を零し。
「俺様だってなぁ、御柱様なんて役割好きでやってねーし……逃げ出したいと思った事だって何度もあるわ。だけど仕方ないって自分に言い聞かせて、他人を恨みながらヘラヘラしてなんとかやってきたんだよ」
虚空を睨むスメラギの横顔は歳相応だ。少年は懐から札を取り出し。
「オイマトもそうだけどよ。お前らスゲェと思うぜ? 好き好んでこんな東方まで来てよ。バカとしか言いようがねーわ」
バカという言葉に目を丸くするシスティーナ。スメラギは鼻頭をこすりながら笑い。
「俺様はこの城から動けねぇけどよ。お前にはどこにでも行ける足があるじゃん。時間だっていっぱいあるじゃねぇか。未来に可能性が無限にある……それが羨ましいよ」
「……スメラギ様」
「悩んだってしょうがねーんだ。人は平等じゃねぇからな。結局は与えられた手札で、そん時々勝負してくしかない。そんで負けて泣いたって、明日はきっと来る」
取り出した札の束を手早くシャッフルし、その中から一枚をシスティーナに選ばせる。
そこには太陽を抱えた少女を龍が取り巻く絵柄が記されていた。
「タロットカード……ですか?」
「西方にもあるんだってな。占い札だよ。あんたはきっと、デッカクなるぜ?」
「信じても良いのでしょうか――明日を」
二人は並んで夜空を見上げる。聞き耳を立てていたヴィルヘルミナは笑みを作り、足音を消して階段を登り始めた。
「爆裂遠隔破城槌、構え……撃てィ――ッ!!」
巨大な城の頭部に該当する部分に紫色の光が収束し、それが光弾となって放たれる。
光は首都を覆う結界に激突すると、爆裂。歪虚を阻む絶対の力である筈の結界は、脆くも崩れ去った。
『ほォ。やればできんじゃねェか、ジジイ』
「とっても興味深いわぁ。あなたとのお仕事……色々と勉強になりそう♪」
「ふはははは! 帝も結界を調整し再起動するじゃろうが、その前に天ノ都に歪虚を送り込む! 作戦開始じゃ!」
有頂天になって高笑いする山本の背後、二体の歪虚は顔を見合わせる。
「……フフ。お互い色々と苦労するけれど……せいぜいうまくやりましょう?」
『なんの事かはわからねェが……フン。俺の邪魔をするってんでなけりゃあ見逃してやるよ、ババア』
雄々しく翼を広げ舞い上がるガルドブルム。巻き起こす風に髪を揺らし、オルクスは目を細める。
この城の構成材質は憤怒の歪虚だが、不足分はこの地に撒き散らされた“死”を呼び起こし、オルクスが補充している。
ガルドブルムの輸送能力とオルクスの生成能力があって初めてこの怪物は誕生した。
「ある意味歴史的快挙よねぇ。歪虚側の協力作戦……だけど……」
山本の背中をじっと見つめるオルクス。ふっと視線を反らと城内へと続く肉の階段を下り始めた。
「これより天ノ都を強襲する! 狙いは帝の首ただ一つ! 雑魚は構わず龍尾城に突貫するよ!」
武器を掲げ吼える鬼たち。そんな中、一人の鬼がアカシラの側に立つ。
「……本当にいいんですかい、姉御?」
帝さえ殺せば結界は消滅する。別の者を御柱にするとしても、結界再起動までの間にこの戦争のケリはつくだろう。
そうなれば、人と鬼の無益な戦争は終わるのかもしれない。だが……。
「皆まで言うんじゃねェよ。アタシ達がアクロと一緒に生きていくには、山本に従うしかねェんだ」
長大な刀を肩に乗せ、アカシラは真っ直ぐに前を向く。
「アタシら鬼は決して仲間を見捨てない。そうだろう?」
だが、西方からやってきた人類の援軍は新しい可能性を示しつつある。
人類と歪虚、そのどちらも鬼にとっては友人足り得ない。ただ勝ち馬に乗り、生存確率の高い選択を行ってきただけだ。
迷いを振り切るように首を振り、鬼たちは駆け出した。
炎上する天ノ都を覆う結界は何の反応も示さず鬼たちを素通しする。
目指すべき戦場は、すぐそこに迫っていた。
「劣勢! 憤怒の歪虚は人間への攻撃よりも建造物への放火を優先している模様!」
と、その時だ。先ほどと同じ強烈な衝撃と閃光が都を襲った。
絶叫が街中から響き渡る、踏ん張って振動に耐えた紫草は顔を上げ。
「状況報告!」
「敵、破城攻撃第二射着弾! 結界は持ち堪えたようです!」
「スメラギ様がうまくやってくれたようですが、そう何度もあれを食らっては彼が持ちませんね」
「上様、上様! 報告です!」
次から次にとうんざりした表情のヴィルヘルミナ。忍者装束の少女は慌てた様子で。
「敵は結界付近に城を建造しています! 城というか……大型の歪虚です!」
「敵の全容は砂嵐でわかりません! それと、道中を強力な竜型の歪虚と多数の憤怒が防衛しています! 偵察隊は全滅!」
それから更に兵士が現れ。
「龍尾城に敵襲! 鬼が城門を突破、一階付近で戦闘中!」
「そこの坊主、案内しろ。立花院卿、私は往く」
「地図と指揮権を一時お渡しします。ご武運を」
城の地下にある祭壇ではスメラギを中心に術者達が結界維持に努めていた。
システィーナはその傍らで事を見守るが、スメラギは苦悶の表情を浮かべ。
「敵はここを狙って来るはずだ。システィーナ、お前は安全な場所に避難しろ!」
「それは……出来ません」
「相手は鬼だ。奴らも生きるのに必死だ……加減なんかしてくれねぇぞ?」
「しかし、スメラギ様が倒れたら全てが終わってしまうのですよね? わたくしは戦う事はできませんけれど、共に祈る事はできます。――そして僅かばかりの時を稼ぐ事も」
顔を赤らめながら舌打ちするスメラギ。
「そんな無様な真似、この俺様がさせるかよ! この城には西方の増援もいる。仲間を信じてどっしり構えてろ!」
「十三魔……ガルドブルム……」
『俺にも色々とシガラミってモンがあってな。ま、「今できる最高の」闘争ってェやつを愉しもうぜ。ちィとばかし待ってやるからよ』
強烈な旋風が兵たちを吹き飛ばす。その暴風に耐えながらバタルトゥは背後に目を向けた。
「ここは俺達で抑える……お前達は先へ進み、敵の城を破壊してくれ」
バタルトゥは抑揚のない、しかし熱意を込めた言葉でハンターを諭す。
「あの城を破壊しなければ勝機はない……。俺は、俺達辺境はなんとしてもここで都を守らねばならない。遠き日の約束を果たす為に」
頷き、ハンターの部隊が敵陣を突破する。ガルドブルムはそれを横目に捉え。
『行ったか。まあ行っちまったモンはしょうがねェよなァ。それにしたって……死んだぜ、オマエら?』
「……死にはしない。俺達はようやく歩み始めたばかりだ。十三魔だろうと、邪魔はさせない」
「大首長に続けぇええーッ!!」
雄叫びを上げる兵たち。この場に残ったハンター達も武器を手に、バタルトゥと肩を並べた。
砂嵐を抜けた先、月光に照らされ巨大な怪物がハンター達を待ち受ける。
それは怪物の肉を集めたキメラにして、不死の化身。悍ましく醜悪な、人の上半身を象った要塞。
「来たか、人間共。さあ、ヨモツヘグリよ! その怒りと怨嗟の本能に従い、存分に蹂躙するがよい!」
城は悲鳴めいた声をあげ、肉の塊である右腕を振り上げる。
ハンターたち目掛けて振り下ろされた一撃は鈍重ではあったが、大地を叩き割り風を巻き起こすだけの威力があった。
負のマテリアルが収束する頭部が破城攻撃の起点。そしてそのマテリアルは龍脈から回収しているのだろう。
ならばそのどちらかを断てば、都の結界を守る事が出来るはずだ。
怪物が再び腕を振り上げる。ハンター達はその一撃から身をかわしつつ、武器を手に駆け出した。
「こうしてスメラギ様をおぶって歩くのは何年ぶりでしょうか」
「何いきなりキモい事言ってんだ?」
「私も一応激戦で疲れている身です。大きくなったスメラギ様の身体は足に堪えます」
「だったら降ろせボケ」
「降ろしませんよ。これが、私の役目ですから」
小さく微笑む男の言葉に少年は目を逸らす。
「スメラギ様」
「あ?」
「九尾討伐、誠に大義でございます。本当に、本当に、よく頑張りました。きっと先代も、お歴々のスメラギ様も、あなたを誇らしくお思いになられるでしょう」
口喧しく生真面目な、しかしどこか自分を子供扱いしていた紫草。
兄のような、そして親代わりのような男の言葉に、少年はふっと目を瞑る。
「――当然だぜ。何故なら俺様は、この国の帝なんだからな」
『ヒトの子らよ。白龍の、そして私の加護を失ったあなた達は、それでも闇より現れし者達との戦いを続けるさだめにあります。それは人に与えられし宿業……運命と呼ぶべき力の流れ』
「歪虚との戦いが……運命?」
『それが世界の……この星の望み。そして多くの精霊達の存在意義でもあります。あなた達ヒトは、存在する限り闇に抗い続けなければなりません。それがどれだけ苦しくとも、悲しくとも……』
紫草の肩を借りながらゆっくりと前に出るスメラギ。黒龍は大きな瞳でその姿を見つめる。
『“血の宿業”がそれを望んでいるのです。しかし悲嘆する必要はありません。あなた達ヒトは、或いはこの世界の守護者足りえるかもしれない……私は今、そう思い始めています』
「どういう事だ? 黒龍……あんたが何を言っているのか、俺にはよくわからないよ……」
『稀代のスメラギよ。今際の時にあなたを瞳に宿せて良かった。私が愛した東の子らよ。確信しているのです。私の愛はきっと間違いであったけれど、どうしようもなく正しかったのだと……』
手を伸ばすスメラギから離れるように、黒龍は上体を起こす。
『己の道を歩み、そして証明しなさい。ヒトはただ、生まれ落ちて死んでいくだけの消耗品ではないのだと』
「黒龍……?」
『残された私の力のありったけをこの国の大地に還元します。それが私の最後の契約。スメラギ……そして白龍の子ヘレ。あなた達にも我が魂の片鱗を託しましょう』
そう言って翼を広げた黒龍の身体を眩い光が覆っていく。
『力を継承し――そして役割を引き継ぐのです。世界の……星の守護者として……』
「待ってくれ、黒龍! あんたは……!?」
その叫び声は光にかき消された。
息が詰まるような莫大なマテリアルが放出される。それは文字通り黒龍の命の光だ。
光の風の中、スメラギは目を細め、しかし確かに感じた。
誰かの優しい指先が頬を撫でた事。これまでずっと側に居てくれたような気がする、誰か。
その気配が消えていく。いや、大地に吸い込まれていく。
沢山の光になって。龍脈の流れに乗って。もう死ぬしかなかった世界へ還元されていく――。
「……黒龍……」
光が消えた後、スメラギは気づけば一人だけで立っていた。
誰に支えられずともその両足で。しっかりと、大地の上に立っていたのだ。
「俺に……生きろって言うのか……?」
「それでも、あなたの命もこの大地の命も残りは限られている。人がまだ精霊を食いつぶすだけなら、直ぐに燃え尽きて終わる」
器の言葉にスメラギはカラッポの祭壇を見つめ、首を横に振り。
「そうはさせねぇよ。この国はきっと美しくしてみせる。黒龍はきっと見ていてくれる。俺はそう信じてる」
スメラギを一瞥しつつフードを被って去っていく器。その傍らでファリフとリムネラが小さな白龍であるヘレを見つめている。
「うーん? 特別な変化はないよね?」
「確かに、マテリアルの感じはスコシ変わりましたケド……」
首を傾げる二人。紫草はそれを遠巻きに眺めつつ。
「黒龍を失い、この国を守っていた結界は消えてしまいました。これで代々続いてきた御柱の役割も終わりですね」
「ああ……そうなるな」
「これからはどこへとなり、お好きな所へ出向けることでしょう」
「そうだな。でも俺は、この国から逃げたりはしないよ」
確かに嫌いだと思う時もあった。面倒だったり、怖かったり。
いい思い出ばかりじゃない。それでも、この国で生まれ育ったから。
「御柱様ではなくなっても、スメラギである事に変わりはねぇ。やっぱこの国は、俺様がいなきゃ始まらねーだろ?」
白い歯を見せ笑う少年に男は複雑な表情を浮かべ。それから納得するように頷いて。
「……ええ、まったくで。これからも誠心誠意お仕えさせていただきますよ、我が君」
そう、微笑むのであった。
●“旅路”
夕暮れの光が水平線に沈み、夜が城下町を覆った。
満天の星空の下、廃墟同然の町にはあちこちに焚き火が灯り、兵達が戦勝を祝う小さな席が設けられていた。
しかしそれは戦の勝利に酔う為のものではなく、失われすぎた多くの命を弔う為にあるようだった。
「……皆、自分が信じた正義を生きてンのさ。それはアンタだけじゃない。アタシ達だって同じだ。その時々正しいと思う事をする。それだけだろ」
「だが私は考えもしなかったのだ。私が正義を振るう時、その切っ先が自分以外の誰かの正義を殺している等と……んぐっ!?」
アカシラの拳骨が朱夏の頭頂部にめり込む。
「痛いではないか……っ」
「そりゃ痛くしてるからね。ゴチャゴチャ過去を悔いたって仕方ないだろう? 憎しみも罪も背負っていく。生きるって事はそういう事なンだから」
「アカシラ……」
「……ぬわっ!? なんで泣いてンだい!?」
「これは……頭が痛くて……うっ、うぅぅぅ……っ」
ちょっと引くくらいの号泣っぷりに思わず冷や汗を流すアカシラ。
隣に座り直すと、また酒を注ぎながら慣れない様子で朱夏の肩を叩く。
「まあ、なんだ……? 元気出せよ……な?」
「もっと注いでくれないか!」
「あ、ああ……でもアンタ、あんまり酒に強くないんじゃ……」
心配通り、朱夏は暫くすると瓦礫の上に仰向けにぶっ倒れてしまった。
頭をわしわしと掻きながらアカシラは仕方なく朱夏の周りの瓦礫を整え、その辺から拾ってきた布切れをかけてやる。
「ハア?……面倒くせェ。これだから人間って奴らは……」
酒瓶を片手に夜空を見上げる。瞬く光は本当に綺麗で、我を失ってしまいそうな程だ。
鬼とヒトは長らく対立してきた。それは不幸なすれ違いから来るものであり、誰かが決定的に悪かったわけではない。
だがその悲劇の中でアクロという一人の鬼が闇に落ち、終わることなく繰り返された彼の悪夢は更に多くの悲劇を呼んだ。
生きている事、それそのものが罪……。そんな一族を救うために下した結論に後悔はない。ないけれど……。
「アクロ……。これが、あんたの望んだ未来の一つ……なのかねェ?」
すやすやと寝息を立てている朱夏に目を向ける。
ヒトと共に戦い、ヒトと共に生きる。そんな未来に、自分達は辿り着けるだろうか……?
とんだ誠意もあったものだ。唾を吐くアカシラにヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は笑顔で腰を持ち上げ、瓦礫を下る。
「君達鬼は九尾との戦いで一定の戦果を示し……救国に貢献した。しかし……君達の処遇が正しく決定されたわけではない。九尾という目先の脅威がいなくなった後、この国の再起において脅威として挙げられるのは……君達、鬼だろう」
そんな事は言われずとも承知の上だ。
所詮、エトファリカ幕府との約束は正式なものではないし、仮に幕府が鬼の受け入れを決定したとしても、国民感情がそれを許すとは限らない。
「悲しみには生贄が必要だ。ヒトはいつでもそうやって心の平静を保っている。憎しみに矛先を……正しい怒りに焼かれる犠牲を……ね」
ゆっくりと、一歩一歩アカシラへ近づき、女は眼と鼻の先に立つ。
その静かな、しかし鋭く切り裂くような眼光をアカシラはまっすぐに見つめ返す。
「亡命したまえ。この世界で鬼を最も効率よく救済できるのは、この私だ」
目の前の女は笑っているのに。敵意はないと示すように、身体に緊張の一つさえ見られないのに。
全てを飲み込むような強烈な圧力を感じる。目を逸したら一瞬で食いつぶされる……そんなあり得るはずのない感覚に陥るほどに。
「どうした? 何を迷う必要がある? 一族を救う……その為だけに全てを捨ててきたのだろう?」
そっと差し出される右手。アカシラは息を呑み、ゆっくりと手を持ち上げ――。
「元犯罪者を国に受け入れると?バッシングがくるぞ?。おじさんたちがうるさいぞ?」
一歩引いたポジションから野次を飛ばすヴィルヘルミナ。それは全くその通り。犯罪者であっても兵力として使う帝国と王国とでは話が変わってくる。
「ところがどっこい、我が帝国は使える者は野盗でも使う。とってもエコロジーな軍事国家です。鬼を受け入れてもだーれも反対しません」
「いえ、流石に一般国民からは反対の声もあがると思いますが……ではなく! そもそも、鬼を犯罪者であるという捕らえ方から異議を申し立てます! 彼女らは止むを得ない事情から犯罪行為に手を染めてしまった……こともありました。しかしそれは彼女らだけの罪ではないはずです!」
「“その罪人を飢えさせたのは、一体、誰なのですか”……だったかな?」
それは以前、鬼を受け入れるべきだとスメラギに主張した時のシスティーナの言葉だ。
「では、“誰”が悪いのかな?」
「それは……今は、誰が悪かったのかという話ではなく……これから、その罪を未然に防ぐにはどうするかという話をしているのです」
すっと笑みを作り、ヴィルヘルミナは新たに酒を注ぐ。
「人の悪感情程管理の難しい物はないよ。いや、ある意味に置いては単純なのだが……そのロジックは常に犠牲を伴う」
「“悪役”を作り、それに罪の全てを着せる……それがヴィルヘルミナ様の仰る救済なのですか?」
僅かに声を震わせながら、しかし少女は逃げずに女を見つめる。
「そうだ。罪は憐憫では濯げない。罰は誰の目にも明らかな形でなければならない。そして罰だけが罪を本当の意味で救う」
「仰ることはわかっているつもりです……それが本当に罪ならば、ですが」
見つめ合う皇帝と王の娘。その緊張に耐えかねるようにシスティーナは小さな手をぎゅっと握り、頬に汗を伝わせる。
しかしそれは長く続かなかった。ヴィルヘルミナは酒を呷ると、前髪を掻き上げながら笑い。
「――いいだろう。それでは君のやり方で救ってみるといい。鬼の一件から、私は手を引こう」
少々呆気なさすぎる軽い口調でヴィルヘルミナはそう言って、地べたに転がっていた朱夏を抱き上げた。
「この子はエスコートしておくから、君達は存分に今後を話しあうと良い。風邪だけは引かないように気をつけるんだよ、システィーナ」
にこりと笑って女は去っていく。それを見送ったシスティーナの足が崩れ、へなへなとその場に座り込んだ。
「……アンタ、大丈夫かい?」
「は、はいぃ……ちょっと緊張しすぎて……」
「無理もないね。アレはちょっとした傑者だ。修羅の類だよ」
そっと手を差し伸べるアカシラの手を取り、システィーナは立ち上がる。
「ヴィルヘルミナ様も、悪いお方ではないのです。どうか誤解しないであげてください」
「違う国の王同士なんだろう? どうして肩を持つんだい?」
「……わたくしはまだ王ではありません、けれど……それは……」
遠ざかった背中はもう見えない。少女は自らの手をじっと見つめ、それを胸に抱きしめた。
「それ、は……」
答えあぐね俯く少女をアカシラはそれ以上問い質さない。
代わりにヴィルヘルミナの言葉を思い出し、毛布をそっと少女の肩にかけるのだった。
「そうだ。これからの俺達がしなきゃならねぇ事は涙を流す事じゃない。笑って笑って、死んでいった連中の戦いが無駄じゃなかったと世界に証明する事だ ニンマリと頬を釣り上げ笑ってみせる。
大丈夫、強がりで笑うのは慣れている。東方民の笑顔は強い。悲しみを吹き飛ばし、未来を勝ち取るだけの力を持っている。
「紫草。俺様は最強のスメラギになるぜ。歴代最高の王だ。俺様は二度と涙は流さない。どんな時でも民を守り、そして恩人であり友でもある西方のモノノフの為に、どんな時でも戦ってやるんだ」
「左様でございますか。しかし、それはきっと茨の道ですよ」
「へっ、承知の上だ。それでも俺様はきっとこの国を建て直してみせる。次の世代に、俺様達の子供やその子供にまで、美しい国を残してみせる。そして語り継ぐんだ。国を守る為に散っていった、大勢の英雄の武勇をな!」
光を背に振り返り、スメラギは笑う。その笑顔はもう作り物ではない。
「まずは都に人を呼び戻すぞ、紫草! 盛大に勝利を祝うんだ! この国はまだ死んでねぇって事を、民の心に思い出させる為にな!」
「そうだね。まだ憤怒の残党も首都圏にいると聞くし、彼らが安心して祭りを楽しめるように、俺達ハンターもできる事をしよう」
駆け出したラキが瓦礫の片付けに協力する後ろ姿を眺め、神薙は青空を見上げた。
歪虚王は倒れたが、まだ解決していない問題はいくつかある。
絶対安全圏と呼ばれた首都圏への歪虚の侵入。地方から人々を呼び戻すには邪魔になるだろう。
そして鬼と呼ばれる亜人の扱い。こちらも神薙としては目が離せない所だった。
「人は、悲しみや憎しみを超えられるのかな……」
あの歪虚王との戦いの中、確かに人々は心を重ね、お互いの境遇を超え勝利へ手を伸ばした。
それが真実かまやかしかを決めるのは、きっと戦いが終わった今でこそなのだ。
「証明していかなきゃな」
まずは自分の言葉にしたがって、できる事からコツコツと。
例えそれが河原に石を積み上げるような儚げな希望だとしても。奇跡を望んだ者の責任として。
所感を記した手帳を閉じ、少年は瓦礫の山を下る。遠くでは少女が割れた壺を抱え急かしているのが見えた。
●東征、斥候?龍尾城(6月10日公開)
|
「ようこそ龍尾城へ! 歓迎するぜ、西方と……異世界リアルブルーの諸君!」 エトファリカ東方連邦首都“天ノ都”への転移は、山本五郎左衛門の策により失敗した。 しかしハンター達は力を合わせ悪路王達“憤怒”の包囲を辛うじて突破。 百年以上分かたれていた西と東の世界が今、再び交わろうとしていた。 今は亡き辺境の白龍と対を成す存在である東方の黒龍。二つを結ぶ転移門の再稼働により、東方から辺境へ援軍を送る事が可能になった。 それに伴いエトファリカ帝、スメラギは憤怒の歪虚に対抗する為の作戦を立案。 ハンター達は来る反攻の時に備え、この新たな戦場での戦いに参加する。 「俺様が“御柱様”こと、エトファリカ東方連邦で最も偉大な王様、スメラギ様だ。まずは先の勝利を讃えてやるぜ?」 龍尾城内の会議室。畳の上に座るハンター達の上座に座り、少年はニっと白い歯を見せ笑う。 「お前らあの山なんとかと悪路王を凌いだんだってな。なかなか見込みがあるじゃねーか、なあ朱夏?」 側に控えた朱夏は無言で一礼する。スメラギはその場にどっかりと寝転がり、頬杖をつく。 「悪いが俺様はまだお前らを信用してねーんだわ。マグレ勝ちかもしんねーし?」 「……スメラギ様。遠路遥々我らの為に危険を顧みずお越しになられたのです。無礼で御座いましょう」 「ハッ! 知るかよ。いいかおめーら。この東方がぶっ潰れたらそっくりそのまま歪虚は西方に雪崩れ込むぜ? おめーらの故郷も、おめーらの未来も、この東方と一蓮托生なんだよ。選択肢なんぞあるかっつーの……おごぉっ!?」 隣に静静と正座していた男がスメラギの頭にげんこつをめり込ませる。 「大変失礼致しました。私は立花院紫草と申します。この東方連邦において、征夷大将軍……言わば、軍事の最高責任者を任されております」 涙目で悶絶するスメラギを一瞥し、深々と頭を下げ。 「スメラギ様はこの東方の指導者……帝であらせられますが、ご覧の通りまだ年若く、特に礼節の面で度し難い欠落を有しておられるのです。我が君に代わり、重ね重ねのご無礼、謝罪させて頂きます」 「おいゴラ紫草! 帝様に人前でぶちかます奴があるか!?」 「なんでしょうか。切腹でもした方がよろしいでしょうか。軍権をお返ししましょうか。管理できるのなら、ですが」 「そこまでしろとは言ってねーよこえーよすいませんでした! まあいいわ。作戦について説明すっぞ、ちこうよれクソが」 |

スメラギ 
朱夏 
立花院紫草 |
――エトファリカ連邦国は、黒龍の加護から成る独自の守護結界を有している。
この守護結界の存在こそ、東方が百年間の孤立無援を凌ぐことが出来た最大の理由であると言えよう。
「今現在、この天ノ都周辺には歪虚を拒絶する結界が張られています。しかし、元々この結界は東方全域を覆う程の力を持っていました」
|
「エトファリカは東方の小国や部族が歪虚に故郷を追われ、対抗する為に結成した連邦国だ。この国の領土は本来、周辺の島々に及ぶ」 大小様々な、地図には映らない程の小さな島も存在するが、主な国土として、本土東側の5つの島が挙げられる。 「俺様達が作っている結界の原動力は黒龍の力がメインだが、それとは別に、大地のマテリアル……“龍脈”を利用している」 エトファリカの守護結界は龍尾城を中心に複数の龍脈をリンクさせる事で、その範囲と強度を高める仕組みになっている。 「元々東方には結界の連結点となる龍脈と、その上に作られた“城”があった。今回の戦いでは、今は歪虚に奪われているコイツを奪還する」 「東方を支配する“憤怒”の本軍は南に控えています。しかし、北側からも別の七眷属による攻撃が予想されます」 東方を完全に包囲する歪虚の軍勢は、南大陸からやってきた憤怒の眷属が主戦力だ。 |
「――即ち、今お前らの住む西方で跋扈している連中の一部だ」
辺境で怠惰の歪虚を退けた西方軍が東方の奪還に動き出せば、西方の歪虚もそれを阻止するため、東方へ向かうだろう。
首都天ノ都の南からは憤怒の歪虚本軍。そして北からは西方歪虚の増援が予想される。つまり、東方は挟み撃ちにされる格好だ。
「今、黒龍の結界は弱っちまってる。転移門を開くのに力を使ってるせいだ。つまり、この結界が破られそうなのはお前ら西方連中のせいでもあるんだな?、これが」
ニンマリと笑うスメラギ。この仕事を断ったら西方に帰れなくなる……そんな予感がした。
「北には歪虚最大の領域、“北荻”が存在します。しかし南側には今のところ憤怒の軍があるのみです」
「元々憤怒の連中は何か目的があって南に行ったみたいなんだがな。お前ら心当たりあるか?」
そう言われても思い当たる節は今のところないのだが、もしかしたら何かを見落としているのかもしれない。
「ともあれ、北の歪虚を全滅させようとしてもほぼ無制限に増援が送り込まれるが……南の孤立した憤怒軍を打ち破れば、事実上東方は開放されるわけだ」
「南へ進軍する為には、まずは西方増援を迎え入れる転移門の安定化と結界強度を上げる為、各地の龍脈を奪還し、黒龍の力を取り戻す必要があります」
「大反攻作戦の為の事前準備ってわけだ。お前らが龍脈を取り返してくれりゃ、俺様がガッチリ結界を広げてやる」
「この作戦には、西方諸国にも協力を依頼しております。転移門の力が安定しない為、大規模な増援は見込めませんが……」
「結界の強度が上がれば転移門に力を注げるようになる。それまでは少数精鋭で事を進めるぜ」
一通り話を終えると、スメラギは指を鳴らし。
「俺様達東方は、百年以上、この時を待ってきた。起こり得ない奇跡と理解しながら、それでもと、な。だがお前達は辺境の地で遂に成し遂げたんだ。歪虚から人類の領土を取り戻すっていう奇跡をな」
「我々だけではとても考えられない作戦でした。これも全ては皆様、西のモノノフの力があってこそ」
「どうせ人生は瞬く間、夢の挾間の出来事よ。恐れず惑わず――笑って死のうぜ?」
スメラギの言葉は嘘でも冗談でもない。
この国において、戦いの中で死ぬ事は恐怖すべき結末ではない。
最も恐るべき事。それは、最期に怯え、竦み、みっともなく命を惜しみ、何も守れずに散る事なのだ。
「勝てば英雄、負ければ死ぬだけ。さあ、楽しい遊戯の幕開けだぜ!」
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●プレストーリー「開戦前」(6月24日公開)
|
「お招き頂き光栄です、スメラギ様」 「いや。俺様別に誰も招いてないぞ?」 恭しく一礼するシスティーナ・グラハム(kz0020)を前にスメラギはあっけらかんと言い放った。 頬を赤らめつつキリキリと首を動かしたシスティーナの視線の先、ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は爽やかに笑い。 「うむ。別に呼ばれてはいないよ。私が勝手に来ただけだ」 ちょこちょこヴィルヘルミナとの幅を狭め、少女はその裾を引く。 「西方諸国の代表として東方へ向かい、憤怒の歪虚への対抗策を相談するという話でしたよね……っ?」 「そうだな」 「ヴィルヘルミナ様が“私が西方諸国の代表である”って仰るから、大司教様が一緒に行けって……っ」 「うむ。でも呼ばれてはいないんだ」 「オイマト大首長がいらっしゃるのは……?」 「アレもほら、勝手に来てるから。その証拠にラウロの爺さんはいないだろう?」 何か色々と騙されたような気がする。小刻みに震えるシスティーナの肩をポンと叩き。 「西方における一大王国、グラズヘイムの名は貴殿もご存知であろう? こちらにおわすはシスティーナ・グラハム王女殿下であらせられる。私はそこからチョコっと独立したゾンネンシュトラール帝国の皇帝、ヴィルヘルミナです」 「そ、そ、そ、そんな事っ、わ、わたくしはっ」 「君のところのストレスが露骨に顔に出ちゃうおじさんがそういう風にしろって……」 「だだだっ、大司教様はそこまで仰っていません!?」 スメラギは無言でバタルトゥ・オイマト(kz0023)に視線を移す。こちらは完全に無言である。 「良くわかんねぇが、西方は愉快な連中ばかりみてぇだな」 龍脈の再起動が進むにつれ、西方と東方を結ぶ転移門も安定し始めた。 これに伴い、西方諸国からの物資の搬入、そして援軍の送り込みが開始された。 それらの先遣隊として視察にやってきたヴィルヘルミナとシスティーナに、先行していたバタルトゥも交えスメラギが説明する。 「ふむ……この国では帝であるスメラギのが結界維持の人柱であるという事か」 「だから“御柱様”……そのような大役をいつ頃から?」 「七歳くらいからかな?。親父は俺様に役割を継承してくばたるその時まで、“西方の友人達は必ず来る”って言ってたよ」 視線を伏せて呟くスメラギにシスティーナは目を伏せ。 「救援が遅くなり、本当に申し訳ありません。忘れていたわけではなかったのです。しかし……」 「いンだよ。オイマトのにも謝って貰ったしな。それにどうせ御柱の役割を負った奴は遅かれ早かれ死ぬんだ」 「大精霊である黒龍と常に同調し……結界を維持する術は命を削る……」 バタルトゥの言葉に驚きを隠せないシスティーナ。ヴィルヘルミナはそんな少女の頭を優しく撫で。 「憤怒の動きを確認したい。補給と結界拡張を受け、東方はどのような反撃を考えている?」 「それに関しては私からご説明申し上げましょう」 側に控えていた立花院紫草(kz0126)が声を上げる。 システィーナは政治的な立場こそあれども武人ではない。こうした作戦会議が始まれば上手く発言出来なくなる。 しかしスメラギは違う。時折ジョーク混じりとは言え、戦術論もヴィルヘルミナやバタルトゥと同じ卓で語っている。 時折求められる同意に頷きながら、少女は少年を見つめていた。 日が暮れる程続いた会議の後、システィーナは龍尾城の廊下に立っていた。 城内には風光明媚な日本庭園が伴っている。王女は雅な景色を眺めながら物思いに耽っていた。 階段を降りてきたヴィルヘルミナが足を止める。しかし声をかけず、女は物陰に隠れた。 「考え事か?」 別方向から歩いてきたスメラギがシスティーナの隣に並んだ。 「今のわたくしに出来る事はなんなのか、それを考えていました」 「は?」 |

システィーナ・グラハム 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル 
バタルトゥ・オイマト 
スメラギ 
立花院紫草 |
「いや、あいつらが変態なだけだろ。嫌いじゃねーが」
「本当に……東方の事を忘れていたわけではありませんでした。ずっと心配していたし、救いたいと考えていました。けれどわたくしにはその理想を実現するだけの力がなくて……」
「闇雲に歪虚の領域を横断してこっちくるなんて無理だろ?」
「はい……。ですからわたくしは、兵の命と東方の皆さんの命を秤にかけ……へうぅっ!?」
急に頬をつねられ涙目になるシスティーナ。スメラギは深々と溜息を零し。
「俺様だってなぁ、御柱様なんて役割好きでやってねーし……逃げ出したいと思った事だって何度もあるわ。だけど仕方ないって自分に言い聞かせて、他人を恨みながらヘラヘラしてなんとかやってきたんだよ」
虚空を睨むスメラギの横顔は歳相応だ。少年は懐から札を取り出し。
「オイマトもそうだけどよ。お前らスゲェと思うぜ? 好き好んでこんな東方まで来てよ。バカとしか言いようがねーわ」
バカという言葉に目を丸くするシスティーナ。スメラギは鼻頭をこすりながら笑い。
「俺様はこの城から動けねぇけどよ。お前にはどこにでも行ける足があるじゃん。時間だっていっぱいあるじゃねぇか。未来に可能性が無限にある……それが羨ましいよ」
「……スメラギ様」
「悩んだってしょうがねーんだ。人は平等じゃねぇからな。結局は与えられた手札で、そん時々勝負してくしかない。そんで負けて泣いたって、明日はきっと来る」
取り出した札の束を手早くシャッフルし、その中から一枚をシスティーナに選ばせる。
そこには太陽を抱えた少女を龍が取り巻く絵柄が記されていた。
「タロットカード……ですか?」
「西方にもあるんだってな。占い札だよ。あんたはきっと、デッカクなるぜ?」
「信じても良いのでしょうか――明日を」
二人は並んで夜空を見上げる。聞き耳を立てていたヴィルヘルミナは笑みを作り、足音を消して階段を登り始めた。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●鳴動、そして開戦(6月25日公開)
|
天ノ都北方に月光を受け蠢く巨大な影があった。 その日の昼間、そこには半壊した城があった。城もそこに眠る龍脈の規模も小さなもので、先の奪還作戦で人類に奪われてもおかしくない場所だ。 城は既に半壊し、憤怒蔓延る歪虚の領域となっていたが、今や拡大された首都結界に最も近い龍脈の一つである。 そこに突如として巨大な何かが姿を表した事に、恐らくまだ人類は誰一人気がついていなかった。 「協力に感謝するぞ、西方の同胞よ。貴様らの力がなければこうも早く完成させる事は不可能であった」 不敵な山本五郎左衛門の笑みの先には二体の歪虚が並んでいる。 片方は腕を組み、興味もなさそうに話を聞き流す悪竜。十三魔が一、ガルドブルム。 そしてもう一体は対象的にニコリと笑顔を作り手を振る吸血鬼。不変の剣妃、オルクス(kz0023)である。 『ハッ。色々あって東方くんだりまで来てんだ、ついでであって別にオマエサンの為じゃねェよ』 「そういう言い方は良くないわよ?ガルドブルム。私達は眷属は違えど同じ歪虚なんだから、手を取り合うのは当然でしょぉ?」 胸の前で手を組み、綺麗な瞳で語りかけるオルクス。ガルドブルムは吐き捨てるように。 『おいバアさんよ、キモチワリィこと言ってんじゃねェよ』 二体のやりとりを他所に山本は遠く天ノ都を見つめる。 上空……否、高度250メートル。突如として出現した巨大な城の天守閣にて山本は札を取り出す。 「ぬしらの協力で策は成った。いざ開幕の時! 起動せよ、生体要塞“ヨモツヘグリ”よ!」 山本の号令に従い、“城”が動き出す。 それは間違いなく城だ。しかし、その様相は人類側のそれとは大きく異なる。 城全体を覆い尽くし、今や外観を成すのは無数の憤怒の歪虚の集合体であった。 夥しい量の憤怒達をこの地に集め、全てを融合させ負の神殿を作る事。それが山本の新たな策であった。 この地は元々龍脈を抱く聖なる地の一つ。そこに存在していた城を取り込み、山本の術に取り込む事で龍脈の性質を逆転させる。 大地からマテリアルを吸い上げ、負の力に変換し収束する。 「ただのマテリアルではないぞ。龍脈を通じ、首都結界の波長と同調させた特別製じゃ」 山本は元々優れた術師であり、龍脈の扱いに関しては帝に匹敵するとまで言われた存在だ。 彼は先の西方からの転移を龍脈に干渉し失敗に終わらせた。 龍脈の力は流れが肝心なのだ。その流れを完全に堰き止める事が不可能だとしても、流れに沿う形で介入する事は出来る。 |

ガルドブルム 
オルクス 
山本五郎左衛門 |
巨大な城の頭部に該当する部分に紫色の光が収束し、それが光弾となって放たれる。
光は首都を覆う結界に激突すると、爆裂。歪虚を阻む絶対の力である筈の結界は、脆くも崩れ去った。
『ほォ。やればできんじゃねェか、ジジイ』
「とっても興味深いわぁ。あなたとのお仕事……色々と勉強になりそう♪」
「ふはははは! 帝も結界を調整し再起動するじゃろうが、その前に天ノ都に歪虚を送り込む! 作戦開始じゃ!」
有頂天になって高笑いする山本の背後、二体の歪虚は顔を見合わせる。
「……フフ。お互い色々と苦労するけれど……せいぜいうまくやりましょう?」
『なんの事かはわからねェが……フン。俺の邪魔をするってんでなけりゃあ見逃してやるよ、ババア』
雄々しく翼を広げ舞い上がるガルドブルム。巻き起こす風に髪を揺らし、オルクスは目を細める。
この城の構成材質は憤怒の歪虚だが、不足分はこの地に撒き散らされた“死”を呼び起こし、オルクスが補充している。
ガルドブルムの輸送能力とオルクスの生成能力があって初めてこの怪物は誕生した。
「ある意味歴史的快挙よねぇ。歪虚側の協力作戦……だけど……」
山本の背中をじっと見つめるオルクス。ふっと視線を反らと城内へと続く肉の階段を下り始めた。
|
「……姉御、都北側で一瞬結界が消失。憤怒の歪虚が侵入して騒ぎが始まりやした」 天ノ都、南側。木々に覆われた森の中に無数の眼光が煌めく。 手頃な岩の上に腰掛けていたアカシラがゆっくりと顔を上げ、都から上がる火の手を見つめた。 「結界は既に再起動したんだな?」 「へい。奇襲を仕掛けるのなら、次の破城攻撃の合間ですぜ」 首都圏を覆う黒龍の結界は、“歪虚”の侵入を拒絶するものだ。 歪虚以外のヒトやモノを阻むような類ではないし、結界を通過したところで探知される事もない。 「お前ェら、準備はぬかりねェな!?」 雄叫びを上げる鬼達。彼らは悪路王とは違う。“歪虚”ではなく、“ヒト”である。 |

アカシラ |
武器を掲げ吼える鬼たち。そんな中、一人の鬼がアカシラの側に立つ。
「……本当にいいんですかい、姉御?」
帝さえ殺せば結界は消滅する。別の者を御柱にするとしても、結界再起動までの間にこの戦争のケリはつくだろう。
そうなれば、人と鬼の無益な戦争は終わるのかもしれない。だが……。
「皆まで言うんじゃねェよ。アタシ達がアクロと一緒に生きていくには、山本に従うしかねェんだ」
長大な刀を肩に乗せ、アカシラは真っ直ぐに前を向く。
「アタシら鬼は決して仲間を見捨てない。そうだろう?」
だが、西方からやってきた人類の援軍は新しい可能性を示しつつある。
人類と歪虚、そのどちらも鬼にとっては友人足り得ない。ただ勝ち馬に乗り、生存確率の高い選択を行ってきただけだ。
迷いを振り切るように首を振り、鬼たちは駆け出した。
炎上する天ノ都を覆う結界は何の反応も示さず鬼たちを素通しする。
目指すべき戦場は、すぐそこに迫っていた。
|
――突然、地響きと共に眩い光が天ノ都を覆った。 揺れる龍尾城内部にて、突然スメラギが何かに弾かれたように吹っ飛び、床に転がる。 「スメラギ様……!?」 慌てて駆け寄るシスティーナ・グラハム(kz0020)。スメラギは白目を向き、口と鼻から血を流していた。 「システィーナ、無事か!?」 「ヴィルヘルミナ様、スメラギ様が! ああ……どうしたら……っ!?」 駆けつけたヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)がスメラギを抱え脈を計る。が、その直後スメラギは勢い良く上体を起こした。 「……何秒だ!?」 「へっ?」 「俺様は何秒気絶していた!?」 その答えよりも早く、城下町で火の手が上がる。スメラギは悔しげに地団駄し。 「クソが! 結界が破られた一瞬で都に歪虚を送り込んできやがった!」 「君の気絶時間は例の衝撃から四十秒ほどだ。結界の再起動は?」 「俺様が目覚めた時点でしてるが、奴ら結界破りの仕込みをしてやがる。今すぐ対策しねぇとまた破られる!」 ふらつきながら立ち上がるスメラギを支えるシスティーナ。 「どこへお連れすればよろしいのですか?」 「……地下だ。地下の祭壇に……ヴィルヘルミナ、紫草と陰陽寮に伝令を頼む! 俺様は手が離せねぇ!」 頷き素早く立ち去るヴィルヘルミナ。 「すまねぇな……」 「よいのです。今の私に出来る事をする……そう決めたばかりですから」 優しく笑いかけるシスティーナにスメラギは目を細める。二人は支え合い、地下へ続く階段を降りた。 城下町では侵入した憤怒との戦いが始まっている。絶対安全圏とされていた都だけに混乱は大きい。 「立花院卿、敵兵力は?」 「不明です。既に結界は再起動していますが、結界の周囲を突然砂嵐が覆い、外部の状況を把握出来ません」 「砂嵐……まさか」 「とにかく外の状況を把握しない事には戦いになりません。既に偵察隊を送り込んでいますが……」 「上様!」 二人の会話に割り込んだのは武者鎧を装備した東方兵である。 「報告致します! 都南方より、鬼により奇襲あり!」 「このタイミングで奇襲ですか……?」 「敵総数不明! 油断していた防衛部隊は既に壊滅状態、敵はこの龍尾城に雪崩れ込んできます!」 「結界をすり抜けた……ということは、アカシラ達ですか」 険しい表情で思案する紫草。ヴィルヘルミナは腰から下げた剣を僅かに掲げ。 「城内への侵入者に関しては私が対処しよう」 「助かります。城下町の戦況は?」 |

システィーナ・グラハム 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル 
スメラギ 
立花院紫草 |
と、その時だ。先ほどと同じ強烈な衝撃と閃光が都を襲った。
絶叫が街中から響き渡る、踏ん張って振動に耐えた紫草は顔を上げ。
「状況報告!」
「敵、破城攻撃第二射着弾! 結界は持ち堪えたようです!」
「スメラギ様がうまくやってくれたようですが、そう何度もあれを食らっては彼が持ちませんね」
「上様、上様! 報告です!」
次から次にとうんざりした表情のヴィルヘルミナ。忍者装束の少女は慌てた様子で。
「敵は結界付近に城を建造しています! 城というか……大型の歪虚です!」
「敵の全容は砂嵐でわかりません! それと、道中を強力な竜型の歪虚と多数の憤怒が防衛しています! 偵察隊は全滅!」
それから更に兵士が現れ。
「龍尾城に敵襲! 鬼が城門を突破、一階付近で戦闘中!」
「そこの坊主、案内しろ。立花院卿、私は往く」
「地図と指揮権を一時お渡しします。ご武運を」
城の地下にある祭壇ではスメラギを中心に術者達が結界維持に努めていた。
システィーナはその傍らで事を見守るが、スメラギは苦悶の表情を浮かべ。
「敵はここを狙って来るはずだ。システィーナ、お前は安全な場所に避難しろ!」
「それは……出来ません」
「相手は鬼だ。奴らも生きるのに必死だ……加減なんかしてくれねぇぞ?」
「しかし、スメラギ様が倒れたら全てが終わってしまうのですよね? わたくしは戦う事はできませんけれど、共に祈る事はできます。――そして僅かばかりの時を稼ぐ事も」
顔を赤らめながら舌打ちするスメラギ。
「そんな無様な真似、この俺様がさせるかよ! この城には西方の増援もいる。仲間を信じてどっしり構えてろ!」
|
城下町に雪崩れ込んだ敵をおおよそ撃退し、バタルトゥ・オイマト(kz0023)は部族の部下や東方兵、そしてハンターと共に都を出た。 都は範囲の拡大した結界に守られている筈だったが、先の破損と破城攻撃への対処で結界範囲そのものが減少している。 その結界の外側には砂嵐が渦巻き、視界不良の奥からはぞろぞろと憤怒の歪虚が迫ってくる。 「族長! 恐らく奥に見えるあれが、敵の本丸かと!」 砂嵐に目を細め、バタルトゥは大地を蹴り、二対の短剣で敵を減らしていく。 「個の戦闘能力は低い……怯まず攻めこむぞ」 あの巨大な歪虚をどうにかしなければ埒があかない。 進軍する兵たち、しかし直後、その一部が轟音と共に吹き飛んだ。文字通り人がまるで事もなく空に舞い上がったのだ。 滑空しながらの一撃で兵を薙ぎ払った影は真上から急降下し、バタルトゥの眼前に降り立つ。 |

バタルトゥ・オイマト |
『俺にも色々とシガラミってモンがあってな。ま、「今できる最高の」闘争ってェやつを愉しもうぜ。ちィとばかし待ってやるからよ』
強烈な旋風が兵たちを吹き飛ばす。その暴風に耐えながらバタルトゥは背後に目を向けた。
「ここは俺達で抑える……お前達は先へ進み、敵の城を破壊してくれ」
バタルトゥは抑揚のない、しかし熱意を込めた言葉でハンターを諭す。
「あの城を破壊しなければ勝機はない……。俺は、俺達辺境はなんとしてもここで都を守らねばならない。遠き日の約束を果たす為に」
頷き、ハンターの部隊が敵陣を突破する。ガルドブルムはそれを横目に捉え。
『行ったか。まあ行っちまったモンはしょうがねェよなァ。それにしたって……死んだぜ、オマエら?』
「……死にはしない。俺達はようやく歩み始めたばかりだ。十三魔だろうと、邪魔はさせない」
「大首長に続けぇええーッ!!」
雄叫びを上げる兵たち。この場に残ったハンター達も武器を手に、バタルトゥと肩を並べた。
砂嵐を抜けた先、月光に照らされ巨大な怪物がハンター達を待ち受ける。
それは怪物の肉を集めたキメラにして、不死の化身。悍ましく醜悪な、人の上半身を象った要塞。
「来たか、人間共。さあ、ヨモツヘグリよ! その怒りと怨嗟の本能に従い、存分に蹂躙するがよい!」
城は悲鳴めいた声をあげ、肉の塊である右腕を振り上げる。
ハンターたち目掛けて振り下ろされた一撃は鈍重ではあったが、大地を叩き割り風を巻き起こすだけの威力があった。
負のマテリアルが収束する頭部が破城攻撃の起点。そしてそのマテリアルは龍脈から回収しているのだろう。
ならばそのどちらかを断てば、都の結界を守る事が出来るはずだ。
怪物が再び腕を振り上げる。ハンター達はその一撃から身をかわしつつ、武器を手に駆け出した。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●妖狐(7月9日公開)
それは、身の内に大きな衝撃を感じ取り、目をゆっくりと開いて、空をにらみつけた。
天ノ都よりはるか南、歪虚に侵食された大地。
それの持つ強大な負のマテリアルは周囲の大地を歪め、侵食し、無へと還していた。
岩に覆われた荒野の中、切り取られたかのような闇としか表現しようのない虚無の空間が広がる世界。
歪虚によって侵食された大地だった。
その中央に横たわるは、邪悪なる狐。淀んだ光を含む毛並みに、雄々しく広がる巨大な九つの尾、狡猾なる智慧をたたえた鋭い眼。
「北……山本か……?」
感じられた衝撃、不快の感覚しか示さぬマテリアルの揺らぎに、大妖狐はふと、眉根をひそめ、くぐもった声でつぶやいた。その言葉の息に合わせて漏れる、舌なめずりのような赤き炎。
「……人間どもが。おとなしく滅びていけばよいものを。まだあがくか、小賢しい」
少し前、はるか西の果てで感じられた、正なるマテリアルの復活。
──不快。
そして西方より現れた覚醒者とかいう、少々力を持っただけの人間によって、奪った龍脈が取り戻されていくこと。
──ただ不快。
滅び行くしかない矮小な人間が、希望という名の戦いに身を投じ、今このときに歪虚である自分い刃を向けて刃向おうとすること。
妖狐には唯々、怒りと含む不快であった。
そして突然、妖狐は大音声の叫びをあげる。淀んだ空気が震え、その勢いに枯れた枝だけの木々が揺れ、あるいは折れて落ちる。
「彼奴らに与えられるのは、歪虚に飲まれて無に還る運命のみ。それを、改めてわからせてやらねばならぬようだな……!」
怒りを押し殺したつぶやきとともに踏み出した前足が、木を踏み折り、その踏みしめた跡に業火が一瞬、立ち上る。
その雄叫びに反応したのか、周囲の歪虚の無から絞り出されるように生まれた闇が、多くの雑魔に変化する。周囲にはその他にも、大型小型を問わず、歪虚が集結をはじめていた。
そして跳躍。
まるで空を飛ぶが如く北へと向かいはじめた妖狐を追うように、百鬼夜行と呼ぶべき歪虚の軍勢は進軍を開始した。
「歪虚の階級……デスカ?」
「うむ」
場所はリゼリオにある資料室。
サルヴァトーレ・ロッソ付きの軍人であるジョン・スミス(kz0004)の問い返しに、奥から浮遊する魔導チェアーに乗って現れたタルヴィーン(kz0029)はうなずいた。
「いわゆる人間の軍隊における階級とは異なる、歪虚の力を元に表したものじゃ。そう名乗っている奴らもおれば、長年の人間たちの調査と努力の結果でわかった部分でもある」
そううそぶく精霊の言葉に、なるほどとジョンはうなずいた。
「力をもとにした、階級ネェ……まあ、敵について知るのはヨイコトです♪ 今の闘いにも、もっと役立つでしょうし、ネ」
「うむ。リアルブルーの有名な言葉に、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」とあると聞く。敵のことを知るのは戦いにおいて非常に重要じゃろうな」
「エエ♪ マッタク、真理ですネ」
精霊のうなずきにジョンは軽く肩をすくめて、にこやかに微笑んで答えていた。
天ノ都よりはるか南、歪虚に侵食された大地。
それの持つ強大な負のマテリアルは周囲の大地を歪め、侵食し、無へと還していた。
岩に覆われた荒野の中、切り取られたかのような闇としか表現しようのない虚無の空間が広がる世界。
歪虚によって侵食された大地だった。
その中央に横たわるは、邪悪なる狐。淀んだ光を含む毛並みに、雄々しく広がる巨大な九つの尾、狡猾なる智慧をたたえた鋭い眼。
「北……山本か……?」
感じられた衝撃、不快の感覚しか示さぬマテリアルの揺らぎに、大妖狐はふと、眉根をひそめ、くぐもった声でつぶやいた。その言葉の息に合わせて漏れる、舌なめずりのような赤き炎。
「……人間どもが。おとなしく滅びていけばよいものを。まだあがくか、小賢しい」
少し前、はるか西の果てで感じられた、正なるマテリアルの復活。
──不快。
そして西方より現れた覚醒者とかいう、少々力を持っただけの人間によって、奪った龍脈が取り戻されていくこと。
──ただ不快。
滅び行くしかない矮小な人間が、希望という名の戦いに身を投じ、今このときに歪虚である自分い刃を向けて刃向おうとすること。
妖狐には唯々、怒りと含む不快であった。
そして突然、妖狐は大音声の叫びをあげる。淀んだ空気が震え、その勢いに枯れた枝だけの木々が揺れ、あるいは折れて落ちる。
「彼奴らに与えられるのは、歪虚に飲まれて無に還る運命のみ。それを、改めてわからせてやらねばならぬようだな……!」
怒りを押し殺したつぶやきとともに踏み出した前足が、木を踏み折り、その踏みしめた跡に業火が一瞬、立ち上る。
その雄叫びに反応したのか、周囲の歪虚の無から絞り出されるように生まれた闇が、多くの雑魔に変化する。周囲にはその他にも、大型小型を問わず、歪虚が集結をはじめていた。
そして跳躍。
まるで空を飛ぶが如く北へと向かいはじめた妖狐を追うように、百鬼夜行と呼ぶべき歪虚の軍勢は進軍を開始した。
「歪虚の階級……デスカ?」
「うむ」
場所はリゼリオにある資料室。
サルヴァトーレ・ロッソ付きの軍人であるジョン・スミス(kz0004)の問い返しに、奥から浮遊する魔導チェアーに乗って現れたタルヴィーン(kz0029)はうなずいた。
「いわゆる人間の軍隊における階級とは異なる、歪虚の力を元に表したものじゃ。そう名乗っている奴らもおれば、長年の人間たちの調査と努力の結果でわかった部分でもある」
そううそぶく精霊の言葉に、なるほどとジョンはうなずいた。
「力をもとにした、階級ネェ……まあ、敵について知るのはヨイコトです♪ 今の闘いにも、もっと役立つでしょうし、ネ」
「うむ。リアルブルーの有名な言葉に、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」とあると聞く。敵のことを知るのは戦いにおいて非常に重要じゃろうな」
「エエ♪ マッタク、真理ですネ」
精霊のうなずきにジョンは軽く肩をすくめて、にこやかに微笑んで答えていた。
(文責:フロンティアワークス)
●九尾狐、襲来(7月13日公開)
●
夜が明ける。清らかな降り注ぐ陽光が照らすは天ノ都。
戦場の名残を生々しく刻んだその土地が――今、鳴動していた。
山本五郎左衛門、そして歪虚要塞ヨモツヘグリの大禍を打ち払った東方は今、湧いていた。その為に散った命は多く、都の被害も決して軽くはない。兵に限らず、民間人にも被害がでた。
――それでも、鬼達と妖怪達の強襲をも退けた天の都は、漸く掴みとった勝利に、漸く辿り着いた首級に、確かな熱を抱いていた。
誰しもが親しい者達の死を悼んでいる。
そして誰しもが、滅びの運命に抗える事に、勝ち取った事実に、震えていた。
●
その言葉に、応じる暇もなかった。スメラギの視界から、ありとあらゆる色が消える。同時に、紫草の絶叫の意味を知った。
闇だ。
「ンだよ、これは……」
結界と繋がっているスメラギには、それが見えた。天ノ都を中心に張り巡らされた結界の向こうから、天を覆う程の闇色の炎が向かってきているのを。闇は、獣の形をしていた。山のような大きさの、大妖狐。
驚嘆すべきはその大きさ――ではない。其の巨体から尚も溢れる黒々とした妖気だった。東方を支えた、黒竜と人柱、そして、『東方』其の物である龍脈からなる結界に込められたマテリアルを、単身で内包する大怪異を前に、スメラギは明確に、恐怖を抱いていた。
「なんなんだよお前は……ッ!!!」
山本五郎左衛門など、悪路王など、そして有象無象の妖怪達など比べる事すら烏滸がましい。
闇炎を曳いた大妖狐は其の巨体で加速し、疾走し、その領域を大きく広げた結界へと真っ直ぐに向かってくる。
――割れる。
直感した。漫然と広げた結界と、この大妖狐では勝負にすらならない。大妖狐の双眸に滲む憤怒は、結界を通してスメラギを刺し貫くかのように鋭く、激しい。その悍ましさにスメラギは死を覚悟した。人柱として、帝としての死を。
死ぬの事自体は良い。とうの昔に受け容れている事だった。
だが、それでも。
「終われる、かよ……」
呟いた。荒らげる息を無理やりに鎮めて、歯を食いしばりながら、力を込める。
「こんなクソッタレな終わりなんかで、死ねるかよ……!!!!」
無駄死にだと解っていても、その選択には、全身が震えるほどの痛みを伴った。
その日。帝になって以来初めて、スメラギは。
――自ら、結界を解いた。
●
憤怒の大妖怪、九尾狐の襲来は束の間の勝利を絶望で塗り潰していた。
スメラギと、主だった東方武人。そして、ハンター達は今、龍尾城の大広間に居た。
大きく広げられ、大広間の奥に飾られた東方の地図。それを背にしたスメラギは、大広間に蔓延る重さを意にも介さぬようにだらしなく胡座をかいていた。
紫草が微かに顎を引く。それを見て、スメラギは声を張った。
「いいかお前ら。知ってるかもしれねえが、こっちに向かっているクソ狐はマジでヤベー。この世界が滅びるのも頷いちまうくらいヤベー」
静寂を破った声は大広間に響き渡る。若さ故の、真っ直ぐな声が。
「あのクソ狐は単身でこれまでの守護結界を破れる。黒竜がどれだけ足掻こうが、俺が血を吐こうが龍脈が増えようがどーーーーーーーしようもねー。そして、アイツがこの都まで辿り着いたら、俺達は終わりだ。精霊門は潰れ、瞬く間にこの国は滅びる」
言葉と同時。左手に掲げられた符が、地図上、天ノ都の位置に突き刺さると、その場に深い沈黙が再び落ちてきた。
しかし、長くは続かない。
「……だが、足掻くぞ。俺達は」
胡座を解いて立ち上がったスメラギが、曇った気配を祓うように言葉を紡ぎ続けている。
「俺たちは永きを耐え、龍脈を取り戻し、山田を退け斃した。そん時の民の声を、お前らは聞いたか。あの熱を、見たかよ」
音が鳴るほどに拳を握る。切願だったのだ。あの光景は。居並ぶ武人達の中から、応じる声や気配が溢れてくる。それらを背負うように――あるいは、貫くように。
「……諦めねぇ。諦めるわけにはいかねぇ。戦えるってことを、奴らに見せてやらなきゃ、俺が帝である意味がねぇ!!」
咆哮にも似た声で、スメラギは言い放った。
言葉と視線から、熱が溢れてくる。東方帝。東方を守護するためだけに存在する人柱の、熱が。
「で、だ」
紫草から大きな筆を受け取ったスメラギは、下手くそな字で「くそ狐」と地図に書き込むと、そこから下方、南方へとずずいと墨を引いた。
「貼り直した結界には『穴』が開いている。あのクソ狐の妖気が結界を塞ぐように大穴をブチあけてんだ。そうして、クソ狐を追ってやってくる百鬼夜行が東方に踏み入って来てる。だから」
地図に、新たに四つの点を描く。だらりと垂れてくる墨に忌々しげに舌打ちをすると、振り返った。
「やることは二つだ。クソ狐の為『だけの』結界を張ってクソ狐を止め――この穴を、塞ぐ。……そして、その為には仕掛けが要る」
四、と。空いた左手で東方式の仕草で数字を示すスメラギ。
「『四神結界』。龍脈の力を”要”を用いて増幅し、クソ狐にあてる。龍脈を使い潰す形になっちまうが、四の五言ってられる場合じゃねェ」
くるり、と左手を翻すと、今度は親指を立ててこう言った。
「そうしてもう一つ。この百鬼夜行を止める。その為に……此処を、落とす」
とん、と。示された先。そこには、一つの城の名があった。その位置は、『クソ狐』と書かれた文字よりも南西にあり――。
「――『恵土城』。九尾を超えた向こうにある龍脈を奪い返すぞ。コイツを使って結界を塞ぎ――四神結界を完成させる」 総力戦だ。スメラギはふてぶてしく笑うい、
「コイツは、お前らハンター達に任せる。実際の儀式はコッチでやるが……」
居並ぶハンター達一人ひとりを見据えて、礼を示した。
そうしてそのまま、こう結んだ。
「頼む。最高の舞台を作ってくれ。永きに渡る戦いの、最終決戦の為の、な」
●
ハンター達が去った後、スメラギは残った東方武人達と――先ほど突き立てられた『符』に向かい、静かに語りだした。
「なあ、東方の兵士達。俺の、同胞達よ」
龍脈の補助を受けたスメラギの符術によって、スメラギの言葉は距離を越え、彼方の土地へと届けられている。
ハンター達が結界を為すまで、九尾を食い止める『誰か』が要る」
血を吐く程の苦さを、呑み込んで。スメラギは、言わねばならなかった。
「アイツらをそこに遣るわけにはいかねえ。だから」
顔も知らぬ兵士達。それでも、この土地で東方のために戦ってきた仲間たちに。
「死んでくれ。この地と、世界の未来のために」
帝としての、命令を、下さねばならなかった。
●
大妖の足を、一体の歪虚が止めていた。忍び装束に身を包み、銀目を爛々と輝かせた――半藏ユエである。
武門から歪虚に身を貶した彼女は愉しげであるが、果たして、九尾の目に入っているのだろうか疑わしい。それほどに妖狐は大きかった。少年のような体躯のユエでは、九尾の爪の先程度の大きさしか無い。
「というわけでね、結構サンモトも人間達も頑張ってたみたいだよ、です、九尾様!」
「この地の者とは違う人間ども……そうか。つくづく我を苛立たせる」
一声を発するごとに空間が震える。鳴動に、ユエの身体が不自然に波打っていた。振動を味わうユエは嬌声をあげ、十分堪能し終えるとその毛並みに縋りつくように手を伸ばした。
「ふふ、結構面白かったよ。ねえ九尾様、『僕達』、もう此処は飽きちゃったから、早くあっちに行きたいなー……あ、です」
配下の言葉に、狗、と九尾の喉が鳴る。
「――ならば、彼奴らの足掻きは尽く無に帰してやらねばなぁ」
九尾の口元から、焔が上がる。笑みを刻んだようだった。あまりにも残虐で、嗜虐的な笑みを。そうして、遠くの気配を辿るように鼻を鳴らす。
「半藏。ぬしには同胞がいたな」
「”御庭”の皆だね……あ、ですね! 今は恵土城にいるけど」
御庭、とは。
かつて武門に属していた者達が憤怒の歪虚に身を堕とした。誰が名乗りだしたかは明らかではないが、九尾御庭番衆、と称されている。『半藏』の出であるイエとユエや、『桔梗門』の織姫が属する一団であった。
「人間どもが何かを企んでおる。ぬしら御庭は人間どもの小賢しき足掻きを喰らえ」
言葉の端には、隠しきれぬ憤怒が溢れていた。矮小な身で自らに盾付き、憤怒の眷属を――延いては九尾自身に噛み付いた窮鼠に斟酌する理由など、ありはしない。
故に、九尾が為すべきは唯一つだけ。
「我は、北へ向かい絶望の只中の彼奴らを蹂躙せしめてくれよう。抗う事の無意味さを知った彼奴らが、どのような顔で我に命乞いをするのかを――此の九尾と爪牙で味わってくれるわ」
夜が明ける。清らかな降り注ぐ陽光が照らすは天ノ都。
戦場の名残を生々しく刻んだその土地が――今、鳴動していた。
山本五郎左衛門、そして歪虚要塞ヨモツヘグリの大禍を打ち払った東方は今、湧いていた。その為に散った命は多く、都の被害も決して軽くはない。兵に限らず、民間人にも被害がでた。
――それでも、鬼達と妖怪達の強襲をも退けた天の都は、漸く掴みとった勝利に、漸く辿り着いた首級に、確かな熱を抱いていた。
誰しもが親しい者達の死を悼んでいる。
そして誰しもが、滅びの運命に抗える事に、勝ち取った事実に、震えていた。
|
歴史的とも言えるその光景を龍尾城の天守閣から見下ろしたスメラギは茫と呟く。 「山田の首ってやつぁ、そんなにデケーもんだったのかね」 「山本です、スメラギ様」 「わーってる! いちいち突っ込んでんじゃねーよ! てめェは俺の…………ッ」 声を荒らげようとした所で、臓腑が傷んだか。腹を抑えて呻くスメラギの背を征夷大将軍の立花院紫草(りっかいん・むらさき)(kz0126)は武人らしからぬ柔らかさで撫でる。 「ご無理をなさらぬよう。より負荷が掛かっていれば死に至っていたかもしれない、と医師に釘を刺されたばかりでしょうに」 「…………っせーな。帝ってやつァそんなもんだろ。解りきってる事を一々言うんじゃねェよ」 返す言葉は、東方帝にしては弱く、呼吸を整えるその額には玉のような汗が浮かんでいた。宿業を呑みこんで言う帝に、紫草は言葉では応じずに、ただその手で自身の意を示す。 ――転瞬。 紫草の視線が、木枠で縁取られた窓の外。蒼天を貫いて向こうへと向けられた。 「…………これは…………ッ」 東方無双の剣士の双眸には様々な色が綯い交ぜになっていた。驚愕し、絶句し、混乱し、恐怖し、戦慄していた。 「っ………………ん? どーしたんだ一体」 只ならぬ様子に警戒し室内へと身を潜めたスメラギだが、何も起こらない事を怪訝に問う、と。 「……っ!」 弾かれるようにスメラギを見て、 「結界を、解除してください! 疾く…………ッ!!」 腹の底から、叫んだ。 |

スメラギ 
立花院紫草 |
●
その言葉に、応じる暇もなかった。スメラギの視界から、ありとあらゆる色が消える。同時に、紫草の絶叫の意味を知った。
闇だ。
「ンだよ、これは……」
結界と繋がっているスメラギには、それが見えた。天ノ都を中心に張り巡らされた結界の向こうから、天を覆う程の闇色の炎が向かってきているのを。闇は、獣の形をしていた。山のような大きさの、大妖狐。
驚嘆すべきはその大きさ――ではない。其の巨体から尚も溢れる黒々とした妖気だった。東方を支えた、黒竜と人柱、そして、『東方』其の物である龍脈からなる結界に込められたマテリアルを、単身で内包する大怪異を前に、スメラギは明確に、恐怖を抱いていた。
「なんなんだよお前は……ッ!!!」
山本五郎左衛門など、悪路王など、そして有象無象の妖怪達など比べる事すら烏滸がましい。
闇炎を曳いた大妖狐は其の巨体で加速し、疾走し、その領域を大きく広げた結界へと真っ直ぐに向かってくる。
――割れる。
直感した。漫然と広げた結界と、この大妖狐では勝負にすらならない。大妖狐の双眸に滲む憤怒は、結界を通してスメラギを刺し貫くかのように鋭く、激しい。その悍ましさにスメラギは死を覚悟した。人柱として、帝としての死を。
死ぬの事自体は良い。とうの昔に受け容れている事だった。
だが、それでも。
「終われる、かよ……」
呟いた。荒らげる息を無理やりに鎮めて、歯を食いしばりながら、力を込める。
「こんなクソッタレな終わりなんかで、死ねるかよ……!!!!」
無駄死にだと解っていても、その選択には、全身が震えるほどの痛みを伴った。
その日。帝になって以来初めて、スメラギは。
――自ら、結界を解いた。
●
憤怒の大妖怪、九尾狐の襲来は束の間の勝利を絶望で塗り潰していた。
スメラギと、主だった東方武人。そして、ハンター達は今、龍尾城の大広間に居た。
大きく広げられ、大広間の奥に飾られた東方の地図。それを背にしたスメラギは、大広間に蔓延る重さを意にも介さぬようにだらしなく胡座をかいていた。
紫草が微かに顎を引く。それを見て、スメラギは声を張った。
「いいかお前ら。知ってるかもしれねえが、こっちに向かっているクソ狐はマジでヤベー。この世界が滅びるのも頷いちまうくらいヤベー」
静寂を破った声は大広間に響き渡る。若さ故の、真っ直ぐな声が。
「あのクソ狐は単身でこれまでの守護結界を破れる。黒竜がどれだけ足掻こうが、俺が血を吐こうが龍脈が増えようがどーーーーーーーしようもねー。そして、アイツがこの都まで辿り着いたら、俺達は終わりだ。精霊門は潰れ、瞬く間にこの国は滅びる」
言葉と同時。左手に掲げられた符が、地図上、天ノ都の位置に突き刺さると、その場に深い沈黙が再び落ちてきた。
しかし、長くは続かない。
「……だが、足掻くぞ。俺達は」
胡座を解いて立ち上がったスメラギが、曇った気配を祓うように言葉を紡ぎ続けている。
「俺たちは永きを耐え、龍脈を取り戻し、山田を退け斃した。そん時の民の声を、お前らは聞いたか。あの熱を、見たかよ」
音が鳴るほどに拳を握る。切願だったのだ。あの光景は。居並ぶ武人達の中から、応じる声や気配が溢れてくる。それらを背負うように――あるいは、貫くように。
「……諦めねぇ。諦めるわけにはいかねぇ。戦えるってことを、奴らに見せてやらなきゃ、俺が帝である意味がねぇ!!」
咆哮にも似た声で、スメラギは言い放った。
言葉と視線から、熱が溢れてくる。東方帝。東方を守護するためだけに存在する人柱の、熱が。
「で、だ」
紫草から大きな筆を受け取ったスメラギは、下手くそな字で「くそ狐」と地図に書き込むと、そこから下方、南方へとずずいと墨を引いた。
「貼り直した結界には『穴』が開いている。あのクソ狐の妖気が結界を塞ぐように大穴をブチあけてんだ。そうして、クソ狐を追ってやってくる百鬼夜行が東方に踏み入って来てる。だから」
地図に、新たに四つの点を描く。だらりと垂れてくる墨に忌々しげに舌打ちをすると、振り返った。
「やることは二つだ。クソ狐の為『だけの』結界を張ってクソ狐を止め――この穴を、塞ぐ。……そして、その為には仕掛けが要る」
四、と。空いた左手で東方式の仕草で数字を示すスメラギ。
「『四神結界』。龍脈の力を”要”を用いて増幅し、クソ狐にあてる。龍脈を使い潰す形になっちまうが、四の五言ってられる場合じゃねェ」
くるり、と左手を翻すと、今度は親指を立ててこう言った。
「そうしてもう一つ。この百鬼夜行を止める。その為に……此処を、落とす」
とん、と。示された先。そこには、一つの城の名があった。その位置は、『クソ狐』と書かれた文字よりも南西にあり――。
「――『恵土城』。九尾を超えた向こうにある龍脈を奪い返すぞ。コイツを使って結界を塞ぎ――四神結界を完成させる」 総力戦だ。スメラギはふてぶてしく笑うい、
「コイツは、お前らハンター達に任せる。実際の儀式はコッチでやるが……」
居並ぶハンター達一人ひとりを見据えて、礼を示した。
そうしてそのまま、こう結んだ。
「頼む。最高の舞台を作ってくれ。永きに渡る戦いの、最終決戦の為の、な」
●
ハンター達が去った後、スメラギは残った東方武人達と――先ほど突き立てられた『符』に向かい、静かに語りだした。
「なあ、東方の兵士達。俺の、同胞達よ」
龍脈の補助を受けたスメラギの符術によって、スメラギの言葉は距離を越え、彼方の土地へと届けられている。
ハンター達が結界を為すまで、九尾を食い止める『誰か』が要る」
血を吐く程の苦さを、呑み込んで。スメラギは、言わねばならなかった。
「アイツらをそこに遣るわけにはいかねえ。だから」
顔も知らぬ兵士達。それでも、この土地で東方のために戦ってきた仲間たちに。
「死んでくれ。この地と、世界の未来のために」
帝としての、命令を、下さねばならなかった。
●
大妖の足を、一体の歪虚が止めていた。忍び装束に身を包み、銀目を爛々と輝かせた――半藏ユエである。
武門から歪虚に身を貶した彼女は愉しげであるが、果たして、九尾の目に入っているのだろうか疑わしい。それほどに妖狐は大きかった。少年のような体躯のユエでは、九尾の爪の先程度の大きさしか無い。
「というわけでね、結構サンモトも人間達も頑張ってたみたいだよ、です、九尾様!」
「この地の者とは違う人間ども……そうか。つくづく我を苛立たせる」
一声を発するごとに空間が震える。鳴動に、ユエの身体が不自然に波打っていた。振動を味わうユエは嬌声をあげ、十分堪能し終えるとその毛並みに縋りつくように手を伸ばした。
「ふふ、結構面白かったよ。ねえ九尾様、『僕達』、もう此処は飽きちゃったから、早くあっちに行きたいなー……あ、です」
配下の言葉に、狗、と九尾の喉が鳴る。
「――ならば、彼奴らの足掻きは尽く無に帰してやらねばなぁ」
九尾の口元から、焔が上がる。笑みを刻んだようだった。あまりにも残虐で、嗜虐的な笑みを。そうして、遠くの気配を辿るように鼻を鳴らす。
「半藏。ぬしには同胞がいたな」
「”御庭”の皆だね……あ、ですね! 今は恵土城にいるけど」
御庭、とは。
かつて武門に属していた者達が憤怒の歪虚に身を堕とした。誰が名乗りだしたかは明らかではないが、九尾御庭番衆、と称されている。『半藏』の出であるイエとユエや、『桔梗門』の織姫が属する一団であった。
「人間どもが何かを企んでおる。ぬしら御庭は人間どもの小賢しき足掻きを喰らえ」
言葉の端には、隠しきれぬ憤怒が溢れていた。矮小な身で自らに盾付き、憤怒の眷属を――延いては九尾自身に噛み付いた窮鼠に斟酌する理由など、ありはしない。
故に、九尾が為すべきは唯一つだけ。
「我は、北へ向かい絶望の只中の彼奴らを蹂躙せしめてくれよう。抗う事の無意味さを知った彼奴らが、どのような顔で我に命乞いをするのかを――此の九尾と爪牙で味わってくれるわ」
(執筆:ムジカ・トラス)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●小高砦陥落(7月23日公開)
「……あれは?」
結界のほつれに伴い、侵入する百鬼夜行、憤怒の歪虚たちを何とかしのいでいた小高砦。
その物見の兵が風景の異様に気が付いたのは、その時であった。
砦から見渡せる敵勢の様子。起伏少なき周囲に群がる歪虚の群れの向こうより現れたるは、突然、山が聳え立ったかのように思える、人などその爪ほどの大きさにも足らぬ巨獣。
憤怒の王、九尾狐。
「て、敵襲ー!」
距離感もおかしく感じるほど、巨大なる敵首魁が現れたことに、砦の状況は悪化する。
「九尾のやつがこちらに向かっているだと?」
「いやしかし、ただの一体ではどうということもできまい……」
「牡丹様へのご連絡を! 戦えるものは準備を整えよ!」
「……あ、ありゃあ、何だ……?」
怒号が轟き、より強く緊迫した息が張り詰める中、物見の兵は九尾を見やり。
ただ目の前の光景、変わりゆく九尾の姿に、絶句した。
「我が名は、獄炎。九蛇頭尾大黒狐・獄炎の名、その意味。存分に思い知るがいい」
大音声の叫びにあわせ、今度は砦からもわかるように確実に、獣の顔が邪悪な笑みに歪んだ。
合わせて大蛇の口元に熱気が集中し、そして赤から青、そして黒へと色を変えていく炎が渦巻き始める。
「……燃え消えろ」
そして吐き気をもよおすような腹に響く哄笑の中、地獄の業火は放たれた。
大蛇の口より一気に吐き出された地獄の炎は、砦を囲んでいた周囲の雑魔を巻き込みながら一直線に、小高砦の城壁に叩きつけられる。
黒き炎の熱量は覆った城壁をあっさりと焼き、壁そのものを瓦解させると、壁に守られていたはずの砦そのものを大きく揺らす。
「さあ滅びるがいい、人間ども。遠慮なく、な……」
大穴があいた城壁に取りつく配下歪虚の様子を見て、九尾・獄炎は興味がなくなったとばかりに踵を返す。
不快。
九尾の狐の心中に渦巻くものは、ただそれだけを示す怒り。
人間ごとき滅びる運命の定命のものが、歪虚の王たる自分に逆らうこと。その傲岸不遜と言える今回の反攻作戦。
先日は自らのマテリアル・龍脈に接触を試みた存在がいた。
あれも、人間だったか?
その後より、ざらつくようにまとわりつく『結界』とやらのせいで、先ほどの炎もやや、力を失っているように感じる。
そういった人類の動きは、周囲を舞う羽虫にイラつくがごとく、唯々、不快であった。
代価は、絶望を。
「150年……少しばかり、長きにすぎた。よい契機だ。人間どもが滅びるのに、な……」
ゆっくりと北進を続ける獄炎の邪悪な笑みとともに、その口腔、牙の隙間よりは炎が漏れ出していた。
結界のほつれに伴い、侵入する百鬼夜行、憤怒の歪虚たちを何とかしのいでいた小高砦。
その物見の兵が風景の異様に気が付いたのは、その時であった。
砦から見渡せる敵勢の様子。起伏少なき周囲に群がる歪虚の群れの向こうより現れたるは、突然、山が聳え立ったかのように思える、人などその爪ほどの大きさにも足らぬ巨獣。
憤怒の王、九尾狐。
「て、敵襲ー!」
距離感もおかしく感じるほど、巨大なる敵首魁が現れたことに、砦の状況は悪化する。
「九尾のやつがこちらに向かっているだと?」
「いやしかし、ただの一体ではどうということもできまい……」
「牡丹様へのご連絡を! 戦えるものは準備を整えよ!」
「……あ、ありゃあ、何だ……?」
怒号が轟き、より強く緊迫した息が張り詰める中、物見の兵は九尾を見やり。
ただ目の前の光景、変わりゆく九尾の姿に、絶句した。
|
「人間よ」 狐の口より、静かに通るくぐもった声が響く。その巨体に見合った声は、叫んではいないが戦場全体に響き渡るほどであった。 「貴様らに、絶望というものを教えてやろう。貴様らの身の程を知らしめてやろう」 獣の顔ゆえにわからぬが、愉悦を含んだ声音より、狐は笑んだと思われた。 それに合わせて九尾の尾が膨らみ、ぐにゃりと形を変えていく。 青白い体毛は徐々に暗き黒緑の色へと変わっていき、その尾を覆う体毛は硬質化した鱗へと変わる。 その変化の先、尾の一つは巨大な大蛇へと姿を変えていた。 蛇は鎌首をもたげ、赤き舌と炎を口の隙間からのぞかせながら、瘴気を吐き出し意思無き瞳で、主たる九尾狐とともに砦をにらみつける。 |

九尾狐 |
大音声の叫びにあわせ、今度は砦からもわかるように確実に、獣の顔が邪悪な笑みに歪んだ。
合わせて大蛇の口元に熱気が集中し、そして赤から青、そして黒へと色を変えていく炎が渦巻き始める。
「……燃え消えろ」
そして吐き気をもよおすような腹に響く哄笑の中、地獄の業火は放たれた。
大蛇の口より一気に吐き出された地獄の炎は、砦を囲んでいた周囲の雑魔を巻き込みながら一直線に、小高砦の城壁に叩きつけられる。
黒き炎の熱量は覆った城壁をあっさりと焼き、壁そのものを瓦解させると、壁に守られていたはずの砦そのものを大きく揺らす。
「さあ滅びるがいい、人間ども。遠慮なく、な……」
大穴があいた城壁に取りつく配下歪虚の様子を見て、九尾・獄炎は興味がなくなったとばかりに踵を返す。
不快。
九尾の狐の心中に渦巻くものは、ただそれだけを示す怒り。
人間ごとき滅びる運命の定命のものが、歪虚の王たる自分に逆らうこと。その傲岸不遜と言える今回の反攻作戦。
先日は自らのマテリアル・龍脈に接触を試みた存在がいた。
あれも、人間だったか?
その後より、ざらつくようにまとわりつく『結界』とやらのせいで、先ほどの炎もやや、力を失っているように感じる。
そういった人類の動きは、周囲を舞う羽虫にイラつくがごとく、唯々、不快であった。
代価は、絶望を。
「150年……少しばかり、長きにすぎた。よい契機だ。人間どもが滅びるのに、な……」
ゆっくりと北進を続ける獄炎の邪悪な笑みとともに、その口腔、牙の隙間よりは炎が漏れ出していた。
(文責:フロンティアワークス)
●九尾阻止へ ‐開戦‐(7月29日公開)
「小高砦の状況はどうなっている!」
「救援を送りましたが、未だ状況は不明! 九尾、尚も北上中! 阻止できません!」
龍尾城の空気が浮足立つのは当然と言えた。
歪虚を構成する七つの眷属、その頂点に君臨する一体。歪虚王、九蛇頭尾大黒狐“獄炎”。
その力は圧倒的で、ちょっとした砦や結界などなんの役にも立たない程だ。
「西方の方々は、ついに歪虚から人類の生活圏を奪還するという快挙を成し遂げられました。しかしそれでも、歪虚王を退けた経験はありませんね?」
「始祖たる七……その存在は王国の長い歴史においても、撃退成功例は一つもありません」
紫草は穏やかに笑みを作り。
「その調子です。借りてきた猫のようなスメラギ様では、お仕えし甲斐がありません」
元々仕えていた先帝に託されたスメラギという小さな命は、戦いの中で大きく成長した。
それを嬉しく、そして少しだけ寂しく思う。だがこれはきっと運命だったのだ。
「籠の中の鳥も、いついつかは飛び立つもの。その翼を守る事、それこそが私の役目……そうですね、“スメラギ様”」
目を瞑り呟いた声は誰にも届かない。だがそれで良い。祈る時間は、これでおしまい。
「――ご指示を、我が君。迷える我らに号令を。兵どもは今か今かと心待ちにしております。さあ王よ。黒龍を戴く我らが王よ。すべての悲劇に終止符を」
会議室に集まった兵達が手を止めスメラギに目を向ける。その一人一人と視線を合わせ、スメラギは右手を掲げた。
「……行くぞ野郎共! 百五十年も俺達を閉じ込めた九尾をぶっ潰し、始祖狩りに名乗りをあげろ! 東方が磨きあげた不屈の魂を刃と成し、親父やお袋やご先祖様の分までぶちかませ!」
振り下ろされた右手が強く卓を叩くと、兵達の瞳に活が宿る。
「全軍戦闘用意! この戦い、勝ちに行くぞッ!!」
割れんばかりの雄叫びが響き渡り、兵達が動き出す。
迷っている場合じゃない。悲しんでいる場合じゃない。諦めている場合じゃない。
「俺にだって……」
守りたいものが、あるのだから――。
「ハンターとの戦いの中で、ユーも見てきたのではありませんか? 人の命の輝きを」
ずきりと傷んだこめかみにアイゼンハンダーの表情が歪む。
「……何故だ。貴官もまた、オルクス兵長に従い革命軍と戦う帝国の戦士の筈。だというのに何故、奴らの肩を持つような事を言う……!」
「Sorry。しかし勘違いしないでくだサーイ。ミーは、弱っちい人類の肩を持つつもりなんてサラサラありまセーン♪」
肩を竦める大げさなポーズの後、おどけるようにそれを上下させ。しかしヘルメット越しの視線は確かな憎悪を湛えている。
「そう。救世主に縋り自らの力で明日を切り開かぬ弱者では、何かを守る事などImpossibleデース。そしてその弱さを背負えぬ者に、世界は救えまセーン」
低い声でそう呟き、男はポンとアイゼンハンダーの肩を叩く。
「この戦いは獄炎ちゃんの圧勝で幕を閉じマース♪ アイちゃんは高みの見物でも決め込んでくだサーイ♪」
See you again! そう叫びながら男はリンドヴルムの背から飛び降りた。
「……奇天烈な方だ」
冷や汗を流しつつ落ちていく影を見送り、眼下の戦場に意識を傾ける。
沢山の怒号、嘆き、命の火が消えていく。刀鬼の言う通り、この戦いはきっと歪虚の勝利に終わるだろう。
「諦めきれないのだな……それでも」
切なげな呟きは風に消え、飛竜は遠ざかる。その影を地上から見上げる別の影があった。
これまでのどんな歪虚よりも強大な、絶対的な力。これが正真正銘、世界を終わらせる怪物――。
「怯むな!」
ヴィルヘルミナの声が戦場に響き渡る。
「これは人の命運を賭けた決戦である! 友を信じ、刃に命を賭けよ! 必ずや歪虚王を討ち、人の力を証明するのだ!」
鼓舞する言葉を耳にしつつバタルトゥは敵を見上げた。
こういうものには向き不向きがある。ヴィルヘルミナのようなやり方で兵を勇気づけるのは苦手だが、先頭に立ち部下を導く事はできる。
「……行くぞ。勝ち目の薄い戦いなど……とうに慣れている」
剣を掲げながらヴィルヘルミナは思案する。
どんなに言葉で強がっても、目の前の怪物にはきっと敵わないだろう。
真正面からぶつかってどうにかなる相手ではないのだ。だからこそ、今はただ時間を稼ぐしかない。
「信じるぞ。すべての道は交わっているのだと。そして我らはいつかきっと、分かり合えるのだと――」
獄炎がゆっくりと口を開き、吼える。それだけで陣が崩れ、戦場が恐怖に包まれる。
そんな中、怯え竦む兵達を掻き分け前に出る者達がいた。
不可能を覆し、世界を変えてきた英雄達……ハンター。
その力一つ一つは歪虚王に遠く及ばずとも。例えこの戦いの中で友を失う事になろうとも。
それでもと前に踏み出す彼らの背中に、兵達は続いていく。
諦めず運命に抗い続ける意志。きっとそれこそが、人の心に残された最後の希望なのだ。
「愚かな……」
大蛇の口に炎が灯る。
憤怒の歪虚王、九蛇頭尾大黒狐獄炎との戦いの火蓋が切って落とされた。
「救援を送りましたが、未だ状況は不明! 九尾、尚も北上中! 阻止できません!」
龍尾城の空気が浮足立つのは当然と言えた。
歪虚を構成する七つの眷属、その頂点に君臨する一体。歪虚王、九蛇頭尾大黒狐“獄炎”。
その力は圧倒的で、ちょっとした砦や結界などなんの役にも立たない程だ。
「西方の方々は、ついに歪虚から人類の生活圏を奪還するという快挙を成し遂げられました。しかしそれでも、歪虚王を退けた経験はありませんね?」
「始祖たる七……その存在は王国の長い歴史においても、撃退成功例は一つもありません」
|
立花院紫草の言葉にシスティーナ・グラハム(kz0020)が神妙な面持ちで頷く。 嘗て北から南下したという歪虚王達は、たった数体で数多の国を闇に飲み込み、人類の生活圏を大きく削りとった。 しかしその後は部下である眷属を送り込むばかりで、その本格的な活動が認識されなくなって久しい。 「連中にとっては百年、二百年程度の時など瞬く間の出来事。少し休憩していた程度の事だろうよ。それが重い腰を上げたというのは、人類の快挙と言える」 「ヴィルヘルミナ様……そんな悠長な」 「だが……いつかはやり合わねばならない相手だ……。それが早いか遅いか、というだけの事……」 バタルトゥ・オイマト(kz0023)が静かに同意の姿勢を見せると、スメラギはゆっくりと頷き。 「ああ。こいつを倒さなければ東方の真の開放はない。そしてこいつを倒す事は、きっとこの世界に希望を示す事でもあるんだ」 龍尾城の会議室から見下ろす町並みは今はまだ穏やかで、ここが時期にひどい戦場になる事など考えられない。 風に吹かれ、少年は髪を揺らしながら穏やかに目を細めた。 「俺にとってこの世界は、城の窓から眺める範囲がすべてだった。それ以外の事なんて正直関係ねぇ……そう思ってたんだ。でもよ、そうじゃなかったんだよ」 遠い遠い西方からやってきた友人たちが、暗澹とした絶望に包まれたこの町に光を齎してくれた。 命がけの転移、命がけの作戦。タイトロープの上を集団で渡り歩くような馬鹿げた戦いの中で、彼らは諦めず未来を求め続けた。 「俺は結界を張る為の人柱。御役目として、御柱として生きて死ぬ。その人生になんの価値があんだって、本当はずっと迷ってた。だけど……」 沢山の部下が死んだ。沢山の西方の友人が死んだ。 どう考えても絶望的な戦況に挑み、命を落とすと理解していながら、それでも彼らが走り続けた道は、決して無意味なんかじゃない。 命はつながっていく。人は歴史を重ね、想いを託す事ができる。その積み重ねが今日の奇跡を作ったのだと知った。 「この戦いで俺が死んだって、無意味じゃねぇんだ。それがうれしくってよ。親父もこんな気持ちで役目を託してくれたのかなって、そう思えるようになったんだ」 風を背に受け振り返り、白い歯を見せ……しかしどこか寂しげにスメラギは笑う。 「死ぬのはやっぱ怖ぇわ! けどよ、今は安心してんだ。きっと俺が駄目でもお前らが……そしてあいつらハンターが受け継いでくれるから」 顔を見合わせるヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)とバタルトゥ。二人が口を開く前に、システィーナがスメラギの手を取った。 「わたくし達は、皆どこかで繋がっている。繋がる事ができる。わたくし達はもう他人ではありません。スメラギ様を無駄死にさせるような事、絶対にさせませんからね」 「システィーナ……」 「無力なわたくしにできる事は、皆さんを信じる事くらいです。信じて、信じて……そして、その無事を祈るくらいです。だからこそ、せめて祈らせて下さい。エクラの加護が、スメラギ様にもあるようにと」 「……ありがとな、システィーナ。いいや。西方の王、システィーナ・グラハム」 二人が手を取り合う姿をヴィルヘルミナは遠巻きに眺め、すっと目を細める。 「皮肉だな。西方と遠く離れたこの地においてこそ、我らは真の意味で手を取り合う事ができる」 「利害も遺恨も関係なく……か」 「お互い色々と初心では居られぬ立場だが、この戦いが終わるまでは」 「ああ……。ただ同じ、人として……友として、ありたいものだな……」 ふと、そこへ立花院 紫草(kz0126)の咳払いが響き。 「スメラギ様。いつまでも女性の手をひしと握っているのは如何なものかと」 「ぬおおぉっ!? う、うるせーよ! これはシスティーナの方が勝手にだな……」 「システィーナ“様”でしょう」 「ぐっ、いちいちうるせーぞ馬鹿!」 |

システィーナ・グラハム 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル 
バタルトゥ・オイマト 
スメラギ 
立花院紫草 |
「その調子です。借りてきた猫のようなスメラギ様では、お仕えし甲斐がありません」
元々仕えていた先帝に託されたスメラギという小さな命は、戦いの中で大きく成長した。
それを嬉しく、そして少しだけ寂しく思う。だがこれはきっと運命だったのだ。
「籠の中の鳥も、いついつかは飛び立つもの。その翼を守る事、それこそが私の役目……そうですね、“スメラギ様”」
目を瞑り呟いた声は誰にも届かない。だがそれで良い。祈る時間は、これでおしまい。
「――ご指示を、我が君。迷える我らに号令を。兵どもは今か今かと心待ちにしております。さあ王よ。黒龍を戴く我らが王よ。すべての悲劇に終止符を」
会議室に集まった兵達が手を止めスメラギに目を向ける。その一人一人と視線を合わせ、スメラギは右手を掲げた。
「……行くぞ野郎共! 百五十年も俺達を閉じ込めた九尾をぶっ潰し、始祖狩りに名乗りをあげろ! 東方が磨きあげた不屈の魂を刃と成し、親父やお袋やご先祖様の分までぶちかませ!」
振り下ろされた右手が強く卓を叩くと、兵達の瞳に活が宿る。
「全軍戦闘用意! この戦い、勝ちに行くぞッ!!」
割れんばかりの雄叫びが響き渡り、兵達が動き出す。
迷っている場合じゃない。悲しんでいる場合じゃない。諦めている場合じゃない。
「俺にだって……」
守りたいものが、あるのだから――。
|
「しかーしデスね。どう考えても準備不足デース」 九尾はゆっくりと北上を続けている。その侵攻を阻止しようと奮闘する東方兵は次々に蹴散らされ、時間稼ぎにもならない。 「Losing battle……結果は見えてマース」 獄炎にとってこんな物は戦いですらないのだ。ただ歩き、進んでいるだけ。その道中を虫けらが塞ごうが、踏み砕けば済むだけの事。 「彼我の戦力差は圧倒的……だというのに何故だ。何故、勝ち目のない戦いに挑み続けるのだ……?」 「アーハン? それはアイちゃんと同じ理由ではないデスかね?」 上空を旋回するゾンビの飛竜、リンドヴルム。その背に二つの歪虚の影があった。 それらは共に災厄の十三魔。この東方での戦いを監視し、場合によっては憤怒に手を貸せと命じられていた。 アイゼンハンダーは自らをただの兵士と認識している。彼女にとって戦いに理由は要らない。その筈だった。 「Those that do not negotiable……例え結末を突きつけられたとしても、認められないワケがある。覆したいと願うから、人は戦いをやめられないのデース」 軍帽を片手で押さえながらアイゼンハンダーは奇妙な男に目を向ける。 十三魔が一、紫電の刀鬼。同じく暴食に属し、四霊剣オルクスの命で東方にやってきた。 しかしこの男はその名から連想できるように、元々は東方の出身であったという。 のらりくらりとふざけた態度で真面目に任務もこなさないこの男は元々苦手ではあったが、東方にきてからそれは悪化したように思う。 |
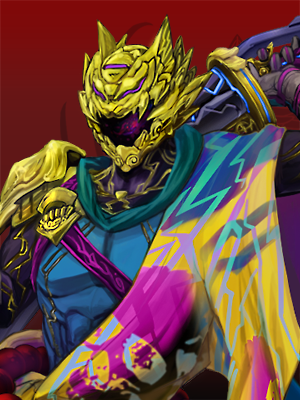
紫電の刀鬼 
アイゼンハンダー |
ずきりと傷んだこめかみにアイゼンハンダーの表情が歪む。
「……何故だ。貴官もまた、オルクス兵長に従い革命軍と戦う帝国の戦士の筈。だというのに何故、奴らの肩を持つような事を言う……!」
「Sorry。しかし勘違いしないでくだサーイ。ミーは、弱っちい人類の肩を持つつもりなんてサラサラありまセーン♪」
肩を竦める大げさなポーズの後、おどけるようにそれを上下させ。しかしヘルメット越しの視線は確かな憎悪を湛えている。
「そう。救世主に縋り自らの力で明日を切り開かぬ弱者では、何かを守る事などImpossibleデース。そしてその弱さを背負えぬ者に、世界は救えまセーン」
低い声でそう呟き、男はポンとアイゼンハンダーの肩を叩く。
「この戦いは獄炎ちゃんの圧勝で幕を閉じマース♪ アイちゃんは高みの見物でも決め込んでくだサーイ♪」
See you again! そう叫びながら男はリンドヴルムの背から飛び降りた。
「……奇天烈な方だ」
冷や汗を流しつつ落ちていく影を見送り、眼下の戦場に意識を傾ける。
沢山の怒号、嘆き、命の火が消えていく。刀鬼の言う通り、この戦いはきっと歪虚の勝利に終わるだろう。
「諦めきれないのだな……それでも」
切なげな呟きは風に消え、飛竜は遠ざかる。その影を地上から見上げる別の影があった。
|
強欲の十三魔、ガルドブルム。主に西方で活動する歪虚だが、アイゼンハンダーや刀鬼と同じく東方の騒乱にも参戦している。 『オルクスのバアさんの犬か。ご苦労なこった』 腕を組み、九尾と人間の戦いに目を凝らす。 『始祖体の力は伊達じゃねェ。ニンゲン風情にどうにかできるモンじゃねェが……』 そう結論付けながらも、どこかでそれをひっくり返すのではないかと期待している自分がいる。 『最強の一角、九尾獄炎。そのチカラ、如何程の物かねェ?』 翼を広げ、空に舞い上がる。幸い九尾は巨大で、遠くからでもよく戦況が把握できた。 そう、この戦いはきっと歪虚の勝利で終わる。だがもしも、万が一の番狂わせが起こるとしたら。 きっと愉快な事になる。どう転んでも損はない。だからこそ、今は見極める時なのだ――。 |

ガルドブルム |
|
巨体が踏み出す一歩が地を鳴らし、その爪の一振りがニンゲンを容易に肉片に変える。 尾が変化した大蛇の口に収束した炎は黒く渦巻き、一度吐出されればすべてを焼きつくしていく。 息も出来ないほどの火炎を背に九尾が進軍する。歪虚王の力を前に、人の力はあまりに無力だ。 「……塵め。払っても払っても湧いてきよる」 隊列を組んだ兵が矢を放ち、刀を掲げ突撃する。それを獄炎は何ら意に介さず灰燼と化した。 「滅びは必然……約束されし世界の運命。人の分際でそれを変えよう等と、身の程を弁えよ」 ハンター達が戦場へ辿り着いた時、そこは既に地獄の炎に包まれていた。 巨大すぎる三つの眼に見つめられるだけで背筋が凍りつき、呼吸の仕方さえ忘れてしまいそうになる。 |

九蛇頭尾大黒狐 獄炎 |
「怯むな!」
ヴィルヘルミナの声が戦場に響き渡る。
「これは人の命運を賭けた決戦である! 友を信じ、刃に命を賭けよ! 必ずや歪虚王を討ち、人の力を証明するのだ!」
鼓舞する言葉を耳にしつつバタルトゥは敵を見上げた。
こういうものには向き不向きがある。ヴィルヘルミナのようなやり方で兵を勇気づけるのは苦手だが、先頭に立ち部下を導く事はできる。
「……行くぞ。勝ち目の薄い戦いなど……とうに慣れている」
剣を掲げながらヴィルヘルミナは思案する。
どんなに言葉で強がっても、目の前の怪物にはきっと敵わないだろう。
真正面からぶつかってどうにかなる相手ではないのだ。だからこそ、今はただ時間を稼ぐしかない。
「信じるぞ。すべての道は交わっているのだと。そして我らはいつかきっと、分かり合えるのだと――」
獄炎がゆっくりと口を開き、吼える。それだけで陣が崩れ、戦場が恐怖に包まれる。
そんな中、怯え竦む兵達を掻き分け前に出る者達がいた。
不可能を覆し、世界を変えてきた英雄達……ハンター。
その力一つ一つは歪虚王に遠く及ばずとも。例えこの戦いの中で友を失う事になろうとも。
それでもと前に踏み出す彼らの背中に、兵達は続いていく。
諦めず運命に抗い続ける意志。きっとそれこそが、人の心に残された最後の希望なのだ。
「愚かな……」
大蛇の口に炎が灯る。
憤怒の歪虚王、九蛇頭尾大黒狐獄炎との戦いの火蓋が切って落とされた。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●共闘の兆し(8月3日公開)
人類は争乱を制し、次なる決戦に挑もうとしている。東方においては史上最も重要な戦いに。
さて。山本五郎左衛門が歪虚要塞ヨモツヘグリを伴い天の都を強襲したことは記憶に新しい。その戦禍はまざまざと都に刻まれたまま、現在に至っている。
――その中で、一人の『鬼』が使者となり、投降を告げたことを知る者は多くはないだろう。
戦乱の只中、鬼の死体に扮した鬼はハンター達に自らの目的と共に、彼らの過去を語った。
鬼、曰く。
妖怪たちの侵攻の中で、彼らが居た国もまた滅びを迎えた。エトファリカ連邦に属することも、結界の恩恵を受ける事もなく。
魔刀を振るう赤鬼アカシラを筆頭に残る鬼達も、かつてはそこにいた。今でこそ彼ら一党を率いるのはアカシラだが、当時は違った。
その青鬼の名を、アクロという。アクロは知恵と人徳で鬼達を導き、彼ら自身の里だけでなく、周囲の人類を護りながら暮らしていた。運命を共にする者達だ、と。互いに補い合いながらの防戦であった。
そのアクロ達の戦振りが目についたわけでもなかろうが、徐々に戦えぬ者が増えていき、盾たる彼らは摩耗し――人類は自らの領土に篭もった結果、鬼達は孤立した。
そのまま、鬼達は滅びを迎えていた筈だった。妖怪の主が、気紛れで手を伸べなければ。
――紆余曲折はあったものの、最終的にアクロはそれを受け容れた。彼を慕ってついてきた鬼達の、延命のために。
鬼達の運命を妖怪に預けたわけではなかった。ただ、人間達は助けには来なかった。
妖怪の手先に成り下がった鬼達は戦線を転々としていたが――その手緩さを攻められ、歪虚に成る事を強いられた。
後のことをアカシラに頼み、「人を恨むな、機を待て」と言い残して、アクロは「悪路王」になった。
西方人類がこの地を訪れるまでの間、悪路王と鬼達は、各地の国を攻め滅ぼし、数々の武門を討ち果たしてきた。
そのことは、人類の『生き残り』達が語ることと同じだった。鬼達は、妖怪たちの監視を受けながら、人類の敵として生きてきた。
今日、この時まで。
●
「二つ。罠だとしたら変な所がある。一つは、鬼達は助命を乞うちゃいるが、それ以外に要求はねェ。そして――」
視線を切ったのは、何れも希望的観測に近しいから、か。
「前の天ノ都に、悪路王が来なかったことだ。妖怪たちだって侵入していたのに、アイツは現れなかった。あの時、アイツまで現れてたら今頃俺らは死んでる……かも知れねぇ。ハンターたちもいたからわかんねーが、今更仕掛けるのも変な話だ。罠にしちゃァ杜撰に過ぎる」
雲行きが怪しくなってきたことを感じ、スメラギが不快げにそう結ぶと、ヴィルヘルミナは頷きを返した。
「なら、こちらから条件を出してやればどうだ。それですべての罪が晴れることはないだろうが、過度に罠を警戒しなくてすむ。鬼を自由にして戦場に出てこられるよりはましだろう?」
「……それじゃあ……!」
システィーナの表情が一息に明るくなったことに、スメラギは嘆息した。面白くない。システィーナの甘さも、ヴィルヘルミナの、使えるものは何でも使おうとする器の広さも。
だが、落とし所としては悪くはなかったから――鬼達の元に、使者が送られる事だけは決まった。
「……気ィ重いぜマジで……」
先々に予測される衝突を思い、スメラギは深く息を吐いた。
――決定から、暫し後のこと。
●
「朱夏殿」
「解っている!」
窘めるような、それでいて愉快げなシンカイの声に苛立ちを込めてそう叫ぶと、次なる敵へと踏み込んで言った。
――はて。どうして此のような事になったのか。
●
「瘴気――とでもいうべきかな、これは」
「シンカイ殿……余所見をしている場合ではないぞ」
命を受けた朱夏が、使者を名乗る鬼の情報を元に少数の手勢を連れて天ノ都を出て、時を惜しみ馬を潰すのも辞さずに進んでいくと、瞬く間に風景が変わっていっていた。見慣れた東方の森は薄墨のような靄を伴う陰鬱な魔境に転じ、妖怪でこそないものの魔獣の姿が目立つようになった。遮るものは切り捨て、打ち倒しながら、一同は伝えられた内容どおりに目印を辿って進んでいった。
――にんげんだ!
最初に朱夏達に気づいたは幼い鬼だった。年の頃は解らない。人間ならば十は超えそうな身体つきだが、言葉の幼さは気になった。
「いやはや、斯様な所でも人は住めるのだと、関心してな」
案内されながら、軽い調子でそういう武僧シンカイは朱夏が頼み込んで同道してもらっていた。かつて戦場で鬼達を目にしており、かつ、他所で現れた屍鬼を弔ったのだと耳にしていたからだ。
「……人ではない」
それでも、短く吐き捨ててしまう自分を、止められなかった。命令とは言え、朱夏自身が承服しかねているのだった。
鬼たちに、手を伸べる、ということを。
「それはいかん、朱夏殿。お主は使者で、これは主命、そうであろう?」
「……」
深く、息を吐く。部下達に気取られぬような細やかなやり取りではあったが、淀んだ澱は自分一人ではどうしようもなかった。そのために、有り体に言えば憂さ晴らしも兼ねてシンカイを喚んだのは、どうやら奏功しそうであった。
「そうだな」
部下の手前もある。毅然とした態度で事に臨もう、と決めていた。
の、だが。
「…………有難い」
深く、深く下げられた頭に、朱夏は言葉を失っていた。目の前の赤鬼――アカシラの苛烈さは伝え聞いていた。こちらを警戒させぬためか、一切の武装を放棄して朱夏の前に現れたアカシラは、すぐに跪き、手をついてその角の生えた額を地につけたのだった。
「朱夏殿」
「……っ」
「どうやら、話は早く済みそうだ」
シンカイの耳打ちに、思考が巡る。アカシラは、解っているのだろう。自らの立場も、今回朱夏達が訪れた意味も――そして、これからのことも。
それ以上の謝意を見せるには彼女たちは、余りに困窮していた。歓待することなど、出来ようもない。
「アカシラ殿。そなたが我らに頭を下げた所で、そなたらが奪った命は、もう戻らぬ」
「ああ」
使者として極めて未熟な事だと我ながら思うが、朱夏は憤慨していたのだった。だが、今のやり取りで、他の如何なる言葉も、意味などあるまいと思い知った。
赦す事は、出来そうにもなかった。だから、朱夏は任を果たす事だけに専心することとした。
「…………我々は、スメラギ様の意思で此方に参った」
元より、荷は多くは無かったのだろう。そして、鬼達も来るべき時に備えていた為か里を発つ事にさして時間はかからなかった。鬼の事情を鑑みると、不用心に過ぎる。手際よく指示を飛ばすアカシラにシンカイが問うと、
「監視の妖怪が、死んだと聞いたのさ。実際探らせると、姿が消えていた」
「誰からだ?」
「西の妖怪だ」
そんな答えが返った。アカシラ自身の苦い表情には、綱渡りに対する忸怩たる想いが見て取れた。
「早く、機会が来るとよいのだが」
「……あァ、心底、そう願うぜ」
シンカイは慰撫するような言葉に、深く頭を垂れたアカシラの苦笑の吐息は、大気に溶けるように消えていった。
――存外、その機が早く巡ることになろうとは、その場の誰も知らなかったのだが。
里を出た彼らが天ノ都へと向かうその道中で、砦へと向かう妖怪達の一団を見つけたのはあるいは僥倖だったのかもしれない。飛び出していったアカシラ達に引き回されながら、朱夏は己の不運を嘆くばかりであった。しかし、絶望的な戦場に身を置く小高砦においては、その限りではなかったことだろう。
滅びに瀕する東方人類と、状況は極めて近しい鬼達は、曲がりなりにも手を取り合うこととなる。
決して平らかな道行きではあるまいが、それでも。西方人類、ハンター達が刻んできた戦果が、少しずつ結実しようとしていた。
さて。山本五郎左衛門が歪虚要塞ヨモツヘグリを伴い天の都を強襲したことは記憶に新しい。その戦禍はまざまざと都に刻まれたまま、現在に至っている。
――その中で、一人の『鬼』が使者となり、投降を告げたことを知る者は多くはないだろう。
戦乱の只中、鬼の死体に扮した鬼はハンター達に自らの目的と共に、彼らの過去を語った。
鬼、曰く。
妖怪たちの侵攻の中で、彼らが居た国もまた滅びを迎えた。エトファリカ連邦に属することも、結界の恩恵を受ける事もなく。
魔刀を振るう赤鬼アカシラを筆頭に残る鬼達も、かつてはそこにいた。今でこそ彼ら一党を率いるのはアカシラだが、当時は違った。
その青鬼の名を、アクロという。アクロは知恵と人徳で鬼達を導き、彼ら自身の里だけでなく、周囲の人類を護りながら暮らしていた。運命を共にする者達だ、と。互いに補い合いながらの防戦であった。
そのアクロ達の戦振りが目についたわけでもなかろうが、徐々に戦えぬ者が増えていき、盾たる彼らは摩耗し――人類は自らの領土に篭もった結果、鬼達は孤立した。
そのまま、鬼達は滅びを迎えていた筈だった。妖怪の主が、気紛れで手を伸べなければ。
――紆余曲折はあったものの、最終的にアクロはそれを受け容れた。彼を慕ってついてきた鬼達の、延命のために。
鬼達の運命を妖怪に預けたわけではなかった。ただ、人間達は助けには来なかった。
妖怪の手先に成り下がった鬼達は戦線を転々としていたが――その手緩さを攻められ、歪虚に成る事を強いられた。
後のことをアカシラに頼み、「人を恨むな、機を待て」と言い残して、アクロは「悪路王」になった。
西方人類がこの地を訪れるまでの間、悪路王と鬼達は、各地の国を攻め滅ぼし、数々の武門を討ち果たしてきた。
そのことは、人類の『生き残り』達が語ることと同じだった。鬼達は、妖怪たちの監視を受けながら、人類の敵として生きてきた。
今日、この時まで。
●
|
滔々と過去を語り、鬼の助命を願う鬼の使者――ヒラツが、立花院紫草(kz0126)の合図で退室させられた後で、スメラギは苛立たしげに舌打ちをこぼした。 「……いやいやいやいや」 だらしなく胡座をかいたままだが、不機嫌そうに言い捨てる。 「散々手を焼かせてきて、何なら都まで焼いてこれかよ、えェ?」 「――スメラギ様。各国の代表の前です」 「わぁーってるよクソッタレ! ……あー。あーもう。めんどくせェェェ……」 紫草の言にスメラギはもう一度舌打ちをすると頭をガリガリと掻き、しばし考え込んだ。 「事情は、ある……かもしんねーけどよ。あいつらのせいで何人死んだ? どれだけのモンが燃えたよ。はいそーですか、で赦せるわけがねぇ」 「そうですね。民間人にまで、被害は出ていますから……」 「そうでなくても、だ。武門にだって、兵にだって亡国の奴らは少なくねえ。それこそ、あいつらに滅ぼされたトコロだってあんだろーが……」 そこまで言って、スメラギは半眼を開いた。その場に居並ぶ面々を順に追っていく。 バタルトゥ・オイマト(kz0023)。沈思するように腕を組み目を閉じている。 ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)はこちらに目を合わせて、愉しげに口の端に笑みを浮かべている。 そして――。 システィーナ・グラハム(kz0020)は、案の定、その瞳に哀切を滲ませて、 「で、も……」 と、言った。スメラギの苛立ちが跳ね上がる。分かっていた。分かっていたのだ。システィーナがそう言うであろうことは。この甘たれ王女のアホさ加減はいい加減骨身に沁みていた。 けれど。 ――俺がワザワザ説明してやってんのになんでまたそー言えるんだよ……ッ!! 「……あの、何とかなりませんか……?」 スメラギの憤怒の一切を無視して、システィーナは話し続ける。 「私には、ヒラツさまが嘘を付いているとは、思えません。アクロさまが悪路王となってしまったのは、そして、鬼達が歪虚に与することになったのは、全て歪虚のせいなのに……それを彼らの罪だと言い切って見殺しにしてしまうのは……」 「じゃあなんだ。飢えで人を殺した人間は罪人じゃねえってのか。そんな理屈で誰が納得するんだよ」 「それは違います!」 努めて冷たく言い放つスメラギに、システィーナは頭を振った。 「その罪人を飢えさせたのは、一体、誰なのですか」 「……っ」 弱々しくも、確かな口ぶりで、続ける。 「彼らは、贖うつもりがあるのではないですか? 私達が赦さなかったら、一体他に誰が彼らを救えるんですか! 誰が、あの人達に……」 「……システィーナ王女。これは、東方の問題だ。内政に……干渉するべきでは、ない……」 それまで押し黙っていたバタルトゥが、システィーナの言葉を遮った。その事に、正直なところスメラギは驚いていた。寡黙なこの男が、このような場で釘を刺すとは思っても居なかったからだ。 「でも!」 「……優先すべきは、他に、あるだろう。今、鬼達に割く余力は、ない……」 「――っ」 だが、続く言葉で納得できた。オイマトは、あくまでも東方を救うためにこの場にいる。なればこそ、優先すべきは他にあるのだから。 見れば、言葉を詰まらせるシスティーナには疲労の影が濃い。風の噂程度にしかスメラギは知らないが、王国も争乱に巻き込まれつつあるという。その中で王国と東方を行き来するのは、覚醒者ならぬ彼女にとっては決して楽な事ではない。 追い打ちをかけるようで気が引けたが、スメラギが結論を述べようとした。そこに。 「実際のところ、どうだろうな」 それまで愉しげに見守っていたヴィルヘルミナの視線が、スメラギに突き刺さる。 「あ?」 試すような目つきに、睨み返すスメラギにヴィルヘルミナは笑みを深める。 「鬼達は、我らの敵か、否か。どうだ。私達は罠に掛けられようとしていると思うか?」 「ンなのわかんねーよ。推測で決められる問題じゃねぇ」 ただ、と。スメラギは続ける。 |

スメラギ 
立花院紫草 
バタルトゥ・オイマト 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル 
システィーナ・グラハム |
視線を切ったのは、何れも希望的観測に近しいから、か。
「前の天ノ都に、悪路王が来なかったことだ。妖怪たちだって侵入していたのに、アイツは現れなかった。あの時、アイツまで現れてたら今頃俺らは死んでる……かも知れねぇ。ハンターたちもいたからわかんねーが、今更仕掛けるのも変な話だ。罠にしちゃァ杜撰に過ぎる」
雲行きが怪しくなってきたことを感じ、スメラギが不快げにそう結ぶと、ヴィルヘルミナは頷きを返した。
「なら、こちらから条件を出してやればどうだ。それですべての罪が晴れることはないだろうが、過度に罠を警戒しなくてすむ。鬼を自由にして戦場に出てこられるよりはましだろう?」
「……それじゃあ……!」
システィーナの表情が一息に明るくなったことに、スメラギは嘆息した。面白くない。システィーナの甘さも、ヴィルヘルミナの、使えるものは何でも使おうとする器の広さも。
だが、落とし所としては悪くはなかったから――鬼達の元に、使者が送られる事だけは決まった。
「……気ィ重いぜマジで……」
先々に予測される衝突を思い、スメラギは深く息を吐いた。
――決定から、暫し後のこと。
●
|
アカシラは、戦場の只中にいた。魔刀が振るわれる度に分断される”敵”から早々に視線を外して次の得物へと向かう。周囲には絶叫と、鬼達の激情の発露が轟いていた。 呵呵、と。アカシラは嗤った。紅い刀身がその心情に添うように紅蓮の如き光輝を放つ。 「ジン、アンタは手勢を連れて先に砦へ向かいな」 「応!! 暴れすぎるんなよ、姐御!!」 「うるせェ、ちんたらしてねェで速く行きな!」 駆け出す気配を背に、アカシラは踏み込んでいく。 「アカシラ殿……ええい!」 そんな中で響いた少女の声は、幾らか理知的だった。 「ぬしらもあの鬼を追え!」 声を張ったのは『朱夏(kz0116))』。エトファリカ東方連邦の武人。 「害意がないことを知らせるのだ! 後は砦の者が上手く差配する!」 意図を汲んですぐに走りだした部下の背に叩き付けるように朱夏はそう言うと、すぐに戦場へと身を躍らせる。武僧シンカイが深い踏み込みと共に妖怪の身を崩した所に、斬撃を重ねた。 「ちと、数が多いな。どこに向かっておるのだ?」 「小高砦だ」 シンカイの問いにすぐに挙がった名は、現在進行形で九尾の手勢に襲撃を受けている砦だ。シンカイはすぐに察し、片頬を釣り上げる。 「……となるとこ奴らは増援か。くく、運が悪いのか良いのか、分からぬな」 「最悪だ」「上等だよ」 愉しげなシンカイの言葉に朱夏が応じたと同時に、もう一つ、言葉が重なった。アカシラだ。続々と湧いてくる『妖怪』達を前に、獰猛に牙を剥く。紅く長い髪がばらりばらりと揺れる姿は頼もしいが――気を許したわけではない朱夏にとっては、現状は、苦い。寝首を掻かれぬように気を張りながらの交戦など、誰が望もうか。 |

アカシラ 
朱夏 |
「解っている!」
窘めるような、それでいて愉快げなシンカイの声に苛立ちを込めてそう叫ぶと、次なる敵へと踏み込んで言った。
――はて。どうして此のような事になったのか。
●
「瘴気――とでもいうべきかな、これは」
「シンカイ殿……余所見をしている場合ではないぞ」
命を受けた朱夏が、使者を名乗る鬼の情報を元に少数の手勢を連れて天ノ都を出て、時を惜しみ馬を潰すのも辞さずに進んでいくと、瞬く間に風景が変わっていっていた。見慣れた東方の森は薄墨のような靄を伴う陰鬱な魔境に転じ、妖怪でこそないものの魔獣の姿が目立つようになった。遮るものは切り捨て、打ち倒しながら、一同は伝えられた内容どおりに目印を辿って進んでいった。
――にんげんだ!
最初に朱夏達に気づいたは幼い鬼だった。年の頃は解らない。人間ならば十は超えそうな身体つきだが、言葉の幼さは気になった。
「いやはや、斯様な所でも人は住めるのだと、関心してな」
案内されながら、軽い調子でそういう武僧シンカイは朱夏が頼み込んで同道してもらっていた。かつて戦場で鬼達を目にしており、かつ、他所で現れた屍鬼を弔ったのだと耳にしていたからだ。
「……人ではない」
それでも、短く吐き捨ててしまう自分を、止められなかった。命令とは言え、朱夏自身が承服しかねているのだった。
鬼たちに、手を伸べる、ということを。
「それはいかん、朱夏殿。お主は使者で、これは主命、そうであろう?」
「……」
深く、息を吐く。部下達に気取られぬような細やかなやり取りではあったが、淀んだ澱は自分一人ではどうしようもなかった。そのために、有り体に言えば憂さ晴らしも兼ねてシンカイを喚んだのは、どうやら奏功しそうであった。
「そうだな」
部下の手前もある。毅然とした態度で事に臨もう、と決めていた。
の、だが。
「…………有難い」
深く、深く下げられた頭に、朱夏は言葉を失っていた。目の前の赤鬼――アカシラの苛烈さは伝え聞いていた。こちらを警戒させぬためか、一切の武装を放棄して朱夏の前に現れたアカシラは、すぐに跪き、手をついてその角の生えた額を地につけたのだった。
「朱夏殿」
「……っ」
「どうやら、話は早く済みそうだ」
シンカイの耳打ちに、思考が巡る。アカシラは、解っているのだろう。自らの立場も、今回朱夏達が訪れた意味も――そして、これからのことも。
それ以上の謝意を見せるには彼女たちは、余りに困窮していた。歓待することなど、出来ようもない。
「アカシラ殿。そなたが我らに頭を下げた所で、そなたらが奪った命は、もう戻らぬ」
「ああ」
使者として極めて未熟な事だと我ながら思うが、朱夏は憤慨していたのだった。だが、今のやり取りで、他の如何なる言葉も、意味などあるまいと思い知った。
赦す事は、出来そうにもなかった。だから、朱夏は任を果たす事だけに専心することとした。
「…………我々は、スメラギ様の意思で此方に参った」
元より、荷は多くは無かったのだろう。そして、鬼達も来るべき時に備えていた為か里を発つ事にさして時間はかからなかった。鬼の事情を鑑みると、不用心に過ぎる。手際よく指示を飛ばすアカシラにシンカイが問うと、
「監視の妖怪が、死んだと聞いたのさ。実際探らせると、姿が消えていた」
「誰からだ?」
「西の妖怪だ」
そんな答えが返った。アカシラ自身の苦い表情には、綱渡りに対する忸怩たる想いが見て取れた。
「早く、機会が来るとよいのだが」
「……あァ、心底、そう願うぜ」
シンカイは慰撫するような言葉に、深く頭を垂れたアカシラの苦笑の吐息は、大気に溶けるように消えていった。
――存外、その機が早く巡ることになろうとは、その場の誰も知らなかったのだが。
里を出た彼らが天ノ都へと向かうその道中で、砦へと向かう妖怪達の一団を見つけたのはあるいは僥倖だったのかもしれない。飛び出していったアカシラ達に引き回されながら、朱夏は己の不運を嘆くばかりであった。しかし、絶望的な戦場に身を置く小高砦においては、その限りではなかったことだろう。
滅びに瀕する東方人類と、状況は極めて近しい鬼達は、曲がりなりにも手を取り合うこととなる。
決して平らかな道行きではあるまいが、それでも。西方人類、ハンター達が刻んできた戦果が、少しずつ結実しようとしていた。
(執筆:ムジカ・トラス)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●異邦人”(8月10日公開)
冒険都市リゼリオ。異世界艦サルヴァトーレ・ロッソが停泊するこの町は多くのハンター達の活動拠点となっている。
オフィスには大々的に東方における九尾との決戦が告知され、援軍を求める声が止まない。
「歪虚王だってよ……」
「歴史上誰も倒したことないんだろ? 無理じゃね?」
「でも勝てば英雄だぜ?」
チラシを手に話し込むハンター達。一方、それを遠巻きに眺め怯える者達も居た。
「最強の七体に含まれる敵らしいじゃないか……」
「勝てるわけがない……無駄死するだけだ」
「東方を滅ぼしたら、次はこの西方に来るんじゃ……」
既に東方へ向かった第一陣が今戦場でどうなっているのかもわからない。
歪虚王の力は国家を屠り尚余りあるという。当然、ここで手引きしたハンターの一部は既に……。
そんな時だ。ハンターの一部が俄に騒ぎ出したのは。
彼らの視線を追いかけ、ミリアも驚いた。そこに立っていたのはここにいる筈のない少女の姿。
「それができたのなら、どれだけよかったでしょう。けれどわたくしは……弱く。力がないから、こうしてお願いする事しかできずにいます」
目を瞑り、少女は深く頭を下げた。それにはハンター達もどよめく。
一国の王女である。気安く下げるような頭ではない。しかしヴィオラはそれを咎めず、共に頭を下げた。
「わたくしの事は、どう仰られても構いません。それでも……どうか、お力をお貸し下さい。それでもわたくしは、彼らを救いたいのです……!」
沈黙するハンター達。ふと、そこへ少女のよく抜ける声が響いた。
「あ?あ! 大の大人が寄ってたかってかっこ悪いったらありゃしないよね!」
振り返るハンター達の視線の先、仁王立ちする少女の姿があった。
「うん。俺もハンターの皆に呼びかけようと思って。まさか王女様が先に来てるとは予想外だったけど」
篠原 神薙(kz0001)の腕の中で僅かに身動ぎするシスティーナ。ヴィオラにそれを預けると、神薙はハンターを見渡し。
「俺は実際に九尾を見てきたよ。遠目に見てもあれはバケモノだ。だけど俺は見てきたんだ。九尾に立ち向かう人々の姿を。仲間であるハンター達の姿を……」
戦場では多くの血が流れていく。歪虚との戦いは元々酸鼻なものだが、今回はこれまで以上の被害が出るだろう。
「だけど……立ち向かわなければ被害は増える一方なんだ。それに、これは他人事じゃないんだよ。東方を滅ぼせば九尾はきっとここにもやってくる」
わかっている。この世界に生きる以上、逃げ場などないのだと。
「確かに、この戦いで人が一丸となるなんて綺麗事なのかもしれない。人は今でも互いに足を引っ張り合ったり、憎みあったりしてる。けど、それが世界のすべてじゃないと俺は思うんだ」
リアルブルーからの転移者がこのクリムゾンウェストで生きていくように。
人々が力を合わせ聖地を奪還したように。東方と西方の人々が今手を取り合おうとしている事には、きっと意味があるのだと信じたい。
「“完璧”な世界なんてない。だからって諦めて手を打たなければ何も変わらない。すべての人が一つになるのが今は不可能だとしても、今できるだけの力を合わせる事が未来に繋がっていくんだ」
「……なんかカナギの言ってるのは難しくて良くわかんないけどさ。こんなカワイイお姫様にお願いされて盛り上がらないって、冒険者としておかしいと思うよ!」
「……えっと、ラキさん……?」
「だってそうでしょ? この特別な力は、間違いなく誰かを救う為にあるんだよ。戦いたくても戦えない人の代わりに、私達が立ち上がらなくてどうするの?」
ハンター達は皆、それぞれの理由を抱えている。
なりたくてハンターになったわけではない……そういった者も少なくはないだろう。
中立の立場として、これまで各国にいいように使われてきた。危険な戦場にばかり送り込まれ、戦いが終われば世界は元通り。
痛みから調和を学ぼうとしない人間達を誰より見つめてきたのも、きっとハンターなのだ。
「……第二次作戦の開始はいつからだ?」
一人の男がそう言ってミリアから依頼書を受け取る。
するとそれに続くように、次々にハンター達が依頼書を手にオフィスを飛び出していく。
「勘違いするなよガキ共。俺達は世界を救いに行くんじゃない」
「ああ、そうだ。仲間であるハンターを見殺しにしたくないだけだ」
頬を掻き苦笑を浮かべる神薙。ラキはそんな少年の手を取り。
「あたし達も行こう! 自分の手で世界を変えるんでしょ?」
「――ああ! ヴィオラさんすみません、先に行きます!」
去っていく二人の姿を見送り、ヴィオラはふっと笑みを浮かべる。
「少し見ない間に、逞しくなりましたね」
「ん……う……」
腕の中で身じろぐ少女に小さく溜息を零し。
「まったく……無茶が過ぎます。しかし……良く頑張りましたね」
慌てた様子でオフィスのスタッフが駆け寄り、システィーナを介抱する。
柔らかいソファの上に少女を横たわらせ、ヴィオラは振り返り遠く東の空を見る。
「私も急がなくては」
オフィスには大々的に東方における九尾との決戦が告知され、援軍を求める声が止まない。
「歪虚王だってよ……」
「歴史上誰も倒したことないんだろ? 無理じゃね?」
「でも勝てば英雄だぜ?」
チラシを手に話し込むハンター達。一方、それを遠巻きに眺め怯える者達も居た。
「最強の七体に含まれる敵らしいじゃないか……」
「勝てるわけがない……無駄死するだけだ」
「東方を滅ぼしたら、次はこの西方に来るんじゃ……」
|
作戦参加者の募集に声を張り上げていたミリア・クロスフィールド(kz0012)も思わず視線を落とす。 皆わかっているのだ。これが嘗てないほど絶望的な戦いになるという事が。 そして今ハンター達を戦場に送り出す事は、彼らの死を強いているのと何も変わらないという事も……。 「流石に尻込みしてるねぇ」 「当然ですよ……相手が相手ですから。私も正直、辛くて……」 恰幅の良いベテラン受付嬢がそっとミリアの肩を叩く。 「ミリアちゃん、あたし達が笑顔でハンターを見送ってやらずにどうするんだい」 「でも……」 |

ミリア・クロスフィールド |
歪虚王の力は国家を屠り尚余りあるという。当然、ここで手引きしたハンターの一部は既に……。
そんな時だ。ハンターの一部が俄に騒ぎ出したのは。
彼らの視線を追いかけ、ミリアも驚いた。そこに立っていたのはここにいる筈のない少女の姿。
|
「おい……システィーナ様だ」 ヴィオラ・フルブライト(kz0007)に支えられ、ふらつくような足取りでシスティーナ・グラハム(kz0020)はそこに立っていた。 「……突然の訪問、お騒がせして申し訳ありません。今日は皆さんに、お願いがあって参りました」 肩で息をし、整え、少女はまっすぐに立ち、集まったハンター一人一人の目を見つめ。 「今、エトファリカ連邦国の首都、天ノ都では歪虚王九尾との戦いが繰り広げられています。旗色は……とても悪く。戦力が足りていない状況です。どうか……どうか、皆さんのお力をお借りできないでしょうか?」 顔を見合わせるハンター達。そこまで……一国の王女が直接願い出る程までに、状況は悪いのか。 「こうしている今この瞬間も、東方ではヴィルヘルミナ様やオイマト様、皆さんのお仲間である大勢のハンターが命を賭して戦っています。彼らの命を救う為に、何卒……」 「……頼むだけならいいよな、簡単で」 誰かがそう呟くと、それが口火を切ってどよめきが広がっていく。 「行ったら死ぬんだぜ。あんなバケモノ……死ねって言ってるのと同じだろ」 「どこの国も自前の問題ばかりで、ややこしい相手は俺達に押し付けるのかよ」 「そんなに戦力が欲しければ自分達で戦えばいいだろ?」 心ない言葉に視線を鋭くするヴィオラ。しかしシスティーナは片手で制し。 「仰る通りです。もしも……もしもわたくしが、この手に剣を取り……」 ――あの人のように、戦えたなら。 |

システィーナ・グラハム 
ヴィオラ・フルブライト |
目を瞑り、少女は深く頭を下げた。それにはハンター達もどよめく。
一国の王女である。気安く下げるような頭ではない。しかしヴィオラはそれを咎めず、共に頭を下げた。
「わたくしの事は、どう仰られても構いません。それでも……どうか、お力をお貸し下さい。それでもわたくしは、彼らを救いたいのです……!」
沈黙するハンター達。ふと、そこへ少女のよく抜ける声が響いた。
「あ?あ! 大の大人が寄ってたかってかっこ悪いったらありゃしないよね!」
振り返るハンター達の視線の先、仁王立ちする少女の姿があった。
|
「ラキ……」 「あのさー、システィーナ……様は覚醒者じゃないんだよ? 転移門であちこち行くのにどんだけ疲れるのか皆知らないワケ?」 そう。非覚醒者の転移門使用は大幅に体力を消耗する。無理をすればそれこそ命に係る事だ。 「それでも命懸けでここに来たんだよ。自分の為じゃない。東方で戦ってる人の為に……。それを皆してイジメてさぁ。恥ずかしくないわけ?」 「そう言うのだったらお前は行くんだろうな、ラキ?」 「うん、行くけど?」 あっけらかんと言い放ち、少女はシスティーナの隣に並ぶ。 「はい、一番乗り。参加しないのにブツブツ言ってるだけの人はもうどっか行ってよ。邪魔だからさ」 「て、てめぇ……っ」 「止せ。時間の無駄だ……行くぞ」 こうして何人かのハンターはオフィスを後にしていく。その後姿に“あっかんべー”するラキ(kz0002)に、システィーナは目を細め。 「ありがとうございます、ラキさん……」 「いーのいーの、ヤな奴の事なんか気にしないで。それより凄く顔色悪いよ? 少し横になった方が……あっ!」 ふっと、視線が空へ向き、システィーナの身体が大きく傾く。 その瞬間横から差し伸べられた手が優しく少女を抱き留めた。 「……カナギ! 東方から戻ってきてたの?」 |

ラキ 
篠原 神薙 |
篠原 神薙(kz0001)の腕の中で僅かに身動ぎするシスティーナ。ヴィオラにそれを預けると、神薙はハンターを見渡し。
「俺は実際に九尾を見てきたよ。遠目に見てもあれはバケモノだ。だけど俺は見てきたんだ。九尾に立ち向かう人々の姿を。仲間であるハンター達の姿を……」
戦場では多くの血が流れていく。歪虚との戦いは元々酸鼻なものだが、今回はこれまで以上の被害が出るだろう。
「だけど……立ち向かわなければ被害は増える一方なんだ。それに、これは他人事じゃないんだよ。東方を滅ぼせば九尾はきっとここにもやってくる」
わかっている。この世界に生きる以上、逃げ場などないのだと。
「確かに、この戦いで人が一丸となるなんて綺麗事なのかもしれない。人は今でも互いに足を引っ張り合ったり、憎みあったりしてる。けど、それが世界のすべてじゃないと俺は思うんだ」
リアルブルーからの転移者がこのクリムゾンウェストで生きていくように。
人々が力を合わせ聖地を奪還したように。東方と西方の人々が今手を取り合おうとしている事には、きっと意味があるのだと信じたい。
「“完璧”な世界なんてない。だからって諦めて手を打たなければ何も変わらない。すべての人が一つになるのが今は不可能だとしても、今できるだけの力を合わせる事が未来に繋がっていくんだ」
「……なんかカナギの言ってるのは難しくて良くわかんないけどさ。こんなカワイイお姫様にお願いされて盛り上がらないって、冒険者としておかしいと思うよ!」
「……えっと、ラキさん……?」
「だってそうでしょ? この特別な力は、間違いなく誰かを救う為にあるんだよ。戦いたくても戦えない人の代わりに、私達が立ち上がらなくてどうするの?」
ハンター達は皆、それぞれの理由を抱えている。
なりたくてハンターになったわけではない……そういった者も少なくはないだろう。
中立の立場として、これまで各国にいいように使われてきた。危険な戦場にばかり送り込まれ、戦いが終われば世界は元通り。
痛みから調和を学ぼうとしない人間達を誰より見つめてきたのも、きっとハンターなのだ。
「……第二次作戦の開始はいつからだ?」
一人の男がそう言ってミリアから依頼書を受け取る。
するとそれに続くように、次々にハンター達が依頼書を手にオフィスを飛び出していく。
「勘違いするなよガキ共。俺達は世界を救いに行くんじゃない」
「ああ、そうだ。仲間であるハンターを見殺しにしたくないだけだ」
頬を掻き苦笑を浮かべる神薙。ラキはそんな少年の手を取り。
「あたし達も行こう! 自分の手で世界を変えるんでしょ?」
「――ああ! ヴィオラさんすみません、先に行きます!」
去っていく二人の姿を見送り、ヴィオラはふっと笑みを浮かべる。
「少し見ない間に、逞しくなりましたね」
「ん……う……」
腕の中で身じろぐ少女に小さく溜息を零し。
「まったく……無茶が過ぎます。しかし……良く頑張りましたね」
慌てた様子でオフィスのスタッフが駆け寄り、システィーナを介抱する。
柔らかいソファの上に少女を横たわらせ、ヴィオラは振り返り遠く東の空を見る。
「私も急がなくては」
|
「――結局、ボク達は見ているだけですか♪」 サルヴァトーレ・ロッソの艦長室。壁を背にしたジョン・スミス(kz0004)が呟く。 「東方へは転移門を使わねば移動できないと聞く。CAMが出せない以上、俺達の出る幕はないよ」 「それ、欺瞞ですよねぇ。ボクには戦わない為の言い訳にしか聞こえませんよ」 「そう言ってくれるなよ。俺だってそう思ってるんだから」 資料から顔を上げたクリストファー・マーティン(kz0019)が溜息を零す。 二人の視線は自然と艦長であるダニエル・ラーゲンベック(kz0024)へと向いた。 「俺達は東方での戦いに関与しない。それは決定事項だ」 「サルヴァトーレ・ロッソ。飛ばせればCAMも魔導アーマーも軽々運べるんじゃないですか?」 「動力や燃料の問題は、魔導型CAMの技術を艦の主機関にも適用すれば、解決の可能性はありますよね?」 帽子を目深に被り、ダニエルは沈黙する。 「あ?あ?可哀想♪ こんなにすごい兵器があるのに、見殺しだなんて♪」 「世界を救うためにVOIDと戦うと誓い、救世主の名を与えられた艦がじっとしているだけというのは……」 「……でぇい、うるせえぞ! 事はそんな単純じゃねぇんだ、わかってんだろ!」 ダニエルの怒号に二人の口がピタリと閉じる。 そう、事は単純ではないのだ。もちろんジョンもクリストファーも理解している。 「こいつにはLH044の難民を始めとした非戦闘員が山程乗っている。中には異世界に適応できず閉じこもってる奴も多い。そんな連中を抱えて戦場を飛べるかよ」 「一年間もこっちにいるのに、まだ適応できないんですかねぇ」 「……仕方ないさ。あんな事件があったんだ。VOIDが怖くて当然だよ」 救済の為に作られた艦が塩水に浸ってはや一年。 救わない言い訳を考えて自分達を偽り続ける事にも、いい加減辟易していた。 だがそれが、大勢の移民とリアルブルーの決戦兵器であるサルヴァトーレ・ロッソを預かった者の責任であり。 この異世界のパワーバランスを崩さない為の、異邦人の責任でもあったのだ。 |

ジョン・スミス 
クリストファー・マーティン 
ダニエル・ラーゲンベック |
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●“新たな結界を”(8月11日公開)
――四神結界により、天ノ都には僅かな静寂が訪れていた。
都が憤怒の軍勢に包囲されている事実には何も変わらず。九尾の影響で結界が崩壊するまで一日とかからないだろう。
負傷兵で埋め尽くされた城下町からは絶望と怨嗟の声が絶え間なく響き。東方は今、滅びの最中にあった。
(親父……)
父の世代は絶望の最中、一切の救いもなく死んでいった。
辺境の友を信じ。西方の援軍は必ず来る。最後までそう言って、希望と共に少年の手を握り締め、男は命を落とした。
役割と共に背負わされたその希望を疎ましく思った。けれど今は違う。
(親父の言ってた事は正しかったぜ。希望はあったんだ。ちゃんと俺達にも……仲間はいたんだぜ)
目には見えない不確かなモノ。愛や友情、祈りや願い、希望……。
人はそれを信じて生きていく。今それが成就せずとも、いつかきっと、未来に繋がると信じて。
それはきっと呪いだ。しかしスメラギは今はそれを愛しく思う。
(俺……頑張ったよな? やれる事は全部やったよ。諦めなかったよ。今なら認めてくれるかな……親父……)
そっと幻に伸ばした手。大きな背中がゆっくりと振り返ろうとした、その時。
「――スメラギサン!」
しなやかな手が身体を支えていた。そして急速に意識が回復していく。
隣には何故か見知らぬ少女が立っていて、少し苦しげに微笑んでいる。
直ぐに分かった。彼女が自分に集中する筈の結界の負担を受け持ってくれているのだと。
「あまねくすべての人々を救う……エクラの教えはこの東方に置いても健在です。専門は違えど一流の術師ばかり。何かお手伝いできる事があるかと」
「これだけの人数が居れば、結界を強化できると思うが……」
「ワタシ達、辺境の巫女が仲介役になりマス。負担をそれぞれで分担すれば、出力が上がりまセンか?」
頷くスメラギ。だがしかし彼はまだこの状況をどこか信じられずにいた。
「こんなタイミングでお前らみたいな腕利きが揃うって、そんな奇跡みたいな事があんのかよ……?」
「奇跡ではありませんよ」
「ハイ。我々はずっと呼びかけを受けてマシタ」
ヴィオラは国内の問題の処理に、そしてリムネラは東方との転移門の安定化にこれまで手間取ってきた。
しかしようやくそれらを他の担当者にパスし、ここに駆けつける準備が整ったのだ。
「システィーナ様が各国の王に頼み込み、伝手を頼ったのです」
「王女殿下のお手紙、私も受け取りマシタ。トッテモ一生懸命……。あなたの事、助けたいって気持ちがイッパイでシタ」
優しく笑いかけるリムネラ。その瞳に映る自分の姿を見て、スメラギは初めて自分が泣いている事に気づく。
「俺……皆に助けられてばっかりだ。ありがとう……本当に、申し訳ねぇ……」
「スメラギサン、とっても頑張りマシタ。謝ることはナンニモありまセン」
「あなたは王としての責務を十分に果たしています。胸を張って良いのですよ」
涙を拭い頷く。諦めなくてよかった。諦めを超えたからこそ、僅かな希望を繋ぐ事ができたのだから。
あまりにも無茶苦茶な提案だが、それくらいの無茶は通せなければ奇跡は起こせない。
それぞれが頷き、近くに集まる。残された時間はあと僅か。
未来を変える為の前哨戦は、夜の帳の中、静かに開始されようとしていた。
都が憤怒の軍勢に包囲されている事実には何も変わらず。九尾の影響で結界が崩壊するまで一日とかからないだろう。
負傷兵で埋め尽くされた城下町からは絶望と怨嗟の声が絶え間なく響き。東方は今、滅びの最中にあった。
|
朦朧とした意識の中、スメラギはただ只管に結界の維持に注力する。最早他にできる事は何もなかった。 (あれから何分……いや、何時間経ったんだ……) 夜明けは遠い。結界維持で身体を貫くような激しい痛みは既に消え、肉体の感覚が薄まっていくのを感じる。 ふわふわと空に浮いているような、或いは夢の中にいるような。そんな中、少年は静かに目を閉じた。 自らの心音がまだ聞こえる。まだ自分は生きていると感じられる。 しかし眼前には果てしない空白が広がり、肉体の枷を失った意識は孤独にそこを彷徨うばかりだ。 (俺……死ぬのか) 直感的にそう感じた。ならこれは死後の世界なのかもしれない。 遠くに見知った背中が見えた。大きくて、強くて、少しだけ忌々しかった父の背中だ。 |

スメラギ |
父の世代は絶望の最中、一切の救いもなく死んでいった。
辺境の友を信じ。西方の援軍は必ず来る。最後までそう言って、希望と共に少年の手を握り締め、男は命を落とした。
役割と共に背負わされたその希望を疎ましく思った。けれど今は違う。
(親父の言ってた事は正しかったぜ。希望はあったんだ。ちゃんと俺達にも……仲間はいたんだぜ)
目には見えない不確かなモノ。愛や友情、祈りや願い、希望……。
人はそれを信じて生きていく。今それが成就せずとも、いつかきっと、未来に繋がると信じて。
それはきっと呪いだ。しかしスメラギは今はそれを愛しく思う。
(俺……頑張ったよな? やれる事は全部やったよ。諦めなかったよ。今なら認めてくれるかな……親父……)
そっと幻に伸ばした手。大きな背中がゆっくりと振り返ろうとした、その時。
「――スメラギサン!」
しなやかな手が身体を支えていた。そして急速に意識が回復していく。
隣には何故か見知らぬ少女が立っていて、少し苦しげに微笑んでいる。
直ぐに分かった。彼女が自分に集中する筈の結界の負担を受け持ってくれているのだと。
|
「お前は……?」 「遅くなってゴメンナサイ。私はリムネラ……辺境の、白龍の巫女デス」 肩に乗った小さな白龍、ヘレが小さく鳴き声を上げる。 「思った通り、黒龍様のマテリアルは白龍様とそっくりデス。私達白龍様にお仕えした巫女なら、直ぐに順応できマス……!」 そう、やってきたのはリムネラ(kz0018)だけではない。辺境の巫女達はそれぞれ東方の術者を支えようとしていた。 「結界を立て直しマス。スメラギサン、私に同調できマスか?」 「……俺様を誰だと思ってんだ!」 笑みを作り、スメラギはリムネラと繋いだ手に意識を集中する。 四神結界の負担は、少なくとも術者においては大きく減少した。単純に分散されただけだが、これで少しは持続時間が伸びるだろう。 「ウッ……スメラギサン、ずっとこんな術の反動に耐えてたんデスね……」 「リムネラ……だったか? お前ら一体どうして……?」 「各国の王から要請があったのです。結界術、そして浄化術のプロフェッショナルを集めるようにと」 質問に答えたのはリムネラではなかった。ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は聖堂教会の術師を引き連れ、スメラギの側に並び立つ。 「エクラ神にお仕えする聖堂教会も微力ながらお力添えを……。本当は法術専門のオーランを連れて来たかったのですが、彼はやや性格に難がありまして……」 遠い目で呟いた後、気持ちを切り替えるようにヴィオラはスメラギと向き合う。 |

リムネラ 
ヴィオラ・フルブライト |
「これだけの人数が居れば、結界を強化できると思うが……」
「ワタシ達、辺境の巫女が仲介役になりマス。負担をそれぞれで分担すれば、出力が上がりまセンか?」
頷くスメラギ。だがしかし彼はまだこの状況をどこか信じられずにいた。
「こんなタイミングでお前らみたいな腕利きが揃うって、そんな奇跡みたいな事があんのかよ……?」
「奇跡ではありませんよ」
「ハイ。我々はずっと呼びかけを受けてマシタ」
ヴィオラは国内の問題の処理に、そしてリムネラは東方との転移門の安定化にこれまで手間取ってきた。
しかしようやくそれらを他の担当者にパスし、ここに駆けつける準備が整ったのだ。
「システィーナ様が各国の王に頼み込み、伝手を頼ったのです」
「王女殿下のお手紙、私も受け取りマシタ。トッテモ一生懸命……。あなたの事、助けたいって気持ちがイッパイでシタ」
優しく笑いかけるリムネラ。その瞳に映る自分の姿を見て、スメラギは初めて自分が泣いている事に気づく。
「俺……皆に助けられてばっかりだ。ありがとう……本当に、申し訳ねぇ……」
「スメラギサン、とっても頑張りマシタ。謝ることはナンニモありまセン」
「あなたは王としての責務を十分に果たしています。胸を張って良いのですよ」
涙を拭い頷く。諦めなくてよかった。諦めを超えたからこそ、僅かな希望を繋ぐ事ができたのだから。
|
「リムネラ! それにヴィオラも!」 そこへ明るい声が響く。振り返ると、フェンリルに跨ったファリフ・スコール(kz0009)とそれに続く篠原神薙、ラキの姿があった。 「うおっ!? 祭壇に犬で乗り込んでくんな!?」 『犬ではない、フェンリルだ。成る程……どこか懐かしいニオイだ。白龍と同じ力を感じる』 フェンリルから降りたファリフはスメラギ達に駆け寄り。 「遅れてごめんね」 「幻獣を従えたのですか。流石ですね、ファリフ」 ふっとヴィオラが微笑みかけると、ファリフは照れくさそうに鼻頭を擦る。 「いやー、外で久しぶりにカナギ達と話し込んじゃって」 「ヴィオラさんに追いぬかれちゃいましたね。俺達ハンターも援軍を連れてきたよ。皆張り切って決戦に備えてる」 「まだ仲間はいるんだよって伝えたくて、ここまで来ちゃった!」 軽快に笑うラキに神薙は苦笑い。スメラギはそんな二人の姿に息を吐き。 「……ったく、お前らを見てると絶望するのが馬鹿馬鹿しくなってくるぜ」 「これで少しは結界を維持して防衛できるんじゃないかな?」 「――でも、それだけでは勝てない」 顔を見合わせ、また振り返る一同。おとなしく座っているフェンリルの後方、祭壇の入り口に黒いローブを纏った小柄な少女が立っていた。 「結界を強化してもそれは時間稼ぎにしかならない。歪虚王を倒すには、結界術を攻撃に転用しないと」 「誰だ? お前らのツレか?」 同時に首を横に振る一行。しかしもうここに駆けつけそうな面子など思いつかない。 少女は複数の黒ずくめの者達を引き連れ祭壇に立ち入ると、一同の視線の真ん中に立った。 「このクリムゾンウェストで最も攻撃的な結界術のプロフェッショナルとして、高いお金と引き換えにやってきました」 「カンペ読むなカンペ」 冷や汗を流しつつのスメラギの突っ込みに少女はメモをしまい、フードを持ち上げる。 「はじめまして。エルフハイムから来ました。どこでもレンタルずばっと解決、人型術具、浄化の器です」 「……ねぇカナギ、今この子エルフハイムって言った?」 「トッテモ珍しいトコロからデスね?」 「おい、お前らだけで納得してねぇで俺様もまぜろ」 「えーと、俺も詳しくないけど、簡単に言うと……秘境?」 ひそひそ話をする面々を眺め、少女は咳払いを一つ。全員がシャキっと居直る。 『……お嬢ちゃん、いいのか? ソレからは嫌な感じがするぞ』 フェンリルの言う通り、特にスメラギとリムネラは強く感じていた。 目の前の少女は確かに自分たちと同じ分野の技術のプロだろう。だが、その性質は大きく異なるのだと……。 「今は細かいことを気にしている状況ではあるまい。彼の地の結界術は歪虚CAMを葬った実績がある。力になるはずだ」 「「 げっ 」」 更に颯爽と入室したヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)にファリフとラキが同時に声を上げた。 「ヴィルヘルミナさん。怪我はもういいんですか?」 「やあ少年。いつぞやを思い出す面子だが……昔話はまた今度。スメラギ殿、彼女らの力は私が保証する。使ってやってくれ」 どちらにせよ迷っている時間はないし、選り好みしている余裕もない。 「わーったよ。素性はよくわからねーが、力を貸してくれ。策があるんだろ?」 浄化の器(kz0120)と呼ばれる少女は頷くと、懐から木製の木刀のような道具を取り出した。 「時間がないので早速はじめる」 「何を?」 「この場で、この場にいる人達の力を合わせて、新しい結界術を作る。それぞれの技術を重ねあわせて、一晩で」 |

ファリフ・スコール 
篠原 神薙 
ラキ 
浄化の器 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル |
それぞれが頷き、近くに集まる。残された時間はあと僅か。
未来を変える為の前哨戦は、夜の帳の中、静かに開始されようとしていた。
●決戦 歪虚王「獄炎」(8月12日公開)
――水平線に茜色の光が差した。
九尾が暁を待ったのはただの気まぐれだ。放っておいても結界の負担は術者を殺すとわかっていたから。
そして九尾の予想は的中した。朝日が差し込む天ノ都から、四神結界が消失していくのを感じた。
「……九尾様の力を遮ろう等、土台不可能な話。崩壊は時間の問題であったな」
「第三次展開準備完了! スメラギ様!」
「――止まりやがれぇええええッ!!」
血反吐を吐きながら雄叫びを上げるスメラギ。
光の束はまるで巨大な龍の身体のように形を成し、九尾の身体を抑えつける。
それは四神結界の、そしてこの当方の土地と術者の命、黒龍のありったけのマテリアルを込めた、新たな封印の力。
「まさか……動けぬと言うのですか、九尾様……?」
九尾の進軍が停止した事実を確認し、牛鬼は驚愕する。
まったくありえない話だ。だがしかしそれが現実。ならばやるべきことは一つだけ。
「この小さき結界を突き破り、龍尾城の術者を殺す」
いや、そもそも小さな結界を破壊していけば術者は負担に耐え切れず勝手に死に至るだろう。
実になりふり構わない、不安定極まりない捨身の策……。
「……拘束が破られるのは時間の問題。それだけでは何も変わらん」
戦線から離れていた悪路王が戻った事を気にかける歪虚はいなかった。
今はそれどころではないというのもあるが、九尾さえ居れば絶対に敗北はあり得ないという確信があるからだ。
龍尾城から九尾まで、直線上に結界の道が作られるのが見える。
成る程、あれなら九尾の取り巻きに邪魔されず直行できる。九尾を落とし、この戦いを決着させるつもりなのだ。
その僅かばかりの希望を摘み取る為、悪路王は光の道へ向かった。
走り去るファリフの背中にふっと笑い、女は太刀を構える。
「何故だ……何故……! たった一つ守りたかったモノさえ奪われたのか……俺は!」
「アクロ……。そうさ、アタシは……アタシらは裏切った。それを許して欲しいなんて言えない。だけどアクロ……だからこそ、アタシ達が……」
「姐さん、一人で背負わんで下せぇ」
「俺達鬼は一蓮托生……そうでしょう?」
駆けつけた部下の鬼達を背にアカシラはきつく目を瞑り、真っ直ぐに友を見つめる。
「――終わりにしよう、アクロ」
悪路王の力は強大で、その手の内をよく知るアカシラ達でも圧倒して余りある。
雷撃に吹き飛ばされ地べたに転がる鬼達の中、アカシラは息を切らしながら刃を強く握り締めた。
「憎しみを超える……アタシにできるのか、そんな事が」
迷いは消えない。悪路王と刃を交える度、胸の痛みは全身を引き裂くほどだ。
罪を背負って生きる事。覚悟はしていたけれど、それはとても重く。気を抜けば挫けそうになる。
「――アカシラ殿!」
顔を上げると、駆け寄る朱夏の姿が見えた。
「朱夏……アンタ、先に行ったんじゃ」
「……ずっと考えていました。憎しみと向き合う事を。答えは出ません。しかし、ここであなたを失えば、永遠に見つけられないような気がしたのです」
差し伸べられた手を取り立ち上がる。
「共に戦ってくれませんか。もう一度、肩を並べて」
「……ったく、馬鹿野郎が」
嬉しそうに、しかし悲しそうに。アカシラの刃は悪路王に向けられる。
「見えるかアクロ。これがアンタが夢見た未来。だから守るんだ。相手が“今”の……アンタだって!!」
龍尾城にリンドヴルムが突っ込んだと思ったら、何故か二体の暴食の十三魔が中庭でやりあっている。
そんな意味不明な状況に呆れたように上空でガルドブルムが溜息を零した。
『しっかし……ハハ! マジで九尾の動きが止まってやがる。こいつはひょっとすると……ひょっとするのかもしれねェな』
まだ人間達の作戦は中途。これから恐らく九尾を倒せるかどうかという局面に突入するだろう。
もしも九尾が倒されるとしても、人間の力ならば時間がかかる。状況を見守る猶予は十分にある。
『山……なんだったかねェ、あのジイさん。アレでもかなりの力だったんだ。歪虚王の力……得られたのならどんな具合かねェ?』
消失しそうな力の場合、完全な略奪は難しいだろう。だが上手くやれば歪虚王に近づく事が可能かもしれない。
『――そしていずれは、すべての歪虚の頂点へ』
悪くない。悪くない筋書きだ。
雄々しく翼を広げ、ガルドブルムは急行する。目指すは九尾獄炎、憤怒の歪虚王。
フェンリルの背に乗り、そこへ辿り着いたハンター達。その手に握るは結界術の標的を定める“楔”と呼ばれる術具。
「これを九尾に突き刺せばいいんだね!?」
「そう。刺せば刺すだけ、力が伝わりやすくなる。九尾が弱れば、攻撃の機会は巡ってくる」
『なんて強烈な負のマテリアル……側にいるだけで身体が焼けそうだ』
「ごめんねフェンリル……だけどお願い、もっと近くへ!」
『言っただろう、ファリフ。俺はお前のナイトだ。お前の願う場所へ、必ず届けてやる』
不自由な身体を動かし、不快感に九尾が吠える。
その圧倒的な迫力に負けず、幻獣達は強く大地を蹴る。
――歪虚王との決戦が今、幕を開けたのだった。
九尾が暁を待ったのはただの気まぐれだ。放っておいても結界の負担は術者を殺すとわかっていたから。
そして九尾の予想は的中した。朝日が差し込む天ノ都から、四神結界が消失していくのを感じた。
「……九尾様の力を遮ろう等、土台不可能な話。崩壊は時間の問題であったな」
|
憤怒の軍勢の先頭に立ち、牛鬼が呟く。 退屈そうに腰を上げた九尾に呼応するように憤怒の歪虚達が前進を開始。 既に都を守る結界はなく。大量の歪虚が城下町へ雪崩れ込んでいく。だが――。 「……何故だ? 全くの無抵抗とは……?」 絶望し、諦めたのかもしれない。術者が結界に耐え切れず死んだのなら、その静寂も頷ける。 だがそうではないと牛鬼の勘が告げていた。しかし進軍は九尾の命令。逆らう程の事には思えない。 「ん……あれは悪路王か」 振り返り、視界の端に悪路王の姿を捉える牛鬼。 「今更駆け付けるとは……一体どこに行っていたのやら――!?」 その時、大地から沸き上がる光が牛鬼の身体を弾き飛ばした。 何が起きたのか。状況を確認する。結界が再起動した……それはわかる、が。 「既に我らは都に入った後だというのに……?」 「敵集団、城下町に侵入! 第一次結界展開完了!」 「続いて第二次展開用意!」 都をピッタリと覆う光の帯、その内側に無数の帯が浮かび上がる。 巨大な円の内側に作られた無数の結界は、それぞれ歪虚の戦力を隔離していく。 祭壇でスメラギは術師達に指示を出しながら結界を維持していた。 「想定通り、敵戦力の半数近くを城下町に引き込めたようです」 「結界陣、正常に作動してマス!」 ヴィオラ(kz0007)とリムネラ(kz0018)の言葉に頷くスメラギ。 「こっちも無傷で勝てるとは思っちゃいねぇんだよ」 いつまでも自分達を閉じ込めていたこの“檻”。その力で今度は羽ばたいてみせる。 「――閉じ込められて自由を奪われる気分はどうだよ、クソったれ」 「……この程度の事で、何かを変えられたつもりか?」 意にも介さず前進を続ける九尾。その足元から突如、眩い光が立ち昇る。 夜明けの空を白く照らす光はやがて姿形を変え、九尾の身体に強く纏わりついていく。 「ぬ……ぐっ、これは……?」 広範囲を長時間守る為に作っていた結界。その形を、あり方を変えただけの事。 短時間の一点集中。そしてもう、都は守らなくていい。どの道アレを倒せなければすべてが終わる。 力を貸してくれた西方の友人らのお陰で結界の威力は更に増している。負担が分散されれば、更に精密に操作する余力も生まれる。 「馬鹿な……この九尾獄炎を……!?」 |

牛鬼 
悪路王 
スメラギ |
「――止まりやがれぇええええッ!!」
血反吐を吐きながら雄叫びを上げるスメラギ。
光の束はまるで巨大な龍の身体のように形を成し、九尾の身体を抑えつける。
それは四神結界の、そしてこの当方の土地と術者の命、黒龍のありったけのマテリアルを込めた、新たな封印の力。
「まさか……動けぬと言うのですか、九尾様……?」
九尾の進軍が停止した事実を確認し、牛鬼は驚愕する。
まったくありえない話だ。だがしかしそれが現実。ならばやるべきことは一つだけ。
「この小さき結界を突き破り、龍尾城の術者を殺す」
いや、そもそも小さな結界を破壊していけば術者は負担に耐え切れず勝手に死に至るだろう。
実になりふり構わない、不安定極まりない捨身の策……。
「……拘束が破られるのは時間の問題。それだけでは何も変わらん」
戦線から離れていた悪路王が戻った事を気にかける歪虚はいなかった。
今はそれどころではないというのもあるが、九尾さえ居れば絶対に敗北はあり得ないという確信があるからだ。
龍尾城から九尾まで、直線上に結界の道が作られるのが見える。
成る程、あれなら九尾の取り巻きに邪魔されず直行できる。九尾を落とし、この戦いを決着させるつもりなのだ。
その僅かばかりの希望を摘み取る為、悪路王は光の道へ向かった。
|
“道”の構築時、内側に巻き込まれた歪虚が進軍を妨害する中、幻獣であるフェンリルに跨ったファリフ・スコール(kz0009)が先を急ぐ。 フェンリルの機動力は馬以上、そして単体でも十分すぎる程の戦闘力を持つ。 「雑魚には構わず一気に行くよ! 後ろの人、ちゃんと掴まってる?」 ファリフにしっかりと抱きついたまま、浄化の器(kz0120)が頷く。 ファリフ達を乗せたフェンリルは敵の迎撃を風のように突っ切り、巨大な九尾へと迫っていく。 「もうすぐ第四次結界が来る! 急がなきゃ!」 そんなファリフの達の前方、九尾の目の前、結界道の切れた場所に悪路王が立ちはだかる。 「西方の援軍……まさかここまでやるとはな」 無数の腕に武器を握り、どこか悲しげな眼差しでファリフへ襲いかかろうとしたその時。 「――アクロッ!!」 声の方に反射的に武器を突き出せば、攻撃を受け止める。 だが目の前の人物が自分に攻撃してきたという現実は、受け止め難い物があった。 「……予感はしていたのだ」 悪路王は憤怒の戦列を離れ、自らの故郷へ足を運んでいた。 彼がまだアクロと呼ばれた鬼であった頃。未来を夢見て共と語り合った故郷。 そこがもぬけの空となっていたのを目にした時、悪路王はこの結末を予感していたのだ。即ち――。 「裏切ったのだな……アカシラァアアアアアアアアッ!!」 怒号と共に放たれた雷撃がアカシラの身体を吹き飛ばすが、空中で回転、女は受け身を取り肩に太刀を乗せる。 「行け! ここはアタシら鬼が受け持った!」 「……うん! 死んじゃだめだよ、アカシラ!」 |

ファリフ・スコール 
アカシラ |
「何故だ……何故……! たった一つ守りたかったモノさえ奪われたのか……俺は!」
「アクロ……。そうさ、アタシは……アタシらは裏切った。それを許して欲しいなんて言えない。だけどアクロ……だからこそ、アタシ達が……」
「姐さん、一人で背負わんで下せぇ」
「俺達鬼は一蓮托生……そうでしょう?」
駆けつけた部下の鬼達を背にアカシラはきつく目を瞑り、真っ直ぐに友を見つめる。
「――終わりにしよう、アクロ」
|
「武家第二十位、楠木香、只今帰還致しました」 「同じく、武家第五位、鳴月牡丹。小高砦より帰還しました。それと……」 二人が龍尾城に辿り着いたのは真夜中の事。そしてそこには二人の部下とは別に朱夏(kz0116)とアカシラ達鬼の姿があった。 「二人共無事で何よりです。朱夏とシンカイも、御役目ご苦労でした」 立花院紫草(kz0126)の言葉にそれぞれが深く頭を垂れる。そして紫草はアカシラの前に立ち。 「遠路遥々ご苦労でした。報告は受けています。彼女らの撤退を支援してくれたそうですね」 「まァ、成り行きっつーか……そういう事になるのか?」 「感謝します。そしてお願いがあります。既に九尾との決戦は数時間後、夜明けに近づいています。どうか鬼の手勢にも力を貸して欲しいのです」 「それは……本当によろしいのですか?」 不安そうに尋ねる香。その視線はちらりと牡丹を見やる。 「確かに、彼女らを直ぐに信頼する事は難しいでしょう。しかし今は余計な揉め事に割いている余力はないのです」 「ですが上様。鬼の狙いは以前のように龍尾城に潜入し、スメラギ様を暗殺する事かもしれません」 朱夏の言葉をアカシラは反論せずじっと聞いている。 「その可能性は低いのではないか? そもそも、九尾の力があれば四神結界は朝まで持たぬという話ではないか」 片目を瞑り、腕を組んだ牡丹が口を開くと、香も驚いた様子だ。 「鬼には我らも助けられた。それが高度な潜入工作であるというには、少々無駄が過ぎる」 「ぼたん様……」 「そんな顔をするな、香姫。勿論、今でも歪虚は憎い。だが、彼女らはそうではなかろう?」 すっと香の肩に手を置き微笑む牡丹。そこへわざとらしい拍手と共にヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が歩み寄る。 「実に素晴らしい。そう、鬼は歪虚ではなく亜人。だから共に戦って……」 アカシラの顔を覗き込むように女は笑い。 「――死んでくれないか?」 「……ヴィルヘルミナ様! そのような物言いは……!」 「違うと言えるのかね? 君のその面構えで」 思わず息を呑み、朱夏は目を逸らす。 「憎しみは簡単には消えん。鬼が奪ったモノも、人が鬼から奪ったモノもな。私も先日、君の部下を斬った。この手で何人もな」 再び朱夏からアカシラへ視線を戻し、ヴィルヘルミナは笑う。 「どうだ? 憎いか?」 「……憎くない……と、言えば嘘になるね。勿論、それを許す気はないし、許されるつもりもない。ただ……何かを憎んで、現実から逃れるように戦って戦って……そうやって悲劇を増やす生活には、もう飽き飽きしてンのさ」 「打ち克てるかい?」 「わからねェさ。だが、堪えるのには慣れてる」 真っ直ぐに見つめ合う二人。ふと、ヴィルヘルミナは笑みを作り。 「帝国には犯罪者を危険な戦場に送り償わせる制度がある。が、死刑はない。憎しみを超えるのなら、その手で明日を切り開いてみろ」 |

楠木香 
鳴月牡丹 
朱夏 
ヴィルヘルミナ・ウランゲル |
悪路王の力は強大で、その手の内をよく知るアカシラ達でも圧倒して余りある。
雷撃に吹き飛ばされ地べたに転がる鬼達の中、アカシラは息を切らしながら刃を強く握り締めた。
「憎しみを超える……アタシにできるのか、そんな事が」
迷いは消えない。悪路王と刃を交える度、胸の痛みは全身を引き裂くほどだ。
罪を背負って生きる事。覚悟はしていたけれど、それはとても重く。気を抜けば挫けそうになる。
「――アカシラ殿!」
顔を上げると、駆け寄る朱夏の姿が見えた。
「朱夏……アンタ、先に行ったんじゃ」
「……ずっと考えていました。憎しみと向き合う事を。答えは出ません。しかし、ここであなたを失えば、永遠に見つけられないような気がしたのです」
差し伸べられた手を取り立ち上がる。
「共に戦ってくれませんか。もう一度、肩を並べて」
「……ったく、馬鹿野郎が」
嬉しそうに、しかし悲しそうに。アカシラの刃は悪路王に向けられる。
「見えるかアクロ。これがアンタが夢見た未来。だから守るんだ。相手が“今”の……アンタだって!!」
|
「くっ、まさかこんな事になるとは!」 上空を飛行していたリンドヴルムの背の上。アイゼンハンダー(kz0108)は唇を噛み締める。 九尾が動きを封じられ、憤怒の軍勢は結界で分散させられている。都の防御を完全に捨てたからこそ可能になった策……。 「Unbelievable! これは万が一があるかもしれまセーン」 「何がだ!?」 「奇跡が起きて――歪虚王が討たれる未来デース」 そんな事が起きてたまるか。 アイゼンハンダーはリンドヴルムを急降下させる。目指すは天ノ都中枢、龍尾城。 本来は結界で遮られて不可能な手段だが、こうなればリンドヴルムで直接乗り付けてしまうのが早い。 「何をするつもりデース!?」 「このまま突っ込み……結界の術者を抹殺する!」 真っ直ぐ龍尾城の壁を突き破り、リンドヴルムごと内部へ雪崩れ込む。 瓦礫と砂塵を振り払ったアイゼンハンダーは周囲を見渡し地下にある祭壇へ続く道を探すが、めぼしいルートは見つからない。 「まだるっこしい! 足元を吹き飛ばす!」 『……ツィカーデ、後ろだ!』 義手の声に背後へ目を向けた刹那、雷撃の瞬きがアイゼンハンダーを襲った。 紫電の刀鬼の体当たりで自分が開けた大穴から飛び出すと、二人は空中でもつれあい、そのまま龍尾城の中庭に落下する。 「刀鬼殿……血迷ったか!?」 「アイちゃんは事を急ぎすぎデース。せっかく何か起こりそうなのだから、様子を見させてくだサーイ」 「そのような余裕があるとでも!?」 「そんなにカリカリせずとも、どうせ人類には何もできまセーン……ワオッ!?」 アイゼンハンダーの鉄拳が大地を粉砕し、中庭に衝撃が走る。空中へ回転しながら回避した刀鬼は人差し指を振り。 「攻撃されては致し方ありまセーン。正当防衛デースよ?」 雷を纏い、そのまま雷速にまで加速した刀鬼がアイゼンハンダーの鉄拳と刃を交える。 「何がしたいのだ、貴様!?」 「さーて……何でしょう? Questionデース♪」 『……何やってんだアイツら?』 |

アイゼンハンダー 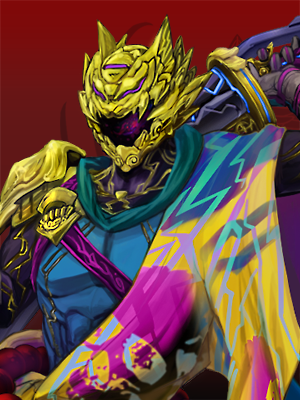
紫電の刀鬼 
ガルドブルム |
そんな意味不明な状況に呆れたように上空でガルドブルムが溜息を零した。
『しっかし……ハハ! マジで九尾の動きが止まってやがる。こいつはひょっとすると……ひょっとするのかもしれねェな』
まだ人間達の作戦は中途。これから恐らく九尾を倒せるかどうかという局面に突入するだろう。
もしも九尾が倒されるとしても、人間の力ならば時間がかかる。状況を見守る猶予は十分にある。
『山……なんだったかねェ、あのジイさん。アレでもかなりの力だったんだ。歪虚王の力……得られたのならどんな具合かねェ?』
消失しそうな力の場合、完全な略奪は難しいだろう。だが上手くやれば歪虚王に近づく事が可能かもしれない。
『――そしていずれは、すべての歪虚の頂点へ』
悪くない。悪くない筋書きだ。
雄々しく翼を広げ、ガルドブルムは急行する。目指すは九尾獄炎、憤怒の歪虚王。
フェンリルの背に乗り、そこへ辿り着いたハンター達。その手に握るは結界術の標的を定める“楔”と呼ばれる術具。
「これを九尾に突き刺せばいいんだね!?」
「そう。刺せば刺すだけ、力が伝わりやすくなる。九尾が弱れば、攻撃の機会は巡ってくる」
『なんて強烈な負のマテリアル……側にいるだけで身体が焼けそうだ』
「ごめんねフェンリル……だけどお願い、もっと近くへ!」
『言っただろう、ファリフ。俺はお前のナイトだ。お前の願う場所へ、必ず届けてやる』
不自由な身体を動かし、不快感に九尾が吠える。
その圧倒的な迫力に負けず、幻獣達は強く大地を蹴る。
――歪虚王との決戦が今、幕を開けたのだった。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●エピローグ「守護者」(8月26日公開)
|
――差し込む茜色の光が目覚めたばかりの瞳に染みた。 見慣れた自室の天井は、しかし半分ほど欠けていた。 歪虚の攻撃を受けた龍尾城は半壊し、スメラギの寝室もその被害を免れられなかったのだ。 「お目覚めですか。気分は如何でしょう?」 「紫草……か?」 首だけを動かすと、傍らに正座した立花院紫草(kz0126)の姿が見えた。 鈍い痛みを堪えながら上体を持ち上げると、ゆっくりと沈んでいく夕焼けが一面に広がっている。 「綺麗だ……」 「ええ。本当に」 「町はボロボロみたいだけどな」 「そうですね。しかし、町は何度でも作り直せます。そこに命の営みさえあれば」 城下町に歪虚を引き入れるという苦肉の策が招いた当然の結果。そこに勝利の余韻はない。 町は静かに佇んでいる。戦いの終わりこそ、この国の終わりであるとでも言うかのように。 「もう少しお休みさせてあげたい所ですが、急ぎの要件があります」 「ああ……わーってるよ」 紫草の手を借りて立ち上がろうとするスメラギだが、身体が満足に動かない。 歪虚王、九尾獄炎を封じるために放った術の反動だ。命があるだけマシなくらいで、ひょっとするとこの足は二度と動かないかもしれない。 「スメラギ様」 無言で腰を下ろした紫草の背に縋り、少年は再び歩き出した。 崩れた城の中を紫草はゆっくりと進んでいく。大きく差し込む茜色の光は、どこか郷愁にかられそうだ。 |

スメラギ 
立花院 紫草 |
「何いきなりキモい事言ってんだ?」
「私も一応激戦で疲れている身です。大きくなったスメラギ様の身体は足に堪えます」
「だったら降ろせボケ」
「降ろしませんよ。これが、私の役目ですから」
小さく微笑む男の言葉に少年は目を逸らす。
「スメラギ様」
「あ?」
「九尾討伐、誠に大義でございます。本当に、本当に、よく頑張りました。きっと先代も、お歴々のスメラギ様も、あなたを誇らしくお思いになられるでしょう」
口喧しく生真面目な、しかしどこか自分を子供扱いしていた紫草。
兄のような、そして親代わりのような男の言葉に、少年はふっと目を瞑る。
「――当然だぜ。何故なら俺様は、この国の帝なんだからな」
|
天ノ都にある龍尾城。その地下深くに黒龍を祀る祭壇はあった。 普段は人が踏み入る事を禁じられた聖域。スメラギ達術師が結界術を使っていた祭壇の中央に安置された龍脈。その井戸のような竪穴を降りれば、黒龍の眠る大空洞へ出る。 濃厚なマテリアルの光に満ちた空間に、巨大な黒い鱗の龍が眠っていた。 先客は三名。リムネラ(kz0018)、ファリフ・スコール(kz0009)、そして浄化の器(kz0120)。幻獣であるフェンリルを加えるのなら四人となる。 彼らの元へ螺旋階段で降り立った紫草はスメラギを降ろし、肩を貸しながら前に出る。 「……久しぶりだな、黒龍。俺が御柱の役割を継承した儀式以来か」 呼び声にゆっくりと龍は双眸を開き、人間達の姿を映し出す。 『……スメラギ。良かった。消える前に、もう一度あなたと話をしておきたかったのです』 頭の中にエコーするような、しかし決して不快感のない声。龍は僅かに顔を上げ。 『この地に集いし精霊の意志を伝える者達よ。あなた達もよくよく聞き覚えなさい。そして私の最期を見届けて欲しいのです』 「……ワカッテいたことデス。あれだけの強大なチカラ……使えば黒龍様の力は持たナイと。そして……」 「この東方の大地のマテリアルも枯渇しようとしてる……そうだよね、フェンリル?」 リムネラに続き、ファリフが口を開く。その疑念に答えるように、腰を下ろしたままのフェンリルが頷く。 『獄炎を封じる為に莫大な量のマテリアルが消費された。この土地は既に枯れ始めている』 「マテリアルを失った大地は死の世界に変わる。でも、それを承知の上で力を使った筈でしょ?」 あっけらかんと無表情に呟く器の言葉に黙り込む面々。スメラギはゆっくりと頷き。 「ああ、わかってたさ。それでも俺様はやると決めた。黒龍……エトファリカの母たるあんたを殺すと知っていたのに」 『それがヒトの出した答えであるというのなら、願いに貴賎はありません。元よりこれは必然……。私はこの地を守護すると決めたその時から、いつかは終わることを知っていたのですから』 とても穏やかで優しい声だ。とても死を目前にした者の言葉とは思えない。 『長い、とても長い生の中で、私はひとつの答えを見届けることが出来ました。ヒトという存在が持つ可能性……その生命の力強さを。ならば私はそれでいい。それだけで十分なのです』 「黒龍様……」 『遠き西の地より訪れた白龍の子らよ。私は、私達はもうあなた達を守れません。これから先の選択はヒト次第……。それは、途方もない困難に満ちた旅路のはじまりを意味しています』 顔を見合わせる人間達へ、黒龍は一度目を瞑り、ゆっくりと語りかける。 |

リムネラ 
ファリフ・スコール 
浄化の器 |
「歪虚との戦いが……運命?」
『それが世界の……この星の望み。そして多くの精霊達の存在意義でもあります。あなた達ヒトは、存在する限り闇に抗い続けなければなりません。それがどれだけ苦しくとも、悲しくとも……』
紫草の肩を借りながらゆっくりと前に出るスメラギ。黒龍は大きな瞳でその姿を見つめる。
『“血の宿業”がそれを望んでいるのです。しかし悲嘆する必要はありません。あなた達ヒトは、或いはこの世界の守護者足りえるかもしれない……私は今、そう思い始めています』
「どういう事だ? 黒龍……あんたが何を言っているのか、俺にはよくわからないよ……」
『稀代のスメラギよ。今際の時にあなたを瞳に宿せて良かった。私が愛した東の子らよ。確信しているのです。私の愛はきっと間違いであったけれど、どうしようもなく正しかったのだと……』
手を伸ばすスメラギから離れるように、黒龍は上体を起こす。
『己の道を歩み、そして証明しなさい。ヒトはただ、生まれ落ちて死んでいくだけの消耗品ではないのだと』
「黒龍……?」
『残された私の力のありったけをこの国の大地に還元します。それが私の最後の契約。スメラギ……そして白龍の子ヘレ。あなた達にも我が魂の片鱗を託しましょう』
そう言って翼を広げた黒龍の身体を眩い光が覆っていく。
『力を継承し――そして役割を引き継ぐのです。世界の……星の守護者として……』
「待ってくれ、黒龍! あんたは……!?」
その叫び声は光にかき消された。
息が詰まるような莫大なマテリアルが放出される。それは文字通り黒龍の命の光だ。
光の風の中、スメラギは目を細め、しかし確かに感じた。
誰かの優しい指先が頬を撫でた事。これまでずっと側に居てくれたような気がする、誰か。
その気配が消えていく。いや、大地に吸い込まれていく。
沢山の光になって。龍脈の流れに乗って。もう死ぬしかなかった世界へ還元されていく――。
「……黒龍……」
光が消えた後、スメラギは気づけば一人だけで立っていた。
誰に支えられずともその両足で。しっかりと、大地の上に立っていたのだ。
「俺に……生きろって言うのか……?」
「それでも、あなたの命もこの大地の命も残りは限られている。人がまだ精霊を食いつぶすだけなら、直ぐに燃え尽きて終わる」
器の言葉にスメラギはカラッポの祭壇を見つめ、首を横に振り。
「そうはさせねぇよ。この国はきっと美しくしてみせる。黒龍はきっと見ていてくれる。俺はそう信じてる」
スメラギを一瞥しつつフードを被って去っていく器。その傍らでファリフとリムネラが小さな白龍であるヘレを見つめている。
「うーん? 特別な変化はないよね?」
「確かに、マテリアルの感じはスコシ変わりましたケド……」
首を傾げる二人。紫草はそれを遠巻きに眺めつつ。
「黒龍を失い、この国を守っていた結界は消えてしまいました。これで代々続いてきた御柱の役割も終わりですね」
「ああ……そうなるな」
「これからはどこへとなり、お好きな所へ出向けることでしょう」
「そうだな。でも俺は、この国から逃げたりはしないよ」
確かに嫌いだと思う時もあった。面倒だったり、怖かったり。
いい思い出ばかりじゃない。それでも、この国で生まれ育ったから。
「御柱様ではなくなっても、スメラギである事に変わりはねぇ。やっぱこの国は、俺様がいなきゃ始まらねーだろ?」
白い歯を見せ笑う少年に男は複雑な表情を浮かべ。それから納得するように頷いて。
「……ええ、まったくで。これからも誠心誠意お仕えさせていただきますよ、我が君」
そう、微笑むのであった。
●“旅路”
夕暮れの光が水平線に沈み、夜が城下町を覆った。
満天の星空の下、廃墟同然の町にはあちこちに焚き火が灯り、兵達が戦勝を祝う小さな席が設けられていた。
しかしそれは戦の勝利に酔う為のものではなく、失われすぎた多くの命を弔う為にあるようだった。
|
最終局面で合流した鬼の軍勢は当然彼らの輪に入れる筈もなく。アカシラは瓦礫に腰を下ろして酒瓶を傾けていた。 「……アカシラ殿。こちらにおられましたか」 「朱夏かい。こんな所にいたらお仲間から白い目で見られちまうよ」 「構いません。ここに足を運んだのは自分の意志ですから」 アカシラの隣にどっかりと腰を下ろし、升に注いだ酒を一気に呷る。 「おいおい……そんな勢いで大丈夫かい?」 「九尾を倒した戦いで……多くの仲間が散りました。夜空を見ているとなんだか無性に泣けてきて……だから、今日くらいは……」 俯いた朱夏(kz0116)にアカシラはふっと笑みを作り、からっぽの升に酒を注ぐ。 「アカシラ殿は……」 「アカシラでいいよ。アンタが畏まるような相手でもねェし」 「……んん。いや……。アカシラ……は、今、どのような気持ちなのだ?」 「はァ?」 「友であった悪路王をその手で打ち滅ぼし、危険な戦場から生還した……。私は悪路王とも刃を交えた事がある。仲間を殺された事もある。だが、彼があなた達の友人であったという事実にはなんら変わりない……そう思うのだ」 「だったらアクロはアンタらの敵だって事も、鬼が憎まれる事も、こっちの事情とは関係ねェだろ」 酒瓶に直接口をつけ煽っていると、隣に腰掛けた朱夏が悔しげに唇をかみしめている事に気づく。 「私は……自分の正義を信じて戦った。そこに後悔はない。戦場に散った数多の英霊たちは皆等しく正しく、等しく尊かったのだと信じている。なのに……迷ってしまう! 私の戦いの日々は、本当に正しかったのかと……本当に、この国の為であったのかと……!」 |

アカシラ 
朱夏 |
「だが私は考えもしなかったのだ。私が正義を振るう時、その切っ先が自分以外の誰かの正義を殺している等と……んぐっ!?」
アカシラの拳骨が朱夏の頭頂部にめり込む。
「痛いではないか……っ」
「そりゃ痛くしてるからね。ゴチャゴチャ過去を悔いたって仕方ないだろう? 憎しみも罪も背負っていく。生きるって事はそういう事なンだから」
「アカシラ……」
「……ぬわっ!? なんで泣いてンだい!?」
「これは……頭が痛くて……うっ、うぅぅぅ……っ」
ちょっと引くくらいの号泣っぷりに思わず冷や汗を流すアカシラ。
隣に座り直すと、また酒を注ぎながら慣れない様子で朱夏の肩を叩く。
「まあ、なんだ……? 元気出せよ……な?」
「もっと注いでくれないか!」
「あ、ああ……でもアンタ、あんまり酒に強くないんじゃ……」
心配通り、朱夏は暫くすると瓦礫の上に仰向けにぶっ倒れてしまった。
頭をわしわしと掻きながらアカシラは仕方なく朱夏の周りの瓦礫を整え、その辺から拾ってきた布切れをかけてやる。
「ハア?……面倒くせェ。これだから人間って奴らは……」
酒瓶を片手に夜空を見上げる。瞬く光は本当に綺麗で、我を失ってしまいそうな程だ。
鬼とヒトは長らく対立してきた。それは不幸なすれ違いから来るものであり、誰かが決定的に悪かったわけではない。
だがその悲劇の中でアクロという一人の鬼が闇に落ち、終わることなく繰り返された彼の悪夢は更に多くの悲劇を呼んだ。
生きている事、それそのものが罪……。そんな一族を救うために下した結論に後悔はない。ないけれど……。
「アクロ……。これが、あんたの望んだ未来の一つ……なのかねェ?」
すやすやと寝息を立てている朱夏に目を向ける。
ヒトと共に戦い、ヒトと共に生きる。そんな未来に、自分達は辿り着けるだろうか……?
|
「――今のままでは難しいだろうね」 声は背後から聞こえた。振り返ると瓦礫の山の上、腰を下ろして月を見ている女がいた。 「アンタは確か……ヴィルヘルミナとかいう、西方の……」 「ゾンネンシュトラール帝国皇帝。騎士皇ヴィルヘルミナ・ウランゲル。覚えておけば地獄の通りも良かろう」 くいっと升に注いだ酒を呷り、女はすっと目を細める。 「単刀直入に行こう。アカシラ、西方に来る気はないか?」 「西方に……?」 「君達鬼は歪虚の汚染に強い種族だと言う。働き口は幾らでも用意してやれるぞ。勿論、世論の事もある。君達は危険な戦場に送り込まれるだろうがね」 「交渉するつもりがあるのなら、そこは少しでも濁す所じゃないのかい?」 「私はアンフェアな交渉を望まない。君へのメリットもデメリットも包み隠さず伝えよう。それが誠意と考える」 |

ヴィルヘルミナ・ウランゲル |
「君達鬼は九尾との戦いで一定の戦果を示し……救国に貢献した。しかし……君達の処遇が正しく決定されたわけではない。九尾という目先の脅威がいなくなった後、この国の再起において脅威として挙げられるのは……君達、鬼だろう」
そんな事は言われずとも承知の上だ。
所詮、エトファリカ幕府との約束は正式なものではないし、仮に幕府が鬼の受け入れを決定したとしても、国民感情がそれを許すとは限らない。
「悲しみには生贄が必要だ。ヒトはいつでもそうやって心の平静を保っている。憎しみに矛先を……正しい怒りに焼かれる犠牲を……ね」
ゆっくりと、一歩一歩アカシラへ近づき、女は眼と鼻の先に立つ。
その静かな、しかし鋭く切り裂くような眼光をアカシラはまっすぐに見つめ返す。
「亡命したまえ。この世界で鬼を最も効率よく救済できるのは、この私だ」
目の前の女は笑っているのに。敵意はないと示すように、身体に緊張の一つさえ見られないのに。
全てを飲み込むような強烈な圧力を感じる。目を逸したら一瞬で食いつぶされる……そんなあり得るはずのない感覚に陥るほどに。
「どうした? 何を迷う必要がある? 一族を救う……その為だけに全てを捨ててきたのだろう?」
そっと差し出される右手。アカシラは息を呑み、ゆっくりと手を持ち上げ――。
|
「――そのお話、待ったをかけさせていただきます!」 手を背後から取ったのはシスティーナ・グラハム(kz0020)であった。 「間に合って良かった……鬼の皆様を探していたのですよ」 「アンタは……?」 「システィーナ・グラハム。グラズヘイム王国の王女様だよ」 ウィンクしつつ酒で唇を濡らすヴィルヘルミナ。システィーナは両手でアカシラの手を握り。 「鬼の皆様には、是非我らグラズヘイム王国へお越し頂きたいと考えています。わたくし達の、よき友人として」 「友人って……アンタ、アタシらがどういう人種なのかわかってンのかい?」 「承知の上です。しかし、このまま東方に皆様を放置した場合、東方に無用な争いを再発させかねません。皆様を保護する事は、スメラギ様やこの国にとってもよい事であると考えます」 |

システィーナ・グラハム |
一歩引いたポジションから野次を飛ばすヴィルヘルミナ。それは全くその通り。犯罪者であっても兵力として使う帝国と王国とでは話が変わってくる。
「ところがどっこい、我が帝国は使える者は野盗でも使う。とってもエコロジーな軍事国家です。鬼を受け入れてもだーれも反対しません」
「いえ、流石に一般国民からは反対の声もあがると思いますが……ではなく! そもそも、鬼を犯罪者であるという捕らえ方から異議を申し立てます! 彼女らは止むを得ない事情から犯罪行為に手を染めてしまった……こともありました。しかしそれは彼女らだけの罪ではないはずです!」
「“その罪人を飢えさせたのは、一体、誰なのですか”……だったかな?」
それは以前、鬼を受け入れるべきだとスメラギに主張した時のシスティーナの言葉だ。
「では、“誰”が悪いのかな?」
「それは……今は、誰が悪かったのかという話ではなく……これから、その罪を未然に防ぐにはどうするかという話をしているのです」
すっと笑みを作り、ヴィルヘルミナは新たに酒を注ぐ。
「人の悪感情程管理の難しい物はないよ。いや、ある意味に置いては単純なのだが……そのロジックは常に犠牲を伴う」
「“悪役”を作り、それに罪の全てを着せる……それがヴィルヘルミナ様の仰る救済なのですか?」
僅かに声を震わせながら、しかし少女は逃げずに女を見つめる。
「そうだ。罪は憐憫では濯げない。罰は誰の目にも明らかな形でなければならない。そして罰だけが罪を本当の意味で救う」
「仰ることはわかっているつもりです……それが本当に罪ならば、ですが」
見つめ合う皇帝と王の娘。その緊張に耐えかねるようにシスティーナは小さな手をぎゅっと握り、頬に汗を伝わせる。
しかしそれは長く続かなかった。ヴィルヘルミナは酒を呷ると、前髪を掻き上げながら笑い。
「――いいだろう。それでは君のやり方で救ってみるといい。鬼の一件から、私は手を引こう」
少々呆気なさすぎる軽い口調でヴィルヘルミナはそう言って、地べたに転がっていた朱夏を抱き上げた。
「この子はエスコートしておくから、君達は存分に今後を話しあうと良い。風邪だけは引かないように気をつけるんだよ、システィーナ」
にこりと笑って女は去っていく。それを見送ったシスティーナの足が崩れ、へなへなとその場に座り込んだ。
「……アンタ、大丈夫かい?」
「は、はいぃ……ちょっと緊張しすぎて……」
「無理もないね。アレはちょっとした傑者だ。修羅の類だよ」
そっと手を差し伸べるアカシラの手を取り、システィーナは立ち上がる。
「ヴィルヘルミナ様も、悪いお方ではないのです。どうか誤解しないであげてください」
「違う国の王同士なんだろう? どうして肩を持つんだい?」
「……わたくしはまだ王ではありません、けれど……それは……」
遠ざかった背中はもう見えない。少女は自らの手をじっと見つめ、それを胸に抱きしめた。
「それ、は……」
答えあぐね俯く少女をアカシラはそれ以上問い質さない。
代わりにヴィルヘルミナの言葉を思い出し、毛布をそっと少女の肩にかけるのだった。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●エピローグ「白紙の未来」(8月31日公開)
|
「九尾を撃破は歴史的快挙ではありますが、これで東方の問題が解決したわけではありません」 立花院紫草(kz0126)の言葉にスメラギは胡座をかいたまま頷く。 「黒龍の結界は消え、絶対安全圏は消失した。だが、南方へ撤退した憤怒の軍勢が全滅したわけじゃねぇ」 最大の脅威であった歪虚王を打ち倒した事で、憤怒の動きは間違いなく鈍るだろう。 恐らく歪虚にとっても王が討たれる事は未曾有の痛手。混乱は当面止む事はない筈だ。 しかしそれも収まれば再び憤怒との戦いが始まる。今度は守護者たる黒龍と結界を失った状態で、である。 「四十八家門はほぼ壊滅状態、陰陽寮も先の作戦で負傷者多数」 「つっても、いつまでも西方連中に頼りきりってわけにもいかねぇからな。こっちはこっちで歩き出さなきゃよ」 そう言って顔を上げたスメラギの表情はどこか晴れやかだ。 これから先に未来は考えれば考えるだけ頭が痛くなる筈なのに、迷いや不安のような感情は見えなかった。 「俺様もこの国も、とっくに死んでてもおかしくなかった。今も未来も、本来は望める筈もなかったんだ。なのに今はそれを想う事ができる。それだけで十分じゃねぇか」 少年は立ち上がり窓辺に立つ。 この足も、この腕も、この視界に映る全ての物も、誰かが自分に繋いでくれたかけがえのない未来……。 「大勢の人が死んだ。それこそ数えきれないくらいにな。けどよ、それを悲しむのは少し違うんじゃねぇかって思うんだ。そいつは東方らしくない」 「……武人にとって死は誉れ。勇敢に散った戦士達に、憐憫は無用です」 |

立花院 紫草 
スメラギ |
大丈夫、強がりで笑うのは慣れている。東方民の笑顔は強い。悲しみを吹き飛ばし、未来を勝ち取るだけの力を持っている。
「紫草。俺様は最強のスメラギになるぜ。歴代最高の王だ。俺様は二度と涙は流さない。どんな時でも民を守り、そして恩人であり友でもある西方のモノノフの為に、どんな時でも戦ってやるんだ」
「左様でございますか。しかし、それはきっと茨の道ですよ」
「へっ、承知の上だ。それでも俺様はきっとこの国を建て直してみせる。次の世代に、俺様達の子供やその子供にまで、美しい国を残してみせる。そして語り継ぐんだ。国を守る為に散っていった、大勢の英雄の武勇をな!」
光を背に振り返り、スメラギは笑う。その笑顔はもう作り物ではない。
「まずは都に人を呼び戻すぞ、紫草! 盛大に勝利を祝うんだ! この国はまだ死んでねぇって事を、民の心に思い出させる為にな!」
|
「それにしても、この状況でお祭りか。スメラギ帝は破天荒だと聞いてはいたけどね」 九尾獄炎との決戦の為に住民を避難させていた天ノ都。そこに少しずつ人々が戻りつつあった。 帰ってきた所で、家が壊れている事もある。これまで通りの生活を取り戻すのにどれだけ時間がかかることやら。 そんな状況だというのに、スメラギが決めたのは盛大な“戦勝会”を街全体で催すという事だった。 「あたしは賛成だけどな?。だってさ、やっと戦いが終わったのにみんなクヨクヨしてたらいつまでも気持ちが悲しいままだもん」 ラキ(kz0002)の言う事にも一理ある。篠原神薙(kz0001)は瓦礫の上に腰を下ろしたままそう考える。 歪虚王との戦いはとても悲壮的だった。まるでこの世の終わりのような状況からの奇跡の生還。それが今を端的に表す言葉だ。 その悲劇に浸ったままではいつまでもこの国は立ち直れない。 「それに見てみなよ、祭りの準備をしてる人達の顔!」 「ああ。この国の人達は生来騒ぎ事が好きだって書物で読んだけど……みんな楽しそうだ」 財産を失った町の人々も、傷ついた兵士達も、笑顔で懸命に祭りの準備を進めている。 崩れてしまった町。散らばる瓦礫をひとつひとつ拾い集め、彼らはいつ終わるとも知れない復興を精一杯楽しもうとしている。 こうして明日へ向かって歩き出す事こそ、東方流の鎮魂であり、これまで歴史に没してきた英雄達への供養でもあるのだ。 「なんかこういうの見てると、あたしも何かしなきゃって気持ちになるよね!」 |

ラキ 
篠原 神薙 |
駆け出したラキが瓦礫の片付けに協力する後ろ姿を眺め、神薙は青空を見上げた。
歪虚王は倒れたが、まだ解決していない問題はいくつかある。
絶対安全圏と呼ばれた首都圏への歪虚の侵入。地方から人々を呼び戻すには邪魔になるだろう。
そして鬼と呼ばれる亜人の扱い。こちらも神薙としては目が離せない所だった。
「人は、悲しみや憎しみを超えられるのかな……」
あの歪虚王との戦いの中、確かに人々は心を重ね、お互いの境遇を超え勝利へ手を伸ばした。
それが真実かまやかしかを決めるのは、きっと戦いが終わった今でこそなのだ。
「証明していかなきゃな」
まずは自分の言葉にしたがって、できる事からコツコツと。
例えそれが河原に石を積み上げるような儚げな希望だとしても。奇跡を望んだ者の責任として。
所感を記した手帳を閉じ、少年は瓦礫の山を下る。遠くでは少女が割れた壺を抱え急かしているのが見えた。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)






