ゲスト
(ka0000)
ぼくらのサマーキャンプ
マスター:四月朔日さくら
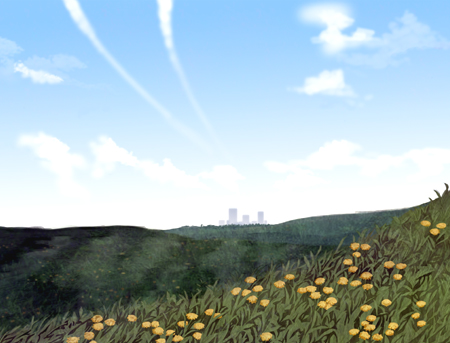
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~8人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2015/08/11 22:00
- 完成日
- 2015/08/24 06:18
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●
大人たちが東方の騒動でてんやわんやしていたって、ぼくたちには分からない。
むしろそのてんやわんやが、ぼくたちにはつまらない。
夏休みで、パパといっしょに遊べると思ったのに。
「いま忙しいから、また今度な」
そう言われて、そう言われて。
ぼくの夏は、つまんない!
●
そんなわけで(?)少年はハンターオフィスの前にいた。
少年の父親はハンターだ。但し、少年にはまだそれらしい兆しもなく、ごく普通の十歳の子どもとして母親と生活している。
「……子どもの遊び相手?」
少年の話を聞いて、オフィスの事務員はむう、とうなった。
正直なところ、東方のごたごたが落ち着くどころでない為に、たしかに多くのハンターがそちらへと向かっている。彼のような立場の子どもは、正直少なくないだろう。
「うーん、手の空いてるハンターや、前線に出づらい初心者ハンター向けになるかもだけど……この子たちの護衛兼遊び相手になれば、面白いかも知れないな」
年配のスタッフがそういうと、ああ、と若手スタッフも相づちを打つ。
「そう言うことなら、受け入れられやすいでしょうしね。ハンターの子どもなら、それだけで話題を提供できるだろうし。いっそキャンプとかもいいかもしれませんよ」
若手スタッフらしいアイデアだ。
「じゃあ、それで。一泊二日でもいい思い出作りができれば、子どもたちも喜ぶだろうしな」
●
そんなわけで、ハンターの子どもたちを対象にした子どもキャンプが開催されることになった。
つきそうのはハンターたち。
一泊二日の小旅行、一体どうなることやら。
大人たちが東方の騒動でてんやわんやしていたって、ぼくたちには分からない。
むしろそのてんやわんやが、ぼくたちにはつまらない。
夏休みで、パパといっしょに遊べると思ったのに。
「いま忙しいから、また今度な」
そう言われて、そう言われて。
ぼくの夏は、つまんない!
●
そんなわけで(?)少年はハンターオフィスの前にいた。
少年の父親はハンターだ。但し、少年にはまだそれらしい兆しもなく、ごく普通の十歳の子どもとして母親と生活している。
「……子どもの遊び相手?」
少年の話を聞いて、オフィスの事務員はむう、とうなった。
正直なところ、東方のごたごたが落ち着くどころでない為に、たしかに多くのハンターがそちらへと向かっている。彼のような立場の子どもは、正直少なくないだろう。
「うーん、手の空いてるハンターや、前線に出づらい初心者ハンター向けになるかもだけど……この子たちの護衛兼遊び相手になれば、面白いかも知れないな」
年配のスタッフがそういうと、ああ、と若手スタッフも相づちを打つ。
「そう言うことなら、受け入れられやすいでしょうしね。ハンターの子どもなら、それだけで話題を提供できるだろうし。いっそキャンプとかもいいかもしれませんよ」
若手スタッフらしいアイデアだ。
「じゃあ、それで。一泊二日でもいい思い出作りができれば、子どもたちも喜ぶだろうしな」
●
そんなわけで、ハンターの子どもたちを対象にした子どもキャンプが開催されることになった。
つきそうのはハンターたち。
一泊二日の小旅行、一体どうなることやら。
リプレイ本文
●
いま、東方では大きな戦いの真っ最中。
だけれど、子どもにはそんな理屈は通用しない。
夏で、学舎も休みで、暇をもてあましているとなれば、本当ならばいつも以上に親にも甘えたいし、冒険だってしたい。
普段なら、親が子どもたちをサポートしながら遊んでくれたのだが、昨年来の歪虚の活性化によってそれも難しいのがくやしいけれど子どもたち――いや、クリムゾンウェスト全体の現状だ。
その結果、夏はどうやら子どもたち、このような緊張下の上に暑い盛りと言うこともあって、友達にも会わずに自宅や商店などの屋内でごろごろするくらいしかないのだという。……むろん例外はあるのだが。
今日は事前準備の為のハンターたちの顔合わせ。
偶然にも、集まったハンターは皆リアルブルー出身であった。もっとも、立場は各人様々である、のだが。
(……でも、遊びたい盛りの子どもたちにはやっぱりつまんないよね)
サマーキャンプの話を聞いて参加を申し出てくれたひとり、天竜寺 詩(ka0396)はそう思う。彼女自身先頃の東方における戦いにおいてかなりの怪我を負ってしまっているが、子どもたちの意見ももっともなのだ。
もともと彼女自身、リアルブルーではやや特殊な環境下――伝統芸能を伝える家系で育ち、幼少期から双子の姉ともどもその芸をたたき込まれてきた。それこそ、休みなんてお構いなしに、だ。だから、子どもたちの気持ちも分からなくない。むしろ、彼ら彼女らの訴えはしごくまっとうで、だからこそ応援したくなる。
「だから、子どもたち皆が楽しい思い出を作れるように……私もがんばらないとね!……ッたた……」
きゅっと拳を握るが、直ぐに引きつるような痛みがぶり返す。
治るとは言え、大怪我を負っているのは間違いない。気を張っていないと、直ぐにいたみが現れてしまう。実際、今もその姿は一部を包帯でくるまれており、少しばかり痛々しかった。
一方、同じリアルブルー出身でも、さまざまな家庭の事情というのはあるもので。
浪風 白露(ka1025)もやはりまた、きょうだいともどもリアルブルーから転移してきたハンターだが、サルヴァトーレ・ロッソ転移前から辺境でたくましく生活をしていた口である。
白露は次女だが、彼女がハンターとしての能力を振るうきっかけはやはり家族を護る為。と同時に、自分よりも何かと優れた兄や姉を見返すことができるのならば、と思っている。
ふだんから弟妹の世話などで子どもの扱いにはなれている方だ、とは思う。けれど、サバイバル感たっぷりな白露たち一家と、リゼリオに暮らすハンターの子どもたちとではそれなりに立場も違うし、そもそも生活のパターン、リズムが大きく異なる。
それに――
白露は脇に立つ灰色の髪の美丈夫、鬼塚 雷蔵(ka3963)をちらりと見やる。白露は雷蔵の営む小料理屋の顔なじみの一人でもあるが、もう一つ、白露は雷蔵のことを異性として気になっているという事実もあった。ほのかな想いとでも言えばいいのだろうか、しかしそれ故に白露の行動はいつもよりもどこかぎこちなさがぬぐえない。
雷蔵のほうはというと白露よりも年長であること、みずから店を営んでいることなどもあって落ち着いたものだ。
「……それにしても、子どもたちとのキャンプ引率か。楽しむのは当然としても実際に何が起るかは分からないし、安全第一を心がけていかないとな」
低い声でそういうと、白露はとくり、と高鳴りそうな胸を押さえながら頷き返す。
「は、はいっ」
そう返事をしたものの、声が裏返っていないか、不自然ではないか、そう言うことが妙に気になる。恋というのはそう言うものなのだ。
そんな白露の戸惑いを横目で見ながら、霧雨 悠月(ka4130)は、小さく微笑んでいた。リアルブルーからの転移者に間違いはないのだが、その前後の記憶が曖昧なせいだろうか、どこか不思議な目をしている。
「でもキャンプなんて楽しそうだね。キャンプ道具一式は借りられるのかな?」
悠月が問うと、ハンターオフィスの職員はもちろん、と頷いた。
もともとキャンプの引率を担当するわけで、しかもそれなりの人数ともなれば各人の所持金だけでどうにかなるわけでもない。それに今回はちゃんとしたハンターオフィスからの要請でもある。ギャランティも支払われるし、準備に必要な道具もまるっと用意してくれると約束してくれた。
「子どもたちとの対面は、当日のお楽しみと言うことで」
職員が言うと、ハンターたちも頷く。
「一体どんな子たちがいるんだろうね。きっと元気なんだろうなぁ」
誰かがそう呟くと、誰からともなく笑みが溢れた。
●
そして、約束の日がやってきた。
「こんにちはー!」
明るい子どもたちの声が、オフィスの前に響く。
待ち合わせはオフィス前――あらかじめ作成されていたしおりに書かれていたことだ。集まった子どもは全部で七人、上は十歳から下は七歳まで、はつらつとした子どもたちだ。
「ハンターの皆さんも忙しい中を来て頂いているんですから、ちゃんと挨拶をしましょうね」
ハンターオフィスの若い女性職員がそう微笑むと、
「よろしくおねがいしまーす!」
これまた元気な声でそう言い、ぺこりと頭を下げる。
「こちらこそ、よろしくな」
雷蔵の言葉に、子どもたちの顔はぱっと輝いた。
「えー、それじゃあみんなリアルブルーのひとなんですか!?」
歩きながら簡単な自己紹介をすませたあと、そんな驚きの声を上げたのは年長男子のサトーだ。彼自身ハンターへの憧れがあるらしく、いつかハンターになれる日をずっと狙っているらしい。
「……でも、リアルブルーからの転移者は多いって聞いていたけれど、こんな風に一度にたくさんのひとにあうことができるなんて思ってませんでした」
同じく最年長、サトーと同じ十歳の少女アンがそう言って笑顔を見せる。
サルヴァトーレ・ロッソの転移で一気にリアルブルーからの転移者ハンターは増えたとは言うものの、実際にあうとなるとまた話は別だ。
少年少女たちは瞳をキラキラさせながら、ハンターたちを憧れの眼差しで見つめている。リアルブルー出身のハンターばかりに護られてのキャンプというのは、たしかに余りにも新鮮だ。
「たのしみだね!」
「うん!」
ミチとデュオ、九歳の男女コンビが嬉しそうに語り合う。話を聞いていて分かったのだが、もともとハンターの親をもつ同士、彼ら七人は以前からの知り合い関係らしい。
その中でも特に行動力があるのはデュオ。この企画の発案者でもある所でそれはだいたい分かるというものだが。逆にサトーは好奇心旺盛ではあるが自分から動くタイプではないらしい。内向的と言うよりも、受動的と言うべきか。
「設営が終わったら、何かやりたいことはあるのかな?」
そう詩が尋ねてみると、
「お料理してみたい!」
ちびっ子たちからそんな声が。どうやらなかなか家では包丁を握らせて貰えないらしく、こういうときならばと言うもくろみでもあるらしい。
「夏休みの課題に使えるものとかないかなぁ」
そんな現実的なことをいうのはセンだ。年齢は比較的高く、学校では優等生らしいが、だからこそ宿題などにも手を抜けないタイプらしい。
クラスに一人はいるタイプだなあと、誰もが苦笑を浮かべる。
「やりたいことはいっぱいありすぎるよ!」
デュオはにっかりわらってそう答える。
「どっちにしても、テントと簡単な竈を作ってから、だけどね」
白露がそういうと、脇にいた雷蔵がわしわしと子どもたちの頭を撫でてやった。
「まあ、重いものを持ったりするのは俺たちも手伝うさ。そのためのハンターだしな。まあ、色々と楽しもうな」
その言葉に子どもたちも嬉しそうにこっくりと頷いた。
●
キャンプの為の場所は子どもの足でも十分問題なくたどり着ける距離だった。
皆疲れたとは言うものの、表情にまだ余裕が見受けられる。
ハンターオフィスから借り受けたキャンプ用具一式を広げて見せれば、子どもたちからも歓声が上がった。
「これがテント、これは御飯を炊く道具の飯ごうだね」
悠月が一つ一つ丁寧に紹介すると、へぇ―と言う歓声が漏れる。
そうだ、と白露が取り出したのは小さな、しかし涼しげな音のする鈴。人数分ある。
「もしかしたら何かがあってはぐれたりしてもいけないから、これをつけておいてね」
音がすればすぐに何らかの異変に気づけるかも知れないし、確かにいいアイデアだ。子どもたちはありがとうと口々に言いながら、ベルトやポケットにそれを着けてちりちりと鳴らして見せたりする。
しかし、まずは設営が第一だ。
「まあ、まずはテント作ろうな!」
「もし怪我したら、救急キットもあるから手当てするからね」
雷蔵と悠月、ふたりの男性陣に言われて、子どもたちも素直に頷いた。
ちなみにやはり悠月は始め男性と思われていなかったらしい。いつものこととは思いつつも、小さくため息をついたのはまあ仕方のないことなのだろうが。
「それじゃあ、この柱になる部分を支えてくれないか。ああ、こっちは縄をぴんと張って、くい打ちしないとな」
こういうときに頼りになるのはやはり男性。子どもたちも言われるとおり、丁寧に手伝っていく。
いっぽう、まだ幼くてテント設営の手伝いが難しいリマとリクの双子は、詩や白露といっしょに簡易かまどの作成の手伝いだ。近くの瓦に落ちている石を拾い集め、それを使ってかまどを作る。重い石については詩たちも運ぶのを手伝っているし、こちらもこちらで順調に仕上がっていた。
やがてテントができあがる頃にはかまどもできあがり、子どもたちも満足そうに笑うことになる。
自分たちで作る非日常の生活というのが、子どもたちには十分どきどきの対象になっているらしい。
おとなしめの子どもたちも、周囲に引きずられてテンションが少しずつ上がっている。こういう場所ではテンションが上がらない方が損なのだ。
労働のあとの心地よい汗を掻きながら、子どもたちもハンターも、すっかり笑顔を浮かべている。
作業の合間に話をしていて、七人の性格は大まかにつかめた。
リーダー格で元気溢れるデュオ。
最年長、将来の夢はハンターだというサトー。
サトーと同い年だが気配り上手の少女、アン。
アンの弟で、趣味は読書というどちらかというとインテリ肌のセン。
少年に負けず劣らずの元気娘で姉御肌なところのあるミチ。
双子のリマとリクは最年少、リマは少し病がちなところがあるぶんリクがフォローをしていたりすると言う関係。
そして誰もが子どもらしいまっすぐな瞳を持った、かわいらしさを備えている。そしてもともと知り合いというのもあるのだろうか、とても結束力の高い七人なのだ。
(元気いっぱいな子どもたちだなあ)
誰からともなくそんな感想がこぼれるのもやむを得ない。
既に子どもという年齢をすぎてしまったハンターたちの多くからは、こんな子どもたちがひどくまぶしかった。
まあ、その分やんちゃ坊主たちから目を離したりするわけにも行かないのだけれど。
●
おあつらえ向きに、キャンプのすぐ近くには森も川もある。
やんちゃな子どもたちはさっそくそちらに行ってみたいと楽しそうに言った。
とはいえ、森や川にどんな危険が潜んでいるかは分からない。
もしかしたら雑魔が潜んでいる可能性だって、ゼロではないのだ。……まあ、ハンターオフィスが提示した場所だから、安全性についてはかなり自信を持てると言えばそうなのだが。
それでもよそ様の子どもをお預かりしているわけで、ヘタなことをして怪我の一つでもさせるわけには行かない。
雷蔵はチェックの意味合いを込めて森に入っていった。
昼下がりの時間帯ではあるが、森の中は少しばかり薄暗く、そして涼しさを感じさせる。
(……ん、あれは)
ぱっと目についたのは立派な木。雷蔵はこれが何の木か、すぐに気がついた。クヌギの木だ。
この時期、クヌギの木と言えばカブトムシをはじめとする昆虫たちが集まる格好の場所になっている。今は昼だからその気配はあまりないけれど、夜中や明け方にはきっと驚くくらいの量の虫たちが集まることだろう。
思いついて、雷蔵はこのクヌギに傷をつけた。じわり、と樹液がにじみ出す。
(こうやって少し傷をつけておいて……夜にまた来れば、それこそ色んな昆虫に出会えるかも知れない)
夏休みの課題で昆虫採集を行なうというのはリアルブルーでも良くあることだった。そうでなくても、カブトムシのような立派な虫を嫌う子どもはそう多くない。それなら、美味しいところ取りをするのがいいではないか、と言うのが結論である。
「……楽しみだな」
思わずそんな言葉が、口をついて出た。
一方川では何が起きているかというと――
白露らがそばにつきながら、川釣りをしていた。
小さい子たちは山菜採り。
皆白露の目の届くところで出来るコトだ。
詩はそのすきにキャンプファイヤーで使えそうな薪を集めに出る。それぞれの役割分担が決まっているから、逆に誰もが素直に従ってくれるのだ。
川魚はだいたいリアルブルーで摂れるものと酷似しており、アユ、ヤマメ、イワナなどと言ったものが釣れる。
山菜は毒草と見間違えないように気を付けながら、白露が指導していた。
むろんキノコの採取は禁止である。キノコとりはプロですら見分けがつかない毒キノコも多く、子どもたちがそれを実践するのはあまりに危険だからだ。
運のいいことにキャンプからすぐの川縁はよいつりのスポットであり、魚は針をおろせば入れ食いというように気持ちいいくらいに釣れていく。
しかし白露は必要量だけを確保したら、あとはキャッチアンドリリースにしていた。
「どうして捕まえないの?」
デュオに尋ねられると、白露は小さく笑う。
「この魚たちも生きているでしょう? たくさん取り過ぎてしまうとこの川から魚がいなくなってしまうかも知れないし、川に魚がいなくなることで川が汚れてしまうかも知れない。自然とのやりとりというのはこういう所も大切なんだよ」
その言葉はたしかに真摯なもので、子どもたちに命の大切さと環境保護の大切さを訴えるものだった。
じつのところ、クリムゾンウェストではまだそこまでエコロジーという発想が追いついていない。公害という概念は少しずつ生まれているが、それの浄化となるとまだまだ浸透していないのが実情である。
一部の辺境部族などでは逆に理解があるかも知れないが、そうでなければまだまだその真意を測ることができないのもまた事実であった。
だからこそ、こんな発想をするハンターたちの世界に対する思いの寄せ方というのが、少しばかり新鮮でもあった。
「折角だし、これも料理に使いたいよね」
新鮮な魚に、摘みたての山菜。
きっとこれらを使えば野趣溢れるキャンプ料理ができるはずだ。
釣りも山菜採りも適度なところでやめ、そのあとはひんやりとした川の水に足を浸す。暑い時分とは言え、自然の川の流れというのは心地のよいものなのだ。子どもたちは水をきらきらとまき散らしながら、川縁で遊んでいる。
深いところには入らないように、雷蔵と白露が見守っている。詩はもしもの時の救護役としてやはり近くに控えているし、悠月はと言えば思い立って近くで簡易ハンモックを拵えている。昼寝にはぴったりだろう。
よく見ると流れの上のほうには網には言った野菜や果物が浸してあり、きっと食べるときには冷たいのだろうなと思わせた。
「さて、ちょっと休憩にするか。冷やしてあるスイカでも食うか?」
雷蔵の声に、子どもたちは目を輝かせる。
自然の中でよく冷えたスイカを食べるなんて、なんて贅沢なのだろう! 子どもたちもその贅沢さははっきりと理解しているわけではなさそうだが、想像するだけで自然と口の中につばが湧き出てくる。
さっそく切ったスイカを食べると、しゃくりという歯触りが何とも冷たく心地よく、夏を満喫している気分になれた。子どもたちだけでなく、ハンターたちも。
ああ、それにハンターの連れてきたペットたちも、ずいぶんと子どもたちに懐いている。
白露の連れているコリーは特におとなしく愛らしく、子どもたちが何度も頭を撫でている。もともと牧羊犬であるコリーは頭も良い為、子どもたちの面倒を見るのも自分の役目の一つと認識したらしい。真面目な性分のコリーはおかげですっかり人気者だ。
ハンターは皆、子どもたちに優しい。それはきっとハンターたちも自分たちの子ども時代を思い出しているからだろう。
「おやつも食べたし、少し昼寝でもする? ハンモックを作ってみたんだけど」
悠月の言葉に、おやつでお腹もふくれた子どもたちはこっくり頷いていた。
●
昼寝は一時間。そのあとは夕食の仕度だ。
今回の夕食はハンター側であらかじめ決めてある。シチューだ。それに、さっきとった魚を塩焼きにしたり山菜をサラダのようにしたり、それだけで十分なご馳走と言えるだろう。
「折角だから、皆をあっと言わせるような美味しい料理にしようね」
詩がキャンプに参加している女の子たち、特に引っ込み思案なところのあるリマににっこりと微笑めば、彼女たちもこっくりと頷く。うまくできれば子どもたちにも自信がつくだろう。女の子は料理が得意である方が、なんだかんだいって自信に繋がるのだ。
それと――さっきまではあまり気づかなかったが、リマはときどきデュオのほうをちらちらと見ている。
ははあ、女の子はませていると言うけれど、なあるほど。
詩は納得して、そっとリマの肩をぽんっと叩く。一瞬少女は驚いたようだが、すぐにぱっと顔を赤く染めて頷いた。
(初恋かなぁ。可愛いなあ)
そんなことを思いながら、包丁の扱い方を教えていく詩であった。
――一方、白露はと言うと。
小料理屋を経営している、つまり料理の心得のある雷蔵の手伝いをしながら炎の扱い方を少年たちに教えているそのそばで作業をしていた。少年たちはやはり同じ男性である雷蔵に懐きがちだが、その雷蔵を含めたハンターたちがせっかくなら山菜もシチューの具にしてしまえと言うことで、あく抜きなどを教えているのが白露になっている感じだ。
ついでに白露は山菜採りの合間にみつけた食べられる木の実を水にさらしたりもしている。
焚き火はやがてあかあかと燃え上がり、その周囲に塩をまぶした川魚を串に刺して遠火で焼く。魚の素材の持ち味を生かすなら、やはり塩焼きが一番伝わりやすい。自分たちでとったものを自分たちで調理して食べる、それは子どもたちの心身の成長にも繋がるだろう。
「皆で作ればきっとおいしい物になるよね」
悠月もそばで微笑めば、子どもたちもこっくり頷く。
やがていい香りが周囲に立ちこめてきた。シチューのどこかとろみのある香り、魚の香ばしく焼ける香り、それに主食となる米の炊ける香り。
リアルブルーではキャンプの定番と言えばカレーだが、何しろこの世界には香辛料の供給がまだまだだ。今回は子どもたちを中心に皆でわいわい作れる料理と言うことでシチューにしたが、これが大人相手のものだったらもっと手の込んだものにしたことだろう。
それでも自分たちで作った料理を自分たちで食べるという行動は少年少女たちの心と身体の栄養をいっぱいに満たす行為であり、だからこそ誰もが満ち足りた顔をして嬉しそうに頬張るのだ。
白露のみつけた木の実をデザート代わりに差し出す。
「これ、食べられるの?」
見たことのあまりない木の実を差し出され、不思議そうに首をかしげる子どもたち。
「俺の家では狩猟で食をまかなっているからなぁ」
苦笑交じりに白露がそういうと、逆にハンターの生活というのに気になったらしいサトーやデュオが手にとって口に含む。
「……おいしい!」
ぱっと顔を輝かせる少年たち。
気づけばあっという間に料理はなくなっていた。
「ごちそうさまでした!」
そう手を合わせて言う子どもたちは、笑顔に満ち溢れていた。
そして食後はキャンプファイア。
詩が三味線の弾き語りをしたり、リアルブルーのフォークダンスを皆で披露したり。いわゆるレクリエーションの時間だ。
子どもたちは見慣れない異世界の文化に触れて、頬を赤く染めていた。
●
やがてテントの中では子どもたちがせがむようにしてハンターの体験談を聞きたがった。
「そうだなぁ……僕は冒険の話ばっかりになっちゃうけど」
悠月がそんなことを苦笑しながら、さまざまな冒険譚を語ると、少年たちは目を輝かせる。
あくびも聞こえるものの、誰もが興味津々になっている様子だ。
「……っと、そうだ。皆、ちょっと外に出てみないか?」
雷蔵はにやっと笑った。
空には満天の星。
特別な灯りとかも必要としないくらいに、きれいな星月夜。
雷蔵はそんな中を、すたすたと森に向かって歩いて行く。子どもたちはそんな雷蔵の後ろをついて行く。
たどり着いたのは――大きなクヌギの木。あらかじめ、雷蔵が傷をつけておいたものだ。
「あーっ、すごーい!」
子どもたちは目を輝かせてその木を見つめた。
何故かというと、そこにはカブトムシが数多くいたのだ。クヌギの樹液のために集まっている昆虫たちの姿に、驚きを隠せない。
「つかまえていい? いい?」
子どもたちは大興奮してハンターたちに尋ねる。
「必要以上に捕まえなければ大丈夫だよ」
悠月の言葉に子どもたちはわっと捕まえにかかる。でももちろん、虫を驚かせないように、逃がしてしまわないように。
雷蔵が試しに捕まえたところを見てコツを覚えた子どもたちは、さっそく捕まえてきらきらした笑顔を浮かべて見せた。
きっとこの満天の星空の下での思い出は、忘れられない物になるだろう。センなどはひどく興味深いという表情を隠しきれない。勉強好きの少年なら、きっと内心大喜びしているに違いなかった。
「子どもたちっていうのはすごく素直でいいね」
ひととおり疲れて子どもたちが眠ったあと、雷蔵は白露に話しかける。一人の女性として意識し始めている相手である白露への語りは、心なしか柔らかい。
「そうだ、ね。なんだか、こっちも心が洗われる感じ」
「本当、そうだな。子どもたちの世話も楽しいものだな」
そっと目を細める雷蔵に、白露もわずかに頬を染めながら小さく頷いた。
●
夢のような一泊二日。
少年少女たちは、ハンターに言われたとおり、綺麗にテントや調理台を片付け、ゴミも全部綺麗に処分した。
「立つ鳥跡を濁さず、って言葉もあるしね」
詩がそういうと、子どもたちも素直に頷く。
「でも、楽しかったよ、おにいちゃん、おねえちゃん」
「うん、すごいいい思い出になったよ」
「ありがとう、ハンターさん」
子どもたちの言葉はとても素直で、だからこそハンターたちもやり甲斐があって。
「こっちこそ、ありがとう」
そう言われて、しかし詩はにっこり笑った。
「ううん、帰りも気を緩めちゃ駄目だよ。家に帰るまでがキャンプなんだからね♪」
その言葉に、笑いのさざ波が起きた。
皆、楽しかった思い出は忘れられないだろう。
楽しい思い出は、きっと宝石なのだから。
いま、東方では大きな戦いの真っ最中。
だけれど、子どもにはそんな理屈は通用しない。
夏で、学舎も休みで、暇をもてあましているとなれば、本当ならばいつも以上に親にも甘えたいし、冒険だってしたい。
普段なら、親が子どもたちをサポートしながら遊んでくれたのだが、昨年来の歪虚の活性化によってそれも難しいのがくやしいけれど子どもたち――いや、クリムゾンウェスト全体の現状だ。
その結果、夏はどうやら子どもたち、このような緊張下の上に暑い盛りと言うこともあって、友達にも会わずに自宅や商店などの屋内でごろごろするくらいしかないのだという。……むろん例外はあるのだが。
今日は事前準備の為のハンターたちの顔合わせ。
偶然にも、集まったハンターは皆リアルブルー出身であった。もっとも、立場は各人様々である、のだが。
(……でも、遊びたい盛りの子どもたちにはやっぱりつまんないよね)
サマーキャンプの話を聞いて参加を申し出てくれたひとり、天竜寺 詩(ka0396)はそう思う。彼女自身先頃の東方における戦いにおいてかなりの怪我を負ってしまっているが、子どもたちの意見ももっともなのだ。
もともと彼女自身、リアルブルーではやや特殊な環境下――伝統芸能を伝える家系で育ち、幼少期から双子の姉ともどもその芸をたたき込まれてきた。それこそ、休みなんてお構いなしに、だ。だから、子どもたちの気持ちも分からなくない。むしろ、彼ら彼女らの訴えはしごくまっとうで、だからこそ応援したくなる。
「だから、子どもたち皆が楽しい思い出を作れるように……私もがんばらないとね!……ッたた……」
きゅっと拳を握るが、直ぐに引きつるような痛みがぶり返す。
治るとは言え、大怪我を負っているのは間違いない。気を張っていないと、直ぐにいたみが現れてしまう。実際、今もその姿は一部を包帯でくるまれており、少しばかり痛々しかった。
一方、同じリアルブルー出身でも、さまざまな家庭の事情というのはあるもので。
浪風 白露(ka1025)もやはりまた、きょうだいともどもリアルブルーから転移してきたハンターだが、サルヴァトーレ・ロッソ転移前から辺境でたくましく生活をしていた口である。
白露は次女だが、彼女がハンターとしての能力を振るうきっかけはやはり家族を護る為。と同時に、自分よりも何かと優れた兄や姉を見返すことができるのならば、と思っている。
ふだんから弟妹の世話などで子どもの扱いにはなれている方だ、とは思う。けれど、サバイバル感たっぷりな白露たち一家と、リゼリオに暮らすハンターの子どもたちとではそれなりに立場も違うし、そもそも生活のパターン、リズムが大きく異なる。
それに――
白露は脇に立つ灰色の髪の美丈夫、鬼塚 雷蔵(ka3963)をちらりと見やる。白露は雷蔵の営む小料理屋の顔なじみの一人でもあるが、もう一つ、白露は雷蔵のことを異性として気になっているという事実もあった。ほのかな想いとでも言えばいいのだろうか、しかしそれ故に白露の行動はいつもよりもどこかぎこちなさがぬぐえない。
雷蔵のほうはというと白露よりも年長であること、みずから店を営んでいることなどもあって落ち着いたものだ。
「……それにしても、子どもたちとのキャンプ引率か。楽しむのは当然としても実際に何が起るかは分からないし、安全第一を心がけていかないとな」
低い声でそういうと、白露はとくり、と高鳴りそうな胸を押さえながら頷き返す。
「は、はいっ」
そう返事をしたものの、声が裏返っていないか、不自然ではないか、そう言うことが妙に気になる。恋というのはそう言うものなのだ。
そんな白露の戸惑いを横目で見ながら、霧雨 悠月(ka4130)は、小さく微笑んでいた。リアルブルーからの転移者に間違いはないのだが、その前後の記憶が曖昧なせいだろうか、どこか不思議な目をしている。
「でもキャンプなんて楽しそうだね。キャンプ道具一式は借りられるのかな?」
悠月が問うと、ハンターオフィスの職員はもちろん、と頷いた。
もともとキャンプの引率を担当するわけで、しかもそれなりの人数ともなれば各人の所持金だけでどうにかなるわけでもない。それに今回はちゃんとしたハンターオフィスからの要請でもある。ギャランティも支払われるし、準備に必要な道具もまるっと用意してくれると約束してくれた。
「子どもたちとの対面は、当日のお楽しみと言うことで」
職員が言うと、ハンターたちも頷く。
「一体どんな子たちがいるんだろうね。きっと元気なんだろうなぁ」
誰かがそう呟くと、誰からともなく笑みが溢れた。
●
そして、約束の日がやってきた。
「こんにちはー!」
明るい子どもたちの声が、オフィスの前に響く。
待ち合わせはオフィス前――あらかじめ作成されていたしおりに書かれていたことだ。集まった子どもは全部で七人、上は十歳から下は七歳まで、はつらつとした子どもたちだ。
「ハンターの皆さんも忙しい中を来て頂いているんですから、ちゃんと挨拶をしましょうね」
ハンターオフィスの若い女性職員がそう微笑むと、
「よろしくおねがいしまーす!」
これまた元気な声でそう言い、ぺこりと頭を下げる。
「こちらこそ、よろしくな」
雷蔵の言葉に、子どもたちの顔はぱっと輝いた。
「えー、それじゃあみんなリアルブルーのひとなんですか!?」
歩きながら簡単な自己紹介をすませたあと、そんな驚きの声を上げたのは年長男子のサトーだ。彼自身ハンターへの憧れがあるらしく、いつかハンターになれる日をずっと狙っているらしい。
「……でも、リアルブルーからの転移者は多いって聞いていたけれど、こんな風に一度にたくさんのひとにあうことができるなんて思ってませんでした」
同じく最年長、サトーと同じ十歳の少女アンがそう言って笑顔を見せる。
サルヴァトーレ・ロッソの転移で一気にリアルブルーからの転移者ハンターは増えたとは言うものの、実際にあうとなるとまた話は別だ。
少年少女たちは瞳をキラキラさせながら、ハンターたちを憧れの眼差しで見つめている。リアルブルー出身のハンターばかりに護られてのキャンプというのは、たしかに余りにも新鮮だ。
「たのしみだね!」
「うん!」
ミチとデュオ、九歳の男女コンビが嬉しそうに語り合う。話を聞いていて分かったのだが、もともとハンターの親をもつ同士、彼ら七人は以前からの知り合い関係らしい。
その中でも特に行動力があるのはデュオ。この企画の発案者でもある所でそれはだいたい分かるというものだが。逆にサトーは好奇心旺盛ではあるが自分から動くタイプではないらしい。内向的と言うよりも、受動的と言うべきか。
「設営が終わったら、何かやりたいことはあるのかな?」
そう詩が尋ねてみると、
「お料理してみたい!」
ちびっ子たちからそんな声が。どうやらなかなか家では包丁を握らせて貰えないらしく、こういうときならばと言うもくろみでもあるらしい。
「夏休みの課題に使えるものとかないかなぁ」
そんな現実的なことをいうのはセンだ。年齢は比較的高く、学校では優等生らしいが、だからこそ宿題などにも手を抜けないタイプらしい。
クラスに一人はいるタイプだなあと、誰もが苦笑を浮かべる。
「やりたいことはいっぱいありすぎるよ!」
デュオはにっかりわらってそう答える。
「どっちにしても、テントと簡単な竈を作ってから、だけどね」
白露がそういうと、脇にいた雷蔵がわしわしと子どもたちの頭を撫でてやった。
「まあ、重いものを持ったりするのは俺たちも手伝うさ。そのためのハンターだしな。まあ、色々と楽しもうな」
その言葉に子どもたちも嬉しそうにこっくりと頷いた。
●
キャンプの為の場所は子どもの足でも十分問題なくたどり着ける距離だった。
皆疲れたとは言うものの、表情にまだ余裕が見受けられる。
ハンターオフィスから借り受けたキャンプ用具一式を広げて見せれば、子どもたちからも歓声が上がった。
「これがテント、これは御飯を炊く道具の飯ごうだね」
悠月が一つ一つ丁寧に紹介すると、へぇ―と言う歓声が漏れる。
そうだ、と白露が取り出したのは小さな、しかし涼しげな音のする鈴。人数分ある。
「もしかしたら何かがあってはぐれたりしてもいけないから、これをつけておいてね」
音がすればすぐに何らかの異変に気づけるかも知れないし、確かにいいアイデアだ。子どもたちはありがとうと口々に言いながら、ベルトやポケットにそれを着けてちりちりと鳴らして見せたりする。
しかし、まずは設営が第一だ。
「まあ、まずはテント作ろうな!」
「もし怪我したら、救急キットもあるから手当てするからね」
雷蔵と悠月、ふたりの男性陣に言われて、子どもたちも素直に頷いた。
ちなみにやはり悠月は始め男性と思われていなかったらしい。いつものこととは思いつつも、小さくため息をついたのはまあ仕方のないことなのだろうが。
「それじゃあ、この柱になる部分を支えてくれないか。ああ、こっちは縄をぴんと張って、くい打ちしないとな」
こういうときに頼りになるのはやはり男性。子どもたちも言われるとおり、丁寧に手伝っていく。
いっぽう、まだ幼くてテント設営の手伝いが難しいリマとリクの双子は、詩や白露といっしょに簡易かまどの作成の手伝いだ。近くの瓦に落ちている石を拾い集め、それを使ってかまどを作る。重い石については詩たちも運ぶのを手伝っているし、こちらもこちらで順調に仕上がっていた。
やがてテントができあがる頃にはかまどもできあがり、子どもたちも満足そうに笑うことになる。
自分たちで作る非日常の生活というのが、子どもたちには十分どきどきの対象になっているらしい。
おとなしめの子どもたちも、周囲に引きずられてテンションが少しずつ上がっている。こういう場所ではテンションが上がらない方が損なのだ。
労働のあとの心地よい汗を掻きながら、子どもたちもハンターも、すっかり笑顔を浮かべている。
作業の合間に話をしていて、七人の性格は大まかにつかめた。
リーダー格で元気溢れるデュオ。
最年長、将来の夢はハンターだというサトー。
サトーと同い年だが気配り上手の少女、アン。
アンの弟で、趣味は読書というどちらかというとインテリ肌のセン。
少年に負けず劣らずの元気娘で姉御肌なところのあるミチ。
双子のリマとリクは最年少、リマは少し病がちなところがあるぶんリクがフォローをしていたりすると言う関係。
そして誰もが子どもらしいまっすぐな瞳を持った、かわいらしさを備えている。そしてもともと知り合いというのもあるのだろうか、とても結束力の高い七人なのだ。
(元気いっぱいな子どもたちだなあ)
誰からともなくそんな感想がこぼれるのもやむを得ない。
既に子どもという年齢をすぎてしまったハンターたちの多くからは、こんな子どもたちがひどくまぶしかった。
まあ、その分やんちゃ坊主たちから目を離したりするわけにも行かないのだけれど。
●
おあつらえ向きに、キャンプのすぐ近くには森も川もある。
やんちゃな子どもたちはさっそくそちらに行ってみたいと楽しそうに言った。
とはいえ、森や川にどんな危険が潜んでいるかは分からない。
もしかしたら雑魔が潜んでいる可能性だって、ゼロではないのだ。……まあ、ハンターオフィスが提示した場所だから、安全性についてはかなり自信を持てると言えばそうなのだが。
それでもよそ様の子どもをお預かりしているわけで、ヘタなことをして怪我の一つでもさせるわけには行かない。
雷蔵はチェックの意味合いを込めて森に入っていった。
昼下がりの時間帯ではあるが、森の中は少しばかり薄暗く、そして涼しさを感じさせる。
(……ん、あれは)
ぱっと目についたのは立派な木。雷蔵はこれが何の木か、すぐに気がついた。クヌギの木だ。
この時期、クヌギの木と言えばカブトムシをはじめとする昆虫たちが集まる格好の場所になっている。今は昼だからその気配はあまりないけれど、夜中や明け方にはきっと驚くくらいの量の虫たちが集まることだろう。
思いついて、雷蔵はこのクヌギに傷をつけた。じわり、と樹液がにじみ出す。
(こうやって少し傷をつけておいて……夜にまた来れば、それこそ色んな昆虫に出会えるかも知れない)
夏休みの課題で昆虫採集を行なうというのはリアルブルーでも良くあることだった。そうでなくても、カブトムシのような立派な虫を嫌う子どもはそう多くない。それなら、美味しいところ取りをするのがいいではないか、と言うのが結論である。
「……楽しみだな」
思わずそんな言葉が、口をついて出た。
一方川では何が起きているかというと――
白露らがそばにつきながら、川釣りをしていた。
小さい子たちは山菜採り。
皆白露の目の届くところで出来るコトだ。
詩はそのすきにキャンプファイヤーで使えそうな薪を集めに出る。それぞれの役割分担が決まっているから、逆に誰もが素直に従ってくれるのだ。
川魚はだいたいリアルブルーで摂れるものと酷似しており、アユ、ヤマメ、イワナなどと言ったものが釣れる。
山菜は毒草と見間違えないように気を付けながら、白露が指導していた。
むろんキノコの採取は禁止である。キノコとりはプロですら見分けがつかない毒キノコも多く、子どもたちがそれを実践するのはあまりに危険だからだ。
運のいいことにキャンプからすぐの川縁はよいつりのスポットであり、魚は針をおろせば入れ食いというように気持ちいいくらいに釣れていく。
しかし白露は必要量だけを確保したら、あとはキャッチアンドリリースにしていた。
「どうして捕まえないの?」
デュオに尋ねられると、白露は小さく笑う。
「この魚たちも生きているでしょう? たくさん取り過ぎてしまうとこの川から魚がいなくなってしまうかも知れないし、川に魚がいなくなることで川が汚れてしまうかも知れない。自然とのやりとりというのはこういう所も大切なんだよ」
その言葉はたしかに真摯なもので、子どもたちに命の大切さと環境保護の大切さを訴えるものだった。
じつのところ、クリムゾンウェストではまだそこまでエコロジーという発想が追いついていない。公害という概念は少しずつ生まれているが、それの浄化となるとまだまだ浸透していないのが実情である。
一部の辺境部族などでは逆に理解があるかも知れないが、そうでなければまだまだその真意を測ることができないのもまた事実であった。
だからこそ、こんな発想をするハンターたちの世界に対する思いの寄せ方というのが、少しばかり新鮮でもあった。
「折角だし、これも料理に使いたいよね」
新鮮な魚に、摘みたての山菜。
きっとこれらを使えば野趣溢れるキャンプ料理ができるはずだ。
釣りも山菜採りも適度なところでやめ、そのあとはひんやりとした川の水に足を浸す。暑い時分とは言え、自然の川の流れというのは心地のよいものなのだ。子どもたちは水をきらきらとまき散らしながら、川縁で遊んでいる。
深いところには入らないように、雷蔵と白露が見守っている。詩はもしもの時の救護役としてやはり近くに控えているし、悠月はと言えば思い立って近くで簡易ハンモックを拵えている。昼寝にはぴったりだろう。
よく見ると流れの上のほうには網には言った野菜や果物が浸してあり、きっと食べるときには冷たいのだろうなと思わせた。
「さて、ちょっと休憩にするか。冷やしてあるスイカでも食うか?」
雷蔵の声に、子どもたちは目を輝かせる。
自然の中でよく冷えたスイカを食べるなんて、なんて贅沢なのだろう! 子どもたちもその贅沢さははっきりと理解しているわけではなさそうだが、想像するだけで自然と口の中につばが湧き出てくる。
さっそく切ったスイカを食べると、しゃくりという歯触りが何とも冷たく心地よく、夏を満喫している気分になれた。子どもたちだけでなく、ハンターたちも。
ああ、それにハンターの連れてきたペットたちも、ずいぶんと子どもたちに懐いている。
白露の連れているコリーは特におとなしく愛らしく、子どもたちが何度も頭を撫でている。もともと牧羊犬であるコリーは頭も良い為、子どもたちの面倒を見るのも自分の役目の一つと認識したらしい。真面目な性分のコリーはおかげですっかり人気者だ。
ハンターは皆、子どもたちに優しい。それはきっとハンターたちも自分たちの子ども時代を思い出しているからだろう。
「おやつも食べたし、少し昼寝でもする? ハンモックを作ってみたんだけど」
悠月の言葉に、おやつでお腹もふくれた子どもたちはこっくり頷いていた。
●
昼寝は一時間。そのあとは夕食の仕度だ。
今回の夕食はハンター側であらかじめ決めてある。シチューだ。それに、さっきとった魚を塩焼きにしたり山菜をサラダのようにしたり、それだけで十分なご馳走と言えるだろう。
「折角だから、皆をあっと言わせるような美味しい料理にしようね」
詩がキャンプに参加している女の子たち、特に引っ込み思案なところのあるリマににっこりと微笑めば、彼女たちもこっくりと頷く。うまくできれば子どもたちにも自信がつくだろう。女の子は料理が得意である方が、なんだかんだいって自信に繋がるのだ。
それと――さっきまではあまり気づかなかったが、リマはときどきデュオのほうをちらちらと見ている。
ははあ、女の子はませていると言うけれど、なあるほど。
詩は納得して、そっとリマの肩をぽんっと叩く。一瞬少女は驚いたようだが、すぐにぱっと顔を赤く染めて頷いた。
(初恋かなぁ。可愛いなあ)
そんなことを思いながら、包丁の扱い方を教えていく詩であった。
――一方、白露はと言うと。
小料理屋を経営している、つまり料理の心得のある雷蔵の手伝いをしながら炎の扱い方を少年たちに教えているそのそばで作業をしていた。少年たちはやはり同じ男性である雷蔵に懐きがちだが、その雷蔵を含めたハンターたちがせっかくなら山菜もシチューの具にしてしまえと言うことで、あく抜きなどを教えているのが白露になっている感じだ。
ついでに白露は山菜採りの合間にみつけた食べられる木の実を水にさらしたりもしている。
焚き火はやがてあかあかと燃え上がり、その周囲に塩をまぶした川魚を串に刺して遠火で焼く。魚の素材の持ち味を生かすなら、やはり塩焼きが一番伝わりやすい。自分たちでとったものを自分たちで調理して食べる、それは子どもたちの心身の成長にも繋がるだろう。
「皆で作ればきっとおいしい物になるよね」
悠月もそばで微笑めば、子どもたちもこっくり頷く。
やがていい香りが周囲に立ちこめてきた。シチューのどこかとろみのある香り、魚の香ばしく焼ける香り、それに主食となる米の炊ける香り。
リアルブルーではキャンプの定番と言えばカレーだが、何しろこの世界には香辛料の供給がまだまだだ。今回は子どもたちを中心に皆でわいわい作れる料理と言うことでシチューにしたが、これが大人相手のものだったらもっと手の込んだものにしたことだろう。
それでも自分たちで作った料理を自分たちで食べるという行動は少年少女たちの心と身体の栄養をいっぱいに満たす行為であり、だからこそ誰もが満ち足りた顔をして嬉しそうに頬張るのだ。
白露のみつけた木の実をデザート代わりに差し出す。
「これ、食べられるの?」
見たことのあまりない木の実を差し出され、不思議そうに首をかしげる子どもたち。
「俺の家では狩猟で食をまかなっているからなぁ」
苦笑交じりに白露がそういうと、逆にハンターの生活というのに気になったらしいサトーやデュオが手にとって口に含む。
「……おいしい!」
ぱっと顔を輝かせる少年たち。
気づけばあっという間に料理はなくなっていた。
「ごちそうさまでした!」
そう手を合わせて言う子どもたちは、笑顔に満ち溢れていた。
そして食後はキャンプファイア。
詩が三味線の弾き語りをしたり、リアルブルーのフォークダンスを皆で披露したり。いわゆるレクリエーションの時間だ。
子どもたちは見慣れない異世界の文化に触れて、頬を赤く染めていた。
●
やがてテントの中では子どもたちがせがむようにしてハンターの体験談を聞きたがった。
「そうだなぁ……僕は冒険の話ばっかりになっちゃうけど」
悠月がそんなことを苦笑しながら、さまざまな冒険譚を語ると、少年たちは目を輝かせる。
あくびも聞こえるものの、誰もが興味津々になっている様子だ。
「……っと、そうだ。皆、ちょっと外に出てみないか?」
雷蔵はにやっと笑った。
空には満天の星。
特別な灯りとかも必要としないくらいに、きれいな星月夜。
雷蔵はそんな中を、すたすたと森に向かって歩いて行く。子どもたちはそんな雷蔵の後ろをついて行く。
たどり着いたのは――大きなクヌギの木。あらかじめ、雷蔵が傷をつけておいたものだ。
「あーっ、すごーい!」
子どもたちは目を輝かせてその木を見つめた。
何故かというと、そこにはカブトムシが数多くいたのだ。クヌギの樹液のために集まっている昆虫たちの姿に、驚きを隠せない。
「つかまえていい? いい?」
子どもたちは大興奮してハンターたちに尋ねる。
「必要以上に捕まえなければ大丈夫だよ」
悠月の言葉に子どもたちはわっと捕まえにかかる。でももちろん、虫を驚かせないように、逃がしてしまわないように。
雷蔵が試しに捕まえたところを見てコツを覚えた子どもたちは、さっそく捕まえてきらきらした笑顔を浮かべて見せた。
きっとこの満天の星空の下での思い出は、忘れられない物になるだろう。センなどはひどく興味深いという表情を隠しきれない。勉強好きの少年なら、きっと内心大喜びしているに違いなかった。
「子どもたちっていうのはすごく素直でいいね」
ひととおり疲れて子どもたちが眠ったあと、雷蔵は白露に話しかける。一人の女性として意識し始めている相手である白露への語りは、心なしか柔らかい。
「そうだ、ね。なんだか、こっちも心が洗われる感じ」
「本当、そうだな。子どもたちの世話も楽しいものだな」
そっと目を細める雷蔵に、白露もわずかに頬を染めながら小さく頷いた。
●
夢のような一泊二日。
少年少女たちは、ハンターに言われたとおり、綺麗にテントや調理台を片付け、ゴミも全部綺麗に処分した。
「立つ鳥跡を濁さず、って言葉もあるしね」
詩がそういうと、子どもたちも素直に頷く。
「でも、楽しかったよ、おにいちゃん、おねえちゃん」
「うん、すごいいい思い出になったよ」
「ありがとう、ハンターさん」
子どもたちの言葉はとても素直で、だからこそハンターたちもやり甲斐があって。
「こっちこそ、ありがとう」
そう言われて、しかし詩はにっこり笑った。
「ううん、帰りも気を緩めちゃ駄目だよ。家に帰るまでがキャンプなんだからね♪」
その言葉に、笑いのさざ波が起きた。
皆、楽しかった思い出は忘れられないだろう。
楽しい思い出は、きっと宝石なのだから。
依頼結果
| 依頼成功度 | 成功 |
|---|
| 面白かった! | 4人 |
|---|
ポイントがありませんので、拍手できません
現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。
あなたの拍手がマスターの活力につながります。
このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!
MVP一覧
重体一覧
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2015/08/10 01:00:26 |
|
|
相談卓だよ 天竜寺 詩(ka0396) 人間(リアルブルー)|18才|女性|聖導士(クルセイダー) |
最終発言 2015/08/11 21:28:20 |
||
















