ゲスト
(ka0000)
白いボールを追いかけろ!
マスター:四月朔日さくら
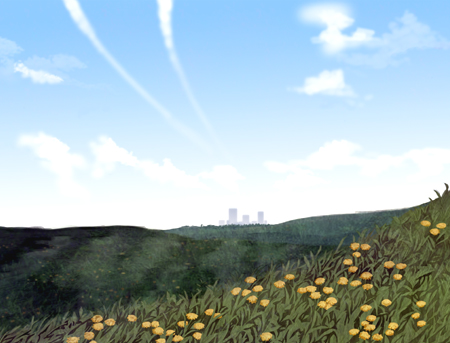
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 1,000
1,000- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~7人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2014/07/02 12:00
- 完成日
- 2014/07/07 21:17
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●
父さんは転移者だ。
クリムゾンウェスト出身の母さんと一緒になって、僕が生まれたわけだけど、父さんは時々リアルブルーのことを懐かしそうに話してくれた。
その父さんに色々教えてもらったこともあって、気づけばぼくもリアルブルーが第二の故郷のように感じるようになっていた。
そんな時だった。
あのサルヴァトーレ・ロッソの話を聞いたのは。
●
今日も今日とてリゼリオのハンターズソサエティは人の出入りが激しい。そんな中、一人の青年が熱弁を振るっていた。
「父さんから昔聞いたことがあるんです。リアルブルーでは、ボールを使って体を動かす人気のスポーツがあるって!」
……非常に曖昧極まりないが、とにかくスポーツの話題らしい。それを聞いたリアルブルー出身のハンターが、ああ、と頷いた。
「たしかにリアルブルーじゃあ、スポーツ選手が職業として成り立ってたけどな。それで稼げるのは、あくまで一握りだぜ」
しかしその言葉に、青年は目を丸くする。
「スポーツで身を立てる人もいるんですね……! どんなスポーツなんですか?」
茶色い髪に茶色い瞳という凡庸な雰囲気のの青年に、黒髪黒目、リアルブルーの極東によくみられる風貌のハンターは、
「たいがいのスポーツであるな。まあ、有名なのは野球やサッカーかな」
「野球……!」
その言葉は青年をひどく刺激したようだった。
「父さんがよく言っていたのも、野球でした。もし良かったら、野球について教えてくれませんか?」
しかしハンターは、ニヤリと笑う。そしてちょいちょいと依頼受付窓口を指さした。
「そういうのは、ちゃんと筋を通してからだな。あいにく俺はこれから別件の依頼があるが、きっと教えてくれる人はいるだろうさ。もしかしたら他にも知りたいってやつもいるかも知れねぇし、こういうのは依頼するに限ると思うぜ?」
青年は目を再び輝かせる。そして窓口に向かい――
「僕に、野球を教えて下さい!」
それはそれはひどく楽しそうに、そう言った。
父さんは転移者だ。
クリムゾンウェスト出身の母さんと一緒になって、僕が生まれたわけだけど、父さんは時々リアルブルーのことを懐かしそうに話してくれた。
その父さんに色々教えてもらったこともあって、気づけばぼくもリアルブルーが第二の故郷のように感じるようになっていた。
そんな時だった。
あのサルヴァトーレ・ロッソの話を聞いたのは。
●
今日も今日とてリゼリオのハンターズソサエティは人の出入りが激しい。そんな中、一人の青年が熱弁を振るっていた。
「父さんから昔聞いたことがあるんです。リアルブルーでは、ボールを使って体を動かす人気のスポーツがあるって!」
……非常に曖昧極まりないが、とにかくスポーツの話題らしい。それを聞いたリアルブルー出身のハンターが、ああ、と頷いた。
「たしかにリアルブルーじゃあ、スポーツ選手が職業として成り立ってたけどな。それで稼げるのは、あくまで一握りだぜ」
しかしその言葉に、青年は目を丸くする。
「スポーツで身を立てる人もいるんですね……! どんなスポーツなんですか?」
茶色い髪に茶色い瞳という凡庸な雰囲気のの青年に、黒髪黒目、リアルブルーの極東によくみられる風貌のハンターは、
「たいがいのスポーツであるな。まあ、有名なのは野球やサッカーかな」
「野球……!」
その言葉は青年をひどく刺激したようだった。
「父さんがよく言っていたのも、野球でした。もし良かったら、野球について教えてくれませんか?」
しかしハンターは、ニヤリと笑う。そしてちょいちょいと依頼受付窓口を指さした。
「そういうのは、ちゃんと筋を通してからだな。あいにく俺はこれから別件の依頼があるが、きっと教えてくれる人はいるだろうさ。もしかしたら他にも知りたいってやつもいるかも知れねぇし、こういうのは依頼するに限ると思うぜ?」
青年は目を再び輝かせる。そして窓口に向かい――
「僕に、野球を教えて下さい!」
それはそれはひどく楽しそうに、そう言った。
リプレイ本文
●
「スポーツで金を稼ぐという発想はありませんでした! さすがリアルブルーです!」
今回の話を聞いて、目を輝かせているのはマーヤ・クランツ(ka1132)。帝国出身の少女だが、リアルブルーへの憧れは人一倍だ。
野球というスポーツは、クリムゾンウェストでは存在しない。いや厳密に言うと類似したスポーツはあるのかもしれないが、少なくとも市井で普及しているとはとても言えない。
何しろ、今回参加したクリムゾンウェスト出身者はほとんどが名前すら知らない状態だったのだから。
スポーツということで動きやすい服装に身を包んだエルフの少女は、あどけなさの抜けきらぬ声で、しかし礼儀正しく挨拶をした。
「エルバッハ・リオン(ka2434)です、エルと呼んでください。どうぞ、今日はよろしくお願いします」
エルバッハというのは彼女の家の長子に付けられる由緒正しい名前――なのだが、エルはその名前をあまり好んでいないらしい。愛称で呼ぶようにというその挨拶が、それを暗に示している。しかし、その表情は朗らかだ。運動で汗をかくだろうからと飲み物などまで用意してくれていた。その裏でちょっとした悪戯心が騒ぐのも事実ではあったが。このエルという少女、年齢や体格よりも大きめな胸をわざと強調してみせるという癖があるのだ。
(あまり露骨なやり方は悪手ですし……どうしましょうか)
少女はそっとほくそ笑む。
一方のリアルブルー出身者はというと、どこか懐かしそうな顔をしていた。
「野球かぁ……」
夕影 風音(ka0275)が思い出すのは、男の幼馴染と混じって泥だらけになるまで遊んでいた懐かしい日々。
とは言えそんなリアルブルーでも野球は男性のスポーツという認識がかつては大きかった。最近は男女の関係が見直され、あらためられているらしいらしいが。プロとは言いがたいが、女性のみの野球チームの世界大会なども開催されていて、それにかける女性選手も多いらしい。
今回の参加者も偶然か、クロード・エクルストン(ka1683)以外は全員女性である。エクラの敬虔な信徒である彼は、リアルブルーで人気と聞いて楽しいスポーツであろうと思っているらしい。
確かに野球は楽しい。実際にプレイする以外でも、観戦したり、野球を題材にした読み物などを鑑賞したり、さまざまな楽しみ方が存在する。
「そう言えば、この間偶然手に入れたのですが……」
そう言いながらクロードが取り出したもの、それは最近始まったハンターズソサエティでの支給品に入っていたバットだった。
「名前と、野球に使うというのはわかったのですが、一体どう使うのでしょうか。手に馴染む感触は武器としても使えそうですけれど……まさか殴り合いに?」
そんな発想にたどり着いてしまうのも仕方ないかもしれない。リアルブルー出身のアマリ・ユーナ (ka0218)がクスクスと笑いながら説明する。
「そうね、そういえばこちらの人が知らないから来たのですっけ。知らないのなら仕方ないかもしれないわね……これは投げたボールを振って当てて遠くへ飛ばすための棒なのよ。まあ、どちらにしてもルールの説明と軽い練習は必要よね」
言われてなるほどと頷くクロード。そしてそれを今回の依頼人である青年・タイガに手渡した。
「タイガさん、よろしかったらこのバットを使ってみてください。今日はタイガさんが主役なのですからね」
タイガはそれを受け取るが、まだどうすればいいのかわかりかねているようにみえた。
言われてみれば名前と概要しか知らないクリムゾンウェストの面々。ボールを使って遊ぶ、それを専門にした職業が存在する等、イメージが曖昧模糊としている。
「そもそも、バットとボールだけでは出来ないと父から聞いているのですが。あと人数」
首を小さく傾げるタイガ。
「そうだね、そこから話さないといけないな」
その反応を見て、Charlotte・V・K(ka0468)がやんわりと頷いた。このクリムゾンウェストという異世界・異文化との交流も、ハンターとして暮らしているリアルブルー人たる者のつとめだろう。隣に立っていた風音と目配せし合い、説明を始める。
「まずチームは二チーム九人ずつで行う。攻める側と守る側があって、ボールと呼ばれる球状のものを、バットと呼ばれる棒で打つ。ボールが戻ってくるまでに、所定の位置まで移動する……こんな感じかな?」
シャルロッテがそこまで言うと、一息ついた。
何の気なしに見知っていたものを噛み砕いて説明するのはなかなかに骨である。それでもクリムゾンウェストの若者たちは熱心に聞いてくれる上に、それをきちんと理解しようとしてくれている。マーヤなどはそれこそ集中して聞いているため、顔つきも変わっている。
「ボールを投げる側が守備。そして攻撃側がバットを振ることになります。これが基本的な流れ」
シャルロッテの話を受けて、風音はどこで仕込んだのか度の入っていないメガネをスチャッと掛け、ちょっぴりお姉さんぽく話をする。なかなかに似合っていて、いかにも頭脳明晰そうに見える。
「だから、バットでボールを遠くまで打てば打つほど、有利になるといった感じだね。基本的なルールはこのくらい。細かいルールまで説明してたらきりがないけど、この基本を知っていれば何とかできるからね」
シャルロッテは頷きながら、バットを軽くスイングする。
「ああ、バットというのはそうやって振るんですね」
クロードが目から鱗、というように呟いた。
「うん、バットでボールを打つときは、こうやって振るんだ。まずはお手本……になるかどうかはともかく、ちょっと試してみたいと思う」
「そうよね。今は楽しむほうが大事!」
アマリもにっこり笑っていうが、思うのは野球好きだったというタイガの父親のこと。
(九人揃ってから教える――ってことは、やっぱり試合をさせたかったのかしら? 今すぐにはムリだろうけれど、もし出来ることならそっちの願いもいつか叶えてあげたいわね)
まずは白球を追うことの楽しさをクリムゾンウェストの人にも知ってもらうこと、それが大事なのだろうから。
●
最初のデモンストレーションは、シャルロッテと風音で行うキャッチボール。
握りこぶしより少し大きいくらいのボールを投げては受け取り、返すように投げてそれをまた受け取る。ごくごくシンプルな運動だが、慣れていないとやはり取りこぼしも発生してしまう。
何事も基礎が大事なのだ。
それを見て目を輝かせているのは、エルフの少女テルヒルト(ka0963)だ。ルールの説明や道具の使い方を聞くだけでもちんぷんかんぷん、頭から煙がでそうだったけれども、実際にその光景を目にすれば飲み込みは早い。
百聞は一見にしかず、という言葉があるように、やはり見たり体験したりするのが何よりの早道なのだ。
そしてまた同時に、案ずるより産むが易しという言葉もある。
実際にボールに触れ、身体を動かしてみれば、予想を大きく上回る勢いで楽しさがついて回る。
バットを振るのはまだ危なっかしいが、おおまかな守備位置については解説した。人数的に九人いないのは少し残念な話だが、ルールについてはあらかた納得してくれたようで風音としても一安心である。練習についてもいろいろ考えはするものの、飲み込みの早い――つまりそれだけ好奇心旺盛なクリムゾンウェストの住人たちにはそんなためらいなど必要なかったようだ。
戯れにボールのようなものを投げるくらいのことは、例外はあれどもクリムゾンウェストの子どもたちだってする。コツさえ掴めてしまえばなんということもない。手にはマーヤ曰く『ユニークな形』の即席グラブをつけ、ヒョイッとボールを投げることくらいはできるのだ。
ただ、野球では『コントロール』が大事になる。ボールを思った方向へ投げられるかというと、それはただ投げるだけ、という訳にはいかない。
実際テルヒルトはボールを投げるのがはじめて。緊張のせいかやや力みがちになりながらも手をブンブンと振り、
「いっくぞー!」
と投げては見たものの、思うようにボールは飛んでいかない。力みすぎて逆にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、逆に力の入れ方が不十分だとボールは手の中からすっぽ抜けて、やはりあらぬ方向へと行ってしまう。
ついでに言うと、エルはタイミングを見計らうようにして身体を軽く上下に動かし、胸をわずかに揺らしてみる。必要そうに見えて必要のない動きなのだが、これがこうかを奏したかというと――残念ながら女ばかりの上に依頼人は野球に夢中、唯一の男性ハンターであるクロードはそういう色ごとに対しては興味をあまり持っていないという有り様。まあその代わりクロードは、どんなに怪我を負ったとしても微笑を浮かべている。たとえボールを身体で受け止めたとしても、むしろそれが試練であるかのように見えてしまうのは、彼が聖導士という立場というのもあるのだろう。しかしその実彼が笑顔を絶やさない理由はもう少し違うところにあるのだが、……口に出すのも野暮というものだ。
一方で風音はバットのスイングの仕方を指導する。タイガなどはそわそわしながらバットを握り、指導をしっかり聞きながら振るう。
「違うわ、ここはこうするの。……そうそう、そんな感じ」
タイガが言われるままにバットを動かせば、こつんと何かがバットに当たる鈍い感触。
「あ、なにか当たった……!」
たとえそれがほんのぼてぼてゴロに過ぎなくても、当てたという事実は揺るがない。それが嬉しくて、タイガはぱあっと顔を明るくさせた。
●
時間はかかったものの、キャッチボールを続けていくうちに身体が慣れてきたのだろう、ボールが最初の頃よりもイメージした場所に届くようになってきた。素振りもなかなか様になってきたように見える。
「うん、そろそろ実践形式の練習に移っても大丈夫かしら?」
アマリがそう頷くと、
「でもここには八人しかいませんよ。どうするんですか?」
タイガが問う。たしかにここには八人――野球は一チーム九人で行うスポーツだから、圧倒的に人数が足りない。しかしアマリはフフンと笑う。
「実践をやる――とは言ったけれど、試合をやるとは言ってないわ。実践に必要なのは投手、保守、それに打者……といったところかしら。私は審判兼応援に回ろうかと思うけど」
明確なルールがあるからには、それを判定するレフェリーは欠かせない。アマリは運動が得意な方ではないが、ルールは十分に理解しているし、それに醍醐味を教える立場の必要性を感じたのだ。
醍醐味とは、つまり野球をプレイする際にどういう行動を取れば面白いかということ。外から見てそれを説明する位置に一人はいたほうがいいだろうということだった。
シャルロッテはふむ、と頷くと、
「まずは全員ひととおりのポジションを楽しめるようにローテーションしてみようか。それも醍醐味がわかるヒントになるかもしれない」
そして何の変哲もない原っぱに、ベースなどをおおよそ配置せねばなるまい。つかの間の休憩、風音はふとタイガに問う。
「タイガ君のお父さんって転移者さんなんだって? こっちの世界でパートナーを見つけて、タイガ君を授かったんだね……なんだかロマンチック」
すると、タイガは苦笑した。
「でも、父さんは馴染みきれなかったんじゃないかな。あの船の噂を聞くだけでも、リアルブルーとクリムゾンウェストの違いがすごくわかるし」
「……そっか、そうかもしれないね。でもね、」
風音は微笑した。
「確かにすごく大変だったと思う。私は幼なじみや弟妹がいなかったら、きっと耐えられなかったもの。そんな中で、タイガ君のお父さんはちゃんとこの世界に自分の足跡を残してる。勝手な考えかもだけど、それはやっぱり素敵なことだと思うわ」
タイガはわずかに照れてから、小さく頷いた。
「……ありがとう。そう言ってくれて」
●
そしてどこか部活動っぽいノリで練習は再開された。まず投げるのはシャルロッテ、捕手は風音というバッテリー。打者席に立つのはタイガ――依頼主が優先というわけである。他のハンター達は、もしボールが飛んできた時のためにグラブをつけ、所定のポジションで待ち構えている。
「さて、打ち取れるかな?」
シャルロッテが小さく笑う。アマリは遠くを指さして、
「高く遠く打ち返したら、ホームラン。無条件で点が入るわ」
そしてそれが打者の最高の醍醐味だ、とも伝える。しかしスイングは虚しく空を切り、空振り三振と相成った。
「――そして投手の醍醐味は、打ち返そうとする打者を空振り三振にすること」
アマリがまた解説する。
「なるほど、これは難しいですね」
内野守備位置にいたクロードが苦笑気味につぶやく。
確かに当てるだけでも難しいのに、更に守備に取られないようにしないといけないわけだから、難しいどころではない。
「しかし奥深い。面白いスポーツですね」
「私も同感です」
エルも手を振りながら言う。野球を知りたいのも本心だから、行動自体はごく真面目なのだ。
「ちゃんとチームがあったりしたら、機会さえあればきちんと遊んでみたいです」
本心からの言葉。見た目は半端に成熟気味だが、中身はまだ少女なのだ。
「まだまだ練習中ですけどね」
ボールを投げるのも打つのも、どれも独特で面白い。それは共通認識らしく、
「バットをこうやって握ればなんだかうまく飛びそうですし、打たれたボールを追いかけるのも面白いです。こういうスポーツって、はじめてです」
マーヤが目をキラキラと輝かせて話す。それは嬉しそうに。以前よりリアルブルーに興味あったマーヤからすれば、もっと知りたいというのも道理だろう。
「ほら、テルヒルトさんも!」
皆に促されてバットを握るテルヒルト、クロードのアドバイスを受けて短く握り、タイガの投げる球を思い切り打ち返す――!
●
「どうもありがとうございました。ボールを打たれるとこんなに悔しいんですね……!」
ボールを打たれたタイガは、しかし清々しい表情だった。
「父さんがこのスポーツを愛していたわけもなんとなくわかりました。皆で夢中になれる、そんなスポーツなんですね」
その言葉に風音は微笑んだ。思いは通じたのだ。
「その気があるのなら、チームを作る手伝いも楽しそうね。とりあえず二チームあれば試合はできるし。こちらの世界で野球を普及させるのも素敵でしょう?」
アマリが笑えば、シャルロッテも頷く。
「そのうちロッソに野球の試合録画があるか聞いてみようか。プロの迫力はまた違うだろうしね」
「何から何までありがとうございます」
タイガは深く、礼をした。
白いボールを追いかけて、野球という名のゲームをしよう。
きっとあなたも、夢中になれるはずだから。
「スポーツで金を稼ぐという発想はありませんでした! さすがリアルブルーです!」
今回の話を聞いて、目を輝かせているのはマーヤ・クランツ(ka1132)。帝国出身の少女だが、リアルブルーへの憧れは人一倍だ。
野球というスポーツは、クリムゾンウェストでは存在しない。いや厳密に言うと類似したスポーツはあるのかもしれないが、少なくとも市井で普及しているとはとても言えない。
何しろ、今回参加したクリムゾンウェスト出身者はほとんどが名前すら知らない状態だったのだから。
スポーツということで動きやすい服装に身を包んだエルフの少女は、あどけなさの抜けきらぬ声で、しかし礼儀正しく挨拶をした。
「エルバッハ・リオン(ka2434)です、エルと呼んでください。どうぞ、今日はよろしくお願いします」
エルバッハというのは彼女の家の長子に付けられる由緒正しい名前――なのだが、エルはその名前をあまり好んでいないらしい。愛称で呼ぶようにというその挨拶が、それを暗に示している。しかし、その表情は朗らかだ。運動で汗をかくだろうからと飲み物などまで用意してくれていた。その裏でちょっとした悪戯心が騒ぐのも事実ではあったが。このエルという少女、年齢や体格よりも大きめな胸をわざと強調してみせるという癖があるのだ。
(あまり露骨なやり方は悪手ですし……どうしましょうか)
少女はそっとほくそ笑む。
一方のリアルブルー出身者はというと、どこか懐かしそうな顔をしていた。
「野球かぁ……」
夕影 風音(ka0275)が思い出すのは、男の幼馴染と混じって泥だらけになるまで遊んでいた懐かしい日々。
とは言えそんなリアルブルーでも野球は男性のスポーツという認識がかつては大きかった。最近は男女の関係が見直され、あらためられているらしいらしいが。プロとは言いがたいが、女性のみの野球チームの世界大会なども開催されていて、それにかける女性選手も多いらしい。
今回の参加者も偶然か、クロード・エクルストン(ka1683)以外は全員女性である。エクラの敬虔な信徒である彼は、リアルブルーで人気と聞いて楽しいスポーツであろうと思っているらしい。
確かに野球は楽しい。実際にプレイする以外でも、観戦したり、野球を題材にした読み物などを鑑賞したり、さまざまな楽しみ方が存在する。
「そう言えば、この間偶然手に入れたのですが……」
そう言いながらクロードが取り出したもの、それは最近始まったハンターズソサエティでの支給品に入っていたバットだった。
「名前と、野球に使うというのはわかったのですが、一体どう使うのでしょうか。手に馴染む感触は武器としても使えそうですけれど……まさか殴り合いに?」
そんな発想にたどり着いてしまうのも仕方ないかもしれない。リアルブルー出身のアマリ・ユーナ (ka0218)がクスクスと笑いながら説明する。
「そうね、そういえばこちらの人が知らないから来たのですっけ。知らないのなら仕方ないかもしれないわね……これは投げたボールを振って当てて遠くへ飛ばすための棒なのよ。まあ、どちらにしてもルールの説明と軽い練習は必要よね」
言われてなるほどと頷くクロード。そしてそれを今回の依頼人である青年・タイガに手渡した。
「タイガさん、よろしかったらこのバットを使ってみてください。今日はタイガさんが主役なのですからね」
タイガはそれを受け取るが、まだどうすればいいのかわかりかねているようにみえた。
言われてみれば名前と概要しか知らないクリムゾンウェストの面々。ボールを使って遊ぶ、それを専門にした職業が存在する等、イメージが曖昧模糊としている。
「そもそも、バットとボールだけでは出来ないと父から聞いているのですが。あと人数」
首を小さく傾げるタイガ。
「そうだね、そこから話さないといけないな」
その反応を見て、Charlotte・V・K(ka0468)がやんわりと頷いた。このクリムゾンウェストという異世界・異文化との交流も、ハンターとして暮らしているリアルブルー人たる者のつとめだろう。隣に立っていた風音と目配せし合い、説明を始める。
「まずチームは二チーム九人ずつで行う。攻める側と守る側があって、ボールと呼ばれる球状のものを、バットと呼ばれる棒で打つ。ボールが戻ってくるまでに、所定の位置まで移動する……こんな感じかな?」
シャルロッテがそこまで言うと、一息ついた。
何の気なしに見知っていたものを噛み砕いて説明するのはなかなかに骨である。それでもクリムゾンウェストの若者たちは熱心に聞いてくれる上に、それをきちんと理解しようとしてくれている。マーヤなどはそれこそ集中して聞いているため、顔つきも変わっている。
「ボールを投げる側が守備。そして攻撃側がバットを振ることになります。これが基本的な流れ」
シャルロッテの話を受けて、風音はどこで仕込んだのか度の入っていないメガネをスチャッと掛け、ちょっぴりお姉さんぽく話をする。なかなかに似合っていて、いかにも頭脳明晰そうに見える。
「だから、バットでボールを遠くまで打てば打つほど、有利になるといった感じだね。基本的なルールはこのくらい。細かいルールまで説明してたらきりがないけど、この基本を知っていれば何とかできるからね」
シャルロッテは頷きながら、バットを軽くスイングする。
「ああ、バットというのはそうやって振るんですね」
クロードが目から鱗、というように呟いた。
「うん、バットでボールを打つときは、こうやって振るんだ。まずはお手本……になるかどうかはともかく、ちょっと試してみたいと思う」
「そうよね。今は楽しむほうが大事!」
アマリもにっこり笑っていうが、思うのは野球好きだったというタイガの父親のこと。
(九人揃ってから教える――ってことは、やっぱり試合をさせたかったのかしら? 今すぐにはムリだろうけれど、もし出来ることならそっちの願いもいつか叶えてあげたいわね)
まずは白球を追うことの楽しさをクリムゾンウェストの人にも知ってもらうこと、それが大事なのだろうから。
●
最初のデモンストレーションは、シャルロッテと風音で行うキャッチボール。
握りこぶしより少し大きいくらいのボールを投げては受け取り、返すように投げてそれをまた受け取る。ごくごくシンプルな運動だが、慣れていないとやはり取りこぼしも発生してしまう。
何事も基礎が大事なのだ。
それを見て目を輝かせているのは、エルフの少女テルヒルト(ka0963)だ。ルールの説明や道具の使い方を聞くだけでもちんぷんかんぷん、頭から煙がでそうだったけれども、実際にその光景を目にすれば飲み込みは早い。
百聞は一見にしかず、という言葉があるように、やはり見たり体験したりするのが何よりの早道なのだ。
そしてまた同時に、案ずるより産むが易しという言葉もある。
実際にボールに触れ、身体を動かしてみれば、予想を大きく上回る勢いで楽しさがついて回る。
バットを振るのはまだ危なっかしいが、おおまかな守備位置については解説した。人数的に九人いないのは少し残念な話だが、ルールについてはあらかた納得してくれたようで風音としても一安心である。練習についてもいろいろ考えはするものの、飲み込みの早い――つまりそれだけ好奇心旺盛なクリムゾンウェストの住人たちにはそんなためらいなど必要なかったようだ。
戯れにボールのようなものを投げるくらいのことは、例外はあれどもクリムゾンウェストの子どもたちだってする。コツさえ掴めてしまえばなんということもない。手にはマーヤ曰く『ユニークな形』の即席グラブをつけ、ヒョイッとボールを投げることくらいはできるのだ。
ただ、野球では『コントロール』が大事になる。ボールを思った方向へ投げられるかというと、それはただ投げるだけ、という訳にはいかない。
実際テルヒルトはボールを投げるのがはじめて。緊張のせいかやや力みがちになりながらも手をブンブンと振り、
「いっくぞー!」
と投げては見たものの、思うようにボールは飛んでいかない。力みすぎて逆にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、逆に力の入れ方が不十分だとボールは手の中からすっぽ抜けて、やはりあらぬ方向へと行ってしまう。
ついでに言うと、エルはタイミングを見計らうようにして身体を軽く上下に動かし、胸をわずかに揺らしてみる。必要そうに見えて必要のない動きなのだが、これがこうかを奏したかというと――残念ながら女ばかりの上に依頼人は野球に夢中、唯一の男性ハンターであるクロードはそういう色ごとに対しては興味をあまり持っていないという有り様。まあその代わりクロードは、どんなに怪我を負ったとしても微笑を浮かべている。たとえボールを身体で受け止めたとしても、むしろそれが試練であるかのように見えてしまうのは、彼が聖導士という立場というのもあるのだろう。しかしその実彼が笑顔を絶やさない理由はもう少し違うところにあるのだが、……口に出すのも野暮というものだ。
一方で風音はバットのスイングの仕方を指導する。タイガなどはそわそわしながらバットを握り、指導をしっかり聞きながら振るう。
「違うわ、ここはこうするの。……そうそう、そんな感じ」
タイガが言われるままにバットを動かせば、こつんと何かがバットに当たる鈍い感触。
「あ、なにか当たった……!」
たとえそれがほんのぼてぼてゴロに過ぎなくても、当てたという事実は揺るがない。それが嬉しくて、タイガはぱあっと顔を明るくさせた。
●
時間はかかったものの、キャッチボールを続けていくうちに身体が慣れてきたのだろう、ボールが最初の頃よりもイメージした場所に届くようになってきた。素振りもなかなか様になってきたように見える。
「うん、そろそろ実践形式の練習に移っても大丈夫かしら?」
アマリがそう頷くと、
「でもここには八人しかいませんよ。どうするんですか?」
タイガが問う。たしかにここには八人――野球は一チーム九人で行うスポーツだから、圧倒的に人数が足りない。しかしアマリはフフンと笑う。
「実践をやる――とは言ったけれど、試合をやるとは言ってないわ。実践に必要なのは投手、保守、それに打者……といったところかしら。私は審判兼応援に回ろうかと思うけど」
明確なルールがあるからには、それを判定するレフェリーは欠かせない。アマリは運動が得意な方ではないが、ルールは十分に理解しているし、それに醍醐味を教える立場の必要性を感じたのだ。
醍醐味とは、つまり野球をプレイする際にどういう行動を取れば面白いかということ。外から見てそれを説明する位置に一人はいたほうがいいだろうということだった。
シャルロッテはふむ、と頷くと、
「まずは全員ひととおりのポジションを楽しめるようにローテーションしてみようか。それも醍醐味がわかるヒントになるかもしれない」
そして何の変哲もない原っぱに、ベースなどをおおよそ配置せねばなるまい。つかの間の休憩、風音はふとタイガに問う。
「タイガ君のお父さんって転移者さんなんだって? こっちの世界でパートナーを見つけて、タイガ君を授かったんだね……なんだかロマンチック」
すると、タイガは苦笑した。
「でも、父さんは馴染みきれなかったんじゃないかな。あの船の噂を聞くだけでも、リアルブルーとクリムゾンウェストの違いがすごくわかるし」
「……そっか、そうかもしれないね。でもね、」
風音は微笑した。
「確かにすごく大変だったと思う。私は幼なじみや弟妹がいなかったら、きっと耐えられなかったもの。そんな中で、タイガ君のお父さんはちゃんとこの世界に自分の足跡を残してる。勝手な考えかもだけど、それはやっぱり素敵なことだと思うわ」
タイガはわずかに照れてから、小さく頷いた。
「……ありがとう。そう言ってくれて」
●
そしてどこか部活動っぽいノリで練習は再開された。まず投げるのはシャルロッテ、捕手は風音というバッテリー。打者席に立つのはタイガ――依頼主が優先というわけである。他のハンター達は、もしボールが飛んできた時のためにグラブをつけ、所定のポジションで待ち構えている。
「さて、打ち取れるかな?」
シャルロッテが小さく笑う。アマリは遠くを指さして、
「高く遠く打ち返したら、ホームラン。無条件で点が入るわ」
そしてそれが打者の最高の醍醐味だ、とも伝える。しかしスイングは虚しく空を切り、空振り三振と相成った。
「――そして投手の醍醐味は、打ち返そうとする打者を空振り三振にすること」
アマリがまた解説する。
「なるほど、これは難しいですね」
内野守備位置にいたクロードが苦笑気味につぶやく。
確かに当てるだけでも難しいのに、更に守備に取られないようにしないといけないわけだから、難しいどころではない。
「しかし奥深い。面白いスポーツですね」
「私も同感です」
エルも手を振りながら言う。野球を知りたいのも本心だから、行動自体はごく真面目なのだ。
「ちゃんとチームがあったりしたら、機会さえあればきちんと遊んでみたいです」
本心からの言葉。見た目は半端に成熟気味だが、中身はまだ少女なのだ。
「まだまだ練習中ですけどね」
ボールを投げるのも打つのも、どれも独特で面白い。それは共通認識らしく、
「バットをこうやって握ればなんだかうまく飛びそうですし、打たれたボールを追いかけるのも面白いです。こういうスポーツって、はじめてです」
マーヤが目をキラキラと輝かせて話す。それは嬉しそうに。以前よりリアルブルーに興味あったマーヤからすれば、もっと知りたいというのも道理だろう。
「ほら、テルヒルトさんも!」
皆に促されてバットを握るテルヒルト、クロードのアドバイスを受けて短く握り、タイガの投げる球を思い切り打ち返す――!
●
「どうもありがとうございました。ボールを打たれるとこんなに悔しいんですね……!」
ボールを打たれたタイガは、しかし清々しい表情だった。
「父さんがこのスポーツを愛していたわけもなんとなくわかりました。皆で夢中になれる、そんなスポーツなんですね」
その言葉に風音は微笑んだ。思いは通じたのだ。
「その気があるのなら、チームを作る手伝いも楽しそうね。とりあえず二チームあれば試合はできるし。こちらの世界で野球を普及させるのも素敵でしょう?」
アマリが笑えば、シャルロッテも頷く。
「そのうちロッソに野球の試合録画があるか聞いてみようか。プロの迫力はまた違うだろうしね」
「何から何までありがとうございます」
タイガは深く、礼をした。
白いボールを追いかけて、野球という名のゲームをしよう。
きっとあなたも、夢中になれるはずだから。
依頼結果
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2014/06/28 09:59:09 |
|
 |
相談卓 クロード・エクルストン(ka1683) 人間(クリムゾンウェスト)|22才|男性|聖導士(クルセイダー) |
最終発言 2014/07/02 07:59:17 |
|














