ゲスト
(ka0000)
はじまりの土地
マスター:石田まきば
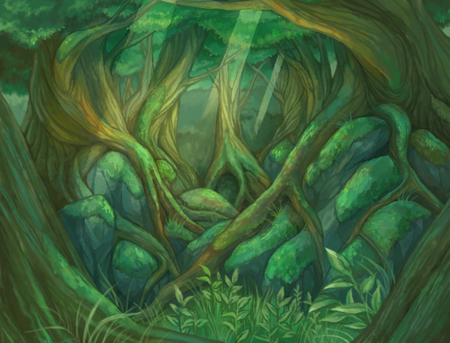
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 難しい
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~8人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 多め
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2016/01/30 19:00
- 完成日
- 2016/02/12 08:45
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●やみ
ナデルハイム。帝都に近く、つまり外界に最も近く……そして、だからこそ様々な思惑が行き交い、潜む区域。
いつまでも森の中で暮らしていきたい恭順派、森を守るためだからこそ森の外を知ろうとする維新派。そして……森の外の脅威に敢えて触れる事を選んだ自分のような存在も。全てを内包する区域。
「それも過去形なのであるな」
ヴォールにとってエルフハイムは故郷である。幼少期を過ごし、青年期を捧げ、裏切られ、捨て去る道を選ばせた……そう考えれば感慨深いものも少しはある……ような気がする。
(何事も効率が大事なのであるな)
生来ヴォールは何かを恐れるという事自体が理解しがたいものだった。大体のことはやれば出来る。学問だろうと研究だろうと、時間をかければかけるだけ答えが返ってきた。だったら恐れる原因だってどうにかすればいい、克服すればいいではないか。今までだって答えを手に入れてきた。できない方がおかしいのだ。
「小さいのである」
精神的にも、範囲的にも。今もやはりエルフハイムに対する自分の考えは変わらない。
物理的に見下ろすだけの、ただの森だ。愚か者達が暮らす場所。惜しいとも思わない。
両親が居たような気もするが、弟がいたような気もするが、これといって大事だとも思えない。ヴォールにとっての大事といえば、自らの研究とその成果だ。
なぜ今ここに居るのか、それが今のヴォールに必要なことだからだ。
サウンドアンカー。新しい浄化術。最高位の術者とはいえたった二人で、六式の威力に匹敵する御業。
それに興味を持った存在が、三人。
その中で実際に行くことになるのは自分だというのも、立場上必然だ。
(新型のオリジナルを作る所であったというのに)
全く人使いが荒い……けれど、逆らうのは得策ではない。
「必要な贄も糧も確保すると取り付けたのである」
これが終われば、すぐにでも取り掛かれる。いや、手に入れたモノの研究が先になるだろうか?
「せめて期待を損なわないモノであれば、無駄もなくなるのではあるがな」
そして愛しげに――科学者が研究対象を凝視するそれだ――視線を配下達へと向ける。
脚。脚。脚。脚。あしあしあしあし……
いくつもの脚が、けれど絡まることなく、静かに歩を進めていた。
●ひかり
機械化された大型の蜘蛛の群れ。それも砲台のようなものを持った、腐ったような部位を持った蜘蛛。
結界林が破壊されている。それも修復の難しい集約地点を的確に狙われた。
剣機と、浄化術と。その両方を併せ持つ敵対者。そうなれば導き出されるのは……
「シャイネ殿」
ユレイテルの執務室。シャイネが愛用の弓を手に立ち上がる。
エルフハイム、特にナデルハイムに向かって歪虚の群が進行してきている。その情報は第三師団長のカミラからも届いていた。
『ハンターに緊急出動を依頼している。揃い次第派遣するので受け入れを頼む』
何のために引き入れた伝話だろうかとも思うが、それだけ第三師団の方も手いっぱいなのだろう。
取り決めではまずナデル側の許可を取って、それから師団兵を派遣するなり、ハンターの手配をするなりと手順があった。それが事後承諾だ。
それほど人手が足りないのだ。先のピースホライズンにおける戦いで、警備の増強や避難民の対応が必要になったと聞いている。十分な数の師団兵を援軍として送り出せないという事。フットワークの軽いハンター達で穴埋めしようという事だ。
そして、もうひとつ読み取れることは。
それだけ素早く対応しなければならない程、敵の数が多い、もしくは質が高い、事前情報が無い……切迫した状況であるという事。
ヴォール。来るのはあの研究者であるのだろう。
そしてその目的は、これまでの行動から考えるに……
「ハイデマリー君のところでいいんだよね?」
「よろしくお願いしたい。ハンター達にもすぐに後を追うよう伝える。私は」
「君は皆の指揮をとらないといけない。違うかい?」
「状況が整ったら、追いかけるつもりでいる」
「杞憂なら、僕も、これから来るハンターの皆も手を回せるはずだよ」
でも。
この襲撃に何らかの決着がつくまで、お互いが顔を合わせることはないだろう。
ユレイテルもシャイネも、それを分かっていた。
●かげ
「は。それは新たな楔か」
最近知り合った声に比べたら響きが擦れた、記憶にあるよりも少し荒れたような声。
ハイデマリー・アルムホルムはその時、ほんの一瞬でも迷ったことを後悔する。
「来ないで!」
振り向きざまに銃口を向ける。けれど相手は既にかわせる場所に居る。
「小娘、それが今の貢物か?」
腐ろうが、堕ちようが。この男はエルフなのだと思い出す。……師匠。そう人に話すこともあるけれど。
お互い名前だってまともに呼んだことが無いような間柄。笑えるわ。
今目の前にいる男は確かにあの変なエルフだ。
「そうよ。同時に貴方を森に眠らせるためのね!」
カチリ。
……シーン
カチッ! カチカチッ!
「繰り返せば暴発するのである」
「っ!」
その隙にヴォールがハイデマリーの腕を拘束。ひょろ長いその体格からは想像できない力。それも歪虚に組したからか。
「汝を奪うが一番の効率化であるな」
人の知識を散々コケにしてきた“スパルタお師匠様”の言い分か、これが?
「ふふっ」
あれは厳密には私の功績じゃないし。でも今はそれが都合いいんだっけ?
誰の都合かしら。帝国かしら、エルフハイムかしら。……両方かしらね。
(ここで利用されたら、この男と同じなのかしら、私も? な~んて面白い冗談!)
こんなにあっさり捕まっちゃって。あと私に出来る役どころは何かしら。
「小娘?」
囚われの姫って柄でもないわね~。
「兄さん、彼女を離してもらえるかな」
「シャイネ! えっあんただけ? ユレイテル……は、無理か~。せめてハンターとか居ないわけ、何ひとりで来てんの」
考えている間にシャイネが工房前にと辿り着いた。すぐに射れるよう構えて狙うのは……ハイデマリーの頭。
「ハイデマリー君、兄さんのモノになるくらいなら僕が、というわけなんだけど、どうしたいかい?」
ああ、そうよね私、人以前。エルフ以前に爆薬みたいなものだったわ。だったらそうなるわよね。
「そうね……」
絶望したかのように顔を伏せる。ヴォールが鼻で笑った気配と、シャイネがくすりと微笑んだ気配。コイツら確かに似てるわ。なんて性悪な兄弟!
「どっちも、ごめんだわっ!」
まだ自由な脚を振り上げ、迷いなくヴォールの股間を蹴り上げた。
「名演技お疲れ様だね、ハイデマリー君♪」
ハイデマリーを背に庇う位置に立つシャイネ。自分も演技だと強引に誤魔化すつもりだ。
(こっちも蹴っていいかしら)
それで二人置き去りにしたいくらいだ。無理だけど。
何とか立ち上がり飛び退ったヴォールが手を挙げると、現れるのは彼の『研究成果』達……
ナデルハイム。帝都に近く、つまり外界に最も近く……そして、だからこそ様々な思惑が行き交い、潜む区域。
いつまでも森の中で暮らしていきたい恭順派、森を守るためだからこそ森の外を知ろうとする維新派。そして……森の外の脅威に敢えて触れる事を選んだ自分のような存在も。全てを内包する区域。
「それも過去形なのであるな」
ヴォールにとってエルフハイムは故郷である。幼少期を過ごし、青年期を捧げ、裏切られ、捨て去る道を選ばせた……そう考えれば感慨深いものも少しはある……ような気がする。
(何事も効率が大事なのであるな)
生来ヴォールは何かを恐れるという事自体が理解しがたいものだった。大体のことはやれば出来る。学問だろうと研究だろうと、時間をかければかけるだけ答えが返ってきた。だったら恐れる原因だってどうにかすればいい、克服すればいいではないか。今までだって答えを手に入れてきた。できない方がおかしいのだ。
「小さいのである」
精神的にも、範囲的にも。今もやはりエルフハイムに対する自分の考えは変わらない。
物理的に見下ろすだけの、ただの森だ。愚か者達が暮らす場所。惜しいとも思わない。
両親が居たような気もするが、弟がいたような気もするが、これといって大事だとも思えない。ヴォールにとっての大事といえば、自らの研究とその成果だ。
なぜ今ここに居るのか、それが今のヴォールに必要なことだからだ。
サウンドアンカー。新しい浄化術。最高位の術者とはいえたった二人で、六式の威力に匹敵する御業。
それに興味を持った存在が、三人。
その中で実際に行くことになるのは自分だというのも、立場上必然だ。
(新型のオリジナルを作る所であったというのに)
全く人使いが荒い……けれど、逆らうのは得策ではない。
「必要な贄も糧も確保すると取り付けたのである」
これが終われば、すぐにでも取り掛かれる。いや、手に入れたモノの研究が先になるだろうか?
「せめて期待を損なわないモノであれば、無駄もなくなるのではあるがな」
そして愛しげに――科学者が研究対象を凝視するそれだ――視線を配下達へと向ける。
脚。脚。脚。脚。あしあしあしあし……
いくつもの脚が、けれど絡まることなく、静かに歩を進めていた。
●ひかり
機械化された大型の蜘蛛の群れ。それも砲台のようなものを持った、腐ったような部位を持った蜘蛛。
結界林が破壊されている。それも修復の難しい集約地点を的確に狙われた。
剣機と、浄化術と。その両方を併せ持つ敵対者。そうなれば導き出されるのは……
「シャイネ殿」
ユレイテルの執務室。シャイネが愛用の弓を手に立ち上がる。
エルフハイム、特にナデルハイムに向かって歪虚の群が進行してきている。その情報は第三師団長のカミラからも届いていた。
『ハンターに緊急出動を依頼している。揃い次第派遣するので受け入れを頼む』
何のために引き入れた伝話だろうかとも思うが、それだけ第三師団の方も手いっぱいなのだろう。
取り決めではまずナデル側の許可を取って、それから師団兵を派遣するなり、ハンターの手配をするなりと手順があった。それが事後承諾だ。
それほど人手が足りないのだ。先のピースホライズンにおける戦いで、警備の増強や避難民の対応が必要になったと聞いている。十分な数の師団兵を援軍として送り出せないという事。フットワークの軽いハンター達で穴埋めしようという事だ。
そして、もうひとつ読み取れることは。
それだけ素早く対応しなければならない程、敵の数が多い、もしくは質が高い、事前情報が無い……切迫した状況であるという事。
ヴォール。来るのはあの研究者であるのだろう。
そしてその目的は、これまでの行動から考えるに……
「ハイデマリー君のところでいいんだよね?」
「よろしくお願いしたい。ハンター達にもすぐに後を追うよう伝える。私は」
「君は皆の指揮をとらないといけない。違うかい?」
「状況が整ったら、追いかけるつもりでいる」
「杞憂なら、僕も、これから来るハンターの皆も手を回せるはずだよ」
でも。
この襲撃に何らかの決着がつくまで、お互いが顔を合わせることはないだろう。
ユレイテルもシャイネも、それを分かっていた。
●かげ
「は。それは新たな楔か」
最近知り合った声に比べたら響きが擦れた、記憶にあるよりも少し荒れたような声。
ハイデマリー・アルムホルムはその時、ほんの一瞬でも迷ったことを後悔する。
「来ないで!」
振り向きざまに銃口を向ける。けれど相手は既にかわせる場所に居る。
「小娘、それが今の貢物か?」
腐ろうが、堕ちようが。この男はエルフなのだと思い出す。……師匠。そう人に話すこともあるけれど。
お互い名前だってまともに呼んだことが無いような間柄。笑えるわ。
今目の前にいる男は確かにあの変なエルフだ。
「そうよ。同時に貴方を森に眠らせるためのね!」
カチリ。
……シーン
カチッ! カチカチッ!
「繰り返せば暴発するのである」
「っ!」
その隙にヴォールがハイデマリーの腕を拘束。ひょろ長いその体格からは想像できない力。それも歪虚に組したからか。
「汝を奪うが一番の効率化であるな」
人の知識を散々コケにしてきた“スパルタお師匠様”の言い分か、これが?
「ふふっ」
あれは厳密には私の功績じゃないし。でも今はそれが都合いいんだっけ?
誰の都合かしら。帝国かしら、エルフハイムかしら。……両方かしらね。
(ここで利用されたら、この男と同じなのかしら、私も? な~んて面白い冗談!)
こんなにあっさり捕まっちゃって。あと私に出来る役どころは何かしら。
「小娘?」
囚われの姫って柄でもないわね~。
「兄さん、彼女を離してもらえるかな」
「シャイネ! えっあんただけ? ユレイテル……は、無理か~。せめてハンターとか居ないわけ、何ひとりで来てんの」
考えている間にシャイネが工房前にと辿り着いた。すぐに射れるよう構えて狙うのは……ハイデマリーの頭。
「ハイデマリー君、兄さんのモノになるくらいなら僕が、というわけなんだけど、どうしたいかい?」
ああ、そうよね私、人以前。エルフ以前に爆薬みたいなものだったわ。だったらそうなるわよね。
「そうね……」
絶望したかのように顔を伏せる。ヴォールが鼻で笑った気配と、シャイネがくすりと微笑んだ気配。コイツら確かに似てるわ。なんて性悪な兄弟!
「どっちも、ごめんだわっ!」
まだ自由な脚を振り上げ、迷いなくヴォールの股間を蹴り上げた。
「名演技お疲れ様だね、ハイデマリー君♪」
ハイデマリーを背に庇う位置に立つシャイネ。自分も演技だと強引に誤魔化すつもりだ。
(こっちも蹴っていいかしら)
それで二人置き去りにしたいくらいだ。無理だけど。
何とか立ち上がり飛び退ったヴォールが手を挙げると、現れるのは彼の『研究成果』達……
リプレイ本文
●
「森に歪虚の群が進行とは……一体何が起こっておるんじゃ!?」
緊急の募集に気付いたイーリス・クルクベウ(ka0481)はすぐに動いていた。実際に目にするまで信じたくはなかったが、道中の慌ただしさ、懐かしい筈の森の違和感に気持ちだけが逸る。
ユレイテルの無事を確認できたことを支えとするべきか。ハイデマリーの護衛任務を示され、来るであろう男の可能性を告げられ。どちらも守りたい気持ちと、どちらかしか選べない、むしろ選択する余裕のない状況に悔しさが募った。
(救援に来たのじゃ、だからより危険に近い娘を優先しているだけ)
工房に向かう間も後ろ髪を引かれ続けた。大丈夫、あの人は周りに仲間がいる。後で無事を確認すればいいだけだ。
「ククッいい様じゃのぅヴォール……クククッ!」
ヴィルマ・ネーベル(ka2549)の笑い声が静かだったはずの森に音を取り戻させる。それもそのはず、いつも高みの見物をして人を見下した喋り方をする自称黒エルフが、股間を押さえて蹲っている姿を目撃したのだから。
「駆けつけてみれば、なかなか面白い展開になっておるのぅ」
クククッ……まだうまく笑い声を抑えることができない。
(笑わない方がおかしいというものじゃ)
ハイデマリーよくやった。と心の底から思っているのだから。むしろ蹴り上げてやりたかったくらいである。溜飲が下がりきるなんてことはないけれど、心底いい気味だと指をさして笑ってやりたい。
指すか、指してしまえ。
よろよろと、少しばかり力ない動作で立ち上がる様子とか、生まれたての小鹿みたいでそのギャップに笑えるくらいだ。
「おやおや。これは修羅場の一種でしょうか?」
興味深い、非常に観察し甲斐のある状況ではありますねと音桐 奏(ka2951)は薄く口元に笑みを浮かべる。
「けれど、黙ってみている訳にもいきませんね」
事は速やかになされなければならない。それこそヴォールが離れないうちに、一石を投じなければ。
(それにしても)
自ら動くことに拘りでもあるのだろうか。毎度律儀なことだとは思う。
(現場型の研究者なんでしょうか?)
確かに自分の目で見た方が早いのは頷ける。効率を求めていることを思えば確かにそうだとは思うけれど。
その度に配下を使い捨てる事はどう思っているのだろうか。
(成果の為の代償は惜しまない……と言ったところですか)
その研究内容もまた興味深いことだけれど。やはり敵である以上。
「ここはお引き取り願いましょうか」
「また、あんたか……」
会うたびに違う玩具を持ち込んでくるのだな。ヴォールの合図により姿を現し始めたアラクネ型に、眉間の皺を寄せるシャーリーン・クリオール(ka0184)。
今回は蜘蛛か。動きを確認することは勿論意識しながらも、どうしても気になるのはハイデマリーの事。
(何か干渉させていると見るべきか)
彼女が何の反撃もしていない筈がない。ならばどうして?
ちらと彼女の銃を見る。安全装置に少しだけ違和感があった。半端な位置。
衝撃は足りず、押し込み切れなかったであろう引き金。
今は義手もなく実質片腕。急な応対。それでこの状態なら、それこそ無防備な状態だったということになる。
暴発しなかったのは幸か不幸か。ここは幸いだったと言うべきだろう。
(その上で、エルフハイムのエルフか)
森林における戦闘術に長けた一族。研究者だと名乗っていても、本質はそこにあるのだと思い知らされる。
アラクネ型にしたってそうだ。蜘蛛としての特性をそのまま残しているというのなら。縦横無尽に移動出来る彼らが森林戦闘のエキスパートによって操られているという事実。
「……数は少ないが、油断できんな」
声に出して仲間達に警告するにしても、タイミングを測るしかない。ヴォールがどこまでこちらの動きを見越してくるか。臨機応変に対応してくるか。出来るなら、見せる隙は少ない方がいいに決まっている。
(あれが……)
幾度も聞いていた噂の男が、目の前にいる。その事実はエステル・クレティエ(ka3783)の腹に黒いものを呼び起こす。
大切な家族が怪我して帰ってくるときの、原因にあげられる名前。その活動記録。
その声にも聞き覚えがあった。東方に出向いた時に聞いた声。確かに記憶と合致する。
何時も、こちらの一歩も二歩も先を行く男。自分もそれを経験しているからこそ怒りが募る。
毎度時間をかけて。試行を重ねているのはアラクネ型を見ればわかる。その勤勉さは認めなくもないけれど、それは敵ではなかったらの話だ。現れる度撃退はしている。けれどそれさえも相手にとっては成功の一助であるのだと理解すれば、腹が立つのは避けられなかった。
「……止めるものは止めるんだから」
止めなければもっと自体は悪い方へ向かって行くから。
きっと睨みつける。そこで小さく首を傾げた。見え覚えのある何かを見た気がして。
「……?」
どうしてだろうか。歪虚の剣機の機械たる部分。そのうちのひとつに、何か。
自分の考えを今一度振り返る。見たことのある機械。それも比較的身近になってきた……
「魔導アーマー!」
とてもよく似た部品。むしろそのものではないだろうか?
「!!」
奏がすぐに理解する。観察してきているからこそ、だろうか。
(北伐後の帝国が混乱している時に襲撃をかけてくる可能性は考慮していましたが……)
そうだ、確かにヴォールも参戦していた。自分だってその場で対峙した。戦場には魔導アーマーも多く参加していたはずで。残骸もまた散らばっていたと記憶している。
「リサイクルなんてまた、地味にやってくれますね」
その割には、アラクネ型に使われている量はそう多くないように見える。
(大半は別の剣機に、と言ったところでしょうか?)
その剣機はこの戦場に持ち込まれているのだろうか。それとも未完成なのか。
いつか対峙しなければならない事だけは確実だ。
「ハイデマリーを攫いに来たというところなのは明白じゃな」
シャイネが庇う位置に居る事に少しばかり驚きを覚えたイーリスである。冗談か本気かはともかく、彼女を攻撃する可能性はあると読んでいた。
「無事で何よりじゃ、あとはわしらが居るからの」
下がれるかと声をかけ、ヴォールへと向き直る。
「この娘はわしがナデルハイムに手引きした身、連れ去られる訳にはいかん!」
故郷の為にすすめてきたことだ、ここで邪魔をされるわけにもいかない。
(ここでの失態はユレイテルの権威に傷を付ける)
それだけではない、自分としても非常に寝覚めが悪くなる。
(いつまでも笑っていられるわけではないのじゃが)
そろそろ切り替えねばと意識を改めるヴィルマ。ヴォールが地上に居るうちに出来ることはしておきたい。ちらりと仲間達を確認する。それぞれ準備は整ったようだった。
「さて、そんなへっぽこから勇ましいお姫様を守りに来たのじゃよ?」
指のかわりに杖を構え、示した。
「ヴォール……ッ!」
恨み声とも違う、強い意思の籠ったクレール(ka0586)の声が木々を縫う。
「今度こそ、そう、今度こそッ……好きにさせない!」
一度闘ったあの時、この男は認められないと、定めた。一度対峙しただけでは止められなかった。これまで何度も止められていないことはわかっていて、けれど止めてみせると、毎度誓いながら拳を握る。
今はどうだか知らないけれど。機導師だったことがある筈の男。人とは外れた道を歩み続けている男。
人を見下すのが得意で悪趣味な勘違い男は、何故か人の名を素直に呼ばない。
(別にいい、あんたが『鋼の声』そう呼ぶなら)
自分は鍛冶師であり技師だ。この目と耳で全て捉えてみせてやる。
そう認めたことを後悔したって遅い、それを分からせてやる。
(歪虚親和? あっさりと堕ちたあんたにヒトの道が分かるわけない)
自らもそうであったはずのヒトの本質を分からないまま、手放した存在なんかに、このままいい顔をさせてやるつもりはなかった。
(ヒトのまま道を進む技術者を、なめるなぁぁぁっ!!!)
剣機。その言葉だけでエステル(ka5826)の胸は痛む。それは剣機が機械による改造を施された、死してなお動くことを強要された存在であるからだ。
聖導士である以前に、自らが聖なる光を扱う存在ではなかったとしても。銀のエステルは、自分が同じように胸を痛めるだろうことを自覚している。
「アンデッドというだけでも痛ましいのに」
強引に活動を強要され、駒として使役される事実。彼らの頂点に君臨する暴食の王がどのような意図で行っているにしても。その王でさえアンデッドであることを鑑みても……それでも、やはり。
「わたくしは……認めたいとは思いません」
死者は送り出すものだ。見届けるものだ。それまでの生を振り返ることはあろうとも、掘り返すような、暴くようなことはしてはならない。その生を更に汚すようなことだって、なおさら。
だから、剣機という存在を生み出した技術そのものを認めない。
出来ることはしてゆくと決めた。それもハンターになった理由に含まれる。
暴かれ汚されてしまったかつての生が、これ以上乱されないように。
「これは中々、分が悪いのではないですかねえ……」
仲間達に聞こえない程に、口の中だけで呟く。
マッシュ・アクラシス(ka0771)はヴォールと初見である。ヴォールに面識のある知り合いはいるけれど、別にその知人のかわりにこの仕事に来た、と言うわけでもなかった。
ただ傭兵として、剣を振るえる仕事があったから、タイミングがあったから、その程度。
(個人的に何かあるわけではありませんがね)
仲間達はそれぞれに思うところがあるようだ、それは察している。其々の事情があろうと自分には関係はないと言った体だ。
(相手は人類の裏切り者としても、ね)
剣を振るえればそれでいい。それで仕事が達成されるというならば。
振るい甲斐があればいい。
目の前の敵は振るうことに躊躇いが必要な相手ではない、それはとても合理的で、ある意味で理想的だった。
仲間達の言葉を聞いていないわけではない。むしろ第三者として冷静に聞けている方だと認識していた。
(退いてくれるのやら)
間近のアラクネ型を潰す、ヴォールを殴りつける……いや、要であるハイデマリーだけでも逃がせればいいのだろうか。
どれも選択肢でしかない。
仲間達の意図がどうであっても自分の予定には関わらないし、構わない。だが、それらを無視するわけではなかった。利益は多いに越したことはないから。
●
戦いの支度は整った。ハンター達も、そしてヴォール率いる剣機軍も。
「良く吠えるのである」
デバイスらしき何かの操作を素早く終えたヴォールが徐々に後ろへと下がっていく。アラクネ型が主であるヴォールを守るように形成した陣はまだ、ただの横並び。けれどその大きさからか、ハンター達に向けて口を開けているかのような威圧感がある。
「囲まれるな!」
シャーリーンの警告が飛ぶと同時に、ヴォールに向けて連射。アラクネ型への指示を途切れさせるため、そして何よりも男の動きを制限させるために。
闇色の障壁がすぐにそれを阻むが、それだって狙い通りだ。
(次は頼んだ)
番えるロスタイムには奏が控えている。
「分かっておるわ。発動させる前に壊してしまえばよいのじゃ」
アラクネ型との位置取りを調節するヴィルマ。今ならヴォールも巻き込めないだろうか。
「……惜しいのじゃ」
あと一歩が足りない。作戦展開上仕方ないこととはいえ。
「いざとなったら本気で代わりに攫われてください」
ヴィルマとの位置調整に追われながらもシャイネに鋭く指示を出す黒髪エステル。とにかくハイデマリーを攫わせないための護りは幾重にも厚くすべきだ。
「大丈夫。そうなったら兄が助けに行きますから」
友人として。妹としてそれを保証していいのかどうか首を傾げたいところではある。しかし今はこう言うしかなかった。
「それまで兄弟水入らずでどうぞ」
「勿論そのつもりだよ」
かわりにさらわれる事か、水入らずの方か。
「それさっきまで私に矢を向けてた人の台詞かしら」
朗らかとも呼べそうな微笑で短く答える吟遊詩人に、呆れた声を向けるハイデマリー。
「やはりの」
恭順派の手前もあったのじゃろうが……イーリスの呟きは小さく空気に溶ける。
「ハイデマリーさん、逃げ足に私のゴースロンを!」
片腕の研究者を助け乗馬させるクレールは、ルーバの耳元に祈るように『そのときは頼むね!』と声をかけた。
今すぐと行きたいところだけど、離れたところを狙われたらいけない。工房の近くはある程度道幅があるけれど、森の中はずっと駆け抜けられるものでもない。
「その為にも……私が」
前に進み出ていた銀髪エステルがそれまでゆっくりと繰り返していた深い呼吸を一度、止めた。
マッシュが頷き得物を構える。
奏のライフルのうなる音が前奏がわりになった。
(力の続く限り、歌います)
敵が汚染結界を目論んでいるのは明白で、皆、それに怯んではいられない。
先に壊せばいい。攻撃は最大の防御。特にいつ起きるかわからない不利な状況は大急ぎで避けなければならない。
特に、歌う自分は。銀髪エステルの思いはその一念に絞られ、だからこそ前線に今、立っている。
(攻撃は出来ませんが……今の私にできる最大限は、彼らに少しでも安息を与える、その切欠を作る事)
歌い上げるのは死者への悼み。生者の命の輝き。
(聖歌隊で鍛えた肺活量の見せ所です……)
自然の中、それこそ自然を、あるがままを称える歌を。効果を信じて歌い続ける。
なるべく多くのアラクネ型を撒きこまなければならない。それは同時に敵のど真ん中に存在し続けることを意味している。
それは理解している。けれど自分が柱になることで敵の動きを鈍らせることが出来るなら。
(まだ稚拙な私の歌ですが……)
戦況を少しでも有利にすることが可能なら。
すぐ傍で守ってくれているマッシュを信じて。敵を減らしてくれる仲間達を信じて。
(最後まで歌いきることが、この場で最初の私の仕事です……!)
「始まりました!」
樹々の無い場所を選びながら黒髪エステルは火球を飛ばす。多少開けてはいるがあくまでもある程度、というのが苦しい。
(完全にばらけられてしまう前に……)
火球だけでも使い切ってしまわなければ。その思いに強く囚われる。剣機の弱点を突くべきか、地形を選ばぬ汎用性を選ぶか。随分と迷った結果である。せめて早いうちに大きなダメージを与えていきたいと切実に思ったゆえの選択だった。
この森ははじめて訪れた場所だ、けれど森と言う場所に思い入れが強い身としては、あまり傷つけたくはない。
(特に足並みが遅れている個体は?)
注意深く見渡す。
結界展開の可能性を減らすためにも、敵の数を減らさなければ。
「……音が、多すぎる」
視覚、聴覚。見慣れた鋼の光沢、聞き慣れた鋼の音。機械が、武器が存在を主張するすべての声を。
これまでの経験から、たったこれだけの行軍ではないだろうと神経を集中させていたクレールが捉えた数はそれこそ、簡単に数えられるものではなかった。
大きい声はわかる。アラクネの6、リンドヴルムの1。ヴォールは鋼と言うほどの声を纏っていない。
問題は、小さい声……それこそ、いつもであれば雑魚と呼んでも差し支えないような音が、大きな声の影に、喧騒のように潜んでいる。
正体は? ……勿論ヴォールの配下、剣機系の歪虚。ただし剣機と呼べるほどではない……何か。
形状は? 少なくとも、クレールははじめて聞く声ばかり。二種類だろうとは判断がつくのだが、目にしたことが無いせいで、情報が足りない。
(飛べるタイプ……だと思う)
「誰か、小型の剣機系歪虚で、飛べるタイプのを知らない!?」
聞くしかない。ヴォールを追っている仲間達の知識を頼る。
「直接見たわけではないが、蝙蝠型なら」
機械パーツを運んでいたらしいので剣機系だと思うがと答えるのはヴィルマ。重体になって気を失っていた彼女は、同行の仲間からその話を聞いた。
「それなら私も、兄から聞いたことあります」
黒髪エステルの同意に、人づてでいいのならと別の声が上がる。
「あたしではないが……前に姉が、鴉型と交戦したことがあると言っていたぞ」
シャーリーンも控えめに続ける。頭部が機械パーツで覆われていたらしいので、剣機系ではないかという話だ。
蝙蝠、鴉。どちらも飛べる。
闘いながら、敵の出方を見ながら時期まで言及している暇はない。
けれどそれらがすべて剣機系の歪虚だとすれば可能性は十分にあり得る。
「クックック……興味深く、そして面白きかな。眩しき高き鋼の声(トライアルトラベラー)……褒美に何を求めるであるかな」
心底楽しげな声がハンター達の緊張に割って入る。勿論それはヴォールのもので。
「貴方の首を」
礼儀正しさを残す口調で物騒な言葉。即座に切り返したのは奏だ。同時に射撃を見舞う。シャーリーンとの連携はまだ途切れさせていない。
「貴方の足止めをするのが私の役目ですし」
観察者が口を開くとどうなるか。その言葉は時に鋭い棘のように核心をつくことがある。ひっそりと忍び寄る夜のように。気付けばすぐそこにある答えのように。
「指揮官を狙うのは定石、という事はご存じですよね? 貴方はこの場合、どう対応するのか見させて貰いましょう」
その上で首を頂けたら。そう続く。
避ける動作をすることもなくゆっくりと片手をあげたように見えた。そのヴォールの手にははじめとは別のデバイス。
ザァ………!!!!!
「一斉に!」
周囲のざわつきとクレールの警告が同時にあがり、混ざる。
輸送型も降りてきている。けれど同時におびただしい数の鴉と蝙蝠がハンター達の視界を塞ぎ、射線を塞ぎ、身動きに制限を加えていく。
黒髪エステルとヴィルマは直前の味方の位置を覚えていたからこそ、どちらも冷気の嵐を放った。
銀髪エステルの歌は確かに二種の歪虚に効果を発揮していたが、これらは本来移動を制限させるものではない。
ヴォールはあくまで弾幕として、これらの配下を使ったのだ。
クレールははじめの賭けに出た。陽掴飛びで配下達を振り切る。ハイデマリーもろとも回収される可能性があったからだ。
気付いたイーリスもシールドの紐を絡みつけた。すぐ傍に居たことは幸いだった。
「……ここで使うつもりはなかったのであるがな。仕方がないのである」
心の底から残念だとは思っていないだろうに、わざとらしく肩をすくめる素振りのヴォール。既にリンドヴルムの機影と重なっている。
猟撃士二人の行動阻害を受けてなお、高速型の俊敏性を利用して合流することが可能だったのだろう。
「弱き作品であろうと、汝等に意味はあったのであるな」
わざとらしくも聞こえるその言葉は、冷気に焼かれるように消えていった配下への弔いの言葉か。
●
「まだ間に合うぞ!」
合流を止めることは叶わなかった。けれど数が減ったことによって視界の確保が叶ったシャーリーンが賭けに出る。射程内に居るリンドヴルムに向けて矢を番える。
あの男の足場をぐらつかせる要素にはなるはず。そう判断したことによる一撃。
(これで駄目なら、次の機会を待つしかないが……)
距離が近い今だからこそである。視界の中をどこまでもちらつく蝙蝠型や鴉型を振り切るようにして一点を見定めた。
「私も一度……お見舞いすべきでしょうね」
奏も同じく高速型を狙う。
すぐにハイデマリーの誘拐を狙いに来てもおかしくない、ならば一度先手を打つのも悪くない。
「主に似ず硬いのじゃな」
何度目かの嵐を巻き起こした後。冗談を交えることで余裕を見せるヴィルマ、しかし内心では小さな不安があった。前よりも自分は強くなった。その自負はある。けれど同様に敵も、正確には敵の作品ではあるが、それも負けじと強くなっている事を実感する。
レクイエムの効果を受けていない個体を見据える。追いつかれぬように、けれどなるべく射程内に集まるよう意図してバイクを駆る。
(あやつの動きも放ってはおけないのじゃが)
ちらと上空の高速型を気にすることも忘れない。降りてくる様子はあるが、その首はヴォールを見ていた。
……ガクン!
「なんじゃっ!?」
一瞬、バイクが急激に遅くなる。身体全体にプレッシャーがのしかかる。咄嗟にアクセルを踏み込んで移動したことで事なきを得たけれど。
何があった?
覚えがある。もっと強い、同じもの。それこそ汚染結界そのもので。
「どうしましたか!?」
組んでいるエステルがすぐに気付く。
「結界じゃ! あやつ、はじめから結界を発動させているのじゃ!」
「なに!?」
アラクネ型の陣形を警戒していたイーリスは驚きを隠しきることができなかった。
イーリスはこの地エルフハイムの出身だ。少なからず浄化術についての知識は持っている。ヴォールはその浄化術の第一人者でもある。だからこそ汚染術、この汚染弾頭にもある程度の法則は適応されると思っていた。
他のハンター達も同様だ。アラクネ型は六体であることから。最高峰の術式だと聞いている、六式結界の汚染術版。これの発動が最大の狙いだと思っていた。
(確かにとてもよく似ているのじゃが、それに限っているだけでは駄目じゃ)
攻撃の手を休めないままに記憶を探るイーリス。出自に由来する知識と、報告書を読み漁った知識の総動員となる。
楔が正多角形の配置に揃えば、術式結界は発動する。つまり三角も、四角も、五画もそれぞれ、三式、四式、五式と呼ばれ浄化術として同様に扱われる。
数が減ればそれだけ展開できる面積が小さくなる。それこそが自分達ハンターの狙い、アラクネ型を一体ずつでも確実に減らしていく理由。それは間違いない。
浄化術は楔となった巫子が繋がり発動する。けれど汚染術の楔は弾頭だ。繋がる為の人為的な行為が無視されている。
地に落ちただけで発動したという報告からも証明できそうだ。
(狼型の時は……)
立ち位置において、二体に挟まれた途端プレッシャーを感じたという報告だったはずだ。それこそヴィルマが先ほど言った状況と同じ。
二式浄化術も勿論存在している。二つの楔を繋ぐ直線状の範囲を浄化する方法。他の方式に比べれば範囲と言う面において効果が小さいものだ。しかしこの特性を持つからこそ、別の技術に応用されていて。浄化目的での利用は今はもうほとんどない、そう思われていたほどだ。
改めてアラクネ型の陣形を見る。その並びは特別に規則性はない。
だが。
どの二体をとっても、それらを繋ぐ直線にすべて汚染結界相当の効果が発揮されているとするなら話は別だ。
汚染弾頭の効果は行動全般の阻害、そして移動力の低下。
「マッシュ、エステル……!?」
戦闘開始から、ほぼずっと。アラクネ型に近い彼らはずっとその影響下にあったのではないのか?
(そういう事ですか)
最前線のマッシュはずっと、プレッシャーに晒され続けていた。つまりすぐ近くに居る銀髪エステルも同じである。
身体が思うように動かない。剣を振るう事も盾を構えることもできているが、全てがどこかゆっくりに感じられる。
それなのに五感は受け身の面においてひどく鋭くなっていて、仲間達の声、ヴォールの声もはっきりと聞き取ることが出来た。
銀髪エステルはまだ歌を止めていない。あまり移動をしないで済んでいる彼女は攻撃の為に体を動かすことが無いからこそ、一定の呼吸を続ける事が出来ていた。
大してマッシュは護衛役。絶え間なく仕掛けられる複数攻撃の対応に追われ、呼吸を維持することがやっとの状態だった。
同時に仕掛けられれば、それだけ避けることも難しくなる。
汚染術は意志を強く持つことではじき返すことができないものだ、そう理解するのに時間はかからなかった。展開されれば問答無用でその影響下に置かれるのだ。
銀髪エステルの歌によって敵も同様の影響下にあることはわかっていたが。移動に制限が無い分、二人とも降下範囲から抜け出すことが出来なくなっていた。
「しかも手ごたえがあまりないと来たもので」
足の関節を狙うことでダメージを与えることが出来ているが。多足の敵に一本や二本破壊したところでその安定性は揺らがないのが実情だった。
それこそ蜘蛛の巣の中に捕らえられた餌になったかのようだ。
足掻けども抜け出せない。
「……こういう手合いにも意図(糸)はある物で」
ぶつけどころのない感情を適当な言葉にかえ舌にのせる。
声を張り上げる余裕はないが、呟くくらいならできる、その程度の余裕。
幸いなことに敵の攻撃絡みを護れる程度の備えができている。
(ここで引き付けたままの方が、他の方の消耗は少ない、そうみるべきですか)
ならば敢えて結界の中に。マッシュは離れようと背を向けたアラクネ型の気を引こうと、衝撃波の構えをとった。
●
銀髪エステルのレクイエムが尽きたあと、それまで少しずつ蓄積していたダメージを理由に一体のアラクネ型が動きを止めた。
阻害の影響が残っている個体もあることから、後は殲滅に向かって行くだけではないかと希望が見えはじめる。
ヴォールはまだ上空でこちらを伺っているし、クレールの五感もまだ鴉型と蝙蝠型の気配を感じ取っている。
「そろそろ諦めどころじゃないのか?」
シャーリーンの軽口はブラフだ。それに感づいているのかどうか。ヴォールはくつくつと笑い続けている。
「ただ倒されるだけでは利がないであろうに。我は汝らの戦闘力も糧にしているのである」
この闘いさえも実験の一環だと答えてくる。
リンドヴルムの首に搭載されているカメラ、そのカバーは開いたり閉じたりとせわしなく動いていた。
「その情報提供の代価はいただけないのですか?」
試しにと話を持ち掛けるのは奏。ヴォールの気分がいい時だからこそ隙があるのではないかと読んだ。
「これだけ何度も観察されて、無償と言うのは不公平だと思いませんか」
交渉の体だが、それだけ意識を引き付けることが可能ならアラクネ型の動きも鈍るのではないか、そんな期待も含んでいる。
(逆効果の可能性もありますが)
試す価値はあると踏んだのだ。
(本音を言えば、聞いてみたいこともありますしね)
倒れた筈なのに、未だ消えないアラクネ型の理由がその筆頭だ。
同じく気にかけていた銀髪エステル、その歌の下でぴくりとも動かなかったアラクネ型の体。
歪虚は倒されれば消えるものだ。歪虚化したばかりの動物などならば元の姿に戻り生き残る可能性は残されているけれど。
剣機は二段階の過程を踏んでいる、そもそも死体を利用している時点で「消えて形も残らない筆頭」だ。
「更に粉砕してしまえばいいのじゃ」
油断して後に回すくらいなら。ヴィルマが容赦なく範囲魔法に巻き込んで、残骸も外殻も破壊していく。ある程度壊されたところで境界があるのか、倒れたアラクネは宙に消えるようになった。
「……空洞、多かったですね?」
黒髪エステルが気にするのは体内の部分。妙に膨らんだ中に何か仕込んであるのではと思ったのだ。
ガササッ!
「一体来ます! 鴉型!」
丁度その時、退避していたらしい蝙蝠型が一体戻って来ていた。数が多かった件の配下は戦闘中のどさくさに紛れて何体かとりこぼしてしまっていたのだった。
それはハンター達の視線を集めながら、たった今破壊されたばかりの二体目のアラクネ型に、コードのようなものを伸ばす。
カチリ
「!?」
一体目と同じように宙に消えようとしていたアラクネ型の残骸が実体を取り戻した。
「楽しみはそこまででとっておくがいいのである」
ガトリングの掃射準備が始められている。そして、まだ残っていたらしい蝙蝠型と鴉型達が再びハンター達の視界を奪おうと寄ってくる。
弾幕を形成するほどではない。
けれどタイミングを合わせて攻撃してきていてうっとうしいことこの上ない。
残ったアラクネ型が皆、この時はじめて射出口を開いた。汚染弾頭の気配が強まる。
「ハイデマリー!」
防御の薄い彼女を護るように立つハンター達。蝙蝠型と鴉型が彼女を狙ってきていたからだ。だから各々が攻撃を回避することを、正面から向かってくる攻撃から目を背けず真っ直ぐ向き合う事を選んだ。彼らの攻撃はそう強いものではないはずだから。耐えきれると信じて。
その上で高速型のガトリングが待っている。こちらだけを避けることは難しく、壁となったハンター達は多くの連撃に晒されることとなる。
汚染結界のプレッシャーと連撃の嵐、嵐、嵐……
「人の気持ちや縁は効率化には邪魔だと思うのだが。だが、こういう時利用できるというのは覚えておこうと思うのである」
笑い声が降る。そのヴォールの肩には鴉型が一体留まっていた。
「……あんのクソ師匠」
護られていたおかげで傷も少ないハイデマリーが、ハンター達の言葉と代弁するかのようにヴォールを罵る。
「結局ここのエルフよね」
続く言葉はハンター達にしか聞こえない程の小声になっていた。
「データも取れたことであるし、我の用は無くなったも同然であるな。汝らの協力無駄にはしないのである」
そんなヴォールの言葉を最後に、飛び去ろうとする高速型。汚染弾頭を放出したアラクネ型もガトリング掃射を受けている。身体はすでに消え始めていた。
「楽しみにしておくといいのである」
「森に歪虚の群が進行とは……一体何が起こっておるんじゃ!?」
緊急の募集に気付いたイーリス・クルクベウ(ka0481)はすぐに動いていた。実際に目にするまで信じたくはなかったが、道中の慌ただしさ、懐かしい筈の森の違和感に気持ちだけが逸る。
ユレイテルの無事を確認できたことを支えとするべきか。ハイデマリーの護衛任務を示され、来るであろう男の可能性を告げられ。どちらも守りたい気持ちと、どちらかしか選べない、むしろ選択する余裕のない状況に悔しさが募った。
(救援に来たのじゃ、だからより危険に近い娘を優先しているだけ)
工房に向かう間も後ろ髪を引かれ続けた。大丈夫、あの人は周りに仲間がいる。後で無事を確認すればいいだけだ。
「ククッいい様じゃのぅヴォール……クククッ!」
ヴィルマ・ネーベル(ka2549)の笑い声が静かだったはずの森に音を取り戻させる。それもそのはず、いつも高みの見物をして人を見下した喋り方をする自称黒エルフが、股間を押さえて蹲っている姿を目撃したのだから。
「駆けつけてみれば、なかなか面白い展開になっておるのぅ」
クククッ……まだうまく笑い声を抑えることができない。
(笑わない方がおかしいというものじゃ)
ハイデマリーよくやった。と心の底から思っているのだから。むしろ蹴り上げてやりたかったくらいである。溜飲が下がりきるなんてことはないけれど、心底いい気味だと指をさして笑ってやりたい。
指すか、指してしまえ。
よろよろと、少しばかり力ない動作で立ち上がる様子とか、生まれたての小鹿みたいでそのギャップに笑えるくらいだ。
「おやおや。これは修羅場の一種でしょうか?」
興味深い、非常に観察し甲斐のある状況ではありますねと音桐 奏(ka2951)は薄く口元に笑みを浮かべる。
「けれど、黙ってみている訳にもいきませんね」
事は速やかになされなければならない。それこそヴォールが離れないうちに、一石を投じなければ。
(それにしても)
自ら動くことに拘りでもあるのだろうか。毎度律儀なことだとは思う。
(現場型の研究者なんでしょうか?)
確かに自分の目で見た方が早いのは頷ける。効率を求めていることを思えば確かにそうだとは思うけれど。
その度に配下を使い捨てる事はどう思っているのだろうか。
(成果の為の代償は惜しまない……と言ったところですか)
その研究内容もまた興味深いことだけれど。やはり敵である以上。
「ここはお引き取り願いましょうか」
「また、あんたか……」
会うたびに違う玩具を持ち込んでくるのだな。ヴォールの合図により姿を現し始めたアラクネ型に、眉間の皺を寄せるシャーリーン・クリオール(ka0184)。
今回は蜘蛛か。動きを確認することは勿論意識しながらも、どうしても気になるのはハイデマリーの事。
(何か干渉させていると見るべきか)
彼女が何の反撃もしていない筈がない。ならばどうして?
ちらと彼女の銃を見る。安全装置に少しだけ違和感があった。半端な位置。
衝撃は足りず、押し込み切れなかったであろう引き金。
今は義手もなく実質片腕。急な応対。それでこの状態なら、それこそ無防備な状態だったということになる。
暴発しなかったのは幸か不幸か。ここは幸いだったと言うべきだろう。
(その上で、エルフハイムのエルフか)
森林における戦闘術に長けた一族。研究者だと名乗っていても、本質はそこにあるのだと思い知らされる。
アラクネ型にしたってそうだ。蜘蛛としての特性をそのまま残しているというのなら。縦横無尽に移動出来る彼らが森林戦闘のエキスパートによって操られているという事実。
「……数は少ないが、油断できんな」
声に出して仲間達に警告するにしても、タイミングを測るしかない。ヴォールがどこまでこちらの動きを見越してくるか。臨機応変に対応してくるか。出来るなら、見せる隙は少ない方がいいに決まっている。
(あれが……)
幾度も聞いていた噂の男が、目の前にいる。その事実はエステル・クレティエ(ka3783)の腹に黒いものを呼び起こす。
大切な家族が怪我して帰ってくるときの、原因にあげられる名前。その活動記録。
その声にも聞き覚えがあった。東方に出向いた時に聞いた声。確かに記憶と合致する。
何時も、こちらの一歩も二歩も先を行く男。自分もそれを経験しているからこそ怒りが募る。
毎度時間をかけて。試行を重ねているのはアラクネ型を見ればわかる。その勤勉さは認めなくもないけれど、それは敵ではなかったらの話だ。現れる度撃退はしている。けれどそれさえも相手にとっては成功の一助であるのだと理解すれば、腹が立つのは避けられなかった。
「……止めるものは止めるんだから」
止めなければもっと自体は悪い方へ向かって行くから。
きっと睨みつける。そこで小さく首を傾げた。見え覚えのある何かを見た気がして。
「……?」
どうしてだろうか。歪虚の剣機の機械たる部分。そのうちのひとつに、何か。
自分の考えを今一度振り返る。見たことのある機械。それも比較的身近になってきた……
「魔導アーマー!」
とてもよく似た部品。むしろそのものではないだろうか?
「!!」
奏がすぐに理解する。観察してきているからこそ、だろうか。
(北伐後の帝国が混乱している時に襲撃をかけてくる可能性は考慮していましたが……)
そうだ、確かにヴォールも参戦していた。自分だってその場で対峙した。戦場には魔導アーマーも多く参加していたはずで。残骸もまた散らばっていたと記憶している。
「リサイクルなんてまた、地味にやってくれますね」
その割には、アラクネ型に使われている量はそう多くないように見える。
(大半は別の剣機に、と言ったところでしょうか?)
その剣機はこの戦場に持ち込まれているのだろうか。それとも未完成なのか。
いつか対峙しなければならない事だけは確実だ。
「ハイデマリーを攫いに来たというところなのは明白じゃな」
シャイネが庇う位置に居る事に少しばかり驚きを覚えたイーリスである。冗談か本気かはともかく、彼女を攻撃する可能性はあると読んでいた。
「無事で何よりじゃ、あとはわしらが居るからの」
下がれるかと声をかけ、ヴォールへと向き直る。
「この娘はわしがナデルハイムに手引きした身、連れ去られる訳にはいかん!」
故郷の為にすすめてきたことだ、ここで邪魔をされるわけにもいかない。
(ここでの失態はユレイテルの権威に傷を付ける)
それだけではない、自分としても非常に寝覚めが悪くなる。
(いつまでも笑っていられるわけではないのじゃが)
そろそろ切り替えねばと意識を改めるヴィルマ。ヴォールが地上に居るうちに出来ることはしておきたい。ちらりと仲間達を確認する。それぞれ準備は整ったようだった。
「さて、そんなへっぽこから勇ましいお姫様を守りに来たのじゃよ?」
指のかわりに杖を構え、示した。
「ヴォール……ッ!」
恨み声とも違う、強い意思の籠ったクレール(ka0586)の声が木々を縫う。
「今度こそ、そう、今度こそッ……好きにさせない!」
一度闘ったあの時、この男は認められないと、定めた。一度対峙しただけでは止められなかった。これまで何度も止められていないことはわかっていて、けれど止めてみせると、毎度誓いながら拳を握る。
今はどうだか知らないけれど。機導師だったことがある筈の男。人とは外れた道を歩み続けている男。
人を見下すのが得意で悪趣味な勘違い男は、何故か人の名を素直に呼ばない。
(別にいい、あんたが『鋼の声』そう呼ぶなら)
自分は鍛冶師であり技師だ。この目と耳で全て捉えてみせてやる。
そう認めたことを後悔したって遅い、それを分からせてやる。
(歪虚親和? あっさりと堕ちたあんたにヒトの道が分かるわけない)
自らもそうであったはずのヒトの本質を分からないまま、手放した存在なんかに、このままいい顔をさせてやるつもりはなかった。
(ヒトのまま道を進む技術者を、なめるなぁぁぁっ!!!)
剣機。その言葉だけでエステル(ka5826)の胸は痛む。それは剣機が機械による改造を施された、死してなお動くことを強要された存在であるからだ。
聖導士である以前に、自らが聖なる光を扱う存在ではなかったとしても。銀のエステルは、自分が同じように胸を痛めるだろうことを自覚している。
「アンデッドというだけでも痛ましいのに」
強引に活動を強要され、駒として使役される事実。彼らの頂点に君臨する暴食の王がどのような意図で行っているにしても。その王でさえアンデッドであることを鑑みても……それでも、やはり。
「わたくしは……認めたいとは思いません」
死者は送り出すものだ。見届けるものだ。それまでの生を振り返ることはあろうとも、掘り返すような、暴くようなことはしてはならない。その生を更に汚すようなことだって、なおさら。
だから、剣機という存在を生み出した技術そのものを認めない。
出来ることはしてゆくと決めた。それもハンターになった理由に含まれる。
暴かれ汚されてしまったかつての生が、これ以上乱されないように。
「これは中々、分が悪いのではないですかねえ……」
仲間達に聞こえない程に、口の中だけで呟く。
マッシュ・アクラシス(ka0771)はヴォールと初見である。ヴォールに面識のある知り合いはいるけれど、別にその知人のかわりにこの仕事に来た、と言うわけでもなかった。
ただ傭兵として、剣を振るえる仕事があったから、タイミングがあったから、その程度。
(個人的に何かあるわけではありませんがね)
仲間達はそれぞれに思うところがあるようだ、それは察している。其々の事情があろうと自分には関係はないと言った体だ。
(相手は人類の裏切り者としても、ね)
剣を振るえればそれでいい。それで仕事が達成されるというならば。
振るい甲斐があればいい。
目の前の敵は振るうことに躊躇いが必要な相手ではない、それはとても合理的で、ある意味で理想的だった。
仲間達の言葉を聞いていないわけではない。むしろ第三者として冷静に聞けている方だと認識していた。
(退いてくれるのやら)
間近のアラクネ型を潰す、ヴォールを殴りつける……いや、要であるハイデマリーだけでも逃がせればいいのだろうか。
どれも選択肢でしかない。
仲間達の意図がどうであっても自分の予定には関わらないし、構わない。だが、それらを無視するわけではなかった。利益は多いに越したことはないから。
●
戦いの支度は整った。ハンター達も、そしてヴォール率いる剣機軍も。
「良く吠えるのである」
デバイスらしき何かの操作を素早く終えたヴォールが徐々に後ろへと下がっていく。アラクネ型が主であるヴォールを守るように形成した陣はまだ、ただの横並び。けれどその大きさからか、ハンター達に向けて口を開けているかのような威圧感がある。
「囲まれるな!」
シャーリーンの警告が飛ぶと同時に、ヴォールに向けて連射。アラクネ型への指示を途切れさせるため、そして何よりも男の動きを制限させるために。
闇色の障壁がすぐにそれを阻むが、それだって狙い通りだ。
(次は頼んだ)
番えるロスタイムには奏が控えている。
「分かっておるわ。発動させる前に壊してしまえばよいのじゃ」
アラクネ型との位置取りを調節するヴィルマ。今ならヴォールも巻き込めないだろうか。
「……惜しいのじゃ」
あと一歩が足りない。作戦展開上仕方ないこととはいえ。
「いざとなったら本気で代わりに攫われてください」
ヴィルマとの位置調整に追われながらもシャイネに鋭く指示を出す黒髪エステル。とにかくハイデマリーを攫わせないための護りは幾重にも厚くすべきだ。
「大丈夫。そうなったら兄が助けに行きますから」
友人として。妹としてそれを保証していいのかどうか首を傾げたいところではある。しかし今はこう言うしかなかった。
「それまで兄弟水入らずでどうぞ」
「勿論そのつもりだよ」
かわりにさらわれる事か、水入らずの方か。
「それさっきまで私に矢を向けてた人の台詞かしら」
朗らかとも呼べそうな微笑で短く答える吟遊詩人に、呆れた声を向けるハイデマリー。
「やはりの」
恭順派の手前もあったのじゃろうが……イーリスの呟きは小さく空気に溶ける。
「ハイデマリーさん、逃げ足に私のゴースロンを!」
片腕の研究者を助け乗馬させるクレールは、ルーバの耳元に祈るように『そのときは頼むね!』と声をかけた。
今すぐと行きたいところだけど、離れたところを狙われたらいけない。工房の近くはある程度道幅があるけれど、森の中はずっと駆け抜けられるものでもない。
「その為にも……私が」
前に進み出ていた銀髪エステルがそれまでゆっくりと繰り返していた深い呼吸を一度、止めた。
マッシュが頷き得物を構える。
奏のライフルのうなる音が前奏がわりになった。
(力の続く限り、歌います)
敵が汚染結界を目論んでいるのは明白で、皆、それに怯んではいられない。
先に壊せばいい。攻撃は最大の防御。特にいつ起きるかわからない不利な状況は大急ぎで避けなければならない。
特に、歌う自分は。銀髪エステルの思いはその一念に絞られ、だからこそ前線に今、立っている。
(攻撃は出来ませんが……今の私にできる最大限は、彼らに少しでも安息を与える、その切欠を作る事)
歌い上げるのは死者への悼み。生者の命の輝き。
(聖歌隊で鍛えた肺活量の見せ所です……)
自然の中、それこそ自然を、あるがままを称える歌を。効果を信じて歌い続ける。
なるべく多くのアラクネ型を撒きこまなければならない。それは同時に敵のど真ん中に存在し続けることを意味している。
それは理解している。けれど自分が柱になることで敵の動きを鈍らせることが出来るなら。
(まだ稚拙な私の歌ですが……)
戦況を少しでも有利にすることが可能なら。
すぐ傍で守ってくれているマッシュを信じて。敵を減らしてくれる仲間達を信じて。
(最後まで歌いきることが、この場で最初の私の仕事です……!)
「始まりました!」
樹々の無い場所を選びながら黒髪エステルは火球を飛ばす。多少開けてはいるがあくまでもある程度、というのが苦しい。
(完全にばらけられてしまう前に……)
火球だけでも使い切ってしまわなければ。その思いに強く囚われる。剣機の弱点を突くべきか、地形を選ばぬ汎用性を選ぶか。随分と迷った結果である。せめて早いうちに大きなダメージを与えていきたいと切実に思ったゆえの選択だった。
この森ははじめて訪れた場所だ、けれど森と言う場所に思い入れが強い身としては、あまり傷つけたくはない。
(特に足並みが遅れている個体は?)
注意深く見渡す。
結界展開の可能性を減らすためにも、敵の数を減らさなければ。
「……音が、多すぎる」
視覚、聴覚。見慣れた鋼の光沢、聞き慣れた鋼の音。機械が、武器が存在を主張するすべての声を。
これまでの経験から、たったこれだけの行軍ではないだろうと神経を集中させていたクレールが捉えた数はそれこそ、簡単に数えられるものではなかった。
大きい声はわかる。アラクネの6、リンドヴルムの1。ヴォールは鋼と言うほどの声を纏っていない。
問題は、小さい声……それこそ、いつもであれば雑魚と呼んでも差し支えないような音が、大きな声の影に、喧騒のように潜んでいる。
正体は? ……勿論ヴォールの配下、剣機系の歪虚。ただし剣機と呼べるほどではない……何か。
形状は? 少なくとも、クレールははじめて聞く声ばかり。二種類だろうとは判断がつくのだが、目にしたことが無いせいで、情報が足りない。
(飛べるタイプ……だと思う)
「誰か、小型の剣機系歪虚で、飛べるタイプのを知らない!?」
聞くしかない。ヴォールを追っている仲間達の知識を頼る。
「直接見たわけではないが、蝙蝠型なら」
機械パーツを運んでいたらしいので剣機系だと思うがと答えるのはヴィルマ。重体になって気を失っていた彼女は、同行の仲間からその話を聞いた。
「それなら私も、兄から聞いたことあります」
黒髪エステルの同意に、人づてでいいのならと別の声が上がる。
「あたしではないが……前に姉が、鴉型と交戦したことがあると言っていたぞ」
シャーリーンも控えめに続ける。頭部が機械パーツで覆われていたらしいので、剣機系ではないかという話だ。
蝙蝠、鴉。どちらも飛べる。
闘いながら、敵の出方を見ながら時期まで言及している暇はない。
けれどそれらがすべて剣機系の歪虚だとすれば可能性は十分にあり得る。
「クックック……興味深く、そして面白きかな。眩しき高き鋼の声(トライアルトラベラー)……褒美に何を求めるであるかな」
心底楽しげな声がハンター達の緊張に割って入る。勿論それはヴォールのもので。
「貴方の首を」
礼儀正しさを残す口調で物騒な言葉。即座に切り返したのは奏だ。同時に射撃を見舞う。シャーリーンとの連携はまだ途切れさせていない。
「貴方の足止めをするのが私の役目ですし」
観察者が口を開くとどうなるか。その言葉は時に鋭い棘のように核心をつくことがある。ひっそりと忍び寄る夜のように。気付けばすぐそこにある答えのように。
「指揮官を狙うのは定石、という事はご存じですよね? 貴方はこの場合、どう対応するのか見させて貰いましょう」
その上で首を頂けたら。そう続く。
避ける動作をすることもなくゆっくりと片手をあげたように見えた。そのヴォールの手にははじめとは別のデバイス。
ザァ………!!!!!
「一斉に!」
周囲のざわつきとクレールの警告が同時にあがり、混ざる。
輸送型も降りてきている。けれど同時におびただしい数の鴉と蝙蝠がハンター達の視界を塞ぎ、射線を塞ぎ、身動きに制限を加えていく。
黒髪エステルとヴィルマは直前の味方の位置を覚えていたからこそ、どちらも冷気の嵐を放った。
銀髪エステルの歌は確かに二種の歪虚に効果を発揮していたが、これらは本来移動を制限させるものではない。
ヴォールはあくまで弾幕として、これらの配下を使ったのだ。
クレールははじめの賭けに出た。陽掴飛びで配下達を振り切る。ハイデマリーもろとも回収される可能性があったからだ。
気付いたイーリスもシールドの紐を絡みつけた。すぐ傍に居たことは幸いだった。
「……ここで使うつもりはなかったのであるがな。仕方がないのである」
心の底から残念だとは思っていないだろうに、わざとらしく肩をすくめる素振りのヴォール。既にリンドヴルムの機影と重なっている。
猟撃士二人の行動阻害を受けてなお、高速型の俊敏性を利用して合流することが可能だったのだろう。
「弱き作品であろうと、汝等に意味はあったのであるな」
わざとらしくも聞こえるその言葉は、冷気に焼かれるように消えていった配下への弔いの言葉か。
●
「まだ間に合うぞ!」
合流を止めることは叶わなかった。けれど数が減ったことによって視界の確保が叶ったシャーリーンが賭けに出る。射程内に居るリンドヴルムに向けて矢を番える。
あの男の足場をぐらつかせる要素にはなるはず。そう判断したことによる一撃。
(これで駄目なら、次の機会を待つしかないが……)
距離が近い今だからこそである。視界の中をどこまでもちらつく蝙蝠型や鴉型を振り切るようにして一点を見定めた。
「私も一度……お見舞いすべきでしょうね」
奏も同じく高速型を狙う。
すぐにハイデマリーの誘拐を狙いに来てもおかしくない、ならば一度先手を打つのも悪くない。
「主に似ず硬いのじゃな」
何度目かの嵐を巻き起こした後。冗談を交えることで余裕を見せるヴィルマ、しかし内心では小さな不安があった。前よりも自分は強くなった。その自負はある。けれど同様に敵も、正確には敵の作品ではあるが、それも負けじと強くなっている事を実感する。
レクイエムの効果を受けていない個体を見据える。追いつかれぬように、けれどなるべく射程内に集まるよう意図してバイクを駆る。
(あやつの動きも放ってはおけないのじゃが)
ちらと上空の高速型を気にすることも忘れない。降りてくる様子はあるが、その首はヴォールを見ていた。
……ガクン!
「なんじゃっ!?」
一瞬、バイクが急激に遅くなる。身体全体にプレッシャーがのしかかる。咄嗟にアクセルを踏み込んで移動したことで事なきを得たけれど。
何があった?
覚えがある。もっと強い、同じもの。それこそ汚染結界そのもので。
「どうしましたか!?」
組んでいるエステルがすぐに気付く。
「結界じゃ! あやつ、はじめから結界を発動させているのじゃ!」
「なに!?」
アラクネ型の陣形を警戒していたイーリスは驚きを隠しきることができなかった。
イーリスはこの地エルフハイムの出身だ。少なからず浄化術についての知識は持っている。ヴォールはその浄化術の第一人者でもある。だからこそ汚染術、この汚染弾頭にもある程度の法則は適応されると思っていた。
他のハンター達も同様だ。アラクネ型は六体であることから。最高峰の術式だと聞いている、六式結界の汚染術版。これの発動が最大の狙いだと思っていた。
(確かにとてもよく似ているのじゃが、それに限っているだけでは駄目じゃ)
攻撃の手を休めないままに記憶を探るイーリス。出自に由来する知識と、報告書を読み漁った知識の総動員となる。
楔が正多角形の配置に揃えば、術式結界は発動する。つまり三角も、四角も、五画もそれぞれ、三式、四式、五式と呼ばれ浄化術として同様に扱われる。
数が減ればそれだけ展開できる面積が小さくなる。それこそが自分達ハンターの狙い、アラクネ型を一体ずつでも確実に減らしていく理由。それは間違いない。
浄化術は楔となった巫子が繋がり発動する。けれど汚染術の楔は弾頭だ。繋がる為の人為的な行為が無視されている。
地に落ちただけで発動したという報告からも証明できそうだ。
(狼型の時は……)
立ち位置において、二体に挟まれた途端プレッシャーを感じたという報告だったはずだ。それこそヴィルマが先ほど言った状況と同じ。
二式浄化術も勿論存在している。二つの楔を繋ぐ直線状の範囲を浄化する方法。他の方式に比べれば範囲と言う面において効果が小さいものだ。しかしこの特性を持つからこそ、別の技術に応用されていて。浄化目的での利用は今はもうほとんどない、そう思われていたほどだ。
改めてアラクネ型の陣形を見る。その並びは特別に規則性はない。
だが。
どの二体をとっても、それらを繋ぐ直線にすべて汚染結界相当の効果が発揮されているとするなら話は別だ。
汚染弾頭の効果は行動全般の阻害、そして移動力の低下。
「マッシュ、エステル……!?」
戦闘開始から、ほぼずっと。アラクネ型に近い彼らはずっとその影響下にあったのではないのか?
(そういう事ですか)
最前線のマッシュはずっと、プレッシャーに晒され続けていた。つまりすぐ近くに居る銀髪エステルも同じである。
身体が思うように動かない。剣を振るう事も盾を構えることもできているが、全てがどこかゆっくりに感じられる。
それなのに五感は受け身の面においてひどく鋭くなっていて、仲間達の声、ヴォールの声もはっきりと聞き取ることが出来た。
銀髪エステルはまだ歌を止めていない。あまり移動をしないで済んでいる彼女は攻撃の為に体を動かすことが無いからこそ、一定の呼吸を続ける事が出来ていた。
大してマッシュは護衛役。絶え間なく仕掛けられる複数攻撃の対応に追われ、呼吸を維持することがやっとの状態だった。
同時に仕掛けられれば、それだけ避けることも難しくなる。
汚染術は意志を強く持つことではじき返すことができないものだ、そう理解するのに時間はかからなかった。展開されれば問答無用でその影響下に置かれるのだ。
銀髪エステルの歌によって敵も同様の影響下にあることはわかっていたが。移動に制限が無い分、二人とも降下範囲から抜け出すことが出来なくなっていた。
「しかも手ごたえがあまりないと来たもので」
足の関節を狙うことでダメージを与えることが出来ているが。多足の敵に一本や二本破壊したところでその安定性は揺らがないのが実情だった。
それこそ蜘蛛の巣の中に捕らえられた餌になったかのようだ。
足掻けども抜け出せない。
「……こういう手合いにも意図(糸)はある物で」
ぶつけどころのない感情を適当な言葉にかえ舌にのせる。
声を張り上げる余裕はないが、呟くくらいならできる、その程度の余裕。
幸いなことに敵の攻撃絡みを護れる程度の備えができている。
(ここで引き付けたままの方が、他の方の消耗は少ない、そうみるべきですか)
ならば敢えて結界の中に。マッシュは離れようと背を向けたアラクネ型の気を引こうと、衝撃波の構えをとった。
●
銀髪エステルのレクイエムが尽きたあと、それまで少しずつ蓄積していたダメージを理由に一体のアラクネ型が動きを止めた。
阻害の影響が残っている個体もあることから、後は殲滅に向かって行くだけではないかと希望が見えはじめる。
ヴォールはまだ上空でこちらを伺っているし、クレールの五感もまだ鴉型と蝙蝠型の気配を感じ取っている。
「そろそろ諦めどころじゃないのか?」
シャーリーンの軽口はブラフだ。それに感づいているのかどうか。ヴォールはくつくつと笑い続けている。
「ただ倒されるだけでは利がないであろうに。我は汝らの戦闘力も糧にしているのである」
この闘いさえも実験の一環だと答えてくる。
リンドヴルムの首に搭載されているカメラ、そのカバーは開いたり閉じたりとせわしなく動いていた。
「その情報提供の代価はいただけないのですか?」
試しにと話を持ち掛けるのは奏。ヴォールの気分がいい時だからこそ隙があるのではないかと読んだ。
「これだけ何度も観察されて、無償と言うのは不公平だと思いませんか」
交渉の体だが、それだけ意識を引き付けることが可能ならアラクネ型の動きも鈍るのではないか、そんな期待も含んでいる。
(逆効果の可能性もありますが)
試す価値はあると踏んだのだ。
(本音を言えば、聞いてみたいこともありますしね)
倒れた筈なのに、未だ消えないアラクネ型の理由がその筆頭だ。
同じく気にかけていた銀髪エステル、その歌の下でぴくりとも動かなかったアラクネ型の体。
歪虚は倒されれば消えるものだ。歪虚化したばかりの動物などならば元の姿に戻り生き残る可能性は残されているけれど。
剣機は二段階の過程を踏んでいる、そもそも死体を利用している時点で「消えて形も残らない筆頭」だ。
「更に粉砕してしまえばいいのじゃ」
油断して後に回すくらいなら。ヴィルマが容赦なく範囲魔法に巻き込んで、残骸も外殻も破壊していく。ある程度壊されたところで境界があるのか、倒れたアラクネは宙に消えるようになった。
「……空洞、多かったですね?」
黒髪エステルが気にするのは体内の部分。妙に膨らんだ中に何か仕込んであるのではと思ったのだ。
ガササッ!
「一体来ます! 鴉型!」
丁度その時、退避していたらしい蝙蝠型が一体戻って来ていた。数が多かった件の配下は戦闘中のどさくさに紛れて何体かとりこぼしてしまっていたのだった。
それはハンター達の視線を集めながら、たった今破壊されたばかりの二体目のアラクネ型に、コードのようなものを伸ばす。
カチリ
「!?」
一体目と同じように宙に消えようとしていたアラクネ型の残骸が実体を取り戻した。
「楽しみはそこまででとっておくがいいのである」
ガトリングの掃射準備が始められている。そして、まだ残っていたらしい蝙蝠型と鴉型達が再びハンター達の視界を奪おうと寄ってくる。
弾幕を形成するほどではない。
けれどタイミングを合わせて攻撃してきていてうっとうしいことこの上ない。
残ったアラクネ型が皆、この時はじめて射出口を開いた。汚染弾頭の気配が強まる。
「ハイデマリー!」
防御の薄い彼女を護るように立つハンター達。蝙蝠型と鴉型が彼女を狙ってきていたからだ。だから各々が攻撃を回避することを、正面から向かってくる攻撃から目を背けず真っ直ぐ向き合う事を選んだ。彼らの攻撃はそう強いものではないはずだから。耐えきれると信じて。
その上で高速型のガトリングが待っている。こちらだけを避けることは難しく、壁となったハンター達は多くの連撃に晒されることとなる。
汚染結界のプレッシャーと連撃の嵐、嵐、嵐……
「人の気持ちや縁は効率化には邪魔だと思うのだが。だが、こういう時利用できるというのは覚えておこうと思うのである」
笑い声が降る。そのヴォールの肩には鴉型が一体留まっていた。
「……あんのクソ師匠」
護られていたおかげで傷も少ないハイデマリーが、ハンター達の言葉と代弁するかのようにヴォールを罵る。
「結局ここのエルフよね」
続く言葉はハンター達にしか聞こえない程の小声になっていた。
「データも取れたことであるし、我の用は無くなったも同然であるな。汝らの協力無駄にはしないのである」
そんなヴォールの言葉を最後に、飛び去ろうとする高速型。汚染弾頭を放出したアラクネ型もガトリング掃射を受けている。身体はすでに消え始めていた。
「楽しみにしておくといいのである」
依頼結果
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
誘拐阻止作戦相談卓 クレール・ディンセルフ(ka0586) 人間(クリムゾンウェスト)|23才|女性|機導師(アルケミスト) |
最終発言 2016/01/30 18:51:43 |
|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2016/01/27 06:06:46 |
|



















