ゲスト
(ka0000)
悪意とたのしいティーパーティー
マスター:T谷
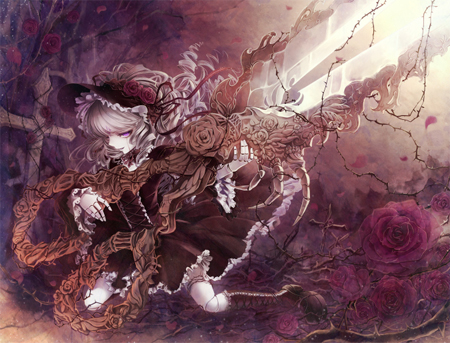
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 不明
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~10人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 多め
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2016/12/04 22:00
- 完成日
- 2016/12/17 16:08
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
星の傷跡での遭遇以来初めて、エリザベート(kz0123)の姿が帝国内で目撃された。それも、第二師団の管理する地域でのことだ。ふらふらと浮かぶ赤色と、その下にぶら下がる円錐状の鈍色が、山の向こうに消えていったのを周辺警邏に当たっていた師団員が目撃したらしい。
「ま、あんな崩落程度でくだばるわきゃねえわな」
脳筋の極みであるような第二師団長シュターク・シュタークスン(kz0075)でさえ、難色を隠せない。面倒そうに溜息をついて、机の上に足を投げ出した。
「ふむ。例え潜伏先が分かったとして、向こうの戦力が未だ未知数な以上、迂闊に手は出せぬな」
「……」
第二師団本部師団長執務室。最も大きな机に行儀悪く座るシュターク・シュタークスンの前で、ソファに腰掛けた老人、副団長のハルクス・クラフトもまた難しそうに眉をひそめる。扉横の壁に背を預けるもう一人の副団長、スザナ・エルマンは、いつもの笑みを消してじっと天井を眺めていた。
「んで、どうするよ」
「出せる戦力は、せいぜい五割といったところか。それ以上は、都市の防備が手薄になりすぎるのう」
そもそもこの師団都市カールスラーエ要塞の立地は最前線であり、危険地帯だ。都市を囲む防壁の機能も、技術者不足で十全に発揮できないでいる。いくら脅威とはいえ、積極的に攻めてくるでもない歪虚一体に割ける余力はない。
「目下、其奴の戦力すら不明なのが問題じゃ。ゾンビ、風船ゾンビ、本人の能力もまた然り」
分からないことが多すぎた。
神出鬼没。危なくなればすぐ逃げる。こそこそと攫った人間の数も、こちらがどれだけ把握できているものか。
さらにはあの雪原で見せた、辺りを真っ赤に染め上げる異質な能力。あれがオルクスの結界と同種のものだとしたら、こちら側が数を揃えればそれが逆の効果を生む可能性すらあり得る。
「……んじゃ、聞いてみるか!」
進まない会話に何を思ったか、閃いたとばかりにそう言ってシュタークが手を叩いた。
後日、防水の施された小箱が撒かれた。主に山林、人里から離れた場所にだ。
その中には、一通の手紙が入っている。
「エリザベートの野郎へ」の書き出しから始まる文にあるのは、茶会への誘いと、日時と場所の指定だった。
「そんで、やつが来てみれば罠も何もない、本当にただ駄弁るだけ。困惑するのを尻目に撤退だ」
「う、うむ。まあ団長殿の意向に従うのは吝かでないのじゃが……かかるのか?」
「あのタイプは、悪い想像なんてしやしねえ。面白そうだって理由で、罠にでも頭から突っ込んでくるさ」
唸るハルクスにむけて、シュタークは自信ありげに笑みを浮かべた。
●
一方的に情報を引き出し、なおかつその意図を悟らせず。そのために終始意味の分からない会合を開く――すなわち、エリザベートと共にテーブルを囲んでお茶を飲んでくれ。そんな依頼がハンター達に舞い込んだ。
「やって欲しいことはいくつかある。一つは、敵の戦力、能力などを聞き出すこと。戦略的に重要だと思われる情報だな。もう一つは……エリザベートの写真を撮ってきてくれるとありがたい、手配書用だ」
そして、これが軍主導による作戦の一つだということを悟らせないのも、重要な事柄らしい。そのためこの作戦に、第二師団からの助力は見込めない。あくまで、好奇心に駆られたハンターが独自に接触を図ったと、特に意味のない会なのだと、そういうことにして欲しいということだった。
内容を説明しに来た第二師団員が、ばつの悪そうに頭を下げる。
「……いや完全に丸投げだな、どんな危険があるか分からないっていうのに。だがその、団長直々の命令なら俺に逆らうなんて出来るわけないし……負担を強いるのは分かっているんだが……」
師団員はしきりに言い訳を繰り返した後、そして最後に。
「これがまた重要なんだが」
釘を刺すよう全員の目を見ながら、
「決して、やつを刺激しないようにしてくれ」
そう言った。
●
「ねえ、どれ着てったらいいと思う?」
「……どれも同じだろう」
「は? 全然ちげえし。目ぇ見えてんの?」
鏡の前で楽しげに、ドレスを体に当てるエリザベート。数着のドレスその全てが真っ赤以外の何物でもなく、虫眼鏡でもなければ違いなど分からないのではと、青黒い全身鎧に身を包む青年オウレルは小さく溜息を吐くのだった。
「ま、あんな崩落程度でくだばるわきゃねえわな」
脳筋の極みであるような第二師団長シュターク・シュタークスン(kz0075)でさえ、難色を隠せない。面倒そうに溜息をついて、机の上に足を投げ出した。
「ふむ。例え潜伏先が分かったとして、向こうの戦力が未だ未知数な以上、迂闊に手は出せぬな」
「……」
第二師団本部師団長執務室。最も大きな机に行儀悪く座るシュターク・シュタークスンの前で、ソファに腰掛けた老人、副団長のハルクス・クラフトもまた難しそうに眉をひそめる。扉横の壁に背を預けるもう一人の副団長、スザナ・エルマンは、いつもの笑みを消してじっと天井を眺めていた。
「んで、どうするよ」
「出せる戦力は、せいぜい五割といったところか。それ以上は、都市の防備が手薄になりすぎるのう」
そもそもこの師団都市カールスラーエ要塞の立地は最前線であり、危険地帯だ。都市を囲む防壁の機能も、技術者不足で十全に発揮できないでいる。いくら脅威とはいえ、積極的に攻めてくるでもない歪虚一体に割ける余力はない。
「目下、其奴の戦力すら不明なのが問題じゃ。ゾンビ、風船ゾンビ、本人の能力もまた然り」
分からないことが多すぎた。
神出鬼没。危なくなればすぐ逃げる。こそこそと攫った人間の数も、こちらがどれだけ把握できているものか。
さらにはあの雪原で見せた、辺りを真っ赤に染め上げる異質な能力。あれがオルクスの結界と同種のものだとしたら、こちら側が数を揃えればそれが逆の効果を生む可能性すらあり得る。
「……んじゃ、聞いてみるか!」
進まない会話に何を思ったか、閃いたとばかりにそう言ってシュタークが手を叩いた。
後日、防水の施された小箱が撒かれた。主に山林、人里から離れた場所にだ。
その中には、一通の手紙が入っている。
「エリザベートの野郎へ」の書き出しから始まる文にあるのは、茶会への誘いと、日時と場所の指定だった。
「そんで、やつが来てみれば罠も何もない、本当にただ駄弁るだけ。困惑するのを尻目に撤退だ」
「う、うむ。まあ団長殿の意向に従うのは吝かでないのじゃが……かかるのか?」
「あのタイプは、悪い想像なんてしやしねえ。面白そうだって理由で、罠にでも頭から突っ込んでくるさ」
唸るハルクスにむけて、シュタークは自信ありげに笑みを浮かべた。
●
一方的に情報を引き出し、なおかつその意図を悟らせず。そのために終始意味の分からない会合を開く――すなわち、エリザベートと共にテーブルを囲んでお茶を飲んでくれ。そんな依頼がハンター達に舞い込んだ。
「やって欲しいことはいくつかある。一つは、敵の戦力、能力などを聞き出すこと。戦略的に重要だと思われる情報だな。もう一つは……エリザベートの写真を撮ってきてくれるとありがたい、手配書用だ」
そして、これが軍主導による作戦の一つだということを悟らせないのも、重要な事柄らしい。そのためこの作戦に、第二師団からの助力は見込めない。あくまで、好奇心に駆られたハンターが独自に接触を図ったと、特に意味のない会なのだと、そういうことにして欲しいということだった。
内容を説明しに来た第二師団員が、ばつの悪そうに頭を下げる。
「……いや完全に丸投げだな、どんな危険があるか分からないっていうのに。だがその、団長直々の命令なら俺に逆らうなんて出来るわけないし……負担を強いるのは分かっているんだが……」
師団員はしきりに言い訳を繰り返した後、そして最後に。
「これがまた重要なんだが」
釘を刺すよう全員の目を見ながら、
「決して、やつを刺激しないようにしてくれ」
そう言った。
●
「ねえ、どれ着てったらいいと思う?」
「……どれも同じだろう」
「は? 全然ちげえし。目ぇ見えてんの?」
鏡の前で楽しげに、ドレスを体に当てるエリザベート。数着のドレスその全てが真っ赤以外の何物でもなく、虫眼鏡でもなければ違いなど分からないのではと、青黒い全身鎧に身を包む青年オウレルは小さく溜息を吐くのだった。
リプレイ本文
空は晴れ渡り、気温も冬にしては良好。穏やかな風が木々を揺らし、鮮やかな木漏れ日が山間の広場を照らしていた。
「まぁ、まるで御伽噺のようなセッティングですわね」
広場の中央に置かれたテーブルや椅子。
どれもがアンティーク調のデザインで、白を基調に花々や鳥などの細かなレリーフが彫り込まれている。テーブルの上には純白のクロスが敷かれ、可愛らしいデザインのティーセットがいくつか並べられていた。
イスタ・イルマティーニ(ka1764)は、その様子を目の前に純粋に笑顔を見せた。身につけたゴシック風のドレスの裾が地面に付かないよう気を付けながら、早速と持参の菓子を準備に掛かる。
「見た目はまあ、メルヘンかもだけど」
対してカーミン・S・フィールズ(ka1559)は懐疑的に、直前で師団員から入手した発注リストに目を通す。何せ、場を用意したのはあの第二師団だ。目立つところは取り繕えても、細かな気配りには期待が出来ず、
「……ちょっと、これトイレは?」
そして案の定、不備を発見していた。
「歪虚とアイドルならいいのかもしれないけど、その辺でしろとか勘弁よ……」
「あー……たぶん、そういうことなんだろうね」
アーク・フォーサイス(ka6568)は、依頼の説明を行った師団員を思い出す。如何にも、そういうことを気にしなさそうな雰囲気だった。男である自分なら、それでも問題はないのだが。
「ほとんど女性なんだし、気にして欲しいよねー」
どちらの立場でかそう話に乗りながらも、十色 エニア(ka0370)は複雑な感情を整理する。
嫌い合い殺し合った仲。その前提があったとしても、場の空気を悪くすることは今回において一番の悪手だ。活かすべきは愛想のスキル。踊り子のバイトで鍛えた崩れぬ笑顔――!
何度か表情を作って練習し、エニアは覚悟を決めた。
●
約束の時間を大幅に過ぎ、「ちょっと突貫で用意してくる!」とトイレの整備に向かったカーミンが戻って来た頃。ようやく、空の向こうにエリザベートの姿が現れた。真紅のドレスに金の髪、憎悪を煮詰めて固めたような瞳にはにやにやと厭らしい笑みが浮かんでいる。
同時に、周囲の森の中にいくつもの気配が現れた。濃密な歪虚のマテリアルを感じ、ハンター達は無意識に体を硬くする。
「本日は」「お嬢様をお招きいただき」「誠に有り難うございます」
そして二つの声が交互に響く。現れたのは、執事服を纏った壮年の風貌を持つゾンビと、メイド服の若い女のゾンビだ。その後ろに、同じく男女で服装の分かれたゾンビが六体現れる。
「うわ、ホントに用意してあるし……何これ、意味分かんなぁい。きゃはははっ!」
ドレスの裾をふわりと翻し、同時に手にしたアイアンメイデンで地面を抉りながらエリザベートが地面に降り立つ。その表情は、嘲り以外の何物でもない笑みに歪んでいた。
「初めまして、エルバッハ・リオンと申します。よろしければ、エルと呼んでください」
エルバッハ・リオン(ka2434)が、エリザベートの前に立って声をかける。
「……んー」
その刹那――エリザベートが一瞬にして、エルバッハの眼前に移動していた。ぐいっと顔を近づけて、赤の瞳がエルバッハを覗き込む。
「その目っ……!」
「……っ!」
彼女の能力を知るエニアとシェリル・マイヤーズ(ka0509)が、はっとして駆け出そうとし、
「ふーん、まあまあかな」
エリザベートが顔を上げる。
「つか、何焦ってんの? 別に、今日は何にもしないっての。シラけんでしょ、そういうの」
睥睨の眼差しが二人に向き、分かってないなと言わんばかりに肩を竦めた。
警戒は解けない。いくら依頼とはいえ、もしあちらがやる気ならば。
「二人とも、私は大丈夫ですから」
エルバッハはそう言って、普段通りに微笑んだ。
どうやら本当に、何もされていないらしい。二人は体内のマテリアルを鎮め、武器に伸びた手を下ろした。
「今日は、『強者』であるあなたとお茶が飲めると、楽しみにしてきたんです」
エルバッハは、エリザベートにも笑みを向ける。
「俺はアーク・フォーサイス。よろしく」
極めて普通に、人間に接するようにアークは穏やかな声をかける。といっても、アークにはエリザベートが普通の人間とそう違いのないように思えていた。当然、空を飛ぶだとか巨大な鉄塊を持ち運ぶだとか、超常的な部分は多々あるが。
「今日は、おもてなしをしようと思って。またお茶会を開いたら、来たいと思って貰えるくらいにね」
「……こっちもまあまあか。おもてなしねぇ、楽しみにしとく」
間近に瞳を覗かれながらも、アークは淡々と言葉を交わした。
「では、わたくしも自己紹介を。古川舞踊、と申します」
白の着物に真紅の簪を合わせた出で立ちの古川 舞踊(ka1777)が、丁寧に頭を下げる。今の季節に沿った組み合わせとはいえこの世界では珍しい格好だが、西洋風の飾り付けに不思議と馴染んでいる。
その顔を、エリザベートはまた覗き込んだ。血を流し込んだような瞳が、真っ直ぐに舞踊を見て。
「――イイじゃん」
今度はニヤリと、不気味に口を歪めてそこから離れていった。
「……やっぱり」
その中で、シェリルの視線は、ゾンビ達の更に背後に向かっていた。木々の陰に紛れるように、青黒い鎧姿が佇んでいる。木に背を預け、腕を組み、その目は伏せられこちらを見もしていない。
別に何をする訳でもないが、シェリルは彼に会いに来た。もちろん、エリザベートとのお茶会も楽しむつもりだ。
それからカーミン、イスタと、面識のない順に自己紹介をすれば、そのたびにエリザベートは同じく品定めをするように顔を近づけた。あるいは本当に、獲物を探しているのかもしれなかったが。
「そうですわ、マカロンとクッキーを持参しましたの。人気菓子店のものなのですけど、お口に合うでしょうか」
「へえ、準備いいじゃん。……やっば、何これすげえ美味そう!」
イスタが菓子を取り出せば、意外なほどにエリザベートは食いついた。
「私は紅茶を用意したわ。王国と同盟のものを持ってきたんだけど、利き茶とかどう?」
「俺は緑茶と桜餅。どんなものか知ってる?」
「あら、奇遇ですね。わたくしが持参したのも和菓子なんです。故郷の味ですね」
「わたしはよさげな茶葉と……お店のもの先に出されちゃったけど、作ったお菓子を持ってきたよ」
ハンター達がそれぞれ同じく、持ってきたものを出していく。
「何これ、飲みホに食べホ? お茶会ってよりパーティじゃん、うわーこんなのマジ久しぶりだしすげえテンション上がるぅ!」
目を細めて楽しそうに、エリザベートは歯を見せて笑った。そしてくるりと踵を返し、
「――で、何のつもり? まさかホントに、お茶したいってんじゃないよねぇ」
こちらを振り返る瞳は、仄赤い光を帯びていた。
牙を見せる禍々しい笑顔。空間を埋め尽くすような、莫大な殺気が放たれる。
「……お茶会に応じてくれそうな方は、エリザベートさんしか知りませんでしたから」
気圧されることなく、エルバッハが口を開いた。
「私もいくつもの戦いをくぐり抜けて、敵だろうと味方だろうと『強者』に興味を持ちます。そして、歪虚の方々の中でこうしてお会い頂ける『強者』は、貴女だと」
「ふーん、興味ねぇ……」
エルバッハの話に、エリザベートはくつくつと笑う。それがどういった感情のものなのかは、想像も付かない。
「ぇと……うん、疑うなって方が無理な話だよね。でもこっちは喧嘩する気も、お茶会をぶち壊す気もないから、どうかそんな目で見ないでくださいな」
エニアも加わり、敵意がないことを何とか伝えようとする。
ほんのしばらく、エリザベートはハンター達の顔を眺める。緊迫の瞬間。ここをミスすれば、依頼は成功は絶望的だ。
――そして不意に、全ての殺気が嘘のように消え去った。
「ま、何でもイイか。細かいこと気にしても、何にも楽しくないしー」
手の平を返してあっけらかんと言い放ち、エリザベートはふわりと浮かんで椅子へと飛んだ。そのまま腰掛け偉そうに足を組み、
「じゃ、始めましょ」
片手を上げて、ゾンビ達に合図を送った。
●
「少し寒かったかしら。でも、この雰囲気に比べればマシよねー……」
羽織った純白のケープを胸元で手繰り、カーミンは苦笑いを浮かべる。
目を通した情報によれば、エニアとシェリルはエリザベートと相当にやり合っているらしい。自分がムードメーカーとして雰囲気を維持しなければと、カーミンは密かに気合いを入れた。
八体のゾンビが、テーブルの周りを忙しく歩き回る。その給仕は、素早く丁寧だ。所々の腐敗に目をつむれば、まるで位の高い貴族の屋敷にお呼ばれでもしたようだ。
「淹れるのは任せてもいいかな? 執事さん達の方が、わたしより上手そうだし」
「こちらも、適当に振る舞っていただけますか? ええと……ゾンビさん、だと呼びにくいですね。なんとお呼びすればよろしいかしら?」
「お嬢様は」「爺や」「婆やと」
「それじゃあ爺やさん、俺も給仕手伝うよ。緑茶淹れるの得意なんだ」
舞踊の和菓子を受け取り質問に答えたのは、特に他との違いのない個体だった。手伝いを申し出たアークが近づけど、その違いは容姿以外に見当たらない。
そうして手早く準備は進められ、あれよあれよのうちにテーブルが埋まっていく。湯気の立つティーポットに、並べられた色とりどりの菓子類。師団の用意したものの中にはパンやケーキなどもあり、それこそパーティのような様相だ。
「……えと、ちょっと気になったのですけど」
「んぁ、何よ」
少し躊躇いがちに呟いたイスタに、エリザベートは摘まんだクッキーをばりばり噛み砕きながら目を向ける。
「お食事中にする話ではないのですが、このゾンビさん達は……あまり臭わないなぁと」
「確かに、ゾンビといえば臭うものだと思っていましたね」
その横で、舞踊が同意する。
「なんだ、そんなの」
それに対してエリザベートは事も無げに、
「洗ったの。川に放り込んでさ、適当に」
ちょっと水真っ黒になっっちゃったけどねぇ、とのたまってみせた。その後に続いた、下流で誰かその水飲んでるかもね、という発言には、ハンター達も苦笑いを浮かべるしかなかったが。
「洗った、ですの? 腐臭を抑える技術があれば、商品化出来るかと思いましたのに……」
イスタは少し残念そうにしながら、紅茶のカップを傾ける。
「そういえば……エリザベート、いつもと雰囲気が……違うね。ドレス……変えた?」
「あ、分かっちゃうー? いいとこ見てんじゃん!」
首を傾げるシェリルの問いに、エリザベートは自慢げに口角を持ち上げて見せた。
「私も……ドレス、着てきたんだけど……どう、かな? 何か、アドバイスとか……貰える?」
「んー、まずもっと身長ないと話になんなくね? ちっちゃすぎんの。牛乳飲んだら? きゃはははっ!」
何が面白いのか。響く甲高い嬌笑に、エリザベート以外の雰囲気は何ともいえず。
「別に、変に着飾んなくても好きなの着たらいんじゃね?」
「それはちょっと、身も蓋もないというか……」
見かねてエニアがフォローに回る。
「それにさー、ドレスって言ったらやっぱ赤っしょ。んでレースいっぱい付いてるやつ。それだったらもっと似合うんじゃねぇ?」
「うん……今度は、考えて……みる」
特に真剣に答えているわけではないのだろう。エリザベートはすぐにシェリルから視線を外し、次の菓子を摘まみ上げている。
「それ、いい赤だよねぇ。私の名前も髪の赤が由来なんだけどさ。日光と経年劣化か色抜けが激しいし、赤って維持大変でしょ? どう管理してるの?」
カーミンが自分の髪を持ち上げながら、尋ねてみる。
「そりゃ、汚れたら捨ててるし。わざわざ管理とかマジ面倒じゃん?」
「あはは、それなら簡単よね」
「あら、そんなに素晴らしい仕立てのドレスですのに勿体ない……」
またも身も蓋もない発言に、カーミンは乾いた笑い、イスタは寂しげに愛着のある自分のドレスを撫でる。
イスタは、作り手の想い、持ち主の愛着、そこに宿る心こそが真の価値であると、そう伝えようかと思ったが、
「わたくしも、裁縫を嗜んでおりましたの。そのドレス、どのような方が仕立てられたのか、大変興味がありますわ」
飲み込んで、話題を変えることにした。少し話しただけだが、エリザベートが情緒を解するタイプであるとはあまり思えなかった。
「うーん、どんな奴って……変な奴? 人から貰ったのだから、よく分かんないんだよねぇ」
「それって、おっきな人形みたいな?」
エニアは過去に出会った歪虚を思い出していた。
「へぇ、よく知ってんじゃん」
「人形? お人形さんが、仕立てているのですか?」
実態はそれとはかけ離れたホラーであっても、聞く限りは夢がある。
「そ。そればっかりやってっからさぁ、ウケるよねぇ」
「お伽噺のようですわねぇ」
それこそメルヘン、童話のような話ではある。
「そいつ結構器用でさぁ、こっちが注文したら色々作ってくれんだけど……そうだ。ここに来る前、あたしドレス選んでたんだけどさぁ」
乗ってきたのか、エリザベートは続けて口を開く。もはやその表情に疑いの色はなく、純粋に楽しんでいるように見えた。
それからくいっと親指を森の方に向け、如何にオウレルが面白みのない奴かという話へと移っていく。ドレスの違いが分かってない、化粧やネイルもそんもの必要あるのかで切り捨てる――捕らえた人間を拷問するときも……
「殿方に服装の感想を聞いても大抵無駄ですものね。色が同じなら、全部同じに見えている印象があります。柄とか形とか、後は小物との組み合わせとか、色々と見るべき所はあるでしょうに」
あまり飲食の席で聞きたい話ではない。舞踊はここぞのタイミング、話の邪魔にならない瞬間を見計らって方向転換を図った。
「ま、別にいいんだけどね。分かってたら、それはそれでキモいし」
エリザベートが肩を竦める。
「エリザベートさんも、和服、着てみたらどうです? 似合うと思いますが」
「えー、趣味じゃないなぁ。動きにくそうだしぃ」
「ドレスもいいですが、和服もいいものですよ? 季節に合わせた柄や小物、選んでいるだけでも楽しいですし。まあ、動きづらいのは仕方ないのですが」
舞踊のおかげで物騒な話題から気を逸らし、それぞれに服装の話題で盛り上がる。エリザベートもなんだかんだ、ドレスにしか興味のないわけではないらしい。こちらが話せば、それなりに聞いてくれるようだ。
それからしばらくし、ひとまずの話題も落ち着いてきた頃。
「あ、もうお茶ないみたい」
ポットが空になりだした。八人分ともあれば、茶葉の消費も早いようだ。
しかし完全に全員のカップが空になる前に、計ったようなタイミングでゾンビ達は新たな紅茶を用意していた。
「エリザベートは、紅茶か緑茶どっちにする?」
ゾンビ達に混ざって、アークがお湯を片手にテーブルを回る。
「どっちでも」
「好みはないの?」
「お茶なんて全部同じじゃん?」
飲み物には本当に関心のなさそうに、エリザベートは菓子を次々に口に運んでいる。
その「全部同じ」という発言が、先ほど自分が言っていたオウレルへの批判と同じだと、気付いているのかいないのか。
「あ、それって私が持ってきたやつ?」
「ん、そうなのかな?」
アークの手にした茶葉を見て、カーミンが思い出したように、
「そうだ、利き茶しようよ利き茶。エリザベートって味覚ある?」
「は? あたしを何だと思ってんの?」
「じゃあどう? 利き茶」
また別の情報を得るためにも、新たな起爆剤を投入するべきだ。
カーミンの仕事は場の維持、雰囲気作り。この先、上手く言葉が引き出せるかどうかは仲間に任せ、ここは繋ぐに徹することとした。
カーミンはゾンビ達に、二種類の紅茶を別々のポットに入れて貰った。唯々諾々と人間の指示に従う歪虚の姿に、何だか不思議な感覚を覚えながら。
「どっちも同じでしょーこんなの」
「産地が違えば、気候も土壌も違いますからね。育て方も発酵の仕方も、それぞれ微妙に違うでしょうし」
「そんなんでそんなに変わんの?」
「どうなんでしょう。だから、確かめてみませんか?」
イスタは純粋に、味が気になったからの発言だったが、それが功を奏したらしい。エリザベートはつまらなそうにしているものの、一応、やってくれる気にはなったようだ。
「じゃあ、私からね!」
率先してカーミンが二つのカップを引き寄せる。こちらが楽しそうにやっていれば、エリザベートも乗ってくれるかもしれない。
「えーと、王国産が自然豊かな香り……同盟産は、しっかりとした味わいの香り高い……」
すんすんと香りを嗅ぎ、色を見て、
「そうだ、リアルブルーだとこうやるんだっけ?」
紅茶を口に含むと舌の上で転がし……そしてぺっと地面に吐きだした。
「……それ、紅茶でやるやつ?」
「え、だって飲み込むと味覚が鈍るって」
呆れたようなエリザベートの視線に晒されきょとんとするカーミン。その目に飛び込んできたのは……友人の笑顔だった。
「マイー!」
「あら、どうしました?」
ニコニコと、一見無垢な笑顔がそのときばかりは悪魔に見えた。
「ちょっと! いっつも嘘ばっかりじゃないの!」
「嘘『も』、教えているのです。そればかりではありませんよ?」
「それをやめてって言ってるのー!」
そんな二人の様子に、場の空気は和やかだ。カーミン一人の犠牲によって平穏が続くのなら、安いものなのかもしれない。
●
シェリルは一人、輪から離れて森の方へと歩いて行く。紅茶のポットと茶菓子を手に、森の緑に紛れるように佇む青黒い鎧を目印に。
「……来ると、思った」
オウレルは何の反応も見せない。気にせず、シェリルはオウレルの隣に腰を下ろす。
「ドレス……似合う? ……形から入って、みた」
完全な一方通行。お茶を勧めても、如何に菓子が美味いか語っても。ただ金属に話しかけているかのように、冷たい沈黙が跳ね返ってくる。
予想は出来たことだ。腹を貫かれたあの時から、簡単に元に戻ってくれるなどとは思っていない。ただ、彼女の気になることは、
「エリザベート……好き、なの……?」
「……何?」
初めて、オウレルが目を開いた。
「……魅了、まだされてるのかな、って」
「誰が、あんなものを好くか」
「嫌い、なの……?」
「当然だ」
「オルクス、は?」
答えはなかった。話は終わりだとばかりに、オウレルは腕を組み直す。
しかし、質問の内容に対する拒絶も見られず、シェリルはふと首を傾げる。
「オウレルの、おにーさんは……どえむ、ってやつ?」
「どっ……!」
素朴な疑問のように尋ねれば、オウレルは小さく噴き出した。
それが最後。以降、彼が口を開くことはなかった。シェリルもまた黙ったまま、隣でカップを傾ける。
●
「そういえば」
思い出したように、エニアがエリザベートに声をかける。
「暫く潜伏してたけれど、何か作ってたの? こっちも最近バタついてるから、ゾンビにしろ兵器にしろ『資材』の確保大変そうだなって」
「別に、資材なんて腐るほどあんだから困ってないけどぉ……最近ねえ」
「何か、嫌なことでも?」
カップに飲み物を注ぎ足しながらアークが尋ねれば、エリザベートは遠い目で溜息をついた。その表情の変化は珍しい。ハンター達は俄然興味が沸くが、焦りは禁物だ。
「エリザベートさん程の『強者』でも、悩みはあるのですね」
「……どんなの?」
「まあ、悩みっつーかねぇ」
エルバッハやシェリルが促すも、それ以上口にする様子はない。煮え切らない様子だが、話したくないのであれば、無理に聞き出す危険を冒すこともない。
「こっちは新しいスキル来て、すっごい威力出せるようになったんだよ! エリザベートは充電してるの? 戦闘なかったから必要ない感じ?」
「充電はずっと続けてるけどねぇ。つかたまにテンション上がって使っちゃうから、マジ全然貯まんねえの」
「色々な能力を持っているというのも、それはそれで大変そうですよね」
「まぁねー、傷なんかすぐ治るからいいんだけどさー。ゴミならいくらでもいるけど、使える玩具はなかなか手に入んないしぃ」
グチグチと、こちらの思惑通りにエリザベートが口を開く。
しかしそろそろ潮時か、あまり聞き過ぎて疑惑を持たれたら堪らない。
「そうだこれ、知ってる?」
そんなとき、カーミンが荷物から何かを取り出した。それは純白で、蛇腹に折られた扇形の、
「名を、『針千』!」
ハリセンだった。
「……は? それって」
「リアルブルーで開発された、約束を違えたものに圧倒的な苦痛と笑劇を与える拷問具なの!」
「いやそれ、そういうもんじゃ」
「エリザベートさん、そういうの好きだって聞いて持ってきたんだけど――」
豆を食らった鳩のように、エリザベートはきょとんとしている。それはいい。むしろプレゼンのしがいがあるというものだ。
しかし次の言葉を紡ぐ寸前、息を吸い込んだその瞬間に、カーミンは視界の端に別の大きな問題を見つけてしまった。
「?」
ニコニコとこちらを見ている、古川舞踊――!
「また嘘情報か!」
「あら、また気付かれてしまいましたか……」
やはりいつもの笑顔でも、考えが読まれ始めているようだ。これはもう少し、ポーカーフェイスの練習をした方がいいかもしれない。
……とはいえ、十分に彼女を泳がすことが出来た。
「ここには悪意しかないーっ?」
そんな表情も読まれてしまったらしい。少し顔を赤くしながら涙目でこちらを睨む友人の姿に、舞踊はより一層楽しげに微笑むのだった。
「……ちょうどいいですわね」
「イスタまでっ?」
「え、あら、そういう意味ではありませんわ! こほん、この楽しい時間を思い出に残したいと思いまして」
イスタは師団員に借り受けていた、魔導カメラを取り出した。
「一枚、よろしいでしょうか?」
「へぇ、用意いいじゃん」
エリザベートは特に嫌がる様子もなく、むしろ顎を引いて顔の角度を少し変え始めた。
「俺も入っていいのかな?」
「当然ですわ。ゾンビ様達も、遠慮なさらずに」
エリザベートを中心に、全員が集まった。
カシャリと甲高いシャッター音が響く。この奇妙な会合が二度と開かれることはなくとも、その薄い紙の中に、確かにこの時間は封じ込められていた。
そして徐々に日も傾き、辺りは薄暗くなり始めた。
「うん、ちょうどお茶もなくなった。そろそろお開きかな」
最後の一滴を注ぎ終わり、アークは息をつく。
給仕をしていた関係上、聞きに回ることが多かったが、女性陣の談笑している姿はいいものだ。たまに、談笑とは行かない瞬間もあったが。
テーブルの上に、ハンター達の持ってきた菓子類はもう残っていない。師匠の好んでいた緑茶や桜餅、これらもエリザベートは喜んで口に運んでくれていた。
歪虚は倒すべきもので、エリザベートはその中でも凶悪な部類に入る。それは分かっていても、こうして対面し話してみれば、彼女は普通……いや少し変わった人間の女性に見えた。
ハンターをやっていく中で、また違う側面が見えてくるのだろうか。
「またこうやって、お茶会を出来るといいね」
「気が向いたらね」
アークの言葉に、エリザベートは挑発的な笑みを浮かべた。
「んじゃ、あたしは帰るわ」
「エリザベート様やゾンビ様、皆様、本日は有り難うございました」
イスタは丁寧に頭を下げる。またこんな機会があればいい、そんな風に思いながら。
エリザベートは飛び去っていく。夕焼けに染まるオレンジの空に、真紅のドレスが溶け込んでいく。それに追従するようにオウレルは踵を返し、
「……っ」
シェリルは駆け出していた。その背に触れようと、まだ残っているかもしれない暖かみを確かめるために手を伸ばす。
しかし――彼を覆う冷たい鎧は、全てを拒絶するようにその小さな手をも肌に触れることを許さなかった。
「……おにーさん、とめる。諦めないから」
消えていく背中に、シェリルは静かな覚悟を届けた。
「奇妙な夢みたいな時間だったけれど……嫌じゃなかったわ」
次に会うときには間違いなく、また元の関係に戻るのだろう。それでも、今日過ごした時間は嘘ではない。
「得た情報で、絶対にあれを止めましょう」
「当然。そのために来たんだからね」
エルバッハの言葉に、エニアが頷く。
「はー、なんだかどっと疲れたわー……」
だらりと椅子にもたれ掛かり、カーミンは残った最後の紅茶を流し込む。
「? カーミンさんは、どうしてそんなに疲れていらっしゃるんですか?」
その様子にふと気付いた舞踊が首を傾げれば、
「……もうツッコむ気力もないわよ」
げんなりと、カーミンは襲い来る疲労に溜息をついた。
●
「……ん? どした、ちっこいの」
全部が終わった後、シェリルは一人、第二師団の本部に訪れていた。
特に何の問題もなく通された師団長の執務室。シュタークはそこで、眠そうにぼんやりと窓の外を眺めていた。
「……オウレルのおにーさんに、会った」
「そうか」
そっけない言葉。
シェリルはそこに、何の感情も見いだせなかった。押し殺しているのだろうか、まるでオウレルという名前に何の興味もないような声色だ。
シェリルはそれが少しだけ癪に障って、僅かに眉をひそめてシュタークを見る。
「お兄さん……オルクスだけじゃ、なくて……何か抱えてそう……だった」
魅了だけではない、そんな気がする。ああなる原因があった、下地は整っていたんだと、シェリルはそう考えていた。
「……何か、あったの……?」
師団に、師団長。それと副団長は、スザナといったか。その辺りで何かがあって、オウレルは何かを抱えたのだ。
――だから、あんな魅了に掛かった。
「答える義理は……ま、あのクソ野郎から引き出してくれた情報分くらいはあるか」
面倒そうに、シュタークが溜息をつく。
「つってもな、言えることはそんなにねえんだよ。――何もなかった。そう言うしかねえからな」
「……何も?」
「ああ、何にも。まあ強いて言や、あいつは昔、団長になる前のあたしの部隊にいたってくらいか? つっても大人しい奴だし、問題もなかった。むしろ大人しすぎて、あたしも最後まで名前覚えらんなかったくらいだしな」
シュタークが嘘を言っているようには見えなかった。
ならばオウレルは、完全に魅了のせいでああなったのか。魅了という力は、歪虚の力は、それほどまでに人を弄ぶのか。
シェリルは唇を噛む。
「ああ、そうだ」
そこにふと、シュタークは思い出したように、
「こりゃ最近分かったことなんだが――って、部外者に教えんのはまずいのか……?」
「……教えて」
「ま、大したことじゃねえか。オウレルの奴だがな、ずっとファミリーネーム隠してやがったんだよ。うちも色々雑だから、そんなもん誰も気にしなかったんだが」
シュタークは一度言葉を切り、机の上に山と積まれた紙束から一枚を引き抜くとシェリルの方に向けた。
「奴のフルネームは、オウレル・エルマン。うちの副団長、スザナ・エルマンの弟だったんだとさ」
調査済みの印が押された紙に、オウレルの来歴が並んでいた。
「まぁ、まるで御伽噺のようなセッティングですわね」
広場の中央に置かれたテーブルや椅子。
どれもがアンティーク調のデザインで、白を基調に花々や鳥などの細かなレリーフが彫り込まれている。テーブルの上には純白のクロスが敷かれ、可愛らしいデザインのティーセットがいくつか並べられていた。
イスタ・イルマティーニ(ka1764)は、その様子を目の前に純粋に笑顔を見せた。身につけたゴシック風のドレスの裾が地面に付かないよう気を付けながら、早速と持参の菓子を準備に掛かる。
「見た目はまあ、メルヘンかもだけど」
対してカーミン・S・フィールズ(ka1559)は懐疑的に、直前で師団員から入手した発注リストに目を通す。何せ、場を用意したのはあの第二師団だ。目立つところは取り繕えても、細かな気配りには期待が出来ず、
「……ちょっと、これトイレは?」
そして案の定、不備を発見していた。
「歪虚とアイドルならいいのかもしれないけど、その辺でしろとか勘弁よ……」
「あー……たぶん、そういうことなんだろうね」
アーク・フォーサイス(ka6568)は、依頼の説明を行った師団員を思い出す。如何にも、そういうことを気にしなさそうな雰囲気だった。男である自分なら、それでも問題はないのだが。
「ほとんど女性なんだし、気にして欲しいよねー」
どちらの立場でかそう話に乗りながらも、十色 エニア(ka0370)は複雑な感情を整理する。
嫌い合い殺し合った仲。その前提があったとしても、場の空気を悪くすることは今回において一番の悪手だ。活かすべきは愛想のスキル。踊り子のバイトで鍛えた崩れぬ笑顔――!
何度か表情を作って練習し、エニアは覚悟を決めた。
●
約束の時間を大幅に過ぎ、「ちょっと突貫で用意してくる!」とトイレの整備に向かったカーミンが戻って来た頃。ようやく、空の向こうにエリザベートの姿が現れた。真紅のドレスに金の髪、憎悪を煮詰めて固めたような瞳にはにやにやと厭らしい笑みが浮かんでいる。
同時に、周囲の森の中にいくつもの気配が現れた。濃密な歪虚のマテリアルを感じ、ハンター達は無意識に体を硬くする。
「本日は」「お嬢様をお招きいただき」「誠に有り難うございます」
そして二つの声が交互に響く。現れたのは、執事服を纏った壮年の風貌を持つゾンビと、メイド服の若い女のゾンビだ。その後ろに、同じく男女で服装の分かれたゾンビが六体現れる。
「うわ、ホントに用意してあるし……何これ、意味分かんなぁい。きゃはははっ!」
ドレスの裾をふわりと翻し、同時に手にしたアイアンメイデンで地面を抉りながらエリザベートが地面に降り立つ。その表情は、嘲り以外の何物でもない笑みに歪んでいた。
「初めまして、エルバッハ・リオンと申します。よろしければ、エルと呼んでください」
エルバッハ・リオン(ka2434)が、エリザベートの前に立って声をかける。
「……んー」
その刹那――エリザベートが一瞬にして、エルバッハの眼前に移動していた。ぐいっと顔を近づけて、赤の瞳がエルバッハを覗き込む。
「その目っ……!」
「……っ!」
彼女の能力を知るエニアとシェリル・マイヤーズ(ka0509)が、はっとして駆け出そうとし、
「ふーん、まあまあかな」
エリザベートが顔を上げる。
「つか、何焦ってんの? 別に、今日は何にもしないっての。シラけんでしょ、そういうの」
睥睨の眼差しが二人に向き、分かってないなと言わんばかりに肩を竦めた。
警戒は解けない。いくら依頼とはいえ、もしあちらがやる気ならば。
「二人とも、私は大丈夫ですから」
エルバッハはそう言って、普段通りに微笑んだ。
どうやら本当に、何もされていないらしい。二人は体内のマテリアルを鎮め、武器に伸びた手を下ろした。
「今日は、『強者』であるあなたとお茶が飲めると、楽しみにしてきたんです」
エルバッハは、エリザベートにも笑みを向ける。
「俺はアーク・フォーサイス。よろしく」
極めて普通に、人間に接するようにアークは穏やかな声をかける。といっても、アークにはエリザベートが普通の人間とそう違いのないように思えていた。当然、空を飛ぶだとか巨大な鉄塊を持ち運ぶだとか、超常的な部分は多々あるが。
「今日は、おもてなしをしようと思って。またお茶会を開いたら、来たいと思って貰えるくらいにね」
「……こっちもまあまあか。おもてなしねぇ、楽しみにしとく」
間近に瞳を覗かれながらも、アークは淡々と言葉を交わした。
「では、わたくしも自己紹介を。古川舞踊、と申します」
白の着物に真紅の簪を合わせた出で立ちの古川 舞踊(ka1777)が、丁寧に頭を下げる。今の季節に沿った組み合わせとはいえこの世界では珍しい格好だが、西洋風の飾り付けに不思議と馴染んでいる。
その顔を、エリザベートはまた覗き込んだ。血を流し込んだような瞳が、真っ直ぐに舞踊を見て。
「――イイじゃん」
今度はニヤリと、不気味に口を歪めてそこから離れていった。
「……やっぱり」
その中で、シェリルの視線は、ゾンビ達の更に背後に向かっていた。木々の陰に紛れるように、青黒い鎧姿が佇んでいる。木に背を預け、腕を組み、その目は伏せられこちらを見もしていない。
別に何をする訳でもないが、シェリルは彼に会いに来た。もちろん、エリザベートとのお茶会も楽しむつもりだ。
それからカーミン、イスタと、面識のない順に自己紹介をすれば、そのたびにエリザベートは同じく品定めをするように顔を近づけた。あるいは本当に、獲物を探しているのかもしれなかったが。
「そうですわ、マカロンとクッキーを持参しましたの。人気菓子店のものなのですけど、お口に合うでしょうか」
「へえ、準備いいじゃん。……やっば、何これすげえ美味そう!」
イスタが菓子を取り出せば、意外なほどにエリザベートは食いついた。
「私は紅茶を用意したわ。王国と同盟のものを持ってきたんだけど、利き茶とかどう?」
「俺は緑茶と桜餅。どんなものか知ってる?」
「あら、奇遇ですね。わたくしが持参したのも和菓子なんです。故郷の味ですね」
「わたしはよさげな茶葉と……お店のもの先に出されちゃったけど、作ったお菓子を持ってきたよ」
ハンター達がそれぞれ同じく、持ってきたものを出していく。
「何これ、飲みホに食べホ? お茶会ってよりパーティじゃん、うわーこんなのマジ久しぶりだしすげえテンション上がるぅ!」
目を細めて楽しそうに、エリザベートは歯を見せて笑った。そしてくるりと踵を返し、
「――で、何のつもり? まさかホントに、お茶したいってんじゃないよねぇ」
こちらを振り返る瞳は、仄赤い光を帯びていた。
牙を見せる禍々しい笑顔。空間を埋め尽くすような、莫大な殺気が放たれる。
「……お茶会に応じてくれそうな方は、エリザベートさんしか知りませんでしたから」
気圧されることなく、エルバッハが口を開いた。
「私もいくつもの戦いをくぐり抜けて、敵だろうと味方だろうと『強者』に興味を持ちます。そして、歪虚の方々の中でこうしてお会い頂ける『強者』は、貴女だと」
「ふーん、興味ねぇ……」
エルバッハの話に、エリザベートはくつくつと笑う。それがどういった感情のものなのかは、想像も付かない。
「ぇと……うん、疑うなって方が無理な話だよね。でもこっちは喧嘩する気も、お茶会をぶち壊す気もないから、どうかそんな目で見ないでくださいな」
エニアも加わり、敵意がないことを何とか伝えようとする。
ほんのしばらく、エリザベートはハンター達の顔を眺める。緊迫の瞬間。ここをミスすれば、依頼は成功は絶望的だ。
――そして不意に、全ての殺気が嘘のように消え去った。
「ま、何でもイイか。細かいこと気にしても、何にも楽しくないしー」
手の平を返してあっけらかんと言い放ち、エリザベートはふわりと浮かんで椅子へと飛んだ。そのまま腰掛け偉そうに足を組み、
「じゃ、始めましょ」
片手を上げて、ゾンビ達に合図を送った。
●
「少し寒かったかしら。でも、この雰囲気に比べればマシよねー……」
羽織った純白のケープを胸元で手繰り、カーミンは苦笑いを浮かべる。
目を通した情報によれば、エニアとシェリルはエリザベートと相当にやり合っているらしい。自分がムードメーカーとして雰囲気を維持しなければと、カーミンは密かに気合いを入れた。
八体のゾンビが、テーブルの周りを忙しく歩き回る。その給仕は、素早く丁寧だ。所々の腐敗に目をつむれば、まるで位の高い貴族の屋敷にお呼ばれでもしたようだ。
「淹れるのは任せてもいいかな? 執事さん達の方が、わたしより上手そうだし」
「こちらも、適当に振る舞っていただけますか? ええと……ゾンビさん、だと呼びにくいですね。なんとお呼びすればよろしいかしら?」
「お嬢様は」「爺や」「婆やと」
「それじゃあ爺やさん、俺も給仕手伝うよ。緑茶淹れるの得意なんだ」
舞踊の和菓子を受け取り質問に答えたのは、特に他との違いのない個体だった。手伝いを申し出たアークが近づけど、その違いは容姿以外に見当たらない。
そうして手早く準備は進められ、あれよあれよのうちにテーブルが埋まっていく。湯気の立つティーポットに、並べられた色とりどりの菓子類。師団の用意したものの中にはパンやケーキなどもあり、それこそパーティのような様相だ。
「……えと、ちょっと気になったのですけど」
「んぁ、何よ」
少し躊躇いがちに呟いたイスタに、エリザベートは摘まんだクッキーをばりばり噛み砕きながら目を向ける。
「お食事中にする話ではないのですが、このゾンビさん達は……あまり臭わないなぁと」
「確かに、ゾンビといえば臭うものだと思っていましたね」
その横で、舞踊が同意する。
「なんだ、そんなの」
それに対してエリザベートは事も無げに、
「洗ったの。川に放り込んでさ、適当に」
ちょっと水真っ黒になっっちゃったけどねぇ、とのたまってみせた。その後に続いた、下流で誰かその水飲んでるかもね、という発言には、ハンター達も苦笑いを浮かべるしかなかったが。
「洗った、ですの? 腐臭を抑える技術があれば、商品化出来るかと思いましたのに……」
イスタは少し残念そうにしながら、紅茶のカップを傾ける。
「そういえば……エリザベート、いつもと雰囲気が……違うね。ドレス……変えた?」
「あ、分かっちゃうー? いいとこ見てんじゃん!」
首を傾げるシェリルの問いに、エリザベートは自慢げに口角を持ち上げて見せた。
「私も……ドレス、着てきたんだけど……どう、かな? 何か、アドバイスとか……貰える?」
「んー、まずもっと身長ないと話になんなくね? ちっちゃすぎんの。牛乳飲んだら? きゃはははっ!」
何が面白いのか。響く甲高い嬌笑に、エリザベート以外の雰囲気は何ともいえず。
「別に、変に着飾んなくても好きなの着たらいんじゃね?」
「それはちょっと、身も蓋もないというか……」
見かねてエニアがフォローに回る。
「それにさー、ドレスって言ったらやっぱ赤っしょ。んでレースいっぱい付いてるやつ。それだったらもっと似合うんじゃねぇ?」
「うん……今度は、考えて……みる」
特に真剣に答えているわけではないのだろう。エリザベートはすぐにシェリルから視線を外し、次の菓子を摘まみ上げている。
「それ、いい赤だよねぇ。私の名前も髪の赤が由来なんだけどさ。日光と経年劣化か色抜けが激しいし、赤って維持大変でしょ? どう管理してるの?」
カーミンが自分の髪を持ち上げながら、尋ねてみる。
「そりゃ、汚れたら捨ててるし。わざわざ管理とかマジ面倒じゃん?」
「あはは、それなら簡単よね」
「あら、そんなに素晴らしい仕立てのドレスですのに勿体ない……」
またも身も蓋もない発言に、カーミンは乾いた笑い、イスタは寂しげに愛着のある自分のドレスを撫でる。
イスタは、作り手の想い、持ち主の愛着、そこに宿る心こそが真の価値であると、そう伝えようかと思ったが、
「わたくしも、裁縫を嗜んでおりましたの。そのドレス、どのような方が仕立てられたのか、大変興味がありますわ」
飲み込んで、話題を変えることにした。少し話しただけだが、エリザベートが情緒を解するタイプであるとはあまり思えなかった。
「うーん、どんな奴って……変な奴? 人から貰ったのだから、よく分かんないんだよねぇ」
「それって、おっきな人形みたいな?」
エニアは過去に出会った歪虚を思い出していた。
「へぇ、よく知ってんじゃん」
「人形? お人形さんが、仕立てているのですか?」
実態はそれとはかけ離れたホラーであっても、聞く限りは夢がある。
「そ。そればっかりやってっからさぁ、ウケるよねぇ」
「お伽噺のようですわねぇ」
それこそメルヘン、童話のような話ではある。
「そいつ結構器用でさぁ、こっちが注文したら色々作ってくれんだけど……そうだ。ここに来る前、あたしドレス選んでたんだけどさぁ」
乗ってきたのか、エリザベートは続けて口を開く。もはやその表情に疑いの色はなく、純粋に楽しんでいるように見えた。
それからくいっと親指を森の方に向け、如何にオウレルが面白みのない奴かという話へと移っていく。ドレスの違いが分かってない、化粧やネイルもそんもの必要あるのかで切り捨てる――捕らえた人間を拷問するときも……
「殿方に服装の感想を聞いても大抵無駄ですものね。色が同じなら、全部同じに見えている印象があります。柄とか形とか、後は小物との組み合わせとか、色々と見るべき所はあるでしょうに」
あまり飲食の席で聞きたい話ではない。舞踊はここぞのタイミング、話の邪魔にならない瞬間を見計らって方向転換を図った。
「ま、別にいいんだけどね。分かってたら、それはそれでキモいし」
エリザベートが肩を竦める。
「エリザベートさんも、和服、着てみたらどうです? 似合うと思いますが」
「えー、趣味じゃないなぁ。動きにくそうだしぃ」
「ドレスもいいですが、和服もいいものですよ? 季節に合わせた柄や小物、選んでいるだけでも楽しいですし。まあ、動きづらいのは仕方ないのですが」
舞踊のおかげで物騒な話題から気を逸らし、それぞれに服装の話題で盛り上がる。エリザベートもなんだかんだ、ドレスにしか興味のないわけではないらしい。こちらが話せば、それなりに聞いてくれるようだ。
それからしばらくし、ひとまずの話題も落ち着いてきた頃。
「あ、もうお茶ないみたい」
ポットが空になりだした。八人分ともあれば、茶葉の消費も早いようだ。
しかし完全に全員のカップが空になる前に、計ったようなタイミングでゾンビ達は新たな紅茶を用意していた。
「エリザベートは、紅茶か緑茶どっちにする?」
ゾンビ達に混ざって、アークがお湯を片手にテーブルを回る。
「どっちでも」
「好みはないの?」
「お茶なんて全部同じじゃん?」
飲み物には本当に関心のなさそうに、エリザベートは菓子を次々に口に運んでいる。
その「全部同じ」という発言が、先ほど自分が言っていたオウレルへの批判と同じだと、気付いているのかいないのか。
「あ、それって私が持ってきたやつ?」
「ん、そうなのかな?」
アークの手にした茶葉を見て、カーミンが思い出したように、
「そうだ、利き茶しようよ利き茶。エリザベートって味覚ある?」
「は? あたしを何だと思ってんの?」
「じゃあどう? 利き茶」
また別の情報を得るためにも、新たな起爆剤を投入するべきだ。
カーミンの仕事は場の維持、雰囲気作り。この先、上手く言葉が引き出せるかどうかは仲間に任せ、ここは繋ぐに徹することとした。
カーミンはゾンビ達に、二種類の紅茶を別々のポットに入れて貰った。唯々諾々と人間の指示に従う歪虚の姿に、何だか不思議な感覚を覚えながら。
「どっちも同じでしょーこんなの」
「産地が違えば、気候も土壌も違いますからね。育て方も発酵の仕方も、それぞれ微妙に違うでしょうし」
「そんなんでそんなに変わんの?」
「どうなんでしょう。だから、確かめてみませんか?」
イスタは純粋に、味が気になったからの発言だったが、それが功を奏したらしい。エリザベートはつまらなそうにしているものの、一応、やってくれる気にはなったようだ。
「じゃあ、私からね!」
率先してカーミンが二つのカップを引き寄せる。こちらが楽しそうにやっていれば、エリザベートも乗ってくれるかもしれない。
「えーと、王国産が自然豊かな香り……同盟産は、しっかりとした味わいの香り高い……」
すんすんと香りを嗅ぎ、色を見て、
「そうだ、リアルブルーだとこうやるんだっけ?」
紅茶を口に含むと舌の上で転がし……そしてぺっと地面に吐きだした。
「……それ、紅茶でやるやつ?」
「え、だって飲み込むと味覚が鈍るって」
呆れたようなエリザベートの視線に晒されきょとんとするカーミン。その目に飛び込んできたのは……友人の笑顔だった。
「マイー!」
「あら、どうしました?」
ニコニコと、一見無垢な笑顔がそのときばかりは悪魔に見えた。
「ちょっと! いっつも嘘ばっかりじゃないの!」
「嘘『も』、教えているのです。そればかりではありませんよ?」
「それをやめてって言ってるのー!」
そんな二人の様子に、場の空気は和やかだ。カーミン一人の犠牲によって平穏が続くのなら、安いものなのかもしれない。
●
シェリルは一人、輪から離れて森の方へと歩いて行く。紅茶のポットと茶菓子を手に、森の緑に紛れるように佇む青黒い鎧を目印に。
「……来ると、思った」
オウレルは何の反応も見せない。気にせず、シェリルはオウレルの隣に腰を下ろす。
「ドレス……似合う? ……形から入って、みた」
完全な一方通行。お茶を勧めても、如何に菓子が美味いか語っても。ただ金属に話しかけているかのように、冷たい沈黙が跳ね返ってくる。
予想は出来たことだ。腹を貫かれたあの時から、簡単に元に戻ってくれるなどとは思っていない。ただ、彼女の気になることは、
「エリザベート……好き、なの……?」
「……何?」
初めて、オウレルが目を開いた。
「……魅了、まだされてるのかな、って」
「誰が、あんなものを好くか」
「嫌い、なの……?」
「当然だ」
「オルクス、は?」
答えはなかった。話は終わりだとばかりに、オウレルは腕を組み直す。
しかし、質問の内容に対する拒絶も見られず、シェリルはふと首を傾げる。
「オウレルの、おにーさんは……どえむ、ってやつ?」
「どっ……!」
素朴な疑問のように尋ねれば、オウレルは小さく噴き出した。
それが最後。以降、彼が口を開くことはなかった。シェリルもまた黙ったまま、隣でカップを傾ける。
●
「そういえば」
思い出したように、エニアがエリザベートに声をかける。
「暫く潜伏してたけれど、何か作ってたの? こっちも最近バタついてるから、ゾンビにしろ兵器にしろ『資材』の確保大変そうだなって」
「別に、資材なんて腐るほどあんだから困ってないけどぉ……最近ねえ」
「何か、嫌なことでも?」
カップに飲み物を注ぎ足しながらアークが尋ねれば、エリザベートは遠い目で溜息をついた。その表情の変化は珍しい。ハンター達は俄然興味が沸くが、焦りは禁物だ。
「エリザベートさん程の『強者』でも、悩みはあるのですね」
「……どんなの?」
「まあ、悩みっつーかねぇ」
エルバッハやシェリルが促すも、それ以上口にする様子はない。煮え切らない様子だが、話したくないのであれば、無理に聞き出す危険を冒すこともない。
「こっちは新しいスキル来て、すっごい威力出せるようになったんだよ! エリザベートは充電してるの? 戦闘なかったから必要ない感じ?」
「充電はずっと続けてるけどねぇ。つかたまにテンション上がって使っちゃうから、マジ全然貯まんねえの」
「色々な能力を持っているというのも、それはそれで大変そうですよね」
「まぁねー、傷なんかすぐ治るからいいんだけどさー。ゴミならいくらでもいるけど、使える玩具はなかなか手に入んないしぃ」
グチグチと、こちらの思惑通りにエリザベートが口を開く。
しかしそろそろ潮時か、あまり聞き過ぎて疑惑を持たれたら堪らない。
「そうだこれ、知ってる?」
そんなとき、カーミンが荷物から何かを取り出した。それは純白で、蛇腹に折られた扇形の、
「名を、『針千』!」
ハリセンだった。
「……は? それって」
「リアルブルーで開発された、約束を違えたものに圧倒的な苦痛と笑劇を与える拷問具なの!」
「いやそれ、そういうもんじゃ」
「エリザベートさん、そういうの好きだって聞いて持ってきたんだけど――」
豆を食らった鳩のように、エリザベートはきょとんとしている。それはいい。むしろプレゼンのしがいがあるというものだ。
しかし次の言葉を紡ぐ寸前、息を吸い込んだその瞬間に、カーミンは視界の端に別の大きな問題を見つけてしまった。
「?」
ニコニコとこちらを見ている、古川舞踊――!
「また嘘情報か!」
「あら、また気付かれてしまいましたか……」
やはりいつもの笑顔でも、考えが読まれ始めているようだ。これはもう少し、ポーカーフェイスの練習をした方がいいかもしれない。
……とはいえ、十分に彼女を泳がすことが出来た。
「ここには悪意しかないーっ?」
そんな表情も読まれてしまったらしい。少し顔を赤くしながら涙目でこちらを睨む友人の姿に、舞踊はより一層楽しげに微笑むのだった。
「……ちょうどいいですわね」
「イスタまでっ?」
「え、あら、そういう意味ではありませんわ! こほん、この楽しい時間を思い出に残したいと思いまして」
イスタは師団員に借り受けていた、魔導カメラを取り出した。
「一枚、よろしいでしょうか?」
「へぇ、用意いいじゃん」
エリザベートは特に嫌がる様子もなく、むしろ顎を引いて顔の角度を少し変え始めた。
「俺も入っていいのかな?」
「当然ですわ。ゾンビ様達も、遠慮なさらずに」
エリザベートを中心に、全員が集まった。
カシャリと甲高いシャッター音が響く。この奇妙な会合が二度と開かれることはなくとも、その薄い紙の中に、確かにこの時間は封じ込められていた。
そして徐々に日も傾き、辺りは薄暗くなり始めた。
「うん、ちょうどお茶もなくなった。そろそろお開きかな」
最後の一滴を注ぎ終わり、アークは息をつく。
給仕をしていた関係上、聞きに回ることが多かったが、女性陣の談笑している姿はいいものだ。たまに、談笑とは行かない瞬間もあったが。
テーブルの上に、ハンター達の持ってきた菓子類はもう残っていない。師匠の好んでいた緑茶や桜餅、これらもエリザベートは喜んで口に運んでくれていた。
歪虚は倒すべきもので、エリザベートはその中でも凶悪な部類に入る。それは分かっていても、こうして対面し話してみれば、彼女は普通……いや少し変わった人間の女性に見えた。
ハンターをやっていく中で、また違う側面が見えてくるのだろうか。
「またこうやって、お茶会を出来るといいね」
「気が向いたらね」
アークの言葉に、エリザベートは挑発的な笑みを浮かべた。
「んじゃ、あたしは帰るわ」
「エリザベート様やゾンビ様、皆様、本日は有り難うございました」
イスタは丁寧に頭を下げる。またこんな機会があればいい、そんな風に思いながら。
エリザベートは飛び去っていく。夕焼けに染まるオレンジの空に、真紅のドレスが溶け込んでいく。それに追従するようにオウレルは踵を返し、
「……っ」
シェリルは駆け出していた。その背に触れようと、まだ残っているかもしれない暖かみを確かめるために手を伸ばす。
しかし――彼を覆う冷たい鎧は、全てを拒絶するようにその小さな手をも肌に触れることを許さなかった。
「……おにーさん、とめる。諦めないから」
消えていく背中に、シェリルは静かな覚悟を届けた。
「奇妙な夢みたいな時間だったけれど……嫌じゃなかったわ」
次に会うときには間違いなく、また元の関係に戻るのだろう。それでも、今日過ごした時間は嘘ではない。
「得た情報で、絶対にあれを止めましょう」
「当然。そのために来たんだからね」
エルバッハの言葉に、エニアが頷く。
「はー、なんだかどっと疲れたわー……」
だらりと椅子にもたれ掛かり、カーミンは残った最後の紅茶を流し込む。
「? カーミンさんは、どうしてそんなに疲れていらっしゃるんですか?」
その様子にふと気付いた舞踊が首を傾げれば、
「……もうツッコむ気力もないわよ」
げんなりと、カーミンは襲い来る疲労に溜息をついた。
●
「……ん? どした、ちっこいの」
全部が終わった後、シェリルは一人、第二師団の本部に訪れていた。
特に何の問題もなく通された師団長の執務室。シュタークはそこで、眠そうにぼんやりと窓の外を眺めていた。
「……オウレルのおにーさんに、会った」
「そうか」
そっけない言葉。
シェリルはそこに、何の感情も見いだせなかった。押し殺しているのだろうか、まるでオウレルという名前に何の興味もないような声色だ。
シェリルはそれが少しだけ癪に障って、僅かに眉をひそめてシュタークを見る。
「お兄さん……オルクスだけじゃ、なくて……何か抱えてそう……だった」
魅了だけではない、そんな気がする。ああなる原因があった、下地は整っていたんだと、シェリルはそう考えていた。
「……何か、あったの……?」
師団に、師団長。それと副団長は、スザナといったか。その辺りで何かがあって、オウレルは何かを抱えたのだ。
――だから、あんな魅了に掛かった。
「答える義理は……ま、あのクソ野郎から引き出してくれた情報分くらいはあるか」
面倒そうに、シュタークが溜息をつく。
「つってもな、言えることはそんなにねえんだよ。――何もなかった。そう言うしかねえからな」
「……何も?」
「ああ、何にも。まあ強いて言や、あいつは昔、団長になる前のあたしの部隊にいたってくらいか? つっても大人しい奴だし、問題もなかった。むしろ大人しすぎて、あたしも最後まで名前覚えらんなかったくらいだしな」
シュタークが嘘を言っているようには見えなかった。
ならばオウレルは、完全に魅了のせいでああなったのか。魅了という力は、歪虚の力は、それほどまでに人を弄ぶのか。
シェリルは唇を噛む。
「ああ、そうだ」
そこにふと、シュタークは思い出したように、
「こりゃ最近分かったことなんだが――って、部外者に教えんのはまずいのか……?」
「……教えて」
「ま、大したことじゃねえか。オウレルの奴だがな、ずっとファミリーネーム隠してやがったんだよ。うちも色々雑だから、そんなもん誰も気にしなかったんだが」
シュタークは一度言葉を切り、机の上に山と積まれた紙束から一枚を引き抜くとシェリルの方に向けた。
「奴のフルネームは、オウレル・エルマン。うちの副団長、スザナ・エルマンの弟だったんだとさ」
調査済みの印が押された紙に、オウレルの来歴が並んでいた。
依頼結果
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
相談卓 エルバッハ・リオン(ka2434) エルフ|12才|女性|魔術師(マギステル) |
最終発言 2016/12/04 10:04:42 |
|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2016/12/04 00:39:56 |
|
















