ゲスト
(ka0000)
【血盟】礫岩の檻
マスター:葉槻
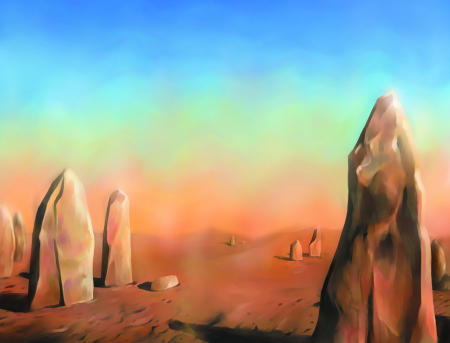
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~6人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2017/03/13 19:00
- 完成日
- 2017/03/28 00:32
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●ねがいのこえ
「……これが噂の『神の夢の中』か」
「……こりゃ、南方大陸だな……この乾いた感じ、暑さ、何より……」
見上げた先には、黒く大きな火山が見える。
白煙を吐いているが間違えるはずも無い“竜の巣”だ。
「……しっ、何か聞こえる」
一人が人差し指を口元に立てて、皆に沈黙するよう伝える。
耳を澄まし聞こえてきたのは、剣戟の音、男の怒声、そして竜の鳴き声。
「行こう!」
強欲竜に襲われているのだとしたら、助けなければ。
6人は音の方へと走って行った。
足元は草木の一本も無い砂礫の大地。
樹木のようにそびえる奇岩の群れの中を駆け抜け、見えたのは屈強な男達が大きな壺状の何かを守りつつ、竜と闘っている姿だ。
……だが、何かがおかしい、と直感が告げる。
そうだ。竜から負のマテリアルの気配を感じない。
だが、襲われているのだとしたら、助けなければと竜と人の間に入る。
「やめるんだ!」
6人がそれぞれ得物を握り、男達と竜を見る。
「お前達は……?」
男達が突如現れた6人に戸惑い、攻撃の手を止める。
その瞬間、竜は尾で石を弾き飛ばすと奥の壺を割った。
「しまった!」「おのれ!」
男達が再び武器を構えるが、竜はひと鳴きすると素早く翼を広げて飛び立っていく。
竜が去ったことに、ほっとして6人が男達へと向き直ると、割れた壺の中から一人の赤い衣を纏った7~8歳の少女が現れていた。
「助太刀感謝する。我々は龍に襲われ立ち往生していたのだ」
「あぁいや。無事で何よりだ」
男達の中でも代表格なのだろう、最も体格が良く、良く言えば筋骨隆々。悪く言えばずんぐりむっくりといった男が声を掛けてきた。
男の1人に支えられ、立ち上がった少女が6人を見て、軽く目を見張った。
「……覚醒者……?」
少女の言葉に男達がハッと6人を見る。
「まさか……あなた方6人とも覚醒者なのか?」
「あ、あぁ……」
「あぁ! 何てことだ……!! 覚醒者よ、どうか我々を助けて下さい!!」
突如男に頭を下げ……いや、もう土下座だ。男達全てが土下座して6人を拝む。
あなた達は何が起こったのかわからないまま……顔を見合わせたのだった。
●もとめのこえ
あなた達が向かったのは現代では『青の一族』と呼ばれるコボルド達が拠点として使っている地下遺跡だった。
どうやらこの時代ではここは彼らの一族の住まいらしい。
男達が少女を連れて帰ると、村中に落胆した色が見えたが、代わりに覚醒者である6人を紹介すると、村中が喜びに沸いた。
案内された地下の広い空間には豪奢な絨毯が敷かれ、香が焚かれているのだろう、ふわりと幽かな煙が鼻腔をくすぐる。
「私がアルタンの長です。ようこそ覚醒者の皆さん。我々はあなた方を歓迎します」
50代ぐらいだろうか。長というよりは現役の戦士のようなたくましい男が6人の前に現れた。
「……随分と若い人が多い。さぞかし優秀な一族の出とお見受けいたしました。どうか我々を助けていただきたい」
お礼には女でも土地でも財宝でもという話しが出て、慌ててあなた達は首を振る。
「とりあえず、話しを聞かせて下さい」
「うむ……皆さんは、先日の“龍の巣”の噴火は見られましたかな?」
問われて全員が首を横に振る。「ではその前は?」と聞かれ、更に首を振った。
「そうですか……噴火の予兆は、代々シャーマンが捉えます。先日の噴火も、その前も、見事言い当て、お陰で我が一族は巻き込まれずに済みました。しかし、まだ噴火は続くと、鎮まりはしないと言うのです」
そのシャーマン曰く。鎮める為には龍の巣の山頂で“儀式”をしなければならない。
“儀式”を行えば、龍の怒りは鎮まり、一族にはまた平穏が訪れる、と。
「そして、今日、男達は伝承の通り、“儀式”を行うために山頂へと向かい旅立ちましたが……龍によりそれを妨害されてしまいました。そこに皆さんが現れたのです!」
長が両膝を付き、両手を前に突き出すようにして地面に突っ伏した。
同時に、周囲にいた男達も皆、同じように土下座する。
「どうか、儀式完遂のため、皆を護衛しては貰えませんでしょうか! 何卒、よろしくお願いいたします!!」
一族の男衆達の土下座するその中央であなた達は顔を見合わせたのだった。
●あかいころも
赤い衣を着た少女は地下の聖堂にある神霊樹の傍らで祈りを捧げていた。
ふわりと少女型のパルムが寄り添い、微笑む。
その笑みに少女も微笑み返し、神霊樹を見上げる。
風もないのに、葉がさやさやと音も無く揺れる。
「上手くいかなかったの?」
少女に声を掛けたのは、指先から肘までが様々な色で斑に染まったひょろりとした若い男だ。
少女は小さく頷いて、男を見る。
「……6人の覚醒者が来たわ」
「え!? それは本当かい!?」
「今、長が“儀式”への協力をお願いしているところ」
「6人の覚醒者……本当にいたんだ……!」
「ムハニエル」
少女に名を呼ばれ、男――ムハニエルは顔を上げた。
「私は必ず“儀式”を完遂させるわ。だから、あなたも……お願いね」
少女の言葉に男は静かに、だが真剣な眼差しで頷き返す。
「あぁ、スーレー。ここ一面に立派な絵を描くよ。それが君との約束だからね」
スーレーと呼ばれた少女は、嬉しそうに笑うとパルムの頭を撫で、神霊樹に視線を移した。
神霊樹はただただ静かに見守るようにそこにあった。
●Unknown
避けようのない悲劇というものは誰しもにある。
それは怪我や病、愛しい者との死別、愛憎渦巻く相手との確執など様々な形で突然に降りかかる。
今、この一族が直面している事態もそうだが、それ以上の災厄がひたりひたりと迫っていた。
――その事実を知る者は、まだ、誰もいない。
「……これが噂の『神の夢の中』か」
「……こりゃ、南方大陸だな……この乾いた感じ、暑さ、何より……」
見上げた先には、黒く大きな火山が見える。
白煙を吐いているが間違えるはずも無い“竜の巣”だ。
「……しっ、何か聞こえる」
一人が人差し指を口元に立てて、皆に沈黙するよう伝える。
耳を澄まし聞こえてきたのは、剣戟の音、男の怒声、そして竜の鳴き声。
「行こう!」
強欲竜に襲われているのだとしたら、助けなければ。
6人は音の方へと走って行った。
足元は草木の一本も無い砂礫の大地。
樹木のようにそびえる奇岩の群れの中を駆け抜け、見えたのは屈強な男達が大きな壺状の何かを守りつつ、竜と闘っている姿だ。
……だが、何かがおかしい、と直感が告げる。
そうだ。竜から負のマテリアルの気配を感じない。
だが、襲われているのだとしたら、助けなければと竜と人の間に入る。
「やめるんだ!」
6人がそれぞれ得物を握り、男達と竜を見る。
「お前達は……?」
男達が突如現れた6人に戸惑い、攻撃の手を止める。
その瞬間、竜は尾で石を弾き飛ばすと奥の壺を割った。
「しまった!」「おのれ!」
男達が再び武器を構えるが、竜はひと鳴きすると素早く翼を広げて飛び立っていく。
竜が去ったことに、ほっとして6人が男達へと向き直ると、割れた壺の中から一人の赤い衣を纏った7~8歳の少女が現れていた。
「助太刀感謝する。我々は龍に襲われ立ち往生していたのだ」
「あぁいや。無事で何よりだ」
男達の中でも代表格なのだろう、最も体格が良く、良く言えば筋骨隆々。悪く言えばずんぐりむっくりといった男が声を掛けてきた。
男の1人に支えられ、立ち上がった少女が6人を見て、軽く目を見張った。
「……覚醒者……?」
少女の言葉に男達がハッと6人を見る。
「まさか……あなた方6人とも覚醒者なのか?」
「あ、あぁ……」
「あぁ! 何てことだ……!! 覚醒者よ、どうか我々を助けて下さい!!」
突如男に頭を下げ……いや、もう土下座だ。男達全てが土下座して6人を拝む。
あなた達は何が起こったのかわからないまま……顔を見合わせたのだった。
●もとめのこえ
あなた達が向かったのは現代では『青の一族』と呼ばれるコボルド達が拠点として使っている地下遺跡だった。
どうやらこの時代ではここは彼らの一族の住まいらしい。
男達が少女を連れて帰ると、村中に落胆した色が見えたが、代わりに覚醒者である6人を紹介すると、村中が喜びに沸いた。
案内された地下の広い空間には豪奢な絨毯が敷かれ、香が焚かれているのだろう、ふわりと幽かな煙が鼻腔をくすぐる。
「私がアルタンの長です。ようこそ覚醒者の皆さん。我々はあなた方を歓迎します」
50代ぐらいだろうか。長というよりは現役の戦士のようなたくましい男が6人の前に現れた。
「……随分と若い人が多い。さぞかし優秀な一族の出とお見受けいたしました。どうか我々を助けていただきたい」
お礼には女でも土地でも財宝でもという話しが出て、慌ててあなた達は首を振る。
「とりあえず、話しを聞かせて下さい」
「うむ……皆さんは、先日の“龍の巣”の噴火は見られましたかな?」
問われて全員が首を横に振る。「ではその前は?」と聞かれ、更に首を振った。
「そうですか……噴火の予兆は、代々シャーマンが捉えます。先日の噴火も、その前も、見事言い当て、お陰で我が一族は巻き込まれずに済みました。しかし、まだ噴火は続くと、鎮まりはしないと言うのです」
そのシャーマン曰く。鎮める為には龍の巣の山頂で“儀式”をしなければならない。
“儀式”を行えば、龍の怒りは鎮まり、一族にはまた平穏が訪れる、と。
「そして、今日、男達は伝承の通り、“儀式”を行うために山頂へと向かい旅立ちましたが……龍によりそれを妨害されてしまいました。そこに皆さんが現れたのです!」
長が両膝を付き、両手を前に突き出すようにして地面に突っ伏した。
同時に、周囲にいた男達も皆、同じように土下座する。
「どうか、儀式完遂のため、皆を護衛しては貰えませんでしょうか! 何卒、よろしくお願いいたします!!」
一族の男衆達の土下座するその中央であなた達は顔を見合わせたのだった。
●あかいころも
赤い衣を着た少女は地下の聖堂にある神霊樹の傍らで祈りを捧げていた。
ふわりと少女型のパルムが寄り添い、微笑む。
その笑みに少女も微笑み返し、神霊樹を見上げる。
風もないのに、葉がさやさやと音も無く揺れる。
「上手くいかなかったの?」
少女に声を掛けたのは、指先から肘までが様々な色で斑に染まったひょろりとした若い男だ。
少女は小さく頷いて、男を見る。
「……6人の覚醒者が来たわ」
「え!? それは本当かい!?」
「今、長が“儀式”への協力をお願いしているところ」
「6人の覚醒者……本当にいたんだ……!」
「ムハニエル」
少女に名を呼ばれ、男――ムハニエルは顔を上げた。
「私は必ず“儀式”を完遂させるわ。だから、あなたも……お願いね」
少女の言葉に男は静かに、だが真剣な眼差しで頷き返す。
「あぁ、スーレー。ここ一面に立派な絵を描くよ。それが君との約束だからね」
スーレーと呼ばれた少女は、嬉しそうに笑うとパルムの頭を撫で、神霊樹に視線を移した。
神霊樹はただただ静かに見守るようにそこにあった。
●Unknown
避けようのない悲劇というものは誰しもにある。
それは怪我や病、愛しい者との死別、愛憎渦巻く相手との確執など様々な形で突然に降りかかる。
今、この一族が直面している事態もそうだが、それ以上の災厄がひたりひたりと迫っていた。
――その事実を知る者は、まだ、誰もいない。
リプレイ本文
●ゆめのおわり
そうだ、知っていた。
これは過ぎ去った『過去』だ。
目の前で助けが必要な状況となっても、どんなに犠牲が出ても、それに手を差し伸べることはできない。
覚悟を以て見届ける、それが俺らの役目だと。
「スーレー」
カラカラに渇いた喉のせいで、名を呼ぶ声が掠れた。
「ありがとう。これで私はお役目を果たせる」
鳥肌が立つほどの負のマテリアルが吹き上がる火口に、ただの人であるはずのスーレーが立った。
「さようなら、6人の覚醒者。あなたたちの願いが叶う日が来る事を、祈っているわ」
晴れやかな笑顔でそう告げたスーレーは、その身を火口へと投げた。
そして、6人の意識もまた暗転した。
●アルタン
そもそもが現代の常識が通じない場所だ。
「シャーマンとは信用出来るのでしょうか」
流石に室内では兜を外し、少女の顔を晒したシルヴィア=ライゼンシュタイン(ka0338)の呟きに、岩井崎 旭(ka0234)は首を横に振る。
「多分、そこを俺達が不審に思ってもどーしよーもねぇ」
「あぁ、彼らにとっては『シャーマンの言葉こそが真実』なのだろうね。まぁ、話しを伺えるということだから……ふむ、来たようだね」
エアルドフリス(ka1856)が足音の方に目をやれば、カーテンを潜って男が1人顔を出した。
「こちらへ。シャーマンがお逢いなさるそうだ」
グリムバルド・グリーンウッド(ka4409)は5人と顔を見合わせて頷くと、前を行く男の後に付いて部屋を出た。
央崎 枢(ka5153)と金目(ka6190)だけがその場に残り、4人を見送る。
地下の町を自由に散策してもいいと、事前にアルタンの長から了承を得ていた。
彼らは驚くほど“客”に対して寛容だった。
それは彼らにとって6人が龍から守ってくれた恩人で有り、覚醒者というこの時代ではまだ稀有な存在であるからなのだろう。
枢と金目はまず、神霊樹のあった“聖堂”へと歩いて行く。
発光するマテリアル鉱石が天井や足元に埋め込まれているお陰で通路も室内も明るい。
迷いやすい地下遺跡だが、枢と金目は現代でコボルト達と交流する中で道を覚えていた。
そしてその道は、“過去”であっても驚くほど変わっていない。
「あぁ、本当に神霊樹だ」
地下へ地下へと降りて行った先では、現代と変わらない大きさの神霊樹が静かに枝葉を揺らしていた。
「あぁ、あなた達が『大精霊の声を聞く方法を探している覚醒者』?」
2人に近付いて来るのは、浅黒い肌に黒い髪の縦に長い印象を持たせる痩せた男だ。
「僕はムハニエル。前に、あなたの仲間が父と会っているから、あなた達のことは少しだけ知っている」
差し出された手を見て枢はギョッとする。
肘から指先までが様々な色に染まっていたからだ。
「あぁ、びっくりさせたかな? 別に病気とかじゃ無いんだ。ただ、染料が染み込んでもう取れないんだ」
「染料でそんなになるんですね……、俺は央崎枢。枢と呼んで下さい」
「ふふふ、カナメは丁寧なヒトだね」
握手を交わす。ムハニエルの手はカサカサに乾いていて、強く握れば砕けてしまいそうだと枢は不安に思った。
「僕は金目です」
金目もムハニエルの斑に染まった骨と皮しかない手を握り、軽く頭を下げた。
「キンメも丁寧なヒトだね。覚醒者は丁寧なヒトが多いのかな?」
ムハニエルは笑って神霊樹の前を指す。
「折角だから、少し話しでも?」
「えぇ、是非」
「聞きたい事とは?」
しわがれた老婆の声が香に燻された部屋に響く。
これは鎮静効果を伴う香だとエアルドフリスは思い当たるが、害はないため追求はせずに膝を折る。
「勿論儀式は協力させて頂きます。余所で巫女をやってましたのでね、重要さは解ります。
ただ、儀式の意義や目的、手順、謂れや歴史について教えていただけたらと」
「男の巫女か。この辺りじゃ見ないが、そういう一族もあると聞いたことはある。……名は?」
「エアルドフリスと申します」
「……聞かぬ音だ。随分と遠くから来たな」
老婆はそう告げると指先で肘掛けを鳴らした。
「何から話そうか。意義と目的と聞いたか? それは赤の龍の怒りを鎮める為だ」
「赤の龍が?」
旭がさらに口を挟もうと身を乗り出すも、エアルドフリスがそれを視線だけで制して、老婆へ続きを促す。
「あぁ。龍の巣には赤の龍と呼ばれる龍の王がいる。これが暴れて火山の噴火を起こす。
だから、穢れない巫女を捧げてその怒りを鎮めるのだ」
「巫女を捧げれば怒りが鎮まる?」
エアルドフリスが反復すれば老婆は深く頷いた。
「遥か昔から繰り返されてきた“儀式”だ。
我々アルタンの民は龍を奉る民。シャーマンは日々祈り、龍の巣を見、風を読み、川の流れ、地の動きからその都度適切な生贄を龍へと捧げる。
だが、50年から100年に1度、赤の龍は巫女を求める。それが今、この時なのだ」
「龍のための儀式が何故妨害されるのですか?」
「それが試練だからだ」
シルヴィアの問いに簡潔な答えが返る。
「試練に助っ人がいてもいいのか?」
「悪かったという例は聞いたことがない。大事なのは“試練を越えた先で儀式を行うこと”だ」
旭の問いにも迷い無く返答がされる。
『巫女を捧げ』『適切な生贄を捧げる』この二つだけで“儀式”が、スーレーと呼ばれていた少女の役割が4人にはわかってしまった。
「……本当に赤の龍がそれを望んでいるのか?」
低い、唸るような声で旭が問う。
「あぁ。噴火を止めるにはそれしかない」
ぎちり、と握った拳が音を立てた。
「……たとえば」
今までただ静かに聞いていたグリムバルドが口を開いた。
「運んだ先で儀式が失敗して、巫女が帰ってきたらどうなるんだ?」
重い沈黙が降りた。
香のせいで視界が白く煙った先で、老婆は身じろぎ一つせず告げる。
「赤の龍に身を捧げられぬ巫女など、必要ない」
「壁画を描くの? 今から?」
「そう、それが僕の仕事なんだ」
雑談をするうちに砕けた口調となった枢が問う。
砂の民の住むアンレス付近は、ナハト川の下流にあり肥沃な土地では植物も良く育った。
ゆえに、植物や動物から布をこさえ、それに染色したり、岩の民から金銀を仕入れ細工をすることで生計を立てる者が多くいたのだとムハニエルは説明する。
「……ただ、アンレスはもうヒトの住める場所じゃ無くなってしまったから……砂の民のほとんどは散り散りに散ってしまってね」
「何故です?」
「川が干上がってしまったんだ。雨期が来ても雨が降らない。それに“呪い”もね……
僕は幸いにしてこの一族に拾って貰えて、衣食住を保証して貰う代わりに壁画を描くことになったんだ」
「呪い……」
枢と金目が何と言葉をかけた物かと言い淀むと、ムハニエルは手を振って笑った。
「でも、良かった。父が常々言っていたんだ。“旅の覚醒者達が来たら力になってやれ”って」
「お父さんは?」
「もう10年前に死んだ。父は僕に沢山の知識を残したがっていたけれど、それが出来ないのが悔しいって言っていた。
だから、僕は絵を覚えた。絵を書けば、他の人に伝え、後に残すことが出来るから」
まだ紙が無い時代だ。識字率はほぼ無いと言っていい。となると、残るは口伝のみだ。
だが、口伝だけでは伝わらないものを残そうとムハニエルは絵を描くのだという。
「どんな絵にするつもり?」
『現代』でみた壁画は立派なものだった。
その意味を知りたくて枢は問うが、ムハニエルは気恥ずかしそうに頭を掻いた。
「……まだ、うまくまとまらなくて。何しろ、神霊樹の間なんて初めてだし……下手なものは書けないからね。
ここでこうやって今構想を練っているところさ」
「そういえば……この辺りにコボルドはいないのですか?」
そわそわと金目が問う。
「コボルド? そうだね……砂の民でも農業をする人たちはよく飼っていたけれど、岩の民は狩ってしまうからあまり見かけないね」
「飼う? 狩る?」
あまり穏やかでない言葉に枢が思わず問い返す。
「そう。広い畑を持っている人だと、人の代わりにコボルドを使って田畑の管理をしていたよ。彼らはちゃんと躾ればよく働くからね。
でもこの辺りは水はあっても基本的に食べるものが少ないから、食べてしまうんだよ」
金目が言葉がうまく紡げず金魚のように口をぱくぱくとさせる横で、枢が蒼白な顔でムハニエルを見る。
「まさか……さっき今日はごちそうだって振る舞ってもらったんだけどそれは……」
「あぁ、それはたぶん、大トカゲのステーキが出たんだろう? ここは祝い事があるとそれを出すから。
コボルドの肉は基本的には保存食として干し肉にするんだ。臭みが強いから」
何にせよ、理解の範疇外だった。
「う、馬とか牛とか……」
「栄えていた頃のアンレスなら多少は手に入ったかもだけど、ほとんど見たことがないな……ラクダの方がよく見たね。
ラクダはいいよ。砂漠を旅するにも、食べるにもいいし、骨は槍や矢に、皮はなめして靴にも出来る」
「お、ぉぉぉ……」
うんうんと頷くムハニエルを見て、ハイライトの消えた瞳で金目が低くうなる。
「そ、そういえば!」
話題を変えようと枢が身を乗り出した。
「スーレーって言ったっけ? あの子はどこにいるんだろう?」
「この時間なら清めの儀式じゃないかな」
「儀式……彼女は巫女なんですか?」
「そうだよ。多分清めが終わったらこっちへ来るんじゃないかな」
「あら、ずるい。私より先にお話に興じているなんて」
その時、まだ幼さの残る軽やかな声が入口から響いた。
「あぁ、スーレー。紹介するよ、覚醒者のカナメとキンメだ」
「先ほどは助けていただいてありがとうございました。あの時、お礼がきちんと言えなくてごめんなさい」
やはり赤い衣に身を包んでいる少女、スーレーがぺこりと頭を下げた。
「あぁ、いや、当然のことをしたまでです」
金目が首を振り、ムハニエルとの間を広げてスーレーの座る場所を設けると、スーレーは素直にそこへ収まった。
それと同時に再び入口付近がにぎやかになる。
「金目」
エアルドフリスらシャーマンと面会していた4人がやってきたのだ。
4人は金目の横に座っているスーレーを見ると軽く目を見張った。
「先ほどは助けていただいてありがとうございました」
静かに立ったスーレーが、4人を見て頭を下げる。
「当然のことをしただけだ」
旭が答えれば、スーレーが思わず声を上げて笑う。
「失礼しました。本当に、皆さんは立派な方ですね」
その笑い声は少女というよりずいぶんと子供っぽくて、年相応に聞こえた。
「あなたは……怖くないのですか?」
”儀式”と”巫女”について知ってしまったシルヴィアが精一杯言葉を選びながら問いかけた。
「怖い? あぁ、儀式が、ですか?」
スーレーはにこりと微笑む。
「こんな光栄なお役目はありません。
皆さんが覚醒者として”当然”に私を助けてくれたのと同じです。私は巫女ですから儀式を行うのは”当然”です」
その言葉に、瞳に、迷いは全く感じられなかった。
「明日は、よろしくお願いします」
深々と頭を下げられては、それ以上何も言えなくて、シルヴィアは下唇を噛む。
「初経前の清らかな少女のみが巫女となり、初経を迎えた後は未来のシャーマンとしての経験を学ぶ。
そもそもどうやらこの岩の民と呼ばれる人々は非常に寿命が短いらしい。
これは俺の憶測だが、負のマテリアルを内包する竜の巣が近いことと関係があるかもしれないな」
アルタンの人々が寝静まった頃。
客室にあてがわれた部屋で一同は円を組んで座りながら互いの情報を交換していく。
エアルドフリスの言葉にグリムバルドが続く。
「遺跡も彼らが作ったもので間違いないようだ。
噴火が起きると、各一定の距離ごとにふたをして、溶岩……彼らは『コーデイ』と呼んでいたけど、それの侵入を拒むらしい。
一族は全員で最下層のシェルター部分に逃げ込んで、噴火が収まるのを待つんだと。
ただ、面白いのは、噴火が起こった翌年は豊作になることが多いらしい」
「どういうことです?」
金目が首を傾げる。
「負のマテリアルが噴火して、その溶岩……コーデイ? に覆われて、それでどうして翌年が豊作になるんでしょう?」
「確かに俺たちが竜の巣のゲート前で戦った時、吹き溜まりにたまっていたのはとんでもない高濃度の負のマテリアルだった。
あれが地面を覆ったら豊作になんてなりようがない気が……」
グリムバルドが記憶を探るようにこめかみを指の腹で押す。
「てっきり、噴火のせいで今の南方大陸になったんだと思っていたんだけど……」
「……赤の龍がいるからじゃないか」
旭がぼそりと呟いた。
「ここと現代との違いは赤の龍がいるか、いないかだ。
赤の龍が噴火をある程度管理しているのだとしたら……」
「あぁ! あの壁画!」
枢は現代で見た壁画を思い出す。
火山とともに描かれた赤い龍。火山の中で眠る龍と、噴火とともに起きる龍。
「でも、噴火は赤の龍の”怒り”だと……あぁ」
シルヴィアは思い至る。
「噴火に赤の龍が関わっているから、彼らはそれを”怒り”と捉えているだけで……実際には違うのかもしれませんね」
「そう。それにこの岩の民は寿命が短い。おおよそ30年だそうだ」
老婆だと思っていたシャーマンが実は20台後半だと知った時の驚きは、ある意味この時代最大のインパクトがあったと言っていいだろう。
「口伝でしか伝承を残せず、それを確かめるすべもない。
下手をすれば3代、5代も噴火が起こらず、口伝の内容そのものがねじ曲がる可能性すらある。
それでも噴火は実際に起きるわけだから、それに対する対処をしなければならない。
たとえば、”たまたま巫女を生贄にした後に噴火が鎮まった”という事象があれば、それだけが延々と口伝として受け継がれる。
それが彼らにとっての『事実』となった……」
「龍が邪魔をするのは望んでいないからか」
旭がシャーマンの部屋で握り込んだ拳をじっと見つめる。
「わからない。そうであってほしい……という気持ちからの憶測にすぎない」
エアルドフリスが柔らかな髪を揺らす。
「……あの竜から負のマテリアルを感じませんでした……なんだか……ズレていて……すっきりしません。なんでしょうこの違和感は」
「とりあえず、俺とシルヴィアは明日、ちょっと先に行って竜の様子を見ていきたい」
旭の提案にエアルドフリスは頷いた。
「わかった。竜についてはあんた達の方が適任だろう。なに、こちらはなんとかするさ。なぁ?」
エアルドフリスに同意を求められ、金目が後頭部を掻きながら苦く笑う。
「……ドンパチするのはちょっと苦手なんですけどね……
まぁ、そうも言っていられませんし、えぇ、彼女が危険にさらされるのを見ているだけというのは……そうだ」
金目ははたと思い出して顔を上げた。
「僕達が来ない史実において儀式は成功したんでしょうか?」
「……どうなんだろうな。前は帰ったら、手元にそのときのファイルがあったから結果を見ることは出来たけど……
今の段階では成功と失敗、どちらが史実なのかわかりようがない」
以前にも南方大陸の過去に飛ばされたことのあるグリムバルドが両肩をすくめた。
「そうですか……」
儀式が成功すること、失敗すること、そのどちらが正解かわからない今、金目はこの部族が望む結果を届けようとしている。
「……複雑、ですね」
金目の言葉に、5人は沈黙で応えた。
●礫岩の山
翌朝。
早朝に(叩き)起こされた6人は朝食を胃に流し込むと、外の広場での待機を命じられていた。
「……朝ご飯がスープでよかった……」
昨夜衝撃の”ごちそう”の中身を知ってしまった枢としては、塩味のスープの中に、”すいとん”のような団子が入っている朝食は非常に食べやすかった。
考えてみれば、昨夜の晩ご飯でも野菜はほとんど出なかった。
見回しても、痩せて今にも枯れそうな草が所々生えてはいるが、おおよそ緑色は見かけない。
ここからもう少し西に行くと川があるそうだが、元は大河の源流だったそこは、現在細い小川と化していると、ハムニエルが言っていた。
そこまで行けば、多少の緑は見られるのだろうか。
そんなことをつらつらと枢が思っていると、奥から、4人の男たちが昨日見たのと同じような壷を担いでやってきた。
さらにそこに2人の屈強な男たちが得物を携えて加わる。
「では、行こう」
こうして巫女を掲げた”試練”が始まった。
「お、みーっけ」
先遣隊として先行した旭とシルヴィアは、赤い鱗のリザードマンを見つけると、「おーい」と呼びかけた。
リザードマンは声をかけられたことに驚いたようで、槍を構え身構える。
「あー、俺たち戦いたい訳じゃないんだ。ちょっと、話を聞きたいんだ」
そう訴えるが、リザードマンは警戒心MAXといった様子で、構えを解く気配はない。
「えーと、これとか……わかる?」
旭が赤い腕輪をリザードマンへと見せる。
それはかつて旭が龍園での戦いの際に青龍から報償として贈った龍鉱石が埋められている。
「先に断っておくけど、青龍からぶんどったとかじゃないから! ちゃんともらったもんだから!」
それを見たリザードマンはさらに険しい表情となった……ように二人には見えた。
「っ!」
大きく槍を横凪に振り、旭とシルヴィアが反射的にバックステップを踏むと、リザードマンはそれを機に奥へと逃げていく。
「えー! 話しさせろよー!!」
旭とシルヴィアはリザードマンの後を追って走り始めた。
リザードマンが走った先には、さらに一回り大きい四足歩行の龍がいた。
「おー? 今度こそ話が通じるかー? 力を示せ系なら、解りやすいんだけどな」
そういいつつも、先ほどと同じように龍に話しかける。
なにやらリザードマンに訴えられていた龍は、旭に話しかけられ、困ったように首を傾げた……ように二人には見えた。
そして、旭とシルヴィアから敵意がないことを読んだようで、二人にちらりと視線を送ったあと、ゆっくりと奥へと歩き始める。
「……付いてこい……ということでしょうか?」
「かな?」
二人は龍とリザードマンの後をついて奥へと進んでいった。
「……ここまで龍と遭遇しないなんて」
リーダー格の男が感嘆の息を吐いた。
「岩井崎さんたち、うまくやってくれているみたいですね?」
壷の右側に付く金目が最後尾に付くエアルドフリスに声をかける。
「……だといいが」
徐々に負のマテリアルが濃くなるのを感じる。
いくら屈強である戦士とは言え、おそらくただの人であるアルタンの男たちには酷な環境になりつつある。
それでも、小さな雑魔を時折見かけることはあっても、大型の歪虚を見かけることはなかった。
……そうだ。元々ここは負のマテリアルが集まる場所。
それなのに歪虚がいない、というのはそれを駆逐しているモノがいるということだ。
「龍以外と戦うことはないのですか?」
エアルドフリスが問うと、男はやや表情を曇らせる。
「もちろんある。訳の分からない化け物どもだ。倒せる程度のモノならいいが、強すぎる時には龍に助けを求める。龍は我らの守護者だから」
それを聞いた左側に付くグリムバルドが眉間にしわを寄せた。
「龍がここ一帯の歪虚……化け物を退治してくれているのか?」
「そうだ。だから、我々は龍に感謝し、龍に捧げ物をして、龍を奉る。
龍は力の象徴であり、繁栄の象徴であり、火山を司る。
……だが、最近そうではないという部族が出始めた」
「どういうことです?」
先頭を行く枢も瞳は前を見ながら、耳は話へと傾ける。
「赤の龍は悪だと。龍が噴火を起こし、我々を苦しめている元凶なのになぜ奉るのかという部族が現れ始めた。
確かに一度噴火が起これば大地から生命は奪われる。
だが、その翌年は雨に恵まれ、大地からは様々な草木が芽吹き、実りは豊かになる。
……しかし、噴火が続けば、せっかく穫れるはずだった実りそのすべてがなくなる。
だから、噴火など起こらないよう、龍を殺そうという部族が出てきている」
「雨が降らなくなったと聞きました」
金目は昨夜ハムニエルから聞いた言葉を思い出す。
雨の量が減り、そのせいで下流にあったアンレスの町は酷い干ばつに遭っていると。
「そうだ。だが、冬を越えてからすでに2度、噴火があった。
シャーマンの話では近日中にもう一度噴火があるだろうと。
だから、来年は今よりはマシになるはずなんだ。だが、それを他の部族は信じない」
噴火に巻き込まれた者が出た部族、噴火により家畜を失った部族、噴火により畑を失った部族。これらから不満が噴出した。
「特に、砂の民を多く保護している部族は砂の民からの不満がすごいらしい。
砂の民は体が弱いから、アルタンまでは呼びでもしない限り来ないが、北の方の部族には逃げてきた砂の民のおかげで食べる物に苦労しているところもあるらしい」
「……それは、大変だ」
「だから、何としても試練を越えて、儀式を行わなければ。龍に怒りを鎮めてもらい、これ以上噴火が起こらないようにしなければ」
彼らから感じた切羽詰まった様子は、他の部族とも関連していたからだと知り、4人はそれぞれに言葉を失う。
同時にこの事実を知れば、巫女という役割を与えられているスーレーが頑として巫女としての役割を果たそうとする理由も見えてきた。
「目的の場所までもうすぐだ、行こう」
男たちの顔色は悪い。
それでも、彼らを止めることは4人には出来なかった。
「麓の岩の民が困ってるみたいだったが、なぜ人を止めるのんだ?
龍の巣の噴火と、儀式はどんな関係があるんだ? そもそもあの儀式って意味あるのか?」
案内された先でさらに一回り大きな龍を前に、旭は問いかけた。
しかし、その龍も人語を理解は出来ても話せる訳ではないらしく、困惑したように首を傾げる。
「……やはり、竜から負のマテリアルを感じません……」
魔物のような全身鎧を装着しているシルヴィアを見かけだけで襲うこともせず、龍達はそこにいる。
「壷を割っただけと考えると……ただ止めているだけのような気がします……」
「敵意さえ感じない」と続けようとしたシルヴィアを遮るように、龍が大きく頷いた……ようにみえた。
「あー、俺の言ってること、わかる?」
問えば、大きな龍が同じようにその巨大な頭部を上げ下げする。
「あ、イエス・ノーで出来る質問ならいけそうか?
竜の巣が危険だから、人の出入りを禁じてる?」
同様に頭部が上げ下げされる。
おぉ! やった! と旭が歓声をあげれば、シルヴィアも兜の下で表情を明るくした。
「竜の巣の噴火と岩の民がやろうとしている儀式って関係がある?」
その問いには少し困ったように首を傾げる。
「あーえーと。儀式をすれば噴火は止まる?」
その問いに、龍は大きく首を横に振った。
「……あぁ」
シルヴィアが安堵の息を吐いた。
やはり、龍が生贄を要求しているわけではないのだ。
壷を割るのは、最も人間に危害を加えずに下山させるための彼らなりの優しさだったのだ。
「なぁ! 赤の龍は王龍は生きているんだよな!?」
旭の問いに、龍は瞬きながら当然だと言わんばかりに首を上下させる。
そのとき、上空から龍の咆哮が響いた。
見上げればさらに大きな光の翼を持った赤い龍がそこにはいた。
「っ!!」
見違えるはずもない。
二度三度と刃を交え、最期にはともに戦い、愛のある明日を、未来を願った。
「ザッハーク!!」
しかし、ザッハークは声が届かなかったのか、そのまま彼は部隊を率いて飛んでいってしまう。
そうしている間に、二人と意志疎通を図ろうとしていた龍達もザッハーク達が向かった方向へと飛び、走り始める。
「な、何だ? どうした?」
「龍が総出で相手にしなければならないような敵が現れたのかもしれません……旭さん」
「行こう!」
迷いなく旭も走り出し、シルヴィアは「はい」と応えるとその背を追った。
8合目ほどまで来ただろうか。
男たちの顔色は悪く、一人が突然飛び出てきた雑魔に足をやられて膝を付いた。
「あとは、俺たちだけで行こう」
グリムバルドの提案に、男たちはほぼ土気色になった顔で、それでもその提案を突っぱねた。
「でも、試練っていうのは頂上に着けばいいんだろ? 助っ人がいてもいいって言ってた。なら、担ぐ人間がその助っ人でもいいんじゃないか?」
「幸い、覚醒者というのは頑丈なんです。必ず辿り着いてみせますから」
グリムバルドの言葉を支えるように金目も頷いて見せる。
これが、雑魔相手に手間取るような駆け出しの覚醒者ならこの問答は長時間に及んだだろうが、ここまで雑魔を文字通り蹴散らしながら来た4人の強さを、男たちは認めていた。
「……すまない。よろしく頼む」
「あぁ、必ず送り届けるよ」
男たちが下山していくのを見送って、4人は壷を抱えた。
「スーレーさん、聞こえますか?」
「はい」
「そんなわけで、ここからは僕達があなたを運びます。ちょっとさっきより揺れたりしたらごめんなさい」
金目の言葉に壷の中からクスクスと笑い声が漏れる。
「わかりました。よろしくお願いします」
旭とシルヴィアが辿り着いた先では、龍たちが炎をまき散らしながら戦っていた。
「……狂気……!!」
小型狂気の群が、龍たちを襲っていた。
「助太刀するぜ!」
「援護します」
旭はエクスプロイドに巻き付けていた布を引き剥がすと同時に龍へと延びていた触手を切り払った。
ザッハークはと旭が視線を彷徨わせると、彼は空から来る中型を相手取っているようだった。
「旭さん!」
シルヴィアの声にとっさにハルバードを横に持ち飛ぶ。
旭のいた場所に背後からクラゲじみた狂気が迫っていたのを、シルヴィアが的確に打ち抜く。
「サンキューな!」
頭上に、まだ強欲竜ではないザッハークがいる。
また、ともに戦える。
それが嬉しくて、旭の口元は自然と綻んだ。
だが、それもこの局面を乗り越えなければ話にならない。
ゆるんだ口元を真一文字に引き絞ると、旭は気合いとともにハルバードを振るった。
●そして……
「あーーーーーーザッハークと会話出来なかったぁっっ!!!」
「旭さん! 気持ちは分かりますが、ここはライブラリです!」
叫ぶ旭にシー! と人差し指を立てたシルヴィアが旭を宥め賺す。
「儀式は、無事終わったよ」
エアルドフリスがファイルを開き、辿る。
「儀式、なんてそんな何かがあるわけじゃなかった。
彼女はただ、皆の幸せを願って、火口へと飛び降りた」
「……そう、ですか」
シルヴィアが視線を落とす。
あんな幼い子が生贄にならないといけないなんて。
そして、”それを竜が望んでいなかった”という事実が、ただただ哀しみを増長する。
「そうか……狂気がもういたんだ……もしかして、噴火が増えたのも狂気のせいなのかな?」
「わからないが……無関係ではない気はするねぇ」
枢の言葉にエアルドフリスが両肩をすくめ、パイプを取り出そうとして……ライブラリという場所を思い出して指でなぞるだけにとどめた。
この『夢』は無意味な物はほとんど見せない。
最後に狂気が出てきたという事は、これが一つのキーなのだろうと誰もが己の思考に落ちていき、場を沈黙が占めた。
「……あぁ、正史でもやはり狂気に襲われ、竜がそちらに向かっている間に儀式は行われたとあるね」
エアルドフリスはファイルを閉じると、「見るかい?」と金目に問うが、金目はそれに否を示す。
「たとえ、僕達がどれだけ『夢』の中で過去に干渉しても、夢は夢なんだなってことがわかったので……」
記録の中にハンターたちの姿はない。ただ、おそらく自分たちが体験した『過去』は『夢』として記録されるのだろう。
「……願わくば、彼女が安らかでありますように」
グリムバルドが呟けば、全員がそれにうなずいて、小さく祈りを捧げたのだった。
●Unknown
「王」
王の間と呼ばれる広い空間に、一体の大きな龍が胸に何かを抱えながら入っていく。
「イケニエの人間がまた」
その両手の平の上には、気を失った赤い衣を着た少女がいた。
「……そうか」
低く、淡々とした声音からは何の感情の機微も感じられない。
「いつもどおりに」
「仰せのままに」
深くお辞儀をして、龍は少女を抱えて出て行く。
それを見送って赤の龍は一つため息を吐いた。
静かに火口そばへと歩き寄ると、みちみちと溜まっている負のマテリアルプールを覗く。
その金の瞳はただただ静かで。
彼が何を考えているのかなど、誰にも察することは出来なかった――
そうだ、知っていた。
これは過ぎ去った『過去』だ。
目の前で助けが必要な状況となっても、どんなに犠牲が出ても、それに手を差し伸べることはできない。
覚悟を以て見届ける、それが俺らの役目だと。
「スーレー」
カラカラに渇いた喉のせいで、名を呼ぶ声が掠れた。
「ありがとう。これで私はお役目を果たせる」
鳥肌が立つほどの負のマテリアルが吹き上がる火口に、ただの人であるはずのスーレーが立った。
「さようなら、6人の覚醒者。あなたたちの願いが叶う日が来る事を、祈っているわ」
晴れやかな笑顔でそう告げたスーレーは、その身を火口へと投げた。
そして、6人の意識もまた暗転した。
●アルタン
そもそもが現代の常識が通じない場所だ。
「シャーマンとは信用出来るのでしょうか」
流石に室内では兜を外し、少女の顔を晒したシルヴィア=ライゼンシュタイン(ka0338)の呟きに、岩井崎 旭(ka0234)は首を横に振る。
「多分、そこを俺達が不審に思ってもどーしよーもねぇ」
「あぁ、彼らにとっては『シャーマンの言葉こそが真実』なのだろうね。まぁ、話しを伺えるということだから……ふむ、来たようだね」
エアルドフリス(ka1856)が足音の方に目をやれば、カーテンを潜って男が1人顔を出した。
「こちらへ。シャーマンがお逢いなさるそうだ」
グリムバルド・グリーンウッド(ka4409)は5人と顔を見合わせて頷くと、前を行く男の後に付いて部屋を出た。
央崎 枢(ka5153)と金目(ka6190)だけがその場に残り、4人を見送る。
地下の町を自由に散策してもいいと、事前にアルタンの長から了承を得ていた。
彼らは驚くほど“客”に対して寛容だった。
それは彼らにとって6人が龍から守ってくれた恩人で有り、覚醒者というこの時代ではまだ稀有な存在であるからなのだろう。
枢と金目はまず、神霊樹のあった“聖堂”へと歩いて行く。
発光するマテリアル鉱石が天井や足元に埋め込まれているお陰で通路も室内も明るい。
迷いやすい地下遺跡だが、枢と金目は現代でコボルト達と交流する中で道を覚えていた。
そしてその道は、“過去”であっても驚くほど変わっていない。
「あぁ、本当に神霊樹だ」
地下へ地下へと降りて行った先では、現代と変わらない大きさの神霊樹が静かに枝葉を揺らしていた。
「あぁ、あなた達が『大精霊の声を聞く方法を探している覚醒者』?」
2人に近付いて来るのは、浅黒い肌に黒い髪の縦に長い印象を持たせる痩せた男だ。
「僕はムハニエル。前に、あなたの仲間が父と会っているから、あなた達のことは少しだけ知っている」
差し出された手を見て枢はギョッとする。
肘から指先までが様々な色に染まっていたからだ。
「あぁ、びっくりさせたかな? 別に病気とかじゃ無いんだ。ただ、染料が染み込んでもう取れないんだ」
「染料でそんなになるんですね……、俺は央崎枢。枢と呼んで下さい」
「ふふふ、カナメは丁寧なヒトだね」
握手を交わす。ムハニエルの手はカサカサに乾いていて、強く握れば砕けてしまいそうだと枢は不安に思った。
「僕は金目です」
金目もムハニエルの斑に染まった骨と皮しかない手を握り、軽く頭を下げた。
「キンメも丁寧なヒトだね。覚醒者は丁寧なヒトが多いのかな?」
ムハニエルは笑って神霊樹の前を指す。
「折角だから、少し話しでも?」
「えぇ、是非」
「聞きたい事とは?」
しわがれた老婆の声が香に燻された部屋に響く。
これは鎮静効果を伴う香だとエアルドフリスは思い当たるが、害はないため追求はせずに膝を折る。
「勿論儀式は協力させて頂きます。余所で巫女をやってましたのでね、重要さは解ります。
ただ、儀式の意義や目的、手順、謂れや歴史について教えていただけたらと」
「男の巫女か。この辺りじゃ見ないが、そういう一族もあると聞いたことはある。……名は?」
「エアルドフリスと申します」
「……聞かぬ音だ。随分と遠くから来たな」
老婆はそう告げると指先で肘掛けを鳴らした。
「何から話そうか。意義と目的と聞いたか? それは赤の龍の怒りを鎮める為だ」
「赤の龍が?」
旭がさらに口を挟もうと身を乗り出すも、エアルドフリスがそれを視線だけで制して、老婆へ続きを促す。
「あぁ。龍の巣には赤の龍と呼ばれる龍の王がいる。これが暴れて火山の噴火を起こす。
だから、穢れない巫女を捧げてその怒りを鎮めるのだ」
「巫女を捧げれば怒りが鎮まる?」
エアルドフリスが反復すれば老婆は深く頷いた。
「遥か昔から繰り返されてきた“儀式”だ。
我々アルタンの民は龍を奉る民。シャーマンは日々祈り、龍の巣を見、風を読み、川の流れ、地の動きからその都度適切な生贄を龍へと捧げる。
だが、50年から100年に1度、赤の龍は巫女を求める。それが今、この時なのだ」
「龍のための儀式が何故妨害されるのですか?」
「それが試練だからだ」
シルヴィアの問いに簡潔な答えが返る。
「試練に助っ人がいてもいいのか?」
「悪かったという例は聞いたことがない。大事なのは“試練を越えた先で儀式を行うこと”だ」
旭の問いにも迷い無く返答がされる。
『巫女を捧げ』『適切な生贄を捧げる』この二つだけで“儀式”が、スーレーと呼ばれていた少女の役割が4人にはわかってしまった。
「……本当に赤の龍がそれを望んでいるのか?」
低い、唸るような声で旭が問う。
「あぁ。噴火を止めるにはそれしかない」
ぎちり、と握った拳が音を立てた。
「……たとえば」
今までただ静かに聞いていたグリムバルドが口を開いた。
「運んだ先で儀式が失敗して、巫女が帰ってきたらどうなるんだ?」
重い沈黙が降りた。
香のせいで視界が白く煙った先で、老婆は身じろぎ一つせず告げる。
「赤の龍に身を捧げられぬ巫女など、必要ない」
「壁画を描くの? 今から?」
「そう、それが僕の仕事なんだ」
雑談をするうちに砕けた口調となった枢が問う。
砂の民の住むアンレス付近は、ナハト川の下流にあり肥沃な土地では植物も良く育った。
ゆえに、植物や動物から布をこさえ、それに染色したり、岩の民から金銀を仕入れ細工をすることで生計を立てる者が多くいたのだとムハニエルは説明する。
「……ただ、アンレスはもうヒトの住める場所じゃ無くなってしまったから……砂の民のほとんどは散り散りに散ってしまってね」
「何故です?」
「川が干上がってしまったんだ。雨期が来ても雨が降らない。それに“呪い”もね……
僕は幸いにしてこの一族に拾って貰えて、衣食住を保証して貰う代わりに壁画を描くことになったんだ」
「呪い……」
枢と金目が何と言葉をかけた物かと言い淀むと、ムハニエルは手を振って笑った。
「でも、良かった。父が常々言っていたんだ。“旅の覚醒者達が来たら力になってやれ”って」
「お父さんは?」
「もう10年前に死んだ。父は僕に沢山の知識を残したがっていたけれど、それが出来ないのが悔しいって言っていた。
だから、僕は絵を覚えた。絵を書けば、他の人に伝え、後に残すことが出来るから」
まだ紙が無い時代だ。識字率はほぼ無いと言っていい。となると、残るは口伝のみだ。
だが、口伝だけでは伝わらないものを残そうとムハニエルは絵を描くのだという。
「どんな絵にするつもり?」
『現代』でみた壁画は立派なものだった。
その意味を知りたくて枢は問うが、ムハニエルは気恥ずかしそうに頭を掻いた。
「……まだ、うまくまとまらなくて。何しろ、神霊樹の間なんて初めてだし……下手なものは書けないからね。
ここでこうやって今構想を練っているところさ」
「そういえば……この辺りにコボルドはいないのですか?」
そわそわと金目が問う。
「コボルド? そうだね……砂の民でも農業をする人たちはよく飼っていたけれど、岩の民は狩ってしまうからあまり見かけないね」
「飼う? 狩る?」
あまり穏やかでない言葉に枢が思わず問い返す。
「そう。広い畑を持っている人だと、人の代わりにコボルドを使って田畑の管理をしていたよ。彼らはちゃんと躾ればよく働くからね。
でもこの辺りは水はあっても基本的に食べるものが少ないから、食べてしまうんだよ」
金目が言葉がうまく紡げず金魚のように口をぱくぱくとさせる横で、枢が蒼白な顔でムハニエルを見る。
「まさか……さっき今日はごちそうだって振る舞ってもらったんだけどそれは……」
「あぁ、それはたぶん、大トカゲのステーキが出たんだろう? ここは祝い事があるとそれを出すから。
コボルドの肉は基本的には保存食として干し肉にするんだ。臭みが強いから」
何にせよ、理解の範疇外だった。
「う、馬とか牛とか……」
「栄えていた頃のアンレスなら多少は手に入ったかもだけど、ほとんど見たことがないな……ラクダの方がよく見たね。
ラクダはいいよ。砂漠を旅するにも、食べるにもいいし、骨は槍や矢に、皮はなめして靴にも出来る」
「お、ぉぉぉ……」
うんうんと頷くムハニエルを見て、ハイライトの消えた瞳で金目が低くうなる。
「そ、そういえば!」
話題を変えようと枢が身を乗り出した。
「スーレーって言ったっけ? あの子はどこにいるんだろう?」
「この時間なら清めの儀式じゃないかな」
「儀式……彼女は巫女なんですか?」
「そうだよ。多分清めが終わったらこっちへ来るんじゃないかな」
「あら、ずるい。私より先にお話に興じているなんて」
その時、まだ幼さの残る軽やかな声が入口から響いた。
「あぁ、スーレー。紹介するよ、覚醒者のカナメとキンメだ」
「先ほどは助けていただいてありがとうございました。あの時、お礼がきちんと言えなくてごめんなさい」
やはり赤い衣に身を包んでいる少女、スーレーがぺこりと頭を下げた。
「あぁ、いや、当然のことをしたまでです」
金目が首を振り、ムハニエルとの間を広げてスーレーの座る場所を設けると、スーレーは素直にそこへ収まった。
それと同時に再び入口付近がにぎやかになる。
「金目」
エアルドフリスらシャーマンと面会していた4人がやってきたのだ。
4人は金目の横に座っているスーレーを見ると軽く目を見張った。
「先ほどは助けていただいてありがとうございました」
静かに立ったスーレーが、4人を見て頭を下げる。
「当然のことをしただけだ」
旭が答えれば、スーレーが思わず声を上げて笑う。
「失礼しました。本当に、皆さんは立派な方ですね」
その笑い声は少女というよりずいぶんと子供っぽくて、年相応に聞こえた。
「あなたは……怖くないのですか?」
”儀式”と”巫女”について知ってしまったシルヴィアが精一杯言葉を選びながら問いかけた。
「怖い? あぁ、儀式が、ですか?」
スーレーはにこりと微笑む。
「こんな光栄なお役目はありません。
皆さんが覚醒者として”当然”に私を助けてくれたのと同じです。私は巫女ですから儀式を行うのは”当然”です」
その言葉に、瞳に、迷いは全く感じられなかった。
「明日は、よろしくお願いします」
深々と頭を下げられては、それ以上何も言えなくて、シルヴィアは下唇を噛む。
「初経前の清らかな少女のみが巫女となり、初経を迎えた後は未来のシャーマンとしての経験を学ぶ。
そもそもどうやらこの岩の民と呼ばれる人々は非常に寿命が短いらしい。
これは俺の憶測だが、負のマテリアルを内包する竜の巣が近いことと関係があるかもしれないな」
アルタンの人々が寝静まった頃。
客室にあてがわれた部屋で一同は円を組んで座りながら互いの情報を交換していく。
エアルドフリスの言葉にグリムバルドが続く。
「遺跡も彼らが作ったもので間違いないようだ。
噴火が起きると、各一定の距離ごとにふたをして、溶岩……彼らは『コーデイ』と呼んでいたけど、それの侵入を拒むらしい。
一族は全員で最下層のシェルター部分に逃げ込んで、噴火が収まるのを待つんだと。
ただ、面白いのは、噴火が起こった翌年は豊作になることが多いらしい」
「どういうことです?」
金目が首を傾げる。
「負のマテリアルが噴火して、その溶岩……コーデイ? に覆われて、それでどうして翌年が豊作になるんでしょう?」
「確かに俺たちが竜の巣のゲート前で戦った時、吹き溜まりにたまっていたのはとんでもない高濃度の負のマテリアルだった。
あれが地面を覆ったら豊作になんてなりようがない気が……」
グリムバルドが記憶を探るようにこめかみを指の腹で押す。
「てっきり、噴火のせいで今の南方大陸になったんだと思っていたんだけど……」
「……赤の龍がいるからじゃないか」
旭がぼそりと呟いた。
「ここと現代との違いは赤の龍がいるか、いないかだ。
赤の龍が噴火をある程度管理しているのだとしたら……」
「あぁ! あの壁画!」
枢は現代で見た壁画を思い出す。
火山とともに描かれた赤い龍。火山の中で眠る龍と、噴火とともに起きる龍。
「でも、噴火は赤の龍の”怒り”だと……あぁ」
シルヴィアは思い至る。
「噴火に赤の龍が関わっているから、彼らはそれを”怒り”と捉えているだけで……実際には違うのかもしれませんね」
「そう。それにこの岩の民は寿命が短い。おおよそ30年だそうだ」
老婆だと思っていたシャーマンが実は20台後半だと知った時の驚きは、ある意味この時代最大のインパクトがあったと言っていいだろう。
「口伝でしか伝承を残せず、それを確かめるすべもない。
下手をすれば3代、5代も噴火が起こらず、口伝の内容そのものがねじ曲がる可能性すらある。
それでも噴火は実際に起きるわけだから、それに対する対処をしなければならない。
たとえば、”たまたま巫女を生贄にした後に噴火が鎮まった”という事象があれば、それだけが延々と口伝として受け継がれる。
それが彼らにとっての『事実』となった……」
「龍が邪魔をするのは望んでいないからか」
旭がシャーマンの部屋で握り込んだ拳をじっと見つめる。
「わからない。そうであってほしい……という気持ちからの憶測にすぎない」
エアルドフリスが柔らかな髪を揺らす。
「……あの竜から負のマテリアルを感じませんでした……なんだか……ズレていて……すっきりしません。なんでしょうこの違和感は」
「とりあえず、俺とシルヴィアは明日、ちょっと先に行って竜の様子を見ていきたい」
旭の提案にエアルドフリスは頷いた。
「わかった。竜についてはあんた達の方が適任だろう。なに、こちらはなんとかするさ。なぁ?」
エアルドフリスに同意を求められ、金目が後頭部を掻きながら苦く笑う。
「……ドンパチするのはちょっと苦手なんですけどね……
まぁ、そうも言っていられませんし、えぇ、彼女が危険にさらされるのを見ているだけというのは……そうだ」
金目ははたと思い出して顔を上げた。
「僕達が来ない史実において儀式は成功したんでしょうか?」
「……どうなんだろうな。前は帰ったら、手元にそのときのファイルがあったから結果を見ることは出来たけど……
今の段階では成功と失敗、どちらが史実なのかわかりようがない」
以前にも南方大陸の過去に飛ばされたことのあるグリムバルドが両肩をすくめた。
「そうですか……」
儀式が成功すること、失敗すること、そのどちらが正解かわからない今、金目はこの部族が望む結果を届けようとしている。
「……複雑、ですね」
金目の言葉に、5人は沈黙で応えた。
●礫岩の山
翌朝。
早朝に(叩き)起こされた6人は朝食を胃に流し込むと、外の広場での待機を命じられていた。
「……朝ご飯がスープでよかった……」
昨夜衝撃の”ごちそう”の中身を知ってしまった枢としては、塩味のスープの中に、”すいとん”のような団子が入っている朝食は非常に食べやすかった。
考えてみれば、昨夜の晩ご飯でも野菜はほとんど出なかった。
見回しても、痩せて今にも枯れそうな草が所々生えてはいるが、おおよそ緑色は見かけない。
ここからもう少し西に行くと川があるそうだが、元は大河の源流だったそこは、現在細い小川と化していると、ハムニエルが言っていた。
そこまで行けば、多少の緑は見られるのだろうか。
そんなことをつらつらと枢が思っていると、奥から、4人の男たちが昨日見たのと同じような壷を担いでやってきた。
さらにそこに2人の屈強な男たちが得物を携えて加わる。
「では、行こう」
こうして巫女を掲げた”試練”が始まった。
「お、みーっけ」
先遣隊として先行した旭とシルヴィアは、赤い鱗のリザードマンを見つけると、「おーい」と呼びかけた。
リザードマンは声をかけられたことに驚いたようで、槍を構え身構える。
「あー、俺たち戦いたい訳じゃないんだ。ちょっと、話を聞きたいんだ」
そう訴えるが、リザードマンは警戒心MAXといった様子で、構えを解く気配はない。
「えーと、これとか……わかる?」
旭が赤い腕輪をリザードマンへと見せる。
それはかつて旭が龍園での戦いの際に青龍から報償として贈った龍鉱石が埋められている。
「先に断っておくけど、青龍からぶんどったとかじゃないから! ちゃんともらったもんだから!」
それを見たリザードマンはさらに険しい表情となった……ように二人には見えた。
「っ!」
大きく槍を横凪に振り、旭とシルヴィアが反射的にバックステップを踏むと、リザードマンはそれを機に奥へと逃げていく。
「えー! 話しさせろよー!!」
旭とシルヴィアはリザードマンの後を追って走り始めた。
リザードマンが走った先には、さらに一回り大きい四足歩行の龍がいた。
「おー? 今度こそ話が通じるかー? 力を示せ系なら、解りやすいんだけどな」
そういいつつも、先ほどと同じように龍に話しかける。
なにやらリザードマンに訴えられていた龍は、旭に話しかけられ、困ったように首を傾げた……ように二人には見えた。
そして、旭とシルヴィアから敵意がないことを読んだようで、二人にちらりと視線を送ったあと、ゆっくりと奥へと歩き始める。
「……付いてこい……ということでしょうか?」
「かな?」
二人は龍とリザードマンの後をついて奥へと進んでいった。
「……ここまで龍と遭遇しないなんて」
リーダー格の男が感嘆の息を吐いた。
「岩井崎さんたち、うまくやってくれているみたいですね?」
壷の右側に付く金目が最後尾に付くエアルドフリスに声をかける。
「……だといいが」
徐々に負のマテリアルが濃くなるのを感じる。
いくら屈強である戦士とは言え、おそらくただの人であるアルタンの男たちには酷な環境になりつつある。
それでも、小さな雑魔を時折見かけることはあっても、大型の歪虚を見かけることはなかった。
……そうだ。元々ここは負のマテリアルが集まる場所。
それなのに歪虚がいない、というのはそれを駆逐しているモノがいるということだ。
「龍以外と戦うことはないのですか?」
エアルドフリスが問うと、男はやや表情を曇らせる。
「もちろんある。訳の分からない化け物どもだ。倒せる程度のモノならいいが、強すぎる時には龍に助けを求める。龍は我らの守護者だから」
それを聞いた左側に付くグリムバルドが眉間にしわを寄せた。
「龍がここ一帯の歪虚……化け物を退治してくれているのか?」
「そうだ。だから、我々は龍に感謝し、龍に捧げ物をして、龍を奉る。
龍は力の象徴であり、繁栄の象徴であり、火山を司る。
……だが、最近そうではないという部族が出始めた」
「どういうことです?」
先頭を行く枢も瞳は前を見ながら、耳は話へと傾ける。
「赤の龍は悪だと。龍が噴火を起こし、我々を苦しめている元凶なのになぜ奉るのかという部族が現れ始めた。
確かに一度噴火が起これば大地から生命は奪われる。
だが、その翌年は雨に恵まれ、大地からは様々な草木が芽吹き、実りは豊かになる。
……しかし、噴火が続けば、せっかく穫れるはずだった実りそのすべてがなくなる。
だから、噴火など起こらないよう、龍を殺そうという部族が出てきている」
「雨が降らなくなったと聞きました」
金目は昨夜ハムニエルから聞いた言葉を思い出す。
雨の量が減り、そのせいで下流にあったアンレスの町は酷い干ばつに遭っていると。
「そうだ。だが、冬を越えてからすでに2度、噴火があった。
シャーマンの話では近日中にもう一度噴火があるだろうと。
だから、来年は今よりはマシになるはずなんだ。だが、それを他の部族は信じない」
噴火に巻き込まれた者が出た部族、噴火により家畜を失った部族、噴火により畑を失った部族。これらから不満が噴出した。
「特に、砂の民を多く保護している部族は砂の民からの不満がすごいらしい。
砂の民は体が弱いから、アルタンまでは呼びでもしない限り来ないが、北の方の部族には逃げてきた砂の民のおかげで食べる物に苦労しているところもあるらしい」
「……それは、大変だ」
「だから、何としても試練を越えて、儀式を行わなければ。龍に怒りを鎮めてもらい、これ以上噴火が起こらないようにしなければ」
彼らから感じた切羽詰まった様子は、他の部族とも関連していたからだと知り、4人はそれぞれに言葉を失う。
同時にこの事実を知れば、巫女という役割を与えられているスーレーが頑として巫女としての役割を果たそうとする理由も見えてきた。
「目的の場所までもうすぐだ、行こう」
男たちの顔色は悪い。
それでも、彼らを止めることは4人には出来なかった。
「麓の岩の民が困ってるみたいだったが、なぜ人を止めるのんだ?
龍の巣の噴火と、儀式はどんな関係があるんだ? そもそもあの儀式って意味あるのか?」
案内された先でさらに一回り大きな龍を前に、旭は問いかけた。
しかし、その龍も人語を理解は出来ても話せる訳ではないらしく、困惑したように首を傾げる。
「……やはり、竜から負のマテリアルを感じません……」
魔物のような全身鎧を装着しているシルヴィアを見かけだけで襲うこともせず、龍達はそこにいる。
「壷を割っただけと考えると……ただ止めているだけのような気がします……」
「敵意さえ感じない」と続けようとしたシルヴィアを遮るように、龍が大きく頷いた……ようにみえた。
「あー、俺の言ってること、わかる?」
問えば、大きな龍が同じようにその巨大な頭部を上げ下げする。
「あ、イエス・ノーで出来る質問ならいけそうか?
竜の巣が危険だから、人の出入りを禁じてる?」
同様に頭部が上げ下げされる。
おぉ! やった! と旭が歓声をあげれば、シルヴィアも兜の下で表情を明るくした。
「竜の巣の噴火と岩の民がやろうとしている儀式って関係がある?」
その問いには少し困ったように首を傾げる。
「あーえーと。儀式をすれば噴火は止まる?」
その問いに、龍は大きく首を横に振った。
「……あぁ」
シルヴィアが安堵の息を吐いた。
やはり、龍が生贄を要求しているわけではないのだ。
壷を割るのは、最も人間に危害を加えずに下山させるための彼らなりの優しさだったのだ。
「なぁ! 赤の龍は王龍は生きているんだよな!?」
旭の問いに、龍は瞬きながら当然だと言わんばかりに首を上下させる。
そのとき、上空から龍の咆哮が響いた。
見上げればさらに大きな光の翼を持った赤い龍がそこにはいた。
「っ!!」
見違えるはずもない。
二度三度と刃を交え、最期にはともに戦い、愛のある明日を、未来を願った。
「ザッハーク!!」
しかし、ザッハークは声が届かなかったのか、そのまま彼は部隊を率いて飛んでいってしまう。
そうしている間に、二人と意志疎通を図ろうとしていた龍達もザッハーク達が向かった方向へと飛び、走り始める。
「な、何だ? どうした?」
「龍が総出で相手にしなければならないような敵が現れたのかもしれません……旭さん」
「行こう!」
迷いなく旭も走り出し、シルヴィアは「はい」と応えるとその背を追った。
8合目ほどまで来ただろうか。
男たちの顔色は悪く、一人が突然飛び出てきた雑魔に足をやられて膝を付いた。
「あとは、俺たちだけで行こう」
グリムバルドの提案に、男たちはほぼ土気色になった顔で、それでもその提案を突っぱねた。
「でも、試練っていうのは頂上に着けばいいんだろ? 助っ人がいてもいいって言ってた。なら、担ぐ人間がその助っ人でもいいんじゃないか?」
「幸い、覚醒者というのは頑丈なんです。必ず辿り着いてみせますから」
グリムバルドの言葉を支えるように金目も頷いて見せる。
これが、雑魔相手に手間取るような駆け出しの覚醒者ならこの問答は長時間に及んだだろうが、ここまで雑魔を文字通り蹴散らしながら来た4人の強さを、男たちは認めていた。
「……すまない。よろしく頼む」
「あぁ、必ず送り届けるよ」
男たちが下山していくのを見送って、4人は壷を抱えた。
「スーレーさん、聞こえますか?」
「はい」
「そんなわけで、ここからは僕達があなたを運びます。ちょっとさっきより揺れたりしたらごめんなさい」
金目の言葉に壷の中からクスクスと笑い声が漏れる。
「わかりました。よろしくお願いします」
旭とシルヴィアが辿り着いた先では、龍たちが炎をまき散らしながら戦っていた。
「……狂気……!!」
小型狂気の群が、龍たちを襲っていた。
「助太刀するぜ!」
「援護します」
旭はエクスプロイドに巻き付けていた布を引き剥がすと同時に龍へと延びていた触手を切り払った。
ザッハークはと旭が視線を彷徨わせると、彼は空から来る中型を相手取っているようだった。
「旭さん!」
シルヴィアの声にとっさにハルバードを横に持ち飛ぶ。
旭のいた場所に背後からクラゲじみた狂気が迫っていたのを、シルヴィアが的確に打ち抜く。
「サンキューな!」
頭上に、まだ強欲竜ではないザッハークがいる。
また、ともに戦える。
それが嬉しくて、旭の口元は自然と綻んだ。
だが、それもこの局面を乗り越えなければ話にならない。
ゆるんだ口元を真一文字に引き絞ると、旭は気合いとともにハルバードを振るった。
●そして……
「あーーーーーーザッハークと会話出来なかったぁっっ!!!」
「旭さん! 気持ちは分かりますが、ここはライブラリです!」
叫ぶ旭にシー! と人差し指を立てたシルヴィアが旭を宥め賺す。
「儀式は、無事終わったよ」
エアルドフリスがファイルを開き、辿る。
「儀式、なんてそんな何かがあるわけじゃなかった。
彼女はただ、皆の幸せを願って、火口へと飛び降りた」
「……そう、ですか」
シルヴィアが視線を落とす。
あんな幼い子が生贄にならないといけないなんて。
そして、”それを竜が望んでいなかった”という事実が、ただただ哀しみを増長する。
「そうか……狂気がもういたんだ……もしかして、噴火が増えたのも狂気のせいなのかな?」
「わからないが……無関係ではない気はするねぇ」
枢の言葉にエアルドフリスが両肩をすくめ、パイプを取り出そうとして……ライブラリという場所を思い出して指でなぞるだけにとどめた。
この『夢』は無意味な物はほとんど見せない。
最後に狂気が出てきたという事は、これが一つのキーなのだろうと誰もが己の思考に落ちていき、場を沈黙が占めた。
「……あぁ、正史でもやはり狂気に襲われ、竜がそちらに向かっている間に儀式は行われたとあるね」
エアルドフリスはファイルを閉じると、「見るかい?」と金目に問うが、金目はそれに否を示す。
「たとえ、僕達がどれだけ『夢』の中で過去に干渉しても、夢は夢なんだなってことがわかったので……」
記録の中にハンターたちの姿はない。ただ、おそらく自分たちが体験した『過去』は『夢』として記録されるのだろう。
「……願わくば、彼女が安らかでありますように」
グリムバルドが呟けば、全員がそれにうなずいて、小さく祈りを捧げたのだった。
●Unknown
「王」
王の間と呼ばれる広い空間に、一体の大きな龍が胸に何かを抱えながら入っていく。
「イケニエの人間がまた」
その両手の平の上には、気を失った赤い衣を着た少女がいた。
「……そうか」
低く、淡々とした声音からは何の感情の機微も感じられない。
「いつもどおりに」
「仰せのままに」
深くお辞儀をして、龍は少女を抱えて出て行く。
それを見送って赤の龍は一つため息を吐いた。
静かに火口そばへと歩き寄ると、みちみちと溜まっている負のマテリアルプールを覗く。
その金の瞳はただただ静かで。
彼が何を考えているのかなど、誰にも察することは出来なかった――
依頼結果
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
|
神の夢の中で【相談卓】 エアルドフリス(ka1856) 人間(クリムゾンウェスト)|30才|男性|魔術師(マギステル) |
最終発言 2017/03/13 18:22:17 |
||
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2017/03/12 00:35:58 |
|













