ゲスト
(ka0000)
異世界武侠 月下粋人
マスター:楠々蛙
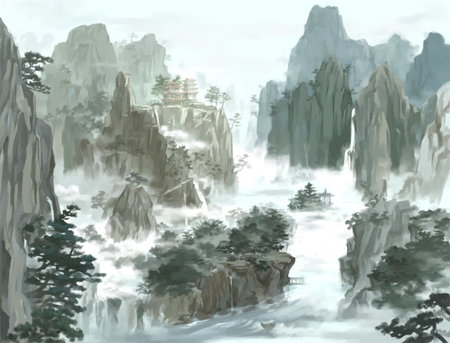
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~6人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2017/05/26 22:00
- 完成日
- 2017/06/06 20:07
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
夜気をしとどと濡らす、篠突く雨。
いや、それもつい最前までの事だった。今となっては、雨は上がり、僅かに晴れた雲間から差す月明かりが、濡れそぼつ廃れた寺院を照らしている。
「──何者だ」
寂れた山門の前に立つ巨漢が、月光に忽然と現れた二本の足を見咎めて、誰何を投げる。その声は硬く、緊張の調を孕んでいた。わざわざ廃寺の門番を務めている事から察するに、脛に傷ある事は確かだろうが、ならばまだしも高圧な態度で追い払えば良いだけだろうに。
いや、彼が気を凝らしたのは、招かれざる客の来訪ばかりが由縁ではなかったのだ。
門番が態勢を半ば臨戦にまで移した理由は、来訪者の気配を悟れなかったという一点に尽きた。散々雨に打たれた石畳には、足を踏めば跳ねる程の嵩に溜まった水が敷かれている。まともに歩けば、水音が鳴り、波紋が立つのは避けられまい。だが、門番たる男の耳も目も、水が報せる来訪の報を感知しなかった。
武芸の心得を持つ門番は、ただそれだけで目前に立つ人影が只者ではないと、見破ったのだ。
「これは異なことを聞く。ただの参拝客だ」
果たして、誰何にいらえたのは、紅く塗られた油紙の向こうから届く声。
「神仏の御前を訪ねる者が、他に居るのか?」
差した唐傘の奥から、声音は低くも張り良い男の声が、嘯く。
「ここは見ての通りの廃寺だ。神も仏も、とうの昔に出払っておるわ」
「はて、おかしいな。聞いた話では、この寺にはここいらの神や仏が集められているということだったが」
「っ……!? 貴様、何処でそれを!」
空言のように発せられた台詞を聞くや、門番の男は瞠目しながら、一歩足を前に踏み出す。──跳ねる、水飛沫。
「──いや、最早聞かぬ」
やがて門番は、山門の柱に立て掛けて置いた、己が得物に手を伸ばした。穂の付け根に朱い飾り房──槍纓の付いた、一柄の槍である。
「そこまで知りながらのこのこと現れて、よもやタダで帰れるとは思うて居るまいな」
槍は青眼、足の運びは弾腿の作法に則った構え。
傘の向こうから殺気に応えたのは、ほぉ──という感心のため息。
「六合大槍……。なるほど、同門だったか」
型を一見したのみで、門番の積んだ功を看破した事からも、傘の主が武芸者であるのは明らか。そしてその声が滲ませる余裕の色もまた、察するまでもなく明白だった。
「侮るなぁ!」
水面に、激しく波立つ波紋を拡げながら、門番は跳んだ。
常歩であれば九歩はあろうかという間合いを、僅か三足で飛躍する。一歩、二歩目は、ただ彼我の間合いを埋める為に、しかし三歩目の踏み足は、震脚にて勁を発っする為の精悍にして精緻な歩法だった。
虚手を一切交えず放った喉元を突き上げるような一刺は、果たして勇猛な攻め手と評するべきか。或は、焦燥の裏返しと表するべきか。
どちらにしたところで、標的に躱されたとあっては同じ事。
傘の主は、露先から水滴を散らしながら、肉迫する槍の穂先をまんまと躱しせしめた。のみならず、すれ違いざまに門番の背中を閉じた傘で叩いて、勢い余らせたたらまで踏ませたのである。
泳いだ身体を立て直して振り返るや、門番はすぐに槍を構え直した。穂の向こうに覗くのは、傘の帳から現れた男の立ち姿。
刺繍を施した紺色の長袍に身を包むのは、精悍な顔立ちをした壮年の男。その立ち振る舞い、閉じた傘を右肩に掛けて、向けられた穂を見返すその挙措、一挙手一投足までもが“いき”だった。
「なにも、そう生き死にを急ぐことはなかろうよ」
その腰には、一振りの刀を佩いている。垢抜けた衣装とは裏腹に、どうにも素朴な拵えの刀剣である。鉄製の鍔に彫金はなく、鞘はワニスを上塗りしただけの木目を晒し、金具や革などの装飾は皆無。やはり飾り気のない柄頭に左手を掛けながら、男は続ける。
「ここいら一帯の寺から霊験あらたかな代物を、あらかた掻っ攫ったのは、まあそう褒められたモノじゃなかろうが、なにも死ぬの殺すのする程のことでもあるまい。素直に門を開けては貰えまいか」
「誰が通すか! 我が武が軽んじられた、ただそれのみで、この槍を走らせる理由には事足りる!」
「そうか──」
男は一言呟くや、柄頭に乗せた手を鍔元にまで下げる。
「盗人に身を窶しても、江湖を生きるなら沽券に重きを置かねばならん時もあるだろう。あくまで意地を通すというなら仕方ない──」
長袍の右袖を翻しながら、男は開いた唐傘を空高く放り投げた。──空いた利き手は、刀の柄に。
「──私も江湖の礼を以って応じよう」
「破ァっ!」
男が抜刀の構えを取るや否や、気勢も激しく、門番は飛沫を蹴り立てて再び跳んだ。
腕と腿の伸びを最大限に生かした必殺を誓う刺突は、しかし──
雨香を孕んだ夜気を劈く鞘鳴り、水面に虚像を映す月の光を裂く刃鳴りによって断ち斬られた。抜き放たれた刀身は、倭刀に似通っていながら反りは浅く、刃長は長大、でありながら細身だ。八極拳の刀法で用いられる苗刀に相違ない。
「がぁぁぁぁっ!?」
槍と共に片腕を断たれた門番の喉から苦鳴が迸る。
「これ以上、意地の張り所を違えるな。腕の一本ではすまなくなるぞ」
「っ……、まだだっ……!」
腕を斬った凶手とすれ違った門番は、諌める声を払うように振り返り、鋭利な切り口を下に向けて、短槍と化した得物を振り翳す。
「やれやれ」
だが彼に、それを突き下ろす暇など与えられはしなかった。
──仏面も、三度撫ぜれば鬼面に変わると習わなかったのか?
振り返ったその時既に、懐に侵入を果たしていた男の鉄山靠により、藁編みの人形もかくやとばかりに吹き飛ばされたからだ。
「が、は……っ」
山門に叩きつけられ、圧迫された肺から意図せずして呼気を吐き出す門番。意思に反して膝が折れる。だが、地に膝が着く事はなかった。
膝を屈するその前に、門番の身体を山門に押し付ける手があったからだ。
「貴様、名は……名はなんという」
「臥城(がじょう)という。──問いはこれで最後だ。是か非か、いかに?」
臥城と名乗った男は問いながら、左手で門番を押さえ、右手で拳を作っていた。
…………
返るのは、その拳がそうであるように、強(こわ)い沈黙のみ。
「そうか」
臥城はそう呟くや拳を前に突き出していた。と同時に、彼の足許に溜まる水が、奇妙な動きを見せた。微塵も動いていないのに、波が立ったのはまだ良い。暗勁なら、あり得ない事でもない。だが、波紋を拡げるのではなく、寧ろ飛沫を足許へ纏うようにして波を起こす現象は、果たして如何なる勁の運用が可能足らしめるのか。
拳が門番の鳩尾に触れたその瞬間、彼は背に付けた門諸共に、境内に吹き飛ばされた。
呼気を吐き、残心を終えた臥城は「さて」と呟き、後ろを振り返る。そこには、月光に浮かび上がる幾つかの人影があった。
「諸君。少々手間を取ったが、門は開かれた。──あとは城を墜とすのみだ」
いや、それもつい最前までの事だった。今となっては、雨は上がり、僅かに晴れた雲間から差す月明かりが、濡れそぼつ廃れた寺院を照らしている。
「──何者だ」
寂れた山門の前に立つ巨漢が、月光に忽然と現れた二本の足を見咎めて、誰何を投げる。その声は硬く、緊張の調を孕んでいた。わざわざ廃寺の門番を務めている事から察するに、脛に傷ある事は確かだろうが、ならばまだしも高圧な態度で追い払えば良いだけだろうに。
いや、彼が気を凝らしたのは、招かれざる客の来訪ばかりが由縁ではなかったのだ。
門番が態勢を半ば臨戦にまで移した理由は、来訪者の気配を悟れなかったという一点に尽きた。散々雨に打たれた石畳には、足を踏めば跳ねる程の嵩に溜まった水が敷かれている。まともに歩けば、水音が鳴り、波紋が立つのは避けられまい。だが、門番たる男の耳も目も、水が報せる来訪の報を感知しなかった。
武芸の心得を持つ門番は、ただそれだけで目前に立つ人影が只者ではないと、見破ったのだ。
「これは異なことを聞く。ただの参拝客だ」
果たして、誰何にいらえたのは、紅く塗られた油紙の向こうから届く声。
「神仏の御前を訪ねる者が、他に居るのか?」
差した唐傘の奥から、声音は低くも張り良い男の声が、嘯く。
「ここは見ての通りの廃寺だ。神も仏も、とうの昔に出払っておるわ」
「はて、おかしいな。聞いた話では、この寺にはここいらの神や仏が集められているということだったが」
「っ……!? 貴様、何処でそれを!」
空言のように発せられた台詞を聞くや、門番の男は瞠目しながら、一歩足を前に踏み出す。──跳ねる、水飛沫。
「──いや、最早聞かぬ」
やがて門番は、山門の柱に立て掛けて置いた、己が得物に手を伸ばした。穂の付け根に朱い飾り房──槍纓の付いた、一柄の槍である。
「そこまで知りながらのこのこと現れて、よもやタダで帰れるとは思うて居るまいな」
槍は青眼、足の運びは弾腿の作法に則った構え。
傘の向こうから殺気に応えたのは、ほぉ──という感心のため息。
「六合大槍……。なるほど、同門だったか」
型を一見したのみで、門番の積んだ功を看破した事からも、傘の主が武芸者であるのは明らか。そしてその声が滲ませる余裕の色もまた、察するまでもなく明白だった。
「侮るなぁ!」
水面に、激しく波立つ波紋を拡げながら、門番は跳んだ。
常歩であれば九歩はあろうかという間合いを、僅か三足で飛躍する。一歩、二歩目は、ただ彼我の間合いを埋める為に、しかし三歩目の踏み足は、震脚にて勁を発っする為の精悍にして精緻な歩法だった。
虚手を一切交えず放った喉元を突き上げるような一刺は、果たして勇猛な攻め手と評するべきか。或は、焦燥の裏返しと表するべきか。
どちらにしたところで、標的に躱されたとあっては同じ事。
傘の主は、露先から水滴を散らしながら、肉迫する槍の穂先をまんまと躱しせしめた。のみならず、すれ違いざまに門番の背中を閉じた傘で叩いて、勢い余らせたたらまで踏ませたのである。
泳いだ身体を立て直して振り返るや、門番はすぐに槍を構え直した。穂の向こうに覗くのは、傘の帳から現れた男の立ち姿。
刺繍を施した紺色の長袍に身を包むのは、精悍な顔立ちをした壮年の男。その立ち振る舞い、閉じた傘を右肩に掛けて、向けられた穂を見返すその挙措、一挙手一投足までもが“いき”だった。
「なにも、そう生き死にを急ぐことはなかろうよ」
その腰には、一振りの刀を佩いている。垢抜けた衣装とは裏腹に、どうにも素朴な拵えの刀剣である。鉄製の鍔に彫金はなく、鞘はワニスを上塗りしただけの木目を晒し、金具や革などの装飾は皆無。やはり飾り気のない柄頭に左手を掛けながら、男は続ける。
「ここいら一帯の寺から霊験あらたかな代物を、あらかた掻っ攫ったのは、まあそう褒められたモノじゃなかろうが、なにも死ぬの殺すのする程のことでもあるまい。素直に門を開けては貰えまいか」
「誰が通すか! 我が武が軽んじられた、ただそれのみで、この槍を走らせる理由には事足りる!」
「そうか──」
男は一言呟くや、柄頭に乗せた手を鍔元にまで下げる。
「盗人に身を窶しても、江湖を生きるなら沽券に重きを置かねばならん時もあるだろう。あくまで意地を通すというなら仕方ない──」
長袍の右袖を翻しながら、男は開いた唐傘を空高く放り投げた。──空いた利き手は、刀の柄に。
「──私も江湖の礼を以って応じよう」
「破ァっ!」
男が抜刀の構えを取るや否や、気勢も激しく、門番は飛沫を蹴り立てて再び跳んだ。
腕と腿の伸びを最大限に生かした必殺を誓う刺突は、しかし──
雨香を孕んだ夜気を劈く鞘鳴り、水面に虚像を映す月の光を裂く刃鳴りによって断ち斬られた。抜き放たれた刀身は、倭刀に似通っていながら反りは浅く、刃長は長大、でありながら細身だ。八極拳の刀法で用いられる苗刀に相違ない。
「がぁぁぁぁっ!?」
槍と共に片腕を断たれた門番の喉から苦鳴が迸る。
「これ以上、意地の張り所を違えるな。腕の一本ではすまなくなるぞ」
「っ……、まだだっ……!」
腕を斬った凶手とすれ違った門番は、諌める声を払うように振り返り、鋭利な切り口を下に向けて、短槍と化した得物を振り翳す。
「やれやれ」
だが彼に、それを突き下ろす暇など与えられはしなかった。
──仏面も、三度撫ぜれば鬼面に変わると習わなかったのか?
振り返ったその時既に、懐に侵入を果たしていた男の鉄山靠により、藁編みの人形もかくやとばかりに吹き飛ばされたからだ。
「が、は……っ」
山門に叩きつけられ、圧迫された肺から意図せずして呼気を吐き出す門番。意思に反して膝が折れる。だが、地に膝が着く事はなかった。
膝を屈するその前に、門番の身体を山門に押し付ける手があったからだ。
「貴様、名は……名はなんという」
「臥城(がじょう)という。──問いはこれで最後だ。是か非か、いかに?」
臥城と名乗った男は問いながら、左手で門番を押さえ、右手で拳を作っていた。
…………
返るのは、その拳がそうであるように、強(こわ)い沈黙のみ。
「そうか」
臥城はそう呟くや拳を前に突き出していた。と同時に、彼の足許に溜まる水が、奇妙な動きを見せた。微塵も動いていないのに、波が立ったのはまだ良い。暗勁なら、あり得ない事でもない。だが、波紋を拡げるのではなく、寧ろ飛沫を足許へ纏うようにして波を起こす現象は、果たして如何なる勁の運用が可能足らしめるのか。
拳が門番の鳩尾に触れたその瞬間、彼は背に付けた門諸共に、境内に吹き飛ばされた。
呼気を吐き、残心を終えた臥城は「さて」と呟き、後ろを振り返る。そこには、月光に浮かび上がる幾つかの人影があった。
「諸君。少々手間を取ったが、門は開かれた。──あとは城を墜とすのみだ」
リプレイ本文
「城攻めってわけね」
振り返った臥城の視界で、舞い落ちてきた唐傘を受け取る者があった。
「任せてちょーだい。景気の良い一発見せ付けられて、ちょっと血が滾っているとこだから」
傘の色と同じく、朱い立ち姿の女である。赤髪を靡かせ、軽装に身を包んで健康的な肢体を晒す彼女は、葉桐 舞矢(ka4741)という。
近頃までクロードという西方風の名を名乗り、間違った西方かぶれの口調をしていたのだが、思うところがあったらしく、今は少なからず地の振舞いで通しているようだ。
彼女は臥城の傍に歩み寄ると、彼に傘を差し出した。
「今のも、リアルブルーのちゅーごく拳法なわけ? いやぁ、やっぱし凄いわね」
「以前に功夫を目にしたことがあるのかね?」
傘を受け取りながら、臥城が問い返す。
「まぁね、ちょっと毛色が違ったけど」
「ほぉ、いやはやなんとも、世界を違えても世間は狭いものだ」
実はこの二人、浅いながらもとある縁があるのだが、双方共与り知らぬ事である。
「──ふむ、どうやら世間話に現を抜かしている場合ではないらしい」
傘を肩に掛けながら、つい──と臥城が視線を巡らせば、山門の破壊音を耳にした盗賊が、各々の得物を構えながら、山門付近の境内に屯していた。
「揃いも揃って御婦人との語らいを邪魔するとは、無粋だとは思わんか」
流し目と共に送られた短い嘆息交じりの台詞に応えたのは、夜気を裂いて飛ぶ匕首のあられ。臥城を貫かんと投げ放たれた短剣は、数えて四つ。背を覆う傘布も、その切っ先までは防げまい。長袍の袖を翻し、臥城が投剣に対応したその瞬間──先んじて割って入った葉桐が、匕首を悉く叩き落とす。
「荒い──が、速いな」
一瞬の内に、四本の投剣を迎撃した手練を見て取った臥城が、感心を滲ます声で呟く。残心する葉桐の両手に納まっているのは、ひどく短い棍に把手を付けた“ト”の字型の打撃器械。中国拳法でいうところの拐のようにも見えたが、短拐よりも尚短い。リアルブルーにおいては、拐を元にして日本の琉球で作られたというトンファーである。
「手数なら、誰にも負けはしないわ」
残心を解き、左手を前にして右手を引く構えを取る葉桐。幾つも波紋を立てながら足を交互に踏むその軽妙な足運びは、臨戦の空気に少なからず悦びを見出しているようで、何処か攻撃的だ。
「背中を任せてもいいかしら?」
取り囲む敵の群れを睥睨した後、葉桐は背後に立つ臥城へ問い掛ける。問いに微笑を浮かべた“いき”な侠客は、唐傘を閉じ、その石突で以って石畳を突いた。その瞬間、サァッ──と、臥城を中心とした細波が水面を駆け抜ける。
「生憎、守るのは不得手だが、御婦人の背中となれば是非もない。──任されようか」
「それはそれは、心強いわね」
足許を吹き抜けた勁の巡りと、尚力強い背後の声を感じて、葉桐は口許に不敵な笑みを浮かばせた。
投剣迎撃の際に見せた葉桐の手練、そして今しがた見せ付けられた臥城の強烈な発勁の片鱗に浮足立った盗賊が、それぞれ携えた得物に功を籠め、己を奮い立たせる叫声を発すると共に二人へと襲い掛かった──!
廃寺の裏門前には、長く続く石段が積まれていた。石畳の上に溜まった雨水が、緩やかな滝となって、石段を下へと流れ落ちて行く。
雲間から差す月光は裏門前のみを照らし、水の行く先には闇の帳が落ちるばかり。
しかし、裏門の番を務める寸胴の大男は、石段をやおら登って来る闖入者の存在を、その男が月明かりに姿を晒す前に知った。
荒い、水音。身を潜めるという事を全く知らない踏み音を立てながら、月光の下に現れたた男の姿を簡潔に言い表すなら、粗にして野。
半着も付けず、赤褐色の肌の上に直接身に付けた羽織りの片袖をはだけさせ、申し訳程度に巻いたさらしを覗かせている。更に不揃いの甲冑を身に纏い、抜き身の倭刀を肩に掛けたその立ち姿は、“粗野”という言葉を絵に描いたかのようだった。
しかし、何よりも目を引くのは、伸びるに任せて乱れた銀髪から覗く、額に映えた一本角。
門番に負けず劣らずの体格を誇るその男は、人ならざる存在──鬼だった。
「オマエ、なにモノ。なにしに来た」
巨漢という点は同じだが、鋼を思わす屈強な肉体を誇る鬼とは異なり、筋肉質というよりは肉の塊と言う方が的確な門番は、その見た目通りの鈍重な口調で、鬼に問い掛けた。
「あぁん? 一遍に二つも訊くんじゃねぇよ、ったく」
鬼は空いた手で銀髪を掻き毟ると、面倒だと言わんばかりに愚痴を零したが、やがて「どっちも見ての通りだよ」と答えを返した。
「名前はイッカク(ka5625)。この寺ぁ根城にしてる盗人共を叩っ斬りに来た」
いらえながら、鬼──イッカクは、大振りの倭刀、その切っ先を門番へと向ける。
「わかったらそこ退きやがれ。てめぇみてぇなウスノロの肉達磨斬っても、オモシロかねぇ」
「それ……ダメ。ここ通ろうとするヤツ、コワセって言われた」
門番は鈍い口調で呟きながら、傍らの柱に立て掛けた武器を手に取った。
長柄の先端に取り付けた円柱状の金属塊に、幾つも鋭い突起をあしらえた打撃器械──狼牙棒である。
「それに、オレ……コワスのスキ。オマエ、ひさしぶりのエモノ。だから──にがさない」
ただただ鈍そうなだけだった顔に、凶相染みた笑みが宿る。
舌打ち、一つ。
「──そうかよ。そんなに死にたきゃ、好きにしな」
イッカクは苛立ち混じりに舌打ちを零すと、門番に突き付けた倭刀を両手で握り、肩の上にまで上げながら、手の中で返した。──刀の峰を下に、刃を上に。
右肩を引いて半身を晒し、歩幅は肩幅に合わせて開く。
出で立ちに反して、その構えは風雨に合わせて静かに揺れる柳の古木を思わせる、静謐の型だった。
「きっちりかっちし、殺してやんよ」
「チガウ……殺されるのオマエ。オレが、コワスゥ!」
ネジの外れた声を上げながら、門番は飛んだ。肉達磨に似合わぬ跳躍力。重力の縛り、物理法則の束縛すらそれを阻めぬ。──軽功の遣い手か。
緩やかな放物線を描いて迫る肉達磨。その頭上には、あの凶悪足る得物が掲げられている。それだけの重量をして飛翔の如き跳躍を可能とする功の妙を知らずして、イッカクは微塵も動じず、ただ倭刀の切っ先をゆらりと揺らすのみだった。
────!
壮絶な破壊音が響き渡り、飛沫が跳ねる。
「コワシタ、コワレタァ♪」
狂喜に顔を歪める肉達磨。だが──
「──誰が殺して、誰が死ぬって?」
その醜悪な面相を見下ろす、赤玉の瞳があった。
振り下ろされた狼牙棒が倭刀に触れたその瞬間、柳の枝のように柔らかく揺れた刀身の反りに導かれるように、渾身の一撃はイッカクの身体を逸れたのだ。
「ヒデェ勘違いもあったもんだな、ウスラデブ」
狼牙棒を片足で踏み締め、二の手を封じたイッカクが、おもむろに倭刀を振り上げた。
「死ぬのはテメェで──」
そしてその出で立ちに相応しい、怒涛の一刀を門番の脳天目掛けて振り下ろす。
「──殺すのが俺だ!」
脳天をかち割った刀身が、
「あ──
──ひ?」
門番の股下まで斬り抜けた──!
綺麗に真っ二つに別たれた巨体が、派手に水飛沫を立てて左右に倒れる。
門より先に、門番を観音開きにしたイッカクは、その真ん中を真っ直ぐに進むと、立ち止まる事なく裏門を蹴り破った。
慎みのない侵入者を、すぐさま集った盗賊一行が出迎える。
「揃いも揃ってぞろぞろと。さっきのデブよか斬り応えあんだろぅな?」
多勢に無勢。しかし、イッカクは口許に不敵な笑みを湛えて、彼らを見渡した。
「貴様、何者だ!?」
その内の一人が誰何を放てば、イッカクはさも面倒そうに首の骨を鳴らし「一晩に二度も名乗るもんじゃねぇ」と言い放つと、その身を翻して背中を晒した。
「名乗りなんざ、こいつで十分だ!」
羽織りに背負った“悪”一文字を魅せ付けたのだ。
月の光が、水面の壇上に立ち、刀を肩に掛けて大見得を切った傾奇者の姿を照らし出す。
「さぁ──タマ惜しかねぇ奴から、得物執りなぁ!」
「裏門からも攻め入られた、急げ──!」
夜半の急襲に慌てふためき、境内を駆け巡る盗賊達。
「おい、止まれ……!」
裏門へ向かおうとしていた彼らは、走る先の薄闇に浮かび上がった、その白い人影に気付いて足を止めた。
「そこのお前、なに奴だ!」
和装に身を包み、長い白髪を雨の匂いを孕んだ夜風に靡かせるその者は、高圧的に発せられたその誰何に苦笑を浮かべた。
「おやおや、これは弱ったねぇ。こんなに早く見付かってしまうとは」
中性的な顔立ちに似合った、妙に落ち着いた響きの声。そして和装の似合う長身ながら痩身の体躯の持ち主は、その風貌に反して、女に生まれた身であった。
彼女は、血気に逸って早くも得物を執った盗賊達をなだめるように、着物の袖をおもむろに上げた。
「およしなよ。こんなひ弱そうなのに構ってる場合じゃないだろうよ。私なんか、ろくに拳を握ったこともないんだ。相手にするだけ時間の無駄だよ」
確かに、捲れた袖から覗く細腕は、到底武芸者のモノとは思えない。白魚のようなその指先は、紛う事なき女性のそれだった。
「向こうの方を見たかい? 鬼が暴れ回ってるじゃないか。そっちに行くといいよ」
「ああ、そうさせて貰おう。──貴様を手早く片付けた、その後でな!」
飄々とした説得の甲斐もなく、盗賊の一人が手斧を振り上げ、桃之枝に踊り掛かった。
「やっぱり、そうなるのか……」盗賊が間合いを詰め寄る中で、動じるでもなく溜息を零した後「なら仕方ない」桃之枝は、上に翳した掌をひらり──と返す。
示指と中指の間に手妻のように現れたのは、一枚の札。彼女の出自、東方の陰陽寮に由来する呪符だ。
「──色界不浄、急急如律令」
必然、二指の間から放たれた呪符がもたらしたのは、陰陽道に連なる秘術。『不浄』という言葉とは相容れない、月光に散る桜吹雪が、術者へと襲い掛かる男の視界を封殺したのである。
「私は桃之枝(ka6824)」
渦を巻く夜桜に渦中に立ちながら、女は先刻の誰何にいらえる。
「しがない通りすがりの、陰陽師だよ」
廃寺の敷地に佇む、小さな墓地。苔生した墓石は、既に文字も掠れ何処の何某がいつからその下で眠っているのか皆目見当が付かない。その場所は、最早無縁墓地も同然の有り様だった。
そんな忘れらるる場所に佇む者が一人居た。
陰気な色合いのコートを身に付けた青年だった。その墓地が西方の仕様、或はその男──央崎 枢(ka5153)の生家に準じたキリスト教の墓地だったなら、その黒衣から聖職者を連想する事ができただろうか。いやそれとも、目深に被ったそのフードから、死神の似姿だと思う者も居たかもしれない。しかし──
「おい! 貴様、一体そこでなにをしている!」
喧しい水音、複数の足音に続いて横合いから掛けられた横暴な声に、おもむろに振り返ったフードの奥に覗く顔は、敬虔なクリスチャンでも、空虚な骸骨でもなく、ただ滑稽な笑みを浮かべる道化のモノだった。
央崎は、果たして何の酔狂か、道化師の仮面をフードの下に被っているのである。
「なぁに、ただの墓参りさ」
仮面の奥から嘯く台詞に耳を貸そうとする者は、当然誰一人として居なかった。央崎を見咎めた盗賊達は、寧ろ彼が肩に担いだ八角棒を注視する。
「おおかた、正門と裏門から攻め入った連中の仲間だろう。陽動に我々の目を牽き付け、身を潜めながら動く腹だったのかもしれんが、ここで見つかったのが運の尽きよ」
「別にそんな小賢しく立ち回ろうだなんて思っちゃいないさ。そっちから見付けて貰って、むしろ手間が省けたとこだよ」
何やら悦に入っている様子の盗賊に肩を竦めながら水を差すと、央崎は肩慣らしがてらに、八角棒を振り回す。腕や肩、腰や脚を軸に旋風を巻くその動きからして、彼が棍法を弁えている事は明らかだった。
締めに足許の水を棒の先端で掻いてみせると、央崎は脇を閉めて棍を背に回しながら構えを取った。空いた手で剣訣を結ぶでもなく、ついついと人差し指を煽るように動かす。
「さぁ来な。俺が遊んでやるよ」
「……っ! 青二才が!」
盗賊の一人──年かさの男が柳葉刀を振り翳して央崎へ踊り掛かった。重量を乗せて、袈裟切りの軌道を描く段平。その一刀を、央崎は危なげなく躱してみせる。
そして躱したその瞬間には、既に反撃を見舞っていた。半身を切ると同時に、背に回した八角棒を突き出して、男の顎を打ち抜いたのだ。
まだ刀を完全に振り切る前、寧ろ躱されるのを見越して次手を放とうとしていた男は、巧みな反撃に不意を突かれて呆気なく意識を失い、そのまま己の刀勢に引っ張られるようにして倒れ込んだ。
「おいおい、張り合いなさ過ぎやしないか」
水面に沈んだ男を一瞥する央崎。にんまりと道化師の面の奥に覗くブラウンの瞳は、仮面の表情に反して、何処か辛辣だった。
「ほざけっ!」
先の男と同じ柳葉刀の使い手が、怒り心頭発した声で、刀を払う。しかし、刃鳴りが墓場に響き渡ったその時にはもう、央崎は無明のまま久しい灯篭の上に立っていた。
滑稽を装う面が、盗賊達を見下ろす。
「どうしたよ。神様仏様に手出したんだ、そんなモンじゃないんだろ?」
発するその声にはやはり、少なからず心穏やかならない調が滲んでいた。
「仏の教えを仰いだ憶えもねえし、神罰代行なんてタチじゃあないが。まぁそのなんだ、骨の一、二本は覚悟しろよな?」
「いい夜だな」
その声は、頭上から振って来た。
境内を西へ東へと奔走する盗賊達は、不意に掛けられた声に、天を振り仰ぐ。果たして声の主は、花を咲かせる事もなくなって久しい桃の梢に腰掛けていた。
背に蒼月を背負っているのは、すらりとした体躯をした褐色肌の男だった。月光を浴びて光る銀髪を後頭で一房に纏めて垂らし、膝を立てて古木の枝に腰掛けている。
「そうは思わないか?」
眼下の盗賊達に向けて、飄々と問う男。
「貴様、何者だ!? なにをしている!」
風情のある会話に興じる事なく、盗賊達は誰何を放った。しかし返答を待つ間でもなく、彼等は既に得物を執っていた。今日この夜に、腰に刀を差して境内に居合わせた男が、ただの月見客というわけもあるまい。賊の中で最も気の早い者は、男が返答を寄越そうと口を開き掛けたその時既に、五指に握り込んでいた擲箭を投げ放っていた。
だが、果たして四つの投擲暗器が射抜いたのは、梢を蹴って樹上から跳び降りる男の残像のみであった。
男が石畳を踏み締めると共に跳ねる、無色透明の飛沫。
いや、それのみならず、今しがた擲箭を投じた盗賊の腕から、赤い飛沫が上がる。──水面に生じた跳ね水の王冠が没するよりも、尚早く。
「無粋な真似するなよ」
背後で囁く声を聞いた賊は、苦鳴を上げる間を惜しんで、振り返り様に擲箭を握る無傷の腕を揮った。不意を打たんとした一手は、しかし、手応えがなく──
「がっ……!」
寧ろ自身の首筋に痛烈な衝撃を受けて、彼は昏倒する事となった。
「神サマ掻っ攫うなんて、大層な連中も居たもんだと思ってみれば、どうしたもんかなこいつは。腕も悪ければ、風情も解せない。期待外れもいいとこだ」
柄頭で賊のうなじを打った刀を掛けながら、男は飄々とした調子で肩を竦めてみせた。縮地と見紛うばかりの瞬動に、尚一層に警戒を露にしながら得物を突き付け、周囲を取り囲む賊達の姿など、眼に入っていないかのような態度である。
「だがまぁしかし、粋の欠片もない輩でも、名も知らないままにぶっ飛ばされんのは、気持ちよくはないだろうからな。一遍だけ、教えてやるよ。そこで伸びてるのにも、後で教えてやるんだな」
倭刀の切っ先を盗賊達に返しながら、終始剣呑とは縁遠い態度で、男は己が名を告げる。
「俺の名は、テオバルト・グリム(ka1824)。生憎、冥土の土産にさせるつもりはないからさ。
安心して、掛かって来な」
「馬鹿共が腑抜けやがって!」
他の盗賊とは、やや風体が上等の男が怒りも露わにした胴間声を響かせているのは、彼らが根城にしている本堂だった。雨風を凌いでいるのは、盗賊一党のみならず、その戦利品である神仏に由来するあれやこれやが、粗雑に陳列されていた。
最も眼を惹くのは、光背を背負った仏像だ。見るも絢爛な金箔が、燈台で揺れる炎を照り返している。
「敵の数は十にも届いてねえっていうじゃねえか。なのに好き放題にさせやがって。これじゃ江湖のいい笑いもんだぜ、情けねえ!」
衣装の割に品のない声で威圧する盗賊一味の香主らしき男に委縮してか、周囲の取り巻き達は、返す言葉を持たなかった。
「──ほんま、あんさんの言う通りやな」
代わりに同調を示したその声は、おっとりとした口調の少女の声。
うじ湧く男やもめの郎党一味には、生憎と華は一輪もない。盗賊達は、瞠目してその声の源──暗がりの奥へと視線を向ける。
「こない美少女に今の今まで気づかんと、男としてなっさけない話やあらへんの」
果たして蝋燭の明かりの中に姿を現したのは、ふわりとした黒髪を二房に結わった少女。特徴的なのは、布端が足許に届きそうな程に長い、真紅のマフラーだ。彼女は黒髪とマフラーを揺らしながら、頻りに男の台詞に頷いている。
「っ…………!?」
彼女が声を掛けるその間際まで、その存在を知る者は、この場には誰一人として居なかった。その事実に盗賊達は声もなく、ただ眼を見張るのみだった。
「……って、なんか返しぃな。なんや、私がサムイみたいになるやんか」
「き、貴様一体なにモンだ!?」
ようやく自失の体から立ち直った香主の男が、お馴染みの誰何を口にした。
「あっちゃこっちゃうろついて聞いてたんやけども、おたくら、ちょいと芸があらへんとちゃうん?」
呆れた様子でかぶりを振る少女。「ま、ええけどもやな」と呟き、居住まいを正す。
「ほなら、名乗うたる。私は琴吹 琉那(ka6082)ゆーねん。ご覧の通り、忍者やらせてもろうてます」
ニンニン、と両手を組んでにわか知識で印を結ぶ少女──琴吹。盗賊達は、またもや押し黙ったまま彼女を睨んだ。今度は、警戒の方が先に立ったようだが。
「またかいな。おたくら、ノリ悪いんと違う?」
「……おめぇは、表の奴らの仲間ってことだな?」
「そうや、ゆうたら、どないするん?」
「こうすんのさっ!」
叫ぶが早いか、香主の男は琴吹へと殴り掛かった。女子供、中でも小柄な琴吹を相手にして慢心がそうさせるのか、初手にあるまじき大振りの拳。琴吹は瞬時に、男の懐中へと身を滑らせた。
────!
踏み足が、気張りの床を打つ。
身を沈めながら懐に潜り込むその所作は、回避の為のみならず。強烈無比な肘撃の破壊力を生む為の震脚も兼ねていた。
下肢から腰へ伝わる力の流れは、更に捻転による加算によって勢いを増し、突き入れた肘から、男の背中へと突き抜ける。
琴吹が懐から身を退くと、男はまた声もなくゆっくりと床へ沈んでいった。今度ばかりは、その沈黙を意に介する事もなく、琴吹はただ呆れた様子で男を見下ろす。
「なんや偉そうにしよったいうに。口だけやねんか」
いとも容易く香主を倒した手練を見せ付けられた盗賊達は、最早琴吹を女子供と軽んじる事なく腰の単刀を抜き放つや、その切っ先を彼女に突き付けた。
幾条の刀身に映る少女の口端が、微笑を浮かべる。
「ようやく、やな。よう気ぃ入れりぃや」
拳は緩やかに握り、左右の手を上下に置く。構えは、千変万化の柔の型。
「こっからが、私の本領やさかいな」
振り掛かる斬撃を避けきれなかった和装の袖が裂ける。
「おっと、これは危ない」
桃之枝の口許は尚も緩やかな曲線を描いてはいたが、その内心は舌を打たんばかりだ。次々と襲い来る盗賊達に、ただ眼晦ましの符術のみで立ち回るのにも限りがある。だが攻めの一手に転じようにも、数で物言う敵の勢いに押されて、その猶予がない。敵勢に押されるがままに、守りの堰が切れるのも時間の問題だった。
「これまでだっ!」
頭上に掲げた手斧を振り下ろさんとする盗賊。その一手は、桃之枝の正中線を正確に捉えていた。
「が、は……!?」
だが、斧頭が彼女の頭をかち割るその前に、賊の胸郭から生える刃の切っ先があった。それと共に、賊の背後から桃之枝に声を掛ける者がある。背後──とは言え、巨体を誇る鬼の面貌は、見るも明らかではあったが。
「なにやってんだ、ひょろいの。足引っ張なんなら、他所行きやがれ」
死体に変じた賊を放り捨て、倭刀の血を払ったイッカクが、その背に桃之枝を庇いながら、盗賊の残党共の前に立ちはだかる。
「おやおや、これは手厳しい。でもまあ、頼もしい限りじゃないか。ではここはお言葉に甘えておこうかな?」
足手纏いと告げられたにも関わらず、桃之枝は寧ろからかうような声でイッカクに応じながら、一歩退いた。
「そう──してなっ!」
鼻を鳴らしながら、肩越しに桃之枝を見遣ったイッカクは、手斧を打って来た盗賊の腕を、一挙動で斬り上げた刀で以って両断した。
明後日の方向へと飛んで行く己が腕を見送る盗賊が眼を見張る。いや、直後に瞠目したのは、彼だけではない。イッカクもまた、赤い瞳を見開いた。
両断した盗賊の腕、その切断面が、突如発火したからだ。
「いやはや、中々景気良く燃えてくれるじゃないか」
火はすぐさま火種を浸食し、人間松明と化して踊り狂う盗賊を見ながら、桃之枝は口許に微笑を滲ませる。
「テメェ……!」
彼女と、いつの間にやら倭刀の刀身に貼り付けられた呪符とを、イッカクは歯噛みしながら見比べた。
「ん? どうしたのかな。それにしても凄いものだね。切り口から燃え出すなんて、剣にはそんな技まであるのかい?」
その眼光を受けて、桃之枝は今度こそ確かに弄うような笑みを返した。
「……好きに言ってやがれ」
忌々しい思いで彼女から視線を切るや、残りの盗賊達へと向き直る。
「……お前らには同情するぜ、まったく。
今から俺の憂さ晴らしに付き合わされにゃなんねぇだからな」
「なんやねんな、騒々しゅうて敵わんわ」
本堂の朽ちかけた引き戸を破って、押し入って来た二つの人影に琴吹が眼を向ける。いや、正確には、押し入ったと言うよりは、吹き飛ばされたと言う方が正確だ。床に伸びている二人の盗賊を吹き飛ばしたのは、六角棒の先端と刀を納めた鞘の鐺だった。
「加勢ってわけかいな」
盗賊に続いて踏み入って来た二つの得物の揮い手は、央崎とデオバルトである
「そのつもり、だったんだが……」
「どうやら要らない世話だったってとこかな」
二人は本堂に倒れ伏した盗賊達を見遣って、苦笑を浮かべた。その数は、未だ二本の足で立っている者のそれを上回っている。
「手ぇ余らせて困ることはあらへんよ。──どうやら、お客はんもお揃いのようやしな」
琴吹が、二人の背後へと眼をやれば、そこには彼らを追って来た盗賊が屯していた。
「困った時はお互い様って言うだろ? 奴さんら、しつこいったらなくてな」
六角棒を振り回し、周囲の賊を牽制しながら琴吹の傍らへ立つ央崎が抜け抜けとそう抜かすと、「よう言うわ。ていうかなんやねんな、そのけったいな面は」と呆れ交じりに琴吹が呟いた。
「ま、連中がうっといのには違いあらへんけども」
そう付け加えた矢先、盗賊の一人が彼女に襲い掛かる。
「ほんまうっとい──」動じる事なく、振り返り様応じようとする琴吹。
しかしそれに先んじて、残像を纏いながらデオバルトが割って入り、倭刀の柄頭で盗賊を吹き飛ばした。
「まったく、女性の背中を斬り付けようなんて、どこまで無粋を働けば気が済むんだ、あんたらは」
鞘を左手に取りながら抜刀しつつ、心底見下げた目で盗賊達を見渡す。
「礼を言うた方がええんやろか」
「要らないさ。俺が勝手に余計な真似しただけだろ?」
琴吹が微笑しながら訊けば、デオバルトは飄々と返す。
それっきり、本堂に居合わせた全ての人間が口を閉じて、各々の得物を構えた。
破られた玄関口より吹き込む、夜気を孕んだ通り風が燈台の灯りを揺らす。と同時に、十幾数の器械が、闘争の音を上げた。
デオバルト、央崎、琴吹。三者共に、その闘争の在り方は、速さを尊ぶモノだった。
だがその速さの性質は、三者三様それぞれである。
刃風を撒き散らしながら、捉える間を与えず敵陣を縦横無尽に駆け抜けるデオバルトは、止む事の決してない颶風。
棍法で旋風を巻いたかと思えば、回転の軸を棍に移して足刀を廻す央崎は、その黒衣も相俟って、砂塵を舞い上げて暴威を振るう黒風竜巻の如く。
時には花を柔らかく揺らす軟風のような挙措で敵刃を絡め取り、時には嵐風を思わす強烈な突き技で賊を吹き飛ばす、琴吹の柔剛兼ね備えた技の数々は、春先に吹く気儘な風を彷彿とさせた。
三種の風に、盗賊達は木の葉の如く翻弄され、或は木端のように吹き飛ばされるのみだった。一人、また一人と伸びてゆき、未だ敵意をその眼に宿す盗賊も、数えるのに片手で足りる程になったその時である。
「まずい……!」
誰が吹き飛ばしたものか、賊の一人が本堂に置かれた仏像へぶつかったのだ。ぐらぐらと危なげに揺れる御仏を見咎めた央崎は、安定を崩してとうとう倒れる寸でのところで駆け寄った。
人丈二倍に達するであろう像は人一人の腕力に悲鳴を上げさせるに十分過ぎる。片手では足りぬと棍を放った央崎に、今こそ好機と接近して来た盗賊へ応じる手は、足技だけしかなかった。それでさえ荷重のある身では満足に揮えず、次々と襲い来る柳葉刀にとうとう足刀が間に合わなくなったと覚った央崎は、咄嗟に足許の六角棒を爪先で掬い上げ、足首と肩で両端を固定して刃閃を受け止めた。
盗賊は舌を打って刀を引くや、ならばと刃を返して先と逆方向から刀を薙ぐ。
打つ手なしかと思われた矢先、峰を返した倭刀が柳葉刀の柄を握る賊の腕を打ち、得物を手放させた。手首の痺れに賊が顔を歪ませるのも束の間、その顎を柄頭の一撃が打ち抜いた。盗賊の最後の一人が、その場に崩れ落ちる。
「悪い、助かった」
「困った時はお互い様なんだろ?」
央崎の礼にデオバルトがにやりと返しながら、仏像を支えるのに手を貸そうとしたその時だった。
味方の三者の他に立つ者は居なくなったと思われた中、気絶した賊の身体を押し退けて立ち上がる者があった。仲間の下に潜んでいたその賊は、立ち上がると共に両手を用いて擲箭を投じていた。的は当然、両手の塞がった央崎とデオバルト両名である。彼らに、飛来する八つの暗器を防ぐ手立てはない。
果たして、一瞬の時も経たぬ内に本堂に響いたのは──鏃が肉を貫く血濡れた音ではなく、鉄が鉄を弾く甲高い音であった。
「なにしてはんの、お二人はん」
投擲した手裏剣で、二人を狙った暗器を撃ち落とした琴吹が、口許に微笑を滲ませる。彼女は、咄嗟に狙いを自身に変えた賊の手に、擲箭よりも早く手裏剣を放っていた。観念したか血の滴る手を押さえて膝を着く賊に一瞥を寄越した琴吹は、やがて仏像を支え続ける二人に言い放った。
「これで、借りも貸しもチャラやさかいな」
臥城は葉桐のトンファー捌きを荒いと言ったが、確かに我流故の荒さを備えてはいたものの、以前までの彼女と比べて、その技には少なからず洗練された“理”が宿っていた。
トンファーに限らず、二つ揃えの器械の真髄は、攻守の切り替えにある。
攻めるを守りとし、守るを攻めに転ずる──それが、双武器の“理”だ。
“多撃必倒”を重んじる余り、そして生来からその身に積んだ来た刀術とは”理“が異なる得物の為に、トンファーでは攻めるに任せる傾向のあった葉桐であったが、難敵との戦闘がそうさせたのか、或は優れた遣い手との共闘から学んだのか、攻守一体の”理“が技の節々に垣間見えた。
本来なら打撃部位である棍を握り、斬り掛かって来た敵の単刀を把手に引っ掛けて振り払うや、即座に反撃を叩き込む。
敵の一刃に対して三打も見舞うところを見れば、“多撃必倒”の信念までもが失われたわけではなく、寧ろ守りに気を払った結果一層に磨きが掛かったと言えた。
「いやはや、これでは私は型なしだな」
その奮闘の余り、先から臥城は手許の苗刀を抜くまでもなく、ただ彼女の背に貼り付くのみだ。
「ご謙遜ね。正直、ぞっとするくらい背中が楽なんだけど」
いや、そう見るなら、それは武の何たるかを心得ていない余人の戯言だろう。闘争の場にあるまじき事に、そしてよりにもよって、葉桐は今己の背後を絶対的な安全圏だと考えていた。
が、安心して背中を任せているのかと言えば、そうではない。寧ろ、攻城兵器を背にして戦っているような、何とも言えない緊張感があった。
守りは不得手とは言い得て妙だ。例えるなら、最強の矛が盾として機能しているような矛盾がある気がしてならないのだ。
ともあれ、後背の憂いがないのは確か。
葉桐はその一瞬、守りの気遣いを一切捨てて、石畳に強く歩を打った。大きく水飛沫を上げる踏み込みから放った乾坤一擲の刺突が盗賊の胴を穿ち、その身を軽々と吹き飛ばす。
残心を終えて、長く呼気を吐きながら、葉桐は自分と臥城の他に立つ者の居なくなった境内を見渡した。
「どうやら皆、片を付けたようだ。葉桐だったかな、我流のようだが見事なモノだ。また機会があれば貴女の背中、幾らでもお守りしよう」
やがて暗がりの向こうから、別行動していた味方が近付いて来るのを見咎めた臥城が、息を整える葉桐に労いの声を掛けた。
「あ、あー……」彼の申し出にしばし言葉を探している風だった葉桐が、歯切れ悪く言う。
「その、気持ちだけ受け取っとくわ」
振り返った臥城の視界で、舞い落ちてきた唐傘を受け取る者があった。
「任せてちょーだい。景気の良い一発見せ付けられて、ちょっと血が滾っているとこだから」
傘の色と同じく、朱い立ち姿の女である。赤髪を靡かせ、軽装に身を包んで健康的な肢体を晒す彼女は、葉桐 舞矢(ka4741)という。
近頃までクロードという西方風の名を名乗り、間違った西方かぶれの口調をしていたのだが、思うところがあったらしく、今は少なからず地の振舞いで通しているようだ。
彼女は臥城の傍に歩み寄ると、彼に傘を差し出した。
「今のも、リアルブルーのちゅーごく拳法なわけ? いやぁ、やっぱし凄いわね」
「以前に功夫を目にしたことがあるのかね?」
傘を受け取りながら、臥城が問い返す。
「まぁね、ちょっと毛色が違ったけど」
「ほぉ、いやはやなんとも、世界を違えても世間は狭いものだ」
実はこの二人、浅いながらもとある縁があるのだが、双方共与り知らぬ事である。
「──ふむ、どうやら世間話に現を抜かしている場合ではないらしい」
傘を肩に掛けながら、つい──と臥城が視線を巡らせば、山門の破壊音を耳にした盗賊が、各々の得物を構えながら、山門付近の境内に屯していた。
「揃いも揃って御婦人との語らいを邪魔するとは、無粋だとは思わんか」
流し目と共に送られた短い嘆息交じりの台詞に応えたのは、夜気を裂いて飛ぶ匕首のあられ。臥城を貫かんと投げ放たれた短剣は、数えて四つ。背を覆う傘布も、その切っ先までは防げまい。長袍の袖を翻し、臥城が投剣に対応したその瞬間──先んじて割って入った葉桐が、匕首を悉く叩き落とす。
「荒い──が、速いな」
一瞬の内に、四本の投剣を迎撃した手練を見て取った臥城が、感心を滲ます声で呟く。残心する葉桐の両手に納まっているのは、ひどく短い棍に把手を付けた“ト”の字型の打撃器械。中国拳法でいうところの拐のようにも見えたが、短拐よりも尚短い。リアルブルーにおいては、拐を元にして日本の琉球で作られたというトンファーである。
「手数なら、誰にも負けはしないわ」
残心を解き、左手を前にして右手を引く構えを取る葉桐。幾つも波紋を立てながら足を交互に踏むその軽妙な足運びは、臨戦の空気に少なからず悦びを見出しているようで、何処か攻撃的だ。
「背中を任せてもいいかしら?」
取り囲む敵の群れを睥睨した後、葉桐は背後に立つ臥城へ問い掛ける。問いに微笑を浮かべた“いき”な侠客は、唐傘を閉じ、その石突で以って石畳を突いた。その瞬間、サァッ──と、臥城を中心とした細波が水面を駆け抜ける。
「生憎、守るのは不得手だが、御婦人の背中となれば是非もない。──任されようか」
「それはそれは、心強いわね」
足許を吹き抜けた勁の巡りと、尚力強い背後の声を感じて、葉桐は口許に不敵な笑みを浮かばせた。
投剣迎撃の際に見せた葉桐の手練、そして今しがた見せ付けられた臥城の強烈な発勁の片鱗に浮足立った盗賊が、それぞれ携えた得物に功を籠め、己を奮い立たせる叫声を発すると共に二人へと襲い掛かった──!
廃寺の裏門前には、長く続く石段が積まれていた。石畳の上に溜まった雨水が、緩やかな滝となって、石段を下へと流れ落ちて行く。
雲間から差す月光は裏門前のみを照らし、水の行く先には闇の帳が落ちるばかり。
しかし、裏門の番を務める寸胴の大男は、石段をやおら登って来る闖入者の存在を、その男が月明かりに姿を晒す前に知った。
荒い、水音。身を潜めるという事を全く知らない踏み音を立てながら、月光の下に現れたた男の姿を簡潔に言い表すなら、粗にして野。
半着も付けず、赤褐色の肌の上に直接身に付けた羽織りの片袖をはだけさせ、申し訳程度に巻いたさらしを覗かせている。更に不揃いの甲冑を身に纏い、抜き身の倭刀を肩に掛けたその立ち姿は、“粗野”という言葉を絵に描いたかのようだった。
しかし、何よりも目を引くのは、伸びるに任せて乱れた銀髪から覗く、額に映えた一本角。
門番に負けず劣らずの体格を誇るその男は、人ならざる存在──鬼だった。
「オマエ、なにモノ。なにしに来た」
巨漢という点は同じだが、鋼を思わす屈強な肉体を誇る鬼とは異なり、筋肉質というよりは肉の塊と言う方が的確な門番は、その見た目通りの鈍重な口調で、鬼に問い掛けた。
「あぁん? 一遍に二つも訊くんじゃねぇよ、ったく」
鬼は空いた手で銀髪を掻き毟ると、面倒だと言わんばかりに愚痴を零したが、やがて「どっちも見ての通りだよ」と答えを返した。
「名前はイッカク(ka5625)。この寺ぁ根城にしてる盗人共を叩っ斬りに来た」
いらえながら、鬼──イッカクは、大振りの倭刀、その切っ先を門番へと向ける。
「わかったらそこ退きやがれ。てめぇみてぇなウスノロの肉達磨斬っても、オモシロかねぇ」
「それ……ダメ。ここ通ろうとするヤツ、コワセって言われた」
門番は鈍い口調で呟きながら、傍らの柱に立て掛けた武器を手に取った。
長柄の先端に取り付けた円柱状の金属塊に、幾つも鋭い突起をあしらえた打撃器械──狼牙棒である。
「それに、オレ……コワスのスキ。オマエ、ひさしぶりのエモノ。だから──にがさない」
ただただ鈍そうなだけだった顔に、凶相染みた笑みが宿る。
舌打ち、一つ。
「──そうかよ。そんなに死にたきゃ、好きにしな」
イッカクは苛立ち混じりに舌打ちを零すと、門番に突き付けた倭刀を両手で握り、肩の上にまで上げながら、手の中で返した。──刀の峰を下に、刃を上に。
右肩を引いて半身を晒し、歩幅は肩幅に合わせて開く。
出で立ちに反して、その構えは風雨に合わせて静かに揺れる柳の古木を思わせる、静謐の型だった。
「きっちりかっちし、殺してやんよ」
「チガウ……殺されるのオマエ。オレが、コワスゥ!」
ネジの外れた声を上げながら、門番は飛んだ。肉達磨に似合わぬ跳躍力。重力の縛り、物理法則の束縛すらそれを阻めぬ。──軽功の遣い手か。
緩やかな放物線を描いて迫る肉達磨。その頭上には、あの凶悪足る得物が掲げられている。それだけの重量をして飛翔の如き跳躍を可能とする功の妙を知らずして、イッカクは微塵も動じず、ただ倭刀の切っ先をゆらりと揺らすのみだった。
────!
壮絶な破壊音が響き渡り、飛沫が跳ねる。
「コワシタ、コワレタァ♪」
狂喜に顔を歪める肉達磨。だが──
「──誰が殺して、誰が死ぬって?」
その醜悪な面相を見下ろす、赤玉の瞳があった。
振り下ろされた狼牙棒が倭刀に触れたその瞬間、柳の枝のように柔らかく揺れた刀身の反りに導かれるように、渾身の一撃はイッカクの身体を逸れたのだ。
「ヒデェ勘違いもあったもんだな、ウスラデブ」
狼牙棒を片足で踏み締め、二の手を封じたイッカクが、おもむろに倭刀を振り上げた。
「死ぬのはテメェで──」
そしてその出で立ちに相応しい、怒涛の一刀を門番の脳天目掛けて振り下ろす。
「──殺すのが俺だ!」
脳天をかち割った刀身が、
「あ──
──ひ?」
門番の股下まで斬り抜けた──!
綺麗に真っ二つに別たれた巨体が、派手に水飛沫を立てて左右に倒れる。
門より先に、門番を観音開きにしたイッカクは、その真ん中を真っ直ぐに進むと、立ち止まる事なく裏門を蹴り破った。
慎みのない侵入者を、すぐさま集った盗賊一行が出迎える。
「揃いも揃ってぞろぞろと。さっきのデブよか斬り応えあんだろぅな?」
多勢に無勢。しかし、イッカクは口許に不敵な笑みを湛えて、彼らを見渡した。
「貴様、何者だ!?」
その内の一人が誰何を放てば、イッカクはさも面倒そうに首の骨を鳴らし「一晩に二度も名乗るもんじゃねぇ」と言い放つと、その身を翻して背中を晒した。
「名乗りなんざ、こいつで十分だ!」
羽織りに背負った“悪”一文字を魅せ付けたのだ。
月の光が、水面の壇上に立ち、刀を肩に掛けて大見得を切った傾奇者の姿を照らし出す。
「さぁ──タマ惜しかねぇ奴から、得物執りなぁ!」
「裏門からも攻め入られた、急げ──!」
夜半の急襲に慌てふためき、境内を駆け巡る盗賊達。
「おい、止まれ……!」
裏門へ向かおうとしていた彼らは、走る先の薄闇に浮かび上がった、その白い人影に気付いて足を止めた。
「そこのお前、なに奴だ!」
和装に身を包み、長い白髪を雨の匂いを孕んだ夜風に靡かせるその者は、高圧的に発せられたその誰何に苦笑を浮かべた。
「おやおや、これは弱ったねぇ。こんなに早く見付かってしまうとは」
中性的な顔立ちに似合った、妙に落ち着いた響きの声。そして和装の似合う長身ながら痩身の体躯の持ち主は、その風貌に反して、女に生まれた身であった。
彼女は、血気に逸って早くも得物を執った盗賊達をなだめるように、着物の袖をおもむろに上げた。
「およしなよ。こんなひ弱そうなのに構ってる場合じゃないだろうよ。私なんか、ろくに拳を握ったこともないんだ。相手にするだけ時間の無駄だよ」
確かに、捲れた袖から覗く細腕は、到底武芸者のモノとは思えない。白魚のようなその指先は、紛う事なき女性のそれだった。
「向こうの方を見たかい? 鬼が暴れ回ってるじゃないか。そっちに行くといいよ」
「ああ、そうさせて貰おう。──貴様を手早く片付けた、その後でな!」
飄々とした説得の甲斐もなく、盗賊の一人が手斧を振り上げ、桃之枝に踊り掛かった。
「やっぱり、そうなるのか……」盗賊が間合いを詰め寄る中で、動じるでもなく溜息を零した後「なら仕方ない」桃之枝は、上に翳した掌をひらり──と返す。
示指と中指の間に手妻のように現れたのは、一枚の札。彼女の出自、東方の陰陽寮に由来する呪符だ。
「──色界不浄、急急如律令」
必然、二指の間から放たれた呪符がもたらしたのは、陰陽道に連なる秘術。『不浄』という言葉とは相容れない、月光に散る桜吹雪が、術者へと襲い掛かる男の視界を封殺したのである。
「私は桃之枝(ka6824)」
渦を巻く夜桜に渦中に立ちながら、女は先刻の誰何にいらえる。
「しがない通りすがりの、陰陽師だよ」
廃寺の敷地に佇む、小さな墓地。苔生した墓石は、既に文字も掠れ何処の何某がいつからその下で眠っているのか皆目見当が付かない。その場所は、最早無縁墓地も同然の有り様だった。
そんな忘れらるる場所に佇む者が一人居た。
陰気な色合いのコートを身に付けた青年だった。その墓地が西方の仕様、或はその男──央崎 枢(ka5153)の生家に準じたキリスト教の墓地だったなら、その黒衣から聖職者を連想する事ができただろうか。いやそれとも、目深に被ったそのフードから、死神の似姿だと思う者も居たかもしれない。しかし──
「おい! 貴様、一体そこでなにをしている!」
喧しい水音、複数の足音に続いて横合いから掛けられた横暴な声に、おもむろに振り返ったフードの奥に覗く顔は、敬虔なクリスチャンでも、空虚な骸骨でもなく、ただ滑稽な笑みを浮かべる道化のモノだった。
央崎は、果たして何の酔狂か、道化師の仮面をフードの下に被っているのである。
「なぁに、ただの墓参りさ」
仮面の奥から嘯く台詞に耳を貸そうとする者は、当然誰一人として居なかった。央崎を見咎めた盗賊達は、寧ろ彼が肩に担いだ八角棒を注視する。
「おおかた、正門と裏門から攻め入った連中の仲間だろう。陽動に我々の目を牽き付け、身を潜めながら動く腹だったのかもしれんが、ここで見つかったのが運の尽きよ」
「別にそんな小賢しく立ち回ろうだなんて思っちゃいないさ。そっちから見付けて貰って、むしろ手間が省けたとこだよ」
何やら悦に入っている様子の盗賊に肩を竦めながら水を差すと、央崎は肩慣らしがてらに、八角棒を振り回す。腕や肩、腰や脚を軸に旋風を巻くその動きからして、彼が棍法を弁えている事は明らかだった。
締めに足許の水を棒の先端で掻いてみせると、央崎は脇を閉めて棍を背に回しながら構えを取った。空いた手で剣訣を結ぶでもなく、ついついと人差し指を煽るように動かす。
「さぁ来な。俺が遊んでやるよ」
「……っ! 青二才が!」
盗賊の一人──年かさの男が柳葉刀を振り翳して央崎へ踊り掛かった。重量を乗せて、袈裟切りの軌道を描く段平。その一刀を、央崎は危なげなく躱してみせる。
そして躱したその瞬間には、既に反撃を見舞っていた。半身を切ると同時に、背に回した八角棒を突き出して、男の顎を打ち抜いたのだ。
まだ刀を完全に振り切る前、寧ろ躱されるのを見越して次手を放とうとしていた男は、巧みな反撃に不意を突かれて呆気なく意識を失い、そのまま己の刀勢に引っ張られるようにして倒れ込んだ。
「おいおい、張り合いなさ過ぎやしないか」
水面に沈んだ男を一瞥する央崎。にんまりと道化師の面の奥に覗くブラウンの瞳は、仮面の表情に反して、何処か辛辣だった。
「ほざけっ!」
先の男と同じ柳葉刀の使い手が、怒り心頭発した声で、刀を払う。しかし、刃鳴りが墓場に響き渡ったその時にはもう、央崎は無明のまま久しい灯篭の上に立っていた。
滑稽を装う面が、盗賊達を見下ろす。
「どうしたよ。神様仏様に手出したんだ、そんなモンじゃないんだろ?」
発するその声にはやはり、少なからず心穏やかならない調が滲んでいた。
「仏の教えを仰いだ憶えもねえし、神罰代行なんてタチじゃあないが。まぁそのなんだ、骨の一、二本は覚悟しろよな?」
「いい夜だな」
その声は、頭上から振って来た。
境内を西へ東へと奔走する盗賊達は、不意に掛けられた声に、天を振り仰ぐ。果たして声の主は、花を咲かせる事もなくなって久しい桃の梢に腰掛けていた。
背に蒼月を背負っているのは、すらりとした体躯をした褐色肌の男だった。月光を浴びて光る銀髪を後頭で一房に纏めて垂らし、膝を立てて古木の枝に腰掛けている。
「そうは思わないか?」
眼下の盗賊達に向けて、飄々と問う男。
「貴様、何者だ!? なにをしている!」
風情のある会話に興じる事なく、盗賊達は誰何を放った。しかし返答を待つ間でもなく、彼等は既に得物を執っていた。今日この夜に、腰に刀を差して境内に居合わせた男が、ただの月見客というわけもあるまい。賊の中で最も気の早い者は、男が返答を寄越そうと口を開き掛けたその時既に、五指に握り込んでいた擲箭を投げ放っていた。
だが、果たして四つの投擲暗器が射抜いたのは、梢を蹴って樹上から跳び降りる男の残像のみであった。
男が石畳を踏み締めると共に跳ねる、無色透明の飛沫。
いや、それのみならず、今しがた擲箭を投じた盗賊の腕から、赤い飛沫が上がる。──水面に生じた跳ね水の王冠が没するよりも、尚早く。
「無粋な真似するなよ」
背後で囁く声を聞いた賊は、苦鳴を上げる間を惜しんで、振り返り様に擲箭を握る無傷の腕を揮った。不意を打たんとした一手は、しかし、手応えがなく──
「がっ……!」
寧ろ自身の首筋に痛烈な衝撃を受けて、彼は昏倒する事となった。
「神サマ掻っ攫うなんて、大層な連中も居たもんだと思ってみれば、どうしたもんかなこいつは。腕も悪ければ、風情も解せない。期待外れもいいとこだ」
柄頭で賊のうなじを打った刀を掛けながら、男は飄々とした調子で肩を竦めてみせた。縮地と見紛うばかりの瞬動に、尚一層に警戒を露にしながら得物を突き付け、周囲を取り囲む賊達の姿など、眼に入っていないかのような態度である。
「だがまぁしかし、粋の欠片もない輩でも、名も知らないままにぶっ飛ばされんのは、気持ちよくはないだろうからな。一遍だけ、教えてやるよ。そこで伸びてるのにも、後で教えてやるんだな」
倭刀の切っ先を盗賊達に返しながら、終始剣呑とは縁遠い態度で、男は己が名を告げる。
「俺の名は、テオバルト・グリム(ka1824)。生憎、冥土の土産にさせるつもりはないからさ。
安心して、掛かって来な」
「馬鹿共が腑抜けやがって!」
他の盗賊とは、やや風体が上等の男が怒りも露わにした胴間声を響かせているのは、彼らが根城にしている本堂だった。雨風を凌いでいるのは、盗賊一党のみならず、その戦利品である神仏に由来するあれやこれやが、粗雑に陳列されていた。
最も眼を惹くのは、光背を背負った仏像だ。見るも絢爛な金箔が、燈台で揺れる炎を照り返している。
「敵の数は十にも届いてねえっていうじゃねえか。なのに好き放題にさせやがって。これじゃ江湖のいい笑いもんだぜ、情けねえ!」
衣装の割に品のない声で威圧する盗賊一味の香主らしき男に委縮してか、周囲の取り巻き達は、返す言葉を持たなかった。
「──ほんま、あんさんの言う通りやな」
代わりに同調を示したその声は、おっとりとした口調の少女の声。
うじ湧く男やもめの郎党一味には、生憎と華は一輪もない。盗賊達は、瞠目してその声の源──暗がりの奥へと視線を向ける。
「こない美少女に今の今まで気づかんと、男としてなっさけない話やあらへんの」
果たして蝋燭の明かりの中に姿を現したのは、ふわりとした黒髪を二房に結わった少女。特徴的なのは、布端が足許に届きそうな程に長い、真紅のマフラーだ。彼女は黒髪とマフラーを揺らしながら、頻りに男の台詞に頷いている。
「っ…………!?」
彼女が声を掛けるその間際まで、その存在を知る者は、この場には誰一人として居なかった。その事実に盗賊達は声もなく、ただ眼を見張るのみだった。
「……って、なんか返しぃな。なんや、私がサムイみたいになるやんか」
「き、貴様一体なにモンだ!?」
ようやく自失の体から立ち直った香主の男が、お馴染みの誰何を口にした。
「あっちゃこっちゃうろついて聞いてたんやけども、おたくら、ちょいと芸があらへんとちゃうん?」
呆れた様子でかぶりを振る少女。「ま、ええけどもやな」と呟き、居住まいを正す。
「ほなら、名乗うたる。私は琴吹 琉那(ka6082)ゆーねん。ご覧の通り、忍者やらせてもろうてます」
ニンニン、と両手を組んでにわか知識で印を結ぶ少女──琴吹。盗賊達は、またもや押し黙ったまま彼女を睨んだ。今度は、警戒の方が先に立ったようだが。
「またかいな。おたくら、ノリ悪いんと違う?」
「……おめぇは、表の奴らの仲間ってことだな?」
「そうや、ゆうたら、どないするん?」
「こうすんのさっ!」
叫ぶが早いか、香主の男は琴吹へと殴り掛かった。女子供、中でも小柄な琴吹を相手にして慢心がそうさせるのか、初手にあるまじき大振りの拳。琴吹は瞬時に、男の懐中へと身を滑らせた。
────!
踏み足が、気張りの床を打つ。
身を沈めながら懐に潜り込むその所作は、回避の為のみならず。強烈無比な肘撃の破壊力を生む為の震脚も兼ねていた。
下肢から腰へ伝わる力の流れは、更に捻転による加算によって勢いを増し、突き入れた肘から、男の背中へと突き抜ける。
琴吹が懐から身を退くと、男はまた声もなくゆっくりと床へ沈んでいった。今度ばかりは、その沈黙を意に介する事もなく、琴吹はただ呆れた様子で男を見下ろす。
「なんや偉そうにしよったいうに。口だけやねんか」
いとも容易く香主を倒した手練を見せ付けられた盗賊達は、最早琴吹を女子供と軽んじる事なく腰の単刀を抜き放つや、その切っ先を彼女に突き付けた。
幾条の刀身に映る少女の口端が、微笑を浮かべる。
「ようやく、やな。よう気ぃ入れりぃや」
拳は緩やかに握り、左右の手を上下に置く。構えは、千変万化の柔の型。
「こっからが、私の本領やさかいな」
振り掛かる斬撃を避けきれなかった和装の袖が裂ける。
「おっと、これは危ない」
桃之枝の口許は尚も緩やかな曲線を描いてはいたが、その内心は舌を打たんばかりだ。次々と襲い来る盗賊達に、ただ眼晦ましの符術のみで立ち回るのにも限りがある。だが攻めの一手に転じようにも、数で物言う敵の勢いに押されて、その猶予がない。敵勢に押されるがままに、守りの堰が切れるのも時間の問題だった。
「これまでだっ!」
頭上に掲げた手斧を振り下ろさんとする盗賊。その一手は、桃之枝の正中線を正確に捉えていた。
「が、は……!?」
だが、斧頭が彼女の頭をかち割るその前に、賊の胸郭から生える刃の切っ先があった。それと共に、賊の背後から桃之枝に声を掛ける者がある。背後──とは言え、巨体を誇る鬼の面貌は、見るも明らかではあったが。
「なにやってんだ、ひょろいの。足引っ張なんなら、他所行きやがれ」
死体に変じた賊を放り捨て、倭刀の血を払ったイッカクが、その背に桃之枝を庇いながら、盗賊の残党共の前に立ちはだかる。
「おやおや、これは手厳しい。でもまあ、頼もしい限りじゃないか。ではここはお言葉に甘えておこうかな?」
足手纏いと告げられたにも関わらず、桃之枝は寧ろからかうような声でイッカクに応じながら、一歩退いた。
「そう──してなっ!」
鼻を鳴らしながら、肩越しに桃之枝を見遣ったイッカクは、手斧を打って来た盗賊の腕を、一挙動で斬り上げた刀で以って両断した。
明後日の方向へと飛んで行く己が腕を見送る盗賊が眼を見張る。いや、直後に瞠目したのは、彼だけではない。イッカクもまた、赤い瞳を見開いた。
両断した盗賊の腕、その切断面が、突如発火したからだ。
「いやはや、中々景気良く燃えてくれるじゃないか」
火はすぐさま火種を浸食し、人間松明と化して踊り狂う盗賊を見ながら、桃之枝は口許に微笑を滲ませる。
「テメェ……!」
彼女と、いつの間にやら倭刀の刀身に貼り付けられた呪符とを、イッカクは歯噛みしながら見比べた。
「ん? どうしたのかな。それにしても凄いものだね。切り口から燃え出すなんて、剣にはそんな技まであるのかい?」
その眼光を受けて、桃之枝は今度こそ確かに弄うような笑みを返した。
「……好きに言ってやがれ」
忌々しい思いで彼女から視線を切るや、残りの盗賊達へと向き直る。
「……お前らには同情するぜ、まったく。
今から俺の憂さ晴らしに付き合わされにゃなんねぇだからな」
「なんやねんな、騒々しゅうて敵わんわ」
本堂の朽ちかけた引き戸を破って、押し入って来た二つの人影に琴吹が眼を向ける。いや、正確には、押し入ったと言うよりは、吹き飛ばされたと言う方が正確だ。床に伸びている二人の盗賊を吹き飛ばしたのは、六角棒の先端と刀を納めた鞘の鐺だった。
「加勢ってわけかいな」
盗賊に続いて踏み入って来た二つの得物の揮い手は、央崎とデオバルトである
「そのつもり、だったんだが……」
「どうやら要らない世話だったってとこかな」
二人は本堂に倒れ伏した盗賊達を見遣って、苦笑を浮かべた。その数は、未だ二本の足で立っている者のそれを上回っている。
「手ぇ余らせて困ることはあらへんよ。──どうやら、お客はんもお揃いのようやしな」
琴吹が、二人の背後へと眼をやれば、そこには彼らを追って来た盗賊が屯していた。
「困った時はお互い様って言うだろ? 奴さんら、しつこいったらなくてな」
六角棒を振り回し、周囲の賊を牽制しながら琴吹の傍らへ立つ央崎が抜け抜けとそう抜かすと、「よう言うわ。ていうかなんやねんな、そのけったいな面は」と呆れ交じりに琴吹が呟いた。
「ま、連中がうっといのには違いあらへんけども」
そう付け加えた矢先、盗賊の一人が彼女に襲い掛かる。
「ほんまうっとい──」動じる事なく、振り返り様応じようとする琴吹。
しかしそれに先んじて、残像を纏いながらデオバルトが割って入り、倭刀の柄頭で盗賊を吹き飛ばした。
「まったく、女性の背中を斬り付けようなんて、どこまで無粋を働けば気が済むんだ、あんたらは」
鞘を左手に取りながら抜刀しつつ、心底見下げた目で盗賊達を見渡す。
「礼を言うた方がええんやろか」
「要らないさ。俺が勝手に余計な真似しただけだろ?」
琴吹が微笑しながら訊けば、デオバルトは飄々と返す。
それっきり、本堂に居合わせた全ての人間が口を閉じて、各々の得物を構えた。
破られた玄関口より吹き込む、夜気を孕んだ通り風が燈台の灯りを揺らす。と同時に、十幾数の器械が、闘争の音を上げた。
デオバルト、央崎、琴吹。三者共に、その闘争の在り方は、速さを尊ぶモノだった。
だがその速さの性質は、三者三様それぞれである。
刃風を撒き散らしながら、捉える間を与えず敵陣を縦横無尽に駆け抜けるデオバルトは、止む事の決してない颶風。
棍法で旋風を巻いたかと思えば、回転の軸を棍に移して足刀を廻す央崎は、その黒衣も相俟って、砂塵を舞い上げて暴威を振るう黒風竜巻の如く。
時には花を柔らかく揺らす軟風のような挙措で敵刃を絡め取り、時には嵐風を思わす強烈な突き技で賊を吹き飛ばす、琴吹の柔剛兼ね備えた技の数々は、春先に吹く気儘な風を彷彿とさせた。
三種の風に、盗賊達は木の葉の如く翻弄され、或は木端のように吹き飛ばされるのみだった。一人、また一人と伸びてゆき、未だ敵意をその眼に宿す盗賊も、数えるのに片手で足りる程になったその時である。
「まずい……!」
誰が吹き飛ばしたものか、賊の一人が本堂に置かれた仏像へぶつかったのだ。ぐらぐらと危なげに揺れる御仏を見咎めた央崎は、安定を崩してとうとう倒れる寸でのところで駆け寄った。
人丈二倍に達するであろう像は人一人の腕力に悲鳴を上げさせるに十分過ぎる。片手では足りぬと棍を放った央崎に、今こそ好機と接近して来た盗賊へ応じる手は、足技だけしかなかった。それでさえ荷重のある身では満足に揮えず、次々と襲い来る柳葉刀にとうとう足刀が間に合わなくなったと覚った央崎は、咄嗟に足許の六角棒を爪先で掬い上げ、足首と肩で両端を固定して刃閃を受け止めた。
盗賊は舌を打って刀を引くや、ならばと刃を返して先と逆方向から刀を薙ぐ。
打つ手なしかと思われた矢先、峰を返した倭刀が柳葉刀の柄を握る賊の腕を打ち、得物を手放させた。手首の痺れに賊が顔を歪ませるのも束の間、その顎を柄頭の一撃が打ち抜いた。盗賊の最後の一人が、その場に崩れ落ちる。
「悪い、助かった」
「困った時はお互い様なんだろ?」
央崎の礼にデオバルトがにやりと返しながら、仏像を支えるのに手を貸そうとしたその時だった。
味方の三者の他に立つ者は居なくなったと思われた中、気絶した賊の身体を押し退けて立ち上がる者があった。仲間の下に潜んでいたその賊は、立ち上がると共に両手を用いて擲箭を投じていた。的は当然、両手の塞がった央崎とデオバルト両名である。彼らに、飛来する八つの暗器を防ぐ手立てはない。
果たして、一瞬の時も経たぬ内に本堂に響いたのは──鏃が肉を貫く血濡れた音ではなく、鉄が鉄を弾く甲高い音であった。
「なにしてはんの、お二人はん」
投擲した手裏剣で、二人を狙った暗器を撃ち落とした琴吹が、口許に微笑を滲ませる。彼女は、咄嗟に狙いを自身に変えた賊の手に、擲箭よりも早く手裏剣を放っていた。観念したか血の滴る手を押さえて膝を着く賊に一瞥を寄越した琴吹は、やがて仏像を支え続ける二人に言い放った。
「これで、借りも貸しもチャラやさかいな」
臥城は葉桐のトンファー捌きを荒いと言ったが、確かに我流故の荒さを備えてはいたものの、以前までの彼女と比べて、その技には少なからず洗練された“理”が宿っていた。
トンファーに限らず、二つ揃えの器械の真髄は、攻守の切り替えにある。
攻めるを守りとし、守るを攻めに転ずる──それが、双武器の“理”だ。
“多撃必倒”を重んじる余り、そして生来からその身に積んだ来た刀術とは”理“が異なる得物の為に、トンファーでは攻めるに任せる傾向のあった葉桐であったが、難敵との戦闘がそうさせたのか、或は優れた遣い手との共闘から学んだのか、攻守一体の”理“が技の節々に垣間見えた。
本来なら打撃部位である棍を握り、斬り掛かって来た敵の単刀を把手に引っ掛けて振り払うや、即座に反撃を叩き込む。
敵の一刃に対して三打も見舞うところを見れば、“多撃必倒”の信念までもが失われたわけではなく、寧ろ守りに気を払った結果一層に磨きが掛かったと言えた。
「いやはや、これでは私は型なしだな」
その奮闘の余り、先から臥城は手許の苗刀を抜くまでもなく、ただ彼女の背に貼り付くのみだ。
「ご謙遜ね。正直、ぞっとするくらい背中が楽なんだけど」
いや、そう見るなら、それは武の何たるかを心得ていない余人の戯言だろう。闘争の場にあるまじき事に、そしてよりにもよって、葉桐は今己の背後を絶対的な安全圏だと考えていた。
が、安心して背中を任せているのかと言えば、そうではない。寧ろ、攻城兵器を背にして戦っているような、何とも言えない緊張感があった。
守りは不得手とは言い得て妙だ。例えるなら、最強の矛が盾として機能しているような矛盾がある気がしてならないのだ。
ともあれ、後背の憂いがないのは確か。
葉桐はその一瞬、守りの気遣いを一切捨てて、石畳に強く歩を打った。大きく水飛沫を上げる踏み込みから放った乾坤一擲の刺突が盗賊の胴を穿ち、その身を軽々と吹き飛ばす。
残心を終えて、長く呼気を吐きながら、葉桐は自分と臥城の他に立つ者の居なくなった境内を見渡した。
「どうやら皆、片を付けたようだ。葉桐だったかな、我流のようだが見事なモノだ。また機会があれば貴女の背中、幾らでもお守りしよう」
やがて暗がりの向こうから、別行動していた味方が近付いて来るのを見咎めた臥城が、息を整える葉桐に労いの声を掛けた。
「あ、あー……」彼の申し出にしばし言葉を探している風だった葉桐が、歯切れ悪く言う。
「その、気持ちだけ受け取っとくわ」
依頼結果
| 依頼成功度 | 成功 |
|---|
| 面白かった! | 6人 |
|---|
ポイントがありませんので、拍手できません
現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。
あなたの拍手がマスターの活力につながります。
このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!
MVP一覧
重体一覧
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2017/05/23 22:57:55 |
|















