ゲスト
(ka0000)
p1000 奇怪なる世界の人々へ
マスター:のどか
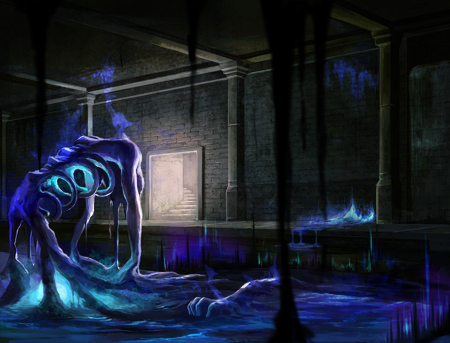
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 不明
- オプション
-
- 参加費
 1,000
1,000- 参加制限
- -
- 参加人数
- 4~8人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2017/10/20 07:30
- 完成日
- 2017/10/27 02:37
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●
薄暗い洞穴の中で、味気ないデザインの椅子に腰かけた白装束の青年は、岩肌のむき出しになった天井を見上げて小さく息を吐いた。
その表情は度重なる徹夜作業で「あまりにひどい」の一言であったが、それとは裏腹にランプの灯りに照らされてゆらめく瞳には、恍惚の色が灯っていた。
隻腕の指先に収めた赤褐色の羽ペンを音もなく机の上にそっと置き、名残惜しむようにその芯を指先でなぞる。
ペン先に染み込んだままのインクを指先に移すように滲ませてから、彼はそれをようやく手放した。
「――ついに、成った」
感入った様子で呟いて、彼はもう一度、至福の吐息を漏らす。
開かれたままの書物は、裏表紙のすぐ隣――最後の1ページが露となっている。
びっしりと文字が書き記されたページの最後の最後に、この本の紡ぎ手が自ら名乗りを上げるかのように走り書きの署名がひとつ記されていた。
――キアーヴェ・アルフレッド・ヴェクター。
青年はインクがちゃんと乾いている事を確認すると、そっと背表紙を閉じる。
それは、これまで紡いで来た物語の終わりを意味し――生涯の大作が完成したという合図でもあった。
この感動を、胸の高ぶりを、今すぐ誰かに伝えたい。
しかし、そういう時に限ってあの仮面の作劇家は姿を現さない。
大方、次なる劇の上演準備に、優雅気ままに駆け回っているのだろう。
「構わないさ。たった1人の読者など、私の求めるところではない。それに――まだ、私の契りは果たされていない」
青年は完成したばかりの本を小脇に抱えると、重い腰を持ち上げる。
しばらくまともに食事も取っていなかったせいか、途端にふらりと貧血に似た感覚に襲われるが、それを圧して立ち上がると乱れた装束を正す。
そうして、遥か遠くに差す外界の光を眺めながら、この素晴らしき日に姿を現さなかった、ただ1人の理解者の姿を思い描いた。
「――カッツォよ。永遠に語り継がれる物語の“創り方”を、君は知っているか?」
その問いに答える者はなく、ただ喉に張り付いたように乾いた笑いだけが、洞穴の中にはらはらと響いていた。
●
ヴァリオス同盟軍本部のエスト隊執務室は、息を吐くことも躊躇われそうなほどに重い空気に包まれていた。
若い活気で賑わいを見せていたあの部屋の様子は見る影もなく、隊長のアンナと事実上の副隊長であるフィオーレが、黙々と書類にペンを走らせている音だけが響いていた。
ことあるごとにいがみ合っていた少年たちの喧騒は記憶に遠く、彼らの影もまた部屋の中にはない。
そんな中でドアがノックされ、アンナが短く「どうぞ」と来客の入室を促す。
古い蝶番が軋む音を響かせながら扉は開き、その先からピーノの仏頂面が覗いた。
「すみません……遅くなりました」
小さく頭を下げたピーノに、アンナは小さく首を横に振る。
「バンの所か」
「はい」
「調子はどうだ」
彼女の問いに、ピーノは視線を逸らしながら自分の襟元に右手を這わせる。
気にするように指先でなぞったその首筋には、ひと筋の大きな傷跡が血の気を帯びて浮かび上がっていた。
「……変わらずです」
「……そうか」
アンナが形式的に返事をすると、ピーノは自分のデスクへ向かい、すとんと腰を下ろした。
そもそも、彼と同じように毎日軍の療養施設に通うアンナにとって、今のやりとりに意味なんてない。
だが、この重苦しい空気と、傷心の部下とを前にすると、何かしらの声を掛けないわけにもいかなかったのだ。
それも徒労に終わってしまったことに自己嫌悪し、彼女は小さくため息をついてから表情を仕事用のそれに戻しす。
そうして、今は2人になってしまった隊の面々へと向き直った。
「ひとまず、分かっていることを改める。各々、気になった点があれば随時指摘してくれ」
そう前置いて、アンナは自分が纏めた過去十数か月分の資料を読み上げる。
・バンの事件から今日まで、異形による狂気事件はなりを潜めている。
・彼は同盟中に目下指名手配となっているが、現在目撃例は報告されていない。
・先の依頼で回収された『刀』に関しては、現在同盟陸軍の管轄下にある。
・研究解析は難航しているが、負のマテリアルによって生成されているものと目される。
「そして、最も重要かつ不可解な点だが――」
一呼吸おいてから、アンナはその条文を読み上げた。
・キアーヴェ・A・ヴェクターは、本件調査上では“人間である”と目される。
「……正直、納得がいきません」
おもむろに舌打ちをして、ピーノは奥歯を噛み締めながら眉を潜める。
「だが、以前ハンターが切り落とした奴の腕を調べた結果、その作りは我々となんら変わりない――少なくとも、負のマテリアルとして消失する事がない、ということは事実だ。確かに可能性に過ぎないが、無下にできるものじゃない」
「だからと言って、その奇行を許して良いんですか!?」
「もちろん、許すことはできない。だが、人間である可能性が示唆された以上――我々の目的は、奴の“討伐”ではなく“確保”だ」
軍人として、そして人間として、ぐうの音も出ない正論を前にピーノは歯がゆそうに押し黙る。
そんな彼の様子を直視できず、フィオーレは思わず視線を手元に落とした。
「……とにかく、今は目撃情報の聞き込みに力を入れるしかない。我々は我々の成すべきことを忘れないよう」
締めくくるように口にして、アンナは資料を机の上にとさりと放る。
「――それでも」
「ん……?」
腹の底から絞り出すような、低く震える返事を耳にして、アンナは思わず顔を上げた。
「それでも……俺は奴を※したい」
強い意志を持って口にしたピーノのその言葉に、アンナは思わず眉間に皺を寄せる。
もとより人間として――彼女も彼の気持ちは痛いほどわかる。
それでも隊長として――彼女は彼の気持ちを肯定するわけにはいかない。
感情の板挟みに小さく頭を振ったアンナは、意を決したようにピーノへと向き直る。
しかし、彼への言葉を口にする前に、執務室の扉はけたたましい音と共に開け放たれた。
「で……伝令ッ! 狂気歪虚がヴァリオス市外に出現ッ! すぐさま出動されたしッ!」
「狂気……? リアルブルーのVOIDか?」
「い、いえ……その形状的な特徴が過去の報告書と一致! 昨年まで同盟近辺を騒がせていたものと、同一個体と思われますッ!」
その言葉に、3人の目の色が変わった。
咄嗟に傍らの武装を手に取り、出撃の身支度を整える。
なぜ今になって?
相次いでいる同盟内の歪虚騒動に関係してか、それとも――
軍服のジャケットに袖を通しながら、アンナの頭の中では目まぐるしく疑問が渦巻く。
そんなえも言われぬ不安を心中に抱きながらも、彼女はデスク脇に鎮座する巨大なアタッシュケースの取っ手を力強く握りしめた。
薄暗い洞穴の中で、味気ないデザインの椅子に腰かけた白装束の青年は、岩肌のむき出しになった天井を見上げて小さく息を吐いた。
その表情は度重なる徹夜作業で「あまりにひどい」の一言であったが、それとは裏腹にランプの灯りに照らされてゆらめく瞳には、恍惚の色が灯っていた。
隻腕の指先に収めた赤褐色の羽ペンを音もなく机の上にそっと置き、名残惜しむようにその芯を指先でなぞる。
ペン先に染み込んだままのインクを指先に移すように滲ませてから、彼はそれをようやく手放した。
「――ついに、成った」
感入った様子で呟いて、彼はもう一度、至福の吐息を漏らす。
開かれたままの書物は、裏表紙のすぐ隣――最後の1ページが露となっている。
びっしりと文字が書き記されたページの最後の最後に、この本の紡ぎ手が自ら名乗りを上げるかのように走り書きの署名がひとつ記されていた。
――キアーヴェ・アルフレッド・ヴェクター。
青年はインクがちゃんと乾いている事を確認すると、そっと背表紙を閉じる。
それは、これまで紡いで来た物語の終わりを意味し――生涯の大作が完成したという合図でもあった。
この感動を、胸の高ぶりを、今すぐ誰かに伝えたい。
しかし、そういう時に限ってあの仮面の作劇家は姿を現さない。
大方、次なる劇の上演準備に、優雅気ままに駆け回っているのだろう。
「構わないさ。たった1人の読者など、私の求めるところではない。それに――まだ、私の契りは果たされていない」
青年は完成したばかりの本を小脇に抱えると、重い腰を持ち上げる。
しばらくまともに食事も取っていなかったせいか、途端にふらりと貧血に似た感覚に襲われるが、それを圧して立ち上がると乱れた装束を正す。
そうして、遥か遠くに差す外界の光を眺めながら、この素晴らしき日に姿を現さなかった、ただ1人の理解者の姿を思い描いた。
「――カッツォよ。永遠に語り継がれる物語の“創り方”を、君は知っているか?」
その問いに答える者はなく、ただ喉に張り付いたように乾いた笑いだけが、洞穴の中にはらはらと響いていた。
●
ヴァリオス同盟軍本部のエスト隊執務室は、息を吐くことも躊躇われそうなほどに重い空気に包まれていた。
若い活気で賑わいを見せていたあの部屋の様子は見る影もなく、隊長のアンナと事実上の副隊長であるフィオーレが、黙々と書類にペンを走らせている音だけが響いていた。
ことあるごとにいがみ合っていた少年たちの喧騒は記憶に遠く、彼らの影もまた部屋の中にはない。
そんな中でドアがノックされ、アンナが短く「どうぞ」と来客の入室を促す。
古い蝶番が軋む音を響かせながら扉は開き、その先からピーノの仏頂面が覗いた。
「すみません……遅くなりました」
小さく頭を下げたピーノに、アンナは小さく首を横に振る。
「バンの所か」
「はい」
「調子はどうだ」
彼女の問いに、ピーノは視線を逸らしながら自分の襟元に右手を這わせる。
気にするように指先でなぞったその首筋には、ひと筋の大きな傷跡が血の気を帯びて浮かび上がっていた。
「……変わらずです」
「……そうか」
アンナが形式的に返事をすると、ピーノは自分のデスクへ向かい、すとんと腰を下ろした。
そもそも、彼と同じように毎日軍の療養施設に通うアンナにとって、今のやりとりに意味なんてない。
だが、この重苦しい空気と、傷心の部下とを前にすると、何かしらの声を掛けないわけにもいかなかったのだ。
それも徒労に終わってしまったことに自己嫌悪し、彼女は小さくため息をついてから表情を仕事用のそれに戻しす。
そうして、今は2人になってしまった隊の面々へと向き直った。
「ひとまず、分かっていることを改める。各々、気になった点があれば随時指摘してくれ」
そう前置いて、アンナは自分が纏めた過去十数か月分の資料を読み上げる。
・バンの事件から今日まで、異形による狂気事件はなりを潜めている。
・彼は同盟中に目下指名手配となっているが、現在目撃例は報告されていない。
・先の依頼で回収された『刀』に関しては、現在同盟陸軍の管轄下にある。
・研究解析は難航しているが、負のマテリアルによって生成されているものと目される。
「そして、最も重要かつ不可解な点だが――」
一呼吸おいてから、アンナはその条文を読み上げた。
・キアーヴェ・A・ヴェクターは、本件調査上では“人間である”と目される。
「……正直、納得がいきません」
おもむろに舌打ちをして、ピーノは奥歯を噛み締めながら眉を潜める。
「だが、以前ハンターが切り落とした奴の腕を調べた結果、その作りは我々となんら変わりない――少なくとも、負のマテリアルとして消失する事がない、ということは事実だ。確かに可能性に過ぎないが、無下にできるものじゃない」
「だからと言って、その奇行を許して良いんですか!?」
「もちろん、許すことはできない。だが、人間である可能性が示唆された以上――我々の目的は、奴の“討伐”ではなく“確保”だ」
軍人として、そして人間として、ぐうの音も出ない正論を前にピーノは歯がゆそうに押し黙る。
そんな彼の様子を直視できず、フィオーレは思わず視線を手元に落とした。
「……とにかく、今は目撃情報の聞き込みに力を入れるしかない。我々は我々の成すべきことを忘れないよう」
締めくくるように口にして、アンナは資料を机の上にとさりと放る。
「――それでも」
「ん……?」
腹の底から絞り出すような、低く震える返事を耳にして、アンナは思わず顔を上げた。
「それでも……俺は奴を※したい」
強い意志を持って口にしたピーノのその言葉に、アンナは思わず眉間に皺を寄せる。
もとより人間として――彼女も彼の気持ちは痛いほどわかる。
それでも隊長として――彼女は彼の気持ちを肯定するわけにはいかない。
感情の板挟みに小さく頭を振ったアンナは、意を決したようにピーノへと向き直る。
しかし、彼への言葉を口にする前に、執務室の扉はけたたましい音と共に開け放たれた。
「で……伝令ッ! 狂気歪虚がヴァリオス市外に出現ッ! すぐさま出動されたしッ!」
「狂気……? リアルブルーのVOIDか?」
「い、いえ……その形状的な特徴が過去の報告書と一致! 昨年まで同盟近辺を騒がせていたものと、同一個体と思われますッ!」
その言葉に、3人の目の色が変わった。
咄嗟に傍らの武装を手に取り、出撃の身支度を整える。
なぜ今になって?
相次いでいる同盟内の歪虚騒動に関係してか、それとも――
軍服のジャケットに袖を通しながら、アンナの頭の中では目まぐるしく疑問が渦巻く。
そんなえも言われぬ不安を心中に抱きながらも、彼女はデスク脇に鎮座する巨大なアタッシュケースの取っ手を力強く握りしめた。
リプレイ本文
●
「なんかいっぱいいるのよ!?」
飛び掛かる黒鉛の犬をすれすれの所で躱しながら、リリア・ノヴィドール(ka3056)は流石にその表情に驚きを隠せない。
どれも一度は見た事のある敵――それでも、一度に相対するとなれば話は別だ。
彼女と共に戦場を駆けるシェリル・マイヤーズ(ka0509)。
仮面から覗く金色の視線の遠く先には、石畳のど真ん中で悠然と立ち尽くすキアーヴェの姿があった。
不意に2人の足元が大きく隆起し、咄嗟にそれぞれ左右に分かれる。
直後、巨大なワームが剣状に固めた触手を唸らせながら、地表を突き破って姿を現した。
「畜生、綺麗な街を穴だらけにしやがってよ……!」
舌打ち気味に吐き捨てたジャック・エルギン(ka1522)は、剣でガリガリと石畳を削る。
それは、決して刀身が重いせいではない。
地中に巣食うワームを、誘い出すためだ。
「なるほど……異形、奇怪、恐怖に狂気。人だからこそ……こんな異貌を生み出すことができるのかしら」
唸りをあげる狂犬達を前にして、アリア・セリウス(ka6424)の澄んだ声が凛と音を紡いだ。
その清らかな響きに触れた狂犬が液状の身体をぎゅっと収縮し強張らせると、吹き荒れる冷気の嵐が群れを纏めて飲み込む。
氷像となって砕け散った歪虚の残滓を遠巻きに、フワ ハヤテ(ka0004)は僅かに背筋を震わせる。
「ふうん、これも狂気の歪虚なのかい? いや面白いね、こうも形を変えるとは」
「多少骨は折れるが、こちらも成長している事を教えてやらねばな」
吹雪の範囲から外れた個体は、ロニ・カルディス(ka0551)が放った鎮魂の魔法によって一斉に身体を硬直させる。
その一瞬の隙を突いて、エスト隊が群れの中を駆け抜けた。
「こっちが終わったらすぐ行くから、それまで抑えてて!」
駆けていく背中にクリス・クロフォード(ka3628)が声を掛けると、アンナは略式の敬礼でそれに応える。
「同じ言葉を、こちらからも返させて貰う」
「それくらい言えれば十分ね!」
隊長であるアンナの掛け声で、各自ポジションへと散開するエスト隊。
人員は欠けながらも、彼女らも指を咥えてこれまでを過ごしてきたわけではない。
それはまた、クリスも同じこと。
「落とし前はつけるし……つけさせるわ」
いまだ前線に戻れない少年兵の姿が脳裏にちらつき、振り払うように頭を振る。
そして、大胆に足を鳴らしながら戦場を走り抜けた。
「以前は音に反応していたそうだが、なかなかどうして、食いつきが悪いようだねぇ」
僅かに引いた位置から戦況を見守る龍宮 アキノ(ka6831)は、逸る鼓動を抑えながら呟いた。
そして、再び姿を現したワームのひと飲みをアリアがひらりと回避したのを見て、答えは容易に至る。
――状況が違う。
以前はワームだけを意識し戦うだけでよかった。
だが今回は、他の戦闘音という“雑音”が戦場に蔓延している。
「クソッ、だが姿さえ表せばよ……!」
ジャックの鞭が、うねうねと動く触手を捉えた。
直後、ものすごい力がジャックの身体を引っ張り、彼はそれを両足の踏ん張りで堪える……が、そう長く続くわけでもない。
だからこそその前に、アキノの雷撃とクリスの光刃が、両サイドから分厚いワームの表皮を貫いた。
長大な身体が稲妻のように痙攣し、その身体を硬直させる。
「抜けるなら今のうちだよ」
どこか楽し気に口元を歪ませるアキノに促され、シェリルとリリアは示し合わせたように乱戦の渦を抜ける。
その先に待つ、狂怖の根源たる彼の下へ――
●
「本、読ませて……くれる?」
「ほう、君はいつかの」
真っ向から相対したシェリルに、キアーヴェは若干驚いたように眉を上げる。
だがすぐにいつもの張り付いたような笑みに戻ると、開かれた本のページからだらりと黒鉛が垂れた。
瞬時にシェリルが放った手裏剣を、キアーヴェはローブの裾を翻して受け流す。
その間に、地面に垂れた2つの液溜まりがボコリと犬の姿に変異し、一斉にシェリルへと飛び掛かった。
しかし、鋭い爪が引き裂いたのは、彼女の残した残光だけだった。
「“ワンちゃん”に襲われるっていうのは、あんまりいい気分じゃないのよ……」
入れ違いに飛び込んだリリアのチャクラムが、狂犬の鼻先をかすめる。
その一瞬の隙にシェリルは、キアーヴェの懐へと潜り込んでいた。
「私は……こっち」
逆手に抜き放たれた彼女の刃が、本を抱える隻腕を捉えた。
狙いは正確……いや、正確すぎた。
鈍い金属音が響くと、シェリルの刃は本から伸びた黒刃に弾かれる。
彼が飛び退くように距離を開けると、刃は液体に姿を変えて、びゅるりと本の隙間に吸い込まれていった。
「私は、私の中の狂気と――私の中の本質と、戦いたかった」
真正面に対峙して、シェリルは絞り出すように口にする。
「人は本質を偽る……なら狂気で偽っている、おじさんの本質は……願いは、何?」
その言葉に、僅かにキアーヴェの表情が歪む。
「――私自身、それを探しているのかもしれないな」
思わぬ答えに、シェリルは思わず目を丸くする。
目の前の男は、まるで分らない問題に突き当たった時のような、苦悶の笑みを浮かべていた。
「ひとまず、黒犬の生成は止んだようだね」
遠巻きにキアーヴェ方が開戦したのを目にしながら、フワの放った冷気の矢が狂犬の眉間を貫く。
内側からはじけ飛ぶようにして四散した黒い液体が、石畳にジュウジュウと溶け込んでいった。
「狂気と妄念に、私の想いと歌は濁らない――」
刃を薙ぎ、舞い踊るように歯牙を交わし、そして再びの剣閃が飛び掛かる狂犬の首をはねる。
はじめは僅かにぎこちなかったステップも、本調子へ戻りつつあった。
その傍らで、ロニの放つ光の波動が彼女の舞に華を添える。
瞬く間に数を減らしていく狂犬だったが、代わりに足元の石畳がぐらりと大きく揺れる。
「あまり派手に動きすぎるのも問題か」
自分を戒めるように口にして、揺れの中心点から離れるロニ。
その目と鼻の先を、巨大なワームが轟音と共に霞めていった。
「分かっちゃいたけど、相変わらず厄介な相手だこと……!」
ロニの背から飛び出したクリスが、軸足の踏み込みから鋭い弧を描いた蹴りを叩きこむ。
その一撃で敵がぐらりとゆらめいたかと思ったが、ワームはそのまま大きく頭を振って鞭のように身体をしならせた。
「どわ……っ!?」
まさに飛び掛かろうとしていたジャックの身体が木の葉のように吹き飛んで、遠くの店の壁に叩きつけられる。
鎧のおかげで衝撃こそ少ないものの、胃の中がひっくり返るような感覚が脳天まで一気に突き抜けた。
「いいねぇ。まるで絶叫マシンに乗っているかのような心境だよ」
しなりが収まったのを見計らい、再びアキノの雷撃がワームを穿つ。
感電で動きを止めた敵へ火炎を放ちながら、ジャックの飛んで行った方へと声を張り上げる。
「おーい、怪我はない……わけはないか!」
ヒビの入った壁からよろりと身を起こして、ジャックは血の混じった唾を吐き捨てた。
「喧嘩で初めて刃物を出された時も、こんな気分だったかね……!」
「減らず口を叩ける余裕があるなら、おおいに結構。このスリルから途中下車することほど、残念至極な事はありゃしないものだよ」
「へっ……同じ気分でそれだけ愉しんでやがると思うと、末恐ろしいなアンタ」
「ははっ、最高の誉め言葉だねぇ」
真っ赤に照らされたアキノの表情が、ニィと不敵な笑みを浮かべる。
その火の粉を掻きわけるようにして踏み込んだジャックの剣が、ワームの皮膚に深々と突き刺さった。
そのまま全身のマテリアルを、握りしめる手のひらを通して一挙に剣へと流し込む。
まるでその血を啜るかのように、刃が真っ赤な輝きを放った。
「喧嘩で相手にビビった時は……ただ本気の一発を、集中してぶち込みゃ良いってな!!」
そのまま渾身の力を込めて振り抜いた一撃は、ワームの身体を縦一文字に大きく引き裂いていた。
●
射杭機を構えるアンナの前で、巨人の身体が大きく揺らいだ。
その鼻先に脚をめり込ませた状態から器用に着地して、クリスは膝を突き出したまま視線だけ振り返る。
「お待たせ。怪我してないでしょうね?」
「クリス! そっちは片が付いたのか?」
それに答えるように放たれた2本の氷矢が、それぞれ巨人の足を貫いて結晶の柱を打ち立てた。
「御覧の通り。流石に年季の入った歪虚じゃ、今のボク達の敵ではなかったね」
柱に囚われ身動きが取れなくなった巨人を前に、フワの視線は流れるように戦場を見渡す。
「僕は、まだやれる……どいてくれ、フィオーレ!」
「ダメよ、そんな身体じゃ……!?」
額からおびただしい血を流しながらも戦意を露にするピーノと、それを支えるように寄り添うフィオーレ。
激しい殴打の痕や、もはや明後日の方向を向いている腕を見て、フワは呆れたようにため息をついて見せた。
「それじゃ無理だ。大人しく下がっていた方が良い」
「それでも……!」
なおも食い下がるピーノ。
しかし、それを諫めるようにして小さくも大きな背中が行く手を遮った。
「そこまでだ。後は俺たちに任せてくれないか」
立ちはだかったロニは、視線こそ巨人へ向けたままながら、その言葉はピーノへと強く投げかける。
「君にはまだやらなければならない事があるはずだ。それとも、ここで朽ちるのが君の使命なのか?」
「それは……」
強い戒めの言葉に、思わず口ごもるピーノ。
「ふむ。内臓も多少やられちゃいるようだが、今ならまだ命に関りはしないよ」
手早く触診したアキノの言葉を聞いて、フィオーレもアンナも思わず胸をなでおろす。
そして改めて向き直った巨人へと、人の手が持つ数多の刃が一斉に突き刺さるのだった。
「――ふむ。あと一息、だったのだがな」
シェリルの太刀を黒刃で何度となくいなしながら、キアーヴェは至極残念そうに呟いた。
その横っ面にチャクラムの閃きが迫り、多少驚いたように身を反らしてそれを躱す。
「ワンちゃんは全部倒したのよ。残りは……!」
マテリアル光と共に急接近したリリアの手が、彼の持つ本へとのびる。
が、キアーヴェはのけ反った勢いのまま地面に倒れ伏し、転がるようにして2人との距離を取った。
そして飛び起きざまに、バラバラと開いた別のページから緑炎の球を2人目掛けて放つ。
「まだちゃんとゴメンも有難うも言えていないのに……彼を狂気には侵させない」
炎を刀で切り払いながら口にしたシェリルのもとへ、持ち場を片付けたジャックとアリアが合流した。
1対4。
数の理は、完全にハンター達にある。
「なるほど……どうも私の仕立てた物語は、悪い方へと転がっていく」
「物語……? まさかあの脚本家も絡んでんじゃねーだろうな?」
その言葉を聞いて、キアーヴェは噴き出すように笑い転げた。
それがなんだか面白くなくて、ジャックの眉間に深い皺が寄る。
「なるほど。それもまた、私と彼との差だということか」
自虐するように頭を抱えると、キアーヴェはパタリと本を閉じる。
それがまるで物語が幕であるかのように、まさに倒れ伏そうとしていた巨人の身体が、吹き抜けた風と共に塵と化すのだった。
●
「これでいい加減に、年貢の納め時なのよ」
どかりと石畳の上に腰を下ろしたキアーヴェに、リリアは吐息交じりに言葉を漏らす。
彼の目の前には、閉じたままの本が無造作に投げ出されていた。
「貴方は人として悪夢のような惨劇を紡いだ……なら、人としてそれを終わらせるべきよ。断罪の法律の場で」
「人として……か」
アリアの言葉に、キアーヴェは含んだような笑みを浮かべる。
「“人”とは何を指す言葉なのだろうな。種か? 形か?」
「そう振る舞い、そう接すれば、それは人と呼べるのではないかしら」
「然り。ならば私も、胸を張って“人”と名乗って良いわけか」
そう口にして面々の顔をぐるりと見渡すと、彼は静かに瞳を閉じた。
「キアーヴェ・A・ヴェクター。大人しく、同行してもらおう」
彼の前にエスト隊の面々が集まり、一歩前に出たアンナが改めて言い放った。
返事がないのを肯定と受け取った彼女は、ピーノを支えるフィオーレに拘束用の縄の準備を命じる。
その時、用心を重ねるクリスだけは漠然とした違和感を覚えていた。
あまりにも呆気なさすぎる幕切れは、本当にこれで終わりなのか――という疑問を、彼女自身に投げかけていたのだ。
そしてそれは、不意に地面の穴から這い出た黒液を視界の端に捉えて、確信へと変わる。
「――危ないっ!!」
咄嗟に身体が動いて、クリスはフィオーレごとピーノの身体を突き飛ばす。
直後に飛び掛かった黒鉛の狂犬が、矢面に立った彼女の身体をどっぷりと飲み込んでいた。
「ああああぁぁぁぁぁぁぁっっっっ!!!」
熱を持った液体が身体に張り付き、肉が焼け、狂乱の叫びが戦場に響く。
まとわりつく狂気を払うかのように、彼女は身を振り乱す。
「ワームの穴から……!」
咄嗟にマシンアームを構えるアキノだったが、すぐに思い留まる。
攻撃したら、中のクリスもただでは済まないのだ。
「本だ! 本はどこにある!?」
「え……あっ!?」
フワの言葉に、シェリルはハッとして振り返る。
そこには、再び本を抱えて立ち上がるキアーヴェの姿があった。
「ご明察の通り、この本を屠れば彼女は助かるだろう」
「キアーヴェぇぇぇええええ!!!」
満面の笑みを湛える彼に、ジャックは抑えきれない怒りを露にする。
だが、彼が弾かれた感情のままに剣を振りかぶるのよりも疾く、赤い閃光が戦場を駆けていた。
「いざというの時の覚悟なら……はじめからしていたのよ」
ダガーの切っ先が、風を切って本へ迫る。
気持ちの良いほどの殺気と怒気を真っ向から肌に受けて、キアーヴェは避けるでも、抵抗するでもなく――ただ勝ち誇った笑みを浮かべて、本ごとその胸に刃を受けとめた。
刃先を伝わった命の雫が、真っ白な本のページに赤い染みを作っていく。
まるで命を吸い取っているかのように、じわり、じわりと、朱に染まっていったそれは、やがて持ち主ごと緑色の炎に包まれた。
リリアが咄嗟に刃を抜いて離れると、血の代わりにより激しい炎が周囲に吹き荒れる。
同時にクリスを包み込んでいた黒犬の姿が霧散し、崩れ落ちたその身体をアリアが抱きとめた。
「……少女よ」
「……え?」
不意に、彼の瞳がシェリルのそれを捉える。
「問いの答えは、いずれ明らかになる」
遺言のように口にして、キアーヴェは石畳の上へと崩れ落ちた。
断末魔もなく、その姿が本と共に骨の髄まで朽ち果てていくのを、ハンター達はただ見下ろしていることしかできなかった。
「なんかいっぱいいるのよ!?」
飛び掛かる黒鉛の犬をすれすれの所で躱しながら、リリア・ノヴィドール(ka3056)は流石にその表情に驚きを隠せない。
どれも一度は見た事のある敵――それでも、一度に相対するとなれば話は別だ。
彼女と共に戦場を駆けるシェリル・マイヤーズ(ka0509)。
仮面から覗く金色の視線の遠く先には、石畳のど真ん中で悠然と立ち尽くすキアーヴェの姿があった。
不意に2人の足元が大きく隆起し、咄嗟にそれぞれ左右に分かれる。
直後、巨大なワームが剣状に固めた触手を唸らせながら、地表を突き破って姿を現した。
「畜生、綺麗な街を穴だらけにしやがってよ……!」
舌打ち気味に吐き捨てたジャック・エルギン(ka1522)は、剣でガリガリと石畳を削る。
それは、決して刀身が重いせいではない。
地中に巣食うワームを、誘い出すためだ。
「なるほど……異形、奇怪、恐怖に狂気。人だからこそ……こんな異貌を生み出すことができるのかしら」
唸りをあげる狂犬達を前にして、アリア・セリウス(ka6424)の澄んだ声が凛と音を紡いだ。
その清らかな響きに触れた狂犬が液状の身体をぎゅっと収縮し強張らせると、吹き荒れる冷気の嵐が群れを纏めて飲み込む。
氷像となって砕け散った歪虚の残滓を遠巻きに、フワ ハヤテ(ka0004)は僅かに背筋を震わせる。
「ふうん、これも狂気の歪虚なのかい? いや面白いね、こうも形を変えるとは」
「多少骨は折れるが、こちらも成長している事を教えてやらねばな」
吹雪の範囲から外れた個体は、ロニ・カルディス(ka0551)が放った鎮魂の魔法によって一斉に身体を硬直させる。
その一瞬の隙を突いて、エスト隊が群れの中を駆け抜けた。
「こっちが終わったらすぐ行くから、それまで抑えてて!」
駆けていく背中にクリス・クロフォード(ka3628)が声を掛けると、アンナは略式の敬礼でそれに応える。
「同じ言葉を、こちらからも返させて貰う」
「それくらい言えれば十分ね!」
隊長であるアンナの掛け声で、各自ポジションへと散開するエスト隊。
人員は欠けながらも、彼女らも指を咥えてこれまでを過ごしてきたわけではない。
それはまた、クリスも同じこと。
「落とし前はつけるし……つけさせるわ」
いまだ前線に戻れない少年兵の姿が脳裏にちらつき、振り払うように頭を振る。
そして、大胆に足を鳴らしながら戦場を走り抜けた。
「以前は音に反応していたそうだが、なかなかどうして、食いつきが悪いようだねぇ」
僅かに引いた位置から戦況を見守る龍宮 アキノ(ka6831)は、逸る鼓動を抑えながら呟いた。
そして、再び姿を現したワームのひと飲みをアリアがひらりと回避したのを見て、答えは容易に至る。
――状況が違う。
以前はワームだけを意識し戦うだけでよかった。
だが今回は、他の戦闘音という“雑音”が戦場に蔓延している。
「クソッ、だが姿さえ表せばよ……!」
ジャックの鞭が、うねうねと動く触手を捉えた。
直後、ものすごい力がジャックの身体を引っ張り、彼はそれを両足の踏ん張りで堪える……が、そう長く続くわけでもない。
だからこそその前に、アキノの雷撃とクリスの光刃が、両サイドから分厚いワームの表皮を貫いた。
長大な身体が稲妻のように痙攣し、その身体を硬直させる。
「抜けるなら今のうちだよ」
どこか楽し気に口元を歪ませるアキノに促され、シェリルとリリアは示し合わせたように乱戦の渦を抜ける。
その先に待つ、狂怖の根源たる彼の下へ――
●
「本、読ませて……くれる?」
「ほう、君はいつかの」
真っ向から相対したシェリルに、キアーヴェは若干驚いたように眉を上げる。
だがすぐにいつもの張り付いたような笑みに戻ると、開かれた本のページからだらりと黒鉛が垂れた。
瞬時にシェリルが放った手裏剣を、キアーヴェはローブの裾を翻して受け流す。
その間に、地面に垂れた2つの液溜まりがボコリと犬の姿に変異し、一斉にシェリルへと飛び掛かった。
しかし、鋭い爪が引き裂いたのは、彼女の残した残光だけだった。
「“ワンちゃん”に襲われるっていうのは、あんまりいい気分じゃないのよ……」
入れ違いに飛び込んだリリアのチャクラムが、狂犬の鼻先をかすめる。
その一瞬の隙にシェリルは、キアーヴェの懐へと潜り込んでいた。
「私は……こっち」
逆手に抜き放たれた彼女の刃が、本を抱える隻腕を捉えた。
狙いは正確……いや、正確すぎた。
鈍い金属音が響くと、シェリルの刃は本から伸びた黒刃に弾かれる。
彼が飛び退くように距離を開けると、刃は液体に姿を変えて、びゅるりと本の隙間に吸い込まれていった。
「私は、私の中の狂気と――私の中の本質と、戦いたかった」
真正面に対峙して、シェリルは絞り出すように口にする。
「人は本質を偽る……なら狂気で偽っている、おじさんの本質は……願いは、何?」
その言葉に、僅かにキアーヴェの表情が歪む。
「――私自身、それを探しているのかもしれないな」
思わぬ答えに、シェリルは思わず目を丸くする。
目の前の男は、まるで分らない問題に突き当たった時のような、苦悶の笑みを浮かべていた。
「ひとまず、黒犬の生成は止んだようだね」
遠巻きにキアーヴェ方が開戦したのを目にしながら、フワの放った冷気の矢が狂犬の眉間を貫く。
内側からはじけ飛ぶようにして四散した黒い液体が、石畳にジュウジュウと溶け込んでいった。
「狂気と妄念に、私の想いと歌は濁らない――」
刃を薙ぎ、舞い踊るように歯牙を交わし、そして再びの剣閃が飛び掛かる狂犬の首をはねる。
はじめは僅かにぎこちなかったステップも、本調子へ戻りつつあった。
その傍らで、ロニの放つ光の波動が彼女の舞に華を添える。
瞬く間に数を減らしていく狂犬だったが、代わりに足元の石畳がぐらりと大きく揺れる。
「あまり派手に動きすぎるのも問題か」
自分を戒めるように口にして、揺れの中心点から離れるロニ。
その目と鼻の先を、巨大なワームが轟音と共に霞めていった。
「分かっちゃいたけど、相変わらず厄介な相手だこと……!」
ロニの背から飛び出したクリスが、軸足の踏み込みから鋭い弧を描いた蹴りを叩きこむ。
その一撃で敵がぐらりとゆらめいたかと思ったが、ワームはそのまま大きく頭を振って鞭のように身体をしならせた。
「どわ……っ!?」
まさに飛び掛かろうとしていたジャックの身体が木の葉のように吹き飛んで、遠くの店の壁に叩きつけられる。
鎧のおかげで衝撃こそ少ないものの、胃の中がひっくり返るような感覚が脳天まで一気に突き抜けた。
「いいねぇ。まるで絶叫マシンに乗っているかのような心境だよ」
しなりが収まったのを見計らい、再びアキノの雷撃がワームを穿つ。
感電で動きを止めた敵へ火炎を放ちながら、ジャックの飛んで行った方へと声を張り上げる。
「おーい、怪我はない……わけはないか!」
ヒビの入った壁からよろりと身を起こして、ジャックは血の混じった唾を吐き捨てた。
「喧嘩で初めて刃物を出された時も、こんな気分だったかね……!」
「減らず口を叩ける余裕があるなら、おおいに結構。このスリルから途中下車することほど、残念至極な事はありゃしないものだよ」
「へっ……同じ気分でそれだけ愉しんでやがると思うと、末恐ろしいなアンタ」
「ははっ、最高の誉め言葉だねぇ」
真っ赤に照らされたアキノの表情が、ニィと不敵な笑みを浮かべる。
その火の粉を掻きわけるようにして踏み込んだジャックの剣が、ワームの皮膚に深々と突き刺さった。
そのまま全身のマテリアルを、握りしめる手のひらを通して一挙に剣へと流し込む。
まるでその血を啜るかのように、刃が真っ赤な輝きを放った。
「喧嘩で相手にビビった時は……ただ本気の一発を、集中してぶち込みゃ良いってな!!」
そのまま渾身の力を込めて振り抜いた一撃は、ワームの身体を縦一文字に大きく引き裂いていた。
●
射杭機を構えるアンナの前で、巨人の身体が大きく揺らいだ。
その鼻先に脚をめり込ませた状態から器用に着地して、クリスは膝を突き出したまま視線だけ振り返る。
「お待たせ。怪我してないでしょうね?」
「クリス! そっちは片が付いたのか?」
それに答えるように放たれた2本の氷矢が、それぞれ巨人の足を貫いて結晶の柱を打ち立てた。
「御覧の通り。流石に年季の入った歪虚じゃ、今のボク達の敵ではなかったね」
柱に囚われ身動きが取れなくなった巨人を前に、フワの視線は流れるように戦場を見渡す。
「僕は、まだやれる……どいてくれ、フィオーレ!」
「ダメよ、そんな身体じゃ……!?」
額からおびただしい血を流しながらも戦意を露にするピーノと、それを支えるように寄り添うフィオーレ。
激しい殴打の痕や、もはや明後日の方向を向いている腕を見て、フワは呆れたようにため息をついて見せた。
「それじゃ無理だ。大人しく下がっていた方が良い」
「それでも……!」
なおも食い下がるピーノ。
しかし、それを諫めるようにして小さくも大きな背中が行く手を遮った。
「そこまでだ。後は俺たちに任せてくれないか」
立ちはだかったロニは、視線こそ巨人へ向けたままながら、その言葉はピーノへと強く投げかける。
「君にはまだやらなければならない事があるはずだ。それとも、ここで朽ちるのが君の使命なのか?」
「それは……」
強い戒めの言葉に、思わず口ごもるピーノ。
「ふむ。内臓も多少やられちゃいるようだが、今ならまだ命に関りはしないよ」
手早く触診したアキノの言葉を聞いて、フィオーレもアンナも思わず胸をなでおろす。
そして改めて向き直った巨人へと、人の手が持つ数多の刃が一斉に突き刺さるのだった。
「――ふむ。あと一息、だったのだがな」
シェリルの太刀を黒刃で何度となくいなしながら、キアーヴェは至極残念そうに呟いた。
その横っ面にチャクラムの閃きが迫り、多少驚いたように身を反らしてそれを躱す。
「ワンちゃんは全部倒したのよ。残りは……!」
マテリアル光と共に急接近したリリアの手が、彼の持つ本へとのびる。
が、キアーヴェはのけ反った勢いのまま地面に倒れ伏し、転がるようにして2人との距離を取った。
そして飛び起きざまに、バラバラと開いた別のページから緑炎の球を2人目掛けて放つ。
「まだちゃんとゴメンも有難うも言えていないのに……彼を狂気には侵させない」
炎を刀で切り払いながら口にしたシェリルのもとへ、持ち場を片付けたジャックとアリアが合流した。
1対4。
数の理は、完全にハンター達にある。
「なるほど……どうも私の仕立てた物語は、悪い方へと転がっていく」
「物語……? まさかあの脚本家も絡んでんじゃねーだろうな?」
その言葉を聞いて、キアーヴェは噴き出すように笑い転げた。
それがなんだか面白くなくて、ジャックの眉間に深い皺が寄る。
「なるほど。それもまた、私と彼との差だということか」
自虐するように頭を抱えると、キアーヴェはパタリと本を閉じる。
それがまるで物語が幕であるかのように、まさに倒れ伏そうとしていた巨人の身体が、吹き抜けた風と共に塵と化すのだった。
●
「これでいい加減に、年貢の納め時なのよ」
どかりと石畳の上に腰を下ろしたキアーヴェに、リリアは吐息交じりに言葉を漏らす。
彼の目の前には、閉じたままの本が無造作に投げ出されていた。
「貴方は人として悪夢のような惨劇を紡いだ……なら、人としてそれを終わらせるべきよ。断罪の法律の場で」
「人として……か」
アリアの言葉に、キアーヴェは含んだような笑みを浮かべる。
「“人”とは何を指す言葉なのだろうな。種か? 形か?」
「そう振る舞い、そう接すれば、それは人と呼べるのではないかしら」
「然り。ならば私も、胸を張って“人”と名乗って良いわけか」
そう口にして面々の顔をぐるりと見渡すと、彼は静かに瞳を閉じた。
「キアーヴェ・A・ヴェクター。大人しく、同行してもらおう」
彼の前にエスト隊の面々が集まり、一歩前に出たアンナが改めて言い放った。
返事がないのを肯定と受け取った彼女は、ピーノを支えるフィオーレに拘束用の縄の準備を命じる。
その時、用心を重ねるクリスだけは漠然とした違和感を覚えていた。
あまりにも呆気なさすぎる幕切れは、本当にこれで終わりなのか――という疑問を、彼女自身に投げかけていたのだ。
そしてそれは、不意に地面の穴から這い出た黒液を視界の端に捉えて、確信へと変わる。
「――危ないっ!!」
咄嗟に身体が動いて、クリスはフィオーレごとピーノの身体を突き飛ばす。
直後に飛び掛かった黒鉛の狂犬が、矢面に立った彼女の身体をどっぷりと飲み込んでいた。
「ああああぁぁぁぁぁぁぁっっっっ!!!」
熱を持った液体が身体に張り付き、肉が焼け、狂乱の叫びが戦場に響く。
まとわりつく狂気を払うかのように、彼女は身を振り乱す。
「ワームの穴から……!」
咄嗟にマシンアームを構えるアキノだったが、すぐに思い留まる。
攻撃したら、中のクリスもただでは済まないのだ。
「本だ! 本はどこにある!?」
「え……あっ!?」
フワの言葉に、シェリルはハッとして振り返る。
そこには、再び本を抱えて立ち上がるキアーヴェの姿があった。
「ご明察の通り、この本を屠れば彼女は助かるだろう」
「キアーヴェぇぇぇええええ!!!」
満面の笑みを湛える彼に、ジャックは抑えきれない怒りを露にする。
だが、彼が弾かれた感情のままに剣を振りかぶるのよりも疾く、赤い閃光が戦場を駆けていた。
「いざというの時の覚悟なら……はじめからしていたのよ」
ダガーの切っ先が、風を切って本へ迫る。
気持ちの良いほどの殺気と怒気を真っ向から肌に受けて、キアーヴェは避けるでも、抵抗するでもなく――ただ勝ち誇った笑みを浮かべて、本ごとその胸に刃を受けとめた。
刃先を伝わった命の雫が、真っ白な本のページに赤い染みを作っていく。
まるで命を吸い取っているかのように、じわり、じわりと、朱に染まっていったそれは、やがて持ち主ごと緑色の炎に包まれた。
リリアが咄嗟に刃を抜いて離れると、血の代わりにより激しい炎が周囲に吹き荒れる。
同時にクリスを包み込んでいた黒犬の姿が霧散し、崩れ落ちたその身体をアリアが抱きとめた。
「……少女よ」
「……え?」
不意に、彼の瞳がシェリルのそれを捉える。
「問いの答えは、いずれ明らかになる」
遺言のように口にして、キアーヴェは石畳の上へと崩れ落ちた。
断末魔もなく、その姿が本と共に骨の髄まで朽ち果てていくのを、ハンター達はただ見下ろしていることしかできなかった。
依頼結果
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2017/10/17 22:09:56 |
|
 |
相談卓 シェリル・マイヤーズ(ka0509) 人間(リアルブルー)|14才|女性|疾影士(ストライダー) |
最終発言 2017/10/20 00:55:43 |
|
















