ゲスト
(ka0000)
【不動】これまでの経緯
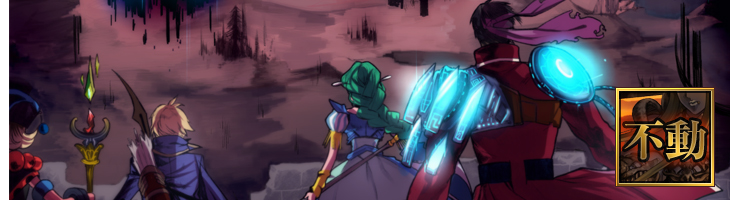

【不動】ストーリーノベル
●プロローグ(1月28日更新)


ヤクシー
しかし、今回の実験が大きな問題を引き起こす事となる。
災厄の十三魔の一人、クラーレ・クラーラの手により引き起こされたCAM強奪事件。
何機かのCAMが歪虚側の手に渡ってしまったものの、ハンターに尽力により奪い返す事ができた。
人類の多くが胸を撫で下ろしたが、問題はここで終わらない。
マギア砦南にて人類が対歪虚兵器の開発を行っていた事が歪虚に露見。辺境地域で侵攻を続ける怠惰側がついに重い腰を上げた。
「小さい連中がこそこそと……。面倒だから、一気に叩いちまいな!」
怠惰侵攻軍を指揮するのは、ヤクシー。辺境周辺で活動する十三魔の支援を受けて
南下を開始する。
その数は1000、一度の侵攻において動いた怠惰の軍は過去最大級である。
CAM実験場を目的地として侵攻する怠惰に対して、人類はケリド川の支流であるナナミ川にて防衛線を構築。
怠惰の軍を押し止めようとするが、防衛線構築の前に怠惰はCAM実験場へ到達してしまう。
そうなれば各国が力を結集した実験が水泡に帰するだろう。
この状況に対して、辺境部族会議側からある提案が行われる。
『敵の目をマギア砦へ引き付け、防衛線構築までの時間を稼ぐ』
だが、この作戦はマギア砦へ籠城する者達を『犠牲』にもしうる作戦であった。
(執筆:近藤豊)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●オープニング(1月29日更新)

グラズヘイム王国

ヴィオラ・フルブライト

ヘクス・シャルシェレット
●
灰色の厚い雲が、実験場を覆っていた。色濃い影が落ちる中、岩肌を風が撫で、土煙が上がる。ヴィオラ・フルブライト(kz0007)はその光景を眺めながら、呟いた。
「――嫌な空気ですね」
「そうか?」
傍ら、木製の作業台に向かっていたアダム・マンスフィールドがそちらに目を向けずに応じる。
「ええ」
互いに、話題が豊富な方ではない。だから、ヴィオラの言葉は短かった。男の寡黙さと集中を尊重するように。
「……」
緩やかな静寂の中、一人黙考するのは――【CAM奪還ゲーム】のことだ。
CAMを奪われた人類にとっては業腹な事に、歪虚にすれば余興に過ぎなかったものが各国に深い爪痕を刻んでいる。
しかして。ヴィオラの懸念は、他にあった。
ヘクス・シャルシェレット(kz0015)は、王国からヴィオラと王国騎士団副団長のダンテ・バルカザールに声をかけた。刻令術の唯一の使い手であるアダムを護るために。
その上で、ヴィオラはこう思うのだ。
――何故、と。
その胸中を埋めるのは、かつての光景だった。この地とは風景も、その音も、香りも、何もかもが違う。それでも、ヴィオラの胸の裡で戦士の勘が叫んでいる。
つと。馬の嘶きが彼方から響いた。早馬だ。
ヴィオラは目を閉じる。これから伝えられるのは恐らく、吉報ではないだろう。
だが。
「せめて、歪虚であってほしい、ですね」
女はそう言って西方を見た。曇天の先に、彼の地を見るように。
●

ファリフ・スコール
曰く。辺境の要衝、マギア砦に歪虚が侵攻しているのだ、という。
この地で大規模な行動が出来る勢力として真っ先に想定されるのが『怠惰』――巨兵の軍勢。
「と、言うわけで、な」
馬上のダンテは、心底嬉しげに歯を剥いて笑う。
「行こうぜ。戦場だ」
「……私達は、アダムの護衛に来たはずですが」
「あァ? アダムを護る。その為に戦場に行く。素晴らしくロンリテキじゃねェか」
「……」
ヴィオラの呆れ顔にダンテも怪訝げな顔をして言うものだから、ヴィオラの落胆ぶりは凄まじかった。
「そ、の……ボクも、君たちがアダムを護りに来たのは、知ってるよ。でも……」
ファリフの気遣わしげな声に、ヴィオラは首を振る。
「気にしないでください。虚無を祓うのは私達の使命です」
ヴィオラの言葉に、ダンテは親指を突き上げてファリフの背を叩いた。
「な? ヴィオラならこう言うって言ったろ?」
「う、うん」
ファリフが気後れしている理由に、ダンテは気づかない。絶対零度の視線を無視して、ダンテは続ける。
「お前はアダムの手助けをしてくれた。アダムは王国の代表。つまり――王国はお前に借りがある、ってことだ」
「……その節はどうも」
「カカッ」
アダムの声を背に、ダンテは一つ笑うと、腰に下げた長剣を掲げる。
――騎士の誓いだ。
「この戦争、俺達にも背負わせろよ」
このロクでもない誓いに盛大に溜息をついたのが誰かは、言うまでもないだろう。
だが。
「……ありがとう」
深い吐息を払うように、ファリフは笑った。遠慮混じりの笑みではあったが、確かに。剣を鞘に収めると、ダンテは一つ高笑いをすると、こう結んだ。
「幸い、滅茶苦茶に攻められた直後だしな。防戦なら任せとけ」
「それは……笑えないかな……」
「……確かに、事実ではありますけどね」

イコニア・カーナボン
「貴女達の力になりましょう。私以外にも、戦士団の司祭がこの地に来ていますから……と」
「どうかしたの?」
言葉を切って懸念するヴィオラに、ファリフが問う、と。
「いえ……一人、無茶をしそうな子を思い出しまして」
――イコニア・カーナボン(kz0040)。
エクラ教の司祭であり、聖導士の少女。
そういえば彼女は最前線を熱望していたのだ、と。
(執筆:ムジカ・トラス)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)

ゾンネンシュトラール帝国

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
●最前線
「マギア砦を視認! これより高度を落とし減速! 降下態勢に移ります!」辺境の空を大翼が羽撃く。連なるようにして飛ぶグリフォンの一団は、その逞しい足で揺り籠を支えている。
二騎のグリフォンを左右につけた長方形の籠には数人の人間が搭乗している。長いようで短かった空の旅も終わりを迎えようとしていた。
「降下作戦は初めてか? 何、臆する事はない。きちんとグリフォンが送り届けてくれるさ」
籠に取り付けられた無数のワイヤーが解かれ地上へ垂らされる。黄金の鎧に身を包んだ女は優しい声で呟き、取っ手に手をかけた。
マギア砦の城壁の内側、開けたスペースを目指してグリフォンは降りていく。徐々にその速度を落としながら、しかし止まる事はなく。
「各員、降下準備! カウント開始!」
女の声で帝国兵に混じり、ハンター達もワイヤーへ手を伸ばし立ち上がる。
「5……4……3……2……1…………降下!」
合図と同時、一際大きく羽ばたいたグリフォンが空中で一瞬停止する。同時に地上へ垂らされたワイヤーを伝い、戦士達はマギア砦へと降り立った。
パラシュートもへったくれもあったものではない。無茶な降下だが、全ての戦士が無事に着地に成功する。女は赤いマントをはためかせ、大地を軽く滑りながら空を仰いだ。
「うむ。降下漏れはなさそうだな。怪我人もいないようで何より」
騒ぎを聞きつけたマギア砦の兵士達が集まる中、女は重苦しい兜に手をかけ、ゆっくりと真紅の髪を解き放った。
「――ゾンネンシュトラール帝国軍、“騎士皇”ヴィルヘルミナ・ウランゲル。同盟軍に先行し推参した。状況の説明を願う」
マギア砦へと誘導された大量の歪虚の軍勢。その緊急事態に帝国が投入した戦力こそ、皇帝であり最高戦力でもあるヴィルヘルミナであった。
同盟海軍に先行し甲板より離陸したグリフォン隊はハンターを含む戦力を降下させ、次のピストン輸送の為に引き返していく。 直に各国の軍も駆けつけるだろうが、事は急を要する。大軍を用意する時間がないというのなら、結局は少数精鋭で対処するしかない。
「だからって自分が来なくてもいいだろうにな。あれ、一番偉い奴なんだろ? ヴィ……ヴィルナ……ヴィルなんとかってのはよ」
眉間を揉みながら呟いたのは帝国軍第二師団長のシュターク・シュタークスンだ。
第二師団は先の歪虚CAMとの戦いでも辺境に派遣された、帝国領北の守りと辺境への対処に特化した戦闘部隊である。
その精鋭が前線に送り込まれるのは道理だろうが、そこに皇帝が混ざっているというのは如何な物なのだろうか。
「ま、ケチつける気はねぇさ。なにせ一番偉いんだからな」
皇帝はこんな状況でも恐怖を感じさせない。ただ冷静に、凛々しく指示を出している。
「せいぜい死なないよう、お互い気をつけようや」
シュタークの強すぎる力で肩を叩かれたハンターがよろける。彼女も恐怖を感じていないのか……それどころか状況を楽しんでいるようにさえ見える。
あの国の責任者達はどこかおかしい。これを頼もしいと感じるべきなのかどうか……ハンターは小さく溜息を零した。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)

自由都市同盟
●再び同盟から辺境へ
辺境へのCAM運搬に始まり、実験場の防衛をも担ったモデスト・サンテ海軍少将。ようやく彼は、ポルトワールの軍港へと戻った。しかし、そうゆっくりもしてられない。CAM実験場は幾度となく、歪虚の危険に晒されている。十分な食糧と追加の人員を率い、また辺境へと取って返さねばならないのだ。
そう考えると、自然と早足になる。出迎えた部下も素早く敬礼し、同行する船団の構成などを伝えた。 「よし、それで構わん。辺境から帰った兵を半分入れ替えるから、任務の引継をしっかりとさせろ」
「わかりました。食糧を積んだ輸送船ですが、一部はヴァリオスからの合流となります」
モデストは「またヴァリオス経由か」と呟きつつ、歩きながら書類にサインしていく。
「出発は明日だ。荷物と人員の用意を怠るな」
そう指示を出し、駐屯所の中へ入ろうとした時だ。情報士官が息を切らせて飛び出してくる。そしてモデストを見るや、「た、大変です!」と大声を張り上げた。
「お前もわかっとるだろうが、もう十分に大変なんだ。この上、何があった?」
士官はズレた眼鏡の位置を直し、敬礼しながら叫ぶ。
「辺境のマギア砦周辺で不穏な動きがあるとの報告がありました! 敵は怠惰の軍と推定されます!」
「なんだとーーーーー!!」
モデストは慌てて執務室へと駆け上がり、ヴァリオスにいるブルーノ・ジェンマ元帥に連絡を入れた。
「ブルーノ! マギア砦で異変があったと聞いた! 詳細はどうなっている?!」
『現段階ではCAM実験場の指揮権を預かる、陸軍のダニエル・コレッティ中佐から救援要請があったのみだ。詳細は随時届けられるだろう』
マギア砦はCAM実験場の北に位置するため、展開によってはどちらも攻め落とされる危険があるのだ。
とはいえ、情報を待って悠長に準備する余裕もないだろう。今から全速力で飛ばして戻れるかどうか……まさに時間との勝負になる。
「ううむ……仕方あるまい。ポルトワールからは準備できた分だけ持って、今すぐ出る。部下に不足分を計算させるんで、ヴァリオス寄港の際に船団を合流させてほしいんだが、そっちは大丈夫か?」
『大丈夫だ、手配しよう。輸送船だけでなく、追加人員と戦艦も準備する』
ブルーノの返事を聞き、モデストは胸を撫で下ろした。
『あと、もうひとつ。ポルトワールの指揮官が留守とわかれば、海賊どもが黙っているまい。そこで手を打っておいた』
その言葉に首を傾げるモデストだが、それと同時に隣の応接室から豪快な笑いが聞こえてきた。
「はっはっは! ワシが臨時の指揮官、イザイア・バッシだ!」
装飾の施された扉を開かれると、黒の制服に身を包んだ老人が杖をついて登場。モデストを大いに驚かせる。
「ご、御老体が指揮官だと! ブ、ブルーノ、お前は誰に何を頼んだのかわかってるのか?!」
『別に俺からは頼んでない。ご自分で志願されたのだ……ポルトワールの留守は任せろとな』
イザイア・バッシ……現在は同盟軍の名誉大将だが、以前は元帥として活躍した男だ。ブルーノもモデストも、元は彼の部下にあたる。
数年前に右脚の負傷し、それが原因で退役。ブルーノに元帥の座を譲ったものの、まったく第一線を退く気がなく、現在は陸軍のてこ入れに尽力している。なお、特機隊設立の立役者のひとりにも数えられる。老いてますます盛んとは、まさに彼を象徴する言葉といえよう。
「ほら、さっさと救援に行かんか、ベアー! ここは任せろ!」
「わかってます! ブルーノ、打ち合わせの続きは白熊号からの通信で頼む!」
モデストは自分の椅子にどっかりと座り込んだ師の姿を見て安堵を覚えながらも、遠き地の異変に心を乱していた。
(執筆:村井朋晴)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)

辺境領域

ヨアキム

ヴェルナー・ブロスフェルト
●
「……って、なんでワシが木材を運んでいるだ!?」ドワーフ王ヨアキム(kz0011)の中では怠惰へ突撃して大暴れする予定だった。
しかし、現実は帝国兵の指示を受けてナナミ川流域で木材をせっせと運んでいるのだ。
――おかしい!
さすがにヨアキムの頭でもその事は理解できたようだ。
「うぉぉぉ! 怠惰は何処だ! ワシが相手してやる!
隠れてないでワシの前に出てきやがれ!」
「無駄口は、いけませんねぇ」
丸太を担いで大騒ぎする背後から、ヴェルナー・ブロスフェルト(kz0032)が苦言を呈する。
ヴェルナーを目にしたヨアキムは、早々に怒鳴り込む。
「おい! ワシはこんなところで木材を運んでいる場合じゃねぇ! 早く戦いに行かねぇと!」
「耳元で大きな声を出さなくても聞こえますよ。
私は、ヨアキムさんにナナミ川で防衛線の構築をお願いしています」
「だから、そんな事するよりも……」
「聞き捨てなりませんね。防衛線構築を『そんな事』と仰るとは。
マギア砦へ向かった方々は、この防衛線構築の時間を稼ぐ為に命を賭けているのです。ヨアキムさんが早期に防衛線を構築できれば、彼らが帰還できる確率は一気に向上します」
ヴェルナーは、ヨアキムにも分かるよう敢えてゆっくりとした口調で語りかける。
その口調の裏に、怒りという感情を忍ばせながら。
「あなたの知り合いが、あの砦で亡くなるのは嫌でしょう?」
「…………ああ、分かった。さっさと防衛線ってぇ奴を作ってやる。それから怠惰の奴をぶっ飛ばせばいいんだろう?」
「ええ、その意気です」
ヨアキムは再び丸太を担ぎ、指定の場所へ運び始めた。
おそらくマギア砦籠城で稼げる時間は、48時間。
それ以降はマギア砦へ籠城する者達が帰還できなくなる恐れがある。
「ヴェルナー様!」
ヨアキムと入れ替わる形で部下が駆け込んできた。
「なんでしょう?」
「斥候より連絡。西方の上空からマギア砦方向へ飛来した者がいます」
「飛来した者? ……報告は明確に、かつ端的にお願いします」
ヴェルナーの一言に、部下は一呼吸を置いてから答える。
「飛来した者は災厄の十三魔の一人『ガルドブルム』と思われます。
現在、マギア砦上空付近を飛び回っている模様です」
(執筆:近藤豊)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●魔導型CAM実験(2月12日更新)

ナサニエル・カロッサ

クリストファー・マーティン
冒険都市リゼリオの会議室を貸し切って行われたワルプルギス錬魔院とサルヴァトーレ・ロッソのCAM運用開発会議。その席は思いの外ゆるい空気で進行していた。
ナサニエル・カロッサ(kz0028)が机にポンを置いた書類の束に手を伸ばすクリストファー・マーティン(kz0019)。そこには新たな姿に生まれ変わったCAMの設計図が記されている。
「この、新たに追加された球体状の装置が魔導エンジンという物ですか?」
「ええ、そうですよぉ」
「動力炉をこうも機体の外側に押し出す形は斬新ですね」
「あえて壊しやすいようにできてるんですけどねぇ。説明要りますかぁ?」
コクコクと頷くクリストファー。ナサニエルはコホンと咳払いを一つ。
「先日のCAM起動実験において、こちらの世界の機導術、即ち魔導エンジンを用いてCAMを動かす事そのものは可能という結論が出ました」
「ええ。尤も、実験は途中であんな事になってしまいましたが」
「あんな事になっちゃった話は後でするので置いといて……まず、現状の問題点を少しおさらいしてみましょうかぁ」
まず、CAMはリアルブルー由来の化石燃料を動力として稼働する兵器だ。その化石燃料がクリムゾンウェストに存在しない、即ち動力源が有限であるというのが最大にして唯一の問題点であった。
CAMがこの異世界に置いても絶大な戦果を発揮するという事は、これまでに僅か数回の対歪虚戦において、そして先の嫉妬の歪虚による暴走で誰の目にも明らかな物となっている。
動かす事さえ出来れば歪虚に対する強力な切り札になる。だからこそ燃料問題を解決する為、帝国と協力し新たなエンジンの開発を進めてきたのだ。
「こちらの世界に、そちらの世界の燃料は存在しない。だからこちらの世界固有の燃料にて代替しようという話でしたが、そこまで簡単な話ではありませんでした」
CAMの主機であるマテリアルエンジンは未知の技術で作られたブラックボックスだ。実際にそれらを異世界で運用していた者達でさえ、その原理は解明出来ていない。
「これを作った人物は間違いなく天才だと思いますよぉ。この私が見てもわけわからないってかなりぶっとんだ変態ですねぇ♪」
「天才なのか変態なのかはさておき、結局ナサニエルさんにもマテリアルエンジンを詳らかには出来なかったんですね?」
「はい。なのでこいつをそっくりそのまま積み替えるのは現状は無理です。そのうちなんとかするのでとりあえず我慢して下さい」
「我慢しましょう。それで、ならばどのようにCAMを動かすんですか?」
「マテリアルエンジンを化石燃料で動かす事は変わりません。そこへ更に外付けの稼働炉を追加します」
それがこの設計図に描かれた、CAMの腕や足、背中に装備された球体状の物体の正体だ。
「化石燃料で主機を回すのは変わりません。それを外付けの動力で補佐し、燃費を大幅に向上させます」
「……成程。つまりリアルブルーとクリムゾンウェストのハイブリッドマシンという事ですね」
CAMの四肢に装備された魔導エンジンは装着部位にエネルギーを供給する。
CAMの主機そのものは全力回転させず、言わばスリープモードのような状態で操縦系のみを動かし、物理的に手足を駆動させるエネルギーは外付けの動力に頼る事で、これまでの何倍も化石燃料の消費を抑える事が可能になるわけだ。
魔導エンジンだけでCAMを動かすには出力が足りない。化石燃料のマテリアルエンジンで動かすには燃料を消費しすぎる。その両方の欠点を折衷案で補おうというのだ。

デュミナス
「ええ。あんな事になってしまった話ですね。実に痛ましい事です」
「嫉妬の歪虚に操られたCAMですが、別にCAMを構成する物質が大幅に変容したわけではなかったようです。実際に撃破された歪虚CAMの残骸を回収した際の調査で、CAMは文字通り操られていただけだと判明しています」
嫉妬の歪虚、クラーレ・クラーラの能力により操られた歪虚CAMは限界を超えて駆動。その破壊力をいかんなく発揮し人類の敵として暴れ回った。
しかし、CAMそのものが歪虚になったわけではないのだ。あれはただ、操られただけ。時間をかけて歪虚に汚染されればどうなるかはわからないが、少なくとも短期間で歪虚そのものになったわけではない。
「なのでまた操られた場合、即座にぶっ壊せるようにしてあります」
「え? CAMを……ですか?」
「手足に搭載された魔導エンジンを自爆させれば、当たり前ですが手足が吹っ飛びますよねぇ。大事なマテリアルエンジンやパイロットは胴体部分にあるわけですし」
「……手足を失えば操られようとCAMは動けなくなる……成程。あまり考えたくはない事ですが、いざという時に最優先である重要機構と人命だけでも確保出来るのなら悪い案ではありませんか」
「手足だけならこっちの技術や素材でも修理出来そうですしねぇ、ウッフ♪」
「しかしその、魔導エンジンが爆発した場合、周囲のマテリアル環境を汚染してしまうのでは?」
口元に手をやりつつ書類から顔をあげるクリストファー。ナサニエルはしばらく無表情に黙り込んだ後。
「というわけで、安全性の確保と動力問題の解決の為に考えられた実に効率的な設計案なのですねぇ」
「なぜ今沈黙したのかはあえて触れませんが、そういうリスクが存在しているというのは把握しておきましょう」
二人はニコニコしながら向かい合う。一見和やかだが、周囲の関係者達は真綿で首を絞められるような奇妙な緊張感を覚えていた。

「安全保障はどうなっていますか?」
「今辺境で実験をするよりは少なくとも安全でしょうね。カールスラーエにせよノアーラ・クンタウにせよ、対歪虚用の要塞ですから。辺境領からは二枚壁に隔たれています。帝国領内でしたら、帝国軍の各方面師団が有事に対応出来ます。帝国の強みは軍事くらいですからねぇ。無論、地球軍やハンターの皆さんにも警備をお願いする予定ですよ」
「ハンターや各国に対しても情報を開示するのですか? 失礼ですがその場合、またどこかから歪虚へ情報が漏れる可能性もあると思いますが」
「だけど、帝国でコッソリ作って完成させましたとなると納得しない人も大勢いるんですよぉ。それで帝国軍とサルヴァトーレ・ロッソが癒着しているとかヤジを飛ばされたら、そちらとしても厄介でしょう?」
そうでなくてもサルヴァトーレ・ロッソは中立の立場でなければならない。今回は機導兵器に特化した錬魔院と手を組んだが、それも各国の承認を経て、致し方なくといった具合だ。
情報はこの世界の人間に開示していく義務があるし、それが余計な争いを避ける事に繋がるだろう。情報漏洩に関して懸念は残るが、人類同士の戦争の引き金になるよりはマシかもしれない。
「……わかりました。監視も兼ね、こちらからも兵力を派遣させて貰いましょう」
「どちらにせよ、嫉妬の歪虚という存在がCAMにとってのカウンターとなる事が証明された現在、何をするにも完全な安全はありません。これから先CAMという切り札を敵の前に晒していく予定があるのなら、尚の事です」

クラーレ・クラーラ
「逆に言うと十三魔をこぞって陽動に使わないと操れなかったと考えるべきです。実験中に十三魔が出てきたらCAMはカールスラーエの地下に隠してしまいましょう」
「物理的に距離を縮める事が操る条件に含まれている可能性が高いと言われていますからね。クラーレ・クラーラは直接CAM倉庫に近づいたとか」
「であれば、今後もCAM単体で運用するようなものではなく、CAMに歩兵をつけ様々なケースに想定できるような運用陣形を考慮する必要があるでしょうねぇ。あ、ついでに基本的には物理的に隠してしまえばどうにもされないというのなら、要塞作って地下ハンガーに隠せばいいかと」
二人は笑顔で淡々と話を進めて行く。それこそ付け入るような隙はなく、関係者各位は事の成り行きを固唾を呑んで見守るしかない。
「では、そんな感じでよろしくお願いしますねぇ♪」
「承知しました。こちらも上に話を通しておきましょう。お互いにとって良い結果になる事を祈ります」
爽やかに笑いかけるクリストファーの手をナサニエルが取ると、途切れた緊張にあちこちからどっと溜息が響くのであった。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●マギア砦籠城戦 エピローグ(2月18日更新)

ヴィオラ・フルブライト

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
その一報を聞いた人々は、奇妙な感覚に襲われた。
マギア砦へ籠城して時間を稼ぎ、その時間をもってナナミ川に防衛線を構築する。
作戦そのものは、見事に達成された。
――だが。
「手放しで喜ぶ気には……なれないものです」
ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は、マギア砦がある方角を見つめていた。
無事、防衛線は構築できたものの、人類側の被害も無視できなかった。
部族会議は拠点であったマギア砦を放棄。救援に駆け付けたハンターの多くが負傷、中には重傷の者も見受けられる。
そして、人類を支えるために命を散らした各国の戦士達。
人類の希望を守る為ではあったが、支払われた代償は決して少なくはなかった。
「悲嘆するばかりでないぞ。敵の指揮官に少なからず傷を負わすことができたからな」
帝国皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、自信をもって答えた。
マギア砦籠城において、多数の有力歪虚の姿があった。
怠惰指揮官ヤクシー。
災厄の十三魔の一人ガエル・ソト。
皇帝は、彼らに奇襲を仕掛けて一定のダメージを与える事に成功した。この成功は、防衛線構築までの時間を大きく稼ぐ事に繋がった。
「ですが、被害が一番甚大だったのも奇襲作戦に関係した方々でした」
ヴィオラは、寂しそうに呟いた。
少数精鋭で敵の本陣へ奇襲を仕掛けたのだ。
リスクは相応に大きい。 事実、ハンターを含む重傷が多かったのも奇襲作戦に関わった者達だった。
「嘆いても仕方あるまい。今は作戦の成功を祝いつつ、敵の動きに注視するしかないだろう」
「そうだよね……今は、防衛線が構築できた事だけでも良しとしないとな」

篠原神薙

ラキ
命を散らした者が居たからこそ、あの防衛線が完成したのだ。
彼らが居なければ、籠城は失敗していたかもしれない。
――しかし、ここでラキ(kz0002)が一つの懸念を投げかける。
「……でも、本当にあの防衛線で怠惰は諦めたのかな?」
ラキの一言。
それは誰しもが思い浮かべていたが、口に出せずにいた事だ。
怠惰はサイクロプスやトロルなどの巨人が主力だ。平均的な深さが三メートル程度のナナミ川を渡るだけなら苦にならない。そんな彼らに突貫で築いた防衛線で本当に足止め出来ているのだろうか。
「たぶん……視覚的な効果だけでしょう」
ヴィオラは、十分に間を置いてから語り始める。
怠惰は防衛線が築かれている事を目にして『ナナミ川を渡るだけなら良いが、あの防衛線を潰すのが面倒』と考えたに過ぎない。 ヤクシーが命令すれば、急拵えの防衛線だけで侵攻を食い止める事は不可能だ。
「そんな……じゃあ、一体何のためマギア砦で……。
ねぇ、教えて! あの戦いは何だったの? 倒れた人達になんて言えばいいの?」
ラキは顔を曇らせて周囲の者へ問い掛けた。
意味がなかった。
そんな事は、認めたくない。
あの激戦の価値は何かあるはずだ。
そうでなければ、あの戦いで傷付いた人達に顔向けできない。
ラキは、訴えかけた。
明確な答えがない事を理解しながら。
「神薙、教えて! どうすればいいの……」
「俺にも分からない。でも、意味はあったと思う。少なくとも、怠惰の侵攻再開に備える時間はできたのだから」
ラキの肩に手を置き、神薙は見つめる。
胸から押し出された言葉でラキが納得するかは分からない。しかし、神薙が今教えられる答えはこれしかない。
「この時間が、あの戦いの価値……」
「そうだ。彼らの犠牲があったからこそ、この貴重な時間が生まれたのだ。無価値ではない」
ラキの言葉に続いて、皇帝は力強く断言した。
倒れた戦士が生み出したのは防衛線だけじゃない。
今こうしている間も、倒れた戦士の犠牲で成り立っている。なら、生き残った者は、この時間を有効に使う義務がある。 「考えなければなりません。怠惰を完全に食い止める手立てを……いえ、今回の籠城戦を立案した者が本物ならば、既に動き始めているかもしれません」
ヴィオラの言葉は、風に乗って舞い上がる。
間もなく始まる次の戦いを――皆に知らせる為に。
(執筆:近藤豊)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●ナナミ河撃滅戦(2月19日更新)

ファリフ・スコール

バタルトゥ・オイマト
スコール族のファリフ・スコール(kz0009)は、ナナミ川の防衛線を見つめていた。
「あれが、防衛線。ボク達が戦っている間に作った壁か」
ファリフは、防衛線を見つめていた。
マギア砦に籠城し、怠惰と死闘を繰り広げて生み出した時間。
その貴重な時間を使って構築された防衛線は、怠惰の軍をマギア砦に押し止める事に成功していた。
比較的広い川幅を持つナナミ川。
その先にある防衛線。
突如現れた存在が放つインパクトは、怠惰を警戒させるには十分だった。
「多くの犠牲……代償は、小さくなかった……」
ファリフが振り返ると、そこにはオイマト族のバタルトゥ・オイマト(kz0023)の姿があった。
オイマトの指摘通り、防衛線と引き替えに人類は大きな代償を支払う結果となった。
1000を越える怠惰の軍勢を前に、決死の覚悟で挑んだ各国の戦士とハンター達。巨体から繰り出される攻撃に、多くの者が倒れて屍を晒した。さらに部族会議の拠点となっているマギア砦も怠惰の手に落ち、部族会議はその拠点を失っていた。幸いにも辺境の巫女・リムネラ(kz0018)が建設に手を貸す開拓地『ホープ』に身を寄せているが、拠点を失った部族の戦士達も士気が下がっている。
「でも、被害は最小限に食い止められたよ。CAMの稼働実験場を守る事はできた」
「それは……甘すぎる」
ファリフの反論を、バタルトゥはあっさり否定した。
「どうして?」
「あの防衛線……怠惰が、乗り越えられないと思うか?」
バタルトゥの言葉は、ファリフの心に突き刺さった。
ナナミ川は深いところでも3メートル程。
巨人の怠惰であれば渡る事は不可能ではない。一度ナナミ川を渡りきってしまえば、構築した防衛線も怠惰の怪力で破壊されてしまうだろう。一度止まった進軍は、再び南下を続ける。CAM稼働実験場へ到達するのも時間の問題だ。
実はファリフもその事には、気が付いていた。
だが、その事はマギア砦で命を賭して戦った事実まで否定されてしまう気がしていたのだ。
「……ねぇ。ボク達がやった事は、無駄だったの?」
「…………」
寂しそうなファリフの問いに、バタルトゥは沈黙で答える他なかった。

ヤクシー

ハイルタイ
一方、マギア砦では納得できないヤクシーが怒りに満ちた叫びを上げていた。
「くそぉ! あいつら!」
CAM稼働実験場を目指して南下していた怠惰の軍は、ハンターと辺境部族に誘き寄せられてマギア砦を攻撃。その間にナナミ川付近に防衛線を構築されてしまったのだ。
だが、その怒りは防衛線を構築されて進軍が止まった為ではない。
砦を攻撃している間に奇襲された上、西の海岸に到着した救援船で脱出されてしまった事である。
「こんな中途半端なところで引っ込めるかってんだ!
一回火が付いちまった以上、目一杯暴れてやらねぇとな!」
「……ん? うるさい。ゆっくりと寝る事もできん」
ヤクシーの叫びで災厄の十三魔の一人、ハイルタイが姿を現した。
ヤクシーは、感情のままにハイルタイへ感情をぶつける。
「なんだよ、おっさん! 戦いにも来なかったくせによ!」
実はハイルタイもマギア砦の戦いに参加する予定だったが、蛇の戦士シバ(kz0048)とハンター達の尽力で撤退。ヤクシーが文句を言うのも無理はなかった。
「ふん、儂はちゃんと戦ったわ、砦から離れた場所でな。そもそも、砦は墜とせているのだ。それで良いではないか」
「そうはいくか! 奴ら、奇襲まで仕掛けてきたんだぜ? あたしに手傷を負わせやがってよぉ……このままでは収まらねぇ!」
ヤクシーは興奮を抑えられないようだった。
怠惰は元々怠け者とされているが、一度火が付けば体力の続く限り暴れ回る。今のヤクシーは籠城戦で火がついて興奮状態にあるようだ。
「また南へ行くというのか? 好きにしろ。ワシは適当にやらせてもらう」
そう言うなり、ハイルタイは欠伸を掻いてその場で横に寝転んだ。
その姿を一瞥したヤクシーは、部下の怠惰へ命令を告げる。
「進軍再開だ! 南に行って、奴らを徹底的に叩き潰してやれ!」

シバ

リムネラ
「臆するな。危機は好機なり」
ファリフとバタルトゥの背後から声を掛けたのは、マギア砦籠城戦を提案したシバだった。弟子のテトに肩を借りて、二人の元へやってきたようだ。
ハイルタイを止めるべく単身突き進んだシバ。重傷を負ったものの、ハンター達のおかげで無事生きて帰還する事ができた。
「シバさん! 寝てなきゃダメだよ!」
「火急の折に寝ている暇などないわ」
「……どういう事だ?」
シバの言葉にバタルトゥが聞き返した。
「実は……斥候からの報せによれば、怠惰が南下を再開したそうでございますにゃ」
「!?」
テトの報告で、ファリフとバタルトゥは衝撃を隠せなかった。
危惧していた展開。
このまま行けば、ナナミ川を越えて怠惰はCAM稼働実験場へ到達してしまう。
あのマギア砦の戦いは、すべて無駄になってしまう――。
「だからこそ、次なる一手を打つべき刻。
……あの防衛線を囮にしてな」
「囮?」
首を傾げるファリフに、シバは笑みを浮かべる。
「怠惰にはあの防衛線に攻撃を仕掛けてもらう」
「え!? マギア砦を諦めてまで作った防衛線だよ! それを……」
興奮せずには居られないファリフ。
そのファリフを手で制したのは、バタルトゥだった。
「シバ老……説明していただこう」
「敵の狙いは南の実験場。怠惰の事、ひとたび楽な勝利に酔えば、奴ら後先考えずに突き進む。
そして、ギリギリまで引きつけたところで……一気に敵を包囲する。こちらも青い巨人を出してな」
蒼い巨人――つまり、CAMを主力として敵を誘き出して一気に敵を駆逐する作戦だ。 興奮している怠惰が防衛線を越える事に集中しているからこそ、様々な工作を仕掛ける事が可能となる。
幸いにも同盟海軍のモデスト・サンテ少将が一度ポルトワールへ戻る際にサルヴァトーレ・ロッソへ立ち寄る事ができる。ここで化石燃料を移送すれば、CAM稼働実験場にあるCAMや魔導アーマーを作戦に投入する事が可能だ。
「なるほど……敵を包囲して殲滅する訳か」
「違うな。『殲滅』じゃない、『撃滅』ぞ。
……どこぞの団長代の言葉らしいが、上手く言うたものよ」
ここで勝利を収めれば、きっと明日の大勝利に繋がる。
もし、失敗すれば稼働実験場だけじゃない。リムネラ(kz0018)が形作った街も大きな被害をもたらすだろう。
――賭け。
リスクは存在するが、今までにはない勝利の可能性を秘めた賭けであった。

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

ヴェルナー・ブロスフェルト
帝国皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、要塞管理者ヴェルナー・ブロスフェルト(kz0032)から受け取った書類に目を通していた。
部族会議から提案された怠惰の撃滅作戦において、CAMや魔導アーマーの出撃を要請された。
おそらく帝国領内でCAMの稼働実験が行われている事を聞きつけて提案してきたのだろう。残念ながら未だ魔導型CAMは実験中で今回の提案に沿うことはできないが、皇帝は抜け目ない存在が辺境内にいる事を感じ取っていた。
「正確には我が国の軍師です、陛下。
かの者はノアーラ・クンタウの山岳猟団に身を置く者。ならば、我が国の臣民に他なりません」
「ああ、もういい。お前は堅苦しくてダメだ。もっと気楽に話せんのか?」
「申し訳ありません。これも私の性分です。お気になさらずに。
それより、この提案は如何致しましょう」
読み終わった提案書を皇帝から受け取ったヴェルナーは、笑みを浮かべながら聞き返す。
皇帝は軽くため息をついた後、椅子に腰掛けて背もたれに体を預ける。
「貸してやれ。怠惰の指揮官――ヤクシーと言ったか。
あれを叩く機会があるのなら、CAMや魔導アーマーを貸すのも悪い話じゃない」
「承知致しました。サルヴァトーレ・ロッソの方とも連携して事に当たります」
「ああ。辺境の部族とも今後は共に歪虚と立ち向かわねばならんのだ。関係を良好に保っておいて損はないだろう」
そう言った皇帝は、ヴェルナーの顔を見つめる。
しかし、その表情は先程の笑みではなく、衝撃を受けているようだった。
「どうした?」
「……あ、いえ。何でもありません。きっと、疲れているのでしょう」
「疲れている? お前がか?
まあ、いい。働き過ぎるのも考えものだ。たまにはゆっくり休むがいい」
皇帝は、ヴェルナーへ休暇を促す。
ヴェルナーは感謝の意を述べた後で、恭しく頭を下げる。
「お気持ち、感謝致します」
●
数刻後、ヴェルナーは信頼する部下を一人呼び出した。
「お呼びでしょうか」
「私がノアーラ・クンタウへ着任してから届いた陛下からの親書を調べてもらえますか? どんな些細な事でも結構です」
「それでしたら秘書官に……」
そう言い掛けた部下だったが、そこでヴェルナーの真意に気付いた。
ヴェルナーの周辺で得体の知れない何かがある。だからこそ信頼できる者に依頼しているのだ。
「承知致しました」
「まだ確証もありません。漠然とした感覚ですが――陛下と私の間に何かズレを感じるのです」
「ズレ、ですか」
「はい。言ってみれば歯車に挟まった小石。それを確かめる必要があります」
杞憂であればそれでもいい。
勘違いであって欲しい。
そう願うヴェルナーだったが、一度気になり出せば次々と疑問が涌き出てくる。
不安が真実へと駆り立て、白日の下へ晒せと命じる。
ヴェルナーは、確かめずには居られなかった。
「お願いします。何もないと良いのですが」
(執筆:近藤豊)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●撃滅戦終結、そして聖地奪還へ(3月10日更新)
ナナミ河で勃発した怠惰撃滅戦は、一定の成果を上げる事ができた。
CAM、新型魔導アーマーの投入が効果的であったが、それ以上に活躍したのはハンター達だろう。彼らが存在していなければ、このような結果を迎えられなかっただろう。
この戦いの勝利は、大きな意味があった。
辺境だけではない。王国、帝国、同盟、サルヴァトーレ・ロッソ??各国が一致団結して歪虚の脅威に立ち向かった。それも今まででは考えられなかった規模での介入だ。
歪虚に――勝てる。
この結果が、人類を新たなる戦いへと誘っていく。

ファリフ・スコール

バタルトゥ・オイマト

シバ
パシュパティ砦。
ナナミ河上流にある古い砦だ。先日、山岳猟団が奪取して拠点として活用している。そこへスコール族のファリフ・スコール(kz0009)は、ある人物から呼び出し受けていたのだ。
マギア砦籠城戦では部族会議の拠点であったマギア砦を失った。結果、ホープを間借りする形で部族会議を運用しているファリフであったが、当の本人はとてもはご機嫌だ。これも先の戦いで勝利できたからだろうか。
「…………」
同じく呼び出されたオイマト族のバタルトゥ・オイマト(kz0023)は、沈黙をもって答えた。
怠惰を巡る作戦は、『あの男』が立案したものだ。
そして、三回目の呼び出し。
こうなれば、あの男が再び新たな作戦を立案したであろう事は、想像に難くない。
「来たか」
「待たせた。ご両人」
「シバさん!」
蛇の戦士シバ(kz0048)の登場に、ファリフは椅子から立ち上がる。
帝国の山岳猟団に身を置くシバだったが、このところ辺境部族の手助けに忙しい。そしてそれは、帝国が監視の目を強めるのに十分だった。
「問題……ないのか? ……シバ老」
バタルトゥは、シバの身を案じた。
それはこの砦が大きく影響している。
実は帝国の監視対象下でありながら、ナナミ河の戦いの最中に山岳猟団がパシュパティ砦を奪還したのだ。帝国からの指示を受けず、勝手に動いたとあれば帝国が問題視しないはずがない。
おかげでシバに対する警戒はより一層強くなっていた。
「そうさな。そろそろ仕事熱心な連中が、この老いぼれの寝首を狙い始めるやもしれん」
「それでは……」
微かに身を乗り出したバタルトゥを、シバは掌を挙げ、制した。
「良い。それには手を打てる。それよりご両人……今の戦況を、如何様に考ておるか?」
「どうって……そりゃ、怠惰に勝って勢いづいているよね」
ファリフは首を傾げながら、そっと答える。
事実、先日の勝利は人類側を活気で包んだ。今も開拓地『ホープ』の辺りでは戦勝気分が満載だ。
その答えを耳にしたシバは大きく頷く。
「そうだ。打撃を受けたマギア砦へ逃げ帰った。おそらく奴らは傷を癒しながら部隊を再編しておる。しばらくは向こうから手を出しては来ぬだろう」
「……一安心という事か」
バタルトゥは、シバへ視線を送る。
そんな事を言うために呼び出したはずがない。おそらくこの質問も別の意図が隠されているのだろう。
事実、シバは『安心』という言葉を全否定した。
「否。お主ら、狩で獲物の熊を手負いにしたとして、安心なぞすまい? 怠惰も同じ事……徹底的に、殺しきらねばならん」
そう言いながら、シバはテーブルの上に地図を開いた。
帝国製の地図ではあったが、重要な拠点はシバが手書きで書き加えている。
「地図だよね。辺境の」
「うむ。先日、ノアーラ・クンタウ北で怠惰の動きを察した故、斥候を出した」

「ここよ」
シバが指差した場所は、エンシンケ洞穴。
辺境部族では試練の洞窟と呼ばれ、一人前の戦士になる為にはここへ一人で赴き試練を受ける事で知られている。もっとも、今は歪虚の勢力下にあって試練を受ける者は誰もいない。
「敵は『何か』を隠しておるようじゃな。そこをつき、この地を急襲してエンシンケ洞穴を奪還する。同時にマギア砦にも襲撃を仕掛け、我等の目的を欺瞞するのだ」
「……奇襲か」
二拠点同時の攻略戦――戦線を二つに割る事でリスクを背負う事になるが、敵は今まで同様マギア砦の防衛を優先するだろう。しかし、人類の本命がエンシンケ洞穴だと予想はしていない状況だ。
「そしたら、試練の山ごと奪い返せるね。怠惰だって、これまで通りには戦えなくなる筈だよ!」
奇襲に賛同するファリフ。
しかし、当のシバは頭を大きく横に振った。
「シバさん?」
「スコール族の長よ。この程度で満足してはならん。この洞穴を襲撃は、あくまでも敵を追い詰めるが目的。真の狙いは……ここよ」
シバの指がエンシンケ洞穴から北へ移動する。
そして、指は辺境一大きな山脈の上で止まる。
リタ・ティト。
『巨龍の背骨』と呼ばれる巨大山脈は、辺境部族の間で聖なる山として扱われている。
だが、エンシンケ洞穴の先にある巨大な山脈、その頂上には??
「……大霊堂!」
はっとして、ファリフとバタルトゥが声を揃えると、シバは心底嬉しそうに、笑った。
「聖地『リタ・ティト』の大霊堂こそは、赤き大地の巫女が住みたもう、聖なる土地にして、我ら部族の魂の拠所でもある。ここを奪い返せれば、巫女の名の下に……きっと我等は、団結できる」
シバの提案は、勢いに乗じて聖地奪還を進言したのだ。
現在リタ・ティトは歪虚の勢力圏にあるが、大霊堂だけは巫女の加護で侵食を免れているという。もし、この地を奪還できれば辺境部族の結束は今まで以上に固くなる。
「やらなきゃ! ここまで頑張ってくれたリムネラ(kz0018)の為にも……ボクらの、故郷の為にも!」
「然り。怠惰はCAM実験場を狙うであろうが、ならば我等も敵の喉元を狙う。
聖地の白龍も探さねばならぬ。古に消息を絶った彼の存在に触れることができたならば、或いは、奪われた地をも取り戻せる」
「……しかし……本当に奪還できるのか……」
シバの案に、バタルトゥが懸念を示す。
本当にシバの言う通り聖地を奪還する事ができるのだろうか。もしそれが叶うのであれば辺境部族は諸手を挙げて喜ぶだろう。だが、失敗すれば落胆も大きい。リスクが大きい作戦だからこそ、慎重になるのも無理はなかった。
「オイマトの長よ。お主は、この戦いで何を見た?」
「…………」
「帝国や王国、同盟の戦力だけではここまでの勝つ事はできなかった。
この勝利は蒼き巨人と魔導の鎧……そして、ハンターの存在よ」
シバは、辺境部族に力を貸してくれた者達の存在を示唆した。
彼らが居れば、必ず聖地を奪還できる。
彼らの力を信じて戦うべきではないか。
少しの間を置いた後、バタルトゥは静かに頷く。
聖地奪還への覚悟を決めたようだ。
「よろしい、ご両人。では、準備を手伝って貰おう。
心せよ。隣人に助けを求む我等は、その恩恵を越える覚悟を、彼等に示さねばならぬ」
●
「シバ老……聞いておきたい事がある」
パシュパティ砦を出る間際、バタルトゥは、シバに問いかける。
「なんだ?」
「シバ老は……あなたは、何を目指している……」
「赤き大地の子として、故郷の行く末を案じておる。当然の事よ」
唐突の質問に、漠然とシバは答える。はぐらかすような笑みと共に。
老人の答えは、恐らくは嘘ではあるまい。だが、バタルトゥは満足していないようだ。
「そうじゃない……シバ老の中で、既に絵図面が描かれている……そんな気がするんだ」
「ほう」
シバはそう言った後、感心したように小さく頷いた。
若くしてオイマト族の長に選ばれた者として、正しい感覚を持っている。シバの意図を感じ取った辺り、将来有望と言えるだろう。もっとも、まだ歩き始めたばかりなのだが……。
「その通り。既に絵図面はある」
「…………」
「赤き大地の部族は歪虚に対して団結する為、他国と交わった。だが、仮に歪虚を駆逐したとして、元の生活に戻れると思うか? 否であろう。一度口にした果実の味は忘れられん。
そして、我等部族が今のままであれば……必ず誰かが、我等を跪かせ、呑み込もうと考える」
シバの言葉に耳を傾け、バタルトゥは部族の先を思い浮かべた。
歪虚を倒した後、部族はどうなってしまうのか。
歪虚が現れる前の生活に戻れるとは思えない。そして、敵を失った各国は領地を求めて辺境へ――考えられない未来ではない。
現に今、辺境部族に服従を迫る者が居るではないか。
「赤き大地の部族は変容する。これは最早、絶対に避けられん。だが……その変容を他者から強いられるか、自ら選択するか。この違いは大きいぞ。判るか」
「……それは……辺境に国を興すという意味か?」
「否。そんな瑣末な括りの話ではない。オイマト族の長バタルトゥよ、その聡き瞳で世界を観よ。鷹より高く、馬より遠く、竜より旧く、人よりも新たなる、遥か世界のあるべき姿を。『辺境』とは一体、誰が定めた『辺境』ぞ? 下らん。全く以て下らん括りよ」
謎掛けのような言葉を残し、老人は、去った。バタルトゥは一人、故郷の将来を考えていた。
●
数日後。
聖地奪還を宣言する一報は、秘密裏に各国へともたらされた。
そして、冒険都市リゼリオで各国首脳が顔を付き合わす。

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

ラウロ・デ・セータ

システィーナ・グラハム
同盟評議会議長ラウロ・デ・セータ(kz0022)は、報告を受けて率直な感想を述べた。
CAM稼働実験場を守る名目で怠惰と対峙した各国だが、聖地奪還は各国にとってCAM程重要な存在ではない。だが、部族会議は既に各国の協力を得られると想定して戦いの準備を開始している。正直、各国にとって辺境を舞台に更なる戦力投入は避けたいところだろう。
「王国も未だ復興が続いています」
辺境の民が憂うように、システィーナ・グラハム(kz0020)も王国の民を憂いていた。
CAM稼働実験場の防衛も大事だが、王国の復興も大切だ。二つの戦いを経て騎士団にも損害は出ている。ここで更なる戦いを始めても良いのだろうか。
――だが。
またしてもこの人物が、とんでもない一言を放つ。
「聖地奪還……結構じゃないか。あの巨人と決着をつけねばならんと思っていたところだ」
帝国皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、部族会議の申し出を受けるつもりだ。
今までの戦いで自ら奇襲を仕掛けてヤクシーを狙う豪胆な皇帝は、怠惰と自らの手で決着を付けたがっているようだ。
この一言にラウロとシスティーナは驚きを隠せない。
「本気なのですか? 帝国も相応の被害は出ていたはずですが……」
「CAMを実戦投入できる機会、データは取り放題だ。
それに聖地を奪還できれば辺境部族は大層感謝するだろうな。連中に恩を売っておいて得する事はあっても、損はあるまい」
ラウロの言葉に、皇帝は自信を持って答える。
そして、その言葉の裏に政治的意図がある事は明確であった。聖地奪還に大きく貢献できれば、その後自国での戦いに支援が得られる事は当然。うまくいけば思わぬ物が手に入るかもしれない。
そして、王国も同盟も帝国の独断専行を許す訳にはいかない。
各国の思惑を巻き込みながら、人類は聖地奪還へと動き出す。
●ファリフの思い、リムネラの思い(3月10日更新)

リムネラ

ファリフ・スコール
歪虚の活動が辺境で活発になっていることは、さまざまな事実を見ても明らかで、自身が号令をかけてやっと軌道に乗り始めた開拓地「ホープ」すら、今や風前の灯火と言えなくない。
ユニオンの誰もが、それを売れいるリムネラに言葉をかけることが出来なかった。彼女の抱えているのはユニオンだけではない――聖なる山『リタ・ティト』の未来をもその細い肩に乗せているのだから。
そんな折、リムネラの元にやってきた少女がいた。大きく手を振留彼女の顔は、リムネラも知っている。
「リムネラさん!」
元気そうな声を上げる少女――ファリフ・スコール (kz0009) の顔を見て、リムネラの顔がわずかに明るくなった。
「ファリフ……サン。あなたコソ、ブジでよかった」
スコール族族長とはいえ、ファリフはまだリムネラよりも幼い少女。リムネラにとっては心やすく話しかけることの出来る存在の一人である。
「うん。なんとかやってるよ。ところで……お願いがあるんだ」
「エ?」
突然のファリフの言葉に、リムネラはわずかに首をかしげる。
「このままじゃあ、マギア砦どころか辺境の多くが歪虚のものになっちゃう。ハンターのみんなにも手伝ってもらわないといけないけど、何よりもみんなの力が必要なんだ。だけど、ボクとかじゃあ、色んな意味で説得が難しい部分があるのも事実で……」 そう、辺境にはさまざまな派閥が存在する。
帝国の介入を喜ばないもの、それに従うもの。
多くの部族が点在する辺境は、一枚岩ではないのが現実だ。
「……だけどね」
ファリフは言葉を続ける。
「リムネラさんは違う。聖地の巫女は、どこにも属さない、中立の存在なんだ。それに、聖地はいまだに歪虚の手の中にあるけれど、それを奪還するための作戦も考えなきゃいけない。そのためには、リムネラさんが説得するのが一番説得力があるんだ」 ファリフはそう言って、もう一度リムネラの顔をしっかりと見据えた。
「リムネラさんだって、聖地を奪還したいと思うでしょ? そのために、みんなを鼓舞するための演説をお願いしたいと思うんだ。お願い」
リムネラは息をのんだ。
ファリフの言葉はとても魅力的だし、確かに彼女自身も聖地の巫女として、聖地の奪還は悲願ともいえる。
だが、自分で良いのだろうか?
「お願い! リムネラさんしか、これが出来る人はいないんだよ」
ファリフの言葉は、とても真剣で。
リムネラはややあってから、小さく頷いたのだった。
●リムネラの言葉
それから数日後。
「皆サン、聞いて下さってありがとうございマス」
『ガーディナ』リーダーのリムネラがなにやら話をすると言うことで、集まったハンターたちはずいぶん多い。
ついでに言うと、会場もファリフなどがセッティングしてくれたらしく、ユニオン本部ではない場所を選んでくれている。辺境ユニオン所属以外の人でも出入りがしやすいようにと言う配慮なのだろう。
リムネラは緊張していた。当然である。普段よりも遙かに多くの人が、彼女の話を聞きにやってきているのだから。
「エエ、と……今、辺境は窮地にたたされていマス」
言葉を少しずつ、ゆっくりと彼女は紡ぎ出す。誰の耳にも、その言葉が届くように。そして、少しずつその声は大きくなっていく。
「辺境に現れた歪虚は、次第に南下を進めています。皆サンのすむエリアを侵食してくるのも、時間の問題でしょう」
言葉はぎこちないながら、出来る限り優しくやわらかく、言葉を使う。
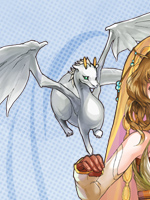
ヘレ

ファリフ・スコール
白龍――リムネラは間違いなくそう言うと、彼女は肩にちょこんと乗っている小さな白龍・ヘレをそっと撫でた。
「なんだって……!?」
龍は、リアルブルーではもちろんのことながら、クリムゾンウェストにおいても伝説に近い存在である。聖地リタ・ティトには白龍がいるというのは驚きの情報であった。
白龍クラスの幻獣となれば、当然ながら信仰の対象だ。たとえリムネラの肩に乗っている小さなヘレでさえ、信仰の対象なり得てしまうのである。いつも彼女の肩にいるのが当たり前で、忘れていた人も多かったけれど。
それを救うことが出来れば――確かに、辺境のみならず、クリムゾンウェストの人類皆の士気は高まるに違いない。
周囲はにわかにざわつき始めた。
「みんな、リムネラさんの話をよく聞いて!」
ファリフが声をあげ、ざわめきを静める。 「コレは、ファリフサンに頼まれて話していることではありません。ワタシは、ワタシ自身として、どう にかして聖地を取り戻したい――そう思っているのです。今、前線が後退することになれば、それは更に遠のくでしょう。聖地の存在は、巫女にとってのホーム、ふるさとのようなモノ。そして、辺境の人たちの心のよりどころです。ドウカ……どうか、ワタシに、辺境に、聖地リタ・ティトに、力を貸していただけませんか……?」
そう言いながら、リムネラは大きく頭を下げる。
こういう公の場で、はっきりと自分の意思をいうのは思えば初めてかも知れない。リムネラの、細い肩がわずかに震えた。巫女がここまでして取り戻したい聖地――それはもしかすると、思っている以上に重要な存在なのではないか。
誰かがぽつりと呟く。
「……聖地の巫女の力があれば……」
すると呼応するように、他のハンターたちも考え始めた。
「幻獣の力も借りることが出来れば……」
「それは大精霊の力を借りることにも繋がるだろうし……」
そうなれば、戦局は、きっと変わる。変えるきっかけが作れる。
ならば。
その場にいたハンターたちは頷いた。
リムネラの思いに応えるため、力を貸そうと。
(執筆:四月朔日さくら)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●機甲兵器、導入へ(3月18日更新)

ナサニエル・カロッサ

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
ナサニエル・カロッサ(kz0028)の胡散臭い笑顔にヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は目を瞑り頷く事で応じた。
「当然だ。こんな所で負けていられる程我々に猶予はない」
「ついこの間撤退戦をやった人の言葉とは思えませんが、ご無事で何よりです」
ナナミ河での戦いから間もなく、試作兵器の実験場として選ばれた帝国北部のカールスラーエ要塞にて二人はテーブルを囲んでいた。
関係各位に実験成果を公開する為にカールスラーエに兵器を集めていたのが、結果的にナナミ河での戦いで活用された。
実用性を確かめると同時に戦況を好転させる切っ掛けの一つとなったのだから、この上ない戦果であったと言える。
「陛下が持ち帰って下さった魔導アーマーの実戦データは大切に使わせて頂きます。魔導型も使えれば良かったんですがねぇ」
「それは出来ないと言ったのは貴様であろう」
「魔導型はCAMであって、所有権は帝国軍ではなくサルヴァトーレ・ロッソにありますからねぇ。運用許可を取るにも手間暇かかるんですよぉ」
何より勝手に帝国がCAMを運用したとなればどこもかしこも黙っていないだろう。ナサニエルは肩を竦め。
「面倒ですねぇ。滅亡の危機に瀕して尚、人は同族を恐れ続けている」
「それも当然だ。我々は負けないし、滅びもしない。歪虚を退けた先にある未来、その秩序の為に人は自らを戒め続ける必要がある」
自ら淹れた安物のコーヒーを啜り、ヴィルヘルミナは小さく息を吐く。
「……話を戻そう。ナサニエル、魔導型CAMと魔導アーマー、今すぐと来たら何機出せる?」
「今すぐ、ですか? 魔導型は六機改修済みで、二機改修途中の機体があります。魔導アーマーは先の戦闘で破損した機体もありますが、まあ二十機くらいでしたら……」
「リゼリオでの首脳会談にて、辺境部族会議から聖地リタ・ティト奪還作戦の提案を受けた。私はそれを了承するつもりだ」
口元に手を当てたままきょとんとするナサニエル。それから思案し、腰に手を当て。
「思い切りましたねぇ。帝国軍の消耗も馬鹿にならないと思いますが」
帝国にほど近いナナミ河や、言わば人類の防衛線でもあったマギア砦と違い、リタ・ティト奪還に帝国軍として旨味は感じられない。
確かにナナミ河の戦いにおいて人類は勝利した。その勢いを確信と固めたいのも理解できる。だが……。
「そこまでする価値、ありますかね?」
「誰にでも希望は必要なのだ。それはわかりやすい程良い。心に拠り所さえあれば、人は幾らでも戦える」
「辺境部族に帝国の盾としての役割を担わせたいと」
「歪虚からの領土奪還は人類全体の命題であると同時に帝国の宿願でもある。奪われたら奪い返す……それだけだ」
コーヒーを飲み干すと女は立ち上がり窓辺に立つ。眼下には今回の実験で集まった人々、そして要塞を守る兵達の営みがある。
「帝国が動けば王国も同盟も無視は出来まい。ソサエティも協力は惜しまんだろう」
「また大勢死にますねぇ」
「そうだ。あのクソ羊の襲撃から立ち直ったと言い難い王国も、意思統一の難しい同盟も結論を先延ばしに出来なくなる。全てが戦禍へ巻かれるだろう」
穏やかな風に赤い髪を揺らし、女は目を細める。
「それでも勝たねばならない。希望の灯火を消さぬ為に。ラウロの爺さんにも、システィーナにも付き合って貰うしかあるまい」
「魔導型、もう少し数を増やせないか、サルヴァトーレ・ロッソと相談してみますよぉ」
マグカップに注がれたコーヒーへ執拗に角砂糖を落としながら男は呟く。
「魔導アーマーも生産ラインは構築できていますから、ウェルクマイスター社に要請し数を揃えます。魔導アーマー四十、魔導型は十五、六。そんなもんでどうです」
「出来るのか?」
「出来なかったら言いませんよぉ。多少無茶はしますけど」
マントを翻し女は男に歩み寄る。肩を抱き、白い歯を見せ無邪気に笑って。
「少しくらいしおらしくしている方が頼み事を聞いてくれるタイプかね、君は?」
「勘違いなさらずに。自分の仕事をしているだけです」
ナサニエルの肩を強めに叩くと笑いながらヴィルヘルミナは部屋を後にする。
「私の仕事は兵器を完璧に仕上げる事。その為に実戦、そしてそれに伴うデータは必要ですから」
人もマシンも、幾ら壊れようが知った事ではない。
大義名分があれば無茶も通しやすくなる。折角与えられた鶴の一声。利用してよいのならさせてもらう。ただそれだけの事だった。
(執筆:神宮寺飛鳥)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●同時作戦、決行の時(3月25日更新)
話は――ナナミ川の戦い直後まで遡る。

 「くそったれがっ!!」
「くそったれがっ!!」
ヤクシーは荒れていた。
満を持してCAM稼働実験場へ向かったはずが、人類の逆襲に遭って逃げ帰ってきたのだ。歪虚としてのプライドも傷つけられ、ヤクシーの怒りは爆発している。
「ヤクシー、このような時こそ落ち着く時。
英雄はいつでも冷静に対処するものだ」
災厄の十三魔の一人、ガエル・ソトは傍らで落ち着くよう諭す。
だが、それでもヤクシーの怒りは収まらない。
「ふざけるな! これが怒らずにいられるか! 部下が手酷くやられたんだよ! しかも、あの妙な鉄の塊に!」
鉄の塊――CAMと新型魔導アーマーを前に、怠惰は手痛い仕打ちを受けた。
今まで見た事もない敵と対峙した事もあり、ナナミ川を渡河した怠惰は次々と倒れていった。
このような失態を怠惰は今まで経験した事がなかった。
だからこそ、ヤクシーの怒りは留まらない。
「ああ、むかつくねぇ! 次にあったらもう容赦しねぇ!」
「だが、その前に傷を癒して部隊を再編するべきだ。本気で戦うつもりがあるのならば、な」
ガエルはヤクシーに傷を癒すよう指摘した。
確かにマギア砦やナナミ川の連戦でヤクシーも少なからず負傷していた。本気で戦うつもりならば、傷を癒して怠惰の部隊を再編する。
そう――怠惰にとって時間はまだまだある。部隊を立て直してから再度戦いを挑んでも遅くはない。
「……ちっ。そうした方がよさそうだね。ガエル、後は頼めるかい? あたしはちょっと傷を癒すとするよ」
「すべて英雄に任せておけ。復帰する頃には直ぐに出陣できるよう手配しよう」
ガエルの言葉を聞いた後、ヤクシーは砦を後にした。
心のマグマが爆発せぬよう必死に押さえつけながら。
こうしてCAM稼働実験場を襲撃しようとしていた敵は二手に分かれた。
怠惰の女指揮官は――エンシンケ洞穴にて療養。
災厄の十三魔は――マギア砦で留守を預かる。
二分された戦力。
このチャンスを人類は決して逃さない。
今こそ雪辱を果たす時が到来する。
「今回の任務は陽動。そして、敵指揮官は災厄の十三魔ですか」
 帝国皇子カッテ・ウランゲル(kz0033)は、ナナミ川を渡河。マギア砦に向かって進軍していた。
帝国皇子カッテ・ウランゲル(kz0033)は、ナナミ川を渡河。マギア砦に向かって進軍していた。
カッテに下された任務は『マギア砦へ進軍して駐留部隊の目を惹き付ける事』、つまり陽動を仕掛けて可能な限りマギア砦の防衛を手薄にする事だ。
「そして、その災厄の十三魔は姉上と多少の因縁があるようですね……『姉がご迷惑をおかけしました』、とでもご挨拶するべきでしょうか?」
カッテが顎に手を当てクスリと笑うと、周囲の軍人や部族の戦士、そしてハンターたちも、思わず表情を緩ませた。
マギア砦の主力部隊を引き受けるにはCAMや魔導アーマーの数が不足しているため、随伴の歩兵や騎馬もカッテの横を通り過ぎていく。
(この戦力で何処まで持ちこたえられるかが鍵、ですね)
恐らく、帝国出身者以外は信じられないだろう。
この、冗談で場を和ませる少年が、周囲の地形の細部にわたる情報、CAMや魔導アーマーの整備や補給の手順、そして混成軍故の命綱となる指揮系統や、連絡体制などの情報を全て把握していること。
そして、それらの情報を元に再現された仮想の戦場では、既に現実の戦場以上の現実性を持って両軍が激突していることに。
帝国皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、マギア砦籠城戦において怠惰指揮官に奇襲を仕掛けた。その際、災厄の十三魔と交戦をしたようだが、その能力は未だ未知数。CAMと魔導アーマーで怠惰の巨人達を抑えたとしても、災厄の十三魔がどのような行動に出るかは予想ができない。
あらゆる可能性を想定しなければ、陽動は成功しないだろう。
「それでも、僕達はやり遂げなければいけない……何故なら今ここにいる僕たちこそが歪虚に対する人類の盾、なのですから」
そうですよね、姉上、父上。そう小さく呟くとカッテは進行方向を見据える。
視界にはマギア砦が見え始めていた。
凶人
一方、マギア砦。
「来たか。むしろ遅いぐらいだったな、人類」
マギア砦の防衛を指揮するのは災厄の十三魔が一人、ガエル・ソト。
英雄に拘る凶人であり、己が英雄である事を理由に辺境各地で人類を攻撃する狂人でもある。
「先日の斥候発見から数えて幾日。襲撃があると読んで砦の防衛を固めていたが……ようやくエリート歪虚である我が辣腕を振るうときが訪れたか」
先日、ハンターがマギア砦への斥候を試みていた。
ガエルにとっては幸いにも、ナナミ川で失われた戦力を歪虚に呑み込んだ部族戦士で補っていた為にハンターの斥候を事前に察知する事ができた。あれから人類の襲撃に備えて可能な限り戦力の増強に努めてきた。
その努力が今、まさに実ろうとしている。
「巨人達を前進させろ。敵の進撃を食い止めるのだ。
部族戦士は巨人が敵の進軍を食い止めている隙に突撃だ。一気に敵を蹴散らせ」
おそらく、ナナミ川で登場したリアルブルーの兵器も登場させるはずだ。
ガエルは凶人にして狂人ではあるが、英雄の自認する歪虚――CAMや魔導アーマーの投入に備えた作戦を検討していたようだ。
「私も出るぞ。英雄である以上、最前線での活躍を見せつけねばならんのでな」
 聖堂戦士団長ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は、マギア砦近くまで進軍していた。
聖堂戦士団長ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は、マギア砦近くまで進軍していた。
カッテが陽動を仕掛けている隙にヴィオラがマギア砦へ攻城戦を仕掛ける。うまくマギア砦を奪還できれば、敵主力を挟撃できるかもしれない。
「皮肉ですね。あれだけ守っていた砦を、今度は襲撃しなければならないのですから」
ヴィオラの脳裏に浮かぶのは、マギア砦で怠惰の軍勢を相手にした、あの籠城戦だ。
巨人という歪虚を相手に、ハンターと各国の戦士達が力を合わせて戦い抜いた。あの戦いで人類側も多くの血を流す事となった。
だが、そのおかげでCAM稼働実験場を守り抜く事ができた。
ヴィオラは、その犠牲を今もしっかりと覚えている。
「マギア砦で散った者達が居たからこそ、私達は今日を迎える事ができました。
そして、今度は彼らの無念を我々が晴らす番です」
砦の壁をよじ登る梯子部隊も準備は完了。
マギア砦東の海岸にある隠し通路への突撃部隊も作戦開始を待ち続けている。
(敵が陽動部隊へ攻撃を仕掛けた時が――チャンスです)
ヴィオラは、西の方角へ視線を向ける。
間もなく、ガエルが陽動部隊へ攻撃を仕掛けるはず。
その間に――マギア砦を奪い返す。
「皆さん、参ります。
籠城戦で味わった雪辱……今日この場で果たしましょう」
ヴィオラは、動き出す。
目指す先は――マギア砦。
必ず奪い返す、と心に誓って。
試練の山にて

 同時刻――辺境の東、試練の山。
同時刻――辺境の東、試練の山。
エンシンケ洞穴近くの森に布陣した二つの軍。
一つは、オイマト族の族長バタルトゥ・オイマト(kz0023)。
もう一つは要塞『ノアーラ・クンタウ』に駐留する第一師団分隊を率いるヴェルナー・ブロスフェルト(kz0032)。
「マギア砦の方は、作戦が開始している頃ですねぇ」
「…………」
ヴェルナーの言葉に、バタルトゥは沈黙で返す。
以前では考えらられなかった辺境部族と帝国軍の共闘。それが聖地奪還という目標を前にして為し得る事ができたのだ。
「しかし、今回の作戦を考えたのがあのシバさんですか。私も驚きを隠せません」
「……その割には……シバ老の扱いが良くないが……」
バタルトゥはヴェルナーへ視線を向ける事無く、そう呟いた。
シバが所属する山岳猟団は、先日攻撃命令が出ていないにも関わらずパシュパティ砦の襲撃。それ以前にも複数の命令違反を犯し、シバは審問隊『ベヨネッテ・シュナイダー』からの監視対象となっていた。
辺境の民から見れば、大きな功績を残しているのだが――。
「ええ。ですが、法は法です。シバさんにも『それなりの』対応はさせていただきます。ですが、今は目の前の事に集中するべきではありませんか?」
目の前の事。
それは先日テトの偵察により発覚した『怠惰指揮官のヤクシーがエンシンケ洞穴に潜んでいる』という事実だ。おそらく傷の療養でもしているのだろうが、人類側としてはこのチャンスを逃す訳にはいかない。
エンシンケ洞穴付近の巨人をCAMと魔導アーマーを主力とした前線部隊が襲撃。同時にファリフ・スコールら突撃部隊が一気にヤクシーを追い詰める。
そして、エンシンケ洞穴を足掛かりにして聖地リタ・ティトへ迫ろうというのだ。
「CAMと魔導アーマーの準備も完了。あなたの号令一つで、部族の誇りを賭けた聖戦が始まります。
……さあ、開戦の合図を!」
わざわざ舞台上のようなセリフ回しで進軍の号令を求めるヴェルナー。
その意図を怪しんだバタルトゥだったが、ここで手を止める訳にはいかない。
「……いくぞ……聖地までの道は、我等が切り拓く」
 「始まったみたいだね」
「始まったみたいだね」
バタルトゥとヴェルナーが進軍した事を確認したファリフ・スコール(kz0009).
巨人とCAMの乱戦が繰り広げられる隙を突いて、エンシンケ洞穴に向かって走る。
テトの情報によれば、洞穴内は天井から光が漏れて中を照らしているらしい。おまけに既に洞穴内の地図も8割方完成している。
これならば、中で迷う可能性も低い。今から油断していたヤクシーに一撃をお見舞いするのが楽しみだ。
「族長、行きましょう! 聖地は俺達の手で取り返すんだ!」
スコール族の戦士がファリフに話し掛ける。
この数ヶ月間、ファリフは多くの人と知り合う事ができた。
そして、様々な事を教えられた。
スコール族を率いる重圧と責任。逃げ出したくなる時もあったが、必ず周りには支えてくれる仲間がいた。
「ハンターのみんなも、ボクに力を貸して!
リムネラの還る場所を、辺境のみんなにとって大切な場所を取り返す為に!」
ファリフは勢い良く洞穴へ飛び込んだ。
手にした斧で目の前の敵を弾き飛ばしながら、ひたすら奥へ向かって突き進む――。
「なんだって? 襲撃!?
馬鹿言ってんじゃないよ、敵はマギア砦じゃないのかい?」
ヤクシーは突然の出来事に混乱していた。
敵が今襲撃を仕掛けるとすればマギア砦の方だ。
何故、辺境でもまったく別方向のこのような場所を襲撃してきたのか。
そもそも、何故ここに自分が居る事が露見しているのか。
すべては人類を侮り、舐めてかかったヤクシーの驕りなのだが、その事を今のヤクシーは理解できないだろう。
「あー、もう!
考えるのも面倒くさい! 要するに、襲ってきた奴は全部ぶっ飛ばせばいいんだろう?」
ヤクシーは悩む事を放棄すると、愛用の鎌を手にした。
襲撃? だからなんだ。
敵は全部殺してやればいい。殺せば悩みも無くなって万事解決だ。
「マギア砦もナナミ川の時も奇襲ばっかりしやがって。正面から攻撃もできない臆病者の小さい奴らにあたしが負ける訳ないんだ。
……さぁ、今からあたしが出るよ。安心して逝っちまいな」
人類と怠惰による大きな戦が、始まった。
様々な思惑を呑み込みながら、戦乱は時代の転機を迎えようとしていた。
妄腕亡兵
ファリフにとっては不幸なことに、そしてヤクシーにとっては幸運というべきか、彼女たちは気付いていなかった。
ファリフ率いる部隊が次々と、突入していくエンシンケ洞窟を険しい視線で見つめる新たなる災厄の十三魔アイゼンハンダー(kz0109)の存在に。
 「革命軍め……野戦病院を襲うなんて……!」
「革命軍め……野戦病院を襲うなんて……!」
成り行き上、怠惰を助けることになったアイゼンハンダーであったが、彼女の目的はあくまでもCAMや魔導アーマーの動向を探ることであり、あの後彼女は再びCAMの偵察に戻っていた。
だが、人類の攻勢が始まったのを見て、再び「友軍」が気になった彼女は居ても立ってもいられず、友軍の気配が集まっているエンシンケ洞窟へと駆けつけたのである。
「行こう。私が背後から仕掛ければ反徒どもを挟み撃ちに出来る。……ヤクシー殿と連携がとれなくても、最悪撤退支援は出来る筈だよ……!」
『だが、戦場が気に食わん。手狭に過ぎるわ』
義手からの声が応じた。
「大丈夫……軍医殿の新兵器なら、閉所での白兵戦にも十分対応出来るよ」と。
アイゼンハンダーが生身の手で握った柄が、マテリアルの刃を形成する。
『笑止。所詮は玩具。儂とお前が全力を出せば持たんのが見えている欠陥品よ……だが、まあ良い。確かにこのくらいは加減してやらねば、興も乗らぬか』

ヤクシー

ガエル・ソト
ヤクシーは荒れていた。
満を持してCAM稼働実験場へ向かったはずが、人類の逆襲に遭って逃げ帰ってきたのだ。歪虚としてのプライドも傷つけられ、ヤクシーの怒りは爆発している。
「ヤクシー、このような時こそ落ち着く時。
英雄はいつでも冷静に対処するものだ」
災厄の十三魔の一人、ガエル・ソトは傍らで落ち着くよう諭す。
だが、それでもヤクシーの怒りは収まらない。
「ふざけるな! これが怒らずにいられるか! 部下が手酷くやられたんだよ! しかも、あの妙な鉄の塊に!」
鉄の塊――CAMと新型魔導アーマーを前に、怠惰は手痛い仕打ちを受けた。
今まで見た事もない敵と対峙した事もあり、ナナミ川を渡河した怠惰は次々と倒れていった。
このような失態を怠惰は今まで経験した事がなかった。
だからこそ、ヤクシーの怒りは留まらない。
「ああ、むかつくねぇ! 次にあったらもう容赦しねぇ!」
「だが、その前に傷を癒して部隊を再編するべきだ。本気で戦うつもりがあるのならば、な」
ガエルはヤクシーに傷を癒すよう指摘した。
確かにマギア砦やナナミ川の連戦でヤクシーも少なからず負傷していた。本気で戦うつもりならば、傷を癒して怠惰の部隊を再編する。
そう――怠惰にとって時間はまだまだある。部隊を立て直してから再度戦いを挑んでも遅くはない。
「……ちっ。そうした方がよさそうだね。ガエル、後は頼めるかい? あたしはちょっと傷を癒すとするよ」
「すべて英雄に任せておけ。復帰する頃には直ぐに出陣できるよう手配しよう」
ガエルの言葉を聞いた後、ヤクシーは砦を後にした。
心のマグマが爆発せぬよう必死に押さえつけながら。
こうしてCAM稼働実験場を襲撃しようとしていた敵は二手に分かれた。
怠惰の女指揮官は――エンシンケ洞穴にて療養。
災厄の十三魔は――マギア砦で留守を預かる。
二分された戦力。
このチャンスを人類は決して逃さない。
今こそ雪辱を果たす時が到来する。
「今回の任務は陽動。そして、敵指揮官は災厄の十三魔ですか」

カッテ・ウランゲル
カッテに下された任務は『マギア砦へ進軍して駐留部隊の目を惹き付ける事』、つまり陽動を仕掛けて可能な限りマギア砦の防衛を手薄にする事だ。
「そして、その災厄の十三魔は姉上と多少の因縁があるようですね……『姉がご迷惑をおかけしました』、とでもご挨拶するべきでしょうか?」
カッテが顎に手を当てクスリと笑うと、周囲の軍人や部族の戦士、そしてハンターたちも、思わず表情を緩ませた。
マギア砦の主力部隊を引き受けるにはCAMや魔導アーマーの数が不足しているため、随伴の歩兵や騎馬もカッテの横を通り過ぎていく。
(この戦力で何処まで持ちこたえられるかが鍵、ですね)
恐らく、帝国出身者以外は信じられないだろう。
この、冗談で場を和ませる少年が、周囲の地形の細部にわたる情報、CAMや魔導アーマーの整備や補給の手順、そして混成軍故の命綱となる指揮系統や、連絡体制などの情報を全て把握していること。
そして、それらの情報を元に再現された仮想の戦場では、既に現実の戦場以上の現実性を持って両軍が激突していることに。
帝国皇帝ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)は、マギア砦籠城戦において怠惰指揮官に奇襲を仕掛けた。その際、災厄の十三魔と交戦をしたようだが、その能力は未だ未知数。CAMと魔導アーマーで怠惰の巨人達を抑えたとしても、災厄の十三魔がどのような行動に出るかは予想ができない。
あらゆる可能性を想定しなければ、陽動は成功しないだろう。
「それでも、僕達はやり遂げなければいけない……何故なら今ここにいる僕たちこそが歪虚に対する人類の盾、なのですから」
そうですよね、姉上、父上。そう小さく呟くとカッテは進行方向を見据える。
視界にはマギア砦が見え始めていた。
凶人
一方、マギア砦。
「来たか。むしろ遅いぐらいだったな、人類」
マギア砦の防衛を指揮するのは災厄の十三魔が一人、ガエル・ソト。
英雄に拘る凶人であり、己が英雄である事を理由に辺境各地で人類を攻撃する狂人でもある。
「先日の斥候発見から数えて幾日。襲撃があると読んで砦の防衛を固めていたが……ようやくエリート歪虚である我が辣腕を振るうときが訪れたか」
先日、ハンターがマギア砦への斥候を試みていた。
ガエルにとっては幸いにも、ナナミ川で失われた戦力を歪虚に呑み込んだ部族戦士で補っていた為にハンターの斥候を事前に察知する事ができた。あれから人類の襲撃に備えて可能な限り戦力の増強に努めてきた。
その努力が今、まさに実ろうとしている。
「巨人達を前進させろ。敵の進撃を食い止めるのだ。
部族戦士は巨人が敵の進軍を食い止めている隙に突撃だ。一気に敵を蹴散らせ」
おそらく、ナナミ川で登場したリアルブルーの兵器も登場させるはずだ。
ガエルは凶人にして狂人ではあるが、英雄の自認する歪虚――CAMや魔導アーマーの投入に備えた作戦を検討していたようだ。
「私も出るぞ。英雄である以上、最前線での活躍を見せつけねばならんのでな」

ヴィオラ・フルブライト
カッテが陽動を仕掛けている隙にヴィオラがマギア砦へ攻城戦を仕掛ける。うまくマギア砦を奪還できれば、敵主力を挟撃できるかもしれない。
「皮肉ですね。あれだけ守っていた砦を、今度は襲撃しなければならないのですから」
ヴィオラの脳裏に浮かぶのは、マギア砦で怠惰の軍勢を相手にした、あの籠城戦だ。
巨人という歪虚を相手に、ハンターと各国の戦士達が力を合わせて戦い抜いた。あの戦いで人類側も多くの血を流す事となった。
だが、そのおかげでCAM稼働実験場を守り抜く事ができた。
ヴィオラは、その犠牲を今もしっかりと覚えている。
「マギア砦で散った者達が居たからこそ、私達は今日を迎える事ができました。
そして、今度は彼らの無念を我々が晴らす番です」
砦の壁をよじ登る梯子部隊も準備は完了。
マギア砦東の海岸にある隠し通路への突撃部隊も作戦開始を待ち続けている。
(敵が陽動部隊へ攻撃を仕掛けた時が――チャンスです)
ヴィオラは、西の方角へ視線を向ける。
間もなく、ガエルが陽動部隊へ攻撃を仕掛けるはず。
その間に――マギア砦を奪い返す。
「皆さん、参ります。
籠城戦で味わった雪辱……今日この場で果たしましょう」
ヴィオラは、動き出す。
目指す先は――マギア砦。
必ず奪い返す、と心に誓って。
試練の山にて

バタルトゥ・オイマト

ヴェルナー・ブロスフェルト
エンシンケ洞穴近くの森に布陣した二つの軍。
一つは、オイマト族の族長バタルトゥ・オイマト(kz0023)。
もう一つは要塞『ノアーラ・クンタウ』に駐留する第一師団分隊を率いるヴェルナー・ブロスフェルト(kz0032)。
「マギア砦の方は、作戦が開始している頃ですねぇ」
「…………」
ヴェルナーの言葉に、バタルトゥは沈黙で返す。
以前では考えらられなかった辺境部族と帝国軍の共闘。それが聖地奪還という目標を前にして為し得る事ができたのだ。
「しかし、今回の作戦を考えたのがあのシバさんですか。私も驚きを隠せません」
「……その割には……シバ老の扱いが良くないが……」
バタルトゥはヴェルナーへ視線を向ける事無く、そう呟いた。
シバが所属する山岳猟団は、先日攻撃命令が出ていないにも関わらずパシュパティ砦の襲撃。それ以前にも複数の命令違反を犯し、シバは審問隊『ベヨネッテ・シュナイダー』からの監視対象となっていた。
辺境の民から見れば、大きな功績を残しているのだが――。
「ええ。ですが、法は法です。シバさんにも『それなりの』対応はさせていただきます。ですが、今は目の前の事に集中するべきではありませんか?」
目の前の事。
それは先日テトの偵察により発覚した『怠惰指揮官のヤクシーがエンシンケ洞穴に潜んでいる』という事実だ。おそらく傷の療養でもしているのだろうが、人類側としてはこのチャンスを逃す訳にはいかない。
エンシンケ洞穴付近の巨人をCAMと魔導アーマーを主力とした前線部隊が襲撃。同時にファリフ・スコールら突撃部隊が一気にヤクシーを追い詰める。
そして、エンシンケ洞穴を足掛かりにして聖地リタ・ティトへ迫ろうというのだ。
「CAMと魔導アーマーの準備も完了。あなたの号令一つで、部族の誇りを賭けた聖戦が始まります。
……さあ、開戦の合図を!」
わざわざ舞台上のようなセリフ回しで進軍の号令を求めるヴェルナー。
その意図を怪しんだバタルトゥだったが、ここで手を止める訳にはいかない。
「……いくぞ……聖地までの道は、我等が切り拓く」

ファリフ・スコール
バタルトゥとヴェルナーが進軍した事を確認したファリフ・スコール(kz0009).
巨人とCAMの乱戦が繰り広げられる隙を突いて、エンシンケ洞穴に向かって走る。
テトの情報によれば、洞穴内は天井から光が漏れて中を照らしているらしい。おまけに既に洞穴内の地図も8割方完成している。
これならば、中で迷う可能性も低い。今から油断していたヤクシーに一撃をお見舞いするのが楽しみだ。
「族長、行きましょう! 聖地は俺達の手で取り返すんだ!」
スコール族の戦士がファリフに話し掛ける。
この数ヶ月間、ファリフは多くの人と知り合う事ができた。
そして、様々な事を教えられた。
スコール族を率いる重圧と責任。逃げ出したくなる時もあったが、必ず周りには支えてくれる仲間がいた。
「ハンターのみんなも、ボクに力を貸して!
リムネラの還る場所を、辺境のみんなにとって大切な場所を取り返す為に!」
ファリフは勢い良く洞穴へ飛び込んだ。
手にした斧で目の前の敵を弾き飛ばしながら、ひたすら奥へ向かって突き進む――。
「なんだって? 襲撃!?
馬鹿言ってんじゃないよ、敵はマギア砦じゃないのかい?」
ヤクシーは突然の出来事に混乱していた。
敵が今襲撃を仕掛けるとすればマギア砦の方だ。
何故、辺境でもまったく別方向のこのような場所を襲撃してきたのか。
そもそも、何故ここに自分が居る事が露見しているのか。
すべては人類を侮り、舐めてかかったヤクシーの驕りなのだが、その事を今のヤクシーは理解できないだろう。
「あー、もう!
考えるのも面倒くさい! 要するに、襲ってきた奴は全部ぶっ飛ばせばいいんだろう?」
ヤクシーは悩む事を放棄すると、愛用の鎌を手にした。
襲撃? だからなんだ。
敵は全部殺してやればいい。殺せば悩みも無くなって万事解決だ。
「マギア砦もナナミ川の時も奇襲ばっかりしやがって。正面から攻撃もできない臆病者の小さい奴らにあたしが負ける訳ないんだ。
……さぁ、今からあたしが出るよ。安心して逝っちまいな」
人類と怠惰による大きな戦が、始まった。
様々な思惑を呑み込みながら、戦乱は時代の転機を迎えようとしていた。
妄腕亡兵
ファリフにとっては不幸なことに、そしてヤクシーにとっては幸運というべきか、彼女たちは気付いていなかった。
ファリフ率いる部隊が次々と、突入していくエンシンケ洞窟を険しい視線で見つめる新たなる災厄の十三魔アイゼンハンダー(kz0109)の存在に。

アイゼンハンダー
成り行き上、怠惰を助けることになったアイゼンハンダーであったが、彼女の目的はあくまでもCAMや魔導アーマーの動向を探ることであり、あの後彼女は再びCAMの偵察に戻っていた。
だが、人類の攻勢が始まったのを見て、再び「友軍」が気になった彼女は居ても立ってもいられず、友軍の気配が集まっているエンシンケ洞窟へと駆けつけたのである。
「行こう。私が背後から仕掛ければ反徒どもを挟み撃ちに出来る。……ヤクシー殿と連携がとれなくても、最悪撤退支援は出来る筈だよ……!」
『だが、戦場が気に食わん。手狭に過ぎるわ』
義手からの声が応じた。
「大丈夫……軍医殿の新兵器なら、閉所での白兵戦にも十分対応出来るよ」と。
アイゼンハンダーが生身の手で握った柄が、マテリアルの刃を形成する。
『笑止。所詮は玩具。儂とお前が全力を出せば持たんのが見えている欠陥品よ……だが、まあ良い。確かにこのくらいは加減してやらねば、興も乗らぬか』
●聖地奪還、その真意(4月8日更新)
聖地奪還を掲げ動き出した人類は、エンシンケ洞穴及びマギア砦に対して同時攻撃を仕掛けた。
マギア砦の襲撃を陽動としながら、本命は敵指揮官ヤクシーが静養していたエンシンケ洞穴。ここを奪還して足掛かりとし、一気に聖地リタ・ティトへ王手をかける手筈となっている。
そして、初戦。
エンシンケ洞穴はヤクシーと災厄の十三魔アイゼンハンダーを取り逃がしながらも奪還に成功。マギア砦も多大なる損害を出しながらも奪還に成功していた。
辛勝ながらも二箇所の戦場で勝利を収めた人類。
だが、ここで一つの疑問が浮かぶ。
本当に聖地を奪還する事が辺境の結束に繋がるのだろうか。
確かに辺境部族の精神的支柱として聖地と白龍は存在している。だが、それらの要素を取り戻して結束を強めようとも辺境部族へ劇的な変化が訪れる事があるのだろうか。
そして、聖地奪還について各国首脳部は迷う事無く自国の戦力を送り込んできた。
――何故。
その謎の答えを持つ者は、辺境で彼らしかいない。


 「お師匠様っ、聞きましたにゃ!? 『なぞのいちだん』の話っ!」
「お師匠様っ、聞きましたにゃ!? 『なぞのいちだん』の話っ!」
「うむ……もはや事態は、一刻を争うやもしれん。かの一団が、我等の待ち人であれば、な」
パシュパティ砦で山岳猟団団員シバ(kz0048)と弟子のテト(kz0107)が何やら密談しているようだ。
シバは進行する怠惰の軍に対してマギア砦籠城戦やナナミ川撃滅戦を提案した人物である。今回の聖地奪還も彼が立案したものだ。
先程、人類側勝利の吉報がもたらされたのだが、その顔に笑顔は浮かんでいない。
「そんにゃ、まだ聖地も奪還してにゃいのに!
そもそもにゃんで今この時期に、わざわざ戦真っ盛りの赤き大地に出てくるですにゃ!? ぜんっぜん空気読めてにゃーですにゃ!」
「『彼等』に取っても想定外の結果であった……としたら、どうじゃ。歪虚共が転送を察し、妨げたとすれば。
これは、急がねばならんぞ。今頃、彼の地は……」
「なんだ、彼の地って?」
二人の密談に突如割って入った第三者。
テトが振り返れば、ドワーフ王ヨアキム(kz0011)の姿があった。
「にゃぎゃー、ひげもじゃ!?」
「お主か。どこから聞いておった」
「『お師匠様っ、聞きましたにゃ!?』からだな」
「最初から全部じゃにゃいですかー!」
「給仕の奴が食料をシバに届けてやれっていうから持ってきたんだが……なんか、とんでもねぇ話を聞いちまったみてぇだな」
いくらヨアキムが馬鹿の筆頭でも今の話を聞けば、聖地奪還の裏に何かある事は想像がつく。
何かを隠していると知ったヨアキムの顔は明らかにシバとテトを怪しんでいる。
「お師匠様……」
「よい。どの道、全て話さねばならぬ状況となった。
テト、今すぐスコールとオイマトの族長も呼べ。彼の地を救うのであれば、彼らの力も必要となる」
東方
「なに? 一体、どうしたの?」
「…………」
エンシンケ洞穴及びマギア砦から召喚されたファリフ・スコール(kz0009)とバタルトゥ・オイマト(kz0023)。
突然の召喚に詳細を知らされていない二人は、戸惑いを隠せなかった。

 「まあ、慌てるんじゃねぇ。連中にも準備ってもんがあるんだろ?」
「まあ、慌てるんじゃねぇ。連中にも準備ってもんがあるんだろ?」
「あれ? ヨワキムは何か知ってるの?」
「ヨアキムだ! 誰が貧弱そうな名前だ!
……ワシも良く知らん。だが、大事な話ってぇのは分かってる」
腕を組み、シバとテトを待つヨアキム。
先に到着していたヨアキムならば何か知っているだろうと期待したが、無駄のようだ。
仮に知っていたとしてもこいつは三歩歩けば重要情報も忘却の彼方だ。
「…………遅いな」
沈黙の中、バタルトゥが呟いた。
通された広間で待たされる事、数分。
バタルトゥとファリフは最前線から急いでパシュパティ砦へと駆け込んできた。
可能ならば再び前線へ戻って次なる戦いの準備をしたいところだが――。
「待たせたな、ご両人」
ようやく姿を現したシバ。その後ろにはテトが続いている。
二人の登場にファリフは安堵の表情を浮かべる。
「ああ、来たっ! 待ってたよ」
「……時間がない……話は手短に頼む」
ファリフと対象的にバタルトゥは、話を進めようとする。
こうしている間にもヤクシーがエンシンケ洞穴へ襲撃を仕掛ける可能性もあるのだ。心中穏やかではないのだろう。
だが、シバはその焦りをいとも簡単に見抜く。
「まあ、焦るな。ここに居る者には、この戦いの真実を話しておこうと思ってな」
「聖地奪還できれば、部族は巫女を象徴として一つに団結できるって言ってたけど……違うの?」
ファリフは、首を傾げる。
事前にシバから聞かされていた話では、聖地を奪還できれば中立的立場である巫女を象徴として部族会議を再出発する事が可能という話だった。
不思議そうな顔でシバを見つめるファリフ。
シバはその様子を見て小さく頷いた。
「それもまた真実。だが、真実はもう一つある。
おぬしら、東方について何処まで知っておる?」
「東方? 東方ってあれだろ?
大豆を固めて作った白くて四角い……」
「東方王国……東南が歪虚に飲まれるまでは、グラズヘイム王国とも交流を続けた古い国家だ……。独特の文化を持ち、舞刀士と呼ばれる戦士が歪虚と戦っていたはずだ……。150年前に辺境部族と交流が途絶えたはずだが……」
バタルトゥが東方王国についての知識を披露する。
かつては東方地域にて大きな勢力を誇っていた王国であったが、歪虚の侵攻により攻め滅ぼされている。東方から逃れてきた者達が辺境へ難民として訪れ、そのまま棲み着いた者達もいる。
さっきまで東方を別の物と勘違いしていたヨアキムが、バタルトゥの話を聞いてようやく東方の事を思い出した。
「ああ! その東方か。
あそこで作られた武具がたまに流通に乗るみてぇだが、うちの工房でも同じ物を作れる奴がいねぇんだよ。似た武具はできるんだが、あの技術がうちにあればみんなにも強ぇ武器を渡せるんだがなぁ」
「で、その滅んだ東方がどうしたの?」
ヨアキムの話が長そうだと判断したファリフが口を挟む。
そのファリフの問いにテトは答えるのだが、その内容は衝撃的なものであった。
「いいえ。東方は……未だ、滅んでおりませんにゃ」
「……シバ老、どういう事だ」
バタルトゥはシバの方へ向き直った。
「東方とは、通信が途絶えたのみ。彼等は歪虚の攻勢が西方に及ぶ事を懸念し、自ら精霊の力を介した連絡を断った。
しかし……その動きを知る手段が、一切無かった訳ではない」
「……『部族なき部族』」
はっとなったファリフの言葉に、テトが無言で頷いた。
部族なき部族……それはシバが率いるとされる、辺境部族の諜報組織の名だった。
「初めはシバ族。それが滅んでからは、部族なき部族が……断続的にではあるが、東方との交信を続けてきた。
自らの、足と命を使ってな」
シバによれば通信手段が途絶えた理由は歪虚の妨害が激しかった事が大きな要因だ。東方で激化する戦火が西方へ及ぶ事を懸念した結果だったようだ。それでも完全に途絶えさせる事を危惧してシバの部族と交流する事で情報を得ていたのようだが――。
「その東方へ行く転移門が聖地の大霊堂にあるにゃ。今は東方の歪虚が転移門を通って移動してくる事を懸念して白龍が閉じているって話にゃけど、ここを通れば東方を助ける事ができるにゃ」
テトが言うには、聖地リタ・ティトにある大霊堂には東方へ向かう転移門が存在しているという。
ここを通れば東方地域へ足を踏み入れる事ができるだろう。
テトの言葉に、シバは続ける。
「東方と手を結ぶ必要はあったが、同時に懸念もあった。『我等は、彼等と手を携えるに値する友か』と。
手を差し伸べる振りをして彼等を脅かし、盾や駒とする者が、我等の中に現れぬだろうかと」
「……」
シバの言う『我等』は、果たして誰から誰までを指したのだろうか。問う者は居ない。
「東方は、ここ西方のいずれの国とも対等でなければならぬ。
部族は、その橋渡しとなる。彼等と同じ窮地に立つ、赤き大地の子が」
シバは東方が大国の影に怯える立場となる事を危惧していた。その窮地を救うのは同じ境遇の辺境であり、お互いが助け合いながら危機に備えるべきだという。
「あれ? そういえばこの間、謎の一団が見つかったって言ってたけど、その集団ってもしかして……」
「東方から来たりし一団でございますにゃぁ」
ファリフが言っている集団とは、マギア砦とエンシンケ洞穴の間に突如現れた謎の集団である。
現在、彼らの正体について各国で調査の動きが出ていたのだが、既にシバとテトはその集団について情報を掴んでいたようだ。
「聖地奪還の件は東方へも伝えていた。あちらも独自の転送技術を用いて、加勢を送ってくれたのだろうが……剛毅というか、まぁ、無茶をする物よ」
「シバさんは人のこと言えないでしょう」
ファリフにつっこまれ、シバは苦笑して目を逸らした。
東方も辺境を案じて部隊を送り込んだのであろうが、シバによれば彼らは東方の地で歪虚と戦っていた戦士である可能性が高いという。だが、彼らがここにいる事は東方の防衛戦力が減少している事を意味する。
状況を把握したバタルトゥにも危険な状況である事が伝わったようだ。
「……彼らは東方の援軍であり……同時に救援を請う使者という訳か」
「左様。そして、儀式の手違いがあったようだ。戦場の真ん中に姿を現した。彼らと合流する為には、今の戦線を維持しながら合流を果たす他あるまい」
東方の集団が発見された位置から考えれば、今の戦線を維持する必要がある。
つまり、マギア砦とエンシンケ洞穴を防衛して戦線を維持。その後、東方の一団と合流して聖地奪還を目指さなければならないようだ。
「あー、もう! よう分からん!
早ぇ話、目の前の歪虚をぶっ倒して。そんで、聖地奪還してから東方の連中を助けりゃいいんだろ?」
馬鹿のヨアキムに懸かれば、どんな話も単純化。
しかし、だからこそ誰しもが分かる目標となる。
「今回は、ドワーフの王が賢いな。赤き大地の将来は聖地の奪還から始まる。
だが、まずは。目の前の敵を撥ね退けねばならん」
シバは、辺境の戦士達を前に満足そうな笑みを浮かべていた。
マギア砦の襲撃を陽動としながら、本命は敵指揮官ヤクシーが静養していたエンシンケ洞穴。ここを奪還して足掛かりとし、一気に聖地リタ・ティトへ王手をかける手筈となっている。
そして、初戦。
エンシンケ洞穴はヤクシーと災厄の十三魔アイゼンハンダーを取り逃がしながらも奪還に成功。マギア砦も多大なる損害を出しながらも奪還に成功していた。
辛勝ながらも二箇所の戦場で勝利を収めた人類。
だが、ここで一つの疑問が浮かぶ。
本当に聖地を奪還する事が辺境の結束に繋がるのだろうか。
確かに辺境部族の精神的支柱として聖地と白龍は存在している。だが、それらの要素を取り戻して結束を強めようとも辺境部族へ劇的な変化が訪れる事があるのだろうか。
そして、聖地奪還について各国首脳部は迷う事無く自国の戦力を送り込んできた。
――何故。
その謎の答えを持つ者は、辺境で彼らしかいない。

テト

シバ

ヨアキム
「うむ……もはや事態は、一刻を争うやもしれん。かの一団が、我等の待ち人であれば、な」
パシュパティ砦で山岳猟団団員シバ(kz0048)と弟子のテト(kz0107)が何やら密談しているようだ。
シバは進行する怠惰の軍に対してマギア砦籠城戦やナナミ川撃滅戦を提案した人物である。今回の聖地奪還も彼が立案したものだ。
先程、人類側勝利の吉報がもたらされたのだが、その顔に笑顔は浮かんでいない。
「そんにゃ、まだ聖地も奪還してにゃいのに!
そもそもにゃんで今この時期に、わざわざ戦真っ盛りの赤き大地に出てくるですにゃ!? ぜんっぜん空気読めてにゃーですにゃ!」
「『彼等』に取っても想定外の結果であった……としたら、どうじゃ。歪虚共が転送を察し、妨げたとすれば。
これは、急がねばならんぞ。今頃、彼の地は……」
「なんだ、彼の地って?」
二人の密談に突如割って入った第三者。
テトが振り返れば、ドワーフ王ヨアキム(kz0011)の姿があった。
「にゃぎゃー、ひげもじゃ!?」
「お主か。どこから聞いておった」
「『お師匠様っ、聞きましたにゃ!?』からだな」
「最初から全部じゃにゃいですかー!」
「給仕の奴が食料をシバに届けてやれっていうから持ってきたんだが……なんか、とんでもねぇ話を聞いちまったみてぇだな」
いくらヨアキムが馬鹿の筆頭でも今の話を聞けば、聖地奪還の裏に何かある事は想像がつく。
何かを隠していると知ったヨアキムの顔は明らかにシバとテトを怪しんでいる。
「お師匠様……」
「よい。どの道、全て話さねばならぬ状況となった。
テト、今すぐスコールとオイマトの族長も呼べ。彼の地を救うのであれば、彼らの力も必要となる」
東方
「なに? 一体、どうしたの?」
「…………」
エンシンケ洞穴及びマギア砦から召喚されたファリフ・スコール(kz0009)とバタルトゥ・オイマト(kz0023)。
突然の召喚に詳細を知らされていない二人は、戸惑いを隠せなかった。

ファリフ・スコール

バタルトゥ・オイマト
「あれ? ヨワキムは何か知ってるの?」
「ヨアキムだ! 誰が貧弱そうな名前だ!
……ワシも良く知らん。だが、大事な話ってぇのは分かってる」
腕を組み、シバとテトを待つヨアキム。
先に到着していたヨアキムならば何か知っているだろうと期待したが、無駄のようだ。
仮に知っていたとしてもこいつは三歩歩けば重要情報も忘却の彼方だ。
「…………遅いな」
沈黙の中、バタルトゥが呟いた。
通された広間で待たされる事、数分。
バタルトゥとファリフは最前線から急いでパシュパティ砦へと駆け込んできた。
可能ならば再び前線へ戻って次なる戦いの準備をしたいところだが――。
「待たせたな、ご両人」
ようやく姿を現したシバ。その後ろにはテトが続いている。
二人の登場にファリフは安堵の表情を浮かべる。
「ああ、来たっ! 待ってたよ」
「……時間がない……話は手短に頼む」
ファリフと対象的にバタルトゥは、話を進めようとする。
こうしている間にもヤクシーがエンシンケ洞穴へ襲撃を仕掛ける可能性もあるのだ。心中穏やかではないのだろう。
だが、シバはその焦りをいとも簡単に見抜く。
「まあ、焦るな。ここに居る者には、この戦いの真実を話しておこうと思ってな」
「聖地奪還できれば、部族は巫女を象徴として一つに団結できるって言ってたけど……違うの?」
ファリフは、首を傾げる。
事前にシバから聞かされていた話では、聖地を奪還できれば中立的立場である巫女を象徴として部族会議を再出発する事が可能という話だった。
不思議そうな顔でシバを見つめるファリフ。
シバはその様子を見て小さく頷いた。
「それもまた真実。だが、真実はもう一つある。
おぬしら、東方について何処まで知っておる?」
「東方? 東方ってあれだろ?
大豆を固めて作った白くて四角い……」
「東方王国……東南が歪虚に飲まれるまでは、グラズヘイム王国とも交流を続けた古い国家だ……。独特の文化を持ち、舞刀士と呼ばれる戦士が歪虚と戦っていたはずだ……。150年前に辺境部族と交流が途絶えたはずだが……」
バタルトゥが東方王国についての知識を披露する。
かつては東方地域にて大きな勢力を誇っていた王国であったが、歪虚の侵攻により攻め滅ぼされている。東方から逃れてきた者達が辺境へ難民として訪れ、そのまま棲み着いた者達もいる。
さっきまで東方を別の物と勘違いしていたヨアキムが、バタルトゥの話を聞いてようやく東方の事を思い出した。
「ああ! その東方か。
あそこで作られた武具がたまに流通に乗るみてぇだが、うちの工房でも同じ物を作れる奴がいねぇんだよ。似た武具はできるんだが、あの技術がうちにあればみんなにも強ぇ武器を渡せるんだがなぁ」
「で、その滅んだ東方がどうしたの?」
ヨアキムの話が長そうだと判断したファリフが口を挟む。
そのファリフの問いにテトは答えるのだが、その内容は衝撃的なものであった。
「いいえ。東方は……未だ、滅んでおりませんにゃ」
「……シバ老、どういう事だ」
バタルトゥはシバの方へ向き直った。
「東方とは、通信が途絶えたのみ。彼等は歪虚の攻勢が西方に及ぶ事を懸念し、自ら精霊の力を介した連絡を断った。
しかし……その動きを知る手段が、一切無かった訳ではない」
「……『部族なき部族』」
はっとなったファリフの言葉に、テトが無言で頷いた。
部族なき部族……それはシバが率いるとされる、辺境部族の諜報組織の名だった。
「初めはシバ族。それが滅んでからは、部族なき部族が……断続的にではあるが、東方との交信を続けてきた。
自らの、足と命を使ってな」
シバによれば通信手段が途絶えた理由は歪虚の妨害が激しかった事が大きな要因だ。東方で激化する戦火が西方へ及ぶ事を懸念した結果だったようだ。それでも完全に途絶えさせる事を危惧してシバの部族と交流する事で情報を得ていたのようだが――。
「その東方へ行く転移門が聖地の大霊堂にあるにゃ。今は東方の歪虚が転移門を通って移動してくる事を懸念して白龍が閉じているって話にゃけど、ここを通れば東方を助ける事ができるにゃ」
テトが言うには、聖地リタ・ティトにある大霊堂には東方へ向かう転移門が存在しているという。
ここを通れば東方地域へ足を踏み入れる事ができるだろう。
テトの言葉に、シバは続ける。
「東方と手を結ぶ必要はあったが、同時に懸念もあった。『我等は、彼等と手を携えるに値する友か』と。
手を差し伸べる振りをして彼等を脅かし、盾や駒とする者が、我等の中に現れぬだろうかと」
「……」
シバの言う『我等』は、果たして誰から誰までを指したのだろうか。問う者は居ない。
「東方は、ここ西方のいずれの国とも対等でなければならぬ。
部族は、その橋渡しとなる。彼等と同じ窮地に立つ、赤き大地の子が」
シバは東方が大国の影に怯える立場となる事を危惧していた。その窮地を救うのは同じ境遇の辺境であり、お互いが助け合いながら危機に備えるべきだという。
「あれ? そういえばこの間、謎の一団が見つかったって言ってたけど、その集団ってもしかして……」
「東方から来たりし一団でございますにゃぁ」
ファリフが言っている集団とは、マギア砦とエンシンケ洞穴の間に突如現れた謎の集団である。
現在、彼らの正体について各国で調査の動きが出ていたのだが、既にシバとテトはその集団について情報を掴んでいたようだ。
「聖地奪還の件は東方へも伝えていた。あちらも独自の転送技術を用いて、加勢を送ってくれたのだろうが……剛毅というか、まぁ、無茶をする物よ」
「シバさんは人のこと言えないでしょう」
ファリフにつっこまれ、シバは苦笑して目を逸らした。
東方も辺境を案じて部隊を送り込んだのであろうが、シバによれば彼らは東方の地で歪虚と戦っていた戦士である可能性が高いという。だが、彼らがここにいる事は東方の防衛戦力が減少している事を意味する。
状況を把握したバタルトゥにも危険な状況である事が伝わったようだ。
「……彼らは東方の援軍であり……同時に救援を請う使者という訳か」
「左様。そして、儀式の手違いがあったようだ。戦場の真ん中に姿を現した。彼らと合流する為には、今の戦線を維持しながら合流を果たす他あるまい」
東方の集団が発見された位置から考えれば、今の戦線を維持する必要がある。
つまり、マギア砦とエンシンケ洞穴を防衛して戦線を維持。その後、東方の一団と合流して聖地奪還を目指さなければならないようだ。
「あー、もう! よう分からん!
早ぇ話、目の前の歪虚をぶっ倒して。そんで、聖地奪還してから東方の連中を助けりゃいいんだろ?」
馬鹿のヨアキムに懸かれば、どんな話も単純化。
しかし、だからこそ誰しもが分かる目標となる。
「今回は、ドワーフの王が賢いな。赤き大地の将来は聖地の奪還から始まる。
だが、まずは。目の前の敵を撥ね退けねばならん」
シバは、辺境の戦士達を前に満足そうな笑みを浮かべていた。
(執筆:近藤豊)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●王女、戦地へ(4月13日更新)
●自室/システィーナ様の楽しみ
「ふぅーむ。なるほどー」
 侍従長マルグリッド・オクレールの見守る先で、システィーナ・グラハム(kz0020)は訳知り顔でその報告書を読んでいた。
侍従長マルグリッド・オクレールの見守る先で、システィーナ・グラハム(kz0020)は訳知り顔でその報告書を読んでいた。
いかにも裏の裏まで察していますと言わんばかりの態度だが、その実、初見では大して理解できていないであろうことはバレバレである。そしてそれがにやけそうな顔を誤魔化すためであることも。
「……システィーナ様、報告書が溜まっております。多くは既にセドリック様が採決したものでございますが、先にそれらに目を通した方がよろしいのでは?」
「う。そう、ですよね……」
王女は名残惜しむようにその――【王国展】の報告書や、その後一ヶ月余の地方経済の動向等が記された資料を机に戻す
手早くオクレールが王女の身支度を整えると、小さな王女は後ろ髪を引かれる思いを断つように大股で執務室へ向かった。
●執務室/わたくしのせんそう
システィーナが扉を開くと、そこには大司教セドリック・マクファーソン(kz0026)と王国騎士団団長エリオット・ヴァレンタイン(kz0025)が仁王立ちしていた。
侍従長と共に入室し、恐る恐る席に座る。机に置かれていた報告書を手に取った。

 「辺境における現在の戦況です、王女殿下」
「辺境における現在の戦況です、王女殿下」
大司教の説明。簡潔に書かれたそれは、実際の戦場などほぼ知らないシスティーナでも理解できるほど分かりやすい。
騎士団長が感触を口にする。
「状況は悪くありません。伝令の離脱後もおそらくそのまま押せているはず」
「そう、ですか……被害は……」
「……、許容範囲内かと」
誠実な騎士団長は僅かに顔を伏せ、できるだけ婉曲的に真実を告げた。
大司教が咳払いして引き継ぐ。
「改めて申しておきますが、殿下、騎士団はこれ以上出せません。貴族連中の頑張り次第で王国軍編成はできるかもしれませんがね」
「分かって、います……」
「騎士団長、今後どうなる?」
「敵の反攻作戦が気がかりです。怠惰は直情径行な性質故、押され続けるのは我慢ならない。指揮官がそれを制御し作戦に組み込めば相当な反攻となるでしょう」
「そうか」大司教が何ごとか試すように、「如何致しますか、王女殿下」
「……わたくしは」 システィーナが二人の男を見上げる。無表情の大司教と、目元に疲労を感じさせる騎士団長。ごめんなさいと呟き、
「わたくしは……できうる限りの救援を送りたい、です」
「『具体的に何を行い、また如何なる理由でそうするのか』、お教えいただけますか?」
「こ、後方支援を……物資、救護……少しでも多くの……。理由は……これを機に辺境部族への影響力を……」
しどろもどろになりながら咄嗟にでっち上げるシスティーナ。
じっと見据えてくる大司教の視線が痛い。が、ほんの一瞬、厳しかった口元が緩んだ――気がした。
「は、仰せのままに。救援物資は城の備蓄から回しましょう。覚醒者に持たせてリゼリオ経由でノアーラ・クンタウへ転移、現地で荷馬車を調達して運び込みます。これなら最低限の人数、ごく短時間の拘束で済む」
「……人員を確保してまいります」
騎士団長の表情は険しい。システィーナはいたたまれずに机に目を落とした。
自分も転移門を使えれば手伝えるのに。
我知らず小さな手を握り締め――ふとソレに思い至った。
「わ、わたくしがっ、わたくしも手伝います……!」
「……は?」
「覚醒者のオクレールさんと一緒なら転移門を使えます! 転移して運ぶなら一人でも多い方がいいですよね?」
唖然。ぽかんと口と目を開いた騎士団長は珍しく慌てて諫めんとし――それを、大司教が腕で制した。
「なるほど面白い。この際、侍従隊員も総動員してみては?」
「な!? 何を言っているのか分かっておられるのか大司教!? 向こうは主戦場が北上したとはいえ未だ全域が戦場、そんな場所に……」
「騎士団長。向こうには『助けを待つ集団』がいるのだ! そして殿下は自ら助けたいと願った。なれば我々が為すべきは万全の手はずを整えること!! 『それ』が分からぬ男ではあるまい?」
「大司教さま……っ」
システィーナは救われたような思いで大司教を仰ぎ見る。対して騎士団長はこれでもかと苦りきった渋面――だったが、やがて諦めたように眉間の皺を深くして嘆息した。
大司教が重ねて、
「『分かっているな。助けを待つ“集団”だ』」
「……なれば俺も行きます。侍従隊と俺が物資を運び、殿下の周りを固める」
「ほう、それはいい。ではついでに辺境部族に馬など贈るのは如何か。相手は任せるがね。ハンター向けに調教したゴースロン種がいただろう。
殿下。殿下であればきっと友好な関係を築けましょう」
「は、はい……がんばりますっ……!」
何やら険悪な雰囲気に尻込みしつつも、システィーナはぐっと気合を入れる。大司教の背後、騎士団長と同様の表情をした侍従長が見え、間髪入れず目を背けた。怖い。
騎士団長が無理矢理抑えたような声色で、
「……大司教、貴方が俺の剣を見る日が来ないことを祈ります」
「私はエクラの下僕なのだ。故に王国が王国である限り、私は王国の下僕だよ。これまでも、そしてこれからも」
かくしてシスティーナ・グラハムは初めて辺境の大地を踏んだ。
人類の最前線を、支える為に。
「ふぅーむ。なるほどー」

システィーナ・グラハム
いかにも裏の裏まで察していますと言わんばかりの態度だが、その実、初見では大して理解できていないであろうことはバレバレである。そしてそれがにやけそうな顔を誤魔化すためであることも。
「……システィーナ様、報告書が溜まっております。多くは既にセドリック様が採決したものでございますが、先にそれらに目を通した方がよろしいのでは?」
「う。そう、ですよね……」
王女は名残惜しむようにその――【王国展】の報告書や、その後一ヶ月余の地方経済の動向等が記された資料を机に戻す
手早くオクレールが王女の身支度を整えると、小さな王女は後ろ髪を引かれる思いを断つように大股で執務室へ向かった。
●執務室/わたくしのせんそう
システィーナが扉を開くと、そこには大司教セドリック・マクファーソン(kz0026)と王国騎士団団長エリオット・ヴァレンタイン(kz0025)が仁王立ちしていた。
侍従長と共に入室し、恐る恐る席に座る。机に置かれていた報告書を手に取った。

セドリック・マクファーソン

エリオット・ヴァレンタイン
大司教の説明。簡潔に書かれたそれは、実際の戦場などほぼ知らないシスティーナでも理解できるほど分かりやすい。
騎士団長が感触を口にする。
「状況は悪くありません。伝令の離脱後もおそらくそのまま押せているはず」
「そう、ですか……被害は……」
「……、許容範囲内かと」
誠実な騎士団長は僅かに顔を伏せ、できるだけ婉曲的に真実を告げた。
大司教が咳払いして引き継ぐ。
「改めて申しておきますが、殿下、騎士団はこれ以上出せません。貴族連中の頑張り次第で王国軍編成はできるかもしれませんがね」
「分かって、います……」
「騎士団長、今後どうなる?」
「敵の反攻作戦が気がかりです。怠惰は直情径行な性質故、押され続けるのは我慢ならない。指揮官がそれを制御し作戦に組み込めば相当な反攻となるでしょう」
「そうか」大司教が何ごとか試すように、「如何致しますか、王女殿下」
「……わたくしは」 システィーナが二人の男を見上げる。無表情の大司教と、目元に疲労を感じさせる騎士団長。ごめんなさいと呟き、
「わたくしは……できうる限りの救援を送りたい、です」
「『具体的に何を行い、また如何なる理由でそうするのか』、お教えいただけますか?」
「こ、後方支援を……物資、救護……少しでも多くの……。理由は……これを機に辺境部族への影響力を……」
しどろもどろになりながら咄嗟にでっち上げるシスティーナ。
じっと見据えてくる大司教の視線が痛い。が、ほんの一瞬、厳しかった口元が緩んだ――気がした。
「は、仰せのままに。救援物資は城の備蓄から回しましょう。覚醒者に持たせてリゼリオ経由でノアーラ・クンタウへ転移、現地で荷馬車を調達して運び込みます。これなら最低限の人数、ごく短時間の拘束で済む」
「……人員を確保してまいります」
騎士団長の表情は険しい。システィーナはいたたまれずに机に目を落とした。
自分も転移門を使えれば手伝えるのに。
我知らず小さな手を握り締め――ふとソレに思い至った。
「わ、わたくしがっ、わたくしも手伝います……!」
「……は?」
「覚醒者のオクレールさんと一緒なら転移門を使えます! 転移して運ぶなら一人でも多い方がいいですよね?」
唖然。ぽかんと口と目を開いた騎士団長は珍しく慌てて諫めんとし――それを、大司教が腕で制した。
「なるほど面白い。この際、侍従隊員も総動員してみては?」
「な!? 何を言っているのか分かっておられるのか大司教!? 向こうは主戦場が北上したとはいえ未だ全域が戦場、そんな場所に……」
「騎士団長。向こうには『助けを待つ集団』がいるのだ! そして殿下は自ら助けたいと願った。なれば我々が為すべきは万全の手はずを整えること!! 『それ』が分からぬ男ではあるまい?」
「大司教さま……っ」
システィーナは救われたような思いで大司教を仰ぎ見る。対して騎士団長はこれでもかと苦りきった渋面――だったが、やがて諦めたように眉間の皺を深くして嘆息した。
大司教が重ねて、
「『分かっているな。助けを待つ“集団”だ』」
「……なれば俺も行きます。侍従隊と俺が物資を運び、殿下の周りを固める」
「ほう、それはいい。ではついでに辺境部族に馬など贈るのは如何か。相手は任せるがね。ハンター向けに調教したゴースロン種がいただろう。
殿下。殿下であればきっと友好な関係を築けましょう」
「は、はい……がんばりますっ……!」
何やら険悪な雰囲気に尻込みしつつも、システィーナはぐっと気合を入れる。大司教の背後、騎士団長と同様の表情をした侍従長が見え、間髪入れず目を背けた。怖い。
騎士団長が無理矢理抑えたような声色で、
「……大司教、貴方が俺の剣を見る日が来ないことを祈ります」
「私はエクラの下僕なのだ。故に王国が王国である限り、私は王国の下僕だよ。これまでも、そしてこれからも」
かくしてシスティーナ・グラハムは初めて辺境の大地を踏んだ。
人類の最前線を、支える為に。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●死者の機甲師団(4月17日更新)

アイゼンハンダー
辺境、恐らくはジグウ連山のどこかにある険しい斜面でアイゼンハンダーは心配そうに遠くを睨んでいた。
『護衛はもう良いと言ったのは彼奴自身だ。ここで斃れるようなら、儂とお前が手を貸す価値もない弱卒に過ぎなかったというだけの事よ』
「……いつも通りだね」
既に興味をなくしたといわんばかりの義手からの声に寂しそうに笑うと、アイゼンハンダーは再び心配そうな表情に戻った。
「オルクス兵長たちはどこに……? 合流ポイントはここの筈なのに」
『それこそ心配無用だ。あのお方たちが……』
義手が言い終わらぬうちに、突如巨大な影が空を横切る。
「リンドヴルム!」
アイゼンハンダーが嬉しそうに叫ぶ。
直後、頭上を通過するリンドヴルムから、火花と共に複数の輸送コンテナが切り離された。
それらはほぼ正確に、アイゼンハンダーの周囲に落下する。
そして、その内の一つは着地と共に展開し、満載された禍々しい銃火器の数々を広げて見せた。
「兵長たちからの補給物資だよ! すごい……散弾銃にシュツルムファウスト、爆導索まである!」
『ツィカーデよ、アレは何だ』
義手の声に、ふと空を見上げたアイゼンハンダーの頭上に、ひらひらと一枚の手紙が舞い降りて来た。
そこに書かれていたのは次のような文章だった。
アイゼンハンダーちゃん江
はぁい、元気にしてるかしらぁ? 待ち合わせの場所に行けなくてごめんねぇ。
実はぁ、コッチに来る途中でにんげ……革命軍が面白そうなモノを運んでいるのを見つけちゃってナイトハルトや私、それに他のコたちもそっちに構いっきりなのよぉ。
お詫びに、新しいオモチャをプレゼントするから許してねえ♪
オルクス兵長より
手紙には、印の代わりにキスマーク(青色)がつけられていた。
「ナイトハルト師団長に、他の兵長たちまで! これだけの戦力がそろえば……!」
鋼鉄の義手でガッツポーズを取るアイゼンハンダーの背後で、残りのコンテナが次々と開いていく。
やがて、朽ちた鋼鉄の身体を固定していたボルトが爆砕され、一体また一体と動き出した改造ゾンビがアイゼンハンダーの前で隊列を組んでいく。
いや、全てが統一された規格で改造されたそれは、もはや機械に近い。
動力源となる、朽ち果てた暴食の歪虚を収めた棺桶のような胴体。
そこに接続された鋼鉄の四肢。装備された様々な機構は本来下級の歪虚に過ぎない動く死体たちに、想像を絶する動きを可能とさせるだろう。
「行こう!」
およそ、人間はおろか覚醒者でさえ保持することが不可能な大量の火器を全て装備したアイゼンハンダーが駈ける。
『何処へ向かうつもりだ? ツィカーデよ』
「この装備は拠点強襲用……襲撃する場所は一つしかないよ! 革命軍の目的はこの地方の制圧。あそこを襲えばヤクシー殿の援護にも繋がる!」
なおも加速するアイゼンハンダー。恐るべきことに、改造ゾンビの群れは遅れることなくアイゼンハンダーに追随してくる。
「凄い……これまでの戦闘データーがしっかりフィードバックされている!」
そして、アイゼンハンダーは正面を見据える。
「待っていろ、革命軍……! この強襲型装備と、軍医殿の新兵器であるアメイジングレッドショルダーズで、お前たちの前線基地を壊滅させてやる……!」
悍ましき死者の機甲師団が山を下るにつれて、濃くなっていく霧の中、ただ赤く染め抜かれた改造ゾンビの右肩の装甲のみが、鈍く輝いて蠢いていた。
(執筆:稲田和夫)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●聖地(4月23日更新)
ささやかな酒宴
辺境の奥深くへと分け入る前線の健闘を祈りつつ、CAM実験場ではささやかな酒宴が開かれた。
その最中、同盟陸軍所属でCAM操縦部隊「特機隊」の隊長、ダニエル・コレッティ(kz0102)は直属の部下たちに声をかける。
「さて、食った分は働かないとねぇ」
周囲を見渡せば、ハンターと避難民が混じって楽しく会食中なので、ダニエルは隊員の耳元に小声で話しかけた。
そこへ巨体を揺らし、同盟海軍所属のモデスト・サンテ(kz0101)が近づく。彼は万が一に備えて、素面のままでいた。
「よし、そろそろ作戦会議に向かうぞ……ってダニエル貴様、酒を飲んだな!」
「あれ、こんなに楽しいお酒なのに飲んでないの? 白熊提督はもったいないことしましたなぁ?」
ニヒルな笑みを浮かべるダニエルは、恨めしそうに睨むモデストをおちょくった。
「勝利の美酒は寝かせておくのが一番なんだ。普段は戦わんお前には、この感性がわからんだろうな」
「なら、ここに迫る敵を追っ払ったら、俺がとっておきの酒を差し上げますよ」
この時、ダニエルは一瞬だけ真剣な眼差しを提督に向けた。モデストはそれを見て、大きくひとつ頷くのだった。
CAM実験場が戦火に包まれるやも知れぬという懸念は、すでに同盟軍内で検討されていた。
この地は今や、聖地奪還における拠点。さらには東方王国からの使者との連携をも担っている。
いくら辺境の状況に暗い歪虚だとしても、ここを「真っ先に潰すべき場所」くらいには認識しているだろう。
だから酒宴から離れた天幕において、同盟軍の面々はしかめっ面を並べて、敵の侵攻への備えを話し合っていた。
「特機隊はもちろんだが、CAMや魔導アーマーは敵の出鼻を挫くのが最優先事項だ。しっかり頼むぞ」
モデストがそう言えば、ダニエルも続ける。
「どんな敵が攻めてこようと、こちらにとってはあまり関係ない。最悪、モデスト少将が兵力をまとめて拠点の外に陣取る時間さえ稼げればいい。それ以上もそれ以下も必要ない。ここ、重要ね」
戦況を聞けば、どこも余裕はない。もし帰還する際に敵が立ち塞がっていようものなら、目を覆わんばかりの被害が予想される。それだけは避けなければならない。
「実験場を防衛する者は、避難民や怪我人は長城付近まで下がらせろ。あとは敵の出方次第だ」
あごに手をやりつつ地図を見るモデストは、「うーん」と唸ってみせた。
「昼行灯、他に言うことは?」
普段は飄々としているが、実は切れ者と名高いダニエルに、モデストは意見を求める。
「まぁ、あんまりビックリしないことかな。いろんなことに」
えらくザックリしたアドバイスに、モデストは眉をひそめるのであった。
巫女の想い
 ――息が詰まる。
――息が詰まる。
リムネラ(kz0019)は無意識にそう感じていた。
現在、彼女はリゼリオで、ハンターたちの成功と聖地の無事を祈り、ユニオン内の礼拝室で祈りを捧げている。
無論そこから動かないわけではない。『ガーディナ』リーダーとしてハンターに出来る限りのことは尽くしている。しかし、祈りたくもなるというものだ。
自分は立場上、前線に経つことは出来ない。
だからこそ、ここで祈りを捧げるのだ。
ハンターたちのことと――そして、聖地のことと。
この前の演説で、リムネラには言えなかったことがある。
それは――聖地の白龍の、いのちの灯火が消えかかっているということだ。
もともと彼の地の白龍は、聖地に歪虚が侵攻するのを押しとどめてくれていた。しかし、白龍とて不老不死の存在ではない。己の持っている力を使い果たしたりすれば、死んでしまう。
事実、聖地の白龍というのは、一度代替わりをしているのだという。
更に加えていうと、聖地の白龍はもう若くない。
リムネラの側にいてくれるヘレはまだ幼いが、聖地の白龍は――限界が近いのだ。
白龍に限らず、ドラゴンという存在が特別視されるのは誰もがわかることと思う。何故そんなに特別視されるのかというと、その持てる膨大な知識とマテリアルの量、さらに成長するまでの期間が人の一生よりも遙かに長いことが挙げられる。もっとも、これらは一般的に知られていることかというとそうでもないのだが……。
ただ、そんな膨大な知識と永い寿命をあわせ持った白龍である。もしかすると――ハンターたちの知らない情報を持ち合わせているかも知れない。
歪虚とはなんたるか、とか。
そして、最近ちらほらと耳にする、『東方』のこと、とか。
ヘレは見た目通り、まだ幼い。巫女の代表たる大巫女がリムネラに託したくらいだ、まだかわいいペットという認識のほうが強いだろう。
しかし聖地の白龍は、今の人間たちが知り得ないだろう情報を持っている可能性が、非常に高いのだ。
特に聖地で過ごしている白龍ならば、その情報量は想像が付かない。
白龍に尋ねることが出来れば、それらの答えはすべてではないにしろ、聞き出せるのではないだろうか。
そう考えていくと、自分の想像以上に白龍という存在は大切なのではないだろうかと、リムネラは思う。
(大巫女様……)
リムネラは、跪いて祈る。
口からは、祈りの言の葉がこぼれていく。
彼女はもともと、辺境のとある一部族の出身の普通の少女だった。しかし神託を受け、聖地に入ってからもうずいぶん経つ為、聖地の巫女たちが家族と言って過言ではない。
そう、聖地というのはリムネラと同様に神託を受けた上で特別な力を授かったとされたものたちが、生まれついた部族をでて――ある意味言葉は悪いが捨て、巫女となる修行を積む場所なのだ。
巫女というのはそれらの特殊の修行を積んだものたちを総称して呼ぶ単語なのだ。そんなわけで、『巫女』という名称ではあるが当然男性も存在する。
――初めて大巫女に会った時、リムネラは本当に幼かった。
しかし、大巫女は巫女としてのリムネラの資質を一目で見抜き、そしてここまで育ててくれた大事な存在だ。リムネラにとっては、まるで実の祖母のような存在でもある。
だから、というわけではない。しかし、巫女も、白龍も、今の辺境や聖地、ひいてはこのクリムゾンウェストに欠かすことの出来ない存在なのではないだろうかと、考えてしまう。
だからこそ、少女は祈る。
聖地の無事を。
仲間たちや、あの優美な白龍に再会できることを。
いや――
……信じなければ、いけないのだった。
 様々な思惑が駆け巡る聖地奪還であったが、ここにきて歪虚側も人類の狙いが見えてきた。
様々な思惑が駆け巡る聖地奪還であったが、ここにきて歪虚側も人類の狙いが見えてきた。
「そうか……小さい連中は、ビャスラグ山の大霊堂が狙いかい」
怠惰侵攻軍を指揮するヤクシーは、人類側の侵攻ルートを整理していた。
ヤクシーは……いや、歪虚達は、侵略者たる自らの本能を以って直感していた。
人類のエンシンケ洞窟襲撃は、ヤクシーの首を狙っての物ではない、と。
「狙いは洞窟の先の、あのクソ聖地や大霊堂か。その為に奴らマギア砦にまで陽動出して、あたしらはまんまとハマった……
小賢しい、クソ小賢しい……だけどねぇ」
ヤクシーは、右手の大鎌を振るう。
一閃した刃は、空気を震動。周囲に強大な殺気を撒き散らす。ヤクシーの表情は――怒りに満ち溢れていた。
「初めからあたしの事は眼中になかったって事かい? 上等だよ。
マギア砦のガエルに緊急の連絡だ。全力で奴らの実験場とかいう場所を攻めるんだ。容赦するなって言っておきな。それから……」
ヤクシーは一呼吸置いた後、ある歪虚の名前を口にする。
一部の辺境部族において忌むべき名とも言える者の名前を。
「もう一度、ハイルタイを呼べ。面倒だ、なんて言っても引っ張ってくるんだよ!」
●



 パシュパティ砦で指揮中継に臨むシバ(kz0048)は、辺境の地図を前に腕を組み、深く溜息を吐いた。
パシュパティ砦で指揮中継に臨むシバ(kz0048)は、辺境の地図を前に腕を組み、深く溜息を吐いた。
「敵は……正面からの力比べを望んだか」
それは、異例とも言える、怠惰からの申し入れ。
聖地とCAM稼働実験場を賭けてどちらが先に攻略できるか、勝負だ……と、ヤクシーが律儀にも人類へ声明を出したのだ。
「あのおばちゃん、よっぽど悔しかったのかな。もう、怠惰って言う感じが全然しないけど」
スコール族のファリフ・スコール(kz0009)は、何気なしに呟いた。
ハンターの協力もあって聖地奪還は人類に優勢。着実に聖地へと近付いている。ファリフにも若干の余裕が見え始めていた。
「スコールの族長よ。事態は急変しておる。我らにそのような余裕はないぞ」
シバに諭され、ファリフは微かに狼狽えた。
「ええっと……ボクたち、ちゃんと怠惰やっつてけるし、それに東方の人達も助けてくれるんだよね。それでも……?」
聖地とマギア砦の間に現れた謎の集団は、東方より現れた使者であった。
先の戦いで戦線後退を避ける事ができた為、以前から連絡を取っていたシバがコンタクトに成功。東方の使者達も聖地奪還を支援してくれる事になっていた。
「怠惰に聖地奪還の目的を悟られた……そこが、問題だ……敵が、聖地付近の防御を固めてくる……と。違うか、シバ老……」
オイマト族のバタルトゥ・オイマト(kz0023)の言葉に、シバは頷く。
東方より援軍が来たことで、かの地と繋がる聖地が人類の目的と悟られた可能性は、シバも考慮していた。
だが、怠惰側の対処がここまで早く、また大胆であるとは、その名前から誰が想像できようか。
「でも、稼働実験場の前にはマギア砦があるよ。あいつらは先に、砦を落とさなくちゃいけないんじゃない?」
ファリフは、人類に置かれた戦況を口にする。
現在、マギア砦は人類が奪還。占領していたガエル・ソトの撃退に成功しており、仮にガエルが稼働実験場を攻撃するためにはマギア砦の横を通過して南下しなければならない。マギア砦でガエルを足止めできれば、人類は聖地奪還に注力すればいい。 しかし、シバは頭を横に振る。
「忘れたか、スコールの長。十三の闇が赤き大地に這っておる」
「災厄の……十三魔か」
人類と怠惰の戦いが繰り広げられる辺境において、幾度も乱入を試みる者達がいた。
強力な戦力を単騎で持ち、状況によっては戦況をひっくり返しかねない相手だ。先の戦いでもアイゼンハンダーがエンシンケ洞穴を襲撃している。
「稼働実験場には防衛戦力を残さねばなるまい。だが……聖地奪還の大仕事、これだけはお主達に託さねばならぬ。その意味がわかるか?」
ファリフ・スコール。
バタルトゥ・オイマト。
かつて帝国への服従を巡り、部族会議では立場を異にした両者。
だが、二人はそれぞれの立場と問題を乗り越え、怠惰と戦ってきた。
その二人が顔を見合わせ、何かを言いかけた時……
「大変ですにゃ?! ゴチューシンですにゃ!」
紡がれ掛かる言葉を遮って、部族なき部族のテト(kz0107)が駆け込んできた。
「落ち着かんかい、騒々しい」
「ぜ、前線の斥候より入伝ですにゃ! 騎馬に乗って弓を携えた巨大な歪虚が聖地付近へ接近中との報告! 『あいつ』……大霊堂へ向かってますにゃ!」
巨大な馬に弓を携えた歪虚。
その存在を、彼等は知っていた。
そして、出会ってもいた。
強力な弓を操る災厄の十三魔の一人――。
「ハイルタイ……奴は、聖地に」
「バタルトゥさん……」
傍らに立つバタルトゥの身を案じたファリフ。
ハイルタイの名前を聞いた瞬間、ファリフはバタルトゥが身を震わせた事に気が付いていた。
●
 ――時間は、少し前まで遡る。
――時間は、少し前まで遡る。
「だから、なんでまたワシがここで戦わねばならんのだ! もう働いたのだから良いではないか」
眠っていたところを叩き起こされたハイルタイは不機嫌だった。
元々、聖地奪還に強い興味もない。言われて渋々戦っていただけだ。今回、ヤクシーに召還されたのもロクな理由じゃない――そう考えていた。
「悪いねぇ。だけど、あんたじゃなけりゃできない仕事なんだよ」
「ワシは働きたくないぞ。働いたら負けじゃ」
「まあ、そう言うなって。
この山、覚えてるだろ? 小さい奴らが聖なる山って呼んでる場所だ」
ヤクシーは、山を見上げる。釣られてハイルタイも首を上に向ける。山の上では雪が風に舞い、忙しそうに飛び回っている。
「確かそんなような……そうでないような……」
「この山には聖地と呼ばれる場所があって、そこに大霊堂ってぇのがあるんだ」
大霊堂。
その一言を聞いた瞬間、ハイルタイの眉が釣り上がる。
「思い出したぞ! 白い龍が見えない壁をこしらえせえで、ワシはそこへ行けなかったんじゃ! せっかくよく眠れそうな洞窟だったのに!」
ハイルタイは珍しく興奮してみせた。
歪虚が未だに聖地を制圧できなかったのは白龍の加護があったからだ。白龍が自らのマテリアルを使って結界を張り、歪虚の聖地侵攻を防いでいたのだ。
「お怒りはごもっとも。だけど、その壁が壊せるって知ったらどうする?」
「なに!?」
振り返るハイルタイ。
普段は怠けているだけの髭ダルマだが、眠りやすい洞窟の前ではテンションもアップするようだ。
「ど、どど、ど、どういう事だ!?」
「焦らなくてもいいよ。あの白い龍、寿命が近いみたいでね。結界が以前よりも薄くなっているんだ。あたしの鎌じゃまだ厳しいけど、ハイルタイの矢を何発か叩き込めば……」
「結界は壊れる、という訳じゃな? なるほど……」
満足そうな笑みを浮かべるハイルタイ。
大霊堂を新たな住処にすべく、本気を出してくれるようだ。
実はヤクシーも結界を破壊する事は可能だ。だが、ハイルタイが聖地を攻略してくれれば、その間ヤクシー自身が聖地付近に集まる人類を蹂躙する時間を作る事ができる。
単に聖地を潰しても面白くない。
馬鹿にしてくれた連中に、たっぷり仕返しをしてやらないと――。
「そういうこった。
まあ、大霊堂へ突入してたっぷり『白蛇』退治を堪能するんだね」
東方よりの援軍
 「ここから先は雪道。みんな、滑り落ちないように気を付けて」
「ここから先は雪道。みんな、滑り落ちないように気を付けて」
朱夏(kz0116)は雪を踏みしめて、顔を上げる。
朱夏の前にそびえるのは、聖なる山『ビャスラグ山』。
シバからの情報によれば、転移門はこの山の大霊堂に存在する。
「朱夏さん、本当にこの山の何処かにあるんですよね。
東方へ導く転移門が……」
慣れない雪道を草履で上がる仲間が、背後から声をかけた。
聖地を取り戻せば、東方へ繋がる転移門が動き出す。
そう、この転移門を起動させる事こそ、朱夏にとって重要なのだ。
「そうね。シバ達が聖地を取り戻せばアレを使って東方へ還る事ができる。東方の窮地を救ってくれる戦士達も一緒に……」
希望を胸に断言する朱夏。
朱夏達がはるばる西方までやってきたのは、東方の危機を救う戦士を探し出す為だ。
シバの話によればその戦士達はハンターと呼ばれており、事情を話せば必ず力を貸してくれると断言していた。
だとするなら――朱夏にできる事は、ただ一つ。
意を決した朱夏は、仲間達の方へ向き直った。
「我等は義によって、蛇の戦士シバへ加勢する。
戦場では悪鬼として剣を振るい、修羅と化して敵を屠れ」
「おおー!」
仲間達が朱夏に呼応して声を上げる。
雪原の中で着物姿は異様にも思えるが、仲間達の足取りはとても力強い。
命を賭けて戦いに挑む覚悟を感じさせる。
朱夏は、仲間達を見守った後――鋭い顔つきで前を見据えた。
「すべては我等がエトファリカと帝の為に……朱夏、推して参る!」
●
「ボクが聖地周辺の歪虚を倒すよ。バタルトゥさんは、ハイルタイをやっつけて」
ハイルタイが聖地へ向かっていると知り、開口一番、ファリフは高らかに言った。
ハイルタイは、オイマト族の仇敵。一矢報いる為にバタルトゥが直接対決を望んでいる事を、ファリフは察したのだ。
だが……シバは、目を見開きながら、しかし異を唱えた。
「……ならん」
「シバ老……」
「一度は昂ぶりに任せて奴に挑み同胞を悪戯に死なせた、その過ちを繰り返す気か」
シバにも、バタルトゥの気持ちは理解できる。
しかし、この戦いは西方世界の覇権にも影響する戦い。今後、歪虚との勢力図は大きく書き換わるかもしれない重要な局面なのだ。
「お主の背後に多くの者がいる。今ここで大地に還る時ではない」
シバにとって、部族にとって、人類にとって……聖地奪還は、通過地点に過ぎない。
ここから東方と手を結び、また辺境部族が他国と並び立って手を取るために、バタルトゥの存在は不可欠。彼を失う事は許されなかった。
この戦いは西方世界の覇権にも影響する戦いであり、今後歪虚との勢力図を大きく書き換えるかもしれない重要な局面なのだ。
だが……ファリフは、譲らなかった。
「ボクだって、バタルトゥさんと同じ間違いをしてた。でも……ボクを支えて、助けてくれる人達がいたから、今こうして戦える。
だから今度は、ボクが助ける番なんだ……ボクらが、下らない仲違いをやめて、本当の仲間になる為に」
族長の重責を背負う少女は、しかしまっすぐな瞳で、朗々とその意思を告げた。
決して、成熟した訳ではない。それでもファリフは、求められるその資質を今、少しずつ自分の中に宿しつつある。
バタルトゥは彼女を見つめてから……一度深く息を吸い、そしてシバに向き直った。
「俺からも、もう一度……頼む。
……ハイルタイはオイマト族、いや……辺境部族に課せられた戒めだ。
これを解き、咎を清めぬ限り……辺境は先には進めん。
復讐ではない。来たる隣人達と、真に手を携えるために……禍根を、絶たせてくれ」
二対の瞳が、黙して佇むシバを見つめた。
聖地奪還を担うのがこの二人でなければならない理由、それが、そこにあった。
「……お師匠さま?」
固まったままのシバを、テトが訝しむ。
シバは笑い、テトの頭に手を載せた。
そして、一呼吸を置いた後に、ファリフとバタルトゥに告げた。
「行け。
赤き大地に産まれし戦士の子よ。
遥か来たる未来を、見せておくれ」
招かざる客
大霊堂の奥――白龍の前に、若き巫女が対峙する。
「白龍さま……」
『……間もなくだ。間もなく、赤と青の戦士が来る。
赤き大地の民と手を携えて……ここを訪れる。
我の命は尽きた時は、彼らを……どうか、彼らを……』
白龍は、ゆっくりと吐き出すように呟いた。
見るからに疲弊している姿だが、巫女達には白龍を救う術はない。
辛い白龍の体に増えて優しい言葉をかける事しかできない。
「白龍さま。今はお休み下さい」
『……良い。命の灯火が尽きる時は、我自身が把握している。
ならば、残された命は巫女と辺境の民へ使う』
白龍は、今も聖地に結界を張って歪虚の侵攻を食い止めている。
自らの命を削って巫女達を歪虚から守っているのだ。
「ですが、それでは白龍さまは……!」
「止しな。白龍さまも覚悟を決めているんだ。巫女が白龍さまの覚悟に水を差しちゃぁいけないよ」
若き巫女が振り返れば、大巫女と呼ばれる老婆が立っていた。
ブロンドの髪をツインテールに束ねた巨躯の老婆――胸は特筆するほど大きいが、脂肪よりも筋肉の塊に近い。
そんな大巫女は大きな体を揺らしながら、豪快に岩へ腰掛ける。
「白龍さまの命が尽きる時はぁ、あたしらも終わりの時だ。
覚悟を決めな。そして、白龍さまの言った戦士を信じるんだ。
そうすりゃ……」
――ドンッ!
突如大霊堂を揺り動かす衝撃。
白龍の結界に何かが触れた事は間違いない。
「噂の戦士達……じゃないね。もう一方の客かい。
まったく、せっかちな奴は嫌われるよ」
白龍の顔を見れば、それが待ち望んだ客でない事はすぐに分かる。
招かれざる客。
早くも大霊堂に歪虚の軍勢が迫りつつあった。
●
一方、聖地『リタ・ティト』の入り口。
先程走った衝撃は周囲の空気を揺さぶり、付近の雪が一瞬にして吹き飛ばされる。
入り口付近に集うは、怠惰の軍。
そして――集団の先頭で矢を番える男は。
「客人を出迎えんか! 無礼者がっ!
この儂が大霊堂をもらってやろうというのだ。白い龍よ、さっさとそこを明け渡せ」
ハイルタイは、再び矢を放った。
――衝撃。
矢は結界に阻まれて先へ行くことができない。
だが、矢の衝撃は確実に大霊堂の結界を蝕んでいく。
「そろそろじゃな……これで終いじゃ!」
放たれた矢は、適確に同じ箇所を射貫き続ける。
そして、三本目の矢が結界に触れた瞬間。
――バリンっ!
砕かれた硝子のように、宙を舞う結界。
雪とは違う煌めきを見せながら落ちるそれは、まるで芸術のようだ。
しかし、現実は無慈悲。
その芸術は大霊堂への道が拓かれた事を意味している。
歩み出す怠惰の軍。
一歩一歩と白龍の元へ突き進んでいく。
レチタティーヴォ
渺々たる赤い大地。連戦に次ぐ連戦。激戦に次ぐ激戦を飲み込んだその地に、長く影を曳く人影が――二つ。
一つは、絢爛な道化服を身にまとった髑髏。”操骸道化”、クロフェド・C・クラウン。
もう一つは、王国貴族の華やかな衣装と金のカツラを身につけた髑髏。”紅凶汲曲”、ラトス・ケーオ。
「どうなりますかな、この演目は」
「よき奏楽となれば良いのですが」
カタカタと乾いた音を立てて、眼窩に赤光を宿したクロフェドが言うと、ラトスはシルクハットを摘んで応じる。蕭々と、風。砂が軽い音と共に舞い上がり、彼方へと流れていく。
「”脇役”は十分に集めました。故に、相応には仕上がりましょうとも……あとは、”主演たる彼ら”がどのような音色を奏でるか」
「クフ!」
懸想するように呟いたラトスに、クロフェドは嗤った。敵意も、悪意も無い、健やかで華やかな声で。
「……愉しみです。此度の演目には各国の精鋭が集い、人類の救世主とも謳われるハンター達が揃っています。きっと、亡者達も浮かばれる事でしょう。
――ねぇ?」
クロフェドの声に、ぬらり、あるいは、カタリ、と音が鳴った。粘質で硬質なそれらが幾らにも重なると、大地が震えているかのような鳴動となる。合奏を背に、ラトスは手元の骨笛をくるりと回す。愉快げに細められた青光が――幾許かの後、再び開いた。そして。 「……そういえば、プエルの姿がありませんが?」
「あの坊やなら、迷子になったようですな。子守が探しに行っております」
「そうですか……」
思いつき、そう言ったのだろう。クロフェドの律儀な応答に興味なさげに言うと、ラトスは慨嘆したようだった。
「……いよいよ話題も尽きました」
「いつもの寄り道、でしょうが……遅い」
退屈だった。歪虚達が、幾らかの空虚を滲ませた声で言った、その時だ。
「――待たせたな」
声が響いた。壮年らしい、渋く、低い声だ。だが、その声は煮え滾る溶鉄のような熱を孕んでいた。声の主の装いは洒脱、の一言に尽きる。炎のように緩やかにウェーブする赤髪。最高級の生地で仕立てられた白い揃いのスーツに、紫がかった濃紺のシャツ。シャツと同色のコートを着崩し、左腰には黒と金からなる突剣を下げているが――洒落た様相を損なうことはなく、そこに在る。
跪いたクロフェドとラトスに目もくれず、男は愉しげに遠方を見た。
「善い空気だ。清浄なる白竜のおわす大地――なんと美しい!」
くつくつと喉を鳴らし、目を細めて、続ける。
「しかし、清冽なる舞台も一興ではあるが汚濁に穢されたそれもまた美しい。
――さて、私の主筆諸君?」
「はい」
二重の応答。男は、彼方を見つめたまま――口の端に、笑みを浮かべた。そして、短く、こう言った。 「役者達を連れてきた」
轟、と。巨大な気配が男たちの後背に湧いた。異質な影に覆われながらも男は、振り返りもしない。ただただ真っ直ぐに見据えるは”舞台”たる戦場。
「桟敷席の皆様もさぞや心待ちにしておられよう。いかに”災厄と花嫁は、いつだって遅れてやってくるもの”とはいえ、だ」
朗々と諳んじる男は、その先に何を見たか。
「……大いに奏で、大いに踊れ。此度の主賓にして主演なる彼らを退屈させるな」
――”退屈は罪だ”。
傲然と。愉快げに、そう言った。
●
 「……来ましたね」
「……来ましたね」
ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は冷然とした眼差しで彼方を見た。濛々たる噴煙を上げて此方に至る、怠惰の軍勢を。
「ヤクシー……」
その中でも一際目立つ指揮官、ヤクシーの威容を見て、ファリフ・スコールが呟いた。去来するのは、数カ月にわたるこの地での出来事。眼前にあるのは長きに渡る争乱の決戦場だった。だから。
「ヴィオラ」
「何でしょう?」
「ありがとう、ココまで、助けてくれて」
真っすぐに前を見つめたままの少女の言葉に、ヴィオラは小さく眼を見開いた。力のある強い眼差しは、ヴィオラがこの地に足を踏み入れた頃と比べるまでも無い。
「此処で、終わらせよう」
「ええ」
少女の決意に微笑と共にヴィオラが頷いた、その時だ。
「援軍です!」
駆け足で至った伝令が、そう告げたのだった。
ARS
 『ツィカーデよ。ヤクシーに助力しようとするとき、自分が何といったか覚えておるか?』
『ツィカーデよ。ヤクシーに助力しようとするとき、自分が何といったか覚えておるか?』
実験場とホープ一帯を見下ろす小高い丘の上でじっと佇むアイゼンハンダーに、「義手」が問う。
「『野戦病院を襲うとは卑劣な』……うん。確かにそう言ったよ」
『では、これから儂らが阿鼻叫喚の渦に叩きこんでやろうというあの陣地は如何? 儂が見る所、ここの所の戦で傷ついた有象無象が運び込まれているように見受けられるがな』
その問いは、責めているようでも案じているようでもなく、ただ愉しんでいた。
「傷病者だけじゃない。非戦闘員も大勢……」
彼女の言う非戦闘員とは非覚醒者を指しているようだ。
『で、お前はそれで良いのか?』
少女は、直接にはその疑問に答えなかった。
一糸乱れぬ隊形を維持したまま背後に控える改造ゾンビたちに振り返ると、凛とした声で告げる。
「これより、建設中の革命軍前線基地を強襲する! 最優先攻撃目標は整備中の機甲兵器と、各種の軍需物資である! 非戦闘員及び傷病者は――」
ここで、アイゼンハンダーは一旦言葉を切り、丘の下で実験場後周辺に集結しつつあるガエル・ソトの命令を受けた歪虚の集団を見た。
「――非戦闘員及び傷病者は無視せよ。無駄弾を、使うな」
目を逸らし、拳を握りしめながら少女はそう締め括った。
その命令が欺瞞であることは彼女自身が良く解っていた。彼女と配下の死者が総攻撃を仕掛ければ広範囲が巻き込まれるのは明らかである。
まして、彼女たちが連携するガエル、ヤクシー配下の歪虚にはそのような命令は行き届くまい。
『――つくづく、哀れで健気な娘よ。だが、それで良い。あの「戦友」二人を助けたいというのであれば、何時もの如く儂はお前の拳となるだけよ』
義手がそう呟いた時、アイゼンハンダーは迷いを振り切ったように号令を下す。
「A分隊はスモークディスチャージャーを一斉発射後友軍の突入を援護せよ! B分隊は私に続け! 敵が混乱している隙に機甲兵器を破壊する!」
轟音と共に連続発射された煙幕弾が実験場周辺で炸裂する。
その白煙の中を、黒い輝きに率いられた、赤い肩の死者たちが次々と駆け抜けていった。
「信じる」ということ

 砲声が、歪虚の咆哮が実験場一帯を揺るがす。この襲撃に際しすぐには動かせない傷病者を除く一般の人々、そして巫女リムネラといった重要人物たちは、予め同盟の軍人たちによって構築されていた避難所に集まっていた。
砲声が、歪虚の咆哮が実験場一帯を揺るがす。この襲撃に際しすぐには動かせない傷病者を除く一般の人々、そして巫女リムネラといった重要人物たちは、予め同盟の軍人たちによって構築されていた避難所に集まっていた。
ガエル・ソトの部下たち、そしてアイゼンハンダーの襲撃に対する悲鳴と怒号が織りなす混乱の渦の中、システィーナ・グラハム(kz0020)は一歩ずつ大地を踏み締めるような、あるいは震えを隠すような足取りで何かの場合に備えて作られた演説用の舞台に歩を進めている。
「システィーナ様!?」
それに気付いたオクレールほか侍従隊が慌てて制止しようとする。
しかし、最初は同じように王女を止めようとしたエリオット・ヴァレンタイン(kz0025)が、無言でオクレールらの前に立った。
「騎士団長殿。どういうおつもりですか?」
咎めるようなオクレールの視線。エリオットは正面からそれを受け止め、静かに首を振る。
システィーナはそんなエリオットに小さく頷くと、儚げな、しかし精一杯の力を込めた声で語り始めた。
「皆さま。ここが何と呼ばれているか、皆さまはご存知でしょうか?」
突然響いた少女の声に、喧騒がやや収まる。
「ここは、ホープ……人類の希望と名付けられました。だから、ここは絶対に安全です……っ」
人々の願いは成就すると、少女は信じて疑わない。
勿論ちょっと冷静になれば「だからどうした」と怒鳴り返されかねない強引な理屈。
故に少女は畳みかけた。
「何故なら、聖地を奪回するという一つの目的のために皆さまの仲間が――あらゆる戦士たちが集い、肩を並べて戦っておられるのですから――!」
確かに少女の言葉は誇張ではない。
現在、実験場には辺境部族の精神的支柱ともいえるリムネラがおり、同盟軍に至ってはモデスト・サンテ、ダニエル・コレッティといった重鎮が指揮を取っている。
少女は言葉を切った。ここからが肝心だとでも言うように。
「そして今ここにいる皆さまをお守りするのは、我がグラズヘイム王国騎士団を率いるエリオット・ヴァレンタイン騎士団長と私の信頼する侍従隊。加えて国という枠組みにとらわれず、幾度も我々の力になってくれたハンターの皆さまです。皆さまの戦士を、私たちの友を信じましょう」
人々が一応の落ち着きを取り戻したことを感じたのだろう。王女は優雅に一礼すると騎士団長の側に戻る。と同時に膝からくずれた。
幸い、騎士団長と侍従長が左右からシスティーナを支えたのに気付いた人はほとんどいなかった。
「ご、ごめ……なさ……」
緊張によるものか恐怖によるものか、しゃくりをあげながら謝るシスティーナ。
だがエリオットは優しく笑ってみせる。「ご立派でございました」と耳元で告げると、続けて自身に至上命題を課した。
「必ずや殿下と、殿下の愛する人々をお護り致します。我が身命を賭してでも……」
そうしてグラズヘイム王国騎士団長は不退転の覚悟を以て北を、ついでハンターたちの方を見た。
決戦

 「……所詮は子供、戦場の空気には耐えられなかったということか」
「……所詮は子供、戦場の空気には耐えられなかったということか」
眼前に立ち塞がる人類の布陣を見て、ガエル・ソトは腕組みをしたまま呟いた。
表情こそ厳めしいが、その口調には僅かに気色が滲んでいる。
「安全な後方に、手勢を引き連れて後退したは良いが……そのせいで中央を守る肝心の機甲部隊に歩兵が随伴していない。これでは――」
中央突破してください、と言っているようなものだとガエルは内心溜息をつく。
「良かろう。躾の悪い子供には灸が必要だ。容赦はせぬぞ皇子とやら。真の英雄は勝利と栄光のためであれば、女子供を手にかけるとことなど、微塵も厭わぬ! 全軍、突撃せよ!」
●
ガエル・ソトは間違っていなかった。カッテ・ウランゲル(kaz0033)はまさしく、「中央突破してください」と彼に頼んでいたのだから。
幾ら機甲兵器の死角をすり抜けるとはいえ、ガエルに追随できるほどの機動力を持った戦力は限られる。自ずと、カッテの前に辿り着く部隊は少数になる。
そして、カッテの護衛に当たる部隊が敵を押し留めている間に、人類側の両翼に潜ませた奇襲部隊が反転し、護衛部隊と共に孤立したガエルを三方向から包囲する。
カッテは、ガエルが必ず乗って来ると踏んでいた。
「強い英雄願望を持つ方です。二度の敗北に屈せず見事に敵の弱点をついて敵将を討ち、一発逆転……という物語はとても魅力的な筈ですから」
事も無げに少年は言い放ち、微笑んだ。
あるいは、驚くハンターもいるかもしれない。
要は、この作戦の要はカッテ自身が囮になる、ということなのだ。
どこか一つでも作戦に綻びが出れば、それは直ちにカッテの危険に繋がる。まして、相手は災厄の十三魔だ。首尾よく包囲したとしても決して油断のできる相手ではない。
「余り……買いかぶらないでくださいね?」
僕だって、怖いんです、と。
その付け加えた言葉とは裏腹に、少年は微塵の淀みもなく、花が咲いたように笑った。
「だから、陛下と僕は皆さんを信じます」
そう言って、カッテは静かに立ち上がる。
それが、戦闘開始の合図となった。
辺境の奥深くへと分け入る前線の健闘を祈りつつ、CAM実験場ではささやかな酒宴が開かれた。
その最中、同盟陸軍所属でCAM操縦部隊「特機隊」の隊長、ダニエル・コレッティ(kz0102)は直属の部下たちに声をかける。
「さて、食った分は働かないとねぇ」
周囲を見渡せば、ハンターと避難民が混じって楽しく会食中なので、ダニエルは隊員の耳元に小声で話しかけた。
そこへ巨体を揺らし、同盟海軍所属のモデスト・サンテ(kz0101)が近づく。彼は万が一に備えて、素面のままでいた。
「よし、そろそろ作戦会議に向かうぞ……ってダニエル貴様、酒を飲んだな!」
「あれ、こんなに楽しいお酒なのに飲んでないの? 白熊提督はもったいないことしましたなぁ?」
ニヒルな笑みを浮かべるダニエルは、恨めしそうに睨むモデストをおちょくった。
「勝利の美酒は寝かせておくのが一番なんだ。普段は戦わんお前には、この感性がわからんだろうな」
「なら、ここに迫る敵を追っ払ったら、俺がとっておきの酒を差し上げますよ」
この時、ダニエルは一瞬だけ真剣な眼差しを提督に向けた。モデストはそれを見て、大きくひとつ頷くのだった。
CAM実験場が戦火に包まれるやも知れぬという懸念は、すでに同盟軍内で検討されていた。
この地は今や、聖地奪還における拠点。さらには東方王国からの使者との連携をも担っている。
いくら辺境の状況に暗い歪虚だとしても、ここを「真っ先に潰すべき場所」くらいには認識しているだろう。
だから酒宴から離れた天幕において、同盟軍の面々はしかめっ面を並べて、敵の侵攻への備えを話し合っていた。
「特機隊はもちろんだが、CAMや魔導アーマーは敵の出鼻を挫くのが最優先事項だ。しっかり頼むぞ」
モデストがそう言えば、ダニエルも続ける。
「どんな敵が攻めてこようと、こちらにとってはあまり関係ない。最悪、モデスト少将が兵力をまとめて拠点の外に陣取る時間さえ稼げればいい。それ以上もそれ以下も必要ない。ここ、重要ね」
戦況を聞けば、どこも余裕はない。もし帰還する際に敵が立ち塞がっていようものなら、目を覆わんばかりの被害が予想される。それだけは避けなければならない。
「実験場を防衛する者は、避難民や怪我人は長城付近まで下がらせろ。あとは敵の出方次第だ」
あごに手をやりつつ地図を見るモデストは、「うーん」と唸ってみせた。
「昼行灯、他に言うことは?」
普段は飄々としているが、実は切れ者と名高いダニエルに、モデストは意見を求める。
「まぁ、あんまりビックリしないことかな。いろんなことに」
えらくザックリしたアドバイスに、モデストは眉をひそめるのであった。
(執筆:村井朋靖)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
巫女の想い

リムネラ
リムネラ(kz0019)は無意識にそう感じていた。
現在、彼女はリゼリオで、ハンターたちの成功と聖地の無事を祈り、ユニオン内の礼拝室で祈りを捧げている。
無論そこから動かないわけではない。『ガーディナ』リーダーとしてハンターに出来る限りのことは尽くしている。しかし、祈りたくもなるというものだ。
自分は立場上、前線に経つことは出来ない。
だからこそ、ここで祈りを捧げるのだ。
ハンターたちのことと――そして、聖地のことと。
この前の演説で、リムネラには言えなかったことがある。
それは――聖地の白龍の、いのちの灯火が消えかかっているということだ。
もともと彼の地の白龍は、聖地に歪虚が侵攻するのを押しとどめてくれていた。しかし、白龍とて不老不死の存在ではない。己の持っている力を使い果たしたりすれば、死んでしまう。
事実、聖地の白龍というのは、一度代替わりをしているのだという。
更に加えていうと、聖地の白龍はもう若くない。
リムネラの側にいてくれるヘレはまだ幼いが、聖地の白龍は――限界が近いのだ。
白龍に限らず、ドラゴンという存在が特別視されるのは誰もがわかることと思う。何故そんなに特別視されるのかというと、その持てる膨大な知識とマテリアルの量、さらに成長するまでの期間が人の一生よりも遙かに長いことが挙げられる。もっとも、これらは一般的に知られていることかというとそうでもないのだが……。
ただ、そんな膨大な知識と永い寿命をあわせ持った白龍である。もしかすると――ハンターたちの知らない情報を持ち合わせているかも知れない。
歪虚とはなんたるか、とか。
そして、最近ちらほらと耳にする、『東方』のこと、とか。
ヘレは見た目通り、まだ幼い。巫女の代表たる大巫女がリムネラに託したくらいだ、まだかわいいペットという認識のほうが強いだろう。
しかし聖地の白龍は、今の人間たちが知り得ないだろう情報を持っている可能性が、非常に高いのだ。
特に聖地で過ごしている白龍ならば、その情報量は想像が付かない。
白龍に尋ねることが出来れば、それらの答えはすべてではないにしろ、聞き出せるのではないだろうか。
そう考えていくと、自分の想像以上に白龍という存在は大切なのではないだろうかと、リムネラは思う。
(大巫女様……)
リムネラは、跪いて祈る。
口からは、祈りの言の葉がこぼれていく。
彼女はもともと、辺境のとある一部族の出身の普通の少女だった。しかし神託を受け、聖地に入ってからもうずいぶん経つ為、聖地の巫女たちが家族と言って過言ではない。
そう、聖地というのはリムネラと同様に神託を受けた上で特別な力を授かったとされたものたちが、生まれついた部族をでて――ある意味言葉は悪いが捨て、巫女となる修行を積む場所なのだ。
巫女というのはそれらの特殊の修行を積んだものたちを総称して呼ぶ単語なのだ。そんなわけで、『巫女』という名称ではあるが当然男性も存在する。
――初めて大巫女に会った時、リムネラは本当に幼かった。
しかし、大巫女は巫女としてのリムネラの資質を一目で見抜き、そしてここまで育ててくれた大事な存在だ。リムネラにとっては、まるで実の祖母のような存在でもある。
だから、というわけではない。しかし、巫女も、白龍も、今の辺境や聖地、ひいてはこのクリムゾンウェストに欠かすことの出来ない存在なのではないだろうかと、考えてしまう。
だからこそ、少女は祈る。
聖地の無事を。
仲間たちや、あの優美な白龍に再会できることを。
いや――
……信じなければ、いけないのだった。

ヤクシー
「そうか……小さい連中は、ビャスラグ山の大霊堂が狙いかい」
怠惰侵攻軍を指揮するヤクシーは、人類側の侵攻ルートを整理していた。
ヤクシーは……いや、歪虚達は、侵略者たる自らの本能を以って直感していた。
人類のエンシンケ洞窟襲撃は、ヤクシーの首を狙っての物ではない、と。
「狙いは洞窟の先の、あのクソ聖地や大霊堂か。その為に奴らマギア砦にまで陽動出して、あたしらはまんまとハマった……
小賢しい、クソ小賢しい……だけどねぇ」
ヤクシーは、右手の大鎌を振るう。
一閃した刃は、空気を震動。周囲に強大な殺気を撒き散らす。ヤクシーの表情は――怒りに満ち溢れていた。
「初めからあたしの事は眼中になかったって事かい? 上等だよ。
マギア砦のガエルに緊急の連絡だ。全力で奴らの実験場とかいう場所を攻めるんだ。容赦するなって言っておきな。それから……」
ヤクシーは一呼吸置いた後、ある歪虚の名前を口にする。
一部の辺境部族において忌むべき名とも言える者の名前を。
「もう一度、ハイルタイを呼べ。面倒だ、なんて言っても引っ張ってくるんだよ!」
●

シバ

ファリフ・スコール

バタルトゥ・オイマト

テト
「敵は……正面からの力比べを望んだか」
それは、異例とも言える、怠惰からの申し入れ。
聖地とCAM稼働実験場を賭けてどちらが先に攻略できるか、勝負だ……と、ヤクシーが律儀にも人類へ声明を出したのだ。
「あのおばちゃん、よっぽど悔しかったのかな。もう、怠惰って言う感じが全然しないけど」
スコール族のファリフ・スコール(kz0009)は、何気なしに呟いた。
ハンターの協力もあって聖地奪還は人類に優勢。着実に聖地へと近付いている。ファリフにも若干の余裕が見え始めていた。
「スコールの族長よ。事態は急変しておる。我らにそのような余裕はないぞ」
シバに諭され、ファリフは微かに狼狽えた。
「ええっと……ボクたち、ちゃんと怠惰やっつてけるし、それに東方の人達も助けてくれるんだよね。それでも……?」
聖地とマギア砦の間に現れた謎の集団は、東方より現れた使者であった。
先の戦いで戦線後退を避ける事ができた為、以前から連絡を取っていたシバがコンタクトに成功。東方の使者達も聖地奪還を支援してくれる事になっていた。
「怠惰に聖地奪還の目的を悟られた……そこが、問題だ……敵が、聖地付近の防御を固めてくる……と。違うか、シバ老……」
オイマト族のバタルトゥ・オイマト(kz0023)の言葉に、シバは頷く。
東方より援軍が来たことで、かの地と繋がる聖地が人類の目的と悟られた可能性は、シバも考慮していた。
だが、怠惰側の対処がここまで早く、また大胆であるとは、その名前から誰が想像できようか。
「でも、稼働実験場の前にはマギア砦があるよ。あいつらは先に、砦を落とさなくちゃいけないんじゃない?」
ファリフは、人類に置かれた戦況を口にする。
現在、マギア砦は人類が奪還。占領していたガエル・ソトの撃退に成功しており、仮にガエルが稼働実験場を攻撃するためにはマギア砦の横を通過して南下しなければならない。マギア砦でガエルを足止めできれば、人類は聖地奪還に注力すればいい。 しかし、シバは頭を横に振る。
「忘れたか、スコールの長。十三の闇が赤き大地に這っておる」
「災厄の……十三魔か」
人類と怠惰の戦いが繰り広げられる辺境において、幾度も乱入を試みる者達がいた。
強力な戦力を単騎で持ち、状況によっては戦況をひっくり返しかねない相手だ。先の戦いでもアイゼンハンダーがエンシンケ洞穴を襲撃している。
「稼働実験場には防衛戦力を残さねばなるまい。だが……聖地奪還の大仕事、これだけはお主達に託さねばならぬ。その意味がわかるか?」
ファリフ・スコール。
バタルトゥ・オイマト。
かつて帝国への服従を巡り、部族会議では立場を異にした両者。
だが、二人はそれぞれの立場と問題を乗り越え、怠惰と戦ってきた。
その二人が顔を見合わせ、何かを言いかけた時……
「大変ですにゃ?! ゴチューシンですにゃ!」
紡がれ掛かる言葉を遮って、部族なき部族のテト(kz0107)が駆け込んできた。
「落ち着かんかい、騒々しい」
「ぜ、前線の斥候より入伝ですにゃ! 騎馬に乗って弓を携えた巨大な歪虚が聖地付近へ接近中との報告! 『あいつ』……大霊堂へ向かってますにゃ!」
巨大な馬に弓を携えた歪虚。
その存在を、彼等は知っていた。
そして、出会ってもいた。
強力な弓を操る災厄の十三魔の一人――。
「ハイルタイ……奴は、聖地に」
「バタルトゥさん……」
傍らに立つバタルトゥの身を案じたファリフ。
ハイルタイの名前を聞いた瞬間、ファリフはバタルトゥが身を震わせた事に気が付いていた。
●

ハイルタイ
「だから、なんでまたワシがここで戦わねばならんのだ! もう働いたのだから良いではないか」
眠っていたところを叩き起こされたハイルタイは不機嫌だった。
元々、聖地奪還に強い興味もない。言われて渋々戦っていただけだ。今回、ヤクシーに召還されたのもロクな理由じゃない――そう考えていた。
「悪いねぇ。だけど、あんたじゃなけりゃできない仕事なんだよ」
「ワシは働きたくないぞ。働いたら負けじゃ」
「まあ、そう言うなって。
この山、覚えてるだろ? 小さい奴らが聖なる山って呼んでる場所だ」
ヤクシーは、山を見上げる。釣られてハイルタイも首を上に向ける。山の上では雪が風に舞い、忙しそうに飛び回っている。
「確かそんなような……そうでないような……」
「この山には聖地と呼ばれる場所があって、そこに大霊堂ってぇのがあるんだ」
大霊堂。
その一言を聞いた瞬間、ハイルタイの眉が釣り上がる。
「思い出したぞ! 白い龍が見えない壁をこしらえせえで、ワシはそこへ行けなかったんじゃ! せっかくよく眠れそうな洞窟だったのに!」
ハイルタイは珍しく興奮してみせた。
歪虚が未だに聖地を制圧できなかったのは白龍の加護があったからだ。白龍が自らのマテリアルを使って結界を張り、歪虚の聖地侵攻を防いでいたのだ。
「お怒りはごもっとも。だけど、その壁が壊せるって知ったらどうする?」
「なに!?」
振り返るハイルタイ。
普段は怠けているだけの髭ダルマだが、眠りやすい洞窟の前ではテンションもアップするようだ。
「ど、どど、ど、どういう事だ!?」
「焦らなくてもいいよ。あの白い龍、寿命が近いみたいでね。結界が以前よりも薄くなっているんだ。あたしの鎌じゃまだ厳しいけど、ハイルタイの矢を何発か叩き込めば……」
「結界は壊れる、という訳じゃな? なるほど……」
満足そうな笑みを浮かべるハイルタイ。
大霊堂を新たな住処にすべく、本気を出してくれるようだ。
実はヤクシーも結界を破壊する事は可能だ。だが、ハイルタイが聖地を攻略してくれれば、その間ヤクシー自身が聖地付近に集まる人類を蹂躙する時間を作る事ができる。
単に聖地を潰しても面白くない。
馬鹿にしてくれた連中に、たっぷり仕返しをしてやらないと――。
「そういうこった。
まあ、大霊堂へ突入してたっぷり『白蛇』退治を堪能するんだね」
東方よりの援軍

朱夏
朱夏(kz0116)は雪を踏みしめて、顔を上げる。
朱夏の前にそびえるのは、聖なる山『ビャスラグ山』。
シバからの情報によれば、転移門はこの山の大霊堂に存在する。
「朱夏さん、本当にこの山の何処かにあるんですよね。
東方へ導く転移門が……」
慣れない雪道を草履で上がる仲間が、背後から声をかけた。
聖地を取り戻せば、東方へ繋がる転移門が動き出す。
そう、この転移門を起動させる事こそ、朱夏にとって重要なのだ。
「そうね。シバ達が聖地を取り戻せばアレを使って東方へ還る事ができる。東方の窮地を救ってくれる戦士達も一緒に……」
希望を胸に断言する朱夏。
朱夏達がはるばる西方までやってきたのは、東方の危機を救う戦士を探し出す為だ。
シバの話によればその戦士達はハンターと呼ばれており、事情を話せば必ず力を貸してくれると断言していた。
だとするなら――朱夏にできる事は、ただ一つ。
意を決した朱夏は、仲間達の方へ向き直った。
「我等は義によって、蛇の戦士シバへ加勢する。
戦場では悪鬼として剣を振るい、修羅と化して敵を屠れ」
「おおー!」
仲間達が朱夏に呼応して声を上げる。
雪原の中で着物姿は異様にも思えるが、仲間達の足取りはとても力強い。
命を賭けて戦いに挑む覚悟を感じさせる。
朱夏は、仲間達を見守った後――鋭い顔つきで前を見据えた。
「すべては我等がエトファリカと帝の為に……朱夏、推して参る!」
●
「ボクが聖地周辺の歪虚を倒すよ。バタルトゥさんは、ハイルタイをやっつけて」
ハイルタイが聖地へ向かっていると知り、開口一番、ファリフは高らかに言った。
ハイルタイは、オイマト族の仇敵。一矢報いる為にバタルトゥが直接対決を望んでいる事を、ファリフは察したのだ。
だが……シバは、目を見開きながら、しかし異を唱えた。
「……ならん」
「シバ老……」
「一度は昂ぶりに任せて奴に挑み同胞を悪戯に死なせた、その過ちを繰り返す気か」
シバにも、バタルトゥの気持ちは理解できる。
しかし、この戦いは西方世界の覇権にも影響する戦い。今後、歪虚との勢力図は大きく書き換わるかもしれない重要な局面なのだ。
「お主の背後に多くの者がいる。今ここで大地に還る時ではない」
シバにとって、部族にとって、人類にとって……聖地奪還は、通過地点に過ぎない。
ここから東方と手を結び、また辺境部族が他国と並び立って手を取るために、バタルトゥの存在は不可欠。彼を失う事は許されなかった。
この戦いは西方世界の覇権にも影響する戦いであり、今後歪虚との勢力図を大きく書き換えるかもしれない重要な局面なのだ。
だが……ファリフは、譲らなかった。
「ボクだって、バタルトゥさんと同じ間違いをしてた。でも……ボクを支えて、助けてくれる人達がいたから、今こうして戦える。
だから今度は、ボクが助ける番なんだ……ボクらが、下らない仲違いをやめて、本当の仲間になる為に」
族長の重責を背負う少女は、しかしまっすぐな瞳で、朗々とその意思を告げた。
決して、成熟した訳ではない。それでもファリフは、求められるその資質を今、少しずつ自分の中に宿しつつある。
バタルトゥは彼女を見つめてから……一度深く息を吸い、そしてシバに向き直った。
「俺からも、もう一度……頼む。
……ハイルタイはオイマト族、いや……辺境部族に課せられた戒めだ。
これを解き、咎を清めぬ限り……辺境は先には進めん。
復讐ではない。来たる隣人達と、真に手を携えるために……禍根を、絶たせてくれ」
二対の瞳が、黙して佇むシバを見つめた。
聖地奪還を担うのがこの二人でなければならない理由、それが、そこにあった。
「……お師匠さま?」
固まったままのシバを、テトが訝しむ。
シバは笑い、テトの頭に手を載せた。
そして、一呼吸を置いた後に、ファリフとバタルトゥに告げた。
「行け。
赤き大地に産まれし戦士の子よ。
遥か来たる未来を、見せておくれ」
招かざる客
大霊堂の奥――白龍の前に、若き巫女が対峙する。
「白龍さま……」
『……間もなくだ。間もなく、赤と青の戦士が来る。
赤き大地の民と手を携えて……ここを訪れる。
我の命は尽きた時は、彼らを……どうか、彼らを……』
白龍は、ゆっくりと吐き出すように呟いた。
見るからに疲弊している姿だが、巫女達には白龍を救う術はない。
辛い白龍の体に増えて優しい言葉をかける事しかできない。
「白龍さま。今はお休み下さい」
『……良い。命の灯火が尽きる時は、我自身が把握している。
ならば、残された命は巫女と辺境の民へ使う』
白龍は、今も聖地に結界を張って歪虚の侵攻を食い止めている。
自らの命を削って巫女達を歪虚から守っているのだ。
「ですが、それでは白龍さまは……!」
「止しな。白龍さまも覚悟を決めているんだ。巫女が白龍さまの覚悟に水を差しちゃぁいけないよ」
若き巫女が振り返れば、大巫女と呼ばれる老婆が立っていた。
ブロンドの髪をツインテールに束ねた巨躯の老婆――胸は特筆するほど大きいが、脂肪よりも筋肉の塊に近い。
そんな大巫女は大きな体を揺らしながら、豪快に岩へ腰掛ける。
「白龍さまの命が尽きる時はぁ、あたしらも終わりの時だ。
覚悟を決めな。そして、白龍さまの言った戦士を信じるんだ。
そうすりゃ……」
――ドンッ!
突如大霊堂を揺り動かす衝撃。
白龍の結界に何かが触れた事は間違いない。
「噂の戦士達……じゃないね。もう一方の客かい。
まったく、せっかちな奴は嫌われるよ」
白龍の顔を見れば、それが待ち望んだ客でない事はすぐに分かる。
招かれざる客。
早くも大霊堂に歪虚の軍勢が迫りつつあった。
●
一方、聖地『リタ・ティト』の入り口。
先程走った衝撃は周囲の空気を揺さぶり、付近の雪が一瞬にして吹き飛ばされる。
入り口付近に集うは、怠惰の軍。
そして――集団の先頭で矢を番える男は。
「客人を出迎えんか! 無礼者がっ!
この儂が大霊堂をもらってやろうというのだ。白い龍よ、さっさとそこを明け渡せ」
ハイルタイは、再び矢を放った。
――衝撃。
矢は結界に阻まれて先へ行くことができない。
だが、矢の衝撃は確実に大霊堂の結界を蝕んでいく。
「そろそろじゃな……これで終いじゃ!」
放たれた矢は、適確に同じ箇所を射貫き続ける。
そして、三本目の矢が結界に触れた瞬間。
――バリンっ!
砕かれた硝子のように、宙を舞う結界。
雪とは違う煌めきを見せながら落ちるそれは、まるで芸術のようだ。
しかし、現実は無慈悲。
その芸術は大霊堂への道が拓かれた事を意味している。
歩み出す怠惰の軍。
一歩一歩と白龍の元へ突き進んでいく。
レチタティーヴォ
渺々たる赤い大地。連戦に次ぐ連戦。激戦に次ぐ激戦を飲み込んだその地に、長く影を曳く人影が――二つ。
一つは、絢爛な道化服を身にまとった髑髏。”操骸道化”、クロフェド・C・クラウン。
もう一つは、王国貴族の華やかな衣装と金のカツラを身につけた髑髏。”紅凶汲曲”、ラトス・ケーオ。
「どうなりますかな、この演目は」
「よき奏楽となれば良いのですが」
カタカタと乾いた音を立てて、眼窩に赤光を宿したクロフェドが言うと、ラトスはシルクハットを摘んで応じる。蕭々と、風。砂が軽い音と共に舞い上がり、彼方へと流れていく。
「”脇役”は十分に集めました。故に、相応には仕上がりましょうとも……あとは、”主演たる彼ら”がどのような音色を奏でるか」
「クフ!」
懸想するように呟いたラトスに、クロフェドは嗤った。敵意も、悪意も無い、健やかで華やかな声で。
「……愉しみです。此度の演目には各国の精鋭が集い、人類の救世主とも謳われるハンター達が揃っています。きっと、亡者達も浮かばれる事でしょう。
――ねぇ?」
クロフェドの声に、ぬらり、あるいは、カタリ、と音が鳴った。粘質で硬質なそれらが幾らにも重なると、大地が震えているかのような鳴動となる。合奏を背に、ラトスは手元の骨笛をくるりと回す。愉快げに細められた青光が――幾許かの後、再び開いた。そして。 「……そういえば、プエルの姿がありませんが?」
「あの坊やなら、迷子になったようですな。子守が探しに行っております」
「そうですか……」
思いつき、そう言ったのだろう。クロフェドの律儀な応答に興味なさげに言うと、ラトスは慨嘆したようだった。
「……いよいよ話題も尽きました」
「いつもの寄り道、でしょうが……遅い」
退屈だった。歪虚達が、幾らかの空虚を滲ませた声で言った、その時だ。
「――待たせたな」
声が響いた。壮年らしい、渋く、低い声だ。だが、その声は煮え滾る溶鉄のような熱を孕んでいた。声の主の装いは洒脱、の一言に尽きる。炎のように緩やかにウェーブする赤髪。最高級の生地で仕立てられた白い揃いのスーツに、紫がかった濃紺のシャツ。シャツと同色のコートを着崩し、左腰には黒と金からなる突剣を下げているが――洒落た様相を損なうことはなく、そこに在る。
跪いたクロフェドとラトスに目もくれず、男は愉しげに遠方を見た。
「善い空気だ。清浄なる白竜のおわす大地――なんと美しい!」
くつくつと喉を鳴らし、目を細めて、続ける。
「しかし、清冽なる舞台も一興ではあるが汚濁に穢されたそれもまた美しい。
――さて、私の主筆諸君?」
「はい」
二重の応答。男は、彼方を見つめたまま――口の端に、笑みを浮かべた。そして、短く、こう言った。 「役者達を連れてきた」
轟、と。巨大な気配が男たちの後背に湧いた。異質な影に覆われながらも男は、振り返りもしない。ただただ真っ直ぐに見据えるは”舞台”たる戦場。
「桟敷席の皆様もさぞや心待ちにしておられよう。いかに”災厄と花嫁は、いつだって遅れてやってくるもの”とはいえ、だ」
朗々と諳んじる男は、その先に何を見たか。
「……大いに奏で、大いに踊れ。此度の主賓にして主演なる彼らを退屈させるな」
――”退屈は罪だ”。
傲然と。愉快げに、そう言った。
●

ヴィオラ・フルブライト
ヴィオラ・フルブライト(kz0007)は冷然とした眼差しで彼方を見た。濛々たる噴煙を上げて此方に至る、怠惰の軍勢を。
「ヤクシー……」
その中でも一際目立つ指揮官、ヤクシーの威容を見て、ファリフ・スコールが呟いた。去来するのは、数カ月にわたるこの地での出来事。眼前にあるのは長きに渡る争乱の決戦場だった。だから。
「ヴィオラ」
「何でしょう?」
「ありがとう、ココまで、助けてくれて」
真っすぐに前を見つめたままの少女の言葉に、ヴィオラは小さく眼を見開いた。力のある強い眼差しは、ヴィオラがこの地に足を踏み入れた頃と比べるまでも無い。
「此処で、終わらせよう」
「ええ」
少女の決意に微笑と共にヴィオラが頷いた、その時だ。
「援軍です!」
駆け足で至った伝令が、そう告げたのだった。
(執筆:ムジカ・トラス)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
ARS

アイゼンハンダー
実験場とホープ一帯を見下ろす小高い丘の上でじっと佇むアイゼンハンダーに、「義手」が問う。
「『野戦病院を襲うとは卑劣な』……うん。確かにそう言ったよ」
『では、これから儂らが阿鼻叫喚の渦に叩きこんでやろうというあの陣地は如何? 儂が見る所、ここの所の戦で傷ついた有象無象が運び込まれているように見受けられるがな』
その問いは、責めているようでも案じているようでもなく、ただ愉しんでいた。
「傷病者だけじゃない。非戦闘員も大勢……」
彼女の言う非戦闘員とは非覚醒者を指しているようだ。
『で、お前はそれで良いのか?』
少女は、直接にはその疑問に答えなかった。
一糸乱れぬ隊形を維持したまま背後に控える改造ゾンビたちに振り返ると、凛とした声で告げる。
「これより、建設中の革命軍前線基地を強襲する! 最優先攻撃目標は整備中の機甲兵器と、各種の軍需物資である! 非戦闘員及び傷病者は――」
ここで、アイゼンハンダーは一旦言葉を切り、丘の下で実験場後周辺に集結しつつあるガエル・ソトの命令を受けた歪虚の集団を見た。
「――非戦闘員及び傷病者は無視せよ。無駄弾を、使うな」
目を逸らし、拳を握りしめながら少女はそう締め括った。
その命令が欺瞞であることは彼女自身が良く解っていた。彼女と配下の死者が総攻撃を仕掛ければ広範囲が巻き込まれるのは明らかである。
まして、彼女たちが連携するガエル、ヤクシー配下の歪虚にはそのような命令は行き届くまい。
『――つくづく、哀れで健気な娘よ。だが、それで良い。あの「戦友」二人を助けたいというのであれば、何時もの如く儂はお前の拳となるだけよ』
義手がそう呟いた時、アイゼンハンダーは迷いを振り切ったように号令を下す。
「A分隊はスモークディスチャージャーを一斉発射後友軍の突入を援護せよ! B分隊は私に続け! 敵が混乱している隙に機甲兵器を破壊する!」
轟音と共に連続発射された煙幕弾が実験場周辺で炸裂する。
その白煙の中を、黒い輝きに率いられた、赤い肩の死者たちが次々と駆け抜けていった。
(執筆:稲田和夫)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
「信じる」ということ

システィーナ・グラハム

エリオット・ヴァレンタイン
ガエル・ソトの部下たち、そしてアイゼンハンダーの襲撃に対する悲鳴と怒号が織りなす混乱の渦の中、システィーナ・グラハム(kz0020)は一歩ずつ大地を踏み締めるような、あるいは震えを隠すような足取りで何かの場合に備えて作られた演説用の舞台に歩を進めている。
「システィーナ様!?」
それに気付いたオクレールほか侍従隊が慌てて制止しようとする。
しかし、最初は同じように王女を止めようとしたエリオット・ヴァレンタイン(kz0025)が、無言でオクレールらの前に立った。
「騎士団長殿。どういうおつもりですか?」
咎めるようなオクレールの視線。エリオットは正面からそれを受け止め、静かに首を振る。
システィーナはそんなエリオットに小さく頷くと、儚げな、しかし精一杯の力を込めた声で語り始めた。
「皆さま。ここが何と呼ばれているか、皆さまはご存知でしょうか?」
突然響いた少女の声に、喧騒がやや収まる。
「ここは、ホープ……人類の希望と名付けられました。だから、ここは絶対に安全です……っ」
人々の願いは成就すると、少女は信じて疑わない。
勿論ちょっと冷静になれば「だからどうした」と怒鳴り返されかねない強引な理屈。
故に少女は畳みかけた。
「何故なら、聖地を奪回するという一つの目的のために皆さまの仲間が――あらゆる戦士たちが集い、肩を並べて戦っておられるのですから――!」
確かに少女の言葉は誇張ではない。
現在、実験場には辺境部族の精神的支柱ともいえるリムネラがおり、同盟軍に至ってはモデスト・サンテ、ダニエル・コレッティといった重鎮が指揮を取っている。
少女は言葉を切った。ここからが肝心だとでも言うように。
「そして今ここにいる皆さまをお守りするのは、我がグラズヘイム王国騎士団を率いるエリオット・ヴァレンタイン騎士団長と私の信頼する侍従隊。加えて国という枠組みにとらわれず、幾度も我々の力になってくれたハンターの皆さまです。皆さまの戦士を、私たちの友を信じましょう」
人々が一応の落ち着きを取り戻したことを感じたのだろう。王女は優雅に一礼すると騎士団長の側に戻る。と同時に膝からくずれた。
幸い、騎士団長と侍従長が左右からシスティーナを支えたのに気付いた人はほとんどいなかった。
「ご、ごめ……なさ……」
緊張によるものか恐怖によるものか、しゃくりをあげながら謝るシスティーナ。
だがエリオットは優しく笑ってみせる。「ご立派でございました」と耳元で告げると、続けて自身に至上命題を課した。
「必ずや殿下と、殿下の愛する人々をお護り致します。我が身命を賭してでも……」
そうしてグラズヘイム王国騎士団長は不退転の覚悟を以て北を、ついでハンターたちの方を見た。
決戦

ガエル・ソト

カッテ・ウランゲル
眼前に立ち塞がる人類の布陣を見て、ガエル・ソトは腕組みをしたまま呟いた。
表情こそ厳めしいが、その口調には僅かに気色が滲んでいる。
「安全な後方に、手勢を引き連れて後退したは良いが……そのせいで中央を守る肝心の機甲部隊に歩兵が随伴していない。これでは――」
中央突破してください、と言っているようなものだとガエルは内心溜息をつく。
「良かろう。躾の悪い子供には灸が必要だ。容赦はせぬぞ皇子とやら。真の英雄は勝利と栄光のためであれば、女子供を手にかけるとことなど、微塵も厭わぬ! 全軍、突撃せよ!」
●
ガエル・ソトは間違っていなかった。カッテ・ウランゲル(kaz0033)はまさしく、「中央突破してください」と彼に頼んでいたのだから。
幾ら機甲兵器の死角をすり抜けるとはいえ、ガエルに追随できるほどの機動力を持った戦力は限られる。自ずと、カッテの前に辿り着く部隊は少数になる。
そして、カッテの護衛に当たる部隊が敵を押し留めている間に、人類側の両翼に潜ませた奇襲部隊が反転し、護衛部隊と共に孤立したガエルを三方向から包囲する。
カッテは、ガエルが必ず乗って来ると踏んでいた。
「強い英雄願望を持つ方です。二度の敗北に屈せず見事に敵の弱点をついて敵将を討ち、一発逆転……という物語はとても魅力的な筈ですから」
事も無げに少年は言い放ち、微笑んだ。
あるいは、驚くハンターもいるかもしれない。
要は、この作戦の要はカッテ自身が囮になる、ということなのだ。
どこか一つでも作戦に綻びが出れば、それは直ちにカッテの危険に繋がる。まして、相手は災厄の十三魔だ。首尾よく包囲したとしても決して油断のできる相手ではない。
「余り……買いかぶらないでくださいね?」
僕だって、怖いんです、と。
その付け加えた言葉とは裏腹に、少年は微塵の淀みもなく、花が咲いたように笑った。
「だから、陛下と僕は皆さんを信じます」
そう言って、カッテは静かに立ち上がる。
それが、戦闘開始の合図となった。
(執筆:稲田和夫)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)
●聖地奪還 エピローグ(5月13日更新)
辺境東部で南下する怠惰に籠城戦を仕掛けた『マギア砦籠城戦』。
CAMの戦力投入を持って怠惰に打撃を加えた『ナナミ川撃滅戦』。
そして――。
辺境にて聖地として慕われる『リタ・ティト』を取り戻すべく大規模な反抗作戦を試みた『聖地奪還』。
三度の戦で流れた血は想像するだけで顔を背けたくなる惨状だ。
特に今回の戦いが一番被害が大きい。聖地は奪還できたものの、災厄の十三魔アイゼンハンダーがCAM実験場へ突入。CAMや物資を徹底的に破壊。さらに魔の手はホープにも及び施設だけではなく、人的被害も深刻なレベルであった。
勝利――だが、手放しで喜ぶ気にはなれなかった。
犠牲は決して無駄にはしない。
各国の想いが、永きに渡る激戦に終止符を打つ。
●
――CAM実験場、及び開拓地ホープ。
無傷で――というわけにはいかなかった。災厄の十三魔・アイゼンハンダーの激しい攻撃を受けた影響で、何れも甚大な被害が生じている。
おそらく、この地での活動を再会するためには、大規模な復興作業が必要となるだろう。
無論、戦闘に参加した多くのハンターも尋常でない傷を負っているものが多かった。ホープには医療施設こそあるものの、そこに収容しきれない怪我人があちこちでうめき声を上げている。人々の顔にはまだ疲労の色が濃くなっていて、辛い現実を目の当たりにした現実が、彼らの精神を蝕んでいるのだった。
勝利と呼ぶにはほど遠い、現在の状態。正直な話、壊滅していてもおかしくないような状況だった。何とか持ちこたえることができたのが、むしろ奇跡にも思えてくる。
しかし、曲がりなりにも歪虚を撤退させることができた――これは紛れもない事実で、結果だけを見れば人類側の勝利、なのだろう。大きな犠牲の上の、紙一重の勝利なのかも知れないが。
 この開拓地ホープを訪れていた『ガーディナ』リーダーにして聖地の巫女・リムネラ(kz0018)も、何か手伝えることはないかと自ら申し出、彼女が出来るだけの医療支援や炊き出しなどにも協力をしていた。
この開拓地ホープを訪れていた『ガーディナ』リーダーにして聖地の巫女・リムネラ(kz0018)も、何か手伝えることはないかと自ら申し出、彼女が出来るだけの医療支援や炊き出しなどにも協力をしていた。
初めて見る戦場が、恐ろしくなかったというとそれは嘘になる。
しかしリムネラには使命があった。
なんとしてでもこの戦いを勝利に導き、そして聖地を奪還するという使命である。
無論彼女自身が戦いに赴くわけではない。しかし今回の戦いにおいて、彼女が旗印のような存在だったのはおそらく間違いの無い事実だろう。
しかし、時間は無情にも過ぎていく。
怪我人が多く収容され、リムネラも右へ左へと手伝いに大わらわだ。出来るだけ笑顔を絶やさぬようにしながら、彼女は手伝いに走り回っていた。
――それでも。
「連絡が入りました、聖地は何とかなったようです――!」
ハンターたちからその言葉を聞いて、リムネラはかたんとくずおれた。
「……っ、リムネラさんっ!」
リムネラの尋常ならざる様子に気づいたハンターたちが慌てて彼女に近づく。……彼女はまるで糸の切れた操り人形のように、呆然と座り込んでいた。
張り詰めていた、緊張の糸がふつりと切れたのだ。
おそらく慣れない状況や作業の連続で、疲労は既に限界だったのだろう――見れば彼女は随分と擦り傷だらけになっている。以前よりも少しやつれている気もするが、しかしそれでも彼女にはやらなければならないことがある。
聖地の無事を確認すること。
ずっと心配し続けていた巫女たちの、そして白龍の状況を確認すること。
でも、ああ。
リムネラは大きな深呼吸を一つすると、ぽろりと一粒、涙をこぼした。それから、止めどなく涙があふれ出してくる。
「大丈夫……大丈夫、デス」
心配してくれるハンターたちにそう言いながら、彼女はハンカチでそっと頬をぬぐった。そして、小さく微笑んでみせる。
それこそが、疲れ切った彼女が今出せる、最大級の喜びの表現――なのだった。
●


 「へぇ。蒼き勇者を導いた者が、こーんなジジイだとは思わなかったよ」
「へぇ。蒼き勇者を導いた者が、こーんなジジイだとは思わなかったよ」
各国の戦士やハンター達を導いて聖地を人類の手に取り戻した功労者の姿を見た大巫女は、開口一番にそう言い放った。
大巫女の視界にいるのは、辺境は蛇の戦士・シバ(kz0048)だ。
「まだ生きておったか」
「お互いにね。しぶとく生き残っちまうのは、定めなのかねぇ」
前にお互い顔を合わせたのは、いつ頃だったろうか。
久しぶりの再会ではあるが、喉から言葉が出てこない。
だが、言葉は無くとも二人の空気が何となく意志を伝えてくれる。
「ここへ来るまで随分無理したみたいだね」
大巫女は、シバの身を案じた。
先程ハンターからシバの状況について話を聞いたのだろう。部族が滅んでも尚、戦い続けようとする姿勢は何一つ変わらない。
「無理をしてでも取り戻さなければならぬ。この聖地も。そして……」
「大巫女っ!」
シバがそう言い掛けた瞬間、傍らから駆け込んできたのはスコール族の族長ファリフ・スコール(kz0009)だ。
勢いそのまま大巫女へ抱きつき、満面の笑顔を浮かべる。大巫女はかなりの高齢なはずだが、まったく肉体に衰えを見せない巨躯がファリフの体当たりを正面から受け止める。
「おお、ファリフかい。元気そうだね」
「うん! ここへ来るまですっごく大変だったけど、みんなで頑張ったからね」
ファリフはスコール族の族長へ就任する前に戦士として聖地を訪れている。
大巫女とはその時から知り合ったようだ。
久しぶりの再会に大巫女にも笑みが浮かぶ。
「それと、オイマトの子も一緒かい。今日は千客万来だね」
顔を上げた大巫女に対してオイマト族の族長バタルトゥ・オイマト(kz0023)は、小さく会釈をする。
大霊堂も一時、災厄の十三魔ハイルタイが到達する事態に見舞われた。
しかし、他の戦線から怠惰侵攻軍指揮官のヤクシーや同じく災厄の十三魔であるガエル・ソトが撃破された事を知ってハイルタイは撤退。聖地にも相応の被害は出ているものの、大霊堂そのものは無事のようだ。
「大巫女……再会を喜ぶのは良いが……白龍を」
バタルトゥ達がここを訪れたのは、大霊堂の無事を確かめるだけではない。
大霊堂の奥に居る白龍と謁見する為だ。永きに渡り生きてきた白龍は、多くの知識を持っている。白龍に相談したい事は山ほどある。少しでも白龍から対歪虚の情報を教えてもらわなければ――。
「そうだね。早く白龍に会った方がいい」
そう言いながら、ファリフを地面に立たせる大巫女。
その表情には先程のような笑顔は消えていた。変わって悲しみ交じりの真剣な表情が顔を見せる。
「白龍に残された時間は少ない。急いだ方がいい」
白龍は大霊堂を歪虚の侵攻から護るべく、残り少ない寿命を削って結界を張り続けていた。この為、白龍の寿命は間もなく尽きようとしている。ファリフ達が大霊堂へ到着したのはギリギリだったようだ。
「……行け御両人、恐らくは今生の別れとなるであろう。白龍の覚悟に……応えて来い」
「シバさんは……行かないの? これが最後なのに……」
ファリフの問いに、シバは穏やかに応えた。
「相応しき器がある。お主等二人が、行かねばならぬのだ」
「……」
シバの後押しでファリフとバタルトゥは、白龍の居る部屋へ歩み出す。
辺境の未来を指し示す道標を手に入れる為に。
●
『……来たか』
白龍は、巨大な部屋の中央で大きな体を丸めるように横たわっていた。
息も絶え絶えで、白く美しい体表から徐々に光の胞子が漏れ出している。マテリアルが白龍から失われていくのが傍目でも分かる。
「白龍……」
ファリフは。白龍の身を案じた。
ファリフの目から見ても寿命が尽きかけているのは一目瞭然だ。
初めてファリフが聖地を訪れた時に、優しい眼差しで見守ってくれた白龍。
体は崩れかけていても、白龍の優しい声は今も変わらない。
『案ずるな……こうなる事は、分かっていた。
時間が惜しい……知りたい事に応えよう』
白龍は、自らの寿命を把握していた。
本来であれば巫女を通して神託を授ける事が慣わしであったが、その慣わしを守る程の時間的余裕がない。だからこそ、ファリフ達と直接白龍が会話する事が大巫女によって認められたようだ。
「じゃあ、ボクから」
最初に問いかけたのは、ファリフだった。
「白龍が前に教えてくれたんだよね。星の友を探せって。
ボク、いろんなところを探しているんだけど、見つからないんだ。星の友が何処にいるか教えて?」
『星の友なら……もう出会っている』
「え?」
ファリフは、驚いた。
神託に従って一緒に辺境を救ってくれる星の友を捜し続けていたファリフ。辺境に限らず、王国にも星の友となってくれる者を捜し続けてきた。
だが、白龍によれば既に星の友と出会っているというのだ。
「どういう事?」
『星の友とは、迷う者を導き共に歩む者。
それは一人ではない。
星の友は星の数だけ存在し、迷った時は共に悩み、共に困難を乗り越えてくれる。そして、既に彼らとの出会いは果たしている』
神託を受けて様々な場所を探していたファリフにとって、衝撃的な事実であった。
既に出会っていた。
それも、一人ではなく星の数程の人々。
ファリフは必死に考えを巡らせる。
だが、その答えは傍らに居たバタルトゥから発せられる。
「……ハンターか」
『否。それに限らぬ。伝説の刺青を持つ者と共に歩む者すべて。即ち、いまこの地に生きる者すべてに資格がある』
「それは……帝国の人達も、星の友かもしれないって事?」
『私が答える事ではない。だが境界に囚われぬ様、心せよ。それを作るのは、他ならぬお前自身だ』
ファリフは再び考え始める。
星の友とは、共に歩むとは、どういう事か。
むしろ、様々な人の出会いがファリフを成長させて星の友を広げていく。
では……対立の先に進むには、どうすれば良いのか?
白龍は応えぬ代わりに、自らの話を続けた。
『我が子らよ、お前達はまだ弱い。力を探すがいい。伝承の狭間に失われた力を、生きる術を』
「どういうこと……?」
ファリフが興味を惹かれ、身を乗り出す。対して白龍の言葉は、あくまで穏やかに。
『かつてこの地にてイステマール、ナーランギと称されていた、幻獣と呼ばれし者達。彼らもいずれ我が子らに力を貸してくれよう。我が半身に会うもよかろうな。我が倒れれば悪い影響は避けられぬが……そこは、蛇の戦士に相談するがいい』
ファリフは考え込み、答えなかった。
沈黙が部屋を支配する前に、白龍はバタルトゥへ声をかける。
『それから……オイマトの者よ。
仇敵を撃つ事に拘るな。仇敵はいずれ撃たねばならぬ相手。だが、その時には傍らに助ける者の存在がある。彼らを蔑ろにしてはいけない』
仇敵――ハイルタイの事を差しているのであろう。
かつてのバタルトゥなら、ハイルタイが絡んだだけで単身動きだそうとする節もあった。白龍はその事を知って釘を刺してきたのだろう。
「……ご配慮、感謝する」
『……仇敵に心を乱される事なく、星の友の一人として……』
白龍がそこまで言い掛けた瞬間、白龍の体から大量の光の粒子が宙に舞う。
白龍の体にあったマテリアルが自然へ還っていく瞬間だ。
ファリフは――叫ぶ。
「白龍! 待ってっ!」
避けられない別れの時が来た。
その事はファリフも頭では理解している。
それでも、叫ばずにはいられない。
『……伝説の子……我は消えるのではない……マテリアルが歪虚に穢されぬ限り、すべてのマテリアルはあるべき場所に還る……だけ。
別れは一時……必ず、またいずこで……』
消えかける体の中、白龍は最後の言葉を残す。
星の友と出会うという事は、いつか別れが来る。
その出会いと別れを乗り越え、ファリフは成長していく。
白龍にとってそれを見届けられない事は無念であるが、マテリアルが還る場所でファリフのを願う事はできる。
『我が対に……会うことが……あれば……詫びを……我は……しばし、眠りを……』
白龍の体から大量のマテリアルが消失した。
白龍がいたはずの場所には、ただ広いだけの空間があった。
失われていく温もりの中、目に涙を溜めたファリフは一言だけ呟いた。
「おやすみ、白龍。……またね」
●
疲れ果てて横になってから、どれくらい経ったろう。
リムネラはぼんやりと目を開け、時間の経過を目の当たりにする。予想外の事態の数々に、リムネラの中の処理能力が追いつかなかったのだろうと、ホープで医療活動を行っているものたちが言って慰めてくれた。
たしかにそうかも知れない。
――と――。
わずかに空気が変わったような――気がした。
それがなんなのか、巫女であるリムネラにすらわかるようなわからないような、そんな本当にわずかな違い。マテリアルの質、といえばいいのだろうか、いやそれもしっくりこないのだが。
聖地が奪還出来たと聞いた時の疲労もある程度癒えてきたこともあり、起き上がろうとしたリムネラだったのだが、ふと顔を上げてみると小さな相棒のヘレが心配そうに彼女のことを見つめていた。
「大丈夫……問題ない、デスよ」
しかしそう言ってはみるものの、ぴりりとした違和感がぬぐえない。
――そこまで考えて、リムネラはふと、白龍のことが気になった。
といっても、ヘレのことではない。
聖地の守護をしていた、愛おしく懐かしい、年老いた白龍――。
あの龍は、無事だろうか。聖地を守り抜くことは、できたのだろうか。
そんなことをぼんやりと思いながら、幼い白龍をそっと撫でてやる。ヘレはいつもながらリムネラによく懐いていて、撫でてやると嬉しそうに喉を鳴らすのだ。
しかし、ヘレは今日はいつもよりおとなしい。
理由はわからないが、静かな雰囲気をたたえている。静謐な雰囲気は、どこか――リムネラの知っているヘレと、違うような気がした。
どうにも聖地の白龍に似ている気がして――しかし彼女は首を小さく横に振る。
いいや、不吉なことは考えまい。
可能性を疑ってばかりでは、動きも鈍ってしまう。
「ヘレ、……ドウかしましたか?」
リムネラがそう言ってそっと手を伸ばすと、ヘレはいつものように彼女の肩に乗る。
そう、いつも通りに。
考えてはいけない。
ユニオンリーダーとしてホープの状態も放って置くことは出来ないが、リムネラはそれ以前に聖地の巫女だ。
その彼女が聖地における良くない可能性を考えてしまえば、それは現実になってしまうかも知れない。
まだ、明らかになっていないのだから。
だからリムネラは考えないことにした、悪い可能性というものの存在を。
もっとも、現実は、やはり甘くないのだけれど――。
「サァ、行きマショウ。皆サン、マダとても困ってイルはずデス」
リムネラはゆっくりと起きて、そしてまだ混乱の続くホープの支援へと向かうのだった。
●
「お初にお目にかかります。エトファリカ連邦国より上様の命を受けて聖地奪還に馳せ参じました朱夏と申します。以後、お見知りおきを」
休んでいたファリフとバタルトゥに東方よりの使者、朱夏(kz0116)は恭しく挨拶をした。
シバを訪ねたが、彼は朱夏をまず二人の族長の前へと通したのだ。それが、器であり、筋であると。
 朱夏はやや緊張気味した面持ちで二人に臨む。
朱夏はやや緊張気味した面持ちで二人に臨む。
「……そうか」
いつものようにバタルトゥは、最低限の口数で応える。
それが朱夏を更に焦らせる。
「あ、何か御無礼が!? 大変、も、申し訳……」
「バタルトゥはいつもこんな感じだよ。
あ、ボクはファリフ・スコール。よろしくね」
「スコール族の族長! 此れよりとも宜しくお願いいたす」
「そんなに固くならなくても良いよ。もっと気軽に……」
「いけませぬ。我が祖国を救うモノノフには礼を尽くせと上様から厳命されております」
祖国を救うモノノフ。
その事が自分達であり、東方――エトファリカ連邦国の事を指し示す事は二人にも分かっていた。彼らは助けを求める為に遠い西方までやってきた。自分達と同じように歪虚に攻められ、窮地に陥っている彼らの身の上をシバから聞いていた。
「我がエトファリカ連邦国は、歪虚の脅威に晒されております。国を護る最後の盾である我等を西方へ送り出した上様のご判断は、一種の賭け。今もエトファリカは危機に瀕しております」
朱夏が最後の盾という事は、最終防衛戦力を救援要請へ回した事を意味している。
その分防衛戦力が手薄になっている事に気付けば、歪虚が一気にすべてを終わらせにかかるだろう。
「話はシバから……聞いている。
我等の助けが必要、とか」
「左様。シバ殿から西方のモノノフは窮地に陥った弱者を救う者と伺っております。何卒、上様にお力添えを」
朱夏は、再び頭を下げた。
仮に東方の歪虚を撃退できたとしてもどのような礼ができるかは分からない。もしかしたら復興に費用がかかって礼らしい礼ができないかもしれない。
そうだとしても、祖国の命運を背負って西方へやってきた朱夏にできる事は頭を下げる事しかない。
「顔を上げてよ。君達は祖国が危ないのに、聖地奪還を助けてくれた。だったら、今度はボク達が君達を助ける番だよね?」
「……では!」
「一つ聞く……西方への転移門は、いつ稼働する?」
バタルトゥの問いに朱夏は答える。
歓喜と感謝が混じった声をあげて。
「……か、かたじけない。転移門は西方から持参した龍の欠片を用いて稼働させるが、今しばらく準備が必要。準備が整ったら、改めて我が東方を救うべく支援をお願いする」
●
「白龍は逝ったか」
「歪虚のせいでちょっとばかり早まったけどね。白龍にも寿命はあるんだよ」
シバと大巫女は、二人だけで会っていた。
大霊堂から出て聖なる山『ビャスラグ山』を背に広がるは、辺境の大地。
まだすべてではないが、怠惰との戦いで取り戻した大地が二人の前に広がっている。
「無論だ。可能なら、もう少し話したかったが……致し方ない」
「相変わらず素っ気ない男だねぇ」
「それより、これより巫女はどうする? 白龍はおらぬぞ」
シバは白龍が不在となった巫女を案じていた。
巫女は白龍に仕えて神託を受ける存在だ。その白龍がいなくなったとすれば、巫女の動揺は計り知れない。
しかし、巫女にして豪胆と評すべき大巫女に動揺は感じられない。
「何を言っているんだい。土地の浄化は巫女にもできる。これから歪虚に穢された土地を浄化していかなきゃならないんだ。泣き言を言っている暇はないよ」
「夜煌祭か」
シバは、ぽつりと呟いた。
辺境巫女に伝わる祭りで大精霊に捧げる感謝と祈りの祭り。
以前、リムネラが狂気の欠片を浄化した祭りとしてハンター達の記憶にも新しい。
だが、大巫女は大きく首を振る。
「そんなもんじゃないよ。大霊堂の巫女が総出で浄化の儀式をやらないといけない。こりゃ大仕事になるよ。新しい白龍が大霊堂に還ってくる日まで辺境を護らないといけないからね」
「ほう、するとやはりあの白い龍が……」
シバにはまだ幼い小さな白い龍の記憶が蘇る。
まだ巫女の背中を追いかけるだけの幼い龍であるが、長い年月をかけて成長すれば亡くなった白龍の後を継いで大霊堂に降り立つ白龍となるかもしれない。
「さぁね。先の事は分からないよ。
だけど、あたしは信じてるよ。あの子と一緒にいるあの龍が、きっと立派になって大霊堂に還ってくる事をね」
大巫女は、空を見上げた。
同じ空の下にいるはずの一人の巫女と小さな白い龍を思い浮かべながら。
 拳を突き上げ勝鬨を上げる者。腰を抜かしたように座り込み、生あることに安堵する者。あるいは巨人との闘争に敗れ、倒れ伏した者。
拳を突き上げ勝鬨を上げる者。腰を抜かしたように座り込み、生あることに安堵する者。あるいは巨人との闘争に敗れ、倒れ伏した者。
闘争の果てにニンゲンどもが見せるそういった狂乱を遥か眼下に見下ろしながら、ガルドブルムは鼻を鳴らして両翼で大気を叩いた。
――悪くはねェ。悪くはなかった、が。
元は嫉妬の木偶人形の報せを受け、気も乗らぬまま首を突っ込んだこと。胸糞悪い始まりの割には愉しめたと言えなくはない。が、それでも満たされぬ塊が躰のうちで燻って、いや猛り狂っている。ドロドロとした塊が、叫んでいる。
さらなる闘争を! あらゆる欲望を!
混沌の如き原始的衝動。
溶岩のようなそれを胸のうちで自覚し、赤子をあやすようにそっと撫でた。
時は腐るほどある。お前を――俺を――満たすものもいずれ現れよう。なればその時まではせいぜい愉しみを探そうではないか。
――さて。んじゃ、次は何をしようかねェ……。
いつだか強奪したあの機械人形――CAMとやらを弄ってみるか。あるいは突然ニンゲンどもの中に現れた、一風変わったニオイの一団を追ってみるか。
――いや。
どっちもやろう。どれもこれもやっちまおう。
何故ならこの身は、強欲なのだから。
 哄笑を上げ天を駆けてゆく竜の姿を見つめ、劇作家は紅い唇を歪めて口角を吊り上げた。
哄笑を上げ天を駆けてゆく竜の姿を見つめ、劇作家は紅い唇を歪めて口角を吊り上げた。
「困った役者だ。私の話など聴きやしない……」
帽子のツバを引き、目元を隠してくつくつと忍び笑いを漏らす。そうして天上の竜がどこかへ去るのを待つと、劇作家の笑いは大笑に変わった。
両腕を広げて天を仰ぐ。
「だがそれこそが一流! 故に私は舞台を整えよう。“王に必要なのは玉座と衣装、けれどそれだけじゃあまだ足りない。群衆こそが王を王たらしめるのさ”」
ひとしきり笑った後で劇作家が視線を地上に移す。そこには、歓喜に沸く人間たちの姿がある。
「“英雄は群衆を殺し、群衆は英雄を殺す”。さあ、私の主筆諸君。唯一無二の戯曲を観せてくれ!」
帽子を被り直すと、劇作家――レチタティーヴォは逢魔時の狭間に消えた。

 「寝ておられなくて宜しいのですか?」
「寝ておられなくて宜しいのですか?」
ノアーラ・クンタウの執務室にて、カッテ・ウランゲル(kz0033)は部屋に入るなりそう口を開いた。
「私は覚醒者だぞ? あんな怪我など数日で治る……まあ、今回は流石に死にかけたがな」
「良かった。負傷したと聞いてずっと心配していたんです」
嬉しそうに笑うカッテに、流石の騎士皇ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)も僅かに口元を緩めた。
「……心配をかけたな」
「全くです」
カッテはその笑顔を全く崩さぬまま、ドンッと分厚い書類の束を机の上に置いた。
「なんだこれは」
眉をひそめるヴィルヘルミナ。
「折角のこれも、姉上の決裁が無くては宝の持ち腐れですから」
その書類は言うまでも無く、今回の『聖地奪還作戦』における、魔導型CAM、そして魔導アーマーの実戦データーを纏めたものだ。
「くっ……傷が……」
「それは、いけませんね。さあ、すぐ横になってください。横になったままでも資料の確認は出来ますよね?」
「歪虚かお前は」
にこにこしている弟を、ジト目で睨みながらもヴィルヘルミナはざっと資料を見た。
「ふむ……斜め読みだが、感触は悪くないか?」
「ええ、ナサニエルとビットマン博士にも喜んで貰えると思います」
その言葉と裏腹に、少年の顔色は曇っていた。
「ナサニエルの奴は聞き流しそうだが、二人には成果を無駄にするなと伝えておけ」
確かに、人類は聖地の奪還に成功し、ヤクシーとガエル・ソトという強力な敵将を討つことにも成功している。
だが、その犠牲は決して少なくは無かった。
戦死者は勿論、ガエルとの戦いでは貴重なCAMが数機修理不能なまでに大破したという。
「負傷者の搬送と処置は第九師団に再度指令を。戦死者への補償は第一師団と各課を総動員して最優先で進めます」
淡々と、感情を抑えた声で必要なことだけを報告したカッテはこう付け加えた。
「二人には、血を流した人々のことを忘れないで欲しいと」
そして、最も被害が大きかったのがCAM実験場「ホープ」だ。
「アイゼンハンダーについては、その後の状況から帝国領内に去ったと見て間違いありません。……残念ですが」
「システィーナの様子は?」
「僕も真っ直ぐこっちへ来たので、お会いしてはいません。大きなお怪我が無かったのは……」
一瞬言葉に詰まった後、カッテは続ける。
「幸いでした」
ヴィルヘルミナも目を伏せ、実験場の被害と、それを目の当たりにしたであろう王女のことを慮った。
「これも、システィーナにとっては試練なのかもしれん」
カッテはそれには敢えて応じず、別の資料を取り出した。
「僕の方で把握している機甲兵器の被害はそこにある通りです。ですが――」
確認するように言葉を切ったカッテにヴィルヘルミナは頷く。
「間違いない。魔導アーマーが連中に奪取された」
聖地奪還に乗じるように姿を見せた暴食の歪虚――帝国で暗躍する四霊剣とその配下によって輸送部隊にも被害が出た他、魔導アーマー2機が歪虚に奪われていたのだ。
「それについても調査を命じましょう。では、失礼します」
皇子はそう言って一礼し、踵を返した。
「カッテ」
その背中に、ヴィルヘルミナは言葉を投げかける。
「親父殿を殺したのは不敗の剣豪だ」
「……そうですか」
カッテは足を止める。
「すまない」
「弟が、自分の命をかけて十三魔の一人を討ったというのに、姉がこれでは恰好がつかんな」
あくまでも冗談めかしたヴィルヘルミナの言葉には、様々な想いが込められていた。
「十三魔を討つことが出来たのは、僕の力ではありません。同じように、姉上が無事だったのは、姉上だけの力だけではない筈です。現に、不変の剣妃についてもこの戦いを通じて新しい情報が集まってきています」
「……そうだな。彼らに、ハンターたちに感謝しよう。我が愛しき剣たちに」
そう言ってから、ヴィルヘルミナは少しだけ優しい口調で呼びかけた。
「……良く頑張ったな。無事で良かったよ」
その言葉に振り返ったカッテは少しだけ柔らかい口調で返した。
「姉上こそ……ご無事で、何よりでした」
カッテの白い手袋を嵌めた細い指が眦を拭い、ヴィルヘルミナがそれを見て微笑む。
この一瞬だけ、ゾンネンシュトラール帝国の皇帝と皇帝代理人は姉弟の表情に戻っていた。
CAMの戦力投入を持って怠惰に打撃を加えた『ナナミ川撃滅戦』。
そして――。
辺境にて聖地として慕われる『リタ・ティト』を取り戻すべく大規模な反抗作戦を試みた『聖地奪還』。
三度の戦で流れた血は想像するだけで顔を背けたくなる惨状だ。
特に今回の戦いが一番被害が大きい。聖地は奪還できたものの、災厄の十三魔アイゼンハンダーがCAM実験場へ突入。CAMや物資を徹底的に破壊。さらに魔の手はホープにも及び施設だけではなく、人的被害も深刻なレベルであった。
勝利――だが、手放しで喜ぶ気にはなれなかった。
犠牲は決して無駄にはしない。
各国の想いが、永きに渡る激戦に終止符を打つ。
●
――CAM実験場、及び開拓地ホープ。
無傷で――というわけにはいかなかった。災厄の十三魔・アイゼンハンダーの激しい攻撃を受けた影響で、何れも甚大な被害が生じている。
おそらく、この地での活動を再会するためには、大規模な復興作業が必要となるだろう。
無論、戦闘に参加した多くのハンターも尋常でない傷を負っているものが多かった。ホープには医療施設こそあるものの、そこに収容しきれない怪我人があちこちでうめき声を上げている。人々の顔にはまだ疲労の色が濃くなっていて、辛い現実を目の当たりにした現実が、彼らの精神を蝕んでいるのだった。
勝利と呼ぶにはほど遠い、現在の状態。正直な話、壊滅していてもおかしくないような状況だった。何とか持ちこたえることができたのが、むしろ奇跡にも思えてくる。
しかし、曲がりなりにも歪虚を撤退させることができた――これは紛れもない事実で、結果だけを見れば人類側の勝利、なのだろう。大きな犠牲の上の、紙一重の勝利なのかも知れないが。

リムネラ
初めて見る戦場が、恐ろしくなかったというとそれは嘘になる。
しかしリムネラには使命があった。
なんとしてでもこの戦いを勝利に導き、そして聖地を奪還するという使命である。
無論彼女自身が戦いに赴くわけではない。しかし今回の戦いにおいて、彼女が旗印のような存在だったのはおそらく間違いの無い事実だろう。
しかし、時間は無情にも過ぎていく。
怪我人が多く収容され、リムネラも右へ左へと手伝いに大わらわだ。出来るだけ笑顔を絶やさぬようにしながら、彼女は手伝いに走り回っていた。
――それでも。
「連絡が入りました、聖地は何とかなったようです――!」
ハンターたちからその言葉を聞いて、リムネラはかたんとくずおれた。
「……っ、リムネラさんっ!」
リムネラの尋常ならざる様子に気づいたハンターたちが慌てて彼女に近づく。……彼女はまるで糸の切れた操り人形のように、呆然と座り込んでいた。
張り詰めていた、緊張の糸がふつりと切れたのだ。
おそらく慣れない状況や作業の連続で、疲労は既に限界だったのだろう――見れば彼女は随分と擦り傷だらけになっている。以前よりも少しやつれている気もするが、しかしそれでも彼女にはやらなければならないことがある。
聖地の無事を確認すること。
ずっと心配し続けていた巫女たちの、そして白龍の状況を確認すること。
でも、ああ。
リムネラは大きな深呼吸を一つすると、ぽろりと一粒、涙をこぼした。それから、止めどなく涙があふれ出してくる。
「大丈夫……大丈夫、デス」
心配してくれるハンターたちにそう言いながら、彼女はハンカチでそっと頬をぬぐった。そして、小さく微笑んでみせる。
それこそが、疲れ切った彼女が今出せる、最大級の喜びの表現――なのだった。
●

シバ

ファリフ・スコール

バタルトゥ・オイマト
各国の戦士やハンター達を導いて聖地を人類の手に取り戻した功労者の姿を見た大巫女は、開口一番にそう言い放った。
大巫女の視界にいるのは、辺境は蛇の戦士・シバ(kz0048)だ。
「まだ生きておったか」
「お互いにね。しぶとく生き残っちまうのは、定めなのかねぇ」
前にお互い顔を合わせたのは、いつ頃だったろうか。
久しぶりの再会ではあるが、喉から言葉が出てこない。
だが、言葉は無くとも二人の空気が何となく意志を伝えてくれる。
「ここへ来るまで随分無理したみたいだね」
大巫女は、シバの身を案じた。
先程ハンターからシバの状況について話を聞いたのだろう。部族が滅んでも尚、戦い続けようとする姿勢は何一つ変わらない。
「無理をしてでも取り戻さなければならぬ。この聖地も。そして……」
「大巫女っ!」
シバがそう言い掛けた瞬間、傍らから駆け込んできたのはスコール族の族長ファリフ・スコール(kz0009)だ。
勢いそのまま大巫女へ抱きつき、満面の笑顔を浮かべる。大巫女はかなりの高齢なはずだが、まったく肉体に衰えを見せない巨躯がファリフの体当たりを正面から受け止める。
「おお、ファリフかい。元気そうだね」
「うん! ここへ来るまですっごく大変だったけど、みんなで頑張ったからね」
ファリフはスコール族の族長へ就任する前に戦士として聖地を訪れている。
大巫女とはその時から知り合ったようだ。
久しぶりの再会に大巫女にも笑みが浮かぶ。
「それと、オイマトの子も一緒かい。今日は千客万来だね」
顔を上げた大巫女に対してオイマト族の族長バタルトゥ・オイマト(kz0023)は、小さく会釈をする。
大霊堂も一時、災厄の十三魔ハイルタイが到達する事態に見舞われた。
しかし、他の戦線から怠惰侵攻軍指揮官のヤクシーや同じく災厄の十三魔であるガエル・ソトが撃破された事を知ってハイルタイは撤退。聖地にも相応の被害は出ているものの、大霊堂そのものは無事のようだ。
「大巫女……再会を喜ぶのは良いが……白龍を」
バタルトゥ達がここを訪れたのは、大霊堂の無事を確かめるだけではない。
大霊堂の奥に居る白龍と謁見する為だ。永きに渡り生きてきた白龍は、多くの知識を持っている。白龍に相談したい事は山ほどある。少しでも白龍から対歪虚の情報を教えてもらわなければ――。
「そうだね。早く白龍に会った方がいい」
そう言いながら、ファリフを地面に立たせる大巫女。
その表情には先程のような笑顔は消えていた。変わって悲しみ交じりの真剣な表情が顔を見せる。
「白龍に残された時間は少ない。急いだ方がいい」
白龍は大霊堂を歪虚の侵攻から護るべく、残り少ない寿命を削って結界を張り続けていた。この為、白龍の寿命は間もなく尽きようとしている。ファリフ達が大霊堂へ到着したのはギリギリだったようだ。
「……行け御両人、恐らくは今生の別れとなるであろう。白龍の覚悟に……応えて来い」
「シバさんは……行かないの? これが最後なのに……」
ファリフの問いに、シバは穏やかに応えた。
「相応しき器がある。お主等二人が、行かねばならぬのだ」
「……」
シバの後押しでファリフとバタルトゥは、白龍の居る部屋へ歩み出す。
辺境の未来を指し示す道標を手に入れる為に。
●
『……来たか』
白龍は、巨大な部屋の中央で大きな体を丸めるように横たわっていた。
息も絶え絶えで、白く美しい体表から徐々に光の胞子が漏れ出している。マテリアルが白龍から失われていくのが傍目でも分かる。
「白龍……」
ファリフは。白龍の身を案じた。
ファリフの目から見ても寿命が尽きかけているのは一目瞭然だ。
初めてファリフが聖地を訪れた時に、優しい眼差しで見守ってくれた白龍。
体は崩れかけていても、白龍の優しい声は今も変わらない。
『案ずるな……こうなる事は、分かっていた。
時間が惜しい……知りたい事に応えよう』
白龍は、自らの寿命を把握していた。
本来であれば巫女を通して神託を授ける事が慣わしであったが、その慣わしを守る程の時間的余裕がない。だからこそ、ファリフ達と直接白龍が会話する事が大巫女によって認められたようだ。
「じゃあ、ボクから」
最初に問いかけたのは、ファリフだった。
「白龍が前に教えてくれたんだよね。星の友を探せって。
ボク、いろんなところを探しているんだけど、見つからないんだ。星の友が何処にいるか教えて?」
『星の友なら……もう出会っている』
「え?」
ファリフは、驚いた。
神託に従って一緒に辺境を救ってくれる星の友を捜し続けていたファリフ。辺境に限らず、王国にも星の友となってくれる者を捜し続けてきた。
だが、白龍によれば既に星の友と出会っているというのだ。
「どういう事?」
『星の友とは、迷う者を導き共に歩む者。
それは一人ではない。
星の友は星の数だけ存在し、迷った時は共に悩み、共に困難を乗り越えてくれる。そして、既に彼らとの出会いは果たしている』
神託を受けて様々な場所を探していたファリフにとって、衝撃的な事実であった。
既に出会っていた。
それも、一人ではなく星の数程の人々。
ファリフは必死に考えを巡らせる。
だが、その答えは傍らに居たバタルトゥから発せられる。
「……ハンターか」
『否。それに限らぬ。伝説の刺青を持つ者と共に歩む者すべて。即ち、いまこの地に生きる者すべてに資格がある』
「それは……帝国の人達も、星の友かもしれないって事?」
『私が答える事ではない。だが境界に囚われぬ様、心せよ。それを作るのは、他ならぬお前自身だ』
ファリフは再び考え始める。
星の友とは、共に歩むとは、どういう事か。
むしろ、様々な人の出会いがファリフを成長させて星の友を広げていく。
では……対立の先に進むには、どうすれば良いのか?
白龍は応えぬ代わりに、自らの話を続けた。
『我が子らよ、お前達はまだ弱い。力を探すがいい。伝承の狭間に失われた力を、生きる術を』
「どういうこと……?」
ファリフが興味を惹かれ、身を乗り出す。対して白龍の言葉は、あくまで穏やかに。
『かつてこの地にてイステマール、ナーランギと称されていた、幻獣と呼ばれし者達。彼らもいずれ我が子らに力を貸してくれよう。我が半身に会うもよかろうな。我が倒れれば悪い影響は避けられぬが……そこは、蛇の戦士に相談するがいい』
ファリフは考え込み、答えなかった。
沈黙が部屋を支配する前に、白龍はバタルトゥへ声をかける。
『それから……オイマトの者よ。
仇敵を撃つ事に拘るな。仇敵はいずれ撃たねばならぬ相手。だが、その時には傍らに助ける者の存在がある。彼らを蔑ろにしてはいけない』
仇敵――ハイルタイの事を差しているのであろう。
かつてのバタルトゥなら、ハイルタイが絡んだだけで単身動きだそうとする節もあった。白龍はその事を知って釘を刺してきたのだろう。
「……ご配慮、感謝する」
『……仇敵に心を乱される事なく、星の友の一人として……』
白龍がそこまで言い掛けた瞬間、白龍の体から大量の光の粒子が宙に舞う。
白龍の体にあったマテリアルが自然へ還っていく瞬間だ。
ファリフは――叫ぶ。
「白龍! 待ってっ!」
避けられない別れの時が来た。
その事はファリフも頭では理解している。
それでも、叫ばずにはいられない。
『……伝説の子……我は消えるのではない……マテリアルが歪虚に穢されぬ限り、すべてのマテリアルはあるべき場所に還る……だけ。
別れは一時……必ず、またいずこで……』
消えかける体の中、白龍は最後の言葉を残す。
星の友と出会うという事は、いつか別れが来る。
その出会いと別れを乗り越え、ファリフは成長していく。
白龍にとってそれを見届けられない事は無念であるが、マテリアルが還る場所でファリフのを願う事はできる。
『我が対に……会うことが……あれば……詫びを……我は……しばし、眠りを……』
白龍の体から大量のマテリアルが消失した。
白龍がいたはずの場所には、ただ広いだけの空間があった。
失われていく温もりの中、目に涙を溜めたファリフは一言だけ呟いた。
「おやすみ、白龍。……またね」
●
疲れ果てて横になってから、どれくらい経ったろう。
リムネラはぼんやりと目を開け、時間の経過を目の当たりにする。予想外の事態の数々に、リムネラの中の処理能力が追いつかなかったのだろうと、ホープで医療活動を行っているものたちが言って慰めてくれた。
たしかにそうかも知れない。
――と――。
わずかに空気が変わったような――気がした。
それがなんなのか、巫女であるリムネラにすらわかるようなわからないような、そんな本当にわずかな違い。マテリアルの質、といえばいいのだろうか、いやそれもしっくりこないのだが。
聖地が奪還出来たと聞いた時の疲労もある程度癒えてきたこともあり、起き上がろうとしたリムネラだったのだが、ふと顔を上げてみると小さな相棒のヘレが心配そうに彼女のことを見つめていた。
「大丈夫……問題ない、デスよ」
しかしそう言ってはみるものの、ぴりりとした違和感がぬぐえない。
――そこまで考えて、リムネラはふと、白龍のことが気になった。
といっても、ヘレのことではない。
聖地の守護をしていた、愛おしく懐かしい、年老いた白龍――。
あの龍は、無事だろうか。聖地を守り抜くことは、できたのだろうか。
そんなことをぼんやりと思いながら、幼い白龍をそっと撫でてやる。ヘレはいつもながらリムネラによく懐いていて、撫でてやると嬉しそうに喉を鳴らすのだ。
しかし、ヘレは今日はいつもよりおとなしい。
理由はわからないが、静かな雰囲気をたたえている。静謐な雰囲気は、どこか――リムネラの知っているヘレと、違うような気がした。
どうにも聖地の白龍に似ている気がして――しかし彼女は首を小さく横に振る。
いいや、不吉なことは考えまい。
可能性を疑ってばかりでは、動きも鈍ってしまう。
「ヘレ、……ドウかしましたか?」
リムネラがそう言ってそっと手を伸ばすと、ヘレはいつものように彼女の肩に乗る。
そう、いつも通りに。
考えてはいけない。
ユニオンリーダーとしてホープの状態も放って置くことは出来ないが、リムネラはそれ以前に聖地の巫女だ。
その彼女が聖地における良くない可能性を考えてしまえば、それは現実になってしまうかも知れない。
まだ、明らかになっていないのだから。
だからリムネラは考えないことにした、悪い可能性というものの存在を。
もっとも、現実は、やはり甘くないのだけれど――。
「サァ、行きマショウ。皆サン、マダとても困ってイルはずデス」
リムネラはゆっくりと起きて、そしてまだ混乱の続くホープの支援へと向かうのだった。
●
「お初にお目にかかります。エトファリカ連邦国より上様の命を受けて聖地奪還に馳せ参じました朱夏と申します。以後、お見知りおきを」
休んでいたファリフとバタルトゥに東方よりの使者、朱夏(kz0116)は恭しく挨拶をした。
シバを訪ねたが、彼は朱夏をまず二人の族長の前へと通したのだ。それが、器であり、筋であると。

朱夏
「……そうか」
いつものようにバタルトゥは、最低限の口数で応える。
それが朱夏を更に焦らせる。
「あ、何か御無礼が!? 大変、も、申し訳……」
「バタルトゥはいつもこんな感じだよ。
あ、ボクはファリフ・スコール。よろしくね」
「スコール族の族長! 此れよりとも宜しくお願いいたす」
「そんなに固くならなくても良いよ。もっと気軽に……」
「いけませぬ。我が祖国を救うモノノフには礼を尽くせと上様から厳命されております」
祖国を救うモノノフ。
その事が自分達であり、東方――エトファリカ連邦国の事を指し示す事は二人にも分かっていた。彼らは助けを求める為に遠い西方までやってきた。自分達と同じように歪虚に攻められ、窮地に陥っている彼らの身の上をシバから聞いていた。
「我がエトファリカ連邦国は、歪虚の脅威に晒されております。国を護る最後の盾である我等を西方へ送り出した上様のご判断は、一種の賭け。今もエトファリカは危機に瀕しております」
朱夏が最後の盾という事は、最終防衛戦力を救援要請へ回した事を意味している。
その分防衛戦力が手薄になっている事に気付けば、歪虚が一気にすべてを終わらせにかかるだろう。
「話はシバから……聞いている。
我等の助けが必要、とか」
「左様。シバ殿から西方のモノノフは窮地に陥った弱者を救う者と伺っております。何卒、上様にお力添えを」
朱夏は、再び頭を下げた。
仮に東方の歪虚を撃退できたとしてもどのような礼ができるかは分からない。もしかしたら復興に費用がかかって礼らしい礼ができないかもしれない。
そうだとしても、祖国の命運を背負って西方へやってきた朱夏にできる事は頭を下げる事しかない。
「顔を上げてよ。君達は祖国が危ないのに、聖地奪還を助けてくれた。だったら、今度はボク達が君達を助ける番だよね?」
「……では!」
「一つ聞く……西方への転移門は、いつ稼働する?」
バタルトゥの問いに朱夏は答える。
歓喜と感謝が混じった声をあげて。
「……か、かたじけない。転移門は西方から持参した龍の欠片を用いて稼働させるが、今しばらく準備が必要。準備が整ったら、改めて我が東方を救うべく支援をお願いする」
●
「白龍は逝ったか」
「歪虚のせいでちょっとばかり早まったけどね。白龍にも寿命はあるんだよ」
シバと大巫女は、二人だけで会っていた。
大霊堂から出て聖なる山『ビャスラグ山』を背に広がるは、辺境の大地。
まだすべてではないが、怠惰との戦いで取り戻した大地が二人の前に広がっている。
「無論だ。可能なら、もう少し話したかったが……致し方ない」
「相変わらず素っ気ない男だねぇ」
「それより、これより巫女はどうする? 白龍はおらぬぞ」
シバは白龍が不在となった巫女を案じていた。
巫女は白龍に仕えて神託を受ける存在だ。その白龍がいなくなったとすれば、巫女の動揺は計り知れない。
しかし、巫女にして豪胆と評すべき大巫女に動揺は感じられない。
「何を言っているんだい。土地の浄化は巫女にもできる。これから歪虚に穢された土地を浄化していかなきゃならないんだ。泣き言を言っている暇はないよ」
「夜煌祭か」
シバは、ぽつりと呟いた。
辺境巫女に伝わる祭りで大精霊に捧げる感謝と祈りの祭り。
以前、リムネラが狂気の欠片を浄化した祭りとしてハンター達の記憶にも新しい。
だが、大巫女は大きく首を振る。
「そんなもんじゃないよ。大霊堂の巫女が総出で浄化の儀式をやらないといけない。こりゃ大仕事になるよ。新しい白龍が大霊堂に還ってくる日まで辺境を護らないといけないからね」
「ほう、するとやはりあの白い龍が……」
シバにはまだ幼い小さな白い龍の記憶が蘇る。
まだ巫女の背中を追いかけるだけの幼い龍であるが、長い年月をかけて成長すれば亡くなった白龍の後を継いで大霊堂に降り立つ白龍となるかもしれない。
「さぁね。先の事は分からないよ。
だけど、あたしは信じてるよ。あの子と一緒にいるあの龍が、きっと立派になって大霊堂に還ってくる事をね」
大巫女は、空を見上げた。
同じ空の下にいるはずの一人の巫女と小さな白い龍を思い浮かべながら。

ガルドブルム
闘争の果てにニンゲンどもが見せるそういった狂乱を遥か眼下に見下ろしながら、ガルドブルムは鼻を鳴らして両翼で大気を叩いた。
――悪くはねェ。悪くはなかった、が。
元は嫉妬の木偶人形の報せを受け、気も乗らぬまま首を突っ込んだこと。胸糞悪い始まりの割には愉しめたと言えなくはない。が、それでも満たされぬ塊が躰のうちで燻って、いや猛り狂っている。ドロドロとした塊が、叫んでいる。
さらなる闘争を! あらゆる欲望を!
混沌の如き原始的衝動。
溶岩のようなそれを胸のうちで自覚し、赤子をあやすようにそっと撫でた。
時は腐るほどある。お前を――俺を――満たすものもいずれ現れよう。なればその時まではせいぜい愉しみを探そうではないか。
――さて。んじゃ、次は何をしようかねェ……。
いつだか強奪したあの機械人形――CAMとやらを弄ってみるか。あるいは突然ニンゲンどもの中に現れた、一風変わったニオイの一団を追ってみるか。
――いや。
どっちもやろう。どれもこれもやっちまおう。
何故ならこの身は、強欲なのだから。

レチタティーヴォ
「困った役者だ。私の話など聴きやしない……」
帽子のツバを引き、目元を隠してくつくつと忍び笑いを漏らす。そうして天上の竜がどこかへ去るのを待つと、劇作家の笑いは大笑に変わった。
両腕を広げて天を仰ぐ。
「だがそれこそが一流! 故に私は舞台を整えよう。“王に必要なのは玉座と衣装、けれどそれだけじゃあまだ足りない。群衆こそが王を王たらしめるのさ”」
ひとしきり笑った後で劇作家が視線を地上に移す。そこには、歓喜に沸く人間たちの姿がある。
「“英雄は群衆を殺し、群衆は英雄を殺す”。さあ、私の主筆諸君。唯一無二の戯曲を観せてくれ!」
帽子を被り直すと、劇作家――レチタティーヴォは逢魔時の狭間に消えた。
(執筆:京乃ゆらさ)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)

カッテ・ウランゲル

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
ノアーラ・クンタウの執務室にて、カッテ・ウランゲル(kz0033)は部屋に入るなりそう口を開いた。
「私は覚醒者だぞ? あんな怪我など数日で治る……まあ、今回は流石に死にかけたがな」
「良かった。負傷したと聞いてずっと心配していたんです」
嬉しそうに笑うカッテに、流石の騎士皇ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)も僅かに口元を緩めた。
「……心配をかけたな」
「全くです」
カッテはその笑顔を全く崩さぬまま、ドンッと分厚い書類の束を机の上に置いた。
「なんだこれは」
眉をひそめるヴィルヘルミナ。
「折角のこれも、姉上の決裁が無くては宝の持ち腐れですから」
その書類は言うまでも無く、今回の『聖地奪還作戦』における、魔導型CAM、そして魔導アーマーの実戦データーを纏めたものだ。
「くっ……傷が……」
「それは、いけませんね。さあ、すぐ横になってください。横になったままでも資料の確認は出来ますよね?」
「歪虚かお前は」
にこにこしている弟を、ジト目で睨みながらもヴィルヘルミナはざっと資料を見た。
「ふむ……斜め読みだが、感触は悪くないか?」
「ええ、ナサニエルとビットマン博士にも喜んで貰えると思います」
その言葉と裏腹に、少年の顔色は曇っていた。
「ナサニエルの奴は聞き流しそうだが、二人には成果を無駄にするなと伝えておけ」
確かに、人類は聖地の奪還に成功し、ヤクシーとガエル・ソトという強力な敵将を討つことにも成功している。
だが、その犠牲は決して少なくは無かった。
戦死者は勿論、ガエルとの戦いでは貴重なCAMが数機修理不能なまでに大破したという。
「負傷者の搬送と処置は第九師団に再度指令を。戦死者への補償は第一師団と各課を総動員して最優先で進めます」
淡々と、感情を抑えた声で必要なことだけを報告したカッテはこう付け加えた。
「二人には、血を流した人々のことを忘れないで欲しいと」
そして、最も被害が大きかったのがCAM実験場「ホープ」だ。
「アイゼンハンダーについては、その後の状況から帝国領内に去ったと見て間違いありません。……残念ですが」
「システィーナの様子は?」
「僕も真っ直ぐこっちへ来たので、お会いしてはいません。大きなお怪我が無かったのは……」
一瞬言葉に詰まった後、カッテは続ける。
「幸いでした」
ヴィルヘルミナも目を伏せ、実験場の被害と、それを目の当たりにしたであろう王女のことを慮った。
「これも、システィーナにとっては試練なのかもしれん」
カッテはそれには敢えて応じず、別の資料を取り出した。
「僕の方で把握している機甲兵器の被害はそこにある通りです。ですが――」
確認するように言葉を切ったカッテにヴィルヘルミナは頷く。
「間違いない。魔導アーマーが連中に奪取された」
聖地奪還に乗じるように姿を見せた暴食の歪虚――帝国で暗躍する四霊剣とその配下によって輸送部隊にも被害が出た他、魔導アーマー2機が歪虚に奪われていたのだ。
「それについても調査を命じましょう。では、失礼します」
皇子はそう言って一礼し、踵を返した。
「カッテ」
その背中に、ヴィルヘルミナは言葉を投げかける。
「親父殿を殺したのは不敗の剣豪だ」
「……そうですか」
カッテは足を止める。
「すまない」
「弟が、自分の命をかけて十三魔の一人を討ったというのに、姉がこれでは恰好がつかんな」
あくまでも冗談めかしたヴィルヘルミナの言葉には、様々な想いが込められていた。
「十三魔を討つことが出来たのは、僕の力ではありません。同じように、姉上が無事だったのは、姉上だけの力だけではない筈です。現に、不変の剣妃についてもこの戦いを通じて新しい情報が集まってきています」
「……そうだな。彼らに、ハンターたちに感謝しよう。我が愛しき剣たちに」
そう言ってから、ヴィルヘルミナは少しだけ優しい口調で呼びかけた。
「……良く頑張ったな。無事で良かったよ」
その言葉に振り返ったカッテは少しだけ柔らかい口調で返した。
「姉上こそ……ご無事で、何よりでした」
カッテの白い手袋を嵌めた細い指が眦を拭い、ヴィルヘルミナがそれを見て微笑む。
この一瞬だけ、ゾンネンシュトラール帝国の皇帝と皇帝代理人は姉弟の表情に戻っていた。
(執筆:稲田和夫)
(文責:フロンティアワークス)
(文責:フロンティアワークス)







