ゲスト
(ka0000)
【血盟】これまでの経緯


更新情報(6月26日更新)
【血盟】ストーリーノベル

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ
「勿体なきお言葉。これも青龍様が龍園への転移門を維持してくださっているおかげです」
『当然の事。お前達には私も随分と助けられている。歪虚共の襲撃も目に見えて少なくなった。礼を言わねばならぬな』
北方王国リグ・サンガマ。龍園の大神殿に青龍は変わらずに座していた。
青龍は星の傷跡に強欲王メイルストロムの心核を封印する為、この場を動くことができない。
また、封印の維持には大きく体力を消耗する。人類に協力したくとも、結局この場を離れられないままでいた。
「暴食王や怠惰王の動きは如何でしょう?」
『あれらも先の戦い以降、姿を見せてはおらぬ。歪虚の側でも、大きな動きがあったのだろう。それが今は私達にも味方している』
「戦線が世界中に広まったからだろうね。おかげで龍園も力を取り戻しつつあるよ。……さて、そろそろ本題に入ろう。以前から調査していた、ハンターシステムと大精霊についてだ」
今回ハンターたちを呼びつけたのはアズラエル・ドラゴネッティ。ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の実の兄であり、事実上龍園を取り仕切る男だ。
彼は龍奏作戦の後も、“覚醒者を簡易に生み出す仕組み”である“ハンターシステム”に関する調査を続けていた。
リアルブルーやエバーグリーンへの転移が始まった後、“覚醒者であること”が異世界への転移を妨害していると判明。
それらの調査結果についての報告を受けるため、ナディアやハンターらはここまで赴いていた。
「色々わかった事もあるんだけど、簡潔にいこう。まず、ハンターシステムについて。あれがリグ・サンガマで作られた契約だというのは周知の事だと思う」
「うむ。本来星の力を得て覚醒するには、何十年も修行が必要じゃ。自分で“気づき”を得て、精霊と結ばれる必要があるからの」
「ハンターシステムは自動的にヒトを精霊のチャンネルに結び付け、そこで契約を得るシステムだ。この時、本来は契約希望者にとって相性のいい精霊などを用意する必要がある。が、ハンターシステムは自動的に多種多様な精霊とのマッチングを行っている。これはより大きな力、つまり大精霊が仲介を行っていると考えるのが自然だ」
「ソサエティで覚醒者になるのめちゃめちゃ簡単じゃからな。何らかのデメリットはあるだろうと考えていたが、その中間マージンがこの世界への隷属なのか?」
「ざっくり言うとそんなところだね。クリムゾンウェストにはいくつかの覚醒プロセスがあるけど、ベースとなっているのはナディアが300年前に公開したハンターシステム。つまりほとんどの覚醒者はこの世界から出られないという道理になる」
「その契約を解除する方法は? 契約がある限り、リアルブルー人が故郷に帰れぬ」
「原則的には存在しないね。覚醒者の契約は基本的に一生モノだ。歪虚やその契約者になって精霊に愛想をつかされない限りはね。故に、まずその契約自体を改める必要がある」
そう言ってアズラエルがリザードマンに運ばせてきたのは大きな石板だった。そこには古い北方王国の言葉がびっしり刻まれている。
「古代文字か」
「ハンターシステムより更に古い契約のスクロールだ。こいつが国外に持ち出せないもので諸君らにご足労願った」
そこにはハンターシステムができるよりも更に昔、大精霊との対話を試みた人類の物語が記録されていた。
古代人類は龍と共に星の傷跡を神殿として整備した。星の傷跡は高濃度のマテリアルが吹き荒れる、惑星の中心に近い場所。
そんな場所への神殿建造には、多大な犠牲を要したという。
「だが結果として古代人はあまたの犠牲の上に、星の意思――大精霊と対話できる場を手に入れた。それが星の傷跡だ。ハンターシステムよりも古の契約、“守護者”の契約はそこで結ばれたらしい」
『守護者とは、特に星に近い生物種の中から選別される“世界守護”を担う存在……。我ら六大龍もそれに当たる。尤も、六大龍は星が能動的に作り出したもので、覚醒者は星が受動的に作り出したものという違いはあるがな』
守護者は大精霊の意思を受ける存在であるからこそ、膨大なマテリアルとそれを扱う術を持つ。
六大龍は守護者だがすべての龍種が大精霊の加護を受けているわけではないように、守護者となれるかどうかは同じ種の中でも才気によって異なるという。
『この世界を救うために大精霊は力を貸している。それは“この世界以外を救う事は認めていない”とも言えるだろう』
「ケチじゃな?。アズラエル、この石板には契約の解除方法が書いてあるのか?」
「いや? それについてはさっぱり」
「おいクソメガネ」
「一つ確かなのは、結局僕たちがどう足掻いたところで力づくでは大精霊に及ばないという事だ。状況を打開したいのなら、大精霊と直接対話を試みるしかない」
とはいえ、大精霊と対話できる場所など限られている。
北方の星の傷跡か、あるいは南方の竜の巣か。
より物理的に星の中心に近い――すなわち地下深くであり、そして大地を巡るマテリアルの収束点であり、更に神殿として整えられた場であるということ。
候補となる場所は蒼乱作戦でいくつか見つかっているが、現実的なのはやはり“対話実績”のある星の傷跡だろう。
「つまり――強欲王を完全に葬る時が来たというわけか」
「強欲王は肉体を失い、結晶化した心臓――心核だけの存在となっている。その戦闘力は事実量半減している筈だ。一方、君たちハンターは強くなった。今ならば以前よりも安全に挑むことができるだろう」
『あやつが星の傷跡から去れば、私も本格的に力を貸せるようになるだろう。老いぼれた身ではあるが、私も六大龍の一柱。お前達にしてやれることもあるはずだ』
既に敵戦力は激減している。イニシャライザーに関しても、より強力なものを、しかも量産できる体制が整いつつある。
「強欲王メイルストロムを討伐すれば、北の守りは盤石となりましょう。それにあそこはヴォイドゲートでもある……どちらにせよ長らく放置はできませぬ」
ナディアは青龍の前に跪き、力強く宣言する。
「狩人を率いる長として、強欲王の討伐――確かに拝命致しました。我が神よ、どうか我らに勝利の加護を!」
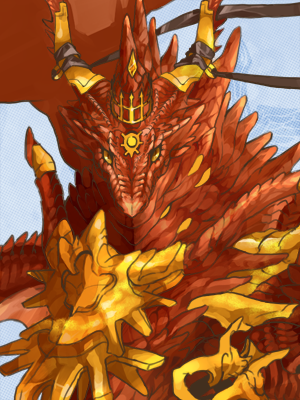
メイルストロム
赤龍の心臓を抉り出し、それが結晶化したシルエットはどちらかと言えばかつての竜の戦士、ザッハークらに近い。
神殿の奥深く、大地の奥底――星の中心に続く大穴からは、絶えずマテリアル光が沸き上がり、それは空を舞い踊るように螺旋を描く。
常人ならばこのマテリアルの密度に耐えきれず燃え尽きるだろう。だが、強欲王はもう何百年もここで炎に焦がれている。
(…………呼びかけに応える声は、ない)
考えていた。自分たち龍は何のために生まれ、そして何のために死んでいくのか。
自分がこれまでしてきたことに意味はあったのか。その答えが知りたかった。
役目と背負い、南の地に座してからというもの、様々な出来事があった。
中には自分に寄り添おうとしてくれた人間もいた。逆に、呪いの言葉と共に刃を向ける人間もいた。
自分を信じて最後までついてきてくれた部下もいれば、尻尾を巻いて逃げ出し、その生に意味はないと叫んだ者もいた。
メイルストロムは無口な王だった。言葉で何かを伝えるという事が苦手で、誤解されてばかり……。
これでよかったのか? ……それとも間違いだったのか?
この凍てついた大事の最果てに攻め込み、聖地を奪ったことに具体的な理由はなかった。所詮は感傷だ。
ただ、知りたかったのだ。ここでなら、大精霊にも声が届くと思った。
光の前に腰を落とし、祈る。その様はさながらヒトが座禅を組んでいるかのようだ。
意識を星の中心に巡らせ、目に見えぬ光を追う。その中にいつか答えが浮かぶと信じて。
すべてを失った王は今も、ありもしない答えを地下の星座に夢見ていた。
(文責:フロンティアワークス)

黙示騎士マクスウェル

黙示騎士ラプラス
砂に覆われたエバーグリーンのビルに背を預け、マクスウェルが呟く。
戦闘から帰還したラプラスは事の顛末を報告。強欲王の敗北は伝えられ、しかしそこに大きな落胆はなかった。これはある程度予想されていた展開だ。
『九尾に続きこれで二体目。これだけ王を倒した世界は前代未聞だな……ククク』
「戦力の低下は著しい。何か対策を考える必要があるな」
『オレ達にはどうにも出来んだろう? 王を作り変え、揃えるのは“邪神”の本能。そしてオレ達は邪神に干渉できない』
「ふむ、その通りだ。結局のところ我ら黙示騎士も、運命の流れにわずか手を添える程度の事しかできぬからな」
『“王”と”邪神”を制御するのは不可能だ。かといってオレたちに眷属をポコポコ生み出す力はないしな。せいぜい奴らを支援するしかない』
肩を竦めるマクスウェル。実際のところ、これはそういうゲームだ。
既定路線にあり、動かすことが困難な運命。それに少しずつ手を加え、望む未来にたどり着けるよう努力する。
それはあの守護者たち――ハンターも、そして黙示騎士も同じこと。
「まったく、実にフェアな展開だ」
『オレは細かいことを考えるのは面倒なんでな。今後の事は、シュレディンガーに任せておくさ』

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ
その帰還を待っていたアズラエル・ドラゴネッティとナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の前に降り立ち、青龍は深く息を吐いた。
「やはり、青龍様でも困難ですか」
『ああ。私の呼びかけにも大精霊が応える事はなかった。ほんの数百年の間に、随分と距離が遠くなったものだ』
強欲王メイルストロム――赤龍との闘いから数日。
未だ北荻と呼ばれた歪虚の領域が消失したわけではないが、少なくとも北方――龍園周辺の歪虚は落ち着きつつあった。
星の傷跡を封鎖する結界を解き、本来の力を取り戻しつつある青龍は、こうして自在に空を舞えるまでになった。
だが、状況は大きくは進展していない。大精霊に通じる聖地である星の傷跡を以てしても、大精霊の意思との対話は叶わなかったのだ。
星の傷跡は高濃度マテリアルが噴出する、光の溶岩地帯。龍として最高位にあり、大精霊とかつて対話していた青龍ならばとの試みも、徒労に終わった。
『何度呼びかけても応えぬ星に、あれもどれだけ心細かったか……。唯一の救いは、最後に新たな守護者の誕生を目せた事であろうな』
「畏れながら我が神よ。星の傷跡の祭壇はヴォイドゲート化し、ハンターにより破壊されたと聞きました。その影響は考えられませんか?」
『祭壇に何の効力もないと断ずるつもりはないが、あれは補助装置の一部に過ぎぬ。あの洞窟の位置、構造すべてが神殿。祭壇の問題ではない』
「では、星の傷跡は既に聖地足りえないと?」
『否。あの場に満ち満ちた生命の息吹、正のマテリアルをして聖地は万全であろう。声自体は、大精霊に間違いなく届いている』
「では……大精霊が“あえて”我らを無視していると?」
ナディアの苛立ちに満ちた声に青龍は目を細める。
『元々大精霊は存在の規模が私たちとは違いすぎるのだ。ナディアよ、その美しき髪先をお前は意識できるか?』
「へ? まあ、意識できますが……」
『では、肌はどうだ? そこに生える産毛の一本一本は? 皮膚の皺一つ一つ、身体を流れる血液、その血液に含まれる成分を意識できるか?』
言葉を失った。確かに“そういうこと”だ。
この世界――星という巨大な枠組みに意識が存在するとして、それはどこまで微細な情報を認識できる?
人間で例えてもその意識圏はごく狭い。自分の肉体に病が巣くっていても気づかないこともあるほど、意識とは当人が思っているより融通が利かないものだ。
星という巨大な生命体に“大精霊”という意識があったとして、それが人という極小の呼びかけに気づく方が本来あり得ない。
『神とは巨大なもの。故に、小さき物を正しく認識するのは難しい。私がお前達人類の成長を見落としたようにな』 「では、より大精霊の意識を人類に向ける方法を探すしかありませんね。ナディア、次の手を打つとしよう」
「んん? 星の傷跡ほどの聖地がダメなら万策尽きたのではないのか?」
「対話の“場”という意味ならこれ以上の土地はないだろう。だが、“術”は他にもある筈だ。それを知る方法なら、アテがある」
「クソメガネ……それならそうと最初から言わんか!」
「大精霊が素直に応じてくれるならそれで万々歳だし、それに他にやるべきことがあったとして、君たちハンターは迅速に強欲王を排除してくれたかい?」
確かに他にやるべきことがあったなら、リスキーな王討伐に二の足を踏んだ可能性はある。
アズラエルにとっては強欲王を打ち倒し、聖地を奪還すると同時に青龍を解き放つ事こそ最優先の目的。ここは立場の違いと言えた。
「ええいこの腹黒、我らを利用しおったな!?」
「ははは、違う違う。星の傷跡は本当に必要だったんだ。これでやっと色々な方法を検証できるだろう?」
『ふむ……何やら考えがあるようだな。アズラエル、正式に私からも命ずる。ハンターズソサエティに赴き、大精霊との対話法を探し出せ』
妹に胸倉を掴まれていた男は、青龍の言葉に恭しく頭を下げた。
「――はい。あれから一週間が経ちました。……アァアアズラエルゥウウウ????!!」
ソサエティ本部内を鬼の形相で練り歩くナディア。その視線の先に目的の男と、意外な人物のツーショットを見つけた。
本部内にはひときわ大きな“神霊樹”があり、その周りとハンターが連れ歩くパルム達がせわしなく歩き回っている。
そんなのどかな景色の中、アズラエルとタルヴィーン(kz0029)が向き合っていた。

タルヴィーン
「ああ。この神霊樹のライブラリを利用させてもらえないかと思ってね」
浮遊する車椅子のような装置に乗ったタルヴィーンは、まったくそうは見えないがパルムの成体とも言うべき高位精霊だ。
ナディアとはこのハンターズソサエティ設立からの付き合いで――尤も、あの頃は小さなパルムの幼体だったが――この本部のライブラリを管理する“司書”と言える。
タルヴィーンはそこらのパルムとは異なり人類と同じ言語を話せる(実際は翻訳しているだけで違うのかもしれないが)貴重な存在だが、それ以外に特別な能力を持っているわけではない。
元々情報の整理を仕事とし、そしてそれを生きがいとしている為、働いているのを見かける事はあっても積極的に関与する者は少ない。
まあ、ハンターも挨拶くらいはしたことがあるだろうか。「こんにちは!」とか。
「タルヴィーンから何か聞き出すつもりなら無駄じゃぞ。そやつは“記録された出来事”しか知らぬからな」
「だが、記録された出来事であれば何でも知っている……そうだろう?」

ソサエティ内ライブラリ
パルムらがせっせと蓄えた世界の情報、ライブラリ。それは世界各地の神霊樹を通じて、このソサエティ本部に集められる。
だからどの国のどんなハンターの活躍でも、ライブラリにアクセスすればまるでその場にいたかのように詳細に追憶することができるのだ。
無論、ハンター諸君も過去の出来事を知るためにこのライブラリの世話になっているはずだ。
「でもすべてを開示しているわけではないね?」
「ほ。当然じゃ?。誰だって知られたくない、見られたくない記録はあろう??」
「だが記録していないわけではない。それを開示してほしい」
「お、おい……どどどどうするのじゃ。ハンターがちゅーとかしてるとこ見ちゃったら……わらわコンプライアンス的にどうなの?」
「ナディア、思い出してくれ。蒼乱作戦でソサエティは、未開の地の神霊樹も活性化し、植樹して回っただろう? あそこで回収されたデータは、やはりここに集約されているんだ」
そういえばそんなこともあったな、と腕を組む。確かに蒼乱作戦では転移の為、世界各地の神霊樹を起動しまくった。
確かに今なら世界中のデータベースとつながっている事だろう。思えばそれを提案してきたのもアズラエルだった。
「おぬし……まさかここまで考えておったのか?」
「タルヴィーン、それでどうなんだい? 情報は確認できるのか、できないのか」
「ううむ、論理的には可能じゃな。ただ、お恥ずかしながら増幅した情報量が多すぎて整理が全く追いついておらぬ。そもそも、わしが存在する以前の記録も山ほどある。わしも自分が整理に参加してからの事はほぼ例外なく記憶しておるが、それより以前……具体的には約300年より前の情報には穴があってのう」
「でも情報が存在しないわけじゃないんだね? だったら、閲覧できる状態に整理すればいい。ハンターもパルムを持ってる者は多いだろうし、協力を要請しよう」
確かにそうすれば、世界各地の情報を閲覧できるようになる。
特に南方や暗黒界域、大渓谷などは古き時代にはそれなりの文明が栄え、星との対話が可能な聖地を持っていた。
だからこそヴォイドゲートの発生場所として利用されてしまったのだ。
「ううむ……しかしのう、“ぷらいばしい”がのう……」
「出、出た?! なんかヤバいところは見せてくれない奴?! おぬしキノコの頃から全然変わらんの?!」
「おぬしも変わらぬのう。えっちな情報を見るためにわしを欺こうとしたり」
「ウワアアアアアアアアアアア何暴露してんだお前!? プライバシー息してないぞ!?」
「ともあれ、ライブラリに眠るのは一つ一つが大切な誰かの物語じゃ。どこまで探れるのかは、わしの塩梅で決めさせてもらう。下手なことをして記録を失うようなことがあれば申し訳が立たんからな」
「わーったわーった、チョットずつやればよいのじゃろう?? チッ、めんどくさい奴?!」
悪態をつくナディアとは裏腹に、アズラエルは思案する。
以前――それこそ蒼乱作戦より前。アズラエルは同じやり取りをタルヴィーンと行っていた。
その時タルヴィーンは明確に拒絶を示し、取りつく島もない様子だった。
(態度が軟化している……? ナディアが相手だからか? いや、それとも……)
こうしてソサエティのライブラリ、図書館の一斉整備が始まった。
その仕事には当然ながらハンターたちも駆り出され、膨大なライブラリデータベースに多くのハンターがアクセスすることとなった。
そうしているうちに、ある時期から奇妙な事件が起き始めた。
いわく、「本を整理していたハンターが消えた」「ライブラリ確認をしていたら、見知らぬ場所にいた」、と。
それは一瞬の出来事で特に問題もなく、激戦で疲れたハンターたちが訴えかける体調不良の一種……。
最初はそう、考えられていた。だが――。
(文責:フロンティアワークス)

ナディア・ドラゴネッティ

トマーゾ・アルキミア
「うむ。これがさっぱり原因がわからんのじゃ。トマーゾ、何か心当たりはないかの?」
リアルブルーの月面基地崑崙との定期通信がてら、ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)は相談を持ち掛けてみた。トマーゾ・アルキミア(kz0214)ならば何か知っているのではと期待したのだ。
神との対話法を得る為、神霊樹ネットワークを使い過去データの探索が開始され早一週間。
その間にちょくちょくと、ハンターが突然いなくなっては戻ってくるという事件が起きていた。
それでどうしたのかというとどうなるわけでもなく、別に怪我もなければ異常もない。
皆一様に「神霊樹にアクセスしていたら、いつの間にか妙な夢を見た」と口を揃える。
『夢というのは言い得て妙じゃな。恐らくそやつらは夢を見たのじゃろう。眠って見る夢ではなく、神の見る夢を』
「神の見る夢……? 急にポエムみあるな」
『そもそも、お主らの世界の神霊樹は誰が何の為に作ったのか知っておるか?』
「は? 神霊樹は元々あったものじゃろう? エバーグリーンでもそうではないのか?」
『いや、エバーグリーンの神霊樹は厳密にはその名前ではなかったし……面倒なので今はそう呼んでおるがな。それに、神霊樹は“ヒトが作りしモノ”。エバーグリーンはガイアプラントやサーバーの中心に星の触角を用いておったからな。ともあれ、クリムゾンウェストの神霊樹も、何者かが何らかの目的を持って作ったと見て間違いない』
「という事は、リアルブルーには神霊樹がないのか……」
『今更何言うとんじゃ阿呆。……貴様らの神霊樹について大凡予想はついている。このデータを見ろ』
そこに映し出されたのは、先日トマーゾか崑崙で検査した覚醒者の生体データだ。
『わしが検査したのは主に貴様らの生体マテリアル、そしてDNA構成じゃ。幾つか面白い事がわかった。まず貴様ら、転移門を使う時に多量のマテリアルを消費しておる』
「当たり前じゃろ?」
転移門はその使用時に大量のマテリアルを消費する。
だから非覚醒者が安易に転移するのは困難で、対価としてマテリアル燃料や覚醒者の生態マテリアルなど、多量のマテリアルを消費する必要がある。
『当たり前と言うが、エバーグリーンでは転移し放題じゃったぞ。設備は必要じゃが、エバーグリーンの転移は別々の空間を繋いでいるだけじゃったからな』
「まじかよ。じゃあわらわたちの転移ってなんなの?」
『貴様ら、どうも転移する時にめちゃめちゃ遠回りしておるな。ほれ、転移時のデータを確認したところ、お主らは一度の転移で最低でも3、4回は不要なパスを経由しておる。これを効率化出来れば転移で消費するマテリアル量を減らすことも可能じゃろう』
「……っていうか、なんじゃここ?」

転移門
転移時に不要なパスを経由しているのはまだ理解できるが、バラバラな中に一つだけどの覚醒者も必ず経由する地点があった。
『座標をもう少し特定してみるか。貴様らの世界で言うとどの場所なのかわしにもまだピンと来ぬのでな。だが、恐らくここに何かがあるのじゃろう。それはさておき、なぜ貴様らが何度も不要なパスを経由しているのか、その理由はわかる。恐らく転移時に生体マテリアルを採取しておるからじゃ』
覚醒者が転移を行う時、その一瞬の間にいくつかのパス――トマーゾが言うには検査機のようなものを通過しているのだという。
『崑崙で貴様らの身体を調査するのに使ったスキャン装置みたいなものをイメージすればわかりやすいか』
そこで覚醒者の生体データと記憶がスキャンされ、転移門と接続された神霊樹に共有される。
「神霊樹ネットワークはパルムが管理運営しておるのではないのか?」
『そのパルムという精霊が神霊樹と通じているのは事実じゃろうが、それだけにしてはデータの収集が完璧過ぎぬか? 恐らく神霊樹は元々、覚醒者と接触する度にデータを収集している』
覚醒者がスキルをセットする、或いは新たにインストールする時。転移門を使って依頼に赴く時。
あるいは――過去の記録にアクセスし、その資料を閲覧する時。
神霊樹システムを利用するその時に、覚醒者は蓄積した情報、記憶を神霊樹に共有しているのだとしたら……。
『パルムはあくまで司書……つまり管理と補足が役割であり、実際に神霊樹ネットワークを作っているのは、ハンターなのかもしれんな。だからパルムはハンターについてくる』
「それと神の見る夢というのに何の関係がある?」
『多数の人間が得た情報、記憶の集積されたデータベースは集合無意識の結晶じゃ。神霊樹が大精霊に通じている事は明らかじゃが、そこに蓄積されるのは人の夢、人の記憶……。大精霊はそれを夢見ておるのかもしれぬな』
顎鬚をいじりつつ、トマーゾは興味深そうにしきりに頷く。
『貴様らは星の守護者であると同時に、星の観測者というわけじゃ』
「それとデータベースにアクセスした者が消える事件に何の関係がある?」
『神の持つ膨大な記憶に引き込まれておるのだろう。元々はヒトの記憶の結晶じゃからな。消えてしまった連中の生体マテリアルを調べてみろ。恐らく、わしが指定した座標に向かっているはずじゃ』
ナディアにはよくわからなかったが、確かに一瞬とはいえどこかに消えてしまった――転移してしまった? 者たちの検査は必要だろう。
やけにうれしそうに仮説を並べ立てるトマーゾに呆れつつ通信を終えようとしたその時だ。
『ああ、そうそう。もう一つ面白い調査結果があるので伝えておこう。貴様らクリムゾンウェスト人とリアルブルー人、二つの世界の人間の生体マテリアル波長とDNAデータが合致した』
「は?」
『簡単な話だ。貴様らは別々の世界で生まれ育っているが――元々は同じ種族だったということじゃよ』
「トマーゾの仮説が正しいとして、何故“ヒト”なんだろう?」
神霊樹ライブラリを操作しつつ、アズラエル・ドラゴネッティは首を傾げる。

アズラエル・ドラゴネッティ

タルヴィーン
「んー……言われてみると妙じゃな。別にディスってるわけではなく、ヒトは脆弱な種じゃ。星という巨大な生命単位の中で何ができるとも思えぬ」
「異世界に転移させないという事もそうだが、どうも大精霊はヒトという種に強い拘りを持っているように思えてならないんだ」
はた、と何かを思いついたようにアズラエルは手を止める。
「もしや神はツンデレなのか?」
「よし、お前頭大丈夫か? 修正してやるから表出ろ?」
「違うんだよナディア。神がヒトに執着を持っているのは明らかだ。でも、その執着とヒトへの対応ができてない。神はコミュ障なんだよ」
胸倉を掴まれながらも真顔で説明するアズラエル。その様子を眺め、タルヴィーン(kz0209)は笑う。
「ふぉふぉふぉ。相変わらず二人とも仲が良いのう」
車椅子のような装置でふわふわと浮かびながら近づいてくるタルヴィーンにナディアは兄を手放す。
「誰がこんなクソメガネと仲いいんじゃ」
「他者との繋がりは大事にせんとなあ。ナディアもそれで苦労したクチじゃろうに」
「ぐぬぬ……」
悔し気に唸るナディアをやさしく見つめ、タルヴィーンは問う。
「おぬしらはそんなにも、星の意思を知りたいのかの?」
「ぬ?」
「それは本当に知る必要があるのじゃろうか。真実が必ずしも都合の良いものであるとは限らぬじゃろう?」
「確かに調べた結果、ガッカリする可能性はあるのう。じゃが、それは立ち止まる理由にはならぬ」
ナディアは即答した。そこに迷いらしきものは一切感じられない。
「行動の結果が望まれぬものであったとしても仕方あるまい。それよりも恐ろしいのは、何も行動せず何も結果を生まぬことだ。正しさも過ちも、目を逸らしてはならない。それと知り考える事が未来を創るということじゃからな」
語る姿をじっと見つめ、タルヴィーンは何かを考えているようだった。
だがそれと気づいたのはアズラエルだけで、ナディアはタルヴィーンの様子の変化に気づいていない。
「ともあれ、過去の情報を閲覧できる現象があるのなら、それを再現し制御できるようにすればよい。アズラエル、タルヴィーン、力を貸してくれるな?」
「ああ。恐らくだけど、転移門の設備が流用できると思う。君ら武闘大会の時にシミュレーターを動かしただろう? あれと接続すれば……」
「そうか、そんなものもあったの! ミーリアー、しまい込んだ装置どこやったかのーーー?」 語り合う二人の様にタルヴィーンは俯く。
「……ヒトの意識は、少しずつ変わっておるのかもしれぬな」
こうしてソサエティは怪現象を人為的に再現するための準備を始めたのであった。
(文責:フロンティアワークス)
ハンターズソサエティ本部にあるネットワーク中枢を担う神霊樹。その周りを転移門に似た装置が覆っていた。
ライブラリの整備中に発生する“事故”を人為的に再現し、コントロールするためのものである。
「これでライブラリに直接介入し、直感的に情報を得る事ができる。大人数のハンターによるマルチダイブも可能だ」
「じゃーこれでズバっと一気に古代の記憶を見ればよいのじゃな! いやー、楽勝じゃなー」

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)に語りながら端末を操作するアズラエル・ドラゴネッティ。空中にふわりと浮かび上がる画面には、ある地域の画像と情報が記されていた。
「……って、リグ・サンガマではないか。しかも682年? そんなに昔ではないが……そうか、大侵攻の頃じゃな」
この世界の北側のほとんどは“北荻”と呼ばれる歪虚の領域であり、その開放をめぐる戦いが続いていたのはハンターも知っての通り。
リグ・サンガマの領土の一部は解放されたものの、今も龍園と辺境の間には歪虚の領域、すなわち北荻と呼べる場所が広がっている。
北伐作戦である程度状況は緩和されたが、辺境部族らの故郷が解放されたわけではないのだ。
「世界の半分以上を飲み込んだ歪虚の大侵攻は人類の結束と多様化を誘発した。当時のグラズヘイム王国はかろうじて大侵攻を退け、その後生存の為に同盟や帝国といった新たな国家を生み出した。滅亡の危機を前に、人類は進化したわけだ」
「その分、余計な諍いも増えた気もするがの。多様化することで様々な可能性が生まれた……そういう意味では進化か」
「それはさておき、そもそもどうして大侵攻は起きてしまったんだろう? と思ってね」
ナディアもアズラエルも非常に長寿であり、当時から既にリグ・サンガマにいた人物だ。
つまり二人ともこの事件の当事者ということになるのだが、実は二人とも大侵攻については詳しくなかった。
「あの戦いの敗因は何だったのか。リグ・サンガマには既にハンターシステムの原型があり、青龍様と契約した龍騎士隊だっていた。多数の守護龍を抱えたリグ・サンガマが敗れなければ、大侵攻は起きなかった」
「それは……大量の歪虚の襲撃じゃろう? 強欲王メイルストロムをはじめ、複数の歪虚王との闘いと……」
「そもそも、“王”という存在が正しく認知されたのもあの時だ。僕らは何が起きているのか理解できず、がむしゃらに戦った。出来たのは強欲王を封じたことくらいで、それ以外の事は記憶にない。それまで星の傷跡は聖地として正しく機能していたし、ヴォイドゲートですらなかった。じゃあ、何がどうなって大侵攻が起きたのか、それが知りたいんだよ」
端末を操作しながら真剣な様子で語るアズラエルにナディアは溜息を零す。
「……まあ、別に危険はないのじゃし、構わんがな。お試しがてら、調査に付き合ってくれるハンターを募集するとしよう」
「記憶の世界とは言え、真相に近づくのなら危険な状況に飛び込むことになる。あーいや、実際に危険はないんだが、記憶の中でやられたらそこで調査は終了だからね」
「シミュレーションとは言え、結局は本当の戦いと同じく行動する必要があるってことじゃな」
「早速ハンターを集めよう。実験開始だ」
――王国暦682年。
北方王国リグ・サンガマが国家としての体裁を保っていられた最後の年。
それまでこのクリムゾンウェストにおいて、歪虚の出現は自然発生的なものが主であった。
すなわち雑魔と呼ばれるような、負のマテリアル溜まりから生じてしまう命の歪み。
これらは非覚醒者の戦力でも十分に対処可能な頻度であり、負の汚染も神職や巫女で十分浄化可能であるとされていた。
王国暦以前にこの世界に存在した古代文明は歪虚の手により滅び去った――そんな歴史家たちの言葉も人々の胸に響くことなく、西方諸国はグラズヘイム王国により統一され、繁栄を極めていた。
王国暦650年前後。この頃から自然発生だけとは言い切れない、散発的な歪虚の出現が確認されるようになる。
その最前線は北の大地。北方王国リグ・サンガマであった。
リグ・サンガマはハンターシステムの前身となる精霊との簡易契約術により、他国に比べても圧倒的な数の優秀な戦士を保有していた。
世界守護を命題とする青龍を中心とした龍種との連携もあり、北の地で始まった歪虚との闘いは、当初人類側の圧勝に終わると信じられていた……しかし。
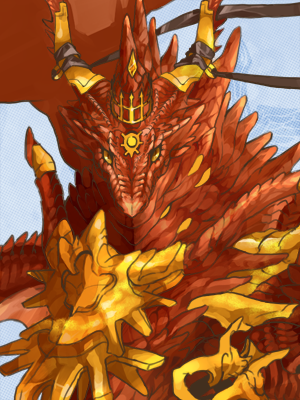
強欲王メイルストロム
『赤龍……貴様、自分が何をしているのかわかっているのか?』
問いかけに赤龍――強欲王メイルストロムはブレスで応じる。
これに青龍もブレスで対抗すると、衝突した光が空に爆ぜ、衝撃波が地上さえも吹き飛ばす。
星の守護龍、精霊の最高峰。六大龍の一柱たる青龍が全力で挑んで尚、強欲王には及ばない。
何故ならば彼の強欲王こそは赤龍メイルストロム。歪虚と化した王は、生前を上回る力を有していた。
その咆哮一つで翼竜程度では薙ぎ払われ、次々に墜落してしまう。
『邪魔をするな、青龍。用があるのは星の傷跡……大精霊のみ』
『見縊るなよ、使命を忘れた愚か者め。この命に代えても、貴様の好きにはさせぬ!』
「青龍様がご出陣なされるなんて……」
「相手は赤龍様だとか。一体何がどうなっているんだ……?」
「皆落ち着け! それぞれ持ち場について龍園の守りを固めるんだ!」
「し、しかし……アズラエル様。青龍様がご不在の今、龍園を守る結界は弱まっております。このままでは……」
龍園ヴリトラルカは青龍を中心に――原動力に結界を展開する機能を持ち合わせている。
これで生半可な歪虚の攻撃は物ともしないし、汚染もシャットアウトできる道理だ。
だがその青龍が星の傷跡防衛に出向いている今、この神殿都市の結界は発動できない。
「それに、赤龍討伐の為に防衛戦力も不足しています。アズラエル様、このままでは……!」
「わかっている。青龍様がお戻りになられるまで、周辺神殿からマテリアルを供給し結界を維持する。部隊を再編し、各神殿に派兵せよ!」
当時から既に神官長の座についていたアズラエル・ドラゴネッティは青龍不在の龍園の防衛に腐心する。
歴史を紐解けば、彼は結果として龍園の防衛には成功する。
だがこのリグ・サンガマの大地において防衛が成立したのは、この龍園のみであったと記録されている。
北方王国には青龍の座する龍園ヴリトラルカの他、ヒトの王国としての王都を持っていた。
リグ・サンガマの政治、外交など、ヒトとしての営みの中枢である王都アルシャンクは、この年を最後に歴史上から姿を消す。
強欲王メイルストロムの襲撃と同時期、この北の大地には複数体の歪虚王による攻撃が確認されている。このアルシャンクも例外ではない。

暴食王ハヴァマール
巨大歪虚となったハヴァマールは、まっすぐにアルシャンクを目指して侵攻を続けていた。
「国王様! 巨大歪虚が既にアルシャンクの目と鼻の先まで迫っております!!」
「すべての龍騎士隊は私に続け! 青龍様にお授けいただいたこの命、雄々しく立派に咲かせてみせよう!!」
リグ・サンガマの国王は、ヒトの側の君主であり、同時に青龍信仰の神官騎士でもある。
龍と共に寄り添う騎士らは龍騎士と呼ばれ、この時代にそのほとんどが途絶えたと言われている。
そしてこの国王もまた、この戦いを最後に歴史上から名を消すことになる。
そうした出来事の記録は数あれど、この襲撃事件……すなわち大侵攻がなぜ始まったのかといった記録は残されていない。
当時、青龍はこの事件を調査させるべく、歪虚の出没した北の地に部隊を派遣していた。
しかしその調査隊はほとんどが全滅。生き残りの証言も要領を得ないものばかりだった。
アズラエル・ドラゴネッティが求めた大侵攻の真実眠る北の地。そこには外界から強制的に開かれた巨大な転移門の姿があった。
いや、それは転移門と呼べるほど論理的なものではない。湾曲した空間、ずれた次元を強引にこじ開けただけのこと。
巨大な二つの手が開く黒い穴の向こう側、腕の持ち主がじっとクリムゾンウェストを覗き込んでいる。
その門の手前では数多の騎士がとある歪虚と刃を交えていた。

???
暗い影に身を包んだ怪物はその爪と牙で騎士を軽々と殴殺していく。
「化け物め……なんという力だ!」
「青龍様に力を授かった我らが、こうも簡単に……」
人型の獣は無言で地を蹴り、音もなく騎士の懐に飛び込むと、その爪で胸を貫いた。
当然ながら致命傷。だが、それだけでは終わらない。
「な、なんだ……う、ぎひいいいい!?」
「ひいいいっ!? おっ、おい!?」
身体を貫かれた騎士の体が激しく痙攣し、体内の至る場所から牙、或いは爪にも似た硬質の物体が噴き出す。
そしてめきめきと音を立て、騎士の体は“作り変えられた”。
かつて騎士だったものは怪物と同じく姿の見えぬ黒い影に覆われ、ごそごそと四つん這いに仲間へ駆け寄ると、とびかかり牙を立てる。
「ぎゃあああっ!?」
「こいつ……ヒトを食うのか!?」
『タス……ケ……テ……』
怪物に変化させられた騎士は、苦悶の声を上げながらも仲間に攻撃を続ける。
それが更に仲間を怪物に変化させ、二体が四体に、四体が八体に、あっという間に戦場の色が塗り替えられていく。
はじまりの怪物は最早手を下すまでもなくなった戦場を一瞥し、ふいに空を見上げる。
降り注ぐ流星のような光。それはこの時代に本来存在しない者。ライブラリ上の仮想領域に観測者がアクセスした徴であった。
(文責:フロンティアワークス)
「アズラエル! これはどういう事じゃ!?」
がなりこんできたナディア・ドラゴネッティ(kz0207)を待ち受けていたかのように、アズラエル・ドラゴネッティは両手で制止する。
「ちょっと待ってくれ。順を追って説明させてほしい」

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ
「まず、彼らは無事だ。ただのショック症状だよ」
神霊樹ライブラリ内に再現された過去の記録。
すなわち王国暦682年、大侵攻始まりの地であるリグ・サンガマにダイブしたハンター達。
そこで彼らが体験したのは、圧倒的な物量に押しつぶされ、一夜にして滅び去ってしまった北方王国の真実だった。
無論これは再現された夢のようなもので、そこで何が起ころうがハンターには関係ない……そう考えられていたのだが。
「帰還したハンターの一部で、精神的な異常を訴える者がいるのは把握している。いわゆる強烈な悪夢を見た結果、目が覚めてもナーバスになっているようなものさ」
「目覚めた途端に気絶した奴とかもおるのじゃぞ! この作戦は安全だったハズじゃ!」
「だから、安全だよ。誰も肉体的な損傷はないんだ。そりゃあ死ぬのは気持ちのいい話じゃないが、本当に体が滅びるわけじゃない。すべては一時的なものなんだ」
しれっと説明するアズラエルの様子にげんなりする。この男、悪気はないのだ。
「はあ……本当に命に別状はないのだな?」
「我が神たる青き龍に誓って。だが確かに少し休憩は必要かもしれないね。次の作戦開始までは、まだ少し時間がかかりそうだ」
『ほう。過去の記憶から邪神の姿を確認したか。クリムゾンウェスト人もなかなかやるではないか』
トマーゾ・アルキミア(kz0214)は会議室のスクリーンで愉快げに笑う。

トマーゾ・アルキミア
邪神と呼ばれる巨大歪虚について、そしてイグノラビムスと呼ばれる謎の歪虚についてだ。
「トマーゾ、そもそもおぬし邪神についても知っておるのだろう?」
『そりゃあ存在はのう。じゃが、前にも言ったがアレは言葉で説明するのが難しい。それにわしにもわからぬことの方が多い。何かわかった事があるのならば、是非共有してもらいたい』
「では、イグノラビムスという歪虚についてはどうじゃ?」
『――イグノラビムス? ふむ……どの様な歪虚だ?』
それは白銀の獣。人狼のような形状を取ることもあれば、手足の数を自在に変える事もできる。
あのリグ・サンガマの北の地に出現し、邪神の介入を防ごうとした龍騎士隊を殲滅した歪虚だ。
「なかなかにハンターの中にも賢い者がおってのう。ヤツはどうも普通の歪虚とは違うと言うのじゃ」
「眷属カテゴリー的には恐らく憤怒だね。ただ、とびきり再生能力と攻撃能力が高い。特に、人間と言う種族を狙う」
『ほう……』
アズラエルの説明に何かピンと来るものがあったのか、トマーゾの目つきが変わる。
「以前おぬしは確か、クリムゾンウェスト人とリアルブルー人はマテリアル的には同じと言っておったな。ハンターの中にはそれを指摘する者もおった」
「イグノラビムスは人間を憎んでいた。ならばそれだけの理由がある存在ではないか、とね」
二人の指摘を受け、トマーゾは低く笑う。そして心底満足そうに溜息を零した。
『鋭いのう。実に鋭い。戦闘狂の若造ばかりと思うておったが、狩人の中にも頭のキレる者がおる』
「では……?」
『イグノラビムスについては心当たりがある。恐らく元々はリアルブルー側の歪虚じゃ。当然特別な能力を持っておるじゃろうから、連中の言葉を借りるなら“黙示騎士”と言ったところか』
マクスウェル、ラプラスに続く三体目の黙示騎士。だが、あれは王国暦682年の出来事であったはず。
「今あなたはリアルブルーの歪虚と言ったね。だが、リアルブルーに歪虚はいないのではないか?」
『今はほとんどおらぬだろうが、18世紀の地球にはそういった怪物もおったかもしれんぞ。まあ、ソレはもっと古い歪虚に思えるがな……。心当たりはあるので、こちらでも調べてみよう』
こうしてひとまず情報については精査を行いつつ、次のダイブ座標を制定することになった。
しかしまだ座標の特定には至っておらず、ライブラリの整備には少し時間がかかる。

タルヴィーン
「ふぉふぉふぉ。次はどの時代を閲覧するつもりじゃ?」
「手に入れた邪神の形跡を検索してみるつもりだよ」
タルヴィーン(kz0029)の問いかけに神霊樹端末を操作する手を止めずに応じ、アズラエルはすらすらと回答する。
「邪神の情報をもっと詳らかにしないといけないしね。それに簡単に検索してみた感じでは、邪神は古代の時代からこの世界に介入している」
「ほう……」
「つまり邪神を追えば、古代の歴史をより詳細に知ることができるってことさ。こいつをガイドにして、より深い時代……古代にまで調査の足を伸ばす」
タルヴィーンはその横顔をじっと見つめ、思案する。そして心の中で何かを決断すると、こう切り出した。
「……本当に邪神を調査する必要はあるのじゃろうか? この世界にとどまり、この世界で生きる……それではいかんのか?」
ふと、アズラエルの手が止まった。なぜかタルヴィーンの口調はとても寂し気だった。
「わしは正直、おぬしらに過去を教えとうない。先の調査で理解した筈じゃ。そんなことをしても絶望的な結果を突き付けられるだけじゃと。わしはいつもおぬしらヒトを見守って来た。わしはヒトの紡ぐ物語が大好きじゃ。おぬしらがただ絶望するだけの物語は見たくないのじゃよ」
「やはり君は何か知っているんだね、タルヴィーン」
「わしからは何も言えぬ。じゃが、考えてみて欲しい。あの大侵攻と同じことが、またこの世界に起きたとしたら? おぬしらには抗えぬ。なぜ好き好んで、“未来に希望はない”と知りたがる? それは緩やかな自殺と同じじゃ。その結果として、この世界は……」
そこまで言って首を横に振り、タルヴィーンは踵を返した。
彼が何を言おうとしたのか、結局アズラエルにはわからなかった。
だが、それももうじき明らかになることだ。このライブラリの中に、過去の真実は眠っているのだから。
(文責:フロンティアワークス)

アズラエル・ドラゴネッティ

ナディア・ドラゴネッティ

タルヴィーン
その残滓は今も世界各地で遺跡のような形で見る事ができるし、“世界が滅んだ”という事実だけはずっと伝承されてきた。
だが、その伝承はいつも途切れ途切れで、この世界の終わりを記録した者はいなかった。
「結論から言うと、遡れる時代には限界があった。つまり、神霊樹ライブラリ始まりの時代までしか時を遡ることはできない」
アズラエル・ドラゴネッティはそう話を切り出した。
ライブラリの整理は概ね完了した。その結果について報告するため、ハンターに先んじてナディア・ドラゴネッティ(kz0207)とタルヴィーン(kz0029)を会議室に呼び出したのは、確認を取るためだった。
「僕は既に概要を把握した。その内容をハンターに伝えるつもりだし、それが僕の義務だとも思う。だけどその前に……タルヴィーン、君に訊ねよう。“どうして僕らの邪魔をしなかったのか”……と」
さっぱり意味がわからないナディアはきょとんとするが、タルヴィーンは重く押し黙ったままだ。
いつもなら飄々とした様子でのらりくらりとハンターを相手するこの精霊が、こんなに緊張するところを見たことがない。
「タルヴィーンに過去の事は関係なかろう? アズラエルも何故そんなことを……」
「いいや。すまぬのう、ナディア。わしは……ずっとおぬしらを騙してきたのじゃよ」
「は?」
「神霊樹ネットワークは……神をあやす夢。そして、いずれ滅ぶと知れた世界の……バックアップにすぎない。わしは知っておった。この世界は再び、必ずや滅ぶのじゃと」
――紀元前のクリムゾンウェストは穏やかな繁栄を迎えていた。
歪虚と言えば自然に発生するものだけで、せいぜいが雑魔の強さ。歪虚は根本的に、世界の脅威足りえなかった。
特にヒトと精霊との距離が近く、それぞれが調和し共存する世界は、争いとも無縁な満たされた文明を築いたという。
しかしだからこそ、クリムゾンウェストに大きな変化はなかった。何十年も何百年も、何千年も……平穏な時代が続いたのだ。
そんなある日の事だ。とある世界からの使いを名乗る者たちが現れ、人々に告げた。
あらゆる世界を食い尽くす、星を渡る邪なる神。世界から世界へ、その怪物は幾度も世を渡り滅びをばら蒔いてきた。
異世界人は言う。「この世界にもいずれ滅びが訪れるだろう。我らの世界は、まもなく終わる」と。
使者はクリムゾンウェストの人々に戦い方を教えた。身の守り、滅びに備える術を与えた。
そして――神と言葉を交わし、心を交わし、共に戦う術を授けたという。
人々は神と通じ合い、莫大な力を手に入れた。その力を用いて闇の眷属との戦いに挑んだのだ。
あらゆる精霊とヒトとが手を結び、異界の神との戦いに挑んだ。それは何百年にも渡り、激しく続く。
だが力及ばず、ひとつ……またひとつと国は滅び、英雄は悉く死に絶えた。
神は自らを信じる者がいなくなるにつれその力を失い、やがて姿形すら保てず世界から消え去った。
これが古代文明の滅びの顛末である。
「要するに、異世界から邪神がやってきて世界を滅ぼしたということか? 確かに邪神が一度世界を滅ぼして居るのは驚きじゃが……」
「邪神は文字通り、この星を食らった。当然、この星は“虫食い”になった。マテリアルとはあらゆるものが存在する為に必要とするエネルギー。それを奪われた世界は、穴だらけになった。当然それでは世界という箱庭を維持できぬし、今もそれは治ってはおらぬ」
「は?」
「実は、この世界はまんまるい球のような形をしておる。その裏側を見たことはなかろう? この世界の裏側はのう……文字通り、存在しないのじゃよ」
ナディアがリアルブルー人ならば、或いは理解しただろうか。
このクリムゾンウェストの大地が――未だその3分の1ほどを消失させたままだということを。
「これは致命傷でな。率直に言うと、この世界はそう遠からず、何もせずとも滅びるのじゃ」
「はああっ!? なんかその……回避する方法はないのか!?」
「ある」
「あるんかーーーーい!」
「他の異世界を、食わせればよい」
ピタリと、ナディアの表情が固まった。その脳裏にはトマーゾの言葉が過る。
「……まさか」
リアルブルーとクリムゾンウェスト、双方に暮らす人間はマテリアル的には同一の存在である。
「既に……食ったというのか? リアルブルーを……」
トマーゾは調査の結果、二つの世界の共通項を上げた。だが、それは間違いだ。
“共通点がある”のではない。“元々同じ”なのだ。
「そうじゃ。この星の大精霊は、“異世界を食う”。それが、わしの隠したかった真実じゃ」
「それでは――」
――まるで邪神と同じではないか。その言葉をぐっと飲み込む。
いや、薄々感づいていた。クリムゾンウェストの大精霊の行いを思い返してみれば理解できる。
大精霊は自らの存続の事しか考えていない。ヒトの都合など知った事ではない。
当然のことだ。今もまさに、滅びの痛みに喘いでいる。“ヒトに構っている場合ではない”のだ。
「ただ、裏話をするともう少し複雑でね。そもそもリアルブルー人の源流はこっち……つまり、クリムゾンウェスト人にもあるんだよ」
アズラエルはそう言って、テーブルに置かれた角砂糖を手に取る。
「古代のクリムゾンウェスト人は世界滅亡の間際、この世界を捨てて逃亡したんだ。その逃亡先こそリアルブルー。つまり、こうやって移動した。でも、“この角砂糖は自分のもの”だと大精霊は思ってる。当然だね、元々は自分の世界の物だったんだから」
「だから召喚したのか? “自分自身を取り戻すつもり”で……異世界から」
リアルブルーの大地の上から、ある時町が一つ消えた。国が一つ消えた。
その大地から誰かが消えても、数の多さから人々が気に留める事はなかった。
それは都市伝説の類になって、誰からも忘れ去られていく。
彼らはクリムゾンウェストに呼びこまれた。そしてその穴だらけの大地に収まって、世界を補完する存在となった。
「恐らくこれが救世主伝説の始まり。そして、大精霊が異世界への転移を許さない理由さ」
「神霊樹ネットワークを作り出した古代人は気づいておったのじゃ。そう遠からずこの世界は滅びると。故に、バックアップを保存しようとした。それが神霊樹ネットワーク。彼らはいつか、自分たちがこの世界に戻ってくるときの為に記録を残した。じゃが、結局人類は帰ってこんかった」
はじめはヒトが作った神霊樹ネットワークは、やがて大精霊へと所有権が移っていった。
より効率的に様々な事象を観測する為にパルムという精霊が生まれ、大精霊は失われた世界の思い出に縋るように、記憶の世界に固執した。

邪神ファナティックブラッド
他の世界を、神をも屠る比類なき力を持つ怪物。
世界の最高単位が“神”ならば、おのずとその正体は明らかとなる。
「アレは――いずこかの世界の大精霊が歪虚化した存在と見て間違いない」
「やはり……か」
ハンターの中にはそれすら予見していた者もいた。
そう、読んで字のごとく、神なのだ。アレは、かつて神だったもの――。
「闇の化身、邪なる神。その名は――ファナティックブラッド」
震える声で絞り出すように、タルヴィーンはその名を告げた。
「いつか世界を終わらせ、やがて世界を滅ぼすモノよ」
肩を縮こませ、タルヴィーンは呟く。その様子は弱弱しく今にも消え去りそうだ。
「ファナティック……ブラッド?」
「狂血の邪神……か」
そう呼ばれるからには、恐らくその由来もあるのだろう。
だが、それを問い質すことはできなかった。タルヴィーンは魂を抜かれたように項垂れていたからだ。
「過去を知れば、未来に希望はないと知るじゃろう。行って、そしてかの邪神と大精霊の戦いを垣間見るがよい。おぬしらがどんな答えを出したとしても、わしは受け入れよう」
「タルヴィーン……」
「疑問に答えよう、アズラエル。わしは本来、おぬしらを止めるべきじゃった。滅びの運命を見てしまう前に……絶望してしまう前にのう……」
車椅子を動かし、タルヴィーンが退席する。
兄妹はその背中を無言で見送っていた。
(文責:フロンティアワークス)
むかしむかし、遠いむかしのお話。
ここではないどこか、遠い世界からやってきた狂った神様は、邪神と呼ばれました。
邪神は沢山の眷属を率いて攻め込むと、あっという間に世界を食べてしまいました。
世界中のありとあらゆる国が燃え、消えてなくなってしまったのです。
困った人々は神様に助けを求めました。
しかし神様も困っていました。神様は人々に祈ってもらわないと、存在し続ける事ができません。
助けてあげたいのはやまやまだけど、神様が力を発揮するにはニンゲンの数が足りませんでした。
だから、ニンゲンは自分たちの命を使って神様に訴えかけます。
自分たちを食べさせて、その力で邪神に対抗しようとしたのです。
イケニエで力を得た神様は、ニンゲンと共に戦いました。
邪神が眷属を使うように、神様にも眷属が必要で、ニンゲンは眷属となりました。
たくさんの精霊とたくさんの眷属を率いた神様の戦いは、何百年にも及びます。
けれど邪神は世界を食べて強くなるばかり。戦いは終わりません。
やがて、イケニエを嫌がるものが現れました。
死ぬのはイヤだと、戦いから逃げるものが現れました。
先に死ぬのは誰だと、そんなことで争うものが現れました。
ニンゲンが争うと神様は弱くなり、だんだんと優劣がはっきりしたのです。
人々は思いました。「このままではこの世界はなくなってしまう」と。
ニンゲンは世界にとどまり全滅するのではなく、どこかの世界で生き残ることを選びました。
神様はそれを知りません。眷属は最後まで自分と一緒に戦うと信じていました。
でも、どんどんニンゲンは減っていきます。
神様を邪神と戦わせ、ニンゲンはこっそりどこかの世界に逃げていたのです。
それがまたニンゲンの中で争いの火種となり、また神様は弱くなります。
それでも神様は気づいていませんでした。
最後の最期のその日まで、気づいていませんでした。
ニンゲンはとっくに、自分を見捨てたのだと――。

邪神ファナティックブラッド
ヒトに近い姿形をした上半身に、蛇のように長い長い下半身が伸びている。
その巨体は人間の街を手で物理的に叩き潰す事すらできるほどに巨大で、邪神の通る場所には深い爪痕が大地に刻まれる。
文字通り、クリムゾンウェストの世界は蹂躙されていた。
「もう少しだ! もう少しで異世界転移門に辿り着けるぞ!」
巨大な邪神の姿を背景に、荒野を進む長蛇の列。各地から逃げ延びた生き残りたちは、最後の希望に向かって歩みを進めていた。
“異世界転移門”。それは魔法文明を極めた古代文明においても高度な技術。
地脈の有無に左右されるため、特に星の力の強い場所にしか作ることができない。
その転移門を使えば、ここではないどこか――滅びを待つだけの世界から逃げ出す事ができる。そう信じて集まって来た。
だが、現実は違っていた。
異世界転移門がある遺跡の周りは人々が行列を作っていた。武装した騎士らが道を塞いでいて、先に進めないのだ。
「既に遺跡周辺には人が集まりすぎています! これ以上入ることはできません!」
「そんな! 私たちはここに来れば助かると聞いて……!」
「順番です! 必ず全員助かりますが、一度に転移させられる数には限界が……」
「嘘をつけ! そんなことを言って、俺たちを見殺しにするつもりだろう!?」
騒ぎはどんどん大きくなり、一人の男が騎士を殴りかかると、あっという間に暴動になる。
この終焉において、既に性善説は意味を持たない。
誰もが自分の命が、或いは大切な人が生き残ることばかりを考えていた。

大精霊
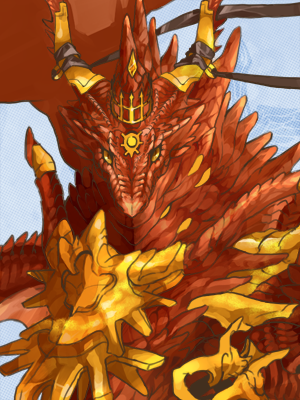
赤龍

白龍
神に自我はない。故に意思疎通も不可能である。そう人々は認識していた。
巨大な光の玉、マテリアルの集合体である大精霊は人々の願い通り邪神と対峙する。
そして双方の眷属が空を埋め尽くし、正面からぶつかり合っていた。
数え切れぬほどの精霊たちが、数え切れぬほどの闇の眷属と互いを潰しあう神話の戦い。
その中には後に五大龍として知られることになる一際強力な龍らの姿もあった。
『ふむ……人間はどうやら抵抗を諦めたようだな』
『わかっていたことではありますが……哀しいものですね』
青龍の言葉に白龍が声のトーンを落とす。
次々と飛来する歪虚にブレスを放つと、光の線が空を駆け、次々に爆発が巻き起こった。
『種の生存を思えば当然の選択でしょう。残念ではありますが、あの子達が生き延びてくれるなら、未来はまだ繋がる』
『大精霊なき世界に、意味があるとは思えぬがな』
黒龍の言葉に赤龍は淡々と返し、翼から無数の光弾を放った。
邪神は眷属に戦わせ、はるか遠くで停止している。それは大精霊による封印が効いているからだ。
だがそれも長くは持たない。今は何とか拮抗しているが、邪神が動き出せば総崩れとなるだろう。
『我らの戦いとは、結局何だったのだ』
『その答えは次の世代に求めましょう、赤龍。私たちはこの戦いで散り、そして大地に還るでしょう。しかし、いずれは生まれ変わる』
『……ああ』
黒龍に反論はしなかった。
いざとなったら自分たちが保持するマテリアルを放出し、滅びかけた世界を再生する算段。龍もまた、既に負けた後のことを考えていた。
彼らはその身を大地にゆだね、滅び、そして生まれ変わる。それで世界を何とか繋ぎとめるつもりだった。
ライブラリデータへの侵入によりハンターらが降り立った大地。それは終焉の世界。
確かに重大な世界の秘密だが、邪神の詳細を知る以上の意味も価値もない……その筈だった。
「なるほど?。どういうからくりなのか気になってたけど、こういうことだったんだね」

黙示騎士シュレディンガー
「初めまして、狩人さん。……いやぁ、ボクはこれまで何度も見てたんだけどね。君たちの介入に便乗させてもらったんだ。案内してくれてありがとう」
少年はそう言って笑うと、恭しく一礼する。
「ボクはシュレディンガー。君たちで言うところの“黙示騎士”ってやつだね。アレ? これはマクスウェルが言い出したんだっけな……まあいいや! ボクはこのまま大精霊を観測させてもらうよ」
ここはあくまでも仮想の世界であり現実ではない。
シュレディンガーが大精霊に何かしたところで過去の歴史が変わるわけではないのだ。
だが、黙示騎士だというのなら放置するわけにはいかない。ハンターが攻撃を仕掛けると、目の前でシュレディンガーは姿形を変えた。
以前目撃された黙示騎士のマクスウェルに似た姿になると同時、彼の大剣を使って攻撃を弾き飛ばす。
「せっかちだなー。別に君たちが見てるんなら、ボクが見てたっていいじゃないか。まあいっか、君たちの事も観測したかったし」
マクスウェルの姿をしたシュレディンガーは、本物さながらの威圧感で両手剣を構える。
「でも、見てどうするの? ねえ、今何を感じてる? これからどうしたい? もっと教えて欲しいなぁ……君たちのこと……」
封印された邪神がもう間もなく動き出す。
世界崩壊の時は、目前にまで迫っていた。
(文責:フロンティアワークス)
夢は甘く――そして優しい。
夢は苦く――そして冷たい。
それは神が見る夢。既に取りこぼしてしまった過去を見つめるための夢……。
(53616c7465645f5f11afcb1da029601d0cd264293a557b6ac2b33cedca10efbb)
『オォォォォーーーーーー!!!』
古の荒野にファナティックブラッドの咆哮が響き渡る。
その背に七つの翼を広げ、邪神が大地からマテリアルを吸い上げる。
それは光の本流となり、螺旋を描いて邪神を取り巻く。そして邪神は翼を広げるように、光の帯を大空へと広げていく。
吸収した正のマテリアルを負のマテリアルへ変換する。ただそれだけの作業が、星に穴を穿つのだ。
世界のすべてはマテリアルによって作られている。マテリアルを失えば、モノもイノチもすべては塵と消える。
負のマテリアルを失った歪虚が塵に還るように。正のマテリアルを失いきった大地も、塵に還るのだ。
邪神の放つ波動は取り残された人々をも飲み込み、そして消し去っていく。
惑星という生物にとって、半分近い体積を失う事は致命傷に他ならない。
この瞬間、クリムゾンウェストと呼ばれる世界の崩壊は確定していた。
(53616c7465645f5f4271394251bde8b041cdde365039f32d52e7022a4382cfebc745d3e4abce663e)
自分が死ぬということに神様が気づいたのは、人間がいなくなったずっとあと。
既に邪神もどこかへ去り、消滅を待つだけの段階になってからだ。
(53616c7465645f5fac70430b7fbc5d7a56fba7d0dbd6261059e68106b0adf14267cc742382c89e85)
探した。探した。探した。
自分の身体の一部なのに、探しても探しても見つからなかった。当然だ。彼らはもう、世界を忘れてしまった。
だから見つけ出すのにはずいぶん時間がかかってしまった。
どこか遠くの世界。そこで、彼らの子孫は生き延びていた。
それを見つけ出した時、仮に神と呼ばれる存在が感情を持つのだとしたら、きっと「喜び」と呼ぶべきだった。
神の考えは、所詮ヒトにはわからない。
ヒトの考えもまた、所詮神にはわからない。
二つの存在の間には絶望的な隔たりがある。だからそれが「良かれと思って」の事だと、ヒトは気づかなかった。
突然異世界に召喚され、故郷と信じたリアルブルーに帰れずに死んでいった多くの人々が、今の世界を作っている。
失われてしまったものを、その穴を埋めようと、神は呼び戻し続けた。
召喚し、召喚し、召喚し……それでもまだ足りない。
満たされぬまま、消滅の痛みにもがきながら、癒されることを願い、求め続けた神の夢。
世界がまだ満たされていた時代の記憶。そして、それが再び失われるに至る記憶……。
(53616c7465645f5f0202a5fa811d5ab0d30c668aa133c01c?)
ある時、いつも見ている夢にいつもと違う登場人物がいる事に気づいた。
所詮夢は繰り返される歴史、現実になるわけではない。それでも彼らは過去と向き合おうとした。
「憤怒の眷属……ですわね!」
ある者は未来の情報から過去を紐解き、大精霊本人も自覚していなかった記録を明らかにした。
「よし。初見殺しさえ防げれば……先輩方は、戦える! 幻影だろうと構わない。龍盟の戦士の、大先輩を……助ける!」
ある者は見知らぬ未来の同志と共に戦った。彼がいれば、龍騎士隊が全滅しない未来もあったのだろうか?
「それじゃ死出の旅路と洒落こむかね。……あとは任せたぜ」
ある者はあえて自らの命を使い、僅かな時間を稼ごうとした。彼も理解していたはずだ。その行いで結末は変わらないと。
「私たちが護りますから、頑張って前に向かって歩いてくださいね」
ある者は亡国を追われ旅をする者たちに寄り添い、共に生存の道を模索した。
それらは、本当に夢なのだろうか? もちろん夢だ。それは間違いない。だが……。
(53616c7465645f5fccc994f4d4779092dc30f7ae591c38a2……?)
「――ほう。これが噂に聞く死後の世界……という奴かな?」

Holmes
さっきまで邪神と戦っていた気もするし、それが随分昔の事にも思える。
ふと、自分の周りを何かが巡っていることに気づく。白い、小さな光の球だ。
それはHolmesの眼前で停止すると――恐らく声をかけた。
『53616c7465645f5fbd03d3f1403aaba0617eded32abcfe8ebbeeeecb764
d46e033609b607bce70edb095743c9f8dc9e9ce9deac70200fa55?』
「ぐっ」
思わず顔をしかめる。これは恐らく何らかの言語だ。だが、理解しようと考えるだけで頭が割れそうなほど痛む。
「……ということは成程。これは光栄だね。まさか、神様の招待を受けることになるとは」
『53616c7465645f5fbd03d3f1403aaba0617eded32abcfe8ebbeeeecb764d46e033609b607bce70edb09574
3c9f8dc9e9ce9deac70200fa55?』

紅薔薇

ユーリ・ヴァレンティヌス

沢城 葵

ラヴィーネ・セルシウス

Gacrux
同じ時間、場所、しかし全く異なる軸。紅薔薇(ka4766)もまた頭を抱えていた。
痛みには慣れっこだが、これはそういうものではない。許容しかねる程の情報量が、存在感が、ヒトという小さな器を破壊しようとしている。
根気よく理解しようと耳を傾け続けると、だんだん言わんとすることがわかる……ような気がしてくる。
「つまり……“なぜ”と問うておるのじゃな? なぜ、邪神から逃げなんだと」
「どうして……それは、確かにそうかもね。未来は変わらないって、私はちゃんと理解していたわ」
ユーリ・ヴァレンティヌス (ka0239)は瞼を閉じて、あの光景を思い出す。
決して逃げずに戦い続ける精霊たち。なのに、ヒトはとっくに尻尾を巻いて逃げ出していた。
目の前で散っていく精霊たちは、根本的に命の形が異なるものだ。死など彼らにとっては至高の恐怖足りえない。
「でも、やっぱり可哀そうだって思ったの。自分だけ逃げるわけにはいかないって……このままだと死ぬってわかっていたのにね」
「知りたいこともあったし、やっぱり仲間が戦っているんだもの。あたし一人だけ逃げられないじゃない?」
沢城 葵(ka3114)はそう言ってウィンクする。だが、小さな光にはいまいちピンと来ていないらしい。
「あそこにはあたしの大切な人たちがいたのよ。みーんなで頑張って、黙示騎士ってやつと戦ったの。やっつけられなかったけど、でも精一杯頑張ったわ」
やはり、光は理解ができない様子で、葵は思わず苦笑する。
「やーねぇ、あなた。そうね……そうなのかもねぇ。確かに、神様には難しいお話かもね?」
「生存するということは、本質的に厳しさを伴うものだ。逃げ出した先にもまた困難が待ち受ける……それは誰でも耐えられるものではなかった」
ラヴィーネ・セルシウス(ka3040)はそう呟きながら眉を顰める。
「リグ・サンガマは滅びた。そして、クリムゾンウェストも一度は滅びた。だが、力強く生きる力を持つ者たちが、歴史をこれまで繋いできたのだ」
そう。たとえ神の真似事と揶揄されても、あそこではより強き者を選ぶ必要があった。
生物淘汰は人間も例外にはしてくれない。だから、生きる為に必要な決断をしたつもりだ。
「――でも、間違いだったのでしょうか? いえ、どこかに間違いがなければ、ああはならないと思うんですよねぇ」
世界の終わりを見届けて、Gacrux(ka2726)はそう結論付ける。
「“諦めたことが間違いだった”と言う者もいました。実際、逃げ出すのが早すぎた気もします。結局ヒトは精霊と共に戦わなかった。そうであったのなら、違う未来もあったかもしれませんね」
僅かな間。それから小さな光はノイズ混じりの意思を伝える。
『――テ――レ?』
ズキズキ痛む頭でGacruxは必死に耳を澄ます。
『――ソバニ……テ――クレ……?』
男は腕を組み思案し、そして答える。
「そうですね。まずは、お友達から始めませんか?」
――夢に紛れ込んだ者たちを、神様はずっと見ていた。
彼らが何を選び、何を感じ、どのような可能性を示すのか。
知らなかった。この世界にまだ、こんな者たちがいるなんて。
気づかなかった。あんな可能性があったなんて。
忘れてしまっていた。遠い昔の時代、自分のそばにも誰かがいたことを。
『ずっと……そばにいてくれますか?』
寂しげな神の言葉に、夢の狭間で彼らは応えた。
ライブラリに光が満ちていく。途切れた言葉がつながっていく。
星を覗く観測者たちに、ついに星が気づいた瞬間であった。
(文責:フロンティアワークス)
「神霊樹ライブラリに何か変化があったと聞いたのじゃが」

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ

タルヴィーン
「今やっと観測が完了した。これは……なるほど。トマーゾ教授が言っていた例の座標と一致するね」
「ふぅむ……興味深いのう」
二人の背後からのぞき込むナディアだが、らちが明かずに飛び跳ねる。
「のう! わらわにもわかるように説明してほしいのじゃ!」
「前にトマーゾ教授が言っていたことを覚えているかい?」
『貴様ら、どうも転移する時にめちゃめちゃ遠回りしておるな。ほれ、転移時のデータを確認したところ、一度の転移で最低でも3、4回は不要なパスを経由しておる』
そういえばトマーゾがそんなことを言っていた。
すべての覚醒者は転移門を使用する時、特定のポイントを通過する。
そしてその場所を通過する時に、ハンターの所持している記憶はライブラリに移動するのだと。
『多数の人間が得た情報、記憶の集積されたデータベースは集合無意識の結晶じゃ。神霊樹が大精霊に通じている事は明らかじゃが、そこに蓄積されるのは人の夢、人の記憶……。大精霊はそれを夢見ておるのかもしれぬな』
「ああ?。なんかそんな事言っておったのう。それがどうしたのじゃ?」
「その座標は、そうだね……暗号化されていたというか、普通に転移門に入力してもいけない場所だったんだ。でも、昨日の作戦の後、暗号化が解除されたんだよ」
「どれどれ……って、ここは……!?」
「そう。“星の傷跡”の地下深く。星の深部にして神の領域。ご丁寧に表示されたこの座標名は……」
「封神領域……マグ・メル?」
それは、“だれ”が“どうして”つけた名前なのだろうか?
そんな疑問と同時に一瞬のさみしさを覚えたナディアだったが、頭を振って考えを改める。
「ちょっと待て。なぜ急に星の傷跡深部にアクセスできるようになったのじゃ?」
元々は神の見る夢を観測することで、古代人がどのようにして大精霊と対話を行っていたのかを知るための作戦だったはずだ。
だが、実質的に神霊樹の歴史は世界が滅んだ紀元前3600年より古いものはなく、そしてその時代にこそ求める知識があった。
神霊樹ネットワークが生じたのがその紀元前3600年だったとすれば、それ以前の記録がないのも頷ける。
では、それで八方ふさがりだったはず。
「恐らく、これまでのライブラリ探索の様子を、大精霊は見ていたんだろう。これは“神の見る夢”――彼らは神の視線の先に割り込んで、存在を証明したんだ」
「神がずっとハンターの行いを見ていたということか?」
「ああ。その存在に気づき、そして対話をしてもいいと考えたのだろう。だから、マグ・メルと呼ばれる場所への転移が可能になった」
過去が実際に変わるわけではない――そう言われながらも、ハンターたちは手を抜かず、最後まで運命に抗った。
その時代に、その人々に、その世界に……同じ目線に立ち、同じ境遇を受け入れ、寄り沿おうとした。
挑んだところで意味などないと、ただ目的を果たす為にその有様を見ていることもできたはずだ。
「だが……彼らはそうしなかった」
アズラエルの口角がわずかに上がる。
「無駄と知りながらそれでもあきらめなかった。最後まで見届けようとした。奇しくも“古代人とは違う”行動をとった」
「それを見ていた大精霊が、興味を持ってくれたと?」
元々彼らはそういうつもりではなかっただろう。別に、神に善性を見せつけたいなんて思っていなかったはずだ。
誰かに評価されるための行いではない。だからこそ、それはヒトの純粋な性質と言える。
「驚いたのう……これは驚いた。さらりと流されておるが、奇跡と呼んで差し支えなかろう。これが“英雄”の資質か……」
タルヴィーンはしきりに溜息を零しながら頷く。これは彼にとっても意外な結末だった。
「しかしのう、マグ・メルなる場所で大精霊がおぬしらを穏やかに受け入れてくれるとは限らぬ」
「そうだね。これは文字通り神の試練だ。何が起きてもおかしくないだろう」
「え? なんで? 神とバトることになるの?」
「相手が大精霊だとすると、本気でやり合って勝ち目はない。それは向こうもわかっているだろうから、何か独自の試練を仕掛けてくるはずだ」
「あー。そういえば辺境の大幻獣とかもそういうことしてくるよネ」
「ともかく、一度ハンターを集めよう。マグ・メルに挑める者を集め、証明するんだ。邪神に対抗するにはそれしかない」
もしかしたら、この時を待っていたのかもしれない。
神の自意識はあまりにも巨大すぎて、自分が求めていたモノがすぐそばにあることにすら気づけなかった。
長い時間、気の遠くなるような時の果て、痛みの記憶にもがきながら、それでも求めていた。
『それは理解しているがね。吾輩としては気がかりなのだよ……そう、健全な肉体を持つ者であれば良いのだがね』
『あら? 試さなければならないのは、そこでしょうか? わたくしは健全な精神を持つかどうかが心配です』
『はっはっは、それは問題ない。健全な肉体を持つのであれば、健全な精神も宿っているのが必然というもの』
『……………………』

『……ヒトは弱く幼い生き物だ。だが、自然を相手に立ち向かい、それを御する勇敢さも持っている』
『意外ですね。イクタサは彼らの来訪を歓迎するのですか?』
『私たちはただ神の意思に従い、彼らを試す……それだけだ』
『うむ、確かに。それでは早速、客人を招くとしよう。我らそれぞれの領域へ!』
星の中心、膨大なマテリアルに満たされた空間において、物質と精神はその境界をあいまいにする。
神に招かれた者だけが訪れることを許される領域で、試練が始まろうとしていた。
(文責:フロンティアワークス)
封神領域マグ・メル。星の中心に形成された、物質と精神の狭間。
マテリアルと呼ばれる命の根源たる力による“ゆらぎ”が生むその場所はとても不安定だ。
四大精霊の試練には、その不安定な場に人類が立つ為に必要なこと。すなわち、己を正しく観測させるためにあった。
『――そもそも。“節制”も“正義”も“知恵”も“勇気”も、お主ら人類だけが持つ概念』
眩い光の本流の中、太くたくましい声が響き渡る。

プラトニス
この圧倒的に広大な世界の中で、ヒトと呼ばれる知的生命体だけが得た“想い”。
本来生物が繁栄存続する上で不必要な概念。だがそれを抱くが故にヒトはヒトであり、ヒト独自の力を持つ。
『神が本当にお主ら人間を全く知らなかったとしたら。認識もせず、意識もしていなかったとしたら。そもそも我輩たちは成立していないのだよ』
大精霊から切り離された四体の精霊。四大精霊は、大精霊がヒトと接触する為に作ったインターフェースだ。
ヒトの側に寄せ、ヒトの概念をベースに構築されている。
四大精霊が存在していることそれ自体が、大精霊の精一杯の譲歩なのかもしれない。
光の中を進み、ハンターは巨大な存在の一端に触れた。
星の中心に浮かぶ光。大精霊と呼ばれるそれは、この星の生命――即ちすべてのマテリアルの集合体。
是は自然であり、是は概念であり、是は英霊である。
目にしただけで存在の全てを焼き払われるような強すぎる力に手を伸ばし、ハンター達はその中へ吸い込まれていった――。
『試練合格、オメデトーーーウ!』
バシバシと豪快に手を叩く音でふっと意識を取り戻したハンター達。
気づけばマグ・メルではなく、ハンターズソサエティ本部に大量のハンターが横たわっている。
どうやらマグ・メルへの転移介入が終了したらしいことはわかるが、あれだけいたハンターの中で気を失わずに立っているのはごく数名。
それ以外のハンターは全員気絶しており、それをオフィス職員が必死に運び出しているところだった。

ジャック・J・グリーヴ

ヴォルテール=アルカナ

サンデルマン

エヴァンス・カルヴィ

アメンスィ

雨を告げる鳥

イクタサ

アルマ・A・エインズワース
『うむ。だが、大精霊の存在規模が大きすぎて、今のお主らでは受け止められなかったようだなあ』
「プラトニス!? なんで現実の方にいやがる!?」
慌てるジャック・J・グリーヴ(ka1305)の視線の先、プラトニスはちょこんと隅っこに座って微笑んでいる。
『うむ。何故も何も、試練を超えたお主らに力を貸すためである。実体化しなければヒトに干渉できまい』
「では、こちらのサンデルマン様が顕現なされたのも、試練を超えた俺たちに力を貸すためでしょうか?」
ヴォルテール=アルカナ(ka2937)の視線の先には神霊樹の傍に浮遊するサンデルマンの姿もある。
『……………………』
姿形をヒトに模倣していないサンデルマンは非常に無口で、ヴォルテールの問いに答える事はなかった。
だがエヴァンス・カルヴィ (ka0639)はニヤリと笑い、その場にどっかりと胡坐をかく。
「ま、正義だなんだとややこしい話もしたが、こうしてみんな生きて帰ってきてんだ。そりゃ認められたってことだろ?」
『ええ……その通りです。未だ大精霊の力を受け入れるには至らぬ器とはいえ、皆さんはわたくし達に確かな意志を示しました』
「私は問う。アメンスィよ、大精霊との対話は成立しなかったのか?」
『対話と呼ぶほどの事は、残念ながら。けれども、大精霊があなたたちの存在を“認めた”のは事実』
「では、大精霊は俺たちに力を貸してくれるでしょうか?」
雨を告げる鳥(ka6258)に続き、神代 誠一(ka2086)がアメンスィに問いかける。
「俺たちはこの世界の過去を見ました。そして邪神という驚異と、それによってもたらされた滅びを知ったのです。俺は……あんな悲劇を繰り返したくありません」
強く拳を握りしめる誠一の脳裏に、神霊樹ライブラリの中で見た光景がフラッシュバックする。
邪神には――今の自分たちでは勝利できない。それはハッキリした。
「今は勝てない。でも……今は無理でも、いつか。力をつけて、彼らの仇をとってあげたいのです」
『その想いは立派だ。しかし、勇気と無謀をはき違えてはならない』
イクタサは冷たい口調でそう告げる。だが、すぐに思い直したように穏やかに語る。
『ボクたちも想いは同じだよ。邪神からこの世界を守りたい。でも試練をして改めて、君たちにはまだ力が足りないって気づいたんだ』
「わふ……お友達みんなで協力して闘っても、イクタサさんにも勝てませんでしたし……」
『死を超えて尚前に進む、その覚悟は見事だったね。けれど、本当に死んでしまったら悲しいじゃないか』
苦笑を浮かべるイクタサにアルマ・A・エインズワース(ka4901)も同じく苦々しい表情を浮かべる。
「ですねー。覚悟しているかどうかと、実際に大切な人を失っていいのかどうかは別ですしー……」
『死とは本来、次の命の始まりに過ぎない。けれど歪虚に滅ぼされれば話は別……命は星に帰れず、迷い子となり自らも歪虚と化すか、或いは完全に無に帰してしまう』
『ヒトの“想い”を示すのに“武力”が必要なのかと問うた者もいたね。その指摘は正しいが、ある意味では間違いである。“想い”だけでは何も成せぬし、“武力”だけでも道は開かれぬ』
「あー。つまり、健全な精神と健全な肉体ってヤツな」
『セッセェイ! その通り!』
ジャックの指摘にプラトニスはマッスルポーズ。隆起する筋肉がミチミチと音を立てている。
『実際、今のお主らは精神的にも肉体的にもまだ鍛え足りない。だから大精霊を受け入れられなかったのだ。今無理に対話すると脳が破裂します』
「マジかよグロすぎんだろ……じゃ修行して強くなればいいんじゃねーか?」
よっこらせと立ち上がり、エヴァンスはあっけらかんと言う。
『そうだね。今の君たちに必要なのは、いきなり大精霊の力を求める事ではないと思う。まずボクたちが、この世界の小さな精霊から力を借りやすくなるよう、話をつけるよ』
「私は問う。既に我々は精霊の力を借りた覚醒者……今以上に精霊の力を得る事は可能なのか?」
イクタサの話が事実ならありがたいが、雨を告げる鳥の言う通り、覚醒者とはすでに精霊の力を借りている存在だ。
だが、アメンスィはくすりと小さく笑い。
『可能ですよ? だってあなた達は……精霊の事を何も知らないでしょう?』
『ヒトと精霊は本来相容れぬ者だ。存在の次元が違うからね。精霊はどこにでも存在してる。でも、ヒトも精霊もその事実に気づいていない。……君たちはすれ違ってるんだ』
『そのすれ違いを是正しつつ、より強き肉体を手に入れてもらう。試練の第2ステージと言ったところであるな。ぬはは!』
豪快に笑い、プラトニスは頭上を仰ぐ。
『さて、まずはヒトの世を今一度知るとしよう。我ら精霊にはそれぞれ活動しやすい地というのがあってな。世界を見て回り、そこを探そうと思う』
『ボクの行先は既に決まっているよ。我が信仰の地、辺境の大地へ』
『では、わたくしは懐かしい同盟の大地へ向かいましょう』
『サンデルマンはどうする? ……うむ、帝国だな。では、我輩は王国領へ向かうとしよう。ぬはは』
「あ、おい……俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ!? おーーーい!?」
慌てて呼び止めるジャックの言葉も空しく、四体の精霊は光の球に変化すると、それぞれがどこかへ飛んで行ってしまった。
非実体化した――つまりヒトに感知できない存在にシフトした精霊がどこに向かったのかなんてわかるはずもないし、物理的な壁も障害にならない。
「いやー、精霊の考える事なんかわかんねーなー! まあ、待ってりゃ沙汰があるだろ?」
「私は肯定する。今の我々には休息が必要だ。それに、倒れた仲間たちを運び出さねばな……」
「そうですね。ひとまず俺は仲間を起こしに行ってきます」
「というわけで、クリムゾンウェストの核がどこにあるのかは観測できたよ」
リアルブルーのマンハッタンにある統一連合議会本部。その議事堂を眺めながら一人の少年が呟く。
ここは先の蒼乱作戦で異世界人が制圧した議事堂。今日は閉鎖されており、誰かが足を踏み入れる可能性は低い。
少なくとも少年が計算した限りでは、今日この時この場所に人間がやってくる可能性は限りなくゼロだ。
『――ほう。無駄に遊びまわっていただけではないようだな、シュレディンガー』

シュレディンガー

マクスウェル

ラプラス
マクスウェルは壁に背を預けたまま、退屈そうに話を聞いていた。
ラプラスはその隣で腕を組み、静かに佇んでいる。
『星核の座標を特定したのであれば、今後は直接制圧も可能か』
「やー。流石に大精霊クラスとガチで対峙したらボクらじゃ即死だよネー。存在のレベルが違いすぎるもん。ま、いざと言う時の保険っていうか? あの世界の人たちすごいね。神と直接対峙してる世界ってまだ二個しか見たことないや」
『……エバーグリーンとクリムゾンウェストか』
フンと鼻を鳴らすマクスウェル。どんな表情をしているのかはさっぱりだが、恐らくあまり面白くない様子だ。
「神の座標がわかると、こっちから転移攻撃仕掛けやすくなるんだよね。意識のスキをつけるからさー」
『邪神があの世界に介入しやすくなったということか』
本来、邪神はその存在の規模が大きすぎるため、異世界に転移しようとすると神による防衛機能が働いてしまう。
故に蒼乱作戦でそうであったように、身体の一部を一時的に転移させるのがやっとというところだ。
だが、神の意識のスキを突くことができるようになれば、邪神という究極の対星兵器を送り込みやすくなる――のだが。
「それが、なんか神の意識が覚醒したっていうか……より地上とヒトに向けられるようになって、ガードが固くなってたよネ」
『ナニィ!? それでは意味がないではないか!』
「骨折り損かもね?。それよりもリアルブルーの大精霊をなんとかしないと、火星から一気に攻め込めないよね。なんか上手い手がないかな」
『オマエが真面目にやらないからグダグダ続いているのだろう! オレは闘いに手を抜く輩が一番嫌いなのだ!』
「そー言われてもボク、他の世界と兼任だしさ?……忙しいんだよー」
『落ち着けマクスウェル……。リアルブルーの大精霊には利用価値がある。星ごと破壊はしたくない』
「この世界の神様――とっくに壊れてるもんね。だから、神様の亡骸を利用してるやつがいるんだよなー」
ズボンのポケットに手を突っ込んだまま、シュレディンガーは思案する。
まあ、見当はついている。というか、これは消去法の話なので間違えようがないのだが。
やるべきことは色々とあるが、課題は難しい方が面白い。
「ま、人間は人間同士で殺し合ってもらうのが一番手っ取り早いんだよな。これまでの世界もみんなそうやって終わって来たし」
できればもう少し積み重ねてから壊したい。きれいに作れば作るほど、壊す時の快感は増すのだから……。
(文責:フロンティアワークス)
「あ????……なんか何も起きてないのに異常に疲れた気がするの??」

ナディア・ドラゴネッティ

アズラエル・ドラゴネッティ
血盟作戦――神との対話は完了した。成功と言えば成功したのだろうし、人類史から見れば偉業なのだが、事が終わった今となっては全てが幻だったような気さえしてくる。
過去の世界滅亡を観測し、挙句の果てには神と直接対峙したというハンター達……だが、その記憶はあいまいで、結局得られた物などなかったのではないかと思える。
「やあナディア、ここにいたのかい」
「アズラエル。マグ・メルの調査はどうなったのじゃ?」
「ダメだね。もう一度あそこに転移しようとしてみたけど、入れないみたいだ。座標情報は間違ってないから、神に拒絶されているとしか思えない」
アズラエル・ドラゴネッティは徹夜明けの凝り固まった首筋をバキバキ鳴らしながらあくびを一つ。
「地上に顕現したという四大精霊の行方もまだはっきりわかっていないし……各国に協力は要請したから、じきに見るかるとは思うけど、相手は神に準ずる力を持つ精霊だ。本気で姿を隠されたら見つけることは不可能だろう」
「今回の戦い、結局のところあやつらは何を得られたのじゃろうな」
――古代のクリムゾンウェストを滅ぼしたという邪神ファナティックブラッド。
それが今またクリムゾンウェストに迫っていることを、ナディアは世界中の人々に伝えられずにいた。
あの絶望を観測すればこそ、力なき一般市民に現実と伝えるのは酷だと感じる。
ハンターはそれでもなおあの終焉に挑む覚悟を見せた。だが、この世界の希望であるハンターが実際に敵わなかったと知れば……。
「ダメじゃ……とても言えぬ。この話は各国の一部重役以外に漏らしてはならぬな……」
「そうだろうか? 僕の意見は正反対だよ」
邪神に勝つ為にはハンターだけでは足りない。その事実が明確になった今、より多くの力を集める必要がある。
「亜人や幻獣、それに異世界の力だって借りなきゃならない。邪神に負けたのは、すべての力をまとめきれなかったからだ」
「それはわかるが……リアルブルーが力を貸してくれるかのう? あの世界、あんまり言いたくないがちょっとヒドいぞ」
人間とは大なり小なり身勝手な物だが、リアルブルー人のエゴはかなり肥大化しているように思える。
利己的な考えを捨て、ありとあらゆる勢力が一丸となる……そんな理想は欺瞞ではないか?
「……さてね。こればかりはやってみないとわからないが、とにかく力を集めるんだ。リアルブルーも、エバーグリーンも、すべての力を一つにして邪神を討つ」
静かな口調ではあったが、アズラエルの横顔には強い決意が満ちていた。
「僕もすぐに北方王国をまとめ、ハンターズソサエティへの完全合流を目指すつもりだ。もう種族や国家の違いでモタついてる場合じゃない。この世界の滅びは、確実に迫っている」
邪神の存在の他にもう一つ明らかになった事がある。
それは、クリムゾンウェストの大地は多くが古代に欠損したままであり、この星は徐々に死に向かって進んでいるということだ。
「邪神に勝利したとしても、この世界は……。ふん、タルヴィーンが隠したがるわけじゃ。八方ふさがりではないか」
「だとしてもやるんだ。世界が壊れているなら修繕すればいい。邪神に勝つ力が足りないなら集めればいい。君たちはいつだって、そうやって不可能を乗り越えてきたはずだよ」
肩を叩く兄の力強い言葉に、ナディアは思わず瞳を潤ませる。
自分が苦しむのはいい。だが、この先に待ち受ける圧倒的な苦難にハンターを仕向けるのは胸が痛かった。
これからどうすればいいのか、道を見失った気がした。結局神様は何にも応えてはくれなかった。
「強く……なりたいのぅ。どんな運命にも負けぬほど……すべてを守れるほど、強く」
「それは、難しいんじゃないかのぅ?」

タルヴィーン
「わしら精霊も、ヒトへの歩み寄りが足らなかった。世界滅亡の時、ヒトはヒトだけで、精霊は精霊だけで戦っておったじゃろう? この世界にはいくつもの交わらぬものがある。互いを理解せず……諦め、切り捨ててきた。それに精霊も気づいたのじゃ」
「どういうことじゃ?」
「四大精霊様が顕現なされてから、クリムゾンウェスト中に力が満ちておる。各地の精霊が呼び起されている、とでも言うのかのう?」
精霊は、極端な話をすればただのマテリアルだ。
そこに方向性を得て、様々な力の源泉となる。だが、彼らは殆どヒトに歩み寄らない。
ずっとそばにいたのに、すぐ隣にいるのに、お互いを認識できない。それがヒトと精霊の間柄だった。
「じゃが、今なら……今からなら、精霊の力を借りられるかもしれぬ。この世界にあふれるマテリアルの力を得られれば、ヒトは更なる高みに至れるかもしれん」
「それって……覚醒者がより強くなるってことかい?」
「或いは、覚醒者の素質を持たぬものが、覚醒に至れる事もあるかもしれん」
それは戦力の純粋な増加を意味している。そして――。
「精霊がヒトと共に戦ってくれるようになれば……クリムゾンウェスト連合軍の戦力は一気に強化されるじゃろう」
「ハンターはヒトと龍の間にある壁も取り去ってくれた。僕は北方王国を中心に世界中の龍種の力を借りられるよう、働きかけてみるつもりだ。龍騎士隊も連合軍に合流させよう」
「しかし、それでは北方の守りはどうするのじゃ?」
「決まってる。――ハンターにでも助けてもらうさ」
どこかの誰かだけに頼るのはもうやめよう。
龍もヒトも、確かに星の守護者だ。けれど、彼らだけがこの世界を構成するすべてではない。
もっとたくさんの力を、たくさんの思いを束ねていこう。これまでヒトが、龍が見落としていた小さな力も……。
亜人も幻獣も精霊も勿論力を借りるのは難しいだろう。ヒトの歴史は彼らをいつも追いやって来た。
だが、これからはそういった力も味方につけなければならない。星を救い、邪神を討ち滅ぼすために。
「……そうじゃな。これはもはやヒトだけの問題ではない。リアルブルーにも協力を要請しよう。あの世界にも邪神の脅威は迫っておるはずじゃ」
拳を握りしめ、己を奮い立たせる。
今はまだ、神と共には歩めない。でもいつかは――この世界の、そして異世界の全ての力を集めて。
大精霊ともまた――同じ未来を目指せるのだろうか?
「ふぃ?……ぜんっぜんだめであるなあ?……」

ドナテロ・バガニーニ
地球統一連合議会――リアルブルーの秩序を維持する組織は、今真っ二つに割れようとしていた。
もっぱらの議題は“異世界人をどうするか”で、相も変わらず各国を代表する議員たちは、ほとんどが異世界人の受け入れを拒絶している。
「なぜなのであるか……そりゃあ、彼らは人間離れした戦闘力を持っているし、違う文明を持つ国々の出身。人種も違う。だが、地球だってそういう世界を一つにまとめてきたはず……」
そりゃあ、VOIDの脅威がなければいつまでも身内で戦争をしていたような国だ。それは知っている。
だがそんな国々が体裁だけとは言え一つになって軍を成したのが統一地球連合軍ではないか。
演説力には自信があるし、実際異世界人はイギリスや日本での活動でも成果を十分に出している。それでもなお拒絶する空気に、違和感を禁じえなかった。
「あれだけの戦闘力……どう考えたって利用するのが正常な判断である。まさか、異世界人に頼らずにVOIDを撃退する方法が存在するとでもいうのか……?」
VOIDは火星から発生しているという。だが、今現在火星がどのようになっているかなどわからない。
そもそもクリムゾンウェストから提供された情報が正しければ、VOIDは異世界から侵攻してきている。
大量破壊兵器でふっ飛ばせば終わりと言ったような簡単な敵ではないのだ。
少なくとも提携し、情報を引き出さねばならない。クリムゾンウェストが持つVOIDの知識は、リアルブルーを圧倒している。
定例通信の度に色々と教えてもらったおかげでだいぶ状況は飲み込めたが、それでもまだわからないところの方が多いのだ。
「ドナテロ様、お疲れ様で?す」
「む? おお、ユイ君」
ユイと呼ばれた少年はこの統一連合議会には不釣り合いな恰好をしていた。 具体的にはお世辞にも洒落ているとは言えないピンク色のジャージ姿で、フォーマルな場には馴染まない。
「議会の調子はどうでしたー?」
「ウム……悩ましいのである。どうしても異世界人を排除したいという声が大きくてなあ」
「異世界人の力なしで勝てると思ってるんですかねぇ??」
「いや?無理だと思うけどね、我輩も。あいつら生身で戦車破壊するからね」
「反対する人たちが丸ごといなくなっちゃえば楽なんですけどねー」
ニヤリと笑みを浮かべるユイ。ドナテロは冷や汗を浮かべながら首を横に振る。
「いやいや。自分にとって不都合な存在を排除したところでそれは平和ではなく弾圧である。異世界の盟友たちを待たせるのは申し訳ないが、根気よく頑張るであるよ! うん!」
拳を握りしめ歩いていくドナテロ。その背中をジャージのポケットに手を突っ込んだまま少年は見つめる。
「……わー、おじさんの精神力スゴくない? アーアー……ボク、暗示かけてるよね? 精神操作レジストできる特殊能力者なの? それか、どっかぶっ壊れてる?」
舌を出しながらそのあとに続くユイ。だが、ユイの存在をすれ違う職員は認識できていない。
「ねードナテロ様ー。もうバンッバン核ミサイル撃ってVOID倒すんじゃダメなんですかねぇ??」
「だめである。そんなことしたら世界中が疑心暗鬼になって戦争になってしまうである」
「それで別によくないっすか??」
「よくないっすであ?る?」
ブツブツ“独り言”をふりまき歩くドナテロを怪訝な表情で見送る職員たち。
彼の身に起きている異常に気付く者は、まだこの世界のどこにもいない――。
(文責:フロンティアワークス)
?プラトニスの場合?
●
ふむ、と巨漢は吐息を零した。
「むはは、きな臭い風が漂っておるなあ!」
満足げに言う男の巨躯たるや、異常の一言に尽きる。身の丈は三メートルを越え、肉厚な身体は、腕一つで女性一人分はあろう。
鋼のように鍛え上げられた筋肉は、筋繊維の連なりが体動のたびに蠢くのが解るほどだ。
男は、とある尖塔の壁に張り付いた。びょうびょうと吹きすさぶ風に身体を晒している巨漢はそのまま、とぅ、と、壁を蹴り、指に力を籠め、自らの身体をその頂きへと運び上げる。
「うむ。やはり、肉はイイ! な……!」

プラトニス

ヘクス・シャルシェレット
「ぬ、ぬはは! やめんか! くすぐったい!」
巨漢は身を捩らせて目に涙を浮かべて笑い出した。
「…………え、何だい、これ?」
それを呆然と眺めていた青年が、思わず声を漏らす。
唐突に壁の外に湧いた気配を警戒していたのだろうか。想定との落差に、青年はあっけにとられていたらしい。
それが、どれだけ珍しい光景かを知る由もない巨漢は、燐光に付きまとわれゲラゲラと笑いながら転がっている。
「――ふむ」
しばらくその様子を眺めていた青年は、青い帽子をかぶり直すと、ぽつりと、こう零した。
「……君は、精霊、なのかい?」
「む、いかにも!」
ぐるりと振り返った巨漢は、"彼"を正しく認めることとなる。
巨漢のそれと比べると小柄に見えてしまう彼の身体は、深い蒼と碧の衣装に包まれている。銀灰の艶やかな髪色は、巨漢が転げ回ったせいで舞い上がったホコリでうっすらと汚れているようではある、が。
理知と警戒、些かの懸念が混じった瞳は、すぐに笑顔に覆い隠された。
「その身に纏うた力と、"光"――さぞ名のある精霊とお見受けいたしますが」
「ぬはは! そう畏まらずとも良いぞ! 我輩は精霊であるからして、そなたらの流儀の埒外に在る!」
「……おや、そうかい? じゃ、遠慮なく――」
巨漢のすい、と手を差し出した青年は、握手を求めると。
「僕はヘクス・シャルシェレット。大いなる精霊の"座"から、こんな辺鄙なところにようこそ」
こう、結んだのだった。
「――節制の精霊、プラトニス様」
●
「我輩が節制オブザ筋肉ストのプラトニスであると、よくわかったな!」
「……いやぁ」
その身体。その服装。その容姿。非常識な言動。そしてその身体。というか、その身体。
情報さえ集めていれば、類推するには難くない大物である。彼ら四柱の精霊が、"そういった"行動に出たことも聞いてはいたからこその推測だ。
故に、問題はそこではない。留意すべきは――。
「ところで、どうしてこんな所に来たんだい?」
何故、此処に来たか、だ。
「ふむ」
プラトニスは嬉しげに笑うと、髭を撫でた。至高の一時に、鼻孔が膨らむ。大きく一息を吐き出すと、遠慮のない眼差しでヘクス・シャルシェレット(kz0015)を見下ろし、問うた。
「お主、その身体はどうしたことだ?」
節制の精霊は、その思考の過程に置いて欲に囚われぬことを善とする。
ただの吝嗇、ただの節約とは違いリアルブルーにおける【四徳】にならうものであろう、とヘクスは推測していた。
――だからこそ、問いを発してしまうんだね、君は……。
やめてくれよ、と内心で吐き捨てるヘクスを他所に、プラトニスはさらに一歩を踏み込んで、ぬふり、と笑いつつ、問いを重ねた。
「何故、そのように在るのだ、ヘクスとやらよ」
●
この日から、王国各所で空中を数多かつ多様な燐光が跳ね回る光景が見られるようになった。
小精霊たちが見せるこの光景は、記録を辿れば古くより見られていたものである。迷い火、あるいは踊り火とも呼ばれるそれは、マテリアルの賦活を意味することが多く、瑞兆の一つとして知られているが――しかし斯様にも各所で見られるのは、珍しい。
賢明なる読者諸君におかれては、間違っても、これら小精霊に無礼を働くことは無きよう、ゆめゆめ注意されたし。
どうやら此度の踊り火は、筋骨隆々なる保護者をお連れのようである。
――ヘルメス通信局、号外記事より。
?サンデルマンの場合?
火と闇、正義を司るサンデルマンは帝国へと降りることとなった。
「とはいえ、正義を司る大精霊殿を一体どこに置くべきか……」
「あそこでいいんじゃないか?」
真面目な顔で考え込むオズワルド(kz0027)にヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)はあっけらかんとした顔で帝国内で今最も使われていない施設の名を告げたのだった。
コロッセオ・シングスピラ。

サンデルマン

オズワルド

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
かつては奴隷階級もしくは重犯罪者などを戦わせ、賭け事に利用していた血生臭い施設ではあるが、歪虚との戦いが激化する中で徐々に廃れ、現在に至ってはここで催し物をするほどの財を持つ者もおらず、時折、師団員達の稽古試合で利用したりする程度となっている。
「ここならば貴殿の姿でも覆い隠せよう」
4m近い巨体を持つサンデルマンであるから、城内は難しいだろうというヴィルヘルミナの配慮であり、オズワルド他としては正義の精霊に執務状況を覗かれるとなれば(別にやましいことはないが)仕事がやりにくい、という実に俗物的な理由からこの場を勧めていた。
顕現したサンデルマンは相変わらず表情が読めない(なにしろ顔が無い)まま、静かに周囲を見回すように顔を左右に動かした。
――と、サンデルマンの火焔光背が一際強く燃え上がる。
「陛下!!」
「どうした」とヴィルヘルミナがサンデルマンに問うより先に、オズワルドが背の槍を取って構える。
オズワルドの視線の先には、大きな戦斧を担いだ武人の姿があった。
「何者だ?」
「急に現れやがった。アレは……このマテリアルはヒトじゃ、ない……?」
「……あぁ」
合点がいったというようにヴィルヘルミナが頷くと、腰のロングソードを引き抜いた。
「サンデルマンの力に触発されて現れた英霊殿……といったところか? 英霊というよりは亡霊に近い気もしなくも無いが」
オズワルドが何か言いたげに口を開くが、言葉にするより武人が駆け出す方が先だった。
2人は同時に左右に跳んで振り下ろされた強烈な一撃を避ける。
そしてその空いた背にヴィルヘルミナが渾身の一撃を叩き込み、次いでオズワルドが喉元へと穂先を突き入れた。
武人は音も無く光の粒子となり、それはサンデルマンへと吸い込まれるように消えた。
「……なんだ、もう終わりか」
あっけなかったな、とヴィルヘルミナが告げ剣を鞘へと戻す。
『そう言うな。あれでも過去にはこの周囲をまとめ上げていた部族の長だった者だ』
「は?」
聞こえてくるステレオ音声にオズワルドが顔を上げて、盛大に顔をしかめた。
「……鏡で見慣れているとはいえ、流石に肉感を持った自分を目の前にするというのは中々不思議な気分だな」
ヴィルヘルミナの前には“ヴィルヘルミナ”がいた。
いや、正しくはサンデルマンが化けた姿なのだが。
『しかし、この国は非常に“居心地が悪い”な……精霊の気配をほとんど感じない』
その言葉にヴィルヘルミナが柳眉を寄せる。
「もともと帝国領は錬金術を取り入れ、機導術を発展させてきた国だ。精霊というのが自然由来ならば、魔法公害をばらまいてきた我々とは相性が悪いだろうな」
『だが、彼らからの力無しでは邪神には対抗できん。皇帝よ』
「なんだ」
『まずは英霊を探せ。この国はヒトが争い奪い合って切り拓いてきた国なれば、英霊を探すのはさほど難しくはないはずだ』
「今のようにか?」
『あぁ。力が弱い者は今のように挑んでくる者もいるだろう。英霊として力が強ければ別の試練を課す者もいるかもしれんが』
「わかった」
『私が姿を維持するためには現状圧倒的に力が足りぬ。今はおおよそ一日3分が限界だ』
3分。短すぎる時間にオズワルドが待ったを掛ける。
「3分経つとどうなる?」
『お前達と意思の疎通が出来なくなる上に、力も貸せぬ。独力で何とかせよ』
そう言うと、ヴィルヘルミナの姿をしていたサンデルマンが銀色に溶け始める。
「サンデルマン!? ……サンデルマン?」
オズワルドが驚きの声を上げ……その後現れたモノを見て眉間のしわをより深くした。
「ふふふ……あははははは」
お腹を抱え笑い始めるヴィルヘルミナの前には、手のひらサイズになったサンデルマンがふよふよと浮いていたのだった。
?アメンスィの場合?
地と光、そして知恵を司るアメンスィの姿は、この日、同盟領中央部の荒れ果てた原野に在った。
「なんだぁ? こんな場所に何の用があるってんだ」
辺りは草木もまばらな荒涼とした大地。魔術師協会広報部長ドメニコ・カファロ(kz0017)は眉を寄せた。
「おーい、大精霊の嬢ちゃんよ。ここに何があるんだ?」
『……』
「わし等も遊びに来たわけじゃねぇんだけどよぉ。何とか答えてくれると嬉しいんだが?

アメンスィ

ドメニコ・カファロ

ラウロ・デ・セータロ
「まぁまぁ、ドメニコ。アメンスィ様にも何か考えがあっての事だろう。しばし待つとしよう」
「ったく、お前は相変わらず暢気だなぁ」
呆れるように溜息をつくドメニコが動であるなら、こちらは静の人。ドミニコの横に立つ静穏なる人物こそ、自由都市評議会議長ラウロ・デ・セータ(kz0022)その人であった。
「我々はアメンスィ様に協力を仰ぐ身なのだ。お話を伺えるまで待つのが礼儀というものだ」
そう言ってラウロは、宙を漂うアメンスィを見やる。
ハンター達の活躍により地上に顕現した四大精霊の一体は、封神領域マグ・メルより同盟の地へ舞い降りるなり、この荒野を目指したのだ。
盛大なもてなしを予定していた評議会と魔術師協会は、当然肩透かしを食らう形となる。これではメンツがと、幾人もの評議会議員や魔術師協会の幹部がアメンスィに話しかけるも、当の本人は『ありがとうございます』と微笑をたたえたまま、立ち寄るどころか、立ち止まる事すらなかった。
結果、評議長自ら級友の魔術師協会幹部を伴い、アメンスィに同行することとなった。
「――アメンスィ様」
日も傾き、夜の帳が迫る中、今度はラウロがアメンスィに声をかけた。
「我々は貴女を祀る神殿を用意しなければならないと思っているのです。いくつか候補を用意しましたので、お気に召す場所を選定してはいただけませんか?」
地上に顕現した四大精霊をまさか野原に放りだすわけにはいかない。
ラウロは評議会や魔術師協会と協議を重ね、アメンスィの住居たり得る祀殿を用意しようとした。
『お心遣い感謝いたします。ですが、わたくしの住まう場所はこの大地。祀られる箱など必要ありません』
しかし、薄く微笑むアメンスィは、目の前に広がる荒野を指さす。
「この様な荒涼とした場所に住まうと仰るのですか……?」
そこは見渡す限りの荒野。お世辞にも四大精霊の一体が居を構えるに相応しい場所とは思えない。
ラウロとドメニコが互いに視線を交え首をひねる中、アメンスィの手が荒れ果てた大地に触れた。
瞬間、小さな手が触れた大地を中心に、目に見えない暖かな波動が広がった。
「こ、これは……」
「なんだってんだ……」
目の前で変わっていく世界に、二人は言葉をなくす。
波動に撫でられた荒野から、ぽつり、またぽつりと新緑が芽吹いてくるのだ。
まるで時間を早送りしているのではないかと錯覚するほどに、新緑は加速度的に大地に広がっていく。
そして、ついにはここが荒野であったことさえ疑うほどの景色が誕生した。
『……遅くなりましたね。ただいま帰りました』
驚愕する二人の事など気にも留めず、アメンスィは新緑に埋め尽くされた大地に囁く。
すると、大地の一部が盛り上がり、そこから小さな塊が姿を現した。
『お帰りなさい、アメンスィ様。おせぇぞ、何百年待たせんだ!』
それは封神領域マグ・メルでハンター達が出会った、小さな砂人形だった。
勿論初対面である二人は、この丁寧なのか無礼なのか判別の付かない砂人形に面食らう。
『礫、息災で何よりです。他の者は?』
礫と呼ばれた無礼な砂人形に対し、アメンスィはヒトには向けることのない穏やかで慈愛に満ちた表情を向けた。
『すぐに参りますよ。みんな、おめぇに会ってやるってよ!』
そんな砂人形の言葉通り、緑芽吹いた大地が次々に隆起してくる。
地の大精霊アメンスィの顕現は、眷属の覚醒と共に、ヒトの眼にその眷属達の存在を感じることを許した。
今まですぐそばにありながら、互いを認知できなかった存在がハンター達の活躍により交わったのだ。
「こりゃすげぇもん見たな……この歳まで生きててよかったぜ」
「ああ……絶句するとはまさにこの事だ」
完全に蚊帳の外であるはずの二人でさえ、目の前の奇跡に感動することしかできない。
隆起した大地は様々な形へと姿を変えていく。
人の形をとる者、獣の形をとる者、植物の形をとる者、無形の者――様々な形の眷属が大地より現れアメンスィを囲んでいった。
『――ヒトの子らよ』
集まった眷属達に一通り挨拶を終えたのか、アメンスィはラウロとドメニコに向かうと。
『これでわかっていただけましたか? わたくし達に気遣いは無用です』
一人ではない。暗にそう言っているのだろうと二人にもわかる。
「し、しかし、貴女との対話は何処で行えば……」
『心配せずとも大地がそこにある限り、わたくしはあなた様方のすぐ傍に居ます。話など望めばいつでも叶いましょう』
そう言って、アメンスィは初めて笑みらしい笑みを浮かべたのだった。
?イクタサの場合?
ノアーラ・クンタウ要塞管理者のヴェルナー・ブロスフェスト(kz0032)は、部下を連れて森の中を歩いていた。
幻獣の森?
――否、ここは辺境地域でもパシュパティ砦の北。
ナナミ川を挟んで向かい側に、一夜にして森林地帯が出現したのだ。一時は歪虚の仕業かとも思われたが、周辺地域で歪虚の活動が活発化したという情報もなし。
部族会議で首長バタルトゥ・オイマトは、ヴェルナーに対して森林地帯の視察を打診してきた。
最近、部族会議の補佐役も担うヴェルナーは要塞管理者の執務を終えた後、森林地帯へ訪れた。報告書から入手した情報から『ある推測』を胸に――。。
「このような所に突然森が出現したと思ったら……そうですか、やはりあなたの仕業ですか」

ヴェルナー・ブロスフェスト

イクタサ
星の傷跡の地下――封神領域「マグ・メル」にてハンター達と対峙した精霊。
勇気を司る四大精霊の一人、イクタサであった。
「あ、早速来たんだ」
イクタサは、既に誰かがこの森を訪れているのを感じていたのだろう。
特段驚く事も様子も無い。
しかし、それは来訪者であるヴェルナーも同様であった。
「突然の来訪、失礼致します。私、ヴェルナーと申します」
「ふーん。その様子だと君はボクがここにいる事を分かってたみたいだね」
「一夜にして森林地帯が生まれるなんて芸当、相応の力が無ければできません。龍園の青龍でも実現は難しい。現在の状況でそれが可能な存在は自然と四大精霊のどなたか……という事になりますね」
笑顔を湛えながら、自らの考えを口にするヴェルナー。
イクタサはその笑顔の向こうに別の思考がある事を感じ取っていた。
何を考えているのかは不明だが、イクタサを警戒しているのだけは間違いない。
「そうだね。でも、それがどうしてボクだと思ったの? 他の四大精霊かもしれないじゃない」
「実は種明かしをしますと連合軍から情報をいただいていました。イクタサさんがこの辺境に向かった、と……」
ヴェルナーは、あっさりとネタ元を明かしてきた。
イクタサにも記憶がある。以前出会ったハンターが、クリムゾンウェストに存在する国々は連合軍を形成して歪虚と対峙していると話してくれた。
つまり、連合軍の中で一定の情報共有が為され、その中でイクタサの行く先も共有されていたのだろう。
「ところでイクタサさんは、何故この森を生み出されたのでしょう?」
「何故? ボクはここに引っ越してきたんだ。自分の家を丸ごとね」
首を傾げるイクタサ。
ヴェルナーは今立っている『シンタチャシ』と呼ばれる場所を見回すが、見えるのは小さな小屋が一つだけ。それ以外の家屋は存在しない。
だが、イクタサは現出させた森のすべてが家だと称している。
「なるほど。つまり、イクタサさんにとってこの森が自分の家という訳ですね。この森の木の実や川魚を捕まえて、一人で生活をしているという所でしょうか」
「そう。ボクの家だからね。何をしようとボクの自由だ。だから……君達は、言うなれば『不法侵入者』ってところかな」
イクタサは表情を変えず、敢えて強い言葉を用いた。
ヴェルナーの出方を見るためだった。
だが、ヴェルナーは頭を振ってイクタサの言葉を否定する。
「ふふ、聞いていたよりもあなたは冗談がお好きなようですね。もし、私がイクタサさんにとって邪魔者であればこの森の幻獣が襲ってきているでしょうし、風が吹いて行く手を塞いだでしょうね」
ヴェルナーは森を進む中でイクタサがこちらを敵視していないと知っていた。
もし、本当に敵視していたのであれば、ハンター達が先日夢で体験したように疑似幻獣が襲ってきているだろう。しかし、森を進んでもその様子は一切無い。
そういう意味ではイクタサがヴェルナーを敵視していない事は明白。
否、それどころか――。
「もっと言ってしまえば、イクタサさんは私に何か聞きたい事がおありなのではないでしょうか。そうでなければ、私の背を押す様な風が都合良く吹くとは思えません」
「…………」
やりにくい相手。
それがイクタサがヴェルナーに抱いた感情だった。
だが、それもイクタサには想定内。このクリムゾンウェストに姿を見せた以上、様々な人間と付き合わなければならない。
この程度でヘソを曲げては心が狭い相手と認識されかねない。
イクタサは、軽くため息をつくとヴェルナーに本題を切り出した。
「分かったよ。
ボクが知りたいのは、『あの子がいつここへ遊びに来てくれるのか』って事。できれば、早い内に都合を付けてくれるとありがたいんだけど」
「ふむ。素晴らしいね」

アズラエル・ドラゴネッティ

シャンカラ
丁寧に手入れをされた飛龍達が思い思いに身体を休めている中、最奥の一体を見つめて頷いた。
「お褒めにあずかり光栄の至りです」
その横で恐縮しているのが少数種族・龍人《ドラグーン》の1人。名をシャンカラという。
「いや、これだけ自分の龍を丁寧に扱う騎士はなかなかいないんじゃ無いか……うん。調子も良さそうだ」
龍人は龍よりも圧倒的に寿命が短い。
この過酷な環境がそうさせるのか、それとも無理矢理“青龍の血液を体内に取り込んだ”人種であるからなのかわからないが、長くとも50年程で皆寿命が尽きる。
戦いに身を置く龍騎士ともなるとさらに短命だ。
その為に一頭の飛龍を何人もの騎士が乗り継ぐことは珍しくない。
半年ほど前に先代の龍騎士隊長もまた若くして強欲竜との戦いの中で落命し、シャンカラは継いで龍騎士隊長に選ばれた若き龍人だった。
「だいぶ慣れたかい?」
「いえ……己の未熟さを痛感する毎日です」
白い髪が音も無く揺れ、アズラエルを見つめる碧い瞳からは謙遜などでは無く、真摯に自分の務めとその責任に立ち向かっているゆえの答えだと言う事が読み取れる。
「たしかハンター達との宴の日がもうすぐではなかったかな?」
「はい、どんなお話が聞けるか楽しみです」
ぱっと輝いたその表情は実年齢に近い若さを感じる。
「彼らはある意味戦いのプロだからね。色々話を聞くといいさ」
その瑞々しさに眩しそうに目を細めてアズラエルが笑いかけると、シャンカラも嬉しそうに頷き返した。
●

ナディア・ドラゴネッティ

ラヴィアン・リュー
「人聞きの悪い。全滅したなんて一言も言ってないだろう? ただ、絶望的に人口が少ないだけだよ」
ぷぅぷぅと唇を尖らせるナディア・ドラゴネッティ(kz0207)に、アズラエルが冷ややかな視線を送る。
龍人はただでさえ短命の一族であるのに、高いマテリアル適性や屈強な肉体から戦士である事も多い。
飛龍に騎乗して戦う事も多い彼らは“龍騎士隊”と呼ばれ、歪虚に包囲された龍園を守るため果敢に戦ったという。
だが歪虚の襲撃があるたびに龍達と共に戦いに赴くため、今となってはもう数百人しか存命しない人種となってしまっていた。
必然的に血は濃くなり少子化の一途を辿っている。滅びかけた彼らをアズラエルが意図的にハンターから隠していたのは事実だ。
2015年12月14日。ラヴィアン・リュー(kz0200)達転移者を発見し救ったのも龍騎士だったのだが、アズラエルはそこでも龍人の存在は伏せるようラヴィアンに依頼をしている。
また、先の龍奏作戦では龍人達は前に出てこないよう厳重に注意していた。
そうでなければ自分の命に無頓着な彼らはハンター達の熱意に流されてメイルストロムに挑みかかってしまうと危惧したからだ。
しかし、状況が変わった。
邪神を倒すには“全ての種”が手を取り合う必要がある。
龍人は短い人生を打ち込むように己を鍛え上げる。彼らは基本的に、誰もが優秀な戦士の素質を持つのだ。
「圧倒的に人口は少ないのに、まだこの龍園の外は負のマテリアルが満ちていて強欲竜どころか全眷属の歪虚が跋扈しているから、龍人にはこれの対処に当たって貰わなきゃいけなかったし」
「んー……まぁ、その点についてはもう少し連合軍を動かせれば良かったんじゃがなぁ……すまん」
蒼乱作戦において南方大陸に東方、西方海域に大渓谷と一気に片を付けようと動いた結果、龍園に向ける人材が足りなくなったことは否めない。
「だが、これらが一端落ち着いた今なら、こちらの問題にもうちょっとだけ積極的に動く事が出来るはずじゃし、龍人の負担を減らすことは出来ると思うんじゃ」

ワイバーン
「じゃから、青のワイバーンと龍人にも世界の為に協力を要請させて欲しいのじゃ」
ナディアの瞳を見つめ返し、アズラエルはわざとらしく大きな溜息を吐いてみせる。
「……今、龍人には限られた者にしか覚醒者となることを許可していない。こっちが止めないとやれ自分たちは守護者だの龍の眷属だのと言って、勇猛果敢に玉砕しかねないからね。……けれど、その枷を外せば協力したがる龍人は幾人か出るだろう。彼らは真面目だから」
だけれど、とアズラエルもまた飛龍を見る。
「龍人達は僕と同様世界を知らない。そしてハンター達も龍人を知らず、ワイバーンの事も分からないだろう? 龍奏作戦や蒼乱作戦もあったが、まずは互いのことを知るところから始めなくてはね」
「そうじゃの……まずは相互理解が大事じゃの……あ。忘れておった」
ぽん、と手を打つナディアにアズラエルが首を傾げた。
「……何を?」
嫌な予感を感じつつアズラエルが問う。

ハンターオフィス
「……なんだい、そのハンターオフィス? とやらは。ハンター達の勤め先かい?」
アズラエルの言葉に、ナディアが衝撃を受けて思わず仰け反った。
「お前……わしが何しに西方に行ったのか忘れたのか……!? もうそんなにボケが始まっちゃったのか……!?」
「ボケててもおかしくない年齢ではあるね。えーと、ハンターソサエティを作ったんだろ? それと何の関係があるのさ」
本当にわからない、という顔をしたアズラエルにナディアは口をぱくぱくとさせた後、机に突っ伏した。
「……何だよ、どうしたんだよ」
「……おぉぉ……まさかこのレベルの会話からリスタートせねばならんとは……」
ナディアの嘆きはそのまま大地に吸われ、消えていった。
それから小一時間かけてナディアは説明する。
オフィスを龍園内におかなければ、緊急時にハンターと連携をとることが困難だということ。
ハンターは今の龍園に市民権が存在しないため、駐留するためには宿などの整備も必要だということ。
ハンターズソサエティは今や国の垣根を超えた組織であり、その支部たるオフィスを配置するということは、政治的にも他国と足並みを揃える意味があるということ。
そもそも龍人のハンターなども今後は生まれるだろうし、そういった時のために龍園全体で「龍人がハンターになるための取り決め」を作る必要があること。
一通り説明した後のアズラエルの反応は、おおよそ想定内だった。
「人間社会って面倒だね」
「社会的ルールじゃから」
「ルールっていうのは、それがないと正しく生きられない弱い人類の考え方さ。龍にルールはない」
「おぬし一応、この国の法の番人じゃろ。自分全否定すんな」
閉鎖的な龍園の人々が、真に国際社会の一員となり、クリムゾンウェスト連合軍に参戦できるのか。
そのあたりの調整役として、ハンターの双肩には多大な期待が積み重ねられているのだ。
(文責:フロンティアワークス)

トマーゾ・アルキミア

ナディア・ドラゴネッティ
血盟作戦の後、世界各地に顕現するようになった精霊たちにまつわる事件を解決したハンター達から、見知らぬ結晶を回収したとの報告があがった。
それは恐らくマテリアル鉱石の一種と思われたが、非常に高濃度であること、そして魔導機械などに馴染まないことから、使い道について悩まれていた。
異世界転移でリアルブルーの崑崙にまで届けられたそれはトマーゾ・アルキミア(kz0214)により調査され、その結果が定例通信で行われているところだ。
『神に認められた証とでもいうべきかの。エバーグリーンでも、神は認めた存在に権能を授ける事があった』
「認められるのはよいのじゃが、何に使えばいいのかさっぱりわからぬぞ?」
クリムゾンウェスト側にいるナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の手にも、同じ結晶が乗せられている。
ナディアもある意味高位の覚醒者であり、その結晶に秘められた強い力を感じる事はできる。だが、エネルギー変換しようとすると、途端に不安定になってしまう。
『単刀直入に言うと、これは恐らく生物の持つ力を更に引き出すためのものと考えられる』
「なぜそんなことがわかる?」
『……先程言ったじゃろう。エバーグリーンでも、神は認めた者に力を授けた。厳密にはこいつは、力を授けるというより、ヒトの枷を外すためのものじゃろう』
「枷を外す……」
『そうじゃ。わしや貴様のようにな』
ナディアも薄々は感づいていた。この結晶がどのようなものなのか。更なる力を得るという事がどういうことなのか。
本来、ヒトの身で成し遂げられることなど程度が知れている。どれだけ優秀な覚醒者でもそれは同じこと。
あらゆる生物には限界というものがある。それを取り払ってしまえば、それはもう「違う生物」になってしまうだろう。
「わらわは青龍様と契約を結び、この不老の身を得た。じゃが……」
『貴様の生命維持は青龍に依存している。青龍が滅びれば貴様も死ぬということじゃな』
「気づいておったのか」
『珍しくもない話だ。ヒトとしての枷を外せば、別の枷をはめられる。貴様ら覚醒者が、クリムゾンウェストに囚われているようにな』
覚醒者になって力を手に入れた代償に、ハンターはこの世界で滅びに抗う運命を押し付けられた。
それでも邪神には勝てない。その認識を神とハンターが共有し、“新たな可能性を模索する”為に生み出された願いの欠片。
仮にその力でハンターが覚醒者の限界を超えた存在となれば、いずれは邪神にすら届く可能性はある。
だが、邪神に届くほどの超越者となってしまったハンターは、きっともう日常には帰れないだろう。
『不死の怪物になるか、血に囚われた守護者となるか……どちらにせよその末路は惨たらしいものだろうよ』
邪神ファナティックブラッドはそこまでしなければ勝てない相手だ。
勝利できなければ多くの世界が滅びるだろう。その犠牲に比べれば、ハンターの犠牲など些細な数かもしれない。
けれど、そんな風に割り切ることはできそうにもなかった。

「新たな側面……?」
『星石は可能性の結晶。そこにあるようで、実はどこにもない。本来あらゆる生物は無数の可能性を宿しておる。その可能性を因果律の海よりサルベージし、強制的に顕現させる』
例えるなら、それは精霊の実体化に近い。
精霊はこの世界に数多存在している。それこそどこにでもいるし、しかしどこにもいないものだ。
波長があった時、偶然実体化してヒトの目に触れ、交わることができる。
ハンターが契約を結んでいる精霊にも、実際には様々な可能性が眠っている。その姿形、力ではない可能性もある。
より深く、より広く可能性を広げ、その中にある力を強制的に顕現させる。可能性の扉を開く鍵こそ、精霊より授かりし星石なのだ。
『ハンターにはまだまだ強くなる可能性が眠っておる。わしも他にハンターを強化する方法を探しておこう』
定例通信はこうして途切れた。邪神に対抗できる可能性……これは吉報に間違いない。
だが、ナディアはどうしてもそれを明るいニュースとして語れる自信がなかった。
ハンターシステムの改修作業は急ピッチで進められることになった。
トマーゾから送られてきた設計図をベースに、ハンターズソサエティは各国技術機関にも協力を要請する。
星石は可能性の鍵であり、高濃度のマテリアル鉱石であり、星に眠る記憶の結晶でもある。
神霊樹の中で見てきた過去の世界の記憶。それも一部は星石として姿を変え、現実世界に顕現したと聞いている。
星石を集め、進化したハンターシステムを用いてハンターの枷を外し、新たな力を顕現させるのだ。
「なんじゃ。浮かない顔をしておるのう、ナディア」

タルヴィーン
「ハンターシステム改良の目途が立ったのじゃ。これで邪神にも対抗できるかもしれぬというのに」
「そりゃあ、たぶんハンターは新しい力ですって言えば喜んで手に入れようとするじゃろうけど……」
「それでは何か問題なのかのぅ?」
「あいつら全然自分の事考えてないからのう。こんな事を続ければ、いつかは人類辞める事になる。当たり前の日常に二度と帰れず、大切な者とは違う時間を生き、崇高な使命の為に命を落とす」
それでも、最期の瞬間まで彼らは諦めず、平然と命を投げ出すだろう。
そんな状況に追い込む世界の運命を呪うこともしないで、きっと喜んで死んでいくだろう。
数年前まで当たり前のヒトらしい営みの中にいたはずの彼らが、もうそこに帰れない。それが何よりナディアには辛かった。
「ハンターズソサエティのやっていることは……あまりにむごい」
「ふむ……そうじゃろうか? 彼らはただ、諦めていないだけだとわしは思う」
たっぷり蓄えた顎鬚をいじりながら、タルヴィーンはしみじみと呟く。
「命あるものは皆いずれ滅び、星に還る。その一瞬の中で、ただ絶望に慄くのではなく、光放ちたい。いや……光放つ為に生まれてくるのが命。彼らは光じゃ。わしはその可能性を信じてみたい」
「タルヴィーン……」
「たとえ彼らの物語がどんな結末を迎えようとも、もう目を逸らしたりはしない。わしはきっと、この物語を最後まで綴るために産まれたのじゃ。それが大精霊様の思し召しじゃよ」
血盟作戦を経て、タルヴィーンの態度は少し変わったように見えた。
これまではハンターと一線を引いた上で接していたが、今は彼らの熱烈なファンにでもなったかのようだ。
「……実際のところ、わらわの杞憂かもしれぬな。じゃが……わらわは忘れたくない。いつか彼らが怪物になったとしても、元々は他愛のないヒトだったのじゃと」
当たり前に生きて、当たり前に何かを愛し、守ろうとして戦った、どこにでもいる人類のひとりに過ぎなかったと。
「――きっと語り継ごう。どんな未来が待っていたとしても……わらわだけは、絶対に忘れたりしないから」

シャンカラ
「……シャンカラ」
深い溜息。まるで『何の用だ邪魔ださっさと帰れ』という文字が彫られているような渋面を見て、シャンカラは笑う。
「これはシャンカラ殿」
「オン殿、調子はどうですか?」
「いや、死ぬ前にこんな大事業に関わらせてもらえて、大工冥利に尽きますわ」
カラカラと明るく笑うその老いた龍人は右の太腿中程から下が消えている。
2人が産まれる前、若き龍騎士として最前線で闘う中で強欲竜に食われたのだと聞いていた。
それ以来建築を学び、この緩やかに滅び行く龍園の建物の修復や改築を引き受ける仕事に就いたのだと。
「あと3日もあれば外側の工事は終わります。内装はまぁ、そのあと2?3日あれば体裁は整うかと」
「それは素晴らしい」
「おい」
仏頂面が氷の刃のように鋭利な一言を発し、会話を打ち切る。
「あぁ、これはこれは、龍園のハンターオフィス代表のサヴィトゥール様ではありませんか」
わぁ、初めて気付いた! と言うように長いまつげをぱたぱたと瞬かせてシャンカラはサヴィトゥールを見た。
「……」
「うわぁ、すごいジト目。竜も殺せそうな凶悪な視線だね!」
「本当にそうだったらどんなにいいだろうな」
そう零すとサヴィトゥールは設計図の一点を指し示し、棟梁に指示を伝えると神官服の長い裾を翻して歩き始める。
その後ろをシャンカラはくっついて歩く。
「……何の用だ。隊長というのはそんなに暇なのか」
「そうじゃないけど、新しい施設が出来るなんて初めてだからワクワクするじゃないか」
「既にあるモノを使えるようリフォームするだけだろう」
「そうだとしても! 向こうのモノも少しずつ取り寄せていくんだろう? 楽しみじゃないか」
ヒトとして見れば外見は20代後半なのだが、実年齢はまだ18歳。シャンカラは好奇心の強いタイプでもあったのでこうやって瞳を輝かせているともっと幼く見える。
「そうか、それはよかったな」
そしてこのサヴィトゥールも外見こそ30手前のようだが、実年齢はシャンカラと同じく18歳。それでも(龍人の)大人顔負けの落ち着き払った態度はこの歳にして神官の要職に抜擢されただけある。
「ねぇ、今度……」
シャンカラの誘いは、通り向こうから聞こえてきた叫び声で遮られた。
2人は示し合わせることも無く同時に声の方向へと走る。
「何事だ?」
「どうし……あれ? バルゴー?」
「あぁ! 隊長!!」
走ってきたのは龍騎士隊の少年兵だった。
「強欲竜が! 結界に攻撃を!! 今、ダルマさんが対応に……!」
「わかった。場所は?」
少年兵が結界の最北を示すと、シャンカラは背に翼でも生えているのかと疑うほどの速さで走り出す。
置いて行かれたサヴィトゥールと少年兵はその背を呆気にとられて思わず見送る。
「……あの莫迦め……」
溜息混じりにサヴィトゥールが何事かぼやくと、「あの……」と少年兵がサヴィトゥールの袖を引いた。
「何だ?」
「あの、その強欲竜、ちょっと変だったんです。『ハンターを呼んでくれ、今すぐに』って言ってて……」
その言葉にサヴィトゥールの眉間のしわが一気に深く刻まれた。
「強欲竜がハンターを求めるだと……? どういうことだ」
鬼の形相となったサヴィトゥールの迫力に圧倒された少年兵は泣きそうになりながら、さらに詳しい状況説明を始めたのだった。
●
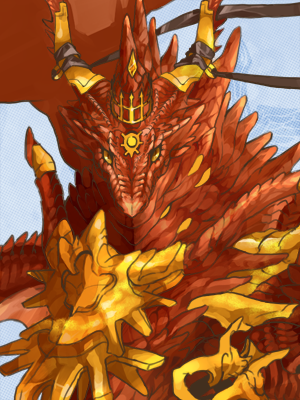
メイルストロム
メイルストロムの眷属にいた龍たちに待っていたのは、強欲の眷属への作り替えだった。
それを拒否した龍には強欲竜へと変わり果てたかつての仲間からの暴行と冷たい死が襲いかかった。
「我は北へと向かう」
そう言って旅立った王の後を追って、強欲へとその身を堕とした竜が群れを成し付き従った。
彼らは、仲間からの暴行を恐れたわけでも、死を恐れた訳でも無く。ただ、敬愛する王の傍にいたいという、願いゆえにその身を捧げていた。
恐ろしいことにメイルストロムの持つ力、技、魅力、その存在感はたとえ正から負に転じようとも何一つとして揺るぎなかった。
いや、むしろその全てが増幅されたようだった。
もちろん、義侠心から王を止めようと牙を向ける龍もいた。
だが、その尽くが王の圧倒的な力の前に屈し、星へと還っていった。
眼下に広がるのは虹色の海。
この南方大陸中を覆った高濃度マテリアルは大地を浄化しつくして、何も生まず何も育まない不毛の地とするだろう。
そしてまた世界の澱みすべてがマテリアル火山の地下へと集まり、定期的な浄化が行われなくなった南方大陸は瞬く間に負のマテリアルの温床となるだろう。
虹色の海に沈んでいく南方大陸。
あの光景を今でもエジュダハは覚えている。
第二次龍奏作戦で王が討たれた後も、強欲竜達はしぶとく龍園との交戦を続けていた。
特に、王と共に北方に渡った竜達は隙あらば王の仇を討とうと、個々が攻撃を仕掛けては龍人や連合軍とぶつかり、痛み分けで退く、という事を繰り返していたのだ。
そんなある日。
強欲竜にしか察することの出来ない集合命令を受け、エジュダハはその発信源へと向かった。
そうして北方へと渡ったエジュダハはその声の主を見て驚いた。
――ネフェルティ……!?
その全身は高濃度の負のマテリアルに晒され続けた結果腐り果て、かつての美しかった赤銅色の鱗はもう見る影も無い。
だが、見間違える訳も無い。龍である頃から共にいて、強欲竜となってからは南方大陸のゲートの守護竜として君臨していた竜だ。
その身が消滅する前に王の下へと行きたいと願い、双子竜をゲートの守護竜に据え置くと北へと飛び立っていった。
――まだ、生きていたのか。
エジュダハとしては再会を喜ぶよりも驚愕の方が大きかった。
『今こそ我ら強欲竜は王の願いを叶えるのだ』
『王の望んだセカイに作り替える』
『我らの王に勝利を』
『我らを裏切り、セカイを穢し蹂躙するヒトの支配から世界を取り戻せ』
『ヒトに荷担する青龍を討つのだ!』
恐らくもう記憶も混濁しているのだろう。吼え立てる声からはかつての知性の片鱗すら伺うことは出来ない。
それでも、かつて愛した王の嘆きを、ヒトから受けた仕打ちを、『星の守護者』としてあった過去を覚えているのだろう。
『ヒトにより穢されるくらいならば、星の守護者たる我々の手でセカイに終焉を』
恐らく、今残っている強欲竜の中で最も古く、そして最強であり最狂であり最凶なのがこのネフェルティだろうとエジュダハは直感する。
――あぁ、ダメだ。今の自分ではネフェルティを止める事は出来ない。
かつては強欲王の側近たるザッハークに近しい力を持っていたエジュダハも、黙示騎士マクスウェルとの闘いで深い傷を負った。
消滅することさえなかったものの、今のエジュダハの力はネフェルティに遠く及ばない。
ネフェルティの呼びかけに集まった強欲竜達は、熱に浮かされるようにその叫びに呼応する。
その数は優に100を越える。
エジュダハはそっと群れから離れると、一気に龍園へ向かって飛んだ。
ヒトに、強欲竜がこの龍園を破壊し、青龍が狙われていることを伝える為に。
かつての彼ならば、そんな発想に思い至ることはなかっただろう。
だが――南方大陸の戦いで遭遇した、彼らなら。
ハンターと呼ばれる境界を超える者たちならば、きっと……そんな希望を胸に、エジュダハは龍園を目指すのだった。

雨を告げる鳥

大伴 鈴太郎

天王寺茜

岩井崎 メル

ルベーノ・バルバライン

アシェ?ル

トマーゾ・アルキミア

ナディア・ドラゴネッティ
「私は考える。大伴鈴、焦る気持ちは分かるがそうしていても意味はない。じっと待つのが最善だ」
「分かってるけどよぉ……」
雨を告げる鳥(ka6258)がウロウロと歩き回っていた大伴 鈴太郎(ka6016)をそう注意した。
カスケードを見事討伐したハンター達に程なくして極秘の依頼が言い渡されていた。その内容とはとある場所の守護であったのだが……。
守護とは思えないほど鈴太郎がこうそわそわするのには理由があった。それは扉の向こうにあった。
「きっと上手く出来るよね」
「うん、『ししょー』としてこの事を任されたからにはやり遂げてみせるさ」
扉の中に居たのは天王寺茜(ka4080)と岩井崎 メル(ka0520)、そしてもう一人、今二人の目の前で静かに眠る少女、ルビーだった。
守護というのは方便だった。ハンターズソサエティからの依頼の本当の意味はルビーの修復だった。準備は全て整っていた。あとはトマーゾ教授からの指示に従って動くのみ。
「やるべきことはそんなに無いよ。今は目の前の事に集中しよう」
「そうです、ね……」
茜には一つ引っかかっていることがあった。ラプラスが言い残したトマーゾ教授の罪、それが何なのか。本人に聞く最大のチャンスだったのだが、とても言えるような状況ではなかった。
だったら仕方ない、またの機会に聞こう、そう気持ちを切り替えて二人は修復作業に向かう。
「鈴太郎、彼女達なら上手くやってくれる。安心して待とうではないか」
「オレはおまえの怪我の方が心配だよ」
鈴太郎と今会話をしていたのはルベーノ・バルバライン(ka6752)。エバーグリーンでの戦いで相当な無茶をした彼であったが、怪我の方はもう治っているようだった。
「俺達が行っても何もわからんし何もできん。こうしているのが一番だ」
その時、突然扉が開いた。
「ううう、上手く行ったのか?」
鈴太郎が今にも飛びかかりそうな勢いで前のめりになるのに、二人は扉の中を示してみせた。そこにはルビーが今だ静かに眠っていた。そしてモニターには大量の文字列が流れていく。
「再起動開始」
「完了」
「通信チェック OK」
「常時接続確認」
最後に一行の文字。
「インターフェース 起動開始」
そして少女はゆっくりと目を開いた。
「……皆さん、おはようございます。どうしたのですか?」
「ルビー!」
鈴太郎を始め皆が飛び込んでいく中、最後にアシェ?ル(ka2983)が入っていった。彼女にはやり逃していたことがあった。それを今から行う。やり方は聞いている。問題ない。
「……ルビーさん、アシェールです。よろしくお願いしますね!」
「アシェールさんですね、認証しました。こちらこそよろしくお願いします」
その言葉を聞いて彼女の顔はぱぁっと明るくなり、一人遅れてルビーに飛びついていた。
●嘘と誠
『……うむ。これで新たなハンターシステムも軌道に乗りそうじゃな』 ハンターズソサエティ本部に設置された、精霊と契約を結ぶためのサークル――即ちハンターシステムは、大きな改修の最中にあった。
各地に顕現し始めたイクシード・プライムと呼ばれる“星石”を用いてハンターを強化する為には、現行のハンターシステムでは限界がある。
故にトマーゾ・アルキミア(kz0214)のアドバイスを受けながら改修を行ったのだが、それはエバーグリーンのオートマトン技術にも通じていたのだ。
「この新ハンターシステムは、ハンターというボディに精霊の力を定着させるもの……つまりオートマトンと同じような理屈なのじゃろう?」
『ああ。本来精霊の力は不定形……それをヒトの形に押し込むことで、強制的にその力を引き出し、ハンターの能力を底上げする』
「それだけ聞くとめちゃめちゃ身体に悪そうなんじゃけど……」
『実際、並の生物では強制的な能力の開花に耐えられぬじゃろうな。しかし、世界との結びつきを強めた今のハンターならば可能じゃ。世界の修正力が貴様らを守る』
トマーゾは今のところ危険性があるならそう説明するし、無理と思うならそう言っていた。
故にナディア・ドラゴネッティ(kz0207)も彼には一定の信頼を置いている。だが……根本的な部分にはまだ疑念が残っていた。
「これでオートマトンの再起動も可能になった。ハンターが回収してきた義体に精霊をインストールし復活させた、クリムゾンウェスト製オートマトンの第一弾が稼働開始する。戦力はこれでまた増加するじゃろう……だが……本当に問題はないのか?」
オートマトンの再起動、そしてサブクラスシステムの実現の為に、トマーゾからは多くの知識を授かった。
その過程でエバーグリーンがどのような理由で滅んだのかも、おぼろげにわかってきた。
「教授が人間を信用しなかった理由も今ならわかる。エバーグリーンの人間がすべてを人任せにして滅んだのであれば、その絶望も理解できる。教授……お主は何の為に守護者となり、生き永らえた? 何故今もこうして戦い続けている?」
ナディアの問いに、トマーゾは腕を組む。いつも通り眉間に皺をよせ、そして答えた。
『贖罪、そして復讐じゃ。わしはエバーグリーンを滅ぼしたファナティックブラッドに……そしてその眷属に堕ちた……“狂気王”ベアトリクスを討つ為にすべてを費やしてきた。わしにとって貴様らやリアルブルーの連中は、復讐のための道具に過ぎん……そう思っていた』
眉尻を下げ、男は深く椅子に背を預ける。その視線の先に、既にナディアはいない。
『永遠の命を得たわしにとって、復讐だけが生きる意味じゃった。その為なら何を犠牲にしても構わなかった。なにせわしは、一度は世界を滅ぼした男なのじゃからな。既に良心などありはしない』
「それは嘘じゃな。教授……お主は結局のところ、復讐と自分を偽りながら、ハンターや人類に新たな答えを求めていたのではないか? そして人類は、これまでの戦いでおぬしの答えを示した。だからおぬしはルビーの復活に協力してくれたのじゃろう?」
『……オートマトン技術は、扱い方ひとつで世界を壊す忌むべき力じゃ。おぬしらがろくでなしであれば、ルビーの復活などさせるつもりはなかったさ』
だが、少しずつ気持ちが変わって行くのを感じていた。
ハンターの行動はやがて世界の垣根すら超え、歴史が示す未来予測すら超えた場所に辿り着こうとしている。
未だ見ぬ答えを示された時、その解が過去に自らが導き出した解と違ったのなら……。
『本当は……あの技術は。オートマトン技術は……あんなことの為に作ったわけではなかった。わしはただ知りたかった。神の想い……神の言葉……世界の真理。森羅万象を超えた、永遠の楽園を……』
きつく目を瞑り、そしてトマーゾは今一度、モニター越しにナディアと向き合う。
『今こそわしの罪を語ろう。その上で改めて貴様らに問う。――世界を救済し、神の理に抗う覚悟は十分か?』
「当然じゃ。必ず世界を救ってみせる。その為に出来ることがあるのなら、どんな場所でも、どんな敵が相手でも戦う。……あいつらは、そういう奴らじゃ」
『……そうじゃったな。ならば貴様らはもう一度赴かねばならない。滅びた世界、罪の果てたる都……。エバーグリーンの、セントラルへ』
●新たな仲間

アズラエル・ドラゴネッティ

ミリア・クロスフィールド

ルビー
元々予定としては組まれていたことで、準備も事前に進めていたのだが……。
北方尾国リグ・サンガマで生き残ったドラグーンの一部が、ハンターとしての登録を開始した。
そしてほぼ同時期、ハンターシステムの改良過程で組み込まれた新機能により、「世界」と契約し目覚めるオートマトンが増え始めた。
龍園にもハンターオフィスの支部が置かれることになり、募集が始まって応募が殺到したとか、エバーグリーンからオートマトン修復技術がもたらされ、パーツさえそろっていれば再起動がある程度容易になったとか、諸々の事情はあるが……。
「やあミリア、景気はどうだい?」
「ご覧の通り大盛況ですよ、アズラエルさん。まあ、盛況過ぎてバタバタしてますけど……」
アズラエル・ドラゴネッティの問いにミリア・クロスフィールド(kz0012)は苦笑で応じる。
なにせ、世間知らずだがやる気だけはバッチリのドラグーンが群れを成してやってきて、目覚めたばかりで状況がよくわかっていないオートマトンもウロウロしている。 どちらも世情に疎い種族だけあり、状況がわかっていない者たちには先輩ハンターの支援が必要そうだ。
「いや?、オートマトンっていうのはルビー以外見たことがなかったけど、こうしていると人間と変わらないね」
「大精霊の側から勝手にインストールしてきたりするので、起動個体数を正確にコントロールできないんですよね?」
「それはなんというか……大変だね……」
「ドラグーンの方は、サヴィトゥールさんが資料をまとめてくれているので、だいぶ楽なんですけど」
二人がそんなやりとりをしていると、一体のオートマトンが歩いてくる。
それは機械的なデザインの装備を身に纏ったルビー(kz0208)だった。
「ルビーさん! よかった、もうお身体の具合はよくなったんですか?」
「ミリアさん……はい、今のところコンディションは万全です」
「それは新装備かい?」
「トマーゾ教授が事前に崑崙より送り込んでくれていたそうです。現在の技術で再現された、高性能オートマトン用バトルドレスです」
スポーツカーを思わせる深紅の装束に身を包んだルビーを、アズラエルは神妙な面持ちで見つめる。
なんだかんだ言ってあの男もルビーを復活させる前提で話を進めていたということだ。
「君はこれからどうするんだい? もう一度、闘いに身を置くつもりなのか?」
「……わかりません。ただ、教授の話を聞いてから判断すべきと考えました。アズラエルさん、あなたもお呼びするよう言付かっています」
「教授が……? 君が目覚めた今、何を話すつもりなのやら」
顔を見合わせるミリアとアズラエル。男は頷き、ルビーの後に続く。
「いよいよ彼の昔話を聞ける時かな。尤も、きっと愉快な話ではないだろうけど」
独り言にルビーは応えない。ただ、ありのままを受け入れる心の準備だけを済ませる。
この先に待つのは、エバーグリーンの過ち……。
そして、この世界の未来を救うための必要な会議なのだから。





