ゲスト
(ka0000)
【血断】これまでの経緯
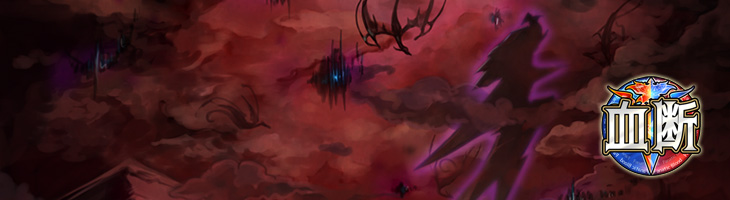


……邪神はこちらの都合などお構いなしですよね。
邪神はリアルブルーで凍結されたままですが、いずれは封印を解いて攻め込んでくるでしょう。
どうしたらあんな敵に勝てるのか……私には見当もつきません。
でも、ただ黙ってやられるのを待っているなんて、そんなのソサエティらしくないですよね。
全力で立ち向かいましょう。この世界の持てるすべての力を、ひとつに束ねて……!
更新情報(8月16日更新)
【血断】ストーリーノベル

トマーゾ・アルキミア

ファナティックブラッド

大精霊リアルブルー

タルヴィーン

ミリア・クロスフィールド

ベアトリクス・アルキミア

ナディア・ドラゴネッティ

ルビー

南雲雪子
空蒼作戦事後の混乱も徐々に収まり始めた頃、リゼリオのハンターズ・ソサエティ本部にて重要な作戦会議が行われた。
「――結論から言おう。邪神ファナティックブラッドが世界凍結結界を解除するまで、計算では残り半年程度と出た」
トマーゾ・アルキミア(kz0214)の言葉に会議場が静まり返る。
世界を喰い滅ぼす邪神ファナティックブラッドは、先の戦いで地球という惑星そのものを代償に封印された。
いずれは破られる想定ではあったが……あまりにも短すぎる。
「……僕の力不足か」
「いや、貴様はよくやっている。信仰が薄れた世界であれだけのことをやれる神はそうおらんじゃろう」
「慰めはいらないよ。それよりも今僕らが考えなければいけないのは、これからどうするかだ」
眉間に皺を作り、リアルブルー大精霊が呟く。
「ハンターズ・ソサエティの戦力はリアルブルー残存戦力との合流で強化されているはずだけど」
「いや……その上で尚、邪神は圧倒的じゃ。真正面からやり合ってアレを葬り去る可能性は、ライブラリの記録からも見つけられぬ」
タルヴィーン(kz0029)が髭を撫でながらため息交じりにぼやくと、ミリア・クロスフィールド(kz0012)が拳を握りしめた。
「トマーゾ教授……なんとか邪神の封印を維持できないでしょうか? 私達には、まだナディア総長が……大精霊の加護が戻っていません」
「封印維持は不可能じゃ。空蒼作戦は相当に念入りな準備の上で行われておる。アレ以上の時間稼ぎはない」
そう。最上位の封印、最高の時間稼ぎだからこそ、地球にまだ多くの人々を残してまで断行したのだ。
あれ以上の封印は、あれ以上の代償――犠牲を要求するに違いない。
「ベアトリクス。ナディアの様子はどうなのじゃ?」
「う?ん……正直、よくはないわねぇ。死んではいないけど、生きてもいないっていうか……」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)の言う通り、ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)は生死の境を彷徨い続けている。
大精霊を憑依させるという奇跡によりなんとか生存しているが、だからこそ危険な状態も続いている。
「急に目覚めるかもしれないし、もう二度と目覚めないかもしれないわ」
「そんな……」
「何度も言うけど、大精霊の力をあそこまで使いこなせる時点でとんでもない奇跡なの。たぶん目覚めたとしても、生物的には“人間”じゃないわね」
それは受け入れがたい現実だった。
ミリア・クロスフィールドは、ただのしがない受付嬢だ。特に肩書などないし、戦う力もない。
いつもハンターを見送るだけの自分を歯がゆく思っていた時、傍に居てくれたのがナディアだった。
総長と呼ぶにはいい加減でだらしない、ダメな大人ではあったが――今となっては替えの効かない、組織に欠かせない存在と言っていいだろう。
「ハンターの皆さんは、総長抜きで邪神と戦わなければならないんですか……?」
「そうなるわね」
「空蒼作戦の記録はライブラリにもあります。真の力を発揮した邪神翼を破壊するのに、空蒼作戦ではサルヴァトーレ級二隻と、大精霊二体の力が必要でした。今の状態で戦うのは不可能です! 下手をしたら、ハンターさんが全滅するだけですよ!?」
ミリアは立ち上がり、机を両手で叩く。
「これ以上、誰かが死んだりいなくなることを前提とした作戦には賛同できませんっ!」
「私も同じ気持ちですが……では、どうすればよいのでしょうか。戦っても勝てない相手に、犠牲もなしに勝利する方法があるのですか?」
ミリアを諭すようにルビー(kz0208)が語り掛けると、南雲雪子が落ち着いた様子で微笑む。
「ありますよ。戦争とは単に力の強さ、数の多さだけで決まるものではありませんから」
席を立ち、雪子は魔導コンソールに接続されたノートパソコンを操作する。
「ソサエティの皆さんが私達リアルブルー人の受け入れを進めてくださった間に、私達も邪神に勝つための方法を模索しました。それを簡単にご説明しましょう」
邪神ファナティックブラッドは、あと半年ほどで地球凍結結界を破り、活動を再開する。
だがそれまでは「封印された状態」にあり、すべての能力を万全に発揮することはできない。
「実際のところ、邪神は半年を待たずにクリムゾンウェストに侵攻してくるはずです」
邪神ファナティックブラッドとは、ひとつの大精霊を中心核とした一種の「世界」だ。
故に少しずつ身体の部位を切り取ったり、分身となる歪虚を繰り出すことができる。
「邪神はこれまでも、自らの世界から切り取った歪虚を送り込んできています。そもそも、半年を待たずとも、地球凍結結界の術者を殺してしまえば自由になれるのですから……尖兵を送り込んでくるはずです」
地球凍結結界の術者は二人いる。
ひとりはクリムゾンウェスト大精霊。そしてもう一人は、リアルブルー大精霊。
「クリムゾンウェスト大精霊はナディア総長と共に生命維持装置に繋がれていますから、狙いを絞りやすい。どちらか片方でも術者が機能しなくなればよいのですから、敵は間違いなくリゼリオを襲ってきます」
「そんな……ここが邪神との戦場になるんですか……!?」
「僕はマスティマを使って動き回れるからね。遅かれ早かれそういうことになる」
そうなれば当然、被害はリゼリオだけにとどまらないだろう。
西方諸国も邪神との闘いに巻き込まれ、甚大な被害を受ける。仮にそれで邪神に勝てたとしても、この世界は再起不能に陥る。
「……ごめんなさい。前提をお話したつもりだったのですが、絶望的に聞こえてしまったかしら」
雪子は眉尻を下げ、優しい声で語り掛ける。
「敵の動き方がわかっているのは、有難いことなんですよ。私達はただ、それに最高のカウンターを決めればいいのだから」
「敵がナディアを狙ってくるとわかっているのなら、ナディアを陽動に使えるということ。そしてここには、ナディアのふりをできる――世界を騙せる偽物がいるじゃないの♪」
ドヤ顔で胸を叩くベアトリクス。
彼女は血盟作戦でそうであったように、自分自身を大精霊だと「世界」に騙ることができる。
邪神が本能的に力を目指してくる存在であれば、ベアトリクスは十分ナディアを隠すことができるはずだ。
「そうすればまず、戦場をリゼリオではなくすことができるわぁ」
「戦いやすい場所におびき出して……待ち伏せするってことですか?」
「そうよ。邪神みたいな凄まじい歪虚が大暴れしても大丈夫な場所が、このクリムゾンウェストにはあるでしょう?」
「北荻――グラウンド・ゼロです」
雪子はパソコンを操作し、魔導ディスプレイに作戦図を浮かび上がらせる。
「まず、ベアトリクスの能力で世界を騙します。そしてクリムゾンウェスト大精霊として、グラウンド・ゼロに移動。ここで敵の先遣隊を迎撃します」
「迎撃するって、そんな……いつ来るかもわからないんですよね?」
「ああ、わからない。でも、わからないならこっちで決めてしまえばいい」
リアルブルー大精霊は腕を組み、力強く宣言する。
「僕(リアルブルー)から、邪神の一部を“強制転移”――こっちの世界に召喚してやるんだ」
そのコントロールが、彼とマスティマにならばできる。
「地球凍結結界で、邪神の力が大きく封じられている間がチャンスなんだ。あいつはできるだけ多くの戦力を送り込もうとするだろう。でも、僕はそれを許可しない。今のクリムゾンウェスト連合軍の戦力で倒しきれる分以外は、召喚を邪魔してやる」
完全に邪神の転移を阻止することはできない。だが、世界にはそもそも異世界を弾くという基本仕様が存在する。
ナディアに成りすましたベアトリクスとリアルブルー大精霊が協力すれば、十分現実的に可能な作戦だ。
「実はこれ、界冥作戦の時にもやっているんだ。火星クラスタをエバーグリーンに“招き”、“送る”ことで弾いただろう?」
「どうしても敵の襲撃を防げないなら、都合のいい状況に招き入れてしまえばいいと……」
相手がどんなに多数だろうが巨大だろうが、一度に戦う規模がこちらと同じかそれ以下ならば十分に渡り合える。
1対100で勝ち目がないというのなら、1対1を100回繰り返せばいい。ごく単純な解だ。
「いい機会だから、僕もハッキリ言っておく。ミリア、僕は……ナディアに託された君たちの命を、ただの一つも使い捨てるつもりはないよ」
「大精霊くん……」
「犠牲を出さないことは、きっと不可能だろう。それでも僕は、その現実から――理想から逃げない」
「私達みんな、同じ気持ちなんです。諦める為に戦うわけじゃない。勝って……これまでの犠牲に報いる為に、未来を掴む為に戦いましょう」
南雲芙蓉の言葉に仲間たちが頷く。
様々な世界の様々な種族が、様々な立場を超えて集まった。
これまでの旅路で手に入れたものがこれだ。
邪神討滅という一つの目的に向かって共に歩む仲間たちがいるなら――。
「……わかりました」
ナディアが目覚めるまで、彼女に代わってハンターに作戦を伝えるのはミリアの仕事だ。
「ハンターズ・ソサエティは、その作戦を承認します」
これが最善かどうかなんて、誰にもわからない。
それでも彼女のように信じよう。諦めないための理由を探して、何度でも戦おう。
当たり前じゃないか。だってこれは――世界を救うための戦いなのだから。
●

マクスウェル

クリュティエ

クドウ・マコト
破損した船を秘密裏に修復させ、黒く塗り変え名も「サルヴァトーレ・ネロ」と改めた船は、ニダヴェリールに代わる新たな黙示騎士の城として機能していた。
『それで、話とはなんなのだクリュティエ。わざわざ全員を集めるとは余程重要な事柄なのだろうな?』
鼻息荒く詰め寄るマクスウェルの背後には、黙示騎士らが一堂に会している。
シュレディンガーを欠いて、マクスウェル、ラプラス、イグノラビムス、テセウス、そして新たに加わったクドウ。
五人を前にクリュティエはゆっくりと語り始める。
「お前たちに話しておきたいことがある。邪神ファナティックブラッドの正体についてだ」
『……ぬ? 邪神の正体……?』
「クドウには触りだけ話したな?」
「ああ。別に俺が聞きたいと言ったわけじゃないが、あんたが勝手にな」
憎まれ口に笑みを浮かべるクリュティエ。マクスウェルは地団太を踏み。
『オイ! よくわからんが、重要なことなら先にオレたちに話すのが筋ってもんじゃないのか!? なぜこんなよくわからん新入りに先に話すのだ!』
「そうだな、すまなかった。なので、改めて今度は全員だ。ところでマクスウェルは、自分がいつから戦っているのか覚えているか?」
『そんなモノ覚えているわけないだろう。オレたち黙示騎士は永遠に戦い続ける歪虚だ。滅ぼした世界の数もいちいち覚えちゃいない』
「そうか。だが、他の者はどうかな?」
クリュティエに促され振り返るマクスウェルの目に留まったのは、やけに落ち着いた様子のイグノラビムスだ。
棺に封印されていなければ暴れまわるのがこの怪物の本性だと思っていたが、リアルブルーでの戦い以降は静かなものだ。
『……それを覚えているかどうかが、何だというのだ。もったいぶらずにさっさと言え!』
「単純な話だ。黙示騎士というのは、邪神という神にとっての“守護者”だ。その前提を説明するかどうかでな」
小さく息をつき、クリュティエはマクスウェルを指さす。
「マクスウェル。お前は本来のお前を取り戻すことで、格段に強くなるだろう」
『何ィ!? オマエ……それは本当なんだろうなァ!?』
「ああ。だからこれは、私達が勝利するために必要な話と考えてもらって構わない。少し長くなると思うが聞いてくれ。なぜ、我々が邪神に生み出されたのか。なぜ、邪神は異世界を滅ぼす神なのか……すべて説明しよう」
●
物語はいつか必ず終わる。それはこの宇宙の理だ。
終わりは常に唐突で、万人にとって納得のいく形であるとは限らない。
どんなに理不尽でも、どんなに馬鹿馬鹿しくても、どんなに中途半端でも……。
物語はそこに誕生した瞬間に、絶対的な終わりを約束されている。
これは摂理だ。しかしだからこそ矛盾する。
物語とは、幸福のためにあるのではなかったか?
誰かを救い、誰かを慰め、誰かに居場所を与えるためにそこにあったはずだ。
ならば問おう。なぜ、物語は――世界は終わる?
――有限だからだ。
有限こそが、物語の成り立ちを根本から矛盾させる。
終わらなければいい。単純で、誰にでも明快な答えだ。
だから終わらせないために、終わりを否定した。
必ず終わってしまう“生”よりも、永遠の“死”を肯定した。
人間だけが、その矛盾に気付ける。
あらゆる世界のあらゆる種の中で人間だけ、そこから派生する知性だけが許された。
ならばこれはきっと特別なこと。きっと成さねばならぬ宿業。
間違いじゃない。だってそれは、正しいから。
“正しい願いが、間違いであるはずがない”――当然だろう?
哀しみを砕き、理不尽に怒り、夢を見るのがヒトの美しさだ。
決して終わらせはしない。
“自分を終わらせないためならば、他の何かを終わらせてもいい”。
その願いを狂気と呼ぶのなら、きっとそれも正しいのだろう。
傲慢。暴食。嫉妬。強欲。憤怒。怠惰。好きなように揶揄すればよい。
紡いだその言葉こそ、お前の本質なのだと理解しろ。
さあ、繰り返そう。
何度でも何度でも。何度でも何度でも、何度でも何度でも何度でも何度でも――。
当たり前じゃないか。
だってこれは――世界を救うための戦いなのだから。
(文責:フロンティアワークス)
北荻――いや、クリムゾンウェストという世界は、西方諸国と東方などの一部地域を除いて、そのほぼ全土が闇に覆われている。
中でも特に被害が大きく、最早あらゆる生命が存在しなくなった鋼の荒野はグラウンド・ゼロと呼ばれていた。
いくら浄化キャンプを作ったところで、グランド・ゼロは汚染領域。非覚醒者が戦えるような世界ではない。
だが、大精霊や青龍の加護に守られたサルヴァトーレ級の内部なら、非覚醒者でも十分に動くことができる。
「この戦いが終わったら俺、改めて火星の開拓に参加しようかな」
サルヴァトーレ・ロッソのCAMハンガーで、クリストファー・マーティン(kz0019)が呟く。

クリストファー・マーティン

ラヴィアン・リュー
「ん? 何が?」
「このタイミングでそういうこと言うと未帰還になりそうじゃない」
ラヴィアン・リュー(kz0200)のコメントにクリストファーはからからと笑う。
「意外だなラヴィアン。ジンクスを信じるタイプだったか」
「ここまで来たらゲンくらい担ぐわよ。世界存亡の危機だもの」
「確かにな。なんとか邪神をやり過ごしてきたが、ここらが年貢の納め時らしい」
次の戦いにはサルヴァトーレ・ロッソ、サルヴァトーレ・ブルそれぞれから機甲部隊が参戦する。
非覚醒者のパイロットもいるが、CAMのコクピットとパイロットスーツに守られていれば、グラウンド・ゼロで戦えるだろう。
「宇宙という死の環境への対策が、異世界でも通用するというのは皮肉ね」
「ありがたいことじゃないか。しかし思うんだが、地球が俺たちの世界……リアルブルーの中心なら、火星はなんなんだろうな」
「そんなこと考える余裕もなかったけど、確かに宇宙って不思議ね」
星に意思があり、それが神と呼ばれるのなら、火星にも神はいるのだろうか。
「だからこの戦いが終わったら、俺……」
「それはもういいから」
●

篠原 神薙

ラキ
魔導アーマーやCAM、ゴーレムの力で急速に構築されていく防衛ラインを横目に、ラキ(kz0002)がカップ麺をすする。
「リアルブルーとかクリムゾンウェストに来る前にはどこかにいて、それでバリーンって宇宙空間を突き破って転移してきたんだよね? ってことは、リアルブルーとは違う宇宙にいたのかな?」
「確かに、邪神は元々どこにいたんだろうな。邪神専用の世界、みたいなものがあるのかもしれないけど」
篠原 神薙(kz0001)もカップ麺をすする。
「リアルブルーから消えた黙示騎士たちもそこいるはずだ。地球というか、リアルブルーという世界そのものが凍ってるんだからね。でも、どうして急にそんな話を?」
「う?ん。なんかね、結局あたしたちって邪神のことよくわかってないまま戦ってるような気がしてさ」
そもそも、なぜ邪神は襲ってくるのだろう?
それはわざわざ世界の壁を超えてまで達成しなければならない侵略なのだろうか?
「あたしもこれまで色々な経験してきたからわかるんだけどさ。これって多分、あたしたちには足りない視点があるんだよね。そもそもの考え方とか見方とか、捉え方みたいなのが足りてないっていうかさ」
「ほうほう。流石はラキ先輩、伊達に“わかんない”を連発してませんね」
「カ?ナギだって、転移してきたばっかりの頃、右も左もわかんなくてアレないだのコレが使えないだの、ぶつくさ言ってたくせに?」
そんな時期もあったが、それももう5年近く前の出来事だ。
思えば5年の歳月をかけても、結局邪神という存在については曖昧なところが大きい。
「ラキの言う通りかもしれないな。この見落としが、作戦に影響しなければいいんだけど」
歪虚はとどのつまり分かり合えない存在だ。
決定的に存在の成り立ちからして、生物と袂を分かっている。
故に議論の余地はなく。考察の必要は薄い。倒せばすべて解決する。少なくとも――今の段階では。
「トマーゾ教授にも、わからないことはあるんだね?」
――本当にそうだろうか?
わからないのなら調べていてもいい気がする。反影作戦でも、ダモクレス内部の調査は行われていた。
次の次の次の手まで予測して動いているあの男が、わからないことを「わからない」と済ませるだろうか。
ハンターが集めたデータは提出されて、神霊樹ライブラリとも照らし合わせつつ、検討されていたはずだ。
トマーゾが今更人類を裏切るようなことをするとは思えない。だから必然的に「調べてもわからなかった」のだと解釈していた。
(でも、伝えない理由は他にも考えられる)
ほとんど考えられない可能性ではあるが。
(伝えると――俺たちが不利になってしまう情報、とか)
●

マクスウェル

クリュティエ

クドウ・マコト
それがどんな世界だったのかも曖昧だが、確かに何かを終わらせた手ごたえだけがあった。
黙示騎士は邪神という「世界」の守護者だ。
故に敵を屠ることは、世界を守る事にも等しい。
彼はそう自覚するかどうかは別として、確かに「守るために戦う騎士」だったのだ。
「“戦うために戦う”者には限界がある」
クリュティエの言葉が脳裏を過る。
「手段と目的を違えてはいけないし、それを束ねてもいけない。戦いとは、どこかに至るための道標だ。それそのものを終着としてしまえば、可能性は閉じてしまう」
最近よく考えるのだ。ハンターと自分とは何が違うのか、と。
ハンターは弱いが、数が多い。あと、だんだん強くなるからむかつく。
それをクリュティエは「仲間と成長」という言葉で表現した。
何かを守るために戦う者。同じ目的の中で力を合わせ、仮に敗北しても学習する。
戦って勝ち負けを決めることは、彼らにとっては「手段」に過ぎない。だからそこに固執することも満足することもなく、次へ次へと意識を向ける。
それが最終的には新たな力、新たな戦術を生み出し、黙示騎士すら凌駕するのだ。
『オレにも必要だというのか……仲間と成長……いや、戦いの先にあるべき目的が』
サルヴァトーレ・ネロの展望室で宇宙を眺めながら悩んでいると、OF-004ことクドウ・マコトが自動ドアをくぐる。
「この広い船内で先客か」
『ムム……新入り。フン、ここは眺めがいいからな。瞑想に耽るには持ってこいなのだ』
「邪神の真実を知って、あんたも思うところがあるのか」
『いいや。真実などに興味はない。オレはただ、より強くなる方法を模索していたのよ』
腕を組み、その場にどっかりと胡坐をかくマクスウェル。ふと、その触覚がピクリと動いた。
『そういえばオマエ、雑魚だったのが突然強くなったそうじゃないか。何があったのだ?』
「別に俺は元々弱いし、今も弱いぞ」
『謙遜など、傲慢たるこのオレにとっては唾棄すべき愚行よ。戯言はいいからさっさと答えんか!』
肩をすくめ、クドウは宇宙に目を向ける。
「悪いが俺は本当に弱いんだよ。俺はあいつらみたいにはなれなかった。もし俺を強くするものがあるとすれば、それは怒りと憧れだろうな」
『ハァ?、下らんなぁ……下らん下らんッ。そんなもので強くなったというのなら、それは“最初から強かったが、それに気づいていなかった”んだろうよ。はい論破?』
実際、マクスウェルの言う通りだろう。強さは感情では変わらない。
ただし――眠っている強さを目覚めさせる引き金にはなるかもしれない。
「じゃあ、あんたはどうやってそこまで強くなった?」
『オレか? オレはだなぁ……ウウム、なんだったか。それが思い出せんのだ……』
クリュティエは、それを思い出せれば強くなれると言っていた。
だが考えても、真実を知っても、テセウスが「あ、一回叩いてみます!?」とやっても記憶は戻らなかった。
「過去を忘れられるのは羨ましいよ。俺は未だに、救えなかった人達のことを夢に見る」
『オマエ雑魚すぎるな。他人がなんだというのだ。オマエはオマエ、他人は他人だろう。救うとか救わないとか、そんな考え自体がズレているのだ』
「耳が痛いな。……それで、何か話してわかったか?」
『いやわからん』
そう言いながらも、マクスウェルの胸中には不思議な感覚があった。“懐かしさ”だ。
なんだかずっと前にもこんなことがあった気がする。
ずっとずっと、ずーっと昔に……同じように、誰かと……。
●

ファナティックブラッド
これは温度の低下による分子運動の停止ではなく、より上位の世界構造的な概念の凍結である。
つまり目に見えているしそこにあるけれど、ガッチリと固定されていて攻撃しても破壊できないし、マテリアルも吸収できない。
仮に邪神だけを凍結させ地球をそのままにしておいたなら、邪神は生きたマテリアルを少しずつ喰らってこの封印を早期に突破できたはずだ。
身動きが取れない状態でも、ファナティックブラッドは圧倒的な抵抗力で少しずつ自由を取り戻していく。
だが、全体を解放するには時間がかかる。それよりは部分的に力を取り戻し、侵攻を再開すべきだ。
七つあった邪神翼も今や残り三つとなった。
ベルフェゴール、マモン、アスモデウスが撃破され、古くに切り離したリヴァイアサンもどこかで果てた。
それでもなお、邪神にあるのは余力だけだ。
今、切り離された新たな邪神翼が、夥しい数の歪虚を伴って動き出す。
この結界を解除するには、結界の起点もしくは術者を破壊すればいい。
世界に穴を開け、尖兵を転移させる。
時は来た。嵐は世界の壁を越え、ついにクリムゾンウェストへと到達する――。
(文責:フロンティアワークス)

大精霊リアルブルー

クドウ・マコト

イグノラビムス
地上の戦況を見届け、口元を緩めながらリアルブルー大精霊が呟く。
「「ブレイズウィング!」」
クドウ・マコトとリアルブルー大精霊の声が重なり、二機のマスティマの羽が激突する。
互いに互いの剣を打ち払いながら急接近し、マテリアルの刃を交える。
「どうやらこの戦い、いくら続けたところで互角のようだな」
「らしいね。一応、神としては業腹なんだけど?」
「フ……。その言葉を慰めに今は引こう。戦いはまだ続くのだからな」
クドウの操る黒いマスティマが瞬時に消え去る。プライマルシフト――マスティマの転移能力だ。
「仲間の救出に行ったか……なんなんだろうな、あいつは」
歪虚のわりにはかなり人間くさいし、かといって人間と呼ぶには常軌を逸した強さだ。
「僕と互角とか……出会いが違えば、よっぽど強い守護者になったろうに」
感傷だと理解している。彼が何者であろうとも、あの憎悪は癒せるものではない。
頭をふり、マスティマを降下させる。
邪神翼ベルゼブルは撃破されたし、歪虚の侵入も停止したが、残留した大量の敵軍は未だ健在。後片付けが必要だ。
ブレイズウィングで歪虚の集団を薙ぎ払いながら低空飛行するマスティマ。瞬間、その前方にイグノラビムスの姿を捉えた。
すれ違いに警戒するリアルブルー。しかし、イグノラビムスは特に迎撃するでもなく、輝く碧光を見送った。
いつだったか、同じように光を仰ぎ見た。
今にも消えてしまいそうな微かな光。所詮、畜生の身では至る事のできぬ高み。
ああ――果てしなく遠い。
触れるべきではなかった。知るべきではなかった。
真に何も知らぬのなら、獣の性分に失意もなかったろうに。
「我ガ……カミ……」
流星のように吹き抜けるその翼に手を伸ばしながら、イグノラビムスは転移に消えた。
「あなたはやはり――美しい」
●
オペレーション・ブラッドアウト、その第一戦はハンターの勝利に終わった。
邪神の侵攻は一時的に停止。グラウンド・ゼロに開いていたヴォイドゲートも既に閉じ、後には激しい戦いの痕跡だけが残された。
今後も敵の転移攻撃を誘導するためにグラウンド・ゼロの防備は固めつつ、サルヴァトーレ級は補給のためにリゼリオへと帰還する。
無論、最前線とは転移門で繋がっており、いつでもハンターはグラウンド・ゼロに出撃可能な状態だ。

ドナテロ・バガニーニ

南雲雪子

トマーゾ・アルキミア

ミリア・クロスフィールド

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
ハンターズ・ソサエティ本部の作戦会議室で行われたデブリーフィングでは、ドナテロ・バガニーニ (kz0213)が渾身のガッツポーズを取っていた。
「これであと邪神翼は二つ! それも破壊してしまえば、大幅に邪神は弱体化するのである! 希望が見えてきたぞ!!」
「そうですね。正直、ハンター……特に一部の精鋭部隊の戦闘力は、リアルブルーの兵法の枠に収まらないレベルです。単一固体で戦況を打開してしまう……あれこそ無双の戦士ですね」
南雲雪子はそう絶賛しながらも、どこか浮かない様子だった。
「今はまだ彼らのお陰で時間が稼げています。しかし、今回のような騙し討ちは何度も通用しません。次回はグラウンド・ゼロ以外の場所に転移攻撃を仕掛けてくるはずです」
当然のことだ。敵は最短ルートで目的を達成しようとして、罠にかけられた。
ならば次は遠回りをする。多少非効率的だろうが時間がかかろうが、それを帳消しにして余りある物量があるのだから。
「それならばこちらにも考えがある。崑崙――リアルブルーの月を使って、“世界結界”を構築するつもりじゃ」
元々、リアルブルーにVOIDは直接転移できないようになっていた。それは、崑崙にある“世界樹”が地球の周囲をぐるぐると回りながら巨大な結界を構築していたからだ。
その為にトマーゾ・アルキミア(kz0214)は地球から月へと世界樹を移植していた。
「それをこちらでもやる。今のあやつ(リアルブルー)なら可能じゃ」
「トマーゾ教授、そこまで考えて月をわざわざ転移させたのであるか?」
「ン? 当然じゃろう。ただの居住空間として使うだけならコロニーの方が安上がりじゃった。わざわざハンターに守らせたのも、後々重要になるからだ」
つまり、ひとまずここまでは予定通り。
敵の次の一手に備える必要はあるが、ハンター的には一息つけるタイミングとなる。
「……でも、やっぱり今回の戦闘でも、大勢の負傷者や……死者が出てしまいましたね」
ミリア・クロスフィールド(kz0012)の発言は、作戦立案者らを責める意図ではない。
だが、彼女は見てしまった。ベルゼブルへ挑むハンターらに時間を作るため、多くのクリムゾンウェスト連合軍の兵士が犠牲になる姿を。
何十人、何百人という戦士たちがベルゼブルに命がけの戦いを挑み、“英雄”に道を繋いだ。
その犠牲がなければきっと彼らも間に合わなかったはずだ。
「犠牲の出ない戦いなんて綺麗事……わかっているんですけど」
張り裂けそうな心臓に手を当てて、ミリアは深く息を吐く。
「あと何回、こんな戦いを繰り返すんでしょうか。あと何回……ハンターさんは、あんな怪物と戦えばいいんでしょうか……」
「――勝つまで何度でも、だろう?」
凛とした声に視線が集まる。会議室の扉をくぐり、ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が微笑んでいた。
「ヴィルヘルミナさん……!」
「駆けつけるのが遅くなってすまない。オペレーション・ブラッドアウト、初戦は勝利で飾ったと聞いている。さすがは私のハンターたちだ」
「いや、あなたのではないような……」
ツッコミを無視して、ヴィルヘルミナは会議の席に加わる。
「ミリア・ライトフィールドからの要請に応じて参上した。これより我がゾンネンシュトラール帝国軍は、オペレーション・ブラッドアウトに全面的に協力させてもらう」
ウィンクする皇帝に思わずミリアは苦笑を浮かべる。
そう。ミリアはハンターを助けるため、各国に助力を要請していた。
元々クリムゾンウェスト連合軍はグラズヘイム王国、ゾンネンシュトラール帝国、自由都市同盟、辺境部族会議、エトファリカ連邦、北方王国リグ・サンガマそれぞれから援助を受けている。
それは物資であったり兵力であったりと様々。各国が抱えている問題、それぞれの歪虚との闘いを考えれば十分なものだ。
だが――邪神との闘いとなれば、それだけでは足りない。
この世界がなくなるかどうかという戦いの中で、これからはより各国に助力を求めていく必要があるだろう。
「幸い、我が帝国は自国内の問題は概ね解決している。四霊剣も撃滅が完了、残すは暴食王ハヴァマールだが――やつは黙示騎士と合流したことを確認している。ついでだ、追い詰めてこれも討ち取ってやろう」
「国内はもうほとんど安全だから、邪神との闘いに兵力を割ける……と?」
「万全とは言い難いが――元々、歪虚の撃滅と人類守護は我が国の国是だ。そのつもりで備え、そのつもりで鍛え、そのつもりで戦ってきた。是非もあるまい」
堂々と応じるヴィルヘルミナ。ミリアは……この人物が苦手だった。
この人は――きっと戦争が好きなんだ。だから東方にも、北荻にも、自ら先陣を切って駆けつけることができる。
部下が何人死んでも……仲間が苦しんでも……それを痛みとして捉えないから、戦い続けられるのだと。
そう思っていた。今日この日までは。
「私は己の生殺与奪の権を他人に明け渡したりはしない。この命は、この世界は、我が国の臣民は、誰もがそれを自らの意思で掴み、行使するべきだ。だから私は、ハンターだけに世界の責任を押し付けたりはしない」
苦しい戦いを経験したからだろうか。ミリアの目に彼女の横顔は少し違って見えた。
「まず、誰かが声を上げねばならない。誰かが痛みを恐れずに歩き出さねばならない。ならば私はその先頭を往こう。システィーナも、ラウロ議長も、オイマトの族長も、スメラギ帝も――必ず来てくれる。憎き歪虚王を倒し、国を一つにまとめてな。それまでの時間稼ぎ、喜んで引き受けようではないか」
単純な話だ。この人はただ、信じているんだ。人類を。この世界を。
みんなもそうだ。ドナテロ議長も、南雲艦長も、トマーゾ教授も、信じている。この世界を――彼らを。
(私は……情けないなぁ……)
仲間が大事だなんて、そんなの誰だって同じじゃないか。
辛くて苦しくて悲しくて、それでも戦っている。それ以外に何かを守る方法なんてないから。
目を閉じて、深呼吸を一つ。
「ヴィルヘルミナさん……よろしくお願いします。それから……来てくださって、ありがとうございます」
深く頭を下げたミリアにヴィルヘルミナは柔らかく笑いかけ、その震える肩をそっと叩いた。
●

マクスウェル

クリュティエ
負けるのに慣れたわけではない。ちゃんとハンターにはむかついている。だが――。
『あの邪神翼を撃破するとは、まったく大したものだ。ニンゲンの分際でつくづく侮れぬ奴よ……』
悔しさよりも称賛が勝っていることに、彼自身は気づいていない。
『やはり奴らを討ち取るのはこのオレ! 邪神翼では役不足ということだなァ! フハハハハハ!』
負けたのに上機嫌でサルヴァトーレ・ネロ内部を徘徊し、再びやってきた展望室で男は足を止めた。
そこには先客がいた。クリュティエだ。彼女は地べたに手足を着き、苦しげに肩を上下させている。
一瞬固まったのち、出ていこうか考え――しかし、男は頬を掻きながらクリュティエに歩み寄る。
『おいオマエ。そんなところに無様に這いつくばって何をしている』
ゆっくりと振り返ったクリュティエの顔色はよくない。その両目からは涙が溢れていた。
「マクウスェルか……? すまない、我に何か用だろうか?」
『いや、用というわけでは……』
涙を拭い、クリュティエはいつもの無愛想さで首を傾げる。
「ああ、そうだ。先の戦いでは援護が至らずにすまなかった。お前ひとりなら、もっとうまくやれたかもしれんな」
『フン、そんな事か。オマエがいようがいまいがオレの力に違いなどないわ。思い上がるんじゃない』
「そうか……ふふ、そうかもしれないな。ありがとう、マクスウェル」
――ありがとう、お兄ちゃん。
これは、誰の記憶だ?
――ありがとう……この世界を守ってくれて。
――お兄ちゃんなら、きっとこの宇宙を……ファナティックブラッドを守ってくれるって信じてる。
――わたし、ここでずっと待ってるね。この世界が終わって……また、みんなが生まれ変われたら……。
――今度は、お兄ちゃんを怒らせない……良い子に生まれ変わりたいな……。
「マクスウェル?」
ゆっくりと首を動かし、クリュティエを見る。
『なんでもない』
「そうか。お前もダメージを受けているんだ、ゆっくり休んでおけ。すぐに次の戦いが始まるからな」
そう言い残して歩き去るクリュティエに、背中を向けたままマクスウェルは問う。
『クリュティエ、聞かせてくれないか』
「なんだ?」
『オレは……オマエの……仲間、か?』
クリュティエは足を止め、優しく微笑んで。
「ああ、勿論だ。お前は我らの、大切な仲間だ」
そう答え去っていく足音に、マクスウェルは言いようのない虚しさを覚えた。
この世界の真実を知った時から……少しずつ、自分の中で何かが変わっていくのを感じていた。
けれど、その想いに向き合う勇気がなくて――。
いつもいつも、一番前を奔っていた。
ラプラスよりも、イグノラビムスよりも、シュレディンガーよりずっと前を。
誰よりも一番先に戦っていた。戦いが好きだから。力を示すのが好きだから。
でも、それだけじゃない。だんだん、自分だけでは勝てなくなってきて、気づいた。
“オレは――仲間が傷つくのを見たくないんだ”。
仲間を信じない男を見た。
人類を見放して、ひとりだけで戦い続けると決断した男を見た。
男はエバーグリーンという自分の世界を見捨ててまで、戦い続ける道を選んだ。
ああ、滑稽だ。なんて下らない。
“闘うために闘う”だなんて、そんなバカげた守護者があってたまるか。
前提を違えている。方策を誤っている。
だってそれじゃあ、ただの“破壊者”じゃないか。
でも……ああ、だからこそ……。
そんなバカが最後にどうなるのか。“オレと同じ”バカがどうなるのか、見届けたかった。
星の海を仰ぎ、男は拳を握りしめる。
記憶は戻らない。ただ、自分の中で見ないようにしてきた何かを見つけ、それを確かに掴んだ時。
『約束は守る。オレはもう――絶対に負けない』
(文責:フロンティアワークス)

トマーゾ・アルキミア

ミリア・クロスフィールド

タルヴィーン

ファナティックブラッド
トマーゾ・アルキミア(kz0214)がそのように説明したところで、クリムゾンウェスト人は首を傾げるばかりである。
なにせ、この世界では宇宙開拓が進んでいない。世界は天が回っているのか地が回っているのかすら検討されていないので。
「タルヴィーンさん、トマーゾ教授のお話わかりました?」
「わしはジジイじゃがパルム故、神霊樹ネットワークと繋がっておる。ハンターの見聞きした情報として理解しておるぞ」
ミリア・クロスフィールド(kz0012)も一応、タルヴィーン(kz0029)と同じく空蒼作戦の映像などは確認しているが、もうなんか規模がスゴくて理解は追いついていない。
「まあ……理解せんでもよいわ。要するに、邪神の転移攻撃から時間を稼ぐために、世界結界の強化が必要という話じゃ」
頬を掻きながらトマーゾは端末を操作する。
ソサエティ本部にある作戦会議室にて用意された最新式の魔導モニターが、クリムゾンウェストと二つの月を描き出した。
「ここまでのあらすじじゃが……まず、わしらは暴食天ベルゼブルの撃破に成功した。しかしこれは敵の攻撃をうまく誘導し、一斉迎撃による勝利であった」
邪神が考えなしにとにかく戦力を突っ込んできた結果、思い切り足元をすくわれてずっこけた初戦。
しかし、ならば次に邪神が送り込んでくる戦力は、目的達成の最短距離ではなくても、迎撃されない場所……グラウンド・ゼロ以外を狙ってくるはずだ。
「引き続きベアトリクスやルビーの力を借りて、なるべく敵の転移先をグラウンド・ゼロに強制させておるが、全ては無理じゃ。するとどうなるかというと、世界各地に無差別に邪神がシェオル型やらなにやらの強めの歪虚を送り込んでくることになるじゃろう」
クリムゾンウェストという世界は戦に優れているが、無関係な民間人は話が別だ。
シェオル型のような強力な歪虚が突然現れたなら、村一つ簡単に壊滅されてしまう。
「それをなるべく防ぐために、世界結界を強化する」
「はい先生! 世界結界ってなんですか!?」
「元々世界が持っている、“自分を正常な状態に保とうとする機構”……今回はその中でも異世界からの干渉をシャットアウトする機能を指す」
この「宇宙」にはたくさんの「世界」が同時に存在している。だが、世界と世界は本来直接的に交わることはない。
世界はそれぞれが独立しており、他所の干渉を許さないのが正常だ。今のクリムゾンウェストとリアルブルーの関係は、基準からするとかなり歪んでいる。
ともあれ、世界には元より異世界からの干渉を防ぐ力がある。だからこそ、邪神は簡単に異世界に入ることはできない。
特にその存在規模が大きければ大きいほど、世界は強く反発し、侵入を許さない。
これまでに邪神が腕だけで侵入しようと試みたり、分体でもある邪神翼だけを転移させたりしているのは、ファナティックブラッドという巨大すぎる存在を分割し、世界結界を潜り抜けるためだ。
「世界結界に穴を空ける事は、邪神ならば簡単にできる。だが、空けた穴に全身が入らんので、チマチマ雑魚とか送り込んで来とるわけだ。そしてこっちの世界を弱らせ、世界結界を無力化し、自ら転移してくることを最終目的としておるはずじゃ」
「世界結界が正常なら、リアルブルーにも邪神は侵入できなかったんですか?」
「ああ。しかし、リアルブルーはシュレディンガーの策略で世界結界が揺らいでおった。そして邪神を呼び込む為に邪神翼やイクシード・アプリを利用していたわけじゃ。終末を望む人類の総意が、邪神を呼んでしまったわけじゃな」
つまるところ、ざっくりまとめてしまえば、空蒼の戦いはひとえに「邪神を召喚させるか、させないか」というものだったわけだ。
「逆に言うと、世界結界を強固にして、人々が邪神に抗う意志を忘れず、大精霊と協力して、邪神翼の侵入も許さなければ……」
「ああ。この世界を守り切ることができるじゃろう」
「なんだかそう考えると思ったよりいけそうな感じがしますね!」
「いけるようにこれまで積み重ねてきたのだから、そりゃそうじゃろう」
「いや、教授が何を考えて作戦を立ててきたかとか、私には全然わからないのでっ!!」
閑話休題。
「そこで、世界結界の強化を行う。方法は二種類あり、ひとつは既に実行しておる」
冒頭で説明した通り、リアルブルーから転移させた第二の月、崑崙を用いた世界結界の強化だ。
崑崙にある「世界樹」と呼ばれるリアルブルー側の神霊樹とリゼリオの神霊樹を結びつつ、惑星を周回する「月」を媒体に二重の結界を展開している。
「これにより相当な数の歪虚の侵入を防げているはずじゃ」
「これがないとどうなるんです?」
「今頃リゼリオとかに10万体くらい歪虚が来てる」
「絶対維持しないとダメだということだけわかりました」
この崑崙の結界には弱点もある。崑崙地下の世界樹とそれを取り巻く機械装置が発動体であるため、これを破壊されると結界が消えてしまうのだ。
当然ながら邪神も崑崙への直接攻撃を狙ってくるだろうから、これからは空蒼作戦よろしく崑崙の防衛も意識する必要があるだろう。
「まあ、崑崙の防衛はさほど心配はしておらん。空蒼作戦残存戦力による防衛艦隊と、取り戻したニダヴェリールがあるからな」
ハンターの助力が必要な戦闘もあるだろうが、以前ほど絶望的な戦況ではない。
「もうひとつの結界強化方法として、神霊樹の分樹をクリムゾンウェスト各地に増やすという方法がある」
「蒼乱作戦の時にやったような感じ、ですよね?」
蒼乱作戦とは、北荻を目指す闇光作戦、そして龍との共闘関係を結ぶに至った龍奏作戦の次に行われた作戦だ。
クリムゾンウェストという世界が、実は異世界からの攻撃を受けていることが発覚し、世界各地にあるヴォイドゲートを探索、破壊するための冒険が繰り広げられた。
そこで行われた神霊樹の植林作業。これは、広がる戦場を転移門ネットワークで結ぶために、新たに神霊樹の設置が迫られたことに由来する。
神霊樹とは本物の木ではなく一種の幻影であり、精霊の中でも特にそれに特化したパルムだけが触れることができる。
そしてパルムは神霊樹を運び、それを新たな大地に植えたり、過去に機能停止に陥った神霊樹を再起動する能力を持っているのだ。
「世界結界は世界樹――神霊樹ネットワークに依存している。つまりこいつの網目を細かくすればするほど、効果は強くなるわけじゃな」
世界結界があって尚、歪虚はこのクリムゾンウェストに侵入してくるだろう。
つまり、そこには世界結界の穴が生まれているはずだ。穴は塞がない限り穴のままで、新たな歪虚を呼んでしまう。
「えっと……じゃあハンターさんには、事件が起きたらパルムを連れて行って、そこに神霊樹を植えて結界の補強をお願いすればいいんですね?」
「そういうことじゃな。パルムは神の眼……世界の観測者として特殊な権能を有するが、戦闘力はまったくのゼロなので、パルムだけで結界の穴埋めは不可能じゃろう」
「そうですよね……特にシェオル型と呼ばれている歪虚は、すごく強いそうですから」
会話の中でふと思い至り、ミリアは軽く問いかける。
「――そういえば。シェオル型って、どういう意味なんですか?」
その問いにトマーゾの眉が僅かに動いた。しかし、男はいつも通りの仏頂面を崩す事なく、あっけらかんと言い放った。
「調査中じゃ」
それ以上語る事は何もないと、拒絶するかのように。
●
ヒトを憎む理由など簡単だ。
知性がなければ理解できない。そして憎しみとは理解の先にある感情だ。
ならば、ヒトを憎めるのは同じヒトのみであると結論づけよう。
では、なぜヒトがヒトを憎むのか。それもやはり簡単なことだ。答えは同じく、ヒトだからである。
ヒトには美しい面も醜悪な面も均等に存在している。
どちらかに偏ったモノは、もうヒトではない。形を模倣しただけの別の何かだと断言しよう。
故にヒトは、何かを救うに至る程の善と、全てを台無しにしてしまうような悪を両立させ得る。
愛するからこそ憎み。憎らしいからこそ愛しい。それも道理だ。矛盾はない。
そう、だから――僅かでも善くあってほしいと願うことすら、ヒトならではの過ちである。
かつて世界があり、そこにおわす神と対話する者がいた。
ヒトではない。形だけの真似事で、中身は違っている。仮にそんな醜悪さを、救世主とでも呼ぶとする。
救世主は神と対話し、世界の真実を悟り、ヒトという存在の本質を知り、それを変えたいと願った。
その時点で既に命運は決していた。ヒトのそぶりを続けるくせにヒトを変えたいなど、不遜極まりない。
世界の運命が否定する。だから結局、そのようになる。
救世主は磔刑に処された。繰り返し何度も、磔刑に処された。
正しさを口にしても、善きことを願っても、ヒトの本質は決して耳を傾けない。
悪を有してこそヒトなのだ。当然のことだった。
それを「知らず、知り得ない」から、救世主は何度でも救おうとして、一様にヒトの手で焼かれた。
ならばそれは、既に「救世主という概念」に含まれた結末なのだろう。
誰かがそう思ったので、そのようになった。精霊とは、そういうものなのだから。
神に愛された容姿も、真実に至る知性も、それでもヒトを見捨てぬ慈愛の心も――。
反転すればただの獣になり果てる。
水瓶の中身をぶどう酒に変えようが、嵐を鎮めようが、病気を治そうが――。
ヒトの罪を赦すことだけはできない。
とどのつまり――憎しみは愛情の裏返しだ。
美しさを尊ぶからこそ、醜いものを赦せない。
ならばそれは正義だ。正しい怒りだ。
頼まれるまでもなく、燃え上がりたまえ。
誰かがそうあれかしと願った。ならば燃えよう。その身は蒼く、なお黒く。
お前こそが、怒りの日(Dies irae)なのだから。
(文責:フロンティアワークス)

ベアトリクス・アルキミア

ルビー
古代文明ではわずかながら交流もあったとされているこの世界は、邪神の襲撃により滅びの運命を辿った。
今や生物は絶滅し、わずかに残された惑星のマテリアルが枯渇するのを待つばかりである。
「そんな世界に鞭打って働かせようなんて、おじいちゃんも鬼よねぇ?」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)とルビー(kz0208)は、エバーグリーンの中枢都市にあたる「セントラル」を歩いていた。
グラウンド・ゼロとも大して変わらない乾いた砂の大地にそびえるこの機械都市に、二人以外の気配はなかった。 この都市は過去にハンターらも何度か訪れている。
そして狂気王ベアトリクスとの決戦の場にもなったので、都市の端には巨大な樹に支えられた火星クラスタの残骸が鎮座しているわけだ。
「もしかしたらまだ狂気クラスタの歪虚がいるかもと警戒していましたが、至って平穏ですね」
「ンフフ……たまたま遭遇してないだけでしょうけど、絶対数は確実に減ってるでしょうねぇ」
ベアトリクスは銃を撃つくらいしか対処できないが、ルビーの戦闘力はかなり高いので、護衛としても適任である。
「ルビーは、世界を滅ぼした後に歪虚がどうなるか知ってるかしら?」
「言われてみると……。黙示騎士のようなケースは例外でしょうし」
一部の高位歪虚は邪神と共に世界を渡り、また別の世界へと襲撃を仕掛けるのだろう。
だが、とるにたらない下級の歪虚は、その時どうなるのか?
実際のところ、このエバーグリーンにはまだ歪虚が残っている。
だがそれも、世界という概念が「無」へと還れば運命を共にすることになる。
「もうやることがなくなっちゃうとね、ポンと消えちゃうのよ?。邪神が連れてってくれることもあるけど」
「最終的には歪虚自体も無になる、ということですか」
「歪虚に寿命はないけど、永遠の存在ではないのよ。結局いつかは想いを遂げてしまうし、古い自分はどんどん消えてしまうから」
その口ぶりはどこか寂しげだった。
思えばこのベアトリクスという人物――オートマトンだが――も、過去とは随分変わっているのだと聞く。
ルビーもまた、自分自身が古代で眠りにつく前の自分と同一の存在であると言い切れる自信はなかった。
●
二人がセントラルにやってきたのは、この巨大な都市を再利用するためだ。
既に世界各地に邪神の眷属が侵攻しているが、ソサエティ側での世界結界の強化がうまく行っている限り、邪神翼のような戦力を送り込めるのは未だグラウンド・ゼロに限られる。
故に、対邪神翼戦力はグラウンド・ゼロに集結させておけばよい道理となる。
しかし、かの荒野に建造物といえばボロボロの遺跡のみ。とても軍事拠点をこれから作っている猶予などない。

トマーゾ・アルキミア
「セントラルのメインシステムはまだ生きていますね」
「以前おじいちゃんが来た時に、生きている機能については調査が済んでいるそうよ。言われた通りにやればいいから」
「さすがですね、トマーゾ教授は」
また来ることを前提に既にシステムは整理されていたので、トマーゾ本人が来るまでもない。
何よりも今必要なのは、大精霊の権限を行使できる存在、つまり神の器の機能を持つオートマトンだ。
「だいぶ都市全体にガタが来てるけど、地下部分は使えそうね。自動兵器もまだ格納されているわ」
「自動兵器を追加戦力として投入できれば、次の戦いでもきっと役立つはずです」
セントラルは戦闘機能を有する要塞都市だ。グラウンド・ゼロに要塞がないのなら、召喚してしまえばいい。
二人はその準備の為にこの地を訪れたのだ。
正直な話、クリムゾンウェスト連合軍には限界がある。
ベルゼブルとの闘いは乗り切れたが、負傷者多数。それもすぐに回復するとは限らない。
ゾンネンシュトラール帝国がその穴を埋める派兵を約束してくれたが、生身の人間を戦わせればコストはいくらでもかかってしまう。
「……でも、この子たちも少しかわいそうね。眠り続けて世界と共に無に還るよりはマシかしら??」
「私は自動兵器を哀れとは思いませんよ。少なくとも私は後悔していませんから」
ベアトリクスの言葉に、ルビーは笑顔を返す。
「私を目覚めさせてくれた人たちのお陰で、沢山の幸せを知りました。自動兵器にオートマトンのように考える心がなかったとしても、どんな道具だってちゃんと使われたい筈です。だってそれが、生まれてきた意味じゃないですか」
「あなたにそう言われると、反論の余地はないわねぇ」
「この世界にはまだ未回収のオートマトンボディもあるはずです。それらの回収も頑張りましょう!」
真っすぐに未来に向かって努力するルビーの姿勢を、ベアトリクスは眩しく感じていた。
ベアトリクスは他の神を騙る能力を持つが、あくまでもその存在はエバーグリーンに由来している。
この世界が完全に無に帰せば、当然ながらベアトリクスも消滅するしかない。そしてこの世界の消滅を止める手段は、ない。
(私もね、もうじゅ?????ぶん長生きしたから、後悔はないのよ)
ちらりと横目にルビーを見る。コンソールを操作する指先は生き生きと踊っていた。
(後継者っぽい子も、見つけられたしね)
クリムゾンウェストで再起動したオートマトンの中身は、クリムゾンウェストの精霊。つまり、エバーグリーンと心中する心配はない。
(そうやって何かを受け継いでいくことだって、オートマトンにはできるんじゃないかな。ね、ラプラス……)
●
世界はいつか終わる。それは邪神がいようがいまいが関係ない。
最初からそういう設計をされているのでそうなる。星のマテリアルはいつか枯渇する。
では――諦めるのか? それは仕方ないことだと、そういうものだから我慢するしかないと、諦めるのか?
“諦め”を超えて道理を覆すのがヒトだろう。ただ従うだけならそれは獣と変わらない。
絶対に諦めない不屈の心。ああ、誰にとっても美しく見えるはずだ。
だからみんなが憧れて、その光を追い求めた。
力を合わせて、大きな願いを叶えよう――それも美しく見えたはずだ。
ああ、きれいだ。とてもきれいで、大きな流れの中で、人間は――。

暗闇の中で、ぼんやりとした灯りが揺れている。
ランタンだ。ゆらゆら、ゆらゆら、小さな影を浮かび上がらせる。
「わたし思ったの。美しいものを美しいままに残すには、その瞬間に終わるのが一番いいんじゃないかって。想い出もいつかは消えちゃうけれど、それで価値が褪せるわけではないでしょ?」
「……道理だな」
低く、気だるげな男の声が、少女の声に応じた。
「喪失への恐怖……永遠への渇望……どちらも道理だ。だが……ならばなぜ、ヒトという異物は生まれたのか。私は未だ答えに到達していない」
「シュレディンガーも途中で諦めちゃったみたいだしね。クリュティエは、クリムゾンウェストと和解することで、その答えに近づけるかもって考えてるんだと思う」
「可能性はゼロではないな」
「お父様は可能性大好きマンだから、頭ごなしに否定はしない。でも、“信じてもいない”のでしょ?」
「お前はどうだ。我が娘、古き王……バニティー」
ランタンの動きが止まり、それを手にした少女の姿を映し出す。
ヒトではない。とうに生物の囲いから超越した存在だ。しかし、その微笑みに邪気はない。
「わたしもわからないわ。だから、少しクリュティエを手伝ってみようかなって」
「介入するのか、あの世界に」
「違うわ。わたしはもう戦わない。役割も王座もなく、今はただの案内人。だから、もしも彼らがそれを望むのなら、クリュティエと一緒に真実を伝えるだけ」
男は眉一つ動かさない。表情筋を動かす感情、その尽くが死滅している。
「それで戦争を回避できて、彼らも救われるのなら……ほら、一番いいでしょ? みんな本当は傷つけるのではなく、誰かに優しくしたいと願ってるんだから」
「私は傍観者だ。ファナティックブラッドの結末を含め、干渉するつもりはない」
「……ごめんね、お父様。少しの間ひとりぼっちにしてしまうけれど……どうか、辛抱してね」
光が消えたのは、ランタンと共に少女もこの闇から消え去った為だ。
そして残されたのは静寂。静寂……――静寂?
静寂だ。何も聞こえはしない。この状態こそもっとも静かなのだ。
落ち着いている。何百何全何万という、繰り返し響き渡る夥しい数の誰かの悲鳴。嘆き。憎悪の中、男はまるで彫像か何かのように、ただじっと座り込んでいる。
もうどれくらいの時間そうしているのだろう。数えるのはとうにやめているし、何も考えなくなった。
考えていたら、ここはうるさすぎる。だから心を殺して、身体を石に変えて、ただ傍観する。
見ろ。ここが――本物の地獄だ。
「“私には、何も救えない”。やり直すのだ……すべてを」
助けを求める怨嗟の声に答えるように、男はそう呟いた。
(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙
果てしなく広がるグラウンド・ゼロの荒野に今や聳える機械の要塞は、エバーグリーンから召喚されたセントラルと呼ばれる都市だったものだ。
ハンターらが召喚マーカーを用いて運んできた自動兵器群の修復や再起動も急ピッチで進められている。
「まさに一夜城だ。自動兵器のコントロールは、コマンダータイプでもあるルビーさんやベアトリクスさんがやってくれるそうだし、大幅な戦力増強に成功したわけだ」
ラキ(kz0002)と篠原 神薙(kz0001)だけではなく、多くのハンターが一様にセントラルを眺めていた。
後方のキャンプ地からでも十分にその雄姿は確認できる。これで包囲網は更に完璧に仕上がっていくだろう。
「でもさ、セントラルって前に邪神と戦って負けちゃったんだよね?」
「だね。セントラルの戦力だけで邪神をどうにかするのは無理だから、これも言ってしまえば気休めみたいなものだ。それでも、戦死者は随分減らせると思う」
グラウンド・ゼロの軍備は、前回のベルゼブル戦よりもさらに充実している。
ここが人類生存の最前線だ。邪神がここにしか大規模戦力を投入できない以上、ここさえ守り切れば勝機はある。
「勝てるのかなぁ……」
不安を隠せないのはラキだけではない。キャンプで休憩中の他のハンターも、どこか落ち着かない様子だった。
前回の戦いでもかなり抑えたとはいえ、相当な被害が出た。あと何度、あんな戦いを繰り返すのかもわからない。
「諦めるつもりはないんだけど、やっぱり怖いよね。なんか、今度こそひどい事になるんじゃないかって気がして」
「やめてよ……ラキの勘はけっこう当たるんだから」
漠然とした不安。だがそれはあながち的外れではない。
邪神とて無能ではないから、修正してくるだろう。前回と同じやり方では、この世界は落とせない。
「次の戦いまで一週間かあ」
邪神の襲撃は今のところコントロールできる。
世界結界を突破しようとする邪神の力を感知し、それが突破される前に、こちらの都合のいいタイミング――即ち軍備を整えたところで“召喚”して迎え撃つからだ。
ハンターズ・ソサエティは次の戦いを予告した。確実に訪れる戦いを。
オペレーション・ブラッドアウトの第二戦が始まろうとしていた。
●

クリュティエ

バニティー

イグノラビムス
サルヴァトーレ・ネロの通路で、クリュティエはひとりの少女を見かけた。
気配から察するに間違いなく歪虚だが、外見に凶悪さは感じられないし、なんなら武装すらしていない。
少女の名をバニティーという。
クリュティエとは以前から――つまり誕生した時から――の知り合いであった。
「クリュティエ! ふ・ふ・ふ……来ちゃった♪」
「歓迎はするが……イグノラビムスと話していたのか?」
視線の先にはもう一人、毛むくじゃらの歪虚が佇んでいる。
イグノラビムスは大人しくバニティーと向き合っていた。暴れる様子はないが、喋る気配もない。
「うん。久しぶりに会えたお友達だから、最近変わった事がないか聞いていたの」
「イグノラビムス……我には返事もくれないのに……」
「この子けっこうシャイだからじゃない? それか、君とは境遇が似てるからかもね」
ふいっと顔を逸らしたイグノラビムスは、のそのそと歩き去っていった。
「彼からだいたい聞いたけど、次が正念場なんだって?」
「イグノラビムスは作戦も理解していたのか」
「彼、ものすご?く頭いいのよ? ただ、頭よすぎるからって頼られるのも嫌なのよ。その結果死んじゃった英雄なわけだし」
「良い話を聞いたな」
バニティーは小さく息を吐き、クリュティエと向き合う。
「次の戦い、私も見物させてもらうね」
「お父様の指示か?」
「あの人は相変わらず毒電波と戦ってるからこっちに興味な?し。だから私は戦いには参加しない。ただ見ているだけだよ」
「見てどうするのだ」
「この世界が最後のピースなのかどうか、確かめるの」
その場でくるりとターンし、バニティーは窓に張り付くようにして星空を見つめる。
「ファナティックブラッドはまだ不完全だわ。その満たされない部分をクリムゾンウェストが埋めてくれるのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。どっちなのかわからないから」
「そうか」
腕を組み、クリュティエも窓の向こうを見やる。
漆黒の闇の中、無数の星々が煌めいていた。
「お父様ってアホだよね。こんなにたっくさんあるすべての光をひとつも余すところなく救いたいなんて、そんなの呆れちゃう。ひとつの命で無限の世界をどうにかしたいって、計算がデタラメだもの」
「そうだな」
「でも、子供みたいな夢を本気で追いかけすぎておかしくなっちゃってるところは……好きよ」
にっこりと笑い、バニティーは大きすぎる帽子を目深に被る。
少女を構成する部品の中で、その帽子だけが蛇足のように違和感を放っていた。
「マクスウェルには会って行かないのか?」
「うん。お兄ちゃんは私のことなんかわかんないだろうし……ね。それじゃ、一足お先に行ってるね?」
コツコツと、戦艦の廊下を少女の踵が何度か叩き、耳で音を追うまでもなく、その痕跡は消え去っていた。
「次で最後にしたいものだな」
クリュティエは別に、クリムゾンウェストを完膚なきまでに叩きのめしたいわけではなかった。
向こうが武器を捨ててくれるならそれでいい。でも彼らは力の差を思い知らせない限り何度でも立ち上がってしまうだろう。
暗澹とした気分だ。暴力は好かない。だが、この手段でしか意志を通せない。
「もう……立ち上がらないでくれ」
疲れたように呟く言葉は、広すぎる船内の静寂に呑まれて消えた。
(文責:フロンティアワークス)

南雲雪子

大精霊リアルブルー
南雲雪子の号令と共に、転移直後の歪虚へ四方八方から砲弾と魔法が降り注いだ。
オペレーション・ブラッドアウトの基本的な作戦は前回と変わらない。
歪虚の軍勢を一か所に召喚し、転移直後、動き出す前に最大火力でまとめて吹き飛ばす。
空に開いたヴォイドゲートからは敵が文字通り雪崩れてくるが、サルヴァトーレ級の砲撃もあって僅か数十秒で数え切れぬ程の敵が消滅した――だが。
「おかしいですね。邪神翼が現れない……?」
邪神翼により世界結界への圧迫を感じ、放置すればどこに出るかわからないからこちらから門を開いている。
本来であれば前回のように、1分も経たずに邪神翼が出現する目算のはずだ。
「これ以上門を開き続ける意味はありませんね。一度ゲートを閉じ、出現した敵を叩く作戦に切り替えます。リアルブルー、出来ますか?」
『そう思ってさっきからやってるんだけど……! まずい、ゲートが閉じない! 感覚的な話で申し訳ないけど、何か詰まってる感じだ!』
サルヴァトーレ・ブルの艦橋にマスティマからの通信が響く。
「確かにヴォイドゲートから感知されているマテリアルエネルギーは、前回のベルゼブルと比較しても二倍以上の規模があります……これが原因では?」
オペレーターの声に雪子は逡巡する。
「リアルブルー、とにかくここは一度ゲートを閉じることに専念して――」
「……待ってください! 強力な転移現象を確認! 邪神翼です!」
邪神翼が現れる瞬間に、大精霊リアルブルーは空中で交戦しながら立ち会うことになった。
目に見えて世界を引き裂く空の亀裂から、暗い光が溢れだす。
そして飛び出してきたのはソードオブジェクト――文字通り剣の形状を取った邪神の翼であった。
飛来する巨大な影をマスティマで受け止めようとするも、負のマテリアルを噴射して突き進む剣を抑えきれない。
「こいつ……っ!! 雪子、地上部隊を下がらせてくれっ!! 僕でも止められない!」
そう口にしたものの、撤退が間に合わないことなど百も承知。
故にリアルブルーは咄嗟にマスティマの翼、ブレイズウウィングによる一斉攻撃と共に、刀身を蹴り飛ばして射角をずらした。
「ダメだ! 逃げろ! 逃げてくれっ!!」
流星は地上部隊の中心には墜落しなかったが――。
「おいおい……落ちてくるぞ!? 他の歪虚はお構いなしか!?」
「逃げろ! 巻き込まれる!」
「いやっ、逃げるってどこに――」
大質量の物体が空気の壁を突き破り、びりびりと激しく大気をかき乱す。
剣は地上に突き刺さり、その衝撃は炎となって爆ぜた。
「ソードオブジェクト墜落! 本隊に被害はありませんが、防衛陣地に直撃しました! 部隊との連絡、途絶!」
「……残念ですが、あれでは救援は無意味です。それよりも包囲を強めてください」
「邪神翼、“天型”への形態変化を確認……したのですが、艦長っ! 敵は二体です! 二体の邪神翼が、融合しています!」
燃え盛る爆心地に刺さった翼はちょうどその真ん中で二つに別れ、そして姿形を変貌させる。
ほぼ同一の外見の、左右対称の歪虚――。
「世界結界を突破するために、ひとつになっていたわけですか」
残りの邪神翼は確かにあと二体。だからそのどちらかが来ると備えていた。
二体同時に転移するというのは、反応を同一にしなければ不可能なはずだった。
文字通り、“一つにならなければ抜けられない”。だから、そのようにしたのだろう。
「そこまで頭が回る……いえ、敵側にも司令官がいるのですね」
二体の邪神翼は共に戦うのではなく、それぞれ別方向に向かって移動を開始する。
「まずいですね……敵はグラウンド・ゼロの突破を目的としています! ここで仕留めなければ、邪神翼はゲートとしての能力を使用して、邪神本体を呼び寄せます! 絶対に二体ともここで倒さなければ……!」
「しかし、戦力を分散させることになります! それに邪神翼以外の通常戦力の数も前回の二倍近くあります!」
「わかっています。邪神翼以外の敵はある程度無視して構いません。全滅を避ける為、防衛戦力はセントラルまで撤退、代わりに自動兵器を前面に。これで少し時間が稼げるはずです。逃走する二体の邪神翼は、精鋭部隊による追撃を」
オペレーターたちの顔色が悪い。雪子の指示を理解しているからだ。

ダニエル・ラーゲンベック

クリュティエ

マクスウェル
セントラルに行っても圧倒的戦力差にさらされるし、邪神翼と戦うにはそもそも突破が必要で、敵軍の中で孤立した状態のまま邪神翼と戦うということ。
ほとんど――死んでこいと言っているようなものだ。
「何人失ったとしても……邪神翼をここで抑えなければ敵の増援が今度は人の暮らしている土地に流れ込みます。邪神翼の撃破は絶対目標です」
『話は理解してる。邪神翼の追撃はサルヴァトーレ級二機でやりゃいいんだろ』
ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は通信を入れつつ、既にロッソを追撃に向けていた。
「前回は鮮やかなものだったが、こうなれば脆い」
遅れて悠々と転移したサルヴァトーレ・ネロの甲板に立ち、クリュティエは目を細める。
「いかに優れた作戦も、圧倒的物量の前では無意味だ。何も考えずただ戦力を叩きつける……それが我々にとって最高の戦略なのだからな」
『連中、前回通り邪神翼を討つつもりだぞ。精鋭はあっちに向かっている……オレたちも向かうか?』
マクスウェルの問いにクリュティエは首を横に振る。
「その必要はない。我々はこのまま、精鋭以外の戦力をすべて叩き潰す」
邪神翼をどうにかできる戦力は限られている。
クリムゾンウェストの防衛戦力でも特記して優れた者たちを片っ端からぶつける以外、方法がない。
「だが……いかに彼らが強かろうと、補給線も援軍もなければ孤立する。帰る場所がなければ、もう二度と立ち上がれなくなる」
『邪神翼を落とされてもか?』
「邪神翼を失ったとしても、彼らの戦意を削ぐ方が優先だ。お前たちは孤立した敵軍をすべて撃破してくれ」
『雑魚の相手は不服だが……いいだろう、引き受けた』
テセウスの能力で黙示騎士は戦場のあちこちに散った。
実際問題、黙示騎士を止められるのはハンターの精鋭だけ。だが、その精鋭は不在――間違いなく甚大な被害が出る。
(それでも引き返せまい? 邪神翼を倒せねば、もっと多くの人間が死ぬのだから)
今目の前で死んでいく人間の数よりも、これから死ぬことになる人間の数が多くなる時――お前たちは“選択”すらできない。
ただ機械的に簡単な足し算引き算をして、その数字として命を弾くしかないのだ。
そんな苦しみを味わわせたくはなかったが――。
(我も同じだ。我もより多くを救うために、今目の前の犠牲に目を瞑ろう。これが、我の覚悟だ)
上空に転移し、そして落下したイグノラビムスはオート・パラディンの頭部を爪で貫いた。

イグノラビムス
何故だ?
何故人は、そうまでして生き延びようとする?
人類は簡単に世界の摂理を破壊する。より良い未来を目指していると言えば聞こえはいいが、人は必ずそれ以外の何かを蔑ろにする。
あの時もそうだった。ヒトは神の――大精霊の存在を理解しようともせず、自分たちを抹殺した。
怒り。怒り。怒り。
怒りがイグノラビムスの身体を内側から蝕んでいく。
憎悪の炎はその体毛を黒く染め上げ、憤怒の念は咆哮となって劈いた。
(もういい。そうまでして生き残るべきではない。ヒトは既に行き詰った。結論から目をそらしてはならない。過去から逃げてはならない。希望に縋ってはならない)
燃え盛る炎は、分かたれるのではなく。
膨らみ爆ぜてうねるように、大きくなっていく。
四つ足の、掛け値なしの獣。イグノラビムスは闇を纏って地を蹴った。
(人類は存続してはならない。これは――“世界の願い”だ)
我は救世主にあらず。我は獣なり。
憎悪より来たりて、報復する者なり。
神の敵を喰らいて吼える、黙示録の獣なり。
我こそは、真なる星の守護者なり――!
物量作戦の前に劣勢に追いやられる連合軍。
しかし、何も受け身のまま黙って流れの転換期を待っている訳ではない。

森山恭子

ジェイミー・ドリスキル
「見つけたザマスね!」
ラズモネ・シャングリラのブリッジにオペレーターの報告。
艦長の森山恭子(kz0216)にも気合いが入る。
各地で歪虚と黙示騎士へ対抗する裏で、対異世界支援部隊『スワローテイル』旗艦のラズモネ・シャングリラはサルヴァトーレ・ロッソへの攻撃命令が下っていた。
「各地からの状況報告は?」
「既に各地で黙示騎士が目撃されています。敵の指揮官級が出払っていると思われます」
サルヴァトーレ・ネロを根城としている黙示騎士達が他の戦場へ転移しているとなれば、眼前のサルヴァトーレ・ネロに障害となる敵はいない――この絶好の機会を逃す手はない。
「主砲発射用意ザマス。目標、サルヴァトーレ・ネロ。先手を打ってこっちから攻撃を仕掛けるザマス!」
恭子の指示で砲撃手がサルヴァトーレ・ネロへ照準を合わせる。
砲身がサルヴァトーレ・ネロへと向けられる。
「艦長、主砲発射準備完了です」
「撃つザマス!」
大きな発射音が響き、主砲のビームがサルヴァトーレ・ネロへと放たれる。
だが、サルヴァトーレ・ネロへ到達する寸前でビームはバリアへ阻まれてしまう。
「……なっ!」
「やっぱりな。敵が何もしねぇ訳ねぇよな。万全の備えって奴かよ」
ラズモネ・シャングリラの甲板で戦車型CAM『ヨルズ』に乗るジェイミー・ドリスキル中尉(kz0231)は吐き捨てるように言い放つ。
黙示騎士不在であっても、簡単に落とせる相手ではない。
更にラズモネ・シャングリラへ不幸が訪れる――。

ブラッドリー
「友軍……じゃないザマスね」
もし連合軍の機体であれば事前に通信を入れるはずだ。
だが、その様子はまったくない。
だとすれば、それは高確率で敵側の戦力という事になる。
「機体確認……白いマスティマです」
「ぬわぁーーんってこったザマス! ここでエンジェルダストザマスか!?」
エンジェルダスト。
白いマスティマタイプの機体であり、今まで二回ハンターと交戦している。
そして、そこに搭乗するのは歪虚ブラッドリー(kz0252)である。
「弁えなさい。神の御前でそのような蛮行。神の御遣い達の家、破壊させる訳にはいきません」
「……くっ。声はイケメンザマスのに」
「バアさん、奴は俺が押さえる。サルヴァトーレ・ネロへの攻撃を継続するようハンターへ指示を出すんだ。おそらく敵はこれから反撃に出るぞ」
通信へ割り込む山岳猟団の八重樫 敦。
先日、エンジェルダストから大きな傷を負わされたばかりなのだが……。
「分かったザマス。でも、体は大丈夫ザマスか?」
「やるしかないだろう。……八重樫、出るぞ」
カタパルトから射出される八重樫のR7エクスシア。
その様子を窺いながら、エンジェルダストはラズモネ・シャングリラをあざ笑う。
「抗う事を選びますか。よろしい。では、新しい道を選び取るよう導きましょう。あなた方は示された道をただ進めばいい。それが……楽園へと続く道……ですから」
ブラッドリーの声にノイズが入り始める。
エンジェルダストの通信妨害が、ハンター達を孤立させていく。
ラズモネ・シャングリラとサルヴァトーレ・ネロ。
艦隊戦が、間もなく始まろうとしていた。
(文責:フロンティアワークス)

ラキ

篠原 神薙

ヴィルヘルミナ・ウランゲル
「ヴォイドゲートが閉じてもまだ敵が残留してるんだ! とにかく負傷者を連れてセントラルまで撤退しよう!」
ラキ(kz0002)と篠原 神薙(kz0001)は未だグラウンド・ゼロの戦場にいた。
遠くで邪神翼が撃破されたらしいことはなんとなくわかったが、戦闘は終わる気配もない。
クリムゾンウェスト連合軍は、大量の敵戦力と黙示騎士により完全に分断され、右も左もわからぬ混戦状態にあった。
「このシェオル型ってやつ、一匹でも強いのにこんなにウジャウジャいるんじゃキリないよ!」
「いやほんと、闇光作戦を思い出すな……!」
遮二無二突進するシェオル型を神薙は無数の剣を操作して切りつけるが、怯む気配すらない。
自分の命を惜しまずに敵の抹殺を優先する――そんな歪虚が大量に押し寄せてきたら、被害が広がって当然だろう。
「少年、こっちだ!」
大剣で歪虚を両断しながらヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が叫ぶ。
帝国軍の部隊が残存戦力の救援に来たのだ。
「ヴィルヘルミナさん、まだ戦場にいたんですか!?」
「うむ。いやあ、兵を残して将が退くのはどうしても好かなくてな」
「前に一回それで皆さんにご迷惑をおかけしてませんでしたっけ?」
ラキのつっこみを聞き流しながら、ヴィルヘルミナは地べたに倒れた負傷者を担ぎ上げる。
「部隊の連携も指揮系統もあったものではないな。物量もあるが、意識してこちらの集団性を潰しに来ている……嫌な敵と当たったな」
「どれくらいやられたんでしょうか」
「今その話はしない方がいい。セントラルまで走る気力が失われる」
ヴィルヘルミナの返答に思わず神薙の表情がこわばる。
わかっていた。口に出すのも憚られるほどの壊滅的打撃だと。
「とにかく走ることだけ考えるんだ。走って走って生き残れ。今はそれで充分だよ」
●

南雲雪子

大精霊リアルブルー

ベアトリクス・アルキミア
まだ活動可能なハンターの精鋭らと共にグラウンド・ゼロのあちこちに降り立ち、友軍を救出していった。
セントラルはなんとか守り抜かれたが戦闘はいつまでも終わらず、孤立してしまった部隊の安否は不明なまま。
全軍の被害状況がおおよそ明らかになったのは、邪神翼撃破から三日が経過してからだった。
「辛勝、ですね」
南雲雪子が呟く。
今だ救出や戦闘が続いているが、サルヴァトーレ級の全力運用には補給も必要となる。
前線に出ているサルヴァトーレ・ロッソに役割を託し、臨時の病院として停泊したサルヴァトーレ・ブルの会議室は、重苦しい空気に包まれていた。
「邪神翼は撃破。セントラルも残っていますから、持ち堪える事はできるでしょう。しかし、友軍戦力をあまりにも失い過ぎました」
「……すまない雪子。僕がもっとちゃんとしていれば……」
「大精霊くんはちゃんとやってくれましたよ。私の作戦が甘かったのです」
大精霊リアルブルーを載せたマスティマも連戦に次ぐ連戦で修理が必要だ。
「ハンターもあの状況で良く邪神翼を倒してくれたわぁ。安全に人が暮らす領域が破壊されるより、死傷者は圧倒的に少なかったはずよ」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)はそう評価する。
実際それはその通りで、この戦いは必要なものだったし、やれるだけの事は皆やったのだ。
それでも、結果としてクリムゾンウェスト連合軍は大打撃を受けた。それが現実だ。
「戦場に絶対はありませんし、そもそもが負け戦……それは分かっていますが、やるせないですね。随分な人数を見殺しにする命令を出してしまいました」
「こっちもせっかく集めた自動兵器、ボッコボコにされちゃったわねぇ……」
これからどうしようか――そんな、何とも言えない空気に満ちていた。
「邪神翼というショートカットを失った以上、邪神本体は自力で地球凍結結界を解除できるまで動けないはず。時間は稼げたわ」
「あとは、稼いだ時間を何に使うかだ。考え続けよう、最後まで……僕らに出来ることは何かを」
●

ミリア・クロスフィールド

ナディア・ドラゴネッティ
転移門を経由して負傷者が運び込まれたり、救援が送り込まれたり、ひっきりなしに人が出入りしている。
最前線に送り込むにはまだ危険だと出撃を禁じられていたリアルブルーからの転移者たちも、今や必要な人手だった。
ミリア・クロスフィールド(kz0012)は、最早一人の努力ではどうにもならない量の仕事に見切りをつけ、作った時間でナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の傍らに腰かける。
「総長……ごめんなさい。また戦いの中で、たくさんのハンターさんが命を落とすことになりました」
魔導機械に繋がれ、ナディアは安らかに眠り続けている。
その手を両手で握り締め、ミリアはきつく目を閉じた。
「こんな時、総長だったら皆さんにどんな言葉をかけるんだろうって、考えるんです。諦めるなって前向きな言葉をかけるのかな……。それとも、もうゆっくり休んでいいから、残された時間を大切な人と使ってほしい……なんて言うのかな……」
自分は――ナディアのようにはなれない。
覚悟も強さも足りない。決断できない。その責任を背負えない。
もうずっと、ここから逃げ出してしまいたいという気持ちでいっぱいで、それ以外何も考えられなかった。
「総長……起きてください。これからどうしたらいいのか……決めてください」
どんな道を選んでも、きっと犠牲は避けられない。
次はもっと人が死ぬ。今度はグラウンド・ゼロでは終わらない。このクリムゾンウェストが、壊されてしまう。
「助けて……! 助けてください、ナディア……! 私じゃ……私じゃ、ダメなんです……!」
●

クリュティエ

イグノラビムス

バニティー
弱くて、無責任で、愚かで、成長もしない。
全体が悪だからこそ、類まれに生まれる善がまばゆく輝くのだ。
悪、悪、悪――どれもこれも悪。あれもこれも間違い。
“間違いを否定しているのだから、自分は正しいに違いない”。
全身を返り血で真っ赤に染めながら、クリュティエは考えていた。
見渡す限りが屍、屍、屍――。
誰が見たってわかる。これが地獄だ。
「なぜだ」
何度目かの呟き。
「なぜ、立ち向かう。なぜ……どうして……」
最後に斬ったハンターは、庇いたてた仲間の死体に折り重なるよう倒れている。
身体が重い。剣を持っていられない。不愉快で吐き気がする。
剣を零し、頬面を外す。息苦しくてどうにかなりそうだった。
『お前が心を痛める必要などない。すべては血の宿業による導きなのだから』
いつの間にか傍らに漆黒の炎に覆われた狼――黙示騎士イグノラビムスの姿があった。
「そしてその背中に立つバニティーちゃんなのであった。どう? 作戦は順調?」
バニティーは愛くるしい笑みを浮かべ、しゅたっ! と口で言いながら地面に降り立つ。
「ああ……極めて順調だ。何も――問題は――ない」
「それにしては顔色がすごく悪いわ。何かとっても許せないものを見たみたい」
ついさっきイグノラビムスが喋ったような気がしたのだが、もう狼は何かを言う気配もなかった。
振り返り、クリュティエは頬についた血を掌で拭う。
「……これで条件は揃った。彼らもきっとわかってくれる。無益な戦争はやめて、話し合う時だ」
「その話し合い、私も同行させて。“お父様”についても説明しなきゃだし、この世界の意向をちゃんと聞いておきたいから」
「好きにするといい」
力なく返答しつつ、クリュティエはその場に座り込む。
膝を抱えながら暗澹とした空を見上げ、深く息を吐いた。
「今回殺した分は……“間に合う”だろうか」
「どうかな? この世界の人がすぐに諦めてくれたら、ワンチャンいけるかもって感じ?」
「そうか。ダメだったら、お父様にお願いしよう。バニティーも一緒に頼んでくれないか? この人たちも、救ってあげてくださいって」
捨てられた子犬みたいな目だと、そう思った。
実際、この仇花の騎士は生まれたての赤ん坊のようなものだ。記録から再現されただけで、存在してから一年未満。
命の成り立ちなんて何一つわかっちゃいない、ただの子供じゃないか。
「いいよ。私も一緒にお願いしてあげる。だから、早く帰ってお休みしようね」
背丈が大きな少女の頭を撫で、バニティーは笑う。
(私達は、狂っている)
ファナティックブラッドは、とうに壊れたシステムだ。
(今更救われたいだなんてムシのいいことは考えない。でも――この物語にだって、きっと何かの意味があったのだと、そう思いたい)
さあ、答え合わせの時だ。
那由多の星にも、万能の神にも出せなかった結論を。
最後のピースを求めて、全ての真実を明らかにしよう。
「お父様を――救ってあげるために」
(文責:フロンティアワークス)
終わりは常に唐突で、万人にとって納得のいく形であるとは限らない。
どんなに理不尽でも、どんなに馬鹿馬鹿しくても、どんなに中途半端でも……。
物語はそこに誕生した瞬間に、絶対的な終わりを約束されている。
これは摂理だ。しかしだからこそ矛盾する。
物語とは、幸福のためにあるのではなかったか?
誰かを救い、誰かを慰め、誰かに居場所を与えるためにそこにあったはずだ。
ならば問おう。なぜ、物語は――世界は終わる?
――有限だからだ。
「彼は遠い遠い昔、皆が忘れてしまうくらいの大昔に、世界の終わりに立ち向かった」
星(セカイ)には寿命がある。
ヒトの都合などお構いなしに、マテリアルはやがて尽き、朽ち果てる。
そしてヒトには悍ましい運命がある。必ず、種そのものを自らの手で滅ぼすという自滅願望だ。
彼はそれを、「血の宿業」と名付けた。
世界の終わりまで人類が存続することは極めて稀である。なぜなら人は星を殺すという手段を以て自殺を果たすことが殆どだからだ。
星の終わりとヒトの滅亡は、極めて近しい。
「でも、その世界では人類が星の寿命まで生き残ったの。血の宿業について研究して、自殺因子になりかねない人類を徹底的に排除したから。結果として善良な種だけが残って、星と寿命を共にできた。でも彼は、そんな終わりをどうしても認められなかった」
一生懸命に頑張って。それでもどうにもならないことだってある。
でも、やってみなくちゃわからないから。
諦めずに、最期の最期まで、足掻いて足掻いて……そうやって生き抜くことこそヒトの美しさだというのなら。
最後の一人になったとしても諦めず、夢を手放さずにいよう。それが彼の願いだった。
ひとつだけおかしなことがあったとするなら、奇跡が起きてしまったことで。
彼が実際に、“世界”を永遠に“保存”するシステムを生み出してしまったことだろう。
「彼は星の中心核――大精霊の力を、この世界でいうところの神霊樹に封じて、その内側にもう一つの世界を作ったの。あなたたちも知ってるでしょう? 神霊樹の中には、過去の世界が再現されているって」
想い出の世界にはただ一つだけ足りないものがあった。それが“未来”である。
過去の記録はリプレイごとに僅かな違いはあれども、大筋においては必ず同じ結末に帰結する。
シミュレーターでは、記録にない未来は再現できないからだ。
「だから、彼は壮大な事業に着手したの。永遠の世界に未来を創るためには、沢山の可能性を、そのデータを蓄積するしかない。たくさんの未来を記録すれば、そこからやがて未来が生まれるかもしれないと考えたのね」
男は心なき大精霊と記録装置たる世界樹を中心としたそのシステムを、ファナティックブラッドと名付けた。
大精霊と契約した彼は、特殊な能力さえなくとも永遠に等しい寿命を手に入れ守護者となった。
そして彼らの旅が始まった。この宇宙のすべてを救うために。
「彼は“終わりかけの世界”を巡り、そこに暮らす人々の思い出を集め始めた」
滅びるしかなかった世界に突如として現れた、デウス・エクス・マキナ。
ファナティックブラッドは、間違いなく世界を救い始めた。
終わるしかなかった世界に、現状維持とはいえ可能性を与えたのだ。
異世界を巡りながら救済を続ける箱舟として、ファナティックブラッドは何千何万という時を過ごした。
「でも、必然かな。彼はやっぱり“限界”に直面する」
無限に等しい容量を持つと思われた大精霊という記録装置が、どんどん圧迫されていったのだ。
いくら男が天才でも、予見は難しかった。
なにせ大精霊は惑星の始まりから終わりまでを記録して余りある膨大な力を持っていたのだし、記録装置として大精霊を運用するなど誰も試したことがない。トラブルはやむを得なかった。
男は当然、諦めなかった。ここまで来て諦めるなど、そんな選択肢はあり得ない。
「そうだ! 異世界の記録を最初から最後まで全部観測して保存するから容量が足りなくなるんだ。未来に繋がりそうな、重要なポイントだけピックアップすればいいじゃないか!」
そうやってファナティックブラッドは「価値ある記録」のみを残し、それ以外は削除するようになっていった。
それでも宇宙はあまりにも広く、救済を続ければ続ける程、どんどん不足が出てくる。
記録した世界を保持し続けるためにはマテリアルが必要だ。もっともっとたくさんのマテリアルを得なければならない。
「そうだ! どうせ保存した後は勝手に消滅してしまうのだから、消えかけの世界を砕いて、そこでマテリアルを補給して次の世界に向かえばいいんだ!」
異世界に暮らす人々の思い出を搭載して、カラッポになった星は砕いてしまえ。
どうせもう搾りカスだ。世界一つを砕いていくつもの世界が救われるのであれば、これは単純な算数。
ひとつを犠牲にして膨大な数を救済できるのであれば、そんなものは考えるまでもない極めて簡単な問題ではないか。
実際、救われる人々はそれを望んだ。
“自分たちが救われるのであれば、終わりかけの世界など構うものか”と。
「それでもどんどん容量は不足して、エネルギーも足りなくなった。救済事業の継続にはどうしてもエネルギーが必要で、救いたい全部を補えない。だから彼は考えたの」
そうだ。そもそも存在の持続が容易なものに置き換えてしまえばいい。
僅かなマテリアルで永遠に近い時を生きられる存在を、自分たちは知っているじゃないか。
「彼は天才で、人間の闇――血の宿業について研究しつくしていたから、それができてしまった」
できなければ、そこまでだったかもしれない。
なのに、諦めないで挑戦して、努力し続けた結果、出来てしまった――。
「たぶんあらゆる世界で初めて、大精霊がそのまま歪虚に堕ちた――邪神が生まれた瞬間だった」

ファナティックブラッド
そしてファナティックブラッドは「世界を渡り」「世界を壊し」「生き残った命を喰らい」「侵略の糧として次の世界へと渡る」神となった。
「歪虚になって存在の維持がものすごくローコストになったのに、それでも容量は足りなかった。だから保存すべき“その世界にとって最も重要な記録”とは何かも吟味しなければならなかった」
それはさして悩む事もなく決まった。
未来に続く可能性があった瞬間。その世界が最も強く命を輝かせた瞬間。
そんなものはただ一つ。“その世界が滅亡する瞬間”に決まっている。
「ファナティックブラッドは世界の終わり……痛みの記憶しか観ない神様になっていった。だから再現された世界は終わりに嘆く瞬間そのもので、それが永遠に続くの。あの宇宙の中では、人々は何度も何度も繰り返し終わりの瞬間を、その絶望と恐怖と痛みを味わい続けるの。何度も、何度も、何度も……」
おかしな話だろう?
最初は間違いなく、正しい願いだったはずだ。
終わりたくない。もっと続けたい。別れは嫌だ。
最期に怯える世界を救ってあげたい。仲間として一緒に旅を続けたい。
「なのに、いつの間にか無間地獄が出来ちゃったんだね」
男はようやく、自分の間違いに気付いた。
すべてを救おうとした結果、取り返しのつかない罪を生み出してしまったと。
そんなつもりじゃなかった。皆に喜んで欲しかった。
なのに聞こえるのは悲鳴と絶叫。ファナティックブラッドはそれだけで埋め尽くされた。
もっと早く諦めていれば。運命に屈服していれば。
何も願わなければ。夢なんて見なければ。
「自分なんて、いなければよかったのに」
男はようやく真実に辿り着いた。そして、自ら命を断った。
ファナティックブラッドは、男の命令を聞くことでしか動けない機械だ。
自分が死ねばファナティックブラッドは止まる。そう考えた。
だがそれならば、ファナティックブラッドに――みんなの夢に、託された願いに、“終われ”と命じるべきだったのに。
自分が楽になりたい、救われたいがために、死を選んでしまったのが更なる間違いだった。
「ファナティックブラッドにとって、男の能力と存在を再現するのなんて簡単だった。だってそういう神様だから。男は自殺しても甦らされてしまった。今度は簡単に死なないように、より強力な歪虚として――」
そこでようやく男は知った。
諦めを知らず。絶望を知らず。
優しさと愛情と、純粋なる願いだけ。
光を信じて前に進み続けた男が、那由多の時の果てに辿り着いた、唯一無二の結論。
「ああ――“私に世界は救えない。私は、失敗したんだ”」

バニティー

大精霊リアルブルー

クリュティエ
グラウンド・ゼロに停泊したサルヴァトーレ・ブルの会議室で、バニティーと呼ばれた少女が長い語りを終えた。
サタンとルシファーとの闘いが一段落した後、和平交渉を行いたいと、このバニティーとクリュティエが人類側の陣地にやってきた。
人類側はこれを真正面から突っぱねられるほどの余力はなく。話だけでも聞いてみようと、この席が設けられた。
「すっごく長い話になっちゃってごめんなさい。最後まで聞いてくれてありがとうね」
バニティーが笑顔でお礼を言っても、場は沈黙を守っている。
何を言えばいいのかわからない。そんな雰囲気だ。
「話はだいたいわかった。その上で、そんな悪魔的な存在に対して一体どんな和平が可能なのかな」
大精霊リアルブルーが怖じることなく問うと、黙っていたクリュティエが口を開く。
「先ほども説明した通り、ファナティックブラッドは世界の終わりを観測し、記録するシステムだ。記録できる期間は短い。早く諦めてくれれば、それだけ“平和な時間”を長く観測し、再現できる。今ならまだ多くの命が想い出の中で救われるんだ」
「それが君の言うところの救済か」
「無論、お前たちにとって最善ではない事は分かっている。だが、ファナティックブラッドは全ての世界を救うために止まれないのだ。今はまだ未来に辿り着けていないが、もっと多くの可能性を取り込み続ければ……この世界には特に、未来を生み出すうえで必要な――」
「そんなもの、この世界にとっては関係ないだろう。君たちが止まれないのはわかった。だからといって過去の失敗を認めたくないから、いつまでも罪を重ねるつもりなのか?」
リアルブルーは立ち上がり、身を乗り出すようにしてクリュティエを睨む。
「闇と絶望しかない世界に、一体どんな未来が描ける!? 君たちはとうに進むべき道を間違えた!」
「だったら……諦めればいいのか? お前は……お前たちはみんなの願いを知らないからそんなことが言えるんだ――!」
それが、想い出の中の幻だったとしても。
ちゃんと生きている。あの子供たちの笑顔も、最期まで運命に抗おうと戦った者たちの勇姿も。
間違いなく――宇宙のどこかにあった本物なのだ。
諦めたら消えてしまう。何もかも全部結論が出てしまう。
無意味に――なってしまう。
「ただ……未来に辿り着けないだけなんだ。それがそんなに悪いのか? 今が続くだけじゃ、ダメなのか!? 今も! 彼らは確かにあそこにいる! 数えきれないほどの命が……文明が……世界がっ!! その全部を“失敗でした”と投げ捨てる権利が私達にあると思うのか!?」
肩で息をしたのは、呼吸を乱したからではない。
「彼らはただ……諦めたくないだけなんだ」
恐ろしい想像をした。この世界ひとつとは比べ物にならない膨大な数の“想い出”が、たったひとつの小さな世界のためだけに、すべて消えてしまう恐怖を。
「私には……できない……。あの子たちを消してしまう事なんて……思い出を否定することなんて、できない……。守るんだ……私が、皆を……守るんだ」
失敗したなんてわかってる。間違ったことだなんて、そんなの知っている。
それでも、そこにある命は間違いだなんて思いたくない。
「これまでの全部が否定されるべき罪だったとしても……いったい誰にそれを裁く権利がある? お前にはあるのか、大精霊。何も救わぬお前に」
リアルブルーはじっとクリュティエを睨む。そして強く歯噛みし、テーブルに拳を叩きつけた。
「くそっ! なんなんだよ、お前は……! 悪党なら悪党らしい顔をしてろよ! “守る”なんて言うな! ふざけるなっ! 許されるわけないだろう、お前たちがっ!! これまで一体どれだけの世界をそうやって地獄に突き落とした!? さっさと諦めれば――!」
『――なぜ諦める? やってみなければわからんじゃろうが』
少年の脳裏に言葉がよぎる。
『博打だろうがなんだろうが、全員助かる可能性があるのなら、その低い可能性に賭ける』
あの日、世界が終わるかどうかという空の上で、ナディアが言ってくれた言葉。
それに胸打たれたからこそ諦めを超えてここにいる自分は、果たして邪神を非難できる立場にあるのか。
潔くあの日あの場所で地球が終わっていれば、自分の世界に苦しみを強いることもなかった。
エゴで未来を求めたのは、自分も同じじゃないか――!
「まあ、お互いの主張は分かるけど、とりあえず落ち着こうよ。ただ否定するだけなら、全面戦争以外の着地点はないんだから。そうなれば不利なのは君たちの方だよね?」
落ち着いた様子で笑いかけ、ついでに隣のクリュティエに着席を促し、バニティーは一同を見渡す。

ベアトリクス・アルキミア
「じゃあ?、あなたは何の為にここにきたのかしら?」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)の問いに、クリュティエは親しみを込めて笑う。
「まず、真実を伝えに。お互いを傷つけずに済む方法があるのなら、それを探しに。何を今更って思われるだろうけど、裏表ない今の気持ちだよ」
「そう……。それにしたってこの事実、全世界に公表するには重すぎるわねぇ……」
「そうだね。事実上これは――この世界と、それ以外全部の世界の争いってことになるんだから」
「その口ぶりだと、このクリムゾンウェスト以外の世界って……」
「――うん。この宇宙はほとんどスッカラカンだよ。ぜーんぶ、ファナティックブラッドが食べちゃった」
可能性を考えなかったわけではない。
だが、最早この宇宙のどこにも逃げ場がないという事実。そして……。
「そう……。そこまでしても、ファナティックブラッドは未来に辿り着けなかったのね」
「だからこの世界がきっと最後のピース。でも、それを喰らって尚、ファナティックブラッドはどこにも辿り着けないかもしれない。やってみなければ、わからないから」
故に、なるべくローリスクでこの世界を喰らいたいのだ。
そして「未来」を信じている者にとって、この世界を喰らうことは救済でもある。
最後のピースがはまって、無限世界に未来が生まれれば、クリムゾンウェストの人々も正しく永遠の命を手に入れられる。
「うわぁ……すっごく複雑ね????!」
「だよね……。簡単に決められることじゃないから、時間をあげるね。ハンターズ・ソサエティだけじゃなくて、人類全体の話し合いも必要だろうし……あるいは誰にも話さずに、あなたたちだけで留めるというのならそれも否定はしない。何にせよ、後悔のないように考えてね」
語りながらバニティーは席を立ち、不安げなクリュティエの手を取って歩き出す。
「それじゃあ、また会いましょう。この世界の皆々様に――良き終末がありますように」
少女の姿はふわりと虚空に消えた。転移したのだろう。
残された面々はそれぞれ考えに耽るように、長く……とても長く黙り込んでいた。
「話なんか……聞くんじゃなかった」
少年のつぶやきは静寂に吸い込まれ、小さくなってどこかに消えた。
(文責:フロンティアワークス)

ミリア・クロスフィールド

ナディア・ドラゴネッティ

トマーゾ・アルキミア
「んごっふぉ……!? ミ、ミリア……わらわは病み上がりなんじゃぞ。驚かすでないわ……」
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)が目を覚ましたのは、バニティーの来訪から数日後のことであった。
知らせを受けたミリア・クロスフィールド(kz0012)が病室に駆けつけると、ちょうどトマーゾ・アルキミア(kz0214)が診察を終え、見舞い品のクッキーをナディアが口に放り込んだところであった。
「よかった……この赤ちゃんみたいなくりっくりの目やぷにぷにのほっぺた……総長そのものです!」
「お前そんなふうに思ってたの!?」
まだベッドに座ったままのナディアに跪き、ミリアはその手をぎゅっと握り締める。
「……ごめんなさい、総長。私……総長がいないと何にもできなくて……」
「何やら色々とややこしい話はトマーゾから既に聞いた。わらわのいない間、苦労をかけたのう」
ミリアの頭を優しく撫で、ナディアは八重歯を見せて笑う。
「人間が無力さの何を嘆く。どうせ人間なんぞ一人ではな?んも出来ぬわ。それはわらわとて同じことよ。皆が支えてくれて、なんとかやれておる。感謝こそすれ、誰がおぬしを責められよう」
「総長……うぅぅ……っ」
堪らず泣き出すミリアを「よしよし」と抱きしめながら、ナディアはトマーゾに目を向ける。
「皆でこの件を相談する前に訊いておきたい。トマーゾ、おぬし――ファナティックブラッドの正体に気付いておったな?」
「なぜそう思う?」
「勘じゃ。おぬし、妙に邪神そのものの研究報告は上げてこんかったしの」
トマーゾは腕を組み、神妙な面持ちで頷く。
「確かに、わしは邪神の正体について概ね検討をつけておった……反影作戦の頃にな」
邪神が元々は“邪神”ではなかったということは、その行動の矛盾点を見ればすぐにわかった。
“世界を滅ぼす者”でありながら“世界を保存する者”であるという意味不明さを掘り下げていけば、そういう結論も見えてくる。
あれは、“元々は世界を滅ぼすつもりなどなかったのではないか”――と。
「黙っておったのは、ハンターのためか」
「まあな。実際のところ、だからといって邪神と分かり合うことなどできん。アレは制御不能の暴走するシステム。元に戻すことも救うことも出来ぬのなら、知らぬままに討つべきだと、そう考えたのじゃ」
「そうじゃな……。我らの戦いとは常に、終わってしまった願いを終わらせることにある」
歪虚とはそういうものだ。
元々は美しい願いを持っていたのに、死後それが淀みとなって歪んでしまう。
もう死んでいて、決定的に生命とは相反するものだから、討伐することこそ唯一の救いなのかもしれない。
「誰かの夢を終わらせて、間違いを正す刃。それこそが我が愛しきハンターの本懐よな」
ハンターは別に相手が悪だから倒すわけではない。
中には人の心を持った歪虚もいるが、倒すことが“解放”になるから倒す。
人が正しく生きること、その願いを背負って、闇そのものを祓うのだ。
「……確かにな。で、黙っておったわしはお咎めなしか?」
「おぬしなりにハンターの為を思っての事であったのなら、これ以上は問わぬ。それより今は我らに出来ることを考えよう」
ナディアはミリアの涙を指先で拭い、優しく微笑む。
「この事実を公表するにあたり、まずは相談せねばな。これから我らが辿れる未来について」
●
ナディアの覚醒から更に数日後――。
冒険都市リゼリオのハンターズ・ソサエティ本部にて、クリムゾンウェスト連合軍の作戦会議が行われた。
バニティーから齎された情報を元に相談を重ねた結果、未来への選択肢が浮き彫りとなっていく。
「ハアハア……。よ、よし。だいぶ見えてきたので一度まとめるぞい……」
選択肢は大きく分けて三つ。
まずはこのまま戦い続け、「邪神を討伐する」こと。
「バニティーの話が本当ならば、ファナティックブラッドの構造はクリムゾンウェストの構造とほぼ同一じゃ。要するに封神領域っぽいところがあり、その中に世界全体の核として大精霊がいる。その大精霊を倒してしまえば、邪神という世界は崩壊するじゃろう」
ただし、ファナティックブラッドは数多の世界を取り込み、いわば第二の宇宙として再誕を迎える直前の状態にある。
見た目も巨大だが、中身はそれに輪をかけて広いのだ。その宇宙の中から中心までたどり着き核を討つのは簡単ではない。
当然ながらクリムゾンウェスト側も致命的な被害を受けるだろう。場合によっては共倒れという事もあり得る。
邪神との正面衝突を避けるという意味では、「邪神を封印する」という選択肢もあるだろう。
「無理に戦わず、何らかの手段で封印を施す。まあ、これも簡単ではないのじゃが……」
今現在リアルブルーの力で邪神の動きを封じられているように、邪神を止めることは不可能ではない。
だが、それを長期にわたって行うためには、より強力な――それこそ世界の法則を丸ごと塗り替えるような封印が必要だ。
「わらわの中の大精霊に訊いてみたところ、封印することは恐らく可能だということじゃが、そのためにはこの星が持てる力の全てを封印に注ぎ込む必要があるらしい。やはり、何らかの犠牲と引き換えじゃ」

バニティー

ファナティックブラッド

大精霊リアルブルー

ベアトリクス・アルキミア

大精霊クリムゾンウェスト
バニティーの言う通り、もしもこの世界がファナティックブラッドの宇宙再誕にとって必要なものであるのなら、この世界を取り込むことで未来が開かれる可能性もある。
「じゃが、そうならない可能性も高い。ダメだった場合は、我らももれなく地獄の無限ループ行きじゃ。それに邪神に取り込まれる時点で生物としては死んでおるので、歪虚になるということでもある」
そうなってしまえば、もはや邪神とは一蓮托生。
何が何でもファナティックブラッドが未来に辿り着くまで、旅を続けなければならない。
或いは――新たな黙示騎士と呼ばれる存在になるのかもしれない。
「邪神から逃げ出してこの世界のお世話になっている身としてはとやかくいう資格はないけど、だからこそ僕は封印を選びたい……かな」
大精霊リアルブルーが迷いながらも発言する。
「邪神の戦力は圧倒的だ。全部を相手にせず、中枢に向かって突撃するとしても、これまでとは比較にならない規模の死者がでるだろう。最悪、こっちが攻撃を仕掛けている間に帰るべき世界がなくなる事さえあり得る。僕はクリムゾンウェストにはなくなってほしくない」
「でも、封印は永遠じゃないわ。どんなに強い封印を敷いても、うーーーーーーーーーんと未来には壊されちゃうかもしれないじゃない?」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)はそう言って、困ったように笑う。
「ずっと先の未来……この世界というバトンを受け取る誰かに、責任を押し付けることでもあるわよねぇ? 私も邪神ほどじゃないけど長生きだからわかるんだけど、すごく長い時間引き継がれたものって、とーっても重たくなるの。未来の人達に、それを受け止める力があるかしら?」
「それはクリムゾンウェストが終わる前に封印が破られる前提だろう? クリムゾンウェストがとりあえず寿命を迎えるまで持てばいいじゃないか。どうせもう、こことリアルブルー以外の世界は殆ど死んでしまったわけだし……リアルブルーは大事だけど、クリムゾンウェストを巻き沿いにするのもどうかと思う」
「でも、世界の仕組みって私はわからないけど、新しい世界が生まれることだってあるでしょう? それは生まれた端からぜーんぶ邪神に食べられちゃうの?」
世界が複数存在していて、寿命を迎えて消滅するということは、どこかに新たな世界もまた生まれている可能性があるということだ。
邪神がこの宇宙を喰いつくしたら、次にどんな行動をとるだろう。
持続コストを保てなくなり自滅する? それとも、それを補うために更なる旅を続けるのか……。
「私は実際に狂気王に取り込まれていたからわかるんだけど、最も辛い記憶、絶望の中でループし続けるのってめちゃくちゃしんどいのよね。それでも、私は邪神に取り込まれることも一つの道だと思うわ」
「正気か? 世界のすべてが闇に堕とされるんだぞ?」
「邪神が第二の宇宙として再誕すれば、問題がすべて解決するのは事実よ。その見込みがあるのに中々アガリを決められないから、彼らは焦りながらも旅を辞められないでいるのでしょう? 実際、この世界の人間は彼らに足りないものを持っていると思う。彼らに未来を見せられるかもしれない」
ベアトリクスはそのまま、ナディアへと視線を移す。
「ナディア。この世界の神様はどう思っているのかしら? どの選択肢を選ぶにも、クリムゾンウェストの意見は無視できないわぁ」
ナディアが目を閉じ、マテリアルを高め超覚醒する。
炎のヴェールを纏った大精霊は、静かに言葉を返した。
「私はこの星の意思として、生存を諦める道は選べません。つまり、邪神とは決して相容れないということです。その上で、封印するにせよ討伐するにせよ、星そのものに甚大な被害が出る事は承知しています」
「君は封印と討伐であればどちらがいいんだ?」
「どちらでも。私の目的は星の存続であり、それさえ出来ていれば良いのですから。しかし、リスクが低いのは封印だと考えます。私にとっては少しばかり残念な選択ですが」
仮に邪神を封印するとなれば、地球凍結結界に匹敵する術式の長期的な行使が必要となる。
それは星の力のすべてをそこに集中させるということである。
「もし封印を望むのなら、世界において人と精霊は分かたれた存在となるでしょう。精霊や幻獣はすべて封印の維持に用いられ、この星の運営はヒトに委ねることになります」
「……そうか。確かに、そういうことになるのか……」
それは、覚醒者という存在すらいない世界だ。
魔法や精霊を忘れた、リアルブルーに近いとも言える。
「そうなれば、クリムゾンウェストとリアルブルーも分かたれるってことになるね」
「はい。お互いに転移者が生まれることもなくなるでしょう。それぞれの世界は、あるべき形に戻るのです」
紅の大精霊は自らの胸に手を当て、目を細める。
「それを――私はほんの少し、寂しく思います」
「お……驚いたな。君にそんな感情があったのか……」
「感情はありませんので、人間の言葉に置き換えるなら、ですが。それでもヒトは、私に沢山の可能性を見せてくれました。今ならば彼らを私に代わる星の運営者として認めてもよいでしょう」
「それはいいけれどぉ……もしも彼らが邪神への恭順を選んだ場合はぁ?」
「止むを得ませんね。そんな道しか選ばせてあげられない己の不徳を嘆きながら、神としての責務を果たします」
「ハンターと戦うってことね……」
三体の大精霊はそれぞれの顔色を伺っていた。
結局もうこんなものは唯一無二の正解などない。何を切り捨て何を選ぶかというだけの話。
「まー、とにかくじゃ」
覚醒を解除し、ナディアは一同に問いかけるように言葉をなげかける。
「この事実と未来の選択を、ハンターズ・ソサエティ総長としてわらわは世界に公表する。皆もそれでよいな?」
「身内の恥を例とするのもなんだけど、それにより世界が混乱して暴動が起きたりしないか?」
「不安に思う者や、やけっぱちになる者がいないとは言わぬが、それでもこれは誰もが考える権利を持つことじゃろう? 特にこれまで戦ってきてくれたハンターには、一度ゆっくり考えて欲しいのじゃ」
その点においては誰も異論はない。
どんな未来を選んでも、その最前線には彼らの姿があるだろう。
ハンターはこれまで、美しいものも醜いものも分け隔てなく見てきたはずだ。
命を奪い合う最前線で。絶望に埋め尽くされた邪神との闘いの中で。
“それでも”と前に進んできた彼らには、未来を思う権利がある。
そんな彼らがちゃんと考えて選んでくれたなら――。
「――そんな未来も悪くない。わらわは、そう思うんじゃ」
●
「お父様は物語には必ず意味があって、誰かの救いにならなきゃいけないって言うんだけどね。私はそうは思わないんだ」
それは、作者の都合だ。
こうあってほしいと願い、こうであればよいのにと夢想した。
それはいい。そうでなければ、物語など紡げない。だが――。
「その物語が結局なんだったのかを決めるのは――作者じゃなくて読者なんだよ」
世界は観測されて初めて存在を証明される。
そこに降り立った誰かが大地を踏みしめ、胸いっぱいに息を吸って、ようやく意味を成す。
最後まで読み進める事は難しいから、途中で折れてしまうこともあるだろう。
生きる事は辛くて苦しいから、ページをめくる指が止まってしまうこともあるだろう。
思い通りにならない願いに苦しみ、望まず誰かを傷つけてしまったとしても――。
「それでもね。物語の所有者は、作者じゃない。救われるかどうかを決めるのは、作者じゃない。仮にこの宇宙を再誕させたとしても、お父様に出来るのはそこまで」
物語に結論を出せるのは、作者ではない。
ピリオドを打てなくなったファナティックブラッドを終わらせるものがいるとしたら、それは“彼”ではない。
「諦めを超えて善より悪へと堕ちた怪物を倒せるのは、やっぱり同じ諦めを超えた善だと思うから」
『信じているのか』
「信じる者は救われる! ……って、あなたの言葉じゃなかったっけ?」
『私ではない。モーセか何かだろう』
「いいじゃん別に、同じようなもんでしょ?? どうせ世界は、見る側の問題だもの」
どれだけ崇高な願いも、言葉も、望まれなければ意味がない。
「私は所詮、ページに挟まれた古い栞に過ぎないけれど……それでも、待っているんだ」
前の持ち主は、栞の存在を忘れてしまった。
だからこのページを再び開く誰かが現れた時には、それを愛そうと決めていた。
昔の誰かにできなかったことを――。
今のままでは辿り着けない未来を――。
「信じているんだよ」
イグノラビムスのふわふわの背中に自らの背中を預け、バニティーは安らかに目を瞑る。
ラブレターの返信を待つ乙女のように。
あるいは――死刑の執行を待つ、罪人のように。
(文責:フロンティアワークス)

ドナテロ・バガニーニ

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ

シュレディンガー
「こちらこそはじめまして、ドナテロおじさん」
ハンターズ・ソサエティの総長室に置かれたソファで、二人は交互に頭を下げた。
例の告白からやや時を置きバニティーがソサエティを訪れたのはナディアと話す為だったが、たまたま居合わせたドナテロ・バガニーニ (kz0213)も交え、三人での会談となった。
「バニティーとやら、どこにでも神出鬼没なのじゃな……」
「そうだよ。だから今日みたいにナディアの傍に直接転移もできるの」
その能力を使えば、組織の中枢も奇襲し放題である。
そうしないのは友好的な関係を築きたいからだろうが、この時点では一種の牽制とも見るべきだろう。
「話をする前に、おぬしが何者なのかをもう少し聞かせてもらってもよいじゃろうか」
「いいよ。何が知りたい?」
「何……というかなんなのじゃ、おぬしは? 歪虚ではあるようじゃが……あまりにも気配が弱弱しすぎる。まるで雑魔のようじゃ」
だからこそ、非覚醒者であるドナテロとも同席できるのだが。
「わたしは型落ちの歪虚王なの。歪虚王ってわかる? 邪神が異世界制圧用に産み落とす、七体の統率者なんだけど……」
「知っておるが……王は入れ替わるのか?」
「うん。その世界の制圧に適した形に毎回作り直すの。前の世界から引き継ぐものもいるけどね。例えばベアトリクスは結構長らく王やってたよ。わたしは引き継がれなかったので、役職なしの歪虚。元々は“虚飾王”って呼ばれていたね」
虚飾眷属の能力は他人からの認識を操るものらしい。
それを極める虚飾王ともなれば、認識だけではなく他人に対して直接的に己の存在を欺けるのだという。
故に、バニティーはあえて人型を取っている。本来の姿は禍々しすぎるので、対話の邪魔になってしまう。
「だから雑魔程度のマテリアルしか感じないでしょう? 余談だけど、シュレディンガーも同じ能力を持っていたんだよ。ランクはわたしの方が上だったけどね」
「シュレディンガーも……そうであったか」
どこか寂し気にドナテロがつぶやくと、バニティーは優しく目を細める。
「いい人なんだね、あなた」
「んむ?」
「なんでもなーい。他にご質問は?」
「おぬしが誰の味方なのかを聞きたい」
黙示騎士と行動を共にしていると思っていたが、どうやらそれも違う。
ファナティックブラッドの造物主、お父様と呼ばれる人物の遣いのようにも見えるが、意図がわからない。
「前にも言ったけど、わたしは中立だよ。ただ、あくまでも個人的な都合で言うのなら――あなた達の味方かな」
「どういう意味じゃ?」
「わたしの願いは、邪神からお父様を解放してあげること。それはどんな方法でも構わない。もちろん、あなた達の手によって倒されるのでもね」
「そんなこと、お父様とやらは認めるのか?」
「認めるわ。だってあの人、わたしが何をしようが興味ないんだもの。このままこっちに残ってずっとあなた達の味方をしたって怒らないわ」
顔を見合わせるナディアとドナテロ。
「話を聞く限り、ファーザー殿はそもそも邪神の侵攻に積極的ではないように思えるのであるが……?」
「うん。あのおっさんは邪神に何も命令しない。止めないし、進めない。逆に、あの人をうまいこと説得して“止まれ”と命令させることができれば、邪神は止まるわ」
「おおおおおっ!? それならば、ぜひ我輩に交渉の席をご用意いただきたい! こう見えても我輩、交渉だけは得意なのである!」
ドナテロがふくよかな胸を叩いて息巻くが、バニティーの表情は硬い。
「難しいと思う。というか、説得はもうわたしとかシュレディンガーもしてるから。あの人は止まれないの。絶望し切っているようで、どこかでまだ諦められないのね。本当に愚かだわ。臆病者。無責任なヘタレ野郎。意気地なし。死ぬまで童貞。重篤な裸族」
「……そ、そうか。もう自分たちではどうにもならぬから、助けを求めた……と考えてよいのだな?」
ナディアの問いかけに、バニティーはゆっくりと頷く。
「……ごめんね。あなた達にとっては何にも関係のない事なのに」
「関係? そんなものあるに決まっているじゃろう。生きるということに無関係な事柄などない。すべては地続きの上にある。関係ないように思えることでも、巡り巡って向き合わねばならぬ時も来る。何より、邪神という外敵に襲われ、それを打破しなければならないというこの状況において、我らは誰よりも当事者じゃ」
キッパリと言い放つと、バニティーは目を丸くしたがら笑った。
「驚いた。あなた、見た目よりずっと立派なレディーね」
「はっはっは、300年モノのロリババアじゃぞ? 降りかかる火の粉は払わねばならない。ただそれだけじゃがな」 ナディアは努めて冷静に、バニティーの瞳を見つめ、告げる。
「悪いがわらわは何よりも自分の世界の存続を優先する。既に終わってしまった物語よりも、未だ終わらぬ物語を続ける。その為ならばすべての世界が敵になっても構わぬ」

クリュティエ
がっくりと肩を落とし、バニティーはしきりに頭を下げる。
「これまでの宇宙の全部の責任を取ってもらうつもりなんてないよ。だから、あなた達は自分の世界のことを優先していいの。生物が自らの存続を優先するのは、当然の理だわ」
「そう言ってもらえるのはありがたいであるが、クリュティエ殿のように本気で邪神を守ろうとする者もいるのだろう? 我輩も結局、敵を慮るほどの余力はないが……」
「少しでもそう思ってくれたなら、それだけで十分だよ。あの話は、単に事の成り立ちを説明しただけ。まずあのわけわかんない話をしないと、わたしのことも信じられなかったでしょ?」
確かに、今こうして落ち着いてバニティーと話ができるのは、邪神の真実を知ったからだ。
邪神がその中に眠る歪虚にとっても暴走状態にあり、その終わりを望む者もいる――という前提がなければ、バニティーという異常な協力者を理解できなかった。
「もし邪神を少しでも憐れんでくれるのなら、お父様と邪神を止めて欲しい。それがわたしの願い……かな」
「クリュティエ殿とは違う考え方、なのであるな」
「まったく違うってわけでもないんだよ。でもさ、あの子だってあのまんまじゃずっと辛いだけだよ。何か……答えを得なきゃ。あの子も自分が間違ってるって頭ではわかってる。どうしたら納得できるのか、わたしにはわからないけど……」
「つまり、バニティーは邪神の討伐に一票というわけじゃな」
「うん? 一票って?」
ハンターズ・ソサエティは、邪神の成り立ちについて世界中に説明した上で、ハンターによる決断を仰いでいた。
その為に大まかに三つの選択肢を用意し、それについて議論を重ねているところであった。
ひとつは殲滅。ひとつは封印。ひとつは恭順――。
「そっか。ごめんね、悩ませちゃって……」
「いや。本質的にヤバすぎる敵に対してどのように勝利を収めるかという相談なので、ちゃんとやるのは当然じゃし」
「どうなってもわたしは手を貸すよ。元々その話をしに来たんだけどね。ホラ、和平の使者です?と言いながら何も提案してなかったし……たはは」
そもそもお前、和平と言いながら邪神倒す気マンマンじゃねぇか……とは二人ともツッコまなかった。
「いやぁ、とりあえず和平という話をしないとわたしがクリュティエに怒られるから……ごめんっ、この通り!」
口にしなくても表情だけで伝わったらしい。
「余計な殺し合いは避けたいのも事実だし、クリュティエの願いも叶えてあげたいんだけどね」
「何かとややこしいであるな、バニティー殿の立場は……」
「まあとにかく、どのパターンでもお父様に会いに行くよね? わたしはその道案内ができるんだよ。これ、実はわたしにしかできないことなんだよね」
虚飾王を降りたバニティーに与えられたのが、魂の案内人という役職だ。
大量の異世界を取り込み、第二の宇宙として再誕する直前のファナティックブラッド内部は、文字通り宇宙としての広さを持っている。
その中には転移門にも似た“ステーション”と呼ばれるエリアがあり、この転移を管理しているのがバニティーなのだ。
「ステーションは元々は人間が作ったものだから、ほとんど転移門まんまと考えてもらっていいと思う。で、お父様のいる中枢に行くためには、複数のステーションを経由していく必要がある。闇雲にワープしまくっても絶対辿り着けないから、わたしが案内するね」
「おお、それは助かるのじゃ。……まあ、おぬしを信じていいのなら、じゃが」
「罠に嵌めるつもりだったらこの話自体しないよー。黙ってればいいんだからさー」
確かにその通りである。

カレンデュラ
「それと、こっちは上手くいくかわからないけど、あなた達と同調する歪虚に邪神内で引き合わせてあげられるかも」
「ん? そんなものがおるのか?」
「あ、そうか。そっちは何にも知らないよね……。えーと、この世界は結構長い間シュレディンガーによって観測されてたのは知ってるかな?」
二人は頷く。まあ、そのような自覚はなかったが、そうなのだろう。
「で、その観測された情報は邪神の中に蓄積されるの。この世界で言うパルムみたいな動きだね。それで、あなた達のこれまでの戦いを、邪神の中でループしまくってる人たちも見たり感じたりしてきたんだよ」
「邪神の中で放送されるテレビ番組のようなものであるか?」
「ざっくりそんな感じ。で、あなた達の戦いを見て、もうこんなことは辞めようって連中も現れたわけ」
「――そうか。“これまでの戦いを観測していた”のだな?」
話を聞いてナディアは直ぐに理解した。
「ならば信用できる。ぜひ引き合わせてもらいたい」
「いいよ。ちょっとこっちで色々動いてみるね」
よくわからないドナテロであったが、ナディアがわかっているのならよいだろう。
「仮に邪神に取り込まれる道を選んだとしても、あなた達の世界は特別だから……。なんなら、邪神を乗っ取っちゃうって方法もあるよね」
負の存在にコンバートされてしまうのがネックだが、邪神という世界の中で優位を勝ち取ることはできなくもない。
あくまでも邪神が主体性のない無限の祈りにより構築されているというのなら、最も輝く祈りとなって未来を作ってしまえばよいのだ。
「こういうのも実はちょっと期待してるかな?」
「物はやりよう、ということか……。殲滅を狙いつつ、ダメだったら邪神を乗っ取る、みたいな予備策もアリじゃな」
「そうだね。全宇宙が相手だと流石にドン引きだろうけど、勝ち目ゼロってわけでもないって考えて欲しいな」
バニティーは一息つくように、用意されたティーカップに口をつけた。
「ふう……いっぱい喋った……。他に何か知りたいことはあるかな?」
「ひとまず十分じゃ。わずかではあるが、希望は見えた。協力に感謝するぞ、バニティー」
「しかし……バニティー殿、このまま黙示騎士と行動を共にしながら我らにも協力してくれるのであるか? ファーザーがいくら放任主義であっても、目的を違える君を黙示騎士が許すだろうか?」
「それは……わたしの意地っていうか。これでもね、黙示騎士はわたしの家族みたいなものなの。できればあの子たちも救ってあげたい。願いを全部叶えるのが無理でも……何か答えに辿り着いて、“ああよかった”って思ってから消えて欲しいんだ」
少女は複雑な表情を浮かべた。笑うでも泣くでもなく、ただ寂しげな顔。
「ごめんね。エゴだよね。わかってるんだ、意味なんかないって。わたしが今こうやってあなた達を手伝おうとしているのも、全部自分の為なんだ。わたしがただ……お父様がどんどん壊れていくのを見ていられなかっただけ。だからあなた達を利用して、ひどい戦いに巻き込もうとしているのも、全部わたしの我儘で……」
「それがどうしたのであるか?」
心から不思議そうにドナテロが首を傾げる。
「エゴに決まっているのである。疑う余地もない。人間は自分にとっての利でしか動けない生き物である。バニティー殿に個人的な願いがある事の何がおかしいのである?」
「同感じゃ。協力者の腹の内などどうでもよい。ただ、我らにとって益となるのならば、その範囲内で許容しよう。“仲間”とは完全な相互理解を指す言葉ではない」
ポカンと口を開け、それからやや遅れバニティーは笑った。
「あはははは! やっぱりすごいね……こんなの、邪神が勝てなくて当然だよ……っ!」
腹を抱えて――涙をぬぐい、笑った。
「……ねぇ。まだこの宇宙に残っている三つの世界、クリムゾンウェスト、リアルブルー、エバーグリーンの共通点、わかる?」
クリムゾンウェストは、古代に一度邪神により砕かれている。
エバーグリーンもそうだ。その命は殆ど吸い上げられ、荒野の世界となった。
リアルブルーも毒牙にかかり、今や時間凍結の憂き目を見ている。
だが、考えてみればおかしな話だ。
星を砕いてそこに住む者を連れ去るのがファナティックブラッドだというのなら、星そのものが既に失われているはず。
エバーグリーンは命のほとんどを奪われながらも、大精霊であるベアトリクスが健在であるように星の灯は消えていない。
クリムゾンウェストも、一度は文明を洗い流されたものの、それでも大精霊も人類も健在である――。
「――それはね。諦めなかったこと。自分たちの運命を、誰かに明け渡さなかったこと」
エバーグリーンの大地で、最期までトマーゾ・アルキミアやオートマトンたちが闘い続けたように。
混迷を極めたリアルブルーの大地で、それでも人々が諦めずに邪神へと立ち向かったように。
クリムゾンウェストという大地から逃れたとしても、それでも生き残り、絶対に星を明け渡さなかった者たちがいた。
もしもあの時、本当に何もかもを諦めていたのなら……。
“大精霊という星の核を明け渡していた”のなら……。
今この時、クリムゾンウェストという世界はなかった。

大精霊クリムゾンウェスト
ナディアの頭の中で、大精霊クリムゾンウェストが呟く。
『わたしを封じていた封神領域マグ・メルは、ヒトの手により作られた場所です。私はそれを……“置いて行かれた”のだと感じていた』
あの日、クリムゾンウェストからリアルブルーへと多くの人類が逃れ。
見捨てられたと思った。でも違う。大精霊の記憶は、人類に封印されることで途切れている。
『あの状況で私を封印した術者は、みな歪虚に屠られたでしょう。本当に逃げ出すつもりなら、そんな大それた儀式などする必要はなかった。私を……邪神に差し出せばそれでよかったのです』
けれども、あの時――。
彼らは必死に、邪神と戦おうとする神を封じ込めた。
今はまだ勝てないと知って、“護る”ために“隠した”のだ。その命を賭して――。
『邪神に……最期まで、絶対に屈しないと。大精霊さえ護れば、いつか星を取り戻せると。信じてくれたのですね……私を』
ナディアの両目を涙が伝っていた。
「……そうじゃな。おぬしは、見捨てられてなどいなかった。今ならそう信じられるのう。……あとおぬしの感情重すぎてキツいからもうちょい気楽にせい。わらわ吐きそうなんですけど」
『大精霊に感情などありませんが……ごめんなさい、ナディア』
「ああもう、泣け泣け! おぬし、泣きもせんからずーっと怒っておったのじゃろう! 泣いとけ! 身体は貸す!」
最後まで戦った三つの世界だけが、完全な滅びから免れた。
戦う事は無意味ではない。抗ったからこそ今があり、希望のバトンは脈々と受け継がれてきた。
「呑み込まれた世界も悪かったとまではいわないけど、自分たちが救われるために運命を人任せにしてしまった。そういう世界とあなた達は決定的に違うわ。……わたしとお兄ちゃんがいた世界も、諦めちゃったクチだけど」
「そうか。バニティー殿も、何処かの世界の人間だったであるな」
「うん。わたしはけっこうサクっと死んじゃったけど、お兄ちゃんは最後の最後まで戦ってた。わたしを邪神に殺されたのが心底頭に来てたのね。まあ……怒り過ぎてわたしの事なんか忘れちゃったみたいだけど」
たはは、と笑いながらため息を零すバニティーを、立ち上がったナディアが手招きする。
首を傾げながら近づいてみると、ナディアは両腕を広げ、そのままバニティーを抱きしめた。
「辛い役目を任せて、本当にすまない。心から感謝する……ありがとうのう、バニティー」
「……………………。いいの。こんなの、全然へーきよ。だってもう、何千年も……ずっと、ずっとね…………」
バニティーは怪物だ。
虚飾の力で少女を装っても、本質までは変えられない。
歪虚である以上、どんなに心があっても、闇に留まる死体に過ぎない。
冷たく淀んだ全身に、ナディアの生物としての暖かさが伝わってくる。
「わたしはね、平気なんだよ。でも……それでもね。ありがとう……一緒に頑張ろうね……!」
「うむ。一緒に……な」
ナディアの身体を抱き返しながら、バニティーはきつく目を閉じた。
邪神が消えれば自分も消える。だが、この狂った命に未練はない。
(わたしに出来るのは、もうこんなことだけ……。だから……ごめんね。ごめんなさい……お兄ちゃん)
あなたが、大好きだったから――。
(わたしはわたしのやり方で、最後まで戦うよ)
バニティーは笑顔で立ち去り、残されたドナテロとナディアは更に相談を進める。
「……やりきれぬものであるなあ。“勝ち残る”ということは」
「ああ。重い責任がある。誰かの夢を踏みにじり、それでも前に進む責任が……の」
選択の時は、間近に迫っていた。
(文責:フロンティアワークス)

ミリア・クロスフィールド

ベアトリクス・アルキミア

ルビー
あくまでもソサエティ内部での行事であるため、意見聴取への投票権を持つのはソサエティに属するハンターのみだが、その様子を確認しようと多くの人々がリゼリオを訪れていた。
投票はパルムの力も借りて、神霊樹ライブラリに集計されるのでそこまで人手はかからない。
しかし、期間中にはさまざまなトラブルや問い合わせが予想され、ミリア・クロスフィールド(kz0012)は準備に追われていた。
「なんだか忙しくてバタバタしていたら、あっという間にこの日が来ちゃいましたね……」
「そうねぇ?。正直混乱もさめやらぬところだけど、いつまでも邪神が大人しくしてくれるとは限らないから」
ほぼお祭りみたいなものなので、街には出店も出ている。
そこで購入してきたらしいソフトクリームをなめながら、ベアトリクス・アルキミア(kz0261)が微笑む。
「先手は打ちたいし、そろそろ……ね。グラウンド・ゼロでは残党との戦いが続いているし、まだシェオル型が転移してくることもあるし。答えを早めに出さないと、不安は膨張するから」
「そうですね。でも、ハンターさんはやると決めたらきっちりやってくれますから!」
「ちょっと気の毒なくらい、よく頑張ってると思うわ?」
なめる動作がトロいのか、だんだん溶けてきたソフトクリームに悪戦苦闘するベアトリクス。
そこへルビー(kz0208)が現れ、声をかける。
「ベアトリクスさん。リアルブルーくんが呼んでいましたよ。B会議室です」
「はいは?い」
だらけた様子で去っていくベアトリクスを見送り、ミリアは思わず笑ってしまう。
「なんだか少し、以前のソサエティに戻ってきたみたい」
「はい。邪神の話を聞いた時の絶望感は凄かったですからね」
「ほぼお通夜だったよね……」
乾いた笑いを浮かべる二人。実際あの頃はミリアも毎日消えてなくなりたいと思っていたものだ。
「でも、大丈夫です! ナディア総長も復活したし、こっちにはベアトリクスさんやリアルブルーくんもいるんですから!」
「そう……ですね」
ミリアの明るい声に対し、ルビーの反応は芳しくなかった。
どこか迷っているような、苦しんでいるような横顔だ。
「ミリアさんは……その、もう……聞きましたか?」
「え? 何をですか? ……あ、三つの選択肢ですか?」
「いえ。その、ナディア総長とベアトリクスさんの……身体のことです」
●
「――ベアトリクスさんっ!」
廊下の真ん中、コーンのお尻をかじっていたベアトリクスが振り返る。
のんびりした様子で――しかしミリアの必死な目を見て、微笑みながら。
「あの……本当なんですか!? ベアトリクスさん……消えちゃうって……」
「本当よ?」
エバーグリーンはもう、とうに惑星を維持できない状態にある。
大精霊という核がまだ残っているが、生物は影も形もない。
オートマトンボディに搭載して延命を図ってきたが、ベアトリクスという大精霊の存在寿命は残り僅かだった。
「でも、私の仕事は全部ルビーに引き継いだから。あとは、邪神との闘いに全部を使い切るだけ」
「そんな……なんとかならないんですか……?」
「なりませ?ん♪ むしろ、まだここにいる事の方が奇跡なんだってば?」
歩み寄り、ベアトリクスはミリアの顔を覗き込む。
「“永遠”なんて不自然なのよ。どんなものにも終わりはあって、いつかはお別れの時がやってくる。私がうろうろしてるとね、エバーグリーンの物語はいつまでも終われないの。ずうっと、ずうっと、誰もいない砂漠でたくさんのマシンがヒトの帰りを待ち続ける……そんな世界、寂しすぎるじゃない?」
「それは……理屈はわかります。世界にとっていいのかとか、悪いのかとか……。でも、“私は”そんなの悲しいです。ベアトリクスさんに、いなくなってほしくないんです……」
「そうねぇ。それも、真実よねぇ。世界がどうとか、そんなの個人には関係ないものねぇ……」
しきりに頷きながら、ベアトリクスはミリアの頭を撫でる。
「その気持ちは、誰にも否定できない本物よ。ありがとうねぇ、ミリアちゃん」
エバーグリーンは滅ぶ。もう、滅ぶと決まり切っている。
知っていた。わかっていた事だ。でも、それが何を意味するのか……考えようとしなかった。
「でもほら?、中身が消えてもこのボディは残るから?! 好きに使っていただければ?♪」
「そういう問題じゃないんですよ??!?」
泣きながら叩く手を取り、白衣の女はミリアを廊下の奥へと導く。
「ほら、私とのお別れは十分でしょう? あなたはもう一人、話しておかなきゃいけない人がいるんだから」
●

ナディア・ドラゴネッティ

大精霊クリムゾンウェスト
空蒼作戦で酷使した肉体は限界を超えて痛めつけられ、数多の後遺症を残している。
大精霊の力があれば、死に体を動かすことも容易い。だが、それはただ動くだけだ。
青龍の心臓と大精霊の加護により動いているだけの人形――。
この状態を、トマーゾ・アルキミア(kz0214)は「生きている」と定義しなかった。
もう一度全力で大精霊の力を使えば、この肉体は歪虚のように塵となって消える。
そうではなくとも、長く持たないのは自明であった。
『ハンターに言わなくてよいのですか?』
ソサエティの執務室の窓からリゼリオを見下ろし、ナディアは心の声に耳を傾ける。
『邪神に勝っても負けても、あなたは消えてしまう。古代の巫女がそうであったように、私の力に押しつぶされて……』
「言うてどうするんじゃ? マジでどうにもならんのに、この大事な時に余計な情報を増やしたら混乱するじゃろうて」
『それは、そうですが……』
「やれやれ……世界の神ともあろうものがそんな情けない声を出すでないぞ」
ナディアは決意を固めているし、大精霊を責めたりもしていない。
彼女の内に居て、それが何よりもはっきりとわかるからこそ、大精霊は苦しみを覚える。
「生きることを諦めたわけではないぞ。ただ……人あらざる理に手を染め奇跡を欲したなら、詮無きことじゃろうて」
大精霊という星の力をその身に降ろし、邪神と戦ったのだ。
どう考えても許される規模の奇跡ではない。
「その代償が死だというのなら、道理と言う他あるまいて。ただ、まあ……なんじゃ。この状況になってみると、ファーザーとやらの気持ちも少しわかる」
諦めを超えて奇跡に手を伸ばしたという点において、ナディアとファーザーは同じだ。
「最後まで世界を……自分が救おうとしたものを、その結末を見守りたかったのじゃろうな」
同じ気持ちだ。ナディアも、最後までこの世界を――この世界に生きる人々の結末を見届けたい。
なまじ数百年生きているからこそ、“もう少しだけ”という気持ちがあるのも事実だった。
「かの御仁を否定するのなら、わらわも“有限”を認めなければ……な」
肩をすくめながら皮肉な笑いを浮かべた時だ。
部屋の扉がノックされ、ミリアが姿を現した。
「どうしたのじゃ? 何か神霊樹ライブラリに問題でも……っと、ぬぉおおっ!?」
ミリアは何も言わず、そのままタックルばりの鋭さでナディアに抱き着いた。
ナディアの方が小柄なので、ほぼ縋りつく格好だ。
自分の胸に顔を埋めて黙り込むミリアを見て、ナディアは困ったように眉を顰め、何かを言おうとして、それを辞めて――目を閉じた。
「――ミリアよ。邪神をどうにかした後も、この世界にはハンターズ・ソサエティが必要じゃ。どうか、わらわの代わりに総長をやってはくれぬだろうか」
返事はない。ナディアは頬を緩め、ミリアの身体を抱き返す。
「わらわは思うのだ。ヒトにはそれぞれ、天より与えられた運命があると。命を授かったその時に、心を覚えたその時に、溢れんばかりの祝福と共に、ヒトはこの紅き大地に降り立つ。そして為すべきことを成し、夢を紡ぎ……いつかは消える」
この人生にも後悔はある。
滅びに瀕したリグ・サンガマから南に逃れ、ソサエティという組織を作ったものの、ナディアは人に絶望していた。
ソサエティという武力が人類にとって、そしてこの世界にとって善なのか悪なのか、見極められぬまま長い時を過ごした。
一人では何もできなかった。何も決められなかった。現実から逃げて、問題を先送りにして、都合よく誰かが救ってくれることを期待した。
「自分の願いを叶えられるのは……自分の理想を現実にできるのは。他の誰でもない、自分だけなのにな」
「でも……だからって……。ナディアがいなくなってしまうなんて……」
ベアトリクスは笑っていた。ナディアもきっと笑っている。
わからない。わからない。わかりたくない。
「言ってほしかった……! あなたに……“死にたくない”って……!」
その苦しみを教えて欲しかった。理解して、共有して……。
だって、それくらいしかできないじゃないか。
これから死にゆく者のためにできるのは、一緒に泣いてあげることくらいしか――。
「いや、わらわもフツーに死にたくないぞい?」
顔を上げる。ナディアの手は、小刻みに震えていた。
「ほれ。自分が消えると考えるだけでこのザマじゃ」
「だったら、どうして……っ!?」
「自分でもわからぬ。ただ、これが“答え”というやつなのかもしれぬな。過去に戻ってやり直すことも、永遠を望むこともないけれど、それでも、確かなものはあったのじゃ」
もう一度、ミリアの両肩を掴んで真っすぐに見つめる。
「心は、想いは、道半ばで倒れても誰かに受け継がれる――そう信じさせて欲しい。おぬしの言葉で……おぬしの心で、おぬしの“今”で」
ミリアはぼろぼろと涙を零しながら歯を食いしばり、ただ一度だけ頷いた。
声にはならなかったから、恐らく不十分だ。ナディアのリクエストには、答えられそうもない。
こんなに悲しくて、ただただ苦しくて……。
逃げ出したくて、堪らなくて、何かを失うと認めなければ進めぬのが未来だというのなら。
誰かの想いを受け継ぐことの、なんと重く……なんと切ないのだろう。
「笑っておくれ。わらわはその笑顔が、何よりも好きだったのだから」
●
突然ですが、わたしは思うんですよ。
世界には大きな運命の流れがあって、それは一人の人間にはどうしようもないのかもしれない。
一生懸命頑張っても、どれだけ泣き叫んでも、思い通りにはならないのかもしれない。
でもそれは、“何もしなくていい”理由にはならないよね?
たったひとつ、叶えられた願いだけに価値があるというのなら。
叶えられなかった数多の願いは、無価値だというのなら。
生きることも、考えることも、何もかもが台無しになっちゃうから。
だから、意味とかじゃないんだよ。
最終的にどうなったか、とかじゃなくてね。
勝ったとか負けたとか、認められたとか認められなかったとかでもなくてさ。
今この瞬間、生きているあなたが……。
あるいはあなたの大切な友達や、家族や、恋人たちと一緒にね。
感じて、想って、何かを好きになったり憎んだり、そんな当たり前のことが、素晴らしいんだよ。
それが、生きている人にしかできないことなんだよ。
わたしは、シュレディンガーに代わって観測する。
この世界に生きる人たちが下す、かけがえのない――決断を!
(文責:フロンティアワークス)

ナディア・ドラゴネッティ

バニティー
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の宣言は妥当なものだ。バニティーはそう思う。
自分の世界をこれまで長らく侵略されてきたのだから、怒りや憎しみも相応であろう。
失われた命、歪められた過去、その上未来まで奪われようというのだ。
生物種であれば当然、そんな道理は受け入れられまい。だが――。
「ただし、可能な限り正面衝突は避けたいと考えておる。その為におぬしに相談に乗ってもらいたいのじゃ」
少なくともナディアの瞳は澄み渡っている。
きわめて冷静で、機械的過ぎるきらいすらあった。
ハンターへの結果発表を前に、バニティーは再びリゼリオを訪れ、ナディアの私室へと招かれた。
今回はドナテロも他の大精霊もいない。完全なナディアとのタイマンである。
「いいよ。どんな相談?」
「それが色々あってな。ハンターに広く意見を募ったところ、問題の解決に寄与しそうなものがいくつかあった。その精査を頼みたい」
「わー。じゃあこの書類の束ってもしかしてソレ?」
相向かいに着座する二人の間には書類の塔がそびえ立つ。
「なははは……紙も積もれば山だねぇ?」
「そっちはベアトリクスらと確認済み。おぬしに見せたいのはこっちじゃ」
紙束を受け取り、バニティーはパラパラとめくってみる。
最初はくりくりとしていた眼差しが、徐々に険しいものへと変わっていく。
「……ちょっと待って。まさかハンターは、本当にファナティックブラッドまで救って見せるつもりなの?」
ハンターの意見は、大抵の場合シンプルだ。
敵だから倒す。問題があるから倒す。他の選択はできないから倒す。
十分な理由だし、それが真実だろう。だがその中に、闘いを回避せんとする意志があった。
それをバニティーは「救済」と捉えたが、ナディアは敢えて否定する。
「仮に結果的にそうであったとしても、望んでいるのは犠牲を抑えた勝利じゃ。“そもそも戦わないで済むならそれが一番”……バニティーも言っておったじゃろう?」
「それはそうだけど……」
眉を顰め、バニティーは思案する。

ファナティックブラッド
それで解決するのならそれが一番――確かにそうだろうが。
「わたしならお父様に取り次ぐことは出来るよ。でも、お父様は簡単に説得に応じる人じゃないわ」
「それは何の解決策も提示できない場合……じゃろう?」
ひとつひとつの意見には、良い所も悪い所もある。
それだけでは実現できないという欠陥。だがそれも、多数の中に繋ぎ込むピースがある。
すべてのピースを繋ぎ合わせれば、第四の未来も見えるかもしれない。
●
「ひとつずつ解決しよう。まず、なぜファーザーは他者の説得に耳を貸さぬのか?」
説得とはお互いの妥協点を探すということだ。
ファーザーの目的を達成できないような一方的な説得は意味がない。
「逆に言えば、ファーザーの目的を部分的にでも達成できるのなら、説得の余地はある」
「部分的にって……。お父様の目的は全宇宙の救済だよ? そして、有限を超えた永遠への再誕……普通に考えて無理じゃない?」
「無理じゃな。なので、諦めてもらう点を絞る。“全宇宙”と“永遠”じゃ」
そもそも、永遠なんてロクなもんじゃない。それは彼だって理解しているはず。
自分が救おうとしたものを見捨てられないのが理由だというのなら、見捨てずに済む方法があればよい。
「ファナティックブラッドには、宇宙再誕の為の正マテリアルが既に存在している。永遠ではなくとも、全宇宙ではなくとも、新たな“世界”を作れぬだろうか」
初期設定された目的があまりも大きすぎて辿り着けないだけで、妥協すれば部分的にその目的を達成できるかもしれない。
それが成れば、ファナティックブラッドは役割を終え、停止するのではないか?
「クリムゾンウェストでもリアルブルーでもエバーグリーンでもない、第四の世界を作るってこと? それなら確かに……交渉のカードにはなるかも。でも、問題はどうやってそれを実現するかだよ」
世界を作りますと言って、ハイ出来ましたというのなら苦労はない。
大精霊すら、世界の始まりにただ存在しただけのものだ。自ら世界をゼロから生み出すことはできない。
「その前に、再誕に必要なものを確認したい」
「えーと……元になる世界の情報。それから、莫大な正のマテリアル。命を生み出すには負のマテリアルじゃダメだから。あとは……なんだろう? わたしにはわからないけど……」
「“それ”こそ、邪神に不足している最後のピース……という考え方もできる。一度質問を変えよう。邪神が世界を取り込むためには、その世界の“同意”が必要なのじゃろう?」
「うん、そうだよ。あなた達は同意しなかった――古代人が、だけど――から、こうやって戦うことになってる」
「ハンターに言われたのじゃ。“諦めなければ邪神と一つにはなれない。だが、絶望や諦観では未来を作れない”と」
矛盾――。
未来を求めようというのに、諦めて一つになる。
これは明確な意志の矛盾だ。未来を人任せにし、“どうにでもなれ”と匙を投げた。
「もしかして……それが最後の鍵だった?」
「諦める為ではなく、真に未来を求めて邪神とひとつになったなら、我々は宇宙を再誕できるのかもしれない。ハンターはそう言っていた」
「でも、それは危険すぎる賭けだよ」
「じゃな。故に最終手段であるとして――つまり、未来を求める意志。これが世界の誕生に必要なのではないかと考える」
元々、世界はヒトの意思と密接に関係している。
観測者が存在するから世界はあり、観測者の意思に応じて変化する。
大地も空も時の流れさえもが、観測者ありきで成立する概念だ。
“誰もそれを見ようとしなければ、そこには何もないのと同じ”なのだから。
「今、邪神の中に存在する人々……シェオルの意志は、本当に未来を求めていると言えるのじゃろうか?」
彼らは既に己の願いも忘れ、“持たざる者”として命を羨み、未来を妬み、ただそれを壊すことだけに囚われている。 繰り返される永遠も、救われぬもの達の憎悪も、ファナティックブラッドを狂わせた理由に数えるべきだ。
「以前バニティーが“お父様は毒電波と戦っている”と言っておったな。それは――“未来を否定する者たちの意思”のことではないのか?」
あるハンターはそれを“反動存在(ルサンチマン)”と呼んだ。
邪神翼のひとつ、リヴァイアサンが救おうとして救えなかったモノ。
命の誕生と存続を否定する。闇に堕ちたヒト、即ち観測者の漆黒の意思である。
「え……嘘でしょ!? わたし、そんな説明一言もしてないのに……どうしてわかったの!?」
「まあ、ハンターも色々経験しておるからな。つまり、ファーザーは――」
「そうだよ。お父様は、世界再誕を否定する負の力を制御しようとしているの。それはお父様の力を以てしても解決できないほど重くて深い」
「だからファーザーはそれにつきっきり、ということか……なるほどな。ならばそれが宇宙の再誕を妨げているのは明白じゃ」
もしも、ファナティックブラッドの主導権が既にファーザーにはなく。
夥しい数の悪意により、邪神と呼ばれる怪物が突き動かされているのだとすれば……。
「クリムゾンウェストが取り込まれたところで、宇宙が再誕できるとは思えぬな」
「……そうだね。だからわたしは、ファナティックブラッドというシステムは消滅させるしかないと思ってた」
「いや。なればこそ、世界救済機能(ファナティックブラッド)は消滅させてはならない。それを扱う知識を持つファーザーも、倒してはいけない」
彼の大罪を赦すことはできない。
だが、その能力は今、この世界を守るために必要だ。
「再誕を防ぐシェオルの意志を祓い、ファーザーを味方につけ、再誕の力を正しく起動できれば、第四の世界を作ることは不可能ではない。その力、勝利の為に利用させてもらう」
「……うん。状況の改善に繋がる。これならお父様も話を聞いてくれるかも……!」
ぱあっと、バニティーが瞳を輝かせる……が。
「でも……歪虚に堕ちてしまったお父様に、世界を生み出すほどの正のマテリアルを扱えるかな……」
邪神の中枢、ファーザーが座する地点は宇宙再誕の中心座標。
世界を生み出す儀式を行うのには最適の場所だが、そこに蓄積した莫大な正マテリアルを負の存在であるファーザーが適切に扱えるかは疑問が残る。
「お手伝いはしてくれると思うけど、核になるモノが必要だと思う」
「その時は、わらわ……というか、クリムゾンウェストがその役割を果たそう」
クリムゾンウェストは、元々異世界を喰らう性質を偶発的に得てしまった世界だ。
過去に邪神の侵攻を受け、終わりを否定し、逃げ回りながら、傷つきながらも生き延びようとした結果の変質。
生物が命を繋ぐために環境に適応することを進化と呼ぶのなら、まさにそれだろう。
進化したクリムゾンウェストは、ファナティックブラッドとよく似ている。とても偶然とは思えない程に。
「再誕のエネルギーさえ確保して、場のコントロールをファーザーに補助してもらえば……恐らく可能じゃ」
「おそらく……」
「だ、誰も試したことすらないからな……。トマーゾに訊いてもわからんかった。だが、わが身に宿る神は、やってやれぬことではないと答えた」
クリムゾンウェストの大精霊は、守護者を通じて多くの人々の願いを受け入れた。
エバーグリーンやリアルブルーを取り込んだからこそ、そこに脈々と流れる世界の在り方を理解し、ひとつにする力を手に入れた。
「わらわの相棒ならできる。いや、あやつにしか出来ぬことじゃ。あやつだけが、邪神の中に散らばる数多の星々を一つに束ね、第四の世界を創造できる」
「宇宙をバラバラに再誕させるのではなく、ひとつにした世界を作る……? リソースも少なくて済む……確かに、それなら……」
「そして世界が再誕してしまえば、敵対する理由など何もない――我らの完全勝利じゃろ?」
これは善悪の話ではない。
最も犠牲少なく勝利する効率的な方法。
世界を救済するために何ができるのか考えた結果だ。
「無論、今はただの理想論じゃ。戦いは避けられぬじゃろう」
「……そうだね。それは、あなたたちが邪神に勝利できるだけの力を持っているという前提だから」
「故に次の戦い、邪神に囚われたすべての世界に伝えたい。我らの力を、信じるに値する――未来を求める意志を」
倒すだけではきっと足りない。
消滅させるにはキリがない。だから、気づいて欲しい。わかってほしい。
何かを憎むだけではなく。過去を振り返るだけではなく。
弱さの殻に閉じこもり、自らの手で可能性を閉ざさないで。
「彼らに問いたい。本当にそのままでいいのか、と。望んで地獄に留まる闇ならば、討つも已む無し。だが、共に未来を求められるなら……」
「仲間に出来る? わたしみたいに」
「できるとも。例え相容れぬ者同士でも、たった一時の幻でも。その意思を示すことこそ、世界再誕に不可欠な最後のピースなのだから」
●

シュレディンガー

マクスウェル

ラプラス

イグノラビムス

クドウ・マコト

クリュティエ
「話はわかったよ。正面衝突より遥かに勝算があると思う」
「ちなみにダメだった場合のリカバリー策も色々あるので、以前に比べるとだいぶ希望が見えたぞ」
犠牲が出ることに変わりはない。戦いも避けられない。
それでも確かに何かが変わったような、そんな気がした。
「不思議だね。ハンターはどうしてこんな答えを導き出せたんだろう?」
「ん……まあ、連中は一人ではないからな。あるハンターが言っておったよ。ファーザーの悲劇は、独りで抱え込んで仲間と相談しなかったことだ、とな」
その言葉にバニティーはなんとも言えない、悲しげな笑みを浮かべる。
「……だね。わたしやシュレディンガーが、もっとちゃんとしてれば良かったんだけど」
「あー、いや、そういう意味では……」
「ちゃんとわかってるよ。でもね、やっぱりわたし達は失敗したんだ。言葉を重ねることも、想いを伝えあうことも、恐れてしまった。ハンターさんの言う通りだよ。わたしたちは何よりもまず、お互いを頼るべきだったんだ。その過去から逃げちゃいけない。だから今度こそ、わたしは……」
悔しさを堪えるように拳を握りしめ、少女は頭を振る。
「お父様にこの話をしてみるけど……すぐには聞いてくれないかも」
「わかっておる。じゃからこそ、次の戦いで証明して見せるのじゃ。永遠に立ち向かうヒトの意思をな」
ナディアは咳ばらいをし、改まってバニティーと向き合う。
「バニティーには、他にも説得してもらいたい者がいるのじゃ」
「うん……クリュティエたち、だよね」
黙示騎士はファナティックブラッドという世界に紐づいた守護者だ。
もしもファナティックブラッドに住まう人々を救える可能性があるのなら、味方につけることもできるかもしれない……そう考えたのだが。
「たぶん、黙示騎士は仲間に出来ないと思う」
マクスウェルはハンターとの決着を望んでいる。
元々世界を守るために戦っているという意識も薄い。
「お兄ちゃんは話せばわかるってタイプじゃないよ。仮にハンターの方が正しいと理解しても、闘いによる決着を好むと思う」
ラプラスは自分の意思や感情で戦っているわけではない。
ファナティックブラッドという世界の命令に従っているだけなので説得の余地がない。
イグノラビムスはどちらかと言えばシェオル型歪虚に近い。
彼は世界の救済をそもそも望んでいない。人類に絶望し、その悪性を滅ぼそうと戦っている。
「一番話が通じる相手だけど、行動理念は相容れないと思う」
クドウ・マコトは、もしかしたら説明すれば手を貸してくれる可能性はある。
だが、猜疑心が強い彼が口先だけの理想論を鵜呑みにするとも思えない。
何らか現実的に問題解決を態度で示さない限り、理解は望めないだろう。
テセウスは新米の黙示騎士であり、邪神との繋がりが薄いだけあって説得の余地はある。
だが、テセウスは黙示騎士を転移させる能力を持ち、チームの中で重要なサポート役だ。裏切りを他の黙示騎士が許さないだろう。
「厄介なのはクリュティエで、たぶん全然話にならない」
クリュティエは冷静そうに見えて、黙示騎士の中で最も感情的に物事を考えている。
仮に多くを救える可能性があるとしても、少しでも犠牲になるものがある、何かを見捨てなければならないとなった時、冷静ではいられない。
「見捨てるという行い自体が、あの子のトラウマなんだよ。邪神の力で宇宙が再誕して、全てが救われる……その未来に縋らなければ心を保てない」
「仇花の騎士の後悔か……」
「誰よりもあの子が自分の矛盾を自覚してるし、それに苦しんでる。あの子を止めるには、やっぱり腕っぷしで黙らせるしかないって言ってた」
「……言ってた? 誰が?」
「あなた達の助っ人だよ。前にも言ったけど、賛同者は既に邪神の中にも存在しているの」
邪神の中にいるのは、邪神により観測された――或いは作り替えられた想い出のみ。
だが条件に合致する者は、ハンターのこれまでの冒険の中にも存在したのだ。
「あの子たちの、名前はね……」
●
邪神の体内に揺蕩う様々な“異界”。
終わりの日を繰り返す絶望に埋め尽くされた世界で、仮に己の間違いに気づいたとしても、それを一体どう正せばいいのだろう?
自分は世界に馴染めていない。この法則性にそぐわないイレギュラーだと自覚して、その何人が地獄から抜け出す勇気を持てるのか。
その世界も何度目かわからない終わりの時を迎えようとしていた。
イレギュラーとして覚醒した誰かが、その終わりを何度も何度も繰り返し観測し――そしてまた絶望する。
痛みも恐怖も枯れ果て、わかりきっている終焉をただぼんやりと眺めることしかできなかった。
シェオル型歪虚の群れが眼前まで迫っても、彼は逃げるそぶりすら見せない。
当たり前だ。だって逃げ場なんてない。必ず殺される。
だったら何もしない方がいい。じっとして、膝を抱えて、両手で耳を塞いでいれば――すぐに、すぐに終わって――。
「…………どぉ????っこいしょおおおおおおおーーーーーっ!!」

カレンデュラ

ザッハーク
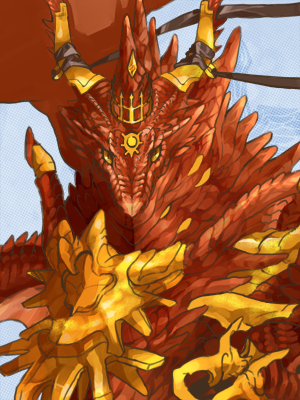
メイルストロム
空から落ちてきたソレは、大地に打ち付けた拳から放つ衝撃波でシェオルを蹂躙せしめる。
「君、大丈夫!? 怪我はない!?」
無意味な質問だ。怪我なんて、死んでループすれば治るもの。
いや、そんなことより――こいつは誰だ? こんな事象、一度だって見たことはなかった。
赤いスカートと髪を風に靡かせて真っすぐに笑うその身体は、シェオルの憎悪に汚染されている。
振り返り、歪んだ左手を差し伸べる。そうしてずっと誰かに言ってほしかった、その言葉を――。
「もう大丈夫だよ。君を――助けにきたんだ!」
手を取ろうとしたその時、少女の背後からシェオルが襲い掛かる。
だが、その刃が少女に届くことはなかった。上空から降り注いだ閃光の雨が、次々に脅威を貫いたからだ。
「勝手に先行するのは構わんが……油断が過ぎるぞ、仇花の」
「いやー、ごめんごめん。一秒でも早く“助けにきた”って言ってあげたかったもので……」
もう片方もやはり赤いシルエット。だが、こちらは明確にヒトですらない。
赤い鱗を持つドラゴンは光の翼を収め、二人の傍に降り立つ。
「あんたたちは……僕たちと同じ、邪神に取り込まれた歪虚……?」
「そうだよ。そして君と同じ、間違いを自覚した“イレギュラー”さ」
黒く闇に覆われた空に、無数の光が雪崩れてくる。
外界からの干渉を受けて異界に産まれたひずみは、巨大なドラゴンを顕現させた。
「カレンデュラ、その少年は任せたぞ。私はメイルストロム様と合流する」
「オッケー! 気を付けてね、ザッハーク!」
光の翼を広げ、赤い龍は飛び去って行く。
それを見送り、赤い騎士の少女はニマリと笑う。
「さてさて少年。君の他にもいるんでしょ? この世界を変えたいと願っているイレギュラーが」
「イレギュラー……? それが、僕たちの名前……?」
「そうだよ。世界がループする限り、ここを凌いでも解決にはならない。だから……あたしたちに力を貸して」
少女の言葉は力強く、その眼差しはとても熱い。
だからだろうか。自然と手が伸びて、闇に歪んだ腕を掴んでしまう。
「僕たちは……どうしたらいいの? どうしたら……良かったの?」
何度ループしてもわからないんだ。
終わっていく世界に対して何ができたのか。どうすることが、正解だったのか――。
「簡単なことだよ」
立ち上がった少年を、騎士は暖かく両腕で抱きしめる。
「未来を信じて、諦めないで。みんなは絶対に来てくれるから」
「みんな……?」
「私の――大事な仲間たち、だよっ!」
過去から連なる願いを、祈りを、そして命を受け継いでくれた。
だから逃げない。
何が出来るのかもわからないけれど、可能性だけは、ゼロにしちゃだめだ。
「運命には負けない。そんなものはぶっ壊せるんだって、未来に教えられたから」
●

ファーザー
そして知ってしまった。目的も願いも何もかもかなぐり捨てて、それでも他者を抹殺したいという意志を。
どれだけ長い時間を彼らとの対話に費やしただろう。
彼らは決して受け入れない。理屈じゃない。終わってしまった何かに縋り、新たな旅路すら否定する。
信じたくなかった。認めたくなかった。これが既存宇宙の出した答えだと。
人類は度し難く醜悪で、その憎悪は未来すら焼き尽くしてしまうのだと。
「今の私に……敗北者たる私に、何が出来る……?」
可能性を信じ、可能性に敗れた。
自ら命を絶ち、闇に支配され、摩耗しきった心に去来する願い。
「願い……願い、だと? まだこの私に、そんなものが許されるとでもいうのか?」
勘違いするな。オマエはもう失敗した。
出来ることなど何もない。
運命に跪き、永劫の中で泣いて許しを乞え。
たったひとつそれだけが、オマエに許された償いだ。
宇宙の果て、異世界に浮かぶクリムゾンウェストを見つめ、男は無感情な瞳を細める。
(ああ――それでも。それでも許されるのなら……どうか最期に見せてほしい)
ぼんやりと口を開き、魅了されるように。
そっと、傷だらけの手を伸ばす。
「可能性を……宇宙の理すら覆す、高潔な魂を。この願いを託すに値する――命の答えを」
選ぶ事すら躊躇うような、重く苦しい血の宿業。
唯一無二の正解も、約束された未来もない。
苦しみの中、それでも選び取ったというのなら。
肯定しよう、その決断を。
振り返るなかれ。
ここに――第四の運命は開かれた。
(文責:フロンティアワークス)

南雲雪子

ダニエル・ラーゲンベック

トマーゾ・アルキミア

トモネ・ムーンリーフ

ユーキ・ソリアーノ

ベアトリクス・アルキミア

大精霊クリムゾンウェスト

ルビー

ナディア・ドラゴネッティ

ミリア・クロスフィールド
南雲雪子がそう結ぶと、広い会議室には静寂が訪れた。
どの作戦も作戦などと呼べないほど、強引かつ無茶苦茶なものばかり。
どれだけ議論を重ねても、それで勝ち目が増えているのか減っているのか。最早誰にもわからなかった。
「全戦力を投入しての短期決戦……ま、それしかねぇわな」
ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は大きな図体を丸めるように腕を組み、深く息を吐いた。
サルヴァトーレ・ロッソならびにダニエルの役割はひとつだ。
何があろうとも絶対に、ハンター部隊を邪神の中枢へと送り届けること。
二言はない。その任務は“何があろうとも”――どれだけの犠牲が出ようとも、ロッソが沈もうとも、絶対である。
「ワカメ頭やらなにやらに改造してもらったロッソだが、いくらなんでも今回は決死戦だ。行きはいいが……ハンターに帰りを保証してやれんのが心残りだ」
5年程度の付き合いだが、ロッソは彼にとって思い入れのある船となった。
何度もハンターと共に戦場を飛んだし、トンデモバトルも繰り広げた。
改修を繰り返し、今や人類の兵器としては最大最強クラスとなったロッソでも、今回の戦いは厳しいだろう。
「確認するが、邪神の体内への突入にはロッソを使うしかないのか?」
「正しくはロッソ単体では不可能じゃな。邪神の外殻を破壊し、空間の裂け目から内部へ突入する――大精霊の力も併せねばな」
トマーゾ・アルキミア(kz0214)が補足する通り、基本的に邪神の外殻破壊は生半可な火力では達成できない。
青龍を搭載したロッソによる主砲(ドラゴンブレス)に大精霊のマテリアルを上乗せして破城槌と成すのだ。
「やれやれ……ロッソが潰れたらそもそも作戦終了か。シビアすぎるぜ」
「邪神に到達するまでの旅路は、我らムーンリーフの象徴――ニダヴェリールの守りを当てにしてもらいたい」
トモネ・ムーンリーフは力強く語る。
「ニダヴェリールのメンテナンスは完了している。反重力バリアの絶対防御は、トマーゾ教授の調整で更に高まった。いかに邪神が強力であろうとも、必ず守り抜いて見せよう」
「計算上は邪神翼クラスの対界攻撃であるメギドフレイムも完全の無力化出来ます。リアルブルーを取り戻すため、私達が希望の盾となりましょう」
ユーキ・ソリアーノは紆余曲折を経て、現在はニダヴェリールの操縦をトモネと共に任されている。
「もとよりニダヴェリールは地球防衛のため、そして世界に希望をもたらすために作り出されたものだ。至らぬ我らだが、財団の悲願を叶えさせてほしい」
「ニダヴェリールの絶対防御であれば、少なくとも一方的に遠距離砲撃で殲滅される危険性はなくなります。心より感謝致します、トモネさん」
「礼には及ばぬ。むしろ、感謝しなければならぬのはこちらの方だ」
雪子の言葉にトモネは穏やかに微笑みを返した。
「その後は?、私とリアルブルーくんの出番ね?!」
「ああ……一応最後にもう一回確認するけど、君ってば本気でアレやるの?」
「本気(マジ)も本気(マジ)よ?!」
ベアトリクス・アルキミア(kz0261)が元気よさそうなので、いっそうリアルブルー(kz0279)は引く。
リアルブルーは地球の凍結を部分的に解除し、機能停止状態で保存されている「使徒」の一斉起動を行う。
これで地球側からも挟撃を行い、邪神の戦力を分散する狙いだ。
一方、ベアトリクスはというと……。
「いや、もう考えるのはやめよう……君がいいって言うんだもん、僕にはどうしようもないよ」
「ベアトリクスさんがすみません……」
「え?? なんでルビーが謝るの??」
「なんとなくですね……。ただ、例のアレをやることで不足する能力は、私がバックアップしますので」
ルビー(kz0208)がぺこぺこと方々に頭を下げるも、ベアトリクスは気にしない様子であった。
「本当にサイコパスだな……」
「ま……まあ、邪神という超質量の存在に対しては有効だとは思うがの」
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)も若干引き気味でフォローしつつ。
「そして、宇宙空間を一気に突っ切って邪神の腹を食い破る、と。そして守りに関しては、四大精霊の力を借りる」
これまでなるべく力を温存してきた四大精霊だが、その力は並の精霊とは比べるべくもない。
その四体の力を使い、引き続き邪神の侵入経路をなるべくグラウンド・ゼロに限定し、防衛線を構築する。
だとしても、世界各地に出現するシェオル型の数は激増する見込みであった。
「世界各地への警告と避難誘導は続けていますが……それこそ世界規模の災害ですから。避難所を用意するのも一苦労です」
ミリア・クロスフィールド(kz0012)の言う通り、グラウンド・ゼロに集めきれない転移攻撃は世界各地にランダムで行われることになる。
邪神を倒したところで帰るべき世界が亡くなっては意味がなく、必然的に各国の戦力は自国の防衛に当てる格好だ。
かつ、ハンターなどの主戦力はグラウンド・ゼロの防衛または邪神体内への突入に費やされる。
「各地の防衛には、元強化人間の方々や、リアルブルーから避難してきた新人ハンターさんが当たることになります」
「シェオル型相手に戦闘経験の浅いハンターをぶつけねばならぬな……じゃが、それをしなければまさに虐殺となろう」
シェオル型はとにかく人間の殺傷に拘っている。
自衛できない村や町に現れでもしたら、老若男女問わず皆殺しにされかねない。
本来、戦闘力の高いシェオル型はなるべく優れたハンターで討伐すべき相手であり、覚醒したての新入りでは手に余る。
それでも、村々の自警団が相手をするよりはいくらかマシ――だと思いたい。
「邪神との対決を選んだ時点で犠牲は避けられないだろ。世界が滅ぶかどうかって時なんだ。例え力が及ばなくとも、戦いたいという連中の気持ちも無視するべきじゃないさ」
リアルブルーは大精霊だが、弱者の気持ちもよくわかる。
臆病者と自負する少年は、だからこそ人の弱さも、弱いからこその想いも理解していた。
強化人間たちは、元々は自分の世界を人任せにしたくなくて立ち上がった勇敢な人々だ。
リアルブルーから転移してきたばかりの新米ハンターも、自分に出来ることを探して力を求めたはずだ。
「弱いやつにだって、頑張る権利はある。僕はハンターみたいには……多分一生なれない。どうせずっとクヨクヨするし、覚悟も決まらないし、赦せないだろう。それでも彼らみたいになりたいと、少しでも近づきたいと、そう願う権利はあるはずだ」
だから、弱さを否定してはいけないと思う。
弱さは罪ではないし、強さは正義ではない。
力があるとかないとか、効率がいいとか悪いとか、安全とか危険とかそういうことではなく。
「ひとりひとりに出来ることをしたいし、させてあげたいんだ。たとえ結果としてそれが犬死であっても」
「……そうじゃな。難しい話じゃ。なまじ力を持つと、どうしても皆を守ってやりたくなる。救ってやれると思い上がる。弱者がそれをどう感じるかなど、お構いなしにな」
ファナティックブラッドは優しいゆりかごだった。
弱い者は弱いまま、圧倒的な力で管理・保護される世界だ。

ファーザー
「彼らは英雄にも救世主にもなれないのかもしれない。それでも――“それでも”と足掻くことは、間違いなんかじゃない」
「そうね。心配だけれど、みんなの力を信じましょう。この世界を守りたいのは、みんな同じだもの」
ベアトリクスはそう言ってから、何かを思いついたように指を鳴らす。
「そうそう! もっとみんなの力を集められるように、今から準備を進めましょう」
ここから先の戦いは大精霊という決戦兵器をぶっ放しまくる超常の戦争だ。
だが、その大精霊は星の中枢にして化身。その力の制御には多大なロスが生じている。
ナディアという依り代を得ても尚、クリムゾンウェストは制御を完全にできぬままだ。
「クリムゾンウェストに住まうすべての人に、祈ってもらいましょう。たったひとつ、同じ祈りを――世界を守りたいという祈りを重ねて」
大精霊の力は漠然としたものだ。
それになんらかの方向性を与えるのはヒト――即ち星の観測者の意思である。
汚染された地で浄化の儀式や祭りを行うことで、その地に大精霊の力が満ちて清浄になるように。
世界中すべての観測者の力を、同じ目的に収束することができれば――。
「大精霊や守護者にさらに力を与えることができるかもしれぬな。じゃが、どうやって人々の心を一つにまとめる?」
「うーん、そこはまだ考え中?。何かいいアイデアがあればいいんだけどねぇ」
それこそこの小さな会議室で唸っているより、世界中にやり方を問うた方が良いかもしれない。
力がなくとも、守られるばかりであったとしても、世界の終わりに伝えたい想いのひとつやふたつ、誰にだってあるはずだ。
たとえ愚かと笑われようとも、運命に抗いたいという想いを毟り取るのは罪なのだ。
(生きていて欲しいと……そう願うことすら……)
ちらりと、ミリアはナディアの横顔に目を向けた。
生きていてほしい。ただ、なんでもいいから生きていてほしい。
けれども、“ただ生かす”ことは、大切な人の尊厳を守れているのだろうか。
命を惜しまず戦うことを、美辞麗句ではどうしても片づけられそうにない。
ああ、それでも。それでも、それでも――それでも。
戦わなければ死んでしまう。その身が無事であったとしても、きっと心が砕かれて。
(だから、私は……もう、泣かない)
視線に気づいたナディアが微笑む。不安など何一つないかのように。
その笑顔を、答えを、踏みにじることだけは……決して。
剣を振り回すだけが“戦い”ではない。
苦しくても理解し、認めよう。
祈りを捧げ、遠い未来にも語り告ごう。
(弱者の戦い方。私はもう、ちゃんとわかったから)
(文責:フロンティアワークス)

バニティー

クリュティエ
宇宙を漂うサルヴァトーレ・ネロの展望室は、いつしか黙示騎士のたむろする場所となっていた。
星の海を望むその場所で、集めた黙示騎士にバニティーは説明する。
第四の世界として、ファナティックブラッドの再誕を目指すハンターたち。
同じ道を往けるというのなら、黙示騎士にも共に戦ってほしいという願い。
バニティーの話を聞き終え、真っ先に口を開いたのはクリュティエ (kz0280)だ。
「……その話、どうやら以前より決まっていたようだな」
バニティーから聞いてたわけではないが、彼女に促されて足を運んだリゼリオでクリュティエは説得を受けた。
出来過ぎた流れであるからして、バニティーが一枚噛んでいたのは間違いないだろう。
「バニティーは我らを裏切ったのか?」
「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。わたしはただ、一番いい方法を探したいだけ。騙すみたいな格好になったのは、悪いと思ってるけど……」
「……そうか。そうだろうな。確かにお前の判断は適切だ。予めそうだと知っていたのなら、我はリゼリオに行かなかっただろう」
「行ってみて、どうだった?」
「どうもこうも……」
腕を組み、クリュティエは苦し気に眉を顰める。
「――どうにもならない。それもお前はわかっていたはずだ」
クリュティエの存在理由が「すべての救済」という無茶である以上、交渉の余地などない。
だが、話し合いの中で徐々にクリュティエは己の矛盾にも気付い始めていた。
「わかっているのだ。我の願いは前提からして壊れている、と。最終的には全てを救える……邪神にはその力がある……奇跡が起こることを前提に我はここにいる。だが仮に、奇跡などないのだとしたら……夢から目覚め、当たり前の結果に目を向けなければならないとしたら……」
きつく目を瞑り、そして女は悪夢を払うように頭を振る。
「わかっていても、我にはできない。この夢が、理想が、奇跡に縋ることだけが、たったひとつのよすがなのだ」
「クリュティエ……」
「教えてくれ、バニティー。どうしたら……ヒトは夢を諦められる? 誰も我に、諦め方なんて教えてくれなかったのだ……」
夢は……希望は、ほとんどの場合、叶わない。
当たり前のことだ。みんなの夢は同時には叶わないから、勝者と敗者という二つに分けられる。
すべてを救えないのはそれと地続きの理屈だ。何かを成すということは、何かを成せないということ。
「諦めたくないんだ。諦めてしまったら、我は……どうしたらいいのかわからない。自分がここにいる理由さえ、失ってしまう」

テセウス

ラプラス
しっかりしているようで、彼女はまだまだ幼い。良し悪しは別としても、その願いは純粋だ。
ハンターと触れ合い、世界を知った今だからこそ、彼女の苦しみも痛みもよくわかる。
(……無理だよ。俺は黙示騎士なんだ。シュレディンガー様から役目を与えられたのに……仲間を見捨てて、ハンターと一緒になんて……)
テセウスもまた、ハンターと話をして答えに苦しむ者のひとりだった。
しかし少なくとも、彼は彼自身の役割を簡単には捨てられない。自分一人だけなら、気ままに何かを選べたかもしれないが……。
そんな時だ。話を聞いていたラプラスが声をかけたのだ。
「ふむ。我にはよくわからないのだが……戦いたくないというのなら、戦わなくてもよいのではないか?」
「え!?」
割と大きめの声を出して反応したのはテセウスの方だった。
「いやっ、でも……ラプラスさんは気にしないんですか? 裏切り……だと思うんだけど」
「裏切り……というのは、何に対する……だ?」
ラプラスは本当にピンと来ていない様子で首を傾げている。
「もしかしたらこの話を理解できていないのは我だけかもしれないな。確認のために、我の主観的な判断を聞いてもらいたい」
バニティー、クリュティエ、テセウスが「どうぞどうぞ」と促す。
「まず、我は特にこの戦いに何の意義も見出していない。我は星の防衛装置として生まれ、その性質のままに邪神の一部となった。故に邪神を守るのは我の基本設計によるものだ。それに対し、義務感のようなものは覚えていない」
「えー? それって義務感じゃなくてなんなのさ?」
「うむ……ヒトの基準でこれをなんと表現するのか我には不明だが……ともあれ、“やめたいと思い、そうできるのなら、やめてもよい”と感じている。少なくとも、嫌々戦うことはないと思う」
『ラプラスの言い分は尤もだ。そもそも我ら黙示騎士と呼ばれる邪神の守護者は、共通の目的意識の下で統率された軍団ではない』

イグノラビムス
ひそやかに驚愕するクリュティエとテセウスである。
『私の立場からも話をさせてもらおう。私は正直、クリムゾンウェストをこのまま滅ぼすべきなのか、その解に困窮している』
「それって、クリムゾンウェストを手伝ってもいいってこと?」
『そこまで安直ではないが……少なくとも、私はこの戦いの結末を見届けたいという欲求に取りつかれている。ヒトとして彼らがどこまでやれるのか、その答えを知りたいのだ』
積極的な肯定ではないが、この怪物が様子見を口にするというのは凄まじい変化であった。
「驚いたぁ。あなたがそんなことを言うなんて……いったいどんな話をしたの?」
バニティーの質問にイグノラビムスは沈黙を返す。
何にせよ、彼は明確に己の立場を表明していた。
「我は特に、イグノラビムスの判断を非難しない。する必要もないからだ。我がすべきことは我のみぞ知る……そうであろう?」
「そりゃあそうですけど……でも、俺がいなくなったら皆さん困るでしょ? 自分じゃ転移もできないんだし」
「ふむ? テセウスもイグノラビムス同様、戦線から退きたいのか?」
「あ」
今はテセウスの話なんてしていないのである。
ボロを出した焦りと共にこみ上げるのは、自分の気持ちを全部言ってしまいたいという欲求だ。
「テセウスも……そうなのか?」
「いや、えっと……俺は、その……」

マクスウェル
やたらと大声でこれ見よがしにマクスウェル(kz0281)が溜息を零す。
『オマエらの愚にもつかない問答など聞き飽きたわ! テセウス! オマエ……思い上がっているんじゃないか?』
ずんずんとテセウスに歩み寄り、かがむようにしてメンチを切る。
『何が自分じゃ転移できないだ。転移などできなくても闘う術はいくらでもある! あと、オレは短い距離ならワープもできるので負けてない』
「ネロにも転移能力はあるからそりゃそうですけど……」
『フン! そもそもオレはオマエのような新米を黙示騎士としてはこれっぽっちも認めていない! 小間使いが一人いなくなったところでなんだというのだ!? オマエなどいてもいなくても同じだ!!』
「おいマクスウェル、何もそこまで言わなくとも……」
『クリュティエ、オマエもオマエだ! 会う度メソメソしおって気持ち悪い! これだから女の形状をした奴は厭なんだ!!』
間に入ったクリュティエの眼前にビシリと指を指し、マクスウェルは詰め寄る。
『闘いたくないなどと軟弱な事をぬかすヤツは闘わんで結構! 足手まといだ! とっととハンターのところへでもどこへでも、好きなところへ行くがいいわ!!』
「……そんな。我は……そんなことは……」
『えええ?????????いい!!! いちいち泣くな鬱陶しい!! ハァ????もう女は本当に腹が立つな!! いいかよく聞け。メソメソしてる時点でオマエ本当はここにいるのも嫌なのだ! そんな自分の気持ちにも気付かないなど愚かすぎて高笑いも出ぬわ!』
「だとしても……我は仲間を、皆を失いたくないんだ」
『仲間? フン、仲間だと!? 馬鹿も休み休み言え! オレとオマエがいつ仲間になったというのだ!? オレとオマエは赤の他人! 何の関係もないわ! そうだろう、ラプラス!?」
「ああ、その通りだな。我らは赤の他人だ。仲間ではない」
クリュティエはその言葉に少なからずショックを受けたようだった。
クールな顔がくしゃりと歪み、みるみる瞳に涙が溜まっていく。
「ちょっと、ひどいですよマクスウェルさん! 俺のことはいいけど、クリュティエにそんなこと……あっ、ちょ、クリュティエ!?」
クリュティエは高位歪虚特有の物凄いスピードでどこかへ走り去っていった。
『フン。ザコはザコ同士よろしくやるがいい。同じ若輩者のザコであるテセウスが慰めてやれ。それがオマエらにはお似合いだ……フハハハハハ! ハーーーーッハハハハハハ!』
困惑した様子でテセウスはクリュティエの後を追う。
そうして展望室に静寂が戻ると、バニティーが溜息をひとつ。
「……もう少し言い方ってもんがないのかな、お兄ちゃん?」
『誰がオニーチャンだ。オレは本当のことしか言っていない。あいつらを見ているとイライラして仕方がないのでな。オレはオレの道を往く。ハンターとの決戦には、オレひとりで十分よ』
「ふむ、確かに。では昔のように、我等だけで戦うとしようか、マクスウェル」
ラプラスの言葉にちらりと振り返り、マクスウェルは「好きにしろ」とだけ返した。
『マクスウェル、ラプラス。私は実は、黙示騎士という呼び名をそれなりに気に入っていてな』
イグノラビムスが低く笑いながら呟く。
『星の守護者という存在に囚われていた私にとって、悪の組織というのは少しばかり小気味よかったのだ。君たちの言う通り、私達は仲間ではない。だが、道すがら出会った君たちのことを、私はきっと忘れないだろう』
一礼し、イグノラビムスは退室する。ラプラスも既に話すことはないと、顔色一つ変えずに去っていった。
残されたのはバニティーとマクスウェル。少女は後ろで両手の指を組み、微笑みかける。
「それで? 一人で戦って勝算はあるの?」
『勝算? そんなモノ闘争には不要だ。“勝てるから闘う”のではない。“闘いたいから闘う”のだ』
「どうして? どうしてあなたは、最後まで戦うことにこだわるの?」
少女の問いかけを無視しても良かったはずだが、何故だか男は自然に答えていた。
『逃げたくないからだ』
「その結果、自分が死んじゃうとしても?」
『戦おうが戦うまいが、どうせすべてはいつか朽ち果てる。終着点が決まっているというのなら、求められるのは過程であろう――な、なんだァ?』
バニティーは背後からマクスウェルの身体にがっしりと抱き着いていた。
鎧のように硬質化した体表にぬくもりはない。それでもバニティーはすりすりと、何度か頬を擦った。
「わたしも逃げないで最後まで頑張る。だから……忘れないで。どんな時でも、あなたはひとりじゃないよ」
『はあ? なんだかわからんが、引っ付くな鬱陶しい』
「はいはい、離れますよ?だ。それで、策はあるの?」
『策ぅ? そんなもの、ひとつに決まっている』
マントを翻し、マクスウェルは高らかに宣言する。
『このオレが一番目立つにふさわしい、決戦の舞台。それが整いそうなタイミングで乱入するのみだ!!』
「それ作戦って言わないよね?」
『何ィ!?』
「強く当たって、あとは流れでお願いしますってこと?」
『まるで意味がわからんぞ?』
「クリュティエはこれからどうするの?」
「……わからない。だが、今更他の道は選べない。我に出来るのは……ただ、力で何かをねじ伏せるだけだ」
クリュティエとテセウスは肩を並べ、通路から宇宙の景色を眺めていた。
「時々、テセウスを羨ましく思うよ。我の能力は妄念を刃と変えるものだが、お前の能力は何かと何かを繋ぐものだ」
「ああ……この眼だね?」
眼球そのものがどうというわけではないが、テセウスは情報や概念に直接繋がりそれを観測する能力がある。
シュレディンガーから引き継いだ、歪虚の中でもかなり特別な能力だ。
世界を観る能力を有する歪虚を、二人は他にバニティーしか知らない。
「ずっと考えてたんだ。この力と、あと……シュレディンガー様の最後の言葉の意味を」
実はこの観測の力は諸刃の剣なのだ。
本来の持ち主だったシュレディンガーはこの観測事象を広く、長く自己と同一化させた結果、精神に異常をきたしていた。
何もかもとひとつになるということは、自分自身の存在がどこにもなくなってしまうことでもある。
シュレディンガーはその危険性を承知の上で、テセウスに引き継いだはずだ。
「まだ答えは見つけられていないけど、ヒントはハンターにもらったんだ」
「……そうか。彼らは色々なことを知っているからな。こんな時でなければ、我も心ゆくまでゆっくりと語らってみたかった」
「そうだね。こんな時じゃなければ……ね」
諦めることも、何かを目指すことも、果てしなく険しい道のりだ。
どうするのが正しいのかなんて、結局後になってみなければわからない。
「俺、さ。やっぱり最期までこの船に付き合ってみるよ」
「いいのか?」
「ん???いや、わかんない! でも、この船にいれば大抵のことは観測できるでしょ? 俺は俺のために、まず見届けた方がいいんじゃないかなって……うん? もしかしてマクスウェルさん、そういうことが言いたかったのかな?」
「ふふふ……彼はああ見えて優しいから、な」
二人して笑い合い、それからクリュティエは目を細める。
「……そうだな。我は我のために求めよう。剣しか握れぬ愚かなこの手にも、答えはあるのだと信じて」
「うん、その調子だ! 結局俺にも細かいことはよくわかんないよ。でも、ここで降りちゃったら一生答えに辿り着けない気がする。だから、辛くてももう一息だ」
それはクリュティエへの、そして自分自身への激励。
迷ったままでも、苦しんだままでも、進むことだけはやめない。
旅の答えは、旅を終えた先にしか待たないのだから……。
(文責:フロンティアワークス)

チューダ

リムネラ
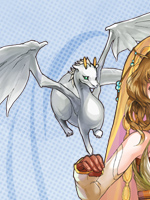
ヘレ
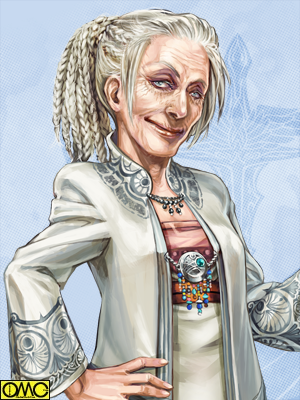
ディエナ
自称『幻獣王』チューダ(kz0173)は切り株の上に、どかりと腰掛ける。
ロクに動かない上、無駄に桃やナッツばかり食いまくる為、マテリアルどころか脂肪も蓄えていると周囲で評判になっている。
「あ、リムネラ。ちょうどいいであります。ちょっと我輩を膝枕して桃を食べさせるであります」
「え?」
辺境巫女のリムネラ(kz0018)は名前を呼ばれて振り返る。
幻獣の森が滅び、歪虚の手から逃れた幻獣達は四大精霊の一人であるイクタサの住むシンタチャシへ隠れ住んでいた。
リムネラはこの非常事態でチューダが何一つ変わらない日常を繰り広げているとは予想していなかった。
「私、デスカ?」
「そうであります。ささ、そこに腰掛けて我輩の口に桃を……ん?」
巨大な座布団のように横たわるチューダの足元に、白龍『ヘレ』が姿を見せる。
「リムネラ、イジメル。ダメ」
「違うであります。王たる我輩へ奉仕……って、暴れてはダメであります!」
横たわるチューダの腹に乗るヘレは、手荒く足で踏み荒らす。
毛並みの良さが自慢のチューダの腹が瞬く間に乱されていく。
「あの馬鹿は放っておいて良いよ」
「……大巫女」
大巫女ディエナ(kz0219)がリムネラへ話し掛けた。
広がる戦火は、確実に辺境の地を蝕んでいた。家を追われ、家族と離散した者達が助けを求めてシンタチャシへ訪れる事もある。大巫女は辺境巫女と共に彼らの支援をし続けていた。
既に疲労もピークに達しているはず。リムネラは休養を取るように進言を試みる。
「大巫女、少しは……」
「リムネラ。あいつらは今も邪神と戦っているのかねぇ」
大巫女はリムネラの言葉を遮った。
何を言おうとしているかは分かっている。
「分かりマセン。でも、きっと彼らなら大丈夫デス」
「おや、リムネラもそう思うのかい」
大巫女は空を見上げる。
遠い場所でハンター達は、今も命を賭して戦っている。
人々の為、世界の為――そして、これからの未来の為に。
「あたし達は多くの経験をしてきた。辛い事も沢山あった。
だけどね、全部どうにかなってきたんだ。今回もきっと彼らが何とかしてくれる」
「そう、デスネ」
大巫女に釣られるようにリムネラも空を見上げる。
皆が無事に帰ってくる事を、白龍と赤き大地に願って――。
●

ファリフ・スコール

ヴェルナー・ブロスフェルト
広がる歪虚の侵攻に対してどう対処するかを話し合う為だ。
如何に被害を最小限に抑えて耐え忍ぶか。知恵を絞る幹部達。
その最中、ファリフ・スコール(kz0009)の口から溢れた言葉があった。
「みんな、大丈夫かなぁ」
それは自然と漏れた本音であった。
ハンター達は邪神との戦いへ赴き、自分は辺境の地を護る為に歪虚と戦う事を選んだ。だが、それは邪神で危機的状況に陥っていてもファリフに助ける事はできない。その状況がファリフの心に不安として振り積もっていく。
「ふふ、心配ですか?」
「はい」
部族会議大首長補佐のヴェルナー・ブロスフェルト(kz0032)から受けた問いかけにファリフは素直に答えた。
こうしている今もハンター達は最後まで諦めずに戦い続ける。大転移の頃から考えれば、実に多くの経験が彼らを、そしてファリフを成長させた。だからこそ、ハンターに対する情も深くなっていく。
「今にも飛んでいきたい。そういう顔をしていますよ。無理もありません。彼らの背にはすべてが乗っているのです。心配するな、というのは酷でしょう」
「ヴェルナーさんも心配なんですか?」
「ええ、当然です」
心配と言いながらヴェルナーはいつもと変わらない笑みを浮かべている。
そして――たった一言だけ、呟いた。
「大丈夫です」
「え?」
「ファリフにはファリフのやるべき事がある。そいつをきっちり終わらせろ。それが、ハンター達にとって最大の支援になるからな」
「あ。うん、そうだね……って、あれ? 今のはヨアキムが言ったの!?」

ヨアキム
そもそもバタルトゥの意識は回復していないので、彼が喋れるはずもない。
まあ、実際彼がここにいたら、そう言いそうではあったが……。
まさか大半が馬鹿なセリフのヨアキムからまともな言葉が出るとは考えてもみなかった。
「何かおかしな事を言ったか?」
「おかしな事は何もないよ。ちょっと驚いただけ」
「そうか。それなら話を戻すぞ。
敵は侵攻ルートを未だにはっきりしねぇ。だが、マギア砦付近の動きは無視できねぇ。今までもホープへちょっかい出してやがるからな。敵の頭を抑えれば、時間を稼ぐ事は難しくねぇ」
「今日はお酒を飲まれてないんですね?」
ヴェルナーの言葉でふと我に返るヨアキム。
その言葉で今日の出来事を思い返してみる。
「あ、そういや忙しくて飲んでねぇな」
「ふふ、その調子で良い案を期待しています」
酒が抜けて頭脳をフル回転させるヨアキムを前に、ヴェルナーは満足そうに頷いた。
●

エリオット・ヴァレンタイン

ヴィオラ・フルブライト
分隊ごとに分かれた騎士たちが流動的に動くたびに敵群は乱れ、その隙を聖堂戦士が衝いていく。横槍が入らないよう周辺警戒をするのが諸侯軍で、微妙に指揮系統の異なる三軍はしかし、上手く役割分担して“敵”に当たっていた。
敵――シェオル・グレイリザードと呼んでいいだろう、灰蜥蜴人の戦士たちだ――は呪い師のような数人を中心に、大きな円を描きながら襲い掛かってくる。矢継ぎ早に別の個体がやって来ては退いていく独特の集団戦を繰り広げた灰蜥蜴人軍だったが、今や算を乱しつつあった。
「黒の隊各位、蹂躙しろ!」
「はっ!」
エリオットの指示に威勢よく応じるグラズヘイム王国騎士団、黒の隊。この場において最精鋭の彼らが一気呵成に攻め立てるや、見る間に敵は数を減らしていく。
黒の粒子を散らして雲散霧消する灰蜥蜴人どもを見つめ、エリオットは僅かに顔をしかめた。
「……掃討完了次第、周辺に偵察を出す。二人一組で二十組集めておけ」
傲慢軍との戦に忙しく、遠征できていないため、このシェオル型との交戦経験は少ないが、どうにもこれは普通の歪虚とは違うような気がする。ただ強いからというだけでなく、何か……。
いや、とエリオットは首を振り、聖堂戦士団と諸侯軍の方へ向かう。部下に回復手段の温存を指示しているらしいヴィオラに声をかけた。
「戦闘終了後、四方に偵察を放つ。そちらからも各隊数人ずつ同行してもらえるとありがたい」
「分かりました。携帯糧食等は……?」
「そう遠くまでは行かせない。ハルトフォートから三時間程度の範囲を隈なく探る」
ここから程近いハルトフォートは先の傲慢軍との戦闘で砦こそほぼ全壊したが、その傍に野営地を作って簡易的な拠点にしている。王都防衛という観点から砦はいずれ再建しなければならないが、それより邪神との戦いの方が喫緊の問題だった。
世界結界の効果が薄れているのか、あるいは物量でとにかく攻めているのか。シェオル型の出現が多くなりつつある。それに伴いエリオットは――そして聖堂戦士団も――国内の巡回をよりきめ細かくするようにしたが、巡回を増やすということは騎士たちに無理を強いるということである。
今年の初めから始まった傲慢軍との戦からここまで、ゆっくり休息できたのは戦勝祭のたった数日だけ。これで邪神との戦が一年や二年続けば、まず間違いなく騎士団は崩壊するだろう。
「三時間ですか。遠方の町村には個別に避難を促すしかありません、ね……」
「最悪、王都西部は放棄し大街道近辺に集中する必要があるやもしれぬな」
「王都の安定にはその西部の安定こそが重要……いや、卿には言うまでもないことでしたか」
苦汁の判断を口にする諸侯軍の老将にエリオットは言いかけ、口を閉ざす。
公的には蟄居させられているはずのこの老将が、歪虚討伐とはいえ外を出歩いていいのか。そんな懊悩はエリオットには既にない。使えるものは何でも使わなければ国が滅ぶ。ようやく傲慢の軛を断ち切ることができたのだ。ここで滅ぶわけにはいかない。
エリオットは剣を納め、東に目をやる。その先には王都があり、さらに向こうにはリゼリオがある。
――シェオル型が増えてきた? それが何だ。こちらは何も問題ない。だから。
生きて邪神を打ち砕け。
近々大規模な作戦を発動するであろうハンターたちに思いを馳せ、エリオットは独りごちた。
●

システィーナ・グラハム

セドリック・マクファーソン

プラトニス

ラウロ・デ・セータ

ロメオ・ガッディ

ドメニコ・カファロ

ジルダ・アマート

エヴァルド・ブラマンデ

セスト・ジェオルジ

ジーナ・サルトリオ

ディアナ・C・フェリックス

ヴィットリオ・フェリーニ

ダニエル・コレッティ

ブルーノ・ジェンマ
身じろぎ一つしてはいけない。礼拝堂で動くのは、小さな灯りの揺らめきだけ。
真摯に祈る。
一心に願う。
想えばきっと通じると、信じて。
国内の治安はエリオットと騎士団に任せた。避難や食糧配給はセドリック・マクファーソン(kz0026)と文官に任せた。システィーナにできるのは、人々に姿を見せて心を一つにすることと、こうして無事を願うこと。たったそれだけ。
『いつまで続けるつもりだ?』
脳裏に響いたのは節制のプラトニスの声。システィーナは内心で返す。
――平穏が訪れるまで。お邪魔かもしれませんけれど、それまで日参させてくださいませ。
『セッセェイ……それもまた一つの戦、か』
ハンターたちはもうじき邪神との戦に赴くと聞いている。詳しい作戦は知らないけれど、おそらくとても難しいものになるだろう。
その戦いを手助けすることは、システィーナにはできない。けれど、だからこそ思うのだ。せめて彼らが帰る場所を守っていようと。そして帰ってきた時にはこう言うのだ。おかえりなさい、と。
――だから、光よ、どうか決して折れぬ力を彼らに与えたまえ。
●
壁に掲げられたコインレリーフの下で、卓を囲む面々の手が一斉に上がった。
「それでは、参謀本部提案の本土防衛案を全会一致で可決ということでよろしいですかな」
評議会議長、ラウロ・デ・セータ(kz0022)の宣言に挙手は拍手へと変わる。
それを受けて、傍らに控える同盟軍将校が礼を示した。
同時に議場に張りつめていた空気がふっと抜けて、ポルトワール代表ロメオ・ガッディ(kz0316)は真っ先に大きなため息をつく。
「正直こういうことはからっきしなので提案には賛同するしかないのですが、不安は募る一方ですな……」
「協会も各都市に魔術師を派遣する。派遣と言っても、みな自分の故郷への自主的な加勢であるがな。少しでも心労を払えればよいのだが」
「ああ、いえ、実力を疑っているわけではなくてですね……その、相手の存在がでかすぎて、いまいちイメージが分かんのです」
ドメニコ・カファロ(kz0017)の進言に、ロメオは苦笑しながら答える。
彼だから口にできたようなものの、実際のところその不安はここにいる――いや、同盟に住む誰もが感じていることだ。
会長であるジルダ・アマート(kz0006)はまだ目を覚まさない。
彼女が起きた時世界がなくなっているなんていうことは、協会の魔術師たちにとっても本意ではないのだ。
「各都市に陸軍師団と海軍艦隊を配備。加えてヴァリオスは『ルナルギャルド号』を旗艦とした本土防衛艦隊。沖合には哨戒船と連合艦隊を配備――我々都市同盟にとっては過去最大の作戦となりますね」
「加えて連合軍へも部隊を送るのでしょう? 各地の部隊へは一般の兵士さんも……本当に、総力戦なのですね」
ヴァリオス代表エヴァルド・ブラマンデ(kz0076)とフマーレ代表サンドラ・ボナッタが、資料へ再度目を通して小さく唸る。
「僕らの願いは市民の生活が守られる事……ですが、力ある人たちに委ねているばかりにもいきません」
ジェオルジ代表セスト・ジェオルジ(kz0034)が、ハッキリとした口調で発言した。
ジェオルジはちょうど夏野菜の時期だ。
各都市へと流通するために各村を挙げて収穫に励んでいる。
フマーレも消耗が激しい日用品の急造に明け暮れている。
それをヴァリオス商人が持つ最も効率がいい流通ルートに乗せ、ポルトワールの海商たちがそれらを担う。
これはカネで独立を買った都市国家としての意地でもある。
この戦いを越えた先にはじめて、自由都市同盟は真の独立を果たしたと言えるのかもしれない。
● それから数日後、通い慣れたロッカールームでジーナ・サルトリオ(kz0103)はパンパンになった鞄を覗き込む。
「起動キーよーし。IDよーし。着替えよーし。これは、えーっと……あっ、ゲーム機か!」
「そんなの持って行ってどうするのよ」
「えー、結構いいシミュレーションになるんですよこれ」
呆れた様子のディアナ・C・フェリックス(kz0105)をよそに、ジーナはゲームが入ったポーチを底に押し込む。
「何でも良いけど、そろそろ時間だから遅れないことね」
「はーい」
ジーナは先に出ていったディアナを見送ると、ロッカーの扉に手を掛ける。
そっと閉めようとして、裏に張りつけた1枚の写真が目に入った。
この間の温泉旅行でみんなで撮った記念写真――ハンター達と並ぶ自分と、仲間達の姿がそこにあった。
ジーナはそれを鞄に詰めようと手に取ったが、すぐにやめて扉へ戻す。
「……ここが帰ってくる場所だもんね」
そう呟いてロッカーを閉めると、彼女は重い鞄を背負った。
「遅いぞジーナ」
「ゴメン、ヴィオ大尉」
ハンガーへ到着すると、ディアナに加えてヴィットリオ・フェリーニ(kz0099)も準備を終えて待っていた。
外にはキャリアーに積み込まれたCAMの姿。
傍には整備スタッフたちがざっくばらんに集まっている。
「あ、ジーナ来た?」
隅の方でタバコを吸っていたダニエル・コレッティ(kz0102)は、よっこらせと腰を上げた。
「それじゃ、行きますか」
「はい!」
ジーナは元気に返事をして、オイルの匂いが染みついた建物を後にした。
●
ヴァリオス広場に大勢の人間が集まっていた。
ひときわ目を引くのは白と黒の2色に染まる軍服を身に纏った同盟軍の兵士たち。
周りに雑多に集まるのは同盟を拠点にしていたり、居合わせたハンターたちだ。
そのさらに外、辺りの建物の軒先には見物の市民が輪をつくる。
やがて評議会議事堂の正門に1人の男性の影が現れると、軍服の列が一斉に姿勢を正した。
同盟陸軍元帥にして総司令官――ブルーノ・ジェンマ(kz0100)は。
彼は隻眼で聴衆を見渡すと、重々しい口を開く。
「集まった英士諸君。今から数時間後、諸君らはリゼリオの連合軍と合流し、世界中の同志と共に赤土の大地を踏みしめることとなる。
既に各都市で作戦にあたる勇士諸君。今この声は届かずとも、共に都市の未来を憂い、都市のために戦った月日は我々の明日への礎となるだろう」
聴衆は息を飲んでブルーノの言葉の1つ1つに目を見張る。
張り詰めた緊張の中には勇気、恐怖、闘志、不安、期待、責任、そして希望、絶望――様々な感情が渦を巻く。
「王国暦712年――共同宣言が出された瞬間より“自由”は我々の旗印となった。同時に“自由”とは何か。それは命題として今日までの我々、都市国家諸氏へと問い続けられてきた。私は、今ここでその解を示すつもりはない。解とはすなわち、自由から最もかけ離れたものだからだ。
だが、あえて1つの解釈を述べるとすれば――“自由”とは“決断”だ。王国からの独立を決断してから、我々は我々の意志で進路を決め、我々の責任で今日までの航海を続けて来た。
我々が抗うのは決断を意図的に左右するモノ。意図的に阻むモノ。先人が無血で手に入れた“自由”のために、今こそ我々は血を流すのだ! しかし大海原を染める朱は我々の血潮ではない!
水平線に臨む旭光こそが、新たな時代に目にする原初の景色である!
暁を望むその時まで、我々の船は決して沈みはしないッ!」
感情の渦が、歓声の嵐へと変わった。
敬礼、喝采、拍手、指笛。
街中が音という音であふれかえる。
――行ってらっしゃい!
――留守は任せてとけ!
市民の声援が大空を埋め尽くす。
それは守られるばかりではない。
自分たちの街は自分たちで守るという1人1人の決意・決断。
総意ではない、それぞれの意志がこの国を形作っているのだ。
●

ヴィルヘルミナ・ウランゲル

篠原 神薙
ヴィルヘルミナ・ウランゲル(kz0021)が見つめる先、リゼリオの港には修復改造中のサルヴァトーレ・ロッソが停泊している。
後に大転移と呼ばれた、サルヴァトーレ・ロッソとそれにともなう大勢のリアルブルー人の転移。その場に篠原 神薙(kz0001)も居合わせていた。
「私はあの時思ったのだ。これだけ巨大な力、扱い方を誤ればヒトは容易に輩をも焼き尽くすと」
ヒトは結局、愚かだ。
お互いを傷つけあうし、いつまでたっても分かり合えない。でもそれは、正しさを求めるが故。
悪の征伐ではなく正義のぶつかり合いだというのなら、弁論で決着はつけられない。だから力に縋る。
「圧倒的な力を持つ者――英雄こそが世界を統べ、そして守るべき……そんな考えは今でも持っているのだ」
だが――正にその結末が、未来の姿がこの世界に牙を剥いた。
圧倒的な強者による救世、ファナティックブラッド。
力による支配と統率。その庇護下に置かれた人々が悪意の煮凝りとなって動き出したのがシェオルだ。
「私は英雄を求め、それと同時に英雄を失う事を求めた」
「俺は英雄になりたいとは思いません。でも……英雄だったらよかったのにと、そう思う時はあります」
神薙の脳裏を過ったのは、ひとりの少年の姿だ。
かつては同じコロニーに暮らし、共に未来を夢見て学んだ友達。
クドウ・マコト――力を求め、英雄に焦がれた彼を、自分は結局救えなかった。
「英雄の要らない世界とは、ひとりひとりが己の頭で正義を求める世界。弱者のいない世界だ。それもまた、健全ではないように思うよ」
「じゃあ、どうすればいいんですか?」
「私にもわからん。だが……結局明確な答えなどないのだ」
こうすれば必ず良くなるとか、これが絶対に正しい道だなんて、そんなこと誰にもわからない。
ヒトは己の歩みを振り返って初めてその所業の価値を知り、喜びや悲しみと向き合う。
「ならば大切なのは考えるのをやめないこと。そして今の自分に出来るせいいっぱいをぶつけることではないかな」
強者も弱者も、正義も悪も、きっと人類全体にとっては必要なのだ。
どれかが欠けても、偏りすぎてもいけない。世界は混沌の中で、己の在り方を磨いていく。
永遠の命も、恒久の平和も、無限の闘争も極端すぎる。
ヒトはヒトらしく。ただ当たり前の日常を続けることそのものが、尊いのだ。
「今は、そう思っているよ」
「……ですね」
「さて、またぞろ私は最前線へと戻る。グラウンド・ゼロの防衛に関しては、我らに任せてもらおうか」
「帝国の守りはいいんですか?」
「はっはっは、いいに決まっている。あれは私達が鍛え上げた人類防衛装置、ひとつながりの反逆心だ。人間同士の争いもないわけではないが、それも人類存続が下敷き。頼れる仲間がたくさんいるからな」
休憩は終わりと言わんばかりに背中をぐっと伸ばし、ヴィルヘルミナは微笑む。
「……少年。どうだったかね、この五年間の旅路は」
向き合い、そして少年は考える。
色々な事があって、そのどれもがつらい思い出ばかりだけれど、なのにどうしてか、今は全てが懐かしい。
たった五年。ヒトの一生に比べたって僅かな時間。世界に刻まれた歴史からすれば、瞬く間の出来事だろう。
でも――確信する。
こうやって小刻みにフィルムを繋げて、命は歴史を紡いできたのだと。
「楽しかったです。だから、この戦いもいつか想い出として笑い合いましょう。五年後も、十年後も……何度だって、またみんなで」
「フ、そうだな。百年……いや、千年は続く伝説を作ってやろうじゃあないか!」
世界中の人々が決戦に備えていた。
ハンターの主要戦力が邪神の討伐に動くというのなら、滅びゆくこの世界を繋ぎとめるのは彼らの役目だ。
王国も、帝国も、同盟も、辺境も、東方も、北方も、皆が願いを一つにする。
彼らなら――これまでも世界を救ってきた、彼らハンターなら。
“必ずやってくれる”と信じられる。
今は絶望する時ではない。夜明けを信じて――走り続ける時だ。

南雲芙蓉

トマーゾ・アルキミア

ドナテロ・バガニーニ
そこに根付いたリアルブルーの「世界樹」を前に、南雲芙蓉とトマーゾ・アルキミア(kz0214)は装置の最終確認を急いでいた。
地下深くに格納された世界樹は、今回の戦いで外側に出ることはない。
だが、大精霊に代わってこれを操る芙蓉にも命の危険はついてまわる。
「不安そうじゃな、芙蓉」
「大精霊の代わりになって、その力を扱う……守護者にしかできない仕事だって、ちゃんとわかってます。でも、私はやっぱり“凡人”ですから」
世界を救う大一番に、きっと自分は大して役立てない。
ハンターとは違って、リアルブルーと肩を並べて闘う事すら……。
「最後までちゃんとやり抜けるのか、不安はありますよ」
「そうか。じゃが、誰しもそんなものじゃ。ハンターも別に、天才だから闘っているわけではない」
いつだったか、ドナテロ・バガニーニ(kz0213)が言っていた。
彼らは普通の人間だと。なんでもない、ただの人間だと。
特別な力はあるかもしれない。でも、それとこれとは別問題だ。
当たり前にあったはずの日常を、未来を、ささやかな幸福を燃やして力を得ているに過ぎない。
“他の誰か”だってよかったはずだ。それでも彼らは、自らの意思で立ち上がった。
「お前は勇気を出して、最後まで共に戦うと決めた。ならばそれで十分、あいつらと肩を並べる資格はある」
「……はい。ありがとうございます、教授」
「フン、礼を言うのは早すぎるわい。早速始めるぞ。この崑崙を使って、世界中を一つに繋げるのじゃ」
邪神がリアルブルーに眠る以上、突入部隊の戦場はリアルブルーとなる。
世界の壁を隔てた地へと友軍を送り込むため、そしてその友軍を支援するために、中間地点としての機能が崑崙に求められた。
今、このクリムゾンウェストはすべてが戦場になろうとしている。
住民は避難や防備を固める作業に追いやられながら、それでも一様に祈りをささげていた。
主戦場ははるか遠く。ならば、その祈りを束ねて送り届ける者も必要となるだろう。
ハンターも提唱した、世界中の力を一つに束ねる大儀式。その中心地こそ、崑崙の世界樹であった。
「感じ取れるか、芙蓉。ひとつひとつの命の光を」
「……はい。世界樹と……我が神と接続すれば、私にも見えます」
仮にリアルブルーやクリムゾンウェストがこの大宇宙にとっては小さな光に過ぎないとしても、ただの人間が見つめるには強すぎる。
長引けば芙蓉の命は削り取られ、やがて肉体は死を迎えるだろう。
「負傷者の救出もお前が頼りじゃ。彼らの為にも、途中で倒れることは許されんぞ」
リアルブルーで戦闘不能に陥ることは死と同義だ。
圧倒的なVOIDの物量に轢き殺されればひとたまりもない。
だから、こちら側から救出する。
クリムゾンウェストから世界樹を通じて戦場の気配を感じ取り、その命をクリムゾンウェストに召喚するのだ。
芙蓉は戦いには向いていない。気持ちが優しすぎるからだ。
その分、これは自分にとって向いていると感じる。
誰かの命を救うためなら――手足が千切れようがなんだろうが、いくらだって頑張れるから。
「任せてください。ここが……想いを繋ぐこの場所が、私の戦場です」
そうだ。ヒトには分相応の場所ってものがある。
不向きな場所には、居ちゃいけないんだ。
(クドウさん……あなただって……そんな所、向いてないんですよ)
何度か戦場で肩を並べた青年は、今も闇の中を彷徨っているという。
星の守護者になった自分と彼とでは何もかもが違いすぎるし、結局自分は彼に何もしてあげられなかったけれど。
(ハンターさんも、ドナテロ議長も、きっとあなたの居場所を作ってくれるから……)
●

プラトニス

サンデルマン

イクタサ

アメンスィ
これはとうに出されていた結論で、故に対策は必須である。
既に実施されているグラウンド・ゼロへの転移攻撃の誘導。これを更に強固にする必要があった。
先の戦いで損傷した自動兵器や「セントラル」の修復は進み、毎日のようにグラウンド・ゼロではシェオルとの戦闘が繰り広げられていた。
そんな最前線に今、世界各国からの援軍はもちろんのこと、ドラゴンやリザード兵、コボルドやゴブリンなどの亜人、更には自動兵器の集団と移植の顔ぶれが集っていた。
「いやはや壮観であるな! セッセイを司る我輩としては、あんまりゴッチャ煮なのもどうかと思うが、一途であることに変わりありませんなぁ」
高台に立ち、顎髭を撫でながら笑みを浮かべるプラトニス。
その背後には四大精霊――サンデルマン、イクタサ、アメンスィもそろい踏みであった。
四大精霊は一度この世界に散り、そしてそれぞれヒトが問題を解決する様を見届けた。
“想いの統一”という地固めが完了した今こそ、四大精霊がその真価を発揮できる時なのだ。
『ヒトは我らに示した。この星の在り様、世界を注ぐ霊長としての答えを……』
「なら、その祈りに応えないわけにはいかないね。真面目な仕事を抜きにしても、この星には僕の可愛い子供達がいるんだ」
「あら、イクタサ……仕事に私情は持ち込まないあなたがそんなことを言うなんて。でも……そうですね。変わったのは、私も同じかもしれません」
四大精霊はお互いに向き合う。その表情は――サンデルマンも含め、晴れやかだ。
「王国の民は光への意思を示した。苛烈を極める傲慢王との戦、まこと千年王国の名に恥じぬセッセイであった」
『正義に揺れる帝国は、新たなる理を求めて歩み始めた。悪さえも飲み干す強かさを、私はヒトの可能性と定義しよう』
「辺境の民族は祈りを忘れなかった。彼らはこの紅き大地で絆を育み、困難の中で成長を、そして未来を示した」
「随分と古ぼけてしまった約束を、同盟の民は果たさせてくれました。嫉妬王への勝利、そして自然と調和する英知を、ヒトは受け継いでいます」
ヒトは示した。
ならば、“見守るだけ”はもう終わりだ。
『「「「我ら、紅き大地の調和を司る四大精霊」」」』
「古き盟約に従い、この世界に光を齎さん! いでよ、我が筋肉彫刻ぅぅぅぅううう???軍ッ団んんんんッ!」
プラトニスの号令に従い、蒼い水鏡のような光が大地に広がる。
次々と出現するのは節制の眷属。筋骨隆々とした肉体を持つ彫刻達だ。
『再び、目覚めの時は今……。この地に集い、霊長を示せ――英霊たちよ』
サンデルマンが導くのは、英霊として世界に名を遺す戦士たちの精霊。
このグラウンド・ゼロは古よりの決戦場。英霊などいくらでも眠っている。
「命の理をこの地に……シンタシャチより出でよ、牙持つ輩たちよ!」
イクタサが召喚するのは、強力な幻獣たち。
獣の姿をした、しかし明確な意志を有する自然の守り手である。
「輝ける意思、輝ける命の結晶。お出でなさい、大地の代弁者、ジュエルゴーレム!」
そしてアメンスィの呼び声は大地から次々に結晶の身体を持つゴーレムを起き上がらせる。
四大精霊が呼び出す精霊たちは、どれも並の覚醒者を上回る戦闘力を有している。
それが数百……いや、数千体。グラウンド・ゼロを包囲するように君臨し、クリムゾンウェスト連合軍と肩を並べるのだ。
「フゥ?……。本当はもっと早く、この地に馳せ参じたかったものだが」
『……仕方あるまい。我らとて、堪える時であった』
「大精霊様がこの世界を離れる時に備えて、力を温存する必要があったからね」
「故に、今こそ解き放つ時。世界の祈り、存分に力と変えましょう」
四大精霊の加勢を受け、戦場は大いに沸き立っていた。
誰がどう考えたって超爆発的な戦力の増加である。喜ばないわけがない。
そう。例え――これだけの戦力を投入しても尚、邪神との闘いが苛烈なものであるとわかっていても。
今は喜ぼう。同じ大地に住まう者たちが心をひとつにしたことを。
どこにも逃げ場はないけれど。せめて最後まで、運命を共にできるということを――。
●

ダニエル・コレッティ

ディアナ・C・フェリックス

ジーナ・サルトリオ

ヴィットリオ・フェリーニ

アスタリスク
最前線へと飛ぶロッソの機動兵器ハンガーに、特機隊の面々が集っていた。
2機のデュミナスに1機のエクスシア――それぞれの機体の足元に並ぶ3人のパイロットが、隊長であるダニエル・コレッティ(kz0102)を囲む。
「さて、いよいよというわけだけど……まあ、今さら俺に言えることは何もないよね」
ダニエルは懐から煙草を取り出そうとするが、すぐさまロッソのスタッフの熱烈な視線を受けて、肩身を狭くしながらポケットへ押し込む。
「行ってこい。そして帰って来い。以上」
「「「はい」」」
3人の声がハンガーに響く。
「子猫ちゃん、緊張してない?」
ディアナ・C・フェリックス(kz0105)に声を掛けられ、ジーナ・サルトリオ(kz0103)はにへらと気のない笑顔を返した。
「大丈夫ですよ。裂目の決戦だって経験してるんですから――」
口にしながら耐衝撃ベストの留め具をはめようとするが、なかなかはまらない。
カチカチと空しく金属音が響く中で、ヴィットリオ・フェリーニ(kz0099)の武骨な手が代わりにそれをはめた。
「ありがとう、ヴィオ大尉」
「ジーナ、これを持っていくといい」
ヴィオはそう言って、自分が首につけていたサメの歯のネックレスをジーナへと手渡す。
「船乗りにとってサメは神聖な生き物でな。それに肖りつつ、同時に食われないようにという意味もある。効果はてき面だ」
「相手はサメじゃないけどね」
水を差したディアナに、ヴィオは鼻で笑って返す。
ジーナは取って、自分の首へとかけた。
「ありがとう。なんか効きそうな気がする」
彼女がいつものように笑ってみせると、誰からともなく拳を突き出す。
中心で重ねた拳から、それぞれの体温が伝わってくるかのようだった。
●
同盟軍の元・総司令官、名誉大将イザイア・バッシ(kz0104)は、傭兵部隊の隊長アスタリスク(kz0234)を呼び出した。
崑崙基地から要請された派遣を打診するためだ。
「あちらも人手が足りないようでな。ワシも貴官は適任だと思う」
勿論、嫌なら断っても構わない。老将はそう付け加えた。
「私は……」
崑崙基地から生きて帰れる保証はない。だがアスタリスクの返答が鈍ったのはその点ではない。
どうせあと何年生きられるかわからない元・強化人間の身だ。思い出深い崑崙基地に果てるならそれもいいだろう。
――だが。
懐かしさ。悔しさ。喜び。執着。
一度に沸き上がった感情はどう説明すればいいのだろう。
彼は崑崙で年若い仲間を犠牲にして長らえた命を持て余し、結果、同盟軍の傭兵部隊にいる身だ。
何もかもが中途半端だった。
そこで不意にイザイアが、悪戯小僧のような笑みを浮かべる。
「言うまでもないことではあるが。ワシとしては、貴官が無事で戻ることを切実に願っておるよ。念願の部隊が瓦解せんうちにな」
釣られてアスタリスクも笑ってしまう。
確かに、アスタリスクの代わりに隊長職を預かるだろう人物と、隊員の相性はすこぶる悪そうだ。
「そもそもこの決戦に敗北するようなことがあれば、我が軍、我が国どころか、クリムゾンウェストそのものも瓦解する。力を貸してはくれんか」
この老将にはかなわない。彼の戸惑いは消えていた。
「謹んで拝命します。皆には宜しくお伝えください」
「……会わずに行くか」
「必ず戻りますから」
アスタリスクは迷いなく、同盟式の敬礼をしてみせた。
●

ハヴァマール

バニティー
『――いい月だ。このような枯れ果てた最果てにも、光は分け隔てなく注ぐのだな』
何度も繰り返し、こんなふうに夜空を見上げた。
その時は隣に色々な歪虚がいたりもした。
ハヴァマールは歪虚王の位を持つが、決して配下を率いる者ではなかった。
古代リグ・サンガマを滅ぼす為に邪神が産み落とした兵器。彼は自ら戦うことでしか在り様を示せない。
「こんばんは、おじいさん。とってもいい月ね」
幼さを残した少女の声にちらりと振り返る。
『おお。シュレディンガーかと思いきや、バニティーか』
「世界一周旅行は終わったの?」
『うむ。我は十分、旅をした。そしてこの地に戻って来たのだ』
実は、ハヴァマールはかなり早い段階で――それこそまだ戦場でハンターと刃を交えていた時から、邪神のからくりに気付いていた。
自分が作られた存在であることにも、邪神という壊れた世界が生み出した兵器であるということも、特に何とも思うことはなく。
シュレディンガーの導きで邪神と接触した後は、シェオルの意思と呼ばれる闇とも語らった。
それを知って尚、特に彼は何もしなかった。“何もする必要がないから”だ。
別に帝国を滅ぼすことに執念を燃やすこともない。そういうのに拘っていた連中は軒並み討伐されてしまった。
なんなら本当の宿敵だったリグ・サンガマはすでに滅んでしまっているわけで。
「世界を知って、邪神を知って、何か答えは見つかった?」
『いいや。我はついぞ知らなかった。青木、シュレディンガー、蓬生、ブラッドリー、そして我が友ナイトハルト。彼らの心も、その何一つもな』
月を見上げ、髑髏の王はカラカラと笑う。
『この世界の裏側を走ってみたが、どこまで行っても虚無そのものよ。この星はそもそも、遠からずして滅ぶのではないかな?』
「その可能性はあるね。クリムゾンウェストは傷つきすぎている。輪をかけて、邪神との決戦に力を使えば……」
『そうまでして戦う心持を我は理解できぬのだが……ま、奴らにとっては重要なのだろうな』
胡坐をかいたハヴァマールの隣、バニティーは膝を抱えるように腰を下ろす。
「このまま虚無の領域に住んでいれば、人類とは鉢合わせないまま星の寿命を迎えられるんじゃない?」
『かもしれぬな。だが、隠居し続けるわけにもいくまいよ』
「あなた、どちらかというとこの星の側でしょう? 邪神に従う理由はないはずよ?」
『かもしれぬな。だが……ふむ。バニティー、我ら歪虚は、何の為にこの世界にあると思う?』
質問に対し、別の質問。バニティーはしばし思案する。
『闇も……光も、どちらもこの世界には必要なのだ』
歪虚自然発生のメカニズムはわかっていない。
だが、邪神の干渉がなくとも世界には負の想念が溜まり、雑魔を生み出す。
これを討伐することで星が秩序を形成するというのなら、産まれた闇が光を食み、それを光が打ち払うのはワンセンテンスの作業と言える。
『我を構成する、死という救いを求める者たちの叫び。“この世界をもう終わらせたい”と願う意志も、確かにヒトの一側面であろう』
「……あなたも、シェオル型歪虚だってこと?」
言われてみれば、リグ・サンガマを滅ぼしたハヴァマールは、シェオル型と行動を共にしていた。
彼自身もシェオルの代弁者であると考えるのは妥当かもしれない。
それも、この星の形にマッチした――世界の負の意思を一身に引き受ける“ゆりかご”だとしたら?
『然り。ならば、終わりを願う者たちの叫びを無視するわけにもゆくまい。我は、わだかまる妄念の導き手なのだから』
「……驚いた。あなた、自分の言ってることの意味をわかってる?」
それは、一種の立派な世界維持だ。
燻り、泣きじゃくる人々の負の祈り。それを拾い集めて「肯定する」ことが彼の宿命だとしたら。
願いを受けて世界のために行動する者。まるで――守護者のようじゃないか。
『我自身に戦う理由はないのでな。ならば歪虚の王として、負の想念の代表として、彼らの為に立つのも悪くはなかろう』
「――自分が討たれる事で、集めたこの世界の負の力を浄化するために?」
『いけないことだろうか? それに、この星の具合がどうにもダメそうだった時、へし折るのも死神の役目だろう』
「戦わないでほしいって説得しても、聞いてくれないよね?」
『ハハハ、聞けぬ相談じゃな』
豪快に笑い飛ばし、そして王は問う。
『時にバニティーよ。“酒”なるものを持っていないか?』
「出すことは出来るけど……あなた呑めるの?」
『口に注げば注いだだけ隙間からこぼれる。が、こういう時には呑むのだろう? ヒトというやつは』
肩をすくめ、バニティはその手にどこからか盃と徳利を取り出した。
ヒトの真似事をしながら、穴だらけの反動存在は夜空を見上げ、酔い痴れる。
楽し気なその横顔を、バニティーは少しだけ寂しそうに見つめていた。
邪神に攻撃を仕掛けるということは、途切れかけた封印を終わらせ、双方が攻撃可能な状態になることを意味していた。
だが戦争は常、仕掛ける側こそ有利である。
邪神が攻勢に出れば、クリムゾンウェストを守り切ることは不可能である。
準備を整えて先手を打つ。これは邪神との闘いにおいて必須の前提であった。
リアルブルーへと転移したハンターらを待ち受けていたのは目を疑うような光景だ。
巨大な青い星、地球。その上に鎮座する――巨大過ぎる邪神ファナティックブラッドの姿。
あれは本来、世界を丸呑みにすらできる怪物だ。異世界に入り込むのに「隙間が小さかった」から、サイズを合わせていたにすぎない。
故に――転移を終え、封印からも解き放たれようとしている今、邪神は本来の姿形を取り戻そうとしている。
その作戦を聞けば、誰もが一笑に付し呆れるだろう。
それは作戦とは言わない――多数の犠牲が伴う無謀な行為だ、と。
だが、この作戦に一切のジョークは存在しない。
彼の邪神に対峙する為には、この方法以外にない。
無謀は承知。それでも、彼らは必ず『やり遂げなければならない』。

トモネ・ムーンリーフ

ユーキ・ソリアーノ
「よし。では、反重力バリアを展開だ」
トモネ・ムーンリーフの号令と共に、ユーキ・ソリアーノはニダヴェリールの反重力バリアを前面へ展開する。
かつて歪虚に奪われた希望――ニダヴェリール。
強力な防御シールドを持ち、災いから守り抜くこの艦は邪神を前に地球統一連合宙軍艦隊と共に転移。己の役割を全うする為、最大の武器を発動する。
「エネルギー出力最大です。邪神まで可能な限り接近します」
ユーキの眼前に広がる数々のモニターが一斉に稼働を開始。
反重力バリアを展開したままニダヴェリールが邪神に接近する事で、邪神の外殻へ痛撃を与える事が狙いだ。
ただ、ユーキにも懸念はある。予定通りであれば反重力バリアを最大展開し続けても邪神への接近は可能だ。だが、邪神へ接近すれば歪虚側の抵抗は激化する。おそらく邪神へ到達する前にエネルギー出力が落ちて反重力バリアは消え失せるだろう。
それでもいい。
邪神へ少しでも近づく事が重要なのだ。可能な限り傷を付けずに主力艦隊を邪神へ届けられればいい。
「良い。そのまま進めのだ。今こそ、この艦は三世界すべての希望を背負う。
あの子達を苦しめた我らが業を、ここで晴らすのだ。これですべてが許される訳ではないが、それでも私達はやらねばならんのだ」
トモネが腕を前へと突き出すように前方を指し示す。
向かうは絶望的な巨大さを誇る邪神。
「大きい。そして、この雰囲気は……」
ユーキの口から思わず言葉が溢れる。
それは率直な感想だった。想像よりも遙かに巨大な大きさ。だが、それ以上に気付くのはその佇まい。そこにあるだけでも黒い何かに心が押しつぶされるような感覚。
これは畏敬? ――否、もっと深くもっと濁った感覚。
近づいてはいけない。本能が警報を発する。
それでも、トモネは臆する事なく前を見据える。
「エネルギーの残量など構うな。後に続く戦士達を少しでも邪神近くへ送り届ける事のみを考えるのだ」
「…………」

レギ
レギ(kz0229)がCAM出撃用のドックから通信回線を開く。
レギはニダヴェリールの護衛任務の命が下り、艦内の警備強化に当たっていた。
「何を申す。ここでやらずに何とするか!」
「トモネ様の身も皆さんにとって大事なんですから。アスガルドの子供達が待ってますし無事に帰らないとですよ。そうですよね、ユーキさん?」
「……あ、はい。そうですね」
レギに突然話を振られ、一瞬に戸惑うユーキ。
既に反重力バリアに邪神からのビームが直撃。巨大なビームを前にしても反重力バリアのおかげで無傷。後方の艦隊も被害は出ていない。
しかし、歪虚側もこちらの動きを察知したと見るべきだろう。
「むぅ。それを言われると困る。だが、この心意気は本当だ」
「はい。分かってます、トモネ様」
「各員、周辺宙域からの敵の襲撃に警戒して下さい」
トモネとレギが話す傍ら、ユーキはニダヴェリール艦内へ一斉放送を流す。
同時にこの状況で脳内で幾度もシミュレーションを繰り返す。
万一の場合、最悪の事態を回避する為には――。
「レギさんも周辺宙域の警戒をお願いします。いつでも対応できるように準備を」
「分かりました」
途切れる回線。
意気揚々と航海する希望の船。頭上に掲げられた女神が、その進路を指し示す。
だが、相手は絶望の象徴とも言える邪神。この船の役目がそう長くない事を肌で感じ取っていた。
(……トモネ様を頼みましたよ、レギさん)
ユーキは再び、前方へ視線を向ける。
漆黒が広がる闇に向かって、希望が輝き始めた。
●

森山恭子

ジェイミー・ドリスキル
「艦長、ニダヴェリールよる入電。『貴艦とハンターの尽力に期待する』です」
「まっ! ユーキさんたら、あたくしの事が心配ザマスね? よござんしょ。あたくし達の力を見せる時ザマス」
艦長の森山恭子(kz0216)はブリッジで照れながらも黄色い声を上げていた。
だが、ブリッジにいるクルーも恭子が無理に明るく振る舞っている事を知っていた。そうしてもらわなければ、あの邪神を前にしてとうに逃げ出している。
いつもと変わらない。いつもと同じ光景。
きっとみんなで揃ってこの戦いから帰還できる。この艦に乗る誰もが自分にそう言い聞かせたかったのだ。
「いつもと変わらねぇな、バアさん。そんなんでニダヴェリールのお守りはできるのかよ!」
戦車型CAM『ヨルズ』の操縦席で待機するジェイミー・ドリスキル(kz0231)は、通信機で恭子を窘める。
このラズモネ・シャングリラの任務はニダヴェリール周辺に集まる歪虚の撃破である。
ニダヴェリールが邪神へ接近できなければ作戦遂行に支障が出る。ラズモネ・シャングリラは歪虚を退けてニダヴェリールを予定宙域まで守り切らなければならない。
言う事は簡単だ。
だが、ニダヴェリール周辺に集まる敵は相当な数に上る。ラズモネ・シャングリラもおそらく無傷では済まない。
「バアさんじゃないザマス。還暦前ザマス」
「変わらねぇな」
「人間、土壇場になってもそう簡単には変わらないザマス。あたくしも、ドリスキルさんも」
恭子の言葉の意味。それは、かつてドリスキルが身を挺してラズモネ・シャングリラを守ろうとした事。敢えてそれを口にする事で釘を刺したかったのだろう。
「そう、かもな。俺だって変わりてぇよ」
ラズモネ・シャングリラの甲板でドリスキルは最終調整に入る。
この戦いですべてを出し切らなければ、おそらく邪神への到達はできない。
必ず、任務を達成する。
それが、この艦にいる者の願いであった。
●

高瀬 康太
高瀬 康太(kz0274)は、サルバトーレ・ブルの艦内でコンフェッサーの整備を受けながら静かにその時を待ち構えていた。
無数の敵、無数の砲火、無数の怨嗟の中へと、自分は飛び込むことになるのだろう。
陽動として、サルバトーレ・ブルの、そしてハンターたちの道を切り開く。
……その作戦を前に、康太にはどうしても言っておきたいことがあった。
「もし僕が、業火に焼かれようとも。決して、振り返らないで下さい。どうせ果てる者のために割く余力があるのならば……一歩でも前へ。ここは邪神に攻撃をするための戦場です。命を守るためではなく、必ず邪神に到達することが目標です」
分かっているのだ。自分達の力が、ハンターたちと比べ不足しているということは。
それでもここに立つ元強化人間たちは、そんなこととっくに覚悟の上でここに立つのだ。
……陽動作戦である以上、敵の標的となる頭数は、数秒でも稼げる時間はあるに越したことはない。そしてそれは、先の無い己たちだからこそ背負える役目だからと信じて。
「後ろの者を見捨てられずに余計な力を使い、そして邪神に及ばないなとということがあれば、その方が僕たちの削られた寿命、それでもこの日のために生き延びてきた意志、今僕たちがここに立つ決意を無駄にするものと知れ!」
簡単に命を諦めるな。ハンターたちはそう言うだろうか。だがそんなのは康太からすれば一方的な言い分だ。勝手に生を最上の価値観とし、選択を取り上げるという行為だ。『命を支払ってでもここに立ちたい』、彼らはそう願ってここに来たのだから。
そう──彼らにとって最早、ここで命を諦めるな、などと言われるのは、例えるならばこんな話だ。貴方たちは百円のパンを買うために百円を支払うことを『百円を諦める』と言うのですか? と。
……だから、良いのだ。康太はそれを諦めるとは言わない。支払う価値があると思うから、支払いに来たのだ。
──そう、ハンターたちが示した第四の道は、彼の心身を捧げうるに相応しい物だったから。
邪神を討つこと自体に意味があるのではない。だがその先に……守りたかった、リアルブルーの平和が約束されるなら。
だから──これは諦めじゃない。これもまた、希望だ。
希望があるからこその覚悟なのだ。
「半端な覚悟で邪神に勝つことなど出来ない。僕は死は覚悟しました。そして、貴方たちには求めます──僕たちの屍を踏み越えていく、その覚悟を」
そして必ずや邪神に打ち勝ち、どうかリアルブルーに未来を。
──未来にたどり着いた者は、どうか夢ある人生を。自分たちの分まで。
先の無い元強化人間たちはそれを希望に、絶望的な戦場を待ち受ける。
如何なる対案を出そうとも、討伐をベースにした以上、彼らがこうなることも見込まれていた事の筈だ。
……選択の意味は、意志は、ここでもまた、問われるだろう。
●

大精霊リアルブルー

ベアトリクス
サルヴァトーレ・ブルの甲板、リアルブルー(kz0279)を載せたマスティマがベアトリクス・アルキミア(kz0261)を掌に載せ、その翼を広げる。
今はまだリアルブルーの上にいる邪神だが、自由に動き始めれば作戦に悪影響が出る。
その動きを封じなければ戦いにすらならない。そこで彼女が選んだのは――。
「いつだったかの仕返しも込めて……! おいでませ、エバーグリーン!」
それは、比喩とかではなく。
邪神の頭上にぽっかりと空いた世界の穴から迫り出した超巨大な球体――即ち、エバーグリーンと名付けられた惑星が。
天も地もない漆黒の宇宙を、しかし確かに“墜ちて”ゆく。
二体の大精霊の操作により、惑星エバーグリーンは凍結された「地球」と共に邪神を文字通り圧殺する。
邪神は本能的に危険を察知し、“防御”を選択せざるを得ない。
四つの巨大な魔腕でエバーグリーンを支え、苦しむように咆哮した。
「……ぐっ! 聞いた時から無茶だと思ったけど、あんまりにも無茶苦茶だっ!!」
「アハハハハ???♪ 効いてる効いてる???!」
ベアトリクスは笑いながら自分自身とも言えるエバーグリーンを見つめる。
アレはもう、終わってしまった世界だ。
何もしなくても消えてしまう絞りカス。なのにハンターは何度も足を運び、まだ使えるものは、まだ生かせるものはと心を砕いてくれた。
そして今、自動兵器たちはクリムゾンウェストを守る戦力としてグラウンド・ゼロにて再戦の機会を与えられた。
「じゅうぶん、よねぇ」
笑いながらベアトリクスが膝をついたのは、この攻撃が残された命を燃やし尽くすものだからだ。
凍結保護された地球とは異なり、いつ崩れてもおかしくなかったエバーグリーンは、この衝撃に、マテリアルの放出に耐えられない。
わかっていたことだが、トマーゾもナディアもリアルブルーも止めはしなかった。
それがエバーグリーンという世界に最期に残された意志が決めたことならば――でも。
「まだ死ぬな、ベアトリクス!」
マスティマから声が響く。
「あんたが死んだら邪神が動き出す! 死ぬのは作戦の成功を見届けてからだ!」
ベアトリクスは助からない。
だったらその命、一滴たりとも無駄にはできない。
「星よ、我が星よ! 僕は帰って来た! 戦うために――もう一度、未来を目指すために!」
マスティマの呼びかけに応じ、地球は輝きを増していく。
星から次々に姿を現すのは「天使」の形を借りた精霊、即ち使徒たちだ。
その数は想定よりも多く、そして想定よりもずっと力強い。
神秘の死に絶えたこの世界においても、精霊に力を与えるのは観測者たるヒトの祈り。
時の流れから切り離される直前、それでも彼らは最後の蒼空に祈った。
世界の救いを。戦い続けた者たちへの救いを。
ハンターが地球に与えた奇跡は今、神の意志により解凍された。
すこしも不思議なことじゃない。
ただ生きたいという、ただ未来が欲しいという。
70億もの、当然の願いが背中を押している。
「反抗の時だ! 僕は、僕(せかい)を――諦めない!!」
●

ブラッドリー
求めるばかりで与えてくれる者は、誰もいないというのに……』
ブラッドリー(kz0252)の心に響く言葉。
あの邪龍が口にしていた記憶――今になって何故思い出すのか。
「終末の天使。罪深き故に、その業は肥大化するばかり。
しかし、その業故に未来は求め続ける」
ブラッドリーの乗るエンジェルダストの視界からは、はっきりとニダヴェリールの姿が見える。
あのバリアを盾にして神の元へ近づくつもりなのだろう。事実、神の遠距離攻撃もあのバリアによって阻まれている。
(彼の船はかつて神の手にあった物。人の手に渡った段階で、崩壊は定められていた。
それは洪水を乗り越えたあの船のもう一つの運命……)
人が神に抗う。それは選択された時から分かっていた。
その戦いが如何に不毛か。如何に残酷か。
――されど。
そのラグナロクこそ、人が人たり得る証。
願い、渇望する。その根源こそが未来を掴む。
そうだ。もし、天使達と共に神が救えるなら……。
そう、考えた事もあった。
一度は共に戦った者達だ。宇宙を、神を、すべてを救えるならそれも悪い話ではない。
だが、ブラッドリーは頭を振って邪念のような思考を振り払う。
「もう道は違えてしまったのです。私は……楽園にいる者達を見捨てる事はできません。楽園の果実を食し、追放されても。神は楽園の住人だった彼らを見守り続けるのです」
楽園が無限に繰り返すループだとしても。
そこからもたらされる怨嗟の声が、神を狂わしたとしても。
楽園に住人がいる限り――。
ブラッドリーは自らの道を変える気はない。神を信じ、突き進むだけだ。
「あの障壁。外部には強いようですが、有効範囲があるようです。神に仇為す者に鉄槌を。神の怒りを持って知りなさい」
意を決したブラッドリーは、堕天使型とシェオル型と共にニダヴェリールへ向かって動き出した。
●
「艦長、ニダヴェリールより入電! 『反重力バリアの内側から敵の襲撃を受けている。至急救援を請う』です」
「……なっ!?」
恭子は絶句する。
反重力バリアは確かに外部へは強力な防御装置だが、エンジェルダストのように内側へ転移されればその機能は一瞬にして役に立たない。既に複数の歪虚がバリアの内側へ入り込み、バリアの破壊を狙っている。
「艦を最大先速。ニダヴェリールの側面で敵の接近を食い止めるザマス!」
ラズモネ・シャングリラを前に出す事で、攻め寄せる敵へ陽動を仕掛ける。
体を張った恭子の無茶な指示だが、これも非常事態。ニダヴェリールを守る為には致し方ない。

八重樫 敦
ブリッジに木霊する恭子の声に続くように、山岳猟団の八重樫 敦(kz0056)が通信を入る。
八重樫ら山岳猟団の面々は、ニダヴェリールへ先に乗り込んで艦の防衛任務に就いていた。反重力バリアを展開すれば敵がニダヴェリールへ殺到すると考えて待機していたが、転移で内部へ入り込まれる事までは想定していなかった。
「こっちも……エクス……で……ず」
「え? なんザマスって?」
「艦長、通信妨害が発生しました! おそらくエンジェルダストが当該宙域に現れました」
エンジェルダスト。
ラズモネ・シャングリラとも因縁を持つマスティマ型歪虚CAMの襲来に、恭子は戦いの激化を感じずにはいられなかった。
●

ナディア・ドラゴネッティ

大精霊クリムゾンウェスト

ファーザー
作戦は少なくとも現時点では成功していた。
後は超覚醒したナディア・ドラゴネッティ(kz0207)を載せたサルヴァトーレ・ロッソが邪神を射程に収めれば、外殻の破壊は一撃で成功する算段であった。
だが――。
『ナディア、正面です!』
「ん? 正面がどうした?」
『わかりません。なんなのですか、あれは!?』
頭の中に響く大精霊の声に焦りと恐怖を感じた。
サルヴァトーレ・ロッソの甲板にはナディア以外にも多くの機動兵器やハンターが同乗していた。
だが、いつからだろう。ナディアの前、50mほど離れた距離に、それは立っていた。
褐色の肌を露出させた男。
ボロボロになったズボンが、脱いだのではなく「風化して着られなくなる」ほど長い時を経たことを意味していた。
「――これがクリムゾンウェスト、か。ファナティックブラッドに比べれば、あまりにも脆い祈りだ」
声は背後から聞こえ、振り返れば確かに姿もそこにある。
男はぼんやりと、ズボンのポケットに両手を突っ込んだままナディアを見ていた。
「なん……じゃ、おぬしは……?」
「お初にお目にかかる。遍歴もあるので説明は難しいが……ファナティックブラッドを作った者、と言えば通じるだろうか?」
気の抜けた、しかし深く滲むような声だった。
ナディアは理解する。これが「ファーザー」と呼ばれる、邪神の生みの親だと。
思考は高速で回転した。
まず、なぜこいつがここにいるのかわからないが、それを理解することは放棄する。
それよりもこれから何をどうするかだ。
(在り得ぬ……なんだ、コレは……)
歪虚とかそういうレベルの存在じゃない。
なにかもっと得体のしれない、既存の概念を超越したバケモノだ。
元は守護者だとかそんな話を聞いたが、真偽を疑う。
(こいつ……明確に……大精霊より強くね?)
神より強い守護者なんて矛盾したものがあるのか?
いやだから、それどころではない。「いる」のだから「前提」を辿るな。
ナディアが選んだのは、手を差し伸べることだった。つまり握手である。
男はしばし思案し、それから表情を変えずに手を取った。その瞬間――。
「ダニエル艦長! 全速力で進路を変更し、友軍艦隊から距離を取れ!」
サルヴァトーレ・ロッソがエンジンを最大出力でぶん回すと同時、何かが爆ぜた。
この比喩は正確ではない。正しくはファーザーとナディアが握手した状態のまま、お互いに「空間の上書き」を行ったのだ。
ナディアはこの男を「どこにもいかせてはならない」と判断した。
このまま艦隊と行動をともにすれば、この男は眠たそうな眼差しのまま、味方を皆殺しにしかねない脅威である。
故に隔離する。物理的に距離を取り、そして空間を切り取って。
そういう超常的な方法で即座に対処しなければ危険だと確信していた。
「確かに、一般的な世界における大精霊よりもはるかに強い力を持っているようだ。だが、それだけではな……」
バニティーの話では、この男は邪神の最深部から動かないはずだった。
それは確実なもののはずで、いきなりこんなところに自ら現れるなど、誰も予想していなかった。
肝心のバニティーはここにはいないし、連絡の取りようもない。
どこかでこちらの様子を観測しているかもしれないが、来たところでどうなるわけでもなく……。
「ぐっ!!」
“圧”が全身に重くのしかかり思わず膝をつく。手を繋いだままなのは、ファーザーの力を抑え込もうとしているからだ。
「話を……バニティーに聞いた。お前たちのやろうとしていることを、私は否定しない」
「仲良くお茶でもしに来たのなら、その殺気は引っ込めんか。これでは話もまともにできぬ」
「話すつもりはない」
「では……何をしに来た!?」
男は答えなかった。ただ、少し困っているような雰囲気を感じた。
まるで自分でも何をしにきたのか分かっていないかのようだ。
「私は、お前たちが進む道の遥か先にいる」
言葉を選ぶように、男はゆっくりと語る。
「――“本当にそうなのか、それを確かめに来た”」
手を離すと同時、ナディアの身体が吹き飛ぶ。
サルヴァトーレ・ロッソはすでに友軍艦隊と大きく距離を取ろうとしていた。
(こんなところで道草を食っている余裕はないというに……!)
邪神の外殻を破壊し、内部に突入するための砲撃は、本来こちらの役割だった。
その主戦力を欠いた状態で作戦を遂行するというのなら、リスクも呑まねばならない。
「アドミニストレーター……起動。世界救済機能に接続。ファナティックブラッド、代行開始」
黄金の輝きを背に、朽ちた救世主がその力を解き放つ。
「未来を否定せよ。異なる道を歩むというのなら、積層した可能性こそお前たちの敵と知れ」

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ

ダニエル・ラーゲンベック

高瀬 康太

メアリ・ロイド
バニティーがサルヴァトーレ・ロッソに姿を見せたのは、ほとんどファーザーと入れ違いのタイミングだった。
「お父様が来てるって“観測”はしてたんだけど、他の作業がけっこう忙しくて……!」
「わかっておる。それより邪神への突入は?」
「サルヴァトーレ・ブルが外殻を破壊してくれたから、ゲートは作れたよ。あとはこっちも乗り込むだけ!」
「聞こえたか、ダニエル艦長っ!」
『ああ、問題ない。ガーディアンには無用の心配だろうが……かなり飛ばすぜ。振り落とされるなよ!』
サルヴァトーレ・ブルのブースターが一気に炎を吐き出す。
青龍と大精霊の力で守られた船は、VOIDの大軍を文字通り薙ぎ払いながら邪神へと突き進んでいく。
「お父様……あなたたちと戦って、少しすっきりしたみたいだった。だから……うまく言えないけど、ありがとうね」
「礼を言うのは早すぎるぞ」
「……だね。サルヴァトーレ・ブルが先行してるから、急いで追いつかないと!」
宇宙にはたくさんの――数えきれないほどのCAMや戦艦の残骸が飛び散っている。
塵に紛れて見えないだけで、人間の死体もたくさん浮かんでいるのだろう。
可能な限り崑崙への召喚で救助を行ったが、どうしても屍は積み重なる。
ナディアはそれをじっと見つめていた。
彼らは死の間際、自らの決断を悔いただろうか。
或いは……その道の正しさを確信したのだろうか。
振り払うように視線を切って、前を見る。
巨大な邪神に空いた小さな穴。渦巻く闇の中へ、サルヴァトーレ・ロッソは飲み込まれていった。
●
閉じた瞼の上からも目を灼く白。生きたままミキサーにでもかけられたのかという振動。その後に聞こえたのは、歓声。
わずかに残っていた意識を散々に揺さぶられた高瀬 康太(kz0274)は、最期の気力を振り絞って目を開け、顔を向ける。
そうして、見た。
邪神の腹に開いた大穴を。
(ああ──道は、開かれたのか)
己が、皆が、命を賭して切り拓こうとした道は、先に続いたのか。
ならば……良い。
その為に流された血を、彼は『支払い』と表現した。
果たしてそれに見合う価値であるのかどうかは、今この結果だけで、彼が評価するものではない。
……この先も生きる者がその価値を見出し、創り出してくれることを祈るばかりだ。
そこまで思い彼が再び目を閉じようとしたところで、近づく機体があった。
R7エクスシア──サンダルフォン。その背にある特殊な、歯車の如きパーツは見間違えようが無いものだ。
康太のコンフェッサーはもはやほとんど破壊され、コックピットも剥き出しの状態となっていた。
メアリ・ロイド(ka6633)は駆け寄り、そしてすぐそばまで来ると自らもハッチを開けて康太のコックピットへと飛び移る。
抱きとめるその腕。その表情は。
救助ではなくただ会いに来たのだと、そう感じた。
そして。
「──康太さん」
彼女がそう呼ぶと、ふいに、康太は理解した。
割れたヘルメットの向こうで、康太の唇が動く。
メアリも咄嗟にヘルメットを跳ね上げた。これは。この言葉は。直接、何の隔たりも無い形で聞かねばならない。半ば本能で、そう感じて。
「──メアリ、さん」
たったそれだけ。
それだけを。
言い終えて、康太は納得する──ああ自分は、これを、直接己の声で聴かせるために、今この瞬間まで生きながらえていたのだと。
そうして、最期に康太は見る。
驚きに見開かれた後、微笑みに変わる、彼女の顔。
焼き付ける。
宇宙。星々の煌き。帰ると願った故郷、その蒼き輝き──それから、愛する者の今までで最も美しい表情。
その光景の中で。
(……邪神だけが……あまりにも邪魔じゃないですか……)
己の躯が。魂が。しばしここで彷徨う事になるのならば。
どうにか早く、何とかしてくださいよと──なおも戦う運命を背負う者たちに、そう託して。
高瀬 康太はここで、その命を燃やし尽くした。
●

大精霊リアルブルー

ベアトリクス・アルキミア

ルビー
突入を試みた艦隊はサルヴァトーレ級を除きその尽くが轟沈したが、僅かに残留した艦や兵士らはリアルブルーから出現する「使徒」と共に戦い続けている。
既に邪神はクリムゾンウェストにも直接転移できる状態にあるのだ。それを阻止し続けるために、二つの惑星――リアルブルーとエバーグリーンの封印が必要だった。
砕けたニダヴェリールの残骸に降り立ったマスティマのコックピットを開き、リアルブルー(kz0279)は戦場を睨む。
「彼らは行ったぞ、ベアトリクス。すべてを終わらせる為に……すべてを救う為に」
マスティマの掌の上、ベアトリクス・アルキミア(kz0261)は力なく横たわっていた。
ボディには傷一つなくとも、中身は既に燃え尽きている。
ここにあった大精霊の分体は消え去り、今やあのエバーグリーンという星の中心核こそが彼女の本質だ。
故に、ここにあるものはただの抜け殻に過ぎない。
そして今はまだ邪神を封じて輝いているあの星も、間もなく死滅するのだろう。
アレは滅ぼされた世界の意地そのものだ。ハンターが帰還するまではなんとか持たせると、ベアトリクスはそう言っていたが。
「――リアルブルーさん」
呼びかけに応じ、ルビー(kz0208)が転移してくる。
マーカーを起動したら“その時”だから、転移して迎えに来るようにと、元から決まっていた。
「ベアトリクスは逝った。その身体は持ち帰ってくれ」
ナディアの体内に顕現したクリムゾンウェストも、この小さな少年の胸に宿ったリアルブルーも、星の意思である「大精霊」全体から見れば小さな分体だ。
本体の力が失われれば分体を維持する余裕などないのだから、それが彼らにとっての「死」とも言えるだろう。
「ここまでベアトリクスさんを守ってくださって、ありがとうございました」
「……僕は何もしてないよ。さあ、ルビーはもう行くんだ。僕はエバーグリーンとリアルブルー、二つの封印の調停者としてここに残らなきゃいけない」
共に邪神の体内に突入したい気持ちもあるが、ここを維持しなければ突入班が帰還できなくなる恐れもあった。
少年の戦いはここで皆を待つことである。
ルビーはベアトリクスだったものを抱き上げ、そして言った。
「リアルブルーさん。ベアトリクスさんは、最後まで見届けていましたよ」
ゆっくりと視線を降ろし、少年は初めて、女の顔を見た。
その表情は眠るように安らかで――微笑みを湛えていた。
「……なんだよ。ちゃんと最後まで見てたんならそう言えよな。あんたに見せてやるために、僕は危険を承知であんたを……」
はた迷惑なヤツだったが、なんだかんだと世話になった。
気の抜けた炭酸みたいな笑顔で自分の頭を撫でる手を、鬱陶しく思い返した。
顔を上げ、燃え盛る碧の星を仰ぐ。
少年は黙ってコクピットに戻り、そしてマスティマは翼を広げる。
「『いってらっしゃい』」
飛び去って行くその光を、ルビーはベアトリクスと共に見送った。
●
「ちょっ……えっ!?」
邪神の体内に広がる「宇宙」。
それは既存の概念とは些か趣が異なる。
漆黒の闇に数多の光が輝いているという点は同じだが、「時間」も「空間」も曖昧な領域だ。
ゆっくりと――きわめてゆっくりと。スローモーションでサルヴァトーレ・ロッソは「なにもない場所」を漂っていた。
上下左右どころか、時間的にも前に進んでいるのか後ろに進んでいるのか……或いは停滞しているのか。
ヒトの自意識は所詮、正しい時間の流れの中で初めて正常に機能する程度である。
無重力空間などとは桁外れに、とにかく何もわからない。自己認識すら、消えてしまう……。
しかし、そんな感覚は長くは続かない。
サルヴァトーレ・ロッソが、“なにか”に“着水”したからだ。
「…………のわあああっ!? な、なにが起きたのじゃ!?」
「“道”に乗ったんだよ! 見て、サルヴァトーレ・ブルもあそこにある!」
闇の中、二つのサルヴァトーレ級は確かに前身していた。
船を乗せているのは――光の海。輝く光の粒が集まって流れを作り、どこかへと彼らを導いていた。
「まるで天の川……銀河のようなもの、か?」
「邪神の体内は基本的に時間も空間もしっちゃかめっちゃかなの。方向性を持たない混沌(カオス)そのものだから」
前後というのも所詮は人間の尺度の考え方だ。カオスの中には前も後ろも過去も未来もない。
そんな状況では人間は何もできないので、バニティーは道を作ったのだ。
「うん。よくわからぬが、わかった」
「あははー、わかんないよネ……。まあとにかく、この光の道から出ちゃだめなの。これは私が――魂の案内人が結んだあなた達みんなの“縁”。邪神の外側から応援してくれる人たちの祈りと、邪神の内側で終わりを求める人たちの祈りがつながったもの。神の世界へ渡るための、虹の橋だよ」

龍崎・カズマ
「さっきは傍にいなかったから出来なかったけど、今ならあなたの願いも叶えられるよ」
「俺の願い……か」
復唱しながら、カズマは目を閉じる。
(俺の本当の願いは……もう叶わないんだけどな)
どうして今、自分はここに立っているのか。
既に失敗した今でも、願いを忘れられなかったとファーザーは言った。その無様な在り方に、少しだけ自分の姿を重ねてみる。
結局、忘れることなんてできやしない。諦めることも、割り切ることも。
それでも命が続く限りを生きて。いつかは終わるために――。
(俺は、ガーディアンになったんだ)
差し出したカズマの手を、バニティーの小さな両手が包み込む。
「対価なら幾らでも払ってやる。俺は、この明日を願う祈りを束ねる!」
邪神の体内とはこの世ならざる領域。
クリムゾンウェストからも、リアルブルーからも、その内情を知る由はない――“本来”ならば。
それでは祈りを届けられない。それでは彼らを見守れない。
最前線に立つのが他人であっても、これは人類全体が当事者となるべき戦いだ。
少しでも彼らと想いを共にするために――。
せめて、目を逸らさずに見つめなければ。

トマーゾ・アルキミア
今だ戦いの続く崑崙の地下でトマーゾ・アルキミア(kz0214)が叫ぶ。
バニティーを通じて送られてくるハンターたちの姿形、命の光。
受け取った情報は世界中に張り巡らされた神霊樹のネットワークを通じ、人々に届けられる。
ハンターオフィスに用意されたモニターに。或いは、神霊樹の周辺に幻として。
そして、街の上空に――空を大きなスクリーンに変えて。
見上げる。見上げる。見上げる。
誰もが同じ思いで、旅立ったハンター達を想う。
その力が光となって崑崙に逆流し、そして邪神の体内へ――。
「はい、接続完了」
ぱっと手を放し、バニティーが笑う。
「……俺に代償はなしか? 想像したより呆気ないもんだな」
「そんなことないよ。あなたの感情をトリガーに世界を束ねたんだから、当然あなたはもう代償を支払ってる」
バニティーはカズマの胸に手を当て。
「これであなたは、その願いから逃げられなくなった。自分の願いに呪われたのよ」
「忘れられなくなった……ってところか? だったら、代償はなかったようなものだな」
どうせ――最初から彼女を忘れるつもりなどないのだから。
「さて、先を急ぎましょう。目指すは最果てにして始まりの星――ファナティックブラッドと呼ばれた大精霊の故郷。“惑星ジュデッカ”だよ!」
二つの船は、光の海を突き進む。
最後の旅が、始まろうとしていた。

南雲雪子

ダニエル・ラーゲンベック
ハンターはよく守っていたが、そもそも二隻のサルヴァトーレ級でこなすべき作戦を一隻で担えただけで僥倖と呼ぶべきだ。
「こちらの船にはロッソのように青龍機関(ドラゴニックエンジン)も搭載していませんから……性能的にも、そろそろ限界かもしれませんね」
邪神の体内にかけられた“光の道”を二隻のサルヴァトーレ級がほぼ横並びに進む。
これも幸運というべきか、結果としてロッソはほぼ無傷で温存された。
「ダニエル艦長。ここから先はブルが先行します」
『……まあ、妥当な判断だな』
南雲雪子の提案をダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は否定しなかった。
ブルを盾にして、最悪ロッソだけでも先に進むべきという意図は了解の上だ。
『崑崙とのリンクは途切れていない。最悪の場合は脱出艇を召喚してもらえ』
「承知していますわ……っと。やはり、このまますんなりとは行きませんね」
進むべき光の道の先。或いは、周囲に渦巻く混沌の中から、再びシェオル型の大群が転移してくる。
大精霊クリムゾンウェストが自らの地表のすべてを把握できていないように、体内に入り込んだ二隻の船を完全には把握できていないらしく、敵の数は「外」に比べればだいぶマシだ。
それでも、今は友軍艦隊もいないたった二隻の強行軍。敵の数は、これを圧殺して余りある規模だ。
「ああもう、いちいち数を数えるのがだんだん馬鹿らしくなってきた! 前後左右上下、とにかく敵です!」
「更にVOIDの転移反応を確認! どんどん増えて……艦長! このままでは完全に包囲されます!」
群れを成して覆いかぶさるシェオルは、まるで黒い雲のようだ。
だがその時。そんな黒い歪虚のカーテンを突き破る光が瞬いた。
「こちらを包囲しようとした増援の一部が……VOID同士で……交戦を始めました!?」
●
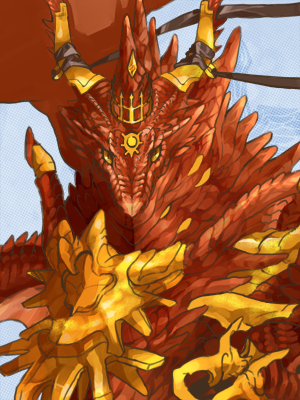
メイルストロム

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ
だが、その地に現れた邪神により滅され、そして想い出と共に“作り替えられた”歪虚だ。
邪神に取り込まれた者は、そのすべてが生前の形で再現され、時を刻むわけではない。
ただひとつの情報に過ぎぬものとして眠り続ける場合もある――彼もまた、そうであった。
そんなメイルストロムを目覚めさせたのは、バニティーが伝えたハンターの“願い”だ。
心無き王としてただ責務に努め、死後に求め続けた星の答え。
まさか、大精霊に姿形を与えてここまで連れてくるとは――まったく、ハンターというのは面白い。
『――さて。我らは既に道を譲った身、所詮は泡沫の幻に過ぎぬが……ヒトの子が新たな未来を求むなら』
強欲王は再び光のブレスを放つ。
一直線に貫かれたシェオルらが、蜘蛛の子散らすようにサルヴァトーレ級に道を開けた。
『今再び、厳格なる星の意思として君臨しよう。畏怖と共に仰ぎ見よ――我が軍勢を』
強欲竜らが次々に雄たけびを上げ、シェオルをその爪で引き裂き、かみ砕き、ブレスで焼き払う。
彼らは高度に統率された軍隊だ。本能だけで動き回るシェオルとは戦力としての質が違うのだ。
「強欲王メイルストロム! 来てくれたのか!」
「彼らだけじゃないよ。今、他の“イレギュラーズ”もどんどんここに向かってる。この戦いの様子はクリムゾンウェストだけじゃない。私の力で、この第二の宇宙全部に放送してるから……」
言葉とは裏腹にバニティーの声は弱弱しい。
見ればたっぷりと汗を掻き、顔を真っ赤にしながら息を切らしていた。
「ど、どうしたのじゃ!?」
「あっちこっちの世界を全部繋いでるから、さすがにちょっと体力がねっ! でも大丈夫……このまま、最後まで持たせて見せる……!」
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)はバニティーの身体を支えながら、彼女の存在感がどんどん薄まっているのを感じていた。
彼女の能力がなければ、この混沌の海の中で誰もが道を見失ってしまう。だが、こんなことを続ければいずれはバニティーが消滅してしまうだろう。
「……すまない……なんとか堪えてくれ」
「これはわたしが選んだ戦いなんだから……心配しないで。簡単にあなたたちを迷子にはしないから」
力強く微笑みを返し、バニティーは一度呼吸を整える。
「……リヴァイアサン、そこにいるの?」
呼びかけに答えるように、闇の中から幽鬼の如く姿を見せた者がいた。
白いドレスを纏った歪虚。彼女はドレスの裾をつまみあげ一礼する。
「はい、ここに」
「ぬおぉびっくりしたぁ!? だ、誰じゃこいつ……!?」

クリピクロウズ
かつてファーザーと袂を分かった邪神翼、リヴァイアサン。それはクリムゾンウェストで「クリピクロウズ」と名付けられていた。
彼女もまたハンターに討伐された身。だが、その想いは観測され、この第二の宇宙にて微睡んでいた。
「あれ、そっちの姿がお好みなの? 今のあなたは壊れた邪神翼じゃないんだから、好きな姿になれるでしょうに」
「好み……そうね。クリムゾンウェストの記憶とマージした時から、この姿を好んでいるみたい」
クリピクロウズは自らの胸に手を当て、己の名を噛みしめる。
「私はたくさんの私達に別れて、今は……あなた達の言葉で“異界”と呼ばれる場所を巡っています。仲間になりたいという歪虚を、ここに導くために」
「まさか邪神翼が味方になるとは……何がどうなるか、わからぬものじゃな」
クリピクロウズはかつて数多の悪意――クリムゾンウェストにおける反動存在により機能不全に陥っていた。
だが、今の彼女(ないし彼)は正しく邪神翼としてメンテナンスされた状態だ。
「ジュデッカの守りを弱める為に、私が反動存在を抑えます。元々……私はそういう役割だったから」
ヒトの心が有する闇。他者を妬み、苦しめようという本能。
邪神が蓄積するその不整合の処理も、本来的には邪神翼に期待された機能だ。
「他の邪神翼は……もう、反動存在に取り込まれてしまったけれど……」
「クリピクロウズは、クリムゾンウェスト側に本来の自我っていうか、あるべき形を残していたの。だからこっち側の存在にマージして……まあ、ともかく、彼女は味方よ」
「それは頼もしいのじゃが……クリピクロウズを再現できるということは、残りの邪神翼も……?」
「ええ。きっと、反動存在に操られて――」
正にそんな話をしていたその時だ。
邪神翼としか思えない強大な負のマテリアルを放つ、巨大な歪虚が進路上に姿を現したのは。
だが――その姿形はこれまでに観測された邪神翼とはかけ離れたものだった。
「なんじゃ……あの肉団子みたいなのは……!?」
「邪神翼の残骸……それを一塊にしてしまったのね。そうまでして、あなたたちを阻もうとするのは……」
怪物は先行しているサルヴァトーレ・ブルへと迫る。
そうしてその看板に取りつくと、汚泥にまみれた咆哮を上げた。
「いかん、サルヴァトーレ・ブルが!」
『いえ、これはむしろ好機です! ブルはこのまま加速し、この怪物をロッソから遠ざけます!』
雪子からの通信にナディアは目を見開く。
『こちらはこちらの任務を必ず全うします。だから、ナディア総長……後はお任せしますね。必ず、最後までこの戦いをやり遂げてください』
「南雲殿!」
「クリピクロウズ、あっちをお願い!」
バニティーの声に頷き、クリピクロウズはふわりと空に浮かぶ。
サルヴァトーレ・ブルは雪子の言う通り加速を続け、敵を引き連れながら遠ざかっていく。
それは誰の目から見ても無謀な行いで――しかし、有効であるが故に止める言葉を持たなかった。
●

マクスウェル

ラプラス

クリュティエ

カレンデュラ
戦闘を続けるサルヴァトーレ・ロッソの甲板に黙示騎士マクスウェル(kz0281)の笑い声が響く。
転移により姿を見せたのはマクウェル、ラプラス、そしてクリュティエの三人だった。
「くぅぅっ、次から次へと……!!」
『フッ、どうした? 随分とお仲間が減ってしまったようだなァ?』
鼻で笑いながら、マクスウェルはナディアの隣で苦しむバニティーに目を向ける。
『……フン。無茶苦茶をやった結果がそれか。無様だな、バニティー』
「まあね……。でも、自分で決めたことなんだ。だから……後悔はしないよ」
「バニティー……」
クリュティエは悲し気に目を瞑り、そして左右の剣を抜刀する。
「これがお前の招いた結末だ。数え切れぬほどの命を踏み台にしてここまで来ても、世界は何も変わらない」
「変わらない……? いいえ、違うわ。何一つ変わらないはずだった邪神の世界だって、今まさに“変わろうとしている”のよ!」
確かに、まだ何かが変わったというほどの違いはないだろう。
でも今、その変化を求めてようやく願い始めたところなのだ。
「誰だって本当はただ座ったままではいられないから……! どこかに行きたいと願うから……! 変わりたいと叫んでる! その声を、芽生えた願いを潰しちゃダメなんだよ!」
バニティーの言葉を遮るように、クリュティエは地を蹴った。
その一撃を防ごうと身を乗り出したナディア――よりも早く、頭上から降り立った別の騎士の姿があった。
繰り出したクリュティエの剣を受け止め、カレンデュラ(kz0262)は歪虚の左腕を繰り出す。
「この――ばっかやろう!!」
拳はクリュティエの頬を打ち、口元を隠していた面頬を砕く。
たたらを踏みながら口元から血を流し、拭いながらクリュティエは別の可能性を辿った自分を睨んだ。
「カレンデュラ! おぬしも来ておったのか!」
「やっほーお待たせ、ギリギリセーフ? ごめんね、積もる話とかも色々あるんだけどさ……!」
頬を抑えながら、表情一つ変えずに。
クリュティエは涙を流していた。ぽろぽろと繰り返し、大粒の雫が溢れ、頬を伝う。
「どうして今更……我の前に立ちはだかるんだ……」
頭の中を埋め尽くすのは、「どうして」という言葉ばかり。
「どうして……どうして! どうしてお前はそんなにも簡単に……っ!」
羨ましいと――素直にそう思った。
自分だって。自分だって。何一つ考えず、ただその時の衝動的な感情に従って動けたらきっと楽なのに。
どうしても考えてしまう。頑張ろうと思ってしまう。諦めてはいけないと、行動してしまう。
なんとなくわかっていた。もう彼らを救うことも、この壊れかけた宇宙が救われることもないのだと。
「いやだ……! イヤだ、イヤだイヤだイヤだっ!! うううっ……あああああああああっ!!!!」
だとしたら、どうなる?
これまで奪った命は、どうなる?
取り戻せない過去が。決して消えない罪の重さが。
その全身に重くのしかかり、恐怖に全身が震えた。
「諦めちゃダメだ……諦めちゃダメだ、諦めちゃダメだ……ダメだっ、ダメだダメだダメだダメだダメだ……!!」
「クリュティエ……」
「ダメなんだ……諦めちゃ……。それじゃあ我は……のために……。なんの……ためにぃぃぃぃ……っ」
子供のように泣きじゃくりながら。何度も涙を袖で拭いながら。
カタカタと切っ先を震わせながら、ありったけの嫌悪と憎悪のすべてを混め、鏡合わせの自分を睨む。
『クリュティエ』
そんな幼子に声をかけたのは、カレンデュラでもナディアでもバニティーでもなかった。
マクスウェルはその肩を叩き、大剣を抜く。
『任せろ』
「マクス……ウェル……?」
『あいつらはこのオレが一人残らずブチのめす。いいか、一度しか言わんぞ。“オマエは何も諦める必要はない”。だから泣くな。今は泣く時じゃない。騎士ってやつはな……最後の最後まで、笑ってなきゃダメなんだぜ』
その言葉にバニティーだけが驚いたように目を見開き、俯き、そして寂しげに笑った。
『ハーーッハハハハハ!! 茶番はここまでだ! 覚悟は出来ているんだろうなァ……ハンターども!!』
この戦いが絶対的な正義の旗の下にあるなどと、誰も思ってはいない。
立場が違って、運命が今とは少しだけ違っていたなら、こんなことにはならなかったのかもしれない。
けれども……現実はこうだ。こうなるべくしてなってしまった。
だから、嘆いていたって始まらない。
『決着だ……ハンター!!』
●
豊富な正のマテリアルに満ち満ちたその惑星を、人類はジュデッカと名付けた。
必然、その力の中心核となる大精霊も、同じくジュデッカと呼ばれた。
やがてその星そのものが、巨大な記憶装置となり果てても尚、名前は変わらなかった。
「私はこのシステムを、ファナティックブラッドと名付けた」
『ファナティックブラッド?』
「人類が持つ無限の可能性。脈々と受け継がれる知恵と勇気。即ち、血の宿業だよ」
私はネジの緩んだ眼鏡をしきりに持ち上げながら、大精霊に語りかけた。
「ジュデッカ。私の願う全世界の救済には、パートナーである君の力が必要だ。どうかこれからも、私の善き隣人でいて欲しい」
『もちろんです、エヴァグリオス。私の守護者、星の救世主。新たなる世界の父祖となる者よ』
そう答えた時、ジュデッカはどのような姿形を取っていただろう。
あえてヒトのような程度の低い存在の象る必要もなかったので、何かもっと高度な生命体を模していた気もする。
何にせよ、彼はヒトの善き理解者にして、善き管理者であった。
あらゆる世界の終焉に現れ、或いはそれを齎すもの。
物語の結末を強制的に幸福へと書き換える、圧倒的な力を有する盤外の存在。
我が友ジュデッカ。
ファナティックブラッドに取り込まれた人々は彼を見上げ――デウス・エクス・マキナと呼んだ。
●
サルヴァトーレ・ブルが成し遂げなければならない任務は残すところ二つ。
惑星ジュデッカが漂う記憶領域へと突入し、その守りを突き崩すこと。そして――。
「甲板に取りついた謎のVOID……やはり、邪神級です!」
オペレーターの報告を受けても南雲雪子は冷静だった。
どちらにせよ、このサルヴァトーレ・ブルはそう長くもたない。それは邪神への突入が完了した時点でわかっていた。
「ここから先は一本道です。すみませんが……付き合ってください」
雪子の声にクルーが頷く。と、その時。
『生者が、この世界に何の用だ』
全員の頭に響き渡る声――いや、音ではない。
思念のようなものが流れ込んでくる。そしてその発生源は、あの奇妙な肉団子だ。
『ここより先は、死者の領域』
『最後の地獄へと続く道』
『警告する。これより先は地獄(インフェルノ)』
『罪なき者のみ通るが良い』
数多の思念が、あの怪物の内に――いや。あの怪物を通じてどこかから送り込まれている。
「これが邪神の……いいえ。邪神に宿った反動存在の意思……?」
「どうしますか、艦長!?」
「艦の火砲で迎撃しつつ、怪物への対処は甲板に出たハンターに要請を。私達は少しでも早く……惑星ジュデッカへ!」
ブルの甲板に並んだ機銃がそれぞれ巨大な怪物へと銃口を向け、発砲する。
体表を覆う黒い肉を弾き飛ばされながら、巨体はゆっくりと前進する。
『警告モード終了。殲滅モードへ移行。これより異世界の救済を開始します』
(文責:フロンティアワークス)

マクスウェル
黙って見ているつもりだった。
だってそうだろう。自分は彼らを裏切ったのだ。
裏切り者がどの面下げて彼らを想うのか。そんなものは例外なく、全てが偽善の自己満足だ。
そうわかっていても、バニティーは倒れたマクスウェルに駆け寄る自分を止められなかった。
ハンターの猛攻を前に、黙示騎士マクスウェルは討たれた。これが決着だ。
『誰がお兄ちゃんだ……』
「うん……でもねっ、あのね……わたしはねっ!! お兄ちゃんを……」
『フン、何も言うな。お前らの声は……耳障りだからな』
聞いているとイライラする。女子供の声ってやつは、大嫌いだ。
本当はただ、バカみたいに笑っていて欲しかった。
誰も泣かせたくなかった。だから世界最強の騎士――英雄になった。
だのに、結局彼は誰も守れなかった。
“世界で最後まで生き残る”ために強くなったんじゃない。
でも、結局はそうなってしまった。
『……ああ。オレは……最後まで……』
その瞬間、マクスウェルは輝く塵となって消えた。
歪虚の最期はいつも決まってあっけない。
バニティーは膝をつき、呆然とその最期を看取る。
涙は流れなかった。そんなもの、流す資格もないのだから。

ラプラス

大伴 鈴太郎

クリュティエ

カレンデュラ
同じく、ハンターに破れたラプラスも消滅を待つばかり。
塵へと変わっていく身体をサルヴァトーレ・ロッソの甲板に横たえながら、大伴 鈴太郎(ka6016)を見上げていた。
『不思議なものだな。負けるつもりはなかったが、仮に我を討つ者があるとすれば、あなただと思っていた』
「おかしなことを言うじゃねぇか。その口ぶりじゃおまえ、まるで満足してるみたいだぜ」
『ふむ。生憎、我はそのような感慨を持ち合わせていないのでな。だが……最期までよく戦いぬいたものだ、ハンターよ』
「ハンターじゃねぇ。オレは大伴 鈴太郎だ。冥土の土産に覚えときな」
『そう、か……。そう……だったな』
ラプラスもまた、塵となって消え果てた。
「……不思議なものだな。仲間の死を目の当たりにしているというのに……我は、なぜ……」
唯一、クリュティエ(kz0280)はこの場に残り、刃を収めていた。
敗北を認め、そしてハンターの歩みについていくことを選んだ今でも、二人はクリュティエの大切な仲間だったはず。
それなのになぜだろう。二人の死に様を、悲しいと感じないのは。
「あたしも二回ほど人生終わった経験あるからわかるんだけどさ。思いっきり何かに打ち込んだ結果なら、敗北も死も意外と悪くないモンだよ」
カレンデュラ(kz0262)はけらけらと笑いながら語る。
「歪虚ってのは、もう終わってる存在だからね。そもそも生きてない。だから消える時は夢から覚めるみたいな感じっていうか……まあ、苦しくはないよ」
「何度も死んだ者は博識だな」
「師匠と呼んでくれたまえ。……マクスウェルもラプラスも、やるべきことをきっちりやった。クリュティエもそう思ってるから、悲しくないんだよ」
「そう……だろうか。ああ……でも、もしもそうだったら……あの二人が満足していたのなら……」
それはきっと素敵なことだ。
敵と味方。歪虚とハンター。命を奪い合い、お互いに憎み合うべきものたちであることに違いはないけれど……。
「そうだったなら……我は嬉しい」
サルヴァトーレ・ロッソの前方には、邪神の中枢、惑星ジュデッカが待ち構えている。
サルヴァトーレ・ブルと先行するハンターたちが道を切り開くことに成功した今、あとは突入を待つのみだ。
だが――。
『それ以上、近づくな』
音ではなかった。だが、確かに空間を震わせるような振動があった。
「うわっ、びっくりしたぁ?!? 急になにさ!?」
「反動存在……ジュデッカを制圧する者たちの意思だ」
意味もないのに耳を塞いだカレンデュラに、クリュティエが説明する。
「デウス・エクス・マキナを生み出したのも、今クリムゾンウェストを飲み込もうとしているのも、すべては反動存在の意思だ。尤も、彼らに明確な意思があるとは我らの思っていなかったが」
反動存在とは集合的な無意識のようなものだ。
人類の悪性の総体ではあるが、だからこそあやふやなものに明確な自我などあるはずもない。
ファナティックブラッドは暴走するシステム。
暴走というからには、明確な方向性など持つはずもない。それが黙示騎士の共通認識だ。
「言葉を話すなど、我も想定外だ」
『近づくな、近づくな、近づくな』
声なき声からは激しい拒絶、そして恐怖を感じられた。
反動存在は恐れているのだ。こんなところまで乗り込んできたハンターという異質な存在を。
ただ暴れていればそれでよかった。すべての世界を平等に飲み込む、暴力装置であればよかった。
それなら何も考えなくていい。愉悦も、恐怖も、すべてがフラットなままでいられる。
だが――この世界は違う。
反動存在という暴走する意思集合体を“冷静にしてしまう”くらいに、この状況は異常なのだ。
『我らに――近づくな!!』
ハンターが取るに足らない塵ならば、きっとジュデッカに乗り込むことも許しただろう。
叩き潰せばいいだけの羽虫なら、警戒することもなかっただろう。
そう思われている。そういう前提で、この作戦は立てられていた。
故に――反動存在が全力でハンターを拒絶し、この体内宇宙のすべてを屈折させ、「混沌」の迷宮にハンターを叩き落とすなど――。
誰も、想定外だったのだ。
●

バニティー
「混沌」の中には上下左右も時間の流れも、自分も他人も存在しない。
最期の記憶は、突然サルヴァトーレ・ロッソを黒い津波のようなものが飲み込む瞬間だった。
逃げ場などなかった。ロッソごと、すべてのハンターが「混沌」に呑まれてしまった。
(わたしが……なんとかしなきゃ)
バニティーは歪虚で案内人の能力を持っているから、混沌の中でもまだ動ける。
だが、ハンターはそれこそ数分も持たずに存在崩壊を起こし、邪神に取り込まれてしまうだろう。
そうなればすべての希望が失われてしまう。
(それだけは、ぜったいさせない!!)
落ち着いて、この広い広い宇宙に意識を巡らせる。
仲間たちは散り散りになっていて、今にも消えてしまいそうだ。
砂浜で小さな宝石を探すかのような、気が遠くなるような作業――。
(ああ、ダメ……消える、消えてしまう……)
こんなわけのわからないところまで、彼らを無理矢理連れてきたのは自分だ。
絶対に守らなければならない。その責任がある。
あれだけ多くの人々が背中を押してくれて、繋いでくれた道。なのに、ここで途切れてしまう。
ひとつ、またひとつ。誰かの命が、存在の輝きが砂に埋れて消えていく。
必死に手を伸ばしてもすり抜けてしまう。バニティーの能力では、これ以上「繋げない」。
絶望だった。
バニティーにしかできないことだ。大精霊にも、ハンターにも、できないことだ。
じゃあ“自分にできない”ってことは――“誰にもできない”ってことじゃないか。
恐怖し、半狂乱になって足掻く。
叫んで、喚いて、何度も手足をばたつかせる。
いやだ。いやだ。いやだ。
これじゃあ誰も救えない。これじゃあなんの意味もない。
お父様も、世界も、ハンターたちも――。
(お兄ちゃんも……無駄死に……)
深く、混沌の海へと沈んでいく。
バニティーが歪虚としてあり続けることを、反動存在はもう許さないだろう。
このままどこにも、どんな結末にも辿り着けないまま、止まった時の中で溶けるように消えていくしかない……。
……そう思っていた。

テセウス
誰かが自分の手を掴んで、バニティーは目を覚ました。
暗闇の中、テセウスがしっかりと少女の身体を抱き寄せる。
「大丈夫!? 良かった、間に合って!」
「テセウス……? どうしてここに……?」
「どうしてって……知ってるでしょ? 俺、シュレディンガー様から“眼”を譲り受けたんだから」
シュレディンガーの能力は、バニティーと対を成すものだ。
世界を観測する力。空間をつなぐ力。世界を虚飾で欺く力。
確かに彼ならば、この混沌の海からバニティーを見つけ出すこともできるだろう。
「お願いテセウス、力を貸して! みんなをもう一度“観測”しないと……!」
「確か、イミショーシツしてシェオルになっちゃうんだよね? 大丈夫、わかってるから」
テセウスはバニティーの身体を「上」に向かって放り投げる。
ふわふわと浮かんだ少女の身体は、巨大な機械天使――マスティマの掌に収まった。

クドウ・マコト
「ああ、引き受けた」
「マコトくん……!? あなたも一緒だったの!?」
「イグノラビムスもな。あいつは分裂しまくって、テセウスの指示でハンターを拾いにいったみたいだが」
思わず眼を丸くする。
彼らはまるで最初からこうなることがわかっていたみたいだ。
いや、そんなことよりも――。
「テセウス! それ以上潜ったら、戻れなくなる!」
「みんなを見つけるのは俺の眼の方が向いてます! 位置情報を共有するから、バニティーはみんなを一箇所に集めて!」
青年は手を振り、笑顔で深淵へと落ちていく。
その姿はやがて闇と一つになって、消えた。

シュレディンガー
黙示騎士シュレディンガーはきっと、最初から彼に何かをさせるつもりで作ったわけではない。
シュレディンガーはハンターという存在を邪神に取り込む為の前準備として、彼を作り出した。
ただの実験体だ。だから、ハンターをベースに歪虚が作れると判明した段階で、彼は既に役割を終えていた。
テセウスという名を与えて、黙示騎士としたのも、創造主の気まぐれから始まったことだったのだろう。
(今ならわかる。シュレディンガー様が見てきた世界の広さ……その深さ)
邪神の体内には、たくさんの可能性が眠っている。
実現されなかった願い。叶えられなかった夢。
数え切れない祈りが零した涙には、ひとつひとつ、小さな想い出が滲んでいた。
テセウスはそれをすべて観測できる。
世界の黎明から終焉まで、このファナティックブラッドという世界に張り巡らされた運命の糸、そこに絡まってしまったハンターの光さえ、何もかも。
だがそれは、たったひとつの自我に許された奇跡ではない。
見れば見るほどテセウスは「個」としての在り方を崩壊させる。
“そこにいるのかいないのか、誰にもわからないもの”になってしまう――。
……それでも。
ずっと分からなかった。
この瞳に宿る『力』が、一体何の役に立つのか。
こうして見続けることに、一体何の意味があるのか。
世界を見たら、一体俺はどうなるのか。
――今、その答えを得た。俺の行動に、存在に、確かに意味はあった。
俺のこれまでは、きっと。この時の為にあったのだ。
「……自己犠牲かぁ。それが、世界を見て君が出した答えなの?」
「……シュレディンガー様!?」
ではないだろう。直感的に理解した。
第二の宇宙と一つになるということは、こういうことだ。
すべての可能性を幻視する。そう、本来はあり得なかった夢も見られる。
いつの間にか二人はリゼリオに立っていた。
そこにはハンターたちの姿が……そして、家族同様に生活してきた黙示騎士たちの姿もある。
その顔はみんな明るく笑顔で、楽しそうで――。
「みんな仲良く、楽しく暮らす。そんな可能性もあったんだねぇ」
「そうですよ。だって本当は俺たちに争わなきゃいけない理由なんてないんですから」
世界は広い。可能性は無限大だ。
見れば見るほど、まだまだ知らない世界に出会う。
それを憂いた者がいて。それを嘆いた者がいて。
全知全能にはなれないからすれ違ったり、思い違いもしたり。
「俺、自己犠牲とか、そんなふうに思ってないですよ」
「じゃあ、何のため?」
「はっきりしたことは俺にもわかりません。でも、世界っていうのは……その一瞬だけとか、誰か一人の考え方とか、そういうものでは決まらないっていうか……。沢山の可能性が繋がって繋がって、今があるんです」
ふわりと浮かぶ水泡には、あの日シュレディンガーを守れた自分が映り込む。
その先に続く未来は、今とはまるで違うけれど。それを羨んだりはしない。
「俺ね、教えてもらったんです。人や物は消えても、大切に思っている限り心から消えないって。今ここで俺の存在が消えても、俺が繋いだものまで消えるわけじゃない。みんなが俺のことを覚えていてくれます。……それが、縁です。あとを任せられる、仲間たちがいます」
「ふうん?」
「俺、決めたんです。何一つ諦めないって。だから……後悔もないし、犠牲になる気もないです」
「…………そっか。んじゃ?、もうひと踏ん張りして、ハンターくんたちに未来を作ってあげますかねぇ」
散り散りになったハンターたちを観測し、バニティーに伝える。
バニティーがそれを認識できれば、あとはクリムゾンウェスト中の人々が――異界からここへ向かっているイレギュラーたちが――再び道を繋いでくれる。
遥か頭上、遠い遠い混沌の果てに虹の橋がかかるのを、二人は確かに見届けた。
「テセウスさぁ」
「はい?」
「いい出会いをしたね」
幻は消えた。
「……そうなんです。聞いてくれますか? シュレディンガー様がいなくなったあと、俺は――」
ハンターさん達と交流して、色々な人に会ったんですよ、と。テセウスは闇の中で独りくすくすと笑う。
心配性で優しい母さん。乱暴だけど面白い姉さん。色々なことを教えてくれるセンセイ。そっけないフリをして、優しくしてくれる友達。
それから……笑うと可愛くて、抱きしめると良い匂いがして、何事にも一生懸命な――特別に大切な人。
「ねえ、テセウス。花がどうやって咲くか、見てみたくない?」
――ついこの間、『世界』を見に行った時。会ったハンターと一緒に、植木鉢に花の種を撒いた。
彼は、『この花は、僕らヒトと歪虚とが共に何かを成せるという可能性の形』だと言った。
可能性の種。それが芽吹いて、綺麗な花を咲かせる姿を見てみたかった。
脳裏に過る咲き誇る花々。そこに、花のような微笑が浮かぶ。
……俺が消えたら、彼女は悲しむのだろうか。それとも、『偉かったね』と頭を撫でてくれるだろうか。
「……シアーシャさん」
暗闇で、その名を呼ぶ。
――悲しまないで欲しい。俺の姿は見えなくなるし、触れられなくなるけれど。
俺のココロは、みんなの傍にいるから。
だから、どうか――。
そして声も消え、深淵には静寂が戻る。
彼はそこにいるのかもしれないし、いないのかもしれない。
もう誰も、それを観測することはできなかった。
●

ダニエル・ラーゲンベック
「やれやれ……艦の状況を報告しろ」
「わかりません……12秒ほど、艦内すべてのシステムが停止していたようですが……」
「12秒……? あれがか……?」
もう何日も闇の中を彷徨っていたような気もする。
ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)は帽子をかぶり直しながら舌打ちした。
「怪奇現象の類には慣れたつもりだったんだがな……悪い夢でも見てたみたいだぜ」
「それがですね、艦長……まだ夢を見ているかもしれません」
「あん?」
「当艦……サルヴァトーレ・ネロに牽引されてます」
再び紡がれた虹の橋の上を、黒いサルヴァトーレ級が悠々と突き進む。
装甲から出現した黒い触手のようなもので、ブルとロッソ、2つの船を率いている。
サルヴァトーレ・ロッソの上に降り立った黒いマスティマは、そっとバニティーを甲板へと下ろした。
「テセウスはやりきったらしいな」
「……うん」
「あいつは消えたのか」
「……ごめんなさい。わたしにもっと力があれば……」
「気持ちはわかるが、謝るのはやめたほうがいい。あいつだって覚悟の上だ」
弱さはどうしようもなく悔しくて、悲しくて……。
でも、弱さの殻に閉じこもればそれこそシェオルと同じになる。
「俺は弱い。昔からずっと弱かったし、今も弱いままだ。それでも俺は、死んでいった連中に侘びたりはしない。理不尽であったとしても……ただ歯を食いしばって、堪えるしかないんだ」

イグノラビムス
その両腕にはぐったりした様子のハンターが抱えられていた。
『これで最後だ。全員、混沌の海から回収した』
「ありがとう、イグノラビムス。……もう、こんなコト二度と許さない! 一度見た可能性がわたしに二度も通用すると思ったら……大間違いだよっ!!」
光の河はジュデッカから迫る黒い波を突き破り、まっすぐに、一直線に、その地表を貫いた。
「ダニエルさん!」
「全速前進! 拒絶する暇なんて与えねぇ。このまま一気に――突っ込めぇ!!」
流星のように、光はジュデッカへと堕ちていく。
沢山の願い、その光に導かれ、ハンター達はついに最終地獄へと辿り着いた。
(文責:フロンティアワークス)

ファナティックブラッド
その様を、多くの者たちが見守っていた。
ここまで共に歩んできた者。あるいは、何かを託すために再びこの地に集った者。
サルヴァトーレ・ロッソは、いつか人類を救うことを願って作り出された鋼鉄の城塞だ。
未完成の力は世界を巡る旅路の中で研磨され、龍の力を宿すに至った。
光の翼を広げ、まっすぐに。
ジュデッカと呼ばれる、邪神ファナティックブラッドの中心に向かって、堕ちていく。
「龍鱗結界、最大出力!」
「同時に主砲もとっくに最大出力ぶっちぎりでチャージ完了です!」
「またどっかに転移させられるのも面倒だ。このまま敵の本丸に突っ込むぞ! 主砲及び全兵装一斉掃射! 食い破れェ!!」
まばゆい光が、数多のシェオルを薙ぎ払い、堕ちていく。
ダメだ、止められない。あれは命を賭した懇親の一撃だ。
シェオルでは止められない。止めるべき駒がもう、どこにもない。
あいつらが来る。人間のフリをした、バケモノどもが――!
あれは、なんなのだ?
誰がなんのためにあんなものを作った?
この宇宙の殆どを平らげた。
あとほんの僅か。あとほんの一押で、目的は達せられるのに。
一体誰がこんな埒外の存在を想定できる!?
憎い。憎い。憎い。
自分達は、あんな風にはなれなかった。
ふざけるな。いい加減にしろ。こんなのあんまりだ。
“誰も救われたいなんて言ってない”のに!
あいつらが来る。勝手に押し入って。
話なんか聞きたくない。これ以上見たくないし、聞きたくもない。
やめろ。やめろ、やめろやめろやめろやめろやめろ!!
こんな理不尽があるか!? あと一歩なのに!
台無しにされる! すべて、すべて……!
「そうだな。私達の主観からすれば、彼らは急に現れて、急にここまで来てしまった。なるほど、確かに理不尽だ。ここまで積み重ねてきたもの、その全てが無意味になる。まったくどうして、くだらない」
男が自らを嗤う。あるいは、我々を――。
「お前達は結局、何をしたかったのだ?」
決まっている。誰も救われないために、全てを救うのだ。
何もかもがゼロならば、強者も弱者も、勝者も敗者も存在しない。
痛みを忘れるために、“永遠に嘆き続ける”のだ。
結論なんてお呼びじゃない。決着なんてあり得ない。
そもそも求めていないのだ、終わりなんて!
「……そうか。永遠を求めるという意味で、私達は同じだったのだな」
何かが終わってしまうのは悲しいから、永遠を求めた。
誰も何も失わなければいい。ずっと冒険を続けたい――そう思ったから。
男の望む永遠は、“前に進み続けること”。
いつか道は途絶えてしまうから、それを無限にすることを望んだ。
だが反動存在は――永遠の求め方が違ったのだ。
“どこにも辿り着かないこと”を、結論を出さないことを求めた。
答えはいつでも冷酷だ。勝敗は付き、何かが終わり、苦しい現実を認めざるを得なくなる。
道があるから有限なのだ。ならば道をなくし、どこにも辿り着かなければそれも永遠となる。
反動存在も永遠を諦めたわけではない。無限のループこそ、彼らの望む永遠だったのだ。
「ならばやはり、私は違うのだな」
男はいつかどこかにはたどり着きたいと、そう強く願っていた。
永遠は求めたけれど、答えは欲しかった。
善悪成否を問わず。己の選んだ道がどこにつながるのか、それを知りたいと求めた。
永遠は――ただの過程にすぎなかった。
「私はね。旅を続けてきたのだよ。君たちとは違って、ね」
男は笑う。楽しげに、満足そうに。
「そして、答えを得たのだ」
●
惑星ジュデッカは既に星としての形を維持できていなかった。
体積は小さくなって、それを補うように無数の柱と板が複雑に絡み合い、表層を覆い尽くしていた。
星としての体裁を保とうとした誰かの努力の痕跡はサルヴァトーレ・ロッソの突撃で粉砕され、天には巨大な穴が開く。
ハンターらを載せたロッソは、ジュデッカの地表に座礁した。
モタモタしては再び敵に雲隠れされる可能性もある。今はとにかく接触することを最優先とした判断の結果だ。
「流石に無茶苦茶しすぎたか……ま、ここまでよく保った方だろうぜ」
衛星兵器コキュートスを先行するブルの部隊が排除してくれたこともあり、突貫も決まってもう中枢は目と鼻の先だ。
やはり図体がでかい船というのはいい。ただ突進するだけで大抵のものはブチ抜ける。
「艦長より全クルーへ。ハンターでもなんでもねぇただの凡人共が、よくぞまあこんなところまで付き合ってくれたもんだ。礼を言うぜ。総員、退艦準備だ」
いざという時には、やはり崑崙へ召喚してもらう手筈となっている。
だが、クルーはそれぞれの持ち場を離れようとはしなかった。
「これだけデカイ船で道を塞いどけば、後方から追撃してくる敵の邪魔になりますよね?」
「ピックアップはサルヴァトーレ・ブルが担当するにしても、まだ砲台くらいにはなれますよ!」
「船はダメでも私達はピンピンしてますからね。崑崙に退却するまで、もう一息粘りましょう」
「くくく、確かになぁ。よーしわかった。俺にもひとつ砲台を回せ。操舵も砲撃も若ぇモンには負けないってところを見せてやる」

ダニエル・ラーゲンベック

バニティー

ナディア・ドラゴネッティ

カレンデュラ

クリュティエ

カッツォ・ヴォイ

クドウ・マコト
ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)の通信はそんな言葉で締めくくられた。
ハンター部隊はロッソから次々にジュデッカへと降り立ち、突入の準備を進めている。
「敵を無視して突っ切ってきちゃったから、やっぱ追撃はあるよね。ジュデッカに残されてるシェオルも、ここに集まってくると思う」
黒き月を機能停止させたことでこの地に外部からシェオルが集まることは防げている。
だが、ジュデッカそのものに残留している反動存在直属のシェオルたちまで停止させることはできない。
「ああ……じゃが、ここで立ち止まるわけには行かぬ。先を急がねば」
バニティーとナディアの側についたカレンデュラ(kz0262)とクリュティエ (kz0280)は、互いに頷き合い。
「ならば、我らが打って出よう」
「空の方はメイルストロムたちが頑張ってるから、ジュデッカ内部の敵はあたしたちが食い止めるってことで」
「いや、しかし……流石に二人では無茶じゃろう?」
「そりゃ?、二人なら、ね?」
振り返るカレンデュラの前に、クリピクロウズと共に様々な姿をした戦士たちが転移してくる。
ハンターにより開放された異界の戦士たち。その中でも選りすぐりの英雄たちだ。
「なんかクリピちゃんには分体に向かって転移する力があるんだってさ。だからハンターと一緒にあちこちの異界に行って、仲間を増やしてきたってわけ」
「数は百にも満たないが……どれも一騎当千の英雄。これならば不足はあるまい」
クリュティエはハンターたちに、そしてバニティーに向き合う。
「……我では、ファナティックブラッドの未来を作ることはできそうにない。だが……お前たちに未来を託し、ここで戦うことはできる」
「やっぱり最後のおいしいところは、生きてる君たちに任せるよ! あたしらはあっちこっちで戦って敵の注意を逸らす陽動ってことで!」
笑いながらカレンデュラはクリュティエの肩を叩き、そのまま抱き寄せる。
「というわけで、仲良くやろうじゃないの、兄弟??」
「お前と兄弟になった覚えはないのだがな……それに、正しくは姉妹ではないだろうか」
「こういう時はキョーダイっていうんだよ! あたしは強いぞー、ついてこれるかな?」
「愚問だな。守る戦いは――大得意だ」
二人は剣を抜き、異界の英雄たちと共に走り出す。
彼らが方々でシェオルを蹴散らしてくれるなら、防衛もかなり楽になるだろう。
「さて……ハンターも送り届けましたから、私の本体は引き続き黒き月でシェオルの弱体化に努めます。皆さん、どうかご武運を」
言うだけ言って、クリピクロウズも姿を消した。ここに来たのは分体だったらしい。
「なにやらへんてこなお祭り騒ぎになってきおったのう」
「……だね。さて、わたしの案内もあと一息だ! 行こう! ジュデッカの中枢はこっちだよ!」
バニティーのあとに続きハンターらが走り出そうとしたその時。
「よもや本当にこんなところまで来てしまうとは。つくづく度し難いな、お前たちは」
立ちはだかるように現れたのはカッツォ・ヴォイ(kz0224)だ。
男の背後には手足のように動くオート・パラディンの他、シェオル型が群れを成している。
「カッツォ……ええい、しつこい! というかおぬし、邪神側についたのか!?」
「勘違いされては困る。この身は一度は王に捧げたもの……だが、今や誰のものでもない。私は私の意思でここに立っている」
シェオルの軍勢もカッツォに率いられているわけではないようだ。
単に、歪虚は邪魔をされない限り同じ歪虚を攻撃しない。彼はこの戦場において歪虚という立場にあるだけの中立なのだ。
「そいつとは話をするだけ無駄だ。あんたら人間とは、モノの考え方が違う」
そんな声と共に現れたのは、黒いマスティマ。即ち、クドウ・マコトだ。
クドウはハンターらの側につくようにカッツォと対峙する。
「クドウ・マコト。お前はそちら側につくことを選んだのだな」
「どちらかを選んだというには優柔不断だけどな。俺は俺の仲間と共に、俺の信じる形で戦い抜くと決めただけだ」
カッツォは残念そうに、しかしどこか嬉しそうに肩を竦めた。
「あんたのしつこさにはこっちもうんざりしてるんだが……昔、少しくらいは世話になったこともあった。出来ることなら、どこか遠くにいなくなってくれると助かる」
「そうはいかないな。お前達はこの世界、この宇宙という巨大な舞台を侮辱しにしようとしている。脚本家として見過ごすことはできない」
カツンと杖を鳴らし、カッツォは仰々しく腕を広げる。
「邪神ファナティックブラッドは、ひとつの巨大な舞台装置だ。デウス・エクス・マキナ……まさしくその類であろう。お前たちも気づいているはずだ。これは、ひとつの巨大な“悲劇”なのだと」
この無限の悲劇を生み出すシステムは、それでも誰かが願い、誰かが綴った脚本に即して動いている。
それをまるごとひっくり返そうとするハンターの所業は、殺人脚本家として認めがたい。
「クドウ・マコト。お前がお前であるためにお前の信じる戦いをするというのなら、私も同じ言葉を返そう。私はこの生き方を選んだ。このようにしか振る舞えないのだ」
「……カッツォ」
「人は皆運命の奴隷であり、世界という舞台の上で踊り続ける人形にすぎない。ならばそれを華々しく演出することこそ、私の使命……私の存在理由!」
そんな生き方を恥ずかしいとも、悲しいとも思わない。
シュレディンガーもナナ・ナインも、クドウ・マコトもそうだったのだ。
ならば自分もそうあることに、疑問などあるものか。
「あいつは俺が引き受ける。あんたらは先を急いでくれ」
「……わかった。クドウ・マコト。おぬしの力添えに感謝する」
「礼なら俺を口説いたハンターにでも言ってくれ。あんたもやらなきゃいけないことがあるんなら、道草食ってないでさっさと行きな」
頷き返し、ハンターと共にナディアは走り去った。
「カッツォ。出来ることなら、あんたをこの手で始末したくはなかったよ」
「ククク……なに、気にするな。ただお互いに譲れぬ生き方があるというだけのこと」
「そうだな。なら――遠慮はなしだ」
黒いマスティマが真紅のオーラを纏い、大気を震わせる。
「ここまで俺を育てたのはあんただったな。この力、存分に見せてやるよ」
(文責:フロンティアワークス)
逃げ場はどこにもない。ここが邪神の中心、それだけは絶対に動かせない真実。
ジュデッカを乗っ取るということはそういうことだ。反動存在は、とうにここに封じられた。
だが――まさかこんな状況を想定しているはずがない。
邪神だぞ? 宇宙そのものだぞ? 一体何がどうなればこんな理不尽が成るのか!
神も宇宙も運命をも粉砕し得る極小数の英雄、だと?
なんだそれは。わけがわからない。そんなバケモノ、想定できるものか!
『理解できない』
『なんなのだ、あれらは』
『本当に人間だというのか?』
『恐れている……? 私達が……?』
『宇宙にして、真実にして、永遠なる我らが……恐怖している?』
『ジュデッカは最強の神ではなかったのか!』
『力ではこちらが勝っている。だのに、この魂を震わせる怒りは、悲しみは、憎悪は……恐怖は……?』
『ここから逃げたい。誰かに代わってほしい』
『助けてくれるものは……誰でもいい、誰か……』
『誰もいないのなら……』
『『『また作ってしまえばよかろう――救世主を』』』
●

ナディア・ドラゴネッティ

バニティー

マクスウェル
惑星ジュデッカは、極限まで延命を図られていた。
魔法技術、機械技術、その双方を用いて失われていく星の力を留めようとした痕跡。それがこの巨大な遺跡である。
「曲がりくねってるけど、一本道だから。星の中心からマテリアルを効率よく運ぶためのパイプラインは、絶対に中枢に繋がってる」
「……ここで生きていた人類は皆、星を救おうと一生懸命だったのじゃな」
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)のつぶやきに、バニティーは頷く。
「彼らは生きることを諦めなかった。それ自体はきっと正しいコトなんだよ。その点は、あなたたちクリムゾンウェストも似てるけどね」
邪神の侵攻から生き残るために、邪神そのものをひっくり返してしまおうと考えた。
神の想定外、不意を突く判断だ。普通に始まって普通に終わる。そんな当たり前を蹴り飛ばしてみせた。
「だからあなたたちは、ジュデッカの願いを継ぐのに一番相応しい……わたしはそう思うな」
ハンターを率いて走る二人。その足が突然停止する。
正面、まさにジュデッカの中枢に辿り着かんとする直前、強烈な負の気配を感じ取ったからだ。
『――ヌオオオオオオオオアアアアアアアアアアアアッ!!』
「……なに!? 黙示騎士マクスウェルじゃと!?」
確かにマクスウェル(kz0281)はつい先程、ハンターとの決戦で撃破されたはずだ。
塵になって消え去るのも確認している。ならば答えはひとつしかない。
「再現したんだ……マクスウェルを。デウス・エクス・マキナとして……」
蘇ったマクスウェルはおぞましい負の力を纏っている。
これまでとは比べ物にならないほど、凄まじい戦闘力を発揮するだろう。
「なりふり構わないってことね……反動存在」
マクスウェルと共に、次々にシェオル型歪虚が出現する。
そのどれもがこれまで以上に強い力を有しているとわかる。
反動存在そのものに近づけば、それだけ強い負の力が迎撃に出てくる。考えてみれば当たり前のことだ。
『グゥゥゥ……オォォォ……ガ、グオオオオアアアアアッ!!』
「お兄ちゃん……反動存在に自我を奪われて……」
「マクスウェル……」
大剣を抜き、構えるマクスウェル。
そして男は――剣で周囲を薙ぎ払った。
「「え?」」
ハンターらの目の前で、シェオルの大群が真っ二つになり……。
残されたのはマクスウェルひとり。
『ふ……ざ……けるなあああああああっ!! 勝手に蘇らせおって!! このオレが許すわけがなかろうが!!』
「あ、ハイ。これはお兄ちゃんですわ」
「そんなことあるの?」
『このオレを誰だと思っている!? 最強の黙示騎士マクスウェル様だぞ! 反応ソーダだか半ドン惣菜だか冠婚葬祭だか知らんが、集合無意識ごときに操られるわけがなかろう!!』
マクスウェルはくるりと振り返り、押し寄せるシェオルの群れを片っ端から薙ぎ払っていく。
その戦闘力は凄まじく、数の差などまるで問題にならない。あっという間に敵は消え去り、道が開かれた。
『フン――さっさといけ、ハンター。冠婚葬祭はオマエたちに任せた』
「む……? 通してくれるのか?」
『既に譲った道だ。騎士に二言はない』
「そ……そうか。では遠慮なく通らせてもらうぞ」
おそるおそる、ナディアとハンターはこの場をあとにする。
なにせ、今のマクスウェルは本当に恐ろしい戦闘力だ。まともに襲われたら消耗は必須である。
だから無視して然るべきなのだが――バニティーはその場を動けずにいた。
「お兄ちゃんは……これでいいの?」
『何がだ』
「わたし……あなたに何もしてあげられなかった。助けられてばかりで……結局最後まで、わたしは……」
マクスウェルはぽりぽりと頬を掻き。
『だったらオマエも戦えばよかろう。好きなだけこのオレを助けろ』
「え?」
『道案内の役割は終えたのだろう? ならば世界のためではなく、自分のために時を使うべきだ』
大地に大剣を突き刺し、挑発するようにマクスウェルは手招きする。
『半ドン惣菜を倒すのに総力は必要あるまい。今こそ最強無敵となったこのオレと死合おうと望むなら、相手をしてやるぞ……ハンター!』
これは紛れもなく最強の敵だ。
ひょっとしたら反動存在よりも強いかもしれない。
ここまでハンターを導いた者として、バニティーは――。
「バニティー!」
先を征くナディアが振り返り、大きな声で叫んだ。
「案内ご苦労じゃった! 感謝する! あとはおぬしの自由にせい!」
「えぇ!? 自由って……でも、わたし……!」
「おぬし、ずーーーーっと我慢しておったのじゃろう? 最後は自分のために、成すべきことを成せ!」
走り去っていくナディアを見送り、バニティーは眉をひそめる。
「成すべきことって……そんなの、わたしには……」
『オレの戦いを見守るのでは不服か?』
背中越しの言葉に目を向け、バニティーは困ったように微笑む。
「……いいのかな? こんな大事な時に、自分の願いを優先したりして……」
いつもいつも、最後まで彼の側にいることは叶わなかった。
だから――どこかで諦めて、折り合いをつけてきたのに。
『オレが許す』
ああ。その言葉を……ずっと、ずっと……。
唇を噛み締め、うつむき、目尻を拭って……困ったように笑いながら。
「何度も出てきて死んだばっかりなのにまた復活して恥ずかしくないんですか?」
『イヤ、正直恥ずかしい。……だが! 復活してしまったものは仕方ないので満喫すると決めた』
「わかったよ。ごめんね、ハンターさん。私達と……戦ってもらえるかな?」
『フ、それでいい。歪虚なんてモンはなァ……どうせ吹けば消える幻のようなものだ。世界も! 宇宙も! 神も! ヒトの抱く想いを縛り付けることなどできやしない! いずれ消えるのなら今この瞬間に全てを賭ける! これがオレの永遠だ!』
再び剣を構え、騎士は嗤う。
『最後のリベンジマッチだ! 超絶究極無敵最強を恐れぬのならかかってこい! ――我が友よッ!!』
●

ファナティックブラッド

ファーザー
あらゆる事象を記録せんと願いながら、完成に至らず停止したままのアカシックレコード。
すべての中心座標でハンターらを待ち受けていたのは、邪神ファナティックブラッドを象った敵であった。
「ふむ……確かに、どうせ形を持つのなら、それが最適じゃろうな」
ハンターと共に邪神を見上げ、ナディアは眉を潜める。
「姿を見せぬと思えば――そんなところにおったのか、ファーザー」
ファーザーと呼ばれた男は今、反動存在の胸部に埋め込まれている。
まるで聖人の磔を思わせる様に、ファーザー自身苦笑を浮かべていた。
「お目汚し失礼する。私は元々、反動存在の支配下にある。先の行動で警戒され……この様だ」
「意外とおぬし余裕そうじゃな……」
「支配されてから永いのでな。おかしいだろうか……?」
「……待っておれ、さっさとそこから引っ剥がしてやろう」
『――何故だ』
それはヒトの声ではなかった。
先んじて発せられたものと同じ、反動存在の思念。それが語りかけてくる。
『オマエたちは何のためにここに来た。何を願い、何を望む?』
「ハ。仔細はハンターが答えてくれようが……そもそも、そんな問いになんの意味がある?」
『オマエたちは、この世界……第二の宇宙すら救わんと告げた。断言する。そのような奇跡は有り得ない』
「だからなんじゃ? ただの侵略戦争の応酬であったとしても、そんなもの見た目の問題じゃろうて」
そうだ。理由などそもそも関係ない。
ナディアは自分が正しいなどと微塵も思っていない。
大切な仲間を犠牲にしたのも、ハンターをこんなところまで連れてきたのも、余すことなくその全てが罪である。
当たり前の事実から目を逸らさない。戦いとは最初から凄惨なものだから。
『有限なる者よ。その思い上がりこそが悪であると知れ』
「おうおう、悪党で結構じゃなあ。それが一体なんじゃと言うのか」
『――何?』
「まさか永遠に等しい時を生きておきながら、未だに善悪だのくだらん言い訳をしていたのか? だとすれば……笑止千万。おぬしらの語る永遠など、児戯に等しい」
反動存在は、弱者の願いの象徴だ。
弱さも、集合体であるからこその強さも、何一つ人間から逸脱しない。
どちらかといえば、逸脱しているのはハンターの方だ。とっくに人間離れしてしまっている。
普通に考えて、個人が背負えるような戦いではないからだ。
故に恐怖する。有象無象の集合体にすぎない反動存在には、理解すらできない。
『認めぬ……オマエたちが、ヒトの答えであるはずがない!』
「いいや。我らは人間だ。ただ当たり前に生まれ、そして死んでいく……弱く儚く愚かしく、そして素晴らしい人間そのものだ」
『認めぬ! 認めぬ! 認めぬ!!』
怪物が吼える。恐怖に負けそうな己を鼓舞するかのように。
『もういい。永遠など捨て去ろう。どこにも辿り着かなくてよい。再誕すら不要となった。我々はただオマエたちを嫌悪する! “弱者”こそヒトの本質! “破滅”こそヒトの願い! ただ何もかもを焼き尽くすために、ファナティックブラッドのすべてを費やそう!!』
膨大な「第二の宇宙」という概念をすべて負のマテリアルに変え、邪神は力を高めていく。
これは最早生物を相手取った闘争ではない。宇宙という途方も無い概念との対決である。

イグノラビムス
「イグノラビムス? おぬしも来ておったのか」
黙示騎士イグノラビムス。獣の姿を取った救世主は、邪神の胸の磔を睨む。
『反動存在は所詮、姿形を持たぬ妄念の集合体。アレはジュデッカとファーザーに接続されて初めて威力を持つ』
「ならばやはり、ファーザーを切り離すのが優先じゃな」
『ファーザーを取り込んでいる限り、やつは不滅の呪いに守られている。あれを引き剥がすのは、同じ救世主の仕事だ』
一歩前に出たイグノラビムスの身体が黒い炎にまかれ、みるみる巨大化する。
黙示録の獣――だが、悍ましいその姿とは裏腹に、確かな知性が感じられた。
『星を継ぐものとして、私は私の成すべきを成そう。祈りに汚れたこの爪と牙ならば、奴にも通用するだろう』
「手を貸してくれるのか? ならば、ここは守護者とおぬしに任せよう」
『……だが、救世主の力で出来るのはそこまでだ。あの集合思念を食い破るのは、神の祝福であってはならない』
反動存在――“神や救世主に救われる権利”を有する彼らは、そうであるが故に神や救世主を貪る特性を有している。
ヒトが祈り、ヒトが求めたものが救世主なら、その救世主を殺すのもいつだってヒトの弱さだ。
守りを剥がすところまでは救世主の仕事。だが、反動存在に止めを刺せるのは、救世主ではない者の一撃に限られる。
『当たり前の人間。それが反動存在の弱点だ』
「…………そうか」
どこか寂しげに、悲しげに、ナディアは短く答えた。
この反動存在と呼ばれるものたちも、きっと悪ではないのだろう。
妬ましかったのは、正しさを知っているから。
悔しかったのは、努力したから。
悲しかったのは、無力だったから。
逃げ出したのは、それしかできなかったから。
それでも縋ったのは――きっと、精一杯の……。
ならば悪ではないと知りながら、それでもすべてを否定しよう。
「ゆくぞ! これがソサエティ総長として最後の命となる! 邪神を打ち倒し、この戦争に終止符を打て!」
『消えろ! 世界も、宇宙も、オマエも我らも……すべて!!』
凶悪な負のマテリアルも、邪神としての姿も、所詮は虚仮威しだ。
強力な敵ではあるだろう。だがそんなもの、今に始まったことではない。
あなた達は勝利できるし、その先に願った未来も掴み取れる。
それだけの時間を、努力を、願いを積み重ねてきたのだから。
闇穿つ意思よ。運命に抗う、星の友よ。
すべての旅路、すべての願いを肯定しよう。
今こそ――ファナティックブラッドに幕を引く時だ。
(文責:フロンティアワークス)

エヴァンス・カルヴィ

夢路 まよい
「……なんだ? 勝ったのはお前だ。トドメを刺さないのか?」
『確かに勝ったのはオレだが――勝敗というなら前回であろうよ。こんなつまらぬところで死なれては困る。オマエ達にはこのオレの最期の戦いを伝えるという義務があるのだからな!』
腕を組み、背中を仰け反らせながら高笑いするマクスウェル。
エヴァンス・カルヴィ(ka0639)は口元の血を拭いながら眉をひくつかせる。
「ちっくしょう、やっぱ負けっぱなしは腹立つぜ……! マクスウェル、もう一回やらせろ!」
『フッハハ?ン、いいだろう――と言いたいところだが、そうもいかないようだな』
続けて、先程よりも大きな衝撃がハンターらを襲った。
立っていられないほどで、くるくる回りながらよろけた夢路 まよい (ka1328)をエヴァンスがキャッチする。
『下では決着がついたらしい。間もなくこの惑星は崩壊するだろう』
「ジュデッカは倒されたんだね! でも……あなた達はどうするの?」
「先に進んだみんなの救出に行くよ」
「だったら私達も……」
『そんな様で何ができる。足手まといだ』
マクスウェルはバニティーを片腕で荷物のように抱える。
『最後まで付き合ってくれたことに感謝する。家に帰るまでが遠征だ……逃げ送れて死ぬなよ!』
猛スピードで走り去っていくマクスウェルを見送り、まよいは笑みを浮かべる。
「……うん。これで決着。いいよね、エヴァンス?」
「んん……まあ、実際もう何も出来やしねぇし……悔しいがここは退散だ! 死ぬために来たわけじゃねぇんだ、生きて帰るぞ!」
●

ナディア・ドラゴネッティ

ファーザー

イグノラビムス

紅薔薇
ジュデッカは内側から光を放ち爆散した。
その身体は崩れ去り、塵となって消えゆく。歪虚の最後は決まっている。だが――。
『最早このジュデッカが崩れ去るのみならば、せめてオマエたちの願いだけは妨げてみせよう』
無数の黒い光――怨霊とも呼ぶべき思念の輝きが渦を巻き、ハンターらを吹き飛ばした。
「勝てないなら道連れか……性根が腐っておるな」
「勝敗――結果を出すことこそ奴らは最も嫌うからな」
ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)の言葉に、相変わらずぼんやりした様子でファーザーが応じる。
「気を抜くな。奴らは救世主や神の類を喰らい、その力を奪う……お前は格好の標的だ」
ファーザーの言う通り、反動存在の狙いはナディアだ。
大精霊にして救世主。その器を奪ったところでだからどうなるわけでもないが、少なくともハンターの願いは阻止できる。
これで「全員不幸」になれる。万々歳の勝利と言っていいだろう。だが――。
『お前たちの出方などお見通しだ』
次の瞬間、反動存在の闇を喰らう者がいた。
黙示騎士イグノラビムス――それが巨大化した“黙示録の獣”の牙が、反動存在を噛み砕いたのだ。
『やめろ! オマエも棄てられた者……救世主でありながら、敗北者の代表であろうが!』
『然り。故に我はどちらでもあり、どちらでもない。私はどこにも辿り着けぬ者――永劫の体現者である。お前たちの好んだ“救世主の器”だ。好きなだけ入るがいい』
咆哮に吸い寄せられるように、反動存在は次々にイグノラビムスへと憑依していく。
その姿が黒く歪み、怪物に成り果てても、しかしイグノラビムスは心を失わなかった。
『反動存在は私が抑える。事を成すなら今の内だ』
ナディアはファーザーと頷き合い、そして前に出る。
大精霊ジュデッカが消え去る時、このアカシックレコードに貯蔵された正のマテリアルも解放される。
それを逃さず捉え、第二の宇宙の記憶とひとつになった時、願いは叶えられるだろう。
「ナディア殿!」
紅薔薇(ka4766)は叫ぶ。その願いが叶えられるということは、ナディアと彼女に憑依する大精霊との別れを意味しているからだ。
「新しい世界を作り出すというのなら、そこにナディア殿と大精霊の器も作り出すことはできぬのか……?」
「命とはそう簡単に置き換えられるものではない。確実性を重視する……といったもの以前に、これは必然じゃ」
別に死にたいわけではない。ただ、余計なことに気を割いている余裕はない。
これから第二の宇宙という膨大なエネルギーをひとつの世界として再編するという大事業を成し遂げねばならないのだ。
生きながらえるかどうかよりも、それを成し遂げられるかどうかの方が重要だった。
「命はいずれ潰える。その当たり前を是とするから、永遠を否定したから我らはここにいるのだから」
アカシックレコードが砕ける。
空間に亀裂が入り、数多の光の粒が吹き出した。
誰かの想い出、誰かの願い、誰かの絶望……。
当たり前に輝いたそれらを束ね、新世界の門を開く。
「ファナティックブラッドよ。世界救済のシステムよ。今こそ正しき力を我らに示せ」
ファーザーの呼びかけに呼応するように、空間がねじれ、歪み、神秘的な輝きがすべてを満たしていく。
世界の滅亡と再誕の光――。
「当然というべきか、このままでは爆ぜるな。超新星爆発に匹敵するエネルギー量だ」
「……じゃろうな。この場には我とファーザーが残る! ハンター部隊は直ちに撤退! クリムゾンウェストに帰還せよ!」
ナディアはきっぱりと別れを告げた。
傷ついたハンター達は再誕の光に照らされ、振り返ったナディアの姿を瞳に焼き付ける。
「ここまでよくぞ戦い抜いてくれた。心より感謝するのじゃ。邪神なき後も、世界は続く。ヒトは歴史を紡ぎ、星と共にあり続けるじゃろう。ヒトの戦いは永久に続く! 生きて責務を果たせ!」
力強く宣言し、そして最後にナディアは子供のように無邪気に笑った。
「あとのコトは、頼んだのじゃ」
●

カレンデュラ

クリュティエ
ここまでは召喚救出が可能であったが、ジュデッカ崩壊が始まれば座標は複雑化する。
安全地帯までサルヴァトーレ・ブルで移動しなければ離脱は叶わなかった。
「そしてシェオルは邪魔をしてくる、と……やれやれ、最後まで慌ただしいな」
クドウ・マコトはシェオルの追手を蹴散らしながらハンターの帰還を待っていた。
同じくシェオルと戦いながら時間を稼ぐカレンデュラ(kz0262)らイレギュラーズであったが……。
「いやー、地面がめちゃめちゃ揺れて戦いづらいね! クリュティエ、ここはもういいから君も船に乗り込むんだ!」
「何を馬鹿なことを……。ここで我だけ退く理由がない」
「理由ならあるよ。忘れたの? あたし達は所詮邪神に再現された想い出なんだって」
クリュティエ(kz0280)の瞳が驚きに開かれる。だが、わかっていたことだ。
カレンデュラの姿は、徐々に透明になりつつあった。周りのイレギュラーズもそうだ。彼らは邪神の力で再現されたモノ、いわば邪神の一部に過ぎない。
「想い出は想い出に還る――あたしたちはジュデッカと一緒に消える運命だからさ。でも、君は再現された存在じゃないし、邪神とも独立してる。君はまだ帰れるんだよ」
「帰る……この我が……」
「それが君の罰だ。ここで死んで楽になることは許されない。君は君が認めたモノが作り出す未来を、その目で確かめる義務がある」
歩み寄り、ポンと肩を叩き、そしてカレンデュラはもうひとりの徒花の騎士を抱きしめた。
「君が生まれてくれてよかった。ちょっと代わりに明日を見てきてよ。それがもしも素敵なものだったなら、あたしの代わりに笑ってほしい」
「カレンデュラ……」
「人生は取り返しのつかないことだってあらぁ! でも、大抵のものは償える。投げっぱなしたり、逃げ出したりしなければね!」
身体を離し、怪物の腕でサムズアップして、騎士は背を向けた。
「諦めんなよ、妹!」
「ああ。ありがとう。そして、さようなら――姉さん」
カレンデュラはシェオルの大群に突撃し、見えなくなった。
もう振り返らないし、涙も流さない。これは罰であり責務。
迷いなく、クリュティエはサルヴァトーレ・ブルへと走った。

ダニエル・ラーゲンベック

南雲雪子
「お気になさらずに。どうせそんなことだろうと思っていましたから」
ダニエル・ラーゲンベック(kz0024)を始め、一部のロッソクルーは結局最後まで居残ってしまい、今はブルの艦橋でサポートにあたっている。
南雲雪子は小さくため息を一つ。部下からハンター収容の報告を受けると、即座に檄を飛ばした。
「これよりジュデッカを離脱! 邪神の外で我々を召喚するリアルブルー大精霊に感知される場所まで移動します!」
大穴の中でサルヴァトーレ・ブルが回頭し、崩れ行くジュデッカから一目散に離脱する。
異界の戦士らは、遠くへ消え去っていく方舟を見送る。
手を降ったり、大きな声で別れを告げたり……。
何にせよ、ジュデッカと共に消えていく彼らの最期は、悲愴とは程遠いものだった。
「惑星ジュデッカより無事離脱! 本艦は帰投ルートに入ります!」
「着水、耐衝撃!」
サルヴァトーレ・ブルはここまで導いてくれた光の道に再び乗り込んだ。
接触と同時に派手に光の飛沫をぶちまけながら、最大加速で一気に前進する。
「ジュデッカを中心に、この空間全体が崩壊していきます!」
「落ち着いて対応を。すべて予定通りです」
中心核を破壊すれば邪神が崩壊する――その前提で乗り込んだのだから、驚くようなことではない。
最初からわかっていた。ナディアを置き去りにすることも、作戦の内――なのだが。
「艦長!!」
「何事です?」
「前方、光の道が途切れます!」
世界崩壊に巻き込まれたわけではない。道は故意に絶たれていた。
黒い靄のようなものが虹を侵食している――。
「反動存在、ですか」
『逃さん……! 誰一人ここから生きては帰さない!!』
「主砲撃っちまえ」
「はい。もう撃ちました」
発射された閃光が靄を貫く。しかし、反動存在は消え去らない。
『我らを何と心得る!? この宇宙の総意が、人間風情の攻撃で消えるものか!』
「掴まってください。退路はありませんので突っ込みます」
むしろ、加速。
サルヴァトーレ・ブルはそのまま巨大な靄に突撃するが、前進を阻まれてしまう。
「ひえええーーーーーーーーー無茶苦茶です艦長おおおおおおおおーーーーーー!?!?」
「普通そこでアクセル踏みますか!?」
「ていうかこの黒い光……間違いありません! 縮退してますっ!」
「ああ。ブラックホールですか?」
「「「「ですっ!!!!!」」」」
クルーが全員青ざめた様子で振り返る。
「困りましたね。打つ手なしです」
いくらサルヴァトーレ級が最新最強の戦艦であったとしても、現時点の人類に宇宙法則をどうにかする技術はない。
『ははははは……はははははははは!!!! 消えろ!! バケモノ共!!』
『喧しい! 消えるのはオマエだッ!!』
一閃――。
空間は切り裂かれた。

マクスウェル

バニティー

クドウ・マコト
『……………………は?』
『感謝するぞ冠婚葬祭。オマエらがこのオレをデウス・エク……ンン?、なんとかカントカにしてくれたお陰で、力が漲りまくりだ』
返す手で更に横一閃。十字に切り裂かれたブラックホールは消滅し、黒い光は霧散する。
「マクスウェル……? あんた死んだんじゃ?」
『クドウ・マコトか。オマエこそしぶといじゃないか』
「帰り道に困ってるかもって、お父様とナディアに言われてね」
マクスウェルとバニティーはハンターとすれ違い、最深部へ向かった。
そこで世界の再誕に注力する二人に代わり、脱出の支援を任されたのだ。
「あんたブラックホールを斬れるのか……」
『斬れると思えば大抵のものは斬れる。オマエら根性が足りんぞ』
「お兄ちゃん、ずっと前から思ってたけどバカだよね」
「それで、総長の方は?」
「世界の再誕は問題なさそう。あとはハンターのみんなが脱出するだけだって」
だが、一度崩れた虹の橋は元には戻らなかった。
ねじれた宇宙の中、行く宛もなく彷徨う船。しかし、バニティーは叫ぶ。
「わたしの言うとおりに飛んで! 道は見えなくなっただけで、消えたわけじゃない!!」
サルヴァトーレ・ブルは、バニティーの言葉に従って飛ぶ。
右へ左へ、上に下へ。時にはUターンしたりすることもあるけれど、壊れゆく宇宙の中で彼らは迷わず飛び続けた。
「後少し……もう一息。だから、頑張れって……」
クドウはふと、ある青年の事を思い出していた。
直感でわかった。これはバニティーの能力ではない。
誰か、彼女よりも強力な観測の力を持つ者が、彼女を通じて指示しているのだ。
黒いマスティマが振り返る。当然、そこには誰もいない。
「見えなくなっても、消えたわけじゃない……か」
ふっと笑みを作り、青年はつぶやく。
きちんと進んでいるのかどうかもわからなかったが、いつの間にか再び現れた虹の上にサルヴァトーレ・ブルは着水した。
「サルヴァトーレ・ブル、ルート復帰! 問題なく離脱できます!」
艦橋からの無線にバニティーが安堵の息を零した。
「よかった。ここまでくれば、あとはもう……」
『そのようだな。オレもここまでだ』
顔を上げると、マクスウェルの身体もまた少しずつ透明になりつつあった。
彼は一度死に、そして邪神に再現された幻に過ぎない。
邪神が消え去れば共に消え去る運命だった。
『ならばオレは最期まで戦おう。どうせ諦めの悪い連中のことだ。なんとかオマエらを追撃しようとするだろうからな』
「わたしも一緒に行くっ!!」
ほぼノータイムでバニティーが叫んだ。
「わたしも一緒に行く」
『なぜ二回言った』
「だって……ぜったい一緒に行くから」
バニティーは邪神の一部ではない。「王」として、神から切り離された存在だ。
腐っても虚飾王をやっていた時期があるだけに、彼女は反動存在からも独立して動くことができていた。
つまり、ジュデッカと共に消えてしまうことはないのだ。
「どうせ消えないんだからお前は一緒に出ていけって言うんでしょ。でも、絶対イヤだからね。わたしはお兄ちゃんと一緒に残る」
『残ってどうする。戦えるわけでもなかろうに……ただ消えるだけだぞ』
「ただ消えるだけじゃないもん。一緒に……だもん」
俯き、両手の指を絡めながら少女は唇を噛みしめる。
「もうやることはやったよっ! 一緒に帰ったってわたしに出来ることなんかなんにもない! わたしはただの役立たずで……足手まといで……それでも、一緒にいたいんだよっ!!」
叫び、駆け寄ってその背中に縋り付く。
「お願いだから……もう……わたしを、おいていかないで……」
『……ハア。別に何も言ってないだろうが。ついてきたければ好きにしろ』
涙に濡れた顔を上げると、マクスウェルの大きな掌がその頭を撫でた。
『観客がいないと戦いにも身が入らなくて困っていたところだ。このオレの武勇、最期の一瞬まで見届けるがいい』
「――うん! ずっといる。ずっと見てるよ。最期の最期の一瞬まで……ずっと、ずっと」
嬉しそうに頬を寄せる少女をひょいっと持ち上げ、肩車する。
『クドウ。オレはお前もクリュティエも、黙示騎士とは認めていない。オマエらは“オマエら”だ。それ以上も以下もなく、な』
「……ああ。おさらばだ、黙示騎士。あんたは確かに最強だった」
『さらばだ、クドウ・マコト! つまらんただのニンゲンよ!』
サルヴァトーレ・ブルの甲板を走り抜け、マクスウェルは跳んだ。
黒い闇がすぐそこまで迫っている。
ザコの群れだ。実にくだらない。そんな連中に、獲物は渡せない。
『あいつらはオレのライバルだ。オマエら如きには勿体ないわ!』
『退けえええええええええええっ!! 黙示騎士ッ!!!!』
『ハッ――嫌だねェ!!』
その日は確か、雪が降っていた。
星は命の熱量を失い、少しずつ冷えて固まっていく。
降り立った巨大な邪神の影を見上げながら、騎士は最後の一人になっても戦い続けた。
多くの仲間は諦めて、死を受け入れたという。
いつかは再生されて、永遠の幸福が手に入るのだという。
くだらない。願い下げだ。永遠? 幸福? ――勝手に決めつけるな!!
オレはここでよかった。オレはただこれだけでよかった。
当たり前の日々が続けばそれでいい。何もいらない。オレは――。
「お兄ちゃん。ジェームズお兄ちゃん」
騎士は振り返る。歪虚に食い殺されたはずの妹がそこに立っていた。
男は守れなかったその幻影を見て後悔した。なのに、妹らしき者は手を振って叫ぶ。
「がんばれ、お兄ちゃん! 負けるなーっ!!」
ああ――幻でもいい。
戦場に風が吹いた気がした。
「ったく、しょうがねぇなあ」
剣を握り締め、構え直す。瞳に光が戻って、男は笑みを浮かべる。
「家族の前で……ダセェところは見せられねぇよなァ!」
雪を踏みしめ、一歩前へ。
どうせ勝てやしないし、死ぬのはわかっているけれど――。
そういう問題じゃないんだ。勝っても負けても、生きても死んでも。格好悪いのはだけは嫌だから。
誰かと一緒なら、寂しくないから――。
白い記憶の中へ騎士の背中が吸い込まれて消えるのを、少女はただずっと、ずっと見つめていた。
●

大精霊リアルブルー
胸部に作られた亀裂は巨大化し、邪神全体が崩れていく中、内部から飛び出す小さな影があった。
「サルヴァトーレ・ブル! 戻ったか!」
嬉しそうに大精霊リアルブルー(kz0279)はコクピット内で身を乗り出す。
即座に翼を広げたマスティマは邪神への突撃を開始した。
邪神は内側に向かって吸い込まれるように砕けながら、その膨大なエネルギーを放出しようとしている。
このまま行けば周囲の空間を――というか「地球」をまるごと吸い込んで、さらに爆散するほどの力がある。
「ったく……消えるんなら誰にも迷惑をかけないところで消えてもらいたいものだね」
邪神の正面に浮かび、マスティマは巨大な魔法陣を背にする。
「ベアトリクス……あんたの力、借りるぞ」
右手を前に。そしてマスティマはコクピット内のリアルブルーと動作を連動させる。
「これで――終幕だ」
パチンと、少年が指を鳴らすと。
崩壊しかけた邪神の全身が別の空間――異世界へと吸い込まれていく。
第三の世界、エバーグリーン。惑星としてのそれをリアルブルーに呼び出したのには、もう一つ理由がある。
「消えろ」
邪神の姿は一瞬で、幻かなにかであったかのように消え去った。
そして――リアルブルー側の空間も歪むほどの大爆発。
邪神が送り込まれたのは、星を置かないただの虚無と化したエバーグリーンの宇宙だった。
エバーグリーンとリアルブルー、2つの惑星はくるくると踊るように回って、静かな軌道を描いた。
「結局、自分以外何も犠牲にせず、か。あんたには敵わないよ……先輩」
ゆっくりと宇宙を漂うサルヴァトーレ・ブルを見上げ、少年は微笑む。
英雄たちを迎えに行くため、マスティマは光の軌跡を描いた。
(文責:フロンティアワークス)

ファナティックブラッド
異世界より侵略する巨大な歪虚、邪神ファナティックブラッドを逆に乗り込んでぶっ潰した人類は、ついに平和を勝ち取ったのだ。
だが、その代償は大きかった。
多くの戦死者。シェオル型の侵略により非戦闘員も多くが殺傷され、星の環境も破壊された。
特に星の弱り方はかなりのもので、せっかくハンターの活躍でここのところ復調の兆しを見せていたところが一気にパアになってしまった。
それでも諦めず人々は木々を植え続け、そして祈り続けた。
四大精霊は再び彼らは地方に飛び、そこに根付いてジックリ回復を促していくらしいので、まあなんとかなるだろう。
もちろん、悪いことばかりではない。邪神由来の歪虚はクリムゾンウェストからも一斉に消え去ったのだ。
代表的なのは、狂気の眷属。それから、北方と南方それぞれに配置されていた強欲竜たち。
あのへんは軍勢ごと邪神に取り込まれ、そこから再現されていた歪虚だったらしく、さらっと一気に消えてしまった。
これによりマテリアル汚染さえどうにかなれば、北方と南方は安全な人類生活圏として再開発が可能になった。
異世界侵略用に切り離された「王」が独自に作り出した歪虚は残されていること、そして雑魔など自然発生する個体までは消えないことから、これから先も歪虚との戦い自体は続くだろう。
だが、邪神とかいう無限勢力との消耗戦に比べれば、遥かに御しやすい。
何より人類はこの戦争の中で進化した。
今の彼らなら、残党程度にどうにかされてしまうことはないだろう。

ベアトリクス・アルキミア

ルビー

ドナテロ・バガニーニ
そうだな。とりあえず、エバーグリーンの話をしよう。
大精霊として命を燃やし尽くしたベアトリクス・アルキミア(kz0261)は帰らぬ人となった。
だが、惑星エバーグリーンは健在だ。もちろん、そう遠くない未来に消え去ることは決まっているが、なんだかんだ完全には消えてしまわないようにベアトリクスが手を回していた結果だ。抜け目ない女である。
全機能の管理権限を移乗されたルビー(kz0208)の手で、さらなる資源回収が進められている。
弱ってしまったリアルブルーをエバーグリーンの土地を召喚してあてこみ、再活性化するといった計画も立てられている。
惑星の基本機能ではなくクリムゾンウェストの特殊能力なので、他の世界では難しいだろうけど……。
なんにせよ、エバーグリーンはまだまだ使い道がありそうだ。
リアルブルーの方は、長らく続いた凍結封印を解除する準備が進んでいる。
けっこうな規模の大魔法だったもので、解除するにも時間がかかるのだ。雑にやるわけにはいかない。
まずはリアルブルーに月を帰さないといけない。当たり前だけど、月がないと地球にも異常をきたす。
ついでに破損したコロニーの修復作業なんかも同時に行われているらしい。
世界が再始動した時に、人々が好きなところで生きていけるようにという配慮だ。
早くリアルブルーに戻りたいと言っていた民衆も、今となっては最後にもう少しクリムゾンウェストを見たいとか贅沢な希望を出している。
そんなに慌てなくても、リアルブルーとクリムゾンウェストの関係が絶たれるわけではない。
法的な整備は必要だろうが、ドナテロ・バガニーニ (kz0213)は2つの世界で有効的な関係を続けられるように努力すると約束した。
まずもう一回議長にならないといけないので、彼の道は険しい。
ともあれ、地球の再起動が済んでしまえば、リアルブルー人が自由に故郷に帰ることも可能となるだろう。
以前はなんだかんだとお互いの世界に対して理解が浅かったが、よくも悪くも空蒼作戦を経て、くだらないことでいがみ合うのは無意味だと骨身に染みている。
リアルブルーへの帰還を望むハンターを拒むことはもうないだろう。
そう考えると、あの過酷な戦いにも意味はあったのだ。

ナディア・ドラゴネッティ

ミリア・クロスフィールド

大精霊リアルブルー
各国それぞれが協力して世界の復興に当たる中、ハンターズ・ソサエティは未だ健在。
ハンターはその能力をいかんなく発揮し、壊れた街の修理や負傷者の治療などで活躍している。
歪虚との大規模な戦いこそ起きていないが、彼らの仕事はまだまだ終わらないみたいだ。
変わらないものもあれば、変わったものもある。
ハンターズ・ソサエティは総長ナディア・ドラゴネッティ(kz0207)を失い、新たなリーダーを必要とした。
……いや、必要とはしていないのかもしれない。元々この組織はリーダー云々という問題ではなかったようだし。
ただ、彼女の意思を継ぐ者は必要で、元々指名されていたミリア・クロスフィールド(kz0012)が新たな総長に就任した。
事務仕事という意味ではナディアより明らかに優秀で、それが求められる時期だったものだからまさにうってつけだった。
ナディアを失ってもさしたる混乱もなく、ハンターズ・ソサエティは今日に至る……。
●
「リアルブルーくん。そんなところで何してるの?」
「やあミリア。今まさに君のことを書いていたところだよ」
冒険都市リゼリオには、少しずつだが以前の雰囲気が戻りつつあった。
ハンターズ・ソサエティ本部にて、リアルブルーは手記を書いていた。
ミリアが覗き込むと、少年は少し照れくさそうに笑う。
「ついに読書好きが高じて書く方に……?」
「見様見真似だけどね。人間はす?ぐ後世に都合よく歴史を書き換えるから、こうなったら神が主観的に書いてやろうかと一計を案じたわけ」 手帳を閉じ、懐に押し込む。
窓を開くと、夜に響く賑やかな喧騒がここまでも聞こえてくる。
少し遅れて始まった祝勝ムードは、戦争が終わった実感を得るためにも必要なものだった。
傷ついたままで人々は歌い、踊り、そして勝利を口にした。
「終戦直後はぐったりだったからね。随分活気が戻ったよ」
「そうですね。命が生きようとする力は、本当にたくましい」
嬉しそうに呟くミリアの横顔は、以前とは少し違う自信と落ち着きに満ちていた。
「リアルブルーくんは、これからどうするんですか?」
「いずれは自分の世界に帰るよ。人間の営みに介入するつもりはないから、とりあえず好きに旅でもしてみるかな」
少年のオートマトンボディは当分持つ。それこそ数百年、数千年は維持できるだろう。
三柱の神の中で自分だけが生き残ったことにはきっと意味がある。いや、意味を成さねばならない。
「それでもしも人が愚かにも争いを繰り返すなら、面倒だけど神として仲裁する」
「ふふふ。神様っていうより、人目を忍ぶヒーローみたいですね」
「ソレだけは恐れ多くて名乗れないよ。僕は本物のヒーローってやつを嫌ってほど見たからね……」
小さく笑い、それから二人は夜空を見上げた。
この世界の外側にはもっと広い世界が広がっている。そこには数多の願いがあり、悲しみがあり、途絶えた道があった。
それでも世界は続いていく。まるで何事もなかったみたいに。
「生まれ変わったジュデッカは、今もどこかで続いてるのかな……」
リアルブルーの呟き。
ミリアは寂しげに笑って、何も言葉を添えようとはしなかった。

ファーザー
ファーザーと共に邪神の体内に残った者たちのその後は知られていない。
確かにナディアはそこで「世界の再誕」を成し遂げた……そのはずだった。
だが、それを知る術がない。彼女その後どうなったのか、誰にもわからない。
ファナティックブラッドという世界は消えた。もう一つ世界がどこかに作られていたとしても、それを観測できなければ答えはわからないままだ。
ナディアは、そして世界の再誕はどうなったのか……。
その痕跡を辿ろうという動きもあったが、手詰まりが続いている。
願いは――祈りは、本当に届いたのだろうか?
「わからん。僕は神だけど、全知全能ではないからね」
邪神は当たり前みたいに「宇宙全部観測した」とかほざいていたが、どう考えたって今の人類には真似できない偉業だ。
異常な敵と戦っていたので感覚が麻痺するが、普通すべての世界を知ることなどできるはずもない。
わからないままでも、知らないままでも、世界は続いていく。
何かを失ったままでも、それでも前に進まざるを得ない。
「結局ね。私にできることなんか、当たり前のことだけなんです。だからそれを一つずつ積み重ねて生きていきます」
ミリアは優しく微笑み、そして空に両手を伸ばす。
「明日はきっと、今日よりいい日になるよ!」
●
世界の再誕に成功しても、問題があった。
ここは全く別の宇宙、別の世界。クリムゾンウェストと連絡を取る手段が――ない。
つまりこのままでは彼らは「成功したのかしてないのかよくわからない状態」のままだ。
せっかくここまでやってくれたというのに、残念にも程がある。
「いやまあ、おぬしの言わんとすることはわからんでもないが……仕方なかろうて」
ナディアはそう言っているが、新たな宇宙の父とか名乗っちゃったワケで、それくらいなんとかしてあげないと名前負けする。
彼らはやれるだけのことをやってくれた。だったら自分もやれるだけの努力を試みるのが礼儀というものだろう。
「ごめんね、なでぃあ。ぼくのせいで、こんなところにきちゃって……」
「自分で選んだことじゃ。おぬしが気にすることではあるまいて」
「でも……えばぐり……えび……でぴゅ……」
「エヴァグリオスという名前は呼びづらいだろう。ファーザー……も、難しいか。パパとかでもいいぞ」
「えびちゃんとぼくが、ぜんぶのせかいをすくいたいなんて……ばかなことはじめちゃったから……」
パパ呼びはイヤだったのか。
ショックだ。もう何億年も表情変えてないからバレてないだろうけれど。
「ほかのせかいに、いけるひと……いないのかな?」
「潜在的可能性としては残されているはずだが、成長して形を得るまではどうにもならないな」
「それ完成するまでにわらわ消えそうなんですけど」
「なでぃあのいたじだいが、きえちゃってるとおもう……ひとのよって、せいぜいすうせんねんだから……」
そうか。人の世ってけっこうすぐ消えるんだよな。
あまりに長生きしすぎて、そんな当たり前のことも忘れていた。
「いせかいりょこう、じかんちょうやく……まえはできたんだけど……」
「おぬしが育つまで時間かかりそーじゃなー。よいよい、無理せずとも。言葉は通じなくとも分かりあえる……それが絆というものじゃ!」
「なかよしでも、だいじなことは、じぶんのことばで、つたえたほうが、いいとおもう。そういったの、きみたちでしょ? ひとにいったことは、じぶんもやらないとだめなんだよ?」
「すいませんでした」
しかし、実際問題どうしたものか。
ナディアはまだここにいるが、既に肉体は消えてしまっているし、思念体として星の中枢に刻まれているだけだ。
それも間もなく消え去ってしまうだろう。そしてナディアが消えるということは、クリムゾンウェストとの縁が絶たれることも意味している。
まいったな。せめて一言、伝える方法があればよいのだが。
死滅し、そして再生する世界。
激しい力の坩堝を前に、私は考え続けた。
(文責:フロンティアワークス)





