ゲスト
(ka0000)
野良犬は帰り路を知らない
マスター:楠々蛙
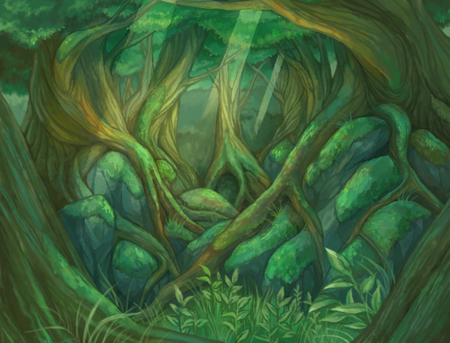
- シナリオ形態
- ショート
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 1,500
1,500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 3~6人
- サポート
- 0~0人
- マテリアルリンク
- ○
- 報酬
- 多め
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2017/09/18 19:00
- 完成日
- 2017/10/03 01:22
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
所は、密林。
そこに、その人型は鎮座していた。
そのシルエットは確かに、人型の輪郭を持っている。しかして、それが人間であるのかと言えば、それは否だ。生い茂る木々の上に、頭一つ抜けているその巨躯は、おおよそ尋常な人間のモノではあるまい。
CAM──人型機動兵器。
だが所詮は、値の張るだけの棺桶だ。
鞍馬(くらま)・秋水(しゅうすい)=べルツは、CAMの起動シーケンスの傍らにそんな感慨を抱く。センサー類、FCS、モーションプログラム、それらの設定を執り行うのも、葬式の手配のようなものだ。
今更、あとに残す者もあるまいに。──と、彼が自嘲めいた笑みを浮かべた時、不意にHMDが通信の報せを告げる。
『大丈夫……? クラマ』
日系ドイツ人の鞍馬は、黒髪黄色肌である彼にとって、唯一アーリア人だった父方の曾祖母の血を感じさせる灰色の瞳をHMD画面に現れたウィンドウに向けた。〈Sound only〉と記されているのみで、通信機から聞こえるか細いソプラノの主の顔を見る事は叶わない。
「ああ……。大丈夫だ、レーネ。すぐに済ませる」
だが見る事は叶わずとも、レーネ=リリエンタールの姿を浮かべる事は容易い。
年の頃は、十にも満たない。白磁の肌は、細い血管を透かして見える程で、髪色は白髪と見紛うばかりのプラチナブロンド。瞳の色が、透き通るようなアクアマリンでさえなければ、アルビノかと疑ってしまう程である。
その姿は、目に入れるまでもなく浮かべる事ができた。彼女本人と会う随分と前から、写真で、或は生身の立ち姿として眼に焼き付いている。娘自慢の過ぎる母親と彼女とは、まるで生き写しのようだ。年齢相応の違いと、容姿を裏切る中身を除いては。かつての上官は、儚げな見た目に反して、とんだじゃじゃ馬だった。
「すぐに帰るから、待っていろ」
帰る。──なんと自分には不似合な台詞だろうか。今や歩く死体も同然である自分には、その言葉を吐く資格はなかろうに。
だが、それでも彼は、この虚ろな言葉を口にしなければならないのだ。
あの人の言葉を虚言にしてしまったのは、紛れもなく、自分なのだから。
『もういいかしら』
レーネとは別に発信機から発せられたのは、温もりのあるアルト。
「うん……、もう大丈夫。……ありがと」
少女の声が遠ざかる。しばらく間が空いたのを見計らって、鞍馬は「すまない」と発信機に向けて言った。
「面倒を掛けるな、ユリア」
『なに? 今更そんなこと』
優しいアルトの声で、ユリア=ランバートは微笑を漏らす。
彼女は、ポーランド系のドイツ人だ。ゆるりとウェーブの拡がる赤毛と、温かみのある髪色に反して理知的な光のある蒼玉が印象的な女性である。
「……そうだな、いつも世話になってすまない」
そう、面倒を掛けるというのなら、それは常の事だ。
レーネ、ユリアが今居るのは、連合宙軍の移動基地である。軍を抜けた鞍馬が、子連れで軍施設を利用しているのも、ひとえに彼女の手回しのお蔭だった。
『相変わらず堅物ね』
くすり──と微笑むユリア。
『いいのよ。あの子、あなたにしか心を許していないから。独りで置いてけぼりにしちゃ、きっともたないでしょ?』
「俺にだけということはないだろう。君にもよく懐いているようだが」
『それはきっと、あなたが私を頼ってくれてるからね。子供って、そういうのに敏感だから』
そういうものだろうか。思わず唸る。その時、コックピットに置いてある女物の腕時計が、アラームを鳴らした。
「そろそろ、作戦開始の時間だ」
『そうね。……クラマ』
「ん?」
『ちゃんと、帰って来なさいね』
咄嗟には、応えられなかった。口を開くまでの間は何を意味していたか、それは自分にもわからない。
「……保証はできない」
『……そう言うと思った』
彼女は、寂しそうに微笑んだ。
作戦目標は、密林の中に築かれた連合宙軍中継基地の奪還。
かの基地は、歪虚に呑まれたのだという。予測される敵戦力は、歪虚に浸食されているであろう、基地に配備されていたCAM。
「早速、おでましか」
密林の只中に佇む中継基地へ密かに接近しつつあった鞍馬の機体は、光学センサーに敵影を捉えた。
魔導エンジンを戦闘駆動に転換。センサー類を、全てパッシブからアクティブに。こうなれば、真夜中にサーチライトを照らしているようなもので、否がおうにも敵の眼を引く事になる。
背面のスラスタが固形推進剤を噴き、その反動で機体が急進。
鞍馬のCAMは、R6M2b“デュミナス”を雛型に、中、近距離戦用にチューンした機体だ。その戦闘法は、操縦者の質実剛健な性格とは裏腹にして、ケンカスタイルと形容するに相応しい。
敵CAM──歪虚に浸食され有機物めいたフォルムに変異したドミニオンが、生物の眼球に似たスコープレンズを鞍馬機に向ける。
撃発に先んじて乱数機動を取り、砲弾を回避。
次弾の間を与えず、鞍馬は操縦レバーのトリガーを絞り込んだ。機体の左マニュピレータに納まるアサルトライフルが火線を放つ。バレルを短くし、敢えて集弾性を低くした銃から発せられる弾幕は、決定打には欠けるものの、牽制射撃としは十二分。
弾をばら撒きながら敵機へ肉迫しつつ、右腕部を引く。
「ERAナックルR、アクティブ」
右前腕部の装甲が展開。握り締めたマニュピレータの券面を、箱型の装甲が覆った。そして敵機を拳の間合いに捉えるや、右ストレートを叩き込む。
轟く、爆炎──!
爆発反応装甲(ERA)。重ねた鋼板の間に爆発性物質を仕込み、着弾と共に発破させて、敵弾による損害を減少させる、戦車装甲。──右腕部の兵装は、その応用だ。指向性地雷を拳に取り付けて殴り付けているようなモノである。
「第一層、パージ──」
弾帯のように連結したERA、今しがた炸裂したばかりのそれが拳から剥がれ落ち、次のERAが拳面へ接続される。
「──第二層、アクティブ」
炸薬の信管が活性化。と共に爆煙が晴れて、敵機のひしゃげた胸郭を向こうに覗く。穿たれた装甲は、しかし、蠢く触手によって塞がろうとしていた。
そこへ、更に拳を叩き込む。
吹き飛ぶ歪虚CAM。胸部装甲を大きく損傷しながら、尚も各部のスラスタを吹かして体勢を立て直そうとする。しかし、
──推進剤の軌跡が、鋭角のラインを描いて、奔る。
「──ERAナックルL、アクティブ」
そこには既に、左券面をERAで覆い、体勢を沈めた鞍馬機が構えていた。
左アッパーが炸裂し、煌々と燃える爆炎が、歪虚CAMを残骸に変える。
左右のマニュピレータからERAが剥がれ、地に落ちる。──息吐く間もなくスラスタを吹かして、襲い来る砲弾を乱数機動で回避。
HMDに、新たな敵機──歪虚に浸食されたCAMの姿を捉える。
「─────」何かが、昂ぶる。
“帰る”という言葉は、もう心の片隅にさえ残っていなかった。
そこに、その人型は鎮座していた。
そのシルエットは確かに、人型の輪郭を持っている。しかして、それが人間であるのかと言えば、それは否だ。生い茂る木々の上に、頭一つ抜けているその巨躯は、おおよそ尋常な人間のモノではあるまい。
CAM──人型機動兵器。
だが所詮は、値の張るだけの棺桶だ。
鞍馬(くらま)・秋水(しゅうすい)=べルツは、CAMの起動シーケンスの傍らにそんな感慨を抱く。センサー類、FCS、モーションプログラム、それらの設定を執り行うのも、葬式の手配のようなものだ。
今更、あとに残す者もあるまいに。──と、彼が自嘲めいた笑みを浮かべた時、不意にHMDが通信の報せを告げる。
『大丈夫……? クラマ』
日系ドイツ人の鞍馬は、黒髪黄色肌である彼にとって、唯一アーリア人だった父方の曾祖母の血を感じさせる灰色の瞳をHMD画面に現れたウィンドウに向けた。〈Sound only〉と記されているのみで、通信機から聞こえるか細いソプラノの主の顔を見る事は叶わない。
「ああ……。大丈夫だ、レーネ。すぐに済ませる」
だが見る事は叶わずとも、レーネ=リリエンタールの姿を浮かべる事は容易い。
年の頃は、十にも満たない。白磁の肌は、細い血管を透かして見える程で、髪色は白髪と見紛うばかりのプラチナブロンド。瞳の色が、透き通るようなアクアマリンでさえなければ、アルビノかと疑ってしまう程である。
その姿は、目に入れるまでもなく浮かべる事ができた。彼女本人と会う随分と前から、写真で、或は生身の立ち姿として眼に焼き付いている。娘自慢の過ぎる母親と彼女とは、まるで生き写しのようだ。年齢相応の違いと、容姿を裏切る中身を除いては。かつての上官は、儚げな見た目に反して、とんだじゃじゃ馬だった。
「すぐに帰るから、待っていろ」
帰る。──なんと自分には不似合な台詞だろうか。今や歩く死体も同然である自分には、その言葉を吐く資格はなかろうに。
だが、それでも彼は、この虚ろな言葉を口にしなければならないのだ。
あの人の言葉を虚言にしてしまったのは、紛れもなく、自分なのだから。
『もういいかしら』
レーネとは別に発信機から発せられたのは、温もりのあるアルト。
「うん……、もう大丈夫。……ありがと」
少女の声が遠ざかる。しばらく間が空いたのを見計らって、鞍馬は「すまない」と発信機に向けて言った。
「面倒を掛けるな、ユリア」
『なに? 今更そんなこと』
優しいアルトの声で、ユリア=ランバートは微笑を漏らす。
彼女は、ポーランド系のドイツ人だ。ゆるりとウェーブの拡がる赤毛と、温かみのある髪色に反して理知的な光のある蒼玉が印象的な女性である。
「……そうだな、いつも世話になってすまない」
そう、面倒を掛けるというのなら、それは常の事だ。
レーネ、ユリアが今居るのは、連合宙軍の移動基地である。軍を抜けた鞍馬が、子連れで軍施設を利用しているのも、ひとえに彼女の手回しのお蔭だった。
『相変わらず堅物ね』
くすり──と微笑むユリア。
『いいのよ。あの子、あなたにしか心を許していないから。独りで置いてけぼりにしちゃ、きっともたないでしょ?』
「俺にだけということはないだろう。君にもよく懐いているようだが」
『それはきっと、あなたが私を頼ってくれてるからね。子供って、そういうのに敏感だから』
そういうものだろうか。思わず唸る。その時、コックピットに置いてある女物の腕時計が、アラームを鳴らした。
「そろそろ、作戦開始の時間だ」
『そうね。……クラマ』
「ん?」
『ちゃんと、帰って来なさいね』
咄嗟には、応えられなかった。口を開くまでの間は何を意味していたか、それは自分にもわからない。
「……保証はできない」
『……そう言うと思った』
彼女は、寂しそうに微笑んだ。
作戦目標は、密林の中に築かれた連合宙軍中継基地の奪還。
かの基地は、歪虚に呑まれたのだという。予測される敵戦力は、歪虚に浸食されているであろう、基地に配備されていたCAM。
「早速、おでましか」
密林の只中に佇む中継基地へ密かに接近しつつあった鞍馬の機体は、光学センサーに敵影を捉えた。
魔導エンジンを戦闘駆動に転換。センサー類を、全てパッシブからアクティブに。こうなれば、真夜中にサーチライトを照らしているようなもので、否がおうにも敵の眼を引く事になる。
背面のスラスタが固形推進剤を噴き、その反動で機体が急進。
鞍馬のCAMは、R6M2b“デュミナス”を雛型に、中、近距離戦用にチューンした機体だ。その戦闘法は、操縦者の質実剛健な性格とは裏腹にして、ケンカスタイルと形容するに相応しい。
敵CAM──歪虚に浸食され有機物めいたフォルムに変異したドミニオンが、生物の眼球に似たスコープレンズを鞍馬機に向ける。
撃発に先んじて乱数機動を取り、砲弾を回避。
次弾の間を与えず、鞍馬は操縦レバーのトリガーを絞り込んだ。機体の左マニュピレータに納まるアサルトライフルが火線を放つ。バレルを短くし、敢えて集弾性を低くした銃から発せられる弾幕は、決定打には欠けるものの、牽制射撃としは十二分。
弾をばら撒きながら敵機へ肉迫しつつ、右腕部を引く。
「ERAナックルR、アクティブ」
右前腕部の装甲が展開。握り締めたマニュピレータの券面を、箱型の装甲が覆った。そして敵機を拳の間合いに捉えるや、右ストレートを叩き込む。
轟く、爆炎──!
爆発反応装甲(ERA)。重ねた鋼板の間に爆発性物質を仕込み、着弾と共に発破させて、敵弾による損害を減少させる、戦車装甲。──右腕部の兵装は、その応用だ。指向性地雷を拳に取り付けて殴り付けているようなモノである。
「第一層、パージ──」
弾帯のように連結したERA、今しがた炸裂したばかりのそれが拳から剥がれ落ち、次のERAが拳面へ接続される。
「──第二層、アクティブ」
炸薬の信管が活性化。と共に爆煙が晴れて、敵機のひしゃげた胸郭を向こうに覗く。穿たれた装甲は、しかし、蠢く触手によって塞がろうとしていた。
そこへ、更に拳を叩き込む。
吹き飛ぶ歪虚CAM。胸部装甲を大きく損傷しながら、尚も各部のスラスタを吹かして体勢を立て直そうとする。しかし、
──推進剤の軌跡が、鋭角のラインを描いて、奔る。
「──ERAナックルL、アクティブ」
そこには既に、左券面をERAで覆い、体勢を沈めた鞍馬機が構えていた。
左アッパーが炸裂し、煌々と燃える爆炎が、歪虚CAMを残骸に変える。
左右のマニュピレータからERAが剥がれ、地に落ちる。──息吐く間もなくスラスタを吹かして、襲い来る砲弾を乱数機動で回避。
HMDに、新たな敵機──歪虚に浸食されたCAMの姿を捉える。
「─────」何かが、昂ぶる。
“帰る”という言葉は、もう心の片隅にさえ残っていなかった。
リプレイ本文
コックピットに鳴り響くアラームが、敵機より照準レーザーを受けている事実を告げる。
回避──頭がその単語に至るよりも早く、機体左半身のスラスタを噴射。射線より逃げ遅れた左マニュピレータのアサルトライフルが被弾。一瞬たりと躊躇わず放棄すると同時に、弾倉内の弾薬が誘爆を起こす。
自身に襲い掛かるGを考慮しない回避行動の影響で、明滅する視界の片隅に、次射を放とうと照準を補正する歪虚CAMの姿を捉える。
回避──不可。
HMDの画面が鮮烈なマズルフラッシュに灼かれる──その刹那、灼光を遮り、青い機影が鞍馬機の前に立ち塞がった。
『俺が受ける、下がってろ!』
五十七ミリの徹甲弾が、青い機影の正面に着弾。
──青い燐光が、飛沫となって散る。
青いカラーリングのR7──R6シリーズの後継機“エクスシア”の肩部が展開。展開部より放出されたマテリアルが防御フィールドを形成し、敵弾を無力化したのである。
射撃を阻まれた歪虚CAMは、一切の動揺を見せずに、インジェクターより空薬莢を排出した狙撃ライフルを構え直す。排莢された直径五センチ程の薬莢が、地面にめり込むと共に、銃口が再び青いエクスシアを捉える。
次の瞬間、一条の光線が、ライフルを構える歪虚CAMの脇腹を貫いた。
真っ直ぐに伸びた光の矢は、鋼鉄の装甲を食い千切ると、余韻めいた残光をちらつかせながら、空へと溶けてゆく。
胴体に大穴を穿たれた歪虚CAMが、密林の中へ沈む。
「一発必中とは、おみそれいった」
それをHMDの拡大ウィンドウで視認した近衛 惣助(ka0510)は、僚機へ通信を繋いで称賛の言葉を送った。
堅牢な盾に、三〇ミリのガトリング砲とカノン砲を装備した、動く要塞のようなCAM──近衛が駆る“真改”の傍らに立つのは、彼の機体と相反して、兵器というよりは天使を模した宗教像のような雰囲気を持つエクスシアだ。
マテリアル兵器に特化したCAMが背負う光背めいた輪状のパーツが展開し、淡い光を放っている。それは、マジックエンハンサーという、言わば魔導エンジンに対するコンデンサーのようなものだ。一時的に出力を上げた魔導エンジンの余剰エネルギーを集積、循環する事によって、マテリアル兵器の補助、強化を担っている。
今しがた光の矢を放ったマテリアルライフルの威力を思えば、その効果は語るまでもないだろう。
『近衛さんの観測データのお蔭です。ありがとうございます』
白と蒼を基調とした、何処か無垢な神聖を帯びているエクスシアから返って来た通信の声は、近衛の無骨なそれとは違い、柔らかな少女の声。いや、流石に今ばかりは、多少の硬さが含まれているだろうか。
神の御使いめいた機体“ステラマリス”のパイロット、羊谷 めい(ka0669)は近衛の眼からしても、おおよそ闘争を好む人種であるようには視えなかった。矛先を向ける相手が、たとえ歪虚であろうとも、何かを“害する”という行為の似合う雰囲気の持ち主ではない。
『鞍馬さんは、……無事みたいですね』
通信機越しに、安堵の溜息が伝わる。
『──近衛さんは、レーネちゃんとお話ししましたか?』
「ん? ああ、あの子のことか。いや、どうにも俺は怯えられているみたいでな」
『わたしも、お話できたのは、ほんの少しだけでした』
苦笑する近衛に合わせて、微笑の気配を声に滲ませる羊谷。だが、僅かに間を置いて『でも』と再び言葉を発した時には、朗らかな笑みは鳴りを潜めて、何処か強固な響きをその声に伴っているように感じられた。
『でも、最後にあの子は言ったんです。わたしの袖を強く引いて、
──クラマを……連れて帰って来て
鞍馬さんを、連れて帰って来てって」
「……そうか」
近衛はそう呟きながら、鞍馬が駆るデュナミスを見遣った。ともすれば自棄的とも言える戦闘スタイル。おおよそ、帰り路の足を残さねばと考えている者の戦い方ではない。
「放っておくわけにもいかないな」
操縦桿を改めて握り直す。その時、アラームが鳴り響き、新たな敵機の接近を告げる。歪虚CAMの姿を光学センサーが捉える共に、照準レーザーの被照警報。
敵の兵装は、ロケット推進のランチャー。砲口から放たれた榴弾が推進剤を噴射。
近衛の駆る真改が、羊谷機を庇うように前へと出る。その正面へ推進剤の尾を引きながら、ロケット弾が着弾。
弾頭の成形炸薬が炸裂する──!
周囲一帯の木々が、爆風に軋みを上げながら大きくしなり、木の葉が吹き荒れる。
やがて爆風が静まり、あとは木の葉が舞い落ちる。しかし、爆音の余韻が途絶えぬ内に、一発の砲声が再び辺りの梢を揺らがせた。
一瞬の間を置いて、今しがたロケット弾を放った歪虚CAMの傍らに立つ樹木が砕け、木端混じりの土柱が立つ。
ロケット弾の炸薬による黒煙が、砲弾の射出に伴う衝撃波によって晴れ、現れ出たのは、CAMの前面投映面積を覆う程に巨大な盾。そして、その盾を銃架代わりにして構えられたカノン砲。
ロケット弾着弾の衝撃はコックピットを大きく揺さぶっただろうに、近衛の表情に苦痛の色はなく、反撃の砲撃を外したというのに、それに落胆する様子もなかった。
元々、初弾が当たるとは思っていない。CAMにも扱えるように取り回しを良くする為、砲身を短くしたカノン砲。おおよそ無茶な改造を施してあるにも関わらず、更に砲口を二つ備えているというゲテモノだ。到底、まともな精度は望めまい。
真改の光学センサ──頭部のメインカメラを、バイザー型の高精度照準器が覆った。
自動装填が次弾を薬室(チャンバー)へ込めると共に、火器管制が誤差修正。
照準器の横調節(ウィンデージ)を右に一・四ミル、縦調整(エレベーション)を上へ一・二ミル微調整。
操縦桿のトリガーに指を這わせて、
「──こいつが本命だ」
再び、カノン砲が火を噴いた。
過たずして、低い放物線を描いて飛んだ二発の榴弾が歪虚CAMの右腕と胸郭を捉え、炸裂。
「一機撃墜した。これより分隊支援に徹底する」
カノン砲を、左肩部のハードポイントアームに保持しておいたガトリング砲へ換装する。
「背中は任された。──後の酒が不味くなるから、勝手に死んでくれるなよ」
青いエクスシアが腰部のハードポイントに接続した鞘から刀を抜き放ち、鞍馬機の前を塞ぐようにして掲げる。
「聞いての通りだ。単身で突出するのは、控えてくれよ」
青いエクスシア──フレイム・オブ・マインド(F・O・M)のコックピットに座す南護 炎(ka6651)は、近衛の通信を聞いて、同じくそれを耳にした鞍馬へと語り掛ける。精力に溢れた、張りのある声だ。その精悍ながら若々しい顔付きも相俟って、青さの残る武人といったところだろうか。
『……ああ、すまない。さっきは、助けられたな。礼を言う』
「…………」
鞍馬の反応に、南護は口を噤んだ。まさか、感謝を示されるとは思っていなかったのだ。その気配を悟ったらしい鞍馬が『どうした』と苦笑というには、苦味の強過ぎる声音で言った。
『余計な事をするな、とでも言うと思ったか? 俺が『死にたがっている』とでも?』
「ああ、いや……」
胸の内を言い当てられ、南護は言い淀む。
『その様子では、ユリアから何か聞かされたか』
苦笑──今度こそそう言える程には笑みの成分の多い声で、鞍馬は言う。
『彼女は何と?』
「あんたが昔、あの月面戦争で、上官を亡くしたと」
『それだけか』
「それだけさ。深く立ち入ったことまでは、聞かされてない。ただ、あんたがそれ以来、無茶な戦い方ばかりしてるってことくらいしかな」
意図せずとも責めるような口調になった南護の台詞に、鞍馬は『そうか』と零したのみで、言葉を重ねる様子はない。その気のない返事に、妙に苛立ちが募る。
「あの女(ひと)は、あんたの事、心の底から案じてたぜ」
でなければ、赤の他人であるはずの南護や他のハンター達に、自分も関わる過去の話をおいそれと語る道理はないだろう。
『ああ、知っている』
「知ってるって……、なんだよ、そりゃぁ」
無性に、腹の立つ返答だった。
「あんた、なに考えてんだ? 死なせてしまった上官や、残されたあの子に責任を感じてるのは、俺でもなんとなくはわかるさ。だからって、死ぬことが償いになるわけじゃないだろ……!」
むかつきのままに吐いた言葉は、激昂というよりは癇癪に近いモノだったかもしれない。ともかく、鞍馬の言動の一つ一つが、一々癇に障るのだ。
『償い……?』
それまで南護の台詞へ気のない態度で応じていた鞍馬が、顕著な反応を見せた。
『死が、償いになる──か。なるほど』
考えたこともなかったな──と鞍馬は言った。
『それで、それだけで済んだなら、どんなに楽だったか』
「なにを……?」
その言葉が何を意味するのか、南護にはわからない。ただ、少なくとも言えることは、この男は死にたがりよりも、更にタチの悪い何かであるという事。
南護が更に問い詰めようとした時、アラーム音が敵の増援の来訪を報せる。HDM越しに、歪虚CAMの凶々しい姿を捉える。
『どうやら、これ以上話している余裕はなさそうだ』
鞍馬機が、ERAを券面に取り付けた両のマニュピレータを構える。
「おい……!」
『わかっている。これ以上、面倒を掛ける気はない』
また独り敵陣へ飛び込むのではないかと勘繰る南護に、鞍馬機の構えが前傾姿勢から僅かに身を起こす。
「……なら、いいさ」
そう言うと、南護は敵影との間合いを図りながら、愛機を進ませる。その歩調に合わせて追随する鞍馬機。臨戦から、いよいよ戦闘の間合いに踏み入ろうとする前に『一つ』と、鞍馬が切り出した。
『一つだけ、訂正しておく』
「なに……?」
『死なせてしまった、というのは誤りだ』
殺した──と、鞍馬は言った。
『俺が自らの手で、あの女(ひと)を殺したんだ』
林立する木々の間を縫うかのように奔る、小さな巨人。
全長、二・八メートル。それは、生身の人間に比べれば十分な巨躯を誇っていたが、CAMと並べれば腰程にも届かない身の丈をしていた。
魔導アーマー。クリムゾンウェスト独自の技術──機導術の力によって開発された、機導兵器。今、足許のホイールを回しながら密林を奔る機体“プラヴァー”は、魔導トラックに手足を付けたのみという粗末な第一世代とは違い、リアルブルーの技術体系を取り入れた第二世代以降の機体である。
その外観及び設計思想は、リアルブルーにおける強化外骨格(パワードスーツ)に相似している。操作体系にマスタースレイブを採用したプラヴァーは、直感的な操作を可能とし、操縦者の手足の延長線上として機能する。
木々の根が張り巡った悪路を、時にはホイールを地面に噛ませながら、時には地面を蹴って宙を舞いながら走破するその身軽な身のこなしは、その設計思想故に、操縦者であるアイビス・グラス(ka2477)本来の動きを、正確に再現していた。
機体を遥かに上回る巨木の幹にホイールを噛ませて駆け上がる。運動エネルギーを位置エネルギーが上回り、重力に背中が捕まる前に、足を蹴って宙へ跳ぶ。その直後、機体の表面を何かが擦過し、最前まで機影のあった幹が爆ぜた。
「ホント、端から身体が鉄でできてたみたい」
風防のない、剥き出しの操縦席──碧色の髪を靡かせながら、持ち前のグリーンアイを覆うゴーグルレンズの表面に撒き散る木端を捉えつつ、アイビスは口許に笑みを湛えた。装甲を撫ぜたソニックウェーブを生み出し、巨木を砕いたモノが何であるのか、今更問うには値しない。
近衛、羊谷、南護、そして鞍馬を入れた追撃を主目的にするメインのA班とは異なり、主に斥候、攪乱を目的とするB班に振り分けられたアイビスは、作戦地域の外周を徐々に中心へと近付き索敵を行いながら巡っていたところ、敵小隊と遭遇し戦闘を開始したのだ。
襲い来る敵弾を回避し、宙を泳ぐプラヴァー。着地するまでの数瞬、機体は無防備になる。自由落下の最中に、照準レーザーの被照警報。
ゴーグルを銃の発火炎が灼く──その寸前に、アイビスは身を沈めた。少なくとも、彼女はそういう感覚で、身体を操作した。
機体背面より散る、残像めいた碧光の残滓を、銃弾が貫く。
重力加速よりも早く機体が斜線を引くように落下し、プラヴァーの二足が地面を踏み締めた。ホイールをドリフト走行気味に横滑りさせながら、体勢を立て直す。
スペルスラスタ──魔導アーマー独自の推進システム。CAMのような推進剤ではなく、機導装置によるマテリアル噴射によるものだ。持続性が少ない為、効果が期待できるのは滞空中の姿勢制御や、瞬間的な加速のみだが、マテリアルに準拠する為、感覚的操作感の強い機能である。
アイビスは着地したのちも、その機能を用いて敵弾を俊敏に密林の中を奔りながら、敵機へと肉迫してゆく。
だが、敵機を追い詰めた座標付近の地形を改めて視認するや、彼女は舌を打つ。
木々の間が狭すぎる。近接兵装しかないこちらの間合いに敵機を捉えようと思えば、直進する他に手段がない。機体に組み込んである、まだ実戦で試した事のない防御機構を頼りに特攻を仕掛けるべきか否か、アイビスが次手に悩み、進攻の速度を緩めようとしたその時、
『構わん、そのまま進め』
耳元のイヤリングを模した通信機が、声を発した。年若いにも関わらず、威厳ある男の声だ。
『案ずるな。貴公の背中は、私の眼の内にある』
「もしも犬死にしたら、化けて出てやるから」
落ち着き払った声音に、アイビスは口許に微笑を湛えながら言った。
『歓迎しよう。私も犬は嫌いではない。狼ともなれば、持て余すかもしれないが』
口許の笑みを深くする。
「良い返事ね」
生真面目に応じられるよりは、よっぽど頼りになる。
「タイミングは?」
『好きに動くと良い。こちらが合わせよう』
なんとも頼り甲斐のある返事に「オーケィ」と応じるや、アイビスはクラウチングスタートを決めた。──少なくとも、彼女はそういう感覚で、肢体を動かした。
背面より、マテリアルを放出し、鉄の躰が疾走する──!
ただまっすぐ、一直線に駆け抜けるプラヴァ―に、歪虚CAMが機械というよりは何処か死人めいた無機的な反応を示した。──ただしその速さばかりは、兵器の機能を損なわずして。
照準レーザーの被射警報──無視。速力を落とさず、いや寧ろ、更に加速する。
『お砂をひとつまみ(Prise Sand)』
通信機が発する子供騙しな呪文──歪虚CAMの頭部に銃痕が穿たれ、メインカメラを失った機体が一瞬動きを停める。
と同時に、プラヴァーが跳んだ。
スペルスラスタをありったけ吹かし、右腕部──五指の代わりに鉤爪を生やした掌を、歪虚CAMの胸郭へ叩き付ける。
むべなるかな、全長に倣い質量で遥かに下回る魔導アーマーの殴打は、体勢を崩したCAMですら、その体幹を倒すまでには至らず、ただ五条の爪が装甲へ喰い込むばかり。
「潰れろ──」
死線に飛び込んだ末の一撃が不発に終わったにも関わらず、しかしアイビスは、口許の笑みを絶やさず、寧ろ口端のカーブを獰猛に歪めて吼える。
「潰れろ、ヴォイドォ──!」
緋色の装甲に覆われた右腕──獲物を逃さじと喰らい付く鉤爪に捉えられた歪虚CAMの胸郭が、不可視の鉄槌を叩き付けられでもしたように大きく陥没する。
掌底に内蔵された魔導機械が、マテリアルを糧に稼働して衝撃波を発生させ、CAMの装甲を圧潰させたのである。
胸部──機体の操作系統を根こそぎ潰された歪虚CAMが、膝から崩れ落ちる。その上体が沈むと同時に歪虚CAMの傍らに足を降ろしたプラヴァーが、足許のホイールで地面に弧状の轍を刻みながら着地の衝撃を殺して、敵の残骸に背を向ける。
「一機撃破。──なかなか悪くないわね、こういうのも」
鮮血よりもなお紅い腕を眺め、口許のカーブがますます深く。
足を止めていたのは、ほんの一時だけだった。アイビスの駆るプラヴァーは、エメラルドよりもなお輝かしい光を撒きながら、森を奔った。
片側が急勾配の崖になった高台に、片膝立ちの体勢で鎮座するCAM。全体に施した迷彩ペイント。油断なく左右へ巡るモノアイが赤く光る。
新興公爵家ブラオラントの保有する魔導発動機製造工場にて、ノックダウン製造──連合宙軍より受け取った各部品を組み立てる事によって製造された、ワンオフのR6M2b現地改修モデルPzI-2M ザントメンヒェン”である。
「ほんとの狼だって、もう少しおとなしいんじゃないかな」
そのコックピット内で、通信を繋ぐでもなしに独り呟く、稚気を含む声。それが、つい今しがた、アイビスの通信機が発したモノと同じ人物の声であるなどとは、そうおいそれとわかるものではない。
「ま、頼りになるのはいいことだけどさ」
だが彼こそが、今しがた狙撃ライフルによってアイビス機に支援射撃を行ったザントメンヒェンのパイロットにして、ブラオラント家次期当主アウレール・V・ブラオラント(ka2531)だ。
「さて、と──」
アイビスの奮闘振りに肩を竦め呆れ交じりの称賛を送ったアウレールは、再び通信を繋ぐ前に、意識を切り替えた。いや、『切り替える』というのとは違うだろうか。『仮面を付ける』、いや、そう『蓋をする』だ。中身を抑える為の、或は中身を見ないで済むようにと造られた蓋。容れ物と中身──理想足らんとする自分と、夢想を語る自分との間に、明確な差などないという事は、とっくに理解してしまったが。
はて、何故こんな感傷に囚われたのか。ザントメンヒェン──子供の頃、母から何度も聞かされた妖精の名を冠する機体の中に居るからだろうか。早く寝ないと、眠り砂の妖精さんが来る──帝国の出身者なら、一度ならずとも聞かされた文句だろう。
寝なくたってへっちゃらだよ。軍人さんになったら、夜も寝ないでみんなを守る為に戦うんだから──そう言う度に、母が何かをこらえるかのような顔をしていた事を想い出した。
感傷を無用と払い、そうする事で意識がブラオラント家次期当主の自分のそれへと替わり、通信を繋ぐ。
「こちらアウレール。ウォーカー、状況の報告を」
同時に、HMD画面に製図、データ化した作戦地域の地図を呼び出す。図内に、通信の送信先、ヒース・R・ウォーカー(ka0145)が操る機体の現座標を示す光点を確認。光点より僅かに距離を置いた地点には、アイビス機を示す光点がある。アイビスが先程まで交戦していた地点には×印。更にヒース機周辺には、敵機を示す光点が二つ点っていた。
現在ヒース機は、アイビスが発見した歪虚CAM三機構成の小隊の内二機を牽き付け、相手取っている。その間に、アイビスが確実に敵一機を撃破しようという策である。
『まぁ、なんとか役割は果たせてるさ。連中遊び弾は放らないで、一々殺しに掛かって来るから、わかりやすくて助かるねぇ』
戦闘中と思えぬ、気怠い声。声に紛れて聞こえる銃声、爆発音にも動じない、気怠い声。
「ご苦労だった。現在、敵一機を撃破し、グラスがそちらへ向かっている。合流し次第──」
台詞を遮るようにして、通信機がアイビスの声を発する。
『あー、お待ちのところ悪いんだけど、ちょっとマズいことになったわ』
「どうした」
『敵さんご一行を発見。数は二機、どうも傭兵さんのとこに、増援で向かってるみたいだけど。どうしたものかしら?』
『おいおい、あと二名サマも追加ってことかい? 勘弁願いたいねぇ、いくらなんでも手が足りそうにないんだが?』
「了解した。そちらは、私が引き受けよう。敵座標データの転送を」
『オーケィ、送ったわ』というアイビスの了承の直後に、データを受信。データが示す座標にモノアイを向ける。そこは、作戦地域内でも特に高い樹木が密集している地点。いかなCAMの図体でも、目視は不可。狙撃ライフルによる精密射撃では、有効な打撃にはならない。
「フロートガンポッド、起動」
背面のハードポイントに接続したガンポッドのロックを解除。ハードポイントより切り離されたガンポッドが、火砲、弾薬、給弾機構と共に内蔵されたフロートシステムによって、機体周囲を浮遊する。
狙撃ライフルと共にそれらの照準を敵座標へと向けて──「制圧射撃を開始する」
銃声が銃声を劈き、密林に弾時雨が降り頻る。
ガンポッドの濃密な斉射に加えて、狙撃ライフルを弾倉が尽きるまで連射。ライフル弾が尽きるや否や、機体を中空へと躍らせる。高台の上から、直下に向けて自由落下。
その直後、最前まで機体が膝を着いていた空間を、敵の応射が薙ぐ。目論見通り、敵がこちらに喰い付いた。
敢えてスラスタによる減速は行わず、そのまま地面に足を落とす。着地の瞬間、衝撃吸収材が蒸発し、落下による衝撃を受け止めた。棺桶サイズの弾倉を落としてライフルをリロードしながら、冷静に通信を行う。
「敵の動きは?」
『撃ち返したと思ったら、行き先を変えてそっちに向かったわ』
「上々だな。そちらは引き続き、ウォーカーと合流を」
『りょーかい。そんじゃ、そっちも気を付けて』
「ああ。互いに最善を尽くして、武運を祈るとしよう」
そう締め括り通信を切るや、アウレールは再びHMD画面に映る地図へと眼を走らせた。等高線を記した図面には、有効な狙撃ポイント、及びアンブッシュに利用できそうな地点まで書き込んである。
現在位置と照らし合わせて、移動ルートを検討。要した時間は、即断と言って差し支えない程だろう。
即座にアウレールは、定めたルートに沿って、機体を走らせた。
せせらぎの音を奏でる、川の中流。平素なら、野生動物の水飲み場として機能していただろう場所を、不躾な巨人の足が踏みしだく。
跳ね上げた水を浴びる漆黒の装甲。日の下にして宵闇を宿すかのようなカラーリングに身を包む、一機のデュナミス──“ウェスペル”。そのコックピット内で、ヒースは小さく舌打ちを漏らした。
右マニュピレータに握る、銃剣付き拳銃──アワフォード社製ハンドガン“トリニティ”を正面に向けて立て続けにトリガーを引く。──発せられた弾丸は、向かって左へと跳ぶ敵影を捉え切れず、ただ空を切るばかり。
接近警報──アラームが耳を劈くよりも早く、左マニュピレータに握るサブマシンガンの銃口を、振り返らずして背後へと向け、トリガーを引く。今度ばかりは、過たずしてCAM用ダガーナイフを片手に背後へと迫りつつあった歪虚CAMを弾丸が叩いた。だが短銃身、小口径の銃では精々足止めが限界で、CAMの装甲を貫くには不足がある。
振り返りざまに、右マニュピレータを振る。と同時に、トリニティの重厚な銃身──単なるハンドガンとしては分不相応に分厚い機関部が展開し、変形してゆく。
果たして、照準を歪虚CAMに向けた時には、トリニティの銃身が伸長し、グレネードランチャーへと姿を変えていた。
スラスタを噴いて後退しながらトリガーを引き、人間の頭程はある塊を射出。
歪虚CAMの胸元三寸で、放たれたプラズマグレネードが弾け、紫電の爆発が迸る。
直後、グレネードの効果圏内より歪虚CAMが抜け出した。ダガーナイフが原型を留めておらず、前面装甲表面も一部融解している様子だが、行動不能にまで至る損傷ではない。CAMと同様に、プラズマ兵器は宇宙空間での使用を想定された兵装だ。端から、決定打になるとは思っていない。
だが、機体前面のスラスタを幾つか潰した事によって、幾らか機動力を削いだだろう。
今なら、ヤれるか?
疼く。血の昂ぶりが、身の内から溢れそうになる。
──舌を、打つ。
その衝動に身を任せるべきではない。状況を正確に把握しろ。己が役割を思い出せ。そして、愛する人の温もりを忘れるな。
お前が帰るべき場所は、いつも必ずそこにある。
トリニティを再びハンドガン形態へと戻しながら手首を捻るように右腕部を動かして、瞬時に右手側へと銃口を走らせる。
逆しまに構えた銃を三度(みたび)、撃発。
ウェスペルの右手側に回り込んでいた歪虚CAMが構えるロケットランチャーを、内二発が捉えた。歪虚CAMが兵装を放棄した直後、ランチャーが爆発。
右方の脅威を一時無力化させると共に、サブマシンガンを正面へと向けようとしたところで、ヒースはトリガーから指を離した。
『お待たせ』
通信機が、陽気な声を発する。
HMDが映す外界の映像に映るのは、アイビスの駆るプラヴァーの背中。
「いいや。そんなに待っちゃいないさ。もう少し遅れても構わなかったくらいだねぇ」
皮肉を交えて、返答。
「だがまぁ、助かったとは言っておくさ。これでようやく、退屈しないで済みそうだ」
『あらそ。それは良かった。それじゃ──』
くすり──と微笑む気配。
『──始めましょうか!』
直後に、プラヴァーが碧光を撒いて疾走した。
スペルスラスタを律動的に噴き、乱数機動で以って歪虚CAMに肉迫するプラヴァー。
それを迎える敵機が、短銃身のアサルトライフルを向ける。迎撃の弾丸をばら撒きながら、スラスタの反動で後ろに退いた。
だが遅い。照準も、動きも──何もかも。
襲い来る弾丸を潜(くぐ)り抜け、敵機の懐へと潜(もぐ)り込み、真紅に彩られた右腕を突き出す。
「潰れろ──!」
アイビスの咆哮に応じるようにして、右掌底部の魔導兵器が起動。
だが、突き出した鉤爪が敵機の胸郭を捉える前に、歪虚CAMは右腕部を盾にした。直後、掴まれた箇所を中心にして歪虚CAMの腕が圧潰する。しかし、腕に守られた胸部は以前、健在。
「まだよっ!」
未だエメラルドの光を瞳に絶やさず、アイビスは左手を突き出す。その動きに呼応したプラヴァーが、左腕部を歪虚CAMの胸郭に突き立てた。
「これが私の本命──正真正銘の“切り札”よ」
前腕に装備した特殊な近接射出兵器──パイルバンカーが、その内に溜め込んだ暴力性を解き放つ。その名に反して、杭とも呼べぬ無骨な鉄の塊が、敵機の胸郭を打ち貫いた。
天を仰ぐように上体を逸らし、膝から崩れ落ちる歪虚CAM。その上に立ちながら、プラヴァーがパイルバンカーの機関部を展開。
中折れ式の射出筒から、空薬莢が跳ねる。
入れ替わりに予備の実包を右腕部の鉤爪で摘まみながら薬室に込めるや、プラヴァーは腕を振り射出筒を戻した。
CAM専用のブレードを振り上げて、歪虚CAMが迫る。
ウェスペルは、左マニュピレータのサブマシンガンを放って、背腰のハードポイントの鞘から斬機刀を逆手に抜き放った。
昏い刀身の刃先に灯る月光めいた淡いレーザー光が走り、刃閃が閃く。
振り落されたブレードの一刀を受け止める、斬機刀。
間近に迫る、歪虚CAMの頭部。本来なら無機的な光を灯すばかりのメインカメラが納まる場所に、ヒースは、由縁も知れぬ怨念が渦巻く両眼合わせて七つの眼球を視た。
その眼が訴える。憎いのだ──と。全てが憎い、何もかもが底抜けに恨めしい。
求めれど、満ちぬ。求めれば、崩れる。
ならば全て、壊れて仕舞え──世界の全ても己が自身も一切合切、壊れて終(しま)え。
「そう──慌てなさんなよ」
機体全身のスラスタ、のみならず斬機刀の峰、鍔に仕込まれたスラスタを巧みに使い、上から下へ剣圧を押して迫るブレードを受け流す。自身の力の行き場を唐突に失った歪虚CAMがたたらを踏んだ。その背後へ、ウェスペルは死神めいた静けさで舞い降りる。
歪虚CAMの胸郭より生えるのは、銃剣の切っ先。
「慌てずとも、終いにしてやるさぁ」
死神は背後を振り返らずして、トリニティのトリガーを引いた。
「余さず残さず──」
何度も、幾度も、弾倉の中身が尽き果てるまで。
ずるり──と銃剣を引き抜くと、同じくずるり──と歪虚CAMが崩れ落ちた
死神が、振り返る。
──その瞬間、一筋の刃閃が走り、歪虚CAMの胴と首を別った。地面に転がる異形の頭部から塵とも霧とも判断の付かぬ黒い無形の物体が昇り、空に溶ける。
「──おまえのすべて」
微かに震える刀身を静かに鞘に納めて、残響を断つ。
ガンポッドの濃密な弾幕が、迫りくるロケット榴弾を迎撃。榴弾が爆発して粉塵を巻き上げる。
爆炎の眩い光を背に受ける、ザントメンヒェン。アウレールは機体を反転させて、スラスタを逆噴射し、退却を図っていた足に急制動を掛ける。
メインカメラが捉える映像を映したHMD画面に、爆炎の中からズッ──と現れ出る歪虚CAMが映り込む。炎を背にしたその姿の、なんと凶々しい事か。
二機構成の敵小隊の内一機を狙撃によって撃墜したまでは良かったが、仕留め損ねたもう一機にここまで接近を許してしまったのだ。この間合い、狙撃ライフルでは分が悪い。
ライフルをハードポイントに戻し、入れ替えにブレードを手に取るや、アウレールは背面のスラスタを噴かし機体を走らせた。
敵機もまた間合いの変化に伴いロケットランチャーを放棄して、腰部ハードポイントに吊り下げたハンドアックスを構え、同じく特攻を仕掛けて来る。
自機と敵機──彼我の間合いが、互いの得物の刃圏にまで至る。
先んじたのは、上方より振り落ちる斧頭の一撃。
しかし、遅れに失したかに思われたブレードの柄頭が、機体頭部をかち割らんとするアックスの側面を弾く。そのまま、流れるような動きで刃を寝かせたブレードが、峰に仕込んだスラスタを噴出。
すれ違いざまに、側腹部を刃で撫でながら、歪虚CAMの脇を過ぎるザントメンヒェン。
その一刀は浅い。しかし駆動系を損傷したか、歪虚CAMの動きが鈍る。
アウレールは再び機体を反転させた。
ザントメンヒェンにブレードを握らせたまま、片腕のみで狙撃ライフルを構えさせる。
機体の速力を完全には殺せぬまま、間を置かずしてトリガーを引く。
火器管制が照準を補正し、撃発。──撃発に伴う反動を、各部のスラスタが小刻みに推進剤を噴射して抑え、射撃姿勢を制御する。
放たれた弾丸は、過たずして命中。胸郭を抉られた歪虚CAMの全身が弛緩し、その場に崩れ落ちた。
ザントメンヒェンの機体脚部が地面を掴み、土煙に蒸発した衝撃吸収材を交えながら、停止する。
赤く光るモノアイが、敵機の残骸を見下ろす。
「くく、あはは」
HMD画面に映るソレを見て、アウレールは肩を震わせた。どちらの自分がそう思っているのかわからぬままに、彼は今確かに『愉しい』と感じていた。
対CAM戦経験のあるCAMパイロットは少ない。
それは当然の事で、R6b2以降のモデルは、そもそも対歪虚戦を想定した機体だからだ。歪虚という最大の敵が存在する以上、人間同士の小競り合いに最大戦力であるところのCAMが使用されることは極めて稀である。
必然、対CAM戦の機会があるとするなら、それはそのCAMが歪虚に浸食された場合が大多数を占める事になる。
そして、その歪虚CAM討伐の依頼を優先して受けるハンターが独り、居る。
その男は、公然の秘密として、軍内部でとある異名を以って語られている。
上官殺し──と。
鞍馬機の背後を取った歪虚CAMが振り下ろしたブレードを、咄嗟に割って入ったステラマリスが両のマニュピレータに握り締めた、穂頭のない槍の柄で受け止める。羊谷が半身を切るようにして機体を操作し、柄を回して剣圧を受け流すや、歪虚CAMが体勢を崩す。
隙の空いた側腹部に柄の先端を押し当て、トリガーを引き絞った。その瞬間──マテリアルによって構成された刃が現出し、歪虚CAMの胴を貫いた。
非実体性の穂頭を動かし、胴体を引き裂く。役目を終えた刃が霧散し、淡い光の粒を撒いた。
「鞍馬さん、あまり、無茶をしないでください……!」
背後に庇った鞍馬機へ、上気した息を整えながら、羊谷は呼び掛けた。
『……ああ、わかっている。これでも、無謀との線引きはしているつもりだ』
確かに、鞍馬は秀でたCAM乗りなのだろう。ひどく好戦的な姿勢に見えて、その実紙一重のところで死線を踏み越える事はしない。だが──
「っ、本当にわかっていますか? わたしには、あなたがご自身を蔑ろにしているようにしか視えません」
彼はその紙一重の差を、何とも感じていないように思うのだ。鞍馬は、そこに恐怖も、或は期待すらも見出してはいないのではないか?
「どうして、どうしてそんな」
『──君が今、斬り捨てたそのCAM』
唐突に、鞍馬はそう切り出した。
『そのCAMに、人が乗っていると知ったら、君はどうする?』
その言葉の意味を理解するのに、一拍の間を要した。
ドクン──と、心臓が一つ、大きく鼓動を打つ。
「そ、んな」
『──いや、すまない。仮定の話だ。安心していい。今回の襲撃では、CAMが出撃する暇すらなかったと聞いている。俺達の相手は、全て無人だ』
その言葉を聞いて、思わず安堵する自分が居た。
『だがもしも、人が乗っているとしたら? コックピットの中に──為す術もなく棺桶の中に閉じ込められている人間が居るとしたら、君はそれを撃てるか?』
すぐに応える事など、できようはずもない。ただ今確実にわかる事は、今さっき心が竦んだ自分が居るという事。
『俺は、撃った』
ぽつりと、独白するような声で、鞍馬は言った。
『俺が、この手で殺した』
「それって、まさか……」
上官の死へ責を感じているという男。例えば、あの移動基地で耳にした彼の異名『上官殺し』が、単なるレトリックでないとしたら。
「それでも、あの子は、あんなにあなたを……。あなたの帰りを待って」
『あの子が全てを知った上で、俺を慕ってくれているとでも?』
それは、そうなのだろう。でも──
「それでも……、それでもあの子は、あなたに帰って来て欲しいって」
おそらく、それはこの男にとって酷薄な言葉なのだろう。それでも、イヤなのだ。誰かが帰りを待っているというのに、自分の命を粗末に扱う人間が。
「あなたは、あの子を二回も、独りぼっちにさせる気ですか」
それに、袖を引くあの小さな手は、あんなにも震えていたのだから。
『辛辣な、台詞だな』
苦笑──だが、苦味はそこまで強くなかった。
『そう言ったのは、君で二人目だ』
二人目──では最初の一人が誰だったのか、それを問うのは野暮だろう。
「きっとその人も、あなたの帰りを」
『ああ……、わかっている。わかっては、いるんだ』
覚悟とは何か。
『覚悟』の二字を刻み込んだ機体に駆りながら、南護は己にそんな事を問うた。あの男、鞍馬の言動が、そんな疑問を彼の内に生じさせた。
南護にとっての覚悟と言えば、大切なモノを守るという誓いだ。その為に力を尽くし、命を賭してでもそれを為す。それが、南護にとっての覚悟だった。
それが揺らいだ、とまでは思わない。その覚悟に偽りはなく、その覚悟に不足はない。
「ああ、駄目だ。うだうだ悩むのは、俺の性分じゃねぇ」
そう、結局自分にできるのは、ただ真っ直ぐに突っ走るのみ。
「俺の名は南護炎、歪虚を断つ剣なり!」
肩部装甲を展開し、防護フィールドを形成。
実体を持たぬマントの裾端を翻しながら、F・O・Mが走る。襲い来る弾時雨、その悉くを弾く。
確認できた最後の歪虚CAMが、ロケット推進のミサイルをF・O・M目掛けて発射。それとて、南護の往路を阻むには至らない。
心眼──刀意即妙。心を以って刀とし、刀を揮って心を為す。
振り上げた刀を、刀の意のままに振り下ろし、榴弾を一刀両断の下に斬り伏せる。
F・O・Mが過ぎ去って、二つに別たれた榴弾がようやく斬られた事を自覚したかのように爆発炎上。
爆炎の光を背に浴びながら、機体が更に加速する。その姿は青い流星の如く。
「あとは叩っ斬るのみだ!」
南護の咆哮に応えるように、人工音声が『レディ』と無機的な声を発する。
刀は水平に寝かせ、構えは抜き胴。
迷いを払った刀の刀速は、刃の冴え以外の全てを置き去りにして、奔った。後に残るは、胴の半ばで二つに別たれた歪虚CAMの残骸と、透き通るような刀の残響のみ。
「俺の覚悟に、断てぬものなし」
鞘口に刀の切っ先を納め、金丁を以って残響を断つ。
「お帰りなさい、クラマ」
少女はいつもそう言いながら、笑顔と共に飛びつく。本当にその言葉とその笑顔で迎えたかったはずの人を奪った男に。その事実も知らずして。
「ああ。ただいま、レーネ」
そして、男は不器用な笑顔で以って、その言葉を返す。その資格があるはずもないと知りながら。
この時だけだ。男が本当に死にたくなるのは。
この時だけだ。自分が歩く死体などではなく、当たり前に生きている人間なのだと自覚するのは。
きっと少女が何もかもを知った時、彼女から「お帰り」と言われる事も、笑顔を向けられる事もなくなるのだろう。
少女が自分以外の誰かに「お帰り」と笑顔と共に言えるようになった時、少女に全てを打ち明けよう。
その時まで、男はこの日だまりのような地獄へ帰り続ける。
回避──頭がその単語に至るよりも早く、機体左半身のスラスタを噴射。射線より逃げ遅れた左マニュピレータのアサルトライフルが被弾。一瞬たりと躊躇わず放棄すると同時に、弾倉内の弾薬が誘爆を起こす。
自身に襲い掛かるGを考慮しない回避行動の影響で、明滅する視界の片隅に、次射を放とうと照準を補正する歪虚CAMの姿を捉える。
回避──不可。
HMDの画面が鮮烈なマズルフラッシュに灼かれる──その刹那、灼光を遮り、青い機影が鞍馬機の前に立ち塞がった。
『俺が受ける、下がってろ!』
五十七ミリの徹甲弾が、青い機影の正面に着弾。
──青い燐光が、飛沫となって散る。
青いカラーリングのR7──R6シリーズの後継機“エクスシア”の肩部が展開。展開部より放出されたマテリアルが防御フィールドを形成し、敵弾を無力化したのである。
射撃を阻まれた歪虚CAMは、一切の動揺を見せずに、インジェクターより空薬莢を排出した狙撃ライフルを構え直す。排莢された直径五センチ程の薬莢が、地面にめり込むと共に、銃口が再び青いエクスシアを捉える。
次の瞬間、一条の光線が、ライフルを構える歪虚CAMの脇腹を貫いた。
真っ直ぐに伸びた光の矢は、鋼鉄の装甲を食い千切ると、余韻めいた残光をちらつかせながら、空へと溶けてゆく。
胴体に大穴を穿たれた歪虚CAMが、密林の中へ沈む。
「一発必中とは、おみそれいった」
それをHMDの拡大ウィンドウで視認した近衛 惣助(ka0510)は、僚機へ通信を繋いで称賛の言葉を送った。
堅牢な盾に、三〇ミリのガトリング砲とカノン砲を装備した、動く要塞のようなCAM──近衛が駆る“真改”の傍らに立つのは、彼の機体と相反して、兵器というよりは天使を模した宗教像のような雰囲気を持つエクスシアだ。
マテリアル兵器に特化したCAMが背負う光背めいた輪状のパーツが展開し、淡い光を放っている。それは、マジックエンハンサーという、言わば魔導エンジンに対するコンデンサーのようなものだ。一時的に出力を上げた魔導エンジンの余剰エネルギーを集積、循環する事によって、マテリアル兵器の補助、強化を担っている。
今しがた光の矢を放ったマテリアルライフルの威力を思えば、その効果は語るまでもないだろう。
『近衛さんの観測データのお蔭です。ありがとうございます』
白と蒼を基調とした、何処か無垢な神聖を帯びているエクスシアから返って来た通信の声は、近衛の無骨なそれとは違い、柔らかな少女の声。いや、流石に今ばかりは、多少の硬さが含まれているだろうか。
神の御使いめいた機体“ステラマリス”のパイロット、羊谷 めい(ka0669)は近衛の眼からしても、おおよそ闘争を好む人種であるようには視えなかった。矛先を向ける相手が、たとえ歪虚であろうとも、何かを“害する”という行為の似合う雰囲気の持ち主ではない。
『鞍馬さんは、……無事みたいですね』
通信機越しに、安堵の溜息が伝わる。
『──近衛さんは、レーネちゃんとお話ししましたか?』
「ん? ああ、あの子のことか。いや、どうにも俺は怯えられているみたいでな」
『わたしも、お話できたのは、ほんの少しだけでした』
苦笑する近衛に合わせて、微笑の気配を声に滲ませる羊谷。だが、僅かに間を置いて『でも』と再び言葉を発した時には、朗らかな笑みは鳴りを潜めて、何処か強固な響きをその声に伴っているように感じられた。
『でも、最後にあの子は言ったんです。わたしの袖を強く引いて、
──クラマを……連れて帰って来て
鞍馬さんを、連れて帰って来てって」
「……そうか」
近衛はそう呟きながら、鞍馬が駆るデュナミスを見遣った。ともすれば自棄的とも言える戦闘スタイル。おおよそ、帰り路の足を残さねばと考えている者の戦い方ではない。
「放っておくわけにもいかないな」
操縦桿を改めて握り直す。その時、アラームが鳴り響き、新たな敵機の接近を告げる。歪虚CAMの姿を光学センサーが捉える共に、照準レーザーの被照警報。
敵の兵装は、ロケット推進のランチャー。砲口から放たれた榴弾が推進剤を噴射。
近衛の駆る真改が、羊谷機を庇うように前へと出る。その正面へ推進剤の尾を引きながら、ロケット弾が着弾。
弾頭の成形炸薬が炸裂する──!
周囲一帯の木々が、爆風に軋みを上げながら大きくしなり、木の葉が吹き荒れる。
やがて爆風が静まり、あとは木の葉が舞い落ちる。しかし、爆音の余韻が途絶えぬ内に、一発の砲声が再び辺りの梢を揺らがせた。
一瞬の間を置いて、今しがたロケット弾を放った歪虚CAMの傍らに立つ樹木が砕け、木端混じりの土柱が立つ。
ロケット弾の炸薬による黒煙が、砲弾の射出に伴う衝撃波によって晴れ、現れ出たのは、CAMの前面投映面積を覆う程に巨大な盾。そして、その盾を銃架代わりにして構えられたカノン砲。
ロケット弾着弾の衝撃はコックピットを大きく揺さぶっただろうに、近衛の表情に苦痛の色はなく、反撃の砲撃を外したというのに、それに落胆する様子もなかった。
元々、初弾が当たるとは思っていない。CAMにも扱えるように取り回しを良くする為、砲身を短くしたカノン砲。おおよそ無茶な改造を施してあるにも関わらず、更に砲口を二つ備えているというゲテモノだ。到底、まともな精度は望めまい。
真改の光学センサ──頭部のメインカメラを、バイザー型の高精度照準器が覆った。
自動装填が次弾を薬室(チャンバー)へ込めると共に、火器管制が誤差修正。
照準器の横調節(ウィンデージ)を右に一・四ミル、縦調整(エレベーション)を上へ一・二ミル微調整。
操縦桿のトリガーに指を這わせて、
「──こいつが本命だ」
再び、カノン砲が火を噴いた。
過たずして、低い放物線を描いて飛んだ二発の榴弾が歪虚CAMの右腕と胸郭を捉え、炸裂。
「一機撃墜した。これより分隊支援に徹底する」
カノン砲を、左肩部のハードポイントアームに保持しておいたガトリング砲へ換装する。
「背中は任された。──後の酒が不味くなるから、勝手に死んでくれるなよ」
青いエクスシアが腰部のハードポイントに接続した鞘から刀を抜き放ち、鞍馬機の前を塞ぐようにして掲げる。
「聞いての通りだ。単身で突出するのは、控えてくれよ」
青いエクスシア──フレイム・オブ・マインド(F・O・M)のコックピットに座す南護 炎(ka6651)は、近衛の通信を聞いて、同じくそれを耳にした鞍馬へと語り掛ける。精力に溢れた、張りのある声だ。その精悍ながら若々しい顔付きも相俟って、青さの残る武人といったところだろうか。
『……ああ、すまない。さっきは、助けられたな。礼を言う』
「…………」
鞍馬の反応に、南護は口を噤んだ。まさか、感謝を示されるとは思っていなかったのだ。その気配を悟ったらしい鞍馬が『どうした』と苦笑というには、苦味の強過ぎる声音で言った。
『余計な事をするな、とでも言うと思ったか? 俺が『死にたがっている』とでも?』
「ああ、いや……」
胸の内を言い当てられ、南護は言い淀む。
『その様子では、ユリアから何か聞かされたか』
苦笑──今度こそそう言える程には笑みの成分の多い声で、鞍馬は言う。
『彼女は何と?』
「あんたが昔、あの月面戦争で、上官を亡くしたと」
『それだけか』
「それだけさ。深く立ち入ったことまでは、聞かされてない。ただ、あんたがそれ以来、無茶な戦い方ばかりしてるってことくらいしかな」
意図せずとも責めるような口調になった南護の台詞に、鞍馬は『そうか』と零したのみで、言葉を重ねる様子はない。その気のない返事に、妙に苛立ちが募る。
「あの女(ひと)は、あんたの事、心の底から案じてたぜ」
でなければ、赤の他人であるはずの南護や他のハンター達に、自分も関わる過去の話をおいそれと語る道理はないだろう。
『ああ、知っている』
「知ってるって……、なんだよ、そりゃぁ」
無性に、腹の立つ返答だった。
「あんた、なに考えてんだ? 死なせてしまった上官や、残されたあの子に責任を感じてるのは、俺でもなんとなくはわかるさ。だからって、死ぬことが償いになるわけじゃないだろ……!」
むかつきのままに吐いた言葉は、激昂というよりは癇癪に近いモノだったかもしれない。ともかく、鞍馬の言動の一つ一つが、一々癇に障るのだ。
『償い……?』
それまで南護の台詞へ気のない態度で応じていた鞍馬が、顕著な反応を見せた。
『死が、償いになる──か。なるほど』
考えたこともなかったな──と鞍馬は言った。
『それで、それだけで済んだなら、どんなに楽だったか』
「なにを……?」
その言葉が何を意味するのか、南護にはわからない。ただ、少なくとも言えることは、この男は死にたがりよりも、更にタチの悪い何かであるという事。
南護が更に問い詰めようとした時、アラーム音が敵の増援の来訪を報せる。HDM越しに、歪虚CAMの凶々しい姿を捉える。
『どうやら、これ以上話している余裕はなさそうだ』
鞍馬機が、ERAを券面に取り付けた両のマニュピレータを構える。
「おい……!」
『わかっている。これ以上、面倒を掛ける気はない』
また独り敵陣へ飛び込むのではないかと勘繰る南護に、鞍馬機の構えが前傾姿勢から僅かに身を起こす。
「……なら、いいさ」
そう言うと、南護は敵影との間合いを図りながら、愛機を進ませる。その歩調に合わせて追随する鞍馬機。臨戦から、いよいよ戦闘の間合いに踏み入ろうとする前に『一つ』と、鞍馬が切り出した。
『一つだけ、訂正しておく』
「なに……?」
『死なせてしまった、というのは誤りだ』
殺した──と、鞍馬は言った。
『俺が自らの手で、あの女(ひと)を殺したんだ』
林立する木々の間を縫うかのように奔る、小さな巨人。
全長、二・八メートル。それは、生身の人間に比べれば十分な巨躯を誇っていたが、CAMと並べれば腰程にも届かない身の丈をしていた。
魔導アーマー。クリムゾンウェスト独自の技術──機導術の力によって開発された、機導兵器。今、足許のホイールを回しながら密林を奔る機体“プラヴァー”は、魔導トラックに手足を付けたのみという粗末な第一世代とは違い、リアルブルーの技術体系を取り入れた第二世代以降の機体である。
その外観及び設計思想は、リアルブルーにおける強化外骨格(パワードスーツ)に相似している。操作体系にマスタースレイブを採用したプラヴァーは、直感的な操作を可能とし、操縦者の手足の延長線上として機能する。
木々の根が張り巡った悪路を、時にはホイールを地面に噛ませながら、時には地面を蹴って宙を舞いながら走破するその身軽な身のこなしは、その設計思想故に、操縦者であるアイビス・グラス(ka2477)本来の動きを、正確に再現していた。
機体を遥かに上回る巨木の幹にホイールを噛ませて駆け上がる。運動エネルギーを位置エネルギーが上回り、重力に背中が捕まる前に、足を蹴って宙へ跳ぶ。その直後、機体の表面を何かが擦過し、最前まで機影のあった幹が爆ぜた。
「ホント、端から身体が鉄でできてたみたい」
風防のない、剥き出しの操縦席──碧色の髪を靡かせながら、持ち前のグリーンアイを覆うゴーグルレンズの表面に撒き散る木端を捉えつつ、アイビスは口許に笑みを湛えた。装甲を撫ぜたソニックウェーブを生み出し、巨木を砕いたモノが何であるのか、今更問うには値しない。
近衛、羊谷、南護、そして鞍馬を入れた追撃を主目的にするメインのA班とは異なり、主に斥候、攪乱を目的とするB班に振り分けられたアイビスは、作戦地域の外周を徐々に中心へと近付き索敵を行いながら巡っていたところ、敵小隊と遭遇し戦闘を開始したのだ。
襲い来る敵弾を回避し、宙を泳ぐプラヴァー。着地するまでの数瞬、機体は無防備になる。自由落下の最中に、照準レーザーの被照警報。
ゴーグルを銃の発火炎が灼く──その寸前に、アイビスは身を沈めた。少なくとも、彼女はそういう感覚で、身体を操作した。
機体背面より散る、残像めいた碧光の残滓を、銃弾が貫く。
重力加速よりも早く機体が斜線を引くように落下し、プラヴァーの二足が地面を踏み締めた。ホイールをドリフト走行気味に横滑りさせながら、体勢を立て直す。
スペルスラスタ──魔導アーマー独自の推進システム。CAMのような推進剤ではなく、機導装置によるマテリアル噴射によるものだ。持続性が少ない為、効果が期待できるのは滞空中の姿勢制御や、瞬間的な加速のみだが、マテリアルに準拠する為、感覚的操作感の強い機能である。
アイビスは着地したのちも、その機能を用いて敵弾を俊敏に密林の中を奔りながら、敵機へと肉迫してゆく。
だが、敵機を追い詰めた座標付近の地形を改めて視認するや、彼女は舌を打つ。
木々の間が狭すぎる。近接兵装しかないこちらの間合いに敵機を捉えようと思えば、直進する他に手段がない。機体に組み込んである、まだ実戦で試した事のない防御機構を頼りに特攻を仕掛けるべきか否か、アイビスが次手に悩み、進攻の速度を緩めようとしたその時、
『構わん、そのまま進め』
耳元のイヤリングを模した通信機が、声を発した。年若いにも関わらず、威厳ある男の声だ。
『案ずるな。貴公の背中は、私の眼の内にある』
「もしも犬死にしたら、化けて出てやるから」
落ち着き払った声音に、アイビスは口許に微笑を湛えながら言った。
『歓迎しよう。私も犬は嫌いではない。狼ともなれば、持て余すかもしれないが』
口許の笑みを深くする。
「良い返事ね」
生真面目に応じられるよりは、よっぽど頼りになる。
「タイミングは?」
『好きに動くと良い。こちらが合わせよう』
なんとも頼り甲斐のある返事に「オーケィ」と応じるや、アイビスはクラウチングスタートを決めた。──少なくとも、彼女はそういう感覚で、肢体を動かした。
背面より、マテリアルを放出し、鉄の躰が疾走する──!
ただまっすぐ、一直線に駆け抜けるプラヴァ―に、歪虚CAMが機械というよりは何処か死人めいた無機的な反応を示した。──ただしその速さばかりは、兵器の機能を損なわずして。
照準レーザーの被射警報──無視。速力を落とさず、いや寧ろ、更に加速する。
『お砂をひとつまみ(Prise Sand)』
通信機が発する子供騙しな呪文──歪虚CAMの頭部に銃痕が穿たれ、メインカメラを失った機体が一瞬動きを停める。
と同時に、プラヴァーが跳んだ。
スペルスラスタをありったけ吹かし、右腕部──五指の代わりに鉤爪を生やした掌を、歪虚CAMの胸郭へ叩き付ける。
むべなるかな、全長に倣い質量で遥かに下回る魔導アーマーの殴打は、体勢を崩したCAMですら、その体幹を倒すまでには至らず、ただ五条の爪が装甲へ喰い込むばかり。
「潰れろ──」
死線に飛び込んだ末の一撃が不発に終わったにも関わらず、しかしアイビスは、口許の笑みを絶やさず、寧ろ口端のカーブを獰猛に歪めて吼える。
「潰れろ、ヴォイドォ──!」
緋色の装甲に覆われた右腕──獲物を逃さじと喰らい付く鉤爪に捉えられた歪虚CAMの胸郭が、不可視の鉄槌を叩き付けられでもしたように大きく陥没する。
掌底に内蔵された魔導機械が、マテリアルを糧に稼働して衝撃波を発生させ、CAMの装甲を圧潰させたのである。
胸部──機体の操作系統を根こそぎ潰された歪虚CAMが、膝から崩れ落ちる。その上体が沈むと同時に歪虚CAMの傍らに足を降ろしたプラヴァーが、足許のホイールで地面に弧状の轍を刻みながら着地の衝撃を殺して、敵の残骸に背を向ける。
「一機撃破。──なかなか悪くないわね、こういうのも」
鮮血よりもなお紅い腕を眺め、口許のカーブがますます深く。
足を止めていたのは、ほんの一時だけだった。アイビスの駆るプラヴァーは、エメラルドよりもなお輝かしい光を撒きながら、森を奔った。
片側が急勾配の崖になった高台に、片膝立ちの体勢で鎮座するCAM。全体に施した迷彩ペイント。油断なく左右へ巡るモノアイが赤く光る。
新興公爵家ブラオラントの保有する魔導発動機製造工場にて、ノックダウン製造──連合宙軍より受け取った各部品を組み立てる事によって製造された、ワンオフのR6M2b現地改修モデルPzI-2M ザントメンヒェン”である。
「ほんとの狼だって、もう少しおとなしいんじゃないかな」
そのコックピット内で、通信を繋ぐでもなしに独り呟く、稚気を含む声。それが、つい今しがた、アイビスの通信機が発したモノと同じ人物の声であるなどとは、そうおいそれとわかるものではない。
「ま、頼りになるのはいいことだけどさ」
だが彼こそが、今しがた狙撃ライフルによってアイビス機に支援射撃を行ったザントメンヒェンのパイロットにして、ブラオラント家次期当主アウレール・V・ブラオラント(ka2531)だ。
「さて、と──」
アイビスの奮闘振りに肩を竦め呆れ交じりの称賛を送ったアウレールは、再び通信を繋ぐ前に、意識を切り替えた。いや、『切り替える』というのとは違うだろうか。『仮面を付ける』、いや、そう『蓋をする』だ。中身を抑える為の、或は中身を見ないで済むようにと造られた蓋。容れ物と中身──理想足らんとする自分と、夢想を語る自分との間に、明確な差などないという事は、とっくに理解してしまったが。
はて、何故こんな感傷に囚われたのか。ザントメンヒェン──子供の頃、母から何度も聞かされた妖精の名を冠する機体の中に居るからだろうか。早く寝ないと、眠り砂の妖精さんが来る──帝国の出身者なら、一度ならずとも聞かされた文句だろう。
寝なくたってへっちゃらだよ。軍人さんになったら、夜も寝ないでみんなを守る為に戦うんだから──そう言う度に、母が何かをこらえるかのような顔をしていた事を想い出した。
感傷を無用と払い、そうする事で意識がブラオラント家次期当主の自分のそれへと替わり、通信を繋ぐ。
「こちらアウレール。ウォーカー、状況の報告を」
同時に、HMD画面に製図、データ化した作戦地域の地図を呼び出す。図内に、通信の送信先、ヒース・R・ウォーカー(ka0145)が操る機体の現座標を示す光点を確認。光点より僅かに距離を置いた地点には、アイビス機を示す光点がある。アイビスが先程まで交戦していた地点には×印。更にヒース機周辺には、敵機を示す光点が二つ点っていた。
現在ヒース機は、アイビスが発見した歪虚CAM三機構成の小隊の内二機を牽き付け、相手取っている。その間に、アイビスが確実に敵一機を撃破しようという策である。
『まぁ、なんとか役割は果たせてるさ。連中遊び弾は放らないで、一々殺しに掛かって来るから、わかりやすくて助かるねぇ』
戦闘中と思えぬ、気怠い声。声に紛れて聞こえる銃声、爆発音にも動じない、気怠い声。
「ご苦労だった。現在、敵一機を撃破し、グラスがそちらへ向かっている。合流し次第──」
台詞を遮るようにして、通信機がアイビスの声を発する。
『あー、お待ちのところ悪いんだけど、ちょっとマズいことになったわ』
「どうした」
『敵さんご一行を発見。数は二機、どうも傭兵さんのとこに、増援で向かってるみたいだけど。どうしたものかしら?』
『おいおい、あと二名サマも追加ってことかい? 勘弁願いたいねぇ、いくらなんでも手が足りそうにないんだが?』
「了解した。そちらは、私が引き受けよう。敵座標データの転送を」
『オーケィ、送ったわ』というアイビスの了承の直後に、データを受信。データが示す座標にモノアイを向ける。そこは、作戦地域内でも特に高い樹木が密集している地点。いかなCAMの図体でも、目視は不可。狙撃ライフルによる精密射撃では、有効な打撃にはならない。
「フロートガンポッド、起動」
背面のハードポイントに接続したガンポッドのロックを解除。ハードポイントより切り離されたガンポッドが、火砲、弾薬、給弾機構と共に内蔵されたフロートシステムによって、機体周囲を浮遊する。
狙撃ライフルと共にそれらの照準を敵座標へと向けて──「制圧射撃を開始する」
銃声が銃声を劈き、密林に弾時雨が降り頻る。
ガンポッドの濃密な斉射に加えて、狙撃ライフルを弾倉が尽きるまで連射。ライフル弾が尽きるや否や、機体を中空へと躍らせる。高台の上から、直下に向けて自由落下。
その直後、最前まで機体が膝を着いていた空間を、敵の応射が薙ぐ。目論見通り、敵がこちらに喰い付いた。
敢えてスラスタによる減速は行わず、そのまま地面に足を落とす。着地の瞬間、衝撃吸収材が蒸発し、落下による衝撃を受け止めた。棺桶サイズの弾倉を落としてライフルをリロードしながら、冷静に通信を行う。
「敵の動きは?」
『撃ち返したと思ったら、行き先を変えてそっちに向かったわ』
「上々だな。そちらは引き続き、ウォーカーと合流を」
『りょーかい。そんじゃ、そっちも気を付けて』
「ああ。互いに最善を尽くして、武運を祈るとしよう」
そう締め括り通信を切るや、アウレールは再びHMD画面に映る地図へと眼を走らせた。等高線を記した図面には、有効な狙撃ポイント、及びアンブッシュに利用できそうな地点まで書き込んである。
現在位置と照らし合わせて、移動ルートを検討。要した時間は、即断と言って差し支えない程だろう。
即座にアウレールは、定めたルートに沿って、機体を走らせた。
せせらぎの音を奏でる、川の中流。平素なら、野生動物の水飲み場として機能していただろう場所を、不躾な巨人の足が踏みしだく。
跳ね上げた水を浴びる漆黒の装甲。日の下にして宵闇を宿すかのようなカラーリングに身を包む、一機のデュナミス──“ウェスペル”。そのコックピット内で、ヒースは小さく舌打ちを漏らした。
右マニュピレータに握る、銃剣付き拳銃──アワフォード社製ハンドガン“トリニティ”を正面に向けて立て続けにトリガーを引く。──発せられた弾丸は、向かって左へと跳ぶ敵影を捉え切れず、ただ空を切るばかり。
接近警報──アラームが耳を劈くよりも早く、左マニュピレータに握るサブマシンガンの銃口を、振り返らずして背後へと向け、トリガーを引く。今度ばかりは、過たずしてCAM用ダガーナイフを片手に背後へと迫りつつあった歪虚CAMを弾丸が叩いた。だが短銃身、小口径の銃では精々足止めが限界で、CAMの装甲を貫くには不足がある。
振り返りざまに、右マニュピレータを振る。と同時に、トリニティの重厚な銃身──単なるハンドガンとしては分不相応に分厚い機関部が展開し、変形してゆく。
果たして、照準を歪虚CAMに向けた時には、トリニティの銃身が伸長し、グレネードランチャーへと姿を変えていた。
スラスタを噴いて後退しながらトリガーを引き、人間の頭程はある塊を射出。
歪虚CAMの胸元三寸で、放たれたプラズマグレネードが弾け、紫電の爆発が迸る。
直後、グレネードの効果圏内より歪虚CAMが抜け出した。ダガーナイフが原型を留めておらず、前面装甲表面も一部融解している様子だが、行動不能にまで至る損傷ではない。CAMと同様に、プラズマ兵器は宇宙空間での使用を想定された兵装だ。端から、決定打になるとは思っていない。
だが、機体前面のスラスタを幾つか潰した事によって、幾らか機動力を削いだだろう。
今なら、ヤれるか?
疼く。血の昂ぶりが、身の内から溢れそうになる。
──舌を、打つ。
その衝動に身を任せるべきではない。状況を正確に把握しろ。己が役割を思い出せ。そして、愛する人の温もりを忘れるな。
お前が帰るべき場所は、いつも必ずそこにある。
トリニティを再びハンドガン形態へと戻しながら手首を捻るように右腕部を動かして、瞬時に右手側へと銃口を走らせる。
逆しまに構えた銃を三度(みたび)、撃発。
ウェスペルの右手側に回り込んでいた歪虚CAMが構えるロケットランチャーを、内二発が捉えた。歪虚CAMが兵装を放棄した直後、ランチャーが爆発。
右方の脅威を一時無力化させると共に、サブマシンガンを正面へと向けようとしたところで、ヒースはトリガーから指を離した。
『お待たせ』
通信機が、陽気な声を発する。
HMDが映す外界の映像に映るのは、アイビスの駆るプラヴァーの背中。
「いいや。そんなに待っちゃいないさ。もう少し遅れても構わなかったくらいだねぇ」
皮肉を交えて、返答。
「だがまぁ、助かったとは言っておくさ。これでようやく、退屈しないで済みそうだ」
『あらそ。それは良かった。それじゃ──』
くすり──と微笑む気配。
『──始めましょうか!』
直後に、プラヴァーが碧光を撒いて疾走した。
スペルスラスタを律動的に噴き、乱数機動で以って歪虚CAMに肉迫するプラヴァー。
それを迎える敵機が、短銃身のアサルトライフルを向ける。迎撃の弾丸をばら撒きながら、スラスタの反動で後ろに退いた。
だが遅い。照準も、動きも──何もかも。
襲い来る弾丸を潜(くぐ)り抜け、敵機の懐へと潜(もぐ)り込み、真紅に彩られた右腕を突き出す。
「潰れろ──!」
アイビスの咆哮に応じるようにして、右掌底部の魔導兵器が起動。
だが、突き出した鉤爪が敵機の胸郭を捉える前に、歪虚CAMは右腕部を盾にした。直後、掴まれた箇所を中心にして歪虚CAMの腕が圧潰する。しかし、腕に守られた胸部は以前、健在。
「まだよっ!」
未だエメラルドの光を瞳に絶やさず、アイビスは左手を突き出す。その動きに呼応したプラヴァーが、左腕部を歪虚CAMの胸郭に突き立てた。
「これが私の本命──正真正銘の“切り札”よ」
前腕に装備した特殊な近接射出兵器──パイルバンカーが、その内に溜め込んだ暴力性を解き放つ。その名に反して、杭とも呼べぬ無骨な鉄の塊が、敵機の胸郭を打ち貫いた。
天を仰ぐように上体を逸らし、膝から崩れ落ちる歪虚CAM。その上に立ちながら、プラヴァーがパイルバンカーの機関部を展開。
中折れ式の射出筒から、空薬莢が跳ねる。
入れ替わりに予備の実包を右腕部の鉤爪で摘まみながら薬室に込めるや、プラヴァーは腕を振り射出筒を戻した。
CAM専用のブレードを振り上げて、歪虚CAMが迫る。
ウェスペルは、左マニュピレータのサブマシンガンを放って、背腰のハードポイントの鞘から斬機刀を逆手に抜き放った。
昏い刀身の刃先に灯る月光めいた淡いレーザー光が走り、刃閃が閃く。
振り落されたブレードの一刀を受け止める、斬機刀。
間近に迫る、歪虚CAMの頭部。本来なら無機的な光を灯すばかりのメインカメラが納まる場所に、ヒースは、由縁も知れぬ怨念が渦巻く両眼合わせて七つの眼球を視た。
その眼が訴える。憎いのだ──と。全てが憎い、何もかもが底抜けに恨めしい。
求めれど、満ちぬ。求めれば、崩れる。
ならば全て、壊れて仕舞え──世界の全ても己が自身も一切合切、壊れて終(しま)え。
「そう──慌てなさんなよ」
機体全身のスラスタ、のみならず斬機刀の峰、鍔に仕込まれたスラスタを巧みに使い、上から下へ剣圧を押して迫るブレードを受け流す。自身の力の行き場を唐突に失った歪虚CAMがたたらを踏んだ。その背後へ、ウェスペルは死神めいた静けさで舞い降りる。
歪虚CAMの胸郭より生えるのは、銃剣の切っ先。
「慌てずとも、終いにしてやるさぁ」
死神は背後を振り返らずして、トリニティのトリガーを引いた。
「余さず残さず──」
何度も、幾度も、弾倉の中身が尽き果てるまで。
ずるり──と銃剣を引き抜くと、同じくずるり──と歪虚CAMが崩れ落ちた
死神が、振り返る。
──その瞬間、一筋の刃閃が走り、歪虚CAMの胴と首を別った。地面に転がる異形の頭部から塵とも霧とも判断の付かぬ黒い無形の物体が昇り、空に溶ける。
「──おまえのすべて」
微かに震える刀身を静かに鞘に納めて、残響を断つ。
ガンポッドの濃密な弾幕が、迫りくるロケット榴弾を迎撃。榴弾が爆発して粉塵を巻き上げる。
爆炎の眩い光を背に受ける、ザントメンヒェン。アウレールは機体を反転させて、スラスタを逆噴射し、退却を図っていた足に急制動を掛ける。
メインカメラが捉える映像を映したHMD画面に、爆炎の中からズッ──と現れ出る歪虚CAMが映り込む。炎を背にしたその姿の、なんと凶々しい事か。
二機構成の敵小隊の内一機を狙撃によって撃墜したまでは良かったが、仕留め損ねたもう一機にここまで接近を許してしまったのだ。この間合い、狙撃ライフルでは分が悪い。
ライフルをハードポイントに戻し、入れ替えにブレードを手に取るや、アウレールは背面のスラスタを噴かし機体を走らせた。
敵機もまた間合いの変化に伴いロケットランチャーを放棄して、腰部ハードポイントに吊り下げたハンドアックスを構え、同じく特攻を仕掛けて来る。
自機と敵機──彼我の間合いが、互いの得物の刃圏にまで至る。
先んじたのは、上方より振り落ちる斧頭の一撃。
しかし、遅れに失したかに思われたブレードの柄頭が、機体頭部をかち割らんとするアックスの側面を弾く。そのまま、流れるような動きで刃を寝かせたブレードが、峰に仕込んだスラスタを噴出。
すれ違いざまに、側腹部を刃で撫でながら、歪虚CAMの脇を過ぎるザントメンヒェン。
その一刀は浅い。しかし駆動系を損傷したか、歪虚CAMの動きが鈍る。
アウレールは再び機体を反転させた。
ザントメンヒェンにブレードを握らせたまま、片腕のみで狙撃ライフルを構えさせる。
機体の速力を完全には殺せぬまま、間を置かずしてトリガーを引く。
火器管制が照準を補正し、撃発。──撃発に伴う反動を、各部のスラスタが小刻みに推進剤を噴射して抑え、射撃姿勢を制御する。
放たれた弾丸は、過たずして命中。胸郭を抉られた歪虚CAMの全身が弛緩し、その場に崩れ落ちた。
ザントメンヒェンの機体脚部が地面を掴み、土煙に蒸発した衝撃吸収材を交えながら、停止する。
赤く光るモノアイが、敵機の残骸を見下ろす。
「くく、あはは」
HMD画面に映るソレを見て、アウレールは肩を震わせた。どちらの自分がそう思っているのかわからぬままに、彼は今確かに『愉しい』と感じていた。
対CAM戦経験のあるCAMパイロットは少ない。
それは当然の事で、R6b2以降のモデルは、そもそも対歪虚戦を想定した機体だからだ。歪虚という最大の敵が存在する以上、人間同士の小競り合いに最大戦力であるところのCAMが使用されることは極めて稀である。
必然、対CAM戦の機会があるとするなら、それはそのCAMが歪虚に浸食された場合が大多数を占める事になる。
そして、その歪虚CAM討伐の依頼を優先して受けるハンターが独り、居る。
その男は、公然の秘密として、軍内部でとある異名を以って語られている。
上官殺し──と。
鞍馬機の背後を取った歪虚CAMが振り下ろしたブレードを、咄嗟に割って入ったステラマリスが両のマニュピレータに握り締めた、穂頭のない槍の柄で受け止める。羊谷が半身を切るようにして機体を操作し、柄を回して剣圧を受け流すや、歪虚CAMが体勢を崩す。
隙の空いた側腹部に柄の先端を押し当て、トリガーを引き絞った。その瞬間──マテリアルによって構成された刃が現出し、歪虚CAMの胴を貫いた。
非実体性の穂頭を動かし、胴体を引き裂く。役目を終えた刃が霧散し、淡い光の粒を撒いた。
「鞍馬さん、あまり、無茶をしないでください……!」
背後に庇った鞍馬機へ、上気した息を整えながら、羊谷は呼び掛けた。
『……ああ、わかっている。これでも、無謀との線引きはしているつもりだ』
確かに、鞍馬は秀でたCAM乗りなのだろう。ひどく好戦的な姿勢に見えて、その実紙一重のところで死線を踏み越える事はしない。だが──
「っ、本当にわかっていますか? わたしには、あなたがご自身を蔑ろにしているようにしか視えません」
彼はその紙一重の差を、何とも感じていないように思うのだ。鞍馬は、そこに恐怖も、或は期待すらも見出してはいないのではないか?
「どうして、どうしてそんな」
『──君が今、斬り捨てたそのCAM』
唐突に、鞍馬はそう切り出した。
『そのCAMに、人が乗っていると知ったら、君はどうする?』
その言葉の意味を理解するのに、一拍の間を要した。
ドクン──と、心臓が一つ、大きく鼓動を打つ。
「そ、んな」
『──いや、すまない。仮定の話だ。安心していい。今回の襲撃では、CAMが出撃する暇すらなかったと聞いている。俺達の相手は、全て無人だ』
その言葉を聞いて、思わず安堵する自分が居た。
『だがもしも、人が乗っているとしたら? コックピットの中に──為す術もなく棺桶の中に閉じ込められている人間が居るとしたら、君はそれを撃てるか?』
すぐに応える事など、できようはずもない。ただ今確実にわかる事は、今さっき心が竦んだ自分が居るという事。
『俺は、撃った』
ぽつりと、独白するような声で、鞍馬は言った。
『俺が、この手で殺した』
「それって、まさか……」
上官の死へ責を感じているという男。例えば、あの移動基地で耳にした彼の異名『上官殺し』が、単なるレトリックでないとしたら。
「それでも、あの子は、あんなにあなたを……。あなたの帰りを待って」
『あの子が全てを知った上で、俺を慕ってくれているとでも?』
それは、そうなのだろう。でも──
「それでも……、それでもあの子は、あなたに帰って来て欲しいって」
おそらく、それはこの男にとって酷薄な言葉なのだろう。それでも、イヤなのだ。誰かが帰りを待っているというのに、自分の命を粗末に扱う人間が。
「あなたは、あの子を二回も、独りぼっちにさせる気ですか」
それに、袖を引くあの小さな手は、あんなにも震えていたのだから。
『辛辣な、台詞だな』
苦笑──だが、苦味はそこまで強くなかった。
『そう言ったのは、君で二人目だ』
二人目──では最初の一人が誰だったのか、それを問うのは野暮だろう。
「きっとその人も、あなたの帰りを」
『ああ……、わかっている。わかっては、いるんだ』
覚悟とは何か。
『覚悟』の二字を刻み込んだ機体に駆りながら、南護は己にそんな事を問うた。あの男、鞍馬の言動が、そんな疑問を彼の内に生じさせた。
南護にとっての覚悟と言えば、大切なモノを守るという誓いだ。その為に力を尽くし、命を賭してでもそれを為す。それが、南護にとっての覚悟だった。
それが揺らいだ、とまでは思わない。その覚悟に偽りはなく、その覚悟に不足はない。
「ああ、駄目だ。うだうだ悩むのは、俺の性分じゃねぇ」
そう、結局自分にできるのは、ただ真っ直ぐに突っ走るのみ。
「俺の名は南護炎、歪虚を断つ剣なり!」
肩部装甲を展開し、防護フィールドを形成。
実体を持たぬマントの裾端を翻しながら、F・O・Mが走る。襲い来る弾時雨、その悉くを弾く。
確認できた最後の歪虚CAMが、ロケット推進のミサイルをF・O・M目掛けて発射。それとて、南護の往路を阻むには至らない。
心眼──刀意即妙。心を以って刀とし、刀を揮って心を為す。
振り上げた刀を、刀の意のままに振り下ろし、榴弾を一刀両断の下に斬り伏せる。
F・O・Mが過ぎ去って、二つに別たれた榴弾がようやく斬られた事を自覚したかのように爆発炎上。
爆炎の光を背に浴びながら、機体が更に加速する。その姿は青い流星の如く。
「あとは叩っ斬るのみだ!」
南護の咆哮に応えるように、人工音声が『レディ』と無機的な声を発する。
刀は水平に寝かせ、構えは抜き胴。
迷いを払った刀の刀速は、刃の冴え以外の全てを置き去りにして、奔った。後に残るは、胴の半ばで二つに別たれた歪虚CAMの残骸と、透き通るような刀の残響のみ。
「俺の覚悟に、断てぬものなし」
鞘口に刀の切っ先を納め、金丁を以って残響を断つ。
「お帰りなさい、クラマ」
少女はいつもそう言いながら、笑顔と共に飛びつく。本当にその言葉とその笑顔で迎えたかったはずの人を奪った男に。その事実も知らずして。
「ああ。ただいま、レーネ」
そして、男は不器用な笑顔で以って、その言葉を返す。その資格があるはずもないと知りながら。
この時だけだ。男が本当に死にたくなるのは。
この時だけだ。自分が歩く死体などではなく、当たり前に生きている人間なのだと自覚するのは。
きっと少女が何もかもを知った時、彼女から「お帰り」と言われる事も、笑顔を向けられる事もなくなるのだろう。
少女が自分以外の誰かに「お帰り」と笑顔と共に言えるようになった時、少女に全てを打ち明けよう。
その時まで、男はこの日だまりのような地獄へ帰り続ける。
依頼結果
| 依頼成功度 | 大成功 |
|---|
| 面白かった! | 13人 |
|---|
ポイントがありませんので、拍手できません
現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。
あなたの拍手がマスターの活力につながります。
このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!
MVP一覧
重体一覧
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2017/09/13 12:34:39 |
|
 |
作戦相談所 ヒース・R・ウォーカー(ka0145) 人間(リアルブルー)|23才|男性|疾影士(ストライダー) |
最終発言 2017/09/17 22:04:07 |
|






















