ゲスト
(ka0000)
鹿送りの夜
マスター:四月朔日さくら
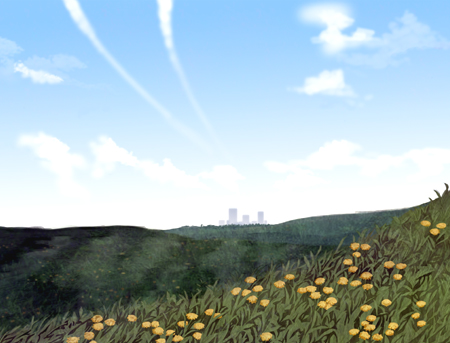
- シナリオ形態
- イベント
- 難易度
- 普通
- オプション
-
- 参加費
 500
500- 参加制限
- -
- 参加人数
- 1~25人
- サポート
- 0~0人
- 報酬
- 普通
- 相談期間
- 5日
- 締切
- 2014/11/14 19:00
- 完成日
- 2014/11/27 06:25
このシナリオは5日間納期が延長されています。
みんなの思い出
思い出設定されたOMC商品がありません。
オープニング
●
天高く馬肥ゆる秋。
本来の意味は異なるらしいが、馬も肥えてしまうくらいもののうまい季節だとつい勘違いしてしまう言葉である。
むろん、その言葉のことを知らずとも、秋は食べ物のおいしい季節。
「そろそろ、あの季節だな」
辺境の一部族――キジャン族の族長たる青年、ユーリィはただそれだけを感じていた。
●
辺境という痩せた土地で生活をしているとはいえ、衣食住に事足りないというわけではない。普段の生活程度なら、十分にまかなえる。
しかし、季節は秋、いやそろそろ初冬。
どんなものでもおいしくなるという季節。
そして、ユーリィたちキジャン族は、この季節になるとご馳走を食べるのが習わしだった。
しかるべき手段でとらえた祖霊たる存在――鹿を一族の恵みとして皆で分け合うというのが、キジャン族独自の祭礼。
基本的に部外者はあまり立ち入らせることのない行事だが、それはあくまで母の代までの慣習。
ユーリィとしては、何かと助けてもらっているハンターに礼をしたいと思っていた。ハンターはリアルブルーの人間も多く、きっとこういう行事は知らないであろう人々も多いのではあるまいか。辺境でも部族ごとの祭礼は異なるので、喜ばれるに違いない――こちらももてなしの心を持って接すれば。
(それに、面白い話を聞かせてもらいたいしな)
ユーリィはそんなことも考える。
ハンターズソサエティにその旨を伝えたのは、それからまもなくであった。
天高く馬肥ゆる秋。
本来の意味は異なるらしいが、馬も肥えてしまうくらいもののうまい季節だとつい勘違いしてしまう言葉である。
むろん、その言葉のことを知らずとも、秋は食べ物のおいしい季節。
「そろそろ、あの季節だな」
辺境の一部族――キジャン族の族長たる青年、ユーリィはただそれだけを感じていた。
●
辺境という痩せた土地で生活をしているとはいえ、衣食住に事足りないというわけではない。普段の生活程度なら、十分にまかなえる。
しかし、季節は秋、いやそろそろ初冬。
どんなものでもおいしくなるという季節。
そして、ユーリィたちキジャン族は、この季節になるとご馳走を食べるのが習わしだった。
しかるべき手段でとらえた祖霊たる存在――鹿を一族の恵みとして皆で分け合うというのが、キジャン族独自の祭礼。
基本的に部外者はあまり立ち入らせることのない行事だが、それはあくまで母の代までの慣習。
ユーリィとしては、何かと助けてもらっているハンターに礼をしたいと思っていた。ハンターはリアルブルーの人間も多く、きっとこういう行事は知らないであろう人々も多いのではあるまいか。辺境でも部族ごとの祭礼は異なるので、喜ばれるに違いない――こちらももてなしの心を持って接すれば。
(それに、面白い話を聞かせてもらいたいしな)
ユーリィはそんなことも考える。
ハンターズソサエティにその旨を伝えたのは、それからまもなくであった。
リプレイ本文
●
キジャン族の住まいは辺境――なのだが。
オフィスで渡された地図を頼りに訪れた場所は、以前彼らのいた場所とはずいぶん離れたところにあった。
以前もキジャン族族長たるユーリィ・キジャンに誘われてキジャン族の集落を訪れたことのあるヴァイス(ka0364)などは、首をふしぎそうにかしげている。と、その困惑を察したのだろう、ユーリィがくすくす笑いながら説明してくれた。
「ああ、キジャンは部族の掟で数ヶ月に一度住まいを変えるんだ」
その説明によると、キジャン族は彼らのまつる祖霊――鹿の逃げ足を移動生活によって体現しているのだという。
と言っても現在の移動生活というのは数ヶ所あるキジャンのベースをローテーションする程度となっているらしいのだが。
それでもそのためには時間もかかるしさまざまな危険も伴う。以前はもっと多かったベースの数も、歪虚の侵攻によって減ってしまったらしい。
「そっか、それなら良かった。夏にお見舞いして以来だから、ちょっと久し振りだね。ユーリィさん、元気だった?」
にっこり笑って頷くのは、金髪碧眼の少年イェルバート(ka1772)、以前ユーリィが病で倒れ助けを求めた際に手を差し伸ばしてくれたハンターのひとりだ。
「ああ、そのせつは随分世話になったけれど、いまはすっかり。いつまでも倒れているわけに行かないからな」
ユーリィも白い歯を見せて笑う。
「でも、こういう習慣の根付いている姿というのはなかなか面白いものですね」
キジャンと同じように辺境の部族出身のUisca Amhran(ka0754)が優しい微笑みを浮かべながら、姉の星輝 Amhran(ka0724)に話しかける。
「うむ。しかも【鹿送り】かや? なんぞ面白そうじゃ、手伝えるかのう?」
キララが無邪気な声でそう言うと、楽しそうに笑った。そうして二人で何やら大きな雉をキジャン族の若者に渡す。
「そしてもてなしにはもてなしを……ワシらの部族祖霊たる雉を捧げようと思うのじゃ♪ 雉は足の早い鳥として戦場を渡り歩く巫女の、我ら一族の象徴であるのじゃ!」
キララがそう言うと、ウィスカも頷いて微笑む。
「そんな、そちらの祖霊をいただくなどというのは、申し訳ない」
驚いた顔を思わず浮かべるキジャン族の若者だが、そんなことは気にしないでいいと言わんばかりに笑顔を浮かべるエルフ姉妹。その脇で、
「うんうん。うちの氏族も似たようなことをしているけれど、余所の儀式に参加する機会はあんまりないからね~」
そう言って瞳をキラキラさせているのはオキクルミ(ka1947)、白いフクロウを祖霊と祀る出身のエルフだ。
(にしても、部族の祭礼――なんだか懐かしい響きだな)
自分の来歴を鑑みて目を細めるのは、黒豹のごときしなやかな体躯のナハティガル・ハーレイ(ka0023)。己の部族が壊滅状態に陥ってからはそんなことをする余裕もなかったのだろう、どこか懐かしそうに見つめている。
「でも辺境からの誘いっつーのはなんか珍しいよな」
デルフィーノ(ka1548)はそんなことを言いながら、興味深そうに周囲をきょろきょろと見回す。確かにパーティのような催し事を開催するのはどちらかというと王国や帝国と言ったところなのだろうが――
「俺はね、結構そういう点については開けた意見を持っててね。ま、時々は怒られるけど……でも閉じた環境ばかりじゃ、このご時世ではやっていけないと思うんだ」
若き族長はそう言って胸を張る。まだ二十歳ほどのユーリィは部族会議でも若い方になるであろうから、どことなくわかるような気がした。
「ウン、そうだね。それにしても、大切な祭礼にお招き頂きアリガトー♪ 折角の機会だし、楽しませて頂くネ」
エルフではあるが複雑な家庭事情を持つアルヴィン = オールドリッチ(ka2378)は、にっこりと笑って、場の賑わいの中、代弁するように挨拶をした。
●
(「獲物を狩り」「恵みに感謝し」「祖霊に捧げ」「皆で分け合う」……ですか)
説明を胸の中で反芻するのは濃い褐色の肌を持つエルフの少女アルメイダ(ka2440)。もっとも、エルフというのは外見年齢にだまされてはいけないのだが。
(鹿送りという儀式、きちんと尊重せねばなりません)
少女は頷いて、土産にともってきていた飲み物をキジャンの民に渡す。むろん、他にも土産を携えて今回の誘いに集まったものは多い。
その土産の多くは、酒や飲み物、食べ物だ。
祭りの宴をもっと楽しく賑やかしくしようというのなら、それらの土産はきっととても良い武器になる。元々生活必需品の一部をキャラバンなどの行商に頼っている辺境部族の民たちにとって、それらの土産がどんなにか嬉しいことか。
「それに、つまるところは収穫祭なのよね? それならこうみえても踊り子なの、あとで披露させてもらおうかしら」
鹿肉にあうであろう白ワインと秋の味覚を使った料理を携えてきた姉御肌のエルフ・リューナ・ヘリオドール(ka2444)がそう言って艶然と微笑んだ。ユーリィもどこか嬉しそうに、
「はは、そいつはありがたいな!」
そう笑ってその言葉をありがたく受け取る。同じように儀式に参加したことに感動を覚えているのはリアルブルー出身の元技術士官ハンター、アルファス(ka3312)。
「神聖な儀式に参加させてもらう、お礼というわけではないけどね」
そう言いながら取り出したのはずいぶんと凝った食品たち。
「これはロートコールとプライゼルベア♪ ロートコールは林檎や酢、赤ワインで葉物野菜を似たもので、酸味が肉の臭みを消して旨味を引き立てます。もう一つのプライゼルベアは酸味の強い果実のジャムで、これを使ったソースで鹿肉を食べるのがリアルブルーでは一般的なんです」
するとそれを聞いたキジャンの女たちが興味深そうに近づいてくる。
「そうそう、肉の臭みを消すのは結構骨でね。むろん、鹿送りの鹿は大事だけれど、普段の生活でも狩猟は欠かせない。鹿を食べるのは基本的にこの機会だけだけれど、良いことを教わったね、今度作り方も調べてみようか」
キジャンの民とて美味しいものを存分に食べたいのは同じだ。この土産物をありがたく受け取ると、キジャンの女たちは早速宴の準備に入っていった。詳しく聞いてみると、宴の本番は鹿を捕まえてからだが、その準備は更に前から行われているらしい。年に一度の大切な祭礼であるからこそ、その準備には時間がかかるというのもうなずける。
「そう言えば、鹿狩りのお手伝いはさすがにできませんが、お料理のお手伝いは可能なのでしょうか」
名前の通り、雪のように銀色の髪と瞳を持つエルフの雪雫(ka3362)が、おずおずと尋ねる。大事な儀式にお邪魔するのに何もしないのも気が引けるので――と言うと、
「それは大歓迎だよ。お嬢ちゃん、こっち来てくれるかい?」
キジャンの女が嬉しそうに雪雫の手を取る。その手のひらの暖かさに、いっしゅん彼女は驚いて。しかしそのあたたかな気持ちも伝わってきて、それがひどく嬉しくて。そしてゆっくりと、彼女はうなずいた。
●
――さて。
その一方で、キジャンの男たちはすでに狩りにでる仕度をしている。
リアルブルーに伝わる太占(ふとまに)と呼ばれるものとよく似た、鹿の骨を用いた占いで、今日は鹿が捕れるだろうということだった。
「ねェ、鹿狩りの手順は不出との事ダケド、奪う命に対スル皆さんの姿勢を見てみたいノデ、もし出来タラ同行したいのだケド……勿論他言はしない、絶対ニ」
そう同行を願い出たのはアルヴィンだ。他にも似た考えのものはいて、ルスティロ・イストワール(ka0252)は目をキラキラと輝かせ、
「捕まえる方法にはすごく……ものすごく興味があるけど! でも、門外不出なんだよね……何か理由があるのっ? 良かったら聞かせてくれないかいっ?」
そんな風にユーリィたちに詰め寄る様、少し怖い。
ジュード・エアハート(ka0410)も、
「キジャン族のことをもっと知りたいんだよね。よく知らない人たちを理解するためにはその人達がなにを大切にしているのかとかをちゃんと知るべきだと思って」
と言ってニッコリと微笑む。辺境に縁の薄かった彼にとって見れば、知的好奇心が騒ぐというものなのだろう。
「ああ。それに、リアルブルーに伝わる、とある民族の祭祀によく似たものがあってな。鹿送りについて、もっと深い理解をしたい……捕獲の様子を見学だけでもすることはできないだろうか」
更に雄弁に言葉を綴るのは、久延毘 大二郎(ka1771)。リアルブルーでフォークロアと呼ばれる考古学・民俗学を学んでおり、もともと覚醒者になった理由も、このクリムゾンウェストという世界やハンターという存在に興味をいだき、知識を得るためだ。
「へぇ……リアルブルーにも似た祭祀があるのか?」
ユーリィが驚いた顔で大二郎の言葉を聞く。
「ああ。リアルブルーの祭祀については後で説明するが……何かしらの共通性があるかもしれない。祭祀に参加はしないつもりだ、いいだろうか」
また、
「うちも、働かざるもの食うべからず、がパパの教えなの。あなたはハンターのお世話になっているのかもしれないけれど、わたしはまだ、あなたのためには何も働いていないわ。ただ食いだなんて、わたしの矜持が許さないの。これでも弓は得意だし、手伝わせてもらえたら嬉しいわ」
イシャラナ・コルビュジエ(ka1846)も、持っていた弓の弦をぴんと軽く弾く。と、近くにいたナハティガルが軽く彼女をにらんだ。
「余所者が首を突っ込むのは、あまり感心できねぇな……?」
その言葉を聞いていっしゅん誰もがひるむ。部族の風習、しかも本来他の部族には秘すべきものであるはずのものに首を突っ込むのは、確かに褒められた行為ではないかも知れない。とはいえ言われてかちんときたのだろう、イシャラナはきりっとにらみ返した。
「あんた、あたしの生き様に口を挟むつもり?」
気の強い彼女にしてみれば、矜持を傷つけられたと感じたのだろう。ナハティガルもさすがに強く言いすぎたかとそっと目をそらした。
彼女らに限らず、ほかにも何人かのそんな申し出を聞いて、ユーリィは腕組みをする。そしておもむろに口を開いた。
「うーん。本来部族の男だけが参加できるのが鹿送りの狩猟だからな。申し訳ないんだが、女性については連れて行くのは難しいな……これは習わしだから、本当にごめんな」
「いいえ、もし可能であるならということでしたし」
自分の部族でもそんなことがあれば悶着が起きるに違いない――そう考えたのだろう、ウィスカは首を横に振る。
「じゃあ、済まないが……飯作りもまだまだ必要だし、もし出来たらそちらを手伝ってくれないか? 子どもたちと遊んでいたってもちろん構わないし」
若き族長は申し訳無さそうにそう言うと、狩りに参加するための仲間たちを伴って出発した。
●
鹿を狩るときは、北の方角へむかって三度頭を垂れ、矢を射る。
用いる矢は、どれも真っ白い矢羽。
その矢羽が血に染まる前に倒れるように、気をつけて。
斃れた鹿に近づくときは、おろしたての、特別な紋様のはいった靴を履いて近づき。
血抜きをするときは、三度その頭をなでてから、頭は北向きで。
角を落とし、そして皮はその場で剥がずに連れて帰る。
連れて帰る時も感謝の気持ちを忘れずに、生きていた時の姿をなるべく保つようにして。
――これが、キジャン族に伝わる、鹿送りの決まりだ。
結局、狩りに参加したものはいなかった。あくまで誰もが見学のみ。まあ、神聖な儀式であるから、無理に介入してしまうのはまずかろう。
「なるほど、難しくはないが……どれも『決まり』なのだな」
興味本位と言うよりも、学究の徒として、大二郎は興味深そうにノートにそれらを記述していく。リアルブルーでは失われかけているアミニズムが、この辺境の地では強く息づいているのだから、興奮するのも無理からぬことだろう。
「昔はこれらの決まりを破った時には疫病が流行ると言われていたんだ」
ユーリィが解説をする。
「昔、この部族は疫病で壊滅寸前に陥ったことがあるということでね。それを助けてくれたのが、祖霊たる鹿――と言われているんだ。だから、歯科は逃げる獣であると同時に、俺たちにとってはいのちを助けてくれる獣でもある」
だからこそ祖霊なのだと、ユーリィは自慢気な調子で言う。
「リアルブルーの祭祀はイオマンテと言って、ヒグマを同じように定められた方法で殺す。別名として熊送りと呼ばれているあたりも似ているな。違いはあれど、似ている」
大二郎の言葉にその場の若者たちが誰しもふぅむとうなった。
遠い世界ではあっても、人の考える事、営み――そんなものはきっと似ているのだ。
「サ、戻ろうカ! 皆待っているヨ♪」
アルヴィンは満足気に、手を動かした。
●
(ただでごはん、ただでごはん!!)
そううずうずとしているのはエヴァ・A・カルブンクルス(ka0029)、言葉を発することはできないが目が口ほどにモノを言う育ち盛りの少女である。
「エヴァ、随分ごきげんそうねぇ♪」
そんなエヴァに声をかけたのはルキハ・ラスティネイル(ka2633)、いわゆる女性言葉を操る男性である。
『当然よ』
エヴァは手元でそう書いて、またも嬉しそうににこーっと笑う。
視線の先にいるのは銀髪碧眼の青年、陽炎(ka0142)だ。彼は料理を手伝うと宣言していたため、二人は楽しみで楽しみで仕方がない。……ただ難点を言えば、陽炎の生活スキルが壊滅的だという事実だろうか。
(早く鹿が届かないかなぁ)
エヴァだけではない、多くのハンター、そしてキジャンの民がそう思っている。と、遠くから聞こえる勝鬨の声。
「あ、帰ってきたんですね!」
「うむ、凱旋じゃな!」
ウィスカやキララがぱっと出迎えるためにそちらに向かう。無論、他の面々も同様だ。
「わぁ、今年の鹿は立派だね!」
子どもたちが嬉しそうに声を上げる。
「今年はハンターさんにも手伝ってもらって、いつも以上のごちそうを用意するよ!」
キジャンの女がそう言って胸をどんと叩くと、周囲のハンターたちも明るい声で笑った。
さばく手伝いをしたいとオキクルミの申し出もあったが、これはこれで儀式の一環。見てもらう方が、いろんな意味で安心だというユーリィの言葉をオキクルミも尊重したのだった。
鹿をさばくのは女達の仕事だ。
白いリボンを柄に巻きつけた包丁を使い、丁寧にさばいていく。
周囲では臭い消しも兼ねた香を焚く。
その香には気分を沸き立たせる、むろん無害の香りがほんのりと混じっていて。
切りわけた鹿は一度白い布で包み清めてから、調理の場へと移される。
そう、これも――『決まり』。
ヴァイスはその様子をつぶさに見守っている。部族の中でも「やって良いこと」と「いけないこと」があるのだろうから、それを注意深く確認して。
「これも由来があるのかな? 気になるなぁ――」
そんなことを興味津々に尋ねているのは御伽噺を書くことを趣味としているルスティロだ。ありったけの炭酸飲料を持ち込んでいた彼はそれらを子どもたちに振る舞い、自作の御伽噺も話してすっかり子どもたちの人気者だ。
と、そこで彼は不思議な違和感に気づいた。
「……あれ? 君、もしかして女の子?」
それは少年の姿をしているが、たしかに女の子であった。よくよく見れば、少年は皆少女であり、少女は皆少年――異性装をしているのである。
「ああ、これはうちら部族の伝統でね。初めての人は驚くかもしれないが、なかなか気づかないらしくて案外気づかれないままのことが多いんだけどね。子どもが健康に育つように、成人前は本来の性別と違う格好をさせるっていう習わしなのさ」
子どもたちもごくごく当然だというように、頷き合う。
「そうか、それはきっと素敵なことだね♪」
ルスティロはそう笑い、そしてこれもまたひとつ噺の材料ができたとそっと思った。
●
「そういえばこちらではこんなものは珍しいのではないですか?」
上泉 澪(ka0518)が差し出したのは、うなぎの蒲焼。東の民の末裔と言われる彼女だが、その真偽の程は定かではない。もっとも、そのうなぎの蒲焼きと言うのはリアルブルーの東方の一地域で好んで食されるものでもあるのだが――
「へぇ。こりゃぁ珍しい魚料理だねぇ。でもいい香りだ」
クンクンとにおいをかげば、香ばしくてほんのりと甘いたれの香り。キジャンの民も気に入ったようだ。
「私も辺境出身ではありますが、他の部族の祭礼に関われるというのも珍しくて。まあ、私の場合は部族との関わりもあまりなかったので、余計なのかもしれませんが」
澪がそう言うと、若い男たちはそんなことはないと言わんばかりに笑顔を向ける。
「それなら縁を作ればいいんだと思うけどな」
難しいことかもしれないが、案ずるより生むが易しという言葉もある。そう言われてはいそうですかというわけにもいかないが、キジャンの人々は気さくに彼女の行為を受け入れてくれた。それを彼女も返せばいいのだと、彼らはそういう。
「……そんなものですか」
「ああ、そんなものだ」
言われた澪の顔は、ほんの少し口元に笑みを浮かべていた。
エルフ姉妹が手土産として持ってきた雉は、まるまるとした大物。これを先ほどの鹿肉や野菜といっしょに炒められることとなった。
「こんなに立派な雉をもらっても良いのかねえ。こちらが申し訳ないくらいだよ」
四十路ほどのキジャンの女が、ありがたくももったいないという顔つきでしみじみ雉を見つめる。
「いや、手ぶらで招待に応じるわけにもいかんだろう」
やはり酒を持ってきていたナハティガルが、そう言ってやる。自分たちの行為はキジャン族の祖霊に対しての、供物でもあるのだと言いながら。
ところで先ほどから百面相をしているのはエヴァである。
陽炎が腕によりをかけて料理を振る舞おう――とするのは良いのだが、なにしろ日常生活スキルをまるっと欠如させている陽炎、
「あ、あれ……ステーキを作るはずだったんだけど……?」
どこからどう見ても、それは謎の蠢くナマコのような物体。
食いしん坊なエヴァも、その様子を思わず何度も目をこすって確認する。あまりにも、あまりにも豪快な化学変化に、ルキハも喉を鳴らす。しかしエヴァはさらさらと筆談する。
『でも食べればきっと美味しいよね』
……エヴァはあくまでもエヴァだったようだ。 貧乏暮らしがそうさせたのか、ただの食いしん坊なだけなのか、判別に困る部分もあるけれど。
その一方でルキハはバゲットを軽くあぶり、その上にチーズなどをのせたおつまみを作っている。
「イイ男の手料理を食べないわけにはいかないわねッ」
肉にはワインという発想は皆同じだし、確かにちょっとしたつまみがあった方が良いだろう。いかにも美味しそうなできばえに、周りの仲間たちも興味津々。更に、
「お酒が苦手なら、果実のジュースはどうかしら?」
これなら未成年でも十分に飲めるはずだからと取り出したジュースも気が利いていた。
「そうそう、こうやってワインや麦酒で煮込むと肉はやわらかくなるんだよ」
言いながら煮込みものをこしらえているのは薬草師でもある母を持ったユリアン(ka1664)、母からの知恵の賜物なのだろう煮物はとても良い香りがする。中には肉の他、馬鈴薯やタマネギ、ローレルなども入っているのだとか。
「ねえ、味加減はどんなものだろ?」
近くにいたリュー・グランフェスト(ka2419)に味見を頼んでみると、
「ん、これはうまいな」
麦酒のおかげでやわらかくなった肉が口の中でとろけていくような感じで、それがまたひどく旨味もひき出している。
料理の方もずいぶん万端整ったようだ。
――さあ、宴の時間だ。
●
「さあ今日は鹿送りだ。みんなどんどん食べてくれ! むろんお客人もご一緒にだ!」
ユーリィの音頭で宴は始まる。素朴な味付けの煮物、焼き物はもちろんのことながら、ハンターたちの土産物もどっさりと、ここにいる部族の人間だけでは食べきれないほどに。
「いただきます」
そんな、小さな祈りの声があちこちから聞こえる。
命を頂くという行為に最大限の感謝を示す言葉だ。その祈りが届かないわけもない。
雪雫もまた、料理の手伝いをして少し疲れてはいるものの、手を合わせてしっかりと祈りを込めていた。
「内容は違えどこの雰囲気……懐かしいな」
わずかに目を細めているのはエアルドフリス(ka1856)、かつて滅ぼされた部族の末裔だ。ユーリィの側にやってきて、思っていたことを問う。
「外部者を招き入れるというのは部族としてもずいぶん挑戦的な試みと思うのだが、これはどんな意図があるのかお教え願えると嬉しいのですが」
するとユーリィはクスッと笑って頷いた。
「ああ、古い考えの部族の者にはそういうことに頭の固い人も確かに多いだろう。だが俺はハンターという存在が歪虚に脅かされているこの世界において、重要な存在であることを認識している。それに俺個人が、幼い頃にハンターにあこがれていてね。たまたま幼い頃に出会ったハンターが世界の広さを教えてくれた。だから、もっと世界を知るために、積極的な行動をしても良いんじゃないかと、……まあこれはあくまでも俺個人の意見だけどな」
そこまで言って口に酒を含む。
「少し饒舌になりすぎてしまったかも知れないが、まあ部族会議はもちろんながら一枚岩じゃない。俺はスコールの族長とも比較的懇意だからな、彼女の手助けになれるよう、少しでも多くの知識を得たいと思っているのさ」
「……なるほど、立ち入ったことをお聞きしてすまない。非礼のわびに一曲披露して良いだろうか」
エアルドフリスはそう言って、朗々と歌い出した。
今はなき彼の部族に伝わる、雨と空の巡りに感謝する歌だ。誰もがその歌声に耳を澄ます。
やがてぱちぱちと拍手の音がして、彼はそっとユーリィの前を去った。
「……俺は、やっぱり、此処の人間なんだよなあ……」
そう、親友のジュードに漏らす。故郷を失っても、根付くものはやはりこの大地にある――しみじみと感じたようだ。
「そっか」
ジュードもそれだけ応じて、そして静かに祭りを眺める。
「ルールーの歌、良かったヨ♪ 大切な歌、すごく綺麗ダッタネ!」
にっこり笑ってアルヴィンが酒をつぎ、そして小さく乾杯した。
中央にあるかがり火付近には祈りを捧げるための台(うてな)があり、そこには命の源といえる心の臓が、頭とともに祀られている。
「本当は食べたかったけど、これも儀式なんだもんね」
オキクルミが苦笑しながらその心臓を見つめていた。
「うちにも似たような風習があるからね、でもやっぱり少し違うんだなぁ……」
そう呟くオキクルミは、しかし儀式の大切さを理解している。相手の思いや考えを尊重するものとして、静かにそれを見つめていた。
続いて中央に立ったのはリューナ。
「よ、待ってましたっ!」
酒が回りつつあるヴァイスが大きな声でもてはやす。
しかしそんな声も気にせず彼女は静かに鈴を振りかざし、そして静けさの中に激しさを込めて、舞を披露する。来年も、キジャンの民に実りがあるようにと、そう祈りを込めて。
踊りが最高潮に達しやがて彼女の鈴の音がおさまると、ふわっと拍手が巻き起こった。更にそこに、ルキハがそっと近づいてきて。
「素敵だったわよぉ♪ 芸能の女神もかくやという感じねぇ~♪」
お疲れ様と言わんばかりに指しだした手の指を小さく鳴らすと、ぽんと現れる一輪の薔薇。それを手渡せば、
「あら、お花? ありがとう、お花を贈られて喜ばない女なんていないものね♪」
そう言ってくすくすと微笑む。ともに喜びを分かち合うために、酒を用意しながら。
その脇で小柄な身体をいっぱい使って食べまくっているのはドワーフのアルマ(ka3330)、こう見えても立派な大人だ。
「アルマはこれでも大人ゆえ、酒もかっくらうのじゃよ」
土産物にともってきたチーズと酒をどんどん腹に収めていく。ただその幼い見た目と酔っ払うと何をしでかすかわからないので、その辺にしておけと周囲から止められてしまうのだが。
その一方で下戸は下戸同士酒を飲まずに炭酸飲料で喉を潤している。
それでもどこか楽しくなるのは、気分の高揚している証だ。
『ところでこの料理は何?』
エヴァが興味深そうに見つめているのは、ミオレスカ(ka3496)が作った鍋に入っている料理だ。
「これは、南蛮漬け、という、リアルブルー由来の料理なのです。神のもたらした食材と、リアルブルーの技術の、崇高なる融合です」
三杯酢に浸かった野菜や揚げ肉はいかにも美味しそう。それを口に運んだのはアルメイダ、興味を持っていたらしい。
「……うん、酒に合うね」
そう言って小さく頷く。そして、そっと荷物から竪琴を取り出し、歌を吟じ始めた。エルフの音楽は耳に心地よく、宴を包んでいく。
「なかなかエルフの音楽を聴くチャンスはないからな。ありがとう、嬉しいな」
ユーリィも満足げに笑った。
「じゃあ次は俺の番かな」
リューも手元のリュートを引き寄せて、陽気な音楽を奏で出す。
この日は宴と言うこともあって基本的に無礼講、そうやってさまざまな文化を楽しめるのもユーリィの決断のおかげである。
「今年の鹿送りはどうなるかと思ったけど、ハンターさんたちのおかげでいつも以上に楽しませてもらっているよ」
キジャンの若者も嬉しそうに声を弾ませた。
リュートが終わればウィスカが歌う。歌にあわせてキララが舞い踊る。歌を途中で止めてしまったのは、
「祖霊がこの歌の続きを聞きたがって、この世界に降りてくると考えられているから――」
だそうだ。部族というのはそれぞれによって信仰のありようも違うのだと言うことを思わせてくれる一幕であった。
――ちなみに陽炎の作ったステーキ改めナマコもどき、本人が意を決して食べたところ案外いけたらしい。まあ、酒の魔術かも知れないが。
「そう言えば土産話と言えば……つい最近は帝国でもいろいろ騒ぎあったけど、まあどうにかこうにか解決した形だね」
僕も防衛には参加したんだ、とイェルバート。他にも『剣機』と呼ばれるその騒ぎに参加したものたちがあれこれと話をしてくれた。
「辺境もずいぶん大変だけど、どこもにたようなもんなんだなあ」
そんな感想を述べるユーリィ。帝国に帰順するつもりはなさそうだが、その住人をけなしたりするつもりはなく、みんな生きているのだからと言うのが素直な感想らしい。
そんな彼だからこそ、若くして族長になったあともやってこれているのだろうが。
「キジャン族の話も聞かせてくれないか。興味深いものもきっとあるからさ」
そうにやりと笑うのはデルフィーノ、リアルブルーを好むエルフ。ギターも持ってきては、それをそっとかき鳴らす。
「礼と言っちゃなんだが、ここらで一曲。ギターの腕はこれでもあるから、キジャンの勇者のために弾きたいねぇ……魂から鼓舞するような、激しいやつを」
まだまだ、宴は長くなりそうだ。
(辺境はいろんな祭りもあって、描き甲斐があるわね……狩りの様子も書いてみたかったなぁ)
エヴァはスケッチブックに色鉛筆を走らせながらそう思う。その表情は幸せそうな笑顔であふれていた。
●
鹿送りの祭りは終わった。
しかしこれも一つのきっかけに過ぎない。
次に彼らと会うとき、互いに笑顔でいられるように――それはきっと、すべてのものの願いなのだろう。
鹿は、きっとそれをかなえてくれる――ユーリィはそう信じて、ハンターたちを見送った。
キジャン族の住まいは辺境――なのだが。
オフィスで渡された地図を頼りに訪れた場所は、以前彼らのいた場所とはずいぶん離れたところにあった。
以前もキジャン族族長たるユーリィ・キジャンに誘われてキジャン族の集落を訪れたことのあるヴァイス(ka0364)などは、首をふしぎそうにかしげている。と、その困惑を察したのだろう、ユーリィがくすくす笑いながら説明してくれた。
「ああ、キジャンは部族の掟で数ヶ月に一度住まいを変えるんだ」
その説明によると、キジャン族は彼らのまつる祖霊――鹿の逃げ足を移動生活によって体現しているのだという。
と言っても現在の移動生活というのは数ヶ所あるキジャンのベースをローテーションする程度となっているらしいのだが。
それでもそのためには時間もかかるしさまざまな危険も伴う。以前はもっと多かったベースの数も、歪虚の侵攻によって減ってしまったらしい。
「そっか、それなら良かった。夏にお見舞いして以来だから、ちょっと久し振りだね。ユーリィさん、元気だった?」
にっこり笑って頷くのは、金髪碧眼の少年イェルバート(ka1772)、以前ユーリィが病で倒れ助けを求めた際に手を差し伸ばしてくれたハンターのひとりだ。
「ああ、そのせつは随分世話になったけれど、いまはすっかり。いつまでも倒れているわけに行かないからな」
ユーリィも白い歯を見せて笑う。
「でも、こういう習慣の根付いている姿というのはなかなか面白いものですね」
キジャンと同じように辺境の部族出身のUisca Amhran(ka0754)が優しい微笑みを浮かべながら、姉の星輝 Amhran(ka0724)に話しかける。
「うむ。しかも【鹿送り】かや? なんぞ面白そうじゃ、手伝えるかのう?」
キララが無邪気な声でそう言うと、楽しそうに笑った。そうして二人で何やら大きな雉をキジャン族の若者に渡す。
「そしてもてなしにはもてなしを……ワシらの部族祖霊たる雉を捧げようと思うのじゃ♪ 雉は足の早い鳥として戦場を渡り歩く巫女の、我ら一族の象徴であるのじゃ!」
キララがそう言うと、ウィスカも頷いて微笑む。
「そんな、そちらの祖霊をいただくなどというのは、申し訳ない」
驚いた顔を思わず浮かべるキジャン族の若者だが、そんなことは気にしないでいいと言わんばかりに笑顔を浮かべるエルフ姉妹。その脇で、
「うんうん。うちの氏族も似たようなことをしているけれど、余所の儀式に参加する機会はあんまりないからね~」
そう言って瞳をキラキラさせているのはオキクルミ(ka1947)、白いフクロウを祖霊と祀る出身のエルフだ。
(にしても、部族の祭礼――なんだか懐かしい響きだな)
自分の来歴を鑑みて目を細めるのは、黒豹のごときしなやかな体躯のナハティガル・ハーレイ(ka0023)。己の部族が壊滅状態に陥ってからはそんなことをする余裕もなかったのだろう、どこか懐かしそうに見つめている。
「でも辺境からの誘いっつーのはなんか珍しいよな」
デルフィーノ(ka1548)はそんなことを言いながら、興味深そうに周囲をきょろきょろと見回す。確かにパーティのような催し事を開催するのはどちらかというと王国や帝国と言ったところなのだろうが――
「俺はね、結構そういう点については開けた意見を持っててね。ま、時々は怒られるけど……でも閉じた環境ばかりじゃ、このご時世ではやっていけないと思うんだ」
若き族長はそう言って胸を張る。まだ二十歳ほどのユーリィは部族会議でも若い方になるであろうから、どことなくわかるような気がした。
「ウン、そうだね。それにしても、大切な祭礼にお招き頂きアリガトー♪ 折角の機会だし、楽しませて頂くネ」
エルフではあるが複雑な家庭事情を持つアルヴィン = オールドリッチ(ka2378)は、にっこりと笑って、場の賑わいの中、代弁するように挨拶をした。
●
(「獲物を狩り」「恵みに感謝し」「祖霊に捧げ」「皆で分け合う」……ですか)
説明を胸の中で反芻するのは濃い褐色の肌を持つエルフの少女アルメイダ(ka2440)。もっとも、エルフというのは外見年齢にだまされてはいけないのだが。
(鹿送りという儀式、きちんと尊重せねばなりません)
少女は頷いて、土産にともってきていた飲み物をキジャンの民に渡す。むろん、他にも土産を携えて今回の誘いに集まったものは多い。
その土産の多くは、酒や飲み物、食べ物だ。
祭りの宴をもっと楽しく賑やかしくしようというのなら、それらの土産はきっととても良い武器になる。元々生活必需品の一部をキャラバンなどの行商に頼っている辺境部族の民たちにとって、それらの土産がどんなにか嬉しいことか。
「それに、つまるところは収穫祭なのよね? それならこうみえても踊り子なの、あとで披露させてもらおうかしら」
鹿肉にあうであろう白ワインと秋の味覚を使った料理を携えてきた姉御肌のエルフ・リューナ・ヘリオドール(ka2444)がそう言って艶然と微笑んだ。ユーリィもどこか嬉しそうに、
「はは、そいつはありがたいな!」
そう笑ってその言葉をありがたく受け取る。同じように儀式に参加したことに感動を覚えているのはリアルブルー出身の元技術士官ハンター、アルファス(ka3312)。
「神聖な儀式に参加させてもらう、お礼というわけではないけどね」
そう言いながら取り出したのはずいぶんと凝った食品たち。
「これはロートコールとプライゼルベア♪ ロートコールは林檎や酢、赤ワインで葉物野菜を似たもので、酸味が肉の臭みを消して旨味を引き立てます。もう一つのプライゼルベアは酸味の強い果実のジャムで、これを使ったソースで鹿肉を食べるのがリアルブルーでは一般的なんです」
するとそれを聞いたキジャンの女たちが興味深そうに近づいてくる。
「そうそう、肉の臭みを消すのは結構骨でね。むろん、鹿送りの鹿は大事だけれど、普段の生活でも狩猟は欠かせない。鹿を食べるのは基本的にこの機会だけだけれど、良いことを教わったね、今度作り方も調べてみようか」
キジャンの民とて美味しいものを存分に食べたいのは同じだ。この土産物をありがたく受け取ると、キジャンの女たちは早速宴の準備に入っていった。詳しく聞いてみると、宴の本番は鹿を捕まえてからだが、その準備は更に前から行われているらしい。年に一度の大切な祭礼であるからこそ、その準備には時間がかかるというのもうなずける。
「そう言えば、鹿狩りのお手伝いはさすがにできませんが、お料理のお手伝いは可能なのでしょうか」
名前の通り、雪のように銀色の髪と瞳を持つエルフの雪雫(ka3362)が、おずおずと尋ねる。大事な儀式にお邪魔するのに何もしないのも気が引けるので――と言うと、
「それは大歓迎だよ。お嬢ちゃん、こっち来てくれるかい?」
キジャンの女が嬉しそうに雪雫の手を取る。その手のひらの暖かさに、いっしゅん彼女は驚いて。しかしそのあたたかな気持ちも伝わってきて、それがひどく嬉しくて。そしてゆっくりと、彼女はうなずいた。
●
――さて。
その一方で、キジャンの男たちはすでに狩りにでる仕度をしている。
リアルブルーに伝わる太占(ふとまに)と呼ばれるものとよく似た、鹿の骨を用いた占いで、今日は鹿が捕れるだろうということだった。
「ねェ、鹿狩りの手順は不出との事ダケド、奪う命に対スル皆さんの姿勢を見てみたいノデ、もし出来タラ同行したいのだケド……勿論他言はしない、絶対ニ」
そう同行を願い出たのはアルヴィンだ。他にも似た考えのものはいて、ルスティロ・イストワール(ka0252)は目をキラキラと輝かせ、
「捕まえる方法にはすごく……ものすごく興味があるけど! でも、門外不出なんだよね……何か理由があるのっ? 良かったら聞かせてくれないかいっ?」
そんな風にユーリィたちに詰め寄る様、少し怖い。
ジュード・エアハート(ka0410)も、
「キジャン族のことをもっと知りたいんだよね。よく知らない人たちを理解するためにはその人達がなにを大切にしているのかとかをちゃんと知るべきだと思って」
と言ってニッコリと微笑む。辺境に縁の薄かった彼にとって見れば、知的好奇心が騒ぐというものなのだろう。
「ああ。それに、リアルブルーに伝わる、とある民族の祭祀によく似たものがあってな。鹿送りについて、もっと深い理解をしたい……捕獲の様子を見学だけでもすることはできないだろうか」
更に雄弁に言葉を綴るのは、久延毘 大二郎(ka1771)。リアルブルーでフォークロアと呼ばれる考古学・民俗学を学んでおり、もともと覚醒者になった理由も、このクリムゾンウェストという世界やハンターという存在に興味をいだき、知識を得るためだ。
「へぇ……リアルブルーにも似た祭祀があるのか?」
ユーリィが驚いた顔で大二郎の言葉を聞く。
「ああ。リアルブルーの祭祀については後で説明するが……何かしらの共通性があるかもしれない。祭祀に参加はしないつもりだ、いいだろうか」
また、
「うちも、働かざるもの食うべからず、がパパの教えなの。あなたはハンターのお世話になっているのかもしれないけれど、わたしはまだ、あなたのためには何も働いていないわ。ただ食いだなんて、わたしの矜持が許さないの。これでも弓は得意だし、手伝わせてもらえたら嬉しいわ」
イシャラナ・コルビュジエ(ka1846)も、持っていた弓の弦をぴんと軽く弾く。と、近くにいたナハティガルが軽く彼女をにらんだ。
「余所者が首を突っ込むのは、あまり感心できねぇな……?」
その言葉を聞いていっしゅん誰もがひるむ。部族の風習、しかも本来他の部族には秘すべきものであるはずのものに首を突っ込むのは、確かに褒められた行為ではないかも知れない。とはいえ言われてかちんときたのだろう、イシャラナはきりっとにらみ返した。
「あんた、あたしの生き様に口を挟むつもり?」
気の強い彼女にしてみれば、矜持を傷つけられたと感じたのだろう。ナハティガルもさすがに強く言いすぎたかとそっと目をそらした。
彼女らに限らず、ほかにも何人かのそんな申し出を聞いて、ユーリィは腕組みをする。そしておもむろに口を開いた。
「うーん。本来部族の男だけが参加できるのが鹿送りの狩猟だからな。申し訳ないんだが、女性については連れて行くのは難しいな……これは習わしだから、本当にごめんな」
「いいえ、もし可能であるならということでしたし」
自分の部族でもそんなことがあれば悶着が起きるに違いない――そう考えたのだろう、ウィスカは首を横に振る。
「じゃあ、済まないが……飯作りもまだまだ必要だし、もし出来たらそちらを手伝ってくれないか? 子どもたちと遊んでいたってもちろん構わないし」
若き族長は申し訳無さそうにそう言うと、狩りに参加するための仲間たちを伴って出発した。
●
鹿を狩るときは、北の方角へむかって三度頭を垂れ、矢を射る。
用いる矢は、どれも真っ白い矢羽。
その矢羽が血に染まる前に倒れるように、気をつけて。
斃れた鹿に近づくときは、おろしたての、特別な紋様のはいった靴を履いて近づき。
血抜きをするときは、三度その頭をなでてから、頭は北向きで。
角を落とし、そして皮はその場で剥がずに連れて帰る。
連れて帰る時も感謝の気持ちを忘れずに、生きていた時の姿をなるべく保つようにして。
――これが、キジャン族に伝わる、鹿送りの決まりだ。
結局、狩りに参加したものはいなかった。あくまで誰もが見学のみ。まあ、神聖な儀式であるから、無理に介入してしまうのはまずかろう。
「なるほど、難しくはないが……どれも『決まり』なのだな」
興味本位と言うよりも、学究の徒として、大二郎は興味深そうにノートにそれらを記述していく。リアルブルーでは失われかけているアミニズムが、この辺境の地では強く息づいているのだから、興奮するのも無理からぬことだろう。
「昔はこれらの決まりを破った時には疫病が流行ると言われていたんだ」
ユーリィが解説をする。
「昔、この部族は疫病で壊滅寸前に陥ったことがあるということでね。それを助けてくれたのが、祖霊たる鹿――と言われているんだ。だから、歯科は逃げる獣であると同時に、俺たちにとってはいのちを助けてくれる獣でもある」
だからこそ祖霊なのだと、ユーリィは自慢気な調子で言う。
「リアルブルーの祭祀はイオマンテと言って、ヒグマを同じように定められた方法で殺す。別名として熊送りと呼ばれているあたりも似ているな。違いはあれど、似ている」
大二郎の言葉にその場の若者たちが誰しもふぅむとうなった。
遠い世界ではあっても、人の考える事、営み――そんなものはきっと似ているのだ。
「サ、戻ろうカ! 皆待っているヨ♪」
アルヴィンは満足気に、手を動かした。
●
(ただでごはん、ただでごはん!!)
そううずうずとしているのはエヴァ・A・カルブンクルス(ka0029)、言葉を発することはできないが目が口ほどにモノを言う育ち盛りの少女である。
「エヴァ、随分ごきげんそうねぇ♪」
そんなエヴァに声をかけたのはルキハ・ラスティネイル(ka2633)、いわゆる女性言葉を操る男性である。
『当然よ』
エヴァは手元でそう書いて、またも嬉しそうににこーっと笑う。
視線の先にいるのは銀髪碧眼の青年、陽炎(ka0142)だ。彼は料理を手伝うと宣言していたため、二人は楽しみで楽しみで仕方がない。……ただ難点を言えば、陽炎の生活スキルが壊滅的だという事実だろうか。
(早く鹿が届かないかなぁ)
エヴァだけではない、多くのハンター、そしてキジャンの民がそう思っている。と、遠くから聞こえる勝鬨の声。
「あ、帰ってきたんですね!」
「うむ、凱旋じゃな!」
ウィスカやキララがぱっと出迎えるためにそちらに向かう。無論、他の面々も同様だ。
「わぁ、今年の鹿は立派だね!」
子どもたちが嬉しそうに声を上げる。
「今年はハンターさんにも手伝ってもらって、いつも以上のごちそうを用意するよ!」
キジャンの女がそう言って胸をどんと叩くと、周囲のハンターたちも明るい声で笑った。
さばく手伝いをしたいとオキクルミの申し出もあったが、これはこれで儀式の一環。見てもらう方が、いろんな意味で安心だというユーリィの言葉をオキクルミも尊重したのだった。
鹿をさばくのは女達の仕事だ。
白いリボンを柄に巻きつけた包丁を使い、丁寧にさばいていく。
周囲では臭い消しも兼ねた香を焚く。
その香には気分を沸き立たせる、むろん無害の香りがほんのりと混じっていて。
切りわけた鹿は一度白い布で包み清めてから、調理の場へと移される。
そう、これも――『決まり』。
ヴァイスはその様子をつぶさに見守っている。部族の中でも「やって良いこと」と「いけないこと」があるのだろうから、それを注意深く確認して。
「これも由来があるのかな? 気になるなぁ――」
そんなことを興味津々に尋ねているのは御伽噺を書くことを趣味としているルスティロだ。ありったけの炭酸飲料を持ち込んでいた彼はそれらを子どもたちに振る舞い、自作の御伽噺も話してすっかり子どもたちの人気者だ。
と、そこで彼は不思議な違和感に気づいた。
「……あれ? 君、もしかして女の子?」
それは少年の姿をしているが、たしかに女の子であった。よくよく見れば、少年は皆少女であり、少女は皆少年――異性装をしているのである。
「ああ、これはうちら部族の伝統でね。初めての人は驚くかもしれないが、なかなか気づかないらしくて案外気づかれないままのことが多いんだけどね。子どもが健康に育つように、成人前は本来の性別と違う格好をさせるっていう習わしなのさ」
子どもたちもごくごく当然だというように、頷き合う。
「そうか、それはきっと素敵なことだね♪」
ルスティロはそう笑い、そしてこれもまたひとつ噺の材料ができたとそっと思った。
●
「そういえばこちらではこんなものは珍しいのではないですか?」
上泉 澪(ka0518)が差し出したのは、うなぎの蒲焼。東の民の末裔と言われる彼女だが、その真偽の程は定かではない。もっとも、そのうなぎの蒲焼きと言うのはリアルブルーの東方の一地域で好んで食されるものでもあるのだが――
「へぇ。こりゃぁ珍しい魚料理だねぇ。でもいい香りだ」
クンクンとにおいをかげば、香ばしくてほんのりと甘いたれの香り。キジャンの民も気に入ったようだ。
「私も辺境出身ではありますが、他の部族の祭礼に関われるというのも珍しくて。まあ、私の場合は部族との関わりもあまりなかったので、余計なのかもしれませんが」
澪がそう言うと、若い男たちはそんなことはないと言わんばかりに笑顔を向ける。
「それなら縁を作ればいいんだと思うけどな」
難しいことかもしれないが、案ずるより生むが易しという言葉もある。そう言われてはいそうですかというわけにもいかないが、キジャンの人々は気さくに彼女の行為を受け入れてくれた。それを彼女も返せばいいのだと、彼らはそういう。
「……そんなものですか」
「ああ、そんなものだ」
言われた澪の顔は、ほんの少し口元に笑みを浮かべていた。
エルフ姉妹が手土産として持ってきた雉は、まるまるとした大物。これを先ほどの鹿肉や野菜といっしょに炒められることとなった。
「こんなに立派な雉をもらっても良いのかねえ。こちらが申し訳ないくらいだよ」
四十路ほどのキジャンの女が、ありがたくももったいないという顔つきでしみじみ雉を見つめる。
「いや、手ぶらで招待に応じるわけにもいかんだろう」
やはり酒を持ってきていたナハティガルが、そう言ってやる。自分たちの行為はキジャン族の祖霊に対しての、供物でもあるのだと言いながら。
ところで先ほどから百面相をしているのはエヴァである。
陽炎が腕によりをかけて料理を振る舞おう――とするのは良いのだが、なにしろ日常生活スキルをまるっと欠如させている陽炎、
「あ、あれ……ステーキを作るはずだったんだけど……?」
どこからどう見ても、それは謎の蠢くナマコのような物体。
食いしん坊なエヴァも、その様子を思わず何度も目をこすって確認する。あまりにも、あまりにも豪快な化学変化に、ルキハも喉を鳴らす。しかしエヴァはさらさらと筆談する。
『でも食べればきっと美味しいよね』
……エヴァはあくまでもエヴァだったようだ。 貧乏暮らしがそうさせたのか、ただの食いしん坊なだけなのか、判別に困る部分もあるけれど。
その一方でルキハはバゲットを軽くあぶり、その上にチーズなどをのせたおつまみを作っている。
「イイ男の手料理を食べないわけにはいかないわねッ」
肉にはワインという発想は皆同じだし、確かにちょっとしたつまみがあった方が良いだろう。いかにも美味しそうなできばえに、周りの仲間たちも興味津々。更に、
「お酒が苦手なら、果実のジュースはどうかしら?」
これなら未成年でも十分に飲めるはずだからと取り出したジュースも気が利いていた。
「そうそう、こうやってワインや麦酒で煮込むと肉はやわらかくなるんだよ」
言いながら煮込みものをこしらえているのは薬草師でもある母を持ったユリアン(ka1664)、母からの知恵の賜物なのだろう煮物はとても良い香りがする。中には肉の他、馬鈴薯やタマネギ、ローレルなども入っているのだとか。
「ねえ、味加減はどんなものだろ?」
近くにいたリュー・グランフェスト(ka2419)に味見を頼んでみると、
「ん、これはうまいな」
麦酒のおかげでやわらかくなった肉が口の中でとろけていくような感じで、それがまたひどく旨味もひき出している。
料理の方もずいぶん万端整ったようだ。
――さあ、宴の時間だ。
●
「さあ今日は鹿送りだ。みんなどんどん食べてくれ! むろんお客人もご一緒にだ!」
ユーリィの音頭で宴は始まる。素朴な味付けの煮物、焼き物はもちろんのことながら、ハンターたちの土産物もどっさりと、ここにいる部族の人間だけでは食べきれないほどに。
「いただきます」
そんな、小さな祈りの声があちこちから聞こえる。
命を頂くという行為に最大限の感謝を示す言葉だ。その祈りが届かないわけもない。
雪雫もまた、料理の手伝いをして少し疲れてはいるものの、手を合わせてしっかりと祈りを込めていた。
「内容は違えどこの雰囲気……懐かしいな」
わずかに目を細めているのはエアルドフリス(ka1856)、かつて滅ぼされた部族の末裔だ。ユーリィの側にやってきて、思っていたことを問う。
「外部者を招き入れるというのは部族としてもずいぶん挑戦的な試みと思うのだが、これはどんな意図があるのかお教え願えると嬉しいのですが」
するとユーリィはクスッと笑って頷いた。
「ああ、古い考えの部族の者にはそういうことに頭の固い人も確かに多いだろう。だが俺はハンターという存在が歪虚に脅かされているこの世界において、重要な存在であることを認識している。それに俺個人が、幼い頃にハンターにあこがれていてね。たまたま幼い頃に出会ったハンターが世界の広さを教えてくれた。だから、もっと世界を知るために、積極的な行動をしても良いんじゃないかと、……まあこれはあくまでも俺個人の意見だけどな」
そこまで言って口に酒を含む。
「少し饒舌になりすぎてしまったかも知れないが、まあ部族会議はもちろんながら一枚岩じゃない。俺はスコールの族長とも比較的懇意だからな、彼女の手助けになれるよう、少しでも多くの知識を得たいと思っているのさ」
「……なるほど、立ち入ったことをお聞きしてすまない。非礼のわびに一曲披露して良いだろうか」
エアルドフリスはそう言って、朗々と歌い出した。
今はなき彼の部族に伝わる、雨と空の巡りに感謝する歌だ。誰もがその歌声に耳を澄ます。
やがてぱちぱちと拍手の音がして、彼はそっとユーリィの前を去った。
「……俺は、やっぱり、此処の人間なんだよなあ……」
そう、親友のジュードに漏らす。故郷を失っても、根付くものはやはりこの大地にある――しみじみと感じたようだ。
「そっか」
ジュードもそれだけ応じて、そして静かに祭りを眺める。
「ルールーの歌、良かったヨ♪ 大切な歌、すごく綺麗ダッタネ!」
にっこり笑ってアルヴィンが酒をつぎ、そして小さく乾杯した。
中央にあるかがり火付近には祈りを捧げるための台(うてな)があり、そこには命の源といえる心の臓が、頭とともに祀られている。
「本当は食べたかったけど、これも儀式なんだもんね」
オキクルミが苦笑しながらその心臓を見つめていた。
「うちにも似たような風習があるからね、でもやっぱり少し違うんだなぁ……」
そう呟くオキクルミは、しかし儀式の大切さを理解している。相手の思いや考えを尊重するものとして、静かにそれを見つめていた。
続いて中央に立ったのはリューナ。
「よ、待ってましたっ!」
酒が回りつつあるヴァイスが大きな声でもてはやす。
しかしそんな声も気にせず彼女は静かに鈴を振りかざし、そして静けさの中に激しさを込めて、舞を披露する。来年も、キジャンの民に実りがあるようにと、そう祈りを込めて。
踊りが最高潮に達しやがて彼女の鈴の音がおさまると、ふわっと拍手が巻き起こった。更にそこに、ルキハがそっと近づいてきて。
「素敵だったわよぉ♪ 芸能の女神もかくやという感じねぇ~♪」
お疲れ様と言わんばかりに指しだした手の指を小さく鳴らすと、ぽんと現れる一輪の薔薇。それを手渡せば、
「あら、お花? ありがとう、お花を贈られて喜ばない女なんていないものね♪」
そう言ってくすくすと微笑む。ともに喜びを分かち合うために、酒を用意しながら。
その脇で小柄な身体をいっぱい使って食べまくっているのはドワーフのアルマ(ka3330)、こう見えても立派な大人だ。
「アルマはこれでも大人ゆえ、酒もかっくらうのじゃよ」
土産物にともってきたチーズと酒をどんどん腹に収めていく。ただその幼い見た目と酔っ払うと何をしでかすかわからないので、その辺にしておけと周囲から止められてしまうのだが。
その一方で下戸は下戸同士酒を飲まずに炭酸飲料で喉を潤している。
それでもどこか楽しくなるのは、気分の高揚している証だ。
『ところでこの料理は何?』
エヴァが興味深そうに見つめているのは、ミオレスカ(ka3496)が作った鍋に入っている料理だ。
「これは、南蛮漬け、という、リアルブルー由来の料理なのです。神のもたらした食材と、リアルブルーの技術の、崇高なる融合です」
三杯酢に浸かった野菜や揚げ肉はいかにも美味しそう。それを口に運んだのはアルメイダ、興味を持っていたらしい。
「……うん、酒に合うね」
そう言って小さく頷く。そして、そっと荷物から竪琴を取り出し、歌を吟じ始めた。エルフの音楽は耳に心地よく、宴を包んでいく。
「なかなかエルフの音楽を聴くチャンスはないからな。ありがとう、嬉しいな」
ユーリィも満足げに笑った。
「じゃあ次は俺の番かな」
リューも手元のリュートを引き寄せて、陽気な音楽を奏で出す。
この日は宴と言うこともあって基本的に無礼講、そうやってさまざまな文化を楽しめるのもユーリィの決断のおかげである。
「今年の鹿送りはどうなるかと思ったけど、ハンターさんたちのおかげでいつも以上に楽しませてもらっているよ」
キジャンの若者も嬉しそうに声を弾ませた。
リュートが終わればウィスカが歌う。歌にあわせてキララが舞い踊る。歌を途中で止めてしまったのは、
「祖霊がこの歌の続きを聞きたがって、この世界に降りてくると考えられているから――」
だそうだ。部族というのはそれぞれによって信仰のありようも違うのだと言うことを思わせてくれる一幕であった。
――ちなみに陽炎の作ったステーキ改めナマコもどき、本人が意を決して食べたところ案外いけたらしい。まあ、酒の魔術かも知れないが。
「そう言えば土産話と言えば……つい最近は帝国でもいろいろ騒ぎあったけど、まあどうにかこうにか解決した形だね」
僕も防衛には参加したんだ、とイェルバート。他にも『剣機』と呼ばれるその騒ぎに参加したものたちがあれこれと話をしてくれた。
「辺境もずいぶん大変だけど、どこもにたようなもんなんだなあ」
そんな感想を述べるユーリィ。帝国に帰順するつもりはなさそうだが、その住人をけなしたりするつもりはなく、みんな生きているのだからと言うのが素直な感想らしい。
そんな彼だからこそ、若くして族長になったあともやってこれているのだろうが。
「キジャン族の話も聞かせてくれないか。興味深いものもきっとあるからさ」
そうにやりと笑うのはデルフィーノ、リアルブルーを好むエルフ。ギターも持ってきては、それをそっとかき鳴らす。
「礼と言っちゃなんだが、ここらで一曲。ギターの腕はこれでもあるから、キジャンの勇者のために弾きたいねぇ……魂から鼓舞するような、激しいやつを」
まだまだ、宴は長くなりそうだ。
(辺境はいろんな祭りもあって、描き甲斐があるわね……狩りの様子も書いてみたかったなぁ)
エヴァはスケッチブックに色鉛筆を走らせながらそう思う。その表情は幸せそうな笑顔であふれていた。
●
鹿送りの祭りは終わった。
しかしこれも一つのきっかけに過ぎない。
次に彼らと会うとき、互いに笑顔でいられるように――それはきっと、すべてのものの願いなのだろう。
鹿は、きっとそれをかなえてくれる――ユーリィはそう信じて、ハンターたちを見送った。
依頼結果
| 依頼成功度 | 大成功 |
|---|
| 面白かった! | 11人 |
|---|
ポイントがありませんので、拍手できません
現在のあなたのポイント:-753 ※拍手1回につき1ポイントを消費します。
あなたの拍手がマスターの活力につながります。
このリプレイが面白かったと感じた人は拍手してみましょう!
MVP一覧
重体一覧
参加者一覧
サポート一覧
マテリアルリンク参加者一覧
| 依頼相談掲示板 | |||
|---|---|---|---|
 |
依頼前の挨拶スレッド ミリア・クロスフィールド(kz0012) 人間(クリムゾンウェスト)|18才|女性|一般人 |
最終発言 2014/11/14 16:40:31 |
|
 |
【相談卓】鹿送りの宴 Uisca=S=Amhran(ka0754) エルフ|17才|女性|聖導士(クルセイダー) |
最終発言 2014/11/14 13:39:04 |
|

















